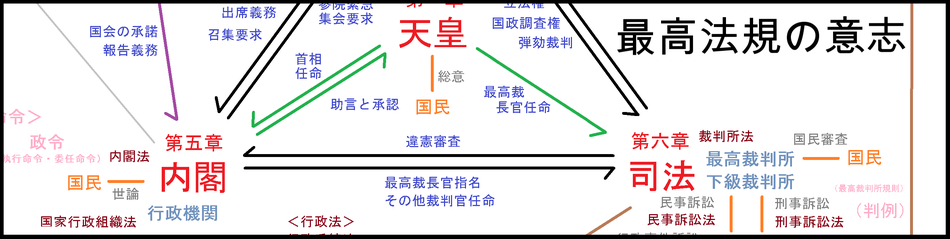同性婚訴訟 東京高裁判決の分析
【このページの目次】
はじめに
ポイント
〇 個人と婚姻の関係
〇 「婚姻」のある社会を選択する意図
〇 24条2項の「婚姻及び家族」の枠組み
〇 「目的」の意味の混同
〇 「平等」の審査方法
・比較の主体
・比較の対象
・差異の基準点
〇 比較する対象の誤り
〇 「カップル間不平等論」の誤り
・人的結合関係を基に比較してはならないこと
・「カップル信仰論」に陥ってはならないこと
〇 「異性と婚姻できるが同性と婚姻できない不平等論」の誤り
・婚姻が成立するための「条件」
〇 「性愛に基づく不平等論」の誤り
・「性愛」による区別取扱いは存在しないこと
・内心による区別取扱いの違憲性
〇 「不利益」を前提とすることの誤り
〇 別の制度を取り上げて比較することの誤り
〇 「原則と例外の逆転論法」の誤り
〇 その他
〇 「婚姻」には内在的な限界があること
〇 婚姻制度と矛盾する制度は立法できないこと
〇 解釈の方法と限界
はじめに
「同性婚訴訟 東京高裁判決」の内容を分析する。
判決
━ 令和6年10月30日 (PDF)
【東京一次・控訴審】判決全文(OCR版) 2024年10月30日 PDF
判決要旨
【東京一次・高裁】判決要旨 2024年10月30日 PDF
【東京一次・高裁判決】判決要旨(OCR版) 2024年10月30日 PDF
【判決要旨全文】東京高裁はなぜ「法の下の平等」などに違反と判断したのか (結婚の平等裁判) 2024年10月30日
この判決文の内容は、問題が多岐にわたる。複数ヵ所の誤りを同時に解きほぐすことが必要となるため、初学者には難解であると思われる。
ここでは、判決の問題点を理解するために必要となるポイントを解説する。
ポイント
判決の誤りを理解するために、前提として必要となる知識を整理する。
個人と婚姻の関係
憲法は「個人の尊厳」の原理に基づいており、自然人は「個人主義」の下に「自律的な個人」として生存していくことを予定している。
そのため、何らの制度も利用していない「個人」の状態で既に完全な状態ということができ、それがすべての法制度を検討する際の基準(スタンダード)となる状態である。
そのような中、それらの個々人は、人的結合関係を形成、維持、解消するなどしながら生活していくことになる。
もちろん、個々人が「共同生活」を営むことも可能である。
このような行為は、「国家からの自由」という「自由権」の性質として、憲法21条1項の「結社の自由」によって保障される。
ただ、国民が「生殖」することによって社会的な不都合が発生することを抑制するために、国家の政策的な要請として「生殖と子の養育」の観点から一定の人的結合関係を選び出し、その枠組みを「婚姻」として扱うことを制度化している。
これが、「結社の自由」で保障される他の様々な人的結合関係から区別する意味で「婚姻」という枠組みを設けている理由である。
この点について、国(行政府)は下記のように理解している。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)ア しかしながら、人は、一般に、社会生活を送る中で、種々の、かつ多様な人的結合関係を生成しつつ、生きていくものであり、当該人的結合関係の構築、維持及び解消をめぐる様々な場面において幾多の自己決定を行っていくものと解されるが、そのような自己決定を故なく国家により妨げられているか否かということと、そのような自己決定の対象となる人的結合関係について国家の保護を求めることができるか否かということとは、少なくとも憲法13条の解釈上は区別して検討されるべきものと解される。そして、被告第2準備書面第5の2(3)イ(ア)(42及び43ページ)で述べたとおり、本件規定に基づく婚姻は、人が社会生活を送る中で生成され得る種々の、かつ多様な人的結合関係のうち、一人の男性と一人の女性との人的結合関係とその間に産まれる子との人的結合関係を制度化し、夫婦の身分関係の発生に伴うものを含め、種々の権利を付与するとともに、これに応じた義務も負担させることによって、夫婦関係の長期にわたる円滑な運営及び維持を図ろうとするものであり、本件規定の目的は、一人の男性と一人の女性が子を産み育てながら共同生活を送るという関係に対して特に法的保護を与えることにあると解するのが相当であって、個人の親密な関係を保護することが自己実現などの権利保護のために必要不可欠であるとして婚姻制度が創設されたものではない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【東京二次・第5回】被告第3準備書面 令和4年6月20日 PDF
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(ア)以上の本件諸規定の立法経緯及びその規定内容からすると,本件諸規定に基づく婚姻は,人が社会生活を送る中で生成され得る種々の,かつ多様な人的結合関係のうち,一人の男性と一人の女性との人的結合関係とその間に産まれる子との人的結合関係を制度化し,夫婦に身分関係の発生に伴うものを含め,種々の権利を付与するとともに,これに応じた義務も負担させることによって,夫婦関係の長期にわたる円滑な運営及び維持を図ろうとするものである。すなわち,本件諸規定の目的は,一人の男性と女性が子を産み育てながら共同生活を送るという関係に対して特に法的保護を与えることにあると解するのが相当である。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【大阪・第9回】被告第5準備書面 令和3年9月24日 PDF
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(ア)婚姻は「伝統的に生殖と子の養育を目的とする男女の結合であった。したがって,同性の性的結合関係や共同生活関係は婚姻たりえないとされてきた」ところ,「国ないし社会が婚姻に法的介入をするのは,婚姻が社会の次世代の構成員を生産し,育成する制度として社会的に重要なものであったからである」(乙第1号証)などと指摘されている。このように,伝統的に,婚姻は,生殖と密接に結び付いて理解されてきており,それが異性間のものであることが前提とされてきた。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【大阪・第9回】被告第5準備書面 令和3年9月24日 PDF
もし「婚姻」という制度を立法する目的から「生殖と子の養育」の趣旨が失われた場合には、その時点で他の人的結合関係とは区別することができなくなり、「婚姻」という概念そのものが消失することになる。
「婚姻」のある社会を選択する意図
その社会の中で何らの制度も設けられていない場合には、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合が発生する。
例えば、「父親不明」の子供が増える、父親を特定できない子供が増える、父親が蒸発して行方不明になった子供が増える、それらにより「子の福祉」が減少する、父親を特定できないことにより近親者の範囲を把握できずに「近親交配」に至り潜性遺伝子の発現した個体が高い確率で生じるようになる、一部の強者が多数人との生殖関係を独占することによって社会の中で「子を持ちたいと希望して相手を見つけようとする男女」の数の不均衡が生じて「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」が生まれる、低年齢での妊娠・出産により母体に危険が及ぶ、などの問題が生じることがある。
これらの不都合を解消するために、下記のような立法目的を有する枠組みを設けることが必要となる。
・「子の福祉」が実現される社会基盤を構築すること
・潜性遺伝子の発現した個体が高い確率で生じることを抑制すること
・「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」を減らすこと
・母体を保護すること
そして、これらの目的を達成するためには、下記の要素を満たす枠組みを設けることが必要となる。
・子の遺伝的な父親を特定できる組み合わせとすること
・特定された子の父親にも子に対する責任を担わせること
・特定された子の父親を基に遺伝的な近親者を把握すること
・未婚の男女の数の不均衡を防止できる組み合わせに限定すること
これらの要素を満たすものとして「一人の男性」と「一人の女性」が選び出され、その間に「貞操義務」を設け、その関係を法的に結び付ける形を「婚姻」と呼んでいる。
そして、この「婚姻」に対して法的効果や一定の優遇措置を設けることで、婚姻制度を利用する者を増やし、これらの目的を達成することを目指すものとなっている。
このように、「婚姻」は国民が「生殖」によって子供を産むことに関係して起き得る問題を抑制することを目的として、「生殖と子の養育」の観点に着目して他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた枠組みである。
このような「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解決しようとする目的を離れて「婚姻」を観念することはできない。
よって、「婚姻」の文言には、これらの目的を達成することを阻害する組み合わせを「婚姻」の中に含めることはできないという内在的な限界が含まれており、その限界を超えるものについては「婚姻」とすることはできない。
また、憲法24条は「婚姻」を規定しており、「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めている。
これについても、上記の要素を満たす枠組みとして定められているものである。
この24条の定める形が「婚姻」であり、これらの要素を満たさないものについては「婚姻」とすることはできない。
24条2項の「婚姻及び家族」の枠組み
24条2項の「婚姻及び家族」について詳しく検討する。
■ 「婚姻」と「家族」はそれ以外の概念ではないこと
「婚姻」や「家族」である以上は、「サークル」「部活」「組合」「雇用」「会社」「町内会」「宗教団体」「政党」など他の様々な人的結合関係とは異なる概念である。
当然、これは「意思表示」「代理」「物権」「即時取得」「売買」など、それとは別の概念を示すものでもない。
このように、「婚姻」や「家族」という概念が用いられている以上は、その概念そのものが有する意味を離れることはできないのであり、その概念が有する意味に拘束されることになる。
よって、「婚姻」や「家族」として扱うことができる範囲には、「婚姻」や「家族」という概念であることそのものによる内在的な限界が存在する。
言い換えれば、「婚姻」や「家族」という言葉それ自体を別の意味に変えてしまうことはできないのであり、これらの言葉に対して、その概念に含まれている内在的な限界を超える意味を与えることが解釈として可能となるわけではない。
もしその概念が有する内在的な限界(意味の範囲)を超える形で新たな枠組みを設けることを望む場合には、解釈によって導き出すことのできる範囲を超えることになるから、その規定を改正して文言を変更するか、その規定そのものを廃止することが必要となる。
■ 「婚姻」と「家族」は異なる概念であること
24条2項には「婚姻及び家族」と記載されている。
ここから分かることは、「婚姻」と「家族」はそれぞれ異なる概念であるということである。
このことから、下記の内容が導かれる。
〇 第一に、「婚姻」と「家族」を同一の概念として扱うことはできない。
〇 第二に、「婚姻」の概念を「家族」の概念に置き換えることや、「家族」の概念を「婚姻」の概念に置き換えることはできない。
〇 第三に、「婚姻」や「家族」という言葉の意味によって形成されている概念の境界線を取り払うことはできない。
〇 第四に、「婚姻」や「家族」という言葉の意味の範囲をどこまでも拡張することができるというものではない。
このように、「婚姻」と「家族」という文言が使われていることそのものによって、これを解釈する際に導き出すことのできる意味の範囲には内在的な限界がある。
それぞれの言葉には一定の意味があり、その意味そのものを同じものとして扱ったり、挿げ替えたり、混同したり、無制限に拡張したりすることはできないからである。
そのため、もし下記のような法律を立法した場合には、24条2項の「婚姻及び家族」の文言に抵触して違憲となる。
① 「婚姻」と「家族」の意味を同一の概念として扱うような法律を立法した場合
② 「婚姻」の意味と「家族」の意味を置き換えるような法律を立法した場合
③ 「婚姻」や「家族」の概念の境界線を取り払うような法律を立法した場合
④ 「婚姻」や「家族」という言葉の意味の範囲をどこまでも拡張することができることを前提とした法律を立法した場合
■ 「婚姻」と「家族」は整合的に理解する必要があること
24条2項の「家族」とは、法学的な意味の「家族」を指すものである。
そのため、社会学的な意味で使われる「家族」のように、どのような意味としてでも自由に用いることができるというわけではない。
24条2項には「婚姻及び家族」と記載されており、これら「婚姻」と「家族」の文言は、一つの条文の中に記されている。
24条2項では「A、B、C、D、E 並びに F」の形で順を追って説明するものとなっており、その中で「婚姻及び家族に関するその他の事項」が一つのまとまりとなっている。
この点で、「婚姻」と「家族」という二つの概念はまとめる形で定められている。
そして、「家族」の文言は、「婚姻及び家族」のように「婚姻」の文言のすぐ後に続く形で、「婚姻」と共に記されている。
そのことから、「家族」の概念は、「婚姻」の概念と結び付くものとして定められており、これらは切り離すことのできるものではない。
よって、「婚姻」と「家族」の意味を解釈する際には、それぞれの概念をまったく別個の目的を有した相互に関わり合いのない枠組みであるかのように考えることはできず、それらを整合的に読み解くことが求められる。
24条2項の「婚姻及び家族」の文言は、1項で「婚姻」について既に定められていることを前提として、それに続く形で「家族」についても触れるものとなっている。
そのため、「家族」の概念は「婚姻」を中心として定められる枠組みであることは明らかである。
これについて、国(行政府)は下記のように説明している。
◇ 「同項における立法上の要請及び指針は、形式的にも内容的にも、同条1項を前提とすることが明らかである。」
◇ 「このように、憲法24条2項が、同条1項の規定内容を踏まえ、これを前提として定められていることは、同条2項の内容面からしても明らかである。」
【東京一次・第1回】控訴答弁書 令和5年6月23日 PDF
国(行政府)は最高裁判決の記述も示している。
【東京二次・第9回】被告第7準備書面 令和5年9月28日 PDF (P14)
【九州・第1回】被控訴人(被告)答弁書 令和6年1月31日 (P15)
■ 「婚姻及び家族」の内在的な限界
「家族」の枠組みを検討するために、初めに、「婚姻」の目的と、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす枠組みから検討する。
▼ 「婚姻」の概念に含まれる内在的な限界
「婚姻」は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的とした形成された枠組みである。
これは、下記のような経緯によるものである。
その社会の中で何らの制度も設けられていない場合には、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合が発生する。
例えば、「父親不明」の子供が増える、父親を特定できない子供が増える、父親が蒸発して行方不明になった子供が増える、それらにより「子の福祉」が減少する、父親を特定できないことにより近親者の範囲を把握できずに「近親交配」に至り潜性遺伝子の発現した個体が高い確率で生じるようになる、一部の強者が多数人との生殖関係を独占することによって社会の中で「子を持ちたいと希望して相手を見つけようとする男女」の数の不均衡が生じて「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」が生まれる、低年齢での妊娠・出産により母体に危険が及ぶ、などの問題が生じることがある。
これらの不都合を解消するために、下記のような立法目的を有する枠組みを設けることが必要となる。
・「子の福祉」が実現される社会基盤を構築すること
・潜性遺伝子の発現した個体が高い確率で生じることを抑制すること
・「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」を減らすこと
・母体を保護すること
そして、これらの目的を達成するためには、下記の要素を満たす枠組みを設けることが必要となる。
・子の遺伝的な父親を特定できる組み合わせとすること
・特定された子の父親にも子に対する責任を担わせること
・特定された子の父親を基に遺伝的な近親者を把握すること
・未婚の男女の数の不均衡を防止できる組み合わせに限定すること
これらの要素を満たすものとして「一人の男性」と「一人の女性」が選び出され、その間に「貞操義務」を設け、その関係を法的に結び付ける形を「婚姻」と呼んでいる。
そして、この制度を利用した場合には一定の法的効果や優遇措置があるという差異を設けることによって、この制度を利用する者を増やし、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成することを目指すものとなっている。
このような「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解決しようとする目的を離れて「婚姻」を観念することはできない。
そのため、「婚姻」である以上は、これらの目的を達成することを阻害する組み合わせを「婚姻」とすることはできないという内在的な限界がある。
また、24条の「婚姻」は、「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めている。
これについても、上記の要素を満たす枠組みとして定められているものである。
よって、「婚姻」の中に含めることのできる人的結合関係の範囲は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成するための手段として整合的な上記の要素を満たす範囲に限られる。
▼ 「家族」の概念に含まれる内在的な限界
次に、「家族」の枠組みを検討する。
▽ 「婚姻」と「家族」の整合的な理解
上で述べたように、「家族」の枠組みは、「婚姻」という枠組みが存在することを前提としており、「婚姻」の枠組みから切り離して独立した形で存在することはできない。
そのため、もし「婚姻」の枠組みが有している目的の実現を「家族」の枠組みが阻害するものとなっている場合、「婚姻」と「家族」は同一の条文の中に記された文言であるにもかかわらず、その間に矛盾・抵触が生じていることとなり、その意味を整合的に読み解くことができていないことになるから、解釈の方法として妥当でない。
そのことから、「家族」の枠組みは、「婚姻」の枠組みが有している目的を達成することを阻害するような形で定めることはできず、「婚姻」の枠組みが有している目的との整合性を切り離して考えることはできない。
これにより、「婚姻」と「家族」は、同一の目的を共有し、その同一の目的に従って相互に矛盾することなく整合性を保った形で統一的に形成される枠組みということになる。
よって、「家族」の枠組みは、「婚姻」の立法政策に付随して同一の目的を共有し、「婚姻」の枠組みと結び付く形で位置付けられることになる。
▽ 「家族」の枠組み
「家族」の枠組みは、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として設けられた「婚姻」の枠組みと結び付いて定められている。
そのため、「家族」の枠組みは、「婚姻」の目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす枠組みが存在することを前提として、その「婚姻」と同一の目的を共有する形で、かつ、その「婚姻」の枠組みとの間で矛盾しない形で、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす形で定められることになる。
「婚姻」とするためには、下記の要素を満たすことが必要である。
・子の遺伝的な父親を特定できる組み合わせとすること
・特定された子の父親にも子に対する責任を担わせること
・特定された子の父親を基に遺伝的な近親者を把握すること
・未婚の男女の数の不均衡を防止できる組み合わせに限定すること
そして、「家族」の枠組みは、「婚姻」と同一の目的を共有し、この「婚姻」の枠組みと矛盾しない形で、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす形で定められることになる。
そのことから、「家族」とするためには、下記の要素を満たすことが必要である。
・「婚姻」と「家族」は異なる概念であること
・「婚姻」と同一の機能を「家族」の概念に担わせることはできないこと
・「生殖」を推進する関係は「婚姻」している夫婦の間に限られること
・「貞操義務」は夫婦の間に限られること
・夫婦以外の関係の間で「生殖」を推進する作用を生じさせないこと
・「生殖」によって子が生じるという生命活動の連鎖による血筋を明らかにすることが骨格となること
・「生殖」によって生じた子とその親による「親子」の関係を規律すること
・遺伝的な近親者とは「婚姻」することができないこと
これらの要素により、「家族」の中に含めることのできる人的結合関係と、含めることのできない人的結合関係が区別されることになる。
このように、「婚姻」が「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的としている以上は、その「婚姻」の目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす枠組みとの関係で、「家族」の枠組みも自ずと明らかとなる。
このことより、「家族」の中に含めることのできる人的結合関係の範囲は、「家族」という概念であることそれ自体による内在的な限界がある。
そのため、もし上記の要素を満たさない人的結合関係を「家族」の中に含めようとする法律を立法した場合には、24条2項の「家族」の文言に抵触して違憲となる。
∵ 「家族」の範囲
上記のように、「家族」は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として「婚姻」という枠組みが設けられていることを前提として、その立法政策に付随する形で同一の目的を共有し、その目的を達成するための手段として設けられる枠組みである。
そのため、「家族」の枠組みは、「生殖」によって「子」が生まれるという生物学的な因果関係を離れて観念することはできない。
よって、「家族」の中に含まれる人的結合関係の範囲は、下記の順に決まることになる。
① 婚姻している「男性」と「女性」の関係 (夫婦)
② 婚姻している「母親」から産まれた「子」とその「夫婦」との関係 (親子)
③ 婚姻していない「母親」から産まれた「子」とその「母親」との関係 (親子)
④ 婚姻している「母親」から産まれた「子」であるが、その「母親」の「夫」に嫡出否認された場合の「子」とその「母親」との関係 (親子)
⑤ 「子」の「父親」であると認知した者との関係〔あるいは『子』の親権を得た『父親』との関係〕 (親子)
このように、婚姻している「夫婦」と、自然生殖の過程を経て生まれてくる「子」とその「親」との関係を規律する「親子」による枠組みを骨格として範囲が決まることになる。
これは、「自然血族」である。
これらの関係が「家族」となるのは、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的によって「婚姻」という枠組みが設けられており、その「婚姻」と同一の目的を共有する形で、生物学上の血のつながりを持つ親子関係を明確にすることを意図した統一的な枠組みといえるからである。
⑥ 「自然血族」の「親子」の関係に擬制して位置付けられる「養子縁組」による「親子」の関係
自然生殖によって生じる「親子」の関係を規律する「自然血族」の枠組みを基本として、その骨格を維持したまま、その骨格に当てはめる形で法的に「親子」の関係として扱う制度が定められることがある。
これは、「法定血族」である。
∵ 結論
このように、24条2項の「家族」の中に含めることのできる人的結合関係の範囲は、「家族」の枠組みが「婚姻」と同一の目的を共有してその目的を達成するための手段として「婚姻」の枠組みとの間で整合性を保つ形で統一的に定められることによる内在的な限界がある。
そして、その限界は、「婚姻」している「夫婦」と、「生殖」によって子が生まれるという生物学的な因果関係を想定した「親子」の関係による「自然血族」と、その「自然血族」の枠組みを基本として、その骨格を維持したまま、その骨格に当てはめる形で位置付けられる「法定血族」までをいう。
まとめると、「家族」とは、「婚姻」している「夫婦」と、「親子」の関係によって結び付けられる「血縁関係者」のことを指す。
国(行政府)は下記のように述べている。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(イ)しかし、現行民法典には「家族」という言葉は存在せず、少なくとも民法の観点からは「家族」を厳密に定義することは困難であるが(大村敦志「家族法(第3版)」23ページ・乙第35号証)、一般的な用語としての「家族」は、「夫婦の配偶関係や親子・兄弟などの血縁関係によって結ばれた親族関係を基礎にして成立する小集団」を意味するものとされている(新村出編「広辞苑(第7版)」560ページ)。……(略)……
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【東京一次・第1回】控訴答弁書 令和5年6月23日 PDF
【参考】家族関係の基本知識 2022.12.19
【参考】血族について学ぼう!範囲や親族・姻族との違いを詳しく解説 2021.8.9
「目的」の意味の混同
「目的」の意味には多義性がある。どのような文脈で使われているかによって、その意味するところは異なっているため、注意して読み解く必要がある。
① 「国の立法目的」の意味
概念や制度の枠組みが導かれ、定められる際の立法目的にあたるもの。
例
・「会社法」の立法目的
・「宗教法人法」の立法目的
・婚姻制度の立法目的 ⇒ 「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消すること
② 「制度が機能することによって生じる結果(目的)」の意味
ある制度が機能すると、何らかの結果が生じることになるが、その結果の部分を「目的」と表現することがある。
制度 ⇒(機能すると)⇒ 結果(目的)
例
・「会社」は、営利を目的として事業を行う社団法人である。【動画】
→ 会社が機能すると、営利(経済的な利益)が生じる。
・「宗教法人法」は、宗教団体に法人格を与えることを目的として作られた法律である。
→ 宗教法人法が機能すると、宗教団体に法人格が与えられる。
・婚姻制度の目的は、次世代再生産の可能性のある組み合わせを優遇することである。
→ 婚姻制度が機能すると、次世代再生産の可能性のある組み合わせが優遇される。
この機能面に着目することによって、ある制度を、他の様々な制度との間で区別して理解することが可能となる。
これは、同じ機能を持ち、同じ結果を生じさせる制度であれば、異なる名前を付けている意味がないからである。
そのため、この意味で「目的」という言葉が使われている場合には、その制度を他の制度との間で区別して理解しようとする文脈であることを意味する。
③ 「個々人の利用目的」の意味
個々人がどのような意思をもって制度を利用・活用するかに関するもの。
例
・私の「会社」は営利を目的としているわけではなく、社会貢献が目的である。
・この「宗教団体」は人を幸せにすることを目的としている。
・私は子供をつくることを目的として婚姻する。
下図は、婚姻制度についての、「① 国の立法目的」と、「② 制度が機能することによって生じる結果(目的)」と、「③ 個々人の利用目的」の位置づけである。
この東京高裁判決では、婚姻制度の「目的」や「意義」について述べようとしている部分がある。
しかし、法制度の枠組みについて定めた条文の意味を読み解く際には、その法制度の枠組みが定められている原因となっている「① 国の立法目的」を明らかにすることにより、その条文に記された規範の意味を明らかにすることが必要となるにもかかわらず、その条文が下位の法令に対してどのような効果を生じさせるかというその条文の有する機能(いわば『② 制度が機能することによって生じる結果(目的)』にあたるもの)について示した上で、それを基にその条文の枠組みそのものの規範を論じようとしている部分があり、誤っている。
また、具体的な制度が存在することを前提とする中で生じる「③ 個々人の利用目的」について触れた上で、あたかもそれが根拠となってその制度が定められていることについての「① 国の立法目的」が明らかになるかのように論じる部分もあり、誤っている。
このような点において、「目的」や「意義」の捉え方について混乱したものとなっている。
この東京高裁判決では、「婚姻の目的」について「両心の和合」のように説明している部分がある。
この点について、国(行政府)は、それが記載された文献の記述は「婚姻を生殖と結びついた男女間の結合と捉えつつ,このような理解を前提とした上で生殖能力のない者の婚姻の可否を論じているもの」であることを指摘している。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ア しかしながら,我が国の婚姻制度が伝統的に生殖と結びついて理解されてきたことは,被告第2準備書面第1の2(1)及び(2)(5ないし8ページ)において引用した文献の記載等からも明らかである。
イ この点,原告らは,「婚姻ハ兩心ノ和合ヲ以テ性質ト為スモノニシテ産子ノ能力ハ一般ニ具備スヘキ條件ナレドモ,必要欠ク可ラサル條件三アラズ」と説明する文献(熊野敏三ほか「民法正義入事編巻之壹(上下)」193ページ・甲A第186号証)を引用し,「我が国の婚姻制度は,必ずしも生殖を目的としない親密な人格的結合(『両心ノ和合』)に基づく共同生活関係に対して法的保護を与えることを中心的な目的に据えてきたものであり,現在においてもそのような前提に変更はないものと解するのが適切である」と主張する(原告ら第6準備書面 22,40ページ)。
しかし,上記文献は,上記の引用部分の前に「産子ノ能力ヲ有セサル男女ト雖モ婚姻ヲ為スヲ得ヘキカ」という問いが設けられているとおり(同号証192ページ),生殖能力が婚姻の必要条件か否かについて論じているのであって,我が国の婚姻制度が,伝統的に,必ずしも生殖を目的としない親密な人格的結合に基づく共同生活関係に対して法的保護を与えることを中心的な目的に据えてきた旨を述べるものではない。むしろ,「産子ノ能力ハ一般ニ具備スヘキ侠件」と明記されているととからすれば,上記文献は,婚姻を生殖と結びついた男女間の結合と捉えつつ,このような理解を前提とした上で生殖能力のない者の婚姻の可否を論じているものと解するのが自然であって,同文献は原告らの上記主張を補強するものではない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【札幌・第5回】被告第3準備書面 令和2年5月15日 (P6)
恣意的な引用 Wikipedia
このように、その文献は、具体的な婚姻制度が存在することを前提として、その制度を利用する意思がある場合に、個々人の個別特性として生殖能力のない者がいた場合に、そのことを婚姻障害事由として婚姻制度を利用することを否定するべきか否かの議論において、それを否定しなかったというものである。
そのため、これは、具体的な婚姻制度が存在することを前提として、個別的な事例に対してその法的効果を及ぼすことができるか否かについて論じているものである。
そのことから、この「両心の和合」というものは婚姻制度の枠組みが導かれる際の「① 国の立法目的」として述べられているものではない。
よって、この「両心の和合」というものを理由として「婚姻」の枠組みの範囲を変更することができるということにはならないし、別の制度を創設することができるとする理由になるものでもない。
また、「両心の和合」という精神的な事柄については、個々人が自由に人的結合関係を形成する中で価値観として営むことは可能であるし、「組合」「会社」「宗教団体」「政党」など、様々な人的結合関係についても「両心の和合」を述べることが可能であり、このような事柄を基にして婚姻制度の枠組みを決めることができるとする理由とはならないことは明らかである。
「平等」の審査方法
比較の主体
〇 憲法14条が「個人権」であること
憲法は「個人の尊厳」の原理の下、「個人主義」に基づいている。
そのため、憲法上で何らかの比較を行う際には、「個人」が主体となり、別の「個人」との間で比較することになる。
また、憲法14条1項の「平等原則」についても、その性質は「個人権」であり、「個人と個人の間の平等」をいう。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ア しかしながら,憲法14条1項が規定する法の下の平等とは,個人と個人の間の平等をいい,同項が禁止する不合理な差別も,個人と他の個人との間の不合理な差別をいうものと考えられる(例えば,芦部信喜教授は,法の下の平等は「個人権」であり,「個人尊重の思想に由来」すると説明している(芦部信喜〔高橋和之補訂〕「憲法第七版」129 ページ)。)。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【大阪・第6回】被告第4準備書面 令和3年2月19日 PDF (P4) (下線は筆者)
【札幌・第7回】被告第4準備書面 令和2年10月21日 PDF (P4)
そのため、法制度について「個人」と「個人」の間に差異がある場合に、「区別取扱い」として認識し、その間を比較することが可能である。
◇ 権利能力
民法上で「権利能力」を有し、法主体としての地位を有するのは「自然人」と「法人」である。
権利能力(ケンリノウリョク) 宅建用語集
民法3条:権利能力とは?わかりやすく解説【権利能力平等の原則】 2021年2月21日
権利能力 Wikipedia
【動画】1分で「権利能力」がわかる! 【#1 民法を1分で勉強シリーズ・総則編】 2021/02/14
【動画】基本講義「民法」単元3後半 権利能力・意思能力・行為能力 2020/03/22
【動画】〔独学〕司法試験・予備試験合格講座 民法(基本知識・論証パターン編)第8講:権利能力と胎児 〔2021年版・民法改正対応済み〕 2021/05/28
【動画】【行政書士試験対策】権利能力//権利・義務の主体となれるのは? 2023/03/25
【動画】司法書士 はじめの一歩 ~Topic.07 胎児は「人」なのか?~【権利能力】 2020/12/18
【動画】民法本論1 01権利能力 2011/04/11
【動画】2021応用インプット講座 民法5(総則5 権利能力) 2020/11/20
【動画】公務員試験対策 民法・権利能力・意思能力・責任能力・行為能力 2021/09/21
▽ 自然人
自然人は出生によって「権利能力」を取得し、死亡することによって「権利能力」が消滅する。
民法
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第二章 人
第一節 権利能力
第三条 私権の享有は、出生に始まる。
2 外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○政府委員(工藤敦夫君)
(略)
民法は、権利能力については出生に始まり死亡に至るまでということでございますが、満二十年をもって成年とすると。……(略)……
(略)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第116回国会 参議院 予算委員会 第3号 平成元年10月24日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
民法は我々の生活関係を権利と義務に分解して規定し、規律するが、この権利及び義務の帰属主体となりうる資格を権利能力という。民法は、権利能力はあらゆる自然人が平等に有するとしているが、このことは近代法によって確立された原則であり、近代法が発達する以前の時代、すなわち奴隷制が存在した時代や、封建時代には、人によっては権利能力を認められない自然人も存在したのである。人は権利能力があって初めて法律的に自由な経済活動が可能となるのであり、その権利能力を自然人に平等に認めるのは、憲法の要請でもある。
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
権利能力の取得時期について、民法は「出生に始まる」としている。この出生がいつか、ということについては諸説あるが、民法の解釈としては、生まれてきた子供の体全体が母体から出たときを基準にする、いわゆる「全部露出説」が通説である。
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
権利能力の喪失時期、つまり死亡の時期については、心臓停止説、つまり、心臓が不可逆的に停止した時を基準とする説が通説である。最近では、脳死を基準とすべきであるという説も有力であるが、倫理や遺族感情などの問題とも絡み合い、脳死を基準とするのは困難であることが指摘されている。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第15課 民法―権利義務の主体(自然人その1) (下線・太字は筆者)
自然人 Wikipedia
人の始期 Wikipedia
▽ 法人
「法人」の「権利能力」は法律の手続きによって形成される。
民法
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(法人の成立等)
第三十三条 法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。
2 (略)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法人 Wikipedia
このことから、憲法14条1項の「平等原則」を用いて審査する場合においても、「権利能力」(法人格)を有し、法主体としての地位を認められている個々の自然人(あるいは法人)を対象として比較することになる。
法律論としては、下図のように「権利能力」を有して法主体としての地位を認められている自然人(あるいは法人)を単位として論じる必要がある。
【動画】司法試験入門講座 プレ講義 「体系マスター」民法5 「契約の成立と効力発生まで~民法総則」 2020/03/17
比較の対象
14条における「平等」を論じる際には、何と何を比較しているのかを明確にする必要がある。これが曖昧になると、区別の有無や、区別の合理性を適切に審査することができなくなる。
下図で、比較の対象となるパターンを(A)~(G)に分類した。
◆ 法の下の平等( A )
14条の「法の下の平等」は、「権利能力」(法人格)を有し、法主体としての地位を認められている個々の自然人を対象として審査するものである。この(A)のパターンは、最も典型的な事例である。
この点について、国(行政府)の主張でも触れられている。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ア しかしながら,憲法14条1項が規定する法の下の平等とは,個人と個人の間の平等をいい,同項が禁止する不合理な差別も,個人と他の個人との間の不合理な差別をいうものと考えられる(例えば,芦部信喜教授は,法の下の平等は「個人権」であり,「個人尊重の思想に由来」すると説明している(芦部信喜〔高橋和之補訂〕「憲法第七版」129 ページ)。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【大阪・第6回】被告第4準備書面 令和3年2月19日 PDF (P4) (下線は筆者)
個々人の間での区別が存在し、その区別に合理性が認められないのであれば、憲法14条1項の「平等原則」に抵触して違憲となる。
◆ 法の下の平等( B )
同種の「法人」と「法人」の間で区別取扱いがある場合には、その合理性が審査されることになる。
区別に合理性がない場合には、憲法14条1項の「平等原則」に抵触して違憲となる。
◆ 法の下の平等( C )
「婚姻している者(既婚者)」に対して比較対象となるのは、常に「婚姻していない者(独身者)」である。
「婚姻している者(既婚者)」に対して、婚姻制度の立法目的を達成するための手段として不必要に過大な優遇措置を行っている場合には、「婚姻していない者(独身者)」との比較においてその合理性が審査されることになる。
優遇措置の内容が合理性を有しない場合は、その優遇措置に関する規定が憲法14条1項の「平等原則」に抵触して違憲・無効となる。
この点について、国(行政府)は下記のように述べている。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
しかしながら、被控訴人としても、本件規定における特定の法的効果(優遇)の内容が婚姻制度の目的との関連で合理性を欠くものであれば、当該効果に係る規定が憲法14条1項に違反すると評価され得る場合があることを否定するものではない。…(略)…
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ 法の下の平等( D )
この( D )の事例は、基本的には先ほど挙げた( C )の事例と同様である。
ただ、( D )の事例は( C )の事例に比べて「生殖」に関する問題で「婚姻している者(既婚者)」との立ち位置が近いことを意識して、あえて( C )と( D )に分けた。
◆ 法の下の平等( E )
この事例は、下記の判例がある。
遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件 最高裁判所大法廷 平成25年9月4日
◆ 法の下の平等( F )と( G )
「婚姻及び家族に関する法制度」の内部の問題で、かつ、「男性」と「女性」の間の「平等」については、憲法14条1項の「法の下の平等」だけでなく、憲法24条2項の「両性の本質的平等」による審査がなされることになる。
14条1項の「平等」と24条2項の「両性の本質的平等」の適用方法については、下記の通りである。
〇 14条の「平等」
個人と個人の間の「平等」を審査するものである。
(『婚姻及び家族』の制度についても審査することが可能である。)
〇 24条2項の「両性の本質的平等」
「婚姻及び家族」の制度について、「男性」と「女性」の間の「平等」を審査するものである。
最高裁の「再婚禁止期間大法廷判決」(平成27年12月16日)と「夫婦同氏制大法廷判決」(平成27年12月16日)は、「婚姻及び家族に関する事項」であり、かつ、「男性」と「女性」の間の「平等」について問われた事例である。
そのため、14条1項の「平等」による審査と、24条2項の「両性の本質的平等」による審査が同時に行われている。
|
あらゆる法制度 個人間の比較 |
「婚姻及び家族」の制度 | ||
|
個人間の比較 |
両性間の比較 | ||
| 14条1項の「平等」 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 24条2項 の「平等」 | × | × | 〇 |
| ↑ | |||
|
夫婦同氏制大法廷判決 再婚禁止期間大法廷判決 |
|||
※ 24条2項は、「婚姻及び家族」の制度で、かつ「両性間」の「平等」が問われた場合にのみ審査することができ、それ以外の場合は審査することができない。
※ 14条1項と24条2項が重なる部分は、「婚姻及び家族」の制度において「両性間」の「平等」が問われている場合のみである。
この場合、24条2項の「平等」に違反すると判断された場合には、同時に14条1項の「平等」にも違反することになる。
ただ、このように審査が重なる場合とは、前提として「婚姻及び家族」の制度について問題となっており、かつ「両性間」の「平等」が問われている場合に限られる。
そのため、「両性間」の「平等」が問われているわけではない場合や、そもそも「婚姻及び家族」の制度に含まれない場合については、審査は重ならない。
この訴訟の事案では、そもそも「婚姻及び家族」の制度に含まれないという点で、24条2項における「平等」を審査する前提を欠いており、それが「両性」であるか否かを問う以前の問題によって審査の対象外となる。
※ 「婚姻及び家族」の制度に含まれない関係について14条1項の「平等」が問われる場合があるとしても、それは「婚姻している者(既婚者)」と「婚姻していない者(独身者)」との間の比較において、「婚姻している者(既婚者)」が婚姻制度の立法目的を達成するための手段として不必要に過大な優遇措置を得るものとなっていないかどうかである。
もし「婚姻している者(既婚者)」が婚姻制度の立法目的を達成するための手段として不必要に過大な優遇措置を得るものとなっていた場合には、その優遇措置に関する規定が個別に失効することによって格差が是正されることになるというものである。
差異の基準点
〇 「区別」による差異の基準点
憲法は「個人の尊厳」の原理に基づいており、自然人は「個人主義」の下に各々「自律的な個人」として生存していくことを予定している。
そして、その個々人は「個人主義」の下に各々「平等」である。
そのため、何らの制度も利用していない状態が基準(スタンダード)である。
そのような中、何らかの目的を達成するための手段として制度を立法し、その制度を利用する者に対して法的効果や優遇措置を設けることがある。
逆に、その制度が定める枠組みに該当しない者については法的効果や優遇措置を設けることはなく、もともとの「個人主義」の下に各々が「自律的な個人」として生存していくことが前提となる。
これがもともとの基準(スタンダード)となる状態だからである。
これにより、「その制度を利用する者」と「その制度を利用しない者」との間に一定の差異が生じることになるが、このような特定の制度が定められることによって生じる差異は、「その制度を利用していない者」が基準点(スタンダード)となって、「その制度を利用している者」がその制度の目的を達成するための手段として不必要に過大な法的効果や優遇措置を得るものとなっていないかという視点によって審査することになる。
そして、「その制度を利用している者」が、「その制度を利用していない者」と比べて、その制度の目的を達成するための手段として不必要に過大な法的効果や優遇措置を得るものとなっていた場合には、「その制度を利用していない者」が基準点(スタンダード)となって、その不必要に過大な法的効果や優遇措置を定めている規定の内容が憲法14条1項の「平等原則」違反することとなり、その規定の内容が個別に失効することによって差異が是正されることになる。
これに対して、「その制度を利用している者」と「その制度を利用していない者」の間に差異が生じていることについて、あたかも「その制度を利用している者」の状態が基準(スタンダード)であるかのような前提に基づいて「不平等」を訴える主張が見られる。
そしてその主張は、「その制度を利用していない者」に対して「その制度を利用している者」と同様の法的効果や優遇措置を設けることによって差異の是正を求めていることがある。
しかし、このような主張は、憲法は「個人の尊厳」の原理に基づいており、自然人は「個人主義」の下に各々「自律的な個人」として生存していくことを前提としており、基準点(スタンダード)となる状態は「その制度を利用していない者」の状態であることを理解していないものであり、誤りである。
また、憲法14条1項の「平等原則」を用いても、現在存在しない数ある法制度の構想の中のいずれかを採用するべきなどという特定の制度を立法することを国会に対して求める形で差異を是正することはできない。
このような主張は、現在存在する法制度が憲法に違反するか否かという問題を超えて、新たな制度の創設を国家に対して求めるものにほかならないのであり、司法権の行使として判断することのできる範囲を超えるものである。
〇 個人と婚姻制度との関係
このことは、婚姻制度についても同様である。
まず、憲法は「個人の尊厳」の原理に基づいており、自然人は「個人主義」の下に各々「自律的な個人」として生存していくことを予定している。
そして、その個々人は「個人主義」の下に各々「平等」である。
そのことから、何らの制度も利用していない状態が基準(スタンダード)である。
そのような中、その社会の中で何らの制度も設けられていない場合には、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合が発生する。
例えば、「父親不明」の子供が増える、父親を特定できない子供が増える、父親が蒸発して行方不明になった子供が増える、それらにより「子の福祉」が減少する、父親を特定できないことにより近親者の範囲を把握できずに「近親交配」に至り潜性遺伝子の発現した個体が高い確率で生じるようになる、一部の強者が多数人との生殖関係を独占することによって社会の中で「子を持ちたいと希望して相手を見つけようとする男女」の数の不均衡が生じて「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」が生まれる、低年齢での妊娠・出産により母体に危険が及ぶ、などの問題が生じることがある。
これらの不都合を解消するために、下記のような立法目的を有する枠組みを設けることが必要となる。
・「子の福祉」が実現される社会基盤を構築すること
・潜性遺伝子の発現した個体が高い確率で生じることを抑制すること
・「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」を減らすこと
・母体を保護すること
そして、これらの目的を達成するためには、下記の要素を満たす枠組みを設けることが必要となる。
・子の遺伝的な父親を特定できる組み合わせとすること
・特定された子の父親にも子に対する責任を担わせること
・特定された子の父親を基に遺伝的な近親者を把握すること
・未婚の男女の数の不均衡を防止できる組み合わせに限定すること
これらの要素を満たすものとして「一人の男性」と「一人の女性」が選び出され、その間に「貞操義務」を設け、その関係を法的に結び付ける形を「婚姻」と呼んでいる。
そして、この制度を利用した場合には一定の法的効果や優遇措置があるという差異を設けることによって、この制度を利用する者を増やし、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成することを目指すものとなっている。
逆に、このような目的を達成するために形成された枠組みに該当しない場合については、そもそも法的効果や優遇措置を設けることは予定されていない。
その場合には、「個人主義」の下に各々が「自律的な個人」として生存していくことが前提となっている。
実際、「婚姻していない者(独身者)」は存在しており、そのような「婚姻していない者(独身者)」の状態こそがもともとの基準(スタンダード)となる状態である。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
厚生労働省の調査によりますと、一人暮らしの世帯数は去年6月時点で1849万5000世帯と全体の34%を占めていて、統計を始めた1986年以来、過去最多となりました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「子どもいる世帯」約983万世帯で過去最少 「一人暮らし」は過去最多 厚生労働省 2024年7月5日
婚姻制度は、婚姻制度を利用する場合と利用しない場合との間に差異を設け、婚姻制度を利用することに対してインセンティブを働かせ、婚姻制度を利用する者を増やすことによって立法目的の達成を目指す仕組みのものである。
そのため、もし「婚姻制度を利用していない者(独身者)」、あるいは「婚姻制度の枠組みの対象とならない人的結合関係を形成している者」に対して法的効果や優遇措置を設けた場合には、婚姻制度を利用することに対してのインセンティブを損ない、その目的を達成するための機能を阻害する影響を与えることになる。
よって、「婚姻制度を利用していない者(独身者)」、あるいは「婚姻制度の枠組みの対象とならない人的結合関係を形成している者」に対しては、意図的に法的効果や優遇措置を定めないことに意味を持たせているという背景も存在する。
そして、もし「婚姻している者(既婚者)」と「婚姻していない者(独身者)」との間を比較して、「婚姻している者(既婚者)」に対して婚姻制度の目的を達成するための手段としては不必要に過大な法的効果や優遇措置を与えるものとなっている場合には、「婚姻していない者(独身者)」が基準(スタンダード)となって、その不必要に過大な法的効果や優遇措置について定めた規定が憲法14条1項の「平等原則」に違反することになり、その不必要に過大な法的効果や優遇措置について定めた規定が個別に失効することによって差異が是正されることになる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
しかしながら、被控訴人としても、本件規定における特定の法的効果(優遇)の内容が婚姻制度の目的との関連で合理性を欠くものであれば、当該効果に係る規定が憲法14条1項に違反すると評価され得る場合があることを否定するものではない。……(略)……
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【札幌・第2回】被控訴人第1準備書面 令和4年3月4日 PDF
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
また、本件諸規定の憲法14条1項適合性を判断するとしても、その判断に当たっては、憲法24条の解釈と整合的に判断する必要があるほか、婚姻及び家族に関する具体的な制度の構築については立法府の合理的裁量に委ねられていることからすると、本件諸規定が憲法14条1項に違反する余地があるとしても、それは、本件諸規定の立法目的に合理的な根拠がなく、又はその手段・方法の具体的内容が立法目的との関連において著しく不合理なものといわざるを得ないような場合であって、立法府に与えられた裁量の範囲を逸脱し又は濫用するものであることが明らかである場合に限られるというべきであるところ、そのような事情が存しないことは、控訴答弁書第4の2ないし4(37ないし57ページ)で詳細に述べたとおりである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【東京一次・第3回】被控訴人第2準備書面 令和6年2月29日 PDF
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
……(略)……控訴人らが、本件諸規定が法律上同性のカップルを「排除」しているとする前提として主張する「婚姻の自由」の内実は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきことを規定する憲法24条2項の要請に従って創設された現行の婚姻制度の枠を超えて、同性間の人的結合関係についても婚姻と同様の積極的な保護や法的な利益の供与を認める法制度の創設を国家に対して求めるものにほかならないのであって、国家からの自由を本質とするものということもできないものである。この点については、仮に本件諸規定が違憲無効であると判断されたとしても、現行の法律婚制度が違憲無効となるだけで、直ちに本件諸規定の下で同性婚が法律上可能となるものではないことをも加味すると、より一層明らかである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【大阪・第6回】被控訴人第2準備書面 令和6年9月25日
これに対して、婚姻制度による法的効果や一定の優遇措置を受けている状態が基準(スタンダード)であるかのような前提に基づいて「不平等」を訴える主張を見ることがある。
そして、その主張は、「婚姻している者(既婚者)」の得ている法的効果や一定の優遇措置と同様ものを、「婚姻していない者(独身者)」、あるいは「婚姻制度の立法目的を達成するための手段として整合的でない人的結合関係を形成している者」に対して設けることによって差異をなくすことを求めていることがある。
しかし、このような主張は憲法が前提としている基準点(スタンダード)を理解しないものであり、誤りである。
また、憲法14条1項の「平等原則」を用いても、現在存在しない数ある法制度の構想の中のいずれかを採用するべきなどという特定の制度を立法することを国会に対して求める形で差異を是正することはできない。
このような主張は、現在存在する法制度が憲法に違反するか否かという問題を超えて、新たな制度の創設を国家に対して求めるものにほかならないのであり、司法権の行使として判断することのできる範囲を超えるものである。
比較する対象の誤り
この東京高裁判決が比較する対象を誤っていることを考えるため、下図で三つの視点を上げる。
これらについて、これより以下で詳しく検討する。
「カップル間不平等論」の誤り
人的結合関係を基に比較してはならないこと
この東京高裁判決では、憲法14条1項の「平等原則」を論じる際に、「異性間の人的結合関係」と「同性間の人的結合関係」のように「二人一組」の人的結合関係を取り上げて、それを一つのまとまりと考えて比較を試みるものとなっている。
これは、一方の「二人一組」と、もう一方の「二人一組」の間で比較を行い、そこに「区別」があるか否かを検討しようとするものである。
しかし、これは比較対象の選択を誤っている。
まず、法律上で比較対象とすることができる事柄は、「権利能力」を有して法主体としての地位を認められている者同士の間だけである。
これを理解するために、下記のような事例については法的な紛争として解決することはできないことを示す。
◇ 「人間」と「亀」は平等か
⇒ 「亀」に「権利能力」はなく、法主体としての地位を認められていない。
◇ 「天国」と「地獄」は平等か
⇒ 特定のフィールドに「権利能力」はない。
◇ 「ソウルメイトの関係」と他の「ソウルメイトの関係」は平等か
⇒ 単位の設定が法律論に基づくものではなく、法律論としてはこのような単位を用いて審査することはできない。これが人的結合関係を指すのであれば、法人格を取得して「権利能力」を有して法主体としての地位を認められていなければ、その人的結合関係を取り上げて審査することはできない。
◇ 「カップル」と「トリオ」は平等か
⇒ 単位の設定が法律論に基づくものではなく、法律論としてはこのような単位を用いて審査することはできない。これが人的結合関係を指すのであれば、それぞれの人的結合関係が法人格を取得して「権利能力」を有して法主体としての地位を認められなければ、その人的結合関係を取り上げて審査することはできない。
これらと同じように、法的な議論として取り扱うためには、前提として「権利能力」を有して法的な主体としての地位を有していることが必要となる。
そして、自然人が「二人一組」の人的結合関係を形成したとしても、それだけでは「権利能力」を取得することにはならず、そこに何らかの法的な主体性を認めることはできない。
そのため、「異性間の人的結合関係」や「同性間の人的結合関係」のように「人的結合関係」を取り上げ、それを一つのまとまりとして持ち出したとしても、法律論としては「権利能力」を有して法主体としての地位を認められているもの同士の関係においてしか法的な審査を行うことはできないのであり、「権利能力」を有していない「人的結合関係」を持ち出して比較しようとする試みそのものが誤っているのである。
そのため、これを法律論上の比較対象として取り上げることはできない。
法律上で「権利」や「義務」を関係づけることができる地位を有するという意味での主体(権利・義務の帰属主体)には、「自然人」と「法人」がある。
そのため、もしそのような形で「人的結合関係」を取り上げてそれを単位として用いたいのであれば、その「人的結合関係」が法人格を取得して「権利能力」を備え、法主体としての地位を認められていることを予め証明することが必要である。
「二人一組」の人的結合関係については、「自然人」ではないことから、法律論上の比較対象として取り上げたいのであれば、この「人的結合関係」が「法人格」を有していることを立証することが求められるのである。
憲法14条の「平等原則」における審査の中でも、「二人一組」の人的結合関係を一つのまとまりとして取り上げた形で比較を行いたいのであれば、先にその「二人一組」の人的結合関係が「権利能力」を有する法主体としての地位を認められていることを示すため、法人格を取得する手続きを行い、「権利能力」を備えて「法人」としての地位を有することを明らかにすることが必要である。
よって、法人の設立手続きや登記の存在を証明しなければならない。
民法には下記のように定められている。
民法
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(法人の成立等)
第三十三条 法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。
2 学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによる。
(法人の能力)
第三十四条 法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「権利能力」(法人格)を有しないのであれば、法主体としての地位を認められていないのであるから、法律論として憲法14条1項の「平等原則」を審査する場合の比較対象(上記の「『平等』の審査方法」の項目の『法の下の平等(B)』のパターン)として取り扱うことはできないのである。
下図で、「権利能力」(法人格)を有する者同士を比較の対象とすることはできるが、「二人一組」(カップル)や「三人一組」(トリオ)など「権利能力」(法人格)を有しない単位を用いて比較することはできないことを示す。
これに対して、この東京高裁判決では、「二人一組」の人的結合関係が「権利能力」(法人格)を有しているかどうかについて何らの立証もしないままに比較対象として取り上げて論じるものとなっている。
しかし、その「二人一組」については、「権利能力」を有していないため法主体としての地位を認められていないのであり、法律論上で比較を行うことのできる対象として取り上げることはできないものである。
そのため、「権利能力」を有しておらず法主体としての地位を認められていない「二人一組」の人的結合関係を取り上げて、それを憲法14条1項の「平等原則」の審査において比較することができるかのような前提で論じ始め、そのまま結論を導こうとしていることは、法的な審査として適正な手順を踏むものとなっておらず、論じ方として誤っている。
このことから、これを前提として特定の結論を述べている部分についても、その結論を正当化することはできない。
▽ 憲法14条1項の「平等原則」における比較の主体となる者
「二人一組」の人的結合関係は、単に「婚姻していない者(独身者)」が集まって人的結合関係を形成しているだけである。
そして、「婚姻している者(既婚者)」との間で比較する対象として取り上げることができるのは、常にその「婚姻していない者(独身者)」としての立場である。
そのため、「婚姻している者(既婚者)」が、「婚姻していない者(独身者)」との間で婚姻制度の立法目的を達成するための手段としては不必要に過大な優遇措置を得るものとなっていないかについて、憲法14条1項の「平等原則」に違反するかどうかが審査されることになる。
そして、もし憲法14条1項の「平等原則」に違反する場合には、「婚姻していない者(独身者)」が基準(スタンダード)となって、「婚姻している者(既婚者)」の得ている不必要に過大な優遇措置に関する規定が個別に失効することによって差異が是正されるというものである。
この審査は、この東京高裁判決が行おうとしている「二人一組」ともう一つの「二人一組」を取り上げるという「カップル間不平等論」による比較ではない。
この判決は、恣意的に「二人一組」の形を選択し、「異性間の人的結合関係」と「同性間の人的結合関係」という人的結合関係を一つのまとまりとして取り上げて比較しようとするのであるが、その人的結合関係は「権利能力」(法人格)を有していないため法的な議論において比較の対象として取り上げることはできないのであり、論じ方として誤っている。
▽ 法人の性質による制限
その他、たとえ法人として「権利能力」を取得したとしても、法人の「権利能力」の性質は自然人に適用されるものとは性質が異なる場合があるため注意が必要である。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法人の権利能力
法律により権利能力(法人格)が認められ、権利義務の主体となることのできるもの(社団または財団)を法人という。法人の権利能力には、以下のような制限がある。
性質による制限
婚姻関係の当事者となるなど、性質上自然人のみが主体となる行為についての権利能力はない。
……(略)……
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
権利能力 Wikipedia (下線は筆者)
「カップル信仰論」に陥ってはならないこと
この東京高裁判決では、「人生の伴侶」という言葉が用いられている。
しかし、このような言葉を用いて論じることができることになれば、下記のように 「カップル」、「パートナー」、「デュオ」、「コンビ」、「バディ」、「ダブルス」、「トリオ」、「相棒」、「仲間」、「ソウルメイト」などの言葉も使うことが可能となってしまうため、妥当でない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
二人組(ふたりぐみ、ににんぐみ)とは、2人から成るグループを指す。人間が組織で活動する際の最小単位であり、様々な分野で見られる。 会話ではふたりぐみ、事件報道では、しばしばににんぐみという読み方が用いられる。分野によっては、デュオ、コンビ[1]、ペア、カップル、バディなどの呼び方も用いられる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
二人組 Wikipedia
関係性を表現する言葉には、「お笑いコンビ」「歌のデュエット」「仕事の相棒」などもある。
・「バディ」という関係がある。
心強い! ダイビングのバディシステム 2016年6月23日
・「ダブルス」もある。
ダブルス Wikipedia
・三人組として「トリオ」がある。
トリオ Wikipedia
・「仲間」という言葉もある。
「お前はおれの仲間だ!!」ルフィがナミに言った名言をワンピース英語版で!! 2014-08-17
・「ソウルメイト」という分類もある。
ソウルメイト Wikipedia
「人生の伴侶」という言葉も含めて、これらは法律用語ではない。
そのため、使う人によってそれぞれ意味するところが異なるものである。
このような言葉の中には、何らかの思想や信条、宗教的な信仰を抱いていることを前提とした用語であるこもあるし、自らの望む結論を導き出すために前提を先取りするために敢えて用いられているという場合もある。
そのため、法律論を論じる際にこのような言葉を安易に用いてはならない。
また、「人生の伴侶」という言葉の用い方を見ても、「二人一組」を前提とするものとなっている。
しかし、根拠もなく「二人一組」の人的結合関係を前提としていることは、なぜ「二人一組」であるのかその根拠を説明しないままに論じる「カップル信仰論」に陥っていることになる。
このような、法律用語ではない言葉を用いてあたかも「二人一組」であるという前提を先取りする形で論じることが可能であるとすれば、「カップル信仰」ではなく、「トリオ信仰」の持ち主が現れた場合には、「トリオの連れ」や「トリオ仲間」などと論じることによって、「三人一組」であるという前提を先取りする形で論じることが可能なってしまうのであり、妥当ではない。
今回の事例においても、法律論として「権利能力」を有する個々の自然人をどのような法律関係によって結び付けるかという視点から論じることが必要である。
それにもかかわらず、法律用語ではない単語を持ち込んで、「二人一組」であるという前提を先取りする形で論じることは、誤った説明である。
「人生の伴侶」という言葉を用いている時点で、それは「二人一組」であることを前提としているものであり、そこには、ある宗教団体の内部でのみ通用している教義や、一定の地域の中でのみ通用している文化に過ぎないものを根拠として前提を先取りしようとする意図が含まれていることが考えられる。
しかし、法解釈を行う際には、そのような宗教的な教義や文化的な背景からは中立的な内容でなければならず、それらの教義や文化を基にして前提を先取りするようなことがあってはならない。
分かりやすく言えば、この判決を書いた裁判官がイスラム教徒であったならば、イスラム教の普及する文化圏で「男性一人と女性四人まで」の一夫多妻型の人的結合関係を形成する者もいることを理解しているはずであるから、安易にここでいう「人生の伴侶」のような「二人一組」を前提とした言葉を用いることはないはずである。
その場合には、一夫多妻制を採用している文化も存在することを前提としながら、日本法における法制度として「権利能力」を有して法主体としての地位を認められている個々の自然人をどのような法律関係で結び付けるかというという観点によって論じるはずである。
これを考えれば、「二人一組」という前提そのものが特定の国々や特定の文化圏に存在する法制度のみを前提として考えるというバイアスのかかったものであることは容易に理解することができる。
この判決が「人生の伴侶」という言葉を用いて、「二人一組」であるという前提に基づいて論じていることは、この判決を書いた裁判官が「二人一組」を前提とした法制度を採用している国々や特定の文化圏、ロマンティック・ラブ・イデオロギーなどの法制度とは別に形成された何らかの文化、この裁判官が属している何らかの宗教団体の教義などを根拠として考えてしまっていることを露顕するものとなっているといえる。
このような論じ方をしていること自体が、既に法律論とは異なる認識を基にして論じようとするものとなっており、妥当ではない。
よって、「人生の伴侶」という言葉を用い、「二人一組」であることを根拠もなく前提としている論じ方は、法律論としては誤った色眼鏡をかけたままに論じるものということができ、結論を導き出すまでの判断の過程が誤っていることになる。
▽ 法的な概念ではないもの用いて論じることの問題姓
法的な審査を行う場面では、「人生の伴侶」などと法的な概念ではなく、個々人の価値観や人生觀、ライフスタイルの在り方に基づく言葉を用いて論じるようなことをしてはならない。
このような言葉は、下記のように一夫多妻制を望む者が、「運命の出逢いは一度とは限らない」などと述べているものと変わらないものである。(運命の相手論)
【参考】「【公約】 「一夫多妻制(多夫多妻制)」の実現」 Twitter
【参考】「advocating polygamy to solve Japan's declining birthrate.」 Twitter
このような、個々人の価値観や人生觀、ライフスタイルの在り方に基づく表現は、法的な議論として扱うことができるとする前提を欠くものである。
この点の、法的な議論の中で扱うことのできる概念と、そうではない概念を切り分けることが必要である。
また、法的な概念ではないとしても、「伴侶」という言葉の語源から考えても、これは一夫一婦制の婚姻制度を前提とするものである。
そのため、この言葉を「同性間の人的結合関係」に対しても同様の意味として用いることができるかどうかについては議論があるものと思われる。
▽ 「二人一組」が導き出される原因
この東京高裁判決では、「二人一組」を前提として論じるものとなっている。
しかし、そもそも「二人一組」という前提の下で論じていること自体が、既に現在の婚姻制度によって創設された枠組みを前提とした考え方に基づく主張であるといえる。
まず、憲法は「個人の尊厳」の原理に基づいており、自然人は「個人主義」の下に各々「自律的な個人」として生存していくことを予定している。
そのような中、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する形で婚姻制度を設けることになる。
具体的には、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」を目的として、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす「一人の男性」と「一人の女性」を選び出し、その間に「貞操義務」を設けるなど一定の形式で法的に結び付け、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によってそれらの目的の達成を目指す枠組みを設けるものである。
これは、人間の有性生殖の仕組みに着目する形で異なる性別の二者を選び出して形づくられている枠組みである。
そのため、このように人間の有性生殖の仕組みに着目して組み合わせを選び出す形で婚姻制度の枠組みが設けられる以前においては、個々の人間が形成する人的結合関係が「二人一組」でなければならないとの前提は存在していない。
つまり、様々な人的結合関係の可能性の中から婚姻制度の枠組みが「二人一組」の形で作られたことの背景にある目的とその目的を達成するための手段の関係がどのように形成されているかという部分を見ることなく、「二人一組」となっていることの根拠を見出すことはできないということである。
他国の場合では、一人の男性と四人の女性による「一夫多妻制」(複婚)が採用されている場合もあり、そのような国では「二人一組」を前提として考えること自体が成り立たないことは容易に理解することができる。
それにもかかわらず、「二人一組」という形が前提となるかのように取り上げて、それを比較対象として持ち出して論じていることは、その背景に、現在ある婚姻制度の枠組みの一側面のみを、その制度が設けられている目的との整合性を勘案しないままに根拠なく切り取り、それが婚姻制度の枠組みが設定される以前から存在する絶対的な単位であるかのように理解しているということになる。
つまり、現在の婚姻制度が「男女二人一組」の枠組みとなっていることを前提とし、その婚姻制度の枠組みが形づくられている背景にある目的とその立法目的を達成するための手段の関係を考えないままに、その枠組みの中から恣意的に「二人一組」という部分のみに着目する形で抜き出し、その数字の部分だけが前提となるかのように取り上げて論じようとしているのである。
しかし、このような、なぜ「二人一組」であるのかその根拠を説明しないままに論じるものは、根拠のない前提を絶対的なものであるかのように言い張ろうとするものであるから、前提となる認識の部分において「カップル信仰論」に陥っているということができ、法律論として妥当なものではない。
「二人一組」という枠組みを前提として論じていること自体が、既に婚姻制度の枠組みが存在することに依存して成り立つ考え方となっているのであり、婚姻制度がどのような立法目的を有しており、その達成手段としてどのような枠組みを定めているかという問題を離れては成り立たないものである。
つまり、これは婚姻制度が様々な人的結合関係の可能性の中から、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」を目的とし、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たすものとして、人間の有性生殖の仕組みに着目する形で異なる性別の二者を選び出すものとして「男女二人一組」という枠組みを定めていることに起因するものである。
また、どちらかといえば、婚姻制度の枠組みが組み立てられている背景にあるものは、人間の有性生殖の仕組みと対応するものとして「男性」と「女性」が揃うことが先にあり、それを満たすことを前提としてそこに付随する形で「二人一組」の部分が後から枠付けられるという関係にあるものであり、この先にある有性生殖の部分を抜きにして「二人一組」という部分のみが単独で成立することができるという関係にあるわけではない。
そのことから、このような婚姻制度の立法目的とその目的を達成するための手段として設けられている枠組みとの関係を離れて、根拠もなく「二人一組」という枠組みが婚姻制度が形成される以前の揺るぎない絶対的なものとして存在しているかのように考えることはできない。
よって、そのような考えに基づいて「二人一組」という形が前提となっているかのように取り上げて、それを比較対象として持ち出して論じること自体が不当であるといえる。
【参考】私たちは「重婚」を認められるか…?「同性婚」問題の先に浮かび上がる「多様性をめぐる根本的な難点」 2023.06.27
「異性と婚姻できるが同性と婚姻できない不平等論」の誤り
婚姻が成立するための「条件」
ある組み合わせにおいては「婚姻」することができるが、ある組み合わせにおいては「婚姻」することができない。
これは、婚姻を成立させるための要件が定められていることによるものであり、「条件」ということができる。
下図は、立法目的を達成するための手段として設けられた「婚姻」という制度を利用する場合の「条件」である。
婚姻制度を利用するための「条件」を満たしているのであれば、個々人は平等に婚姻制度を利用することができる。
ここで、個々人を「区別」しているという事実はない。
この「条件」に従った形で「婚姻」することができる場合の組み合わせと、「条件」を満たさずに「婚姻」することができない場合の組み合わせを下図に示す。
次に、婚姻の「条件」の内容について、これが個々人について「区別」をするものと考えるべきなのかを検討する。
〇 比較の対象は「個人」であること
憲法は「個人の尊厳」の原理に基づいており、自然人は「個人主義」の下に各々「自律的な個人」として生存していくことを予定している。
そのため、法的な主体となることのできる地位(権利・義務を関係づけることができる地位)は、「個人」に属する。
これにより、憲法上で比較を行う際の主体となるのは、「個人」と別の「個人」との間である。
憲法14条の「平等原則」についても、その性質は「個人権」であり、「個人と個人の間の平等」をいう。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ア しかしながら,憲法14条1項が規定する法の下の平等とは,個人と個人の間の平等をいい,同項が禁止する不合理な差別も,個人と他の個人との間の不合理な差別をいうものと考えられる(例えば,芦部信喜教授は,法の下の平等は「個人権」であり,「個人尊重の思想に由来」すると説明している(芦部信喜〔高橋和之補訂〕「憲法第七版」129 ページ)。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【大阪・第6回】被告第4準備書面 令和3年2月19日 PDF (P4)
婚姻制度は「男女」「近親者等でない」「二人一組」「婚姻適齢」の条件を満たすことを求めている。
この条件の中で、個々人が婚姻制度を利用することができるか否かについて検討する。
◇ 身長の高い人:婚姻することができる
◇ 身長の低い人:婚姻することができる
→ ここに「身長」による「区別」は存在しない。
◇ 年収の多い人:婚姻することができる
◇ 年収の少ない人:婚姻することができる
→ ここに「年収」による「区別」は存在しない。
◇ 生殖能力のある人:婚姻することができる
◇ 生殖能力のない人:婚姻することができる
→ ここに個々人の「生殖能力」による「区別」は存在しない。
(これは、個々人の個別特性としての生殖能力の有無であり、人と人とを組み合わせた場合に生殖可能性のある組み合わせとなるか否かを問うものではない。そのため、婚姻制度の内容が一般的・抽象的に自然生殖可能性のある組み合わせを対象として制度を設けていることについては、これとは別の論点である。)
◇ 婚姻適齢を満たしている者:婚姻することができる
◇ 婚姻適齢を満たしていない者:婚姻することができない
→ ここに「年齢」による「区別」が存在する ⇒ 合理的な理由の存否の判断へ
◇ 男性:「異性」と婚姻することができるが、「同性」と婚姻することができない
◇ 女性:「異性」と婚姻することができるが、「同性」と婚姻することができない
→ ここに男女の「性別」による「区別」は存在しない
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
しかしながら,憲法14条1項が規定する法の下の平等とは,同一の事情と条件の下では均等に取り扱うことを意味すると解されるところ(芦部信喜〔高橋和之補訂〕「憲法第七版」132ページ参照),本件規定の下では,男性も女性も異性とは婚姻をすることができる一方で,どちらの性も同性とは婚姻をすることは認められていないのであるから,本件規定が性別を理由に差別的取扱いを生じさせていると評価することはできない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【東京二次・第3回】被告第2準備書面 令和3年11月30日 PDF
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被告第2準備書面第5の2(2)エ(ア)(34及び35ページ)における主張は、男性と女性の間の差別を念頭に置いたものである。上記主張における「性別」は、原告らが「生物学的な特徴をもとに割り当てられることとされている」性別として主張する性別(法律上の性別)(訴状15ページ)上の男性と女性の区別を主張するものであり、男性間又は女性間の区別は憲法14条1項の「性別」による「差別」には当たらない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【東京二次・第5回】被告第3準備書面 令和4年6月30日 PDF
◇ 男性:婚姻している場合に、別の人と重ねて婚姻することはできない
◇ 女性:婚姻している場合に、別の人と重ねて婚姻することはできない
→ ここに男女の「性別」による「区別」は存在しない
◇ 男性:「婚姻適齢に満たない者」と婚姻することができない
◇ 女性:「婚姻適齢に満たない者」と婚姻することができない
→ ここに男女の「性別」による「区別」は存在しない
◇ 男性:婚姻の際に相手方の「女性」の「氏」を選べる
◇ 女性:婚姻の際に相手方の「男性」の「氏」を選べる
→ ここに男女の「性別」による「区別」は存在しない
◇ 男性:「再婚禁止期間」は存在しない
◇ 女性:「再婚禁止期間」が存在する場合がある
→ ここに男女の「性別」による「区別」が存在する ⇒ 合理的な理由の存否の判断へ
このように、憲法14条1項の「平等原則」の審査では、「権利能力」を有して法主体としての地位を認められている個々の自然人を単位として考えることが必要である。
そのため、上記のような「個人」と別の「個人」との間で「区別」(異なる扱い)がある場合に、それを審査することになる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
また、本件諸規定の憲法14条1項適合性を判断するとしても、その判断に当たっては、憲法24条の解釈と整合的に判断する必要があるほか、婚姻及び家族に関する具体的な制度の構築については立法府の合理的裁量に委ねられていることからすると、本件諸規定の立法目的に合理的な根拠がなく、又はその手段・方法の具体的内容が立法目的との関連において著しく不合理なものといわざるを得ないような場合であって、立法府に与えられた裁量の範囲を逸脱し又は濫用するものであることが明らかである場合に限られるというべきであるところ、そのような場合に当たらないことは、被控訴人第1準備書面第3の3ないし5(22ないし48ページ)で詳細に述べた通りである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【大阪・第6回】被控訴人第2準備書面 令和6年9月25日
〇 「人的結合関係」を単位として比較することはできないこと
「男女二人一組」の組み合わせは婚姻することができるが、それ以外の組み合わせでは婚姻することができない。
○ 一定の条件を満たした「男女二人一組」
× 近親者との人的結合関係
× 三人以上の人的結合関係
× 三人一組の人的結合関係
× 四人一組の人的結合関係
× 五人一組の人的結合関係
× 六人一組の人的結合関係
× __人一組の人的結合関係
× 婚姻適齢に満たない者との人的結合関係
× 同性同士の人的結合関係
これは、「婚姻」の対象となる範囲を論じるものである。
このような婚姻制度の対象となる人的結合関係の範囲が限られていることは、婚姻制度がその立法目的を達成するための手段として整合的な形(統一的な理念に従って一般的・抽象的・定型的・画一的に規格化された形)で枠組みを設けていることによるものである。
そして、誰もが「近親者」「二人以上の者」「婚姻適齢に満たない者」「同性の者」との間で婚姻することはできないことに違いはないことから、その「誰も」にあたる個々人に着目して「区別」をしているという事実はない。
よって、憲法14条1項の「平等原則」は、「区別」がないものを審査することはできないことから、結果として、憲法14条1項の「平等原則」に違反するということにはならない。
また、上記のような婚姻制度の対象となる人的結合関係と、対象とならない人的結合関係が存在することについても、憲法14条1項の「平等原則」において「区別」を審査することができるのは、常に「権利能力」を有して法主体としていの地位を認められている者と、もう一方の「権利能力」を有して法主体としての地位を認められている者との間であることから、このような「権利能力」を有して法主体としての地位を認められているわけではない人的結合関係を取り上げたとしても、それを憲法14条1項の「平等原則」の審査における「区別」(個々人の間の区別)と考えることはできない。
よって、このような制度の対象となる人的結合関係と、制度の対象とならない人的結合関係が存在するということそのものについては、憲法14条1項の「平等原則」の審査における「区別」(個々人の間の区別)とはいえず、「区別」がないものを審査することはできないことから、結果として、憲法14条1項の「平等原則」に違反するということにもならない。
その他、この訴訟で問われている「同性間の人的結合関係」については、「婚姻」という概念そのものに含めることのできる人的結合関係の範囲には内在的な限界があることから「婚姻」とすることはできないし、憲法上の規定で定められていることが同一の憲法上の他の規定との間で矛盾するということにはならないことから、憲法24条が「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めている部分については、憲法14条1項の「平等原則」によって審査する対象とはならないものである。
このため、この意味でも憲法14条1項の「平等原則」に違反するということにはならない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) しかしながら、被控訴人第1準備書面第3の2(2)(21及び22ページ)で述べたとおり、憲法24条1項の定める婚姻が異性間の人的結合関係のみを対象とするものとして本件諸規定により制度化され、他方、同性間の人的結合関係を対象とするものとして制度化されず、同性間で婚姻することができない事態が生じることは、憲法自体が予定し、かつ許容するものであるから、このような事態(差異)が生じることをもって、本件諸規定が憲法14条1項に違反すると解することはできない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【大阪・第6回】被控訴人第2準備書面 令和6年9月25日
「性愛に基づく不平等論」の誤り
「性愛」による区別取扱いは存在しないこと
婚姻制度は「性愛」を保護することを目的とする制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いをする制度ではないし、「性愛」に基づいて制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもない。
そのため、婚姻制度は「性愛」による区別取扱いをする制度であるとはいえない。
この点について、国(行政府)は下記のように説明している。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
しかしながら,法律の規定が特定の事由に基づく区別により法的取扱いを異にしているか否かについては,結果(実態)として生じている,又は生じ得る差異から判断するのは相当でなく,当該規定の趣旨・内容や在り方から客観的に判断するのが相当である。この点,夫婦同氏制を定める民法750条の規定の憲法14条1項適合性が争われた平成27年夫婦別姓訴訟最高裁判決も,民法750条の規定が「その文言上性別に基づく法的な差別的取扱いを定めているわけではなく,本件規定(引用者注:民法750条)の定める夫婦同氏制それ自体に男女間の形式的な不平等が存在するわけではない。」,「夫婦となろうとする者の間の個々の協議の結果として夫の氏を選択する夫婦が圧倒的多数を占めることが認められるとしても,それが,本件規定の在り方自体から生じた結果であるということはできない。」と判示し,上記の考え方に沿う判断を示している。また,国籍法(平成20年法律第88号による改正前のもの。)3条1項の規定の憲法14条1項適合性が争われた最高裁平成20年6月4日大法廷判決・民集62巻6号1367ページ,民法(平成25年法律第94号による改正前のもの。)900条4号ただし書前段の規定の憲法14条1項適合性が争われた最高裁平成7年7月5日大法廷判決・民集49巻7号1789ページ及び最高裁平成25年9月4日大法廷判決・民集67巻6号1320ページ,民法(平成28年法律第71号による改正前のもの。)733条1項の規定の憲法14条1項適合性が争われた再婚禁止期間違憲判決等も,上記の考え方を当然の前提としているものと解される。
このような観点から本件諸規定をみると,本件諸規定は,その文言上,婚姻の成立要件として当事者に特定の性的指向を有することを求めたり,当事者が特定の性的指向を有することを理由に婚姻を禁じたりするものではなく,その趣旨・内容や在り方自体が性的指向に応じて婚姻制度の利用の可否を定めているものとはいえないから,性的指向について中立的な規定であるということができる。そうであるとすると,本件諸規定は,区別の事由を性的指向に求めているものと解することは相当でない。本件諸規定から,結果として同性愛者がその性的指向に合致する者と婚姻することができないという事態が生じ,同性愛者と異性愛者との間に性的指向による差異が生じているとしても,それは,性的指向につき中立的な本件諸規定から生じる事実上の結果ないし間接的な効果にすぎないというべきである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【大阪・第9回】被告第5準備書面 令和3年9月24日 PDF (P12)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(イ) 本件規定は、性的指向に基づいて差別的取扱いを生じさせるものではないこと(前記②の主張に対する反論)
被告第4準備書面第3の2(2)エ(25ないし27ページ)において述べたとおり、法律の規定が特定の事由に基づく区別により法的取扱いを異にしているか否かは、当該規定の趣旨・内容や在り方から客観的に判断すぺきであって、結果(実態)として生じている、又は生じ得る差異から判断するのは相当でない。
このような観点から本件規定をみると、本件規定は、一人の男性とー人の女性との問の婚姻を定めるものであり、その文言上、婚姻の成立要件として当事者に特定の性的指向を有することを求めたり、当事者が特定の性的指向を有することを理由に婚姻を禁じたりするものではなく、その趣旨・内容や在り方自体が性的指向に応じて婚姻制度の利用の可否を定めているものとはいえないから、性的指向について中立的な規定であるということができる。さらに、本件規定は、異性間の婚姻を前提とする憲法24条の規定を受けて定められたものである上、本件規定の淵源は、被告第4準備害面第3の2(3)ウ(7)(37及び38ページ)において述べたとおり、我が国において、ー人の男性と一人の女性の人的結合関係が、今後の社会を支える次世代の子を産み、育みつつ、我が国の社会を構成し、支える自然的かつ基礎的な集団単位である家族をその中心となって形成しているという実態があって、当該実態に対して歴史的に形成されてきた社会的な承認が存在していることを背景に、男女間の結合としての婚姻の慣習が法制度化されたことにあるところ、そのような経緯で成立した本件規定の立法目的である「一人の男性と一人の女性が子を産み育てながら共同生活を送るという関係に対して特に法的保護を与えること」は、それ自体、性的指向に着目して法的な差別的取扱いを生じさせることを趣旨として含むものではなく本件規定が性的指向について中立的なものであることは明らかである。そうであるとすると、本件規定が区別の事由を性的指向に求めているものと解することは相当ではない。多種多様な人的結合関係のうち、本件規定が一人の男性と一人の女性の人的結合関係について婚姻を認める結果として同性愛者がその性的指向に合致する者と婚姻をすることができないという事態が生じ、同性愛者と異性愛者との間に性的指向による差異が生じているとしても、それは、性的指向につき中立的な本件規定から生じる事実上の結果ないし間接的な効果にすぎないというべきであり、性的指向に基づいて差別的取扱いを生じさせるものと評価することは相当ではない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【九州・第9回】被告第5準備書面 令和4年6月16日 PDF (P16)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
また、本件規定は、異性間の婚姻を前提とする憲法24条の規定を受けて定められたものである上、本件規定の淵源は、被告第2準備書面第5の2(3)イ(ア)(42及び43ページ)で述べたとおり、我が国において、一人の男性と一人の女性の人的結合関係が、今後の社会を支える次世代の子を産み、育みつつ、我が国の社会を構成し、支える自然的かつ基礎的な集団単位である家族をその中心となって形成しているという実態があって、当該実態に対して歴史的に形成されてきた社会的承認が存在していることを背景に、男女間の結合としての婚姻の慣習が法制度化されたことにあるところ、そのような経緯で成立した本件規定の立法目的である「一人の男性と一人の女性が子を産み育てながら共同生活を送るという関係に対して特に法的保護を与えること」は、それ自体、性自認や性的指向に着目して法的な差別取扱いを生じさせることを趣旨として含むものではなく本件規定が性自認や性的指向について中立的なものであることは明らかである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【東京二次・第5回】被告第3準備書面 令和4年6月30日 PDF
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
他方,原告らの主張が,個々の国民という個人を主体とする法令上の区別をいうものと解したとしても,被告第2準備書面第3の3 (1)イ(21ページ)で述べたとおり,本件規定は,制度を利用することができるか否かの基準を,具体的・個別的な婚姻当事者の性的指向の点に設けたものではなく,本件規定の文言上,同性愛者であることに基づく法的な差別的取扱いを定めているものではないから,この点に法令上の区別は存在しない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【大阪・第6回】被告第4準備書面 令和3年2月19日 PDF
内心による区別取扱いの違憲性
特定の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的とした制度を立法した場合には違憲になる。
また、人の内心に着目して区別取扱いを行う制度を立法することも違憲になる。
上図のように、特定の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的として制度を立法すると違憲になる。
そのため、婚姻制度を立法する際にも、特定の思想・信条・感情を保護することを目的とする場合には、違憲になる。
これに対して、この東京高裁判決では、婚姻制度について「性的指向」による「区別」をする制度であると論じている。
しかし、もし婚姻制度が「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかという「性的指向」を審査して、その審査の結果に基づいて「区別」するような内容であった場合には、そのこと自体が憲法14条1項に違反することになる。
また、婚姻制度が特定の「性愛」を保護することを目的として定められていることになるから、憲法20条1項後段・3項、89条の「政教分離原則」に違反することになる。
他にも、婚姻制度を利用する者に対して「性愛」に基づいて利用することを求めたり勧めたりする制度ということになり、国家が個人の内心に対して介入するものとなるから、憲法19条の「思想良心の自由」、憲法20条1項前段の「信教の自由」に違反することになる。
そのため、もし婚姻制度が「性的指向」による「区別」をするものであり、そのような目的を含める形で定められているのであれば、そのこと自体を違憲としなければならないものである。
それにもかかわらず、その「性愛」を保護することを目的とした制度を拡大するべきであるとか、同様の制度を別に設けるべきであるなどと述べていることは、法制度が思想、信条、信仰、感情に対して中立性を保たなければならないということを理解していないものであり、誤りである。
そのため、むしろこの判決が婚姻制度について「性的指向」による「区別」をする制度であると示してあたかも「性愛」と関わる形で定められているかのように論じている内容こそが、憲法に違反するものである。
「不利益」を前提とすることの誤り
この東京高裁判決では「不利益」との言葉が用いられ、その「不利益」があることを前提として憲法に違反するか否かの判断を試みるものとなっている。
しかし、法的な意味において「不利益」といえるものが存在しているかを検討することが必要である。
〇 婚姻制度の性質
「不利益」が存在するか否かを判断する際には、基準となる地点がどこにあるかを検討することが必要である。
なぜならば、基準点を下回った場合には「不利益」が見出される場合があるが、基準点を下回っていないのであればそこに「不利益」があるとはいえないからである。
そこで考える必要があるのは、「婚姻」における法的効果や優遇措置の性質である。
「婚姻」における法的効果や優遇措置は、法制度によって定められたものである。
逆にいえば、法制度が存在しない場合には、「婚姻」における法的効果や優遇措置は存在しないということである。
そのことから、「婚姻」における法的効果や優遇措置は、個々人が前国家的に有している自由や権利(生来的な自然権)とは異なるものといえる。
そのため、「婚姻」における法的効果や優遇措置の性質は、「国家からの自由」という「自由権」として保障される性質の自由や権利ではなく、法制度の創設によって初めて具体的に捉えられるものである。
そして、「婚姻」の枠組みは、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する形で設けられているものである。
具体的には、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」を目的として、その目的との関係で整合的な要素を満たす「一人の男性」と「一人の女性」を選び出し、その間に「貞操義務」を設けるなど一定の形式で法的に結び付け、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によってそれらの目的の達成を目指すものである。
そして、その「婚姻」の枠組みに対して法的効果や一定の優遇措置を設けることで、婚姻制度を利用することに対してインセンティブを働かせ、婚姻制度を利用する者を増やすことによってそれらの目的の達成を目指すことになるものである。
憲法24条は「婚姻」を規定しており、「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めており、このような枠組みによって「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成することを目指すことを「要請」しているのであるから、婚姻制度の対象となる場合とならない場合があることは初めから予定されているといえる。
〇 「個人」の状態について「不利益」があるとはいえないこと
そこで、婚姻制度の対象となっていない場合で、「婚姻制度を利用していない者(独身者)」の状態であることについて、「不利益」であるとの主張について検討する。
憲法は「個人の尊厳」の原理に基づいており、自然人は「個人主義」の下に「自律的な個人」として生存していくことを予定している。
そのため、何らの制度も利用していない者の状態で既に完全な状態であり、そこに「不利益」と称されるものはない。
当然、「婚姻制度を利用していない者(独身者)」の状態が基準(スタンダード)となるものであり、その状態について、何らの「不利益」と称されるものはない。
実際に日本国内には「婚姻制度を利用していない者(独身者)」として生活している者がいるのであり、その者の状態について「不利益」といわれるものは存在しない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
厚生労働省の調査によりますと、一人暮らしの世帯数は去年6月時点で1849万5000世帯と全体の34%を占めていて、統計を始めた1986年以来、過去最多となりました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「子どもいる世帯」約983万世帯で過去最少 「一人暮らし」は過去最多 厚生労働省 2024年7月5日
よって、「婚姻制度を利用していない者(独身者)」の状態であることについて、「不利益」が生じているとの前提で論じることは誤りである。
また、その「不利益」のない「婚姻制度を利用していない者(独身者)」が人的結合関係を形成したとしても、その段階で初めて「不利益」が生じるかのように述べることも、基準点(スタンダード)が個人であることを押さえていないものであり、誤りである。
よって、その「婚姻制度を利用していない者(独身者)」の状態について「不利益」があるとの前提で論じることは誤りである。
他にも、婚姻制度は、「婚姻制度を利用していない者(独身者)」の有している「国家からの自由」という「自由権」に対する具体的な侵害行為について定めているものでもない。
そのため、この点から見ても、その「婚姻制度を利用していない者(独身者)」の状態であることについて、「不利益」が存在するということにはならない。
〇 「婚姻」は差異を設けることを前提とした制度であること
そもそも「婚姻」とは、一定の枠組みを定めて対象者の範囲を限定し、その対象となる場合に対して法的効果や一定の優遇措置を設け、その対象とならない場合に対して法的効果や優遇措置を設けないという差異を生じさせることによって、婚姻制度を利用することに対してインセンティブを働かせ、それにより婚姻制度を利用する者を増やし、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成することを目指す制度である。
そのため、婚姻制度が一定の枠組みを定めて対象者の範囲を限定しており、その範囲に含まれない場合があるということは、その性質上予定されていることである。
このように、婚姻制度の対象となる場合とならない場合があり、そこに差異が生じるということは、婚姻制度そのものの性質上初めから予定されていることであり、それに対して「不利益」と表現することは誤りである。
よって、法律論としては、婚姻制度を利用していない状態について何ら「不利益」と称されるものはないのであり、この東京高裁判決が「不利益は重大なものである。」のように「不利益」があることを前提として論じていることは誤りである。
また、これを「不利益」と考えることを理由として憲法に違反するということにもならないものである。
〇 対象となる範囲を限定することで目的の達成を目指す制度であること
あらゆる法制度には「目的」が存在し、その「目的を達成するための手段」として定められているものである。
そのため、ある目的をもって定められている法制度について、その対象となる場合とならない場合との間に差異が生じることは初めから予定されていることである。
例えば、「公務員」としての身分を有する者や「弁護士」としての資格を有する者と、それらを有しない者との間では、法的効果や得られる利益の内容に差異が生じることになる。
これは「公務員」や「弁護士」の制度を定めている立法目的を達成するための手段として整合的な形で法的効果や得られる利益の内容を定めていることによるものである。
このような制度を利用する者と利用しない者との間で何らかの差異が生じるとしても、そのことをもって「公務員」や「弁護士」の制度としての目的を達成するための手段として整合的でない者に対して、「公務員」や「弁護士」としての法的効果や利益を与えなければならないということにはならない。
このように、特定の目的をもって定められている制度を利用する者と利用しない者との間で差異が生じるとしても、それはその制度を利用していない者が「不利益」を受けているということにはならない。
また、その「不利益」があることを前提として、特定の目的をもって定められている制度を利用する地位にあり、実際に利用している者が得ている法的効果や得ている利益の内容を、その制度を利用する地位にない者や、その制度を利用していない者に対して与えなければならないということにはならない。
このことは、婚姻制度においても同様である。
婚姻制度の対象となる場合とならない場合に差異があり、その婚姻制度の対象とならない場合や、「婚姻制度を利用していない者(独身者)」の状態であることについて、「不利益」と称されるものが存在するとはいえない。
また、その「不利益」があることを前提として、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成するための手段として統一的な理念の下に定められている婚姻制度における法的効果や優遇措置の内容を、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たさない者(人的結合関係)に対して与えなければならないということにはならない。
そのため、「婚姻制度を利用していない者(独身者)」の状態であることについて、そこに「不利益」があることを前提として憲法に違反するということにはならないものである。
(「そもそも法律は要件を設けて人を区別するためにある」ことについて参考。)
【動画】シンポジウム 国葬を考える【The Burning Issues vol.27】 2022/09/25
〇 制度に対する不満は憲法違反の理由にはならないこと
上記で述べたように、「婚姻制度を利用していない者(独身者)」の状態であることについて、法的な視点から客観的に考えると何らの「不利益」と称される状態にあるとはいえないものである。
そのため、「不利益」との主張があるとしても、それは結局、法制度が自己の望み通りの形となっていないことに対する不満や憤りの感情を表現しているという以外にないものである。
このような法制度が自らの望む形で定められていないことに対する不満や憤りの気持ちをどのように考えるかについては、下記が参考になる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
このように、原告らの主張は、結局のところ、自らの思想、信条、政治的見解等と相容れない内容である本件各行為が行われたことにより、精神的な苦痛を感じたというものであるところ、多数決原理を基礎とする代表民主制を採用している我が国においては、多様な意見を有する国民が、表現の自由、政治活動の自由、選挙権等の権利を行使し、それぞれの立場・方法で国や政府による立法や政策決定過程に参画した上で、最終的には、全国民の代表者として選出された議員により組織される国会において個々の法令が制定されるのであるから、その結果として、ある個人の思想、信条、政治的見解等とは相容れない内容の法令が制定されることは、全国民の意見が一致しているというおよそ想定し難い場面以外では、不可避的に発生する事態である。そうすると、自らの思想、信条、政治的見解等とは相容れない行為が行われたことで精神的苦痛を感じたとしても、そのような精神的苦痛は社会的に受忍しなければならないものというほかない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
国家賠償請求事件 高知地方裁判所 令和6年3月29日 (PDF)
このように、民主主義の下では当然、そのような自らの望む形で法制度が定められていないという事態が生じることは予定されていることである。
そのため、このような事柄を述べたとしても、これは憲法上の条文を用いて下位の法令の内容を無効としたり、特定の制度を創設するように国家に対して求めることができるとする根拠となるものではない。
よって、婚姻制度の対象となっていない場合について取り上げたとしても、それを法的な視点から考えれば「不利益」ということにはならないのであり、それを憲法に違反すると結論付けるための根拠として用いることができるということにはならないものである。
法制度というものがもともと上記で述べたような性質であることを踏まえれば、婚姻制度の内容について不満や憤りの感情を持つ者がいるとしても、それは結局、婚姻制度が「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的の下に定められ、その目的を達成するための手段として整合的な範囲の人的結合関係に対して法的効果や一定の優遇措置が与えられ、その制度の対象とならない場合との間に差異が生じることになるという事実に対する評価として不満や憤りの感情を抱いたり、気に食わないという気持ちを抱いているという意味に収束するといえるものである。
どのような法制度を立法しても不可避的に何らかの差異が生じることになるのであり、その制度を利用する者に対して不満や憤りの感情を抱くことがあるとしても、そのことがその制度の内容に合理性がないことを根拠付ける理由とはならないものである。
他にも、もし個々人がある特定の社会集団の中で生活する中において強い不満や憤りの感情、不快感を抱くような出来事があるとしても、それが不法行為によるものではないのであれば法的に是正する対象とはならないし、特定の組織の中で設けられているガイドラインに照らしてハラスメントに認定されるものでないのであればその組織で用いられているガイドラインによって対応する対象ともならない。
また、実際に不法行為やハラスメントが行われているのであれば、不法行為やハラスメントとして解決することが適切な手段となるのであって、そのような事情があったことを理由として直ちに法制度そのものを合理性がないものとみなすことのできる事情となるわけではない。
まして、その法制度が憲法に違反するとの事情を基礎づける理由となることもない。
よって、そのような事情を根拠として憲法に違反するなどと論じることは誤りである。
(選択的夫婦別氏制を求める主張の事例であるが、このような側面について参考。)
【参考】「推進派は、」……「パトリアーキー(家父長制)やその意識という架空の敵と戦っているというイデオロギー的側面がある」 Twitter
〇 特定の制度の創設を国家に対して求める主張は憲法違反の理由にはならないこと
「不利益」という言葉で表現されているものは、ある個人が特定の法制度を利用しようと考えた場合に、その個人にとってその法制度が自らの望む形で定められていないことを理由に思い通りとはならず、その法制度の利用を控えるという場合について、その者個人の受け止め方として「不利益」などと表現しているものである。
しかし、法制度は立法目的を達成するための手段として定められるものであり、制度が政策的なものである以上は、その制度が自らの望む形で定められていないという事態が起こり得ることはもともと予定されていることである。
その状態を法的な視点から客観的に捉えた場合には、その者個人が「不利益」を受けているということにはならない。
そのため、ここで「不利益」という表現を用いている背景には、法制度が自らの望む形で定められている状態を完全な状態と捉えた上で、現在の法制度がその状態に至っていないという認識を基にして、その完全な状態と設定したゴールまでの距離(その間の差の部分)を「不利益」と呼ぼうとする動機が含まれていることになる。
◇ この判決の認識
自らの望む法制度(ゴール)
↑
↑ (この差異を『不利益』と表現している。)
↑
現在地点
しかし、法的な視点から見れば、憲法は「個人の尊厳」の原理に基づいており、自然人は「個人主義」の下に各々「自律的な個人」として生存していくことを予定していることから、法制度を利用していない状態で既に完全な状態ということができ、「不利益」は存在してない。
◇ 法律論として客観的な視点
現在地点 ← (法制度がない状態で既に完全であり、『不利益』は存在しない)
そのため、その者が「不利益」と表現している場合があるとしても、それは自らの望む形で法制度が定められている状態をゴールと考えることを前提とした上での、そのゴールと現在地点との間の距離について述べているものであり、その者個人が抱いている理想の法制度を前提とする主観的な思いを表現しているに過ぎないものである。
しかし、そのことを法的な視点から客観的に考えると、そこには「不利益」と称されるものを認めることはできないものである。
よって、法的な議論においては法制度の性質について客観的な視点から論じることが必要とされており、このようなある個人が現在の法制度をどのように受け止めているかという主観的な立ち位置から見た場合の言葉遣いを用いて論じることは適切ではない。
法的な議論においては、このような前提となる状況認識の設定について法的な視点からの客観性を保つことができていない色の付いた言葉は取り除き、結論を導くまでの判断の過程における中立性が損なわれることのない形で論じることが求められる。
このような前提となる認識についての法的な整理を誤ると、その影響で誤った結論を導き出すことに繋がるため注意が必要である。
このような主張の扱い方について、国(行政府)は下記のように整理している。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
そうすると、原告らが本件規定により侵害されていると主張する権利又は利益は、憲法24条2項の要請に基づき、異性間の人的結合関係を対象とする婚姻について具体的な内容として定められた権利又は利益であり、結局のところ、これらが侵害されたとする原告らの主張の本質は、同性間の人的結合関係についても、異性間の人的結合関係を対象とする婚姻と同様の積極的な保護や法的な利益の供与を認める法制度の創設を国家に対して求めるものにほかならない。
従って、本件規定が「婚姻の自由」ないし婚姻に伴う種々の権利及び利益を奪うものとはいえないから、原告らの主張は理由がない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【東京二次・第5回】被告第3準備書面 令和4年6月20日 PDF
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
そうすると,原告らが「婚姻の自由」として主張するものの内実は,「両性」の本質的平等に立脚すべきことを規定する憲法24条2項の要請に従って創設された現行の婚姻制度の枠を超えて,同性間の人的結合関係についても婚姻と同様の積極的な保護や法的な利益の供与を認める法制度の創設を国家に対して求めるものにほかならないのであって,国家からの自由を本質とするものではないから,このような自由が憲法13条の幸福追求権の一内容を構成するものと解することはできない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【九州・第6回】被告第4準備書面 令和3年l0月29日 PDF
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
控訴人らが本件規定により侵害されていると主張する権利又は利益の本質は、結局のところ、同性間の人的結合関係についても異性間の人的結合関係を対象とする婚姻と同様の積極的な保護や法的な利益の供与を認める法制度の創設を国家に対して求めるものにほかならず、法制度を離れた生来的、自然権的な権利又は人格的生存に不可欠の利益として憲法で保障されているものではないから、このような内実のものが憲法13条の規定する幸福追求権の一内容を構成すると解することはできない。……(略)……
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【札幌・第4回】被控訴人第2準備書面 令和5年6月8日 PDF
このように、「不利益」があることを前提として主張している内容は、結局は「婚姻」の中に含まれない人的結合関係に対して、新たな制度を立法することを国家に対して求めるものにほかならないといえる。
ただ、これは憲法24条1項の「婚姻」や憲法24条2項の定める「婚姻及び家族」の枠組みの「要請」に従って法律上の婚姻制度が立法されているか否かを審査する中で論じることができるものではない。
また、憲法14条1項の「平等原則」の審査についても、これは「婚姻制度を利用していない者(独身者)」の状態が基準となって、「婚姻制度を利用している者(既婚者)」が婚姻制度の立法目的を達成するための手段として不必要に過大な法的効果や優遇措置を得るものとなっていないかを審査し、その結果、不必要に過大な法的効果や優遇措置を得るものとなっている場合には、その不必要に過大な法的効果や優遇措置を定めている規定が個別に失効することによって差異が是正されるというものである。
これは、婚姻制度の対象となっていない人的結合関係を形成している者(『婚姻していない者〔独身者〕』)に対して法的効果や優遇措置を設けることによって差異を解消するというものではないため、これを憲法14条1項の「平等原則」の審査として論じることができるということにはならない。
そのため、このような新たな制度の創設を国家に対して求める主張を、憲法24条1項や2項、14条1項に違反するか否かという審査の中で取り扱うことができるかのような前提の下に論じることは誤りである。
別の制度を取り上げて比較することの誤り
〇 現在の制度に対する形で別の制度を持ち出してそれと比較して論じることの誤り
憲法に違反するか否かを論じようとする中において、現在の制度に対する形で別の制度を持ち出して論じることの問題性について検討する。
まず、権利の性質に応じて下記の二つの性質を分けて考えることが必要である。
① 「生来的、自然権的な権利又は利益、人が当然に享受すべき権利又は利益」
「法制度を離れた生来的、自然権的な権利又は利益として憲法で保障されているもの」
② 「法律によって定められる制度に基づき初めて具体的に捉えられる」「権利利益等」
「法律(…)に基づく制度によって初めて個人に与えられる、あるいはそれを前提とした自由」
上記は、国(行政府)が下記のように説明しているものである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
もっとも、婚姻及び家族に関する事項については、前記2(1)のとおり、憲法24条2項に基づき、法律によって具体的な内容を規律するものとされているから、婚姻及び家族に関する権利利益等の内容は、憲法上一義的に捉えられるべきものではなく、憲法の趣旨を踏まえつつ、法律によって定められる制度に基づき初めて具体的に捉えられるものである。そうすると、婚姻の法的効果(例えば、民法の規定に基づく、夫婦財産制、同居・協力・扶助の義務、財産分与、相続、離婚の制限、嫡出推定に基づく親子関係の発生、姻族の発生、戸籍法の規定に基づく公証等)を享受する利益や、「婚姻をするかどうか、いつ誰と婚姻をするか」を当事者間で自由に意思決定し、故なくこれを妨げられないという婚姻をすることについての自由は、憲法の定める婚姻を具体化する法律(本件諸規定)に基づく制度によって初めて個人に与えられる、あるいはそれを前提とした自由であり、生来的、自然権的な権利又は利益、人が当然に享受すべき権利又は利益ということはできない。このように、婚姻の法的効果を享受する利益や婚姻をすることについての自由は、法制度を離れた生来的、自然権的な権利又は利益として憲法で保障されているものではないというべきである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【九州・第1回】被控訴人(被告)答弁書 令和6年1月31日
①は、「国家からの自由」という意味の「自由権」に対応するものである。
これは、刑法が刑罰を科す場合のように、個々人の有する「国家からの自由」という「自由権」を制限するタイプの法制度において使われる考え方である。
②は、何らかの制度を個々人が利用するタイプの法制度において使われる考え方である。
そして、①の「国家からの自由」という「自由権」(生来的な自然権、前国家的権利)と呼ばれる事柄と、②の法律によって具体的な制度が定められることによって初めて捉えられる事柄では、憲法に違反するか否かを審査する方法が異なる。
まず、①の「国家からの自由」という「自由権」については、個々人が有する「自由権」に対する規制(制限)の内容を捉え、制約される「自由権」の性質に応じる形で「考慮要素」や「識別基準」となるものを検討しながら「立法目的の合理性」と「その立法目的を達成するための手段の合理性」を審査することになる。
そして、その「自由権」に対する制約が著しく不相当な内容であることが明らかとなった場合などには、憲法上の具体的な権利について定めた条文を根拠としてその規制(制限)について定めた法律の規定が無効となるというものである。
次に、②の法律によって具体的な制度が定められることによって初めて捉えられる事柄については、現在定められている制度の内容について憲法に違反するか否かが審査され、その審査の結果として憲法上の何らかの規定に違反することが明らかとなった場合には、その制度が個別に失効するというものである。
その場合には、その制度を無効としたままその状態を維持するか、その制度に代わる別の制度を構想するかは、その後、国会が立法裁量の中において判断することになるものである。
そのような中、②の法律によって具体的な制度が定められることによって初めて捉えられる事柄については上記のような形で処理されるにもかかわらず、この手順を踏まえずに、現在存在している制度に対する形で、現在存在していない別の制度を取り上げて、その別の制度が存在しないことを理由として憲法に違反するなどという主張を見ることがある。
しかし、そのような主張は、現在存在していない制度を取り上げるものであるから、それは国民の中で様々な政治的な主張が行われる中で生じた数多の制度の構想の中から一部の制度のみを取り上げて、それを現在の制度と対比する形で制度としての良し悪しを論じようとするものである。
これは、現在の制度の内容が憲法に違反するか否かという問題を超えて、特定の内容を持つ制度の創設を国家に対して求めるものにほかならないのであり、国会の有する立法権の内容に踏み込む主張である。
このような主張は、憲法に違反するか否か、あるいは、法令に違反するか否かという問題しか判断することのできない司法権を行使するという枠の中で論じることのできるものではない。
そのため、数ある制度の構想の中の一部に過ぎない別の制度を取り上げて、それと現在の制度を比較することによって憲法に違反するか否かについての結論を導き出すことができるかのような前提で論じることは誤りである。
よって、憲法に違反するか否かという法的な審査として論じる中において、数ある制度の在り方の中の一つに過ぎない別の制度を持ち出して、それが定められていないことを理由として現在の制度が憲法に違反するなどという論じ方は、意味の通らないものである。
〇 婚姻制度に対する形で別の制度を持ち出してそれと比較して論じることの誤り
このことは、婚姻制度についても同様である。
「婚姻」は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する形で設けられた枠組みである。
具体的には、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」を目的として、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす「一人の男性」と「一人の女性」の間に「貞操義務」を設けるなど一定の形式で法的に結び付け、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によってそれらの目的の達成を目指すものである。
そのため、「婚姻」は、「国家からの自由」という「自由権」(生来的、自然権的な権利)として保障されるものではなく、「法律によって具体的な内容を規律するものとされて」おり、「法律によって定められる制度に基づき初めて具体的に捉えられるもの」である。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
もっとも、婚姻及び家族に関する事項については、前記2(1)のとおり、憲法24条2項に基づき、法律によって具体的な内容を規律するものとされているから、婚姻及び家族に関する権利利益等の内容は、憲法上一義的に捉えられるべきものではなく、憲法の趣旨を踏まえつつ、法律によって定められる制度に基づき初めて具体的に捉えられるものである。そうすると、婚姻の法的効果(例えば、民法の規定に基づく、夫婦財産制、同居・協力・扶助の義務、財産分与、相続、離婚の制限、嫡出推定に基づく親子関係の発生、姻族の発生、戸籍法の規定に基づく公証等)を享受する利益や、「婚姻をするかどうか、いつ誰と婚姻をするか」を当事者間で自由に意思決定し、故なくこれを妨げられないという婚姻をすることについての自由は、憲法の定める婚姻を具体化する法律(本件諸規定)に基づく制度によって初めて個人に与えられる、あるいはそれを前提とした自由であり、生来的、自然権的な権利又は利益、人が当然に享受すべき権利又は利益ということはできない。このように、婚姻の法的効果を享受する利益や婚姻をすることについての自由は、法制度を離れた生来的、自然権的な権利又は利益として憲法で保障されているものではないというべきである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【九州・第1回】被控訴人(被告)答弁書 令和6年1月31日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
氏を含む婚姻及び家族に関する法制度は、その在り方が憲法上一義的に定められておらず、憲法24条2項により、具体的な内容は法律によって規律されることが予定されているから、原告らが主張する「氏名に関する人格的利益」も、憲法の趣旨を踏まえて定められる法制度を待って初めて具体的に捉えられるものである。このような一定の法制度を前提とする権利ないし利益については、いわゆる生来的な権利とは異なる考慮が必要であって、具体的な法制度の構築と共に形成されていくものであるから、当該法制度において認められた権利や利益を把握した上でそれが憲法上の権利であるかを検討することになる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【東京】20240906_被告準備書面(1) 令和6年9月6日 PDF
そして、現在の婚姻制度(男女二人一組)の内容として定められている法的効果や優遇措置の内容について憲法に違反するか否かを審査し、もし憲法上の何らかの規定に違反することになるとすれば、それは単に、その婚姻制度(男女二人一組)の内容となっている規定が個別に失効し、その規定が廃止されることによって是正されるというものである。
その場合には、その規定を無効としたままその状態を維持するか、その規定に代わる別の規定を設けることにするかは、その後、国会が立法裁量の中において判断することになるものである。
例えば、「婚姻制度を利用する者(既婚者)」が、「婚姻制度を利用していない者(独身者)」との間で婚姻制度の立法目的を達成するための手段として不必要に過大な優遇措置を得るものとなっていないかについて、憲法14条1項の「平等原則」に違反するか否かが審査されることになる。
そして、その審査の結果として、婚姻制度の立法目的を達成するための手段として不必要に過大なものと認められた場合には、「婚姻制度を利用していない者(独身者)」が基準(スタンダード)となって、その過大な優遇措置について定めた規定が個別に失効することによって格差が是正されることになる。
これに対して、婚姻制度(男女二人一組)の内容に対して不満を持つ者が、「同性間の人的結合関係」を対象とした制度を望むという発想に基づき、現在の制度に対するものとして「同性婚」という言葉を使って制度の創設を主張し始めることがある。
これは、現在の婚姻制度が「男女二人一組」を対象としていることに着目し、これに対する形で「同性間の人的結合関係」を対象とする制度を望むという発想に基づいた「同性婚」と称する制度を取り上げて、その制度が存在しないことをもって憲法に違反するなどと主張するものである。
しかし、そもそも現在の婚姻制度の内容は、ありとあらゆる人的結合関係が存在する中において、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという統一的な理念の下に、その目的を達成するための手段として整合的な範囲の者として一般的・抽象的にその間で自然生殖を想定することができる「一人の男性」と「一人の女性」を選び出し、「婚姻」という枠組みを設けているだけである。
そのことから、この婚姻制度(男女二人一組)に不満を持つ者がいるとしても、現在の制度に対する形で「同性婚」と称する「同性間の人的結合関係」を対象とした制度のみを取り上げて比較して論じれば結論が導き出されるという性質のものではない。
現在の制度に対して不満を抱く者がいるとしても、現在の制度に対して不満を抱く者の中では数多の制度の構想が存在しているのであって、その中の一部の制度の形のみを取り上げ、それと比較して論じることによって、現在の制度が憲法に違反するか否かの結論を導くことができるということには繋がらないものである。
そのため、このような前提で比較して論じることは誤りである。
結局、これは、現在の制度の内容が憲法に違反するか否かという問題を超えて、特定の内容を持つ制度の創設を国家に対して求めるものにほかならないのであり、国会の立法権の内容に踏み込む主張であるということになる。
これは、憲法に違反するか否か、あるいは、法令に違反するか否かという問題しか判断することのできない司法権を行使するという枠の中で論じることのできるものではない。
そのため、憲法に違反するか否かという法的な審査として論じる中において、あらゆる制度の構想が存在し、あらゆる人的結合関係を対象とした制度を想定し得るという中で、その中の一つに過ぎない「同性婚」と称する「同性間の人的結合関係」を対象とした制度のみを持ち出して、それと現在の制度を比較することによって憲法に違反するか否かについての結論を導き出すことができるかのような前提で論じることは、意味の通らないものである。
また、その制度が定められていないことを理由として現在の制度が憲法に違反すると結論付けることは誤りであるし、その制度が定められていないことを対象として憲法に違反すると結論付けることも誤りである。
この論点について、国(行政府)は婚姻制度はパッケージとして定められているものであることから、その一部だけを切り出してそれを含む別の枠組みを設けていないことを憲法14条1項の「平等原則」に違反すると述べることの誤りについて指摘している。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)このように、原判決は、本件諸規定が、同性カップルに対して、その関係を国の制度によって公証し、その関係を保護するのにふさわしい効果を付与するための枠組みすら与えていないことを殊更に問題視しているが、前記第4の3(2)で述べたとおり、そもそも控訴人らは、本件諸規定が同性婚を認めていないことが憲法14条1項に違反すると主張していたのであって、本件規定が、同性カップルに対して、その関係を国の制度によって公証し、その関係を保護するのにふさわしい効果を付与するための枠組みすら与えていないことを問題としていたわけではない。原判決のいう「同性カップルに対して、その関係を国の制度によって公証し、その関係を保護するのにふさわしい効果を付与するための枠組み」の立法不作為が憲法14条1項に違反するかについても、本来、控訴人の請求に理由があるか否かを判断するに当たって審理判断する必要のない事柄というべきである。
のみならず、本件諸規定は、憲法の定める婚姻を具体化するパッケージとして定められた規定であるから、その一部だけを切り出して、同性カップルに対して、その関係を国の制度によって公証し、その関係を保護するのにふさわしい効果を付与するための枠組みを設けるべきかということを本件諸規定と関連させて論じる性質のものではないと考えられる。これらの点で、原判決の問題の捉え方には根本的な誤りがあるというべきである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【名古屋・第1回】控訴答弁書 令和5年10月12日
これを整理して理解するためには、下記を踏まえる必要がある。
まず、憲法は「個人の尊厳」の原理に基づいており、自然人は「個人主義」の下に各々「自律的な個人」として生存していくことを前提としている。
それら個々人は、人的結合関係を形成、維持、解消するなどしながら自由に生活することが可能である。
そのような中、「婚姻」は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた枠組みであり、その法的効果や一定の優遇措置の内容は、その目的を達成するための手段として整合的な内容として定められている。
そして、憲法14条1項の「平等原則」によって制度の内容を審査する場合があるとしても、その審査の内容は、憲法14条1項は「個人権」であることから、第一に個人を基本とすることが必要であり、第二に何らの制度も利用していない状態を基準(スタンダード)として考えることが必要である。
よって、「婚姻制度を利用している者(既婚者)」が婚姻制度の立法目的を達成するための手段として不必要に過大な優遇措置を得ている場合には、「婚姻制度を利用していない者(独身者)」との間での比較において憲法14条1項の「平等原則」に抵触して違憲となり、その不必要に過大な優遇措置に関する規定が個別に失効することによって格差が是正されることになる。
これに対して、この判決の内容は、憲法14条1項の「平等原則」の審査として比較する対象とすることのできない「同性間の人的結合関係」という「二人一組」の形で取り上げている点で誤っているし、憲法14条1項に違反するとした場合においても、婚姻制度に設けられている法的効果や優遇措置の内容が個別に失効することによって格差が是正されるというものではなく、婚姻制度の内容を構成している一部分を切り出した別の枠組みを設けるべきであると述べるものとなっており、審査する際に前提となっている基準点(スタンダード)を見誤ったものということができる。
よって、国(行政府)の指摘は妥当である。
▽ 対比して論じる際の前提に誤りがあること
政策的な議論の中で、「異性婚」と「同性婚」などいう形で二つの制度を対比しながら論じられることがある。
しかし、そこでいう「同性婚」というものは、法制度として構想される数ある制度イメージの中の一つを取り上げているものに過ぎない。
人的結合関係の中には、「三人一組」、「四人一組」、「五人一組」など、様々な人的結合関係が存在しているのであり、その組み合わせは無限である。
現在の婚姻制度の内容は、個々人が「自律的な個人」として生存していくことを前提としている中において、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす形で「一人の男性」と「一人の女性」を選び出して法的に結び付けるという視点によって対象となる範囲を定めているものである。
これは、人間の有性生殖の仕組みに着目する形で異なる性別の二者を選び出して形づくられている枠組みであり、この有性生殖の仕組みに着目して組み合わせを選び出す以前においては、個々の人間が形成する人的結合関係が「二人一組」となるという前提は存在しないのである。
そのため、現在の婚姻制度の内容は、「異性間の人的結合関係」と「同性間の人的結合関係」という二者択一の選択肢しか存在しないという中で、その中の「異性間の人的結合関係」を選択して立法されたなどという位置づけのものではない。
よって、前提として「異性婚」と「同性婚」などと二つの制度のみを取り上げて、それを対比して論じることで結論が導き出されると考える発想そのものが誤っているのである。
〇 新たな制度の創設を国家に対して求める主張は憲法違反の理由にはならないこと
憲法上の具体的な条文によって制度の創設が「要請」されていないのであれば、特定の制度が定められていないことが理由となって憲法に違反するということにはならない。
また、現在の制度と異なる別の制度を持ち出してそれと比較して論じる主張についても、結局は、新たな制度の創設を国家に対して求めるものにほかならないのであり、その制度が定められていないことが根拠となって憲法に違反するということにはならないものである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
そうすると,原告らが「婚姻の自由」として主張するものの内実は,「両性」の本質的平等に立脚すべきことを規定する憲法24条2項の要請に従って創設された現行の婚姻制度の枠を超えて,同性間の人的結合関係についても婚姻と同様の積極的な保護や法的な利益の供与を認める法制度の創設を国家に対して求めるものにほかならないのであって,国家からの自由を本質とするものではないから,このような自由が憲法13条の幸福追求権の一内容を構成するものと解することはできない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【九州・第6回】被告第4準備書面 令和3年l0月29日 PDF
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
そうすると、原告らが本件規定により侵害されていると主張する権利又は利益は、憲法24条2項の要請に基づき、異性間の人的結合関係を対象とする婚姻について具体的な内容として定められた権利又は利益であり、結局のところ、これらが侵害されたとする原告らの主張の本質は、同性間の人的結合関係についても、異性間の人的結合関係を対象とする婚姻と同様の積極的な保護や法的な利益の供与を認める法制度の創設を国家に対して求めるものにほかならない。
従って、本件規定が「婚姻の自由」ないし婚姻に伴う種々の権利及び利益を奪うものとはいえないから、原告らの主張は理由がない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【東京二次・第5回】被告第3準備書面 令和4年6月20日 PDF
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
控訴人らが本件規定により侵害されていると主張する権利又は利益の本質は、結局のところ、同性間の人的結合関係についても異性間の人的結合関係を対象とする婚姻と同様の積極的な保護や法的な利益の供与を認める法制度の創設を国家に対して求めるものにほかならず、法制度を離れた生来的、自然権的な権利又は人格的生存に不可欠の利益として憲法で保障されているものではないから、このような内実のものが憲法13条の規定する幸福追求権の一内容を構成すると解することはできない。……(略)……
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【札幌・第4回】被控訴人第2準備書面 令和5年6月8日 PDF
この東京高裁判決では、現在の制度とは異なる別の制度を持ち出して、その制度が定められていないことを理由として憲法に違反するなどと述べている。
このような主張は、まさに新たな制度の創設を国家に対して求めるものにほかならないということができる。
しかし、これは憲法上の具体的な規定によって創設することを「要請」されているわけではないにもかかわらず、憲法に違反すると述べることによって制度の創設を要求するものとなっており、憲法に違反するとの結論を導き出すための根拠を欠くものである。
よって、このような国家に対して特定の制度を求める主張は、憲法違反の理由とはならないものである。
「原則と例外の逆転論法」の誤り
〇 例外を理由にして原則を変えることはできないこと
ある立法目的を達成するために、その手段として一定の規範が導き出され、それが「原則」として定められることになる。
その後、その「原則」の規範に対する形で、特定の目的を達成するために、その手段として別に「例外」的な規範が設けられることがある。
そのような中、「例外」的な規範が存在することを理由として、「原則」となっている規範を維持する理由がないだとか、「原則」となっている規範の立法目的は既に失われているなどとして、「原則」となっている規範を変更するべきであると主張する者が現れることがある。
しかし、その「例外」的な規範は、あくまで「原則」の規範が存在し、その「原則」の規範が維持されていることによって初めて成り立つことのできる事柄である。
そのため、その「例外」の存在を理由にして「原則」の方を変えるべきであると主張することはできない。
むしろ、「原則」と「例外」の関係が存在する中において、その両者の間で一貫性が保たれていないというのであれば、立法政策としては「例外」として位置付けられている制度の方を、その制度全体の機能(理念)の一貫性を保つことに沿わないものとして失効させ、「原則」に立ち戻るという形で解決が図られることになる。
つまり、本来であれば「例外」として位置付けられている制度の方こそが存在を許される理由がなくなり、その結果、その「例外」的な事例に関する規定の方が廃止されるという方向で整理され、もともとの「原則」に関する規定だけが残るという形で解決が図られるということである。
それにもかかわらず、「例外」が存在していることを理由として「原則」の方を変更しようとすることは、そもそもその制度が本来的に意図している目的を達成するための機能を果たさないものへと変容させてしまうことに繋がる。
これは、制度そのものを一貫性のある筋の通ったものとして成り立たせることを不能としてしまうことになるため、方法として誤りである。
そのため、「例外」の存在を理由として「原則」となっている制度の方を変更するように迫る主張は、「例外」が「例外」として成り立つための根拠を破壊してまで制度を変更しようとしている点で誤りである。
そのことから、「例外」の規範が存在することを理由として、「原則」となっている規範の機能を損なわせるような変更が可能となるということはない。
また、「原則」として位置付けられている規範と「例外」として位置付けられている規範を区別せずに、「例外」として位置付けられている規範があたかも「原則」の中にあるものとして位置づけられているかのように前提となっている位置づけを捉え変えた上で主張する言説を基にして、「原則」となっている制度の変更を許すことはできない。
そのため、もし「例外」として位置付けられている規範を理由として「原則」となっている規範の方を変更しようとしても、そのような変更が許されるということはない。
このように、「例外」として位置付けられている制度が存在することを取り上げて、それを理由として「原則」となっている制度に不備があるかのように論じたり、また、あたかもそれが「原則」であるかのような前提の下に論じ始め、そのことを理由として本来の「原則」となっている制度の方について憲法に違反するなどと主張することは、意味の通らないものである。
よって、その「原則」と「例外」の関係を逆転させて考えて、「原則」となっている制度の方が憲法に違反するかのように述べて、その「原則」について定めた制度の方を変更させることによって解決を図ろうとすることは誤りである。
また、このような主張は、「例外」となる制度が存在していることを理由として「原則」となっている制度の内容を自らが望む形へと自由に変更することができるかのような前提で論じている点においても誤りである。
(原則と例外の逆転現象の問題性について参考)
【動画】石川健治他 戦争とめよう!安倍9条改憲NO!新春のつどい 2018/01/07
〇 「婚姻及び家族」の制度の「原則」と「例外」の関係
この「原則」と「例外」の関係は、「婚姻及び家族」の枠組みについても当てはまる。
まず、「婚姻」は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた枠組みである。
具体的には、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」を目的として、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす「一人の男性」と「一人の女性」を選び出し、その間にて「貞操義務」を設けるなど一定の形式で法的に結び付け、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によってそれらの目的の達成を目指すものである。
そして、「家族」は、この「婚姻」の枠組みと整合的な形で「夫婦」と「親子」による「血縁関係者」を定める枠組みである。
このような統一的な理念に基づいて、一般的・抽象的・定型的・画一的に規格化された形で制度の枠組みを定め、これらの目的を達成するための手段として機能することが予定されており、これが「原則」である。
その後、「養子」という「例外」的な制度が定められることがある。
そのような中、その「養子」の制度によって生物学的な血のつながりのない親子の夫婦がいることを理由として、生物学的な繋がりのない親子の関係となることが前提となる「同性間の人的結合関係」を「婚姻」として扱う仕組みを設けることも可能ではないかとの主張がなされることがある。
しかし、「養子」の制度は、あくまで「原則」として「婚姻及び家族」の制度が「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するための制度として機能することを前提に、その「原則」が保たれていることによって初めて存立することができるという「例外」として位置付けられた制度である。
「婚姻及び家族」の制度が「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成することを目指す仕組みとして設けられた制度であることを前提に、その男女の間で「生殖」が行われて子が生じるという血縁関係を明確にする機能としての骨格が定められていることが「原則」となる中で、その後から「養子」としての親子の関係をその「例外」として位置付けている制度である。
そのため、あくまで自然生殖によって生じる「親子」の関係を規律する「自然血族」の枠組みが先にあり、それを基本として、その骨格を維持したまま、その骨格に当てはめる形で位置付けられている制度である。
これは、「婚姻及び家族」の枠組みが、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成するという統一的な理念の下に形成されている中で、全体の整合性が保たれてその機能を阻害しない枠組みの中で、例外的に許容されているものである。
そのことから、このような「例外」として位置付けられている制度が存在することを理由にして、既に「婚姻」の制度そのものについての立法目的が変容しているだとか、婚姻制度から「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するための機能は失われているだとかを主張して、「原則」となっている「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成するための手段として統一的な理念の下に形成されている婚姻制度の人的結合関係の範囲そのものを変更することができるということにはならない。
むしろ、もし「例外」として位置付けられている「養子」の制度の内容について、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという婚姻制度の立法目的を達成するための手段として一貫性がなく、整合性が保たれていない部分が発見されたり、後にそのような法的効果が加えられるなどした場合には、その「養子」の制度における整合性が保たれていない部分を廃止するという方向で整理され、「原則」となっている制度のみが残るという形で解決が図られることになるものである。
そのため、あたかも「養子」の制度が基本形であるかのように考えて、それを基にして派生する制度を組み立てることができるということにはならない。
よって、この「例外」として位置付けられている事例を取り上げて、それを根拠にして血縁関係を明確にすることによって立法目的を達成することを目指すという「原則」となっている仕組みの方を変更することができるということにはならない。
このことから、「養子」の制度によって生物学的な血のつながりのない親子の夫婦がいることを理由として、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」の中に含めることができるとする主張は、婚姻制度が生まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進する仕組みを「原則」としており、「養子」の制度はあくまでその仕組みが保たれている中においてその「例外」として位置付けられていることを理解しないものであり、誤りである。
よって、「養子」の制度があることは、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」として扱うことができるとする根拠となるものではない。
他にも、もしこのような形で「原則」を覆すことが可能となるとすれば、それは結局、その「原則」を覆した後に残った制度について、また別の「例外」的な事例を見つけ出して比較することで、またその制度の枠組みを覆すことが可能となり、このような方法が繰り返されることで無制限に制度の対象が拡大していくことになる。
これは、結果として制度が一定の枠を設けることによって目的を達成しようとしている意味が失われ、制度そのものが破壊され、制度そのものが成り立たなくなることに繋がるものである。
そのため、このような「例外」として位置付けられている制度の存在を根拠として、「原則」となっている制度の方を覆そうとする主張は、全体の整合性を保つ形で制度を組み立てる観点から誤った方法であり、解釈の方法としても誤りである。
そのため、「例外」となる制度が存在していることを理由として、「原則」となっている制度に不備があるかのように論じ、そのことを根拠として憲法に違反するなどと主張することは、意味の通らないものである。
また、このような主張は、「例外」となる制度が存在していることを理由として「原則」となっている制度の内容を自らが望む形へと自由に変更することができるかのような前提で論じている点においても誤りである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2については、「特別養子縁組」とは、子供の福祉の増進を図るために、養子となる子の実親との法的な親子関係を解消し、実の子と同じ親子関係を結ぶ制度であり、養親になることを望む夫婦の請求に対し、厳格な要件を満たす場合に、家庭裁判所の決定を受けて認められるものである。同性婚を認めることになると、男と女の「夫婦」がなくなり、「婚姻の当事者」といふことになる。それに伴つて、男同士または女同士の「婚姻の当事者」にも特別養子縁組を認めようといふのである。
しかし、これは本末転倒の議論である。子供の福祉のために特別養子縁組が創設されたのであり、夫婦や「婚姻の当事者」のために創設されたのではない。子供はペットとは異なる。子供は実親である「夫婦」に育てられることが原則で、何らかの事情のある場合、子供の福祉のために「夫婦」の養子が認められるのである。これを男同士または女同士の「婚姻の当事者」の養子にする必要はないし、認めるべきではない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【第1146回】同性婚を法制化する民法改正案に反対する 2024.05.13 (下線は筆者)
【動画】【後半】同性婚は不要!子どもを持つ権利などない!LGBT左派の嘘 2024/10/11
「同性婚カップルが子をもつことを認める? 認めない?」…日本人が知っておくべき「同性婚に関する重大な法的知識」 2024.11.18
ゲイ・コミュニティの皆さんへ~あなたの娘より 2021年8月27日
ゲイ・カップルに育てられた私が、子どもには父と母が必要だと思うわけ 2021年9月9日
レズビアン・カップルに育てられた息子の苦悩 2021年10月16日
レズビアン・カップルに育てられた娘が父を想うことは”差別”なのか 2021年10月30日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
民法の実親子に関する現行法制は,血縁上の親子関係を基礎に置くものであるが,民法が,出産という事実により当然に法的な母子関係が成立するものとしているのは,その制定当時においては懐胎し出産した女性は遺伝的にも例外なく出生した子とのつながりがあるという事情が存在し,その上で出産という客観的かつ外形上明らかな事実をとらえて母子関係の成立を認めることにしたものであり,かつ,出産と同時に出生した子と子を出産した女性との間に母子関係を早期に一義的に確定させることが子の福祉にかなうということもその理由となっていたものと解される。
民法の母子関係の成立に関する定めや上記判例は,民法の制定時期や判決の言渡しの時期からみると,女性が自らの卵子により懐胎し出産することが当然の前提となっていることが明らかであるが,現在では,生殖補助医療技術を用いた人工生殖は,自然生殖の過程の一部を代替するものにとどまらず,およそ自然生殖では不可能な懐胎も可能にするまでになっており,女性が自己以外の女性の卵子を用いた生殖補助医療により子を懐胎し出産することも可能になっている。そこで,子を懐胎し出産した女性とその子に係る卵子を提供した女性とが異なる場合についても,現行民法の解釈として,出生した子とその子を懐胎し出産した女性との間に出産により当然に母子関係が成立することとなるのかが問題となる。この点について検討すると,民法には,出生した子を懐胎,出産していない女性をもってその子の母とすべき趣旨をうかがわせる規定は見当たらず,このような場合における法律関係を定める規定がないことは,同法制定当時そのような事態が想定されなかったことによるものではあるが,前記のとおり実親子関係が公益及び子の福祉に深くかかわるものであり,一義的に明確な基準によって一律に決せられるべきであることにかんがみると,現行民法の解釈としては,出生した子を懐胎し出産した女性をその子の母と解さざるを得ず,その子を懐胎,出産していない女性との間には,その女性が卵子を提供した場合であっても,母子関係の成立を認めることはできない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
市町村長の処分に対する不服申立て却下審判に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件 最高裁判所第二小法廷 平成19年3月23日 (PDF)
▽ 「養子」の制度を廃止するべきか
その他、「養子」の制度が「婚姻及び家族」の制度として一貫性がなく、廃止するべきかどうかを検討する。
ある「夫婦」が「養子」をとった場合でも、婚姻制度の枠組みが「男女二人一組」の形となっていることは変わるものではない。
そのため、その後、その「夫婦」の間で「生殖」によって「実子」が生まれた場合においても、遺伝上の父親を特定することができる状態であることに変わりはなく、それによって「子の福祉」の実現を目指そうとする機能を阻害するものではない。
また、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態であることに変わりはないことから、「近親交配の回避」という目的の実現を阻害することもない。
婚姻制度の枠組みが「男女二人一組」の形であることに変わりはないから、「生殖機会の公平」という目的の実現を阻害することもない。
婚姻制度の枠組みが「男女二人一組」の形であることに変わりはないから、婚姻制度が「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するための制度として機能することに対する国民の信頼を損なうことはなく、婚姻制度を利用する中で子を持つことに対して魅力を感じる者が増えることによって全体として「婚姻適齢」に満たない若年の女性が「生殖」(性的な接触)に誘引され、それに続く妊娠・出産のリスクを負うことを抑制することによって「母体の保護」という目的を達成することを目指す仕組みを阻害することもない。
これらの点で、「養子」の制度は、婚姻制度の「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成するための手段としての仕組みや、婚姻制度を利用することに対してインセンティブを働かせること等の意図を損なわせるものとはなっていない。
そのため、「養子」の制度が「婚姻及び家族」の制度として一貫性がなく、廃止するべきとまではいえないと考える。
また、上記のことから、「養子」の制度が存在するとしても、そのことは、婚姻制度が「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成するための手段として仕組みを定めていることの趣旨そのものが変わることを裏付けるものであるとはいえない。
よって、この観点からしても、「養子」の制度が存在することが根拠となって、婚姻制度の対象が「男女二人一組」のみであることが不合理であるとの結論を導くことには繋がらないものである。
〇 婚姻制度の枠組みと「生殖無能力者」の関係
婚姻制度は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成するための手段として設けられているものである。
そのため、生殖関係を整理するために自然人を「生殖」との関係において定義される「男性」と「女性」を区別し、その区別に基づく形で一般的・抽象的・定型的・画一的に制度を組み立てることによって、その目的の達成を目指すものとなっている。
そして、法制度としては基本的に生殖器官の形状を外観から判定してその者を「男性」か「女性」かのいずれかとして把握し、制度を適用するか否かを決することになる。
この場合に、婚姻制度が「男性」と「女性」を区別することによって生殖関係を整理することで「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成するものとして定めていることから、生殖機能の違いに着目するものとして「男性」と「女性」という概念を用いている意味において、一般的・抽象的に生殖能力がある者として想定した概念を用いて区別を行うものとなっている。
そのような中、婚姻制度の要件を満たして制度を利用する者の中には、個々人の個別特性として生殖能力がない者もいることは考えられる。
その場合、法制度として生殖関係を整理するために生殖機能の違いに着目する形で「男性」と「女性」を一般的・抽象的・定型的・画一的に要件を定めて適用の可否を定めていることは、個別的な事情として「生殖能力」がないことから、その生殖機能の違いに着目する形で「男性」と「女性」を区別するという意味としては直接的に対応するとはいえないと感じる者もいるかもしれない。
しかし、このような個別的な事情として生殖能力がない者が婚姻制度を利用している場合があるとしても、そのことは、婚姻制度そのものが「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成するための手段として整合的な形で、一般的・抽象的・定型的・画一的に規格化された形で「男性」と「女性」という生殖機能の違いに着目する形で制度を定めることによってその目的を達成することを目指すという仕組みを採用していることについて何らの影響も与えないものである。
具体的には、下記の事情を認めることができる。
個々人の個別特性として生殖能力のない者がいるとしても、その者は生殖能力がないことから、自身の子供をつくることはない。
そのため、婚姻制度が生まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進することによって「子の福祉」という目的を達成することを目指す仕組みとの間で直接的な問題が生じることはない。
たとえ「生殖能力のない者」との間で夫婦となっている相手方の配偶者について考えるとしても、その者は「貞操義務」を負うことから、基本的にはその夫婦以外の他者との間で「生殖」によって子をつくることは抑制的に作用することになる。
すると、やはり婚姻制度が産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進することによって「子の福祉」という目的を達成することを目指す仕組みとの間で問題が生じにくいと考えられる。
他にも、自身の子供をつくることはないことから、婚姻制度が遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進することによって「近親交配の回避」という目的を達成することを目指す仕組みに影響を与えることはない。
婚姻制度の対象とする人的結合関係の範囲も「男女二人一組」の形のままであるから、これによって未婚の男女に数の不均衡が生じることもないため「生殖機会の公平」という目的の達成を目指す仕組みを阻害することもない。
このように、「生殖能力のない者」と夫婦となっている相手方の配偶者についても「貞操義務」を負っていることから、その夫婦以外の他者との間で「生殖」によって子をつくることは抑制されるという意味において、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」の観点からも比較的望ましい状態となるということもできる。
さらに、「生殖能力がない者」については、もともと生殖能力がないことから、妊娠・出産することはなく、妊娠・出産を前提とする「母体の保護」という目的を達成することを目指す仕組みとの間で問題が生じることはない。
また、そもそも法制度が一般的・抽象的・定型的・画一的に規格化された形で「母体の保護」の観点から「婚姻適齢」を設定しており、「生殖能力がない者」についてもその「婚姻適齢」を超えた形で婚姻制度を利用していることになるから、この点の問題には関りがないともいえる。
他にも、これまでの婚姻制度(男女二人一組)の枠組みを変えるものではないことから、婚姻制度が「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するための制度として機能することに対する国民の信頼も損なうことはなく、婚姻制度を利用する中で子を持つことに対して魅力を感じる者が増えることによって全体として「婚姻適齢」に満たない若年の女性が「生殖」(性的な接触)に誘引され、それに続く妊娠・出産のリスクを負うことを抑制することによって「母体の保護」という目的を達成することを目指す仕組みを阻害することもない。
よって、個々人の個別特性として生殖能力のない者が婚姻制度を利用している事実があるとしても、それは婚姻制度の立法目的を達成するための手段としての機能を阻害するものではないことから、一般的・抽象的・定型的・画一的に規格化する形で制度を定めることによりそれらの目的の達成を目指すという仕組みとして定めていることの意義を失わせるものとなっているわけではない。
また、もし個々人の個別特性として生殖能力のない者について、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成するための手段として整合的ではなく、制度の枠組みの一貫性を損なうような事情が発見されたのであれば、その個々人の個別特性として生殖能力のない者に対して適用されている法的効果や優遇措置の内容を個別に失効させることによって差異を是正するものである。
例えば、実子であることを証明するための血液型検査やDNA検査を実施する制度を設け、それについて金銭的な補助を与えた場合、生殖能力のない者については子供は産まれないはずであるから、その制度の適用や補助金を与えることはしないという方向で整理されることが考えられる。
そのため、個々人の個別特性として生殖能力のない者に対して適用されている法的効果や優遇措置の内容が減らされる方向で整理されることはあっても、生殖能力がない者が婚姻制度の想定する基本形(原則)であるかのように考えて、婚姻制度の枠組みを定めている意図の中に「生殖」の視点が存在しないことを基礎づける事情となることはない。
そのため、婚姻制度が生物学的な生殖機能の観点から見て一般的・抽象的に自然生殖を想定することができる組み合わせとなっている中において、個々人の個別特性として生殖能力のない者が制度を利用している場合があるとしても、そのことを理由として、一般的・抽象的に自然生殖の可能性のある組み合わせを対象として定型的・画一的に規格化する形で制度を定めることによって「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成することを目指す仕組みとしているという事情が失われているとはいえない。
そのことから、このことを理由として、初めから一般的・抽象的に自然生殖を想定することができない組み合わせ(同性間の人的結合関係)に対してまで、同様の制度の枠組みを設けるべきであるとする結論を導くことに繋がるものではない。
むしろ、「同性間の人的結合関係」に対して制度を設けることは、婚姻制度が産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進することによって「子の福祉」や「近親交配の回避」を目指すという目的の実現を阻害する影響を与えることになる。
また、未婚(制度を利用しない)の男女の数の不均衡が生じることによって「生殖機会の公平」という目的の実現を阻害する影響を与えることになる。
婚姻制度の「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという機能が変容し、それにより婚姻制度の効用が低下することで婚姻制度の信頼性が損なわれ、婚姻制度を利用する中で子を持つことを選択しようとする者が減少することにより、婚姻適齢に満たない若年者が「生殖」の機会に誘引されることが増加し、「母体の保護」という目的の実現も阻害することに繋がる。
そのため、この意味でも一般的・抽象的に生殖機能の違いに着目して「男性」と「女性」を選び出すことによって形作られている制度が存在することを前提に、その制度を利用する者の中に個々人の個別特性として生殖能力のない者がいるとしても、そのことが理由となって、その制度の立法目的とその立法目的を達成するための手段として定められている枠組みの合理性が失われる事情と考えることはできない。
よって、そのことを理由として、一般的・抽象的に生殖機能の違いに着目して「男性」と「女性」を区別した上で、初めからその間で「生殖」を想定することができない人的結合関係(同性間の人的結合関係)に対して同様の制度を設けなければならないという結論を導き出すことには繋がらないものである。
このように、「原則」と「例外」の関係と同様に、一般的・抽象的・定型的・画一的に定められている制度が達成しようとしている目的との関係において、その制度を利用する個々人の個別的な事情によってその制度のすべての機能を活用していない者がいるとしても、そのことはその制度が一般的・抽象的・定型的・画一的な制度の枠組みを設けることによって、その目的を達成しようとしている意義を何ら変容させる事情にはならないものである。
よって、制度を利用している者の個々人の個別的な事情を、その制度そのものを変更することができるとする理由として取り上げることは誤りである。
この論点について、国(行政府)は下記のように述べている。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被控訴人原審第4 準備書面第3 の2 (3)ウ(37ないし43ページ)及び同(4)ア(43及び44 ページ)において述べたとおり、民法(本件諸規定)は、一人の男性と一人の女性が子を産み育てながら共同生活を送るという関係に対して特に法的保護を与えることを立法目的とし、実際の自然生殖可能性の有無にかかわらず婚姻を認めているところ、これは、生物学的な自然生殖可能性を基礎として抽象的・定型的に立法目的を捉えて、婚姻をすることができる夫婦の範囲を定めていることによるものである。そして、憲法24 条は、一人の男性と一人の女性の人的結合関係である婚姻及びそれを前提として営まれることになる共同生活関係である家族について明文で規定し、このような婚姻及び家族に関する事項について立法上の配慮を求めているところ、夫婦間に実際に子がなくとも、又は子を産もうとする意思や子が生まれる可能性がなくとも、夫婦間の人的結合関係を前提とする家族が自然的かつ基礎的な集団単位となっているという社会的な実態とこれに対する社会的な承認が存在することに変わりがないことや、婚姻関係を含む家族に関する基本的な制度については、その目的について抽象的・定型的に捉えざるを得ない上、当該制度を利用することができるか否かの基準は明確である必要があることからすれば、婚姻をすることができる夫婦の範囲を前記のとおり定めることには、合理性が認められる。そして、被控訴人原審第5準備書面第3の4(1)イ(28及び29ページ)において述べたとおり、「一人の男性と一人の女性が子を産み育てながら共同生活を送るという関係に対して法的保護を与える」という立法目的は、婚姻制度の対象として生物学的にみて生殖の可能性のある男女の組合せ(ペア)としての夫婦を抽象的・定型的に想定したものであるから、このような目的を達成するに当たり、実際の自然生殖可能性の有無にかかわらず婚姻を認めることは、基準として何ら不合理と評価されるものではない。むしろ、パッケージとして構築される婚姻及び家族に関する制度においては、制度を利用することができるか否かの基準が明確である必要があるから、実際の自然生殖可能性の有無にかかわらず婚姻を認めることは、本件諸規定の目的との関連において合理性を有するといえる。そして、夫婦間に実際に子がなくとも、又は子を産もうとする意思や子が生まれる可能性がなくとも、夫婦間の人的結合関係を前提とする家族が自然的かつ基礎的な集団単位となっているという社会的な実態とこれに対する社会的な承認が存在するという事実は、実際の自然生殖可能性の有無にかかわらず婚姻を認めることが本件諸規定の立法目的との関連で合理性を有することを裏付けるーつの事情であり、このような事実(立法目的を達成するための手段・方法の合理性を基礎づける事情)から遡って本件諸規定の立法目的を推測し、それが夫婦の生殖及び子の養育の要素を除いた共同生活自体の保護にあると解釈することは相当でない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【九州・第1回】被控訴人(被告)答弁書 令和6年1月31日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
イ 婚姻制度との関係
婚姻夫婦は、形の上では二人の間の関係であっても、法律制度としてみれば、家族制度の一部として構成され、身近な第三者ばかりでなく広く社会に効果を及ぼすことがあるものとして位置づけられる。このような法律制度としての性格や、現実に夫婦、親子などからなる家族が広く社会の基本的構成要素となっているという事情などからすると、法律上の仕組みとしての婚姻夫婦も、その他の家族関係と同様、社会の構成員一般からみてもそう複雑でないものとして捉えることができるよう規格化された形で作られていて、個々の当事者の多様な意思に沿って変容させることに対しては抑制的であるべきである。
このように、複雑さを避け、規格化するという要請の中で仕組みを構成しようとする場合に、法律上の効果となる柱を想定し、これとの整合性を追求しつつ他の部分を作り上げていくことに何ら不合理な点はない。
この点、現行民法における婚姻は、相続関係(民法890条及び900条等)、日常の生活において生ずる取引関係(同法761条)など、当事者相互の関係にとどまらない意義・効力を有するが、制度としての婚姻を特徴づけるのは嫡出子の仕組み(同法772条以下)であるといえ、これこそが婚姻制度において想定される「法律上の効果となる柱」であるといえる。夫婦の氏に関する規定は、夫婦それぞれと等しく同じ氏を称する程のつながりを持った存在として嫡出子が意義づけられていること(同法790条1項)を反映していると考えられるところ、婚姻制度について、複雑さを避け、規格化するという要請の中で、本件各規定が、法律上の効果となる柱である嫡出子の仕組みとの整合性を追求しつつ、婚姻をする夫婦の氏をそのいずれかの氏とする仕組みを設けていることは、これを社会の多数が受け入れるときには、その原則としての位置づけの合理性を疑う余地は乏しいというべきである(以上につき、平成27年大法廷判決における寺田逸郎裁判官の補足意見参照)。
この点については、平成27年大法廷判決においても、「婚姻の重要な効果として夫婦間の子が夫婦の共同親権に服する嫡出子となるということがあるところ、嫡出子であることを示すために子が両親双方と同氏である仕組みを確保することにも一定の意義があると考えられる。」と判示されているところである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【東京】20240906_被告準備書面(1) 令和6年9月6日 PDF (夫婦別氏訴訟)
(【札幌】240930_答弁書 令和6年9月30日 PDF)
▽ 「生殖無能力者婚姻可能論」
婚姻制度が「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成するための手段として機能するためには、一夫一婦制(男女二人一組)の枠組みが保たれていることが必要である。
そして、婚姻制度を利用する者の中に、個々人の個別特性として生殖能力がない者がいるとしても、それは、あくまで「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成するための手段としての一夫一婦制(男女二人一組)の枠組みが保たれている中において、個々人の個別的な事情として生殖能力がない場合に制度を利用することを否定するということまでしていないという意味に留まるものである。
また、婚姻制度は、個々人の個別特性として生殖能力の有無を審査していないことから、その審査が存在することを前提として、その審査の結果として生殖能力がないと判明した者を選び出し、敢えてその選び出された者が婚姻制度を利用することについて作為的に可能としているという事情も存在しない。
そのため、個々人の個別特性として生殖能力がない者が制度を利用することが認められているという事情を理由として、この一夫一婦制(男女二人一組)の枠組みを変えることを正当化することはできない。
よって、婚姻制度を利用する者の個別的な事情を取り上げて、それを理由として婚姻制度が一夫一婦制(男女二人一組)の枠組みで形成されていることに含まれる意図が変わっているなどとして、一夫一婦制(男女二人一組)の枠組みを変更することができるかのように論じることは誤りである。
その他
その他、下記の点を理解すると、東京高裁判決の論旨の問題点を理解しやすくなる。
〇 人的結合関係を形成することについては、憲法21条1項の「結社の自由」により保障されるものである。
そのため、人的結合関係を形成することについての法的な保護とは、憲法21条1項が「結社の自由」であるということになる。
この東京高裁判決では「個人の人格的存在と結び付いた重要な法的利益」と述べている部分があるが、これと重なる論点ついて国(行政府)は下記のように説明している。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
そうすると、札幌高裁判決が、「憲法13条によっても、人格権の一内容を構成する可能性があり、十分に尊重されるべき重要な法的利益であ」ると判示する「同性間の婚姻の自由」の本質は、結局のところ、同性間の人的結合関係についても異性間の人的結合関係を対象とする婚姻と同様の積極的な保護や法的な利益の供与を認める法制度の創設を国家に対して求めるものにほかならず、法制度を離れた生来的、自然権的な権利又は利益として憲法で保障されているものではない。……(略)……
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【大阪・第6回】被控訴人第2準備書面 令和6年9月25日
混乱しやすいため意味を補足する。
まず、前提として「人的結合関係」を形成することそのものについては「法制度を離れた生来的、自然権的な権利又は利益」といえる。
しかし、「婚姻」という法制度ついての「法的利益」については、「法制度の創設」によるものであるから、「法制度を離れた生来的、自然権的な権利又は利益として憲法で保障されているものではない。」というものである。
〇 憲法24条2項は「婚姻及び家族」の枠組みとして「夫婦」(男女二人一組)と「親子」による「血縁関係者」について定めた法律を立法することを「要請」しているが、それ以外の制度を立法することを「要請」していない。
そのため、それ以外の制度が存在しないことを理由として、憲法24条2項に違反するということにはならない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
しかしながら、被控訴人原審第2準備書面第3の2(3)及び(4)(19及び20ページ)で述べたとおり、憲法24条が婚姻について異性間の人的結合関係のみを対象とするものとして明文で定め、婚姻に係る法制度の構築を法律に委ねているものの、それ以外の法制度の構築を明文で定めていないことからすると、憲法は、法律(本件諸規定)により異性間の人的結合関係のみを対象とする婚姻を制度化することを予定しているとはいえるものの、同性間の人的結合関係を対象とする婚姻制度を構築することを想定していないことはもとより、同性間の人的結合関係を対象とする新たな婚姻に準じる法制度を構築することを具体的に想定しておらず、同制度の構築を立法府に要請しているものでもないから、同制度の不存在が憲法24条2項に違反する又は同項に違反する状態となることもないと解される。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【大阪・第6回】被控訴人第2準備書面 令和6年9月25日
「婚姻」には内在的な限界があること
この東京高裁判決では、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることができるかのような前提の下に論じるものとなっている。
しかし、そもそも「婚姻」という概念の中に「同性間の人的結合関係」を含めることができるのかという部分から検討することが必要である。
■ 「婚姻」の中に含めることができるもの
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
これらの学説を参照すると、憲法24条のいう「婚姻」の内実として同性カップルの「婚姻」というものが観念しうるのか、憲法上の「婚姻」とはそもそも男女が取り結ぶ一定の関係なのではないか、そして「同性」と「婚姻」を結びつけることが法的に可能なのかという問いが浮かぶ。
憲法24条が同性婚を想定していないのは確かだとして、憲法学説も民法学説も、従来、憲法24条の「婚姻」としては男女のカップルのそれを暗黙のうちに想定してきたと言える。「同性」という言葉と「婚姻」という言葉がそこでは結びついておらず、したがって「同性婚の自由」なるものが憲法上存在するかも定かではないのだ。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
生殖可能性のない同性婚を法律で認める理由はない…憲法学の専門家が「同性婚の法制化」にクギを刺す理由 2023/02/18
そこで、「婚姻」という概念が形成されている由来や、「婚姻」が有している目的とその目的を達成するための手段となる枠組みについて検討する。
■ 「婚姻」の概念による制約
▼ 「婚姻」の概念に含まれる内在的な限界
「婚姻」は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために設けられた枠組みである。
これは、下記のような経緯によるものである。
その国の中で「生殖と子の養育」に関する事柄について何らの制度も存在しない場合には、社会的な不都合が発生することがある。
例えば、「父親不明」の子供が増える、父親を特定できない子供が増える、父親が蒸発して行方不明になった子供が増える、それらにより「子の福祉」が減少する、父親を特定できないことにより近親者の範囲を把握できずに「近親交配」に至り潜性遺伝子の発現した個体が高い確率で生じるようになる、一部の強者が多数人との生殖関係を独占することによって社会の中で「子を持ちたいと希望して相手を見つけようとする男女」の数の不均衡が生じて「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」が生まれる、低年齢での妊娠・出産により母体に危険が及ぶ、などの問題が生じることがある。
これらの不都合を解消するために、下記のような立法目的を有する枠組みを設けることが必要となる。
・「子の福祉」が実現される社会基盤を構築すること
・潜性遺伝子の発現した個体が高い確率で生じることを抑制すること
・「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」を減らすこと
・母体を保護すること
そして、これらの目的を達成するためには、目的との関係で整合的な下記の要素を満たす枠組みを設けることが必要となる。
・子の遺伝的な父親を特定できる組み合わせとすること
・特定された子の父親にも子に対する責任を担わせること
・特定された子の父親を基に遺伝的な近親者を把握すること
・未婚の男女の数の不均衡を防止できる組み合わせに限定すること
これらの要素を満たすものとして「一人の男性」と「一人の女性」が選び出され、その間に「貞操義務」を設け、その関係を法的に結び付ける形を「婚姻」と呼んでいる。
そして、この「婚姻」に対して法的効果や一定の優遇措置を設けることによって、制度を利用する者を増やし、これらの立法目的の実現を目指す仕組みとなっている。
これが、「婚姻」という概念が生じる経緯である。
このように「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという「目的」に従って、「その目的を達成するための手段」となる枠組みを定めるところに「婚姻」という概念が生じているのである。
これは、これらの目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす人的結合関係を、他の様々な人的結合関係との間で区別する形で枠づけることの必要性に基づいて形成されている。
そのため、このような国民が「生殖」によって子供を産むことに関係して起き得る問題を解決しようとする目的を離れて「婚姻」を観念することはできない。
つまり、 このような「目的」と、「その目的を達成するための手段」として整合的な要素を満たす枠組みとの関係を切り離して「婚姻」を観念することはできない。
そのことから、「婚姻」という概念である以上は、国民が「生殖」によって子を産むことに関わる制度であることを前提としている。
これにより、「婚姻」は、上記の要素と対応する形で「生殖と子の養育」の趣旨により統一的な理念に従って定められ、他の様々な人的結合関係との間で区別する意味で設けられている枠組みであるといえる。
また、その社会の中で「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することが求められ、その目的を達成するための手段となる枠組みを「婚姻」という概念が担っている以上は、「婚姻」はそれを解消するものとして機能することが求められている。
そのため、「婚姻」の文言の中には、これらの目的を達成することを阻害する組み合わせを「婚姻」とすることはできないという内在的な限界が含まれている。
よって、「婚姻」という概念の中に含めることができる人的結合関係は、これらの目的を達成するための手段として整合的な上記の要素を満たす範囲に限られる。
もし「婚姻」の中にこれらの要素を満たさない人的結合関係を含めようとした場合には、その時点で、これらの要素を満たさないことが理由となって 「婚姻」の立法目的を達成することができなくなる。
そのことから、これらの要素は、「婚姻」という枠組みが機能するために最低限必要となるものであり、「婚姻」という概念そのものが他の様々な人的結合関係とは区別して成り立つための境界線となるものである。
よって、これらの要素を満たさないものについては、「婚姻」という枠組みそのものを他の様々な人的結合関係との間で区別するための境界線となっている一線を損なうこととなり、「婚姻」という枠組みそのものを他の様々な人的結合関係との間で区別することができなくなり、「婚姻」という概念自体が成り立たなくなり、「婚姻」という概念そのものを雲散霧消させてしまうことになることから、「婚姻」とすることはできない。
このため、「婚姻」が「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために設けられた枠組みである以上、その目的との関係により、「婚姻」の中に含めることができる人的結合関係の範囲は自ずと画されることになる。
そのことから、どのような人的結合関係でも「婚姻」の中に含めることができるというわけではない。
そして、このような差異が生じることは、「婚姻」という概念そのものが目的を達成するための手段として形成されている枠組みである以上は、もともと予定されていることである。
▼ 憲法24条の「婚姻」による限界
憲法24条の「婚姻」は、この意味の「婚姻」を引き継ぐ形で定められている。
そのため、憲法24条の「婚姻」の文言の中には「生殖と子の養育」の趣旨が含まれている。
また、憲法24条が定めているものが「婚姻」である以上は、そこにはこれらの目的を達成することを阻害する組み合わせを「婚姻」とすることはできないという内在的な限界が含まれている。
よって、憲法24条の下では、先ほど挙げた下記の要素を満たさない人的結合関係を「婚姻」とすることはできない。
・子の遺伝的な父親を特定できる組み合わせとすること
・特定された子の父親にも子に対する責任を担わせること
・特定された子の父親を基に遺伝的な近親者を把握すること
・未婚の男女の数の不均衡を防止できる組み合わせに限定すること
また、憲法24条は「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて、一夫一婦制(男女二人一組)を定めている。
その理由は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成するための手段として整合的な上記の要素を満たすからである。
そのため、これらの要素を満たさない人的結合関係については、憲法24条の「婚姻」の文言そのものや、「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言の趣旨に当てはまらず、「婚姻」とすることはできない。
もし、これらの要素を満たさない人的結合関係を「婚姻」として扱う法律を立法しようとした場合には、憲法24条の「婚姻」の文言そのものや「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言に抵触して違憲となる。
よって、憲法24条「婚姻」は、上記の要素と対応する形で「生殖と子の養育」の趣旨により統一的な理念に従って定められる枠組みであり、この憲法24条の下でこの趣旨を満たさない人的結合関係を「婚姻」とすることはできない。
▽ 憲法24条の「婚姻」が「生殖と子の養育」に関わる制度を一元的に集約していること
「婚姻」は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「生殖と子の養育」の観点から他の人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度である。
そして、24条は「婚姻」の内容について、「両性の合意のみ」や「個人の尊厳」「両性の本質的平等」を満たすように求めている。
これは、「婚姻」という制度については特に注意を払い、24条の統制に服させ、その内容に対して立法裁量の限界を画することが目的である。
この24条の規定が有する意図を実現するためには、「生殖と子の養育」に関わる制度を24条の「婚姻」の文言の中に一元的に集約する形で解釈することが必要であり、「生殖と子の養育」に関わる制度を24条の「婚姻」を離れて立法することはできない。
これは、下記が理由である。
仮に「生殖と子の養育」に関わる制度を、24条の「婚姻」から離れて別の制度として立法することができるとする場合を考えてみる。
すると、「生殖と子の養育」に関わる制度でありながら、24条によって統制(管理)することができない状態を許すことになる。
例えば、24条のいう「婚姻」とは別に「生殖関連制度」や「三人以上の生殖結社制度」などが立法されることが考えられる。
そうなると、24条は「婚姻」に対しては「両性の合意のみ」や「個人の尊厳」「両性の本質的平等」を満たすように求めて立法裁量の限界を画しているが、その「生殖と子の養育」に関わる制度は「婚姻」とは別の制度であることから、24条の統制が及ばないことになる。
すると、その「生殖と子の養育」に関わる制度は「婚姻」ではないため、「両性の合意」以外の条件を設けるものでも、「個人の尊厳」や「両性の本質的平等」に立脚しないものでも構わないことになる。
例えば、戦前の明治民法のような「戸主」の同意を必要とする「戸主付き生殖関連制度」や「家制度的生殖関連制度」を立法することも可能となる。
また、その「婚姻」とは異なる「生殖と子の養育」に関わる制度に対して「婚姻」よりも充実した優遇措置を整備した場合には、人々の大半はその制度を利用することを選択し、次第に「婚姻」を利用しなくなっていくことが考えられる。
すると、「婚姻」という制度が衰退していき、「婚姻」が「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するための制度として機能しなくなることが考えられる。
これでは、24条が「婚姻」に対して立法裁量の限界を画することによって、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために設けられた制度の内容が「両性の合意のみ」や「個人の尊厳」「両性の本質的平等」を満たすものとなるよう求める憲法上の立法政策としての目的を達成できない事態に陥る。
これでは、24条の趣旨が損なわれ、何のために24条が設けられているのか分からなくなる。
そのため、24条の規定の効果が保たれるためには、「生殖と子の養育」に関わる制度は24条の「婚姻」の文言が一元的に集約するものとして解釈することが必要となる。
このことから、「生殖と子の養育」に関わる制度を、24条の「婚姻」を離れて別の制度として立法することはできない。
もし「生殖と子の養育」に関わる制度を、24条の「婚姻」から離れて別の制度として立法しようとした場合には、24条の「婚姻」に抵触して違憲となる。
この前提がある以上は、24条の「婚姻」という文言の中には「生殖と子の養育」の趣旨が含まれており、この24条の「婚姻」の文言から「生殖と子の養育」の趣旨を切り離して考えることはできない。
これにより、「生殖と子の養育」の趣旨を満たさない人的結合関係を24条の「婚姻」として扱うことはできない。
▽ 憲法24条の「婚姻」から「生殖と子の養育」の趣旨が失われると24条の規定が有している目的を達成できないこと
仮に24条の「婚姻」という概念から「生殖と子の養育」の趣旨を切り離して考えることができるとする前提に立つとする。
すると、24条の「婚姻」の文言には「生殖と子の養育」の趣旨が含まれていないことになるから、24条の「婚姻」の文言には「生殖と子の養育」に関わる制度を一元的に集約しようとする趣旨も含まれていないことになる。
そうなると、「生殖と子の養育」に関わる制度について、24条の「婚姻」を離れて別の制度として立法することが可能となる。
「生殖と子の養育」に関わる制度が「婚姻」とは別の形で存在することを許すことになるから、「婚姻」が「生殖と子の養育」に関する様々な問題の発生を抑制しようとする機能を果たさなくなり、「婚姻」の政策効果が損なわれることになる。
また、その「生殖と子の養育」に関わる制度は、24条の「婚姻」とは別の制度であることから、24条の「両性の合意のみ」や「個人の尊厳」「両性の本質的平等」による統制が及ばないことになる。
つまり、その「生殖と子の養育」に関わる制度が、24条の「両性の合意のみ」や「個人の尊厳」「両性の本質的平等」を満たさないものとなっていても、それがもともと24条の「婚姻」ではないことを理由に、その制度の内容を是正することができなくなる。
これでは、本来「婚姻」を24条の統制の下に置くことによって、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するための制度の内容に対して「両性の合意のみ」や「個人の尊厳」「両性の本質的平等」を満たすように求めるという憲法上の立法政策を実現することができない事態に陥る。
これでは、24条の規定そのものが有する意図・目的を達成することができず、24条の規定が骨抜きとなる。
このような考えは解釈として妥当でない。
そのことから、「生殖と子の養育」に関わる制度については、24条の「婚姻」に結び付けて考える必要があり、24条の「婚姻」は「生殖と子の養育」に関わる制度を一元的に集約する趣旨を有している。
そのため、24条の「婚姻」を「生殖と子の養育」の趣旨と切り離して考えることはできない。
よって、「生殖と子の養育」の趣旨を満たさない人的結合関係を、24条の示している「婚姻」として扱うことはできない。
▼ 言葉の置き換えを繰り返すことはできないこと
上記のように、「婚姻」という枠組みが形成されている立法目的がある以上は、その「婚姻」という概念の中には、他の様々な人的結合関係との間で区別するための要素が存在する。
それは、「婚姻」の立法目的を達成するための手段として整合的な要素であり、下記が不可欠である。
・子の遺伝的な父親を特定できる組み合わせとすること
・特定された子の父親にも子に対する責任を担わせること
・特定された子の父親を基に遺伝的な近親者を把握すること
・未婚の男女の数の不均衡を防止できる組み合わせに限定すること
もしこれらの要素を満たさない人的結合関係を「婚姻」の中に含めようとした場合には、その時点で、これらの要素を満たさないことから、「婚姻」の立法目的を達成することができなくなることを意味する。
すると、そもそもそのような制度に対して法的効果や優遇措置を行う意味も失われ、制度を継続する必要性がなくなるし、制度を利用していない者との間でも不平等を生じさせるものとなることから、その「婚姻」と呼んでいる制度を廃止することに行き着く。
また、その「婚姻」と呼んでいる枠組みによっては、既に立法目的を達成することができなくなっていることから、その目的を達成するために「婚姻」以外の新たな制度を立法することが求められることになる。
しかし、それは結局、それまで機能していた本来の「婚姻」とまったく同様の目的を達成することを意図して立法されることになるから、上記の要素を満たす人的結合関係を新たな枠組みとして他の様々な人的結合関係とは区別する形で設けることになるものである。
こうなると、それはもともと「婚姻」が有していた機能を、新たな枠組みの制度が担おうとするものとなることから、そもそも「婚姻」から新たな枠組みの制度へと言葉の入れ替えを行っているだけの状態となるのである。
このような言葉の置き換えという無意味なループを繰り返すことを防ぐためには、「婚姻」という枠組みが存在する時点で、そこには「婚姻」という枠組みを形成している立法目的が存在しており、その「婚姻」という枠組みそのものにその立法目的との間で整合性を保つことができる内在的な限界が含まれていることを捉える必要がある。
そして、その内在的な限界となる要素を満たさない人的結合関係を「婚姻」の中に含めようとする試みは、「婚姻」という概念そのものが有している本来の意味、内在的な機能を改変し、消失させようとするものとして排斥することが必要となる。
これによって、「婚姻」という概念そのものの枠組みを維持し、「婚姻」という概念そのものが消失することを防ぎ、「婚姻」という言葉の意味が成立する状態を保つことができるからである。
そのことから、「婚姻」という枠組みが形成されている背景にある立法目的が正当である以上は、その立法目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす人的結合関係については「婚姻」として扱うことができ、それを満たさない人的結合関係については「婚姻」として扱うことはできない。
このような差異が生じることは「婚姻」という枠組みが形成されている時点でもともと予定されていることである。
この差異を否定するのであれば、それはそもそも「婚姻」の立法目的を否定することになることを意味する。
「婚姻」の立法目的が正当と認められる以上は、その立法目的を達成するための手段として設けられている枠組みによって生じる差異は、法制度が政策的なものであることからくる誰もが甘受しなければならないものである。
▼ 主張の基盤を失わせる主張であること
24条が定めている「両性の合意のみ」や「個人の尊厳」の文言を根拠として、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」の中に含めることができるはずであるとの主張がある。
しかし、この主張に従って「同性間の人的結合関係」を「婚姻」の中に含めた場合には、24条の「婚姻」から「生殖と子の養育」の趣旨が失われることになる。
こうなると、24条の「婚姻」の文言は「生殖と子の養育」に関わる制度を一元的に集約する趣旨を有していないことになる。
すると、「生殖と子の養育」に関わる制度を、24条の「婚姻」を離れて別の制度として立法することが可能となる。
その「生殖と子の養育」に関わる制度は、「婚姻」ではないことから、24条の「両性の合意のみ」や「個人の尊厳」「両性の本質的平等」を満たさなくとも構わないことになる。
例えば、戦前の明治民法のような「戸主」の同意を必要とする「戸主付き生殖関連制度」や「家制度的生殖関連制度」を立法することも可能となる。
そして、その「婚姻」とは異なる「生殖と子の養育」に関わる制度に対して「婚姻」よりも充実した優遇措置を整備するようになった場合には、人々の大半はその制度を利用することを選択し、次第に「婚姻」を利用しなくなっていくことが考えられる。
この影響で、「婚姻」という制度が衰退していき、「婚姻」が「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するための制度として機能しなくなることが考えられる。
すると、実質的に24条の規定が無意味なものとなり、24条が「婚姻」に対して「両性の合意のみ」や「個人の尊厳」「両性の本質的平等」を満たすものとなるように立法裁量の限界を画している意味が希薄化してしまう。
そうなると、もともと24条の「両性の合意のみ」や「個人の尊厳」を根拠として、「同性間の人的結合関係」を24条の「婚姻」の中に含めることができると主張し、それによって「同性間の人的結合関係」についても優遇措置を得られると期待していたにもかかわらず、それをした場合には、そもそも「婚姻」から「生殖と子の養育」の趣旨が失われることから、結果として「生殖と子の養育」に関わる制度を「婚姻」とは別の制度として立法することを許すことに繋がり、その別の制度の優遇措置が増えるなどしてその制度が主流化し、もともと「婚姻」の中に「同性間の人的結合関係」を含めることによって得られると期待していただけの優遇措置を「婚姻」という制度からは得られない状態に陥ることになるのである。
そのため、24条が定めている「両性の合意のみ」や「個人の尊厳」の文言を根拠として、「生殖と子の養育」の趣旨を満たさない人的結合関係についても「婚姻」の中に含めるべきであるとの主張は、結果として、自己の主張の基盤さえも失わせる主張となっているということができる。
よって、24条の定める「両性の合意のみ」や「個人の尊厳」の文言を根拠として、24条の「婚姻」の中に「生殖と子の養育」の趣旨を満たさない人的結合関係を含めることができるとの主張は成り立たない。
もし「生殖と子の養育」の趣旨を満たさない人的結合関係を「婚姻」とする法律を立法しようとした場合には、24条の「婚姻」に抵触して違憲となる。
(「両性の合意のみ」や「個人の尊厳」の文言を用いて憲法24条の「婚姻」の枠組みを変更することができないことについては、「同性婚訴訟 札幌高裁判決の分析」のページでも詳しく解説している。)
■ 整合的な理解
これらを前提として、改めて検討する。
「婚姻」という概念は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために設けられた枠組みである。
そのため、「婚姻」という概念に含めることができる人的結合関係には、その概念が形成されている目的との関係で内在的な限界がある。
そして、「婚姻」の中には「生殖と子の養育」の趣旨が含まれており、これを満たさない人的結合関係を「婚姻」の中に含めることはできない。
また、憲法24条が「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めており、これもこの「生殖と子の養育」の趣旨と整合する形で定められたものとなっている。
「同性間の人的結合関係」については、その間で「生殖」を想定することができず、この「生殖と子の養育」の趣旨を満たすとはいえないことから、「婚姻」の中に含めることはできない。
また、憲法24条の「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言の趣旨にも当てはまらないため、「婚姻」とすることはできない。
結果として、憲法24条は「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とする法律を立法することを認めていないことになる。
他にも、憲法24条は「婚姻」を定めていることから、この憲法24条の「婚姻」や「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言が、法律で立法される婚姻制度の意味や内容を「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するものとして機能しないものに変えてしまうことを許しているはずがない。
そのため、婚姻制度の中に「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することが不能となるような人的結合関係を含めようとする法律を立法することを、憲法24条の「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言に照らし合わせて考えた際に、これらの文言はそれを許容していない。
よって、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することが不能となるような人的結合関係を「婚姻」として扱おうとする法律を立法した場合には、憲法24条の「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言に抵触して違憲となる。
このことから、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とする法律を立法しようとした場合には、憲法24条の「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言に抵触して違憲となる。
■ 生殖関係を整理するために性別は不可欠であること
「婚姻」は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられている枠組みである。
「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することは不可欠の目的であり、法制度として「婚姻」以外にこれを担うものは存在していない。
また、そもそも「婚姻」は、婚姻制度を利用した場合に法的効果や一定の優遇措置を得られるようにし、婚姻制度を利用しない場合との間に差異を設けることにより、婚姻制度を利用することに対してインセンティブを働かせ、婚姻制度を利用する者を増やすことによって目的の達成を目指す仕組みのものである。
そのため、その「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するための枠組みを規律するものとして唯一の制度となっていることがその機能を果たすための本質的な要素であるということができる。
このことから、この「婚姻」が排他的にその機能を担うことが本来的に求められている。
そして、その機能を担うものとして「生殖」との間で定義される「男性」と「女性」の「性別」を区別することを予定し、その区別に従った組み合わせを法的に結び付けることで、その目的を達成することを目指すものとして定められている。
そのため、このように「性別」によって区別され、その「性別」に基づいた形で制度を利用できる組み合わせを指定することは、その目的を達成するための手段として不可欠の要素として設けられる枠組みであるといえる。
そして、憲法24条は「婚姻」を規定し、この規範を「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)として定めているのであるから、「生殖」の関係において定義される「男性」と「女性」を組み合わせ、その間で子供が産まれた場合に遺伝的な父親を特定することができるというところにその枠組みを定めていることの意義を見出すことができるといえる。
このように、その目的を達成するための手段として整合的な枠組みとなっていることを確認することができる以上は、そこに規範的な意味を見出し、その枠に従った形で法制度を運用することにより、立法目的を達成することが予定されている。
このことから、憲法24条の「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言が、目的を達成するための手段となる枠組みに対応するものとして意味を構成している事実を確認できる以上は、その文言が示している枠組みに含まれている趣旨や、目的とその目的を達成するための手段の関係を無視することは解釈として正当化することのできるものではない。
そのため、憲法24条が「婚姻」について「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めることによって立法目的を達成しようとしている枠組みを変えることはできない。
これにより、憲法24条が「婚姻」を規定し、「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)の枠組みを定めていることについて、これをそれ以外の人的結合関係を指すものとして読み解くことはできない。
よって、これらの文言の中に「同性間」の人的結合関係が含まれるかのように考えることは誤りとなる。
■ 男女を区別する制度として定められていること
憲法24条1項には「両性」「夫婦」の文言が定められている。
これらの文言は「男性」と「女性」を区別することを前提としていることから、「性別」を区別することによって立法目的を達成することを意図するものであることは明らかである。
また、その「性別」による区別を前提とした上で、「男性」のグループと「女性」のグループのように同じ「性別」の者を集めてグループにするわけではなく、敢えて「男性」と「女性」という異なる性別の者同士を組み合わせることによって立法目的を達成することを意図していることも明らかである。
このように、異なる性別の二者を法的に結び付ける枠組みを設ける意図は、生物学的な因果関係から見て「男性」と「女性」の間に「貞操義務」を設けた場合に、産まれてきた子供の遺伝的な父親を特定することができる関係になるというところにある。
これは、人間が生命体として有性生殖を行う仕組みに着目し、人間の性質を「生殖」との関係において定義される「精子を生成し、陰茎を有するタイプ」の「男性」と、「卵子を生成し、妊娠し、子を産む機能を備え、膣を有するタイプ」の「女性」とに区別した上で、女性の子宮の中で「精子」と「卵子」が結合することによって子が生じるという状態に至る際に、その女性の「卵子」と、どの男性の「精子」が結合したかが明らかであるならば、そこで産まれてきた子に対して責任を担う者を特定することができる状態となるというところに意図があるといえる。
このため、「両性」「夫婦」という文言が使われていることの意味は、「男性」と「女性」を区別するものであることを前提とし、かつ、その区別を前提に敢えてその異なる性別の者同士を法的に結び付けることを意図していることは明らかである。
このような枠組みを設けることによって、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目指すものとして定められていることから、「両性」「夫婦」の文言を「生殖」との関係から切り離して用いることはできない。
そのことから、「婚姻」における「両性」「夫婦」などの文言は、「生殖」という営みと対応するものとして位置付けられている言葉であり、これを「男性」と「女性」の意味を離れて理解することは不可能である。
そのため、このような意図を達成することを阻害するものを、この「両性」「夫婦」の文言と照らし合わせて考えた場合には、その制度が「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するものとして機能するか否かという点で根本的に異なるものであり、相いれないものということになる。
そのようなものについては「両性」「夫婦」の中に含まれないこととなる。
このことから、「婚姻」とすることができる人的結合関係の範囲は、これらの意図を満たす「男性」と「女性」の両方が揃うことが必要であり、それを満たさない組み合わせについては「婚姻」とすることができない。
よって、「同性間の人的結合関係」が「両性」「夫婦」の文言の中に含まれると考えることはできず、「同性間の人的結合関係」がここに含まれるかのように述べることは誤りとなる。
■ 「法の支配」との関係
文字によって記されている言葉があり、その言葉の意味を理解し、その言葉が示す通りの行動を行った場合に、何らかの紛争を解決する機能を有しているのであれば、そこには法としての規範性を見出すことができるものとなっていることを意味する。
これを無視して、その文言の意味に沿わない制度の創設を許すことになれば、言語(文字)によって規範を設定し、予め基準を示すことによって、為政者の恣意的な権力行使を防ごうとする法の支配や立憲主義、法治主義を採用して国家運営を行っていることにはならない。
もしこれが可能となった場合には、法の条文にどのような文字を定めたとしても、その意味をその時々に権力を行使する者がいかようにでも無効化することができてしまうこととなり、法の支配、立憲主義、法治主義を採用している意味そのものが失われることになる。
つまり、条文を定める際にどんなに丁寧に言葉を選んだとしても意味がなくなるということである。
これでは、紛争の解決を法によって、つまり、客観性・明確性を持つ形で言語化された公のものとして示された基準に従って紛争を解決する作用によって行おうとする姿勢に反するものとなる。
そのため、日本国憲法を掲げ、法という秩序によって国家運営を行っている以上は、言葉が示す規範を歪める形で運用することは行ってはならないことである。
憲法24条に「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」という言葉が使われているのであれば、それは制度の枠組みについて具体的に基準を示していることを意味するのであって、その文言の意味に沿わない制度を立法することはできない。
そのため、憲法24条の「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言が一夫一婦制(男女二人一組)を定めていることの趣旨に沿わない人的結合関係がこの中に含まれているかのように主張することは誤りである。
■ 法解釈の限界との関係
「法の支配」とは、予め言語を用いて規範を示すことで将来起こる紛争を解決するための基準とするものであることから、法を解釈する過程の中で言葉の意味や定義そのものを変更することはできない。
もしそれをしようとすることは法解釈の限界を超えるものとして、そこで解釈しようとした条文そのものに反して違法となる。
そのため、その領域に踏み込む問題については、立法府によって条文を改正あるいは廃止するか、憲法改正の手続きによって憲法上の条文を改正あるいは廃止することによって対応することが必要である。
憲法は改正する手続きを用意しており、これによって憲法上の規定を改廃することが可能である以上は、憲法上の文言の意味そのものを別の意味に変えようとすることは、解釈の限界を超えるものである。
「婚姻」の文言の中に「男女」を満たさない人的結合関係が含まれているとか、含まれるべきであるとの主張は、「婚姻」という言葉を単なる「音の響き」に過ぎないものにまで解体し、言葉の意味そのものを改変して新たな意味を付与しようと試みるものということになる。
これは、言葉の意味を読み取って規範の意味を明らかにしようとするものとはいえないことから、法を解釈するという営みの中で正当化することができる範囲を超えており、法解釈としての限界を超えるものである。
これは、憲法上の規定を改廃する手続きによってしか行うことのできない領域に踏み込むものであり、解釈として妥当性を有しておらず、規範の意味から逸脱した違法な解釈となる。
このような解釈の限界を超えた判断を行うことは、後に別の角度から訴訟が起こされた場合に、その解釈そのものが否定され、その解釈が憲法に違反すると判断されることを導くことになる。
そのため、法の条文の中に具体的な定義について逐一触れていないとしても、その文言そのものが有する意味や条文の構造、条文の持つ趣旨や目的に拘束されるのであり、裁判所がそれを超える意味を新たに加えることが可能となるわけではない。
つまり、言葉の意味が歪められるようなことがあってはならないということである。
よって、憲法24条の「婚姻」の概念が有する内在的な限界を考慮せずに、どのような人的結合関係でも「婚姻」に含まれる余地があるかのように主張することは誤りである。
もし憲法24条の「婚姻」の範囲を超える制度が設けられたとしても、後に訴訟が起こされた場合には、憲法上の文言に含まれているものではないことから、これが含まれるとした裁判所の判決の違法性が発見され、その内容が見直され、その判決の内容が無効化されることになる。
■ いくつかの立場との関係性
上記のような理解について、憲法24条の条文の意味を読み取る際のいくつかの立場との関係は下記のように整理することができる。
▼ 「婚姻」の由来
この立場は、「婚姻」という枠組みが形成された由来を遡り、「婚姻」という概念そのものが有している「目的」とその目的を達成するための「手段」とを整合的な形で考えるものである。
「婚姻」という枠組みが形成された由来を考えるため、「婚姻」という概念そのものが有している内在的な限界も考慮することになる。
これについては、上記で解説した通りである。
◇ 存在しない説
この立場は、「婚姻」とは自然生殖可能性のある組み合わせを優遇する制度であることから、それを満たさない形の「婚姻」というものは存在しないと考えるものである。
「同性間」についても、その間で自然生殖を想定することができないことから、「婚姻」とはいえず、「同性間」の「婚姻」という概念は存在しないことになる。
国(行政府)の主張の中で、この立場に重なる部分は下記がある。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
イ しかしながら、法の解釈に際し、文言の日本語としての意味や文法が重視・尊重されなければならず、文言からかけ離れた解釈が許されないのは当然であるところ、前記2(2)
において述べたとおり、「両性」とは、両方の性、男性と女性又は二つの異なった性を意味し、「夫婦」とは、夫と妻又は適法の婚姻をした男女の身分を意味する文言であり、「両性」及び「夫婦」が男性又は女性のいずれかを欠き当事者双方の性別が同一である場合を含む概念であると理解する余地はなく、このような理解は、憲法24条1項の制定過程及び審議状況からも裏付けられている。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【東京一次・第1回】控訴答弁書 令和5年6月23日 PDF (P22~23)
◇ 成立条件説
この立場は、憲法24条1項の「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、」の文は「婚姻」の成立条件を示すものと考えるものである。
「婚姻」を成立させるためには「両性」である「男性」と「女性」の合意を必要とすると定めていることから、「同性間」で合意しても「婚姻」としては成立しないことになる。
国(行政府)は下記のように述べている。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
他方、同条2項は、婚姻等に関する事項について具体的な制度を構築するに当たっての立法上の要請及び指針を示したものであるが、上記のとおり、婚姻の成立については、同条1項により、両性の合意のみに基づいて成立する旨が明らかにされていることから、婚姻の成立要件等を定める法律は、かかる同条1項の規定に則した内容でなければならない。そのため、婚姻等に関する事項について立法上の要請及び指針を示した同条2項においては、同条1項の内容も踏まえ、配偶者の選択ないし婚姻等に関する法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならないとしたものである(憲法24条2項における配偶者の選択とは婚姻の相手の選択であるから、それについて、法律が個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならないということは、婚姻が当事者の自由な合意のみによって成立すべきことを意味し、同条1項の規定と同趣旨であると解されている(佐藤功「憲法(上)[新版]」414ページ。乙第33号証))。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【東京一次・第1回】控訴答弁書 令和5年6月23日 PDF
◇ 想定していない説
この立場は、憲法24条は「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを想定していないと考えるものである。
上記の三説と下記の三説のいずれの可能性もある。
国(行政府)は、下記のように「成立させること」と「想定していない」の両方を用いて説明している。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ア もっとも、前記(1) のとおり、憲法24条1項は、「両性」及び「夫婦」という文言を用いているところ、一般的に、「両性」とは、両方の性、男性と女性又は二つの異なった性を意味し、「夫婦」とは、夫と妻又は適法の婚姻をした男女の身分を意味するものとされている(新村出編・広辞苑第7版2526及び3095ページ)ことからすると、同項にいう「夫婦」や「両性」もこれと同義とみるべきであるから、憲法は、「両性」の一方を欠き当事者双方の性別が同一である場合に婚姻を成立させることをそもそも想定していないというべきである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【東京一次・第1回】控訴答弁書 令和5年6月23日 PDF (P14)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ア しかしながら、法の解釈に際し、文言の日本語としての意味や文法が重視・尊重されなければならず、文言からかけ離れた解釈が許されないのは当然であるところ、これまで繰り返し述べているとおり、憲法24条1項は、「両性」及び「夫婦」という文言を用いており、一般に、「両性」とは、両方の性、男性と女性又は二つの異なった性を意味し、「夫婦」とは、夫と妻又は適法の婚姻をした男女の身分を意味するものとされている(新村出編・広辞苑第7版2526及び3095ページ)ことからすると、同項にいう「夫婦」や「両性」もこれと同義とみるべきであるから、憲法は、「両性」の一方を欠き当事者双方の性別が同一である場合に婚姻を成立させることをそもそも想定していないというべきである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【東京二次・第9回】被告第7準備書面 令和5年9月28日 PDF (P5)
◇ 立法裁量の限界を画するもの
この立場は、憲法24条は立法裁量の限界を画する規定であることから、24条の文言に沿わない関係については、「婚姻」とすることができないと考えるものである。
憲法24条は「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めており、この形に限定して立法裁量の限界を画していることから、それ以外の人的結合関係を「婚姻」とすることはできない。
「同性間の人的結合関係」についても、これを満たさないため「婚姻」とすることはできないことになる。
◇ 禁止説
この立場は、憲法24条の規定は、何かを認知した上でそれを防ぐ意図をもって定められていることから、その規定に合わないものについては禁止されていると考えるものである。
「同性間の人的結合関係」についても、憲法24条の規定が「両性」「夫婦」の文言を定めていることに合わないことから、憲法24条は「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることの論点を認知した上で、それを防ぐ意図をもって禁止していることになる。
◇ 義務文・否定文による禁止説
この立場は、憲法24条1項の規定は「両性~に基づいて成立し、~なければならない。」(shall)という義務文・否定文による禁止の意味を有すると考えるものである。
これによれば、憲法24条1項は「両性」を満たさない人的結合関係を「婚姻」とすることを義務文・否定文によって禁止していることになる。
「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることについても、「両性」を満たさないため義務文・否定文によって禁止されていることになる。
■ 条文解釈の方法
条文の意味を解釈する際には、その条文に記された文言がどのような意味を持っているかを検討することが必要である。
また、単にその条文の文言から意味を読み取るというだけでなく、その条文に関連する他の規定が存在するのであれば、その関連する規定と照らし合わせて整合的に読み解くことが必要である。
それでもまだ意味が不明瞭な部分については、その条文を含む制度の枠組みの全体を整合的に読み解くことができる目的を特定することが求められる。
これは、その制度の全体をその目的に照らし合わせて整合的な形で統一的に理解することにより、一つ一つの条文の意味を正確に読み解くことが可能となるからである。
このように制度の全体を整合的に読み解くことができる理解を基にして考えることで、条文に記された一つ一つの文言が持つ意図を正確に導き出すことが可能となり、その文言の持つ意味の射程を把握することが可能となる。
これにより、具体的な事例に対してその条文を適用することができる場合であるか否かや、その条文の下で定められている制度(下位法)があればその制度の形を変更することができるか否か、また、その限界を判断することが可能となる。
しかし、その判断の過程でこの目的を特定する作業に失敗すると、その誤った目的に従って制度の枠組みを変更したことによって、その制度が本来予定していた機能が損なわれたり、その制度全体を整合的に理解することが不可能となって制度そのものが成り立たなくなるなど、制度そのものが破壊されてしまうことが起こり得る。
また、一度その「目的」を見誤って、その「手段」となっている制度の枠組みを変えてしまった場合には、その誤った「目的」が別の事案においても主張され続けることとなり、次々にその「手段」となっている制度の枠組みが突き崩されていくことに繋がる。
すると、その制度が本来予定していた機能を果たさない状態に変わってしまうことになる。
そのため、「目的」を特定するにあたっては、このような事態に陥ることがないように、断片的な判断を行うのではなく、制度の全体を見渡してすべての規定の意味を整合的に理解することができる状態を保つことができるように注意深く検討することが必要である。
特に、その制度がもたらす個別の効果のみに着目して、その個別の効果を生じさせている個別の規定が有している目的を基にして考えてしまうことで、その制度の全体が存在していることそのものが有している目的を見失うようなことがあってはならない。
また、目的を特定する際に注意するべきなのは、現在の制度がよく機能しており、その制度が有している目的が十分に達成されていることから、現在の社会の中で問題が表面化していないという場合を見逃してはならないことである。
これについて、下記の動画が参考になる。
【動画】天皇と合理性。伝統は伝統であるが故に尊い!合理性という浅知恵と何世代も培った伝統という叡智|竹田恒泰チャンネル2 2024/04/04
このように、その制度が有する目的が十分に達成されており、社会的な不都合に出くわす場面が少ない中では、逆にその制度が存在しない場合に起こり得る問題を十分に想定することができなくなってしまい、その制度が有する目的を正確に捉えることができていない者が現れることがある。
そして、その制度が有している立法目的を捉え間違えた者によって国家権力(立法権、行政権、司法権)が行使されることで、むやみに制度の内容が変更されたり、制度そのものが廃止されたりすることによって、今までその制度が存在する中では表面化していなかった問題が後に顕在化するということが起こり得る。
そのため、そもそも何を目的として定められた制度なのかを十分に捉えることができなくなっている場合や、制度の有している目的とその目的を達成するための手段となる具体的な枠組みとの関係にどのような意図が含まれているのかを忘れてしまっている場合に制度を変更しようとすることは危険である。
そのことから、安易に制度の目的を理解したかのように思い込んでしまい、その目的であると思い込んだ事柄を理由にして制度を変更することができると結論付けてしまうようなことがあってはならない。
そのため、その制度全体が有している目的が定まるまでの背景にある社会的な不都合を解消しようとする事実を見ないままに、安易に目的を理解したと思い込んでしまっていないか、常々点検しながら検討することが必要である。
このため、この目的を特定する作業を失敗しないためには、その制度が機能している以前の状態の中で、何が求められ、どのような目的をもって形成されたのか、その原点に立ち戻って検討することが必要である。
つまり、その社会の中でその制度が存在しない状態にまで遡り、その状態で起こり得る問題を勘案し、そこで生じる不都合を解消するという視点を基にして目的となっているものを導き出すことが必要である。
この過程で、制度の全体を整合的に理解することができなくなったり、制度を機能しないものに変えてしまうような一線を損なわせることに繋がる事柄については、それをその制度の目的として理解することはできないことになる。
つまり、そのような事柄をその制度の「目的」として考えることを正当化することはできず、そのような事柄は退けられるということである。
また、このように、その社会の中でその制度が存在しない状態で起こり得る問題を勘案することによって、その制度の目的とその目的を達成するための手段となっている具体的な条文との関係を特定することが可能となる。
そして、その条文が、その目的を達成するための手段としてどのような関係の下に位置付けられているかを明らかにすることにより、その条文に記された一つ一つの文言の意味を正確に読み解くことが可能となり、その文言に含まれる規範の意味を導き出すことが可能となる。
これを前提に、「婚姻」についても、法が「婚姻」という制度を設けることによって、何を実現しようとしているのかを考え、その目的を特定することが必要である。
これは、その目的と照らし合わせて考えることによって、「婚姻」という制度について定めた条文や、その条文に記された一つ一つの文言の意味を正確に読み解くことが可能となり、制度を変更することの可否やその限界を見出すことが可能となるからである。
ここで注意するべきなのは、現在の婚姻制度がよく機能していることによって、婚姻制度の有する目的が十分に達成されており、現在の社会の中で不都合な問題が表面化していないという場合を見逃してはならないことである。
そのため、その社会の中で婚姻制度が存在しない状態にまで遡り、その状態で起こり得る問題を勘案し、そこで生じる不都合を解消するという視点を基にしてその目的を導き出すことが必要である。
この過程で、「婚姻」の枠組みが予定している機能が損なわれるような事柄や、「婚姻」の枠組みを整合的に理解することができない事柄、今回の事案では直ちに何らかの影響が見られないとしても、その後、他の訴訟が提起された場合などに、そこで用いられた目的と称しているものを理由として制度の変更がなされると「婚姻」の枠組みが予定している機能が損なわれてしまうような整合性のないものについては、それを「婚姻」という枠組みの目的として理解することはできない。
そこで、「婚姻」という概念が担っている事柄を検討し、その目的と、その目的を達成するための手段となる枠組みとの関係を検討する。
その社会の中で何らの制度も設けられていない場合には、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合が発生する。
例えば、「父親不明」の子供が増える、父親を特定できない子供が増える、父親が蒸発して行方不明になった子供が増える、それらにより「子の福祉」が減少する、父親を特定できないことにより近親者の範囲を把握できずに「近親交配」に至り潜性遺伝子の発現した個体が高い確率で生じるようになる、一部の強者が多数人との生殖関係を独占することによって社会の中で「子を持ちたいと希望して相手を見つけようとする男女」の数の不均衡が生じて「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」が生まれる、低年齢での妊娠・出産により母体に危険が及ぶ、などの問題が生じることがある。
これらの不都合を解消するために、下記のような立法目的を有する枠組みを設けることが必要となる。
・「子の福祉」が実現される社会基盤を構築すること
・潜性遺伝子の発現した個体が高い確率で生じることを抑制すること
・「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」を減らすこと
・母体を保護すること
そして、これらの目的を達成するためには、下記の要素を満たす枠組みを設けることが必要となる。
・子の遺伝的な父親を特定できる組み合わせとすること
・特定された子の父親にも子に対する責任を担わせること
・特定された子の父親を基に遺伝的な近親者を把握すること
・未婚の男女の数の不均衡を防止できる組み合わせに限定すること
これらの要素を満たすものとして「一人の男性」と「一人の女性」が選び出され、その間に「貞操義務」を設け、その関係を法的に結び付ける形を「婚姻」と呼んでいる。
そして、この「婚姻」に対して法的効果や一定の優遇措置を設けることで、婚姻制度を利用する者を増やし、これらの目的を達成することを目指すことになる。
憲法24条はこの「婚姻」について規定しており、「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めている。
これも、上記の要素と対応するものとして定められている。
これが「婚姻」という概念が有している目的とその目的を達成するための手段として導かれる枠組みとの関係である。
このように、「婚姻」は、人間が有性生殖を行うことによって子孫を産むという身体機能を有しており、その男女の間で行われる「生殖」の営みに関わって生じる不都合が社会的な課題となっていることから、その不都合を解消するために設けられている枠組みである。
つまり、人間の有性生殖の営みに着目して設けられている枠組みということである。
そして、この「婚姻」という枠組みが形成された当初から現在までの間に、人類が有性生殖の機能を失ったり、人類が無性生殖をする生き物に進化したりしたという事情は認められない。
そのため、その「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することの必要性は「婚姻」という枠組みが形成された当初から現在においてまで何ら変わるものではない。
このため、その社会の中で「婚姻」という枠組みがその不都合を解消するものとして機能することが求められていることにも変わりはない。
そのことから、「婚姻」の概念が「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消する仕組みとしての役割を担っていることに変わりはなく、これをこの機能を果たさない別の概念へと変えてしまうということはできない。
そのため、「婚姻」という枠組みが形成された当初から現在においてまで、上記で示した「婚姻」の枠組みが有している目的と、その目的を達成するための手段として整合的な要素との関係に何らの変わりはない。
よって、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的と、憲法24条の「婚姻」という文言それ自体や「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言との対応関係を照らし合わせて考えた場合に、これらの文言は一夫一婦制(男女二人一組)の婚姻制度を定めることによってその目的を達成することを予定しているものであるということができる。
このように目的との間で対応関係の見られる文言が条文の中に具体的に存在している以上は、その文言を意味を無視することは許されず、この憲法24条の「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言の意味を自由に変更することができるということにはならない。
このことから、憲法24条が「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)の枠組みを定めており、この枠組みに従う形で法律を立法することを「要請」していることから、これらの文言は婚姻制度の内容を一夫一婦制(男女二人一組)で定めることを「要請」しているということができる。
そして、もしこれを満たさないものを「婚姻」とする法律を立法した場合には、憲法24条がこのような意図を持つ枠組みを定めることによってその目的を達成することを「要請」している趣旨に反するものとなるから、憲法24条に違反することになる。
■ 区別により意味が成り立つ概念であること
そもそも「婚姻」とは、「婚姻」と「それ以外の人的結合関係」や「人的結合関係以外の概念」との間で「区別」するものとして意味を形成している概念である。
これは、特定の事柄について、「婚姻」という名前を付けることによって他の事柄との間で区別し、それを識別することを可能としているものだからである。
そのため、「婚姻」という言葉を用いてそれ以外の概念と「区別」しているという時点で、「婚姻」の中に含まれる人的結合関係と含まれない人的結合関係とが存在することはもともと予定されているといえるものである。
そのことから、「婚姻」という言葉を用いて何らかの対象を指し示そうとしているにもかかわらず、「区別」をするべきではないとか、「区別」してはならないだとか、「区別」はなされるべきではないなどという前提はそもそも成り立たないものである。
そして、そこでいう「婚姻」は、人間が有性生殖を行うことによって子を産むという身体機能を有していることに着目し、その「生殖」によって生じる社会的な不都合を解消するために、その「生殖」との関係において整合的な形で「男性」と「女性」を選び出し、その間に「貞操義務」を設けるなど一定の形式で法的に結び付けるものとして不都合の解消を目指すものである。
この機能を有する概念は「婚姻」以外に存在しておらず、その社会の中で「婚姻」という概念がこの目的を達成するための手段として機能することが求められている以上は、この「婚姻」という言葉を別の意味として用いることができることにはならない。
そして、人間が有性生殖という2つの異なる生殖細胞を有する個体が互いの生殖細胞を交配させることによって子孫を産むという身体機能を有しており、その「生殖」という営みに関わって社会的な不都合が生じる限りは、それを解消するという目的を達成するための手段として、その「生殖」との関係において異なる身体的な特徴を有する者として定義される「男性」と「女性」を区別し、その区別に従って生殖関係を整理し、社会的な不都合を解消する仕組みを持つ制度を設けるという方法は、その目的を達成するための手段として最低限必要となる要素に着目して枠組みを設けているという意味で合理的なものである。
そのことから、その間で「生殖」を想定することができる「異性間の人的結合関係」と、「生殖」を想定することができない人的結合関係(同性間の人的結合関係)とを区別することは、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成するための手段として意図的に区別されているものである。
そのため、「婚姻」という言葉そのものを、これを区別しないものとして扱うことはできない。
よって、「婚姻」という言葉の中に、「同性間の人的結合関係」を含めることはできない。
「婚姻」という概念が形成されている背景にある「目的」と「その目的を達成するための手段」となる枠組みの関係を切り離して、「婚姻」の意味そのものを単なる「音の響き」に過ぎないものにまで解体した上で、その空箱となった「音の響き」に過ぎないものに対してどのような人的結合関係でも詰め込むことができるかのように論じることは妥当でない。
そのような論じ方は、条文に記された文言の意味を解体して無意味なものとし、法律上の規範としての意味を失わせるものとなるから、法解釈として不適切である。
このような「婚姻」の定義や意味そのものを変えようとする試みの不当性について、「説得定義」の議論が参考になる。
【動画】【ハイライト】憲法を変えるな!~安保法制違憲訴訟の勝利を目指して ―講演:石川健治 東京大学教授 2022.1.27
■ 結論
このように、憲法上の文言に従う解釈を行った場合に、そこに目的を達成するための手段として整合的な枠組みとなっていることを確認することができ、憲法上の規範としての意義を見出すことができる以上は、そこに規範的な力を認めることによって、憲法の規範性を保つことが求められる。
そのため、この判決では「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることができるかのように論じようとしているが、上記の点を考慮しないものであり、その結論は正当化することができない。
婚姻制度と矛盾する制度は立法できないこと
この東京高裁判決では、「同性間の人的結合関係」を対象とした制度を立法することができることを前提として論じている。
しかし、そもそも「同性間の人的結合関係」を対象とした制度を立法することができるのかという点から検討することが必要である。
■ 婚姻制度の概要
「婚姻」は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために設けられた枠組みである。
これは、下記のような経緯によるものである。
その国の中で「生殖と子の養育」に関する事柄について何らの制度も存在しない場合には、社会的な不都合が発生することがある。
例えば、「父親不明」の子供が増える、父親を特定できない子供が増える、父親が蒸発して行方不明になった子供が増える、それらにより「子の福祉」が減少する、父親を特定できないことにより近親者の範囲を把握できずに「近親交配」に至り潜性遺伝子の発現した個体が高い確率で生じるようになる、一部の強者が多数人との生殖関係を独占することによって社会の中で「子を持ちたいと希望して相手を見つけようとする男女」の数の不均衡が生じて「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」が生まれる、低年齢での妊娠・出産により母体に危険が及ぶ、などの問題が生じることがある。
これらの不都合を解消するために、下記のような立法目的を有する枠組みを設けることが必要となる。
・「子の福祉」が実現される社会基盤を構築すること
・潜性遺伝子の発現した個体が高い確率で生じることを抑制すること
・「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」を減らすこと
・母体を保護すること
そして、これらの目的を達成するためには、目的との関係で整合的な下記の要素を満たす枠組みを設けることが必要となる。
・子の遺伝的な父親を特定できる組み合わせとすること
・特定された子の父親にも子に対する責任を担わせること
・特定された子の父親を基に遺伝的な近親者を把握すること
・未婚の男女の数の不均衡を防止できる組み合わせに限定すること
これらの要素を満たすものとして「一人の男性」と「一人の女性」が選び出され、その間に「貞操義務」を設け、その関係を法的に結び付ける形を「婚姻」と呼んでいる。
そして、この「婚姻」に対して法的効果や一定の優遇措置を設けることによって、制度を利用する者を増やし、これらの立法目的の実現を目指す仕組みとなっている。
憲法24条でも「婚姻」について「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて、一夫一婦制(男女二人一組)を定めている。
憲法24条が一夫一婦制(男女二人一組)を定めている理由は、「婚姻」が有している目的を達成するための手段として整合的な上記の要素を満たすからである。
そして、憲法24条の「婚姻」の枠組みの「要請」に従って、法律上で具体的な婚姻制度が定められることになる。
■ 婚姻制度の「趣旨・目的・内容・効果」
婚姻制度は、「男性」と「女性」の間に「貞操義務」を設けることによって、その「女性」から生まれてくる子供の遺伝的な父親を特定することを重視するものとなってる。
これは、産まれてくる子供に対して、母親だけでなく、父親にも責任を担わせることによって、「子の福祉」の充実を期待するものとなっているからである。
子は何らの因果関係もなく突然「女性」の腹から生まれてくるわけではないため、その子が生じるという因果関係の一旦を担う父親に対してその子に対する責任を担わせる仕組みとすることは、逃れることのできない責任を有する者として合理的ということができるからである。
また、遺伝上の父親を特定できることは、遺伝上の近親者を把握することが可能となるため、その近親者との間で「婚姻」することができない仕組みを導入することで、「近親交配」に至ることを防止することが可能となる。
これによって、産まれてくる子供に潜性遺伝子が発現することを抑えることが可能となり、産まれてくる子に遺伝上の障害が生じるリスクを減らすこともできるからである。
他にも、婚姻制度の枠組みが「男女二人一組」となっていることは、その社会の中に男女がほぼ同数生まれているという前提の下では、未婚の男女の数に不均衡が生じることはないため、より多くの者に「子を持つ機会」を確保することを可能とするものとなっている。
その他、婚姻制度のもつ子供の遺伝上の父親を特定することができる形での「生殖」を推進する仕組みからは、婚姻制度を利用する形で子供を妊娠し、出産することを期待する(インセンティブを与える)ものとなっているが、その妊娠、出産に関して母体の保護の観点からリスクのある状態を推奨することはできないし、親となる者が低年齢のままに子を持つという責任を担う立場に置かれることを推進することも望ましくないことから、婚姻制度の利用に対して「婚姻適齢」という形で一定の年齢制限を設けるものとなっている。
これらの意図を満たす形で「男女二人一組」という枠組みを設定し、その婚姻制度の枠組みに従う者に対して、一定の優遇措置を講じることによって、婚姻制度の利用者を増やし、その立法目的を達成することを目指すものとなっている。
このことから、婚姻制度の立法目的とその立法目的を達成するための手段は下記のように整理することができる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
① 「子の福祉」が実現される社会基盤を構築すること
(→ 嫡出子として父親を特定することができる状態で生まれることを重視)
② 潜性遺伝子の発現した個体が高い確率で生じることを抑制すること
(→ 貞操義務と嫡出推定〔、再婚禁止期間〕によって遺伝的な父親を極力特定し、それを基に遺伝的な近親者を把握し、近親婚を認めないことによって『近親交配』に至ることを防止)
③ 「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」を減らすこと
(→ 未婚の男女の数の不均衡を防止できる組み合わせに限定。一夫一婦制。重婚や重婚状態、複婚や複婚状態の防止。)
④ 母体を保護すること
(→ 婚姻適齢を設定)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
このような婚姻制度の「趣旨・目的・内容・効果」を前提として、婚姻制度とは別に「同性間の人的結合関係」を対象とした制度を設けることができるかどうかを検討する。
■ 婚姻制度との間で生じる齟齬
▼ 婚姻制度の政策効果を阻害すること
▽ 子の福祉
婚姻制度は、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によって立法目的の達成を目指すものである。
つまり、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定し、母親だけでなくその者にも子に対する養育の責任を担わせることにより、「子の福祉」の実現を目指す仕組みとなっている。
また、子供にとって遺伝上の父親を特定することができることによる利益を得られるように配慮するものとなっている。
そのため、「生殖」によって子供をつくろうとする者が婚姻制度を利用することによって遺伝上の父親を特定することができる人的結合関係を形成するようにインセンティブ(動機付け)を与えるものとなっている。
しかし、「同性間の人的結合関係」を対象とした制度を設けた場合は、その制度によって婚姻制度を利用した場合と同様、あるいは類似した優遇措置を得られることが原因となって、婚姻制度を利用することに対してインセンティブが働かなくなる。
また、「女性同士の組み合わせ」を形成して子供を産むことに対してインセンティブが働くことになり、遺伝上の父親を特定することができない状態で子供を産むことを推進する作用が生じることとなる。
これは、子供にとって遺伝上の父親を特定することができない状態となることから、「子の福祉」の充実に沿わないことが考えられる。
そのため、「同性間の人的結合関係」を対象とした制度を設け、婚姻制度と同様、あるいは類似した優遇措置を得られるようにすることは、婚姻制度の政策的な効果を弱める影響を与えることとなり、婚姻制度の立法目的の実現が阻害され、婚姻制度との間で矛盾するものとなる。
▽ 近親交配の回避
婚姻制度は、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によって立法目的の達成を目指すものである。
その中に、遺伝上の父親を特定することによって近親者の範囲を把握し、その近親者との間では「婚姻」することができないことにすることで、「近親交配」に至ることを防ぎ、潜性遺伝子の発現した個体が高い確率で生じることを防ぐ仕組みがある。
しかし、「同性間の人的結合関係」を対象とした制度を設け、法的効果や一定の優遇措置を与えた場合には、「女性同士の組み合わせ」を形成することに対してインセンティブが働くことになり、遺伝上の父親を特定することができない関係の中で子供を産むことを促進する作用が生じ、近親者の範囲を把握することができない状態を推進することになる。
そうなると、婚姻制度を設けることによって「近親交配」に至ることを回避することができる社会環境を整備しているにもかかわらず、その仕組みに沿わない制度が別に存在することによって、婚姻制度を設けることによって「近親交配」に至ることを防ぐという一貫性のある政策を行うという前提が成り立たなくなる。
つまり、婚姻制度が近親者の範囲を把握することを前提とした上でその近親者との間では「婚姻」することができないことにすることで「近親交配」に至ることを未然に防ぐ仕組みとしているにもかかわらず、その仕組みが十分に機能しなくなり、その社会の中で「近親交配」に至ることを十分に防止することができなくなるということである。
すると、婚姻制度が潜性遺伝子の発現した個体が高い確率で生じることを防ごうとする意図を達成することができなくなり、子供の世代において意図せずに「近親交配」に至る確率が高くなる。
そして、実際に「近親交配」に至ってしまった場合には、子供は潜性遺伝子が発現するリスクが高くなり、遺伝上の障害を抱えやすくなる。
これは、婚姻制度を設けていること自体の価値を損なわせ、人々が婚姻制度に対して抱いている信頼感を失わせることに繋がる。
そのため、「同性間の人的結合関係」(特に女性同士の組み合わせ〔女性三人以上の組み合わせであっても同様〕)を対象とした制度を設け、婚姻制度と同様、あるいは類似した優遇措置を得られるようにすることは、婚姻制度の政策的な効果を弱める影響を与えることとなり、婚姻制度の立法目的の達成が阻害され、婚姻制度との間で矛盾するものとなる。
▽ 生殖機会の公平
婚姻制度は、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によって立法目的の達成を目指すものである。
その中に、一夫一婦制(男女二人一組)とすることにより、未婚の男女の数の不均衡が生じることを防止し、未婚の男女にとっての「生殖機会の公平」が保たれるように配慮し、その社会の中で「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」が生じることを抑制しようとする仕組みがある。
しかし、「同性間の人的結合関係」を対象とした制度を設けた場合には、その制度を利用することによって婚姻制度と同様、あるいは類似の法的効果や優遇措置を得られることを理由として、「同性間の人的結合関係」を形成する者が増えることが考えられる。
すると、その社会の中で未婚の男女の数(制度を利用しない男女の数)に不均衡が生じることに繋がることから、その社会環境が未婚の男女(制度を利用しない男女)にとって「子を持つ機会」の公平性が保たれなくなり、「子を持ちたくても相手が見つからずに子を持つ機会に恵まれない者」が増えることに繋がる。
そのような社会の中で生活することを強いることになることは、「公共の福祉」の観点からも障害となると考えられる。
そのため、「同性間の人的結合関係」を対象とした制度を設け、婚姻制度と同様、あるいは類似した優遇措置を得られるようにすることは、婚姻制度が「男女二人一組」の形に限定することによって「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」を減らそうとする立法目的の達成を阻害するものとなるから、婚姻制度との間で矛盾するものとなる。
▽ インセンティブの減少
婚姻制度は、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によって立法目的の達成を目指すものである。
このことから、婚姻制度を利用しない人的結合関係に対しては意図的に優遇措置を設けないことにより、「生殖」によって子供をつくろうとする者が婚姻制度を利用することによって遺伝的な父親を特定することができる人的結合関係を形成するようにインセンティブを与えるものとなっている。
つまり、婚姻制度を利用する者に対して法的効果や一定の優遇措置を与え、婚姻制度を利用していない者にはそれを与えないという差異を設けることによって、婚姻制度を利用することに対してインセンティブを働かせ、婚姻制度を利用する者を増やし、その立法目的を達成することを目指すものである。
そのことから、婚姻制度を利用しない人的結合関係に対しては意図的に法的効果や優遇措置を与えないということを予定しているものである。
しかし、「同性間の人的結合関係」を対象とした制度を設けた場合には、国民がその制度を利用することにより、婚姻制度を利用した場合と同様、あるいは類似した優遇措置を得られることを理由に、婚姻制度を利用するのではなくその制度を利用することを選択する者が増加していくこととなる。
すると、婚姻制度が遺伝的な父親を特定することができる状態を推進することによって達成しようとした立法目的の達成を阻害する影響を与えることになる。
そのため、「同性間の人的結合関係」を対象とした制度を設け、婚姻制度と同様、あるいは類似した優遇措置を得られるようにすることは、婚姻制度の政策的な効果を弱める影響を与えるものとなることから、婚姻制度との間で矛盾するものとなる。
▽ 母体の保護
上記のような問題により、婚姻制度が「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するための制度として十分に機能しないものとなると、その社会の中で人々が抱いている婚姻制度に対する信頼性が損なわれることになる。
すると、その社会の中で子を産むことを希望する者が次第に婚姻制度を利用しなくなっていき、婚姻制度が存在している意義そのものが希薄化していくことになる。
そうなると、婚姻制度を利用して子を持つという形を求める者が減少し、反対に、婚姻制度を利用しない形で「生殖」をしたり、子を持つ者が増加していくことになる。
すると、それまでは婚姻制度を利用する形で子供を妊娠し、出産することに対してインセンティブを与えていたことから、婚姻制度を利用して子を持つという形を求める者が多く、婚姻適齢に満たない者が「生殖」の営みに誘引される機会がそれなりに少ない社会状況を維持することができていたが、婚姻制度の価値や信頼性が損なわれている結果、婚姻制度を利用することについて十分なインセンティブが働かない状態となっていることから、婚姻制度を利用しない中で「生殖」を営み、子を持つ者が増加していくこととなり、その影響で婚姻適齢に満たない者が「生殖」の営みに誘引される機会も増加していくことに繋がる。
その結果、婚姻適齢に満たない若年の女性が「生殖」(性的な接触や性行為)に続いて、妊娠、出産のリスクを背負うことが増加し、「母体の保護」の観点から見れば望ましくない状態で妊娠、出産に至ることが抑制されなくなる。
また、低年齢のままに親として子を持つという責任を担う立場に置かれることも増加し、婚姻制度の政策的な効果が十分に機能していないことから父親が特定されていなかったり、知識レベルや経済力が十分でないままに子を育てるという過酷な状況に陥ることが抑制されなくなる。
このことは、「母体の保護」の観点や、倫理的な観点、望ましい社会の在り方を考える上で問題となる。
このように、「同性間の人的結合関係」に対して制度を設けることは、婚姻制度の政策効果を阻害することに繋がり、その結果、それまで人々が婚姻制度を利用することに対して魅力を感じていたことにより抑制されていた問題が表出することになる。
▼ 24条の「婚姻」を離れて「生殖と子の養育」に関わる制度を立法することはできないこと
憲法24条の「婚姻」の文言は、「生殖と子の養育」に関わる制度を一元的に集約して規律する趣旨を有していることから、もし「生殖と子の養育」に関わる制度を憲法24条の「婚姻」を離れて別の制度として立法した場合には、憲法24条の「婚姻」の文言に抵触して違憲となる。
なぜならば、憲法24条が「婚姻」の内容に対して立法裁量の限界を画することによって、法律上の「婚姻」の制度を規律しているにもかかわらず、その憲法24条の制約を回避する形で制度を立法することができることになれば、憲法24条の規定そのものが有する効力が損なわれた状態となり、憲法24条の規定が骨抜きとなるからである。
よって、「婚姻」が「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として、「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた枠組みである以上は、その「生殖と子の養育」に関わる制度については、憲法24条の「婚姻」の文言が一元的に集約して規律する趣旨を有しており、これを離れて「生殖と子の養育」に関わる制度を立法することはできない。
そのため、ここでいう「同性間の人的結合関係」について制度を設けた場合に、その内容が「生殖と子の養育」に関わる制度となっている場合や、「生殖と子の養育」に影響を与えることが考えられる制度となっている場合には、そのこと自体で憲法24条の「婚姻」に抵触して違憲となる。
▼ 制度を利用していない者との間の差異を正当化できないこと
一般的・抽象的にその間で自然生殖を想定することができる「一人の男性」と「一人の女性」の組み合わせに対して「貞操義務」など一定の形式で法的に結び付けることは、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的の実現に資することから、必然性を見出すことができる。
つまり、「男女二人一組」については、その間で自然生殖が行われた場合に、遺伝的な父親を特定することができる関係となることから、その特定された父親に対しても子に対する責任を担わせることができる。
また、父親を特定することによって「近親交配」に至ることを回避することも可能となる。
他にも、「男女二人一組」の制度であれば、未婚の男女の数の不均衡を防止することが可能となるため、その社会全体の中で「生殖機会の公平」を実現することに寄与するものとなる。
「婚姻適齢」を満たした者の間での「生殖と子の養育」に関する制度であれば、「母体の保護」の観点や、「子育ての能力」の観点からも一般には支障がないものと考えられる。
これらは、結果として「子の福祉」を目指す仕組みとして合理的であるということができる。
そのため、「男女二人一組」の関係性に対して制度を設けてその制度を利用する者に対して一定の優遇措置を与えるとしても、それはその制度を利用していない者との間で生じる差異を正当化することが可能である。
しかし、「同性間の人的結合関係」については、その間で「生殖」を想定することができないことから、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する形で制度を設けるという目的からは導かれないものである。
そのため、「同性間の人的結合関係」に対して制度を設けることは、その制度を利用していない者との間で合理的な理由を説明することのできない差異を生じさせるものとなり、「平等原則」に反することになる。
▼ 他の人的結合関係との間の差異を正当化できないこと
「同性間の人的結合関係」を対象とする制度は「二人一組」を対象とすることが想定されている。
しかし、「同性間の人的結合関係」については、婚姻制度のように「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的との関係により一般的・抽象的にその間で「生殖」を想定することができる「男性」と「女性」の揃う「二人一組」を対象として枠組みを定めるという意図からは導き出されないものである。
そのため、その内容を「二人一組」とする必然性もないのであり、理由なく「二人一組」としていることは、「カップル信仰論」に基づくものとなっている。
人的結合関係には、「三人一組」や「四人一組」、「それ以上の人的結合関係」も存在するのであり、「二人一組」だけを特別視して制度を設けること自体についても、合理的な理由を説明することができないものとなっており、妥当でない。
■ 結論
このように、もし「同性間の人的結合関係」を対象とした制度を設けた場合には、婚姻制度の立法目的の実現を阻害し、婚姻制度の政策効果を弱めることに繋がる。
また、「同性間の人的結合関係」を対象とした制度を立法した場合には、憲法24条の「婚姻」の文言が「生殖と子の養育」に関わる制度を一元的に集約して規律している趣旨や、憲法14条1項の「平等原則」の関係で違憲となることが考えられ、そのような制度を立法することはできない。
そのため、上記のような問題点を何ら検討することもなく「同性間の人的結合関係」を対象とした制度を設けることができるかのような説明をしていることは、婚姻制度の有している機能や果たしている役割、婚姻制度の立法目的とその立法目的を達成するための手段となっている枠組みとの整合性を理解していないものであり、誤りである。
解釈の方法と限界
法令を解釈する方法と、その限界について検討する。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
イ しかし、控訴答弁書第3の3(2)イ(22及び23ページ)で述べたとおり、法の解釈に際し、文言の日本語としての意味や文法が重視・尊重されなければならないのは当然のことであり、文言からかけ離れた解釈は許されない。そして、前記 (2)アで述べたとおり、「両性」とは、一般に、両方の性、男性と女性を意味する文言であり、「両性」が男性又は女性のいずれかを欠き当事者双方の性別が同一である場合を含む概念であると理解する余地はなく、憲法24条1項及び2項における「両性」の意味もこのように理解すべきことは、憲法24条の制定過程及び審議状況からも裏付けられている。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【東京一次・第3回】被控訴人第2準備書面 令和6年2月29日 PDF
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○政府委員(大出峻郎君) 一般論として申し上げますというと、憲法を初め法令の解釈といいますのは、当該法令の規定の文言とか趣旨等に即して、立案者の意図なども考慮し、また、議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定されるべきものであると考えられるわけであります。
政府による憲法解釈についての見解は、このような考え方に基づき、それぞれ論理的な追求の結果として示されてきたものと承知をいたしており、最高法規である憲法の解釈は、政府がこうした考え方を離れて自由に変更することができるという性質のものではないというふうに考えておるところであります。
特に、国会等における論議の積み重ねを経て確立され定着しているような解釈については、政府がこれを基本的に変更することは困難であるということでございます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第134回国会 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第3号 平成7年11月27日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
憲法を始めとする法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、また、議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定されるべきものであり、政府による憲法の解釈は、このような考え方に基づき、それぞれ論理的な追求の結果として示されてきたものであって、諸情勢の変化とそれから生ずる新たな要請を考慮すべきことは当然であるとしても、なお、前記のような考え方を離れて政府が自由に憲法の解釈を変更することができるという性質のものではないと考えている。仮に、政府において、憲法解釈を便宜的、意図的に変更するようなことをするとすれば、政府の憲法解釈ひいては憲法規範そのものに対する国民の信頼が損なわれかねないと考えられる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書 平成16年6月18日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
また、お尋ねの「法的安定性」とは、法の制定、改廃や、法の適用を安定的に行い、ある行為がどのような法的効果を生ずるかが予見可能な状態をいい、人々の法秩序に対する信頼を保護する原則を指すものと考えている。仮に、政府において、論理的整合性に留意することなく、憲法解釈を便宜的、意図的に変更するようなことをするとすれば、法的安定性を害し、政府の憲法解釈ひいては憲法規範そのものに対する国民の信頼が損なわれかねないと考えられる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
七・一閣議決定の法的安定性と論理的整合性の意味等に関する質問に対する答弁書 平成29年6月27日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法を解釈することと、法を解釈していると思い込んでいることとを区別しうるためには、解釈は個人的・私的なものではなく、社会的な、つまり原理的には誰にも共通にアクセス可能な、公的活動でなければならないはずである。各人がそれぞれ異なった形で得心がいっただけでは、法解釈として十分とはいえない。解釈者は、他人を説得し、同じように既存の法源(判例・法令)を見るように議論を進める必要がある。もちろん、その結果、つねに同一の結論へと人々の意見が集約されるとは限らない。同じ程度に説得力を持つ複数の解釈が競合することは珍しいことではない。
解釈が解釈であるためには、つまり、それが原理的に誰もが参加しうる公的な活動であるためには、第一に、法源の核心的な意味の理解を可能とする共通の言語作用が背景として存在していなければならない。そして、第二に、解釈の目的は、例外的・病理的現象である法の意味の不明瞭化に対して、人々の合意をとりつけることで、正常な法の機能を回復すること、人々が再び疑いをもたずに法に従いうる状態を回復することになければならない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
憲法の理性 長谷部恭男 (P210) (下線は筆者)
憲法
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━