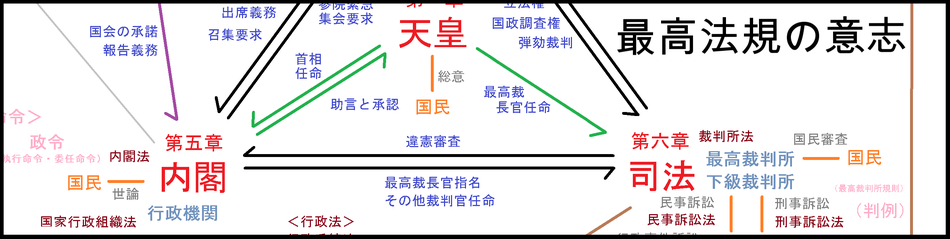同性婚訴訟 東京地裁判決の分析
【このページの目次】
はじめに
ポイント
〇 「性愛」を論じる誤り
〇 カップル信仰論
〇 「社会的な承認」の二義性の混乱
〇 「社会通念」の背景には立法目的と達成手段があること
〇 「婚姻の本質」の誤用
〇 「家族」の意味の誤用
〇 24条2項の「個人の尊厳」の適用対象の誤り
〇 13条の「個人の尊重」は「特定の制度を求める権利」を保障するものではないこと
〇 「人格的生存に対する重大な脅威、障害」が問われる問題ではないこと
東京地裁判決の内容
判決の誤りを継承する解説
はじめに
「同性婚訴訟 東京地裁判決」の内容を分析する。
判決
国家賠償請求事件 東京地方裁判所 令和4年11月30日 (PDF)
【東京一次】判決全文 PDF
【東京一次】判決全文 PDF
判決要旨
【東京一次】判決要旨 PDF
【判決要旨全文】「違憲状態」と東京地裁が判断した理由は? (結婚の平等裁判) 2022/11/30
この判決文の内容は、誤った前提認識や、法律論でない部分、判例引用の間違いなど、問題が多岐にわたる。複数ヵ所の誤りを同時に解きほぐすことが必要となるため、初学者には難解であると思われる。
ここでは、その誤りを丁寧に確認していきたい。
ポイント
判決の誤りを理解するために、前提として必要となる知識を整理する。
「性愛」を論じる誤り
この判決は「異性愛者」と「同性愛者」の二分論しか想定していないようである。(『両性愛』は出てくるが、『同性愛者等』として扱っている。)
しかし、その他にも様々なバリエーションが存在する。
例えば、「両性愛者」「全性愛者」「近親性愛者」「多性愛者」「小児性愛者」「老人性愛者」「死体性愛者」「動物性愛者」「対物性愛者」「対二次元性愛者」「無性愛者」などが議論されている。
個々人が「性愛」を抱く場合の対象は様々であり、「性別」という視点に限られるものではなく、「年齢」「身長」「体型」「外見」「部位」「性格」など様々な視点も存在している。
また、「性愛」を抱く対象が「自分自身」に向かう者もいる。
他にも、「性愛」を抱かない「無性愛者」とされる者もいるし、自分の年齢や時期、その時々の気分やタイミング、環境、対象との関係性などによっても、個々人が「性愛」を抱く場合や抱かない場合は様々である。
それにもかかわらず、「性愛」の対象の向かう対象の範囲を「人」に限り、その上でさらに「性別」の視点に限り、「性的指向」と称するものも「異性」あるいは「同性」に二分できることを前提とし、すべての人間を「異性愛者/同性愛者」の二分論で区別することができるかのような論じ方をしている部分は、「性愛」に対する理解を誤っている。
また、この判決では「性的指向」のみを取り上げるのであるが、「性的指向」と「恋愛的指向」を区別するべきであるとの考え方も存在する。
「恋愛」を抱くが、それが「性愛」に結び付くとは限らず、「恋愛」していれば相手を性欲を満たすための対象であるかのように捉えることは、重大な誤認であり、著しく不適切であるとするものである。
他にも、「性愛」を「性的欲求」の側面に限られない意味で使っているのであれば、「愛」の取り上げ方には「友愛」「親子愛」「兄弟愛」「姉妹愛」「会社愛」「宗教愛」などいくらでもある。
さらに、「性愛」であっても、「恋愛」であっても、「友愛」であっても、「兄弟姉妹愛」であっても、「親子愛」であっても、「孫への愛」てあっても、「子孫への愛」であっても、「会社への愛」であっても、「宗教的な愛」であっても、「国家への愛(愛国心)」であっても、「人類愛」であっても、「生命愛」であっても、すべて個々人の内心にのみ存在する精神的なものであることから、これらの様々な「愛」などと称される感情をそれぞれの間で明確に区別することができるという性質のものではない。
そのため、これらはすべて「内心の自由」によって捉えられるべきものである。
また、「愛」などと称される感情もあれば、「嫌悪」など不快な感情も存在する。
そのどちらの感情であっても、そこに法律論上の優劣はないのであり、殊更に「愛」を正当化して法制度を立法することができるという性質のものではない。
一人の人間の中でも、感情は様々な要素を有している。
【イメージの参考】脳内メーカー
このような個々人の有する内心の一側面のみを切り取って、その者を「異性愛者」や「同性愛者」などと明確に区別することができるわけではないのであり、法律論を論じる際に「異性愛者」や「同性愛者」などと区別して考えることができるかのような前提で論じていること自体が誤りである。
これと関連して、この判決が「男女二人一組」の婚姻制度を利用している者をすべて「異性愛者」と考えている点でも誤りである。
婚姻制度は「性愛」の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にどのような対象に向かうかを審査するものではないし、「性愛」に基づいて「婚姻」することを求めるものでも勧めるものでもない。
そのため、法律論としては法制度を利用する者の内心には立ち入ってはならないのであり、「男女二人一組」の婚姻制度を利用する者を「異性愛者」と称する者であるかのような理解を前提として論じるようなこともしてはならない。
カップル信仰論
この判決では、何らの根拠もなく「カップル」や「パートナー」という言葉を用いて論じるものとなっている。
しかし、このような言葉を用いて論じることができることになれば、下記のように 「デュオ」、「コンビ」、「バディ」、「ダブルス」、「トリオ」、「相棒」、「仲間」、「ソウルメイト」などの言葉も使うことが可能となってしまうため、妥当でない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
二人組(ふたりぐみ、ににんぐみ)とは、2人から成るグループを指す。人間が組織で活動する際の最小単位であり、様々な分野で見られる。 会話ではふたりぐみ、事件報道では、しばしばににんぐみという読み方が用いられる。分野によっては、デュオ、コンビ[1]、ペア、カップル、バディなどの呼び方も用いられる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
二人組 Wikipedia
関係性を表現する言葉には、「お笑いコンビ」「歌のデュエット」「仕事の相棒」などもある。
・「バディ」という関係がある。
心強い! ダイビングのバディシステム 2016年6月23日
・「ダブルス」もある。
ダブルス Wikipedia
・三人組として「トリオ」がある。
トリオ Wikipedia
・「仲間」という言葉もある。
「お前はおれの仲間だ!!」ルフィがナミに言った名言をワンピース英語版で!! 2014-08-17
・「ソウルメイト」という分類もある。
ソウルメイト Wikipedia
「カップル」や「パートナー」という言葉も含めて、これらは法律用語ではないため、使う人によってそれぞれ意味するところが異なるものである。
このような言葉の中には、何らかの思想や信条、宗教的な信仰を抱いていることを前提とした用語であるこもあるし、自らの望む結論を導き出すために前提を先取りするために敢えて用いられている場合もある。
そのため、法律論を論じる際にこのような言葉を安易に用いてはならない。
また、「パートナー」とは、基本的に「二人一組となる場合の相手」を意味することから、「二人一組」を前提とした言葉である。
しかし、根拠もなく人的結合関係が「二人一組」であることを前提としていることは、なぜ「二人一組」であるのかその根拠を説明しないままに論じる「カップル信仰論」に陥っていることになる。
このような、法律用語ではない言葉を用いてあたかも「二人一組」であるという前提を先取りする形で論じることが可能であるとすれば、「カップル信仰」ではなく、「トリオ信仰」の持ち主が現れた場合には、「トリオの連れ」や「トリオ仲間」などと論じることによって、「三人一組」であるという前提を先取りする形で論じることが可能なってしまうのであり、妥当ではない。
法律論としては、下図のように「権利能力」を有して法主体としての地位を認められている自然人(あるいは法人)を単位として、それらをどのような法律関係によって結び付けるかという視点によって論じる必要がある。
【動画】司法試験入門講座 プレ講義 「体系マスター」民法5 「契約の成立と効力発生まで~民法総則」 2020/03/17
今回の事例においても、「権利能力」を有する個々の自然人をどのような法律関係によって結び付けるか、という視点から論じるべき問題である。
それにもかかわらず、法律用語ではない単語を持ち込んで、「二人一組」であるという前提を先取りする形で論じることは、誤った説明である。
「カップル」や「パートナー」という言葉を用いている時点で、それは「二人一組」であることを前提としているものであり、そこには、ある宗教団体の内部でのみ通用している教義や、一定の地域の中でのみ通用している文化に過ぎないものを根拠として前提を先取りしようとする意図が含まれていることが考えられる。
しかし、法解釈を行う際には、そのような宗教的な教義や文化的な背景からは中立的な内容でなければならず、それらの教義や文化を基にして前提を先取りするようなことがあってはならない。
分かりやすく言えば、この判決を書いた裁判官がイスラム教徒であったならば、イスラム教の普及する文化圏で「男性一人と女性四人まで」の一夫多妻型の人的結合関係を形成する者もいることを理解しているはずであるから、安易に「パートナー」という「二人一組」を前提とした言葉を用いることはないはずである。
その場合には、一夫多妻制を採用している文化も存在することを前提としながら、日本法における法制度として「権利能力」を有し、法主体としての地位を認められている個々の自然人をどのような法律関係で結び付けるかというという観点によって論じるはずである。
これを考えれば、「二人一組」という前提そのものが特定の国々や特定の文化圏に存在する法制度のみを前提として考えるというバイアスのかかったものであることは容易に理解することができる。
この判決が「カップル」や「パートナー」の文言を用いて、「二人一組」であるという前提に基づいて論じていることは、この判決を書いた裁判官が「二人一組」を前提とした法制度を採用している国々や特定の文化圏、ロマンチック・ラブ・イデオロギーなどの法制度とは別に形成された何らかの文化、この裁判官が属している何らかの宗教団体の教義などを根拠として考えてしまっていることを露顕するものとなっているのである。
このような論じ方をしていること自体が、既に法律論とは異なる認識によって論じようとしているものとなっており、妥当ではない。
そのため、「カップル」や「パートナー」という言葉を用い、「二人一組」を根拠もなく前提としている論じ方は、法律論としては誤った色眼鏡をかけたままに論じるものということができ、結論を導き出すまでの判断の過程が誤っていることになる。
勝手に言葉を作って定義してしまえば、法律論として通用するかのような論じ方をするべきではない。
【参考】私たちは「重婚」を認められるか…?「同性婚」問題の先に浮かび上がる「多様性をめぐる根本的な難点」 2023.06.27
「社会的な承認」の二義性の混乱
この判決では、「社会的な承認」という文言が異なる二つの次元で使われている。
ある人的結合関係を「婚姻」とすることができるか否かについての「社会的な承認」と、「婚姻」した者が周囲から得られるとする「社会的な承認」の二つである。
◇ ある人的結合関係を「婚姻」と考えることができるか否かについての「社会的な承認」≒「社会通念」
この意味の「社会的な承認」とは、ある人的結合関係を「婚姻」とすることができるか否かを考えるものである。
この「社会通念」、「社会的な承認」と称しているもの背景には、「婚姻」という概念そのものが有する目的と、その目的を達成するための手段となる枠組みが存在すると考えられる。
◇ 「婚姻」した者が他者から得られるとする「社会的な承認」
この意味の「社会的な承認」とは、「婚姻」している者には「社会的な承認」があると考えるものである。
しかし、法律論上は「婚姻している者」は単に他者から「婚姻制度を利用している者(既婚者)」として認識されており、「婚姻していない者」は単に他者から「婚姻制度を利用していない者(独身者)」として認識されているだけであるから、「婚姻」している者にだけ「社会的な承認」があると考えることはできないように思われる。
もし法律論として「婚姻制度を利用している者(既婚者)」について「社会的な承認」があるとすれば、同様に「婚姻制度を利用していない者(独身者)」についても「社会的な承認」があることになるのである。
これら同一の文言が異なる次元で用いられているため、判決の論理展開を理解しづらくなっている。
「社会通念」の背景には立法目的と達成手段があること
この判決は「婚姻」の枠組みについての「社会通念」や「社会的承認」の背景に「伝統的な価値観」があるとしている。
しかし、その「伝統的な価値観」と称しているものの背景には「立法目的」と「その立法目的を達成するための手段」となる枠組みが存在する考えられる。
この点について、十分に述べられているわけではない。
立法目的
〇 「子の福祉」が実現される社会基盤を構築すること
〇 遺伝的な劣勢を有する個体が高い確率で発現することを抑制すること
〇 「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」を減らすこと
〇 母体を保護すること
↑ ↑ ↑
立法目的を達成するための手段として整合的な要素
・ 子の遺伝的な父親を特定できる組み合わせとすること
・ 特定された子の父親にも子に対する責任を担わせること
・ 特定された子の父親を基に遺伝的な近親者を把握すること
・ 未婚の男女の数の不均衡を防止できる組み合わせに限定すること
↑ ↑ ↑
「伝統的な価値観」
「1(2)ア」:「男女の生活共同体として子の監護養育や共同生活等の維持によって家族の中核を形成するもの」
「1(2)ア」:「伝統的に男女間の人的結合に対して婚姻としての社会的承認が与えられてきた背景、根底には、夫婦となった男女が子を産み育て、家族として共同生活を送りながら、次の世代につないでいくという社会にとって重要かつ不可欠な役割を果たしてきた事実がある」
「2⑴エ(イ)」:「男女が共同生活を送る中で子を産み育てるという営み」
「2⑴エ(イ)」:「夫婦となった男女が子を産み育て、家族として共同生活を送りながら、次の世代につないでいくという古くからの人間の営みに由来するものである」
「2⑵ウ」:「婚姻を異性間のものとする社会通念の背景には、夫婦となった男女が子を産み育て、家族として共同生活を送りながら、次の世代につないでいくという古くからの人間の営みがある」
↑ ↑ ↑ (背景)
「社会通念」や「社会的承認」
「2⑴エ(ア)」:「婚姻とは男女間のものという考え方が当然の前提」
「2⑴エ(ア)」:「婚姻は男女間のものとする社会通念」
「2⑴エ(イ)」:「伝統的に男女間の人的結合に対して婚姻としての社会的承認が与えられてきた」
「2⑵ウ」:「婚姻を異性間のものとする社会通念」
「婚姻の本質」の誤用
最高裁判決(昭和62年9月2日・PDF)は、「婚姻の本質は、両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもつて共同生活を営むことにある」と説明している。
この「婚姻の本質」と称する説明は、具体的な法律上の婚姻制度の枠組みが存在することを前提として、その制度の内容を読み解いた際に、その制度を利用する者の法的な権利・義務の結び付きによる法律関係の状態を簡潔に示したものである。
その理由は、この「婚姻の本質」と称している説明と、具体的な法律上の婚姻制度の枠組みとの対応関係を、下記のように整理することができるからである。
◇ 「両性」との部分は、現在の婚姻制度が「男性」と「女性」を要件としていることから導かれたものと考えられる。
◇ 「永続的な」との部分は、現在の婚姻制度には有効期限がなく、利用者が死亡するまで利用することができるという点から導かれたものと考えられる。
(もし婚姻制度が改正されて有効期限が定められることがあるとすれば、この『永続的な』との説明は根拠を失ってなくなることになる。)
◇ 「精神的及び肉体的結合を目的として」との部分は、現在の婚姻制度が相互の協力を求めていることや、「貞操義務」があることことから導かれたものと考えられる。
(『貞操義務』のある制度を読み解くことによって『肉体的結合』と表現しているのであり、もし『貞操義務』がなければ『肉体的結合』という表現は導かれないことになる。)
◇ 「共同生活を営む」との部分は、現在の婚姻制度が「同居義務」を定めていることから導かれているものと考えられる。
このように、具体的な婚姻制度の枠組みが存在することを前提として、その婚姻制度を利用する者の間で生じる法律関係について、「婚姻の本質」と称する説明として示されているものである。
そのことから、この「婚姻の本質」と称する説明は、具体的な婚姻制度の枠組みが存在することに依存して導かれているものであり、「婚姻」という概念そのものから根拠もなく直ちに導き出されるという性質のものではない。
また、この「婚姻の本質」と称している説明は、具体的な婚姻制度の枠組みが存在することに依存して、その法律関係を示すために導かれた説明であることから、具体的な婚姻制度の上位概念として存在するものではないし、婚姻制度を構築する際の「国の立法目的」を示したものでもない。
そのことから、具体的な法制度として示されている婚姻制度の枠組みを離れて、「婚姻の本質」と称する説明に当てはまるか否かを基準とすることによって、「婚姻」の中に含めることができる人的結合関係と、含めることができない人的結合関係とを区別することができるということにはならない。
そのため、この「婚姻の本質」として説明されているものを根拠として具体的な婚姻制度の枠組みを変更するための根拠とすることはできない。
当然、この「婚姻の本質」と称する説明を、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」として扱うことができるか否かを判断するための基準として用いることができることにもならない。
この東京地裁判決は、この「婚姻の本質」と称する説明を具体的な婚姻制度の枠組みに基づかずに根拠なく切り取り、婚姻制度を利用する者の権利・義務による法律関係の状態を示す意味から離れて、別の意味として用いているため、誤っている。
「家族」の意味の誤用
〇 「家族」の意味の区別
法学的な意味で用いられる「家族」と、社会学的な意味で用いられる「家族」とは異なる。
◇ 法学的な意味の「家族」
法学的な意味の「家族」とは、憲法24条2項で規定された「家族」のことである。
これは、憲法24条2項でも「婚姻及び家族」と記されているとおり、「婚姻」と密接に関係するものとして規律される枠組みである。
そのことから、「家族」として扱うことのできる人的結合関係の範囲は、「婚姻」の立法目的の実現を阻害しない範囲で規律される枠組みとして定められることになる。
この法学的な意味の「婚姻及び家族」は、「婚姻及び家族」という法制度の立法目的と、その立法目的を達成するための手段として枠組みが定められるものであることから、この立法目的と、その立法目的を達成するための手段との整合性を検討することなく、どのような人的結合関係でも「家族」の中に含めることができるという性質のものではない。
◇ 社会学的な意味の「家族」
社会学的な意味の「家族」とは、「共同生活者」を意味することが多い。
会社組織の中には、構成員同士の仲の良さを取り上げて「家族」と表現している場合もある。
(犬、猫、鳥などのペットについても『家族』の中に含めて考えている者もいる。)
このような「共同生活者」などの人的結合関係については、憲法21条1項の「結社の自由」によって保障されることになる。
これは、「生活共同体」や「生活結社」とでもいうものである。
これらの、法学的な意味(法律用語)の「家族」と、社会学的な意味(日常用語)の「家族」とを区別して考えることが必要である。
この判決は、この点を区別できていないままに論じるものとなっている。
【参考】「社会学の家族と法が想定する家族は別」 Twitter
【参考】「社会学と法の家族は別。」 Twitter
24条2項の「個人の尊厳」の適用対象の誤り
憲法24条2項は、「婚姻及び家族」の制度の中身について「個人の尊厳」を満たすことを要請する規定である。
しかし、そもそも「婚姻及び家族」の制度の対象となっていない場合については、この憲法24条2項の「個人の尊厳」が適用されることはない。
この「婚姻及び家族」とは、法学的な意味の「婚姻」(法律婚)であり、法学的な意味の「家族」(法律家族)である。
「婚姻」は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として設けられた枠組みであり、「家族」は「婚姻」の立法目的の実現を阻害しない範囲で規律される「夫婦」や「親子」の関係を基本とした血縁関係者(自然血族・法定血族)による枠組みである。
そのため、この「婚姻」や「家族」の中にどのような人的結合関係でも含めることができるという性質のものではない。
この「婚姻及び家族」の対象となっていない場合には、憲法24条2項の「個人の尊厳」の規定が適用されないため、「婚姻及び家族」の対象となっていない場合に対して、憲法24条2項が適用されることを前提として「個人の尊厳」との関係を論じようとしたり、憲法24条2項に違反するか否かを述べることは誤りとなる。
13条の「個人の尊重」は「特定の制度を求める権利」を保障するものではないこと
〇 24条の「個人の尊厳」の観点
この東京地裁判決では、「2⑶オ(オ)」ところで、「現行法上、同性愛者についてパートナーと家族になるための法制度が存在しないことは、同性愛者の人格的生存に対する重大な脅威、障害であり、個人の尊厳に照らして合理的な理由があるとはいえず、憲法24条2項に違反する状態にあるということができる。」と述べている。
しかし、24条2項の「個人の尊厳」の文言は、「婚姻及び家族」の対象となっている場合にのみ適用されるものであるから、その「婚姻及び家族」の立法目的とその立法目的を達成するための手段となる枠組みに当てはまらない場合については適用されることはない。
そのため、この「婚姻及び家族」に当てはまらない人的結合関係について、24条2項の「個人の尊厳」が適用されることを前提として、この「個人の尊厳」を根拠とする形で「憲法24条2項に違反する状態にある」と述べている部分は、誤っている。
〇 13条の「個人の尊重」の観点
これについて、学説上、13条の「個人の尊重」と24条2項の「個人の尊厳」が同様の趣旨のものとされていることから、この判決のいう24条の「個人の尊厳」に違反するか否かの観点を、13条の「個人の尊重」に違反するか否かの観点に置き換えて考えた場合について、このような論理を正当化する余地があるかを検討する。
これについては、既に大阪地裁判決が述べているものと共通する。
大阪地裁判決
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
イ 憲法13条に違反するかについて
原告らは、同性間の婚姻をするについての自由が憲法24条1項で規定されていないとしても、このような自由は自己決定権の重要な一内容として、憲法上の権利としても保障されるべきものであるとして、本件諸規定は憲法13条に違反する旨主張する。
しかし、婚姻及び家族に関する事項は、憲法24条2項に基づき法律によって具体的な内容を規律するものとされているから、婚姻及び家族に関する権利利益等の内容は、憲法上一義的に捉えられるべきものではなく、憲法の趣旨を踏まえつつ、法律によって定められる制度に基づき初めて具体的に捉えられるものである。そうすると、婚姻をするについての自由は、憲法の定める婚姻を具体化する法律に基づく制度によって初めて個人に与えられるか、又はそれを前提とした自由であり、生来的、自然権的な権利又は利益であるということはできない。
したがって、憲法24条が異性間の婚姻のみを定めており、これを前提とする婚姻制度しか存在しない現行法の下では、同性間で婚姻をするについての自由が憲法13条で保障されている人格権の一内容であるとはいえない。また、包括的な人権規定である同条によって、同性間の婚姻制度を含む特定の制度を求める権利が保障されていると解することもできない。
よって、本件諸規定が憲法13条に反するとはいえない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
損害賠償請求事件 大阪地方裁判所 令和4年6月20日 (PDF)
よって、憲法13条の「個人の尊重」の観点から考えても、憲法13条に違反するとは言えないし、「包括的な人権規定である同条によって、」「特定の制度を求める権利が保障されていると解することもできない。」ことになる。
そのため、この東京地裁判決のいう「パートナーと家族になるための法制度」と称するものを求める権利が13条によって保障されているとはいえない。
このことから、東京地裁判決が24条2項は「婚姻及び家族」の対象となっている場合について適用される条文であるにもかかわらず、この24条2項から「婚姻及び家族」に含まれていない人的結合関係についての「パートナーと家族になるための法制度」と称するものの創設を求めることができるとする前提に立った上で、さらに「個人の尊厳に照らして合理的な理由があるとはいえず、憲法24条2項に違反する状態にあるということができる。」と述べていることについては、誤りとなる。
国(行政府)の主張も参考になる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
……(略)……このように,被告は,現行の法制度が憲法の要請に従って構築されたものであることを前提に,かかる法制度を超える上記の新たな制度の創設を求める権利が憲法13条における自己決定権に含まれるものではないと主張しているのであって,国家の制度を前提にするか否かによって憲法上の保障に値するか否かが決定されると主張しているのではない。
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
そして,婚姻の自由が憲法13条によって保障されるとの見解についてみれば,被告第3準備書面第2の2 (2)イ(ア)(7,8ページ)で述べたとおり,婚姻は,必然的に一定の法制度の存在を前提としている以上,仮に婚姻に関する自己決定権を観念できるとしても,その自己決定権は憲法の要請に従って構築された法制度の枠内で保障されるものにとどまると考えられる。しかるところ,上記見解のいう「婚姻の自由」が,性別を問わず配偶者を選択する自由を含む権利であるとすると,それは,「両性」の本質的平等に立脚すぺきことを規定する憲法24条2項の要請に従って創設された現行の法制度の枠を超えて,同性の者を婚姻相手として選択できることを含む内容の法制度の創設を求めるものにほかならない。……(略)……
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【東京・第6回】被告第4準備書面 PDF (P9~12)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ア(ア)しかしながら、被告第4準備書面第2の2 (8及び9ページ)及び同3(2) (13ないし16ページ)で述ぺたとおり、婚姻及び家族に関する事項については、憲法24条2項に基づき、法律によって具体的な内容を規律するものとされているから、婚姻及び家族に関する権利利益等の内容は、憲法の趣旨を踏まえつつ、法律によって定められる制度に基づき初めて具体的に捉えられるものである。そうすると、婚姻の法的効果を享受する利益や、「婚姻をするかどうか、いつ誰と婚姻をするか」を当事者間で自由に意思決定し、故なくこれを妨げられないという婚姻をするについての自由は、憲法の定める婚姻を具体化する法律(本件規定)に基づく制度によって初めて個人に与えられる、あるいはそれを前提とした自由であり、法制度を離れた生来的、自然権的な自由権として憲法上保障されていると解することはできない。
そうすると、原告らの「婚姻の自由」に関する主張について、自由権の侵害を問題とするものとしては前提を欠いているというぺきである。
(イ)原告らは、上記(1)のとおり、同性力ップルにおいても婚姻の自由は憲法13条により保障されている旨及ぴ同性カップルを婚姻から排除することが違憲である旨主張するが、原告らの主張の本質は、同性間の人的結合関係についても、異性間の人的結合関係を対象とする婚姻と同様の積極的な保護や法的な利益の供与を認める法制度の創設を国家に対して求めるものにほかならない。このような内実のものにすぎない個々の権利若しくは利益又はその総体が憲法13
条の規定する幸福追求権の一内容を構成するものと解することはできず、これは、同性間の人的結合関係を婚姻の対象に含めることが、同性間の婚姻を指向する当事者の自由や幸福追求に資する面があるとしても変わるものではないことは被告第4 準備書面第2の2 (8及び9ページ)で述べたとおりである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【九州・第11回】被告第6準備書面 令和4年11月30日 PDF (P7~8)
このように、13条を根拠として「新たな法制度」の創設を国家に対して求めることはできない。
「人格的生存に対する重大な脅威、障害」が問われる問題ではないこと
この東京地裁判決は、「人格的生存に対する重大な脅威、障害」であると述べている部分がある。
〇 24条の「個人の尊厳」の観点
しかし、まず、24条2項は「婚姻及び家族」に対してのみ、24条2項の「個人の尊厳」が適用されるのであり、「婚姻及び家族」の範囲に含まれないのであれば、24条2項の「個人の尊厳」が適用されることはない。
よって、今回の事例も「婚姻及び家族」に含まれない場合であるから、24条2項の「個人の尊厳」は適用されないのであり、24条2項の「個人の尊厳」が適用されることを前提として「人格的生存に対する重大な脅威、障害」と述べるのであれば誤りとなる。
〇 13条の「個人の尊重」の観点
13条の「個人の尊重」や「幸福追求権」の観点から、「人格的利益」(個人の人格的生存に不可欠な利益を内容とする権利の総体)が検討されることは考えられる。
この判決で「人格的生存に対する重大な脅威、障害」と述べていることから、この観点に関係するかのような論じ方をしているように見受けられる。
しかし、下記の国(行政府)の主張のように、「婚姻及び家族に関する権利利益等の内容は、憲法の趣旨を踏まえつつ、法律によって定められる制度に基づき初めて具体的に捉えられるもの」であり、「法制度を離れた生来的、自然権的な自由権として憲法上保障されていると解することはできない。」と考えられる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ア(ア)しかしながら、被告第4準備書面第2の2 (8及び9ページ)及び同3(2) (13ないし16ページ)で述ぺたとおり、婚姻及び家族に関する事項については、憲法24条2項に基づき、法律によって具体的な内容を規律するものとされているから、婚姻及び家族に関する権利利益等の内容は、憲法の趣旨を踏まえつつ、法律によって定められる制度に基づき初めて具体的に捉えられるものである。そうすると、婚姻の法的効果を享受する利益や、「婚姻をするかどうか、いつ誰と婚姻をするか」を当事者間で自由に意思決定し、故なくこれを妨げられないという婚姻をするについての自由は、憲法の定める婚姻を具体化する法律(本件規定)に基づく制度によって初めて個人に与えられる、あるいはそれを前提とした自由であり、法制度を離れた生来的、自然権的な自由権として憲法上保障されていると解することはできない。
そうすると、原告らの「婚姻の自由」に関する主張について、自由権の侵害を問題とするものとしては前提を欠いているというぺきである。
(イ)原告らは、上記(1)のとおり、同性力ップルにおいても婚姻の自由は憲法13条により保障されている旨及ぴ同性カップルを婚姻から排除することが違憲である旨主張するが、原告らの主張の本質は、同性間の人的結合関係についても、異性間の人的結合関係を対象とする婚姻と同様の積極的な保護や法的な利益の供与を認める法制度の創設を国家に対して求めるものにほかならない。このような内実のものにすぎない個々の権利若しくは利益又はその総体が憲法13
条の規定する幸福追求権の一内容を構成するものと解することはできず、これは、同性間の人的結合関係を婚姻の対象に含めることが、同性間の婚姻を指向する当事者の自由や幸福追求に資する面があるとしても変わるものではないことは被告第4 準備書面第2の2 (8及び9ページ)で述べたとおりである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【九州・第11回】被告第6準備書面 令和4年11月30日 PDF (P7~8)
そのため、「自由権の侵害を問題とするものとしては前提を欠いている」事例であり、13条の「個人の尊重」の観点から検討されることのある「人格的生存に対する重大な脅威、障害」であるか否かを論じる対象ではないと思われる。
個々人が人的結合関係を形成することは自由であり、それが「公共の福祉」や「公序良俗」に反しないのであれば、国家によって制約されることもない。
これは、21条1項の「結社の自由」によっても保障されている。
このような自由が国家によって合理的な理由もなく制約されることがあったならば、「国家からの自由」という「自由権」に対する制約の観点から「人格的生存に対する重大な脅威、障害」と述べることができる場合は考えられる。
しかし、今回の事例はそのような国家から個人に対する具体的な侵害行為を論じているものではない。
そのため、この東京地裁判決が「人格的生存に対する重大な脅威、障害」を理由として憲法違反を論じていることは、誤りであると考えられる。
東京地裁判決の内容
具体的に、判決の誤りを確認する。
〇 項目のタイトルの文字サイズを拡大したところと、太字にしたところがある。
〇 「性愛」「異性愛」「両性愛」「同性愛者」「同性愛者等」に色付けをした。
〇 「カップル信仰論」を前提とした「カップル」「異性カップル」「同性カップル」や「パートナー」という言葉に色付けした。
〇 「同性間の婚姻」「同性間の婚姻制度」に色付けした。
〇 「現行の婚姻制度とは一部異なる制度を同性間の人的結合関係へ適用する制度」に色付けした。
〇 「婚姻に類する制度」に色付けした。
〇 「登録パートナーシップ制度」「登録パートナーシップ制度等」に色付けした。
〇 「パートナーシップ」「パートナーシップ証明」「パートナーシップ証明制度」に色付けした。
〇 「パートナーと家族になるための法制度」「パートナーと家族になることを可能にする法制度」「パートナーと家族になり、共同生活を送ることについて家族としての法的保護を受け、社会的公証を受けるための制度」に色付けした。
〇 「個人の尊厳」に色付けした。
〇 「人格的生存」に色付けした。
〇 「社会的な承認」の言葉が二つの次元で使われているため、意味に応じて別のものとして色付けした。
・ ある人的結合関係を「婚姻」として認める「社会的な承認」≒「社会通念」があるか否かの場合
・ 「婚姻」している者について「社会的な承認」があるか否かの場合
〇 「社会的に公証」「社会的公証」「社会内での公証」「公証」に色付けした。
〇 「婚姻及び家族」「婚姻及び家族制度」「婚姻及び家族に関する事項」「婚姻及び家族に関するその他の事項」「婚姻や家族に関する事項」を太字にした。
〇 憲法24条の「婚姻及び家族」と同一の法学的な意味の「家族」と、この判決が独自に考えている「家族」の文言を色分けした。
〇 主要な文に色付けているところがある。
〇 リンクを加えた。
【筆者】
インデント(字下げ)を加えて記載したところは、筆者の分析である。
令和4年11月30日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官
平成31年(ワ)第3465号 国家賠償請求事件
口頭弁論終結日 令和4年5月30日
判 決
主 文
1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は、原告らの負担とする。
事実及び理 由
第1 請求
被告は、原告らに対し、各100万円及びこれらに対する平成31年2月28日
から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要等
1 事案の概要
本件は、同性の者との婚姻を希望する原告らが、婚姻を異性間のものに限り同性間の婚姻を認めていない民法及び戸籍法の諸規定が憲法14条1項、24条1項及び2項に違反しているから、国会は民法及び戸籍法の諸規定が定める婚姻を同性間でも可能とする立法措置を講ずべき義務があるにもかかわらず、これを講じていないことが国家賠償法1条1項の適用上違法であると主張して、慰謝料各100万円及びこれらに対する訴状送達の日である平成31年2月28日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
2 前提事実等
当事者間に争いのない事実並びに後掲証拠(証拠番号は、特に断らない限り枝番号を含む。以下同じ。)及び弁論の全趣旨によって明らかに認定できる事実は以下のとおりである。
【筆者】
ここでは「当事者間に争いのない事実」として、下記の(1)では「性的指向」を取り上げている。
しかし、「性愛」は「内心の自由」に属するものであり、法制度とは明確に区別する必要がある。
そのため、人が「性愛」という心理状態を抱く場合があることを認めたとしても、その「性愛」の感情を満たすために法制度を立法しなけれはならないということにはならない。
また、「婚姻」は「性愛」という思想・信条・感情を保護することを立法目的とする制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合における「性愛」の対象となるもの(性的指向)を審査して異なる取扱いをするものでもないし、「性愛」に基づいて「婚姻」することを勧めるものでもない。
よって、この判決では「婚姻」する場合には「性愛」に基づくべきであるという特定の価値観を前提として論じようとしている部分があるが、この裁判において「性的指向」については「当事者間に争いのない事実」として提示されているとしても、「婚姻」する場合には「性愛」に基づくべきであるというような特定の価値観に対してまで「当事者間に争いのない事実」として双方の主張が合致しているわけではないことに注意が必要である。
(1) 性的指向、性的少数者
性的指向(sexual orientation)とは、人が情緒的、感情的、性的な意味で、人に対して魅力を感じることであり、このような恋愛、性愛の対象が異性に向くことが異性愛、同性に向くことが同性愛(ゲイ、レズビアン)、双方の性別に向くことが両性愛(バイセクシャル)である(以下、性的指向が異性愛である者を「異性愛者」、性的指向が同性愛である者を「同性愛者」といい、同性愛者と性的指向が両性愛である者を併せて「同性愛者等」という。)。また、身体的性別と性自認(gender identity)が一致しない者がトランスジェンダーである(以下、同性愛者等とトランスジェンダーを併せて「性的少数者」と呼ぶことがある。)。
【筆者】
「性的指向(sexual orientation)とは、人が情緒的、感情的、性的な意味で、人に対して魅力を感じることであり、」との記載がある。
ここに示されているように、「性的指向」と称するものの内容は「情緒的、感情的」なもので「魅力を感じること」であるというのであるから、これは精神的なものであり、「内心の自由」の範囲のものである。
憲法上の具体的な条文においては、19条の「思想良心の自由」や14条の「信条」によって捉えられるべきものである。
法律論としては、このような思想や感情を基にして自然人を分類することはできないし、このような人の内心を基準として異なる取扱いをすることは、19条の「思想良心の自由」に抵触して違憲となるし、14条の「平等原則」に抵触して違憲となる。
「恋愛、性愛の対象が異性に向くことが異性愛、同性に向くことが同性愛(ゲイ、レズビアン)、双方の性別に向くことが両性愛(バイセクシャル)である(以下、性的指向が異性愛である者を「異性愛者」、性的指向が同性愛である者を「同性愛者」といい、同性愛者と性的指向が両性愛である者を併せて「同性愛者等」という。)。」との記載がある。
上記のように一つの文として書いてあると分かりづらいので、まとめると下記のようになる。
・ 恋愛、性愛の対象が異性に向くことが異性愛
・ (恋愛、性愛の対象が)同性に向くことが同性愛(ゲイ、レズビアン)
・ (恋愛、性愛の対象が)双方の性別に向くことが両性愛(バイセクシャル)
・ 性的指向が異性愛である者を「異性愛者」
・ 性的指向が同性愛である者を「同性愛者」
・ 同性愛者と性的指向が両性愛である者を併せて「同性愛者等」
これらは、人の心理状態について、ある視点から分類したものに過ぎず、法律論として扱うこができる性質のものではない。
この判決は上記を取り上げるのみであるが、他にもまだまだ存在することを忘れてはならない。
・ 恋愛、性愛の対象が両性に向く者を「両性愛者」
・ 恋愛、性愛の対象が全てに向く者を「全性愛者」
・ 恋愛、性愛の対象が近親者に向く者を「近親性愛者」
・ 恋愛、性愛の対象が多方に向く者を「多性愛者」
・ 恋愛、性愛の対象が子供に向く者を「小児性愛者」
・ 恋愛、性愛の対象が老人に向く者を「老人性愛者」
・ 恋愛、性愛の対象が死体に向く者を「死体性愛者」
・ 恋愛、性愛の対象が動物に向く者を「動物性愛者」
・ 恋愛、性愛の対象が物に向く者を「対物性愛者」
・ 恋愛、性愛の対象が二次元に向く者を「対二次元性愛者」
・ 恋愛、性愛の対象が無い者を「無性愛者」
また、愛の感情が「国家」に対して向くことが「愛国」、愛の感情が「国家」である者を「愛国者」という。
他にも、下記を挙げることができる。
・ 愛の対象が軍事的なことに向く者を「軍事オタク」
・ 愛の対象が鉄道に向く者を「鉄道オタク」
・ 愛の対象がアニメに向く者を「アニメオタク」
・ 愛の対象が映画に向く者を「映画オタク」
・ 愛の対象がアイドルに向く者を「アイドルオタク」
・ ハリー・ポッターの作品を愛好する者を「ポッタリアン」
・ 植物性食品ばかりを摂る人を「ベジタリアン」
・ キリスト教を信じる者を「キリスト教徒」
・ イスラム教を信じる者を「イスラム教徒」
・ ユダヤ教を信じる者を「ユダヤ教徒」
・ ゾロアスター教を信じる者を「ゾロアスター教徒」
・ 仏教を信じる者を「仏教徒」
・ 神道を信じる者を「神道を信じる者」
・ 武士道を重んじる者を「武士道を重んじる者」
・ 脳の機能がADHDの状態にある者を「ADHDを持つ者」
・ 脳の機能がアスペルガーの状態にある者を「アスペルガーを持つ者」
・ 脳の機能が自閉症の状態にある者を「自閉症を持つ者」
・ 脳の機能が強迫神経症の状態にある者を「強迫神経症を持つ者」
・ 脳の機能が妄想症の状態にある者を「妄想症を持つ者」
・ 脳の機能が境界性パーソナリティー障害の状態にある者を「境界性パーソナリティー障害を持つ者」
・ 脳の機能が解離性同一性障害の状態にある者を「解離性同一性障害を持つ者」
・ 脳の機能が統合失調症の状態にある者を「統合失調症を持つ者」
・ 脳の機能がサイコパスの状態にある者を「サイコパス」
・ 迷える者を「迷える子羊」または「凡夫」
・ 迷いのない者を「解脱者」
・ 1/20 ~ 2/18生まれの人を「みずがめ座」
・ 4/20 ~ 5/20生まれの人を「おうし座」
・ 6/22 ~ 7/22生まれの人を「かに座」
人のタイプの分け方には、様々な方法がある。
エニアグラム性格診断【無料/90問式】あなたは9タイプのどれ?
これらはすべて心理的、精神的なものであり、「内心の自由」として扱われるものである。
「性愛」の分類の話も、「内心の自由」として保障される分類方法の一つに過ぎないものということである。
これらは法律論として区別して扱うことができるものではないし、これらを基にして法制度を立法することができることにはならない。
「身体的性別と性自認(gender identity)が一致しない者がトランスジェンダーである」との記載がある。
「身体的性別」については「セックス(sex)」を指すことが明らかであるが、「性自認」と称しているものの内実は「セックス(sex)」とは全く異なっており、その認識の様は心理学や精神分析学的な視点によって捉えられるべきものである。
また、この「性自認」という概念には議論がある。
【参考】「心の性別」の神話ーー性別、ジェンダー、GID 2022年10月14日
【参考】トランス問題をどのように考えるべきか ――最初の一歩―― 2022年11月28日
これについても、「内心の自由」に属するものであるから、法律論として扱うことができる性質のものではない。
これらについて、詳しくは当サイト「性別と思想」で解説している。
(2) 原告ら
ア 原告aと原告bは、共に同性愛者の女性で、平成6年から同居して共同生活を送っており、平成30年9月6日、居住する地方公共団体のパートナーシップ証明制度(地方公共団体によって呼称及び具体的内容は異なるが、大要、地方公共団体が同性カップルをパートナーとして公証する制度をいう。以下同じ。)を利用して、パートナーシップの宣誓を行った。原告aと原告bは、平成31年1月17日に婚姻届を提出したが、受理されなかった。(甲C1、2、5~10)
【筆者】
「原告aと原告bは、共に同性愛者の女性で、」との記載があるが、「同性愛者」であるかないかは、個々人の内心の中でしか分からないものであるから、客観的に証明することは不可能である。
このような客観性を有しないものを根拠とする形で法律論を組み立てることはできないことに注意が必要である。
このような内心に基づいて何かを論じることができるとすれば、「同性愛者」を称する者だけでなく、「両性愛者」を称する者も、「全性愛者」を称する者も、「多性愛者」を称する者も、「小児性愛者」を称する者も、「老人性愛者」を称する者であっても、「死体性愛者」を称する者も、「動物性愛者」を称する者も、「対物性愛者」を称する者も、「対二次元性愛者」を称する者も、「無性愛者」を称する者も論じることが可能となってしまう。
そのため、個々人を取り上げる際に、個々人の抱く内心に踏み込む形で論じることは妥当でない。
恐らくこの判決を書いた裁判官は、自分自身についても、何らかの「性愛」に基づいて「〇〇性愛者」であると認識しているのかもしれないが、そのような「性愛」に基づいた分類で人を区別して考えていること自体が、特定の思想や信条、信仰を抱く者の中でのみ通用する価値観でしかないものである。
占いを行う者であれば、「オーラ診断」によって人をオーラの色で分ける者もいるし、「どうぶつ診断」によって、個々人の性格を動物の特性に応じて分類する者もいる。
判決文を書く際に、「オーラの色は緑色である」とか、「どうぶつ診断ではヤギである」などと述べていたとすれば、それは既に特定の価値観を信じている者の主張か、特定の思想に基づく分類を用いている者の主張に過ぎないものとなるのであり、法律論として妥当な内容ではなくなる。
この判決が「同性愛者」かどうかという視点で見ていること自体が、既に「性愛診断」という特定の価値観に基づく主張を行っていることになるのであり、法律論として妥当な内容ではなくなるのである。
また、「同性愛者」と称する者がいるとしても、その者が「同性愛」の思想、信条、信仰、感情を有しているか否かなど、個々人の内心にのみ存在するものであることから、それを外部から客観的に判定することのできる性質のものではない。
よって、「同性愛者」と分類していること自体も、その者がそう言っているだけという自称でしかないものである。
法律を学ぶ者に対して「司法試験」などの試験によって、個々人の能力を評価し、試験に合格した者に、何らかの資格を付与することはあり得るが、「同性愛者」を名乗ることに、何らの試験も必要ないのである。
これは結局、「私は真の愛国者である」だとか、「私はキリストを愛する」だとか、「私は孫を愛する」だとか、「私は社員を愛する」だとか、そのような思想、信条、信仰、感情を述べるに過ぎないものと同じである。
裁判所が「愛国者」であるか否かを認定することが妥当でないことと同様に、個々人の内心に基づいて人を分類するようなことをするべきではないし、自己の内心を告白するに過ぎない者の主張をそのまま取り上げて認定することも妥当でない。
そのため、「同性愛者」などと分類していること自体が、法律論として誤った判断である。
「居住する地方公共団体のパートナーシップ証明制度(地方公共団体によって呼称及び具体的内容は異なるが、大要、地方公共団体が同性カップルをパートナーとして公証する制度をいう。以下同じ。)を利用して、パートナーシップの宣誓を行った。」との記載がある。
これについて、「地方公共団体」の「パートナーシップ証明制度」の内容が民法上の婚姻制度や憲法上の規定に抵触している場合には、その制度は違法となる。
詳しくは、当サイト「パートナーシップ制度」で解説している。
イ 原告dと原告cは、共に同性愛者の女性で、平成18年頃からお互いの子供3人とともに同居して共同生活を送っており、平成27年11月5日、居住する地方公共団体のパートナーシップ証明制度を利用して、パートナーとなることの宣誓を行った。原告dと原告cは、平成31年2月7日に婚姻届を提出したが、受理されなかった。(甲D1~8)
ウ 原告eと原告fは、共に同性愛者の男性で、平成28年頃から同居して共同生活を送っており、平成31年2月1日に婚姻届を提出したが、受理されなかった。(甲E1~3、7)
エ 亡gと原告hは、共に同性愛者の男性で、平成15年頃から同居して共同生活を送り、平成31年1月4日に婚姻届を提出したが、受理されなかった。亡gは本件訴訟提起後である令和▲年▲月▲日に死亡し、原告hはその包括受遺者である。(甲F1、3~9)
オ 原告iは、ドイツ連邦共和国籍の同性愛者の女性であり、平成25年に来日した。原告iは、日本人女性と2018年(平成30年)9月10日にベルリン市において婚姻した。原告iと上記日本人女性は、平成31年1月16日、日本国内の居住地において婚姻届を提出したが受理されなかった。(甲G1~3、6、10)
【筆者】
上記は、「同性愛者」であることが何度も認定されているが、自己の思想、信条、信仰、感情を告白するものに過ぎず、このような事柄は法律論として区別して取扱うことのできる性質のものではない。
これは「同性愛者」に限られるものではなく、「異性愛者」を称する者も、「無性愛者」を称する者も、それ以外の「性愛」を持つと称する者も同じである。
そもそも「性愛」の分類を使っていない者もいるし、そのような分類で人を見ていない者もいるし、「性愛」を重視していない者もいるし、考えたことない者もいるのであり、「性愛」の存否や傾向を述べること自体が、特定の価値観で人を分類しようとする者の用いている一つの思想、信条、信仰に過ぎないものを公の機関が安易に受け入れて推進しようとしている状態となっているのであり、極めて不適切である。
3 法律の定め
民法は、第4編第2章「婚姻」を設け、婚姻に関する諸規定を置き(731条以下)、婚姻の成立要件、効力等について定めているところ、その中で、婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる旨を定め(739条1項)、婚姻した当事者を「夫婦」と呼称し、そのいずれかを「夫」又は「妻」と呼称している(750条、767条等)。
また、戸籍法は、婚姻をしようとする者は、夫婦が称する氏等の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならず(74条)、婚姻の届出があったときは、夫婦について新戸籍を編成し(16条1項本文)、当該戸籍には、戸籍内の各人について、夫又は妻である旨が記載されることとされている(13条6号)。
このように、婚姻制度に関する民法第4編第2章及び戸籍法の諸規定(以下、これらを併せて「本件諸規定」という。)は、同性の者同士の婚姻を明文で禁止しているものではないが、婚姻を「夫」と「妻」の間のもの、すなわち異性間のものとして定めており、同性間の婚姻は認められていない。
4 争点
(1) 同性間の婚姻を認めていない本件諸規定の憲法適合性
(2) 国会が同性間の婚姻を可能とする立法措置を講じないことが国家賠償法1条1項の適用上違法と評価されるか
(3) 損害の有無及び額
(4) 国家賠償法6条所定の相互保証の存否(原告i関係)
5 争点に関する当事者の主張
⑴ 同性間の婚姻を認めていない本件諸規定の憲法適合性(争点⑴)
(原告らの主張)
ア 本件諸規定が憲法24条1項に違反することについて
(ア) 人と人が、親密な関係を基礎として一定の永続性を持った共同生活を営み、家族を形成することは、人生の喜びや悲しみを分かち合うことを通じた人生の充実をもたらすものであり、その人らしい人生、その人らしい幸福追求をなす上で重要な意味を持つ。このような家族の形成について、法律が要件と効果を定めて承認・公証し、社会の構成単位として位置付け、権利義務の束を付与する仕組みが婚姻(法律婚)であるが、婚姻は、上記のとおり人生の充実をもたらすばかりでなく、法制度を通じた様々な権利義務の付与やそれに伴う社会的承認を通じ、その当事者を社会の構成単位として正式に認め迎える契機ともなるものである。このように、婚姻はその人の人生と人格に深く関わるものであり、個人が人格的生存を図る上で不可欠の事柄である。そのため、婚姻をするかどうか、いつ誰とするかについての自己決定権(以下「婚姻の自由」という。)は、全ての人が個人として尊重される(憲法13条)という憲法の基本原理に照らし、自己決定権の重要な一内容をなすものというべきである。
そして、婚姻及び家族制度に関する規定である憲法24条の法意は、個人よりも「家」を優位に置いて婚姻の自由が制限されるなどした昭和22年法律第222号による改正前の民法の下での婚姻制度の在り方を根本から否定した上、婚姻が自己決定権の重要な一内容であることに鑑み、新たな婚姻制度の下では人が望む相手との意思の合致のみにより自律的に婚姻をなし得ることが確保されなければならないことを命ずるというものに他ならない。このように、法制度の存在を前提に、人が自己の望む相手と意思の合致のみにより自律的に婚姻をする権利としての婚姻の自由は、憲法24条1項により保障される。
(イ) この婚姻の自由は、法律婚を定めた法制度の存在を前提とするものではあるが、人と人が生活を共にしようとするに当たり、社会が一定の条件の下でこれを承認し、これに様々な利益や責任を結びつける仕組みは、前国家的なものであり、婚姻に関する法制度は、このような性格を有する婚姻に対し、法律による規律・整序を及ぼしたものにすぎない。したがって、憲法24条1項は、婚姻に関する法制度の枠内でのみ婚姻の自由を保障しているのではなく、国家以前の個人の尊厳に直接由来する自由として婚姻の自由を保障していると解すべきであり、憲法が婚姻制度について要請し想定した核心部分を婚姻に関する法制度が何らの正当化根拠なく制約する場合には、その法律は違憲となる。
そして、憲法24条1項が、婚姻は両性の合意にのみに基づいて成立するとして、婚姻が当事者間の自由かつ平等な意思決定により成立すべきことを定めていること、同条2項が、配偶者の選択が個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきことを求めていること、婚姻は個人の人格的自律に深く関わり、個人の幸福追求において最も重要な意味を持つものの一つであることなどからすると、憲法が婚姻制度について要請し想定した核心部分とは、望む相手と両当事者の合意のみに基づいて婚姻が成立するという点であると解すべきである。
(ウ) 同性カップルも、異性カップルと全く同様に婚姻の本質を伴った共同生活を営むことができ、現に原告らは異性カップルと同様にパートナーとの間で信頼関係に基づく関係を築いている。同性愛者等にとって、婚姻による法的保護を受けることが人格的生存に不可欠であることは異性愛者と何ら異なるところはなく、このことは、原告らがパートナーと婚姻できないために周囲から夫婦としての承認を得ることができず、具体的な不利益を受けている事実からしても明らかである。さらに、異性愛者に婚姻の自由を保障する一方で同性愛者等を婚姻の自由から排除することは、同性愛者等に対し、異性愛者よりも劣った存在であり、社会の正式な構成員ではないとのスティグマを与えるものであり、このことは民主主義社会の基盤を弱体化させることにもつながる。
したがって、憲法が婚姻の自由を保障した趣旨は同性カップルにも当然に妥当し、これらを別異に扱うべき憲法上の根拠は存在しないから、憲法24条1項は、異性愛者のみならず、同性愛者等にも婚姻の自由を保障するものであり、同項の婚姻の自由は同性間の婚姻にも及ぶものと解すべきである。
(エ) これに対し、憲法24条1項は「両性」の文言を用いており、その制定の際には異性間の婚姻のみが想定されていたことがうかがわれる。
しかし、憲法制定過程において、婚姻の当事者を男女に限定することが議論されたり、そのために「両性」という文言が使用されたりした事実はない。憲法24条の制定趣旨は、旧憲法下の家制度の制約を婚姻及び家族の法制から排除し、婚姻については対等な当事者の自由な意思によるべく、戸主等の同意を要件とする制度を排除することであり、同条における「両性」の文言は、同性間の婚姻を排除する趣旨に出たものではないというべきである。
また、憲法24条が「両性」の文言を用いたのは、憲法制定時、同性愛が精神疾患と認識されており、同性間の親密な関係や共同生活が法的保護を及ぼす対象として意識されることがなかったためである。しかし、その後、精神医学の分野において、同性愛を精神疾患とする知見に合理的な根拠がないことが実証的に明らかにされ、現在では同性愛は精神疾患に当たらないとする認識が確立している。これに伴い、性的指向に基づく人権の制約は許されないという認識が国際的に浸透し、諸外国では同性カップルの婚姻の法制化が次々に実現している。我が国においても、多くの地方自治体において同性カップルを承認する制度であるいわゆるパートナーシップ証明制度の導入が進んでいるほか、国民の中でも、同性間の婚姻制度の導入に賛成する者が約6割を占めるなど、同性カップルを異性カップルと等しく婚姻により保護すべきであるという意識は高まり続けている。
以上のとおり、憲法の原理に即し、また社会の変化を踏まえて考察すれば、憲法が婚姻制度について要請し想定した核心部分である、望む相手と両当事者の合意のみに基づいて婚姻が成立するというときの「両当事者」には、同性の者同士も含まれると解釈するのが、今日の解釈として相応しいものというべきである。憲法制定当時に想定されていなかった権利がその後の社会の変化を受けて憲法上の権利として認められるに至った例は数多く存在するのであり、上記のごとく考えることは何ら不当なものではない。そもそも、婚姻の自由が憲法上の権利として保障される究極的な根拠は、それが憲法の基本価値である個人の尊厳に不可欠だからであるところ、婚姻がもたらす法律上・事実上の価値の重要性や、婚姻をするかどうか、いつ誰とするかを自律的に決定することができることの重要性は、異性愛者であると同性愛者等であると、何ら異なるところはないのであって、婚姻の自由が異性間の婚姻については保障される一方で、同性間の婚姻については保障されないなどとする解釈がおよそ不当であることは明らかである。
よって、憲法24条1項における「両性」とは「両当事者」を意味すると解すべきであり、同項は異性愛者と同様、同性愛者等に対しても婚姻の自由を保障しているというべきである。
(オ) なお、被告は、本件諸規定の目的は生殖と養育に対する法的な保護であるから、異性カップルにのみ婚姻の資格を与える本件諸規定の立法目的は合理性を有すると主張する。しかし、民法上、生殖能力及び意思が婚姻の要件となっていないことからも明らかなとおり、生殖と養育は婚姻の目的ではなく、一つの機能・役割にすぎない。かえって、子を産み育てながら共同生活を送ることは異性カップルと同様に同性カップルでも行い得るのであるから、生殖と養育に対する法的な保護を婚姻の目的として挙げるのであれば、なおさら同性カップルの保護の必要性は高いというべきである。
そして、同性愛者等を婚姻から排除することを正当化する根拠は何ら存在せず、それどころか、本件諸規定の基礎となる立法事実であった、異性愛こそが正常な人的結合の在り方であり、その反面、同性愛は正常ならざる人的結合であるとする観念(いわゆる異性愛規範)は現在では失われているのであるから、本件諸規定は、今日においては何らの合理性を有しない。
よって、同性間の婚姻を認めていない本件諸規定は、憲法24条1項に違反するものである。
イ 本件諸規定が憲法24条2項に違反することについて
(ア) 憲法24条2項は、婚姻及び家族に関する立法について、その制定の指針を示すと同時に、「個人の尊厳と両性の本質的平等」に反する立法については、これを無効ならしめる効力を有する規定である。
ところで、婚姻をするかどうか、いつ誰と婚姻するかについての意思決定、とりわけ誰と婚姻するかという配偶者の選択に係る意思決定は、その人の人格に深く関わり、個人の幸福の追求について自ら行う意思決定の中で最も重要なものの一つであり、もし婚姻、とりわけ配偶者の選択を自由に行えないのであれば、個人が尊厳ある存在として尊重されたとは到底いえない。したがって、婚姻の自由、とりわけ配偶者選択の自由は、憲法24条2項にいう「個人の尊厳と両性の本質的平等」の最も重要な内容の一つに当たるというべきであり、同項が「配偶者の選択」を明文で掲げ、更に同条1項が婚姻の自由について特に規定を設けたのは、上記の内容を実定法に具現化したものであると解される。そして、婚姻の自由、とりわけ配偶者選択の自由が上記のごとき重要性を有することに鑑みれば、法律が婚姻の自由、とりわけ配偶者選択の自由を直接否定したり、婚姻の成立や配偶者の選択に個人の人格を否定するような条件を設けて自由な意思決定を制約したりするような場合には、このような制約に真にやむを得ない理由が存在するか否かが厳格に審査される必要があり、このような理由が存在すると認められない限り、当該法律は、憲法24条2項に違反するものと解すべきである。
なお、被告は、憲法24条2項が立法府の広い裁量を認めたものである旨主張する。しかし、同項は、婚姻及び家族に関する立法が「個人の尊厳及び両性の本質的平等」に立脚したものでなければならないとして立法に対する直接的な拘束を及ぼしているのであるから、立法府は正当な理由のない限り上記拘束に従った立法をするほかないのであって、立法裁量を行使する余地はない。被告の主張は失当である。
(イ) 本件諸規定は、同性間の婚姻を禁止するものであるから、本件諸規定により同性愛者等は自らが望む相手との婚姻をすること自体ができなくなる。よって、本件諸規定は、同性愛者等の婚姻の自由を直接的かつ強度に制約するものである。婚姻は、戸籍によって身分関係が公証され、様々な権利義務の束を発生させるとともに、その身分に応じた社会的承認が付随する法律行為であり、婚姻により、共同生活関係は法的な家族として保障され、社会的に承認されることとなる。同性愛者等は、婚姻をすること自体ができなくなることにより、配偶者としての様々な権利義務の束を享受できず、夫婦としての社会的承認を受けることもできないという重大な不利益を被ることになる。
また、性的指向は人の性の重要な構成要素であり、人格に深く根差した個性であって、自らの意思で変えることは困難である。そのような中、同性愛者等に対して異性間の婚姻を前提とする婚姻制度を強いることは、性的指向及び性自認を根拠に社会の重要な制度から排除することにつながるものであり、その人の人格そのものを否定するものである。
しかも、本件諸規定の存在自体、同性愛者等に対する社会的な差別・偏見を助長させ、社会を分断するものである。
以上からすれば、本件諸規定は同性愛者等の個人の尊厳を極めて深刻に毀損するものというほかなく、「個人の尊厳と両性の本質的平等」に立脚したものとは到底いうことができず、これを正当化する根拠もおよそ見出すことができない。
したがって、本件諸規定は、憲法24条2項に違反するものである。
(ウ) また、同性間の婚姻に憲法24条1項による婚姻の自由の保障が及ぶか否かをおくとしても、本件諸規定は同条2項に違反するものである。
すなわち、婚姻及び家族に関する立法が「個人の尊厳と両性の本質的平等」に立脚したものでなければならないとする憲法24条2項の要請は、当該立法が憲法上の権利として保障される人格権を不当に侵害してはならないとか、両性の形式的な平等が保たれなければならないということのみを求めるものにとどまらず、憲法上直接保障された権利とまではいえない人格的利益をも尊重すべきこと、両性の実質的な平等が保たれるように図ること、婚姻制度の内容により婚姻をすることが事実上不当に制約されることのないように図ること等についても十分に配慮した法律の制定を求めるものである。よって、法律が婚姻の自由に対する直接の制約とはならない場合でも、事実上これを制約するものである場合には、当該法律は、やはり憲法24条2項に違反することとなる。
そして、結婚をするかどうか、いつ誰と結婚するかといった事柄に関する意思決定は、少なくとも個人の人格的生存にとって不可欠の利益であることは疑いがないから、憲法24条2項の適用上は、このような人格的利益も尊重すべきである。そして、本件諸規定は、同性カップルが異性カップルと何ら異なるところのない共同生活を営んでいるにもかかわらず同性カップルを婚姻から排除している点で、同性カップルと異性カップルの本質的平等を害しているし、本件諸規定は同性愛者等にとって婚姻に対する不当な制約となっていることは明らかである。
(エ) さらに、前記アで述べたとおり、憲法24条1項の「両性」の文言に異性間の婚姻以外を否定あるいは排除する趣旨はない。また、同項が制定当時は異性間の婚姻を想定していたとしても、同条2項は、「配偶者の選択」が「個人の尊厳」に立脚せねばならないと定め、男女間のものに限定していない。むしろ、同条1項は、同条2項が定める「個人の尊厳と両性の本質的平等」のうち特に重要な内容を定めたものであり、同条2項の内容が同条1項の内容に限定される関係にはなく、同条2項の「婚姻及び家族に関するその他の事項」について異性カップル以外の家族についてその保護範囲が及ばないなどという解釈は成立しない。
ウ 本件諸規定が憲法14条1項に違反することについて
(ア) 本件諸規定の下では、異性愛者が自らの性的指向に従って異性のパートナーと婚姻することができる一方で、同性愛者等はその性的指向に従って同性のパートナーと婚姻することができない。これは、性的指向が異性に向いているか同性に向いているか、すなわち性的指向によって、婚姻の可否それ自体に関して区別取扱いを行うものである。本件諸規定において「性的指向」という文言が婚姻の要件に挙げられているものではないが、婚姻が異性間のものに限定されていれば、同性愛者等が婚姻から排除される結果となることは当然のことであるから、性的指向が直接に婚姻の成立要件を構成するものでないからといって上記区別取扱いの存在を否定することは許されない。
また、上記の観点とは別に、本件諸規定の下では、ある者との婚姻を望む者がいた場合に、異性の者は婚姻をすることができるのに、同性の者は婚姻をすることができないのであるから、自分自身の性別あるいは婚姻を希望する相手の性別によって婚姻の可否が区別されているといえ、性別による区別取扱いであるともいうことができる。
(イ) そして、上記区別取扱いは、同性愛者等に対して婚姻をすることを直接的かつ全面的に制約するものであり、同性愛者等は、民法上の配偶者の地位という重要な法的地位を得られないのみならず、多岐にわたる婚姻による法律上・事実上の効果・利益を享受することができず、婚姻した異性カップルと同等の社会的承認も得ることができないから、その不利益は甚大なものであり、このことは、原告らが現に婚姻ができないことによって法律上・事実上多岐に渡る不利益を受けてきたという事実をみればなおさら明らかである。また、上記区別取扱いが性的指向ないし性別という本人のコントロールの及ばない事由に基づくものであり、憲法14条1項後段列挙事由である社会的身分又は性別によるものであること、異性愛以外の性的指向を有する者は全体の1割以下であって上記区別取扱いについて民主政の過程を通じた救済が期待できないことからすれば、上記区別取扱いに合理的根拠が認められるかの審査は、厳格に行わなければならない。
(ウ) その上で、これまで述べたとおり、上記区別取扱いが自らコントロールできない事由に基づくものであること、婚姻の自由に対する法的かつ直接的な制約であり、被侵害権利、不利益は重大かつ甚大であること、婚姻制度の目的が親密性に基づく共同生活の保護にあることからすれば同性愛者等に婚姻を認めない理由は存在しないこと、婚姻に伴う個別の法的効果の趣旨に照らしても、同性カップルにこのような法的効果を与えない理論的根拠が存在しないこと、さらに、同性愛者等を婚姻から排除する本件諸規定の存在自体が同性愛者等に対する社会的偏見を強力に維持し再生産する役割を果たしていることからすれば、本件諸規定が婚姻の可否について異性愛者と同性愛者等とで区別取扱いを設けていることに合理的理由が存在しないことは明らかである。
(エ) 被告は、婚姻制度の目的は生殖の保護にあると主張する。しかし、異性カップルの中には、そもそも生殖の意思・能力がないものもあるところ、そのようなカップルが婚姻制度の本来の目的に合致しない存在であると一般的に見なされていないことは明らかである。婚姻制度の目的は、親密な関係(親密性に基づく共同生活)の保護であり、生殖の保護はそこから派生する重要な機能・役割の一つと位置付けるのが妥当であり、被告の上記主張は理由がない。
(被告の主張)
ア 本件諸規定が憲法24条1項に違反しないことについて
(ア) 憲法解釈に当たっては条文の文言に着目することが重要であるところ、憲法24条は、1項において「両性」及び「夫婦」という文言を用い、2項において「両性の本質的平等」という文言を用いている。これらの文言の一般的な語義や、憲法制定過程において同条で用いられた文言、更には憲法審議における議論の状況等からすると、憲法24条1項にいう「両性」が男女を意味することは明らかであり、憲法は同性間に婚姻を成立させることをそもそも想定していないというべきである。
(イ) また、異性間の人的結合関係が婚姻として制度化された背景には、一人の男性と一人の女性という異性間の人的結合関係が、今後の社会を支える次世代の子を産み育てつつ、我が国の社会を構成して支える自然的かつ基礎的な集団単位である家族を形成しているという社会的実態があり、そのことに対して歴史的に形成されてきた社会的な承認がある。これに対し、同性間の人的結合関係には自然生殖の可能性が認められないし、同性間の人的結合関係を我が国における婚姻の在り方との関係でどのように位置付けるかは未だ社会的な議論の途上にあり、我が国において、同性間の人的結合関係に対して異性間の人的結合関係と同視し得るほどの社会的な承認が存在しているとはいい難い。そうすると、憲法24条1項は現在でもなお異性間の婚姻のみを保護の対象としていると解するのが相当である。
(ウ) 婚姻が必然的に一定の法制度の存在を前提としている以上、仮に原告ら主張のような婚姻に関する自己決定権(婚姻の自由)を観念できるとしても、その自己決定権は、憲法の要請に従って構築された法制度の枠内で保障されるものにとどまり、法制度を離れた生来的、自然権的な権利又は利益として憲法で保障されているものではない。そして、憲法24条1項は、婚姻について異性間の人的結合関係のみを対象としており、同性間の人的結合関係を対象とすることを想定していないのであるから、原告らの主張は、同性間の人的結合関係についても異性間の人的結合関係を対象とする婚姻と同様の積極的な保護や法的利益の供与を認める法制度の創設を国会に対して求めるものにすぎず、このような内実のものが自己決定権により基礎づけられると解することはできない。これは、同性間の人的結合関係を婚姻に含めることが、これを志向する当事者の幸福追求に資する面があるとしても変わるものではない。
(エ) また、原告らは、同性愛を精神疾患とする知見が否定されたことを主張するが、民法が定める婚姻制度は、昭和22年法律第222号による民法の改正(以下「昭和22年民法改正」という。)の前後を通じ、飽くまで我が国において婚姻が生殖と子の養育を目的とする男女の結合であるとの伝統・慣習を立法化したものにすぎず、その過程で同性愛が精神疾患であるとの知見が積極的に立法に反映された形跡は見当たらない。したがって、同性愛を精神疾患とする知見が否定されたことは、本件諸規定の合理性を左右するものではないというべきである。
(オ) しかるに、憲法24条1項は、異性間の婚姻に限って婚姻の自由を保障しているところ、本件諸規定はその趣旨を具体化したものにすぎないから、本件諸規定は何ら憲法24条1項に違反するものではない。
イ 本件諸規定が憲法24条2項に違反しないことについて
(ア) 憲法24条2項は、婚姻及び家族に関する事項について、国の伝統や国民感情を含めた社会状況における種々の要因を踏まえつつ、それぞれの時代における夫婦や親子関係についての全体の規律を見据えた総合的な判断を行うことによって定められるべきものであるとの観点から、具体的な制度の構築を第一次的には国会の合理的な立法裁量に委ねるとともに、その立法に当たっては、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきであるとする要請、指針を示すことによって、その裁量の限界を画したものである。
前記アに述べたとおり、憲法24条1項は異性間の人的結合関係に限って婚姻の自由を保障するものである。同条2項はこのような前提の下で婚姻の在り方を具体化する制度の整備を立法府に要請するものであり、同性間の人的結合関係をも対象として婚姻を認める立法措置をとることを要請していると解することはできない。そして、同項にいう「個人の尊厳」の意義も、このような規定の在り方に即して解釈されるべきであるところ、本件諸規定は、上記の要請に従った立法の結果に他ならないのであるから、何ら違憲の問題を生ずる余地はない。
また、憲法24条2項の要請の範囲を超えて同性間の婚姻を可能とする立法を行うか否かについては、国会に広範な立法裁量が認められるところ、国会が同性間の婚姻を可能とする立法をしないことについて立法裁量の逸脱があるということはできない。
(イ) 原告らは、本件諸規定が性自認及び性的指向に基づいて差別するものであるとか、本件諸規定が同性愛者等に対するスティグマを醸成するものであるなどとして、本件諸規定の存在自体が同性愛者等の「個人の尊厳」を著しく毀損していると主張する。
しかし、本件諸規定は、婚姻制度を利用することができるか否かの基準を具体的・個別的な婚姻当事者の性自認及び性的指向の点に設けたものではなく、本件諸規定の文言上、同性愛者等であることによって法的な差別的取扱いを定めているものではないから、これをもって性自認及び性的指向に基づく差別と評価する余地はない。また、前記アのとおり、多種多様な人的結合関係のうち、異性間の人的結合関係が婚姻として制度化された背景には、自然生殖可能性を前提とする一人の男性と一人の女性の人的結合関係が、我が国の社会を構成して支える自然的かつ基礎的な集団単位である家族を形成しているという社会的な実態があり、このような実態に対して歴史的に形成されてきた社会的な承認があるのに対し、同性間の人的結合関係には未だこれと同視し得るほどの社会的な承認が存在するとはいえないのであるから、婚姻という法制度の対象を異性間の婚姻に限定することには合理的な理由がある。これらに加え、本件諸規定の存在にかかわらず同性間で婚姻と同様の人的結合関係を結ぶことは何ら妨げられないことも考慮すれば、本件諸規定が同性愛者等に対するスティグマを醸成するものであると評価することも相当でないというべきである。
(ウ) 以上から、本件諸規定は、憲法24条2項に違反しない。
ウ 本件諸規定が憲法14条1項に違反しないことについて
(ア) 原告らは、本件諸規定により同性愛者等はその性的指向に合致する者との婚姻を妨げられているから、本件諸規定は性的指向によって婚姻の可否それ自体についての区別取扱いを設けていると主張する。
しかし、法律の規定が特定の事由に基づいて区別取扱いを設けているといえるか否かは、当該規定の趣旨・内容や在り方から客観的に判断すべきであり、当該規定が存在する結果として実際上生じ、又は生じ得る帰結から判断することは相当でない。そして、本件諸規定は、飽くまでも一人の男性と一人の女性の間の婚姻を定めるものにすぎず、その文言上、婚姻の成立要件として当事者に特定の性的指向を有することを求めたり、当事者が特定の性的指向を有することを理由に婚姻を禁じたりするものではないから、性的指向に応じて婚姻の可否を定めているわけではない。このように、本件諸規定は性的指向からは中立的な規定であり、同性愛者等がその性的指向に合致する者との間で婚姻をすることができないとの事態が生じ、それにより同性愛者等と異性愛者との間で婚姻の可能性についての差異が生じているとしても、それは本件諸規定から生ずる事実上の結果又は間接的な効果にすぎない。本件諸規定は、全ての人に対して一律に婚姻制度の利用を認めており、本件諸規定それ自体に性的指向に応じた形式的不平等が存在するわけではない。
また、原告らは、本件諸規定は性別に基づく区別取扱いであるとも主張する。しかし、本件諸規定の下では男性も女性もそれぞれ異性とは婚姻することができるのであるから、本件諸規定は性別に基づく区別取扱いを定めたものとはいえない。
(イ) 本件諸規定が憲法14条1項に適合するか否かを検討するに当たっては、立法府の広範な立法裁量を前提に、緩やかな審査がされるのが相当である。
すなわち、本件諸規定の定める婚姻制度は、憲法24条2項の要請に基づいて創設された制度であるところ、同項は、婚姻及び家族に関する事項について、国の伝統や国民感情を含めた社会状況における種々の要因を踏まえた総合的な判断を行うべきであるとの趣旨から、具体的な制度の構築を第一次的には国会の合理的な裁量に委ねている。そうであれば、本件諸規定が憲法14条1項に適合するか否かを審査するに当たっては、憲法24条2項が立法府に与えた広範な立法裁量を考慮することは不可欠であるというべきである。このことに加え、憲法上、婚姻の自由は異性間の人的結合関係について保障されているにとどまり、同性間の人的結合関係については婚姻の自由が保障されているわけではないこと、同性間の婚姻を認める立法がなくとも、同性間において婚姻類似の人的結合関係を形成、維持したり、共同生活を営んだりすることは何ら妨げられていないことを考慮すると、本件諸規定が憲法14条1項に違反しているといえるのは、本件諸規定の立法目的に合理的な根拠がなく、又はその手段・方法の具体的内容が立法目的との関連において著しく不合理なものといわざるを得ないような場合であって、立法府に与えられた広範な立法裁量の範囲を逸脱又は濫用するものであることが明らかである場合に限られるというべきである。
(ウ) その上で、異性間の人的結合関係が婚姻として法制度化される前から、婚姻は男女間のものであるとする慣習が存在していたこと、婚姻の効果に関する民法の諸規定、とりわけ嫡出の推定(民法772条)や子が父母の氏を称すること(同法790条)の存在などからすると、本件諸規定の目的は、一人の男性と一人の女性が子を産み育てながら共同生活を送るという関係に対して特に法的保護を与えることにあると解するのが相当である。そして、我が国において、一人の男性と一人の女性による人的結合関係により子を産み育てる関係が我が国の社会を構成する基礎的な集団単位として機能してきたという実態があり、そのことに対して歴史を通じて社会的な承認が醸成されてきたことを考えれば、このような立法目的が合理性を有することは明らかである。
そして、同性間の人的結合関係には生殖可能性がなく、また我が国においては同性間の人的結合関係を異性間の婚姻関係と同視し得るほどの社会的承認が存在しているとはいい難いこと、他方で、同性間の婚姻が認められていないとしても、同性間で婚姻類似の親密な人的結合関係を構築、維持したり、共同生活を営んだりすることは何ら妨げられないこと、また、契約や遺言等の活用によって婚姻が認められていないことによる事実上の不利益は相当程度解消することを考慮すれば、同性間の人的結合関係を婚姻の対象に含めないことが本件諸規定の立法目的との関連において合理性を欠くと評価することはできない。
なお、本件諸規定の下では、子を持つ意思や可能性(能力)がない男女であっても、婚姻をすることは可能である。しかし、本件諸規定の立法目的は、その対象となる当事者として抽象的・定型的な男女のペアを想定しているところ、男女のペアには少なくとも抽象的・定型的には生殖可能性があるのであるから、実際の自然生殖可能性の有無にかかわらず婚姻を認めることは、基準として不合理ではない。加えて、夫婦間に子がなくとも、また子を持つ意思や可能性がなくても、夫婦間の人的結合関係に基づく家族関係に対する社会的な承認が存在することには変わりがない。よって、子を持つ意思や可能性(能力)を問うことなく男女のペアに対して婚姻を認めている本件諸規定の定めが、上記立法目的に照らして合理性を欠くとはいえない。
(エ) 以上によれば、本件諸規定は、憲法14条1項に違反しない。
⑵ 国会が同性間の婚姻を可能とする立法措置を講じないことが国家賠償法1条1項の適用上違法と評価されるか(争点⑵)
(原告らの主張)
ア 法律の規定が憲法上保障され又は保護されている権利利益を合理的な理由なく制約するものとして憲法の規定に違反するものであることが明白であるにもかかわらず、国会が正当な理由なく長期にわたってその改廃等の立法措置を怠る場合等においては、国会議員の立法過程における行動が職務上の法的義務に違反したものとして、例外的に、その立法不作為は、国家賠償法1条1項の規定の適用上違法の評価を受ける。
以下に述べるとおり、本件諸規定が憲法14条1項、24条1項及び2項に違反するものであることが遅くとも平成20年には明白になっていたにもかかわらず、国会は正当な理由なく長期にわたって、本件諸規定が定める婚姻を同性間でも可能とする立法措置(以下「同性間の婚姻を可能とする立法措置」という。)をとることを懈怠しているから、このような立法の不作為は、国家賠償法上違法である。
イ 20世紀後半、精神医学等の分野において相次いで同性愛が精神疾患に当たるとする知見が否定された。それに引き続き、立法・行政等の分野でも、平成6年3月、市民的及び政治的権利に関する国際規約(以下「自由権規約」という。)2条1項及び26条の「性」には「性的指向を含む」との判断が自由権規約委員会によって示され、主要な人権条約として初めて同性愛を人権問題と位置付けた。その後、平成18年に「性的指向と性自認に関する国際人権法の適用に関するジョグジャカルタ原則」が採択されたことなどを通じ、性的指向や性自認に基づく権利利益の制約や差別は許されないとの法規範が国際的に浸透するようになった。そして、平成18年までに5か国において同性間の婚姻が法制化されていた。
そのような中、我が国においては、平成12年に人権教育及び人権啓発の推進に関する法律が成立し、性的指向と性自認に基づく差別が人権侵害であるという認識が定着していった。そして、平成20年5月、我が国は、国連人権理事会の普遍的定期審査の過程で勧告を受け、その後も性的指向と性自認に関する人権保障に関して複数回にわたり条約機関からの勧告等を受ける中で、国際社会に対し、性的指向と性自認に基づく差別が許されないことを繰り返し表明している。
以上の経緯のほか、性的指向と性自認に基づく差別の解消に向けた国内外の各種の動向等に照らせば、婚姻に関して性的指向や性自認に基づく権利利益の制約や差別が許されないことは、どんなに遅くとも平成20年の時点では国会にとって当然に認識可能となっていたといえる。
他方で、婚姻が個人の尊重に不可欠な自己決定の一内容であることは、憲法制定当時から明らかであり、当然、国会にとっても認識可能であった。
以上からすれば、同性間の婚姻を認めない本件諸規定が憲法14条1項、24条1項及び2項に違反することは、遅くとも平成20年には国会にとって明白になっていたというべきである。
ウ そして、同性間の婚姻を可能とする立法措置をとることについて立法技術的な困難が伴うものでもないことからすれば、遅くとも原告iがドイツで日本人女性との婚姻を挙行した平成30年9月の時点では、国会が正当な理由なく長期にわたって上記立法措置を懈怠していたと評価するに足りる期間が経過していたというべきであるところ、国会は現在に至るまで同性間の婚姻を可能とする立法措置を講じていない。
エ したがって、本件諸規定が憲法14条1項、24条1項及び2項に違反することが明白であるにもかかわらず、国会が同性間の婚姻を可能とする立法措置を講じない不作為は、国家賠償法1条1項の適用上違法である。
(被告の主張)
立法不作為が国家賠償法1条1項の適用上違法と評価されるのは、法律の規定が憲法上保障され又は保護されている権利利益を合理的な理由なく制約するものとして憲法の規定に違反するものであることが明白であるにもかかわらず、国会が正当な理由なく長期にわたってその改廃等の立法措置を怠る場合等の例外的な場合に限られる。
しかし、本件諸規定は憲法14条1項、24条1項又は2項に違反するものではなく、少なくともその違反が明白であるとは到底いえないのであるから、国会が同性間の婚姻を可能とする立法をしていないことが国家賠償法1条1項の適用上違法と評価される余地はない。
⑶ 損害の有無及び額(争点⑶)
(原告らの主張)
被告の立法不作為により、原告らは憲法上保障される婚姻の自由を侵害され、婚姻に対して与えられる社会的承認に伴う心理的・社会的利益、婚姻に伴う法的及び経済的な権利、利益並びに事実上の利益を受けることができなかった。そればかりでなく、原告らはパートナーとの婚姻をすることができなかったことにより、パートナーとの関係に対してそれがあたかも「社会が承認しない関係性」であるかのようなスティグマを与えられ、その尊厳を深刻に傷つけられた。
そして、原告らが受けた精神的苦痛を金銭に評価すれば、原告らそれぞれについて少なくとも100万円は下らない。
(被告の主張)
否認ないし争う。
⑷ 国家賠償法6条所定の相互保証の存否(原告i関係)(争点⑷)
(原告iの主張)
国家賠償請求権について定めた憲法17条及び国家賠償請求権の直接の根拠となる国家賠償法1条1項及び2条1項は、その文言上、請求の主体について何ら限定を加えておらず、同法6条において初めて請求の主体が外国人である場合に「相互の保証」を要する旨が規定されているにすぎない。このような条文の構造からすると、相互保証については、その不存在が抗弁事実となると解するのが相当である。
しかるに、被告は相互保証の不存在について何ら主張立証をしないから、原告iは相互の保証が存在しないことが認められないものとして被告に対して本件請求を行うことができる。
もっとも、この点をおくとしても、原告iの国籍国であるドイツ連邦共和国では、ドイツ連邦共和国基本法及び民法の定めにより、公務員に故意又は過失がある場合に国又は団体が当該故意又は過失によって第三者に生じた損害を賠償しなければならないとされている上、日本国民に対するドイツ連邦共和国の責任についての告示(1961年9月5日)が、被害者が日本国民である場合、ドイツ連邦共和国の賠償責任について日本の立法により相互の保証があることを明言しているのであるから、ドイツ連邦共和国との間では相互保証が存在している。よって、原告iは、相互保証があるものとして、本件請求をすることができる。
(被告の主張)
国家賠償法6条の趣旨に照らすと、同条は、外国人に対しては「相互の保証」があることを条件として国家賠償請求権を付与したものと解されるから、外国人による国家賠償請求については相互保証の存在が請求原因事実となる。したがって、相互の保証の存在については、原告iにおいて主張立証すべきである。
第3 当裁判所の判断
1 認定事実
前記前提事実並びに後掲証拠及び弁論の全趣旨を総合すると、次の事実を認めることができる。
(1) 性的指向、性的少数者に関する知見等
ア 性的指向の決定に関する知見
性的指向が決定される原因や同性愛となる原因は必ずしも解明されていないが、精神衛生に関わる専門家の間では、ほとんどの場合において、性的指向は人生の初期に決定されるか、出生前に決定され、本人によって選択されるものではないと考えられており、養育環境、家庭環境が特定のものであったことや性的体験が同性愛の原因となったことを示す研究結果等は知られていない。(甲A2、7、345~347)
また、精神医学の専門家の間では、いかなる精神医学的療法によっても性的指向が変わることはないだろうと考えられている。(甲A2)
【筆者】
婚姻制度は「性愛」の思想や信条、感情を保護することを目的とした制度ではないし、個々人が「性愛」の思想や信条、感情を有しているか否かや、その「性愛」の対象がどのようなものであるかを審査して区別取扱いを行うものではないし、「性愛」に基づいて「婚姻」することを勧めるものではない。
そのため、個々人が「性愛」の思想や信条、感情を有しているとしても、有していないとしても、有していると告白する者の「性的指向」がいかなる対象に向かうとしても、その者は法制度において存在する「男女二人一組」の婚姻制度を利用することが可能である。
そのため、「性愛」と法制度における婚姻制度を利用することができるか否かの間には直接的な因果関係は存在しない。
実際に「性愛」の対象が主に同性の者に対して向かうと告白する者であっても、「男女二人一組」の婚姻制度を利用していることが認められるのであり、「性愛」に応じて「婚姻」することに価値があると考えるか否かは、個々人の価値観によるものである。
制度を利用するか否かは、その個々人の抱いている価値観によって、制度を利用することを望むか望まないかの問題ということである。
よって、法律論としては、「性愛」の思想や信条、感情の有無を論じることや、「性愛」を有すると告白する者について「性愛」の思想や信条、感情がどのような対象に向かうかなどは、法制度においては一切関知していない。
そのことから「性愛」の思想や信条、感情がいかなる対象に向かうかという「性的指向」を論じることは、法律論を構成する際に関係性を認めることができないものであり、不必要である。
イ 同性愛に関する知見の変遷
(ア) 欧米諸国においては、中世からキリスト教の影響により同性愛を否定する考え方が存在し、19世紀においても、同性間の性行為を処罰の対象とし、また、同性愛を精神疾患として治療の対象としていた。
我が国でも明治時代に同性愛を変態性欲として治療の対象とする考え方が広まり、法律上、男性同士の性行為が犯罪とされていた時期もあった。
(以上につき、甲A24、26、48、335、337)
(イ) 第二次世界大戦終結後、ヨーロッパ人権条約が発効し、ドイツやオーストリアのソドミー法の同条約適合性が争われるようになった。また、オーストラリアのタスマニア州におけるソドミー法の自由権規約適合性が争われたトゥーネン対オーストラリア事件において、自由権規約委員会は、同規約2条1項と26条について、性的指向の概念が差別禁止分類としての「性」と「その他の地位」に含まれるとの解釈を示し、ソドミー法の廃止こそが効果的な救済手段であるとの見解を下した。
その後、欧米諸国において、同性間の性行為を処罰の対象とする法律は次第に廃止されていった。(甲A24、31)
(ウ) アメリカ精神医学会は、1952年(昭和27年)に発表したDSM(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders)-Ⅰ(精神障害のための診断と統計の手引き第1版)において、同性愛を性的逸脱の一つであるとし、社会病質パーソナリティ障害という大分類に分類した。その後、1968年(昭和43年)のDSM-Ⅱにおいて、同性愛を独立した診断名とし、「パーソナリティ障害及びその他の非精神病性精神障害」との大分類の中の「性的逸脱」との小分類の中に同性愛を分類した。(甲A48、335)
しかし、1973年(昭和48年)、アメリカ精神医学会は、DSMから同性愛を削除することを決定し、同性愛者に対する差別を解消することと同性愛者の権利を保障することを表明した。1980年(昭和55年)に発表されたDSM-Ⅲにおいては、精神障害から同性愛が除外され、より限定的な「自我違和的同性愛ego-dystonic homosexuality」(大要、同性愛者である患者自身が同性に性的興奮を感じる状態を望まず、その状態が苦痛で、変わりたい旨を訴える場合を指す。)へ改められた。さらに、アメリカ精神医学会は、1987年(昭和62年)に発表したDSM-Ⅲ-Rにおいては、上記の「自我違和的同性愛」も除外した。(甲A7、24、27、28、48、335)
また、世界保健機関(WHO)は、ICD(International Classification of Diseases)-9(国際疾病分類第9版)までは、同性愛を疾病としていたが、1992年(平成4年)のICD-10において、同性愛のみでは障害とみなされないとした。(甲A29、30)
我が国においても、かつては同性愛が治療の対象となるとの考え方があったが、日本精神神経学会は、平成7年、市民団体からの求めに応じて、「ICD-10に準拠し、同性への性指向それ自体を精神障害とみなさない」との見解を明らかにした。(甲A48、335、342)
(エ) 現在、精神医学及び心理学の専門家の間では、同性愛それ自体は病気ではないという見方が一般的見解となっている。(甲A48、335、343)
ウ 性的少数者の状況に関する調査
(ア) アメリカ合衆国で2009年(平成21年)に行われた疫学調査では、自分を同性愛者とみなしている人の割合は、男性では6.8%、女性では4.5%であった。その他にアメリカ合衆国、カナダ等で行われた複数の調査によれば、自分をレズビアン又はゲイだと認識している成人の割合は0.7~2.5%であった。(甲A8、335)
【筆者】
調査によっては、アメリカの若者の30%以上が「自分はLGBTQ」であると認識している場合もある。
【参考】アメリカの若者の30%以上が「自分はLGBTQ」と認識していることが判明 2021年10月26日
しかし、これも客観的に判断できるものではなく、自己の思想、信条、信仰、感情を述べるに過ぎないものであるから、「内心の自由」として捉えられるべき問題であり、法律論として扱うことはできない。
(イ) 名古屋市が平成30年に行った調査によれば、1.6%の人が自分が性的少数者であると回答している。(甲A9)
(ウ) NHKが平成27年に性的少数者に対して行った調査によれば、「地方公共団体によるパートナーシップ証明制度を申請したい」と回答した人は82.4%(パートナーができたら申請したいと回答した人も含む。)、「同性間の結婚を認める法律を作ってほしい」と回答した人は65.4%、「結婚ではなくパートナー関係の登録制度を国が作ってほしい」と回答した人は25.3%、「現状のままで良い」と回答した人は2.9%であった。(甲A103)
(エ) ライフネット生命保険株式会社及び日高庸晴宝塚大学教授が令和元年に1万人以上の性的少数者を対象に行った調査によれば、「同性婚やパートナーシップのような同性間の関係を公的に認める制度について、どう思いますか」との調査項目について、「異性婚と同じ法律婚(同性婚)を同性間にも適用してほしい」との回答が60.4%、「公的制度を作る必要はないが、社会の理解は今より浸透してほしい」との回答が16.2%、それ以外の者のほとんどは「国レベルのパートナーシップを制定してほしい」又は「自治体レベルのパートナーシップを制定してほしい」と回答した。(甲A320、321)
【筆者】
本人が「性的少数者」であるかどうかを第三者が外部から客観的に判断できるものはないのであり、このような「調査」と称するものも、すべて本人が「性的少数者」であると「自称」しているだけのものを根拠としたものである。
法律論を組み立てる際に、このような内容を取り上げて論じることはできないことに注意が必要である。
(2) 婚姻制度
ア 近代的婚姻制度
歴史上、人間は男女の性的結合関係によって、子孫を残し、種の保存を図ってきたところ、この古くから続く関係を規範によって統制しようとするところに婚姻制度(法律婚制度)が生まれた。それぞれの時代、社会によって、どのような人的結合関係を婚姻として承認するかは異なるが、婚姻とは、いかなる社会においても、単なる当事者間の性愛に基づく結合ではなく、社会制度として、社会に承認された人的結合として存在するものと考えられ、ほとんどの社会において、婚姻の成立に一定の要件を定めている。そして、伝統的に、婚姻とは、単純な男女の性関係ではなく、男女の生活共同体として子の監護養育や分業的共同生活等の維持によって家族の中核を形成するものと捉えられてきた。
【筆者】
「歴史上、人間は男女の性的結合関係によって、子孫を残し、種の保存を図ってきたところ、この古くから続く関係を規範によって統制しようとするところに婚姻制度(法律婚制度)が生まれた。」との部分であるが、その通りである。
ただ、その「規範によって統制しようとするところに婚姻制度(法律婚制度)が生まれた。」とする背景には、「生殖」に関わって社会的な不都合が生じていることが原因である。
もし何らの不都合も存在しないのであれば、そもそも「規範によって統制しようとする」ことも必要ないはずだからである。
そのため、婚姻制度が「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として形成されていることは明らかである。
「婚姻とは、いかなる社会においても、単なる当事者間の性愛に基づく結合ではなく、」との記載があるが、大変重要なことを述べている。
「婚姻」は、「性愛結社」とは異なることを明らかにしている点で、その通りということができる。
「性愛結社」は、憲法21条1項の「結社の自由」のような「自由権」によって形成することが可能であり、これは「婚姻」である必要もないことも押さえる必要がある。
ヨーロッパにおいては、中世において教会による統制の下で宗教婚が行われていたが、フランス革命後の近代的市民社会への移行に伴い、男女の意思の合致に基づく婚姻に一定の要件の下で国家が承認を与える近代的婚姻制度が確立されていった。近代的婚姻制度は、前近代社会の家父長的な家族共同体の支配関係からの離脱、平等で独立した主体者間の権利義務関係として捉えられた。
(以上につき、甲A211の25・27~29、乙22)
【筆者】
ここでは「宗教婚」と「国家が承認を与える近代的婚姻制度」の違いを述べているが、重要な点である。
「国家」の制度としての「婚姻」は、思想、信条、信仰、感情に対して中立的な内容でなければならないのであり、特定の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的として制度を立法してはならない。
イ 明治期の民法
(ア) 我が国においては、明治初年にあっては、婚姻の実質的要件は慣習に委ねられ、統一的な実体法は存在しなかった。明治23年法律第98号(旧民法)において初めて実体的要件が定められ、これは施行には至らなかったものの、明治31年法律第9号の民法(以下、昭和22年民法改正による改正前の民法を「明治民法」という。)に受け継がれた。(甲A211の25・28)
(イ) 明治民法において、婚姻は、国家に対する届出によって成立する法律婚とされた。従来の家制度に基づき、家長である戸主に家を統率するための戸主権を与え、婚姻は家のためのものであるとして戸主や親の同意が要件とされ、夫婦は必ず家を共にすることを要するから、当事者の一方(通常は妻)が婚姻により他方の家(通常は夫の家)に入ることを要するものとされた。妾制度は廃止されたが、夫の妻に対する優位が認められており、夫は妻の財産を管理し、その収益権を持つものとされた。
当時の外国法には同性間の婚姻を明示的に禁止するものがあったが、明治民法においては、婚姻とは男女間の関係を定めるものであるから同性間で婚姻することはできないことは明らかであるとして、これを禁止する明文の規定は置かれなかった。学説上も、婚姻の当事者の一方は男性、他方は女性であることを要し、同性間において終生的共同生活を約しても婚姻関係は生じないとされていた。
(以上につき、甲A211の18・26・28・38)
また、明治民法の条文上、生殖能力を有することは婚姻の要件とはされていない。学説上も、婚姻は夫婦の共同生活を目的とし、必ずしも子を得ることを目的とするものではないとされ、生殖能力は一般に具備すべき条件ではあるが、これを欠くことは婚姻の障害にはならず、離婚又は婚姻の無効・取消の原因とはならないと解されていた。(甲A210、211の18・33~35・38・41)
ウ 憲法(日本国憲法)の制定
(ア) 連合軍総司令部(GHQ)の下で、大日本帝国憲法改正作業が憲法問題調査委員会において進められた。
人権条項の起草を担当したGHQ民生局の女性職員ベアテ・シロタ・ゴードンは、かつて日本で生活していた際に感じた女性の地位の低さ等の問題意識に基づき、現行の憲法24条に相当する条文として、「…婚姻と家族とは、両性が法律的にも社会的にも平等であることは当然であるとの考えに基礎をおき、親の強制ではなく相互の合意に基づき、かつ男性の支配ではなく両性の協力に基づくべきことを、ここに定める。…配偶者の選択、財産権、相続、本拠の選択、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項を、個人の尊厳と両性の本質的平等の見地に立って定める法律が制定されるべきである。」とのシロタ草案18条を作成した。
上記シロタ草案に基づき1946年(昭和21年)2月にGHQ草案23条が作成され、これに基づいて日本政府が起草した「3月2日案」37条、GHQとの交渉を経て作成された「3月5日案」22条、口語化憲法改正草案22条、同年6月20日に帝国議会に提出された帝国憲法改正案22条が作成され、帝国議会での審議を経て現行の憲法24条となった。GHQ草案23条には「婚姻ハ男女両性ノ法律上及社会上ノ争フ可カラサル平等ノ上ニ存シ」との、「3月2日案」37条及び「3月5日案」22条には「婚姻ハ男女相互ノ合意ニ基キテノミ成立シ」との文言があったが、最終的には、「男女相互」が「両性」に変更された。また、日本政府は家族関係についての条項を憲法に規定することに消極的な姿勢を示し、「3月2日案」37条は現行の憲法24条1項に当たる部分のみの案となったが、「3月5日案」22条は、現行の憲法24条2項に当たる条項が加わった。
このような経緯を経て、日本国憲法に大日本帝国憲法には存在しなかった家族に関する規定が設けられた。
(以上につき、甲A156~161、211の22・23・29、241、427)
(イ) 第90回帝国議会で憲法改正案が審議され、その際には、従来の家制度が維持されるか否かが主たる論点となったが、特に貴族院における審議を経て、従来の家制度は否定されるべきことが明確になっていった。なお、現行の憲法24条1項の「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し」の「のみ」の意味について、当時の司法大臣から、明治民法において婚姻に戸主や親権者の同意を要するものとされていた制限を排除し、両性の合意だけで成立させようという趣意である旨の答弁がされた。
また、この審議において、同性間の婚姻について議論が行われた形跡は見当たらず、「婚姻はどうしてもこの男女が相寄り相助ける所に基礎があるのであります。」といった答弁がされるなど、婚姻は男女間のものであることを前提として議論が行われた。
(以上につき、甲A156、157、159~161、241、乙18)
(ウ) 憲法24条に基づき、「日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律」(昭和22年法律第74号)が制定され、明治民法の家制度に関する規定の適用が停止され、その後、民法第4編及び第5編が全面的に改正され(昭和22年民法改正。同改正後の民法を「現行民法」ということがある。)、昭和23年1月1日に施行された。(甲A19、211の28、546)
エ 昭和22年民法改正
(ア) 昭和22年民法改正により、父母の婚姻同意権は未成年者に限られることとなり、戸主の婚姻同意権及び戸主又は法定推定家督相続人の他家へ入る婚姻の禁止に関する規定は廃止されるなど、家制度による制約が除去されたほか、財産は各自で管理収益するものとされるなど夫婦間の不平等が改められた。(甲A16、19、211の21・28)
国会審議においては、明治民法の特に親族編、相続編には、憲法13条、14条、24条の定める基本原則に抵触する規定があることから、これを改正することが提案理由とされ、上記の抵触する規定が削除された一方、抵触しない規定についてはこれを維持することとされた。その中で、同性間の婚姻について議論が行われた形跡は見当たらない。(甲A16、211の21)
(イ) 昭和22年民法改正の後、現行民法が定める婚姻について、婚姻をなすとは、その時代の社会通念に従って婚姻とみられるような関係を形成することであり、同性間の「婚姻」は、婚姻ではないとの学者の見解が示されている。(甲A211の27・28)
【筆者】
ここで出てくる「学者の見解」である「社会通念」は後ほど憲法24条の「婚姻」の意味を解釈する際に出てくることになる。
ただ、この「社会通念」は何らの根拠もなく形成されているわけではないのであって、その「社会通念」が形成されている背景には、「婚姻」という概念そのものが有している「目的」と「その目的を達成するための手段」となる枠組みがあることを捉えることが必要である。
(3) 諸外国における同性間の人的結合関係に関する立法等の状況
ア 同性間の人的結合関係に関する婚姻制度以外の制度
(ア) 1989年(平成元年)、デンマークにおいて、法律上、同性の二者間の関係を公証し、一定の地位や法的効果を付与する制度である登録パートナーシップ制度が導入された。同様の制度(各国によって呼称や具体的な制度内容は異なるが、以下では総称して「登録パートナーシップ制度」といい、後述の(イ)の制度と併せて「登録パートナーシップ制度等」という。)は、ヨーロッパ諸国を中心に広がり、ノルウェー(1993年(平成5年))、オランダ(1998年(平成10年))、ドイツ(2001年(平成13年))、フィンランド(同年)、ルクセンブルク(2004年(平成16年))、ニュージーランド(同年)、英国(2004~2005年(平成16~17年))、オーストリア(2009年(平成21年))、アイルランド(2011年(平成23年))等において導入された。これらのうち、多くの国の登録パートナーシップ制度は、同性間の人的結合関係のみを対象としているが、異性間の人的結合関係をも対象とするものもある(オランダ、ポルトガル等)。
(甲A98、169、205、211の7・29、甲G8)
(イ) また、登録パートナーシップ制度ほどには強力な法的効果を望まないカップルに関して、一定の同棲関係に対して主に財産法上の法的効果を与える法定同棲と呼ばれる制度を設けている国(ベルギー、スウェーデン)や、当事者の契約によって権利及び義務を設定し公的機関に登録することで第三者や国に対してカップルであることを対抗することができるようになる市民連帯協約(PACS)の制度を設けている国(フランス)もあり、これらの制度は異性カップルであるか同性カップルであるかを問わず、利用することができる。(甲A98、169、205、211の7・29)
(ウ) イタリアにおいては、憲法裁判所が2010年(平成22年)に婚姻は異性間の結合を指す旨判断し、2014年(平成26年)にもその判断を維持したものの、同性の当事者間の権利及び義務を適切に定めた婚姻とは別の形式が同国の法制度上存在しないことは憲法に違反する旨判示した。これを受けて、2016年(平成28年)に「同性間の民事的結合に関する規則及び共同生活の規律」が成立した。この民事的結合は、同性の両当事者が証人とともに身分取扱担当官の面前で宣言することによって形成され、民事的結合によって生ずる権利及び義務については、養子縁組に関する規定等を除き、基本的に婚姻に関する規定が準用されるものとされている。(甲A98)
イ 同性間の婚姻制度
(ア) 2001年(平成13年)にオランダが同性間の婚姻制度を導入し、世界で初めて同性間の婚姻を法律上認めた国となった。その後、ベルギー(2003年(平成15年))、スペイン(2005年(平成17年))、カナダ(同年)、南アフリカ(2006年(平成18年))、ノルウェー(2009年(平成21年))、スウェーデン(同年)、ポルトガル(2010年(平成22年))、アイスランド(同年)、アルゼンチン(同年)、デンマーク(2012年(平成24年))、ブラジル(2013年(平成25年))、フランス(同年)、ウルグアイ(同年)、ニュージーランド(同年)、英国(北アイルランドを除く)(2014年(平成26年))、ルクセンブルク(2015年(平成27年))、アイルランド(同年)、コロンビア(2016年(平成28年))、フィンランド(2017年(平成29年))、マルタ(同年)、ドイツ(同年)、オーストラリア(同年)、オーストリア(2019年(平成31年、令和元年))、台湾(同年)、エクアドル(同年)、コスタリカ(2020年(令和2年))、英国(北アイルランド)(同年)、チリ(2022年(令和4年))、スイス(同年)において同性間の婚姻制度が導入された(いずれも施行年である。)。
これらの国・地域の多くでは、登録パートナーシップ制度等を導入した後に同性間の婚姻制度が導入されているが、登録パートナーシップ制度等の導入により、社会的な承認が進んだことが同性間の婚姻制度導入を可能にしたとの指摘もされている。そして、同性間の婚姻制度の導入に際して従前の登録パートナーシップ制度等を廃止する国もあるが、維持する国も存在し、後者においては、登録パートナーシップ制度等の内容は、改正を重ね、財産的な結合のみならず人格的義務を伴うものとなるなど、婚姻制度に近似しつつある例がある。
(以上につき、甲A98、145~148、169、205、210、211の7・29、319、417、533、534、甲G8)
(イ) また、以下のとおり、同性間の婚姻を認める法律の規定を合憲とする司法判断、同性間の婚姻を認めない法令を違憲とする司法判断等がされた。
① スペイン憲法裁判所は、2012年(平成24年)11月6日、同性間の婚姻を認める民法の規定は憲法に違反しない旨判示した。(甲A169)
② アメリカ合衆国連邦最高裁判所は、2015年(平成27年)6月26日、いわゆるObergefell事件において、婚姻の要件を異性カップルに限り、同性間の婚姻を認めないオハイオ州、ミシガン州、ケンタッキー州及びテネシー州の各州法の規定は、アメリカ合衆国憲法のデュー・プロセス条項及び平等保護条項に違反する旨判示した。(甲A98、99、164)
③ 台湾の憲法裁判所に当たる司法院は、2017年(平成29年)5月24日、同性間の婚姻を認めていない民法の規定は中華民国憲法に違反する旨判示した。(甲A98、101)
④ オーストリア憲法裁判所は、2017年(平成29年)12月4日、前記アのとおり既に導入され、改正もされていた登録パートナーシップ制度について、婚姻と法的構造が同じであっても、異性間関係と同性間関係とを二つの法制度によって区別することは、性的指向等の個人の属性を理由とする差別を禁止する平等原則に違反する旨判示した。(甲A98)
(ウ) 同性間の婚姻を認める国においても、異性間の婚姻と同性間の婚姻の内容に相違がある場合(又は、導入当初は相違があった場合)があり、その主なものとして嫡出推定規定の適用の有無、養子縁組の可否、生殖補助医療利用の可否等が挙げられる。(甲A169、211の29)
(エ) 韓国においては、2016年(平成28年)、地方裁判所に相当する地方法院において、同性間の婚姻を認めるか否かは立法的判断によって解決されるべきであり、司法により解決できる問題ではないとの判断が示された。(甲A98)
【筆者】
この部分では、「同性間」の人的結合関係をその国の法制度によって位置付けているものが取り上げられている。
(それぞれの国は、それぞれの国の社会事情に応じて、そこで生じる問題を解決することを目的として法制度を定めているだけであるから、ここで日本法のいう『婚姻』という概念と完全な対応関係にあるわけではない。そのため、『婚姻』という言葉を使って同一の概念であるかのように扱うことには抵抗がある。)
しかし、外国では、「一夫多妻型」の制度を立法している場合もあるのであり、「同性間」の人的結合関係のみを取り上げて論じようとすることは、特定の結論を導き出すために恣意的に視野を狭めようとするものとなるため妥当ではない。
【参考】「一夫多妻制が認められているところが世界にはあるって言ったらどうなる」 Twitter
【参考】一夫多妻制 Wikipedia
(4) 我が国における性的少数者をめぐる状況
ア 地方公共団体における取組の状況
(ア) 平成27年10月に東京都渋谷区が、同年11月に東京都世田谷区が地方公共団体レベルでのパートナーシップ証明制度を導入したのをはじめとして、パートナーシップ証明制度を導入する地方公共団体が増加しており、これらの制度を利用した同性カップルも多く存在する。また、一部の地方公共団体が協定を締結して当該地方公共団体間での相互利用を可能とする例や同性パートナーの子を含めたファミリーシップ証明も可能とする例もある。渋谷区等の調査によれば、令和4年4月1日時点でパートナーシップ証明制度を導入した地方公共団体は209に及び、人口カバー率は52.1%となっている。(甲A75~91、119~134、266~302、352~391、445~519)
上記渋谷区の制度は、渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例に基づき、区長がパートナーシップ証明を行うものであり、同区が平成29年にパートナーシップ証明を取得した者に対して行った調査では、証明書は社会からの承認であると捉えているとの意見がみられた。(甲A75、434)
(イ) また、上記のほかにも、地方公共団体において、犯罪被害者の遺族等に対する助成金につきパートナーシップ証明を受けている同性パートナーを受給者に含める、同性カップルの職員に結婚休暇や出産支援休暇の利用を認めるなどの取組みがされている。(甲A307~309、392、393)
【筆者】
「地方公共団体」の「パートナーシップ証明制度」の内容が民法上の婚姻制度や憲法上の規定に抵触している場合には、その制度は違法となる。
詳しくは、当サイト「パートナーシップ制度」で解説している。
イ 民間企業等における取組の状況
一般社団法人日本経済団体連合会は、平成29年5月16日、「ダイバーシティ・インクルージョン社会の実現に向けて」と題する提言を発表し、性的少数者の理解促進、差別解消を呼びかけた。(甲A94)
多数の民間企業において、性的少数者の抱える困難を解消するなどの目的の下で、同性パートナーについて慶弔休暇を適用する例や家族手当の対象とする例、同性のパートナーの子を社内制度上「子」として扱うファミリーシップ申請制度を導入した例等、企業における福利厚生について同性カップル及びその子に関して拡大を図る取組がされている。(甲A314、315、318、399)
また、一部の金融機関において、住宅ローンの連帯債務者を従来は夫婦に限っていたものについて、同性パートナーにも拡大するなどの取組もされている。(甲A312、313)
【筆者】
民間企業の契約の内容については、憲法上の「公共の福祉」や民法上の「公序良俗」や「強行規定」に違反しないかを個別に検討しなければ、そのような扱いが適法となるかは判断することができない。
「愛人契約」が違法であることはよく知られていることであり、民間企業が「愛人契約」を制度化している場合には、その契約は違法となる。
そのため、これらの契約の内容を個別に検討することもなく、適法な制度であることを前提として取り上げているのであれば妥当ではない。
ウ 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成15年法律第111号)が平成16年7月16日に施行された。同法3条1項は、性同一性障害者につき性別の取扱いの変更の審判が認められるための要件として、「現に婚姻をしていないこと」(2号)を定めているところ、最高裁判所は、同規定について、現に婚姻をしている者について性別の取扱いの変更を認めた場合、異性間においてのみ婚姻が認められている現在の婚姻秩序に混乱を生じさせかねない等の配慮に基づくものとして、合理性を欠くものとはいえないから、国会の裁量権の範囲を逸脱するものということはできず、憲法13条、14条1項、24条に違反するものとはいえないとの判断をした(最高裁令和元年(ク)第791号同2年3月11日第二小法廷決定)。
【筆者】
この段落と関連する内容について、当サイト「性別と思想」で解説している。
(5) 同性間の婚姻、同性カップルの法的保障に関する世論調査等
ア 日本世論調査会が平成26年に行った調査によれば、同性婚を法的に認めることについて、賛成(どちらかといえば賛成を含む。)が42.3%(男性では35.4%、女性では48.7%)、反対(どちらかといえば反対を含む。)が52.4%であった。(甲A104)
イ 河口和也広島修道大学教授を研究代表者とするグループが平成27年に全国の20~79歳の男女に対して行った調査によれば、同性同士の結婚を法で認めることについて賛成(やや賛成を含む。)が51.2%(男性では44.8%、女性では56.7%)、反対(やや反対を含む。)が41.3%(男性では50.0%、女性では33.8%)であった。(甲A104)
ウ 毎日新聞社が平成27年に行った全国調査(回答者数1018人)によれば、同性婚について、賛成が44%(男性では38%、女性では50%)、反対が39%(男性では49%、女性では30%)であった。(甲A104、105)
エ NHKが平成29年に全国18歳以上の国民に行った調査(調査有効数2643人)によれば、男性同士、女性同士が結婚することを認めるべきだとの調査項目について、そう思うとの意見は50.9%、そうは思わないとの意見は40.7%であった。(甲A106、107)
オ 朝日新聞社が平成29年に行った全国世論調査によれば、同性婚を法律で認めるべきかとの調査項目に対し、「認めるべきだ」との回答は49%(男性では44%、女性では54%)、「認めるべきではない」との回答は39%であった。また、18~29歳、30代では「認めるべきだ」との回答が7割を超えるのに対し、60代では「認めるべきだ」と「認めるべきではない」が拮抗し、70歳以上では「認めるべきではない」が63%となった。(甲A108、109)
カ 株式会社電通が平成30年に20~59歳の6万人を対象に行った調査によれば、性的少数者の当事者は8.9%であった。6万人から抽出した6229人のうち、同性婚の合法化に「賛成」又は「どちらかというと賛成」と回答した者は78.4%であり、性的少数者ではない5640人でみると女性は87.9%、男性は69.2%が「賛成」又は「どちらかというと賛成」であった。(甲A110、211の57)
キ 国立社会保障・人口問題研究所が平成30年に行った第6回全国家庭動向調査によれば、既婚女性6142人のうち、①男性同士や女性同士の結婚(同性婚)を法律で認めるべきだとの調査項目について、「まったく賛成」又は「どちらかといえば賛成」と回答した者は69.5%、「まったく反対」又は「どちらかといえば反対」と回答した者は30.5%、②男性同士や女性同士のカップルにも何らかの法的保障が認められるべきだとの調査項目について、「まったく賛成」又は「どちらかといえば賛成」と回答した者は75.1%、「まったく反対」又は「どちらかといえば反対」と回答した者は25.0%、③同性同士のカップルも男女のカップルと同じように子供を育てる能力があるとの調査項目について、「まったく賛成」又は「どちらかといえば賛成」と回答した者は69.4%、「まったく反対」又は「どちらかといえば反対」と回答した者は30.6%であった。(甲A149、165、166、226)
ク 朝日新聞社と東京大学谷口将紀研究室が令和2年3~4月に全国の有権者2053人から回答を得て行った調査によれば、同性婚について、「賛成」又は「どちらかと言えば賛成」と回答した者は46%、「どちらとも言えない」と回答した者は31%、「反対」又は「どちらかと言えば反対」と回答した者は23%であった。平成17年に有権者を対象として行った調査と比較すると、同性婚については賛成意見が14%増加した。また、自由民主党支持層でも賛成意見が増加し、反対意見を上回った。(甲A224)
(6) 婚姻についての意識調査
ア 内閣府の平成17年版国民生活白書によれば、結婚の良い点・メリットは何かとの調査項目につき、「家族や子どもを持てる」が既婚者で63.5%、未婚者で58.2%、「精神的な安定が得られる」が既婚者で61.9%、未婚者で54.3%、「好きな人と一緒にいられる」が既婚者で58.0%、未婚者で57.7%であった。
また、家庭はどのような意味を持つと感じているかとの調査項目につき、「家族の団らんの場」が有配偶者で63.8%、未婚者で54.9%、「休息・やすらぎの場」が有配偶者で57.3%、未婚者で55.4%、「家族の絆を強める場」が有配偶者で50.6%、未婚者で37.6%、「子どもを生み、育てる場」が有配偶者で27.0%、未婚者で19.5%であった。
(以上につき、甲A211の54)
イ(ア) 内閣府が平成22年から平成23年にかけて実施した結婚・家族形成に関する調査によれば、既婚者が結婚した理由は、「好きな人と一緒にいたかった」が61.0%、「家族を持ちたかった」が44.2%、「子どもが欲しかった」が32.5%であった。
また、未婚者(将来結婚したい人)が結婚したい理由は、「好きな人と一緒にいたい」が61.0%、「家族を持ちたい」が59.2%、「子どもが欲しい」が57.1%であった。
(以上につき、甲A211の55の1)
(イ) 内閣府が平成26年から平成27年にかけて実施した結婚・家族形成に関する意識調査によれば、未婚者(将来結婚したい人)が結婚したい理由は、「家族を持ちたい」と「子どもが欲しい」が共に70.0%、「好きな人と一緒にいたい」が68.9%であった。(甲A211の55の2)
ウ 国立社会保障・人口問題研究所が平成27年に実施した第15回出生動向基本調査における対象となる18~34歳の未婚者による回答結果は、以下のとおりであった。(甲A211の52、544)
(ア) 「生涯を独身で過ごすというのは、望ましい生き方ではない」との調査項目について賛成した者は、男性で64.7%、女性で58.2%であった。
(イ) 「いずれ結婚するつもり」と回答した者は、男性が85.7%、女性が89.3%であり、おおむね微減傾向にあるものの、高い水準にあった。
(ウ) 「結婚に利点がある」と回答した者は、男性が64.3%、女性が77.8%であり、具体的な利点としては、「自分の子どもや家族をもてる」と回答した者が男性で35.8%、女性で49.8%と最も多く、続いて「精神的安らぎの場が得られる」と回答した者が男性で31.1%、女性で28.1%であった。
(エ) 子供を持つ理由について、「子どもがいると生活が楽しく豊かになるから」と回答した者が男性で66.5%、女性で73.3%であり、「結婚して子どもを持つことは自然なことだから」と回答した者は男性で48.4%、女性で39.0%であった。
エ NHKが平成30年に全国の16歳以上の5400人を対象に行った調査(回答率50.9%)によれば、「必ずしも結婚する必要はない」と回答した者は68%であり、過去の調査結果に比べ増加し、他方で「人は結婚するのが当たり前だ」と回答した者は27%であり、過去の調査結果に比べ減少した。また、「結婚しても、必ずしも子どもをもたなくてよい」と回答した者は60%であり、過去の調査結果に比べ増加し、「結婚したら、子どもをもつのが当たり前だ」と回答した者は33%であり、過去の調査結果に比べ減少した。(甲A211の50)
オ 国立社会保障・人口問題研究所が平成30年に行った第6回全国家庭動向調査によれば、既婚女性6142人のうち、「夫婦は子どもを持ってはじめて社会的に認められる」との調査項目について、「まったく賛成」又は「どちらかといえば賛成」と回答した者は24.7%であり、「まったく反対」又は「どちらかといえば反対」と回答した者は75.4%であった。賛成割合は同研究所が平成20年に行った調査における35.8%、平成25年に行った調査における32.1%から減少した。(甲A211の51)
2 争点⑴(同性間の婚姻を認めていない本件諸規定の憲法適合性)について
⑴ 憲法24条1項適合性について
ア 原告らは、憲法24条1項は、国家以前の個人の尊厳に直接由来する自由として婚姻の自由を保障していると解すべきであり、その婚姻の自由は同性間の婚姻についても及ぶものとした上で、本件諸規定は、憲法が婚姻制度について要請し想定した核心部分を正当化根拠なく制約するものであり、憲法24条1項に違反する旨主張する。
イ 憲法24条1項は、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」と規定するところ、これは、婚姻をするかどうか、いつ誰と婚姻をするかについては、当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたものであると解される。婚姻は、これにより、配偶者の相続権(民法890条)や夫婦間の子が嫡出子となること(同法772条1項等)などの重要な法律上の効果が与えられるものとされているほか、近年家族等に関する国民の意識の多様化が指摘されつつも、国民の中にはなお法律婚を尊重する意識が幅広く浸透していると考えられることをも併せ考慮すると、上記のような婚姻をするについての自由は、憲法24条1項の規定の趣旨に照らし、十分尊重に値するものと解することができる。
また、憲法24条2項は、「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。」と規定する。婚姻及び家族に関する事項は、国の伝統や国民感情を含めた社会状況における夫婦や親子関係についての全体の規律を見据えた総合的な判断を行うことによって定められるべきものであるから、その内容の詳細については、憲法が一義的に定めるのではなく、法律によってこれを具体化することがふさわしいものと考えられる。憲法24条2項は、このような観点から、婚姻及び家族に関する事項について、具体的な制度の構築を第一次的に国会の合理的な立法裁量に委ねるとともに、その立法に当たっては、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきであるとする要請、指針を示すことによって、その裁量の限界を画したものということができる(以上につき、最高裁平成25年(オ)第1079号同27年12月16日大法廷判決・民集69巻8号2427頁〔以下「平成27年再婚禁止期間大法廷判決」という。〕、最高裁平成26年(オ)第1023号同27年12月16日大法廷判決・民集69巻8号2586号〔以下「平成27年夫婦同氏制大法廷判決」という。〕参照)。
【筆者】
上記の内容は、「平成27年再婚禁止期間大法廷判決」と「平成27年夫婦同氏制大法廷判決」の二つの判決文の内容を、この東京地裁判決が独自にまとめたものとなっている。
下記で、具体的にどのような形で引用しているのかを確認する。
・ 灰色で潰した部分は、最高裁の二つの「大法廷判決」とこの東京地裁判決とを合わせて三つの判決の間で共通する部分である。
・ 黄緑色で潰したの部分は、「平成27年再婚禁止期間大法廷判決」とこの東京地裁判決の間で共通する部分である。
・ 黄色で潰した部分は、最高裁の二つの「大法廷判決」の間でのみ共通する部分である。
・ 潰していない残った部分が、それぞれの「大法廷判決」とこの東京地裁判決の上記の部分とは共通していないところである。
・ 太字の部分は、対応関係を見つけやすくするために、共通していても例外的に潰していない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ところで,婚姻及び家族に関する事項は,国の伝統や国民感情を含めた社会状況における種々の要因を踏まえつつ,それぞれの時代における夫婦や親子関係についての全体の規律を見据えた総合的な判断を行うことによって定められるべきものである。したがって,その内容の詳細については,憲法が一義的に定めるのではなく,法律によってこれを具体化することがふさわしいものと考えられる。憲法24条2項は,このような観点から,婚姻及び家族に関する事項について,具体的な制度の構築を第一次的には国会の合理的な立法裁量に委ねるとともに,その立法に当たっては,個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきであるとする要請,指針を示すことによって,その裁量の限界を画したものといえる。また,同条1項は,「婚姻は,両性の合意のみに基いて成立し,夫婦が同等の権利を有することを基本として,相互の協力により,維持されなければならない。」と規定しており,婚姻をするかどうか,いつ誰と婚姻をするかについては,当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたものと解される。婚姻は,これにより,配偶者の相続権(民法890条)や夫婦間の子が嫡出子となること(同法772条1項等)などの重要な法律上の効果が与えられるものとされているほか,近年家族等に関する国民の意識の多様化が指摘されつつも,国民の中にはなお法律婚を尊重する意識が幅広く浸透していると考えられることをも併せ考慮すると,上記のような婚姻をするについての自由は,憲法24条1項の規定の趣旨に照らし,十分尊重に値するものと解することができる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「平成27年再婚禁止期間大法廷判決」 (PDF)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2(1) 憲法24条は,1項において「婚姻は,両性の合意のみに基いて成立し,夫婦が同等の権利を有することを基本として,相互の協力により,維持されなければならない。」と規定しているところ,これは,婚姻をするかどうか,いつ誰と婚姻をするかについては,当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたものと解される。
(略)
(2) 憲法24条は,2項において「配偶者の選択,財産権,相続,住居の選定,離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては,法律は,個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して,制定されなければならない。」と規定している。
婚姻及び家族に関する事項は,関連する法制度においてその具体的内容が定められていくものであることから,当該法制度の制度設計が重要な意味を持つものであるところ,憲法24条2項は,具体的な制度の構築を第一次的には国会の合理的な立法裁量に委ねるとともに,その立法に当たっては,同条1項も前提としつつ,個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきであるとする要請,指針を示すことによって,その裁量の限界を画したものといえる。
そして,憲法24条が,本質的に様々な要素を検討して行われるべき立法作用に対してあえて立法上の要請,指針を明示していることからすると,その要請,指針は,単に,憲法上の権利として保障される人格権を不当に侵害するものでなく,かつ,両性の形式的な平等が保たれた内容の法律が制定されればそれで足りるというものではないのであって,憲法上直接保障された権利とまではいえない人格的利益をも尊重すべきこと,両性の実質的な平等が保たれるように図ること,婚姻制度の内容により婚姻をすることが事実上不当に制約されることのないように図ること等についても十分に配慮した法律の制定を求めるものであり,この点でも立法裁量に限定的な指針を与えるものといえる。
3(1) 他方で,婚姻及び家族に関する事項は,国の伝統や国民感情を含めた社会状況における種々の要因を踏まえつつ,それぞれの時代における夫婦や親子関係についての全体の規律を見据えた総合的な判断によって定められるべきものである。特に,憲法上直接保障された権利とまではいえない人格的利益や実質的平等は,その内容として多様なものが考えられ,それらの実現の在り方は,その時々における社会的条件,国民生活の状況,家族の在り方等との関係において決められるべきものである。
(2) そうすると,憲法上の権利として保障される人格権を不当に侵害して憲法13条に違反する立法措置や不合理な差別を定めて憲法14条1項に違反する立法措置を講じてはならないことは当然であるとはいえ,憲法24条の要請,指針に応えて具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定が上記(1)のとおり国会の多方面にわたる検討と判断に委ねられているものであることからすれば,婚姻及び家族に関する法制度を定めた法律の規定が憲法13条,14条1項に違反しない場合に,更に憲法24条にも適合するものとして是認されるか否かは,当該法制度の趣旨や同制度を採用することにより生ずる影響につき検討し,当該規定が個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理性を欠き,国会の立法裁量の範囲を超えるものとみざるを得ないような場合に当たるか否かという観点から判断すべきものとするのが相当である。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「平成27年夫婦同氏制大法廷判決」 (PDF)
この東京地裁判決は、「平成27年再婚禁止期間大法廷判決」の内容が「24条2項 → 24条1項」の順番で説明されていることを入れ替え、「24条1項 → 24条2項」の順番で説明することを試みるものとなっている。
そしてその試みは、「平成27年夫婦同氏制大法廷判決」でも「24条1項 → 24条2項」の順番で説明し、同様の文を用いている部分が見られることから、問題ないと考えているように思われる。
しかし、この東京地裁判決が「憲法24条1項」についての説明において、「婚姻は、これにより、配偶者の相続権(民法890条)や夫婦間の子が嫡出子となること(同法772条1項等)などの重要な法律上の効果が与えられるものとされているほか、」と述べている部分は、本来は「平成27年再婚禁止期間大法廷判決」の中で「婚姻及び家族に関する事項」は「夫婦や親子関係についての全体の規律を見据えた総合的な判断」を行って「法律によってこれを具体化することがふさわしい」との説明をし、24条2項の要請に立脚した法律上の婚姻制度の存在を前提とした上で、「憲法24条1項」に従ってその婚姻制度を利用した場合として述べられている文である。
しかし、このように24条2項の要請に立脚した法律上の婚姻制度の存在を説明することなく、単に「憲法24条1項」の規定の解説をしている文脈の中で、突然「配偶者の相続権(民法890条)や夫婦間の子が嫡出子となること(同法772条1項等)」などの「法律上の効果が与えられる」と述べることは、不自然である。
このような説明の仕方は、「婚姻は、これにより、」との接続の言葉と相まって、具体的な法律上の婚姻制度の存在を前提とせずとも、「憲法24条1項」の文言そのものから「配偶者の相続権(民法890条)や夫婦間の子が嫡出子となること(同法772条1項等)など」などの具体的な法的効果を導き出すことが可能であるかのような誤解を生じさせることとなる。
このような形でもともとの判決文を切り貼りすることは、法律の専門家や、この家族法の法分野に精通した者であれば、その意図を誤解することなく読み取ることが可能な場合もあるが、法律の初学者や法律の深い知識を持ち合わせていない一般人を誤った理解へと導くものになりやすいため適切であるとは言い難い。
また、この判決文自体でも、下記の「⑵イ(イ)」と「⑶ア(イ)」の最高裁判決(昭和62年9月2日)の「婚姻の本質は、両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもつて共同生活を営むことにある」の文を引用していると思われる部分で、ここに示された「両性」の文言を勝手に「当事者」の文言に変更するという不正と思われる記述が見られるように、もともとの判決文を切り貼りする行為の中で、この判決を書いた裁判官が自らの望む結論を導き出すことを意図して、その判決文に示された内容の本来の意味を恣意的に変更しようとすることも起こり得る。
そのため、司法判断として判決の内容を引用する際には、このような不正な手続きが行われることを極限まで排除するために、より厳格な形での引用を行うように徹底することが望ましいということができる。
もともとの判決文を切り貼りする行為が行われることによって、もともとの判決文の解釈の過程で示されている規範の意味が曖昧化したり、変更されたり、別の裁判体が判決を積み重ねていくうちに規範の内容が流動化するようなことがあってはならないと考える。
以上によれば、憲法24条は、その2項において、婚姻及び家族に関する事項についての具体的な制度の構築を国会の合理的な立法裁量に委ねるとともに、その立法に当たっては個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきであるとする要請、指針を示すことによって、その裁量の限界を画したものであり、1項は、その中でも婚姻に関する立法すなわち法律婚制度の構築にあたっては、婚姻をするかどうか、いつ誰と婚姻をするかについて、当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられることとすることを立法府に対して要請する趣旨のものと解される。
【筆者】
ここでは、「24条2項 → 24条1項」の順に、上記のいくつかの部分を繰り返すものとなっている。
しかし、結局「24条2項 → 24条1項」の順にまとめ直すのであれば、最初から一つ前の段落ではこの段落と同じように「24条2項 → 24条1項」で説明されている「平成27年再婚禁止期間大法廷判決」をそのまま正確に引用すればよかったのであって、わざわざ「24条1項 → 24条2項」の順に変更して説明する必要はなかったはずである。
引用の不正確性に加えて、まとめ直しによる無駄が生じており、判決の全体が読み取りづらいものとなっている。
ウ 以上の理解を前提として、憲法24条1項が法律婚制度の構築を求めた同条の「婚姻」について、異性間の婚姻のみならず同性間の婚姻も含むものと解することができるかについて検討する。
【筆者】
まず、「同性間の婚姻」という文言について検討する。
「婚姻」は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「生殖子の養育」の観点から21条1項の「結社の自由」によって保障される他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度である。
そのため、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的との関係で、「婚姻」という概念の中に含めることのできる人的結合関係の範囲には内在的な限界がある。
そのことから、「婚姻」という概念そのものによって、「婚姻」という概念の中に含めることのできる人的結合関係と、含めることのできない人的結合関係とが区別されることになる。
よって、「婚姻」という概念が形成されている目的や、その目的を達成するための手段として必要となる機能を明らかにしないままに、あたかも「同性間」の人的結合関係を「婚姻」とすることができるかのような前提の下に「同性間の婚姻」という文言を用いていることは、何らの根拠も存在しないままに、結論を先取りしようとする意図が含まれていることとなり、妥当でない。
次に、この文全体を検討する。
憲法24条1項の文言は「両性」「夫婦」「相互」の文言を定めており、一夫一婦制を前提としている。
この一夫一婦制(男女二人一組)を前提とする24条の「婚姻」の中に、この範囲を超える「同性間」の人的結合関係を含めることができるか否かを「検討する」のであれば、同様に、この範囲を超える「三人以上」の人的結合関係を含めることができるかどうかも「検討する」ことが必要である。
これは、制度の一部分だけを切り取って比較するような論じ方をするだけでは、制度の全体を統一的な理念に基づいて整合性を保った形で理解するものにはならないからである。
この判決は、24条の「婚姻」が一夫一妻制(男女二人一組)を前提としていることの「二人一組」の部分だけを切り取って、「同性間」の「二人一組」と比較することが可能であるかのような前提で考えているように見受けられる。
その考えにより、「異性間」と「同性間」を比較することが可能であるかのような論じ方をしているが、これだけを比較してその他の人的結合関係を検討していないことは、なぜ「二人一組」であるのか、その根拠を説明しないままに論じる「カップル信仰論」に陥るものとなっている。
「一夫一妻制」の立法目的として最低限求められる条件が「異なる性別の者である」というところにある可能性を考えず、「二人一組である」という部分にのみ着目して比較対象とすることができるかのような取り上げ方をしているが、着眼点が既に「カップル信仰論」に陥っているか、裁判官が特定の結論を導き出したいという動機に基づいて恣意的に「二人一組である」という部分のみを切り取って論じれば済むことであるかのように見せかけようとしているかのいずれかであると考えられる。
まず、憲法24条1項は、「両性」、「夫婦」という男性と女性を示す文言を用いている。この点について、憲法24条の制定経緯をみると、GHQ草案23条では「男女両性」という文言が、これを受けて日本側で作られた「3月2日案」37条及び「3月5日案」22条では「男女相互」という文言がそれぞれ用いられているなど、一貫して男性と女性を示す文言が用いられており、これを踏まえて最終的には「男女相互ノ合意」に代えて「両性の合意」という文言が用いられたことが認められる(前記認定事実(2)ウ)。そうすると、これらの文言からは、同条にいう「婚姻」は、異性間の婚姻を指すものと解するのが自然である。
【筆者】
「異性間の婚姻を指すものと解するのが自然である。」との記載がある。
ここで使われている「異性間の婚姻を指すもの」という部分は、「婚姻」の内容が「男性」と「女性」を含むものとして形成されているという意味であれば、その通りということができる。
しかし、この「異性間の婚姻」という文言を用いていることは、あたかも「異性間」の「婚姻」と、それ以外の「婚姻」が存在するかのような言葉遣いとなっており、正しい説明であるとは言い難い。
まず、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として、「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で枠組みを形成する際に、「男性」と「女性」の組み合わせが選び出され、それを一定の形式で法的に結び付ける概念を「婚姻」と呼んでいる。
この段落で説明する「両性」や「夫婦」、「男女両性」、「男女相互」、「両性の合意」の文言についても、すべてこの意味に対応するものとして用いられているものと考えられる。
そのため、「婚姻」であることそれ自体において、「男性」と「女性」の組み合わせしか存在しないのであり、この判決が述べている「異性間の婚姻を指す」どころか、「婚姻」であれば、それは「異性間」しか存在しないことになる。
よって、「異性間の婚姻」という言葉は、「婚姻」という「男性」と「女性」の組み合わせを指す概念と「異性間」という「男性」と「女性」を指す言葉を同時に用いるという「同義反復」(同語反復/トートロジー)となっており、文法上は誤用となる。
「同語(同義)反復」の例を下記に挙げる。
・「金持ち富裕層」 トートロジーに陥ってはいけない
・「やる気に満ちたモチベーション」 (〃)
・「実際にあったノンフィクション」 (〃)
・「未成年の小学生」 同語反復
・「私の親は男の父だ。」 トートロジー Wikipedia
・「頭痛が痛い。」 (〃)
・「馬から落馬した。」 (〃)
上記の「金持ち富裕層」の例を取り上げれば、「富裕層」であれば「金持ち」しか存在しないのであり、「金持ち」と「富裕層」を組み合わせることは、「同義反復」となる。
同じように、この判決が「異性間の婚姻」という言葉を使っていることについても、「婚姻」であることそれ自体において「男性」と「女性」の組み合わせによる「異性間」しか存在しないのであり、「異性間」と「婚姻」を組み合わせることは、「同義反復」となる。
また、「同義反復」となることを無視して、「金持ち富裕層」という言葉を使ったとしても、「富裕層」であることそれ自体で「金持ち」しか存在しないのであり、それに対する形で「貧乏な富裕層」というものが存在することにはならない。
同じように、「同義反復」となることを無視して、この判決のように「異性間の婚姻」という言葉を使ったとしても、「婚姻」であることそれ自体で既に「男性」と「女性」の組み合わせによる「異性間」しか存在しないのであり、それに対する形で「同性間の婚姻」というものが存在することにはならない。
そのため、「異性間の婚姻」という言葉に対する形で、それ以外の「婚姻」というものが成立するという余地はなく、「婚姻」であることそれ自体で「男性」と「女性」(異性間)の組み合わせを指す意味しか存在しないことになる。
よって、「男性」と「女性」の組み合わせを備えない形で「婚姻」という概念は成立し得ないのであり、その「婚姻」という言葉だけを刈り取ってその概念が形成されている目的から切り離して考えて「婚姻」という空の箱(言葉の意味から切り離された『音の響き』に過ぎないもの)の中に何らかの人的結合関係を詰め込むことができるという性質のものではない。
◇ 本来の意味
「男性」と「女性」の組み合わせ ⇒ 法的に結び付ける形を「婚姻」とする
◇ この判決の言葉の使い方
「婚姻」は空箱 ⇒ どのような人的結合関係でも詰め込むことができる
そのことから、「異性間の婚姻」という言葉を使うことは適切ではなく、このような「婚姻」という概念そのものを、その概念が形成されている目的との間で切り離して、どのような意味としてでも用いることができるような前提を含む形で論じるべきではない。
また、前記認定事実(2)ウのとおり、憲法制定時の帝国議会における審議の過程においても同性間の婚姻について議論が行われた形跡は見当たらず、婚姻は男女間のものであることが当然の前提とされていたことがうかがわれ、これは、憲法24条等の制定に伴い改正された現行民法の審議の過程においても同様である(前記認定事実(2)イ、エ)。
【筆者】
「同性間の婚姻」という文言は、あたかも「婚姻」の中に「同性間」の人的結合関係を含めることができるかのような前提で論じているようであるが、そももそも「婚姻」という概念それ自体が「男女間のもの」であり、その「男女間のもの」である「婚姻」という概念の中に「同性間」の人的結合関係を含めることはできないと考えられる。
そのため、「同性間の婚姻」という言葉自体が成り立たず、このような言葉を用いていることは誤りと考えられる。
そうすると、憲法24条にいう「婚姻」とは、異性間の婚姻を指し、同性間の婚姻を含まないものと解するのが相当である。
【筆者】
「憲法24条にいう「婚姻」とは、異性間の婚姻を指し、同性間の婚姻を含まないものと解するのが相当である。」との記載がある。
この文からは、憲法24条の「婚姻」の意味が、「異性間」の人的結合関係を指していることが明らかとなった。
しかし、ここで「同性間の婚姻」という文言が使われている部分は、あたかも「同性間」の人的結合関係を「婚姻」として扱うことができることを前提として論じているように見受けられるが、「婚姻」という概念にはその概念が形成されている目的との関係で内在的な限界が存在し、「婚姻」という概念の中に「同性間」の人的結合関係を含めることができないと考えられる。
これについて、詳しく検討する。
「婚姻」は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「生殖と子の養育」の観点に着目して他の人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度である。
これは、下記のような経緯によるものである。
その国の中で「生殖と子の養育」に関する事柄について何らの制度も存在しない場合には、社会的な不都合が発生することがある。
例えば、「父親不明」の子供が増える、父親を特定できない子供が増える、父親が蒸発して行方不明になった子供が増える、それらにより「子の福祉」が減少する、父親を特定できないことにより近親者の範囲を把握できずに「近親交配」に至り遺伝的な劣勢を有する個体が高い確率で発現するようになる、一部の強者が多数人との生殖関係を独占することによって社会の中で「子を持ちたいと希望して相手を見つけようとする男女」の数の不均衡が生じて「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」が生まれる、低年齢での妊娠・出産により母体に危険が及ぶ、などの問題が生じることがある。
「婚姻」は、これらの国民が「生殖」によって子供を産むことに関係して起き得る問題を抑制することを目的として、「生殖と子の養育」の観点に着目し、国家の政策の手段として一般的・抽象的に規格化する形(パッケージ)で設けられるようになった枠組みである。
そのため、「婚姻」には、下記の立法目的が存在すると考えられる。
・「子の福祉」が実現される社会基盤を構築すること
・遺伝的な劣勢を有する個体が高い確率で発現することを抑制すること
・「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」を減らすこと
・母体を保護すること
このような「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解決しようとする立法目的を離れて「婚姻」を観念することはできない。
そのことから、「婚姻」という概念である以上は、国民が「生殖」によって子を産むことに関わる制度であることを前提としている。
そのため、「婚姻」の文言の中には「生殖と子の養育」の趣旨が含まれている。
また、この「生殖と子の養育」の趣旨を満たすためには、単に何らかの生殖があり、子を養育することができる地位があればよいというものではなく、下記の要素を満たすことが求められると考えられる。
・子の遺伝的な父親を特定できる組み合わせとすること
・特定された子の父親にも子に対する責任を担わせること
・特定された子の父親を基に遺伝的な近親者を把握すること
・未婚の男女の数の不均衡を防止できる組み合わせに限定すること
これらの要素を満たすことは、「婚姻」という枠組みが形成されている目的との関係で整合的であり、他の人的結合関係とは区別する形で「婚姻」という概念そのものが成り立つために必要となる境界線を保つことができるからである。
そして、24条に定められたものが「婚姻」である以上は、これが「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で形成された制度であることは明らかである。
そのため、24条の「婚姻」の文言の中にも、「生殖と子の養育」の趣旨が含まれている。
また、24条の規定は「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言が用いられており、「一夫一婦制」(男女二人一組)を定めている。
24条が「一夫一婦制」(男女二人一組)を定めていることの理由は、24条の「婚姻」の中に「生殖と子の養育」の趣旨が含まれていることと同様に、下記の要素を満たすからであると考えられる。
・子の遺伝的な父親を特定できる組み合わせとすること
・特定された子の父親にも子に対する責任を担わせること
・特定された子の父親を基に遺伝的な近親者を把握すること
・未婚の男女の数の不均衡を防止できる組み合わせに限定すること
このことは、24条に定められた「婚姻」が、他の様々な人的結合関係とは「生殖と子の養育」の観点から区別する意味で設けられた制度であることを裏付けるものでもある。
この部分は、この判決が上記で「同条にいう「婚姻」は、異性間の婚姻を指すものと解するのが自然である。」と述べていることや、「憲法24条にいう「婚姻」とは、異性間の婚姻を指し、」と述べていることとも整合する。
ここで、「同性間」の人的結合関係を「婚姻」とすることができるか否かを検討する。
「同性間」の人的結合関係については、上記の要素(『生殖と子の養育』の趣旨)を満たすものではないため、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的との間で整合性を保つことができない。
そのため、「同性間」の人的結合関係を「婚姻」とすることはできない。
このことから、この判決では「同性間の婚姻」という文言があるが、そもそも「同性間」の人的結合関係を「婚姻」として扱うことはできないという点で、言葉の使い方を誤っていると考えられる。
エ これに対し、原告らは、憲法制定当時は24条の「婚姻」が異性間の婚姻を指していたとしても、憲法の原理及びその後の社会の変化を踏まえれば、今日の解釈としては同性間の婚姻をも含むものと解すべき旨主張するので、この点について検討する。
【筆者】
一つ前の段落で説明したように、「同性間」の人的結合関係を「婚姻」とすることはできず、「同性間の婚姻」という文言を用いていることは妥当でない。
(ア) 前記認定事実(2)アのとおり、婚姻とは、当事者間の親密な人的結合全般ではなく、その時代の社会通念に従って婚姻とみられるような関係、いわば社会的な承認を受けた人的結合関係をいうものと解されてきたところ、前記ウのとおり、憲法制定時においては、婚姻とは男女間のものという考え方が当然の前提となっており、同性間の人的結合関係については、これを婚姻に含めるか否かの議論すらされていないことが認められる。また、前記認定事実(2)ア及び(3)イのとおり、当時、我が国に限らず、諸外国においても同性間の婚姻を認める立法例は存在していなかったことが認められる。そうすると、憲法制定当時においては、我が国において、同性間の人的結合関係を婚姻とする旨の社会通念、社会的な承認は存在しておらず、婚姻は男女間のものとする社会通念に従って、前記のとおり異性間の人的結合関係のみを「婚姻」とする憲法が制定されたものと認められる。
【筆者】
「婚姻とは、当事者間の親密な人的結合全般ではなく、その時代の社会通念に従って婚姻とみられるような関係、いわば社会的な承認を受けた人的結合関係をいうものと解されてきた」との記載がある。
おおむねその通りであるが、その意味を詳しく検討する必要がある。
「婚姻とは、当事者間の親密な人的結合全般ではなく、」との部分であるが、これは「婚姻」が、憲法21条1項の「結社の自由」などの「自由権(国家からの自由)」によって保障される人的結合関係(ここでいう『当事者間の親密な人的結合全般』)とは区別する意味で設けられた枠組みであることを意味するものと考えられる。
そのため、「婚姻」が「当事者間の親密な人的結合全般」とは区別する意味で設けられている以上、「婚姻」という概念にはそれらの人的結合関係との間で区別することを可能とするための立法目的が存在しており、その立法目的との関係で「婚姻」の中に含めることのできる人的結合関係の範囲には、内在的な限界があることになる。
「婚姻とは、……(略)……その時代の社会通念に従って婚姻とみられるような関係、いわば社会的な承認を受けた人的結合関係をいう」との記載がある。
これは、「婚姻」という枠組みの人的結合関係の範囲は、「社会通念」や「社会的な承認」によって成り立っていることを述べるものである。
ただ、その時代、その社会の中で「婚姻」としての「社会通念」や「社会的な承認」が存在するかどうかは、その社会の中で生じる社会的な不都合を解消することを目的として法制度等の枠組みが定められることによって成立するものである。
そのため、まずその時代、その社会の中で生じている社会的な不都合を捉え、その問題を解消することを目的として掲げ、その目的を達成するための手段としてどのような枠組みを定めるかという問題によって決まることになる。
よって、何らの目的も存在していないにもかかわらず、制度の枠組みが定められているわけではない。
そのため、「社会通念」や「社会的な承認」と称しているものの内容は、「立法目的」と、「立法目的を達成するための手段」となる枠組みを具体的に検討することによって理解されることになる。
その目的の合理性や、目的達成のための手段の合理性を検討することもなく、「社会通念」や「社会的な承認」の存否だけを論じたとしても、制度の内容の当否を論じることはできないことに注意が必要である。
「憲法制定時においては、婚姻とは男女間のものという考え方が当然の前提となっており、同性間の人的結合関係については、これを婚姻に含めるか否かの議論すらされていないことが認められる。」との記載がある。
この「婚姻とは男女間のものという考え方が当然の前提となって」いることの背景には、「婚姻」という概念そのものが有する「目的」と、「その目的を達成するための手段」の関係が存在する。
これは、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として、「生殖と子の養育」の観点から「男性」と「女性」の組み合わせを選び出し、それを一定の枠組みによって結び付けるものとして「婚姻」という概念が形成されていることである。
そのため、このような「目的」と「その目的を達成するための手段」となる枠組みを「婚姻」と呼んでいることによって、「婚姻とは男女間のものという考え方が当然の前提」となっているということである。
そのことから、このような「目的」と「その目的を達成するための手段」の関係を切り離して「婚姻」という枠組みが存在するわけではないのであり、この「婚姻」の言葉の中に、どのような人的結合関係でも含めることができるということにはならない。
そのことから、ここでは「同性間の人的結合関係については、これを婚姻に含めるか否かの議論」のように、「婚姻」の中に「同性間の人的結合関係」を含めることが可能であるかのような前提で論じている部分があるが、そもそも「婚姻」という概念そのものに内在する「目的」と「その目的を達成するための手段」との関係において、「同性間」の人的結合関係を「婚姻」の中に含めることはできないと考えられる。
「当時、我が国に限らず、諸外国においても同性間の婚姻を認める立法例は存在していなかったことが認められる。」との記載がある。
「我が国」の法制度と、「諸外国」の法制度は、それぞれ自国の社会事情の中で生じた何らかの問題を解決することを目的として、その目的を達成するための手段として定められているものである。
そのため、外国語を翻訳する者が「諸外国」の法制度について「婚姻」という言葉を用いて説明しているからといって、「我が国」の法制度における「婚姻」と同一の制度を指していることにはならないことに注意が必要である。
それぞれの法制度は、それぞれ異なった立法目的が存在し、その立法目的を達成するための手段にも様々な違いがあるからである。
よって、「諸外国」において「同性間の婚姻を認める立法例」が存在しているとしても、日本国の婚姻制度の立法目的や、立法目的を達成するための手段として形成される枠組みが変動するわけではない。
もし翻訳者が「婚姻」という言葉を使って翻訳している「諸外国」の法制度によって、「我が国」の「婚姻」の立法目的や、その立法目的を達成するための手段となる枠組みが変動したり、変更することを要請することが可能となるようなことがあれば、「諸外国」の法制度の中には「近親婚」や「複婚(一夫多妻)」、「児童婚」などにあたる制度が存在した場合に、「我が国」の「婚姻」においてもそれを認めなければならないことになり、妥当でない。
「憲法制定当時においては、我が国において、同性間の人的結合関係を婚姻とする旨の社会通念、社会的な承認は存在しておらず、婚姻は男女間のものとする社会通念に従って、前記のとおり異性間の人的結合関係のみを「婚姻」とする憲法が制定されたものと認められる。」との記載がある。
ここでは、「婚姻は男女間のものとする社会通念」と述べているのであるが、そもそも「婚姻」は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として「生殖と子の養育」の観点から「男性」と「女性」の組み合わせを選び出し、一定の枠組みによって結び付けるものとして形成されているものであり、その「婚姻」が「男女間のもの」とされる「社会通念」は、「婚姻」という枠組みが「男性」と「女性」の組み合わせを一定の枠組みによって結び付けるものとして形成された概念であることが理由である。
よって、「婚姻」という言葉が使われている時点で、それは「男性」と「女性」の組み合わせを一定の枠組みによって結び付けるものとして形成されている概念を指していることになるのであり、その言葉の「社会通念」を問うたところで、「男女のもの」という答えが出ることは当然である。
◇ 「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消する目的
↓
◇ 「男性」と「女性」の組み合わせ
↓
◇ 「婚姻」という枠組みを形成
↓
◇ 「婚姻は男女間のものとする社会通念」
↓
◇ 「異性間の人的結合関係のみを「婚姻」とする憲法が制定された」
これは、「婚姻」が「男女間のもの」であることは、「社会通念」が「男女間のもの」であることが理由なのではなく、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として「男性」と「女性」の組み合わせを一定の枠組みによって結び付けるものとして形成された概念が「婚姻」であることが理由である。
しかし、この判決では他の部分でも見られるが、「婚姻」という概念が形成される際の「目的」と「その目的を達成するための手段」となる枠組みの関係を切り離して、「婚姻」の意味そのものを単なる「音の響き」に過ぎないものにまで解体した上で、その空箱となった「音の響き」に過ぎないものに対してどのような人的結合関係でも詰め込むことができるかのような前提で論じている部分があり、妥当でない。
そのような論じ方は、条文に記された文言の意味を解体して無意味なものとし、法律上の規範としての意味を失わせるものとなるから、法解釈として不適切である。
「婚姻」の定義や意味そのものを変えようとする試みについて、「説得定義」の議論も参考になるかもしれない。
【動画】【ハイライト】憲法を変えるな!~安保法制違憲訴訟の勝利を目指して ―講演:石川健治 東京大学教授 2022.1.27
婚姻や家族についての社会通念や国民の意識、価値観は変化し得るものであるところ、近時、同性愛者を含む性的少数者に対する社会内での理解が進み、前記認定事実のとおり、精神医療等の専門家の間では同性愛を疾病とする見解が否定されるに至ったこと(前記認定事実(1)イ(ウ) )、かつて同性間の性交渉を処罰する法律を有していた国においても当該法律を廃止する動きが進んでいること(同(1)イ(イ) )、多くの国において同性カップルに一定の地位や法的保護、公証を与える登録パートナーシップ制度等が導入され(同(3)ア)、さらに、平成13年以降、約30の国・地域において、同性間の婚姻を認める立法が次々にされてきたこと(同(3)イ(ア)及び(イ))、我が国においても、多くの地方公共団体においてパートナーシップ証明制度が導入されるなど、同性カップルについて一定の法的保護を与えようとする動きがあること(同(4)ア)などの事実を認めることができ、同性愛を異常なもの、病的なものとするかつての認識の誤りは多くの国において改善されつつあり、同性愛に対する差別、偏見を克服しようとする動きがあることが認められる。このとおり、同性愛者等を取り巻く社会状況に大きな変化があることを踏まえれば、今日においては憲法24条の「婚姻」に同性間の婚姻を含むものと解釈すべきとの原告らの主張を直ちに否定することはできない。
【筆者】
「婚姻や家族についての社会通念や国民の意識、価値観は変化し得るものであるところ、」との記載がある。
しかし、法学的な意味の「婚姻や家族」である以上は、どのような人的結合関係でも「婚姻や家族」として扱うことができるという性質のものではないため、「婚姻」や「家族」という概念であることによって「変化」の範囲には内在的な限界がある。
その理由は、下記の通りである。
まず、「婚姻や家族」とは、21条1項の「結社の自由」で保障される他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられている枠組みである。
そのことから、「婚姻や家族」という概念そのものの中に、その「婚姻や家族」という概念が形成されている立法目的との関係で、他の様々な人的結合関係との間で区別することを可能とするための要素が含まれていることになる。
そのため、それらの要素を満たす人的結合関係については「婚姻や家族」として扱うことができるが、それらの要素を満たさない人的結合関係については「婚姻や家族」として扱うことはできない。
これは、「婚姻」や「家族」という概念そのものが成り立つために必要となる境界線である。
そのため、それらの要素を満たすことでその「婚姻や家族」という枠組みを維持することのできる範囲内で、「婚姻適齢」が多少変わるとか、「法定相続分」が変更されるとかいうことは考えられる。
このような内容については、「社会通念や国民の意識、価値観は変化し得る」ことは考えられる。
しかし、法学的な意味の「婚姻や家族」の概念を用いて説明しているにもかかわらず、それをその内在的な限界を取り払うことを意味する形で「婚姻や家族」の文言を用いることができることにはならない。
それは、21条1項の「結社の自由」で保障される他の様々な人的結合関係とは区別する形で設けられた枠組みである「婚姻や家族」ではなく、その概念を廃止し、21条1項の「結社の自由」で保障される他の様々な人的結合関係と同化させ、混同させることになるからである。
そのため、「婚姻や家族」という言葉を用いている時点で、そこには内在的な限界が含まれているのであり、「社会通念や国民の意識、価値観は変化し得る」という場合においても、その限界の範囲内の「変化」であることが前提である。
その枠組みを形成していることによる内在的な限界を超える形で、あらゆる人的結合関係を「婚姻や家族」の中に含めることができるということにはならない。
「近時、同性愛者を含む性的少数者に対する社会内での理解が進み、……(略)……精神医療等の専門家の間では同性愛を疾病とする見解が否定されるに至ったこと……(略)……、かつて同性間の性交渉を処罰する法律を有していた国においても当該法律を廃止する動きが進んでいること」との記載がある。
まず、「近時、同性愛者を含む性的少数者に対する社会内での理解が進み、」の部分から検討する。
婚姻制度は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として、21条1項の「結社の自由」で保障されている他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度である。
そして、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」などの立法目的を達成するための手段として、一般的・抽象的に「生殖と子の養育」の趣旨を満たす人的結合関係として「男女二人一組」の制度となっている。
この婚姻制度は、個々人の内心を審査して区別取扱いをするものではないし、特定の思想、信条、信仰、感情を有する者であるか否かなど、まったく感知していない。
そのため、婚姻制度を利用する者が「性愛」の思想、信条、信仰、感情を有するか否かや、「性愛」の思想、信条、信仰、感情を有する場合にどのような対象に向かうかなどについても、一切関知していない。
このことから、ここでは「同性愛者を含む性的少数者」などと、特定の思想、信条、信仰、感情を有する者を取り上げているが、そもそも法律論として婚姻制度の内容を論じる際に、このような特定の思想、信条、信仰、感情と結び付けて考えて、何らかの結論を導き出そうとする試みそのものが誤っている。
また、この判決は「男女二人一組」の婚姻制度を利用する者はすべて「異性愛者」であると考える推測があるようであるが、婚姻制度は「性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いをする制度ではないし、「性愛」に基づいて「婚姻」することを求めるものでも勧めるものでもないのであり、「男女二人一組」の婚姻制度を利用する者が「異性愛者」称する者であるとは限らない。
そのため、「男女二人一組」の婚姻制度を利用する者が「異性愛者」と称する者であると考えた上で、「同性愛者」を称する者を比較対象に取り上げようとする試みも誤っている。
次に、「精神医療等の専門家の間では同性愛を疾病とする見解が否定されるに至ったこと」との部分であるが、精神的なものについては、それを「疾病」と評価するか否かには難解な論点がある。
基本的には、その精神状態が社会生活を送る上で支障があるとすれば、それは「疾病」と評価することも可能であるが、それを「疾病」と評価することによって本人が社会生活を送る上で支障が生じる場合には、それを「疾病」とは評価しないという場合もある。
本人がある一定の精神状態にあるとしても、それが社会生活を送る上で支障が生じるか否かが重要な要素となるものであり、その精神状態そのものが否定されたり、肯定されたりするような意味で「疾病」か否かを評価することができるという性質のものではないのである。
そのため、精神的なものについては、それが内心にとどまる限りは「内心の自由」として絶対的に保障されるのであり、そのこと自体が「疾病」であるか否かという評価を受けて否定されたり、肯定されたりするようなことはない。
その内心が外部的な行為に現れるに至ったときに、それが「公共の福祉」に反する場合には、法的な規制の対象となる場合は考えられるが、内心にとどまる限りは何者にも侵されるものではないし、否定されることもないのである。
ここでは「精神医療等の専門家の間では」として、「精神医療等の専門家」を取り上げているのであるが、「精神医療等の専門家の間」では精神的なものを「疾病」と評価するか否かについてこのような論点が存在することは、基本的には了解済みであると思われる。
そのため、ここでは「同性愛を疾病とする見解が否定されるに至ったこと」と述べているのであるが、そもそも「同性愛」に限らず、「両性愛」も、「全性愛」も、「多性愛」も、「小児性愛」も、「老人性愛」も、「死体性愛」も、「動物性愛」も、「対物性愛」も、「対二次元性愛」も、「無性愛」も、それが内心に留まる限りは「内心の自由」として保障されており、「疾病」か否かという評価の対象ではない。
社会生活を送る上で支障があり、それを「疾病」として扱うことが本人にとって望ましい場合には、「疾病」として考えることも可能であるが、「疾病」として考えなければならないものとして定義されているものではないのである。
また、「異性愛」の思想、信条、信仰、感情を抱く者であるとしても、それが社会生活を送る上で支障があり、それを「疾病」として扱うことが本人にとって望ましい場合には、それを「疾病」として考えることも可能なものであり、それが「異性愛」か「同性愛」かそれ以外かによって「疾病」か否かが変わるというものではないのである。
ここでは「精神医療等の専門家の間では同性愛を疾病とする見解が否定されるに至ったこと」などと述べるのであるが、「精神医療等の専門家の間」では基本的には、このような論点は理解しているはずであり、ここで「疾病とする見解が否定されるに至った」などと述べたところで、これを理由として何らかの法制度を立法しなければならないとする根拠とはならない。
「かつて同性間の性交渉を処罰する法律を有していた国においても当該法律を廃止する動きが進んでいること」との部分について検討する。
日本法の下では、個々人の有する思想、信条、信仰、感情については、それが内心にとどまる限りは絶対保障であるが、それが外部的行為に至った場合には、「公共の福祉」による制約を受ける場合がある。
ここでいう「同性間の性交渉」であるが、日本法の下では刑法等に触れるような行為を行っているわけではないのであれば、違法ではないということができる。
ここでいう「同性間の性交渉」であるが、これは「同性愛」の思想、信条、信仰、感情を有する「同性愛者」を称する者が「同性間の性交渉」をする場合は考えられるが、その行為を行う者が「同性愛」の思想、信条、信仰、感情を有する「同性愛者」を称する者に限られるかのような前提で論じているのであれば、誤りである。
この文脈からは、「同性愛」の思想、信条、信仰、感情を有する者しか、「同性間の性交渉」をしないかのような前提で論じているように見受けられるが、そのような個々人の内心と、個々人の行う行為を結び付けて考えることは、法律論として妥当な説明であるとはいえない。
これと同様に、「同性愛者」を称する者であるとしても、「異性間」の「性交渉」を行っている場合もあるのであり、このような個々人の内心とその者の外部的行為を結び付けて論じるような説明は法律論として妥当ではない。
(ここでは『同性間の性交渉』との文言を使っているが、『異性間』では『性交渉』は存在するが、『同性間』では『性交類似行為』であって『性交』ではないとする見解も存在する。刑法では厳密な定義があるはずである。この点の文言の正確さも考える必要がある。)
「多くの国において同性カップルに一定の地位や法的保護、公証を与える登録パートナーシップ制度等が導入され……(略)……、さらに、平成13年以降、約30の国・地域において、同性間の婚姻を認める立法が次々にされてきたこと」との記載がある。
ここでは「多くの国」や「約30の国・地域」を取り上げているが、日本国との間では社会事情が異なることから、そこで課題となる問題も異なっており、それらの課題を解決することを意図して法制度を構築する際の立法目的も異なっている。
そのため、外国の法制度と日本国の法制度を比較する際には、外国語を翻訳する際に、翻訳者がある制度に対して「婚姻」という言葉を当てて説明しているからといって、日本国の法制度における「婚姻」と同一のものを指していることにはならない。
それぞれの国・地域における社会事情の中で課題となる問題を解決することを意図してそれらの法制度が構築されているだけであり、その立法目的やそれを達成するための手段・方法には様々な違いがあるからである。
そのため、それらの国がここでいう「同性間の婚姻」と称する何らかの制度をそれぞれの国で有しているとしても、そのことは日本国の法制度における「婚姻」とは直接的な関係性がない。
そのことから、それらの国がそれらの国における制度において「同性間」の人的結合関係を対象とした制度を設けているとしても、日本国の法制度における「婚姻」の中に「同性間」の人的結合関係を含めることができるとする根拠にはならないことに注意が必要である。
「我が国においても、多くの地方公共団体においてパートナーシップ証明制度が導入されるなど、同性カップルについて一定の法的保護を与えようとする動きがあること」との記載がある。
まず、憲法20条1項・3項、89条には「政教分離原則」が定められており、「同性愛」という特定の思想や信条、信仰、感情を保護することを目的として制度を立法することは違憲となる。
また、特定の思想、信条、信仰、感情を保護することは、他の思想、信条、信仰、感情との間で憲法14条の「平等原則」に抵触して違憲となる。
他にも、個々人の抱く思想、信条、信仰、感情によって区別取扱いをすることは、憲法19条の「思想良心の自由」に抵触して違憲となる。
そのことから、「地方公共団体」の「パートナーシップ証明制度」の内容が「同性愛」という思想や信条に着目して分類された「同性愛者」にあたる者を対象とした制度となっていれば、その制度はそのこと自体で違憲となる。
よって、この文の前後には、「近時、同性愛者を含む性的少数者に対する社会内での理解が進み、」や「同性愛を異常なもの、病的なものとするかつての認識の誤りは多くの国において改善されつつあり、同性愛に対する差別、偏見を克服しようとする動きがあることが認められる。」と述べていることから、「同性愛」という思想、信条、信仰、感情を保護することを目的として「地方自治体」の「パートナーシップ証明制度」が存在するという前提にあることになるが、そのような「同性愛」という特定の思想、信条、信仰、感情と結び付く形で制度を設けていることは、そのこと自体で違憲となるのであり、そのような制度を行政主体が運用していることを正当化できるかのように論じている部分は誤った理解である。
法制度は思想、信条、信仰、感情に対して中立的でなければならず、特定の思想や信条を取り上げて制度化したり、その制度を利用する者に対して一定の優遇措置を設けていること自体が違憲となるのである。
詳しくは当サイト「パートナーシップ制度」で解説している。
「同性愛を異常なもの、病的なものとするかつての認識の誤りは多くの国において改善されつつあり、同性愛に対する差別、偏見を克服しようとする動きがあることが認められる。」との記載がある。
少なくとも日本法の下では「同性愛」の思想、信条、信仰、感情については、「内心の自由」によって保障される。
「同性愛者等を取り巻く社会状況に大きな変化があることを踏まえれば、今日においては憲法24条の「婚姻」に同性間の婚姻を含むものと解釈すべきとの原告らの主張を直ちに否定することはできない。」との記載がある。
しかし、「法の支配」、「近代立憲主義」を採用している憲法の下では、法制度を特定の思想、信条、信仰、感情などに基づいた形で立法してはならないのであり、「婚姻」の内容を「性愛」という特定の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的とするものとして扱ってはならない。
また、現在の「男女二人一組」の婚姻制度についても、それは「異性愛」という思想、信条、信仰、感情を保護することを目的とした制度ではないのであり、婚姻制度は「異性愛者」を称する者を保護する制度であるという誤った認識を基にして、「同性愛者等を取り巻く社会状況に大きな変化」があれば、「同性愛者等」を称する者も婚姻制度によって保護されるはずであるとの主張そのものが成り立たないものである。
このような理解をこの判決は「直ちに否定することはできない。」と述べるのであるが、婚姻制度が「性愛」(その中でも特に『異性愛』)を保護することを目的として存在していることが許されると考えていること自体が誤りである。
「憲法24条の「婚姻」に同性間の婚姻を含むものと解釈すべき」との部分であるが、「婚姻」は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度であることから、「婚姻」であることそれ自体によって、「婚姻」の中に含めることのできる人的結合関係の範囲には内在的な限界がある。
ここでは、「同性間の婚姻」のように「同性間」の人的結合関係を「婚姻」とすることが可能であることを前提としている文言が見られるが、「同性間」の人的結合関係はその間で一般的・抽象的に「生殖」を想定することができないため、「生殖と子の養育」の趣旨を満たすとはいえず、「婚姻」とすることはできないと考えられる。
(イ) しかしながら、前記認定事実のとおり、歴史上、人間は男女の性的結合関係によって、子孫を残し、種の保存を図ってきたところ、このような前国家的な関係を規範によって統制するために婚姻制度(法律婚制度)が生じ、その中で、婚姻とは、伝統的に、男女の生活共同体として子の監護養育や共同生活等の維持によって家族の中核を形成するものと捉えられてきたことが認められる(前記認定事実(2)ア)。そして、このような婚姻についての捉え方は、オランダにおいて同性間の婚姻の制度が導入される平成13年までは諸外国においても共通しており、婚姻は男女間のものとされてきたところである(前記認定事実(2)ア、(3)イ)。これらの事実等からすれば、伝統的に男女間の人的結合に対して婚姻としての社会的承認が与えられてきた背景、根底には、夫婦となった男女が子を産み育て、家族として共同生活を送りながら、次の世代につないでいくという社会にとって重要かつ不可欠な役割を果たしてきた事実があることは否定できないところであろう。
【筆者】
「歴史上、人間は男女の性的結合関係によって、子孫を残し、種の保存を図ってきたところ、このような前国家的な関係を規範によって統制するために婚姻制度(法律婚制度)が生じ、」との記載がある。
この点は、その通りであると考えられる。
ただ、その「規範によって統制するために婚姻制度(法律婚制度)が生じ」る背景には、「生殖」に関わって社会的な不都合が生じていることが原因である。
もし何らの不都合も存在しないのであれば、そもそも「規範によって統制する」ことそのものが必要ないからである。
そのため、その「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために必要となる立法目的と、その立法目的を達成するための手段となる枠組みを検討することが必要である。
その国の中で「生殖と子の養育」に関する事柄について何らの制度も存在しない場合には、社会的な不都合が発生することがある。
例えば、「父親不明」の子供が増える、父親を特定できない子供が増える、父親が蒸発して行方不明になった子供が増える、それらにより「子の福祉」が減少する、父親を特定できないことにより近親者の範囲を把握できずに「近親交配」に至り遺伝的な劣勢を有する個体が高い確率で発現するようになる、一部の強者が多数人との生殖関係を独占することによって社会の中で「子を持ちたいと希望して相手を見つけようとする男女」の数の不均衡が生じて「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」が生まれる、低年齢での妊娠・出産により母体に危険が及ぶ、などの問題が生じることがある。
そのため、これらを解決するための枠組みには、下記の立法目的が存在すると考えられる。
・「子の福祉」が実現される社会基盤を構築すること
・遺伝的な劣勢を有する個体が高い確率で発現することを抑制すること
・「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」を減らすこと
・母体を保護すること
そして、これらの目的を達成するためには、これらの目的を達成するための手段として整合的な、下記の要素を満たす人的結合関係を、他の様々な人的結合関係とは区別することが必要となる。
・子の遺伝的な父親を特定できる組み合わせとすること
・特定された子の父親にも子に対する責任を担わせること
・特定された子の父親を基に遺伝的な近親者を把握すること
・未婚の男女の数の不均衡を防止できる組み合わせに限定すること
これらの要素を満たす人的結合関係に対して、一定の優遇措置を与えることによって、立法目的の実現を目指す仕組みとする必要がある。
このような「目的」と「その目的を達成するための手段」となる枠組みを定めることが、「婚姻」という概念が生じる経緯である。
「婚姻とは、伝統的に、男女の生活共同体として子の監護養育や共同生活等の維持によって家族の中核を形成するものと捉えられてきたことが認められる」との記載がある。
ここで述べられている「婚姻」が「伝統的に、男女の生活共同体として子の監護養育や共同生活等の維持によって家族の中核を形成するものと捉えられてきた」ことの背景には、上記のような「目的」と「その目的を達成するための手段」となる枠組み(必要となる要素)が存在すると考えられる。
そのため、上記のような「目的」と「その目的を達成するための手段」となる枠組み(必要となる要素)を明らかにしないままに、「婚姻」の内容である「男女の生活共同体として子の監護養育や共同生活等の維持によって家族の中核を形成するもの」を説明したとしても、その形にどのような意図が含まれているのかを説明しているとは言えない。
「このような婚姻についての捉え方は、オランダにおいて同性間の婚姻の制度が導入される平成13年までは諸外国においても共通しており、婚姻は男女間のものとされてきたところである」との記載がある。
まず、「諸外国」についてであるが、それぞれの国は社会事情が異なることから、そこで課題となる問題も異なっており、それらの課題を解決することを意図して法制度を構築する際の立法目的も異なっている。
そのため、「諸外国」の法制度を比較する際には、外国語を翻訳する際に、翻訳者がある制度に対して「婚姻」という同一の言葉を当てて説明しているからといって、それぞれの制度が同一のものを指していることにはならない。
それぞれの国・地域における社会事情の中で課題となる問題を解決することを意図してそれらの法制度が構築されているだけであり、その立法目的やそれを達成するための手段・方法には様々な違いがあるからである。
そのことから、「このような婚姻についての捉え方」という部分についても、似たような制度に対して外国語を翻訳する者が「婚姻」という同一の言葉を使って説明しているからといって、それぞれが同一の制度を指していることにはならないのであり、「婚姻についての捉え方」などと、「婚姻」という言葉を統一的に理解することが可能であることを前提とした上でその「捉え方」を論じることは、それぞれの国の間では完全に同一の制度として比較ができるという性質のものではないことから、誤りとなる。
また、「諸外国」におけるここで「婚姻」という言葉を使って説明している制度と、日本法における「婚姻」についても、同一の制度を指していることにはならないことは同様である。
このような婚姻についての捉え方は、オランダにおいて同性間の婚姻の制度が導入される平成13年までは諸外国においても共通しており、」との文についてであるが、ここでは「諸外国」の法制度が「共通」していたことを前提としているように論じているが、古くから「一夫多妻制」を採用している国々も存在する点で、「共通」との認識は取り上げ方を誤っているように思われる。
【参考】一夫多妻制 Wikipedia
裁判官が参考としたい国だけを「諸外国」として想定し、それ以外の国々の法制度を考えないというのでは、自らの望む結論を導き出したいがために、恣意的な取り上げ方をしていることとなるため、妥当でない。
「伝統的に男女間の人的結合に対して婚姻としての社会的承認が与えられてきた背景、根底には、夫婦となった男女が子を産み育て、家族として共同生活を送りながら、次の世代につないでいくという社会にとって重要かつ不可欠な役割を果たしてきた事実があることは否定できない」との記載がある。
「夫婦となった男女が子を産み育て、家族として共同生活を送りながら、次の世代につないでいく」の部分は、「婚姻」の内容が「男女二人一組」となっていることによって果たされている機能の重要性を述べるものである。
ただ、これはなぜ「婚姻」の内容が「男女二人一組」となっているのか、その背景にある「立法目的」と「その立法目的を達成するための手段」となる枠組みの当否を述べているものではない。
「婚姻」の立法目的とその目的を達成するための手段となる枠組みは、下記のように整理できると考えられる。
〇 「子の福祉」が実現される社会基盤を構築すること
(→ 達成手段:嫡出子として生まれることの重視)
〇 遺伝的な劣勢を有する個体が高い確率で発現することを抑制すること
(→ 達成手段:父親と近親者を特定して『近親交配』を防ぐ仕組みを導入)
〇 「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」を減らすこと
(→ 達成手段:未婚の男女の数の不均衡の防止。一夫一婦制、複婚の禁止)
〇 母体を保護すること
(→ 達成手段:婚姻適齢)
「男女間の人的結合」によって形成される「婚姻」という枠組みが「社会的承認」を得ている「背景」や「根底」にあるものは、これらの立法目的を達成するための手段として妥当な内容であるからであると考えられる。
前述のとおり、婚姻や家族に関する社会通念や国民の意識、価値観は時代、社会によって変遷するものであり、我が国においても、従来に比べて結婚について多様な考え方が存在するようになり、また、婚姻しないという選択又は婚姻しても子を持たないという選択をすることも当該個人の自由であることは論を俟たないところではある。しかしながら、婚姻についての意識調査の結果(前記認定事実(6))によれば、生涯を独身で過ごすというのは望ましい生き方ではないとの回答や、結婚をする理由として子供を持ちたいことを挙げる回答が過半数を占める調査結果も存在することが認められ、法律婚を尊重する考え方や婚姻と子供を持つことを結びつける考え方を有する人は今なお一定の割合を占めていることが認められる。
【筆者】
「婚姻や家族に関する社会通念や国民の意識、価値観は時代、社会によって変遷するものであり、」との記載がある。
しかし、法学的な意味の「婚姻や家族」である以上は、どのような人的結合関係でも「婚姻や家族」として扱うことができるという性質のものではないため、「婚姻」や「家族」という概念であることによって「変遷」の範囲には内在的な限界がある。
その理由は、下記の通りである。
まず、「婚姻や家族」とは、21条1項の「結社の自由」で保障される他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられている枠組みである。
そのことから、「婚姻や家族」という概念そのものの中に、その「婚姻や家族」という概念が形成されている立法目的との関係で、他の様々な人的結合関係との間で区別することを可能とするための要素が含まれていることになる。
そのため、それらの要素を満たす人的結合関係については「婚姻や家族」として扱うことができるが、それらの要素を満たさない人的結合関係については「婚姻や家族」として扱うことはできない。
これは、「婚姻」や「家族」という概念そのものが成り立つために必要となる境界線であり、内在的な限界である。
そのため、それらの要素を満たすことによって、その「婚姻や家族」という枠組みを維持することのできる人的結合関係の範囲内で、「婚姻適齢」が多少変わるとか、「法定相続分」が変更されるとかいうことは考えられる。
このような内容については、「社会通念や国民の意識、価値観は時代、社会によって変遷する」ことは考えられる。
しかし、法学的な意味の「婚姻や家族」の概念を用いて説明しているにもかかわらず、それをその内在的な限界を取り払うことを意味する形で「婚姻や家族」の文言を用いることができることにはならない。
それは、21条1項の「結社の自由」で保障される他の様々な人的結合関係とは区別する形で設けられた枠組みである「婚姻や家族」ではなく、その概念を廃止し、21条1項の「結社の自由」で保障される他の様々な人的結合関係と同化し、混同させることになるからである。
そのため、「婚姻や家族」という言葉を用いている時点で、そこには内在的な限界が含まれているのであり、「社会通念や国民の意識、価値観は時代、社会によって変遷する」という場合においても、その限界の範囲内の「変遷」であることが前提である。
その枠組みを形成していることによる内在的な限界を超える形で、あらゆる人的結合関係を「婚姻や家族」の中に含めることができるということにはならないのである。
もしかすると、「婚姻や家族に関する社会通念や国民の意識、価値観は時代、社会によって変遷するものであり、」の部分は、この段落の後に続く文との関係で、法制度として具体化された「婚姻や家族」の制度を「個々人の利用目的」としてどのように活用するかという事柄について「社会通念や国民の意識、価値観は時代、社会によって変遷するもの」と述べているのかもしれないが、それは法制度によって具体化された「婚姻や家族」の制度を個々人がどのような価値観に従って活用するかという個々人の個別的な利用目的に過ぎないのであり、法律論として論じることのできる対象ではない。
それを取り上げて述べようとしているものであれば、法解釈を述べているものとはいえず、適切ではない。
「我が国においても、従来に比べて結婚について多様な考え方が存在するようになり、」との記載がある。
この「従来に比べて結婚について多様な考え方が存在する」との部分であるが、婚姻制度の枠組みについての「多様な考え方」を説明しているのか、婚姻制度を利用する者の利用方法における価値観についての「多様な考え方」なのかが不明確なものとなっている。
婚姻制度を論じる際には、「国の立法目的」と「個々人の利用目的」を明確に区別して考えなければ議論が混乱することと同じように、意味が不明確であり、混乱するものとなっている。
「婚姻しないという選択又は婚姻しても子を持たないという選択をすることも当該個人の自由であることは論を俟たない」との記載がある。
これは、「婚姻」制度を利用するか否かの選択についてと、婚姻制度を利用する場合において「個々人の利用目的」として「子を持たないという選択」をする場合について述べているものである。
この判決は「婚姻しても子を持たないという選択をすることも当該個人の自由であることは論を俟たない」と述べているということは、「子供を持つ婚姻こそが正しい価値観である」とはいえないと分かっているはずである。
そうであれば、「『性愛』に基づく婚姻こそが正しい価値観である」ともいえないことは理解できるはずである。
婚姻制度についての「個々人の利用目的」として「性愛」の思想、信条、信仰、感情を満たすことを目的とするか否かは、「当該個人の自由であることは論を俟たない」ということである。
それにもかかわらず、この判決が個々人の価値観の一つである「性愛」の思想、信条、信仰、感情を取り上げ、婚姻制度がその中でも特に「異性愛」の思想、信条、信仰、感情を保護するものとして「性的指向による区別取扱い」を行っているかのように論じていることは、誤った理解である。
婚姻制度を利用する際に「性愛」の思想、信条、信仰、感情が満たされることを重視するか否かは、婚姻制度を利用する際に子を持つか持たないかを選択することと同じ次元に属するものであり、「個々人の利用目的」として扱われるべきものである。
「生涯を独身で過ごすというのは望ましい生き方ではないとの回答や、結婚をする理由として子供を持ちたいことを挙げる回答が過半数を占める調査結果も存在することが認められ、法律婚を尊重する考え方や婚姻と子供を持つことを結びつける考え方を有する人は今なお一定の割合を占めていることが認められる。」との記載がある。
まず、「法律婚を尊重する考え方」であるが、その「法律婚」が「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するための制度として役立っていることが人々に認識されており、その枠組みを利用することの妥当性によって形成されているものと考えられる。
そのため、「法律婚」の内容そのものが改変され、社会的な不都合を解消するための制度として役立たないものに変わってしまったならば、そもそも「法律婚を尊重する考え方」も人々の間から失われていく性質のものである。
よって、婚姻制度を利用する者について、「法律婚を尊重する考え方」によって得られている何らかの利益があるとしても、それはその「法律婚」の枠組みが社会的な不都合を解消するための制度として役立っている限りで生じる利益であり、その枠組みを変更するにもかかわらず、「法律婚を尊重する考え方」による何らかの利益を得られ続けるというものではないことに注意する必要がある。
「結婚をする理由として子供を持ちたいこと」や「婚姻と子供を持つことを結びつける考え方」の部分であるが、これは婚姻制度が「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するための制度として十分に機能しており、その制度を利用した場合には一定の優遇措置を得ることができるし、「貞操義務」と「嫡出推定」によって父子関係が明確となり、「子供を持つこと」についても婚姻制度を利用していない場合よりは一定のメリットがあることが国民の間で広く知られていることによるものと考えられる。
ただ、このような国民の意識が「一定の割合を占めている」ことは、婚姻制度が「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するための制度として十分に機能している場合においてのみ生じるものであり、婚姻制度の内容が改変され、社会的な不都合を解消するための制度として機能しないものに変わってしまった場合には、そのような国民の意識も失われていくことを押さえる必要がある。
そのため、この判決のこの部分では国民の意識を取り上げるのであるが、このような国民の意識は、現在の婚姻制度の内容に依存して生じているものであり、婚姻制度の枠組みを変更した場合でも、このような意識が国民の間で継続されるという保証のあるものではない。
よって、婚姻制度の枠組みを変更するかどうかを論じる場面において、このような現在の婚姻制度を利用しようとする国民の意識のみを根拠(理由)として変更の可否を論じることができることにはならないことに注意する必要がある。
そうすると、原告らが指摘する同性愛者等を取り巻く社会状況の変化や同性愛に対する差別、偏見の解消の重要性を踏まえたとしても、当事者間における自然生殖の可能性がないことが明らかである同性カップルについて、その人的結合関係に対して一定の法的保護を与えることを超えて、本件諸規定が対象としている異性間の婚姻と同じ「婚姻」と捉えるべきとの社会通念や社会的な承認が生じているか否かについては、更なる慎重な検討を要するものといわざるを得ない(なお、この点は、女性の同性カップルであっても生殖補助医療を受けることなどにより出産することが可能であることや同性カップルが子を養育することが可能であることを否定するものではなく、古くから続いてきた男女が共同生活を送る中で子を産み育てるという営みが同性カップルには当てはまらないことをいうものである。)。
【筆者】
「同性愛者等を取り巻く社会状況の変化や同性愛に対する差別、偏見の解消の重要性を踏まえたとしても、」との部分について検討する。
まず、婚姻制度は「性愛」の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にどのような対象に向かうかを審査して区別して取扱うものではないし、「性愛」に基づいて「婚姻」することを求めるものでも勧めるものでもない。
また、法制度であることから、思想や信条、信仰、感情に対して中立的な内容でなければならず、婚姻制度を「性愛」という特定の思想や信条、信仰、感情を保護するものとして立法することもできない。
そのため、そもそも「同性愛」の思想、信条、信仰、感情を抱く「同性愛者」と称する者や、ここで述べられている「同性愛者等」に対する社会状況が変化したとしても、それによって婚姻制度の内容を変更しなければならないとする理由にはならない。
法制度と、個々人の思想、信条、信仰、感情は切り離して考えることが必要である。
これとは別に、もし個々人が「性愛」の思想、信条、信仰、感情に基づく形で、何らかの人的結合関係を形成したいのであれば、21条1項の「結社の自由」によって「性愛結社」を形成することが可能である。
「当事者間における自然生殖の可能性がないことが明らかである同性カップルについて、その人的結合関係に対して一定の法的保護を与えることを超えて、本件諸規定が対象としている異性間の婚姻と同じ「婚姻」と捉えるべきとの社会通念や社会的な承認が生じているか否かについては、」との部分について検討する。
この文は、「同性カップル」と称する「同性間」の人的結合関係について、「異性間の婚姻と同じ「婚姻」と捉えるべきとの社会通念や社会的な承認が生じているか否か」を問うものとなっている。
ここは「婚姻」の中に、「同性カップル」という「同性間」の人的結合関係を含めることができるとの前提で論じるものとなっているが、この部分から検討することが必要である。
なぜならば、「婚姻」という概念そのものが、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として、「生殖と子の養育」の観点から「男性」と「女性」の組み合わせを一定の形式で結び付けることを意味して形成された概念であり、「婚姻」という概念それ自体であることによって、「婚姻」の中に含めることのできる人的結合関係の範囲には内在的な限界があるからである。
「同性間」の人的結合関係については、一般的・抽象的にその間で「生殖」を想定することができないことから、「生殖と子の養育」の趣旨を満たすとはいえず、「婚姻」の立法目的との関係で「婚姻」とすることができないと考えられる。
よって、この部分で「同性間」の人的結合関係を「婚姻」とすることができることを前提として論じていることは誤りとなる。
ここで「社会通念や社会的な承認」と述べている部分についても、そもそも「婚姻」という概念が形成されている「目的」と「その目的を達成するための手段」となる枠組みを離れて、「婚姻」という概念を観念することはできないのであり、「社会通念や社会的な承認」が有るとか無いとか述べるだけで、「婚姻」という概念に内在する「目的」と「その目的を達成するための手段」となる枠組みを変更することができることにはならない。
ここで「同性カップル」として「同性間」の「二人一組」のみを取り上げて比較しようとするものとなっている。
この「同性カップル」という言葉は、現在の婚姻制度が「男女二人一組」の形となっていることを前提として、その中から「二人一組」の部分だけを恣意的に切り取った上で、その「二人一組」に「同性間」を当てはめようとすることによって主張されているものと考えられる。
しかし、そもそも婚姻制度は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として設けられた枠組みであり、その内容は一般的・抽象的にその間で「生殖」を想定することができる「男性」と「女性」であることが枠組みの根幹部分であると考えられ、単なる「二人一組」であることだけを重要視して形成されているわけではない。
そのため、そもそも「二人一組」であることを前提として、単に「『異性間』があれば『同性間』もあるだろう」というような安易な発想によって、「異性間」の「二人一組」と「同性間」の「二人一組」を比較対象として取り上げることができるという性質のものではない。
人的結合関係の中には、「カップル」という「二人一組」だけでなく、「トリオ」という「三人一組」もあるし、「四人一組」の関係も存在するのであり、それらの人的結合関係との比較についても網羅的に検討するということをしないままに、単に「二人一組」の人的結合関係だけを比較対象として論じれば済むと考えているのであれば、なぜ「二人一組」であるのかその根拠を説明しないままに論じる「カップル信仰論」に陥っていることになる。
「(なお、この点は、女性の同性カップルであっても生殖補助医療を受けることなどにより出産することが可能であることや同性カップルが子を養育することが可能であることを否定するものではなく、古くから続いてきた男女が共同生活を送る中で子を産み育てるという営みが同性カップルには当てはまらないことをいうものである。)」との部分について検討する。
ここでは、「同性カップル」というように「二人一組」の人的結合関係のみを取り上げるものとなっている。
しかし、人的結合関係においては「同性トリオ」という「三人一組」も考えられるし、「四人一組」、「七人一組」など、様々な人的結合関係が考えられる。
それらの可能性を考えずに、単に「同性カップル」というように「二人一組」であることを前提として論じていることは、なぜ「二人一組」であるのかその根拠を説明しないままに論じる「カップル信仰論」に陥っており、妥当でない。
現在の婚姻制度が「男女二人一組」となっていることは、「貞操義務」の下で「男性」と「女性」が自然生殖を行った場合に、その下で遺伝的な父親を特定することができるという仕組みを基にして形成されているものである。
そのことから、そもそも自然生殖を想定することができない人的結合関係について、それが「二人一組」でなければならないという前提そのものが成り立たないことにも注目する必要がある。
そして、前記認定事実(5)のとおり、我が国における世論調査等の結果によれば、同性間の婚姻の導入について反対意見を有する人の割合は減少傾向にあることが認められるものの、依然として一定の割合を占めており、社会内において価値観の対立があることが認められる。このような反対意見の多くは、婚姻を男女間の人的結合関係と捉える伝統的な価値観に根差したものであると考えられるところ、そのような伝統的な価値観が、夫婦となった男女が子を産み育て、家族として共同生活を送りながら、次の世代につないでいくという古くからの人間の営みに由来するものであることからすれば、これを一方的に排斥することも困難であるといわざるを得ない。
【筆者】
「我が国における世論調査等の結果によれば、同性間の婚姻の導入について反対意見を有する人の割合は減少傾向にあることが認められるものの、依然として一定の割合を占めており、社会内において価値観の対立があることが認められる。」との記載がある。
この文は、「婚姻」という概念が形成される際の「目的」と「その目的を達成するための手段」となる枠組みからどのような人的結合関係を「婚姻」として扱うことができるかという観点から論じるのではなく、「社会内」における「価値観の対立」によって、「婚姻」の中に「同性間」の人的結合関係を含めることができるか否かが変わるかのように論じようとするものとなっている。
しかし、ここでは法解釈が問われているのであるから、「社会内」における「価値観の対立」によって、「婚姻」として扱うことができる人的結合関係の範囲が広がったり狭まったりするような論じ方をすることは妥当でない。
そのような「社会内」における「価値観の対立」を反映することによって規範を変更することができる場合とは、国会によって法律の規定を改廃するか、憲法改正によって憲法上の規定を改廃する場合のことである。
裁判所が法解釈を行う際には、国民意識などという漠然とした説明や、「世論調査等の結果」などというその時々の調査によって結論が変わるような資料を根拠として規範の意味を論じるべきではない。
立法府の国会が担うべき問題と、司法府の裁判所が担うべき問題を区別することが必要である。
「このような反対意見の多くは、婚姻を男女間の人的結合関係と捉える伝統的な価値観に根差したものであると考えられるところ、そのような伝統的な価値観が、夫婦となった男女が子を産み育て、家族として共同生活を送りながら、次の世代につないでいくという古くからの人間の営みに由来するものである」との記載がある。
まず、「このような反対意見の多くは、」との部分であるが、法解釈を行う際には、法の中に規範を見出さなければならないのであり、賛成意見があるか、「反対意見」があるか、それが多いか少ないかなどという漠然とした国民意識に委ねるような形で結論を導き出そうとすることは妥当でない。
このような国民意識の集積を行って、法的な規範を変更するか否かを決めることは、国会が法律の改廃を行う場合や、憲法改正において憲法規定を改廃する場合の問題である。
具体的な条文が存在するにもかかわらず、その条文の中に規範の意味を見出すのではなく、規範の意味そのものを国民の意識に委ねるような説明となっていることは、法解釈とは言えない。
次に、「夫婦となった男女が子を産み育て、家族として共同生活を送りながら、次の世代につないでいくという古くからの人間の営みに由来する」「婚姻を男女間の人的結合関係と捉える伝統的な価値観」の部分であるが、このような理解が形成されている背景にある「立法目的」と、「その立法目的を達成するための手段」について十分な説明がなされているわけではない。
この「伝統的な価値観」というものが特定の思想や信条、信仰、感情によるものであってはならないのであり、法律論としては、その「伝統的な価値観」と称するものの内容が、どのような「立法目的」を有しており、制度の内容が「その立法目的を達成するための手段」として合理的な内容であるかを論じることが必要である。
この判決では、この「伝統的な価値観」にあたるものとして、下記のように説明されている。
◇ 1(2)ア
「歴史上、人間は男女の性的結合関係によって、子孫を残し、種の保存を図ってきたところ、この古くから続く関係を規範によって統制しようとするところに婚姻制度(法律婚制度)が生まれた。」
◇ 2⑴エ(イ) 第一段落
「歴史上、人間は男女の性的結合関係によって、子孫を残し、種の保存を図ってきたところ、このような前国家的な関係を規範によって統制するために婚姻制度(法律婚制度)が生じ、その中で、婚姻とは、伝統的に、男女の生活共同体として子の監護養育や共同生活等の維持によって家族の中核を形成するものと捉えられてきたことが認められる」
「伝統的に男女間の人的結合に対して婚姻としての社会的承認が与えられてきた背景、根底には、夫婦となった男女が子を産み育て、家族として共同生活を送りながら、次の世代につないでいくという社会にとって重要かつ不可欠な役割を果たしてきた事実があることは否定できない」
◇ 2⑴エ(イ) 第三段落
「古くから続いてきた男女が共同生活を送る中で子を産み育てるという営み」
上記の文には、「人間は男女の性的結合関係によって、子孫を残し、種の保存を図ってきた」や「男女が子を産み育て、」とあることから、「男性」と「女性」が自然生殖を行うことによって「子」が生まれるという因果関係を想定していることを読み取ることができる。
そして、「この古くから続く関係を規範によって統制しようとするところに婚姻制度(法律婚制度)が生まれた。」や「このような前国家的な関係を規範によって統制するために婚姻制度(法律婚制度)が生じ、」という文言があることから、婚姻制度が「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的とした制度であることを読み取ることができる。
これが、この判決のいう「伝統的な価値観」の内容である。
その社会の中で「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的が存在している限りは、それに応じた何らかの制度が必要となるのであり、それを「婚姻」という制度が担っている以上は、「婚姻」の文言から「生殖と子の養育」の趣旨を切り離して考えることはできない。
このような立法目的を「伝統的な価値観」と称するかは別としても、「婚姻」が「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的とした制度であることは明らかである。
「これを一方的に排斥することも困難であるといわざるを得ない。」との記載がある。
もしこの判決が「伝統的な価値観」と称している「婚姻」の中に含まれた「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を「一方的に排斥する」ようなことがあったならば、その社会の中で「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することができなくなることを意味し、社会的な不都合が生じることを防ぐことができなくなることに注意が必要である。
(ウ) 以上によれば、我が国においても、同性愛に対する差別・偏見を解消しようとする動き、同性カップルに一定の法的保護を与えようとする動きがあることは前述のとおりであるものの、現段階において、同性間の人的結合関係を異性間の夫婦と同じ「婚姻」とすることの社会的承認があるものとまでは認め難いものといわざるを得ない。
【筆者】
「同性愛に対する差別・偏見を解消しようとする動き、同性カップルに一定の法的保護を与えようとする動きがあることは前述のとおりであるものの、」との記載がある。
しかし、婚姻制度は「性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にどのような対象に向かうかを審査して区別して取扱うものではないし、「性愛」に基づいて「婚姻」することを求めるものでも勧めるものでもない。
また、法制度は特定の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的として立法してはならないのであり、「性愛」という思想、信条、信仰、感情を保護することを目的として立法することはできない。
よって、「同性愛」という思想、信条、信仰、感情に対して社会の受け止め方がどのような状態となったとしても、そのことによって法制度が何らかの影響を受けるということはない。
「現段階において、同性間の人的結合関係を異性間の夫婦と同じ「婚姻」とすることの社会的承認があるものとまでは認め難いものといわざるを得ない。」との記載がある。
先ほども述べたように、「同性愛」という特定の思想、信条、信仰、感情に対して社会の受け止め方がどのような状態となったとしても、そのことによって法制度が何らかの影響を受けるわけではないし、法制度の解釈が変更されるとする原因となることはない。
そのため、ここでは「同性愛」などの特定の思想、信条、信仰、感情を論じた上で、「現段階において、」などと「婚姻」の枠組みが変更される余地があるかのように述べるものとなっているが、そもそも法制度は「性愛」という特定の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的として立法したり、そのような思想、信条、信仰、感情を満たすために制度が設けられていることを前提とした解釈を行ってはならないのであり、特定の思想、信条、信仰、感情の普及の有無を理由として法解釈が変更されることがあるかのような説明となっていることは誤りである。
また、ここでは「社会的承認」とも述べられているが、「婚姻」という概念は「目的」と「その目的を達成するための手段」として形成されている枠組みであり、この「目的」と「その目的を達成するための手段」を切り離す形で、単なる「社会的承認」があるかどうかを認定するだけで、「婚姻」の中にいかなる人的結合関係でも含めることができるという性質のものではない。
そのため、「社会的承認」の存否を根拠として「婚姻」の意味が変わるような説明となっていることは、解釈の過程を示すものとはいえず、結論のみを述べているだけとなってしまうため、妥当とは言い難い。
したがって、憲法制定時からの社会状況の変化等を踏まえても、現段階において、憲法24条の「婚姻」について、これに同性間の婚姻を含まないという前記ウの解釈が不当であり解釈を変更すべき状態となっているものということはできない。
【筆者】
「憲法制定時からの社会状況の変化等を踏まえても、」との部分について検討する。
「婚姻」という概念は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として、「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で、「男性」と「女性」の組み合わせを一定の形式で法的に結び付けるものとして形成されたものである。
そのため、「婚姻」であることそれ自体によって、その目的との関係により「婚姻」の中に含めることのできる人的結合関係の範囲には内在的な限界がある。
この目的を達成することを阻害する人的結合関係を「婚姻」として扱うことは、そもそもできない。
この内在的な限界は、この判決が持ち出すような「婚姻についての意識調査の結果」や「世論調査等の結果」などによって左右されるような性質のものではない。
そのため、「婚姻」という概念であることそのものによる内在的な限界を検討することもなく、「社会状況の変化等」によって、どのような人的結合関係でも「婚姻」の中に含めることができるかのような前提で論じている部分が妥当でない。
また、「社会状況の変化等」を根拠として法の内容の意味が変動することになれば、今まで認められていなかった何かが、後に「社会状況の変化等」によって認められることになるが、また再び「社会状況の変化等」を理由として認められなくなることも起こり得るのであり、法的な根拠を何ら説明するものではないことも押さえる必要がある。
法規範の内容を論じる際には、「社会状況の変化等」などという感覚的なものを根拠とすることは不適切ということである。
「現段階において、憲法24条の「婚姻」について、これに同性間の婚姻を含まないという前記ウの解釈が不当であり解釈を変更すべき状態となっているものということはできない。」との部分について検討する。
まず、「ウの解釈」とは、結論部分で「憲法24条にいう「婚姻」とは、異性間の婚姻を指し、同性間の婚姻を含まないものと解するのが相当である。」と述べている解釈のことである。
ここでは、この解釈について「現段階において、」「解釈を変更すべき状態となっているものということはできない。」と述べるのであるが、それは「現段階において、」のように留保を示すような書きぶりとなっている。
この「現段階において、」の文言は、「社会状況の変化等」と対応する意味で使われているものと思われるが、その「社会状況の変化等」の例として挙げられているものは、「同性愛に対する差別・偏見を解消しようとする動き、」等のことである。
しかし、法制度は特定の思想、信条、信仰、感情に対して中立的な内容でなければならないのであり、日本国が「近代立憲主義」を採用している以上は、「性愛」という特定の思想や信条、信仰、感情を保護することを目的とした法制度を立法することはできない。
そのため、「性愛」という特定の思想、信条、信仰、感情に対する社会の受け止め方に何らかの変化があるとしても、それを理由として法制度を立法することはできないのであり、そのような特定の思想、信条、信仰、感情に対する社会の受け止め方によって、法規範の意味や内容が変動するような解釈を行うことはできない。
そのため、「現段階において、」などと、将来的に「性愛」という特定の思想や信条、信仰、感情を保護することを目的とした法制度を立法することが可能となる余地があるかのような理解をしているとすれば、誤りである。
また、ここでは「同性愛に対する差別・偏見を解消しようとする動き、」と解釈の変更の可能性を論じていることから、現在の婚姻制度が「性愛」の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的としており、その中でも特に「異性愛」という思想、信条、信仰、感情を保護することを目的としているかのような前提を持ち、それと比較する形で「同性愛」の思想、信条、信仰、感情を取り上げようとするものとなっている。
しかし、そもそも法学的な意味の「婚姻」は、法制度であることから、思想、信条、信仰、感情に対しては中立的な内容でなければならないのであり、「性愛」という特定の思想、信条、信仰、感情を保護することはできないことから、現在の婚姻制度が「性愛」の思想、信条、信仰、感情を保護する制度であるのように考えていることが誤りであるし、その中でも特に「異性愛」という思想、信条、信仰、感情を対象とするものとなっているかのような理解も誤りである。
このような誤った前提で現在の法制度を見てしまっていることが原因となって、「現段階において、」のように解釈を変更する余地を示す書きぶりも誤った理解を基にするものとなっている。
「憲法24条の「婚姻」について、これに同性間の婚姻を含まないという前記ウの解釈が不当であり解釈を変更すべき状態となっているものということはできない。」との部分について検討する。
まず、「同性間の婚姻を含まない」との部分であるが、ここでは「同性間の婚姻」のように、あたかも「同性間」の人的結合関係を「婚姻」として扱うことができるかのような前提の下に論じている。
しかし、「婚姻」は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として「生殖と子の養育」の観点から、他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた枠組みである。
そのため、「婚姻」の目的との整合性の観点から、「婚姻」の中に含めることのできる人的結合関係の範囲には内在的な限界が存在し、「婚姻」の中に含めることのできる人的結合関係と、含めることができない人的結合関係とが区別されることになる。
そして、「同性間」の人的結合関係については、一般的・抽象的にその間で「生殖」を想定することができないため、「生殖と子の養育」の趣旨を満たすとはいえず、「婚姻」の中に含めることができないと考えられる。
このことから、このような「婚姻」の概念そのものに含まれた内在的な限界を検討することもなく、「同性間の婚姻」というように「同性間」の人的結合関係を「婚姻」として扱うことができることを前提とした論じ方をしている点は妥当でない。
また、「解釈を変更すべき状態となっているものということはできない。」との部分についても、「憲法24条の「婚姻」」の中に「同性間」の人的結合関係を含めることができるかのように論じている点で、妥当でない。
オ また、原告らは、憲法が婚姻制度について要請した核心部分は、望む相手と両当事者の合意のみに基づいて婚姻が成立するという点であるから、婚姻の自由は同性間の婚姻についても保障される旨主張する。
【筆者】
この文の「憲法が婚姻制度について要請」の部分や、「望む相手と両当事者の合意のみに基づいて婚姻が成立する」の部分が示している「婚姻制度」や「婚姻」の意味を明らかにする必要がある。
まず、「婚姻」は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として、他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた枠組みである。
そのため、「婚姻」には「生殖と子の養育」の趣旨が含まれており、これを切り離して「婚姻」を観念することはできない。
そして、この文がいう「憲法が婚姻制度について要請」するものがあるとしても、それは「婚姻」であることを前提としているのであり、「婚姻」が有している「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を離れて何らかの「要請」が優先されるというような性質のものではない。
また、「望む相手と両当事者の合意のみに基づいて婚姻が成立する」の部分についても、「婚姻が成立する」ということから、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的とした制度を利用する者としての関係が「成立する」ということを意味するのであり、この「婚姻」の有する「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的による制度の枠組みを離れる形で「望む相手と両当事者の合意のみに基づい」た何か別の法的な効果が成立するという性質のものではない。
「婚姻の自由は同性間の婚姻についても保障される旨主張する。」との部分についても、そもそも「婚姻」それ自体が、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として「生殖と子の養育」の観点から他の人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度であり、「婚姻」それ自体であることによって「生殖と子の養育」の趣旨を満たさない人的結合関係を「婚姻」とすることはできないという内在的な限界があるのであり、この趣旨を満たさない「同性間」の人的結合関係については、「婚姻」として扱うことができないと考えられる。
そのため、ここでいう「婚姻の自由」(最高裁判決では『婚姻をするについての自由』と表現されることがある)についても、常に「婚姻」が「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として設けられた制度であり、「生殖と子の養育」の趣旨を満たす人的結合関係を対象とするものとして形成されている背景を離れては観念することができないのであり、「同性間」の人的結合関係については対象となっていないものと考えられる。
よって、この文では「婚姻の自由は同性間の婚姻についても保障される」という文となっているが、そもそも「同性間」の人的結合関係は「婚姻」とすることはできないし、ここでいう「婚姻の自由」(最高裁判決のいう『婚姻をするについての自由』にあたるものと思われる。)についても、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として「生殖と子の養育」の観点から他の人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度の枠組みを利用するか否かに関する自由をいうものであるから、「同性間」の人的結合関係に対して何らかの法的な効果を及ぼすものとして用いることができるという性質のものではない。
そのため、複数ヵ所の誤りによって、文の意味そのものが成り立っていないことになる。
憲法制定時に明治民法による家制度の廃止が議論され、婚姻について戸主等による同意を要するものとせず、両当事者の合意のみによって成立することとされたことは原告ら主張のとおりであるが、その前提として、婚姻は、その社会において「婚姻」とする旨の承認を得た人的結合関係をいうものと解されるところ、同性間の婚姻について、現段階において、このような社会における承認があるとまでは認められないことは前述のとおりである。したがって、原告らの主張はその前提を欠き、採用することができない。
【筆者】
「婚姻は、その社会において「婚姻」とする旨の承認を得た人的結合関係をいうものと解されるところ、同性間の婚姻について、現段階において、このような社会における承認があるとまでは認められない」との記載がある。
この「その社会において「婚姻」とする旨の承認を得た人的結合関係をいうもの」の部分であるが、その背景には「目的」と「その目的を達成するための手段」としての枠組みがあると考えられる。
その「目的」や「その目的を達成するための手段」を検討することなく、「承認」の存否のみを国民意識などの漠然としたものを根拠とすることになってはならない。
「現段階において、このような社会における承認があるとまでは認められない」の部分についても、「社会における承認」の存否ではなく、「婚姻」という概念が形成される際の「目的」と「その目的を達成するための手段」となる枠組みの問題として根拠を捉えることが必要である。
カ 以上によれば、憲法24条の「婚姻」に同性間の婚姻を含むものと解することはできず、憲法24条1項が同性間の婚姻に関する立法に関して当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられることとすることを要請したものと解することはできない。
【筆者】
「憲法24条の「婚姻」に同性間の婚姻を含むものと解することはできず、」との記載がある。
この「同性間の婚姻」との文言は、あたかも「婚姻」の中に「同性間」の人的結合関係を含めることができるかのような前提で論じるものとなっている。
しかし、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で、「男性」と「女性」の組み合わせを一定の枠組みによって結び付けるものとして「婚姻」という概念が形成されていることから、「同性間」の人的結合関係を「婚姻」として扱うことはできないと考えられる。
また、「憲法24条の「婚姻」に同性間の婚姻を含むものと解すること」ができるか否かという視点となっているが、憲法24条は「婚姻」を規定しており、日本法における「婚姻」という概念はすべて24条の「婚姻」を意味するものであるから、この24条を離れて「婚姻」を立法することはできない。
憲法24条は「婚姻」の内容を24条の統制が及ぶように求める規定であり、法律上で24条の「婚姻」が及ばない形で「婚姻」と称する制度を定めようとした場合には、24条の「婚姻」に抵触して違憲となる。
そのため、「憲法24条の「婚姻」」と、憲法24条に基づかない別の「婚姻」と称する制度が併存することはあり得ない。
このことから、「憲法24条の「婚姻」に同性間の婚姻を含むものと解することはできず、」との部分については、あたかも憲法24条を離れた別の形式として存在する「同性間の婚姻」という制度が存在することを前提として、それを「憲法24条の「婚姻」」の中に含めることができるか否かという視点から論じているように見受けられるが、そもそも「憲法24条の「婚姻」」が「異性間」に限られている以上は、それ以外の形式の「婚姻」と称する制度が「憲法24条の「婚姻」」の下で存在することはできない。
よって、「憲法24条の「婚姻」」の中に「同性間の人的結合関係」を含めることができるか否かという視点の議論をしようとしているのであればこの文の意味としては理解することが可能であるが、「憲法24条の「婚姻」」を離れて別の法形式として「婚姻」と称する制度が存在することを前提として、その中の一つである「同性間の婚姻」という制度を「憲法24条の「婚姻」」の中に含めることができるか否かという視点で論じているのであれば、誤りである。
「憲法24条1項が同性間の婚姻に関する立法に関して当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられることとすることを要請したものと解することはできない。」との記載がある。
「同性間の婚姻」という言葉についてはそもそも「婚姻」の意味と両立しない表現となるとため、妥当でない。
ただ、この文の全体の意味は、その通りであると考える。
したがって、婚姻を異性間のものに限り同性間の婚姻を認めていない本件諸規定が憲法24条1項に違反するとはいえない。
⑵ 憲法14条1項適合性について
ア 憲法14条1項は、法の下の平等を定めており、事柄の性質に応じた合理的な根拠に基づくものでない限り、法的な差別的取扱いを禁止する趣旨であると解すべきである(最高裁昭和37年(オ)第1472号同39年5月27日大法廷判決・民集18巻4号676頁、最高裁昭和45年(あ)第1310号同48年4月4日大法廷判決・刑集27巻3号265頁、平成27年再婚禁止期間大法廷判決、平成27年夫婦同氏制大法廷判決等参照)。
【筆者】
ここで示された判決は、下記の通りである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
……(略)……しかし、右各法条は、国民に対し絶対的な平等を保障したものではなく、差別すべき合理的な理由なくして差別することを禁止している趣旨と解すべきであるから、事柄の性質に即応して合理的と認められる差別的取扱をすることは、なんら右各法条の否定するところではない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
最高裁昭和39年5月27日大法廷判決 (PDF)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
よつて案ずるに、憲法一四条一項は、国民に対し法の下の平等を保障した規定であつて、同項後段列挙の事項は例示的なものであること、およびこの平等の要請は、事柄の性質に即応した合理的な根拠に基づくものでないかぎり、差別的な取扱いをすることを禁止する趣旨と解すべきことは、当裁判所大法廷判決(昭和三七年(オ)第一四七二号同三九年五月二七日・民集一八巻四号六七六頁)の示すとおりである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
最高裁昭和48年4月4日大法廷判決 (PDF)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1 憲法14条1項は,法の下の平等を定めており,この規定が,事柄の性質に応じた合理的な根拠に基づくものでない限り,法的な差別的取扱いを禁止する趣旨のものであると解すべきことは,当裁判所の判例とするところである(最高裁昭和37年(オ)第1472号同39年5月27日大法廷判決・民集18巻4号676頁,最高裁昭和45年(あ)第1310号同48年4月4日大法廷判決・刑集27巻3号265頁等)。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
平成27年再婚禁止期間大法廷判決 (PDF)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2 憲法14条1項は,法の下の平等を定めており,この規定が,事柄の性質に応じた合理的な根拠に基づくものでない限り,法的な差別的取扱いを禁止する趣旨のものであると解すべきことは,当裁判所の判例とするところである(最高裁昭和37年(オ)第1472号同39年5月27日大法廷判決・民集18巻4号676頁,最高裁昭和45年(あ)第1310号同48年4月4日大法廷判決・刑集27巻3号265頁等)。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
平成27年夫婦同氏制大法廷判決等 (PDF)
この14条の「平等原則」を判断する際に必要となる視点は、下記の通りである。
◇ 「法適用の平等」と「法内容の平等」の違い
14条の「平等原則」における審査では、「法適用の平等」と「法内容の平等」を分けて考える必要がある。
【動画】シンポジウム 国葬を考える【The Burning Issues vol.27】 2022/09/25
◇ 「法内容の平等」の審査
「法内容の平等」については、➀「区別(差別)」の存否と、②「区別(差別)」が存在した場合における「合理的な理由」の存否が問われることになる。
そして、②の「合理的な理由」の内容については、「立法目的」とその「達成手段」が問われることになる。
➀ 「区別(差別)」が存在するか否か
② 「区別(差別)」が存在する場合にその区別に「合理的な理由」が存在するか
「合理的な理由」の判断方法
・「立法目的」の合理性
・「立法目的を達成するための手段」の合理性
この判決の内容は、➀の「区別取扱い」が存在するか否かという判断から誤っているため、②の判断を行おうと試みている論旨についても、全面的に誤っている。
もう一つ、14条の「平等原則」の審査を行う際に、日常用語として使われる「差別であるか否か」という議論の仕方とは明確に切り離して考える必要があることに注意が必要である。
日常用語として「差別」の言葉が使われた場合には、何らかの否定的な意味を背負っていることが多い。
そのため、この「差別」という言葉の使われ方は、既に「合理的な理由」がないという結論を示すものであることが前提となっている。
しかし、憲法14条の「平等原則」を審査する際に使われている「差別」の意味は、何らかの違いを見出して異なるものに分けている状態を指しているだけである。
ここには否定的な意味合いを含んでおらず、「区別」の文言と全く同様の意味で使われている。
そのため、その「差別=区別」の内容が「合理的な理由」に基づくものであるか否かがさらに検討されなければ、未だに結論を示すものではないのである。
・日常用語:「差別」⇒「合理的な理由」のない区別があるという結論
・法的判断:「差別」⇒何らかの区別があるという状態
→さらに「合理的な理由」があるかを審査しなければ結論の当否は分からない
このことから、14条についての法的な審査の際には、日常的に使われる「差別であるか否か」が問われているのではなく、「差別(区別)が存在する場合に、そこに合理的な理由があるか否か」が問われていることになる。
この点、この判決は「イ(ア)」や「イ(イ)」の部分で「性的指向による区別取扱いに当たるものと認められる。」と述べながら(筆者はこの判断は誤っていると考えている)、「イ(イ)ウ」の部分では「性的指向による差別に当たるとして、憲法14条1項に違反するとはいえない。」という説明をしており、混乱したものとなっている。
・「イ(ア)」:「性的指向による区別取扱いに当たるものと認められる。」
・「イ(イ)」:「性的指向による区別取扱いに当たるものと認められる。」
・「イ(イ)ウ」:「性的指向による差別に当たるとして、憲法14条1項に違反するとはいえない。」
前提として「区別取扱いに当たる」と述べながら、「差別に当たるとして、憲法14条1項に違反するとはいえない。」と述べることは、法的な判断において「区別」と「差別」の意味が同じであることを押さえれば、矛盾したことを述べているように見えるのである。
これは、「イ(イ)ウ」で使われている「差別」の文言が、法的な判断において使われる「差別」の意味ではなく、日常用語として使われる「差別」の意味で使われていることが原因である。
このように、この判決は法的な判断における「差別」の言葉の使い方を理解しておらず、不当な内容となっている。
また、前記⑴イで述べたとおり、憲法24条2項は、婚姻及び家族に関する事項について、具体的な制度の構築を第一次的に国会の合理的な立法裁量に委ねるとともに、その立法に当たっては、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきであるとする要請、指針を示すことによって、その裁量の限界を画したものであるから、婚姻及び家族に関する事項についての区別取扱いについては、立法府に与えられた上記の裁量権を考慮しても、そのような区別をすることに合理的な根拠が認められない場合には、当該区別は、憲法14条1項に違反するものということができる(最高裁平成24年(ク)第984号、第985号同25年9月4日大法廷決定・民集67巻6号1320頁参照)。
【筆者】
ここに記載された「前記⑴イ」とは、「平成27年再婚禁止期間大法廷判決」と「平成27年夫婦同氏制大法廷判決」を基にして説明しようとしている部分のことである。(ただ、この東京地裁判決のする最高裁判決の引用は正確な引用となっていないことに注意。)
そして、この文は、その「前記⑴イ」に記している文章から、「憲法24条2項は、」と「婚姻及び家族に関する事項について、具体的な制度の構築を第一次的に国会の合理的な立法裁量に委ねるとともに、その立法に当たっては、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきであるとする要請、指針を示すことによって、その裁量の限界を画したもの」という文を抜き出したものとなっている。
この東京地裁判決の引用しようとしている本来の「平成27年再婚禁止期間大法廷判決」と「平成27年夫婦同氏制大法廷判決」では、下記のように述べられている部分である。
同様の文言を灰色で塗りつぶした。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
……(略)……憲法24条2項は,このような観点から,婚姻及び家族に関する事項について,具体的な制度の構築を第一次的には国会の合理的な立法裁量に委ねるとともに,その立法に当たっては,個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきであるとする要請,指針を示すことによって,その裁量の限界を画したものといえる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「平成27年再婚禁止期間大法廷判決」 (PDF)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
婚姻及び家族に関する事項は,関連する法制度においてその具体的内容が定められていくものであることから,当該法制度の制度設計が重要な意味を持つものであるところ,憲法24条2項は,具体的な制度の構築を第一次的には国会の合理的な立法裁量に委ねるとともに,その立法に当たっては,同条1項も前提としつつ,個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきであるとする要請,指針を示すことによって,その裁量の限界を画したものといえる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「平成27年夫婦同氏制大法廷判決」 (PDF)
「前記⑴イで述べたとおり、」で述べた部分に対応するものはここまでであり、その後、この東京地裁判決の「であるから、」の文言以下は、これらの判決に対応するものではない。
「婚姻及び家族に関する事項についての区別取扱いについては、立法府に与えられた上記の裁量権を考慮しても、そのような区別をすることに合理的な根拠が認められない場合には、当該区別は、憲法14条1項に違反するものということができる」との部分を検討する。
まず、「同性間の人的結合関係」については、「婚姻」ではないし、「親子」や、「親子」を基本とした関係である「兄弟」「姉妹」などに当てはまらないのであれば、「婚姻及び家族に関する事項」には含まれない。
そのため、「婚姻及び家族に関する事項についての区別取扱い」のように、「婚姻及び家族に関する事項」に含まれることを前提として「区別取扱い」の合理性を判断できるかのように述べている部分から誤っていると考えられる。
イ(ア) 原告らは、本件諸規定は性的指向によって婚姻の可否について区別取扱いを行うものであると主張する。
【筆者】
まず、婚姻制度は「性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、「性愛」を有するか否かや「性愛」を有するとされた場合に「性愛」の向かう対象を審査して区別取扱いを行うものではないし、「性愛」に基づいて「婚姻」することを求めるものでも、勧めるものでもない。
そのため、「性的指向」と称するものの存否など、一切関知していないのであり、「性的指向」によって区別取扱いをしているという事実はない。
よって、「性的指向によって婚姻の可否について区別取扱いを行うものである」との認識は、事実誤認である。
この点、国(行政府)は下記のように述べている。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
……(略)……本件規定は,制度を利用することができるか否かの基準を,具体的・個別的な婚姻当事者の性的指向の点に設けたものではなく,本件規定の文言上,同性愛者であることに基づく法的な差別的取扱いを定めているものではないから,この点に法令上の区別は存在しない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【東京・第6回】被告第4準備書面 PDF (P17)
また、「性愛」という特定の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的として法制度を立法した場合には、その法制度は20条1項後段・3項、89条の「政教分離原則」に抵触して違憲となる。
よって、もし婚姻制度の内容が「性的指向によって婚姻の可否について区別取扱いを行うもの」であった場合には、そもそも「性的指向」以前に、「性愛」という特定の思想、信条、信仰、感情を法制度によって保護しようとしていることそのものが20条1項後段、3項、89条の「政教分離原則」に抵触して違憲となる。
また、「性愛」ではなく、「恋愛」、「友愛」、「友情」、「兄弟姉妹愛」、「親子愛」、「慈悲」、「御心」などの思想、信条、信仰、感情や、その他あらゆる思想、信条、信仰、感情との間で14条の「平等原則」に抵触して違憲となる。
よって、「性的指向」による「区別取扱い」の存否を問うことそのものが、「性愛」という特定の価値観のみを強調する形で独自の主張を行っているに過ぎないのであって、法制度を論じる法解釈の場面では、そのような主張を取り上げることはできないし、その当否を論じることもできない。
本件諸規定は、性的指向が異性愛であることを婚姻の要件としたものではないが、婚姻を異性間のものに限ることによって、実質的には同性愛者の婚姻を不可能とする結果を生ぜしめているから、性的指向による区別取扱いに当たるものと認められる。
【筆者】
「本件諸規定は、性的指向が異性愛であることを婚姻の要件としたものではないが、」との部分について検討する。
まず、婚姻制度は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度である。
そして、その立法目的には下記を挙げることができる。
〇 「子の福祉」が実現される社会基盤を構築すること
(→ 達成手段:嫡出子として生まれることの重視)
〇 遺伝的な劣勢を有する個体が高い確率で発現することを抑制すること
(→ 達成手段:父親と近親者を特定して『近親交配』を防ぐ仕組みを導入)
〇 「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」を減らすこと
(→ 達成手段:未婚の男女の数の不均衡の防止。一夫一婦制、複婚の禁止)
〇 母体を保護すること
(→ 達成手段:婚姻適齢)
これらの目的を達成するための手段として、「男女二人一組」の婚姻制度が定められているものであり、何らかの思想、信条、信仰、感情を保護する目的を有するものではない。
また、個々人の内心に踏み込むものではなく、制度を利用する際に特定の思想、信条、信仰、感情を有することを求めるものでも、勧めるものでもない。
そのことから、個々人がどのような内心を有しているとしても、制度上の要件を満たした上で、その制度を利用する意思があれば、その制度を利用することが可能である。
ここで述べられている「性的指向が異性愛であることを婚姻の要件としたものではないが、」の部分の意味は、「が、」という逆説の接続を使って後に何かを否定しようとしていること以外は、その通りということができる。
つまり、法制度は、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にどのような対象に向かうかなどの個々人の内心に対しては中立的であり、「婚姻の要件」は「異性愛者」と称する者であるかなど、一切関知していないし、制度を利用する場合に「異性愛」の思想、信条、信仰、感情を抱いていることを求めるものでも、勧めるものでもない。
そのため、「同性愛者」を称する者も、「両性愛者」を称する者も、「全性愛者」を称する者も、「多性愛者」を称する者も、「小児性愛者」を称する者も、「老人性愛者」を称する者であっても、「死体性愛者」を称する者も、「動物性愛者」を称する者も、「対物性愛者」を称する者も、「対二次元性愛者」を称する者も、「無性愛者」を称する者も、「キリスト教徒」を称する者も、「イスラム教徒」を称する者も、「ユダヤ教徒」を称する者も、「ゾロアスター教徒」を称する者も、「仏教徒」を称する者も、「神道を信じる者」を称する者も、「武士道を重んじる者」を称する者も、「軍事オタク」を称する者も、「鉄道オタク」を称する者も、「アニメオタク」称する者も、「アイドルオタク」を称する者も、「ADHD」を称する者も、「アスペルガー」を称する者も、「自閉症」を称する者も、「サイコパス」を称する者も、「統合失調症」を称する者も、婚姻制度を利用することが可能である。
「性的指向が異性愛であることを婚姻の要件としたものではない」との部分までは、このような意味で正しいということができる。
「婚姻を異性間のものに限ることによって、実質的には同性愛者の婚姻を不可能とする結果を生ぜしめているから、」との部分があるが、誤りである。
まず、先ほども述べたように、婚姻制度は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度である。
そして、個々人の内心に踏み込むものではないことから、個々人がどのような思想、信条、信仰、感情を有していようとも、婚姻制度の要件を満たし、婚姻意思を有しているのであれば、婚姻制度を利用することが可能である。
そのため、婚姻制度の内容が「異性間のもの」(男女二人一組)の制度となっているとしても、その制度を利用する際に求められる要件を満たし、その制度を利用する意思を有しているのであれば、適法に「婚姻」することが可能であり、「同性愛者」を称する者も、「両性愛者」を称する者も、「全性愛者」を称する者も、「多性愛者」を称する者も、「小児性愛者」を称する者も、「老人性愛者」を称する者であっても、「死体性愛者」を称する者も、「動物性愛者」を称する者も、「対物性愛者」を称する者も、「対二次元性愛者」を称する者も、「無性愛者」を称する者も、「キリスト教徒」を称する者も、「イスラム教徒」を称する者も、「ユダヤ教徒」を称する者も、「ゾロアスター教徒」を称する者も、「仏教徒」を称する者も、「神道を信じる者」を称する者も、「武士道を重んじる者」を称する者も、「軍事オタク」を称する者も、「鉄道オタク」を称する者も、「アニメオタク」称する者も、「アイドルオタク」を称する者も、「ADHD」を称する者も、「アスペルガー」を称する者も、「自閉症」を称する者も、「サイコパス」を称する者も、「統合失調症」を称する者も、適法に婚姻制度を利用することが可能である。
実際、ここで述べられているような「同性愛者」を称する者であるとしても、婚姻制度を利用している者もいる。
これを「婚姻を不可能とする」などと論じることは、「同性愛者」と称する者に対して現在の婚姻制度の法的効果を適用しないことを宣言するものであり、憲法14条の「平等原則」における「法適用の平等」に違反するものである。
「同性愛者」を称する者であるとしても、婚姻制度を利用することは可能であり、制度の要件を満たし、制度を利用する意思があれば、適法に制度を利用することができるのであり、「婚姻」は「可能」ということができる。
よって、「実質的には同性愛者の婚姻を不可能とする結果を生ぜしめている」との認識は誤りである。
「性的指向による区別取扱いに当たるものと認められる。」との記載があるが、誤りである。
「区別取扱い」の存否を判断する際の前提であるが、下記の点を押さえる必要がある。
① 「婚姻及び家族に関する事項」は、「性愛」を保護することを目的とした制度ではないこと。
② 「婚姻及び家族に関する事項」は、個々人の「性愛」の向かう対象である「性的指向」と称しているものを審査して「区別取扱い」を行っている事実はないこと。
③ 「婚姻及び家族に関する事項」は、個々人に対して「性愛」に応じて制度を利用することを求めるものでも、勧めるものでもないこと。
そのことから、この判決は「本件諸規定」が「婚姻を異性間のものに限ること」が、「性的指向による区別取扱いに当たるものと認められる。」と述べているが、そのような区別取扱いは存在しない。
そもそも、20条1項後段・3項、89条では「政教分離原則」を定めており、特定の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的すると法制度を立法してはならない。
また、憲法は19条で「思想良心の自由」、20条1項で「信教の自由」を定めており、法制度を立法する際には、個々人の内心を審査して区別取扱いをするような制度を創設することを許してはいない。
さらに、個々人の内心に基づいて区別取扱いを行うような制度は、14条の「平等原則」にも違反するため、そのような制度は立法してはならない。
そのため、個々人の内心に基づいて区別取扱いを行うような法制度が存在すれば、そのこと自体で違憲となる。
このことから、この判決は「性的指向による区別取扱いに当たるものと認められる。」と述べるのであるが、もし「性的指向」というような個々人の内心に属する「性愛」の思想、信条、信仰、感情などの向かう対象に基づいて人を異なるものに分類し、そのような内心による区別取扱いを行うことを認めるような法制度が存在すれば、そのこと自体が違憲となる。
また、この判決はこのような内心を審査して区別取扱いを行うことを認めるような法制度が存在しているとしても、それが許されるかのような前提で論じていること自体が違憲である。
よって、「性的指向」による「区別取扱い」は存在しないし、そのような「区別取扱い」をするような制度は憲法に違反するし、そのような「区別取扱い」を行う制度が存在していても許されるかのような解釈を行っているこの判決の内容も違憲である。
この判決には「性愛」に基づいて「婚姻」することが正しい価値観であるとする前提を有しているように見受けられる部分があるが、「性愛」に基づいて「婚姻」することは個々人の価値観に過ぎないのであり、それに対してどの程度の比重を置くかも、個々人によって異なるものである。
人によっては、婚姻制度の枠組みに従う形で存在する選択肢の中で、年齢、身長、体型、顔、血液型、家系、出身地、性格、趣味、学歴、職業、年収、宗教、相性診断などで相手を選択する者もいるのであり、それは個々人の自由の範囲のものである。
それにもかかわらず、「性愛」に基づいて「婚姻」することを勧めるような物言いは、特定の価値観に基づいて婚姻制度を利用することを推奨するものとなっているのであり、憲法20条1項後段・3項、89条の「政教分離原則」に抵触して違憲となる。
(イ) これに対し、被告は、本件諸規定は飽くまでも一人の男性と一人の女性の間の婚姻を定めるものにすぎず、本件諸規定の文言上も特定の性的指向を婚姻の成立要件等とするものではないから、性的指向による形式的不平等が存在するものではないと主張する。
【筆者】
この「被告」の主張の部分はその通りということができる。
婚姻制度は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として、「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係との間で区別する意味で設けられた制度であり、その内容が「一人の男性と一人の女性の間の婚姻を定めるもの」となっていることは、この目的を達成するための手段として妥当だからである。
この制度を利用する際に、個々人がどのような思想、信条、信仰、感情を抱いているかなど、法制度はまったく感知していないのであり、「本件諸規定の文言上も特定の性的指向を婚姻の成立要件等とするものではない」との理解は、その通りである。
また、法制度は思想、信条、信仰、感情に対して中立的な内容でなければならず、もし法制度が特定の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的として立法されたとすれば、そのこと自体が憲法20条1項・3項、89条の「政教分離原則」に抵触して違憲となる。
他にも、他の思想、信条、信仰、感情を抱く者との間でも、一方を優遇し、もう一方を優遇しないことになることから、憲法14条の「平等原則」に抵触して違憲となる。
そのため、「性愛」という特定の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的として法制度を立法することはできない。
また、法制度がその制度を利用する個々人の内心に踏み込んで、特定の思想、信条、信仰、感情を抱くことを求めるようなことがあれば、憲法19条の「思想良心の自由」に抵触して違憲となる。
他にも、特定の思想、信条、信仰、感情を抱く者であるかを審査して区別して扱うような制度を立法した場合には、憲法14条の「平等原則」に抵触して違憲となる。
よって、個々人の「性愛」の有無を審査したり、「性愛」を有する場合にどのような対象に向かうかという「性的指向」と称するものによって異なるものに区別して扱うような制度を立法することもしてはならない。
この点を押さえて考えることが必要である。
しかしながら、婚姻の本質は、当事者が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもって共同生活を営むことにあるところ、同性愛者にとっては、異性との婚姻はこのような婚姻の本質を伴ったものにはならないのであるから、形式的には異性との婚姻制度を利用することができたとしても、実質的には婚姻ができないことに等しい。そうすると、本件諸規定は、それ自体には性的指向についての要件等を設けておらず、性的指向について中立的な制度にはなっているものの、同性愛者が婚姻することを実質的には不可能としているものであり、このような効果は本件諸規定が婚姻を異性間のものに限っていることによって生じた結果であるといえるから、性的指向による区別取扱いに当たるものと認められる。この点の被告の主張は理由がない。
【筆者】
「婚姻の本質は、当事者が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもって共同生活を営むことにある」との記載がある。
この「婚姻の本質」と称する説明は何を根拠として導かれたものであるのかを検討する必要がある。
なぜならば、もし何らの根拠もなく、この判決を書いた裁判官が独断で決めているとすれば、別の裁判官が判決を下す時に「婚姻の本質は、子供を産むことにある」や「婚姻の本質は、一夫多妻である」、「婚姻の本質は、親の決めた相手と結ばれることである」と述べてしまえば、それが絶対的な定義となってしまうことを意味するのであり、妥当でないからである。
この「婚姻の本質」と称する説明は、下記の最高裁判決を参考としているように見受けられる。
しかし、最高裁判決をそのまま抜き出したものとはなっていないことに注意が必要である。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2 思うに、婚姻の本質は、両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもつて共同生活を営むことにあるから、夫婦の一方又は双方が既に右の意思を確定的に喪失するとともに、夫婦としての共同生活の実体を欠くようになり、その回復の見込みが全くない状態に至つた場合には、当該婚姻は、もはや社会生活上の実質的基礎を失つているものというべきであり、かかる状態においてなお戸籍上だけの婚姻を存続させることは、かえつて不自然であるということができよう。しかしながら、離婚は社会的・法的秩序としての婚姻を廃絶するものであるから、離婚請求は、正義・公平の観念、社会的倫理観に反するものであつてはならないことは当然であつて、この意味で離婚請求は、身分法をも包含する民法全体の指導理念たる信義誠実の原則に照らしても容認されうるものであることを要するものといわなければならない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
まず、この東京地裁判決の上記の「⑵ア」の所では「再婚禁止期間大法廷判決」や「夫婦同氏制大法廷判決」など具体的な裁判所の判例を引用する形で示しているにもかかわらず、この「婚姻の本質」と称する説明を持ちだす際には、そのような判例を引用していることを示していないことは不自然である。
この判決を書いた裁判官が何の根拠もなく独断で「婚姻の本質」と称する説明を展開しているのであれば、恣意的な意図をもって断定を行っているだけのものに過ぎないことになるため妥当でない。
次に、最高裁判決においては明確に「両性」と書かれているが、この東京地裁判決では「当事者」に変えられている。
この東京地裁判決が最高裁判決に示された文面を正確に引用していない背景には、この裁判官が「婚姻」の内容について「両性」という「男女」を意味する言葉を用いてその範囲が確定されている事実を意図的に排除することによって、「婚姻」が「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として設けられた枠組みであることを原因とした「婚姻」という概念そのものに含まれた内在的な限界を考慮することなく、それを超える人的結合関係を「婚姻」の中に含めるという特定の結論を導き出すために、恣意的に文言を変更している可能性が考えられる。
これは、そのような意図に基づいて最高裁判決に示された「両性」の文言を「当事者」という文言に変更しているのであれば、「婚姻」という概念そのものに含まれた内在的な限界を何ら考慮することなく恣意的な形で結論を導き出そうとする不正であるし、最高裁判決で用いられた文面の意味を改竄するものということができ、解釈の過程を誤った違法なものというべきである。
(このような文面の意味を勝手に変更する不正は、2014年7月1日閣議決定において、1972年〔昭和47年〕政府見解に示された「あくまで外国の武力攻撃によつて」という文言が「我が国に対する武力攻撃」の意味に限られているにもかかわらず、これを「他国に対する武力攻撃」の意味が含まれることを前提として「存立危機事態」での「武力の行使」を導きだそうとする違法な解釈過程にも共通するものである。詳しくは、当サイト「集団的自衛権行使の違憲審査」で解説している。)
法解釈は、論理的整合性の積み重ねによって結論を正当化することが可能となるのであり、解釈の過程で根拠となっている判例の文章の意味を読み替えたり、文言を勝手に変更したり、文章の内容を改竄することは、不正であり、違法な手続きということができる。
このような解釈の過程に不正、違法が含まれている場合には、根拠となっているもともとの条文や判例との間で完全に断絶するものとなるのであり、その結論は正当化することはできないことになる。
よって、この判決が「婚姻の本質」と称している説明を根拠として、何らかの解釈を行おうとしても、もともとの「婚姻の本質」と称している説明そのものが、具体的な条文やそれを基にして示された最高裁判決の文面の意味や内容から切り離された不当な内容であることになるから、それを根拠とした解釈や判断の枠組みについても、正当化することができないことになる。
下記の記事でも、最高裁判決では「両性」と示されていることや、「夫婦」の文言を前提としているものであることが説明されている。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
もっとも昭和62年9月2日の最高裁大法廷判決は、「婚姻の本質は、両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもつて共同生活を営むこと」としているが、この定義に続いて「夫婦」の言葉も見え、最高裁は、男女のカップルの共同生活を「婚姻」としているように読める〔最高裁判所大法廷 昭和61年(オ)260号 判決〕。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
生殖可能性のない同性婚を法律で認める理由はない…憲法学の専門家が「同性婚の法制化」にクギを刺す理由 2023/02/18
この東京地裁判決が上記の最高裁判決を参考にしているのであれば、そこには明確に「両性」と書かれており、「婚姻の本質」の意味についても「男女」であることを前提としているものである。
三つ目に、この最高裁判決が「婚姻の本質は、両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもつて共同生活を営むことにある」と説明している根拠を検討する。
先ほども述べたように、もし最高裁判所の裁判官が何らの根拠もなく独断で決めているとすれば、法の支配、法治主義を逸脱することになって妥当でないからである。
・ 「両性」との部分は、現在の婚姻制度が「男性」と「女性」が必要であることを要件としていることから導かれたものと考えられる。
・ 「永続的な」との部分は、現在の婚姻制度には有効期限がなく、利用者が死亡するまで利用することができるという点から導かれたものと考えられる。
もし婚姻制度が改正されて有効期限が定められることがあるとすれば、この「永続的な」との説明は根拠を失ってなくなることになる。
・ 「精神的及び肉体的結合を目的として」との部分は、現在の婚姻制度が相互の協力を求めていることや、「貞操義務」があることから導かれたものと考えられる。
憲法
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
② (略)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
民法
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
このように、「貞操義務」のある制度を読み解くことによって「肉体的結合」と表現しているのであり、もし「貞操義務」がなければ「肉体的結合」という表現は導かれないことになる。
・ 「共同生活を営む」との部分は、現在の婚姻制度が「同居義務」を定めていることから導かれているものと考えられる。
民法
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(同居、協力及び扶助の義務)
第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
このように、最高裁判決の示す「婚姻の本質」と称する説明は、立法目的を達成するための手段として設けられた具体的な婚姻制度の枠組みが存在することを前提とし、その婚姻制度を利用する者の間で生じる法律関係について示されているものである。
立法目的:国の立法目的
↓
達成手段:婚姻制度の枠組み
↓
法律関係:「婚姻の本質」と称する説明
この「婚姻の本質」と称する説明は、具体的な婚姻制度の枠組みが存在することに依存して、その法律関係を示すために導かれた説明であることから、婚姻制度が形成される際の「国の立法目的」を説明したものとは異なる。
よって、「婚姻の本質」と称する説明が、具体的な婚姻制度の上位概念として存在するわけではないし、婚姻制度を構築する際の「国の立法目的」を示したものでもない。
そのため、この「婚姻の本質」として説明されているものを根拠として具体的な婚姻制度の枠組みを変更するための根拠とすることはできず、同性間の人的結合関係を「婚姻」として扱うことができるか否かを判断するための基準とすることができる性質のものではない。
「同性愛者にとっては、異性との婚姻はこのような婚姻の本質を伴ったものにはならないのであるから、」との部分について検討する。
まず、「婚姻の本質」の意味は、上記のように、憲法が要請する「婚姻」についての具体的な法制度が存在することを前提として、その婚姻制度を利用する者の間に生じる法的な権利・義務関係の結び付きによる法律関係の状態を説明するものであることから、「同性愛者」と称する者であっても、婚姻制度(男女二人一組/ここでいう『異性との婚姻』)を適法に利用しているのであれば、婚姻制度の下で完全な法律関係を形成することが可能であり、「婚姻の本質」を「伴ったもの」になるということができる。
これについては、たとえ「両性愛者」を称する者であっても、「全性愛者」を称する者であっても、「近親性愛者」を称する者であっても、「小児性愛者」を称する者であっても、同様である。
婚姻制度は個々人の「内心の自由」に対して中立的な内容であり、思想や信条、信仰、感情によって法律関係の内容が変動するような性質のものではないからである。
よって、「同性愛者にとっては、異性との婚姻はこのような婚姻の本質を伴ったものにはならない」などと、「同性愛者」を称する者が婚姻制度を利用する際に、「婚姻の本質を伴ったものにはならない」などと、法的な権利・義務の結び付きによる法律関係を形成することができないかのような説明を行うことは、誤りである。
法制度はその内心を審査して区別取扱いをすることはないのであり、「同性愛者」を称する者であるとしても、婚姻制度(男女二人一組)を利用することによって形成される「両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもつて共同生活を営むこと」という法律関係を完全に形成することが可能である。
具体的には、
・ 「同性愛者」を称する者であるとしても、「両性」である「男女」の間で婚姻制度(男女二人一組)を適法に利用することが可能である。
・ 「同性愛者」を称する者であるとしても、「永続的な」という死亡するまで有効期限のない婚姻制度(男女二人一組)を適法に利用することが可能である。
・ 「同性愛者」を称する者であるとしても、「精神的及び肉体的結合を目的」の意味である「相互の協力」や「貞操義務」のある婚姻制度(男女二人一組)を適法に利用することが可能である。
・ 「同性愛者」を称する者であるとしても「共同生活を営む」の意味である「同居義務」のある婚姻制度(男女二人一組)を適法に利用することが可能である。
いたずらに個々人の「内心の自由」に属する思想や信条、信仰、感情の一つに過ぎない「同性愛」を取り上げ、それを抱く者を「同性愛者」として区別し、その「同性愛者」を称する者が婚姻制度(男女二人一組)を利用しようとしているにもかかわず、「婚姻の本質を伴ったものにはならない」などと、法的な権利・義務の結び付きによる適法な法律関係を形成することができない人物であるかのように扱うことは、憲法14条の「平等原則」における「法適用の平等」に違反する判断に他ならない。
この判決が「同性愛者」を称する者に対して、「婚姻の本質を伴ったものにはならない」などと婚姻制度が適用される主体として認めないことは、「同性愛者」を称する者に対して「権利能力」を剥奪するものということができる。
このような判断を行ったことは、憲法19条の「思想良心の自由」、20条の「信教の自由」、14条の「平等原則」にも抵触して違憲となる。
「形式的には異性との婚姻制度を利用することができたとしても、実質的には婚姻ができないことに等しい。」との部分について検討する。
婚姻制度は「性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」を審査して区別取扱いをするものではないし、「性愛」に基づいて婚姻制度を利用することを求めるものでも、勧めるものでもない。
そのため、婚姻制度(男女二人一組)を適法に利用する意思があるのであれば、「同性愛者」を称する者であっても完全に「婚姻」することができるのであり、「実質的」な「婚姻」は可能である。
実際に「同性愛者」を称する者であっても、婚姻制度(男女二人一組)を利用している者もいるのであり、その者が「実質的」に「婚姻」していないと考えることは、「同性愛者」を称する者に対して法制度の適用を阻害しようとする試みということができ、憲法14条の「平等原則」に違反するものである。
「形式的」に婚姻制度を利用している外形が認められるとしても、「実質的」に「婚姻」していないという場合は、書面上は婚姻制度を利用するために必要となる要件を満たしているが、当事者間に「婚姻意思」が存在しない場合のことである。
このような場合には、「形式的」に婚姻制度を利用するために必要となる要件を満たしているとしても、「婚姻」が無効となる場合が考えられる。
しかし、「同性愛者」を称する者が適法に婚姻制度を利用する意思を有し、婚姻制度を利用するために必要となる要件を満たした上で、「婚姻」しているにもかかわらず、その「婚姻」が「実質的には婚姻ができない」などと、婚姻制度の適用を否定するかのような言説を持ちだすことは、「同性愛者」を称する者が適法に婚姻制度を利用している状態の「婚姻意思」を否定するものであり、明らかに不当である。
「同性愛者」を称する者も、「両性愛者」を称する者も、「全性愛者」を称する者も、「多性愛者」を称する者も、「小児性愛者」を称する者も、「老人性愛者」を称する者であっても、「死体性愛者」を称する者も、「動物性愛者」を称する者も、「対物性愛者」を称する者も、「対二次元性愛者」を称する者も、「無性愛者」を称する者も、日本法の下で婚姻制度を利用するために必要となる要件を満たして適法に婚姻制度を利用する意思を有しているのであれば、「実質的」に「婚姻」することは可能であり、完全な法律関係を形成することができるのである。
このことは、「キリスト教徒」を称する者も、「イスラム教徒」を称する者も、「ユダヤ教徒」を称する者も、「ゾロアスター教徒」を称する者も、「仏教徒」を称する者も、「神道を信じる者」を称する者も、「武士道を重んじる者」を称する者も、同様である。
さらに、「軍事オタク」を称する者も、「鉄道オタク」を称する者も、「アニメオタク」称する者も、「アイドルオタク」を称する者も、同様である。
個々人の「内心の自由」に属する思想や信条、信仰、感情に基づいて法律関係を形成することが「実質的」に可能か否かを区別して取扱うことができるかのような説明は、法解釈として誤っている。
「本件諸規定は、それ自体には性的指向についての要件等を設けておらず、性的指向について中立的な制度にはなっているものの、同性愛者が婚姻することを実質的には不可能としているものであり、このような効果は本件諸規定が婚姻を異性間のものに限っていることによって生じた結果であるといえるから、性的指向による区別取扱いに当たるものと認められる。」との記載がある。
まず、「本件諸規定は、それ自体には性的指向についての要件等を設けておらず、」との部分を検討する。
憲法は20条1項後段・3項、89条で「政教分離原則」を定めている。
また、19条で「思想良心の自由」、20条1項前段で「信教の自由」を定めており、14条で「平等原則」を定めている。
そのことから、法制度が特定の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的として立法された場合には、違憲となる。
また、個々人の内心に属する思想、信条、信仰、感情を審査して区別するような制度を立法した場合には、違憲となる。
そのため、「性愛」という思想、信条、信仰、感情を保護することを目的として法制度を立法することはできないし、個々人の「性愛」の有無を審査したり、「性愛」を有する場合にどのような対象に向かうかという「性的指向」と称するものに応じて区別するような制度を立法してはならない。
そのため、「性的指向についての要件等を設けておらず、」との部分は、法制度が憲法に違反しないために必要となるものである。
次に、「性的指向について中立的な制度にはなっているものの、」との部分を検討する。
これについても、法制度は特定の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的として立法してはならないし、個々人がどのような思想、信条、信仰、感情を有するかを審査したり、区別して取扱ってはならないことから、思想、信条、信仰、感情に対して「中立的な制度」となっていることは、憲法に違反しないために必要となるものである。
三つ目に、「同性愛者が婚姻することを実質的には不可能としているものであり、」との部分を検討する。
まず、婚姻制度は「性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」を審査して区別取扱いをするものではないし、「性愛」に基づいて婚姻制度を利用することを求めるものでも、勧めるものでもない。
そのため、「性愛」の思想、信条、信仰、感情を抱いて婚姻制度を利用することに価値を見出すかどうかは、個々人の価値観によるものに過ぎない。
そのことから、上記の「婚姻の本質」の所でも述べたが、「同性愛者」を称する者であるとしても、「両性」という「男女」の間で、「永続的な」という死亡するまで有効期限のない、「精神的及び肉体的結合を目的」という「相互の協力」や「貞操義務」を負う、「共同生活を営む」という「同居義務」を伴う法制度を適法に利用することができるのであり、「婚姻すること」は「実質的」に「可能」である。
「同性愛者」と称する者についても、婚姻制度を利用する際には完全な法律関係を形成することができるのである。
これをこの判決は「同性愛者が婚姻することを実質的には不可能としている」などと述べるのであるが、個々人の「内心の自由」に属する思想や信条、信仰、感情に基づいて「同性愛者」と称する者が婚姻制度を利用することを「実質的には不可能」などと、その法的な地位を剥奪するような説明となっており、不当である。
「同性愛者」と称している者であるとしても、「男女二人一組」の婚姻制度を利用している事実は存在するのである。
四つ目に、「このような効果は本件諸規定が婚姻を異性間のものに限っていることによって生じた結果であるといえるから、」との部分を検討する。
まず、「同性愛者」を称する者であっても、「男女二人一組」の婚姻制度を利用している事実が認められるし、その者も適法に制度を利用しているのであるから、「同性愛者が婚姻すること」が「実質的には不可能」などという事実はない。
そのため、「実質的には不可能」との理解の下に「このような効果」と論じていることは、「効果」に対する理解を誤ったものである。
また、もしこの判決が婚姻制度が「異性間のもの」という「男女二人一組」となっていることに対して、「男女二人一組」の婚姻制度を利用している者は、すべて「異性愛」の思想、信条、信仰、感情を抱く「異性愛者」を称する者であるとの誤った推測や、婚姻制度を利用する際には「性愛」に基づくべきであるなどという特定の価値観に基づいて、「同性愛者」を称する者は「男女二人一組」の婚姻制度を利用しているはずがないだとか、「性愛」に基づかない形で婚姻制度を利用することは正当でないという理解によって、「同性愛者が婚姻することを実質的には不可能」などと説明しているものであるとすれば、この東京地裁判決は「男女二人一組」の婚姻制度が「異性愛」という特定の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的としていたり、「異性愛者」を称する者に対して優遇することを目的とした制度となっているとしても、それが憲法に違反しないと論じていることとなるのであり、誤りである。
法制度が「性愛」という思想、信条、信仰、感情を保護することを目的として制定されてはならないし、法制度が「異性愛」などという特定の思想、信条、信仰、感情に対して法制度が肩入れするものとなっていることを前提として解釈することも誤りである。
五つ目に、「性的指向による区別取扱いに当たるものと認められる。」との部分を検討する。
まず、法制度は特定の思想、信条、信仰、感情に着目して区別取扱いを行ってはならないのであり、個々人の「性愛」の有無を審査したり、「性愛」を有する場合にどのような対象に向かうかという「性的指向」と称するものに基づいて区別取扱いを行うこともしてはならない。
そして、婚姻制度を利用する際に、個々人の内心を審査して異なる取扱いをしている事実はないことから、個々人の思想、信条、信仰、感情、性格、気質、考え方、感じ方などによって区別取扱いをしているという事実はない。
そのため、婚姻制度が「性的指向による区別取扱い」をしているという事実はない。
よって、「性的指向による区別取扱いに当たるものと認められる。」との部分は、誤った理解である。
他の事例を出すとすれば、婚姻制度を利用している者の大半が「穏当な性格の人」であるとしても、「気質の粗い性格の人」も婚姻制度を利用することができるのであり、「気質の粗い性格の人」を区別して取扱っているということにはならない。
「穏当な性格の人」と婚姻するべきなどというのは個々人の価値観に過ぎないものであるし、法律論として「気質の粗い性格の人」であっても、法律上の要件を満たして制度を利用する意思があるのであれば、「婚姻の本質」を伴っているのであり、これを否定されるいわれはないのである。
そのため、これを理由として「性格」によって「区別取扱い」をしているなどいうことにはならないのである。
「性愛」にどの程度の比重を置くか、「性格」にどの程度の比重を置くか、「宗教」にどの程度の比重を置くか、「運動神経」にどの程度の比重を置くか、「趣味」にどの程度の比重を置くかなど、個々人の価値観によるものであり、法制度は関知していないのである。
「この点の被告の主張は理由がない。」との記載があるが、「被告の主張」に問題があるわけではなく、この判決の内容が違憲な内容となっており、誤っている。
ウ 以上のとおり、本件諸規定は、婚姻の可否について性的指向による区別取扱いをするものであるところ、これにより、同性愛者は、婚姻(法律婚)制度全体を利用することができない状況に置かれ、異性愛者とは異なり、婚姻によって生ずる様々な法的効果等を享受することができないという不利益を受けているということができる。
【筆者】
「本件諸規定は、婚姻の可否について性的指向による区別取扱いをするものであるところ、」との部分について検討する。
まず、婚姻制度は「性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にどのような対象に向かうかなど審査して区別して取扱っている事実はないし、「性愛」に基づいて「婚姻」することを求めるものでも勧めるものでもない。
よって、「婚姻の可否について性的指向による区別取扱いをするものである」との理解は誤りである。
次に、婚姻制度が「婚姻の可否について」、「性愛」の有無を審査したり、「性愛」を有する場合にどのような対象に向かうかという「性的指向」と称するものを審査して「区別取扱い」を行うものとなっていた場合には、憲法19条の「思想良心の自由」、20条1項前段の「信教の自由」に抵触して違憲となるし、他の「性愛」の思想、信条、信仰、感情や、「性愛」以外の「友情」「友愛」「宗教愛」「人類愛」を含め、他の思想、信条、信仰、感情との間で14条の「平等原則」に抵触して違憲となる。
また、婚姻制度が「婚姻の可否について性的指向による区別取扱いをするもの」となっている場合には、「性愛」という特定の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的として立法されていることになるから、20条1項後段・3項、89条の「政教分離原則」に抵触して違憲となる。
よって、「本件諸規定は、婚姻の可否について性的指向による区別取扱いをするものである」などと、「性的指向」と称するものに基づいて「区別取扱い」を行う法制度が存在しているとしても、それが許されるかのように考えている点で誤りである。
「同性愛者は、婚姻(法律婚)制度全体を利用することができない状況に置かれ、」との部分であるが、誤りである。
まず、婚姻制度は「性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」を審査して区別取扱いを行っている事実はないし、「性愛」に基づいて婚姻制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもない。
よって、「同性愛者」を称している者も適法に「男女二人一組」の「婚姻(法律婚)制度全体を利用すること」ができることから、「同性愛者は、婚姻(法律婚)制度全体を利用することができない状況に置かれ、」との理解は誤っている。
これについては、「同性愛者」を称する者だけでなく、「両性愛者」、「全性愛者」、「多性愛者」、「小児性愛者」、「老人性愛者」、「死体性愛者」、「動物性愛者」、「対物性愛者」、「対二次元性愛者」「無性愛者」を称する者であっても、同様である。
また、「キリスト教徒」、「イスラム教」、「ユダヤ教徒」、「ゾロアスター教徒」、「仏教徒」、「神道を信じる者」、「武士道を重んじる者」を称する者であっても同様である。
他にも、「軍事オタク」、「鉄道オタク」、「アニメオタク」、「アイドルオタク」を称する者であっても、同様である。
婚姻制度は個々人の内心を審査していないのであるから、その者がどのような思想、信条、信仰、感情を有しているとしても、利用することが可能であり、「婚姻(法律婚)制度全体を利用すること」はできる状態ということができる。
その「男女二人一組」の婚姻制度を利用することを望むか望まないかの問題に過ぎず、望まないというのであれば、「婚姻(法律婚)制度全体を利用すること」は可能であるが、個人の意思によって利用していないというだけである。
「異性愛者とは異なり、婚姻によって生ずる様々な法的効果等を享受することができないという不利益を受けているということができる。」との部分であるが、誤りである。
婚姻制度は「性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」を審査して区別取扱いを行っている事実はないし、「性愛」に基づいて「婚姻」することを求めるものでも勧めるものでもない。
そのため、個々人が「性愛」を有していようとも、有していないとしても、「性愛」を有していた場合にどのような対象に向かうとしても、婚姻制度を利用することは可能である。
よって、「異性愛者とは異なり、」のように、ある特定の思想、信条、信仰、感情を有する者と、それを有しない者とを「異な」るものとして取り扱っている事実はないため、「異性愛者」を称する者も、それを称しない者も、婚姻制度の要件を満たす限りは、「婚姻によって生ずる様々な法的効果等を享受すること」は可能である。
よって、「異性愛者」も「同性愛者」も区別されている事実はないことから、「同性愛者」を称する者について、「婚姻によって生ずる様々な法的効果等を享受することができないという不利益を受けているということができる。」との理解は誤りである。
しかしながら、前述のとおり、憲法24条1項は、異性間の婚姻について法律婚としての立法を要請しているものと解すべきものであるところ、このように婚姻を異性間のものとする社会通念の背景には、夫婦となった男女が子を産み育て、家族として共同生活を送りながら、次の世代につないでいくという古くからの人間の営みがあることは前述のとおりである。そうすると、本件諸規定が婚姻を異性間のものに限り、同性間の婚姻を認めていないことは、上記のような社会通念を前提とした憲法24条1項の法律婚制度の構築に関する要請に基づくものであって、上記区別取扱いについては合理的な根拠が存するものと認められる。
【筆者】
この段落の第一文が文章として読み取りにくい理由は、「前述のとおり、……(略)……前述のとおりである。」のように、「前述のとおり」が二回繰り返されているためである。
文を読み取る者がこのような言い回しに惑わされると、判決の内容全体の論理的な過程を明確な形で読み取ることを困難とするため、改めていくことが望ましい。
「憲法24条1項は、異性間の婚姻について法律婚としての立法を要請しているものと解すべきものであるところ、このように婚姻を異性間のものとする社会通念の背景には、夫婦となった男女が子を産み育て、家族として共同生活を送りながら、次の世代につないでいくという古くからの人間の営みがある」との部分について検討する。
この文の意味をまとめると、下記のようになる。
◇ 「夫婦となった男女が子を産み育て、家族として共同生活を送りながら、次の世代につないでいくという古くからの人間の営み」 (背景)
↓ ↓
◇ 「婚姻を異性間のものとする社会通念」
↓ ↓
◇ 「憲法24条1項は、異性間の婚姻について法律婚としての立法を要請している」
「本件諸規定が婚姻を異性間のものに限り、同性間の婚姻を認めていないことは、上記のような社会通念を前提とした憲法24条1項の法律婚制度の構築に関する要請に基づくものであって、上記区別取扱いについては合理的な根拠が存するものと認められる。」との部分について検討する。
この文の意味をまとめると、下記のようになる。
◇ 「社会通念」 (前提)
↓ ↓
◇ 「憲法24条1項の法律婚制度の構築に関する要請」
↓ ↓ (に基づくもの)
◇ 「本件諸規定が婚姻を異性間のものに限り、同性間の婚姻を認めていない」
↓ ↓
◇ 「上記区別取扱いについては合理的な根拠が存する」
この文の「上記区別取扱い」とは、この判決が「婚姻の可否について性的指向による区別取扱い」と述べているものに対応するもののはずである。
ただ、この点で、国(行政府)の主張と混乱するものとなっていないか注意して読み解く必要がある。
国(行政府)が述べている「区別取扱い」は、「婚姻について異性間の人的結合関係を対象とし,同性間の人的結合関係を対象とするものとして定めておらず」のことである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
そうすると,本件規定が婚姻について異性間の人的結合関係を対象とし,同性間の人的結合関係を対象とするものとして定めておらず(かかる区別取扱いを,以下「本件規定による区別取扱い」という。), 本件規定に基づき同性問で婚姻をすることができないことは,憲法自体が予定し,かつ許容しているものであって,意法24条に違反するものといえないことはもとより,憲法14条1項に違反すると解することもできないというべきである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【東京・第9回】被告第5準備書面 PDF (P7)
そして、国(行政府)は「性的指向」による「区別取扱い」は存在しないとした上で、「婚姻について異性間の人的結合関係を対象とし,同性間の人的結合関係を対象とするものとして定めておらず」の「区別取扱い」に関して、憲法14条に違反しないと述べている。
この東京地裁判決の言葉でいえば、「本件諸規定が婚姻を異性間のものに限り、同性間の婚姻を認めていない」の部分を、国(行政府)は「区別取扱い」と考えているのである。
この点で「区別取扱い」の対象となっているものが分かりづらく、混乱しやすいため、注意が必要である。
この段落をまとめると、下記のようになる。
◇ 「夫婦となった男女が子を産み育て、家族として共同生活を送りながら、次の世代につないでいくという古くからの人間の営み」 (背景)
↓ ↓
◇ 「婚姻を異性間のものとする社会通念」
「社会通念」 (前提)
↓ ↓
◇ 「憲法24条1項は、異性間の婚姻について法律婚としての立法を要請している」
「憲法24条1項の法律婚制度の構築に関する要請」
↓ ↓ (に基づくもの)
◇ 「本件諸規定が婚姻を異性間のものに限り、同性間の婚姻を認めていない」
↓ ↓
◇ 「上記区別取扱いについては合理的な根拠が存する」
ここで、「本件諸規定」が「婚姻を異性間のものに限り、同性間の婚姻を認めていない」ことは、「合理的な根拠が存する」と述べており、その理由は、「憲法24条1項」の前提となっている「婚姻を異性間のものとする社会通念」であり、「社会通念」の「背景」には「夫婦となった男女が子を産み育て、家族として共同生活を送りながら、次の世代につないでいくという古くからの人間の営み」があるとしている。
そうであれば、憲法24条が「婚姻」について「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて、婚姻制度の内容に対して立法裁量の限界を画し、「男女二人一組」の形に限定する趣旨を有しているとしても、その背景には「夫婦となった男女が子を産み育て、家族として共同生活を送りながら、次の世代につないでいくという古くからの人間の営み」があることから、「合理的な根拠が存する」として正当化できるということを述べていることになる。
この判決では「2⑶ア(イ)」のところで「憲法24条は、本件諸規定が定める婚姻を同性間にも認める立法をすること、……(略)……などを禁止するものではなく、……(略)……憲法24条に違反するものではないということができる。」や、「⑶カ(イ)」のところで「憲法24条が同性間の婚姻に関する立法を禁止するものとは解されない」と述べているが、法律上の立法政策として「本件諸規定」が「婚姻を異性間のものに限り、同性間の婚姻を認めていない」ことについて「合理的な根拠が存する」と述べているのであれば、同じ理由によって憲法上の立法政策として「憲法24条1項」が「婚姻」の内容を「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を使って「男女二人一組」の形に限定し、それ以外の人的結合関係を「婚姻」として認めないという意味で立法裁量の限界を画しているとしても、その結論を正当化していることになるのであり、この点に一貫性がないことは整合性を欠くものとなっている。
このような一貫性を欠く解釈を行うことは、他の解釈を退けるだけの説得的な根拠が示されているとはいえないのであり、解釈の客観性が保たれているともいえない。
これでは、正しい解釈をめぐって紛争を招くことになり、法的安定性を損なうことになる。
したがって、本件諸規定が婚姻を異性間のものに限り同性間の婚姻を認めていないこと自体が、立法裁量の範囲を超え、性的指向による差別に当たるとして、憲法14条1項に違反するとはいえない。
【筆者】
この文は、この一文だけでは意味が分かりづらいものとなっている。
読み取りづらい原因は、下記の通りである。
◇ 「婚姻を異性間のものに限り同性間の婚姻を認めていないこと」についての合理性だけを論じるのではなく、そこに「性的指向」による「差別」の話を持ち込む誤りがあること。
◇ 法律論上は「区別」あるいは「差別」(法的にはどちらでも意味は同じ)についての『合理性』の有無が焦点となっているにもかかわらず、日常用語としての「差別に当たる」か否かを問う視点で論じている誤りがあること。
下記の動画では、14条における「平等」とは、「区別」の存否ではなく、「区別」の「合理性」の有無が論点であることが説明されている。
【動画】シンポジウム 国葬を考える【The Burning Issues vol.27】 2022/09/25
最高裁判決でも「差別」の文言を使っているが、「合理的」であれば禁じられないとしている。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1 憲法14条1項は,法の下の平等を定めており,この規定が,事柄の性質に応じた合理的な根拠に基づくものでない限り,法的な差別的取扱いを禁止する趣旨のものであると解すべきことは,当裁判所の判例とするところである(最高裁昭和37年(オ)第1472号同39年5月27日大法廷判決・民集18巻4号676頁,最高裁昭和45年(あ)第1310号同48年4月4日大法廷判決・刑集27巻3号265頁等)。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
損害賠償請求事件 最高裁判所大法廷 平成27年12月16日 (PDF) (再婚禁止期間違憲訴訟)
よって、法律論上は「区別」と呼ぼうと「差別」と呼ぼうと、「合理性」の存否が問題なのであり、日常的に使う言葉としての「差別であるかどうか」という問題ではない。
この点で、「性的指向による差別に当たるとして、」という言葉を用いることは、読み手の理解を混乱させるものとなっている。
また、この判決の文面では、⑵イの(ア)や(イ)の所で「性的指向による区別取扱いに当たるものと認められる。」と自ら述べていたはずである。
それにもにもかかわらず、この文では「性的指向による差別に当たるとして、憲法14条1項に違反するとはいえない。」として、先ほどの「区別取扱い」(差別)としていたものを取り消して否定しているかのように見えてしまうのである。
このような分かりづらい文面となってしまう原因は、「本件諸規定が婚姻を異性間のものに限り同性間の婚姻を認めていないこと」を「性的指向による区別取扱いに当たる」(性的指向による差別)と考える誤りがあるからである。
婚姻制度は「性愛」を保護することを目的とする制度ではないし、個々人の内心を審査して区別取扱いをしている事実はないのであり、これを「性的指向」による「区別取扱い」(差別)ということはできないのである。
このようなものに対して「性的指向」による「区別取扱い」が存在すると考えてしまっている背景には、「性愛」に基づく「婚姻」こそが正しい価値観であるとする思想・信条・信仰が存在すると考えられる。(ロマンチック・ラブ・イデオロギーなどもそのような思想、信条、信仰の一つである。)
その「性愛」に基づく「婚姻」こそが正当な価値観であると考え、その思想・信条・信仰によって「区別取扱い」がなされているだとか、なされるべきであるとかいう立場によって、「区別取扱い」を認定しようとするものということができる。
しかし、法制度が個々人の内心に属する「性愛」の有無やロマンチック・ラブ・イデオロギーなとの思想・信条・信仰の有無を審査したり、それらの思想・信条・信仰を保護することを理由として法制度を立法することは、それ自体で違憲となる。
この判決は「性的指向」に基づく「区別取扱い」が存在することを前提としていたり、そのような「区別取扱い」が存在するとしても、14条に違反しないと述べているが、個々人の内心を審査して「性的指向」に基づく「区別取扱い」を行う法制度が存在するのであれば、それ自体で憲法19条の「思想良心の自由」や、20条の「信教の自由」に抵触して違憲となる。
また、個々人を内心に基づいて異なる取扱いをするものであるから、合理的な理由があるとはいえず、14条の「平等原則」に抵触して違憲となる。
そのため、この判決が「性的指向」という個々人の内心に基づいて「区別取扱い」を行うような法制度が存在しても良いと考えているところが、既に憲法19条の「思想良心の自由」や20条の「信教の自由」、14条の「平等原則」に抵触して違憲となるものである。
◇ 「立法裁量の範囲を超え、……(略)……憲法14条1項に違反するとはいえない。」の「超え」の文が、「超え『るから』憲法14条1項に違反するとはいえない。」なのか、「超え『てしまい』憲法14条1項に違反するとはいえない。」なのか、「超え『て』憲法14条1項に違反する『、』とはいえない。」なのか、「超え『ていないから』憲法14条1項に違反するとはいえない。」なのか、迷うこと。
憲法14条に違反する場合の前提知識を有している者が、 この判決の⑵アの部分から文脈を丁寧にたどったならば、「超え」の意味はどういう意味であるか理解することは可能である。
しかし、前後の様々な繋がりが存在する文面の中で、この論点も前後を遡りながら意識して考えなければ読み取りづらくなるような文を用いることは最適な文であるとは言えない。
前段落と合わせて考えると、要するに、「憲法24条1項は、異性間の婚姻について法律婚としての立法を要請しているものと解すべきものであ」って、その「婚姻を異性間のものとする社会通念の背景には、夫婦となった男女が子を産み育て、家族として共同生活を送りながら、次の世代につないでいくという古くからの人間の営みがある」のであり、「本件諸規定が婚姻を異性間のものに限り同性間の婚姻を認めていないこと」は、「社会通念を前提とした憲法24条1項の法律婚制度の構築に関する要請に基づくもの」であり、「区別取扱いについては合理的な根拠が存するものと認められ」、「立法裁量の範囲を超え、」て「憲法14条1項に違反するとはいえない。」ということである。
「憲法24条1項は、異性間の婚姻について法律婚としての立法を要請しているものと解すべきものである」
↓ ↓
「婚姻を異性間のものとする社会通念の背景には、夫婦となった男女が子を産み育て、家族として共同生活を送りながら、次の世代につないでいくという古くからの人間の営みがある」
↓ ↓
「本件諸規定が婚姻を異性間のものに限り、同性間の婚姻を認めていないことは、」「社会通念を前提とした憲法24条1項の法律婚制度の構築に関する要請に基づくもの」
↓ ↓
(性的指向による)「区別取扱いについては合理的な根拠が存するものと認められる。」
↓ ↓
(性的指向による区別取扱い)は「立法裁量の範囲を超え、」「憲法14条1項に違反するとはいえない。」
エ これに対し、原告らは、上記区別取扱いに合理的根拠が認められるかの審査は厳格に行われるべきであり、同性愛者の不利益は甚大であることや、婚姻制度の目的が親密性に基づく共同生活の保護にあることなどからすれば、上記区別取扱いに合理的理由が存在しないことは明らかである旨主張する。
【筆者】
「上記区別取扱いに合理的根拠が認められるかの審査は厳格に行われるべきであり、」との記載がある。
しかし、婚姻制度は「性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いを行っている事実はないし、「性愛」に基づいて「婚姻」することを求めるものでも勧めるものでもない。
そのため、ここで「上記区別取扱い」と述べている「婚姻の可否について性的指向による区別取扱い」というものが、そもそも存在していない。
そのため、「区別取扱い」があることを前提として「合理的根拠が認められるか」否かを判断しようとする試みそのものが誤っている。
よって、「審査は厳格に行われるべき」との部分についても、「区別取扱い」が存在しないものに対して何かを「審査」することはできないのであり、それが「厳格に行われるべき」であるかどうかも、その主張の前提を欠くものである。
「同性愛者の不利益は甚大であることや、」との部分であるが、婚姻制度は個々人の内心を審査して区別取扱いを行っているという事実がないため、「同性愛者」を称している者であっても、婚姻制度の要件に従って制度を利用するのであれば、「婚姻」することは可能であるため、「同性愛者」と称する者であることを理由として法的な「不利益」が存在するわけではない。
「婚姻制度の目的が親密性に基づく共同生活の保護にあることなどからすれば、」との記載があるが、誤りである。
「婚姻制度」の目的は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することにある。
そして、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす人的結合関係に対して一定の優遇措置を行うことによって、目的の達成を目指す仕組みとなっている。
そのため、「共同生活の保護」という側面があるとしても、それは「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成するための手段として設けられた「保護」であるから、その目的との整合性を満たす人的結合関係のみを対象とするものであることが前提となっている。
そのことから、立法目的を達成するための手段となる枠組みの対象外となっている人的結合関係の「共同生活」が「保護」されないことは当然のことである。
よって、「婚姻制度の目的」の理解を誤っているし、婚姻制度の内容について「共同生活の保護」という側面があるとしても、それは「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成するための手段となる枠組みに当てはまる者を対象とするものであり、そこに当てはまらない者について「保護」が受けられることを期待することも誤りである。
「上記区別取扱いに合理的理由が存在しないことは明らかである旨主張する。」との記載がある。
しかし、そもそも「区別取扱い」が存在しないため、「合理的理由」の存否を判断する前提を欠いている。
よって、ここでは「合理的理由が存在しないことは明らかである旨主張」するものとなっているが、「区別取扱い」が存在しないというそれ以前の論点によって排斥されるべき主張である。
しかしながら、前述のとおり、憲法24条の「婚姻」は異性間の婚姻を指し、同条1項が異性間の婚姻について法律婚制度の構築を要請している一方、同性間の婚姻については、異性間の婚姻と同等の保障をしているとは解されないことからすれば、婚姻制度の目的の一つが人的結合関係における共同生活の保護にあると考えられることなどを考慮したとしても、本件諸規定が婚姻を異性間のものに限り同性間の婚姻を認めていないことが立法裁量の範囲を超え、憲法14条1項に違反するとはいい難い。
【筆者】
「憲法24条の「婚姻」は異性間の婚姻を指し、同条1項が異性間の婚姻について法律婚制度の構築を要請している」との部分について検討する。
まず、「憲法24条の「婚姻」」が「異性間の婚姻」を指しているということは、「男女の組み合わせ」であることを意味している。
この「男女の組み合わせ」の枠組みであることは、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する形で「婚姻」が設けられたことを裏付けるものであると考えられる。
「同条1項が異性間の婚姻について法律婚制度の構築を要請している」の部分についても、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的とした具体的な法律上の制度を構築することを要請することを意味していることになる。
「同性間の婚姻については、異性間の婚姻と同等の保障をしているとは解されない」との部分について検討する。
まず、「同性間の婚姻」との文言について検討する。
「婚姻」は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として、21条1項の「結社の自由」で保障される他の様々な人的結合関係とは区別する形で設けられた制度である。
そのため、このような目的を離れて「婚姻」を観念することはできない。
そのことから、「婚姻」という概念が形成されている目的との関係により、「婚姻」の中に含めることのできる人的結合関係と含めることのできない人的結合関係が区別されることになる。
つまり、「婚姻」という概念であることそれ自体によって、「婚姻」の中に含めることのできる人的結合関係の範囲には内在的な限界があるということである。
そして、「同性間」の人的結合関係については、一般的・抽象的にその間で「生殖」を想定することができない組み合わせであることから、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的に沿うものではなく、「婚姻」の中に含めることはできないと考えられる。
よって、「同性間の婚姻」という文言からは、あたかも「同性間」の人的結合関係を「婚姻」として扱うことが可能であるかのような前提で論じられている部分があるが、そもそも「婚姻」とすることはできないという点で、誤っていると考えられる。
次に、「異性間の婚姻と同等の保障をしているとは解されない」との部分について検討する。
「同性間」の人的結合関係について、「婚姻」として扱うことが可能であるとの前提の下に、それが「同等の保障をしている」かどうかを問うものとなっているが、そもそも「同性間」の人的結合関係については、「婚姻」として扱うことができないと考えられることから、「同等の保障をしている」か否かを論じる前提にない。
そのため、「同等の保障をしている」か否かを論じようとしている点でも誤っている。
その他、「婚姻」は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために設けられた制度であり、24条は「婚姻」を定めていることから、この24条の「婚姻」「夫婦」「両性」「相互」の文言が、法律で立法される婚姻制度の意味や内容を「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するものとして機能しないものに変えてしまうことを許しているはずがない。
そのため、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成することが不能となるような人的結合関係を、24条の「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」の文言に照らし合わせて考えた場合に、これらの文言がそれらの人的結合関係を法律上の婚姻制度によって扱うことを許しているはずがない。
そのことから、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的に沿わない人的結合関係や、その目的を達成することを阻害する人的結合関係を「婚姻」として扱おうとする法律を立法した場合には、24条の「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」の文言に抵触して違憲となることは明らかである。
「婚姻制度の目的の一つが人的結合関係における共同生活の保護にあると考えられることなどを考慮したとしても、」との部分について検討する。
まず、「婚姻制度の目的」の部分であるが、これを単純に「人的結合関係における共同生活の保護」にあると考えてよいかどうか考える必要がある。
そこで、「婚姻制度の目的」を検討する。
その国の中で「生殖と子の養育」に関する事柄について何らの制度も存在しない場合には、社会的な不都合が発生することがある。
例えば、「父親不明」の子供が増える、父親を特定できない子供が増える、父親が蒸発して行方不明になった子供が増える、それらにより「子の福祉」が減少する、父親を特定できないことにより近親者の範囲を把握できずに「近親交配」に至り遺伝的な劣勢を有する個体が高い確率で発現するようになる、一部の強者が多数人との生殖関係を独占することによって社会の中で「子を持ちたいと希望して相手を見つけようとする男女」の数の不均衡が生じて「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」が生まれる、低年齢での妊娠・出産により母体に危険が及ぶ、などの問題が生じることがある。
「婚姻」は、これらの国民が「生殖」によって子供を産むことに関係して起き得る問題を抑制することを目的として、他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた枠組みである。
そのため、「婚姻」には、下記の立法目的が存在すると考えられる。
・「子の福祉」が実現される社会基盤を構築すること
・遺伝的な劣勢を有する個体が高い確率で発現することを抑制すること
・「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」を減らすこと
・母体を保護すること
このような「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解決しようとする立法目的を離れて「婚姻」を観念することはできない。
そして、これらの目的を達成するための手段として整合的な、下記の要素を満たす人的結合関係を他の人的結合関係とは区別することが必要となる。
・子の遺伝的な父親を特定できる組み合わせとすること
・特定された子の父親にも子に対する責任を担わせること
・特定された子の父親を基に遺伝的な近親者を把握すること
・未婚の男女の数の不均衡を防止できる組み合わせに限定すること
これらの要素を満たす人的結合関係に対して、一定の優遇措置を与えることによって、婚姻制度の立法目的の実現を目指す仕組みとなっている。
この判決は「婚姻制度の目的の一つが人的結合関係における共同生活の保護にあると考えられる」と述べているが、婚姻制度の立法目的は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的とするものであり、単なる「人的結合関係における共同生活の保護」にあるわけではない。
そのため、個々人が「人的結合関係」を形成して「共同生活」をしているだけでは、「婚姻」として「保護」される理由にはならない。
婚姻制度が「人的結合関係における共同生活の保護」を行う場合があるとしても、それは「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成するための手段として整合的な上記の要素を満たす人的結合関係に対するものに限られる。
そのため、婚姻制度の立法目的との整合性を検討しないままに、どのような人的結合関係であっても婚姻制度による「共同生活の保護」が与えられることを前提とするような論じ方が可能となるわけではない。
そのことから、ここでは「婚姻制度の目的の一つが人的結合関係における共同生活の保護にあると考えられることなどを考慮したとしても、」と述べられているのであるが、そもそも婚姻制度の立法目的の実現に沿わない「人的結合関係」に対して「共同生活の保護」が与えられるという前提にはないのであり、婚姻制度の対象でない者に対して「共同生活の保護」との関係を検討しなければならないことにはならないのであり、このような話を持ち出していること自体が不適切である。
㊥ 「本件諸規定が婚姻を異性間のものに限り同性間の婚姻を認めていないことが立法裁量の範囲を超え、憲法14条1項に違反するとはいい難い。」との部分について検討する。
オ また、原告らは、本件諸規定は性別に基づく区別取扱いであるとも主張する。
しかし、本件諸規定の下では男性も女性もそれぞれ異性とは婚姻することができ、また、同性とは婚姻することができないのであって、男性か女性のどちらか一方が性別を理由に不利益な取扱いを受けているものではないから、本件諸規定は性別に基づく区別取扱いをするものとはいえない。
したがって、この点の原告らの主張は採用することができない。
【筆者】
この部分は、その通りである。
⑶ 憲法24条2項適合性について
ア(ア) これまで述べたとおり、憲法24条の「婚姻」が異性間の婚姻を指していると解されることからすれば、本件諸規定が婚姻を異性間のものに限り同性間の婚姻を認めていないこと自体が憲法24条1項、14条1項に違反するものとはいえない。
(イ) もっとも、前記のとおり、憲法24条1項は、同条の「婚姻」すなわち異性間の婚姻に関する立法について婚姻をするかどうか、いつ誰と婚姻をするかについては、当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられることとすることを立法府に対して求める趣旨の規定であり、法律婚制度に同性間の婚姻を含めることについては何ら触れられていない。その制定時の議論をみても、同条は、明治民法の下での家制度に付随する戸主の権限を廃止し、当事者双方の合意のみに基づく婚姻を可能とすることに主眼があったことが認められ、婚姻は異性間のものであるとの前提に立つものではあるものの、同性間の婚姻を積極的に排除、禁止しようとしたものとはうかがわれない(前記認定事実(2)ウ)。
【筆者】
「法律婚制度に同性間の婚姻を含めることについては何ら触れられていない。」との部分に、「同性間の婚姻」との言葉がある。
この「同性間の婚姻」という言葉は、あたかも「同性間」の人的結合関係を「婚姻」として扱うことができることを前提としているように見受けられる。
しかし、「婚姻」は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた枠組みであり、この目的を離れて「婚姻」を観念することはできないことから、「婚姻」であることそれ自体によって、「婚姻」の中に含めることのできる人的結合関係には内在的な限界がある。
「同性間」の人的結合関係については、その間で一般的・抽象的に「生殖」を想定することができないことから、「生殖と子の養育」の趣旨を満たすとはいえず、「婚姻」とすることはできない。
よって、ここでは「婚姻」の中に「同性間」の人的結合関係を含めることができるとの認識を前提として、「法律婚制度」に「同性間」の人的結合関係を「含めること」について「何ら触れられていない。」と述べているが、そもそも「婚姻」という概念のそのものによって「婚姻」という概念の中に含めるこのできる人的結合関係の範囲には内在的な限界があるのであり、その「何ら触れられていない。」ことを理由としても、「婚姻」という概念が有する内在的な限界を超える人的結合関係を「婚姻」の中に含めることができるとする理由とはならない。
「その制定時の議論をみても、同条は、明治民法の下での家制度に付随する戸主の権限を廃止し、当事者双方の合意のみに基づく婚姻を可能とすることに主眼があったことが認められ、婚姻は異性間のものであるとの前提に立つものではあるものの、」との部分について検討する。
ここでいう「同条」という憲法24条1項の規定が設けられた背景に「明治民法の下での家制度に付随する戸主の権限を廃止し、当事者双方の合意のみに基づく婚姻を可能とすることに主眼があった」との認識は、その通りであると考えられる。
そして、「婚姻は異性間のものであるとの前提に立つもの」との部分も、その通りであると考えられる。
しかし、そこでいう「婚姻」は、常に「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を持った概念であることから、その意味を離れて「婚姻」を観念することはできないものである。
そのため、その「婚姻」の中に含まれている目的そのものを離れて、ここでいう「同条」である憲法24条1項が定められる際の背景にあった意図の一部分のみを切り取る形で取り上げ、それを反対解釈すれば、「婚姻」の中に含まれる目的やその目的との関係によって導き出される内在的な限界を超える人的結合関係を「婚姻」の中に含めることができるとする理由となるわけではない。
これは、規定の一部を部分的に反対解釈しているだけであって、規定のすべての意味を読み取った上ですべての意図を統一的に理解しようとするものとはなっていないのであり、自らの望む結論を導き出すために規定の一部分に存在する意図のみが、その規定に込められた意図のすべてであるかのように見せかけようとするものである。
法解釈を行う上では、このような規定の一部分に含まれる意図が、その規定が有するすべての意味であるかのような詐術に惑わされることのないように注意する必要がある。(メディアや政治家、商売広告などがこのようなトリックを用いている場合があることは、専門的な知識を獲得すれば見抜くことができるようになるものである。)
「憲法24条1項」について「制定時の議論をみても、」「同性間の婚姻を積極的に排除、禁止しようとしたものとはうかがわれない」という趣旨の記載がある。
しかし、「婚姻」は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために国家の政策の手段として設けられた制度であることから、この目的を達成することのできる枠組みとして機能することこそが「婚姻」という概念を成り立たせるものということができることから、「婚姻」ということそれ自体で「婚姻」の中に含めることができる人的結合関係の範囲には内在的な限界が存在する。
そのため、この判決は「同性間の婚姻」のように、「同性間」の人的結合関係を「婚姻」として扱うことができることを前提として、それを「憲法24条1項」が「積極的に排除、禁止しようとしたもの」かどうかを検討すればよいかのような前提で述べているが、「婚姻」という概念が形成されている目的との関係で「婚姻」の中に含めることのできる人的結合関係の範囲には内在的な限界が存在するのであり、「婚姻」の中に「同性間」の人的結合関係を含めることができるとは限らない。
「婚姻」の中に「同性間」の人的結合関係を含めることができることを前提として、「憲法24条1項」がそれを「積極的に排除、禁止しようとしたもの」かどうかを論じることは結論を先取りしようとするものとなるため妥当でなく、その前に「婚姻」の中に「同性間」の人的結合関係を含めることができるか否かを論じることが必要である。
ここで、具体的に「同性間」の人的結合関係を「婚姻」とすることができるか否かを検討する。
その国の中で「生殖と子の養育」に関する事柄について何らの制度も存在しない場合には、社会的な不都合が発生することがある。
例えば、「父親不明」の子供が増える、父親を特定できない子供が増える、父親が蒸発して行方不明になった子供が増える、それらにより「子の福祉」が減少する、父親を特定できないことにより近親者の範囲を把握できずに「近親交配」に至り遺伝的な劣勢を有する個体が高い確率で発現するようになる、一部の強者が多数人との生殖関係を独占することによって社会の中で「子を持ちたいと希望して相手を見つけようとする男女」の数の不均衡が生じて「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」が生まれる、低年齢での妊娠・出産により母体に危険が及ぶ、などの問題が生じることがある。
「婚姻」は、これらの「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する形で設けられた枠組みである。
そのため、「婚姻」には、下記の立法目的が存在すると考えられる。
・「子の福祉」が実現される社会基盤を構築すること
・遺伝的な劣勢を有する個体が高い確率で発現することを抑制すること
・「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」を減らすこと
・母体を保護すること
このような「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解決しようとする立法目的を離れて「婚姻」を観念することはできない。
よって、「婚姻」という概念である以上は、国民が「生殖」によって子を産むことに関わる制度であることを前提としている。
そして、「婚姻」である以上は、その概念そのものの中に、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消しようとする目的を達成することを損なうことはできないという内在的な限界が存在する。
これは、「婚姻」が他の様々な人的結合関係との間で「生殖と子の養育」の観点から区別する形で枠づけられていることからくるものであり、「婚姻」という概念そのものを成り立たせるために必要となる境界線である。
これは、もしこの境界線となる一線を損なった場合には、「婚姻」という枠組みそのものを他の人的結合関係との間で区別することができなくなり、「婚姻」という概念自体が成り立たなくなり、「婚姻」という概念そのものが雲散霧消してしまうこととなるからである。
その内在的な限界となる一線は、「婚姻」の立法目的を達成するための手段として整合的な、他の人的結合関係との間で区別することを可能とするための要素である。(『生殖と子の養育』の趣旨)
それは、下記が不可欠である。
・子の遺伝的な父親を特定できる組み合わせとすること
・特定された子の父親にも子に対する責任を担わせること
・特定された子の父親を基に遺伝的な近親者を把握すること
・未婚の男女の数の不均衡を防止できる組み合わせに限定すること
もしこれらの要素を満たさない人的結合関係を「婚姻」の中に含めようとした場合には、その時点で、これらの要素を満たさないことから、 「婚姻」の立法目的を達成することができなくなることを意味する。
そのため、これらの要素を満たさない人的結合関係については、「婚姻」として扱うことはできない。
24条は「婚姻」を定めていることから、上記の要素を満たさない人的結合関係を「婚姻」として扱うことはできない。
もし上記の要素を満たさない人的結合関係を「婚姻」として扱おうとする立法を試みた場合には、24条の許容する立法裁量の限界を超え、24条に抵触して違憲となる。
そこで、「同性間」の人的結合関係を「婚姻」とすることができるかどうかであるが、上記の要素を満たさない(『生殖と子の養育』の趣旨を満たさない)ことから、「婚姻」とすることはできない。
そのため、この判決では「同性間の婚姻」という言葉が使われているが、そもそも「同性間」の人的結合関係を「婚姻」として扱うことはできないという点で、誤っていると考えられる。
よって、ここでは「同性間の婚姻」のように、「婚姻」という概念の中に「同性間」の人的結合関係を含めることができるという前提の下で、「憲法24条1項」の規定が「同性間」の人的結合関係を「婚姻」とすることを「積極的に排除、禁止しようとしたもの」であるか否かを判断しようとするものとなっているが、それ以前にそもそも「同性間」の人的結合関係を「婚姻」という概念の中に含めることはできないという点で誤っていることになる。
この点で、この判決は「婚姻」が「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために設けられた制度であることからくる内在的な限界について何ら検討することもなく、「同性間」の人的結合関係を「婚姻」として扱うことができるとする前提に立っている点で、法解釈の過程に明示しない形で自らの好む結論を先取りしようする意図が感じられ、不適切である。
そして、婚姻の本質は、当事者が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもって共同生活を営むことにあると解されるところ、このような目的、意思をもって共同生活を営むこと自体は同性カップルにも等しく当てはまるものであるし、その性的指向にかかわらず、個人の人格的生存において重要なものであると認められる。
【筆者】
「婚姻の本質は、当事者が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもって共同生活を営むことにあると解されるところ、」との記載がある。
しかし、上記でも述べたように、この「婚姻の本質」と称する説明は、最高裁判決(昭和62年9月2日)の「婚姻の本質は、両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもつて共同生活を営むことにある」という文面の「両性」の部分が「当事者」に変わっている点で、判例引用を誤ったか、文言を意図的に改竄する不正な手続きによるものと考えられる。
もしこの判決を書いた裁判官が何らの根拠もなく独断で「婚姻の本質」と称する説明を決めているとすれば、別の裁判官が判決を下す時に「婚姻の本質は、子供を産むことにある」や「婚姻の本質は、一夫多妻である」、「婚姻の本質は、親の決めた相手と結ばれることである」と述べてしまえば、それが絶対的な定義となってしまうことを意味するのであり、法解釈として妥当でない。
また、この最高裁判決の「婚姻の本質」と称している説明は、憲法が要請する「婚姻」に基づく形で存在する具体的な法律上の婚姻制度の枠組みが存在することを前提として、その婚姻制度の内容を読み解いた際に、婚姻制度を利用する者の法的な権利・義務関係の結び付きによる法律関係の状態を簡潔に示したものと考えられる。
その理由は、この「婚姻の本質」と称している説明と、具体的な法律上の婚姻制度の枠組みとの対応関係を、下記のように整理することができるからである。
・ 「両性」との部分は、現在の婚姻制度が「男性」と「女性」を要件としていることから導かれたものと考えられる。
・ 「永続的な」との部分は、現在の婚姻制度には有効期限がなく、利用者が死亡するまで利用することができるという点から導かれたものと考えられる。
もし婚姻制度が改正されて有効期限が定められることがあるとすれば、この「永続的な」との説明は根拠を失ってなくなることになる。
・ 「精神的及び肉体的結合を目的として」との部分は、現在の婚姻制度が相互の協力を求めていることや、「貞操義務」があることことから導かれたものと考えられる。
「貞操義務」のある制度を読み解くことによって「肉体的結合」と表現しているのであり、もし「貞操義務」がなければ「肉体的結合」という表現は導かれないことになる。
・ 「共同生活を営む」との部分は、現在の婚姻制度が「同居義務」を定めていることから導かれているものと考えられる。
そのため、具体的な法制度が存在しないにもかかわらず、直ちに「婚姻」という概念そのものから「婚姻の本質」と称する説明が根拠もなく導き出されるという性質のものではない。
また、この「婚姻の本質」と称している説明は、具体的な婚姻制度の上位概念として存在するものではないし、婚姻制度を構築する際の「国の立法目的」を示したものでもない。
そのことから、具体的な法制度として示されている婚姻制度の枠組みを離れて、「婚姻の本質」と称する説明に当てはまるか否かを基準とすることによって、「婚姻」の中に含めることができる人的結合関係と、含めることができない人的結合関係とを区別することができることにはならない。
そのため、「婚姻の本質」と称する説明に照らし合わせることによって、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」として扱うことができるか否かに関する結論を導き出すことができるわけではない。
もしこの「婚姻の本質」と称する説明に当てはまるか否かを論じるだけで「婚姻」の中に含めることができる人的結合関係を特定することができるとすれば、「近親者」や「三人以上の複数名」、「婚姻適齢に満たない者」との人的結合関係についても「婚姻」として扱うことができることとなってしまうことにも注目する必要がある。
そのため、この「婚姻の本質」と称する説明を基準として考えて、「婚姻」の中に含めることのできる人的結合関係の範囲を検討しようとする試みは誤りである。
「このような目的、意思をもって共同生活を営むこと自体は同性カップルにも等しく当てはまるものであるし、」との記載があるが、誤った理解である。
まず、「このような目的、意思をもって共同生活を営むこと」との部分であるが、先ほど述べたように、「婚姻の本質」と称する説明は、具体的な法律上の婚姻制度の枠組みが存在することを前提として、その婚姻制度の内容を読み解いた際に、婚姻制度を利用する者の法的な権利・義務関係の結び付きによる法律関係の状態を簡潔に示したものであり、「目的、意思」を示したものではない。
次に、ここでいう「同性カップル」という「同性間」の人的結合関係については、そもそも婚姻制度の対象とはなっていないのであるから、婚姻制度が適用されることによって生じる法的な権利・義務の結び付きによる法律関係を形成することはできないのであり、その法律関係の状態を指す意味で用いられている「婚姻の本質」と称する説明の状態になることはできない。
そのため、ここでいう「同性カップル」という「同性間」の人的結合関係に対して、「婚姻の本質」と称する説明が「等しく当てはまるものである」と述べていることについては、誤りである。
これは「同性間」の人的結合関係に限られず、「近親者」との人的結合関係や、「三人以上」の人的結合関係、「婚姻適齢に満たない者」との人的結合関係についても同様である。
婚姻制度の対象となっている者が、婚姻制度を利用した場合に「婚姻の本質」と称して説明される法律関係を形成することが可能となるだけであり、その対象となっていない者や、婚姻制度を利用しない者、婚姻制度の枠組みに当てはまらない人的結合関係については、「婚姻の本質」と称する法律関係を形成することはできないのである。
もし個々人が何らかの「目的、意思」をもって人的結合関係を形成するというのであれば、それは憲法21条の「結社の自由」によって保障されることになるものである。
これについて、ここでいう「同性カップル」という「同性間」の人的結合関係についても、何らかの「目的、意思」をもって「共同生活を営む」のであれば、それは21条1項の「結社の自由」によって保障されることになる。
【参考】「それって「婚姻」じゃなくてもよくない?と言いたくなるような婚姻の本質論は何か微妙ね。」 Twitter
「その性的指向にかかわらず、個人の人格的生存において重要なものであると認められる。」との部分について検討する。
「個人の人格的生存」との部分であるが、この「人格的生存」とは、国家から個人に対して何らかの侵害があった場合に、それが正当化できるか否かを検討し、それを正当化できない場合に、その侵害を排除することが認められる場合に、その正当化根拠の一つとして論じられているものである。
これは、国家による侵害を排除するという視点によって論じられているものであり、通常は「国家からの自由」や「自由権」として論じられるものである。
しかし、婚姻制度は「立法目的」に従って形成された「立法目的を達成するための手段」となる枠組みに当てはまる者を対象とした制度であり、それに当てはまらない場合には制度を利用できないということは当然に予定されている。
また、婚姻制度の対象となっていないとしても、それは婚姻制度による優遇措置が得られないという状態にとどまり、その状態が「個人主義」の下で生存していく上での基準(スタンダード)であることから、そのこと自体が国家による侵害を生じさせている状態とは言えない。
よって、婚姻制度の対象となっていない場合においても、国家からの侵害があるわけではなく、「人格的生存」に対する侵害を検討する前提を欠いていると考えられる。
その他、「婚姻の本質」と称する説明も、具体的な婚姻制度の枠組みを前提として、その婚姻制度を利用した者についての法律関係を示すものであることから、婚姻制度の対象となっていない者が、この「婚姻の本質」と称する説明を根拠として何らかの権利・利益を求めることはできないし、それを「国家からの自由」という「自由権」の一つである「人格的生存」で裏付けようとすることも意味の通らないものである。
「その性的指向にかかわらず、」との部分であるが、「性愛」の思想、信条、信仰、感情を満たすという「目的、意思」をもって人的結合関係を形成することについては、憲法21条1項の「結社の自由」によって保障される。
「結社の自由」については、「国家からの自由」という「自由権」の側面を有することから、このような人的結合関係を形成することが国家によって侵害されている事実が認められた場合には、ここでいう「人格的生存」の観点からもそれを正当化することができるか否かを検討する余地が考えられる。
しかし、今回の事例では、このような「自由権」が侵害されている事例ではないため、「人格的生存」を取り上げることは適切でない。
したがって、憲法24条は、本件諸規定が定める婚姻を同性間にも認める立法をすること、又は同性間の人的結合関係について婚姻に類する制度を法律により構築することなどを禁止するものではなく、上記のような立法は、その内容が個人の尊厳と両性の本質的平等に反し立法府に与えられた裁量権の範囲を逸脱するものでない限り、憲法24条に違反するものではないということができる。
【筆者】
「したがって、憲法24条は、本件諸規定が定める婚姻を同性間にも認める立法をすること、又は同性間の人的結合関係について婚姻に類する制度を法律により構築することなどを禁止するものではなく、……(略)……憲法24条に違反するものではない」との記載がある。
まず、「したがって、」の部分であるが、一段落前のところで述べたように、「婚姻の本質」と称する説明は、具体的な婚姻制度の枠組みが存在することを前提として、その婚姻制度を利用した者の法律関係を説明したものであるから、この「婚姻の本質」と称するものを基準として、「婚姻」の中に「同性間」の人的結合関係を含めることができるか否かについての結論を導き出すことはできない。
そのため、「したがって、」というように、前の段落で述べられた「婚姻の本質」と称する説明を根拠とする形で、「憲法24条」が「婚姻」の中に「同性間」の人的結合関係を含めることを「禁止するものではな」いと説明することは、誤りである。
◇ 24条「婚姻」
↓ (要請)
◇ 法律上の「婚姻」
↓ (解釈)
◇ 「婚姻の本質」と称する説明(法律関係)
↓
× 「婚姻の本質」に照らせば、「婚姻」の範囲が分かると考える
↓
× 「婚姻」に「同性間」の人的結合関係を含めることは「禁止」されていないと考える
上記のように、「婚姻の本質」と称する説明は、憲法24条の「婚姻」や、具体的な法律上の婚姻制度を解釈した下位法にあたるものであるにもかかわらず、その下位法を根拠として、上位法の「婚姻」の意味を変更することの可否を論じようとすることは、法の階層構造を損なわせる誤った説明となっている。
憲法24条の「婚姻」の中に「同性間」の人的結合関係を含めることができるか否かについては、この東京地裁判決の考え方を使うとすれば、「2⑵ウ」のところで「憲法24条1項」について「婚姻を異性間のものとする社会通念」があり、その「背景」には「夫婦となった男女が子を産み育て、家族として共同生活を送りながら、次の世代につないでいくという古くからの人間の営みがある」と述べていることから導き出すことが必要である。
筆者はこの説明では不十分であると考えているが、少なくともこの東京地裁判決においても、憲法24条の「婚姻」の上位にあるものとして考えている点では、整合性があるからである。
◇ 「夫婦となった男女が子を産み育て、家族として共同生活を送りながら、次の世代につないでいくという古くからの人間の営みがある」(背景)
↓
◇ 「婚姻を異性間のものとする社会通念」
↓
◇ 24条「婚姻」
↓ (要請)
◇ 法律上の「婚姻」
↓ (解釈)
◇ 「婚姻の本質」と称する説明(法律関係)
このように、24条の「婚姻」が「同性間」の人的結合関係を「婚姻」とすることを認めているか否かという意味で、ここでいう「禁止するもの」であるか否かは、24条の「婚姻」よりも上位のものを基準にして導かれるのであり、下位法にあたる「婚姻の本質」と称する説明を根拠として「禁止するものではなく、」とか、「憲法24条に違反するものではない」とか述べることは、誤りである。
次に、「憲法24条は、本件諸規定が定める婚姻を同性間にも認める立法をすること……(略)……を禁止するものではなく、……(略)……憲法24条に違反するものではない」との部分を詳しく検討する。
この文は、「婚姻」の中に「同性間の人的結合関係」を含めることが可能であることを前提として、その「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを憲法24条が「禁止」しているか否か、つまり、「憲法24条に違反するもの」であるか否かを論じようとするものとなっている。
しかし、そもそも「婚姻」の中に「同性間の人的結合関係」を含めることができるのかどうかという部分から検討する必要がある。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
これらの学説を参照すると、憲法24条のいう「婚姻」の内実として同性カップルの「婚姻」というものが観念しうるのか、憲法上の「婚姻」とはそもそも男女が取り結ぶ一定の関係なのではないか、そして「同性」と「婚姻」を結びつけることが法的に可能なのかという問いが浮かぶ。
憲法24条が同性婚を想定していないのは確かだとして、憲法学説も民法学説も、従来、憲法24条の「婚姻」としては男女のカップルのそれを暗黙のうちに想定してきたと言える。「同性」という言葉と「婚姻」という言葉がそこでは結びついておらず、したがって「同性婚の自由」なるものが憲法上存在するかも定かではないのだ。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
生殖可能性のない同性婚を法律で認める理由はない…憲法学の専門家が「同性婚の法制化」にクギを刺す理由 2023/02/18
そこで、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」として扱うことができるかどうかを検討する。
■ いくつかの立場との関係性
24条の解釈について、いくつかの立場から検討する。
▼ 「婚姻」の由来説
この立場は、「婚姻」という枠組みが形成された由来を遡り、「婚姻」という概念そのものが有している「目的」とその目的を達成するための「手段」とを整合的な形で考えるものである。
「婚姻」という枠組みが形成された由来を考えるため、「婚姻」という概念そのものが有している内在的な限界も考慮することになる。
これについて、後ほど「24条の『婚姻』が『生殖と子の養育』の趣旨を含むこと」の項目でも解説する。
◇ 存在しない説
この立場は、「婚姻」とは自然生殖可能性のある組み合わせを優遇する制度であることから、それを満たさない形の「婚姻」というものは存在しないと考えるものである。
「同性間」についても、その間で自然生殖を想定することができないことから、「婚姻」とは言えず、「同性間」の「婚姻」という概念は存在しないことになる。
◇ 成立条件説
この立場は、24条1項の「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、」の文は「婚姻」の成立条件を示すものと考えるものである。
「両性」の部分が「婚姻」を成立させるために「男性」と「女性」の合意を必要とすると定めていることから、「同性間」で合意しても「婚姻」としては成立しないことになる。
◇ 想定していない説
この立場は、24条は「同性間」の人的結合関係を「婚姻」とすることを想定していないと考えるものである。
上記の三説と下記の三説のいずれの可能性もある。
◇ 立法裁量の限界を画するもの
この立場は、24条は立法裁量の限界を画する規定であることから、24条の文言に沿わない関係については、「婚姻」とすることができないと考えるものである。
そして、24条は一夫一婦制(男女二人一組)を定めており、この形に限定して立法裁量の限界を画していることから、それ以外の人的結合関係を「婚姻」とすることはできない。
このことから、「同性間」の人的結合関係についても、これを満たさないため、「婚姻」とすることはできないことになる。
◇ 禁止説
この立場は、24条の規定は、何かを想定した上でそれを防ぐ意図をもって定められていることから、その規定に合わないものについては禁止されていると考えるものである。
「同性間」の人的結合関係についても、24条の規定が「両性」「夫婦」の文言を定めていることに合わないことから、24条は「同性間」の人的結合関係を「婚姻」とすることの論点を認知した上で、それを防ぐ意図をもって禁止していることになる。
◇ 義務文・否定文による禁止説
24条1項の規定は「両性~に基づいて成立し、~なければならない。」(shall)という義務文・否定文による禁止の意味を有すると考えるものである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
Article 24. Marriage shall be based only on the mutual consent of both sexes and it shall be maintained through mutual cooperation with the equal rights of husband and wife as a basis.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24条1項の「両性の合意のみに基いて成立し、」の部分は、「~~してはならない。」というような義務文・否定文の形で何かを禁止するような書き方をしているわけではないが、24条1項全体で見れば、最後に「されなければならない。」と記載されている。
また、英語では「shall」の文言が2回使われており、「両性の合意のみに基いて成立し、」の部分についても「shall」で表現されている。
そのため、24条1項は義務文・否定文によって「禁止」する意味を有していると読むことが可能である。
これによれば、24条1項は「両性」を満たさない人的結合関係を「婚姻」とすることを義務文・否定文によって禁止していることになる。
「同性間」の人的結合関係を「婚姻」とすることについても、「両性」を満たさないため義務文・否定文によって禁止されていることになる。
どの説で考えることが妥当であるかを検討するためにも、「婚姻」という概念が形成されている由来を検討することが必要である。
そこで、下記ではさらに「婚姻」という概念が形成されている由来や、その目的と、その目的を達成するための手段となる枠組みについて検討する。
■ 「婚姻」が「生殖と子の養育」の趣旨を含むこと
▼ 「婚姻」の概念に含まれる内在的な限界
「婚姻」は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「生殖と子の養育」の観点に着目して他の人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度である。
これは、下記のような経緯によるものである。
その国の中で「生殖と子の養育」に関する事柄について何らの制度も存在しない場合には、社会的な不都合が発生することがある。
例えば、「父親不明」の子供が増える、父親を特定できない子供が増える、父親が蒸発して行方不明になった子供が増える、それらにより「子の福祉」が減少する、父親を特定できないことにより近親者の範囲を把握できずに「近親交配」に至り遺伝的な劣勢を有する個体が高い確率で発現するようになる、一部の強者が多数人との生殖関係を独占することによって社会の中で「子を持ちたいと希望して相手を見つけようとする男女」の数の不均衡が生じて「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」が生まれる、低年齢での妊娠・出産により母体に危険が及ぶ、などの問題が生じることがある。
「婚姻」は、これらの国民が「生殖」によって子供を産むことに関係して起き得る問題を抑制することを目的として、「生殖と子の養育」の観点に着目し、国家の政策の手段として一般的・抽象的に規格化する形(パッケージ)で設けられるようになった枠組みである。
そのため、「婚姻」には、下記の立法目的が存在すると考えられる。
・「子の福祉」が実現される社会基盤を構築すること
・遺伝的な劣勢を有する個体が高い確率で発現することを抑制すること
・「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」を減らすこと
・母体を保護すること
このような「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解決しようとする立法目的を離れて「婚姻」を観念することはできない。
そのため、「婚姻」という概念である以上は、国民が「生殖」によって子を産むことに関わる制度であることを前提としており、「婚姻」の文言の中には「生殖と子の養育」の趣旨が含まれている。
そして、「婚姻」である以上は、これらの目的を達成することを阻害する組み合わせを「婚姻」とすることはできないという内在的な限界がある。
そのため、「生殖と子の養育」の趣旨を満たさない人的結合関係を「婚姻」とすることはできない。
「同性間」の人的結合関係(同性三人以上の人的結合関係も同様)については、一般的・抽象的にその間で「生殖」を想定することができないことから、「生殖と子の養育」の趣旨を満たすとは言えず、「婚姻」の中に含めることはできない。
▼ 24条の「婚姻」による限界
24条に定められたものが「婚姻」である以上は、「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で形成された制度を引き継いでいることは明らかである。
そのことから、24条の「婚姻」の文言の中にも、「生殖と子の養育」の趣旨が含まれている。
これにより、24条の下で「生殖と子の養育」の趣旨を満たさない人的結合関係を「婚姻」とすることはできない。
もし、そのような人的結合関係を「婚姻」として立法しようとした場合には、24条に抵触して違憲となる。
「同性間」の人的結合関係については、一般的・抽象的にその間で「生殖」を想定することができず、「生殖と子の養育」の趣旨を満たすとはいえないから、24条の「婚姻」の中には含まれない。
そのため、「同性間」の人的結合関係を「婚姻」として立法しようとした場合には、24条の「婚姻」に抵触して違憲となる。
▽ 24条の「婚姻」が「生殖と子の養育」に関わる制度を一元的に集約していること
「婚姻」は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「生殖と子の養育」の観点から他の人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度である。
そして、24条は「婚姻」の内容について、「両性の合意のみ」や「個人の尊厳」「両性の本質的平等」を満たすように求めている。
これは、「婚姻」という制度については特に注意を払い、24条の統制に服させ、その内容に対して立法裁量の限界を画することが目的である。
この24条の規定が有する意図を実現するためには、「生殖と子の養育」に関わる制度を24条の「婚姻」の文言の中に一元的に集約する形で解釈することが必要であり、「生殖と子の養育」に関わる制度を24条の「婚姻」を離れて立法することはできない。
これは、下記が理由である。
仮に「生殖と子の養育」に関わる制度を、24条の「婚姻」から離れて別の制度として立法することができるとする場合を考えてみる。
すると、「生殖と子の養育」に関わる制度でありながら、24条によって統制(管理)することができない状態を許すことになる。
例えば、24条のいう「婚姻」とは別に「生殖関連制度」や「三人以上の生殖結社制度」などが立法されることが考えられる。
そうなると、24条は「婚姻」に対しては「両性の合意のみ」や「個人の尊厳」「両性の本質的平等」を満たすように求めて立法裁量の限界を画しているが、その「生殖と子の養育」に関わる制度は「婚姻」とは別の制度であることから、24条の統制が及ばないことになる。
すると、その「生殖と子の養育」に関わる制度は「婚姻」ではないため、「両性の合意」以外の条件を設けるものでも、「個人の尊厳」や「両性の本質的平等」に立脚しないものでも構わないことになる。
例えば、戦前の明治民法のような「戸主」の同意を必要とする「戸主付き生殖関連制度」や「家制度的生殖関連制度」を立法することも可能となる。
また、その「婚姻」とは異なる「生殖と子の養育」に関わる制度に対して「婚姻」よりも充実した優遇措置を整備した場合には、人々の大半はその制度を利用することを選択し、次第に「婚姻」を利用しなくなっていくことが考えられる。
すると、「婚姻」という制度が衰退していき、「婚姻」が「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するための制度として機能しなくなることが考えられる。
これでは、24条が「婚姻」に対して立法裁量の限界を画することによって、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために設けられた制度の内容が「両性の合意のみ」や「個人の尊厳」「両性の本質的平等」を満たすものとなるよう求める憲法上の立法政策としての目的を達成できない事態に陥る。
これでは、24条の趣旨が損なわれ、何のために24条が設けられているのか分からなくなる。
そのため、24条の規定の効果が保たれるためには、「生殖と子の養育」に関わる制度は24条の「婚姻」の文言が一元的に集約するものとして解釈することが必要となる。
このことから、「生殖と子の養育」に関わる制度を、24条の「婚姻」を離れて別の制度として立法することはできない。
もし「生殖と子の養育」に関わる制度を、24条の「婚姻」から離れて別の制度として立法しようとした場合には、24条の「婚姻」に抵触して違憲となる。
この前提がある以上は、24条の「婚姻」という文言の中には「生殖と子の養育」の趣旨が含まれており、この24条の「婚姻」の文言から「生殖と子の養育」の趣旨を切り離して考えることはできない。
これにより、「生殖と子の養育」の趣旨を満たさない人的結合関係を24条の「婚姻」として扱うことはできない。
よって、「同性間」の人的結合関係については「生殖と子の養育」の趣旨を満たさないため「婚姻」とすることはできない。
▽ 24条の「婚姻」から「生殖と子の養育」の趣旨が失われると24条の規定が有している目的を達成できないこと
仮に24条の「婚姻」という概念から「生殖と子の養育」の趣旨を切り離して考えることができるとする前提に立つとする。
すると、24条の「婚姻」の文言には「生殖と子の養育」の趣旨が含まれていないことになるから、24条の「婚姻」の文言には「生殖と子の養育」に関わる制度を一元的に集約しようとする趣旨も含まれていないことになる。
そうなると、「生殖と子の養育」に関わる制度について、24条の「婚姻」を離れて別の制度として立法することが可能となる。
「生殖と子の養育」に関わる制度が「婚姻」とは別の形で存在することを許すことになるから、「婚姻」が「生殖と子の養育」に関する様々な問題の発生を抑制しようとする機能を果たさなくなり、「婚姻」の政策効果が損なわれることになる。
また、その「生殖と子の養育」に関わる制度は、24条の「婚姻」とは別の制度であることから、24条の「両性の合意のみ」や「個人の尊厳」「両性の本質的平等」による統制が及ばないことになる。
つまり、その「生殖と子の養育」に関わる制度が、24条の「両性の合意のみ」や「個人の尊厳」「両性の本質的平等」を満たさないものとなっていても、それがもともと24条の「婚姻」ではないことを理由に、その制度の内容を是正することができなくなる。
これでは、本来「婚姻」を24条の統制の下に置くことによって、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するための制度の内容に対して「両性の合意のみ」や「個人の尊厳」「両性の本質的平等」を満たすように求めるという憲法上の立法政策を実現することができない事態に陥る。
これでは、24条の規定そのものが有する意図・目的を達成することができず、24条の規定が骨抜きとなる。
このような考えは解釈として妥当でない。
そのことから、「生殖と子の養育」に関わる制度については、24条の「婚姻」に結び付けて考える必要があり、24条の「婚姻」は「生殖と子の養育」に関わる制度を一元的に集約する趣旨を有している。
そのため、24条の「婚姻」を「生殖と子の養育」の趣旨と切り離して考えることはできない。
そのことから、「生殖と子の養育」の趣旨を満たさない人的結合関係を、24条の示している「婚姻」として扱うことはできない。
よって、「同性間」の人的結合関係については「生殖と子の養育」の趣旨を満たさないため「婚姻」とすることはできない。
▽ 「生殖と子の養育」の趣旨の内容
「婚姻」の中に「生殖と子の養育」の趣旨を含んだままでも、「同性間」の人的結合関係を「婚姻」として扱うことができるのではないかとの主張が考えられる。
これを検討する。
「婚姻」は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するため「生殖と子の養育」の観点から他の人的結合関係とは区別する意味で設けられた枠組みである。
そのため、下記の立法目的が存在すると考えられる。
・「子の福祉」が実現される社会基盤を構築すること
・遺伝的な劣勢を有する個体が高い確率で発現することを抑制すること
・「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」を減らすこと
・母体を保護すること
このような立法目的を離れて「婚姻」を観念することはできず、「婚姻」という概念である以上は、国民が「生殖」によって子を産むことに関わる制度であることを前提としている。
そのため、「婚姻」の文言の中には「生殖と子の養育」の趣旨が含まれている。
また、「婚姻」に含まれる「生殖と子の養育」の趣旨を満たすためには、単に何らかの生殖があり、子を養育することができる地位があればよいというものではなく、下記の要素を満たすことが求められると考えられる。
・子の遺伝的な父親を特定できる組み合わせとすること
・特定された子の父親にも子に対する責任を担わせること
・特定された子の父親を基に遺伝的な近親者を把握すること
・未婚の男女の数の不均衡を防止できる組み合わせに限定すること
これらの要素を満たすことは、「婚姻」という枠組みが形成されている目的との関係で整合的であり、他の人的結合関係とは区別する形で「婚姻」という概念が成り立つための境界線を保つことができるからである。
このことから、これらの要素を満たさない人的結合関係については、「婚姻」とすることはできない。
「同性間」の人的結合関係については、これらの要素を満たさないことから、「婚姻」とすることはできない。
そして、憲法24条の「婚姻」は、この意味の「婚姻」を引き継ぐ形で定められている。
24条が「婚姻」を定めている以上は、「婚姻」の立法目的を達成することを損なうことはできないという内在的な限界が含まれている。
また、24条の規定は「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言が定められており、「一夫一婦制」(男女二人一組)を前提としている。
ここで24条の「婚姻」の中に「生殖と子の養育」の趣旨が含まれていることや、「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言によって「一夫一婦制」(男女二人一組)を定めていることの理由は、下記の要素を満たすからであると考えられる。
・子の遺伝的な父親を特定できる組み合わせとすること
・特定された子の父親にも子に対する責任を担わせること
・特定された子の父親を基に遺伝的な近親者を把握すること
・未婚の男女の数の不均衡を防止できる組み合わせに限定すること
そのため、これらの要素を満たさない人的結合関係については、24条の「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言の趣旨に当てはまらず、「婚姻」とすることはできない。
もし、これらの要素を満たさない人的結合関係を「婚姻」として扱う立法を試みた場合には、24条の許容する立法裁量の限界を超え、24条に抵触して違憲となる。
「同性間」の人的結合関係については、これらの要素を満たさないため、「婚姻」とすることはできない。
また、24条の「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言の趣旨に当てはまらないため、「婚姻」とすることはできない。
もし「同性間」の人的結合関係を「婚姻」として扱おうとする法律を立法した場合には、24条に抵触して違憲となる。
これを前提として、この判決が「憲法24条は、本件諸規定が定める婚姻を同性間にも認める立法をすること……(略)……を禁止するものではなく、……(略)……憲法24条に違反するものではない」と述べている部分を改めて検討する。
24条の定める「婚姻」という概念は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために設けられた概念であり、その概念が形成されている目的との関係で内在的な限界がある。
そして、「婚姻」の中には「生殖と子の養育」の趣旨が含まれており、これを満たさない人的結合関係を「婚姻」の中に含めることはできない。
24条の「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言についても、この「生殖と子の養育」の趣旨と整合する形で定められたものとなっている。
そのことから、「同性間」の人的結合関係については、一般的・抽象的にその間で「生殖」を想定することができないことから、「生殖と子の養育」の趣旨を満たすとはいえず、「婚姻」とすることはできない。
また、24条の「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言の趣旨に当てはまらないため、「婚姻」とすることはできない。
結果として、「憲法24条は、」「婚姻を同性間にも認める立法をすること、」を認めていないことになる。
他にも、24条は「婚姻」を定めていることから、この24条の「婚姻」や「両性」「夫婦」「相互」の文言が、法律で立法される婚姻制度の意味や内容を「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するものとして機能しないものに変えてしまうことを許しているはずがない。
そのため、婚姻制度の中に「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することが不能となるような人的結合関係を含めようとする立法をすることを、「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」の文言に照らし合わせて考えた際に、これらの文言がそれを許容しているはずがない。
よって、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することが不能となるような人的結合関係を「婚姻」として扱おうとする法律を立法した場合には、「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」の文言に抵触して違憲となる。
この観点から、この判決が「憲法24条は、本件諸規定が定める婚姻を同性間にも認める立法をすること……(略)……を禁止するものではなく、……(略)……憲法24条に違反するものではない」と述べていることは誤っており、「同性間」の人的結合関係を「婚姻」として扱おうとする立法を試みた場合には、「憲法24条に違反する」ことになる。
「禁止するものではなく」との部分についても、24条が「同性間」の人的結合関係を「婚姻」とすることの論点を認知した上で、それを防ぐ意図をもって規定されていることから禁止するものであると考える説もあるし、24条の規定には「~なければならない。」(shall)と記載されていることから、義務文・否定文による禁止であると考える説もあるし、24条の下で婚姻制度を「同性間」の人的結合関係を含む形で立法しようとした場合には「憲法24条に違反する」ことを理由として、結果としてこれを「禁止するもの」という場合もある。
そのため、この点の整合性を何らの説明もないままに「禁止するものではなく」のように結論だけを述べて正当化できるという性質のものではない。
法解釈を論じる際には、結論だけを述べるだけでは何も正当化することはできないし、結論だけを戦わせるような議論をすることも意味はない。
法解釈では、結論に至るまでの過程が適切であるかどうかが問われているのであり、その過程が正当化できる理由によって支えられていないのであれば、結論も不当なものとなるのである。
この点で、解釈の過程において不当な内容が含まれており、「同性間」の人的結合関係を「婚姻」とすることができることを前提とする意味で、「禁止するものではなく」と述べていることについても正当化することはできない。
「憲法24条は、……(略)……同性間の人的結合関係について婚姻に類する制度を法律により構築することなどを禁止するものではなく、」との部分では、「婚姻に類する制度」と称するものについて述べているので、これについて検討する。
まず、憲法24条の「婚姻」の文言は「生殖と子の養育」に関わる制度を一元的に集約する趣旨を有しており、「生殖と子の養育」に関わる制度を24条の「婚姻」を離れて別の制度として立法することはできない。
そのことから、24条の「婚姻」を離れて別の制度として「生殖と子の養育」に関わる内容を有する制度を設けた場合には、24条の「婚姻」に抵触して違憲となる。
(これについては、『婚姻に類する制度』と称するものであっても同様である。)
これについて、下記で詳述する。
■ 「婚姻」が「生殖と子の養育」の趣旨を含むこと
「婚姻」は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「生殖と子の養育」の観点に着目して他の人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度である。
これは、下記のような経緯によるものである。
その国の中で「生殖と子の養育」に関する事柄について何らの制度も存在しない場合には、社会的な不都合が発生することがある。
例えば、「父親不明」の子供が増える、父親を特定できない子供が増える、父親が蒸発して行方不明になった子供が増える、それらにより「子の福祉」が減少する、父親を特定できないことにより近親者の範囲を把握できずに「近親交配」に至り遺伝的な劣勢を有する個体が高い確率で発現するようになる、一部の強者が多数人との生殖関係を独占することによって社会の中で「子を持ちたいと希望して相手を見つけようとする男女」の数の不均衡が生じて「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」が生まれる、低年齢での妊娠・出産により母体に危険が及ぶ、などの問題が生じることがある。
「婚姻」は、これらの国民が「生殖」によって子供を産むことに関係して起き得る問題を抑制することを目的として、「生殖と子の養育」の観点に着目し、国家の政策の手段として一般的・抽象的に規格化する形(パッケージ)で設けられるようになった枠組みである。
そのため、「婚姻」には、下記の立法目的が存在すると考えられる。
・「子の福祉」が実現される社会基盤を構築すること
・遺伝的な劣勢を有する個体が高い確率で発現することを抑制すること
・「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」を減らすこと
・母体を保護すること
このような「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解決しようとする立法目的を離れて「婚姻」を観念することはできない。
よって、「婚姻」という概念である以上は、国民が「生殖」によって子を産むことに関わる制度であることを前提としており、「婚姻」の文言の中には「生殖と子の養育」の趣旨が含まれている。
■ 「生殖と子の養育」の趣旨の内容
また、「婚姻」に含まれる「生殖と子の養育」の趣旨を満たすためには、単に何らかの生殖があり、子を養育することができる地位があればよいというものではなく、下記の要素を満たすことが求められると考えられる。
・子の遺伝的な父親を特定できる組み合わせとすること
・特定された子の父親にも子に対する責任を担わせること
・特定された子の父親を基に遺伝的な近親者を把握すること
・未婚の男女の数の不均衡を防止できる組み合わせに限定すること
これらの要素を満たすことは、「婚姻」という枠組みが形成されている目的との関係で整合的であり、他の人的結合関係とは区別する形で「婚姻」という概念が成り立つための境界線を保つことができるからである。
(「婚姻」である以上は、「婚姻」という概念を成り立たせるための「婚姻」という概念そのものが内在的に有している限界が存在する。「婚姻」という概念が他の様々な人的結合関係とは区別する形で枠づけられていることからくる境界線である。「婚姻」という概念そのものに、他の様々な人的結合関係との間で区別することを可能とする要素が含まれているということである。これは、もし「婚姻」という概念を成り立たせる境界線となる一線を損なった場合には、「婚姻」という枠組みそのものを他の人的結合関係との間で区別することができなくなり、「婚姻」という概念自体が成り立たなくなり、「婚姻」という概念そのものが雲散霧消してしまうからである。)
■ 24条の「婚姻」が「生殖と子の養育」の趣旨を含むこと
24条に定められたものが「婚姻」である以上は、「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で形成された制度を引き継いでいることは明らかである。
そのため、24条の「婚姻」の文言の中にも、「生殖と子の養育」の趣旨が含まれている。
また、24条の規定は「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言が定められており、「一夫一婦制」(男女二人一組)を前提としている。
「一夫一婦制」(男女二人一組)を定めていることの理由は、24条の「婚姻」の中に「生殖と子の養育」の趣旨が含まれていることと同様に、下記の要素を満たすからであると考えられる。
・子の遺伝的な父親を特定できる組み合わせとすること
・特定された子の父親にも子に対する責任を担わせること
・特定された子の父親を基に遺伝的な近親者を把握すること
・未婚の男女の数の不均衡を防止できる組み合わせに限定すること
このことは、24条に定められた「婚姻」が、他の様々な人的結合関係とは「生殖と子の養育」の観点から区別する意味で設けられた制度であることを裏付けるものでもある。
■ 24条の「婚姻」が「生殖と子の養育」に関わる制度を一元的に集約していること
24条は「婚姻」の内容について、「両性の合意のみ」や「個人の尊厳」「両性の本質的平等」を満たすように求めている。
これは、「婚姻」という制度については特に注意を払い、24条の統制に服させ、その内容に対して立法裁量の限界を画することが目的である。
この24条の規定が有する意図を実現するためには、「生殖と子の養育」に関わる制度を24条の「婚姻」の文言の中に一元的に集約する形で解釈することが必要であり、「生殖と子の養育」に関わる制度を24条の「婚姻」を離れて立法することはできない。
これは、下記が理由である。
仮に、「生殖と子の養育」に関わる制度を24条の「婚姻」を離れて別の制度として立法することが可能であるとする。
すると、「生殖と子の養育」に関わる制度でありながら、24条によって統制(管理)することができない状態が存在することを許すことになる。
例えば、24条の「婚姻」とは別に、「生殖関連制度」や「三人以上の生殖結社制度」などが立法されることが考えられる。
そうなると、その「生殖と子の養育」に関わる制度は「婚姻」とは別の制度であることから、24条の統制は及ばない。
すると、その制度は「婚姻」ではないため、「両性の合意」以外の条件を設けるものでも、「個人の尊厳」や「両性の本質的平等」に立脚しないものでも構わないことになる。
戦前の明治民法のような「戸主」の同意を必要とする「戸主付き生殖関連制度」や「家制度的生殖関連制度」を立法することも可能ということである。
また、その「婚姻」とは異なる「生殖と子の養育」に関わる制度に対して「婚姻」よりも充実した優遇措置を整備した場合には、人々の大半はその制度を利用することを選択し、次第に「婚姻」を利用しなくなっていくことが考えられる。
すると、「婚姻」という制度が衰退していき、「婚姻」が「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するための制度として機能しなくなる。
これでは、24条が「婚姻」に対して立法裁量の限界を画することによって、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために設けられた制度の内容が「両性の合意のみ」や「個人の尊厳」「両性の本質的平等」を満たすものとなるよう求める憲法上の立法政策としての目的を達成できない事態に陥る。
このように考えることは、24条の趣旨が損なわれ、何のために24条が設けられているのか分からなくなるため妥当でない。
そのため、24条の規定の効果が保たれるためには、「生殖と子の養育」に関わる制度は24条の「婚姻」の文言が一元的に集約するものとして解釈することが求められる。
このため、「生殖と子の養育」に関わる制度を、24条の「婚姻」を離れて別の制度として立法することはできない。
もし「生殖と子の養育」に関わる制度を、24条の「婚姻」から離れて別の制度として立法しようとした場合には、24条の「婚姻」に抵触して違憲となる。
■ 24条の「婚姻」から「生殖と子の養育」の趣旨が失われると24条の規定が有している目的を達成できないこと
仮に24条の「婚姻」という概念から「生殖と子の養育」の趣旨を切り離して考えることができるとする前提に立つとする。
すると、24条の「婚姻」の文言には「生殖と子の養育」の趣旨が含まれていないことになるから、24条の「婚姻」の文言には「生殖と子の養育」に関わる制度を一元的に集約しようとする趣旨も含まれていないことになる。
そうなると、「生殖と子の養育」に関わる制度について、24条の「婚姻」を離れて別の制度として立法することが可能となる。
「生殖と子の養育」に関わる制度が「婚姻」とは別の形で存在することを許すことになるから、「婚姻」が「生殖と子の養育」に関する様々な問題の発生を抑制しようとする機能を果たさなくなり、「婚姻」の政策効果が損なわれることになる。
また、その「生殖と子の養育」に関わる制度は、24条の「婚姻」とは別の制度であることから、24条の「両性の合意のみ」や「個人の尊厳」「両性の本質的平等」による統制が及ばないことになる。
つまり、その「生殖と子の養育」に関わる制度が、24条の「両性の合意のみ」や「個人の尊厳」「両性の本質的平等」を満たさないものとなっていても、それがもともと24条の「婚姻」ではないことを理由に、その制度の内容を是正することができなくなる。
これでは、本来「婚姻」を24条の統制の下に置くことによって、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するための制度の内容に対して「両性の合意のみ」や「個人の尊厳」「両性の本質的平等」を満たすように求めるという憲法上の立法政策を実現することができない事態に陥る。
これでは、24条の規定そのものが有する意図・目的を達成することができず、24条の規定が骨抜きとなる。
このような考えは解釈として妥当でない。
そのことから、「生殖と子の養育」に関わる制度については、24条の「婚姻」に結び付けて考える必要があり、24条の「婚姻」は「生殖と子の養育」に関わる制度を一元的に集約する趣旨を有している。
このことから、「生殖と子の養育」に関わる制度を、24条の「婚姻」を離れて別の制度として立法することはできない。
もし「生殖と子の養育」に関わる制度を、24条の「婚姻」から離れて別の制度として立法しようとした場合には、24条の「婚姻」に抵触して違憲となる。
よって、この判決のいう「婚姻に類する制度」の内容が「生殖と子の養育」に関わる制度となっている場合には、24条の「婚姻」に抵触して違憲となる。
これより、「婚姻に類する制度」の内容が、「婚姻に類する制度」を利用する個々人に対して何らかの「生殖」によって子を持つことにインセンティブを与えることに繋がる(影響を与える)場合や、子を含む形で規定され「子の養育」に関わる内容を有している(影響を与える)場合など、「生殖と子の養育」に結び付くものとなっている場合には、「生殖と子の養育」に関わる制度となっていることを意味する。
これは、「生殖と子の養育」に関わる制度を24条の「婚姻」を離れて別の制度として立法しようとするものということができ、24条が「生殖と子の養育」に関わる制度の内容を24条の「婚姻」の文言の中に一元的に集約して規律しようとする趣旨を満たすものではなく、24条の「婚姻」に抵触して違憲となる。
よって、この判決では「憲法24条は、……(略)……同性間の人的結合関係について婚姻に類する制度を法律により構築することなどを禁止するものではなく、」のように、「憲法24条」の下で「婚姻に類する制度」と称するものを「法律により構築すること」が可能であるかのような前提で論じるものとなっているが、上記のような内容となっている場合には、24条の「婚姻」に抵触して違憲となるため、「禁止するものではなく」と断定することはできないという点で、誤りとなる。
その他の論点で、「婚姻に類する制度」と称するものについても、既に「婚姻に類する」と述べている時点で、「婚姻」の立法目的の実現を阻害するものとなってはならないとの内在的な限界が含まれていることが明らかであるし、そもそも婚姻制度の立法目的との関係で婚姻制度の下では「婚姻に類する制度」と称するものは立法してはならないという結論が導き出されることも考えられるのであり、その点の整合性を明らかにしないままに「婚姻に類する制度」と称するものを立法することが可能であるかのような前提で論じていることも妥当でない。
「婚姻に類する制度」と称するものを立法した場合には、婚姻制度の立法目的の実現を阻害することに繋がることが考えられ、そのような制度を立法していないことの意味が重視されている場合があることを看過してはならない。
「上記のような立法は、その内容が個人の尊厳と両性の本質的平等に反し立法府に与えられた裁量権の範囲を逸脱するものでない限り、憲法24条に違反するものではないということができる。」との部分を検討する。
「上記のような立法」の部分であるが、「同性間の人的結合関係」についてはそもそも「婚姻」とすることができないと考えられ、24条における「婚姻」として24条2項の「個人の尊厳」や「両性の本質的平等」が適用される対象ではない。
よって、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」として認めることができるとの前提に立ち、24条の「個人の尊厳」や「両性の本質的平等」が適用される対象であるかのように考えた上で、これに反して「立法府に与えられた裁量権の範囲を逸脱する」か否かを検討することができるかのように考えている部分が誤りである。
また、「婚姻に類する制度」と称するものについても、そもそも24条の「婚姻」は「生殖と子の養育」に関わる制度を一元的に集約して規律する趣旨を有していることから、24条の「婚姻」を離れて別の制度として「生殖と子の養育」に関わる制度を立法することはできないのであり、「婚姻に類する制度」として「生殖と子の養育」に関わる制度を立法することが可能であるかのように考えているのであれば誤りである。
また、ここでいう「婚姻に類する制度」と称するかどうかは別として、何らかの制度を立法する場合を考えようとしても、それは「婚姻及び家族」ではないのであるから、24条2項の「個人の尊厳」や「両性の本質的平等」が適用される対象ではない。
そのため、「婚姻及び家族」ではない制度であるにもかかわらず、24条2項の「個人の尊厳」や「両性の本質的平等」が適用される対象であるかのように考えた上で、これに反して「立法府に与えられた裁量権の範囲を逸脱する」か否かを検討することができるかのようなに考えている部分も誤りである。
(ウ) 同性愛者は、性的指向という本人の意思で変えることのできない事由により、本件諸規定により婚姻制度を利用することができない状態に置かれている。また、前記認定事実(4)アのとおり、一定数の地方公共団体がパートナーシップ証明制度を導入し、同性カップルをパートナーすなわち家族として公証することを行っているものの、これは地方公共団体ごとの取組みであって、国においてはこのような制度は存在しない。その結果、同性愛者は、そのパートナーとの共同生活について、家族として法的保護を受け、社会的に公証を受けることが法律上できない状態にある。
【筆者】
「同性愛者は、性的指向という本人の意思で変えることのできない事由により、本件諸規定により婚姻制度を利用することができない状態に置かれている。」との記載がある。
しかし、婚姻制度は「性愛」の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いを行うものではないし、「性愛」に基づいて「婚姻」することを求めるものでも、勧めるものでもない。
そのため、「同性愛者」と称する者であるとしても、婚姻制度(男女二人一組)の要件を満たした上で、婚姻制度を利用する意思があれば、適法に「本件諸規定により婚姻制度を利用すること」ができるのであり、これを「本件諸規定により婚姻制度を利用することができない状態に置かれている。」と論じることは誤りである。
また、「性的指向という本人の意思で変えることのできない事由により、」との部分についても、そもそも婚姻制度は「性愛」の思想、信条、信仰、感情の有無を審査していないし、「性愛」に基づいて「婚姻」することを求めるものでも、勧めるものでもない。
そのため、「性的指向」に基づいて区別取扱いをしている事実はないことから、それが「本人の意思で変えることのできない」ものであるか否かも、一切関係がない。
「本人の意思で変えることのできない事由」とは、例えば、人間を「コーカソイド(白色人種)」・「モンゴロイド(黄色人種)」・「ニグロイド(黒色人種)」に区別した上で、その区別に従う形で法的な取り扱いを変えた場合に生じるものである。
しかし、婚姻制度は「性愛」の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にどのような対象に向かうかを審査していないし、「性愛」に基づいて「婚姻」することを求めるものでも勧めるものでもなく、「性愛」に基づいた区別をしているという事実が存在しない。
そのため、区別取扱いをしている事実が存在する上で、それが「本人の意思で変えることのできない事由」による区別取扱いであるか否かを検討するものとは性質を異にしている。
むしろ、この東京地裁判決が、「イ(ア)」や「イ(イ)」のところで「性的指向による区別取扱いに当たるものと認められる。」などと、婚姻制度が「性的指向による区別取扱い」を行っていることを前提として論じていること自体が、個々人を「性的指向」(この判決では『本人の意思で変えることのできない事由』とも述べられているもの)に基づいて区別することを前提とするものとなっており、不適切である。
このような法制度が「性的指向」に基づいて区別取扱いを行っているかのような理解は、特定の「性愛」の思想、信条、信仰、感情を保護することになるから、憲法20条1項後段、3項、89条の「政教分離原則」に抵触して違憲となる。
また、「性愛」を有する場合にどのような対象に向かうかという「性的指向」と称する内心に基づいて、法制度の利用の可否を変えるものであるから、憲法19条の「思想良心の自由」に抵触して違憲となる。
さらに、「性愛」という思想、信条、信仰、感情を保護し、それ以外の思想、信条、信仰、感情を保護しないということについても、憲法14条の「平等原則」に抵触して違憲となる。
そのため、この東京地裁判決がいう「性的指向という本人の意思で変えることのできない事由」によって、区別取扱いを行っていることを前提としていること自体が、憲法違反となるものということができる。
一方、現行の婚姻制度そのものは、そもそも区別取扱いを行っている事実がないことにより、憲法違反とはならない。
「同性愛者は、……(略)……本件諸規定により婚姻制度を利用することができない状態に置かれている。」との部分の誤りを理解するために、下記の事例を挙げる。
まず、「性愛」とは個々人の「内心の自由」によって捉えられるものであり、それを客観的に識別することができる性質のものではない。
そして、「性愛」は、「異性愛」と「同性愛」だけではないため、それを「異性愛者」と「同性愛者」とに完結に二分できるわけではない。
「両性愛者」、「全性愛者」、「近親性愛者」、「多性愛者」、「小児性愛者」、「老人性愛者」、「死体性愛者」、「動物性愛者」、「対物性愛者」、「対二次元性愛者」、「無性愛者」など様々な分類が論じられている。
それを前提に、例えば、「無性愛者」を称する者が「婚姻制度を利用すること」はまったく支障はないはずである。
婚姻制度は個々人の内心を審査して区別取扱いをするものではないからである。
また、「小児性愛者」、「老人性愛者」、「死体性愛者」を称する者であるとしても、同様に「婚姻制度を利用すること」はまったく支障はないはずである。
それにもかかわらず、この判決はそれが「同性愛者」であるとした場合には、「本件諸規定により婚姻制度を利用することができない状態に置かれている。」と論じているのである。
これは、個々人の内心を審査して、「同性愛者」を称する者に対して、婚姻制度の適用を否定するものであるから、憲法14条の「平等原則」における「法適用の平等」に違反するものである。
○ 「無性愛者」 → 「婚姻制度を利用すること」に支障はない。
○ 「近親性愛者」 → 「婚姻制度を利用すること」に支障はない。
○ 「多性愛者」 → 「婚姻制度を利用すること」に支障はない。
○ 「小児性愛者」 → 「婚姻制度を利用すること」に支障はない。
× 「同性愛者」 → 「婚姻制度を利用することができない状態に置かれている。」
「同性愛者」を称する者に対するこのような評価は、法的にはまったく整合性がないものであり、不当な主張である。
よって、「同性愛者」を称する者も、「婚姻制度を利用すること」は可能である。
「一定数の地方公共団体がパートナーシップ証明制度を導入し、同性カップルをパートナーすなわち家族として公証することを行っているものの、これは地方公共団体ごとの取組みであって、国においてはこのような制度は存在しない。」との記載がある。
まず、「一定数の地方公共団体がパートナーシップ証明制度を導入し、」との部分であるが、「地方公共団体」の「パートナーシップ証明制度」の内容が民法上の婚姻制度に抵触する場合には違法となる。
婚姻制度は下記の立法目的に応じて、それを達成するための手段として枠組みが定められていると考えられる。
〇 「子の福祉」が実現される社会基盤を構築すること
(→ 達成手段:嫡出子として生まれることの重視)
〇 遺伝的な劣勢を有する個体が高い確率で発現することを抑制すること
(→ 達成手段:父親と近親者を特定して『近親交配』を防ぐ仕組みを導入)
〇 「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」を減らすこと
(→ 達成手段:未婚の男女の数の不均衡の防止。一夫一婦制、複婚の禁止)
〇 母体を保護すること
(→ 達成手段:婚姻適齢)
「地方自治体」の「パートナーシップ証明制度」の内容が、これらの目的を達成することを阻害するものとなっている場合には、民法の婚姻制度に抵触して違法となる。
また、憲法は14条で「平等原則」、19条で「思想良心の自由」、20条1項・3項、89条で「政教分離原則」を定めており、特定の思想や信条に着目して法制度を整備し、何らかの優遇措置を与えることは違憲となる。
「地方自治体」の「パートナーシップ証明制度」の内容が、「同性愛」という特定の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的として定められたものとなっている場合には、憲法20条1項・3項、89条の「政教分離原則」に抵触して違憲となる。
また、「同性愛」という特定の思想、信条、信仰、感情を保護し、その他の思想、信条、信仰、感情を保護しないことになることから、憲法14条の「平等原則」抵触して違憲となる。
他にも、「同性愛」の思想、信条、信仰、感情を有する「同性愛者」を称する者を対象とした制度となっていることについても、個々人の内心に基づいて区別取扱いを行い、その他の思想、信条、信仰、感情を有する者との間で、憲法14条の「平等原則」に抵触して違憲となる。
さらに、婚姻制度が「生殖と子の養育」の観点から一般的・抽象的にその間で「生殖」を想定することができる「男女二人一組」を対象としていることに対して、「パートナーシップ証明制度」はそのような観点を含まない「二人一組」のみを制度として一定の優遇措置を設けるものとなっている。
このような措置は、「三人一組」や「四人一組」などその他の人的結合関係を形成する者との間や、何らの人的結合関係も形成していない者との間で正当化することのできない差異を生じさせるものであることから、憲法14条の「平等原則」に抵触して違憲となる。
そのため、民法上の婚姻制度や憲法上の規定との整合性を検討をしないままに、「地方公共団体」の「パートナーシップ証明制度」が適法な制度であることを前提として論じていることは、妥当でない。
詳しくは当サイト「パートナーシップ制度」で解説している。
「同性カップルをパートナーすなわち家族として公証することを行っているものの、」の部分であるが、「家族」の文言の意味を検討する必要がある。
「家族」には、法学的な意味の「家族」と、社会学的な意味の「家族」がある。
法学的な意味の「家族」とは、憲法24条2項が「婚姻及び家族」と示している場合の「家族」の意味である。
この「家族」は、「婚姻」と密接に関わる形で、「婚姻」の立法目的の実現を阻害しない範囲で規律される枠組みである。
社会学的な意味の「家族」とは、日常用語として「共同生活者」を指すものとして使われることが多い。
この社会学的な意味の「家族」の範囲は、それぞれの人が「家族」と考えるものを「家族」と呼んでいるだけであることから、共通した定義が存在するわけではない。
そして、「共同生活者」のことを「家族」と呼んでいる場合には、その人的結合関係は憲法21条1項の「結社の自由」によって保障されることになる。
この東京地裁判決のこの部分で使われている「地方公共団体」が「パートナーシップ証明制度」によって「家族として公証することを行っている」という場合の「家族」の意味であるが、これは、憲法24条2項の「婚姻及び家族」の文言の要請に従って定められた法律上の「家族」とは異なるものであり、法学的な意味の「家族」とはいえない。
そのため、一般人が何らかの結社を行った場合にその構成員のことを日常用語として「家族」と呼称することはあり得るとしても、裁判所が判決文を書く際に、この点の法学的な意味の「家族」と社会学的な意味の「家族」の意味を混同し、これを区別しないままに「地方自治体」が実施している「パートナーシップ証明制度」における人的結合関係のことを「家族」と表現することは誤った説明となる。
「同性カップルをパートナー」との部分については、「地方自治体」の「パートナーシップ証明制度」が「二人一組」を前提とした制度であることを述べているものである。
しかし、そもそも「地方自治体」の「パートナーシップ証明制度」や、その制度について説明するこの東京地裁判決は、なぜ人的結合関係が「二人一組」であるのか、その根拠を説明しないままに制度を正当化しようとするものとなっており、「カップル信仰論」に陥っている。
婚姻制度が「男女二人一組」の形となっていることについては、「生殖と子の養育」の観点から、「男性」と「女性」の間に「貞操義務」を設けることによって、その間で自然生殖が行われた場合に、遺伝的な父親を特定することができるという部分から、「男性」と「女性」を組み合わせた「二人一組」であることに必然性を見出すことができる。
そして、父親を特定することによって、「近親交配」を回避することが可能となるし、「男女二人一組」の形に限定している場合においては、未婚の男女の数の不均衡を防止することが可能となるため、「生殖機会の公平」にも寄与することになる。「婚姻適齢」を満たした者の間での「生殖と子の養育」であれば、「母体の保護」の観点や、「子育ての能力」の観点からも、一般には支障がないものと考えられる。
このような関係性を形成した者に対して一定の優遇措置を講じることは、その社会の中で「生殖」に関わって生じる不都合を解消するという目的に資することから、その「婚姻制度を利用している者(既婚者)」は、「婚姻制度を利用していない者(独身者)」との間で優遇措置が与えられることが正当化されることになる。
しかし、ここでいう「同性カップル」という「同性間」の人的結合関係については、その間で「生殖」を想定することができず、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する形で制度を設けるという目的からは導かれないものである。
そのため、「同性間」の人的結合関係に対して、何らかの優遇措置を講じることは、何らの人的結合関係も形成していない者との間で、合理的な理由を説明することのできない利益の差異を生じさせるものとなる。
よって、「同性間」の人的結合関係に対して、「パートナーシップ証明制度」などを設けて、何らかの優遇措置を講じることは、その制度を利用しておらず、何らの人的結合関係も形成していない者との間で、得られる利益の内容に合理的な理由のない差異を生じさせるものであることから、憲法14条の「平等原則」に抵触して違憲となる。
また、「同性間」については、そもそもその間で「生殖」を想定することができないのであり、婚姻制度のような「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を有する制度ではないことから、その内容を「二人一組」とする必然性もないのであり、理由もなく「二人一組」としているのであれば、「カップル信仰論」となっているものである。
人的結合関係には、「三人以上」の人的結合関係も存在するのであり、「二人一組」だけを特別視して制度を設けていること自体にも合理的な理由はないのである。
「国においてはこのような制度は存在しない。」との部分であるが、婚姻制度の枠組みに当てはまらない人的結合関係に対して何らかの法的効果を及ぼす法制度を立法した場合には、婚姻制度の政策効果を阻害し、婚姻制度の立法目的を達成することを困難とすることが考えられるのであり、「このような制度」が存在しないことそのものに意味があるという場合もあり得る。
そのことから、「このような制度」が存在しなければならないかのような前提で論じていることは、妥当でない。
「同性愛者は、そのパートナーとの共同生活について、家族として法的保護を受け、社会的に公証を受けることが法律上できない状態にある。」との記載がある。
まず、「同性愛者は、」との部分であるが、婚姻制度は「性愛」の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いを行うものではないし、「性愛」に基づいて「婚姻」することを求めるものでも勧めるものでもない。
また、「同性愛者」を称する者であっても、「男女二人一組」の婚姻制度を利用することは可能であるし、実際に婚姻制度を利用している者もいるのであり、婚姻制度を利用する形で、法学的な意味の「家族」となることができる。
そのため、「同性愛者」と称する者が、婚姻制度を利用した場合には、法学的な意味の「家族」となることができるのであり、「法律上」において、「同性愛者」であることを理由として法学的な意味での法制度上の「家族」とすることを否定している事実はなく、これが「法律上できない状態にある。」と述べていることは誤りである。
これについては、「両性愛者」、「全性愛者」、「近親性愛者」、「多性愛者」、「小児性愛者」、「死体性愛者」、「動物性愛者」を称する者であるとしても同様であり、それらを称する者が婚姻制度を利用した場合には、法学的な意味の法制度上の「家族」となることが可能である。
それらを称する者であることを理由として法学的な意味での法制度上の「家族」とすることを否定している事実はないのである。
婚姻制度の枠組みに当てはまる形で制度を利用することは、その者の内心がどのようなものであるとしても利用することができ、婚姻制度の枠組みに当てはまらない者は、その者の内心がどのようなものであるとしても、利用することはできないのである。
これは、「同性愛者」を称する者であるかどうかは、一切関わりのないことである。
次に、「パートナーとの共同生活」の部分であるが、通常、「共同生活」については、憲法21条1項の「結社の自由」によって保障されることになる。
よって、「家族として」との部分の「家族」の意味を広く社会学的な意味の「家族」と考えた場合については、「共同生活」は憲法21条1項の「結社の自由」によって保障されるものである。
これについては、「パートナー」という「二人一組」の「共同生活」に限らず、「トリオ」である「三人一組」の「共同生活」であっても、「四人一組」の「共同生活」であっても、それ以上組み合わせによる「共同生活」であっても、同様に憲法21条1項の「結社の自由」によって保障されることになる。
憲法24条2項は、婚姻に関する事項のみならず、家族に関する事項についても、その立法に当たり個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべき旨を示しているところ、このような状態が、憲法24条2項が掲げる個人の尊厳に照らして合理性を欠き、立法裁量の範囲を超えるものとみざるを得ないような場合に当たるか否かという点を踏まえ、本件諸規定の憲法24条2項適合性を検討する。
【筆者】
「憲法24条2項」の「婚姻」や「家族」の文言は、法学的な意味の「婚姻」や「家族」を指しており、その中に含まれる人的結合関係の範囲には内在的な限界がある。
それにもかかわらず、どのような人的結合関係でも「婚姻」や「家族」の中に含まれることを前提として「憲法24条2項適合性」を論じようとしている点で誤りである。
イ 前記 イのとおり、憲法24条2項は、具体的な制度の構築を第一次的には国会の合理的な立法裁量に委ねるとともに、その立法に当たっては、同条1項も前提としつつ、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきであるとする要請、指針を示すことによって、その裁量の限界を画したものといえる。
そして、憲法24条が、本質的に様々な要素を検討して行われるべき立法作用に対してあえて立法上の要請、指針を明示していることからすると、その要請、指針は、単に、憲法上の権利として保障される人格権を不当に侵害するものでなく、かつ、両性の形式的な平等が保たれた内容の法律が制定されればそれで足りるというものではないのであって、憲法上直接保障された権利とまではいえない人格的利益をも尊重すべきこと、両性の実質的な平等が保たれるように図ること、婚姻制度の内容により婚姻をすることが事実上不当に制約されることのないように図ること等についても十分に配慮した法律の制定を求めるものであり、この点でも立法裁量に限定的な要請をし、指針を与えるものといえる。
他方で、婚姻及び家族に関する事項は、国の伝統や国民感情を含めた社会状況における種々の要因を踏まえつつ、それぞれの時代における家族関係についての全体の規律を見据えた総合的な判断によって定められるべきものである。特に、憲法上直接保障された権利とまではいえない人格的利益や実質的平等は、その内容として多様なものが考えられ、それらの実現の在り方は、その時々における社会的条件、国民生活の状況、家族の在り方等との関係において決められるべきものである。
したがって、婚姻及び家族に関する法制度を定めた法律の規定が憲法14条1項に違反しない場合に、更に憲法24条2項にも適合するものとして是認されるか否かは、当該法制度の趣旨や同制度を採用することにより生ずる影響につき検討し、当該規定が個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理性を欠き、国会の立法裁量の範囲を超えるものとみざるを得ないような場合に当たるか否かという観点から判断すべきものと解するのが相当である。(以上につき、平成27年夫婦同氏制大法廷判決参照)
【筆者】
最後の部分で「平成27年夫婦同氏制大法廷判決」を参照として示しているため、正確な引用となっているのかを確認する。
・この東京地裁判決と「平成27年夫婦同氏制大法廷判決」でまったく同じ文となっているところは灰色で潰した。
・この東京地裁判決が、「平成27年夫婦同氏制大法廷判決」の文面を変更(改竄)しているところは赤字で示した。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2(1) 憲法24条は,1項において「婚姻は,両性の合意のみに基いて成立し,夫婦が同等の権利を有することを基本として,相互の協力により,維持されなければならない。」と規定しているところ,これは,婚姻をするかどうか,いつ誰と婚姻をするかについては,当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたものと解される。
(略)
(2) 憲法24条は,2項において「配偶者の選択,財産権,相続,住居の選定,離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては,法律は,個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して,制定されなければならない。」と規定している。
婚姻及び家族に関する事項は,関連する法制度においてその具体的内容が定められていくものであることから,当該法制度の制度設計が重要な意味を持つものであるところ,憲法24条2項は,具体的な制度の構築を第一次的には国会の合理的な立法裁量に委ねるとともに,その立法に当たっては,同条1項も前提としつつ,個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきであるとする要請,指針を示すことによって,その裁量の限界を画したものといえる。
そして,憲法24条が,本質的に様々な要素を検討して行われるべき立法作用に対してあえて立法上の要請,指針を明示していることからすると,その要請,指針は,単に,憲法上の権利として保障される人格権を不当に侵害するものでなく,かつ,両性の形式的な平等が保たれた内容の法律が制定されればそれで足りるというものではないのであって,憲法上直接保障された権利とまではいえない人格的利益をも尊重すべきこと,両性の実質的な平等が保たれるように図ること,婚姻制度の内容により婚姻をすることが事実上不当に制約されることのないように図ること等についても十分に配慮した法律の制定を求めるものであり,この点でも立法裁量に限定的な指針を与えるものといえる。
3(1) 他方で,婚姻及び家族に関する事項は,国の伝統や国民感情を含めた社会状況における種々の要因を踏まえつつ,それぞれの時代における夫婦や親子関係についての全体の規律を見据えた総合的な判断によって定められるべきものである。特に,憲法上直接保障された権利とまではいえない人格的利益や実質的平等は,その内容として多様なものが考えられ,それらの実現の在り方は,その時々における社会的条件,国民生活の状況,家族の在り方等との関係において決められるべきものである。
(2) そうすると,憲法上の権利として保障される人格権を不当に侵害して憲法13条に違反する立法措置や不合理な差別を定めて憲法14条1項に違反する立法措置を講じてはならないことは当然であるとはいえ,憲法24条の要請,指針に応えて具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定が上記(1)のとおり国会の多方面にわたる検討と判断に委ねられているものであることからすれば,婚姻及び家族に関する法制度を定めた法律の規定が憲法13条,14条1項に違反しない場合に,更に憲法24条にも適合するものとして是認されるか否かは,当該法制度の趣旨や同制度を採用することにより生ずる影響につき検討し,当該規定が個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理性を欠き,国会の立法裁量の範囲を超えるものとみざるを得ないような場合に当たるか否かという観点から判断すべきものとするのが相当である。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「平成27年夫婦同氏制大法廷判決」 (PDF)
赤字の変更(改竄)されている部分は、下記の通りである。
「平成27年夫婦同氏制大法廷判決」→「東京地裁判決」
・「限定的な指針を与える」→「限定的な要請をし、指針を与える」
・「夫婦や親子関係」→「家族関係」
・「憲法24条にも」→「憲法24条2項にも」
このような変更(改竄)を行っている部分から、この東京地裁判決が結論を下す際に、恣意的な意図をもって論理を捻じ曲げようとしている部分がないかを読み取っていくことが必要である。
特に、「婚姻及び家族」の「家族」とは、「夫婦」と「親子」の関係によってつくられるものであり、「平成27年夫婦同氏制大法廷判決」でも「夫婦や親子関係」と具体的な文言によって示しているにもかかわらず、これを「家族関係」という文言に変更している点は、この東京地裁判決が「家族」の意味を「平成27年夫婦同氏制大法廷判決」で示されている意味から離れて別のものへと変えようとしている可能性が考えられる。
このような、引用を示しながら、元の文面に示された文言を変更したり、その文面で用いられている文意の理解や前提となっている事柄から離れる形で用いることは、不正な手続きということができる。
裁判所が、裁判体ごとにこのような誤った引用を繰り返していけば、判例の体系的な整合性が損なわれていき、法規範の意味が流動化し、裁判体ごとに別々の結論が下されてしまうことに繋がる。
そうなれば、同様の事件であれば誰が裁判を行っても同様の結論が導き出されるはずであるとの公平性や公正性への期待感が損なわれ、法的安定性も損なわれ、国民の抱く司法への信頼も失われることになる。
ウ(ア) 婚姻(法律婚)制度は、様々な法制度のパッケージとして構築されており、婚姻することによって様々な法的効果が発生する。例えば、民法においては、同居、協力及び扶助の義務(752条)、婚姻費用の分担(760条)、財産の共有推定(762条2項)、離婚時の財産分与(768条)、嫡出の推定(772条)、特別養子縁組についての夫婦共同縁組(817条の3)、夫婦の共同親権(818条)、配偶者の相続権(890条)と法定相続分(900条)、配偶者居住権(1028条)、配偶者短期居住権(1037条)、遺留分(1042条)等が挙げられ、戸籍法においては、婚姻の届出があったときは、夫婦について新戸籍を編成し(16条1項本文)、子が出生した場合には、子は親の戸籍に入ること(18条)等が挙げられる。その他にも、税、社会保障、出入国管理の分野等において、個別法規において婚姻(配偶者であること)が効果発生のための要件とされているものが多数存在する。これらの規定の多くは、夫婦が共同生活を送り、場合によっては子を産み育てるにあたり、その家族関係を法的に保護する趣旨のものであるということができる。
【筆者】
「婚姻(法律婚)制度は、様々な法制度のパッケージとして構築されており、婚姻することによって様々な法的効果が発生する。」との記載がある。
「法制度のパッケージ」としての「婚姻(法律婚)制度」における「様々な法的効果」は、「婚姻」の有する「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的に従って定められるものである。
そのため、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的に資する人的結合関係に対してのみ、「婚姻(法律婚)制度」という「法制度のパッケージ」としての「様々な法的効果」の適用を受ける地位を与えることになる。
もし「法制度のパッケージ」としての「婚姻(法律婚)制度」における「様々な法的効果」の内容が、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を実現するために不必要に過大な優遇措置を行っている場合には、「婚姻制度を利用している者(既婚者)」と「婚姻制度を利用していない者(独身者)」との間の比較において、憲法14条の「平等原則」に抵触して違憲となる。
この場合には、その不必要に過大な優遇措置を行っている規定が個別に失効することによって、不平等が是正されることになる。
「これらの規定の多くは、夫婦が共同生活を送り、場合によっては子を産み育てるにあたり、その家族関係を法的に保護する趣旨のものであるということができる。」との記載がある。
まず、ここに記載された「夫婦」であるが、それは「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的に従って形成された婚姻制度を利用する者を指す意味である。
そのため、「夫婦が共同生活を送り、……(略)……その家族関係を法的に保護する趣旨のものである」との部分は、単なる人的結合関係を形成した者が「共同生活」を送っていることを「法的に保護する趣旨」を意味しているわけではなく、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的に従って形成された婚姻制度を利用している者が「共同生活」を送っていることを「法的に保護する趣旨」ということである。
これは、婚姻制度が「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を実現するために必要となる要素を満たす人的結合関係に対してのみ一定の優遇措置を与え、その目的を達成することを目指す仕組みであることによるものである。
そのことから、この「共同生活」や「法的に保護する趣旨」という部分だけを取り上げて、単なる人的結合関係を形成した者の「共同生活」に対しても「法的に保護する」ことを求めることができることにはならない。
この判決の内容の後の部分では、この部分の誤解を基に論じられている部分があるため注意する必要がある。
また、このような明文による法的効果に限らず、婚姻により、その当事者は、社会内において家族として公に認知され、それにより家族として安定した共同生活を営むことが可能となるという効果も生ずる。
【筆者】
この文では最初に「このような明文による法的効果に限らず、」と述べていることから、最後に「効果も生ずる。」と述べている部分の内容については、法律上の効果ではないことになる。
つまり、「婚姻により、その当事者は、社会内において家族として公に認知され、それにより家族として安定した共同生活を営むことが可能となる」という「効果」と称するものは、法律論上の効果とは異なる。
そのため、この文の意味は、「『弁護士』となった者が、社会内において『弁護士』として公に認知され、それにより『弁護士』として職業を営むことが可能となる」という話と同じ次元のものであり、いわば当然のことを述べているに過ぎないものである。
ただ、このような「効果」と称するものを得たいと望む者がいるとしても、その制度の立法目的と、その立法目的を達成するための手段としての枠組みの当否の問題を超えて、その制度の対象とならない者に対して「公に認知」されることや、何かを「営む」ためのメリットを与えなければならないことにはならない。
これらの法律上の効果ではない「効果」と称するものは、立法目的とその立法目的を達成するための手段として整合的な枠組みを利用する者に対してそれらの事象が生じているだけであり、その事象だけを制度の立法目的とその立法目的を達成するための手段となる枠組みの当否の問題から切り離して考えることはできないからである。
もし、そのような何らかの「公に認知」されることや、何かを「営む」ためのメリットだけを得ようとするならば、何らかの「資格」を有する者の「公に認知」されていることや何かを「営む」ためのメリットとなるものを、その「資格」を有しない者に対しても同様に与えるべきなどという「資格」の意味を失わせる主張と変わらないものとなるのであり、妥当でないからである。
(イ) このように、婚姻は、親密な人的結合関係について、その共同生活に法的保護を与えるとともに、社会的承認を与えるものである。このように親密な人的結合関係を結び、一定の永続性を持った共同生活を営み、家族を形成することは、当該当事者の人生に充実をもたらす極めて重要な意義を有し、その人生において最も重要な事項の一つであるということができるから、それについて法的保護や社会的公証を受けることもまた極めて重要な意義を持つものということができる。
【筆者】
「このように、婚姻は、親密な人的結合関係について、その共同生活に法的保護を与えるとともに、社会的承認を与えるものである。」の記載があるが、誤った理解がある。
まず、「婚姻は、親密な人的結合関係について、その共同生活に法的保護を与える」との部分であるが、婚姻は単なる「親密な人的結合関係」の「共同生活に法的保護を与える」ことを目的とした制度ではない。
「婚姻」の目的は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することにある。
そして、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす人的結合関係に対して一定の優遇措置を行うことによって、目的の達成を目指す仕組みとなっている。
そのため、「共同生活に法的保護を与える」という側面があるとしても、それは「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成するための手段として設けられた「法的保護」であるから、その目的との整合性を満たす人的結合関係のみを対象とするものであることが前提となっている。
そのことから、立法目的を達成するための手段となる枠組みの対象外となっている人的結合関係の「共同生活」が「婚姻」によって「保護」されることはない。
よって、単なる「親密な人的結合関係」であるからと言って、「その共同生活に法的保護を与える」という性質のものではない。
この誤った理解は、この判決の後の部分で誤った結論を導く原因となっていることから、しっかりと押さえておく必要がある。
次に「婚姻は、親密な人的結合関係について、……(略)……社会的承認を与えるものである。」との部分であるが、誤りである。
先ほども述べたように、「婚姻」の目的は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することにあり、その目的を達成するための手段として整合的な形で枠組みを定め、その制度の利用を促進するために、「法的保護」などを与えるものとなっている。
これは単なる「親密な人的結合関係」であることを理由とするものではない。
「社会的承認」の意味について検討する。
まず、日本国憲法の下では「結社の自由(21条1項)」が定められており、個々人が人的結合関係を形成することは「公共の福祉(憲法12条、13条)」や「公序良俗(民法90条)」、個別の法律に違反しない限りは自由である。そのため、人的結合関係を形成することが「社会的承認」を得ていないかのような理解に基づいて、「婚姻は、……(略)……社会的承認を与えるもの」のように「婚姻」することによって初めて「社会的承認」が与えられるかのような理解であれば誤りである。
次に、婚姻制度を利用する者は「婚姻している者(既婚者)」として認識され、婚姻制度を利用していない者は「婚姻していない者(独身者)」として認識されているだけであるから、「婚姻している者(既婚者)」だけに特別に与えられるような「社会的承認」というものがあるのか疑問である。もし「社会的承認」というものがあるとしても、それは婚姻制度の立法目的を達成するための手段となる枠組みが存在することを前提として、その枠組みに従う形で適法に制度を利用した場合に、その制度を利用する者に対して生じる社会の受け止め方によるものである。これは「婚姻は、……(略)……社会的承認を与えるもの」というような形で、「婚姻」という制度によって「与える」という論じ方をしていることは、適切な表現とはいえない。
ここで「社会的承認」と述べているものは、「婚姻している者(既婚者)」に対する社会の受け止め方の意味と思われるが、この判決が「2⑴エ」の「(ア)」、「(イ)」、「(ウ)」のところで、「婚姻」として捉えることができるかどうかに関して「社会的承認」や「社会的な承認」などと述べている意味とは異なった意味で使われていることに注意する必要がある。
この点で、混乱を招きやすいものとなっている。
「このように親密な人的結合関係を結び、一定の永続性を持った共同生活を営み、家族を形成することは、当該当事者の人生に充実をもたらす極めて重要な意義を有し、その人生において最も重要な事項の一つであるということができるから、それについて法的保護や社会的公証を受けることもまた極めて重要な意義を持つものということができる。」との記載がある。
まず、「家族を形成することは、」との部分であるが、「家族」の文言が、法学的な意味の「家族」であるか、社会学的な意味の「家族」であるのかを考える必要がある。
いくつか前の「⑶イ」の項目から「⑶ウ(ア)」と続いてこの段落である「⑶ウ(イ)」の第一文まで一貫して「婚姻」と「家族」を述べていることから、法学的な意味の「家族」を指しているように思われる。
しかし、「親密な人的結合関係を結び、一定の永続性を持った共同生活を営み」との部分については、憲法21条1項の「結社の自由」によって保障される性質のものであり、法学的な意味の「家族」の要素を説明するものではない。
特に、「夫婦」については「同居義務」が存在するが、子は親から独立して同居していない場合もあるのであり、「一定の永続性を持った共同生活を営み」の部分が法学的な意味の「家族」を指すと考えることは不自然だからである。
そのため、「親密な人的結合関係を結び、一定の永続性を持った共同生活を営み」の文に続く形で「家族を形成することは、」という表現をしていることからすれば、ここで意味する「家族」は社会学的な意味の「家族」と考えられる。
「当該当事者の人生に充実をもたらす極めて重要な意義を有し、その人生において最も重要な事項の一つであるということができる」との部分について検討する。
上記で述べたような、憲法21条1項の「結社の自由」で保障される社会学的な意味の「家族」を形成することについては、「国家からの自由」という「自由権」の性質として保障されるものであり、この自由が国家によって侵害されていた場合には、ここで述べられている「当事者の人生に充実をもたらす極めて重要な意義を有し、その人生において最も重要な事項の一つである」などと述べて、その侵害を排除することが可能となる場合が考えられる。
しかし、憲法24条の「婚姻及び家族」に規定されている法学的な意味の「家族」については、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的に従って形成された枠組みである「婚姻」と、その「婚姻」の立法目的と整合的な形でその目的の実現を阻害しない形で規律される枠組みである法律上の「家族」であるから、その制度を利用することができる者の範囲は立法目的との整合性を保つ形で定められているものであり、「国家からの自由」という「自由権」とは異なる性質のものである。
また、この法律上の「家族」の制度は、個々人が人的結合関係を形成することを妨げるものではないことから、「国家からの自由」という「自由権」を侵害する性質のものではない。
そのため、もともと「国家からの自由」という「自由権」が侵害されているわけではないため、法律上の「家族」の制度について「当事者の人生に充実をもたらす極めて重要な意義を有し、その人生において最も重要な事項の一つであるということができる」と述べたところで、侵害を排除する根拠として用いられていることにはならず、単に法律上の「家族」の制度を利用する者の個々人の価値観や感想を述べるものに過ぎず、これによって法律上の「家族」の制度の変更を求めることができるとする理由にはならない。
「それについて法的保護や社会的公証を受けることもまた極めて重要な意義を持つものということができる。」との部分について検討する。
婚姻制度の枠組に従う形で、適法に婚姻制度を利用した場合には、婚姻制度による「法的保護や社会的公証」を受けることになることはその通りである。
前記認定事実(6)ウのとおり、未婚の男女に対する調査で「生涯を独身で過ごすというのは、望ましい生き方ではない」との調査項目に対して賛成の回答をした者は約6割、「いずれ結婚するつもり」との調査項目について賛成の回答をした者は9割近くに達していることが認められる。婚姻や家族に関する国民の意識や価値観が多様化している中で、やはり法律婚を尊重する考え方が浸透しているといえるのも、このような婚姻による法的効果や社会内での公証を受けられることについての意義、価値が大きいと考えられていることの証左といえる。
【筆者】
「婚姻や家族に関する国民の意識や価値観が多様化している中で、」との記載がある。
ここでいう「婚姻や家族」とは、憲法21条の「結社の自由」で保障される他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度である。
そのため、ここではその法律上の「婚姻や家族」に関する「国民の意識や価値観」が「多様化している」ことを述べるものであることから、これは「国民」が法律上の「婚姻や家族」の制度を利用するか否かや、利用する場合における「個々人の利用目的」が「多様化している」ことを説明するものと考えられる。
「婚姻や家族に関する国民の意識や価値観が多様化している中で、やはり法律婚を尊重する考え方が浸透している」との文脈についても、「国民」が法律上の「婚姻や家族」の制度を利用するか否かや、利用する場合における「個々人の利用目的」が「多様化している」が、それでも「法律婚を尊重する考え方が浸透している」と述べているものと考えられる。
「法律婚を尊重する考え方が浸透しているといえるのも、このような婚姻による法的効果や社会内での公証を受けられることについての意義、価値が大きいと考えられていることの証左といえる。」との記載がある。
この「法律婚を尊重する考え方」であるが、これは、その社会の中で「法律婚」の枠組みが「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を実現するための制度して機能しており、社会的な不都合を解消するものとして役立っていることが認識されていることが原因となっているものと考えられる。
そのため、この判決は「法律婚を尊重する考え方」の原因として「婚姻による法的効果や社会内での公証を受けられることについての意義、価値が大きいと考えられていること」であると考えているようであるが、それは単に「法的効果や社会内での公証を受けられる」ものであればよいというものではなく、その制度の目的が「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することにあり、その内容がその目的を実現するための仕組みとして整合的な「法的効果」を設定した制度となっていることの妥当性が認識されていることが大本にあるものと思われる。
しかし、もし「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的の達成に沿わない人的結合関係に対して何らかの「法的効果」を設定した場合には、その社会の中で「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを十分に果たせなくなることを意味する。
すると、その社会の中で社会的な不都合が生じることになることから、そのような内容の制度を「法律婚」と呼んだとしても、人々はその制度を「尊重する考え方」を抱くことはなくなるはずである。
このように、「法律婚を尊重する考え方」が存在することの背景には、常に「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的の実現に役立つ制度となっていることが人々の間で認識されていることが存在するのであり、この目的を切り離した形でその制度に対する人々の「尊重する考え方」を維持することができるわけではないことに注意する必要がある。
そのため、この判決の後の部分で出てくるが、この目的を切り離す形で何らかの「法的効果や社会内での公証を受けられる」制度を設けることによって、人々からの「尊重する考え方」を得ようとすることは、誤った論じ方である。
そうすると、婚姻により得ることができる、パートナーと家族となり、共同生活を送ることについて家族としての法的保護を受け、社会的公証を受けることができる利益は、個人の尊厳に関わる重要な人格的利益ということができる。
【筆者】
「婚姻により得ることができる、パートナーと家族となり、共同生活を送ることについて家族としての法的保護を受け、社会的公証を受けることができる利益」との部分であるが、法律上の「婚姻」や法律上の「家族」については、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす人的結合関係のみを対象とするものであり、その「法的保護」やこの判決が「社会的公証」と称するものについても、その目的を達成するための手段として設けられているものである。
そのため、「婚姻」や「家族」の制度の対象となっている場合においては、「法的保護」やこの判決が「社会的公証」と称するものを得られるが、そもそも「婚姻」や「家族」の制度の対象となっていない場合には、「法的保護」やこの判決が「社会的公証」と称するものを得られないという差異が生じることは、制度が政策的なものである以上、当然のことである。
また、「婚姻」や「家族」の制度の対象となっている場合においては、その制度を利用する者についての「個人の尊厳に関わる重要な人格的利益」を論じる余地があるとしても、そもそも「婚姻」や「家族」の制度の対象となっていない場合には、その者についての「個人の尊厳に関わる重要な人格的利益」を論じる余地はない。
そのため、この判決の後の部分で出てくるが、「婚姻」や「家族」の制度の対象となっていない場合について、その者が「婚姻」や「家族」の制度による「法的保護」やこの判決のいう「社会的公証」と称するものの「利益」を、「個人の尊厳に関わる重要な人格的利益」によって導き出そうとすることは誤った論じ方となることに注意が必要である。
分かりやすく言えば、「目の見えない人」が「自動車運転免許」によって得られる利益が得られないと主張したところで、「自動車運転免許」は安全な交通などを理由として目が見えていることを前提として、一定の視力を有する者を対象とした制度であることから、その目的に沿わない「目の見えない人」については、「自動車運転免許」によって得られる利益を得られないことは当然のことである。
それにもかかわらず、この判決の後の部分で出てくるものは、法律上の「婚姻」や法律上の「家族」の制度の対象となっていない場合についても、そこで得られる利益を、その制度の目的に沿わない場合にも与えるべきとの論じ方となっており、誤った説明となっている。
「婚姻により得ることができる、パートナーと家族となり、」との部分についても検討する。
この「パートナー」という言葉であるが、「二人一組」の一方を指す言葉であることから、「婚姻」の「二人一組」の制度となっていることに注目した表現となっている。
ただ、この「パートナー」という言葉は、現在の婚姻制度が「男女二人一組」となっていることを前提として用いている言葉であり、この婚姻制度の枠組みを「男女二人一組」の形から変更することができるか否かを考える際には、「二人一組」に限られる形で論じることは妥当でない。
人的結合関係の中には、「三人一組」や「四人一組」もあるし、それ以上の組み合わせも考えられるのである。
人類が必ず「二人一組」の人的結合関係を形成するというような性質のものではないため、「パートナーと家族となり、」というように、「二人一組」の形だけが、法制度を形成する際の絶対的な前提となるわけではないのである。
よって、この判決の後の部分で出てくるが、何らの根拠もなく「二人一組」の人的結合関係だけを特別視して、婚姻制度の「男女二人一組」の形に対する形で、「同性間」の「二人一組」のみを比較対象として持ち出した上で、何らかの「利益」を得られるか否かを論じるものとなっていることは、妥当な説明ではない。
婚姻制度が「男女二人一組」の形となっていることには、「男性」と「女性」の間で自然生殖を想定することができ、その者たちの間に「貞操義務」を設けることによって、産まれた子供の遺伝上の父親を特定することができるというところに理由がある。
これは、「男性」と「女性」の組み合わせによって、産まれた子供の遺伝上の父親を特定することができるところに本質的な要素があり、「二人一組」であることはその後に導かれているものである。
そのため、婚姻制度において比較することができる対象となるものは、「生殖」を想定することができる組み合わせとして「男女二人一組」の形によって法的効果が設定された「婚姻している者(既婚者)」と、それ以外の「婚姻していない者(独身者)」との間である。
この点で、婚姻制度の目的との関係を検討することなく、「二人一組」という単位を取り上げて比較対象とすることができるとの考えは、「カップル信仰論」に陥っているものということができる。
「パートナーと家族となり、共同生活を送ること」との部分であるが、この「家族」の意味が社会学的な意味の「家族」と考えた場合には、このような「共同生活」は憲法21条1項の「結社の自由」によって保障されることになる。
しかし、法学的な意味の「婚姻」や「家族」については、このような憲法21条1項の「結社の自由」で保障される様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度であることから、その目的との関係で内在的な限界があり、どのような人的結合関係でもこの「婚姻」や「家族」の中に含めることができるという性質のものではない。
よって、法学的な意味の「婚姻」や「家族」の立法目的の実現に沿わない人的結合関係に対しては、憲法21条1項の「結社の自由」によって保障される範囲を超えて、「婚姻」や「家族」の制度による「法的保護」やこの判決のいう「社会的公証」と称しているものを与えなければならないということにはならない。
「個人の尊厳に関わる重要な人格的利益ということができる。」との部分について検討する。
「個人の尊厳」は、憲法24条2項に記された文言である。
この憲法24条2項の「個人の尊厳」の文言は、「婚姻及び家族」に当てはまる場合に対してのみ、その者に適用されることが前提であり、そもそも「婚姻及び家族」に当てはまらない場合には、その者にこの24条2項の「個人の尊厳」が適用されることはない。
よって、「婚姻及び家族」に当てはまらない場合について、24条2項の「個人の尊厳」を用いて説明することができることにはならないことに注意が必要である。
また、「個人の尊厳」を憲法13条前段の「個人の尊重」と同一の憲法上の理念として捉えたとしても、憲法13条前段の「個人の尊重」の文言によって、具体的な法制度の創設を国家に対して求めることができるとする根拠となるものではない。
そのため、この憲法13条前段の「個人の尊重」と同一の意味で「個人の尊厳」という文言を用い、これに関わる「重要な人格的利益」と論じることによって、特定の法制度の創設を国家に対して求めることができることにはならない。
この点も押さえておく必要がある。
(ウ) そして、原告らの本人尋問の結果及び弁論の全趣旨によれば、同性愛者においても、親密な人的結合関係を築き、パートナーと共同生活を送り、場合によっては子供を養育するなどして、社会の一員として生活しており、その実態は、男女の夫婦と変わるところがないのであって、パートナーと法的に家族となることは、その人格的生存にとって極めて重要な意義を有するものということができる。
【筆者】
まず、「同性愛者においても、」との部分から検討する。
婚姻制度は「性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いを行っているわけではないし、「性愛」に基づいて「婚姻」することを求めるものでも勧めるものでもない。
そのため、「同性愛者」を称する者であるとしても、「男女二人一組」の婚姻制度を適法に利用することが可能である。
また、婚姻制度を利用した形で「親密な人的結合関係」を形成することや「共同生活」を送ることができるし、婚姻制度を利用する形で「子供を養育する」こともできる。
なぜならば、単なる法制度としての枠組みである婚姻制度に対して、どのような価値観に従って利用するかは個々人の自由だからである。
婚姻制度の枠組みに沿う形で存在する選択肢の中で、それでもなおその婚姻制度を利用することを望む者がいた場合に、その者は相手方を、年齢、身長、体型、顔、血液型、家系、出身地、性格、趣味、学歴、職業、年収、宗教、相性診断などで選ぶこともある。
自らの「性愛」の思想、信条、信仰、感情が満たされることを重視する者もいれば、重視しない者もいる。
「性愛」が満たされることを希望するか否かは、婚姻制度に対する「個々人の利用目的」として捉えられるべきものであり、個々人の価値観の一つということである。
実際に「同性愛者」を称している者であるとしても、「男女二人一組」の婚姻制度を利用している実態が認められるのであり、婚姻制度が個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いを行っているわけではないことは明らかである。
そして、その者が婚姻制度を利用しているのであれば、「その実態」は「男女の夫婦と変わるところがない」どころか、完全に「男女の夫婦」ということができる。
その婚姻制度を利用する「同性愛者」を称する者の形成する「男女二人一組」の「夫婦」については、「法的に家族」ということができる。
次に、「親密な人的結合関係を築き、パートナーと共同生活を送り、場合によっては子供を養育するなどして、社会の一員として生活しており、」との部分について検討する。
まず、「親密な人的結合関係を築き」や「共同生活を送り」の部分については、憲法21条1項の「結社の自由」によって保障されるものである。
ここでは「パートナー」という言葉を使い、「二人一組」であることを前提としているが、この憲法21条の「結社の自由」によって保障される範囲は、「二人一組」に限られるものではなく、「三人一組」や「四人一組」、「五人一組」、それ以上の組み合わせにおいて同様に保障されることになる。
これに対して法律上の「婚姻」や「家族」については、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、これらの憲法21条の「結社の自由」によって保障される様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度であり、これらの「親密な人的結合関係」や「共同生活」とは区別されたものである。
よって、「婚姻」や「家族」の制度の立法目的との整合性を考慮することなく、「婚姻」や「家族」の制度の対象となっている人的結合関係と、対象となっていない人的結合関係を比較し、「婚姻」や「家族」の制度の対象となっていない者に対して、その「婚姻」や「家族」の制度による何らかの利益を与えなければならないことにはならない。
三つ目に、「その実態は、男女の夫婦と変わるところがないのであって、」との部分であるが、この「男女の夫婦」における「夫婦」の意味は、適法な法律上の「婚姻」をした男女の双方を指す言葉であることから、「婚姻」という制度を利用している者を指している。
この「婚姻」という制度を利用している者は、当事者間で「夫婦同氏」や「同居義務」、「貞操義務」、「嫡出推定」、「共同親権」などの法律関係を形成し、互いを権利・義務によって法的に拘束し合う関係にある者のことをいうことから、このような法律関係を形成しているという背景事情が存在しないのであれば、例え共同生活を共にしていたとしても、法律上の意味においては「婚姻」における「夫婦」ということはできない。
そのため、「男女の夫婦と変わるところがない」という部分については、裁判所が法的判断の場面で論じているのであるから、その内容は法律関係の内容において「変わるところがない」か否かという視点によって判断する必要があるのであって、単なる社会学的な意味の共同生活者として「変わるところがない」と論じるだけで、法律関係における法的な意味の「夫婦」と同様であることを示すことができるわけではない。
そして、ここでいう「パートナーと共同生活を送り、場合によっては子供を養育するなどして、社会の一員として生活して」いる者については、単に「婚姻していない者(独身者)」が複数名で共同生活を送っているというだけであり、法律的な視点から見れば、「婚姻」における「夫婦」と同様の法律関係にあるとはいえない。
よって、法律論として考えれば、ここでいう「パートナーと共同生活を送り、場合によっては子供を養育するなどして、社会の一員として生活して」いる者については、「男女の夫婦」とはまったく異なる状態であり、「変わるところがない」との理解は誤った理解である。
これについては、この判決では何らの根拠もなく「パートナー」という「二人一組」の形に限定して考えることを前提として比較対象として持ち出すのであるが、これを「トリオ」の「三人一組」の形や、「四人一組」の形、もしくはそれ以上の組み合わせによって、「親密な人的結合関係を築き」、それらの者と「共同生活を送り、場合によっては子供を養育するなどして、社会の一員として生活して」いる者もいることを考えれば、さらに理解しやすい。
この者たちについては、婚姻制度を利用していないのであるから、当事者間で「夫婦同氏」や「同居義務」、「貞操義務」、「嫡出推定」、「共同親権」などの法律関係を形成しておらず、互いを権利・義務によって法的に拘束し合う関係にもないのであるから、法的にはまったく「夫婦」とは異なっているのである。
これが「二人一組」の人的結合関係であった場合にだけ、「男女の夫婦と変わるところがない」と説明することができることにはならないのである。
また、「三人一組」の人的結合関係を形成している者が、自らを「トリオ」と称して生活していたとして、それについては「男女の夫婦と変わるところがない」と評価することはできないが、そのうちの一人が死亡した場合に、残りの者が「二人一組」となったからといって、「男女の夫婦と変わるところがない」という状態に変わるということにはならないのである。
よって、法律論として考えれば、「その実態は、男女の夫婦と変わるところがないのであって、」と論じている部分は誤りとなる。
四つ目に、「パートナーと法的に家族となることは、その人格的生存にとって極めて重要な意義を有するものということができる。」との部分について検討する。
「パートナーと法的に家族となることは、」との部分について、「家族」の文言が社会学的な意味の「家族」である場合には、その人的結合関係は憲法21条1項の「結社の自由」によって保障されることになる。
「結社の自由」については、「国家からの自由」という「自由権」の側面を有していることから、これが侵害されている場合には、「人格的生存にとって極めて重要な意義を有するもの」などと述べて、その侵害を排除することを求める余地が考えられる。
これに対して、「家族」の文言が法学的な意味の「家族」である場合には、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を実現するために設けられた「婚姻」と関わる「家族」の制度を指すことから、その「婚姻」や「家族」の制度の対象となる場合に、その制度を利用することができるというものである。
この「婚姻」や「家族」の制度を利用できるか否かについては、具体的な法制度の枠組みを前提とするものであり、「国家からの自由」という「自由権」とは性質を異にしている。
そのため、法学的な意味の「家族」における「婚姻」や「家族」の制度の対象となっていない場合について、その者が「人格的生存にとって極めて重要な意義を有するもの」などと述べたところで、その制度に対する個々人の価値観や感想に過ぎず、これを理由として「家族」の制度の対象とならない場合にも、その者に対して、その制度から得られる利益を与えなければならないとする根拠とはならない。
また、「同性愛者」を称する者であっても、「男女二人一組」の婚姻制度を利用することができることから、婚姻制度の枠組みに沿う形で存在する選択肢の中で、なお婚姻制度を利用したいと望んだ場合には、婚姻制度を利用することが可能である。
そのため、「同性愛者」を称する者であっても、法学的な意味の「家族となること」が可能である。
「婚姻」や「家族」の制度を利用することについては、「国家からの自由」という「自由権」とは性質が異なっているため、国家からの侵害を排除する根拠として使われることのある「人格的生存」という概念を持ち出すことは適切ではないが、個々人の価値観として「極めて重要な意義を有する」と考えるのであれば、制度の要件に従って制度を利用すればよいというだけである。
そうすると、同性愛者にとっても、パートナーと家族となり、共同生活を送ることについて家族としての法的保護を受け、社会的公証を受けることができる利益は、個人の尊厳に関わる重大な人格的利益に当たるということができる。
【筆者】
「同性愛者にとっても、」の部分から検討する。
まず、ここでいう「家族」の文言が、法学的な意味の「家族」の場合を検討する。
婚姻制度は、「性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いを行っている事実はないし、「性愛」に基づいて「婚姻」することを求めるものでも勧めるものでもない。
そのため、「同性愛者」を称する者でも、「両性愛者」、「全性愛者」、「多性愛者」、「小児性愛者」、「老人性愛者」、「近親性愛者」、「死体性愛者」、「動物性愛者」、「対物性愛者」、「対二次元性愛者」、「無性愛者」を称する者でも、婚姻制度を利用することができる。
婚姻制度の枠組みに沿う形で存在する選択肢の中で、なお「婚姻」したいと望むのであれば、制度の要件に従って「婚姻」すればよいのである。
そのため、「同性愛者」と称する者でも、婚姻制度の枠組みに沿う形で婚姻制度を利用することによって、法学的な意味の「家族」となることができる。
この意味で、「家族となり、共同生活を送ることについて家族としての法的保護を受け、社会的公証を受けることができる利益」は完全に有していることになる。
次に、「家族」の文言が、社会学的な意味の「家族」の場合を検討する。
「パートナーと家族となり、共同生活を送ることについて家族としての法的保護を受け」ることは、21条1項の「結社の自由」によって保障されることになる。
これについては、法学的な意味の「家族」ではないこととから、憲法24条2項の「婚姻及び家族」には当たらず、24条2項の「個人の尊厳」が適用されることはない。
よって、この判決が「個人の尊厳に関わる重大な人格的利益に当たるということができる。」と述べている部分については、「個人の尊厳」という24条2項に記載された文言が見られるが、24条2項が適用される事例ではないため誤りとなる。
この「個人の尊厳」の意味が、13条の「個人の尊重」と同一の意味と解されることを根拠として、そこから「重大な人格的利益」と述べようとしている可能性が考えられる。
これについては、13条の「個人の尊重」の意味を、21条1項の「結社の自由」と同様の「国家からの自由」という「自由権」の側面を見出し、「共同生活を送ること」が国家によって侵害されている事実が認められた場合には、その侵害を排除することを求めることができる場合が考えられる。
しかし、この13条の「個人の尊重」の規定から、具体的な法制度を国家に対して求めることができるということにはならないことに注意が必要である。
エ(ア) 前記ウ
に挙げた婚姻による法的効果の中には、同性間の人的結合関係においても、当事者間の契約等により一定程度は実現可能であるものも存在する。例えば、同居、協力及び扶助の義務(民法752条)については、契約により同様の効果を生じさせることが可能であるといえるし、相続のように当事者の一方の死後にその財産を他方に帰属させることは、契約や遺言等によっても可能であるなど、契約や民法上の他の制度等を用いることによって、一定程度は実現可能である。
【筆者】
この段落であるが、説明する際に基準(スタンダード)の採り方を誤っていると考えられる。
まず、憲法13条前端では「個人の尊重」を定めており、憲法24条2項でも「個人の尊厳」の文言があり、憲法は「個人主義」の下に自律的な個人として生存していくことが予定されている。
そのため、何らの法制度も利用していない「個人」の状態が法律関係を論じる際のすべての基準(スタンダード)となるべき状態である。
そして、個々人が「契約等」によって、何らかの法律関係を形成し、法律効果を得ながら生活している状態が基準(スタンダード)である。
そのため、ここでいう「同性間の人的結合関係」であろうと、「男女間の人的結合関係」であろうと、「三人一組の人的結合関係」であろうと、「十人一組の人的結合関係」であろうと、「契約や遺言等」によって「同居、協力及び扶助の義務」を形成することや「当事者の一方の死後にその財産を他方に帰属させること」が可能である。
これが「個人主義」の下で形成される法律関係の基準(スタンダード)となるべきものである。
この状態がすべての基準(スタンダード)であるから、このような状態が別の制度と比較して劣っているなどということはなく、否定的な評価を受ける必要はないものである。
その上で、「婚姻」は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的に従って、その目的を達成する手段として整合的な要素を満たす人的結合関係について一定の枠組みを定め、そこにその目的の実現に資する形での法的効果や、その目的の実現に資する形での優遇措置を定め、「法制度のパッケージ」としたものである。
このため、法律論としては「婚姻制度を利用している者(既婚者)」を基準(スタンダード)として「婚姻制度を利用していない者(独身者)」における法的効果の実現可能性を論じるのではなく、「婚姻制度を利用していない者(独身者)」における法的効果の形を基準(スタンダード)として「婚姻制度を利用している者(既婚者)」の法的効果や優遇措置が目的を達成するための手段として不必要に過大なものとなっていないかを論じる必要がある。
そして、そこで「婚姻制度を利用している者(既婚者)」が「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成するための手段として不必要に過大な法的効果や優遇措置を得ている場合には、憲法14条の「平等原則」に抵触して違憲となり、その不必要に過大な法的効果や優遇措置に関する規定が個別に失効することとなって、格差が是正されることになる。
これに対して、この段落では、婚姻制度の法的効果を基準(スタンダード)として考えた上で、「婚姻していない者(独身者)」の形成する法的効果の実現可能性を論じるものとなっており、基準の採り方を誤っている。
このような論じ方は、文面そのものに「婚姻していない者(独身者)」の形成する法的効果が何か欠けている劣ったものであるかのような否定的な評価を伴うものとなりやすく、不適切である。
司法権を担う裁判所には政治的中立性が求められるのであり、特定の制度や法的効果に対して優劣を付けるような論じ方をするべきではない。
「同性間の人的結合関係においても、」との記載があるが、これは婚姻制度が「男女二人一組」であることを前提として、「異性間」があるならば「同性間」もあるのではないかとの安易な発想によって、「同性間の人的結合関係」を比較対象として持ち出しているものと考えられる。
しかし、婚姻制度が「男女二人一組」であることの理由は、「男性」と「女性」の間では自然生殖を想定することができ、その間に「貞操義務」を設けたならば、子供が産まれた場合にも遺伝上の父親を特定することができるとするところにある。
そのため、単に「二人一組」であればよいというものではないのであって、「異性間」があれば、「同性間」もあるのではないかとの発想によって、「同性間の人的結合関係」を持ち出して比較を試みることは、婚姻制度の目的との整合性の観点から考えて誤っている。
また、現在存在する婚姻制度の枠組みを超えて人的結合関係を考えるのであれば、人的結合関係の中には「三人一組」の「トリオ」や「四人一組」の者、それ以上の人的結合関係を形成している者もいるのであり、それらを想定することもなく、「二人一組」だけを比較対象として考えれば済むと考えているところも妥当でない。
これは、なぜ「二人一組」であるのか、その根拠を説明しないままに論じる「カップル信仰論」に陥っているものである。
しかし、共同親権や税法上の優遇措置等、契約等によっては実現困難なものや婚姻制度による場合とは完全に同じ効果を得ることができないものも存在する上、契約等による場合には、婚姻とは異なり、事前に個別の契約等を行っておく必要があるという相違点がある。
【筆者】
「共同親権や税法上の優遇措置等」は、婚姻制度の立法目的の実現のために設けられているものであり、婚姻制度に定められた枠組みを利用しない者に対して与えられないことは当然である。
(イ) また、同性カップルでも共同生活を営むこと自体は自由であって、本件諸規定はそれ自体を制約するものではない。しかしながら、我が国において、法律婚を重視する考え方が依然として根強く存在することは前記のとおりであり、婚姻することによって社会内で家族として認知、承認され、それによって安定した社会生活を営むことができるという実態があることが認められるところ、同性間の人的結合関係については、法律上、このような社会的公証を受ける手段がないため、社会内で生活する中で家族として扱われないという不利益を受けている。この点につき、原告らの本人尋問の結果によれば、例えばパートナーが医療機関で診療を受けた際に家族として認められなかったために病状の説明を受けられなかったり、入院の際の保証人になることができなかったりするなどの不利益を受けた経験を有する者があることが認められる。
【筆者】
「同性カップルでも共同生活を営むこと自体は自由であって、本件諸規定はそれ自体を制約するものではない。」との記載があるが、その通りである。
民法や戸籍法の規定は個々人が人的結合関係を形成して「共同生活を営むこと」を制約するものではない。
ここでは「同性カップル」のように「二人一組」について書かれているが、「二人一組」に限らず、「三人一組」の「トリオ」であっても、「四人一組」であっても、それ以上の多数でも「共同生活を営むこと自体は自由」ということができる。
これについては、「公共の福祉」に反しない限り、憲法13条の「幸福追求権」や、憲法21条1項の「結社の自由」によって保障されるものである。
「我が国において、法律婚を重視する考え方が依然として根強く存在することは前記のとおりであり、婚姻することによって社会内で家族として認知、承認され、それによって安定した社会生活を営むことができるという実態があることが認められる」との記載がある。
「我が国において、法律婚を重視する考え方が依然として根強く存在すること」との部分であるが、これは、「我が国」の婚姻制度が「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成するための仕組みとして機能しており、その立法目的とその立法目的を達成するための手段となる枠組みの妥当性が人々の間で認識されていることによるものと考えられる。
「婚姻することによって社会内で家族として認知、承認され、」との部分であるが、婚姻制度は単なる法制度に過ぎないものであるから、「婚姻することによって社会内で家族として認知」されることについては、単に「婚姻制度を利用している者(既婚者)」として「認知」されているに過ぎない。
「婚姻制度を利用していない者(独身者)」についても、単に「婚姻制度を利用していない者(独身者)」として「認知」されているのであり、その法的地位そのものに優劣があるわけではない。
「承認され、」の部分であるが、婚姻制度を利用した者については、単に「婚姻制度を利用している者(既婚者)」として認識されているだけであり、それを「承認」するかどうかは、個々人の価値観によるものである。
婚姻制度を廃止するべきであると訴える者からすれば、婚姻制度を利用する者に対して否定的に考えることもあるはずである。
また、法制度を利用する者が法制度を利用していることについて、社会の中でどのような評価を受けるかどうかは、その法制度の内容が社会的な不都合を解消するための制度として役立つものとなっているかどうかが関わるものである。
そのため、もし制度を変更した場合には、その制度が社会的な不都合を解消するための制度として機能しなくなったり、制度の全体の整合性が乱れることによって人々の抱く制度に対する信頼性が損なわれるなどして、制度そのものに対する「尊重する考え方」が失われることもある。
よって、制度を変更した場合においても、人々の間で「尊重する考え方」が維持されるとは限らないにもかかわらず、「尊重する考え方」があることを理由として制度を変更することを求めるような主張は、「ブランドを身に纏いたい」という結論だけを求めるあまりに、そのブランドがどのような原因によって成り立っているかという根拠を理解しないままに制度を変更しようとするものであることから、結局その根拠を破壊してしまい、本来求めていたブランドの価値そのものまで失われるという事態に陥るものである。
このような理由に基づいて制度を変更しようとすることは、制度そのものの意義を失わせる行為となることから、正当化することはできない。
「それによって安定した社会生活を営むことができるという実態があることが認められる」との部分について検討する。
まず、婚姻制度は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として、「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度である。
そして、その制度の内容が「男女二人一組」となっていることは、「男性」と「女性」の間では自然生殖を想定することができ、その間に「貞操義務」を設けることで子供が生まれた際に遺伝上の父親を特定することができることに理由があると考えられる。
このようにして制度の枠組みが定められ、立法目的の実現を目指すものであることから、婚姻制度における法的効果や一定の優遇措置については、この目的を達成するための手段として整備されているものである。
そのような内容の法制度を利用することに何らかの有益性を感じる者は、制度を利用した場合に「安定した社会生活を営むこと」に繋がると考えるかもしれないが、そのような内容の法制度を利用することに何らの有益性も感じない者であれば、その制度を利用したとしても「安定した社会生活を営むこと」に繋がるとは考えないと思われる。
むしろ、「婚姻制度を利用しない者(独身者)」として生活することの方が「安定した社会生活を営むこと」に繋がると考える者もいるのであり、実際に婚姻制度を利用していない者も存在する。
その者も、「婚姻制度を利用していない者(独身者)」として「認知、承認され、」ているともいうことができる。
また、ある制度に何らかの法的効果や優遇措置があるとしても、それはその制度の目的を達成するための手段となる枠組みに当てはまる者を対象として法的効果や優遇措置を与えることに意味があるのであり、その枠組みに当てはまらない者に対しても法的効果や優遇措置を与えた場合には、制度そのものが成り立たなくなる。
よって、その制度の目的や、その目的を達成するための手段となる枠組みの当否を離れて法的効果や優遇措置を、その制度の枠組みの対象となっていない者に対しても与えなければならないということにはならない。
そのため、ここでいう「それによって安定した社会生活を営むことができる」という部分について、これが何らかの法的効果や優遇措置を指すとしても、それは婚姻制度の立法目的と、その立法目的を達成するための手段となる枠組みに当てはまる者に対してのみ法的効果を及ぼし、優遇措置を与えることに意義があるのであり、その立法目的と、その立法目的を達成するための手段となる枠組みの当否の問題を超えて、その枠組みに当てはまらない者に対して法的効果や優遇措置を与えなければならないということにはならないことも押さえる必要がある。
「同性間の人的結合関係については、法律上、このような社会的公証を受ける手段がないため、社会内で生活する中で家族として扱われないという不利益を受けている。」との記載がある。
まず、婚姻制度は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として、「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度である。
具体的な立法目的と、その達成手段は下記のように整理することができると考えられる。
〇 「子の福祉」が実現される社会基盤を構築すること
(→ 達成手段:嫡出子として生まれることの重視)
〇 遺伝的な劣勢を有する個体が高い確率で発現することを抑制すること
(→ 達成手段:父親と近親者を特定して『近親交配』を防ぐ仕組みを導入)
〇 「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」を減らすこと
(→ 達成手段:未婚の男女の数の不均衡の防止。一夫一婦制、複婚の禁止)
〇 母体を保護すること
(→ 達成手段:婚姻適齢)
そして、婚姻制度の内容が「男女二人一組」となっていることは、「男性」と「女性」の間では自然生殖を想定することができ、その間に「貞操義務」を設けることによって、遺伝的な父親を特定することができることに理由がある。
ここでいう「同性間の人的結合関係」については、婚姻制度の枠組みが「男女二人一組」となっているため、婚姻制度の対象ではないということができる。
婚姻制度を利用する形によっては、法学的な意味の「家族」となることができないというのは、その通りである。
これについては、何も「同性間の人的結合関係」に限られるものではなく、婚姻制度の対象とはなっていない「近親者との人的結合関係」や「三人以上の人的結合関係」、「婚姻適齢に満たない者との人的結合関係」についても同様である。
婚姻制度の立法目的を達成するための手段となる枠組みに当てはまる者は制度を利用することができ、それに当てはまらない者については制度を利用できないという差異が生じることは、制度が政策的なものである以上は当然のことである。
また、婚姻制度の対象でない場合について、ここでは「法律上、このような社会的公証を受ける手段がないため、社会内で生活する中で家族として扱われないという不利益を受けている。」と述べているが、「不利益を受けている。」との評価をすることは誤りである。
憲法は13条で「個人の尊重」、24条2項でも「個人の尊厳」を記しており、「個人主義」の下に、各々自律的な個人として生存していくことを予定していることから、個々人が何らの人的結合関係も形成していない状態が基準(スタンダード)となるべき状態である。
この状態が基準(スタンダード)であり、そこに「不利益」が認められないにもかかわらず、個々人が人的結合関係を形成した場合において、「不利益を受けている。」という状態となるはずがないからである。
また、憲法の下では「個人主義」の下に自律的な個人として生存していくことを予定しているのであり、その個々人が何らかの人的結合関係を形成したからといって、何らかの積極的な保護を与えなければならないということにはならない。
これに対して、婚姻制度は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成するための手段となる枠組みを定め、その制度を利用する者に対して一定の優遇措置を講じることによって、その目的の実現を目指すものであり、その対象となる者に対してのみ利用を可能とするものである。
これは、個々人が何らかの人的結合関係を形成している場合とは区別されるものとして設けられているものである。
そのため、「婚姻制度を利用している者(既婚者)」が基準(スタンダード)となるかのような前提を基にして、それと比較する形で、「婚姻制度を利用していない者(独身者)」が「不利益を受けている。」と考えることは誤りである。
比較の際には、「婚姻制度を利用していない者(独身者)」が基準(スタンダード)であることを前提として、「婚姻制度を利用している者(既婚者)」が婚姻制度の目的を達成するための手段としては不必要に過大な優遇措置を得るものとなっていないかどうかを比較することが必要である。
そのため、「婚姻制度を利用していない者(独身者)」である「同性間の人的結合関係」のみを取り上げて、「婚姻制度を利用している者(既婚者)」が基準(スタンダード)となるかのような前提の下に、「社会内で生活する中で家族として扱われないという不利益を受けている。」のように「不利益を受けている。」と考えることは誤った論じ方である。
ここで「同性間の人的結合関係」のみ取り上げていることの背景には、現在の婚姻制度が「男女二人一組」となっていることを前提として、その「二人一組」の部分が揺るがないものであるかのように考えた上で、「異性間」があれば「同性間」もあるのではないかとの発想があると思われる。
しかし、婚姻制度が「男女二人一組」となっていることは、婚姻制度が「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として設けられた制度であり、その目的を実現するために「男性」と「女性」という自然生殖を想定することができる組み合わせを選び出し、その間に「貞操義務」を設けることで子供の遺伝的な父親を特定することができる関係となることに主な理由がある。
よって、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的からは、自然生殖を想定することが可能な「男性」と「女性」の組み合わせ(異性間)であることが重視されるものである。
そのため、「男女二人一組」の婚姻制度について、「二人一組」という部分だけを取り上げて、その他の人的結合関係との間で比較することが可能であるかのような前提に立って、「同性間の人的結合関係」を取り上げていることは、比較対象の選択を行う時点で自らの望む結論を導き出すために恣意的な選択を行ったものと考えられる。
また、現在の婚姻制度に存在しない人的結合関係を論じるのであれば、「二人一組」に限られるものではなく、「三人一組」や「四人一組」、それ以上の組み合わせなど、様々な人的結合関係を取り上げて網羅的に論じる必要があるが、それを怠り、「同性間の人的結合関係」という「二人一組」のみを比較対象として論じればそれで済むかのようなものとなっていることは、なぜ「二人一組」であるのかその根拠を説明しないままに論じる「カップル信仰論」に陥っているものである。
「社会内で生活する中で家族として扱われない」との部分の「家族」の意味について、これが社会学的な意味の「家族」を指すとすれば、憲法21条1項の「結社の自由」によって保障されることになる。
「社会内で生活する中」で、「結社の自由」によって保障される人的結合関係として、扱われることになるものである。
これに対して、法学的な意味の「家族」を指す場合には、それは「家族」の制度の立法目的と、その立法目的を達成するための手段となる枠組みを満たす者を対象としたものであることから、「家族」の中に含めることのできる人的結合関係と、「家族」の中に含めることのできない人的結合関係の間に差異が生じる当然のことである。
これは「家族」の制度に限られるものでなく、あらゆる法制度について同様にいえることである。
あらゆる法制度は立法目的を有しており、その立法目的を達成するための手段となる枠組みを設定しているものである。
そのため、その立法目的を達成するための手段として導かれている枠組みを無視する形で、どのような人的結合関係でもその制度の中に含めることができるとした場合には、その制度は立法目的を達成するための手段として機能しなくなり、制度そのものが成り立たなくなってしまうからである。
「例えばパートナーが医療機関で診療を受けた際に家族として認められなかったために病状の説明を受けられなかったり、入院の際の保証人になることができなかったりするなどの不利益を受けた経験を有する者があることが認められる。」との記載がある。
しかし、「病状の説明を受けられ」る者の範囲や「入院の際の保証人になること」ができるか否かは、「病状の説明」についての制度や「保証人」の制度の目的と、その目的を達成するための手段としてどのような範囲の者に対してその制度の利用を認めるかの問題である。
その制度の定める枠組みが、たまたま法学的な意味の「婚姻」や「家族」を対象としていたからといって、その法学的な意味の「婚姻」や「家族」の制度の立法目的と、その立法目的を達成するための手段となる枠組みの当否の問題を超えて、「婚姻」や「家族」の制度の方を変更しなければならないとする理由にはならない。
単に、「病状の説明」についての制度や「保証人」の制度の目的に従って、どのような人物を対象とするかをその医療機関がその医療機関の事情に応じて決定すればよいものである。
【参考】「病院の面会等は面会制度の問題であって同性婚法制化と関係ないと思われます。」 Twitter
【参考】「それは手術の同意書のあり方の問題にすぎません。」 Twitter
(ウ) そして、性的指向は本人の努力や治療により変えられるものではなく(前記認定事実(1)ア)、現行法上、同性愛者が婚姻することが実質的に困難であることは、前述のとおりである。
【筆者】
「性的指向は本人の努力や治療により変えられるものではなく」との記載がある。
まず、婚姻制度は「性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いを行っている事実はないし、「性愛」に基づいて婚姻することを求めるものでも勧めるものでもない。
そのため、婚姻制度は「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にどのような対象に向かうかという「性的指向」には一切関知していない。
そのため、「性的指向は本人の努力や治療により変えられるものではなく」と述べたとしても、それは婚姻制度の関知しない事柄である。
この判決は「婚姻すること」と、「性愛」の思想、信条、信仰、感情を結び付けて考えることは、「性愛」という特定の思想、信条、信仰、感情を保護するために法制度が存在するかのように解釈しようとするものであることから、憲法20条1項後段・3項、89条の「政教分離原則」に抵触して違憲となると考えられる。
婚姻制度は個々人の「性愛」に関知していないにもかかわらず、「性愛」を満たすための「婚姻」こそが正しい価値観であるとする特定の思想、信条、信仰、感情に対して肩入れするものであることから、それ以外の思想、信条、信仰、感情との間で憲法14条の「平等原則」にも抵触して違憲となる。
法制度は思想、信条、信仰、感情に対して中立的なものでなければならないし、その法制度を解釈する際にも同様に思想、信条、信仰、感情に対して中立的でなければならないのである。
「現行法上、同性愛者が婚姻することが実質的に困難である」との記載がある。
しかし、婚姻制度は「性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いを行っている事実はないし、「性愛」に基づいて婚姻することを求めるものでも勧めるものでもないことから、法律上の要件に従っているのであれば、「同性愛者」を称する者でも適法に婚姻制度を利用することが可能であり、「実質的に困難である」などと法的な障壁があるかのような説明は誤りである。
これについては、「同性愛者」と称する者に限られる話ではなく、「両性愛者」、「全性愛者」、「多性愛者」、「小児性愛者」、「老人性愛者」、「死体性愛者」、「動物性愛者」、「対物性愛者」、「対二次元性愛者」、「無性愛者」を称する者であっても同様であり、法律上の要件に従っているのであれば、適法に婚姻制度を利用することが可能である。
よって、「同性愛者」を称する者について、「婚姻することが実質的に困難である」などと、婚姻制度を利用することについて法的な障害があるかのような説明は誤りである。
これとは別の論点で、婚姻制度の対象となっていない場合については、その者は婚姻制度を利用することはできない。
これは婚姻制度が「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成するための手段として枠組みが定められていることによるものであり、その目的を達成するための手段として整合的な範囲の者のみを対象としていることによるものである。
このように、婚姻制度の対象となる場合と、対象とならない場合に差異が生じることは、制度が政策的なものである以上当然のことである。
(エ) このように、現在、同性愛者には、パートナーと家族になることを可能にする法制度がなく、同性愛者は、その生涯を通じて、家族を持ち、家庭を築くことが法律上極めて困難な状況に置かれている。家族を持たないという選択をすることも当該個人の自由であることは当然であるが、特定のパートナーと家族になるという希望を有していても同性愛者というだけでこれが生涯を通じて不可能になることは、その人格的生存に対する重大な脅威、障害であるということができる。なお、同性カップルにおいて、婚姻が認められていないことから養子縁組をする例があることがうかがわれるが、男女の夫婦と同様の人的結合関係について、親族関係を構築するために養子縁組を用いて親子関係となるのは、飽くまでその他の制度がないことによりやむを得ず行う代替手段であり、当該人的結合関係の本来の実態、実情には適合していないものといわざるを得ない。
【筆者】
「同性愛者には、パートナーと家族になることを可能にする法制度がなく、同性愛者は、その生涯を通じて、家族を持ち、家庭を築くことが法律上極めて困難な状況に置かれている。」との記載がある。
「同性愛者には、」との部分であるが、婚姻制度は「性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いを行っている事実はないし、「性愛」に基づいて「婚姻」することを求めるものでも勧めるものでもないことから、「同性愛者」を称する者でも婚姻制度を利用することは可能である。
そのため、「同性愛者」と称する者についても、婚姻制度の枠組みに従う形で存在する選択肢の中で、それでもなお婚姻制度を利用したいと望んだのであれば、婚姻制度を利用することができるのであり、「家族になることを可能にする法制度がなく、」との認識については誤りである。
これについては、「同性愛者」と称する者に限らず、「両性愛者」、「全性愛者」、「多性愛者」、「小児性愛者」、「老人性愛者」、「死体性愛者」、「動物性愛者」、「対物性愛者」、「対二次元性愛者」、「無性愛者」を称する者であっても同様であり、婚姻制度の枠組みに従う形で存在する選択肢の中で、それでもなお婚姻制度を利用することを望んだのであれば、婚姻制度を利用することが可能である。
また、「同性愛者」と称する者であることを理由として法的な障害となる事由があるわけではないため、「その生涯を通じて、家族を持ち、家庭を築くことが法律上極めて困難な状況に置かれている。」との評価も誤りである。
これとは別の論点として、婚姻制度の対象となっていない組み合わせについては、婚姻制度の対象ではないことから、それを「婚姻」とすることは認められていない。
例えば、「近親者との組み合わせ」、「三人以上の組み合わせ」、「婚姻適齢に満たない者との組み合わせ」、「同性間の組み合わせ」については、婚姻制度の対象ではないため、それを「婚姻」とすることはできない。
婚姻制度の枠組みは、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成するための手段となる枠組みを定めているものであり、その目的の達成するための手段として整合的な範囲の組み合わせを制度の対象とし、それ以外の組み合わせを制度の対象としないという差異を設けることによって、立法目的の実現を目指すものとなっている。
法制度は政策目的を実現するために設けられるものである以上は、制度の対象となる場合とならない場合の間に差異が生じることは当然のことである。
ここでいう「家族」の意味を社会学的な意味の「家族」として考えた場合には、個々人が人的結合関係を形成することについては、憲法21条1項の「結社の自由」によって保障されていることから、社会学的な意味での「家族になること」が否定されているかのようにと考えているのであれば誤りである。
これについて、ここでは「パートナー」という「二人一組」の一方を指す言葉を使い、「二人一組」であることを前提として論じるものとなっているが、憲法21条1項の「結社の自由」は、「二人一組」に限らず、「三人一組」や「四人一組」など「三人以上の組み合わせ」についても同様に保障しているものである。
それらの人的結合関係を考慮することなく、「パートナー」という「二人一組」のみを比較対象として取り上げていることは、なぜ「二人一組」であるのかその根拠を説明しないままに論じる「カップル信仰論」となっているものである。
「特定のパートナーと家族になるという希望を有していても同性愛者というだけでこれが生涯を通じて不可能になることは、その人格的生存に対する重大な脅威、障害であるということができる。」との記載がある。
この文には、複数の誤りがある。
まず、「特定のパートナーと家族になるという希望を有していても同性愛者というだけでこれが生涯を通じて不可能になることは、」との部分について検討する。
ここでいう「家族」の意味が法学的な意味の「家族」である場合について、「婚姻」や「家族」の制度は、「性愛」の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にどのような対象に向かうかを審査して区別してと扱うものではないし、「性愛」に基づいて制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもない。
そのため、「同性愛者」を称する者であるとしても、「婚姻」や「家族」の制度の枠組みに沿う形で存在する選択肢の中で、なお制度を利用することを希望した場合には、適法に制度を利用することができる。
よって、「同性愛者というだけで」法学的な意味の「家族になる」ことが「生涯を通じて不可能になる」と述べていることは誤りとなる。
他の論点として、法学的な意味の「婚姻」や「家族」の制度の対象となる場合と、対象とならない場合があり、対象とならない場合については、「家族」とすることができない。
これは、「婚姻」や「家族」の制度が、政策目的を達成するための手段となる枠組みである以上は、当然のことである。
例えば、「婚姻」とすることができないものとして、「近親者との組み合わせ」、「三人以上の組み合わせ」、「婚姻適齢に満たない者との組み合わせ」、「同性間の組み合わせ」を挙げることができる。
ここでいう「家族」の意味が社会学的な意味の「家族」である場合については、憲法21条の「結社の自由」によって保障されている。
よって、「同性愛者というだけで」社会学的な意味の「家族になる」ことが「生涯を通じて不可能になる」と述べていることも誤りとなる。
次に、「その人格的生存に対する重大な脅威、障害であるということができる。」との部分について検討する。
まず、「人格的生存」とは、国家から個々人に対して何らかの侵害があった場合に、その侵害を排除することを求めるという「国家からの自由」のいう「自由権」についての議論で論じられることのあるものである。
これについて、個々人が人的結合関係を形成することについて、国家から何らかの制限が加えられた場合には、その制限が正当化できるかが審査され、それが正当化することができない場合には、憲法21条1項の「結社の自由」などの「自由権」を用いて、その侵害を排除することが考えられる。
この際に、その「自由権」の性質を説明する際に「人格的生存」などの視点が理由の一つとして持ち出されることは考えられる。
しかし、法学的な意味の「家族」については、「婚姻」や「家族」の制度の立法目的とその立法目的を達成するための手段として枠組みが定められているものであるから、その枠組みに当てはまる者は制度を利用することができ、その枠組みに当てはまらない者は制度を利用できないという差異が生じることは当然予定されていることである。
そして、このような具体的な制度の存在を前提として、個々人がその制度を利用することができるか否かの問題については、「国家からの自由」という「自由権」とは性質を異にするものである。
そのため、「婚姻」や「家族」の制度の対象とならないからといって、国家から個々人に対して何らかの侵害が生じているというわけではないため、「国家からの自由」という「自由権」によって侵害を排除しなければならないとする対象となるような国家行為があるわけではない。
よって、「人格的生存」という国家からの侵害を排除する側面で用いられる概念が登場することはないと考えられる。
法制度上の「婚姻」や「家族」の制度の対象となっていない場合があるとしても、そのことが国家から個々人に対して何らかの侵害を行うものとはいえないことから、「人格的生存」を持ち出して排除しなければならないという国家による侵害行為そのものが存在しないのであり、「人格的生存」を持ち出すことは不自然というべきである。
よって、法学的な意味の「家族」について論じているのであれば、「婚姻」や「家族」の制度の対象となっていない場合について、「その人格的生存に対する重大な脅威、障害であるということができる。」と述べていることは、誤りということができる。
「同性カップルにおいて、婚姻が認められていないことから養子縁組をする例があることがうかがわれるが、男女の夫婦と同様の人的結合関係について、親族関係を構築するために養子縁組を用いて親子関係となるのは、飽くまでその他の制度がないことによりやむを得ず行う代替手段であり、当該人的結合関係の本来の実態、実情には適合していないものといわざるを得ない。」との記載がある。
この文には、法的な視点によって内容を解きほぐし、意味を整理して考える必要がある。
ここでいう「同性カップル」という「同性間の人的結合関係」について、「男女の夫婦と同様の人的結合関係」と述べている部分について検討する。
これについて、憲法21条1項の「結社の自由」によって保障される意味での「人的結合関係」として考えた場合には、「同様」の部分を見出せる場合があると考えられる。
これは、ここでいう「同性カップル」のような「二人一組」に限られるものではなく、「三人一組」や「四人一組」、それ以上の組み合わせにおいても「同様」である。
しかし、「男女の夫婦」の部分を「婚姻制度を利用する者」と捉えた場合には、ここでいう「同性カップル」という「同性間の人的結合関係」と「同様」であるとはいえない。
これは、下記の理由によるものである。
婚姻制度は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として設けられた制度である。
そのため、その立法目的を達成するための手段として、「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する形で枠組みを定めており、一般的・抽象的にその間で「生殖」を想定することができる「男性」と「女性」の組み合わせを一定の形式で法的に結び付けるものとなっている。
そして、このような枠組みであることにより、立法目的を達成することを目指すものとなっている。
この点で、一般的・抽象的にその間で「生殖」を想定することができる「男女」の人的結合関係と、一般的・抽象的にその間で「生殖」を想定することができない「同性間の人的結合関係」との間には立法政策の観点から「同様」には取扱うことができない。
なぜならば、これらを「同様」に取り扱った場合には、立法目的を達成することを阻害する影響が生じるという点で、違うものとして分けて考えなければならないからである。
よって、この意味でここでいう「同性カップル」という「同性間の人的結合関係」について、「男女の夫婦と同様の人的結合関係」と述べているのであれば、誤りである。
「親族関係を構築するために養子縁組を用いて親子関係となるのは、飽くまでその他の制度がないことによりやむを得ず行う代替手段であり、当該人的結合関係の本来の実態、実情には適合していないもの」との評価であるが、法解釈を行ったものとは言うことができず、妥当でない。
「婚姻」や「家族」の制度は、立法目的を達成するための手段として整合的な形で枠組みを定めるものとして形成されており、その枠を超える形での人的結合関係についてはもともと対象とはしていないものである。
なぜならば、その枠を超える人的結合関係を制度の中に含めようとした場合には、立法目的を達成するための手段として整合的な枠組みではなくなり、立法目的を達成することを阻害することに繋がるからである。
その枠組みの中で「親族関係を構築するために養子縁組を用いて親子関係となる」者がいるとすれば、それは完全な「親子関係」なのであり、それが「本来の実態、実情には適合していない」などと、「親子関係」であることを否定するような説明を行っていることは誤りである。
また、婚姻制度の対象となっていない人的結合関係について述べようとしているのであれば、「同性間の人的結合関係」だけでなく、「近親者との人的結合関係」や「三人以上の人的結合関係」、「婚姻適齢に満たない者との人的結合関係」についても「婚姻」することはできないことは同様である。
その者たちも同様に「養子縁組を用いて親子関係となる」場合も存在するにもかかわらず、それらとの整合性を検討することもなく、「同性間の人的結合関係」のみを取り上げて「当該人的結合関係の本来の実態、実情には適合していないもの」などと述べて新たな制度の創設を国家に対して求めることができることにはならない。
オ(ア) 以上を踏まえ、本件諸規定を含む現行法上、同性間の人的結合関係について、パートナーと家族になり、共同生活を送ることについて家族としての法的保護を受け、社会的公証を受けるための制度(以下「パートナーと家族になるための法制度」という。)が設けられていないことについて、個人の尊厳に照らして合理性を欠き、国会の立法裁量の範囲を超えるものとみざるを得ないような場合に当たるか否か、本件諸規定の憲法24条2項適合性について検討する。
【筆者】
「同性間の人的結合関係について、パートナーと家族になり、共同生活を送ることについて家族としての法的保護を受け、社会的公証を受けるための制度(……(略)……)が設けられていないことについて、」との部分について検討する。
まず、「家族」の意味について、これが社会学的な意味の「家族」である場合について検討する。
社会学的な意味の「家族」とは、日常用語として使われる共同生活者などのことである。
これは、人に限らず、人によっては犬や猫、鳥などのペットも「家族」の中に含めて考えている場合もある。
これについて、「同性間の人的結合関係」で「共同生活を送ること」については、憲法21条1項の「結社の自由」によって保障されている。
これは何も「同性間の人的結合関係」という「二人一組」の関係に限られるわけではなく、「三人一組」や「四人一組」、「五人一組」、「六人一組」、それ以上の組み合わせにおいても同様であり、憲法21条1項の「結社の自由」によって保障されている。
よって、このような人的結合関係は憲法21条1項によって「法的保護」を受けているということができる。
そして、もしこのような人的結合関係を形成することについて、国家が制限を行っている場合には、その制限が正当化できるものとなっているかを審査し、その制限が正当化できるものではない場合には、憲法21条1項の「結社の自由」などの規定を用いて、その「国家からの自由」といわれる「自由権」の側面より、その制限を排除することを求めることが可能である。
これに対して、「家族」の意味が、法学的な意味の「家族」である場合を検討する。
法学的な意味の「家族」とは、憲法24条2項の「婚姻及び家族」として示されている「家族」であり、この規定に従って立法された法制度上の「家族」のことをいう。
この「家族」の範囲は、「婚姻及び家族」の制度の立法目的と、その立法目的を達成するための手段として枠組みが定められるものである。
そのため、その「婚姻及び家族」の制度の対象となる場合には、「家族」の制度を利用することができるが、「婚姻及び家族」の制度の対象とならない場合には、「家族」の制度を利用することはできない。
このような差異が生じることは、「婚姻及び家族」という枠組みそのものが、その概念が形成されている目的を達成するために、憲法21条1項の「結社の自由」によって保障される他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられたものである以上は当然のことである。
ここでいう「同性間の人的結合関係」について、「婚姻及び家族」の制度における立法目的を達成するための手段となる枠組みの中の「親子」、「兄弟」、「姉妹」などに当てはまらないのであれば、法学的な意味の「家族」とすることはできない。
これについては、「同性間の人的結合関係」に限られるものではなく、「三人以上の人的結合関係」、「婚姻適齢に満たない者との人的結合関係」についても、それが「親子」、「兄弟」、「姉妹」などに当てはまらないのであれば、法学的な意味の「家族」とすることはできない。
このような、法制度の対象となる場合と、法制度の対象とならない場合があることは、法制度そのものが政策目的を実現するための手段として組み立てられるものである以上は、当然のことである。
「個人の尊厳に照らして合理性を欠き、国会の立法裁量の範囲を超えるものとみざるを得ないような場合に当たるか否か、本件諸規定の憲法24条2項適合性について検討する。」との部分について検討する。
まず、「個人の尊厳」という文言を持ち出して、「憲法24条2項適合性について検討する。」と述べていることから、この「個人の尊厳」は、「憲法24条2項」に記されたものを指していると考えられる。
しかし、「憲法24条2項」の規定は、「婚姻及び家族」の制度に対してのみ「個人の尊厳」を満たすことを求めるものであり、そもそも「婚姻及び家族」の制度の対象とならない場合については、この「個人の尊厳」が適用される余地はない。
「同性間の人的結合関係」については、「婚姻」ではないし、「親子」や、「親子」の関係を基本として形成される「兄弟」、「姉妹」などに含まれないのであれば、法学的な意味の「家族」とすることはできない。
そのため、「同性間の人的結合関係」について、それが「親子」「兄弟」「姉妹」などに含まれないのであれば、「憲法24条2項」が適用されることはないし、「憲法24条2項」が適用されることを前提として「個人の尊厳」に照らして考えようとしていることも誤りである。
「パートナーと家族になり、共同生活を送ることについて家族としての法的保護を受け、社会的公証を受けるための制度(……(略)……)が設けられていないことについて、個人の尊厳に照らして合理性を欠き、国会の立法裁量の範囲を超えるものとみざるを得ないような場合に当たるか否か、」との文脈について検討する。
まず、ここでいう「家族」が法学的な意味の「家族」の場合であるが、それは「婚姻及び家族」の制度の立法目的とその立法目的を達成するための手段として枠組みが定められているものであることから、その立法目的を達成するための手段として整合的な範囲の人的結合関係のみを対象とするものである。
また、その「婚姻及び家族」の制度の対象となっていない場合については「個人の尊厳」が適用されることはないため、「婚姻及び家族」の制度の対象とならない場合について「個人の尊厳に照らして合理性を欠き、国会の立法裁量の範囲を超えるものとみざるを得ないような場合に当たるか否か、」を検討しようとしているのであれば、誤りである。
次に、ここでいう「家族」の意味が社会学的な意味の「家族」の場合であるが、それは憲法21条1項の「結社の自由」が適用されるとしても、憲法24条2項が適用されることはない。
そのため、憲法24条2項の「個人の尊厳」が適用されることを前提として「個人の尊厳に照らして合理性を欠き、国会の立法裁量の範囲を超えるものとみざるを得ないような場合に当たるか否か、」を検討しようとしているのであれば、誤りである。
そこで、「個人の尊厳」の意味が、学問上、憲法13条前段の「個人の尊重」と同一の趣旨とされていることから、ここでいう「個人の尊厳」を憲法13条前段の「個人の尊重」の意味に捉え直した場合にどうなるかを検討する。
これについては、大阪地裁判決においても述べられているように、憲法13条によって特定の制度を求める権利が保障されているわけではない。
大阪地裁判決
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
したがって、憲法24条が異性間の婚姻のみを定めており、これを前提とする婚姻制度しか存在しない現行法の下では、同性間で婚姻をするについての自由が憲法13条で保障されている人格権の一内容であるとはいえない。また、包括的な人権規定である同条によって、同性間の婚姻制度を含む特定の制度を求める権利が保障されていると解することもできない。
よって、本件諸規定が憲法13条に反するとはいえない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
損害賠償請求事件 大阪地方裁判所 令和4年6月20日 (PDF)
そのため、この憲法13条前段の「個人の尊重」の趣旨によって、ここでいう「パートナーと家族になり、共同生活を送ることについて家族としての法的保護を受け、社会的公証を受けるための制度」などの具体的な法制度を創設を国家に対して求めることができることにはならない。
この段落は、「本件諸規定」の内容が、「憲法24条2項」に適合するか否かに関する判断枠組みを示そうとするものと考えられるが、上記のように、その判断枠組みそのものが法律論として成り立っていないことから、このようなものに基づいて「本件諸規定」の「憲法24条2項適合性」を判断することはできない。
「同性間の人的結合関係」との部分は、「二人一組」であることを前提とするものである。
また、「パートナーと家族になり、」との部分についても、「パートナー」という言葉は「二人一組」の一方を指す言葉であることから、「二人一組」を前提とするものとなっている。
ここで「二人一組」を比較対象として取り上げていることは、婚姻制度の枠組みが「男女二人一組」であることを前提として、その「男女」の部分を切り取って、「二人一組」の部分だけを取り上げて比較対象とすることができるのではないかとの発想によるものと思われる。
しかし、婚姻制度は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として設けられた枠組みであり、婚姻制度の枠組みが「男女二人一組」となっていることは、「男性」と「女性」の間では自然生殖を想定することができ、その者の間に「貞操義務」を設けることによって、子供が産まれた場合に、その子供の遺伝的な父親を特定することができるという仕組みに理由がある。
そのため、婚姻制度の枠組みが「男女二人一組」となっていることは、その間で自然生殖を想定することができる「男性」と「女性」の組み合わせであることが重要な要素となっているものであり、これを切り取って、「二人一組」の部分だけを前提として比較対象とすることができるという性質のものではない。
そのことから、婚姻制度の枠組みを超える人的結合関係との間で比較をする場合には、「二人一組」に限らず、「三人一組」や「四人一組」、「それ以上の組み合わせ」などを網羅的に論じなければならないものである。
それにもかかわらず、「同性間の人的結合関係」や「パートナー」という言葉を用い、「二人一組」の人的結合関係のみを比較対象として取り上げれば済むかのような説明となっていることは、なぜ「二人一組」であるのかその根拠を説明しないままに論じる「カップル信仰論」に陥っているものである。
その他、この段落の「個人の尊厳に照らして合理性を欠き、国会の立法裁量の範囲を超えるものとみざるを得ないような場合に当たるか否か」の結論は下記の(オ)に記載されているが、そこに至るまでの下記の(イ)(ウ)(エ)の内容を見ても、ここでいう「個人の尊厳」(13条の『個人の尊重』と同じ意味として)が何であるか、また、「個人の尊厳」に「照らして」「合理性」を欠くか否かを判断する手がかりとなるような記述は見当たらないように思われる。
(イ) 前記 エのとおり、近時、同性愛者等を取り巻く社会状況には大きな変化があり、同性愛を異常なもの、病的なものとするかつての認識は改められつつあり、多くの国において同性間の人的結合関係に一定の地位や法的効果を与える登録パートナーシップ制度等が導入され、さらに、平成13年以降、約30の国・地域において、同性間の婚姻を認める立法が次々にされてきたことが認められる。我が国においても、多くの地方公共団体においてパートナーシップ証明制度が導入され、民間企業においても同性間の人的結合関係を夫婦と同等に扱う例があるなど、同性カップルについて一定の保護を与えようとする動きがある。
【筆者】
「近時、同性愛者等を取り巻く社会状況には大きな変化があり、同性愛を異常なもの、病的なものとするかつての認識は改められつつあり、」との記載がある。
まず、「同性愛者等」との部分であるが、この東京地裁判決では「同性愛者等」の意味について「2(1)」のところで「同性愛者と性的指向が両性愛である者」と説明していることから、「同性愛者」と「両性愛者」のことを指しているようである。
しかし、個々人の内心における「性愛」の思想、信条、信仰、感情には、「同性愛」や「両性愛」の他にも、「全性愛者」「近親性愛者」「多性愛者」「小児性愛者」「老人性愛者」「死体性愛者」「動物性愛者」「対物性愛者」「対二次元性愛者」「無性愛者」など様々な分類が議論されているのであり、その中で「同性愛者」と「両性愛者」を称する者を「取り巻く社会状況」の変化だけを見て、そのことを根拠として何らかの法制度を設けるべきであると論じることが可能であるかのような前提で論じていることは、それ以外の「性愛」を有する者や、「性愛」以外の思想、信条、信仰、感情との間で区別するものとなることから、憲法14条の「平等原則」に抵触して違憲となる。
法制度を創設する際には、個々人の内心に中立的な内容でなければならないのであり、特定の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的としたり、特定の思想、信条、信仰、感情の有無を審査したり、それに基づいて区別取扱いをするような制度を設けてはならないからである。
もちろん現在の婚姻制度についても、それが「男女二人一組」の形に限定されているとしても、それは「異性愛」という思想、信条、信仰、感情を保護することを目的とした制度ではないし、「異性愛者」と称する者を対象としたものでもない。
また、婚姻制度が「異性愛」という思想、信条、信仰、感情を保護することを目的とするものであってはならないし、個々人の「性愛」の有無や、「性愛」を有する場合にそれが「異性愛」であるか否かを審査することがあってはならないし、「異性愛」に基づいて「婚姻」することを求めてもいけないし、勧めるようなこともしてはならない。
もしそのような制度となっている場合には、憲法20条1項後段・3項、89条の「政教分離原則」、憲法19条の「思想良心の自由」、憲法20条1項前段の「信教の自由」、憲法14条の「平等原則」に抵触して違憲となる。
よって、「近時、同性愛者等を取り巻く社会状況には大きな変化があり、同性愛を異常なもの、病的なものとするかつての認識は改められつつあり、」と述べたところで、法制度については、そのような特定の思想、信条、信仰、感情とは切り離して論じなければならないのであり、そのような事柄を取り上げて、法制度の存否についての適否を判断するための根拠としてはならない。
「多くの国において同性間の人的結合関係に一定の地位や法的効果を与える登録パートナーシップ制度等が導入され、さらに、平成13年以降、約30の国・地域において、同性間の婚姻を認める立法が次々にされてきたことが認められる。」との記載がある。
まず、「国・地域」の部分であるが、日本国との間では社会事情が異なることから、そこで課題となる問題も異なっており、それらの課題を解決することを意図して法制度を構築する際の立法目的も異なっている。
そのため、それらの「国・地域」と日本国の法制度を比較する際には、外国語を翻訳する際に、翻訳者がある制度に対して「婚姻」という言葉を当てて説明しているからといって、日本国の法制度における「婚姻」と同一のものを指していることにはならない。
それぞれの「国・地域」における社会事情の中で課題となる問題を解決することを意図してそれらの法制度が構築されているだけであり、その立法目的やそれを達成するための手段・方法には様々な違いがあるからである。
そのことから、ここで「約30の国・地域において、同性間の婚姻を認める立法が次々にされてきた」と説明したところで、それらの「国・地域」におけるここで「婚姻」と翻訳している法制度と、日本国の法制度における「婚姻」とは、同一のものを指していることにはならない。
そのため、「約30の国・地域において、同性間の婚姻を認める立法が次々にされてきた」と説明したところで、日本国の法制度に対して直接的な影響を与えるようなことはない。
「我が国においても、多くの地方公共団体においてパートナーシップ証明制度が導入され、民間企業においても同性間の人的結合関係を夫婦と同等に扱う例があるなど、同性カップルについて一定の保護を与えようとする動きがある。」との記載がある。
しかし、「地方公共団体」の「パートナーシップ証明制度」の内容が、民法上の婚姻制度や憲法上の規定に抵触した場合には違法となるのであり、この点の民法上の婚姻制度や憲法上の規定との整合性を検討しないままに、「地方自治体」の「パートナーシップ証明制度」が適法な制度であることを前提として論じている部分は妥当でない。
詳しくは、当サイト「パートナーシップ制度」で解説している。
「民間企業においても同性間の人的結合関係を夫婦と同等に扱う例があるなど、」の部分であるが、民間企業の契約の内容については、憲法上の「公共の福祉」や民法上の「公序良俗」や「強行規定」に違反しないかを個別に検討しなければ、そのような扱いが適法となるかは判断することができない。
「愛人契約」が違法であることはよく知られていることであり、民間企業が「愛人契約」を制度化している場合には、その契約は違法となる。
【動画】司法試験入門講座 プレ講義 「体系マスター」民法2 「民法の役割、考え方」 2020/03/16
そのため、これらの契約の内容を個別に検討することもなく、適法な制度であることを前提として取り上げていることは妥当とはいえない。
また、民間企業の契約の内容が、国の法制度の内容についての合憲・違憲の判断において影響を与えることはないのであり、このような事例を持ち出して論じることそのものについても妥当でない。
また、性的少数者に対する調査によれば、8~9割の者が、同性間の婚姻の制度又は国レベルのパートナーシップの登録制度を要望していることが認められる(前記認定事実(1)ウ(ウ)及び(エ))。
さらに、世論調査の結果によれば、平成26年に行われた調査においては、同性間の婚姻を法的に認めることについて、反対意見が賛成意見を上回っていたが、平成27年以降は賛成意見が反対意見を上回るようになり、令和2年に全国の有権者を対象として実施された調査では、賛成意見が46%、反対意見が23%であり、平成17年に行われた調査より賛成意見が14%増えたことが認められるほか、平成30年に行われた調査では同性カップルにも何らかの法的保障が認められるべきであるとの回答が75%を超えていることが認められる(前記認定事実(5))。
【筆者】
「性的少数者に対する調査によれば、」との記載がある。
しかし、「性的少数者」であるか否かは、そもそも「内心の自由」に属する個々人の内心によるものであることから、本人が「性的少数者」であるか否かを明確に判断することのできる客観的な基準となるものは存在しない。
そのため、「性的少数者に対する調査」としているすべての資料の内実は、本人が自らを「性的少数者」であると自称している者を対象にした調査に過ぎない。
【参考】アメリカの若者の30%以上が「自分はLGBTQ」と認識していることが判明 2021年10月26日
例えば、「ネッシー信者に対する調査」を行ったところで、それは本人が自らを「ネッシーを信じる者」であると自称している者を対象とした調査でしかないことは容易に理解することができる。
このような調査を取り上げたいのであれば、その調査の内容が法律論を組み立てる際に用いることができるような性質のものであるかを一つ一つ検証することが必要である。
今回の事例でも、その「性的少数者」を称する者が、「自称」によるものでない客観的な基準が存在するかどうかについても検証することが必要である。
「認定事実」の部分で示された資料を見ても、そのような「性的少数者」であることが「自称」によるものではないことを裏付けるような客観性のある基準が用いられていることを示すようなものはない。
よって、このような「調査」と称するものを根拠として法律論を論じることはできないし、このような「調査」と称するものを根拠として法律論上の規範となる枠組みが左右されるようなことがあってはならないし、法律論上の結論が変わるようなこともあってはならない。
「性的少数者」であるか否かそれ自体がそれを名乗り出た者による自称でしかないことを押さえれば、このような調査を前提として論じているこの判決の内容そのものも、説得的な説明を行っているものではないことが明らかとなる。
「世論調査の結果」を取り上げている部分であるが、憲法に抵触するか否かの判断が「世論調査の結果」によって変わるというような意味でこの「世論調査の結果」を取り上げているのであれば、明らかに誤りである。
下記の「⑶オ(オ)」のところで、「以上の点を総合的に考慮すると、」として「憲法24条2項に違反する状態にあるということができる。」と述べているが、このような「世論調査の結果」を含めた「総合的に考慮」を行うことによって、憲法に違反するか否かを判断できるとすれば、「世論調査の結果」によって逆の判断が出ていた場合には、「憲法24条2項に違反する状態にある」とはいえないことになるということになるものである。
これは、憲法上の規範の意味を明らかにした上で、具体的な法律の規定がその規範に当てはまるか否かによって憲法適合性を論じるのではなく、「『世論調査の結果』などを『総合的に考慮』したら、違憲としておいた方がいいのではないか」というようなその時々の「空気」に委ねるものといえるから、裁判官個人の恣意的な判断であることを「世論調査の結果」という形で覆い隠そうとするものに過ぎず、法律論として正当化することのできるものではない。
「同性カップルにも何らかの法的保障が認められるべきであるとの回答が」との部分であるが、既に憲法21条1項の「結社の自由」によって「法的保障」が存在するものである。
これは、ここでいう「同性カップル」のいう「二人一組」に限られるものではなく、「三人一組」や「四人一組」、「五人一組」、それ以上の組み合わせにおいても同様である。
もし何らの根拠もなく「カップル」という「二人一組」だけを比較対象として持ち出せば足りると考えているのであれば、なぜ「二人一組」であるのかその根拠を説明しないままに論じる「カップル信仰論」に陥っているものということができる。
(ウ) 現在、同性愛者についてパートナーと家族になるための法制度が設けられていないのは、前述のとおり伝統的に婚姻が異性間のものと考えられてきたことに負うところが大きいものと考えられるが、パートナーと家族になるための法制度としては、同性間の婚姻制度以外にも、イタリア等の諸外国で導入されている制度(前記認定事実(3)ア)のような婚姻に類する制度も考えられるところであり、少なくともこのような婚姻に類する制度は、前記の婚姻についての伝統的な価値観とも両立し得るものと考えられる。
【筆者】
「同性愛者についてパートナーと家族になるための法制度が設けられていないのは、前述のとおり伝統的に婚姻が異性間のものと考えられてきたことに負うところが大きいものと考えられるが、」との記載がある。
「同性愛者について」との部分について検討する。
まず、婚姻制度は「性愛」の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いを行うものではないし、「性愛」に基づいて「婚姻」することを求めるものでも勧めるものでもない。
そのため、「同性愛者」を称する者であるとしても、婚姻制度の枠組みに従う形で存在する選択肢の中で、それでもなお「婚姻」したいと望んだ場合には、その婚姻制度を利用することが可能である。
このことは「同性愛者」を称する者だけでなく、「両性愛者」、「全性愛者」、「近親性愛者」、「多性愛者」、「小児性愛者」、「老人性愛者」、「死体性愛者」、「動物性愛者」、「対物性愛者」、「対二次元性愛者」、「無性愛者」を称する者であるとしても同様である。
よって、「同性愛者」と称する者について、法学的な意味で「家族」について、「家族になるための法制度が設けられていない」と述べている部分は、誤りである。
これに対して、法学的な意味の「婚姻」や「家族」の制度の対象となっていない場合については、「婚姻」や「家族」の制度を利用することができないことは当然である。
これは、「婚姻」や「家族」の制度が、その立法目的を達成するための手段として設けられた枠組みであり、もともと制度の対象となる者と、対象とならない者を区別することによって、その政策目的を達成することを目指すものとなっているからである。
たとえば、「近親者との人的結合関係」や「三人以上の人的結合関係」、「婚姻適齢に満たない者との人的結合関係」、「同性間の人的結合関係」については、「婚姻」という形によっては「家族」とすることはできない。
これについても、「同性愛者」を称する者だけでなく、「異性愛者」「両性愛者」、「全性愛者」、「近親性愛者」、「多性愛者」、「小児性愛者」、「老人性愛者」、「死体性愛者」、「動物性愛者」、「対物性愛者」、「対二次元性愛者」、「無性愛者」を称する者であるとしても同様である。
「異性間」を超える「法制度が設けられていない」ことの理由について、ここでは「伝統的に婚姻が異性間のものと考えられてきた」ことが原因であると考えているようである。
しかし、「伝統的に婚姻が異性間のものと考えられてきた」ことについて、その枠組みを形成している「目的」と「その目的を達成するための手段」の関係を見なければ、「法制度が設けられていない」ことがどのような意味を有するのかを理解することはできない。
また、その意味を理解しなければ、「異性間」を超える人的結合関係についての「法制度」を設けることが適切であるかどうかを判断することはできない。
その他、そのような「法制度」は、憲法24条の「婚姻」に抵触して違憲となることが考えられるし、他の様々な人的結合関係との間や、何らの制度も利用していない者との間で合理的な理由を説明することのできない差異を生じさせることとなり、憲法14条の「平等原則」に抵触して違憲となることが考えられる。
「パートナーと家族になるための法制度としては、同性間の婚姻制度以外にも、イタリア等の諸外国で導入されている制度……(略)……のような婚姻に類する制度も考えられるところであり、」との記載がある。
まず、「同性間の婚姻制度以外にも、」の部分では、あたかも「同性間」の人的結合関係を「婚姻」とすることが可能であるかのような前提で論じているが、「婚姻」の中に「同性間」の人的結合関係」を含めることができるかどうかから検討する必要がある。
「婚姻」は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として、他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度であり、このような目的を離れて「婚姻」を観念することはできない。
そのことから、「婚姻」という概念が形成される際の目的との関係により、「婚姻」の中に含めることのできる人的結合関係には内在的な限界がある。
「婚姻」という概念であることそれ自体によって、「婚姻」の中に含めることのできる人的結合関係と、含めることのできない人的結合関係が区別されるということである。
そして、婚姻は下記が欠くことのできない重要な目的となっていると考えられる。
〇 「子の福祉」が実現される社会基盤を構築すること
〇 遺伝的な劣勢を有する個体が高い確率で発現することを抑制すること
〇 「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」を減らすこと
〇 母体を保護すること
そして、これらの目的を達成するための手段として整合的な下記の要素を満たす関係のみを対象とすることで、立法目的を達成することを目指すものとなっている。
・ 子の遺伝的な父親を特定できる組み合わせとすること
・ 特定された子の父親にも子に対する責任を担わせること
・ 特定された子の父親を基に遺伝的な近親者を把握すること
・ 未婚の男女の数の不均衡を防止できる組み合わせに限定すること
これらの要素を満たす人的結合関係であることによって、「婚姻」は、他の様々な人的結合関係との間で区別することが可能となり、「婚姻」という概念そのものを成り立たせることが可能となる。
「同性間」の人的結合関係については、一般的・抽象的にその間で「生殖」を想定することができないことから、上記の要素を満たすものではない。
よって、「同性間」の人的結合関係は「婚姻」の中に含めることはできない。
そのことから、ここでは「同性間の婚姻制度」のように、「同性間」の人的結合関係を「婚姻」とすることができるかのような前提で論じられているが、そもそも「同性間」の人的結合関係については、「婚姻」とすることができないという点で誤っていると考えられる。
「イタリア等の諸外国で導入されている制度」との部分について検討する。
まず、外国の法制度は、その外国の社会事情の中で生じている問題を解決することを目的として、その目的を達成するための手段として設けられているものである。
そのため、その外国の法制度と自国の法制度に対して何らかの類似点を見出す場合があるとしても、それはそれぞれの国の社会事情の中で形成された別個の制度であることから、同じ制度を指していることにはならない。
そのため、ここでは「イタリア等の諸外国で導入されている制度」と論じるのであるが、その制度はその国の事情に応じて生じたものであり、日本国でその制度と類似点を見出すことのできる何らかの制度を設けることが適切であるとは限らない。
また、この東京地裁判決の上記の「1(3)ア」や「1(3)イ」のところや、ここで「イタリア等」と示している内容は、外国における「同性間」の人的結合関係を対象とした法制度のみを取り上げるものとなっているが、外国の法制度の中には「男性一人と女性四人まで」の人的結合関係による「一夫多妻」を法制度としている国も存在するのであり、それらを一切取り上げることなく、「同性間」の人的結合関係、あるいは「二人一組」の人的結合関係における法制度を有する国のみを比較対象として取り上げることは、この判決を書いた裁判官が特定の結論を導き出すために意図的に「二人一組」であるという前提を先取りする形で論じようとする恣意的な判断が含まれていることが考えられる。
このような、「二人一組」であることを前提とする論じ方は、なぜ「二人一組」であるのかその根拠を説明しないままに論じる「カップル信仰論」に陥っているものということができる。
「婚姻に類する制度も考えられるところであり、少なくともこのような婚姻に類する制度は、前記の婚姻についての伝統的な価値観とも両立し得るものと考えられる。」との記載がある。
しかし、「婚姻に類する制度」と称するものの立法が可能となるとは限らないし、そのような制度は「婚姻についての伝統的な価値観とも両立し得る」とも限らないため、婚姻制度の「立法目的」と「それを達成するための手段」との関係から詳しく検討する。
婚姻制度は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度である。
そして、その「立法目的」と「その立法目的を達成するための手段」となる枠組みは、下記のように整理できると考えられる。
〇 「子の福祉」が実現される社会基盤を構築すること
(→ 達成手段:嫡出子として生まれることの重視)
〇 遺伝的な劣勢を有する個体が高い確率で発現することを抑制すること
(→ 達成手段:父親と近親者を特定して『近親交配』を防ぐ仕組みを導入)
〇 「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」を減らすこと
(→ 達成手段:未婚の男女の数の不均衡の防止。一夫一婦制、複婚の禁止)
〇 母体を保護すること
(→ 達成手段:婚姻適齢)
婚姻制度が機能するためには、このような立法目的を達成することを阻害するような法制度を立法することはできない。
そこで、「婚姻に類する制度」を設けることができるかどうかであるが、下記のような点で問題が生じると考えられる。
「同性間」の人的結合関係に何らかの法的効果や優遇措置を行った場合には、遺伝上の父親を特定することができない関係の中で子を産むことを推進することとなり、婚姻制度が遺伝上の父親を特定することによって「子の福祉」の充実を目指す仕組みとなっていることと矛盾することとなる。
また、遺伝上の父親を特定できない中で子を産むことを推進する作用を持つ制度を設けることは、婚姻制度が遺伝上の近親者を把握して、その者との間で「婚姻」することができない仕組みとすることによって、「近親交配」に至ることを回避しようとする枠組みとなっていることと矛盾することなる。
他にも、「同性間」の人的結合関係に何らかの法的効果や優遇措置を行った場合には、その制度を利用することによって「同性間」の人的結合関係を形成する者が増えることから、何らの制度も利用していない男女の数に不均衡が生じ、「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」が増えてしまうことに繋がり、婚姻制度が「一夫一妻制」とすることによって、「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」を減らそうとする仕組みとなっていることと矛盾する。
このように、「同性間」の人的結合関係について「婚姻に類する制度」と称するものを設けた場合には、婚姻制度の立法目的を達成するための機能を阻害することに繋がることが考えられる。
また、憲法24条の「婚姻」の文言は、「生殖と子の養育」に関わる制度を一元的に集約して規律していることから、憲法24条の「婚姻」を離れて「生殖と子の養育」に関わる制度を立法することはできない。
そのため、「同性間」の人的結合関係に対して何らかの法的効果や優遇措置を設けた場合には、「生殖」や「子の養育」に影響を与えるものとなることが考えられ、憲法24条の「婚姻」に抵触して違憲となると考えられる。
さらに、「同性間」の人的結合関係に対して「婚姻に類する制度」と称するものを立法することは、その他の人的結合関係を形成する者との間や、何らの人的結合関係を形成していない者との間で、憲法14条の「平等原則」に抵触して違憲となることが考えられる。
これは、婚姻制度の枠組みが一般的・抽象的に「生殖」を想定することができる「男性」と「女性」の揃う「二人一組」を対象として立法目的の実現を目指すものとは異なっており、「同性間」の人的結合関係についてはその他の人的結合関係や何らの制度も利用していない者との間で法的効果や優遇措置に差異を設ける理由を見出すことができず、正当化することができないからである。
よって、「婚姻に類する制度も考えられる」のように「婚姻に類する制度」と称するものを立法することが可能であるかのように考えている部分は、誤っていると考えられる。
また、このような「婚姻に類する制度」は、婚姻制度の立法目的の実現を阻害することに繋がると考えられ、この判決が「伝統的な価値観」と述べている婚姻制度の機能と矛盾するものとなっていることから、「婚姻に類する制度」が「婚姻についての伝統的な価値観とも両立し得るものと考えられる。」と述べていることも誤りとなる。
詳しくは、当サイト「パートナーシップ制度」で解説している。
この段落は、「パートナー」という「二人一組」の一方を示す言葉が二回登場するため、人的結合関係が「二人一組」であることを前提とするものとなっているが、人的結合関係の中には「三人一組」の者もいるし、「四人一組」の者もいるのであって、それらの人的結合関係の可能性を検討せずに、「二人一組」の人的結合関係のみを取り上げていることは、「カップル信仰論」に陥っているものということができる。
そして、多数の地方公共団体においてパートナーシップ証明制度が導入され、利用され、広がりをみせていることは前述のとおりであり、さらに国において同性間の人的結合関係について婚姻に類する制度を構築することについて大きな障害となるような事由があることはうかがわれない。むしろ、上記のような制度を構築することは、その同性間の人的結合関係を強め、その中で養育される子も含めた共同生活の安定に資するものであり、これは、社会的基盤を強化させ、異性愛者も含めた社会全体の安定につながるものということもできる。
【筆者】
「多数の地方公共団体においてパートナーシップ証明制度が導入され、利用され、広がりをみせていることは前述のとおりであり、」との記載がある。
しかし、地方公共団体の制定する「条例」や「規則」、「要綱」などは、国会の制定する法律に違反してはならないため、民法に定められた婚姻制度に抵触するものとなっている場合には違法となる。
下記で条例制定権の限界に関する判例を読み取る。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
すなわち、地方自治法一四条一項は、普通地方公共団体は法令に違反しない限りにおいて同法二条二項の事務に関し条例を制定することができる、と規定しているから、普通地方公共団体の制定する条例が国の法令に違反する場合には効力を有しないことは明らかであるが、条例が国の法令に違反するかどうかは、両者の対象事項と規定文言を対比するのみでなく、それぞれの趣旨、目的、内容及び効果を比較し、両者の間に矛盾牴触があるかどうかによつてこれを決しなければならない。例えば、ある事項について国の法令中にこれを規律する明文の規定がない場合でも、当該法令全体からみて、右規定の欠如が特に当該事項についていかなる規制をも施すことなく放置すべきものとする趣旨であると解されるときは、これについて規律を設ける条例の規定は国の法令に違反することとなりうるし、逆に、特定事項についてこれを規律する国の法令と条例とが併存する場合でも、後者が前者とは別の目的に基づく規律を意図するものであり、その適用によつて前者の規定の意図する目的と効果をなんら阻害することがないときや、両者が同一の目的に出たものであつても、国の法令が必ずしもその規定によつて全国的に一律に同一内容の規制を施す趣旨ではなく、それぞれの普通地方公共団体において、その地方の実情に応じて、別段の規制を施すことを容認する趣旨であると解されるときは、国の法令と条例との間にはなんらの矛盾牴触はなく、条例が国の法令に違反する問題は生じえないのである。�
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
集団行進及び集団示威運動に関する徳島市条例違反、道路交通法違反 最高裁判所大法廷 昭和50年9月10日 (PDF) (徳島市公安条例事件)
この判例によれば、下記の場合には、「地方公共団体」において「パートナーシップ証明制度」を導入していることは、違法となる。
◇ 「国の法令中にこれを規律する明文の規定がない場合でも、当該法令全体からみて、右規定の欠如が特に当該事項についていかなる規制をも施すことなく放置すべきものとする趣旨であると解されるとき」
◇ 条例の「適用によつて」、国の法令「の規定の意図する目的と効果を」「阻害する」場合
そこで、民法上の婚姻制度の「趣旨、目的、内容及び効果」を検討すると婚姻制度の立法目的と、その達成手段は下記のように整理することができると考えられる。
〇 「子の福祉」が実現される社会基盤を構築すること
(→ 達成手段:嫡出子として生まれることの重視)
〇 遺伝的な劣勢を有する個体が高い確率で発現することを抑制すること
(→ 達成手段:父親と近親者を特定して『近親交配』を防ぐ仕組みを導入)
〇 「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」を減らすこと
(→ 達成手段:未婚の男女の数の不均衡の防止。一夫一婦制、複婚の禁止)
〇 母体を保護すること
(→ 達成手段:婚姻適齢)
「パートナーシップ証明制度」の内容が、これらの目的を達成することを阻害するものとなっている場合には、民法の婚姻制度に抵触して違法となる。
婚姻制度は遺伝上の父親を特定することにより、その者にも子に対する養育の責任を担わせることによって、「子の福祉」を実現しようとするものとなっていることから、父親を特定することができない人的結合関係に対して何らかの優遇措置を与えることは、この目的を達成することを阻害することになるから、婚姻制度に抵触して違法となると考えられる。
また、「パートナーシップ証明制度」の内容が「男女二人一組」の形であるとしても、そこに「貞操義務」が設けられていないのであれば、結局は制度の内容に従って適法な行動をしていたとしても、子の母親となる者は「パートナーシップ証明制度」を利用する相手方とは異なる他の男性との間で生殖を行っている可能性を排除することができないことから、父親を特定することができなくなるため、このような人的結合関係に対して何らかの優遇措置を与えることは、婚姻制度に抵触して違法となる。
婚姻制度は遺伝上の父親を特定することにより、その父親にも子に対する養育の責任を担わせることによって「子の福祉」を実現しようとするものであるから、婚姻制度を利用しない人的結合関係に対しては意図的に優遇措置を与えないことにより、「生殖」によって子供をつくる者が婚姻制度を利用することによって遺伝的な父親を特定できる人的結合関係を形成するようにインセンティブを与えるものとなっている。しかし、国民が「パートナーシップ証明制度」を利用することにより、婚姻制度を利用した場合と同様の優遇措置や類似した優遇措置を得られることを理由に、婚姻制度を利用するのではなく「パートナーシップ証明制度」を利用することに安住してしまうことになれば、婚姻制度が遺伝的な父親を特定することによって達成しようとした立法目的の達成を阻害することになる。よって、婚姻制度とは異なる選択肢として「パートナーシップ証明制度」を設け、婚姻制度と同様の優遇措置や類似した優遇措置を得られるようにすることは、婚姻制度に抵触して違法となる。
(ここで『婚姻制度とは異なる選択肢として』と記載している意味は、『企業間パートナーシップ』『商工業パートナーシップ』『貿易におけるパートナーシップ』など、婚姻とはまったく関わらない制度については、婚姻制度には抵触しないことを意味するものである。単に地方公共団体の政策担当者が『パートナーシップ証明制度』について『婚姻制度とは異なる制度である』と言い張るだけで、その『パートナーシップ証明制度』が民法の婚姻制度に違反しなくなって適法となるわけではなく、その『趣旨、目的、内容及び効果』が実質的に婚姻制度と競合するかどうかを判断することが必要である。)
婚姻制度には、遺伝上の父親を特定することによって近親者の範囲を把握し、それらの者との間で婚姻制度を利用できないことにすることで、「近親交配」に至ることを防ぎ、遺伝的な劣勢を有する個体が高い確率で発現することを防ぐ目的がある。この観点から、「女性同士の組み合わせ」に対して優遇措置を与えることは、遺伝的な父親を特定することができない関係の中で子供を産むことを促進する作用を持つものとなるから、遺伝的な近親者の範囲を把握することができなくなり、子供の世代において意図せずに「近親交配」に至る確率が高くなる。そうなれば、婚姻制度が遺伝的な劣勢を有する個体が高い確率で発現することを防ごうとする意図を達成することができなくなるのであり、婚姻制度の立法目的の達成を阻害することになる。よって、「パートナーシップ証明制度」の内容が、「女性同士の組み合わせ」(『女性三人以上の組み合わせ』であっても同様)に対して婚姻制度と同様の、あるいは類似する優遇措置を与えることは、婚姻制度に抵触して違法となる。
さらに、「パートナーシップ証明制度」においても婚姻制度と同様の、あるいは類似した優遇措置を得られることを理由として、同性間の人的結合関係を結んで「パートナーシップ証明制度」を利用する者が増えた場合には、制度を利用していない男女の数の不均衡が生じることにより、「子を持ちたくても相手が見つからずに子を持つ機会に恵まれない者」が増えることに繋がる。これは、婚姻制度が「男女二人一組」の形に限定することによって、「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」を減らそうとする立法目的の達成を阻害するものとなるから、婚姻制度に抵触して違法となる。
さらに、「パートナーシップ証明制度」の中には、「性愛(性的指向)」という特定の思想や信条、感情を保護することを目的としているものがあり、このような目的をもって制度を立法することは憲法20条1項後段・3項、89条の「政教分離原則」に抵触して違憲となる。
他にも、ある特定の人的結合関係の間に生じる「性愛(性的指向)」のみを制度の対象とし、それ以外の人的結合関係の間に生じる「性愛(性的指向)」を制度の対象としていないことは、個々人の内心に基づいて区別取扱いをするものであるから、憲法19条の「思想良心の自由」に抵触して違憲となるし、そのような区別取扱いは、憲法14条の「平等原則」に抵触して違憲となる。
よって、このように「パートナーシップ証明制度」が民法上の婚姻制度や憲法上の規定に抵触するか否かの論点が存在するにもかかわらず、あたかも「パートナーシップ証明制度」が適法な制度であるかのような前提に基づいて「多数の地方公共団体においてパートナーシップ証明制度が導入され、利用され、広がりをみせている」などと、正当化できるかのように述べることは妥当でない。
「パートナーシップ証明制度」が法律に違反するか否かそのものが、婚姻制度の立法目的とそれを達成するための手段となる枠組みの当否の問題に直接的に関わっているにもかかわらず、これを論じずに「パートナーシップ証明制度」が適法に成立することができることを前提に話を進めている点で、十分な検討を行っているとはいえない。
詳しくは当サイト「パートナーシップ制度」で解説している。
「国において同性間の人的結合関係について婚姻に類する制度を構築することについて大きな障害となるような事由があることはうかがわれない。」との記載がある。
先ほども述べたように、婚姻制度の立法目的とその立法目的を達成するための手段は下記のように整理することができると考えられる。
〇 「子の福祉」が実現される社会基盤を構築すること
(→ 達成手段:嫡出子として生まれることの重視)
〇 遺伝的な劣勢を有する個体が高い確率で発現することを抑制すること
(→ 達成手段:父親と近親者を特定して『近親交配』を防ぐ仕組みを導入)
〇 「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」を減らすこと
(→ 達成手段:未婚の男女の数の不均衡の防止。一夫一婦制、複婚の禁止)
〇 母体を保護すること
(→ 達成手段:婚姻適齢)
次に、「同性間の人的結合関係」について「婚姻に類する制度」と称するものを構築した場合に、「障害となるような事由」があるか否かを検討する。
まず、婚姻制度は、「男性」と「女性」の間に「貞操義務」を設けることによって、その「女性」から生まれてくる子供の遺伝的な父親を特定することを重視するものとなってる。
これは、産まれてくる子供に対して、母親だけでなく、父親にも責任を担わせることによって、「子の福祉」の充実を期待するものとなっているからである。
子は何らの因果関係もなく突然「女性」の腹から生まれてくるわけではないため、その子が生じるという因果関係の一旦を担う父親に対してその子に対する責任を担わせる仕組みとすることは、逃れることのできない責任を有する者として合理的ということができるからである。
また、遺伝上の父親を特定できることは、遺伝上の近親者を把握することが可能となるため、その近親者との間で「婚姻」することができない仕組みを導入することで、「近親交配」に至ることを防止することが可能となる。
これによって、産まれてくる子供に潜性遺伝子が発現することを抑えることが可能となり、産まれてくる子に遺伝上の障害が生じるリスクを減らすこともできるからである。
他にも、婚姻制度の枠組みが「男女二人一組」となっていることは、その社会の中に男女がほぼ同数生まれているという前提の下では、未婚の男女の数に不均衡が生じることはないため、より多くの者に「子を持つ機会」を確保することを可能とするものとなっている。
その他、婚姻制度のもつ子供の遺伝上の父親を特定することができる形での「生殖」を推進する仕組みからは、婚姻制度を利用する形で子供を妊娠し、出産することを期待する(インセンティブを与える)ものとなっているが、その妊娠、出産に関して母体の保護の観点からリスクのある状態を推奨することはできないし、親となる者が低年齢のままに子を持つという責任を担う立場に置かれることを推進することも望ましくないことから、婚姻制度の利用に対して「婚姻適齢」という形で一定の年齢制限を設けるものとなっている。
これらの意図を満たす形で「男女二人一組」という枠組みを設定し、その婚姻制度の枠組みに従う者に対して、一定の優遇措置を講じることによって、婚姻制度の利用者を増やし、その立法目的を達成することを目指すものとなっている。
ここで、もし「同性間の人的結合関係」に対して、「婚姻に類する制度」と称するものを設けた場合には、これらの婚姻制度の立法目的の実現を阻害し、婚姻制度の政策効果を弱めることに繋がることが考えられる。
具体的には、「同性間の人的結合関係」に対して「婚姻」と同様、あるいは類似の法的効果や優遇措置を与えた場合には、「同性間の人的結合関係」(女性同士)を形成して子供を産む状態を推進する作用が生じ、遺伝上の父親を特定することができない状態で子供を産むことを促進することに繋がる。
これは、子供にとって遺伝上の父親を特定することができない状態となることから、「子の福祉」の充実に沿わないことが考えられる。
また、遺伝上の父親を特定することができないことによって、近親者の範囲を把握することができなくなるため、近親者の範囲を把握することを前提とした上で、その近親者との間では「婚姻」することができない仕組みとすることにより、「近親交配」に至ることを未然に防ぐ仕組みとすることができなくなったり、その仕組みを設けているつもりでも十分に機能しなくなることを意味する。
すると、婚姻制度を利用した場合には「近親交配」となることを回避することができるはずであるとの前提が成り立たなくなり、婚姻制度を利用したとしても「近親交配」に至ることを十分に防止することができなくなるため、婚姻制度に対する人々の信頼性を失わせることに繋がる。(制度そのものの価値を損なわせることに繋がる。)
また、実際に「近親交配」に至ってしまった場合には、子供は潜性遺伝子が発現するリスクが高くなり、遺伝上の障害を抱えやすくなる。
さらに、「男女二人一組」の婚姻制度と同様、あるいは類似の法的効果や優遇措置を「同性間の人的結合関係」に対して与えた場合には、「同性間の人的結合関係」を形成する者が増えることが考えられる。
すると、その社会の中で未婚の男女の数(制度を利用しない男女の数)に不均衡が生じることに繋がることから、その社会環境が未婚の男女(制度を利用しない男女)にとって「子を持つ機会」の公平性が保たれなくなることを意味する。
そのような社会の中で生活することを強いることになることは、「公共の福祉」の観点からも障害となると考えられる。
他にも、憲法24条の「婚姻」の文言は、「生殖と子の養育」に関わる制度を一元的に集約して規律する趣旨を有しているのであり、もし「生殖と子の養育」に関わる制度を24条の「婚姻」を離れて別の制度として立法した場合には、24条の「婚姻」の文言に抵触して違憲となる。
なぜならば、憲法24条が「婚姻」の内容に対して立法裁量の限界を画することによって、法律上の「婚姻」の制度を規律しているにもかかわらず、その憲法24条の制約を回避する形で制度を立法することができることになれば、憲法24条の規定そのものが有する効力が損なわれた状態となり、24条の規定が骨抜きとなるからである。
よって、「婚姻」が「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として、「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた枠組みである以上は、その「生殖と子の養育」に関わる制度については、24条の「婚姻」の文言が一元的に集約して規律する趣旨を有しており、これを離れて「生殖と子の養育」に関わる制度を立法することはできない。
そのため、ここでいう「同性間の人的結合関係」について制度を設けた場合に、その内容が「生殖と子の養育」に関わる制度となっている場合や、「生殖と子の養育」に影響を与えることが考えられる制度となっている場合には、そのこと自体で憲法24条の「婚姻」に抵触して違憲となる。
これらのことから、上記のような問題点を何ら検討することもなく「国において同性間の人的結合関係について婚姻に類する制度を構築することについて大きな障害となるような事由があることはうかがわれない」などと、「障害となるような事由」が見当たらないような説明をすることは、婚姻制度の立法目的とその立法目的を達成するための手段となっている枠組みとの整合性や、婚姻制度の有している機能、果たしている役割を理解していないものであり、妥当でない。
「上記のような制度を構築することは、その同性間の人的結合関係を強め、その中で養育される子も含めた共同生活の安定に資するものであり、これは、社会的基盤を強化させ、異性愛者も含めた社会全体の安定につながるものということもできる。」との記載がある。
「上記のような制度を構築すること」の部分であるが、これは「同性間の婚姻制度」や「
同性間の人的結合関係について婚姻に類する制度」と称しているものを指していると考えられる。
「その同性間の人的結合関係を強め、その中で養育される子も含めた共同生活の安定に資するものであり、」との記載がある。
まず、婚姻制度が「男女二人一組」の枠組みを定めていることは、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成するための手段として妥当な内容だからである。
婚姻制度の立法目的には、下記を挙げることができる。
〇 「子の福祉」が実現される社会基盤を構築すること
〇 遺伝的な劣勢を有する個体が高い確率で発現することを抑制すること
〇 「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」を減らすこと
〇 母体を保護すること
上記、最初に記載している「『子の福祉』が実現される社会基盤を構築すること」については、子供が産まれた場合に、何らの制度も設けずに放置するような社会よりも、子供が産まれた場合にその原因となった者にその子供の養育について責任を担わせる社会を選択するという意味や、子の遺伝上の父親を特定することができる関係とすること、遺伝上の父親を特定できることによって近親者を把握して「近親交配」に至ることを防ぐ仕組みを持つ制度であること、生活する上で次世代の者が子を持ちたいとの望んだ場合に「子を持つ機会」を公平に得られる社会となっていること、低年齢での妊娠・出産のリスクを減らせる社会となっていることなども含まれている。
これは、単に子の養育者を増やせばよいという意味ではなく、社会的な制度が「生殖」という人間の世代を渡る生命活動の連鎖を適切にサポートし、安定的で持続可能な形にとどまるような仕組みとなっていることを求める意味が含まれている。
そして、これらの目的を達成するためには、下記の要素を満たす人的結合関係を制度とし、法的効果や一定の優遇措置を設定することが必要となる。
・ 子の遺伝的な父親を特定できる組み合わせとすること
・ 特定された子の父親にも子に対する責任を担わせること
・ 特定された子の父親を基に遺伝的な近親者を把握すること
・ 未婚の男女の数の不均衡を防止できる組み合わせに限定すること
(・ 一定の年齢に達していること)
婚姻制度の枠組みが「男女二人一組」となっていることは、このような立法目的を達成するための手段として整合的だからである。
そして、これらの要素を満たす人的結合関係に対して、法的効果や一定の優遇措置を与える仕組みとなっている。
これは、それらの法的効果や一定の優遇措置を与えることが、立法目的を達成することに資するからである。
このことからは、法的効果の内容や一定の優遇措置を与えることは、これらの立法目的を達成するための手段として整合的な範囲でのみ正当化されるものであることから、その目的との整合性の観点から不必要に過大なものであった場合には、「婚姻制度を利用していない者(独身者)」との間で憲法14条の「平等原則」に違反することになる。
婚姻制度の法的効果や一定の優遇措置の内容が、この段落で取り上げているような「養育される子も含めた共同生活の安定に資するもの」が含まれているとしても、それは、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという立法目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす人的結合関係に対してのみ与えられるものであり、これらの要素を満たさない人的結合関係に対しては与えることはできないものである。
もしこれらの要素を満たさない人的結合関係に対して婚姻制度と同様、あるいは類似の法的効果や優遇措置を与えた場合には、婚姻制度が一定の枠組みを定め、その枠組みを利用する者を増やすことによって立法目的の実現を目指す仕組みとなっているにもかかわらず、その機能を阻害することになるからである。
よって、婚姻制度の内容に「養育される子も含めた共同生活の安定に資するもの」が含まれているとしても、それはこれらの要素を満たす人的結合関係に対してのみ与えることに意義があるのであり、これらの要素を満たさない人的結合関係に対して与えることはできない。
この判決は「その同性間の人的結合関係を強め、その中で養育される子も含めた共同生活の安定に資するものであり、」と述べて、「同性間の人的結合関係」を「強め」ることや、「共同生活の安定」についての制度を提案するものとなっている。
しかし、そもそも婚姻制度は人的結合関係を「強め」ることや「共同生活の安定」を目的として立法された制度ではない。
婚姻制度は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的とした制度である。
婚姻制度の内容にここでいうような人的結合関係を「強め」る効果や「共同生活の安定」に関わる内容があるとしても、それは「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成するための手段として設けられているものである。
そのため、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす人的結合関係に対してのみ人的結合関係を「強め」ることや「共同生活の安定」に関わる内容を設けているものであり、その要素を満たさない人的結合関係に対してはそのような法的効果や優遇措置は与えることはできないものである。
この判決は、婚姻制度が立法目的を達成するための「手段」として設けている法的効果や優遇措置の部分だけを見て、それがあたかも婚姻制度の「目的」であるかのように誤解して、婚姻制度の枠組みを超える人的結合関係に対しても同様、あるいは類似の法的効果や優遇措置を与えることができると考えて、「同性間の人的結合関係」にも同様、あるいは類似の法的効果や優遇措置を与えることを提案するものとなっているが、婚姻制度の目的に対する理解を誤っているため、妥当でない。
「社会的基盤を強化させ、」や「社会全体の安定につながる」との部分であるが、「同性間の人的結合関係」について、「婚姻」と同様、あるいは類似の法的効果や優遇措置を与えた場合には、婚姻制度の政策効果を阻害することが考えられる。
例えば、
・ 遺伝上の父親を特定することができない状態で子を産むことを推進することになる。
・ 遺伝上の父親を特定することができないため、近親者の範囲を把握することができなくなり、婚姻制度が近親婚を認めないことによって「近親交配」に至ることを防ごうとする仕組みが機能しなくなる。
・ 「近親交配」に至った場合に、子は潜性遺伝子が発現しやすくなり、身体障害などを抱えやすくなる。
・ 未婚の男女や制度を利用していない男女の数の不均衡が生じた社会の中で生活することとなり、子を持ちたいと望んでも、「子を持つ機会」を公平には得られない社会となる。
婚姻制度は「生殖」に関わって生じる上記のような問題が生じることを防ごうとするものとなっているが、このような政策効果を阻害することになる制度を設けることは、「社会的基盤を強化させ、」ることや「社会全体の安定」には繋がらず、むしろ「社会的基盤」を弱体化させ「社会全体」を不安定化させることに繋がると考えられる。
そのため、この点の整合性を検討することもなく、「社会的基盤を強化させ、」や「社会全体の安定につながる」などと、一方の意見のみを支持することを明言することは、特定の政治的な主張に肩入れするものとなっており、裁判所の中立性を損なうものとなっている。
他にも、この判決では後に「以上の点を総合的に考慮すると、」、「憲法24条2項に違反する状態にある」として憲法違反を述べるのであるが、そもそも憲法上の規範の意味を捉えた上で、具体的な法律上の規定がその規範に当てはまるか否かを判断することによって、憲法に違反するか否かを検討するのではなく、「社会的基盤を強化させ、」や「社会全体の安定につながる」と考えるから、憲法に違反するなどと述べるものとなっている。
これは、政治的な判断を行って、メリットがあるか否かを論じるものに過ぎず、憲法上の規範の意味を法解釈として解き明かすものとはいえないことから、裁判官が特定の結論を導きたいがために行った恣意的な判断ではないことを示すものとはいえないことになる。
政策的な判断によって憲法上の規範が揺らぐような形で論じることは不適切である。
「同性間の人的結合関係を強め、」の部分であるが、「同性間」という「二人一組」のみを取り上げて、それ以外の組み合わせについて論じないことは、なぜ「二人一組」であるのかその根拠を説明しないままに論じる「カップル信仰論」となっているものである。
「同性間の人的結合関係」のみを論じることは、他の組み合わせとの間で公平性を保てないという観点からも、妥当であるとはいえない。
「異性愛者も含めた」との部分であるが、ここで「異性愛者」を持ち出している背景には、前提として人はほぼすべて「異性愛者」と「同性愛者」に二分できるはずであるとの前提によって考えているように見受けられる。
しかし、「性愛」の思想、信条、信仰、感情には、他にも 「両性愛者」「全性愛者」「近親性愛者」「多性愛者」「小児性愛者」「老人性愛者」「死体性愛者」「動物性愛者」「対物性愛者」「対二次元性愛者」「無性愛者」など様々な分類が議論されているし、これらは明確に区別して割り切ることのできる性質のものではないし、複数の心理を同時に有していると称する者もいる。
また、「性愛」の思想、信条、信仰、感情があれば、「友愛」、「友情」などの思想、信条、信仰、感情もあるし、「愛」の感情があれば「嫌悪」、「憎悪」の思想、信条、信仰、感情もあるのであり、「性愛」の思想、信条、信仰、感情のみを殊更に取り上げることが正当化されるという性質のものでもない。
「愛」の感情と「憎しみ」の感情を明確に区別できるものではないし、「愛」の感情が「憎しみ」に変わることもあれば、反対に「憎しみ」の感情が「愛」の感情に変わることもある。
そのため、これらの心理的、精神的なものは、すべて「内心の自由」として捉えられるものであり、法律論としてその心理的、精神的なものを基準として個々人を区別することができるということにはならない。
そのため、「異性愛者も含めた」などと、人類が「同性愛者」と称する者と「異性愛者」と称する者に二分できるかのような考えの下に論じていることが誤りであるし、そもそも個々人を個々人の抱く心理的なものや精神的なものを取り上げて区別して取扱うことができると考えていること自体が誤りである。
また、「異性愛者も含めた」との部分は、「男女二人一組」の婚姻制度を利用している者が「異性愛者」であるとの前提の下に論じているように見受けられるが、婚姻制度は「性愛」の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有するとした場合にどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いを行うものではないし、「性愛」に基づいて「婚姻」することを求めるものでも勧めるものでもないことから、婚姻制度を利用している者が「異性愛者」であると考えていることも誤りである。
このような推測は、「男女二人一組」の婚姻制度を利用している者はすべて「キリスト教徒」であると考えることが誤りであることと同様の誤った推測である。
(エ) 他方で、同性間において、パートナーと家族になるための法制度をどのように構築するかという点については、原告らが主張するように現行の婚姻制度に同性間の婚姻も含める方法のほか、諸外国で導入されている制度(前記認定事実(3)ア)のように、現行の婚姻制度とは別に同性間でも利用可能な婚姻に類する制度を構築し、そのパートナーには婚姻における配偶者と同様の法的保護を与えることも考えられる。
【筆者】
「同性間において、パートナーと家族になるための法制度をどのように構築するかという点については、」との記載がある。
ここでいう「家族」の意味が、社会学的な意味の「家族」である場合には、「同性間」で人的結合関係を形成することについて、憲法21条1項の「結社の自由」によって保障されることになる。
これはここで「パートナー」として「二人一組」のみを取り上げているが、「三人一組」や「四人一組」、それ以上の組み合わせにおいても同様である。
これに対して、法学的な意味の「家族」については、上記の「結社の自由」で保障される他の様々な人的結合関係とは、「生殖と子の養育」の観点から区別する意味で設けられた「婚姻」と、その「婚姻」との整合性を保つ形で「夫婦」や「親子」の関係を基本として定められるものである。
その範囲は憲法24条2項の「婚姻及び家族」における立法目的とその立法目的を達成するための手段となる枠組みとして定められているものであることから、どのような人的結合関係でも「婚姻及び家族」の中に含めることができるというものであるわけではなく、「婚姻及び家族」であることそれ自体によって内在的な限界がある。
「婚姻」は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するための制度であり、下記の立法目的を有していると考えられる。
〇 「子の福祉」が実現される社会基盤を構築すること
〇 遺伝的な劣勢を有する個体が高い確率で発現することを抑制すること
〇 「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」を減らすこと
〇 母体を保護すること
そして、これらの目的を達成するための手段として整合的な下記の要素を満たす人的結合関係が「婚姻」とすることのできる範囲であると考えられる。
・ 子の遺伝的な父親を特定できる組み合わせとすること
・ 特定された子の父親にも子に対する責任を担わせること
・ 特定された子の父親を基に遺伝的な近親者を把握すること
・ 未婚の男女の数の不均衡を防止できる組み合わせに限定すること
「同性間」の人的結合関係については、これらの要素を満たさないため、「婚姻」という概念そのものが有している目的との整合性の観点から「婚姻」とすることはできない。
そして、憲法24条2項の「婚姻及び家族」と定められている「家族」とは、法学的な意味の「家族」であり、この「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するための「婚姻」という枠組みと整合的に形成されるものであることから、これらの「婚姻」における「夫婦」の関係と、「親子」の関係を基本として骨格が定められるものである。
「同性間」の人的結合関係については、「婚姻」ではないし、「親子」や、その「親子」の関係を基に生じる「兄弟」「姉妹」などに含まれないのであれば、法学的な意味の「家族」とも言えない。
ここで検討されている「同性間」の人的結合関係についての「法制度」であるが、それが「契約」によるものや「組合」、「会社」、「宗教団体」、「学校」、「政党」などであれば、「法制度」は既に存在するため、それらの「法制度」を利用することが可能である。
これは「同性間」の人的結合関係に限らるものではなく、「異性間」の人的結合関係においても、「三人一組」や「四人一組」、「五人一組」、それ以上の組み合わせにおいても同様である。
「同性間」の人的結合関係についての「法制度」の内容が、この判決のいう「婚姻に類する制度」と称するものであれば、「婚姻」の立法目的との関係で問題が生じると考えられる。
そのため、婚姻制度の立法目的と、その立法目的を達成するための手段について詳しく検討する。
婚姻制度は、下記の立法目的と、その立法目的を達成するための手段として枠組みが定められる考えられる。
〇 「子の福祉」が実現される社会基盤を構築すること
(→ 達成手段:嫡出子として生まれることの重視)
〇 遺伝的な劣勢を有する個体が高い確率で発現することを抑制すること
(→ 達成手段:父親と近親者を特定して『近親交配』を防ぐ仕組みを導入)
〇 「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」を減らすこと
(→ 達成手段:未婚の男女の数の不均衡の防止。一夫一婦制、複婚の禁止)
〇 母体を保護すること
(→ 達成手段:婚姻適齢)
まず、婚姻制度は、「男性」と「女性」の間に「貞操義務」を設けることによって、その「女性」から生まれてくる子供の遺伝的な父親を特定することを重視するものとなってる。
これは、産まれてくる子供に対して、母親だけでなく、父親にも責任を担わせることによって、「子の福祉」の充実を期待するものとなっているからである。
子は何らの因果関係もなく突然「女性」の腹から生まれてくるわけではないため、その子が生じるという因果関係の一旦を担う父親に対してその子に対する責任を担わせる仕組みとすることは、逃れることのできない責任を有する者として合理的ということができるからである。
また、遺伝上の父親を特定できることは、遺伝上の近親者を把握することが可能となるため、その近親者との間で「婚姻」することができない仕組みを導入することで、「近親交配」に至ることを防止することが可能となる。
これによって、産まれてくる子供に潜性遺伝子が発現することを抑えることが可能となり、産まれてくる子に遺伝上の障害が生じるリスクを減らすこともできるからである。
他にも、婚姻制度の枠組みが「男女二人一組」となっていることは、その社会の中に男女がほぼ同数生まれているという前提の下では、未婚の男女の数に不均衡が生じることはないため、より多くの者に「子を持つ機会」を確保することを可能とするものとなっている。
その他、婚姻制度のもつ子供の遺伝上の父親を特定することができる形での「生殖」を推進する仕組みからは、婚姻制度を利用する形で子供を妊娠し、出産することを期待する(インセンティブを与える)ものとなっているが、その妊娠、出産に関して母体の保護の観点からリスクのある状態を推奨することはできないし、親となる者が低年齢のままに子を持つという責任を担う立場に置かれることを推進することも望ましくないことから、婚姻制度の利用に対して「婚姻適齢」という形で一定の年齢制限を設けるものとなっている。
これらの意図を満たす形で「男女二人一組」という枠組みを設定し、その婚姻制度の枠組みに従う者に対して、一定の優遇措置を講じることによって、婚姻制度の利用者を増やし、その立法目的を達成することを目指すものとなっている。
婚姻制度を設けている以上は、婚姻制度の立法目的を達成することを阻害するような影響を与えるような制度を別に創設することはできない。
もしそれをした場合には、婚姻制度の立法目的を達成することができなくなり、婚姻制度を設けている意味がなくなるからである。
「同性間」の人的結合関係に対して、「婚姻に類する制度」と称するものを設けた場合には、これらの婚姻制度の立法目的の実現を阻害し、婚姻制度の政策効果を弱めることに繋がることが考えられる。
具体的には、「同性間」の人的結合関係に対して「婚姻」と同様、あるいは類似の法的効果や優遇措置を与えた場合には、「同性間」の人的結合関係(女性同士)を形成して子供を産む状態を推進する作用が生じ、遺伝上の父親を特定することができない状態で子供を産むことを促進することに繋がる。
これは、子供にとって遺伝上の父親を特定することができない状態となることから、「子の福祉」の充実に沿わないことが考えられる。
また、遺伝上の父親を特定することができないことによって、近親者の範囲を把握することができなくなるため、近親者の範囲を把握することを前提とした上で、その近親者との間では「婚姻」することができない仕組みとすることにより、「近親交配」に至ることを未然に防ぐ仕組みとすることができなくなったり、その仕組みを設けているつもりでも十分に機能しなくなることを意味する。
すると、婚姻制度を利用した場合には「近親交配」となることを回避することができるはずであるとの前提が成り立たなくなり、婚姻制度を利用したとしても「近親交配」に至ることを十分に防止することができなくなるため、婚姻制度に対する人々の信頼性を失わせることに繋がる。(制度そのものの価値を損なわせることに繋がる。)
また、実際に「近親交配」に至ってしまった場合には、子供は潜性遺伝子が発現するリスクが高くなり、遺伝上の障害を抱えやすくなる。
さらに、「男女二人一組」の婚姻制度と同様、あるいは類似の法的効果や優遇措置を「同性間の人的結合関係」に対して与えた場合には、「同性間」の人的結合関係を形成する者が増えることが考えられる。
すると、その社会の中で未婚の男女の数(制度を利用しない男女の数)に不均衡が生じることに繋がることから、その社会環境が未婚の男女(制度を利用しない男女の数)にとって「子を持つ機会」の公平性が保たれなくなることを意味する。
そのような社会の中で生活することを強いることになることは、「公共の福祉」の観点からも障害となると考えられる。
他にも、憲法24条の「婚姻」の文言は、「生殖と子の養育」に関わる制度を一元的に集約して規律する趣旨を有しているのであり、もし「生殖と子の養育」に関わる制度を24条の「婚姻」を離れて別の制度として立法した場合には、24条の「婚姻」の文言に抵触して違憲となる。
なぜならば、憲法24条が「婚姻」の内容に対して立法裁量の限界を画することによって、法律上の「婚姻」の制度を規律しているにもかかわらず、その憲法24条の制約を回避する形で制度を立法することができることになれば、憲法24条の規定そのものが有する効力が損なわれた状態となり、24条の規定が骨抜きとなるからである。
よって、「婚姻」が「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として、「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた枠組みである以上は、その「生殖と子の養育」に関わる制度については、24条の「婚姻」の文言が一元的に集約して規律する趣旨を有しており、これを離れて「生殖と子の養育」に関わる制度を立法することはできない。
よって、ここでいう「同性間」の人的結合関係について制度を設けた場合に、その内容が「生殖と子の養育」に関わる制度となっている場合や、「生殖と子の養育」に影響を与えることが考えられる制度となっている場合には、そのこと自体で憲法24条の「婚姻」に抵触して違憲となる。
よって、これらの検討をしないままに、「法制度をどのように構築するかという点については、」などと、「同性間」の人的結合関係についての「法制度」を新たに立法することができることを前提として論じていることは妥当でない。
また、この判決は「同性間」のように「二人一組」を前提とするものとなっているが、人的結合関係の中には「三人一組」や「四人一組」、それ以上の組み合わせなど様々な形があるのであって、それらについても何ら検討することもなく、「二人一組」のみを説明していることは、なぜ「二人一組」であるのかその根拠を説明しないままに論じる「カップル信仰論」に陥っているものである。
「現行の婚姻制度に同性間の婚姻も含める方法のほか、」との記載がある。
しかし、「婚姻」は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度であり、「婚姻」という概念から「生殖と子の養育」の趣旨を切り離して考えることはできない。
「同性間」については、その間で「生殖」を想定することができないことから、「生殖と子の養育」の趣旨を満たすとはいえず、「婚姻」とすることはできない。
そのため、「同性間の婚姻」のように、「同性間」の人的結合関係を「婚姻」とすることができるかのような前提で論じていることは、誤っていると考えられる。
また、「現行の婚姻制度に同性間の婚姻も含める方法」のように、「婚姻」である「現行の婚姻制度」の中に「同性間」の人的結合関係を含めることができるかのように論じていることも誤っていると考えられる。
「諸外国で導入されている制度……(略)……のように、現行の婚姻制度とは別に同性間でも利用可能な婚姻に類する制度を構築し、そのパートナーには婚姻における配偶者と同様の法的保護を与えることも考えられる。」との記載がある。
「諸外国」の法制度は、その「諸外国」の社会事情の中で発生している不都合を解消することを目的として、その目的を達成するための手段として設けられたものである。
そのため、「諸外国」の「現行の婚姻制度」と称している法制度については、外国語を翻訳する際に翻訳者が「婚姻制度」と翻訳しているからといって、日本国の「婚姻」と同一の制度を指していることにはならない。
それぞれの国の制度は、それぞれの国の社会事情の中で、その中で生じる問題を解消することを目的としたものであり、その目的や手段には様々な違いがあるからである。
「諸外国」の法制度と比較して論じる際には、このような違いを押さえて考える必要がある。
また、この判決では「諸外国」の「同性間」やここでいう「パートナー」という言葉による「二人一組」の人的結合関係における法制度のみを取り上げて論じるものとなっているが、「諸外国」の中には「男性一人」と「女性四人まで」の「一夫多妻型」の人的結合関係における法制度を有している国もあるのであり、これらを一切取り上げることなく、「二人一組」の人的結合関係のみを比較対象として取り上げれば何らかの結論を導き出せるのではないかとの前提で論じている点で妥当でない。
「諸外国」の法制度と比較する際には、比較対象の選択が恣意的なものとなってはならない。
他にも、「諸外国」の中には「性愛」の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的とした法制度を定めているものが考えられるところ、日本国の法制度においては特定の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的とした法制度を立法した場合には、20条1項後段・3項、89条の「政教分離原則」に抵触して違憲となる。
そのため、この判決のいう「性的指向」の前提となる「性愛」を保護することを目的として婚姻制度を設けることもできないことに注意する必要がある。
「諸外国」の法制度との間で比較する際には、このような点も押さえる必要がある。
「同性間でも利用可能な婚姻に類する制度を構築し、そのパートナーには婚姻における配偶者と同様の法的保護を与えること」であるが、この段落の始めの部分で述べたように、「同性間」の人的結合関係に対して「婚姻に類する制度」を設けること、「婚姻における配偶者と同様の法的保護を与えること」は、婚姻制度の立法目的の達成を阻害することになると考えられる。
また、憲法24条の「婚姻」は「生殖と子の養育」に関わる制度を一元的に集約して規律する趣旨を有していることから、それらの制度が「生殖と子の養育」に影響を与えるものとなっている場合には、憲法24条の「婚姻」に抵触して違憲となる。
また、前記認定事実(3)イ(ウ)のとおり、同性間の婚姻を認める外国の立法例においても、異性間の「婚姻」と同性間の「婚姻」の法的効果に相違がある場合(又は、導入当初は相違があった場合)があり、その主なものとして嫡出推定規定の適用の有無、養子縁組の可否、生殖補助医療利用の可否等が挙げられることが認められる。我が国においても、同性間の人的結合関係についてパートナーと家族になるための法制度を導入する場合に上記のような点についていかなる制度とすべきかについては、国の伝統や国民感情を含めた社会状況における種々の要因を踏まえつつ、また、子の福祉等にも配慮した上で、立法府において十分に議論、検討がされるべきであるということができる。
【筆者】
「同性間の婚姻を認める外国の立法例においても、異性間の「婚姻」と同性間の「婚姻」の法的効果に相違がある場合(又は、導入当初は相違があった場合)があり、その主なものとして嫡出推定規定の適用の有無、養子縁組の可否、生殖補助医療利用の可否等が挙げられることが認められる。」との記載がある。
「外国」の法制度は、その「外国」の社会事情の中で生じる不都合を解消することを目的として、その目的を達成するための手段として設けられたものである。
そのため、外国語を翻訳する者が「婚姻」という言葉を使って翻訳しているからといって、日本国の「婚姻」と同一の制度を指していることにはならない。
そもそも社会事情が異なれば、その中で生じる不都合も異なっており、それを解消するための立法目的も違えば、立法目的を達成するための手段となる枠組みも異なるからである。
そのため、「外国」で「同性間」の人的結合関係について定めた法制度が存在するとしても、それを日本国の法制度における「婚姻」の中に当てはめて考えることができるという性質のものではない。
この判決のこの段落では、「外国」の法制度の「同性間」の人的結合関係について、日本国の「婚姻」の中に当てはめて考えることができるとする前提の下に、個別の「法的効果」の相違を「十分に議論、検討がされるべきである」と述べているが、それ以前に、そもそも日本法の「婚姻」の中に「同性間」の人的結合関係を含めることができるか否かから検討することが必要である。
また、日本法における婚姻制度の立法目的とその立法目的を達成するための手段となる枠組みとの整合性の観点から、「同性間」の人的結合関係に対しては、何らの法制度も創設しないことが妥当であるとの結論に至ることもある。
よって、「同性間」の人的結合関係に対する法制度の創設をするべきであるとの結論を先取りする形で、「同性間」の人的結合関係の法制度の「法的効果」について「議論、検討がされるべき」と述べることも妥当でない。
ここでは「同性間」や「異性間」と述べて、「外国の立法例」の中でも「二人一組」の人的結合関係のみを取り上げるのであるが、外国の法制度の中には「男性一人と女性四人まで」の「一夫多妻制」を設けている場合もあり、それを比較対象として取り上げないことは、裁判官が特定の結論を導き出すために比較対象を恣意的な形で選択していることが考えられる。
この点、なぜ「二人一組」であるのかその根拠を説明しないままに論じる「カップル信仰論」となっている。
「我が国においても、同性間の人的結合関係についてパートナーと家族になるための法制度を導入する場合に上記のような点についていかなる制度とすべきかについては、国の伝統や国民感情を含めた社会状況における種々の要因を踏まえつつ、また、子の福祉等にも配慮した上で、立法府において十分に議論、検討がされるべきであるということができる。」との記載がある。
「我が国においても、同性間の人的結合関係についてパートナーと家族になるための法制度を導入する場合に上記のような点についていかなる制度とすべきかについて」との部分は、既に「我が国」において「同性間の人的結合関係」についての「法制度」を「導入する」ことを前提として、「いかなる制度とすべきか」を論じるものとなっている。
しかし、この裁判の過程で議論となっているものは、婚姻制度の中に「同性間」の人的結合関係が含まれていないことが、憲法に違反するか否かであり、「同性間」の人的結合関係についての法制度を導入するべきか否かではない。
また、この判決が憲法に違反すると述べている部分は、次の段落の「(オ)」で初めて登場するのであり、その判断が示される前に、「我が国」において「同性間の人的結合関係」についての「法制度」を「導入する」という結論を述べることも、憲法上の規定の規範の意味を明らかにした上で現在の法制度が憲法に違反するか否かを判断する以前に、憲法上の規定に違反していると判断された場合に限って認められる「法制度」を「導入する」という結論を述べるものであるから、判断の過程では生じない結論が出た上での話をするものであることから、判断の過程を説明するものとしては妥当でなく、誤っている。
このような説明は、「法制度を導入するべきであるから違憲である」という形で、裁判官が「法制度を導入するべきである」との特定の政治的な立場を採った上で、それを正当化する材料として憲法上の規定を後追いで用いるものとなっている。
これは、憲法上の規定の規範の意味を明らかにした上で、現在の法制度がその規範に適合するか否かという過程を通った判断ではないことから、法解釈の手続きとして誤ったものである。
(オ) 以上の点を総合的に考慮すると、現行法上、同性愛者についてパートナーと家族になるための法制度が存在しないことは、同性愛者の人格的生存に対する重大な脅威、障害であり、個人の尊厳に照らして合理的な理由があるとはいえず、憲法24条2項に違反する状態にあるということができる。しかしながら、そのような法制度を構築する方法については多様なものが想定され、それは立法裁量に委ねられており、必ずしも本件諸規定が定める現行の婚姻制度に同性間の婚姻を含める方法に限られない(現行の婚姻制度とは一部異なる制度を同性間の人的結合関係へ適用する制度とする方法や、同性間でも利用可能な婚姻に類する制度を別途構築する方法を採ること等も可能である。)ことからすれば、同性間の婚姻を認めていない本件諸規定が憲法24条2項に違反すると断ずることはできない。
【筆者】
「現行法上、同性愛者についてパートナーと家族になるための法制度が存在しないことは、同性愛者の人格的生存に対する重大な脅威、障害であり、個人の尊厳に照らして合理的な理由があるとはいえず、憲法24条2項に違反する状態にあるということができる。」との記載がある。
「同性愛者についてパートナーと家族になるための法制度が存在しないことは、」との部分について検討する。
まず、婚姻制度は「性愛」の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いを行っている事実はないし、「性愛」に基づいて「婚姻」することを求めるものでも勧めるものでもない。
よって、「同性愛者」を称する者であるとしても、婚姻制度の枠組みに従う形で存在する選択肢の中で、なお婚姻制度を利用することを望んだ場合には、婚姻制度を利用することが可能である。
そのため「同性愛者」を称する者についても「家族になるための法制度」は存在するため、「同性愛者」と称する者について「家族になるための法制度が存在しない」と述べていることは誤りである。
これは「同性愛者」と称する者に限られず、「両性愛者」、「全性愛者」、「多性愛者」、「小児性愛者」、「老人性愛者」、「死体性愛者」、「動物性愛者」、「対物性愛者」、「対二次元性愛者」、「無性愛者」、「キリスト教徒」、「イスラム教」、「ユダヤ教徒」、「ゾロアスター教徒」、「仏教徒」、「神道を信じる者」、「武士道を重んじる者」、「軍事オタク」、「鉄道オタク」、「アニメオタク」、「アイドルオタク」、「ADHD」、「アスペルガー」、「自閉症」、「サイコパス」、「統合失調症」を称する者であっても同様である。
次に、ここでいう「家族」の意味を、社会学的な意味の「家族」と考えた場合についても、「同性愛者」と称する者が人的結合関係を形成することは憲法21条1項の「結社の自由」によって保障されていることから、この意味で「家族になる」ことは可能である。
これについても、「同性愛者」と称する者に限られず、「両性愛者」、「全性愛者」、「多性愛者」、「小児性愛者」、「老人性愛者」、「死体性愛者」、「動物性愛者」、「対物性愛者」、「対二次元性愛者」、「無性愛者」、「キリスト教徒」、「イスラム教」、「ユダヤ教徒」、「ゾロアスター教徒」、「仏教徒」、「神道を信じる者」、「武士道を重んじる者」、「軍事オタク」、「鉄道オタク」、「アニメオタク」、「アイドルオタク」、「ADHD」、「アスペルガー」、「自閉症」、「サイコパス」、「統合失調症」を称する者であっても同様である。
また、ここでは「パートナー」という「二人一組」の一方を指す言葉を用いて、「二人一組」を前提とするものとなっているが、「トリオ」を称する「三人一組」や、「四人一組」、「五人一組」、それ以上の人的結合関係においても同様である。
「法制度が存在しないこと」の部分について、憲法24条2項は「婚姻及び家族」の制度の創設を要請するものであるが、「婚姻及び家族」の範囲を超える人的結合関係についての法制度の創設を要請するものではない。
そのため、「婚姻及び家族」の範囲を超える人的結合関係についての法制度を創設を憲法24条2項から導き出すことはできないのであり、「婚姻及び家族」の範囲を超える人的結合関係に関する「法制度が存在しないこと」について、憲法24条2項に違反することにはならない。
よって、「婚姻及び家族」の範囲を超える人的結合関係に関する「法制度が存在しないこと」について、「憲法24条2項に違反する状態にある」と述べようとしているのであれば、誤りである。
「個人の尊厳に照らして合理的な理由があるとはいえず、」との部分であるが、「個人の尊厳」の文言は、憲法24条2項の示す「婚姻及び家族」に対して適用されるものであり、それ以外に対して適用されることはない。
そのため、「婚姻及び家族」の範囲を超える人的結合関係に関する「法制度」の創設を、この「個人の尊厳」を用いて求めることができることにはならない。
また、憲法24条2項の「個人の尊厳」は、学問上、憲法13条の「個人の尊重」と同一の趣旨とされていることから、憲法13条の「個人の尊厳」に違反するか否かという観点から検討するとしても、憲法13条の規定によって、特定の「法制度」の創設を国家に対して求めることができることにはならない。
「人格的生存に対する重大な脅威、障害であり、」との部分であるが、国家から個人に対して何らかの侵害行為がある場合において、その侵害行為を正当化する合理的な理由がない場合において、「国家からの自由」という「自由権」の側面からその侵害行為を排除する場合に、「人格的生存」の観点が説明されることは考えられる。
しかし、憲法24条2項の「婚姻及び家族」とは、憲法21条1項の「結社の自由」によって保障されている他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度であり、もともとその対象となる場合は制度を利用することができ、その対象とならない場合は制度を利用することができないとする差異が生じることは当然に予定されているし、その制度の対象とならない場合においても、単に優遇措置がないというだけであり、国家から個人に対して何らかの行為を制限したり、不利益を課すという性質のものでもない。
よって、国家から個人に対して何らかの行為を制限しているという事実はないため、「国家からの自由」という「自由権」によって排除しなければならないとする具体的な侵害そのものが存在しないのであり、「自由権」の性質を説明する中で使われることのある「人格的生存」の観点を検討する場面でもない。
そのため、「婚姻及び家族」の範囲を超える人的結合関係についての「法制度が存在しないこと」について、「人格的生存に対する重大な脅威、障害であり、」と述べることは、事柄の性質を捉え誤ったものであり、意味が通じていないと考えられる。
よって、この文は「憲法24条2項に違反する状態にあるということができる。」と結論を述べようとするが、その判断を導き出すための過程で、複数ヵ所の誤りがあり、その誤った認識に基づいて正当化しようとしているこの結論部分についても、誤っているということができる。
「以上の点を総合的に考慮すると、」の記載があるが、「以上の点」として述べられているものは、おおよそ下記のようにまとめることができる。
・ 「同性愛」への認識
・ 「諸外国」の法制度
・ 「地方公共団体」の「パートナーシップ証明制度」
・ 「民間企業」の例
・ 「世論調査の結果」
しかし、上記で解説したように、どれをとっても「同性間」の人的結合関係を「婚姻」とすることができるとする根拠にはならない。
また、憲法24条2項の「個人の尊厳」の文言は、「婚姻及び家族」の制度に対してのみ適用されるものであり、「婚姻及び家族」の制度の対象でない場合には、「個人の尊厳」の文言が適用されることにはならない。
「婚姻」は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度である。
憲法24条2項の「家族」についても、これは法学的な意味の「家族」であることから、どのような人的結合関係でも「家族」の中に含めることができることにはならず、「婚姻」における「夫婦」と、「親子」の関係を基本として骨格が定められるものである。
「同性間」の人的結合関係については、その間で「生殖」を想定することができないことから、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的との整合性において「婚姻」とすることはできないし、それが「親子」や「親子」の関係を軸とした「兄弟」「姉妹」などに含まれないのであれば、法学的な意味の「家族」とすることもできない。
このような憲法24条2項の「婚姻及び家族」の制度の枠組みの中に当てはまらない人的結合関係に対しては、憲法24条2項の「個人の尊厳」の文言は適用されないため、これが適用されることを根拠として「憲法24条2項に違反する状態にあるということができる。」と述べているのであれば、誤った判断である。
また、この「個人の尊厳」の意味は、学問上は憲法13条の「個人の尊重」と同義であるとされていることを根拠として、憲法13条に置き換えて考えたとしても、この「以上の点を総合的に考慮」したとしても、憲法13条の「個人の尊重」に抵触するとする理由となるもの(因果関係)は見当たらない。
他にも、憲法13条の「個人の尊重」によって、具体的な法制度の創設を国家に対して求めることもできない。
「しかしながら、そのような法制度を構築する方法については多様なものが想定され、それは立法裁量に委ねられており、必ずしも本件諸規定が定める現行の婚姻制度に同性間の婚姻を含める方法に限られない(……(略)……)ことからすれば、同性間の婚姻を認めていない本件諸規定が憲法24条2項に違反すると断ずることはできない。」との記載がある。
一文前で「憲法24条2項に違反する状態にあるということができる。」と述べた上で、ここで「そのような法制度を構築する方法については多様なものが想定され、」と述べている。
しかし、「憲法24条2項」は「婚姻及び家族」についての制度の創設を求めるものであるが、「婚姻及び家族」の範囲に含まれない人的結合関係についての「法制度」を構築することを求める規定ではない。
そのため、「婚姻及び家族」の範囲を超える人的結合関係についての「法制度」が存在しないことが「憲法24条2項」に違反するとはいえないし、「憲法24条2項」から「そのような法制度」と称するものを導き出すこともできない。
「それは立法裁量に委ねられており、」との部分であるが、「憲法24条2項」は「婚姻及び家族」の制度の創設を求めているだけであり、「婚姻及び家族」の範囲を超える人的結合関係についての「法制度」の創設を求めるものではないことから、あたかも「婚姻及び家族」の範囲を超える人的結合関係についての「法制度」を構築しなければ「憲法24条2項に違反する」ことを前提として、その内容について「立法裁量に委ねられており、」のように話を進めようとしている部分については、それ以前に「憲法24条2項」に違反しないという点で正当化できないものである。
「婚姻制度に同性間の婚姻を含める方法」との記載がある。
しかし、「婚姻」は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度であり、その目的との関係で「婚姻」の中に含めることができる人的結合関係の範囲には内在的な限界がある。
これは、もしどのような人的結合関係でも「婚姻」の中に含めることができることになれば、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成できない状態となり、「婚姻」という枠組みを設けている意味がなくなってしまうからである。
そのため、ここでは「同性間の婚姻」のように、「婚姻」の中に「同性間」の人的結合関係を含めることができるかのような前提の下に説明するものとなっているが、そもそも「同性間」の人的結合関係については、その間で「生殖」を想定することができないことから、「生殖と子の養育」の趣旨を満たすとはいえず、「婚姻」という概念の中に含まれない。
よって、この文は「婚姻制度に同性間の婚姻を含める」と記載されているが、「婚姻」の中に「同性間」の人的結合関係を含めることはできないし、その「婚姻」の制度である「婚姻制度」の部分についても「同性間」の人的結合関係を含めることはできない。
「(現行の婚姻制度とは一部異なる制度を同性間の人的結合関係へ適用する制度とする方法や、同性間でも利用可能な婚姻に類する制度を別途構築する方法を採ること等も可能である。)」との記載がある。
まず、「婚姻」は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために「生殖と子の養育」の観点から 他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度であり、「婚姻」という概念の中に含めることのできる人的結合関係の範囲には内在的な限界がある。
「同性間の人的結合関係」については、一般的・抽象的にその間で「生殖」を想定することができず、「生殖と子の養育」の趣旨を満たさないことから、「婚姻」とすることはできない。
よって、「現行の婚姻制度とは一部異なる制度」の部分について、婚姻制度の中に「同性間の人的結合関係」を含めることができると考えているのであれば、誤りとなる。
次に、「婚姻に類する制度」を立法することができるかであるが、婚姻制度の「立法目的」と「その立法目的を達成するための手段」となる枠組みとの関係を検討する必要がある。
婚姻制度の立法目的と、その立法目的の達成手段として下記を挙げることができる。
〇 「子の福祉」が実現される社会基盤を構築すること
(→ 達成手段:嫡出子として生まれることの重視)
〇 遺伝的な劣勢を有する個体が高い確率で発現することを抑制すること
(→ 達成手段:父親と近親者を特定して『近親交配』を防ぐ仕組みを導入)
〇 「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」を減らすこと
(→ 達成手段:未婚の男女の数の不均衡の防止。一夫一婦制、複婚の禁止)
〇 母体を保護すること
(→ 達成手段:婚姻適齢)
「同性間の人的結合関係」に対して「婚姻に類する制度」と称するものを設けた場合には、「同性間の人的結合関係」の制度を利用して子を産む者が増えることが考えられる。
すると、婚姻制度が遺伝上の父親を特定することのできる人的結合関係を制度とし、法的効果や一定の優遇措置を与えることによって、遺伝上の父親を特定することができることによる「子の福祉」の実現を目指そうとする仕組みが阻害されることになる。
また、遺伝上の父親を特定することができない状態を推進することになることから、婚姻制度が婚姻制度を利用することによって遺伝上の父親を特定することによって近親者を特定し、その近親者との「婚姻」を認めないことによって「近親交配」に至ることをを防ごうとする仕組みが阻害されることになる。
さらに、何らの制度も利用していない男女の数に不均衡が生じることから、「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」が増えることが考えられる。
そのため、「同性間の人的結合関係」に対して「婚姻に類する制度」と称するものを設けることは、婚姻制度の機能を阻害することに繋がることから、妥当でないと考えられる。
ここで「婚姻に類する制度」と称していることについても、ここに「婚姻に類する」と書かれているように「婚姻」の枠組みを前提とする制度なのであって、その「婚姻」の立法目的の達成を阻害することはできないことが前提となるものである。
そのため、そもそも「婚姻」との関係で、「婚姻に類する制度」と称するものは立法することはできないと考えられる。
他にも、憲法24条の「婚姻」の文言は、「生殖と子の養育」に関わる制度を一元的に集約して規律する趣旨を有しており、24条の「婚姻」を離れて別の制度として「生殖と子の養育」に関わる制度を立法することはできない。
そのため、「婚姻に類する制度」などと称する何らかの制度が、「生殖」や「子の養育」に関わるものとなっていたり、影響を与えるものとなっている場合には、憲法24条の「婚姻」に抵触して違憲となる。
さらに、ここでは「同性間の人的結合関係へ適用する」や「同性間でも利用可能な」のように、「同性間」という文言を使い、「二人一組」を前提とするものとなっているが、婚姻制度のような「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的との関係で、一般的・抽象的にその間で「生殖」を想定することができる「男性」と「女性」の組み合わせとは異なるものであることから、そのような目的を有しない「二人一組」の間に何らかの制度を設けることは、「三人一組」や「四人一組」などの他の様々な人的結合関係との間で異なる取扱いをすることを正当化することのできる理由はないし、何らの制度も利用していない者との間でも、その差異を正当化することはできない。
そのため、「二人一組」の人的結合関係のみを制度の対象とすることについても、憲法14条の「平等原則」に抵触して違憲となる。
ここでは「同性間の人的結合関係へ適用する」や「同性間でも利用可能な」のように、「同性間」という文言を使い、「二人一組」を前提とするものとなっているが、なぜ「二人一組」であるのか、その根拠を説明しないままに論じる「カップル信仰論」に陥っているものである。
この段落は二つの文で構成されているが、文の順番を入れ替えると分かりやすくなる。
◇ 「同性間の婚姻を認めていない本件諸規定が憲法24条2項に違反すると断ずることはできない。」
◇ 「現行法上、同性愛者についてパートナーと家族になるための法制度が存在しないことは、……(略)……憲法24条2項に違反する状態にある」
しかし、「同性間の婚姻」の部分については、そもそも「婚姻」という概念に含めることのできる人的結合関係の範囲には内在的な限界があり、「同性間」の人的結合関係を「婚姻」とすることはできない。
このことを前提に考えた場合でも、この判決と同様の「本件諸規定が憲法24条2項に違反すると断ずることはできない。」との結論が導き出されることになるが、判断の過程の部分に相違がある。
また、「憲法24条2項」は「婚姻及び家族」の範囲を超える人的結合関係についての「法制度」の創設を求めるものではないことから、「婚姻及び家族」の範囲を超える人的結合関係についての「法制度」が「存在しないこと」について「憲法24条2項に違反する状態にある」と述べている部分も誤りである。
カ (ア) 以上に対し、原告らは、同性間の婚姻を認めていない本件諸規定は、同性カップルは異性カップルと何ら異なるところのない共同生活を営んでいるにもかかわらず同性カップルを婚姻から排除しており、その存在自体、同性愛者等に対する社会的な差別・偏見を助長させ、社会を分断するものであるから、本件諸規定は憲法24条2項に違反する旨主張する。
【筆者】
「同性間の婚姻を認めていない本件諸規定は、同性カップルは異性カップルと何ら異なるところのない共同生活を営んでいるにもかかわらず同性カップルを婚姻から排除しており、」との記載がある。
まず、「共同生活を営んでいる」ことについては、憲法21条1項の「結社の自由」によって保障されている。
これについては、ここでいう「同性カップル」という「同性間」の人的結合関係についても、ここでいう「異性カップル」という「異性間」の人的結合関係についても同様である。
また、「共同生活を営んでいる」ことについては、「二人一組」の人的結合関係に限られるものではなく、「三人一組」や「四人一組」、「五人一組」、「六人一組」、それ以上の人的結合関係についても同様であり、憲法21条1項の「結社の自由」によって保障されている。
ここで「同性カップル」や「異性カップル」のように、「二人一組」の人的結合関係のみを比較対象として取り上げて、それ以外の人的結合関係を論じないことは、なぜ「二人一組」であるのかその根拠を説明しないままに論じる「カップル信仰論」に陥るものとなっている。
次に、「同性間の婚姻」の文言があるが、そもそも「婚姻」という概念の中に「同性間」の人的結合関係を含めることができるかどうかから検討する。
「婚姻」は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「生殖と子の養育」の観点から、憲法21条の「結社の自由」によって保障される他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度である。
そのため、「婚姻」という概念の有する目的との関係で、「婚姻」の中に含めることのできる人的結合関係の範囲には内在的な限界ががある。
「同性間」については、その間で「生殖」を想定することができないことから、「生殖と子の養育」の趣旨を満たすとはいえないため、「婚姻」とすることはできない。
よって、「同性間の婚姻」の文言は、あたかも「婚姻」の中に「同性間」の人的結合関係を含めることができることを前提とした言葉となっているが、そもそも「婚姻」の中に「同性間」の人的結合関係を含めることができないという点で誤っていると考えられる。
「同性間の婚姻を認めていない本件諸規定は、……(略)……同性カップルを婚姻から排除しており、」との部分を検討する。
まず、「婚姻」とは「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として、「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度である。
そして、この制度の対象となる場合には制度を利用することができ、この制度の対象とならない場合には制度を利用することができないという差異を設けることによって、政策目的を達成することを目指す仕組みとなっていることから、制度の対象となる場合と制度の対象とならない場合の間に差異が生じることは当然のことである。
ここでは「同性間」や「同性カップル」との記載があり、「同性の二人一組」が「婚姻から排除」されていると主張しているが、婚姻制度の対象ではない場合は他にも「近親者との人的結合関係」、「三人以上の人的結合関係」、「婚姻適齢に満たない者との人的結合関係」が存在しており、ここでいう「同性の二人一組」についても、その一つということである。
ここでは「同性カップルは異性カップルと何ら異なるところのない共同生活を営んでいるにもかかわらず」のように、「共同生活を営んでいる」ことを理由として「婚姻から排除」されていることが不当であると主張するものとなっているが、そもそも婚姻制度は「共同生活を営んでいる」者に対して法的効果や優遇措置を講じることを目的とした制度ではない。
婚姻制度は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」などを立法目的として、この立法目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす組み合わせを対象として枠組みが定められ、その利用を促進するために、何らかの法的効果や優遇措置を講じるものである。
婚姻制度を利用する形で「共同生活を営んでいる」者についても、そのような婚姻制度の有する立法目的を達成するための手段となる枠組みを利用していることから、法的効果や一定の優遇措置を得られているだけであり、それは単に「共同生活を営んでいる」ことを理由として法的効果や優遇措置が与えられているというものではない。
もし「共同生活を営んでいる」というだけで婚姻制度の法的効果や優遇措置を得られるとすれば、ここでいう「同性カップル」という「同性間の人的結合関係」だけでなく、「近親者との人的結合関係」、「三人以上の人的結合関係」、「婚姻適齢に満たない者との人的結合関係」についても「共同生活を営んでいる」ことを理由として同様に婚姻制度の法的効果や優遇措置を得られることになってしまう点でも妥当な主張ではない。
「その存在自体、同性愛者等に対する社会的な差別・偏見を助長させ、社会を分断するものであるから、本件諸規定は憲法24条2項に違反する旨主張する。」との記載がある。
「その存在自体、同性愛者等に対する社会的な差別・偏見を助長させ、社会を分断するものであるから、」との部分について検討する。
「その存在自体、」とは、ここでいう「同性カップル」という「同性間」の人的結合関係が「婚姻」の対象となっていないことを意味していると考えられる。
そして、「同性間」の人的結合関係が「婚姻」の対象となっていないことが、「同性愛者等に対する社会的な差別・偏見を助長させ、社会を分断するもの」と考えているようである。
しかし、そもそも婚姻制度は「性愛」の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いをする制度ではないし、「性愛」に基づいて「婚姻」することを求めるものでも勧めるものでもない。
また、法制度は思想、信条、信仰、感情に対して中立的な内容でなければならず、「性愛」というような特定の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的として立法してはならないし、個々人の思想、信条、信仰、感情を審査したり、審査した結果を基にして区別取扱いを行うような制度を設けてはならないことから、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にどのような対象に向かうかを審査して把握したり、その審査の結果を基にして区別取扱いを行うような制度を立法するようなこともしてはならない。
このことから、ここでいう「同性愛者等」についても、婚姻制度の枠組みに従って存在する選択肢の中で、婚姻制度を利用することを望むのであれば、婚姻制度を利用することは可能である。
そのため、この意味で「同性愛者等」を称する者に対して婚姻制度の利用を認めていないとする事実はなく、法制度の法的効果を適用することを否定しているというような意味によって「同性愛者等」を称する者に対する「社会的な差別・偏見を助長させ、社会を分断する」ような取扱いがあるかのような主張であれば、誤りである。
これとは別に、「原告ら」は、婚姻制度が「性愛」という特定の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的とした制度であると考え、その婚姻制度が「男女二人一組」の枠組みを定めていることは、「性愛」の中でも特に「異性愛」の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的としてた制度となっており、その内容も「異性愛者」を称する者を対象とした制度となっていると考えた上で、「性愛」の思想、信条、信仰、感情を有する場合にそれがどのような対象に向かうかという事柄には優劣はないため、「同性愛」の思想、信条、信仰、感情も同様に保護するべきであり、婚姻制度の内容も「同性愛」の思想、信条、信仰、感情も保護する制度に変え、「同性愛者」を称する者も婚姻制度の対象とするべきであると主張していることが考えられる。
しかし、法制度は思想、信条、信仰、感情に対して中立的な内容でなければならず、婚姻制度を立法する際にも、特定の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的としてはならない。
そのため、婚姻制度の内容が「性愛」という特定の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的として立法された場合には、憲法20条1項後段・3項、89条の「政教分離原則」に抵触して違憲となる。
また、婚姻制度を「性愛」という特定の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的とするものとした場合には、その他の思想、信条、信仰、感情との間で憲法14条の「平等原則」に違反する。
他にも、婚姻制度の内容が個々人の「性愛」の有無を審査するものとなっていた場合には、憲法19条の「思想良心の自由」や、憲法20条1項前段の「信教の自由」に抵触して違憲となるし、「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかによって区別取扱いを行うものとなっていた場合には、憲法14条の「平等原則」の観点からも違憲となる。
そのため、そもそも婚姻制度が「性愛」という特定の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的とした制度であると考えている部分が誤りであるし、法制度が特定の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的として立法されているとしても、それが許されるかのように考えている点で誤りである。
また、婚姻制度は「性愛」の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いを行うものではないし、「性愛」に基づいて「婚姻」することを求めるものでも勧めるものでもない。
そのことから、婚姻制度の内容が「男女二人一組」であるとしても、そのことは「異性愛」という思想、信条、信仰、感情を保護することを意味しないし、「異性愛者」を称する者を対象とする制度であることも意味していない。
そのため、「男女二人一組」の婚姻制度を利用している人がすべて「異性愛者」を称する者であるとの推測も誤っている。
また、もし法制度が「異性愛」の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的としていたり、「異性愛者」を称する者を対象とするものとなっていた場合には、そのこと自体が憲法20条1項後段・3項、89条の「政教分離原則」、憲法19条の「思想良心の自由」、憲法20条1項前段の「信教の自由」、憲法14条の「平等原則」に抵触して違憲となる。
これは、もし法制度の内容が「同性愛」の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的としていたり、「同性愛者」を称する者を対象するものとなっていた場合であっても同様であり、そのこと自体が憲法20条1項後段・3項、89条の「政教分離原則」、憲法19条の「思想良心の自由」、憲法20条1項前段の「信教の自由」、憲法14条の「平等原則」に抵触して違憲となる。
よって、婚姻制度の内容に対して「同性愛者等に対する社会的な差別・偏見を助長させ、社会を分断するもの」のように論じている部分は、婚姻制度の内容が「性愛」という特定の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的とした制度であると考えている点で誤りであるし、婚姻制度の枠組みが「性愛」の中でも特に「異性愛」の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的としていたり、「異性愛者」を対象とするものであると考えている点で誤りであるし、そのような「性愛」の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的とした制度が存在するとしても許されると考えている点で誤りである。
(イ) この点、本件諸規定が同性愛者を法律上の家族の枠組みから排除しており、その結果、現行法上、同性愛者についてパートナーと家族になるための法制度が存在しない状態にあることが憲法24条2項に違反する状態であることについては前述のとおりであるところ、立法府において現行の婚姻制度に同性間の婚姻も含める立法を行うことは、上記の状態を解決するために採り得る選択肢の一つである(なお、憲法24条が同性間の婚姻に関する立法を禁止するものとは解されないことは前記アのとおりである。)。
【筆者】
「本件諸規定が同性愛者を法律上の家族の枠組みから排除しており、」との記載がある。
しかし、婚姻制度は「性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にどのような対象に向かうかを審査して区別するものではないし、「性愛」に基づいて「婚姻」することを求めるものでも勧めるものでもない。
そのため、「同性愛者」を称する者でも、婚姻制度の枠組みに従う形で存在する選択肢の中で、なお「婚姻」することを望む場合には婚姻制度を利用することができることから、「本件諸規定が同性愛者を法律上の家族の枠組みから排除」しているという事実はない。
このことは、「同性愛者」を称する者に限らず、「両性愛者」、「全性愛者」、「近親性愛者」、「多性愛者」、「小児性愛者」、「老人性愛者」、「死体性愛者」、「動物性愛者」、「対物性愛者」、「対二次元性愛者」、「無性愛者」を称する者であっても同じことである。
そのことから、「本件諸規定が同性愛者を法律上の家族の枠組みから排除しており、」との評価は誤りである。
「その結果、現行法上、同性愛者についてパートナーと家族になるための法制度が存在しない状態にあることが憲法24条2項に違反する状態である」との記載がある。
ここでも前の部分と同様に、婚姻制度は個々人の内心に中立的な内容であることから、「同性愛者」を称する者であることを取り上げて婚姻制度の利用を制約するものではないことから、「同性愛者」を称する者も適法に婚姻制度を利用することが可能であり、「同性愛者」を称する者にだけ「パートナーと家族になるための法制度が存在しない状態にある」との認識は誤りである。
また、「憲法24条2項に違反する状態である」との部分については、上記の「 ⑶オ(オ)」のところで解説したように、「憲法24条2項」は「婚姻及び家族」の制度を立法することを求めるものであるが、それ以外の制度を立法することを求めるものではないし、「憲法24条2項」に規定された「個人の尊厳」の文言は、「婚姻及び家族」の対象となっている場合にのみ適用されるものであり、「婚姻及び家族」の対象となっていない場合には適用されない。
よって、「婚姻及び家族」の範囲を超える人的結合関係について「法制度が存在しない状態にあること」について、「憲法24条2項に違反する状態である」と述べていることも誤りとなる。
ここで「パートナー」という「二人一組」の一方を指す言葉を使っているが、婚姻制度の枠組みが定められる以前の段階で人的結合関係が「二人一組」でなければならないという前提は存在しないのであり、婚姻制度の枠組みを超える人的結合関係について論じられる場合においても「二人一組」であることを根拠もなく前提として話を進めていることは、なぜ「二人一組」であるのかその根拠を説明しない「カップル信仰論」に陥った言葉の使い方となっている。
法律論としては、立法目的とその立法目的を達成するための手段として枠組みが定められるのであり、そのような立法目的とその立法目的を達成するための手段となる枠組みが存在しないままに、「二人一組」という枠組みだけを当然の前提であるかのように論じることは、恣意的な形で論点を先取するものとなっていることが考えられる。
何らかの結論を導き出すために、本来の立法目的を覆い隠し、その立法目的を達成するための手段として導かれる枠組みに込められた意図を無視していることが考えらるため、注意して読み解く必要がある。
「立法府において現行の婚姻制度に同性間の婚姻も含める立法を行うことは、上記の状態を解決するために採り得る選択肢の一つである(なお、憲法24条が同性間の婚姻に関する立法を禁止するものとは解されないことは前記アのとおりである。)。」との記載がある。
「立法府において現行の婚姻制度に同性間の婚姻も含める立法を行うことは、上記の状態を解決するために採り得る選択肢の一つである」との部分は、「婚姻」の中に「同性間」の人的結合関係を含めることができることを前提とするものとなっている。
また、「憲法24条が同性間の婚姻に関する立法を禁止するものとは解されない」との部分についても、「同性間」の人的結合関係を「婚姻」として立法することが可能であることを前提とするものとなっている。
この二つの文は、「同性間の婚姻」という言葉を使っていることから、「婚姻」という概念の中に「同性間」の人的結合関係を含めることができることを前提とするものとなっている。
しかし、「婚姻」という概念には、「婚姻」という概念が形成されている目的との関係で内在的な限界があり、「同性間」の人的結合関係を含めることがができるかどうか検討する必要がある。
その国の中で「生殖と子の養育」に関する事柄について何らの制度も存在しない場合には、社会的な不都合が発生することがある。
例えば、「父親不明」の子供が増える、父親を特定できない子供が増える、父親が蒸発して行方不明になった子供が増える、それらにより「子の福祉」が減少する、父親を特定できないことにより近親者の範囲を把握できずに「近親交配」に至り遺伝的な劣勢を有する個体が高い確率で発現するようになる、一部の強者が多数人との生殖関係を独占することによって社会の中で「子を持ちたいと希望して相手を見つけようとする男女」の数の不均衡が生じて「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」が生まれる、低年齢での妊娠・出産により母体に危険が及ぶ、などの問題が生じることがある。
「婚姻」は、これらの「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、他の人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度である。
そのため、「婚姻」には、下記の立法目的が存在すると考えられる。
・「子の福祉」が実現される社会基盤を構築すること
・遺伝的な劣勢を有する個体が高い確率で発現することを抑制すること
・「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」を減らすこと
・母体を保護すること
このような「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解決しようとする立法目的を離れて「婚姻」を観念することはできない。
そのため、「婚姻」である以上は、その概念そのものの中に、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消しようとする目的を達成することを損なうことはできないという内在的な限界が含まれていることになる。
また、「婚姻」という概念である以上は、国民が「生殖」によって子を産むことに関わる制度であることを前提としており、「婚姻」の文言の中には「生殖と子の養育」の趣旨が含まれている。
この「生殖と子の養育」の趣旨を満たすためには、単に何らかの生殖があり、子を養育することができる地位があればよいというものではなく、下記の要素を満たすことが求められると考えられる。
・子の遺伝的な父親を特定できる組み合わせとすること
・特定された子の父親にも子に対する責任を担わせること
・特定された子の父親を基に遺伝的な近親者を把握すること
・未婚の男女の数の不均衡を防止できる組み合わせに限定すること
これらの要素を満たすことは、「婚姻」という枠組みが形成されている目的との関係で整合的であり、他の人的結合関係とは区別する形で「婚姻」という概念が成り立つための境界線を保つことができるからである。
もしこれらの要素を満たさない人的結合関係を「婚姻」の中に含めようとした場合には、その時点で、これらの要素を満たさないことから、 「婚姻」の立法目的を達成することができなくなることを意味する。
そのため、これらの要素を満たさない人的結合関係については、「婚姻」として扱うことはできない。
憲法24条は「婚姻」を定めており、「婚姻」が「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた枠組みであることは明らかである。
24条は「両性」「夫婦」「相互」の文言を定めており、一夫一婦制(男女二人一組)を規定している。
このことも、「婚姻」の立法目的を達成するための手段として整合的な上記の要素(「生殖と子の養育」の趣旨)を満たすことが理由であると考えられる。
そのため、憲法24条が一夫一婦制(男女二人一組)を定めていることからは、これらの要素を満たす人的結合関係を「婚姻」として扱い、これらの要素を満たさない人的結合関係については「婚姻」として扱わないという意味が含まれていると考えられる。
もしそのような差異を設けないとすれば、「婚姻」が「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消しようとする枠組みとして機能しなくなり、妥当でないからである。
このような差異を設けることは、「婚姻」の立法目的を達成するために不可欠の要素ということである。
よって、24条は「婚姻」を定めていることから、24条の「婚姻」の下では、上記の要素を満たさない人的結合関係を「婚姻」として扱うことはできない。
もし上記の要素を満たさない人的結合関係を「婚姻」として扱おうとする立法を試みた場合には、24条の許容する立法裁量の限界を超え、24条に抵触して違憲となる。
そこで、この判決がいう「同性間」の人的結合関係を「婚姻」とすることができるかどうかであるが、「同性間」の人的結合関係については、上記の要素を満たさない(『生殖と子の養育』の趣旨を満たさない)ことから、「婚姻」とすることはできない。
よって、「立法府において現行の婚姻制度に同性間の婚姻も含める立法を行うことは、上記の状態を解決するために採り得る選択肢の一つである」との部分は誤りとなり、「立法府において現行の婚姻制度」に「同性間」の人的結合関係を「含める立法を行うこと」はできない。
ここでいう「上記の状態を解決するために」の部分であるが、そもそも24条2項に違反しないという点で「上記の状態」についての認識も謝っており、「解決する」必要がないものである。
また、「憲法24条が同性間の婚姻に関する立法を禁止するものとは解されない」についても、「婚姻」という概念の中に「同性間」の人的結合関係を含めることはできないし、「憲法24条」の下で「婚姻」の中に「同性間」の人的結合関係を含めようとする「立法」を行った場合には、「憲法24条」の「婚姻」や「両性」「夫婦」の文言や、「両性」「夫婦」「相互」の文言が一夫一妻制を定めている趣旨に反して違憲となるため、その意味で「禁止するものとは解されない」と述べている部分についても誤りである。
また、近時は改善されつつあるものの、同性愛が長らく異常なものとして認識され、差別や偏見の対象となってきたことからすれば、現行の婚姻制度に同性間の婚姻を含めることにより、異性間の婚姻と全く同じ制度を構築することが差別や偏見の解消に資するとの原告らの主張にも首肯できる点はある。
【筆者】
「近時は改善されつつあるものの、同性愛が長らく異常なものとして認識され、差別や偏見の対象となってきたことからすれば、」との部分について検討する。
日本国憲法には19条で「思想良心の自由」、20条1項で「信教の自由」を定めていることから、心理的、精神的なものである「同性愛」という思想、信条、信仰、感情は「内心の自由」として保障されている。
よって、少なくとも日本国憲法下では、「同性愛」の思想、信条、信仰、感情を抱くこと理由として法的に「差別」をしているという事実はない。
「現行の婚姻制度に同性間の婚姻を含めることにより、異性間の婚姻と全く同じ制度を構築することが差別や偏見の解消に資する」との部分について検討する。
まず、「同性愛」の思想、信条、信仰、感情を抱くことは「内心の自由」として保障されており、これを理由とする法的な「差別」は存在しないため、「解消」しなければならないとする取扱いの違いは存在しない。
これとは別に、ここでは「現行の婚姻制度」が「異性愛」の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的とした制度となっているかのような認識を持った上で、「異性愛」も「同性愛」も同様に保護することを目的として制度を立法することで、「同性愛」の思想、信条、信仰、感情を抱く者への「差別や偏見」を「解消」することを述べるものとなっている。
しかし、法制度は思想、信条、信仰、感情に対して中立的な内容でなければならないのであり、「性愛」という思想、信条、信仰、感情を保護することを目的として婚姻制度を立法することはできないし、その中でも特に「異性愛」という思想、信条、信仰、感情を保護するものとして婚姻制度を立法することも当然できない。
よって、「現行の婚姻制度」が「異性愛」の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的とした制度であるかのように考えていることも誤りであるし、「現行の婚姻制度」が「異性愛」の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的とした制度として存在している場合にも、それが許されると考えていることも誤りである。
同様に、法制度を「同性愛」の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的とした制度として立法することも許されないのであり、そのような制度を立法することによって「差別や偏見の解消」を行おうとすることも正当化することはできない。
この判決は、このような主張に対して「首肯できる点はある。」と述べているが、法律論としてこのような主張に「首肯」することは、法解釈として誤っている。
まずは、「男女二人一組」の婚姻制度を利用する者はすべて「異性愛」の思想、信条、信仰、感情を抱く「異性愛者」を称する者であるとする誤った前提(偏見)を見直す必要がある。
婚姻制度が「男女二人一組」の枠組みとなっていることについて、「異性愛」の思想、信条、信仰、感情を抱く者が利用しているとか、利用するべきであるという考え方は、単なる法制度に対して「異性愛」という思想や感情を重ね合わせて認識しようとする者の思想の一つである。
法制度上の「婚姻」の枠組みに対して、「ロマンチック・ラブ・イデオロギー」を持ち込んでその当否や情熱の深さの優劣を論じようとする主張と何ら変わらないのであり、法律論から逸脱するものである。
そのため、「現行の婚姻制度に同性間の婚姻を含めることにより」「同性愛」に対する「差別や偏見の解消」をしようと試みることについても、そもそも「男女二人一組」の婚姻制度を「異性愛」を保護するための制度であると考える誤った前提から出発した理解となっており、妥当でない。
そもそも婚姻制度の枠組みと個々人の「性愛」との間に関係性がないことを理解することによって、その問題は「解消」されることになる。
(ウ) しかしながら、婚姻や家族に関する事項については、国の伝統や国民感情を含めた社会状況における種々の要因を踏まえつつ、それぞれの時代における家族関係についての全体の規律を見据えた総合的な判断によって定められるべきであるから、この点に関しては立法府が合理的な立法裁量を有しているものと解される。同性間の婚姻の制度を導入した国においても、その導入に先行して、まずは登録パートナーシップ制度を導入した国も多く(前記認定事実(3)ア及びイ)、その導入過程は様々である。また、前述のとおり、同性間の婚姻を導入した国においても、嫡出推定規定の適用の有無、養子縁組の可否、生殖補助医療利用の可否等について議論がされていることが認められ、我が国においても、これらの点について、子の福祉や生命倫理の観点からの検討、他の制度との整合性の検討等を行うことが不可避であり、この点は第一次的には立法府の立法裁量に委ねられているものといわざるを得ない。そして、婚姻制度から同性間の人的結合関係を排除することは差別や偏見を助長するとの原告らが指摘する観点についても、同様に立法府における検討において考慮されるべき事項の一つであるということはできるが、それによって立法府が採り得る選択肢が、現行の婚姻制度に同性間の婚姻を含める立法という一つの方法に収れんし、同性間の婚姻を認めていない本件諸規定が憲法24条2項に違反するとはいい難い。なお、前記認定事実(5)のとおり、同性間の婚姻を認めることや同性カップルに対して法的保障を認めることについて、近年、肯定的な世論が広がりを見せていることなどからすれば、上記の点についての議論、検討を第一次的には立法府に委ねることが必ずしも現実的でないとはいえない。
【筆者】
「婚姻や家族に関する事項については、国の伝統や国民感情を含めた社会状況における種々の要因を踏まえつつ、それぞれの時代における家族関係についての全体の規律を見据えた総合的な判断によって定められるべきであるから、この点に関しては立法府が合理的な立法裁量を有しているものと解される。」との記載がある。
この文の「定められるべきである」までは、おおよそ「平成27年夫婦同氏制大法廷判決」から抜き出した、この東京地裁判決の上記「⑶イ」のところに記載している分を繰り返すものてなっている。
・この東京地裁判決と「平成27年夫婦同氏制大法廷判決」でまったく同じ文となっているところは灰色で潰した。
・この東京地裁判決が、「平成27年夫婦同氏制大法廷判決」の文面を変更(改竄)しているところは赤字で示した。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3(1) 他方で,婚姻及び家族に関する事項は,国の伝統や国民感情を含めた社会状況における種々の要因を踏まえつつ,それぞれの時代における夫婦や親子関係についての全体の規律を見据えた総合的な判断によって定められるべきものである。特に,憲法上直接保障された権利とまではいえない人格的利益や実質的平等は,その内容として多様なものが考えられ,それらの実現の在り方は,その時々における社会的条件,国民生活の状況,家族の在り方等との関係において決められるべきものである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「平成27年夫婦同氏制大法廷判決」 (PDF)
ここでも、「平成27年夫婦同氏制大法廷判決」の「夫婦や親子関係」という重要な文言が「家族関係」の文言に変更(改竄)されていることを見て取ることができる。
「定められるべきである」以降の、「から、この点に関しては立法府が合理的な立法裁量を有しているものと解される。」の部分は、この文が独自に付け足してあるものである。
㊥ 「同性間の婚姻の制度を導入した国においても、その導入に先行して、まずは登録パートナーシップ制度を導入した国も多く(前記認定事実(3)ア及びイ)、その導入過程は様々である。」
㊥ 「同性間の婚姻を導入した国においても、嫡出推定規定の適用の有無、養子縁組の可否、生殖補助医療利用の可否等について議論がされていることが認められ、我が国においても、これらの点について、子の福祉や生命倫理の観点からの検討、他の制度との整合性の検討等を行うことが不可避であり、この点は第一次的には立法府の立法裁量に委ねられているものといわざるを得ない。」
㊥ 「婚姻制度から同性間の人的結合関係を排除することは差別や偏見を助長するとの原告らが指摘する観点についても、同様に立法府における検討において考慮されるべき事項の一つであるということはできるが、それによって立法府が採り得る選択肢が、現行の婚姻制度に同性間の婚姻を含める立法という一つの方法に収れんし、同性間の婚姻を認めていない本件諸規定が憲法24条2項に違反するとはいい難い。」
㊥ 「同性間の婚姻を認めることや同性カップルに対して法的保障を認めることについて、近年、肯定的な世論が広がりを見せていることなどからすれば、上記の点についての議論、検討を第一次的には立法府に委ねることが必ずしも現実的でないとはいえない。」
キ 以上によれば、婚姻を異性間のものに限り同性間の婚姻を認めていない本件諸規定が憲法24条2項に違反するとはいえない。
【筆者】
「婚姻を異性間のものに限り」との部分は不自然ではないが、「同性間の婚姻」という文言は適切ではない。
「婚姻」は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度であり、「婚姻」の中に含めることのできる人的結合関係はその目的との関係で内在的な限界がある。
「同性間」の人的結合関係」については、その間で「生殖」を想定することができないことから、「生殖と子の養育」の趣旨を満たすとはいえないため、「婚姻」の中に含めることはできない。
よって、「同性間の婚姻」との部分は、あたかも「婚姻」の中に「同性間」の人的結合関係を含めることができるかのような前提で論じるものとなっているが、「婚姻」の中に「同性間」の人的結合関係を含めることができないという点で誤っている。
3 争点 (国会が同性間の婚姻を可能とする立法措置を講じないことが国家賠償法1条1項の適用上違法と評価されるか)について
(1) 国家賠償法1条1項は、国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が個々の国民に対して負担する職務上の法的義務に違反して当該国民に損害を加えたときに、国又は公共団体がこれを賠償する責任を負うことを規定するものであるところ、国会議員の立法行為又は立法不作為が同項の適用上違法となるかどうかは、国会議員の立法過程における行動が個々の国民に対して負う職務上の法的義務に違反したかどうかの問題であり、立法の内容の違憲性の問題とは区別されるべきものである。そして、上記行動についての評価は原則として国民の政治的判断に委ねられるべき事柄であって、仮に当該立法の内容が憲法の規定に違反するものであるとしても、そのゆえに国会議員の立法行為又は立法不作為が直ちに国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではない。
もっとも、法律の規定が憲法上保障され又は保護されている権利利益を合理的な理由なく制約するものとして憲法の規定に違反するものであることが明白であるにもかかわらず、国会が正当な理由なく長期にわたってその改廃等の立法措置を怠る場合などにおいては、国会議員の立法過程における行動が上記職務上の法的義務に違反したものとして、例外的に、その立法不作為は、国家賠償法1条1項の規定の適用上違法の評価を受けることがあるというべきである(最高裁昭和53年(オ)第1240号同60年11月21日第一小法廷判決・民集39巻7号1512頁、最高裁平成13年(行ツ)第82号、第83号、同年(行ヒ)第76号、第77号同17年9月14日大法廷判決・民集59巻7号2087頁、平成27年再婚禁止期間大法廷判決参照)。
(2) 原告らは、本件諸規定が憲法14条1項、24条1項及び2項に違反するものであるにもかかわらず、国会が長期にわたって、本件諸規定が定める婚姻を同性間でも可能とする立法措置(同性間の婚姻を可能とする立法措置)を怠っている旨主張する。
しかしながら、本件諸規定が憲法14条1項、24条1項ないし2項に違反するものではないことは前記2において述べたとおりであるから、原告らの主張は前提を欠くものといわざるを得ない。なお、前記2 のとおり、現行法上、同性愛者についてパートナーと家族になるための法制度が存在しないことは、同性愛者の人格的生存に対する重大な脅威、障害であり、個人の尊厳に照らして合理的な理由があるとはいえず、憲法24条2項に違反する状態にあるということができるが、上記の法制度を構築する方法は同性間の婚姻を現行の婚姻制度に含める旨の立法を行うこと以外にも存在するのであるから、上記の状態にあることから原告らが主張する同性間の婚姻を可能とする立法措置を講ずべき義務が直ちに生ずるものとは認められない。
したがって、国会が同性間の婚姻を可能とする立法措置を講じないことが国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるとはいえない。
第4 結論
以上の次第であるから、原告らの請求は、その余の争点について判断するまでもなくいずれも理由がないことに帰するから、これらを棄却することとして、主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第16部
裁判長裁判官 池原桃子
裁判官 益留龍也
裁判官 横山怜太郎
<理解の補強>
国(行政府)は、裁判所が原告と被告の双方の主張の中で論じられていない「パートナーと家族になるための法制度」と称するものが存在しないという点について勝手に取り上げて憲法適合性を判断をしたことは不当である旨を指摘している。
【東京一次・第1回】控訴答弁書 令和5年6月23日 PDF (P31~34)
判決の誤りを継承する解説
下記に挙げたこの東京地裁判決の記事や解説について、当サイトをお読みの方ならば、どの部分が妥当でないかを見抜くことができるはずである。
実質的な「違憲」誇っていい。東京地裁判決を傍聴、感じた希望と葛藤 2022/12/1
[木村草太の憲法の新手](189)同性婚訴訟 東京地裁判決 制度新設、差別感情の表れ 尊厳守る「婚姻」保障を 2022年12月4日
「黒人専用列車を作るのと同じ」 同性カップル用に“別の婚姻制度”を作る?憲法学者が厳しく批判する理由 2022年12月6日
「同性婚制度なしは『違憲状態』 日本の同性婚は実現できるか?」 2022年12月10日 Twitter
同性婚訴訟とパートナーシップ制度。 2022年12月11日
「結婚の平等」裁判、東京地裁では“違憲“判決だった。専門家が指摘する理由 2022年12月13日
「結婚の自由をすべての人に」訴訟(いわゆる同性婚訴訟)の現状と今後 2023.03.17
同性婚訴訟の分析 : 札幌、大阪、東京地裁判決を素材に 春山習 2023-09-28
同性婚訴訟、請求棄却でも「すごく大きな一歩」 違憲状態判断に「今すぐ法改正に動いて」国会にも注文 2022年11月30日
同性婚 法制度ないのは違憲状態も憲法には違反せず 東京地裁 2022年11月30日
<社説>同性婚判決 社会の変化とらえねば 2022年12月1日
同性カップルが家族になれない現状は「違憲状態」…「個人の尊厳」回復に向けて国会の議論は進むのか 2022年12月1日
同性婚訴訟判決 「個人の尊厳」保障へ法整備を 2022年12月2日
社説[同性婚否定は違憲状態]法制化へ動き出す時だ 2022年12月2日
同性婚訴訟で「違憲状態」 権利保障へ法整備急げ 2022/12/2
同性婚訴訟判決 「違憲状態」解消へ立法急げ 社説 2022年12月2日
「同性婚」判決 国会の立法措置は急務だ 2022/12/2
[同性婚訴訟] 国の「放置」許されない 2022/12/2
社説:同性婚東京判決 早急に法整備の議論を 2022年12月2日
<社説>同性婚訴訟判決 国会に法整備を促した 2022年12月2日
同性婚訴訟判決/違憲状態の解消は急務だ 2022/12/03
同性婚の法制化 実現に向けた議論加速を 2022/12/4
【同性婚訴訟】法的保護へ議論を急げ 2022.12.05
同性婚不受理「違憲状態」 議論本格化の契機とせよ 2022/12/06
社説:同性婚訴訟判決 国会、法整備へ議論急げ 2022年12月6日
裁判の結果「同性婚」は認められたのか? 2022.12.06
<社説>同性婚訴訟「違憲状態」 早急に法整備の検討を 2022年12月7日
同性婚不受理「違憲状態」 国会での議論本格化させよ 2022年12月7日
論説 同性婚不受理 「違憲状態」議論本格化の契機に 2022/12/8
同性婚認めぬ法制度は「違憲状態」~東京地裁判決、国会に立法措置を促す 2022.12.09
制度なしは「違憲状態」 結婚の自由訴訟で東京地裁 2022年12月9日
同性婚訴訟 東京地裁判決は「違憲状態」と判断 2022年12月10日
同性婚訴訟判決 家族になれる法制度早く 2022/12/10
同性婚訴訟/課題向き合い議論するとき 2022年12月13日
「上級国民と二級国民の線引き、必要ですか」同性カップルが国と司法に求めること【結婚の平等訴訟】 2022年12月13日
報道: 同性婚集団訴訟3例目の地裁判決は違憲状態の合憲 2022-12-16
(社説)同性婚法制化 国会の無策は許されぬ 2023年1月15日
お読みいただきありがとうございました。