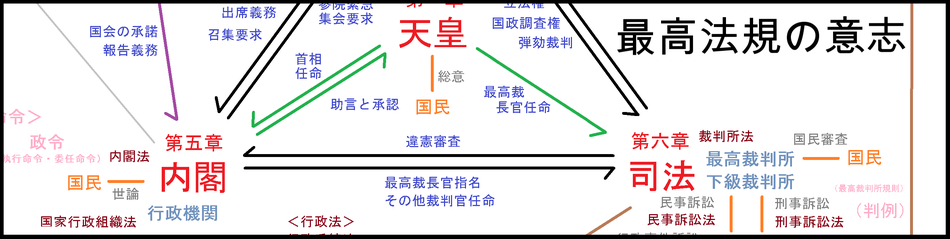同性婚訴訟 名古屋地裁判決の分析
【このページの目次】
はじめに
ポイント
〇 「婚姻」のある社会を選択する意図
〇 24条2項の「婚姻及び家族」の枠組み
〇 24条2項の「家族」の範囲
〇 24条2項の「個人の尊厳」と「両性の本質的平等」の適用対象
〇 論じている対象の違い
〇 14条1項の「平等」と24条2項の「両性の本質的平等」の射程
〇 カップル間不平等論の誤り
〇 婚姻が成立するための「条件」
〇 「目的」の意味の混同
〇 「性愛」による区別取扱いは存在しないこと
〇 「人格」とはどういう意味か
名古屋地裁判決の内容
判決の誤りを継承する解説
はじめに
「同性婚訴訟 名古屋地裁判決」の内容を分析する。
判決
国家賠償請求事件 名古屋地方裁判所 民事第8部 令和5年5月30日 (PDF)
国家賠償請求事件 名古屋地方裁判所 民事第8部 令和5年5月30日
【愛知】判決全文 PDF
判決要旨
【愛知】判決要旨 PDF
【判決要旨全文】「同性同士の結婚が認められないのは、14条1項と24条2項違反」名古屋地裁で違憲判決。その内容は? 2023年05月30日
この判決文の内容は、誤った前提認識や、法律論でない部分、判例引用の間違いなど、問題が多岐にわたる。複数ヵ所の誤りを同時に解きほぐすことが必要となるため、初学者には難解であると思われる。
ここでは、その誤りを丁寧に確認していきたい。
ポイント
判決の誤りを理解するために、前提として必要となる知識を整理する。
「婚姻」のある社会を選択する意図
その社会の中で何らの制度も設けられていない場合には、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合が発生する。
例えば、「父親不明」の子供が増える、父親を特定できない子供が増える、父親が蒸発して行方不明になった子供が増える、それらにより「子の福祉」が減少する、父親を特定できないことにより近親者の範囲を把握できずに「近親交配」に至り潜性遺伝子を有する個体が高い確率で発現するようになる、一部の強者が多数人との生殖関係を独占することによって社会の中で「子を持ちたいと希望して相手を見つけようとする男女」の数の不均衡が生じて「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」が生まれる、低年齢での妊娠・出産により母体に危険が及ぶ、などの問題が生じることがある。
これらの不都合を解消するために、下記のような立法目的を有する枠組みを設けることが必要となる。
・「子の福祉」が実現される社会基盤を構築すること
・潜性遺伝子を有する個体が高い確率で発現することを抑制すること
・「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」を減らすこと
・母体を保護すること
そして、これらの目的を達成するためには、下記の要素を満たす枠組みを設けることが必要となる。
・子の遺伝的な父親を特定できる組み合わせとすること
・特定された子の父親にも子に対する責任を担わせること
・特定された子の父親を基に遺伝的な近親者を把握すること
・未婚の男女の数の不均衡を防止できる組み合わせに限定すること
これらの要素を満たすものとして「一人の男性」と「一人の女性」が選び出され、その間に「貞操義務」を設け、その関係を法的に結び付ける形を「婚姻」と呼んでいる。
そして、この「婚姻」に対して法的効果や一定の優遇措置を設けることで、婚姻制度を利用する者を増やし、これらの目的を達成することを目指すものとなっている。
このように、「婚姻」は国民が「生殖」によって子供を産むことに関係して起き得る問題を抑制することを目的として、「生殖と子の養育」の観点に着目して他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた枠組みである。
このような「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解決しようとする目的を離れて「婚姻」を観念することはできない。
よって、「婚姻」の文言には、これらの目的を達成することを阻害する組み合わせを「婚姻」の中に含めることはできないという内在的な限界が含まれており、その限界を超えるものについては「婚姻」とすることはできない。
また、憲法24条は「婚姻」を規定しており、「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めている。
これについても、上記の要素を満たす枠組みとして定められているものである。
この24条の定める形が「婚姻」であり、これらの要素を満たさないものについては「婚姻」とすることはできない。
24条2項の「婚姻及び家族」の枠組み
24条2項の「婚姻及び家族」について詳しく検討する。
■ 「婚姻」と「家族」はそれ以外の概念ではないこと
「婚姻」や「家族」である以上は、「サークル」「部活」「組合」「雇用」「会社」「町内会」「宗教団体」「政党」など他の様々な人的結合関係とは異なる概念である。
当然、これは「意思表示」「代理」「物権」「即時取得」「売買」など、それとは別の概念を示すものでもない。
このように、「婚姻」や「家族」という概念が用いられている以上は、その概念そのものが有する意味を離れることはできないのであり、その概念が有する意味に拘束されることになる。
よって、「婚姻」や「家族」として扱うことができる範囲には、「婚姻」や「家族」という概念であることそのものによる内在的な限界が存在する。
言い換えれば、「婚姻」や「家族」という言葉それ自体を別の意味に変えてしまうことはできないのであり、これらの言葉に対して、その概念に含まれている内在的な限界を超える意味を与えることが解釈として可能となるわけではない。
もしその概念が有する内在的な限界(意味の範囲)を超える形で新たな枠組みを設けることを望む場合には、解釈によって導き出すことのできる範囲を超えることになるから、その規定を改正して文言を変更するか、その規定そのものを廃止することが必要となる。
■ 「婚姻」と「家族」は異なる概念であること
24条2項には「婚姻及び家族」と記載されている。
ここから分かることは、「婚姻」と「家族」はそれぞれ異なる概念であるということである。
このことから、下記の内容が導かれる。
〇 第一に、「婚姻」と「家族」を同一の概念として扱うことはできない。
〇 第二に、「婚姻」の概念を「家族」の概念に置き換えることや、「家族」の概念を「婚姻」の概念に置き換えることはできない。
〇 第三に、「婚姻」や「家族」という言葉の意味によって形成されている概念の境界線を取り払うことはできない。
〇 第四に、「婚姻」や「家族」という言葉の意味の範囲をどこまでも拡張することができるというものではない。
このように、「婚姻」と「家族」という文言が使われていることそのものによって、これを解釈する際に導き出すことのできる意味の範囲には内在的な限界がある。
それぞれの言葉には一定の意味があり、その意味そのものを同じものとして扱ったり、挿げ替えたり、混同したり、無制限に拡張したりすることはできないからである。
そのため、もし下記のような法律を立法した場合には、24条2項の「婚姻及び家族」の文言に抵触して違憲となる。
① 「婚姻」と「家族」の意味を同一の概念として扱うような法律を立法した場合
② 「婚姻」の意味と「家族」の意味を置き換えるような法律を立法した場合
③ 「婚姻」や「家族」の概念の境界線を取り払うような法律を立法した場合
④ 「婚姻」や「家族」という言葉の意味の範囲をどこまでも拡張することができることを前提とした法律を立法した場合
■ 「婚姻」と「家族」は整合的に理解する必要があること
24条2項の「家族」とは、法学的な意味の「家族」を指すものである。
そのため、社会学的な意味で使われる「家族」のように、どのような意味としてでも自由に用いることができるというわけではない。
24条2項には「婚姻及び家族」と記載されており、これら「婚姻」と「家族」の文言は、一つの条文の中に記されている。
24条2項では「A、B、C、D、E 並びに F」の形で順を追って説明するものとなっており、その中で「婚姻及び家族に関するその他の事項」が一つのまとまりとなっている。
この点で、「婚姻」と「家族」という二つの概念はまとめる形で定められている。
そして、「家族」の文言は、「婚姻及び家族」のように「婚姻」の文言のすぐ後に続く形で、「婚姻」と共に記されている。
そのことから、「家族」の概念は、「婚姻」の概念と結び付くものとして定められており、これらは切り離すことのできるものではない。
よって、「婚姻」と「家族」の意味を解釈する際には、それぞれの概念をまったく別個の目的を有した相互に関わり合いのない枠組みであるかのように考えることはできず、それらを整合的に読み解くことが求められる。
24条2項の「婚姻及び家族」の文言は、1項で「婚姻」について既に定められていることを前提として、それに続く形で「家族」についても触れるものとなっている。
そのため、「家族」の概念は「婚姻」を中心として定められる枠組みであることは明らかである。
これについて、国(行政府)は下記のように説明している。
◇ 「同項における立法上の要請及び指針は、形式的にも内容的にも、同条1項を前提とすることが明らかである。」
◇ 「このように、憲法24条2項が、同条1項の規定内容を踏まえ、これを前提として定められていることは、同条2項の内容面からしても明らかである。」
【東京一次・第1回】控訴答弁書 令和5年6月23日 PDF
国(行政府)は最高裁判決の記述も示している。
【東京二次・第9回】被告第7準備書面 令和5年9月28日 PDF (P14)
【九州・第1回】被控訴人(被告)答弁書 令和6年1月31日 (P15)
■ 「婚姻及び家族」の内在的な限界
「家族」の枠組みを検討するために、初めに、「婚姻」の目的と、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす枠組みから検討する。
▼ 「婚姻」の概念に含まれる内在的な限界
「婚姻」は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的とした形成された枠組みである。
これは、下記のような経緯によるものである。
その社会の中で何らの制度も設けられていない場合には、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合が発生する。
例えば、「父親不明」の子供が増える、父親を特定できない子供が増える、父親が蒸発して行方不明になった子供が増える、それらにより「子の福祉」が減少する、父親を特定できないことにより近親者の範囲を把握できずに「近親交配」に至り潜性遺伝子の発現した個体が高い確率で生じるようになる、一部の強者が多数人との生殖関係を独占することによって社会の中で「子を持ちたいと希望して相手を見つけようとする男女」の数の不均衡が生じて「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」が生まれる、低年齢での妊娠・出産により母体に危険が及ぶ、などの問題が生じることがある。
これらの不都合を解消するために、下記のような立法目的を有する枠組みを設けることが必要となる。
・「子の福祉」が実現される社会基盤を構築すること
・潜性遺伝子の発現した個体が高い確率で生じることを抑制すること
・「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」を減らすこと
・母体を保護すること
そして、これらの目的を達成するためには、下記の要素を満たす枠組みを設けることが必要となる。
・子の遺伝的な父親を特定できる組み合わせとすること
・特定された子の父親にも子に対する責任を担わせること
・特定された子の父親を基に遺伝的な近親者を把握すること
・未婚の男女の数の不均衡を防止できる組み合わせに限定すること
これらの要素を満たすものとして「一人の男性」と「一人の女性」が選び出され、その間に「貞操義務」を設け、その関係を法的に結び付ける形を「婚姻」と呼んでいる。
そして、この制度を利用した場合には一定の法的効果や優遇措置があるという差異を設けることによって、この制度を利用する者を増やし、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成することを目指すものとなっている。
このような「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解決しようとする目的を離れて「婚姻」を観念することはできない。
そのため、「婚姻」である以上は、これらの目的を達成することを阻害する組み合わせを「婚姻」とすることはできないという内在的な限界がある。
また、24条の「婚姻」は、「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めている。
これについても、上記の要素を満たす枠組みとして定められているものである。
よって、「婚姻」の中に含めることのできる人的結合関係の範囲は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成するための手段として整合的な上記の要素を満たす範囲に限られる。
▼ 「家族」の概念に含まれる内在的な限界
次に、「家族」の枠組みを検討する。
▽ 「婚姻」と「家族」の整合的な理解
上で述べたように、「家族」の枠組みは、「婚姻」という枠組みが存在することを前提としており、「婚姻」の枠組みから切り離して独立した形で存在することはできない。
そのため、もし「婚姻」の枠組みが有している目的の実現を「家族」の枠組みが阻害するものとなっている場合、「婚姻」と「家族」は同一の条文の中に記された文言であるにもかかわらず、その間に矛盾・抵触が生じていることとなり、その意味を整合的に読み解くことができていないことになるから、解釈の方法として妥当でない。
そのことから、「家族」の枠組みは、「婚姻」の枠組みが有している目的を達成することを阻害するような形で定めることはできず、「婚姻」の枠組みが有している目的との整合性を切り離して考えることはできない。
これにより、「婚姻」と「家族」は、同一の目的を共有し、その同一の目的に従って相互に矛盾することなく整合性を保った形で統一的に形成される枠組みということになる。
よって、「家族」の枠組みは、「婚姻」の立法政策に付随して同一の目的を共有し、「婚姻」の枠組みと結び付く形で位置付けられることになる。
▽ 「家族」の枠組み
「家族」の枠組みは、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として設けられた「婚姻」の枠組みと結び付いて定められている。
そのため、「家族」の枠組みは、「婚姻」の目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす枠組みが存在することを前提として、その「婚姻」と同一の目的を共有する形で、かつ、その「婚姻」の枠組みとの間で矛盾しない形で、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす形で定められることになる。
「婚姻」とするためには、下記の要素を満たすことが必要である。
・子の遺伝的な父親を特定できる組み合わせとすること
・特定された子の父親にも子に対する責任を担わせること
・特定された子の父親を基に遺伝的な近親者を把握すること
・未婚の男女の数の不均衡を防止できる組み合わせに限定すること
そして、「家族」の枠組みは、「婚姻」と同一の目的を共有し、この「婚姻」の枠組みと矛盾しない形で、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす形で定められることになる。
そのことから、「家族」とするためには、下記の要素を満たすことが必要である。
・「婚姻」と「家族」は異なる概念であること
・「婚姻」と同一の機能を「家族」の概念に担わせることはできないこと
・「生殖」を推進する関係は「婚姻」している夫婦の間に限られること
・「貞操義務」は夫婦の間に限られること
・夫婦以外の関係の間で「生殖」を推進する作用を生じさせないこと
・「生殖」によって子が生じるという生命活動の連鎖による血筋を明らかにすることが骨格となること
・「生殖」によって生じた子とその親による「親子」の関係を規律すること
・遺伝的な近親者とは「婚姻」することができないこと
これらの要素により、「家族」の中に含めることのできる人的結合関係と、含めることのできない人的結合関係が区別されることになる。
このように、「婚姻」が「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的としている以上は、その「婚姻」の目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす枠組みとの関係で、「家族」の枠組みも自ずと明らかとなる。
このことより、「家族」の中に含めることのできる人的結合関係の範囲は、「家族」という概念であることそれ自体による内在的な限界がある。
そのため、もし上記の要素を満たさない人的結合関係を「家族」の中に含めようとする法律を立法した場合には、24条2項の「家族」の文言に抵触して違憲となる。
∵ 「家族」の範囲
上記のように、「家族」は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として「婚姻」という枠組みが設けられていることを前提として、その立法政策に付随する形で同一の目的を共有し、その目的を達成するための手段として設けられる枠組みである。
そのため、「家族」の枠組みは、「生殖」によって「子」が生まれるという生物学的な因果関係を離れて観念することはできない。
よって、「家族」の中に含まれる人的結合関係の範囲は、下記の順に決まることになる。
① 婚姻している「男性」と「女性」の関係 (夫婦)
② 婚姻している「母親」から産まれた「子」とその「夫婦」との関係 (親子)
③ 婚姻していない「母親」から産まれた「子」とその「母親」との関係 (親子)
④ 婚姻している「母親」から産まれた「子」であるが、その「母親」の「夫」に嫡出否認された場合の「子」とその「母親」との関係 (親子)
⑤ 「子」の「父親」であると認知した者との関係〔あるいは『子』の親権を得た『父親』との関係〕 (親子)
このように、婚姻している「夫婦」と、自然生殖の過程を経て生まれてくる「子」とその「親」との関係を規律する「親子」による枠組みを骨格として範囲が決まることになる。
これは、「自然血族」である。
これらの関係が「家族」となるのは、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的によって「婚姻」という枠組みが設けられており、その「婚姻」と同一の目的を共有する形で、生物学上の血のつながりを持つ親子関係を明確にすることを意図した統一的な枠組みといえるからである。
⑥ 「自然血族」の「親子」の関係に擬制して位置付けられる「養子縁組」による「親子」の関係
自然生殖によって生じる「親子」の関係を規律する「自然血族」の枠組みを基本として、その骨格を維持したまま、その骨格に当てはめる形で法的に「親子」の関係として扱う制度が定められることがある。
これは、「法定血族」である。
∵ 結論
このように、24条2項の「家族」の中に含めることのできる人的結合関係の範囲は、「家族」の枠組みが「婚姻」と同一の目的を共有してその目的を達成するための手段として「婚姻」の枠組みとの間で整合性を保つ形で統一的に定められることによる内在的な限界がある。
そして、その限界は、「婚姻」している「夫婦」と、「生殖」によって子が生まれるという生物学的な因果関係を想定した「親子」の関係による「自然血族」と、その「自然血族」の枠組みを基本として、その骨格を維持したまま、その骨格に当てはめる形で位置付けられる「法定血族」までをいう。
まとめると、「家族」とは、「婚姻」している「夫婦」と、「親子」の関係によって結び付けられる「血縁関係者」のことを指す。
24条2項の「家族」の範囲
24条2項の「家族」の範囲は、下記の説に整理することができると考える。
◇ 同性婚訴訟の福岡地裁判決では、「「家族」の概念については憲法24条の制定過程からすれば夫婦及びその子の総体を中心とする概念であると理解されるものの、」と述べている。
これは、もともと①を前提として理解していると考えられる。
◇ 「夫婦別姓訴訟」の最高裁判決では、①か②を採用しているように見える記述がある。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) そこで,民法における氏に関する規定を通覧すると,人は,出生の際に,嫡出である子については父母の氏を,嫡出でない子については母の氏を称することによって氏を取得し(民法790条),婚姻の際に,夫婦の一方は,他方の氏を称することによって氏が改められ(本件規定),離婚や婚姻の取消しの際に,婚姻によって氏を改めた者は婚姻前の氏に復する(同法767条1項,771条,749条)等と規定されている。また,養子は,縁組の際に,養親の氏を称することによって氏が改められ(同法810条),離縁や縁組の取消しによって縁組前の氏に復する(同法816条1項,808条2項)等と規定されている。
これらの規定は,氏の性質に関し,氏に,名と同様に個人の呼称としての意義があるものの,名とは切り離された存在として,夫婦及びその間の未婚の子や養親子が同一の氏を称するとすることにより,社会の構成要素である家族の呼称としての意義があるとの理解を示しているものといえる。そして,家族は社会の自然かつ基礎的な集団単位であるから,このように個人の呼称の一部である氏をその個人の属する集団を想起させるものとして一つに定めることにも合理性があるといえる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
損害賠償請求事件 最高裁判所大法廷 平成27年12月16日 (PDF)
◇ 国(行政府)は下記のように述べている。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(イ)しかし、現行民法典には「家族」という言葉は存在せず、少なくとも民法の観点からは「家族」を厳密に定義することは困難であるが(大村敦志「家族法(第3版)」23ページ・乙第35号証)、一般的な用語としての「家族」は、「夫婦の配偶関係や親子・兄弟などの血縁関係によって結ばれた親族関係を基礎にして成立する小集団」を意味するものとされている(新村出編「広辞苑(第7版)」560ページ)。……(略)……
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【東京一次・第1回】控訴答弁書 令和5年6月23日 PDF
<理解の補強>
【参考】家族関係の基本知識 2022.12.19
【参考】血族について学ぼう!範囲や親族・姻族との違いを詳しく解説 2021.8.9
24条2項の「個人の尊厳」と「両性の本質的平等」の適用対象
24条2項の「個人の尊厳」と「両性の本質的平等」の文言が適用される対象を検討するために、24条2項の条文の読み方や意味を整理する。
〇 読み方と意味
24条2項の「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項」の「並びに」と「及び」の読み方を整理する。
・ A、B、C、D、E 並びに F
・ F = x 及び y に関するその他の事項
この文を図にすると、下図のようになる。
〇 「個人の尊厳」と「両性の本質的平等」の適用対象
次に、24条2項の「個人の尊厳」と「両性の本質的平等」の文言が適用される対象を検討する。
24条2項の「個人の尊厳」と「両性の本質的平等」の文言は、「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項」に対して適用される。
そのため、この範囲に含まれない場合については、24条2項の「個人の尊厳」と「両性の本質的平等」は適用されない。
論じている対象の違い
この名古屋地裁判決は、「夫婦同氏制大法廷判決」(平成27年12月16日)が示した基準を用いて、「親子」にも「親子」の関係を基本とした「兄弟」「姉妹」などにも含まれない「同性間の人的結合関係」を対象とした制度を立法していないことが憲法24条2項に違反するか否かを検討しようとしている。
しかし、「夫婦同氏制大法廷判決」が論じている対象は、具体的な法律上の制度が存在することを前提として、その制度の内容が「個人の尊厳」と「両性の本質的平等」に立脚しているか否かを問うものであり、「法律」の内容が問われているのに対して、この名古屋地裁判決が論じている対象は、憲法24条2項の「家族」が「要請」しているか否かを問うものであり、「憲法」の規範の意味そのものが問われているものである。
これらは、論じている対象の次元が異なっている。
そのため、この名古屋地裁判決の中で問われている論点について、「夫婦同氏制大法廷判決」の示した基準を用いて結論を導き出すことができるかのように論じている部分は誤りである。
また、この名古屋地裁判決は「夫婦同氏制大法廷判決」の示した基準を基にして、その基準を基にして憲法上の規範の意味を明らかにしようとするのであるが、その「夫婦同氏制大法廷判決」の内容は憲法を解釈することによって導き出されたものであり、決して憲法よりも上位にある基準や原則として示されたものではない。
よって、「夫婦同氏制大法廷判決」が示した基準を基にして「法律」の内容がその基準に適合するか否かを判断することができる場合はあるとしても、「夫婦同氏制大法廷判決」が示した基準を基にして「憲法」の内容そのものを改変することはできないのであり、これによって憲法上の規範が制度を立法することを「要請」しているか否かを判断するための基準とすることはできない。
分かりやすくいうと、法律の内容が憲法に違反しているか否かを判断するための基準(違憲審査基準)を用いて、憲法の規範の意味を変更することはできないということである。
◇ 本来の上下関係
憲法24条2項
↓
(『婚姻及び家族』の意味を検討)
↓
制度を立法することを「要請」しているか否かの結論
憲法24条2項
↓
「夫婦同氏制大法廷判決」の違憲審査基準
↓
「法律」の内容
◇ この名古屋地裁判決の混乱した説明
憲法24条2項
↓
「夫婦同氏制大法廷判決」の違憲審査基準
↓
憲法24条2項 … (憲法を解釈した違憲審査基準を、その憲法の上位規範と位置付けて再解釈)
↓
制度を立法することを「要請」しているか否かの結論
この名古屋地裁判決が混乱した説明となっているのは、「夫婦同氏制大法廷判決」は憲法の内容を解釈した結果として導かれるいわば下位法に当たる基準であり、これに基づいて法律の内容が憲法に違反するか否かを判断するためのものであるにもかかわらず、それを憲法よりも上位法として位置付けて、それによって憲法の規範の意味を変更し、憲法24条2項の「要請」の有無を判断しようとするものとなっているからである。
このような説明は、法秩序の階層構造を損なわせるものであり(下剋上解釈論)、解釈の手続きとして誤っている。
14条1項の「平等」と24条2項の「両性の本質的平等」の射程
14条1項の「平等」と24条2項の「両性の本質的平等」の適用方法については、下記の通りである。
〇 14条の「平等」
個人と個人の間の「平等」を審査するものである。
(『婚姻及び家族』の制度についても審査することが可能である。)
〇 24条2項の「両性の本質的平等」
「婚姻及び家族」の制度について、「男性」と「女性」の間の「平等」を審査するものである。
下記では、①②③④でこれまでの判例とその考察を述べ、➄でこの「名古屋地裁判決」の誤りを検討する。
① 最高裁判決
最高裁判決の「再婚禁止期間大法廷判決」(平成27年)と「夫婦同氏制大法廷判決」(平成27年)は、「婚姻及び家族に関する事項」であり、かつ、「男性」と「女性」の間の「平等」について問われた事例である。
そのため、14条1項の「平等」による審査と、24条2項の「両性の本質的平等」による審査が同時に行われている。
② 札幌地裁判決
「同性婚訴訟の札幌地裁判決」では、「同性間の人的結合関係」が「婚姻及び家族に関する事項」であることを前提に、14条1項の「平等」に違反するとした。
しかし、この判断は前提として下記の点で誤っている。
◇ 「婚姻及び家族に関する事項」ではない
「同性間の人的結合関係」が「親子」や「親子」の関係を基本として導かれる「兄弟」「姉妹」などに含まれないのであれば、「婚姻及び家族に関する事項」として取り上げることはできない。
◇ 「カップル間不平等論」の誤り
「カップル」という「二人一組」を取り上げて比較を試みているが、これは「法人格」を取得していないことから、「権利能力」を有しておらず法主体としての地位を認められておらず、法律論として比較することはできない。
◇ 「性愛に基づく不平等論」の誤り
「異性愛者」と「同性愛者」を比較している部分があるが、そもそも法制度は個々人の内心を審査しておらず、「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかによって区別取扱いをしている事実はない。
③ 国(行政府)の主張
国(行政府)は、「同性婚訴訟の札幌地裁判決」が、「婚姻及び家族に関する事項」に当たると述べながら、24条2項の「両性の本質的平等」の部分に違反しないとしているにもかかわらず、14条の「平等」には違反すると述べることは、特異であると述べている。
④ 当サイトの認識
筆者は、当サイト「同性婚訴訟 大阪地裁判決の分析」のページで、「同性婚訴訟の札幌地裁判決」が「同性間の人的結合関係」について、「婚姻及び家族に関する事項」であると述べている点について、その「同性間の人的結合関係」が「親子」や「親子」の関係を基本として導かれる「兄弟」「姉妹」などに含まれないのであれば、「婚姻及び家族に関する事項」に含まれないため、誤りであることを述べた。
そして、「婚姻及び家族」に含まれない以上は、24条2項の「両性の本質的平等」も適用されることはないとした。
また、「同性婚訴訟の札幌地裁判決」は、下記の点でも誤っているとした。
・ 「カップル間不平等論」になっていること
・ 「性愛に基づく不平等論」になっていること
これらに加えて、国(行政府)が、「婚姻及び家族に関する事項」について14条1項の「平等」の審査を行うときには、より厳格な24条2項の審査が同時に行われていることから、「同性婚訴訟の札幌地裁判決」が24条2項に違反しないと述べながら、14条1項に違反すると論じている点は、最高裁判決に示された基準から見ても特異であると批判している点について、「婚姻及び家族に関する事項」に当てはまる場合においては妥当であると考えていた。
しかし、国(行政府)が示している最高裁判決の内容は「再婚禁止期間大法廷判決」と「夫婦同氏制大法廷判決」であり、いずれも「婚姻及び家族に関する事項」が問われた上で、かつ、「男性」と「女性」の間での「平等」が問題となっていた事例である。
そのため、14条1項の「平等」と、24条2項の「両性の本質的平等」という「男性」と「女性」の間の「平等」についての審査が同時に行われる事例であった。
しかし、「婚姻及び家族に関する事項」であっても、例えば、「長男」と「次男」の間、あるいは、「長女」と「次女」の間についての「平等」が問われる事例については、それは「男性」と「女性」の間の「平等」が問われる事例ではない。
そのため、この事例に対しては、24条2項の「両性の本質的平等」を適用することはできない。
そうなると、筆者としては、「同性婚訴訟の札幌地裁判決」については、
◇ 「婚姻及び家族に関する事項」ではない
「同性間の人的結合関係」が「親子」や「親子」の関係を基本として導かれる「兄弟」「姉妹」などに含まれないのであれば、「婚姻及び家族に関する事項」には当てはまらないにもかかわらず、「婚姻及び家族に関する事項」として扱っていること
◇ 「カップル間不平等論」の誤り
「カップル」という「二人一組」を取り上げて比較を試みているが、これは「法人格」を取得していないことから、「権利能力」を有しておらず法主体としての地位を認められておらず、法律論として比較することのできる対象ではないこと
◇ 「性愛に基づく不平等論」の誤り
個々人の「性愛」の有無や、「性愛」を有する場合にどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いをしている事実はないにもかかわらず、それによる区別取扱いがあるとしていること
などの点で、誤っているという前提を置いた上で、国(行政府)が、「婚姻及び家族に関する事項」について14条1項の「平等」に違反するか否かが審査されるときには、24条2項と整合的に審査されるべきであると述べ、「同性婚訴訟の札幌地裁判決」が24条2項に違反しないとしながらも14条1項に違反すると述べている点は、最高裁判決の示した基準から見ても特異であるとの主張は、上記のような誤りが正されている場合においては妥当なものと考えていたが、認識を修正する必要がありそうである。
国(行政府)の主張は、最高裁判決の示した基準がもともと「男性」と「女性」の間の「平等」を審査する場合を前提とするものとして解説されている事例であることを十分に認識しないままに反論を試みている可能性があり、これに一定の理由があると考えていたことについては妥当でない可能性がある。
これを前提とすれば、国(行政府)は「同性婚訴訟の札幌地裁判決」の内容が不適切であることを指摘する際には、14条1項と24条2項の整合性に関する論点よりも、筆者が先ほど示した三つの論点を中心として指摘することの方が妥当であると思われる。
➄ 名古屋地裁判決
この名古屋地裁判決では、「⑶ 憲法24条2項に違反するかについて」の項目の「イ」第四段落の第四文において、24条2項の「両性の本質的平等」の文言は、「両性が必ずしも関わらない家族の問題をも含めて規律している」と述べている。
そのため、24条2項の「両性の本質的平等」の文言は、「家族」の問題であれば、「男性」と「女性」の間に限られず「平等」を審査できると考えているようである。
しかし、24条2項の「両性の本質的平等」の文言には、「平等」が問われる対象として「両性」のように「男性」と「女性」の間の比較がテーマとなっていることが明確に記されていることから、これを「男性」と「男性」の間(長男と次男の間など)や、「女性」と「女性」の間(長女と次女の間など)にまで、比較することのできる対象の範囲を広げることはできない。
また、上記のように、最高裁判決の「再婚禁止期間大法廷判決」と「夫婦同氏制大法廷判決」で示した24条2項と14条1項の整合性の基準は、前提として「男性」と「女性」の間の「平等」が問われている事例であり、この名古屋地裁判決の内容はそれらの最高裁判決の内容に沿った判断であるとはいえない。
よって、この名古屋地裁判決のこの点の説明は誤っている。
|
あらゆる法制度 個人間の比較 |
「婚姻及び家族」の制度 | ||
|
個人間の比較 |
両性間の比較 | ||
| 14条1項の「平等」 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 24条2項 の「平等」 | × | × | 〇 |
| ↑ | ↑ | ||
|
この名古屋地裁判決のいう 家督相続制度の復活の是非 |
夫婦同氏制大法廷判決 再婚禁止期間大法廷判決 |
||
※ 24条2項は、「婚姻及び家族」の制度で、かつ「両性間」の「平等」が問われた場合にのみ審査することができ、それ以外の場合は審査することができない。
※ 14条1項と24条2項が重なる部分は、「婚姻及び家族」の制度において「両性間」の「平等」が問われている場合のみである。
この場合、24条2項の「平等」に違反すると判断された場合には、同時に14条1項の「平等」にも違反することになる。(これについて、14条1項よりも24条2項の方が審査密度が高い(厳格)という考え方によれば、『14条1項には違反しないが、24条2項に違反する』のように判断が分かれる場合も考えられる。〔その逆の判断が出ることはない。〕)
ただ、この点の指摘ができる場合とは、前提として「婚姻及び家族」の制度について問題となっており、かつ「両性間」の「平等」が問われている場合に限られる。
そのため、「両性間」の「平等」が問われているわけではない場合や、そもそも「婚姻及び家族」の制度に含まれない場合については、この点の指摘を行うことはできない。
この訴訟の事案では、そもそも「婚姻及び家族」の制度に含まれないという点で、24条2項における「平等」を審査する前提を欠いており、それが「両性」であるか否かを問う以前の問題によって審査の対象外となる。
※ 「婚姻及び家族」の制度に含まれない関係について14条1項の「平等」が問われる場合があるとしても、それは「婚姻している者(既婚者)」と「婚姻していない者(独身者)」との間の比較において、「婚姻している者(既婚者)」が婚姻制度の立法目的を達成するための手段として不必要に過大な優遇措置を得るものとなっていないかどうかである。
もし「婚姻している者(既婚者)」が婚姻制度の立法目的を達成するための手段として不必要に過大な優遇措置を得るものとなっていた場合には、その優遇措置に関する規定が個別に失効することによって格差が是正されることになるというものである。
カップル間不平等論の誤り
憲法は「個人の尊厳」の原理の下、「個人主義」に基づいている。
また、民法上で「権利能力」を有し、法主体としての地位を有するのは「自然人」と「法人」である。
〇 権利能力
権利能力(ケンリノウリョク) 宅建用語集
民法3条:権利能力とは?わかりやすく解説【権利能力平等の原則】 2021年2月21日
権利能力 Wikipedia
【動画】1分で「権利能力」がわかる! 【#1 民法を1分で勉強シリーズ・総則編】 2021/02/14
【動画】基本講義「民法」単元3後半 権利能力・意思能力・行為能力 2020/03/22
【動画】〔独学〕司法試験・予備試験合格講座 民法(基本知識・論証パターン編)第8講:権利能力と胎児 〔2021年版・民法改正対応済み〕 2021/05/28
【動画】【行政書士試験対策】権利能力//権利・義務の主体となれるのは? 2023/03/25
【動画】司法書士 はじめの一歩 ~Topic.07 胎児は「人」なのか?~【権利能力】 2020/12/18
【動画】民法本論1 01権利能力 2011/04/11
【動画】2021応用インプット講座 民法5(総則5 権利能力) 2020/11/20
【動画】公務員試験対策 民法・権利能力・意思能力・責任能力・行為能力 2021/09/21
◇ 自然人
自然人は出生によって「権利能力」を取得し、死亡することによって「権利能力」が消滅する。
民法
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第二章 人
第一節 権利能力
第三条 私権の享有は、出生に始まる。
2 外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○政府委員(工藤敦夫君)
(略)
民法は、権利能力については出生に始まり死亡に至るまでということでございますが、満二十年をもって成年とすると。……(略)……
(略)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第116回国会 参議院 予算委員会 第3号 平成元年10月24日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
民法は我々の生活関係を権利と義務に分解して規定し、規律するが、この権利及び義務の帰属主体となりうる資格を権利能力という。民法は、権利能力はあらゆる自然人が平等に有するとしているが、このことは近代法によって確立された原則であり、近代法が発達する以前の時代、すなわち奴隷制が存在した時代や、封建時代には、人によっては権利能力を認められない自然人も存在したのである。人は権利能力があって初めて法律的に自由な経済活動が可能となるのであり、その権利能力を自然人に平等に認めるのは、憲法の要請でもある。
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
権利能力の取得時期について、民法は「出生に始まる」としている。この出生がいつか、ということについては諸説あるが、民法の解釈としては、生まれてきた子供の体全体が母体から出たときを基準にする、いわゆる「全部露出説」が通説である。
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
権利能力の喪失時期、つまり死亡の時期については、心臓停止説、つまり、心臓が不可逆的に停止した時を基準とする説が通説である。最近では、脳死を基準とすべきであるという説も有力であるが、倫理や遺族感情などの問題とも絡み合い、脳死を基準とするのは困難であることが指摘されている。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第15課 民法―権利義務の主体(自然人その1) (下線・太字は筆者)
自然人 Wikipedia
人の始期 Wikipedia
◇ 法人
「法人」の「権利能力」は法律の手続きによって形成される。
民法
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(法人の成立等)
第三十三条 法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。
2 (略)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法人 Wikipedia
このことから、14条の「平等原則」を用いて審査する場合においても、「権利能力」(法人格)を有し、法主体としての地位を認められている個々の自然人(あるいは法人)を対象として比較することになる。
この点について、国(行政府)の主張でも触れられている。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ア しかしながら,憲法14条1項が規定する法の下の平等とは,個人と個人の間の平等をいい,同項が禁止する不合理な差別も,個人と他の個人との間の不合理な差別をいうものと考えられる(例えば,芦部信喜教授は,法の下の平等は「個人権」であり,「個人尊重の思想に由来」すると説明している(芦部信喜〔高橋和之補訂〕「憲法第七版」129 ページ)。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【大阪・第6回】被告第4準備書面 令和3年2月19日 PDF (P4)
これに対して、この判決は「カップル」という「二人一組」を取り上げて、それを一つの単位と考えて比較を試みようとしている部分がある。
しかし、「カップル」という「二人一組」については、「権利能力」を有していないため、法主体としての地位を認められていない。
そのため、法律論上で比較を行うことのできる対象として取り上げることはできない。
もし「カップル」という「二人一組」を取り上げた形で比較を行いたいのであれば、法人格を取得する手続きを行い、「権利能力」を備えて「法人」としての地位を明らかにすることが必要である。
自然人が「二人一組」の人的結合関係(この判決のいう『カップル』と称するもの)を形成したとしても、それだけでは「権利能力」を取得することにはならず、そこに何らかの法的な主体性を認めることはできないのである。
そのため、これを法律論上の比較対象として取り上げることはできない。
下図で、「権利能力」(法人格)を有する者同士を比較の対象とすることはできるが、「カップル」や「トリオ」など「権利能力」(法人格)を有しない単位を用いて比較することはできないことを示す。
婚姻が成立するための「条件」
ある組み合わせにおいては「婚姻」することができるが、ある組み合わせにおいては「婚姻」することができない。
これは、婚姻を成立させるための要件が定められていることによるものであり、「条件」ということができる。
下図は、立法目的を達成するための手段として設けられた「婚姻」という制度を利用する場合の「条件」である。
婚姻制度を利用するための「条件」を満たしているのであれば、個々人は平等に婚姻制度を利用することができる。
ここで、個々人を「区別取扱い」しているという事実はない。
この「条件」に従った形で「婚姻」することができる場合の組み合わせと、「条件」を満たさずに「婚姻」することができない場合の組み合わせを下図に示す。
次に、婚姻の「条件」の内容について、これが個々人について「区別」をするものと考えるべきなのかを検討する。
〇 比較の視点 A (個人に着目した区別の存否)
憲法は「個人の尊厳」の原理を定めており、自然人は「個人主義」の下に各々「自律的な個人」として生存していくことを予定している。
そのため、権利・義務を関係づけることができる法主体としての地位は、「個人」に属する。
よって、憲法上で比較を行う際の主体となるのは、「個人」と別の「個人」との間である。
また、憲法14条の「平等原則」(法の下の平等)についても、「個人権」であり、「個人と個人の間の平等」をいう。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ア しかしながら,憲法14条1項が規定する法の下の平等とは,個人と個人の間の平等をいい,同項が禁止する不合理な差別も,個人と他の個人との間の不合理な差別をいうものと考えられる(例えば,芦部信喜教授は,法の下の平等は「個人権」であり,「個人尊重の思想に由来」すると説明している(芦部信喜〔高橋和之補訂〕「憲法第七版」129 ページ)。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【大阪・第6回】被告第4準備書面 令和3年2月19日 PDF (P4) (下線は筆者)
◇ 身長の高い人:婚姻することができる
◇ 身長の低い人:婚姻することができる
ここに「身長」による「区別」は存在しない。
◇ 年収の多い人:婚姻することができる
◇ 年収の少ない人:婚姻することができる
ここに「年収」による「区別」は存在しない。
◇ 生殖能力のある人:婚姻することができる
◇ 生殖能力のない人:婚姻することができる
ここに個々人の「生殖能力」による「区別」は存在しない。
(これは、個々人の個別特性としての生殖能力の有無であり、人と人とを組み合わせた場合に生殖可能性のある組み合わせとなるか否かを問うものではない。そのため、婚姻制度の内容が一般的・抽象的に自然生殖可能性のある組み合わせを対象として制度を設けていることについては、これとは別の論点である。)
◇ 婚姻適齢を満たしている者:婚姻することができる
◇ 婚姻適齢を満たしていない者:婚姻することができない
ここに「年齢」による「区別」が存在する ⇒ 合理的な理由の存否の判断へ
◇ 男性:「異性」と婚姻することができるが、「同性」と婚姻することができない
◇ 女性:「異性」と婚姻することができるが、「同性」と婚姻することができない
ここに男女の「性別」による区別取扱いはない
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
しかしながら,憲法14条1項が規定する法の下の平等とは,同一の事情と条件の下では均等に取り扱うことを意味すると解されるところ(芦部信喜〔高橋和之補訂〕「憲法第七版」132ページ参照),本件規定の下では,男性も女性も異性とは婚姻をすることができる一方で,どちらの性も同性とは婚姻をすることは認められていないのであるから,本件規定が性別を理由に差別的取扱いを生じさせていると評価することはできない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【東京二次・第3回】被告第2準備書面 令和3年11月30日 PDF
◇ 男性:婚姻している場合に、別の人と重ねて婚姻することはできない
◇ 女性:婚姻している場合に、別の人と重ねて婚姻することはできない
ここに男女の「性別」による「区別」は存在しない
◇ 男性:「婚姻適齢に満たない者」と婚姻することができない
◇ 女性:「婚姻適齢に満たない者」と婚姻することができない
ここに男女の「性別」による「区別」は存在しない
◇ 男性:婚姻の際に相手方の「女性」の「氏」を選べる
◇ 女性:婚姻の際に相手方の「男性」の「氏」を選べる
ここに男女の「性別」による「区別」は存在しない
◇ 男性:「再婚禁止期間」は存在しない
◇ 女性:「再婚禁止期間」が存在する場合がある
ここに男女の「性別」による「区別」が存在する ⇒ 合理的な理由の存否の判断へ
判断の結論として、いくつかの方法がある。
・女性の再婚禁止期間に合理的な理由がある場合には続ける
・女性の再婚禁止期間に合理的な理由がある場合、それに合わせて、男性にも再婚禁止期間を設けて差異を解消する (男性にも冷却期間として設けるべきとの説がある)
・女性の再婚禁止期間に合理的な理由がない場合には撤廃して差異を解消する
〇 比較の視点 B (相手との関係性に着目する考え方)
「男女二人一組」の組み合わせは婚姻することができるが、それ以外の組み合わせでは婚姻することができない。
○ 一定の条件を満たした「男女二人一組」
× 近親者との人的結合関係
× 三人以上の人的結合関係
× 三人一組の人的結合関係
× 四人一組の人的結合関係
× 五人一組の人的結合関係
× 六人一組の人的結合関係
× __人一組の人的結合関係
× 婚姻適齢に満たない者との人的結合関係
× 同性同士の人的結合関係
ただ、これらの組み合わせがそれぞれ「婚姻」の対象なるかどうかを考えるとしても、「人的結合関係」そのものについては「権利能力」を有しておらず、法主体としての地位を認められていないため、法律論としてはこれらの「人的結合関係」を単位とする形で比較することはできない。(「カップル間不平等論」になってはならない。)
そのため、これらの組み合わせがそれぞれ「婚姻」の対象となるかどうかについて論じる場合であっても、それは「権利能力」を有し、法主体としての地位を認められている個々の自然人を単位として考えることが必要である。
これら、婚姻制度の対象となる組み合わせと、対象とならない組み合わせが存在することは確かであるが、これを「区別取扱い」と考えるべきであるかは疑問がある。
14条の「平等原則」において「区別取扱い」が審査される場合とは、常に「権利能力」を有して法主体としての地位を認められている者と、もう一方の「権利能力」を有して法主体としての地位を認められている者との間を比較するものである。
しかし、この制度の対象となる組み合わせと、対象とならない組み合わせが存在することについては、「権利能力」を有する法主体としての地位を認められている者を比較するものとは異なるため、14条の「平等原則」で論じられる「区別取扱い」と同様の文言が妥当する事例と考えていいのかは検討の余地があるように思われる。
なぜならば、誰もが「近親者」「二人以上の者」「婚姻適齢に満たない者」「同性の者」との間で婚姻することはできないことに違いはなく、その「誰も」にあたる個々人に着目して「区別取扱い」をしているという事実はないからである。
これを「人的結合関係」の視点で取り上げたときに、それを「区別取扱い」と表現してしまうと、先ほど指摘したような「権利能力」を有しておらず法主体としての地位を認められていない単なる「人的結合関係」を単位として比較を試みるという誤りを引き起こしやすくなるのである。(「カップル間不平等論」の誤りに陥りやすくなる。)
このような誤った論じ方を誘発することは相応しくないため、これを「区別取扱い」と表現するべきではないように思われる。
〇 比較の視点 C (特定の個人との間での婚姻の可否を考えるもの)
「ある特定の人物(婚姻適齢は満たしている)」と婚姻できるか検討する場合に、婚姻の「条件」を満たす者と満たさない者との間で婚姻の可否が分かれる。
◇ その者との間で異性に当たる場合には婚姻できる
→ 「性別」による区別?
◇ その者との間で近親者等でない場合には婚姻できる
→ 「社会的身分」による区別?
◇ その者との間で一人だけは婚姻できる
→ 「機会・人数・希望者同士」による区別?
◇ その者との間で婚姻適齢を満たしている場合には婚姻できる
→ 「年齢」による区別?
これは、「ある特定の人物(婚姻適齢は満たしている)」と婚姻することができるか否かという視点で考えたときに、婚姻の「条件」を満たす者と満たさない者との間に違いがあるという点に注目した議論である。
そのため、婚姻するための一般的・抽象的な「条件」の中で、一般的・抽象的な法主体としての地位を有する者を比較するものとは視点が異なっている。
しかし、この視点によってこれを「区別」であると考えたとしても、結局は、制度の内容そのものを一般的・抽象的な法主体としての地位を有する者をどのように扱うかという視点にまで遡り、その制度の内容について、立法目的の合理性と、その立法目的を達成するための手段の合理性を審査することによって、同様の判断が導かれることになる。
すると、婚姻制度の立法目的とその立法目的を達成するための手段の合理性(その枠組みによる婚姻制度を利用する場合に必要となる「条件」の合理性)を審査する場合と同様の結論が導かれることになる。
結局、それは「婚姻」するために必要となる「条件」を満たすか否かという問題に収まることになる。
ただ、「婚姻」という概念そのものに含めることのできる人的結合関係の範囲には内在的な限界があるし、憲法24条は「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めており、この訴訟で問われている「同性間の人的結合関係」については、これを満たさないという点で憲法14条1項の「平等原則」によって審査するという前提にない。
そのため、これらについて、「区別取扱い」と表現することが妥当であるかという論点に関わらないままに結論が導き出される問題であるといえる。
「目的」の意味の混同
「目的」の意味には多義性がある。どのような文脈で使われているかによって、その意味するところは異なっているため、注意して読み解く必要がある。
① 「国の立法目的」の意味
概念や制度の枠組みが導かれ、定められる際の立法目的にあたるもの。
例
・「会社法」の立法目的
・「宗教法人法」の立法目的
・婚姻制度の立法目的 ⇒ 「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消すること
② 「制度が機能することによって生じる結果(目的)」の意味
ある制度が機能すると、何らかの結果が生じることになるが、その結果の部分を「目的」と表現することがある。
制度 ⇒(機能すると)⇒ 結果(目的)
例
・「会社」は、営利を目的として事業を行う社団法人である。【動画】
→ 会社が機能すると、営利(経済的な利益)が生じる。
・「宗教法人法」は、宗教団体に法人格を与えることを目的として作られた法律である。
→ 宗教法人法が機能すると、宗教団体に法人格が与えられる。
・婚姻制度の目的は、次世代再生産の可能性のある組み合わせを優遇することである。
→ 婚姻制度が機能すると、次世代再生産の可能性のある組み合わせが優遇される。
この機能面に着目することによって、ある制度を、他の様々な制度との間で区別して理解することが可能となる。
これは、同じ機能を持ち、同じ結果を生じさせる制度であれば、異なる名前を付けている意味がないからである。
そのため、この意味で「目的」という言葉が使われている場合には、その制度を他の制度との間で区別して理解しようとする文脈であることを意味する。
③ 「個々人の利用目的」の意味
個々人がどのような意思をもって制度を利用・活用するかに関するもの。
例
・私の「会社」は営利を目的としているわけではなく、社会貢献が目的である。
・この「宗教団体」は人を幸せにすることを目的としている。
・私は子供をつくることを目的として婚姻する。
下図は、婚姻制度についての、「① 国の立法目的」と、「② 制度が機能することによって生じる結果(目的)」と、「③ 個々人の利用目的」の位置づけである。
この判決では、②の「制度が機能することによって生じる結果(目的)」の意味で用いられている「目的」の文言や、③の「個々人の利用目的」についての「意義」の意味を拾って、これがあたかも①の「国の立法目的」の意味であるかのように意味の位置付けを変更した上で論じようとしている部分があり、誤っている。
「性愛」による区別取扱いは存在しないこと
婚姻制度は「性愛」を保護することを目的とする制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いをする制度ではないし、「性愛」に基づいて制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもない。
そのため、婚姻制度は「性愛」による区別取扱いをする制度であるとはいえない。
「性愛」による区別取扱いを行う制度とは、例えば下記のようなものが該当する。
【参考】<わいせつ行為で処分された教員は9年連続200人以上>愛知医科大准教授が小児性愛障害診断テストを開発中「日本版DBSだけでは子どもへの性犯罪を防げない」 2023.09.28
これは、個々人の「性愛」の有無や、「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して、その審査の結果によって区別取扱いを行うものということができる。
これは、人の内心を審査した結果に応じて不利益を課すものであるから、「内心の自由」を侵害するものであり、憲法19条の「思想良心の自由」や20条1項の「信教の自由」に抵触して違憲となる。
刑事法の分野においては、その者の行った行為の外形を法の基準に当てはめることによって、その者が有罪であるか否かを判断することはできるが、その者の内心そのものを取り上げてそれを罰したり、不利益を課すことは許されないからである。
このような事件の発生を防ぐための対策としては、下記のような方法が考えられる。
◇ 一般に研修の機会を提供する。
◇ 希望者にはカウンセリングを実施する。
◇ より高いレベルの研修を希望する者に対して特典を設けるなどして訓練の機会を増やす。
◇ すべての者を対象として、どのような行為がセクハラやわいせつ行為に当たり刑事的な事件として取り扱われるのかについて詳しく出題される試験を実施する。
これらの方法により、事件が発生する可能性を減らしていくことは可能であると考えられる。
しかし、個々人の内心そのものを取り上げて不利益を課すことは許されない。
【動画】家庭教師の時に… 子どもへの“性加害”10回以上くり返した男性の告白 政府なぜ見送り?「日本版DBS」【news23】 2023/09/26
【動画】「思春期前の男児にときめきを…」子どもへの“性加害”10回以上 小児性愛障害の男性が「実名」「顔出し」で証言【news23】 2023/10/08
この事件も「小児性愛者」であることが刑事責任の対象となっているのではなく、その者の行為が予め定められている法の規範に抵触したことが問題となっているものである。
たとえ「小児性愛者」を称する者でないとしても、その行為をすれば法に抵触することは同じである。
睡眠導入剤飲ませ、女児に性的暴行の疑い 39~55歳の5人逮捕 2024/1/15
「人格」とはどういう意味か
この分野の判決では、下記のように「人格」に関する文言を根拠として法的審査を行おうとしている場合がある。
・人格的尊厳 (大阪地裁判決)(名古屋地裁判決では『人の尊厳』が登場)
・人格的自律 (福岡地裁判決〔人格的自律権として登場〕)
・人格的生存 (東京地裁判決)(名古屋地裁判決)
・人格的利益 (東京地裁判決)(大阪地裁判決)(名古屋地裁判決)(福岡地裁判決)
・人格権 (大阪地裁判決)(東京地裁判決〔最高裁判決の引用として登場〕)(名古屋地裁判〔最高裁判決の引用として登場〕)
しかし、その意味を理解して使っているのか疑わしい。
そこで、「人格的尊厳」、「人格的自律」、「人格的生存」、「人格的利益」、「人格権」の意味を下記でまとめる。
◇ 人格的尊厳
人間として尊重されること、あるいは、個人として尊重されることを指す。(個人の尊重・個人の尊厳)
これは、すべての人が持っている普遍的で不可侵のものであり、他人に譲渡したり放棄したりすることはできない性質である。
◇ 人格的自律
個人が自分の意思に基づいて行動し、自分の人生を自分自身で決めること、また、その自己決定する能力を指す。(自己決定権)
◇ 人格的生存
人が生命を維持し、生存し、生活していくために必要となる(最低限の)ものを指す。
例えば、生命、身体、健康、住居、食料、衣服などがある。
・身体的側面:生命・身体・健康・自由・貞操など
・精神的側面:名誉・信用・氏名・肖像・プライバシーなど
◇ 人格的利益
個人の人格的生存に不可欠な利益であり、他者から侵害されることなく確保されるべきものを指す。
・身体的側面:生命・身体・健康・自由・貞操など
・精神的側面:名誉・信用・氏名・肖像・プライバシーなど
◇ 人格権
個人が社会生活の上で有する人格的利益を保護するための権利を指す。
・身体的側面:生命・身体・健康・自由・貞操など
・精神的側面:名誉・信用・氏名・肖像・プライバシーなど
・名誉:人の価値に対する社会の評価
・プライバシー:社会的評価にかかわりのない私的領域
これらの「人格」に関するものは、憲法13条と関わるものである。
「人格的尊厳」は、法律論上において、人間が権利・義務を結び付けることができる法主体としての地位を認められるかに関わるものであるが、それ以上に何か具体的な内容を引き出すことができるものではない。
「人格的自律」は、個人が自由な意思に基づいて意思決定を行うことを正当化する場合に用いられるが、具体的な制度の創設を求めることができるものではない。
「人格的生存」は、個人が生存していくために必要となる最低限のものを指し、その不可欠な利益を「人格的利益」、その利益を保護するための権利を「人格権」と呼んでおり、国家から個人に対する具体的な侵害行為が生じた場合などに用いることがあるが、具体的な制度の創設を国家に対して求めることができるものではない。
よって、これら「人格」に関する文言を根拠として、具体的な制度の創設を国家に対して求めることができるかのような論旨は誤りとなる。
名古屋地裁判決の内容
具体的に、判決の誤りを確認する。
〇 項目のタイトルの文字サイズを拡大したところと、太字にしたところがある。
〇 「性愛」「異性愛」「同性愛」「異性愛者」「同性愛者」に色付けをした。
〇 「カップル信仰論」を前提とした「カップル」「異性カップル」「同性カップル」「男性カップル」や「パートナー」「パートナー関係」「異性パートナー」「同性パートナー」という言葉に色付けした。
〇 「同性間の婚姻」「同性間の婚姻制度」に色付けした。
〇 「同性婚」「同性婚制度」に色付けした。
〇 「特別の規律」に色付けした。
〇 「パートナーシップ」「パートナーシップ制度等」「登録パートナー」「登録パートナーシップ制度」「登録パートナーシップ制度等」「パートナーシップ登録」に色付けした。
〇 「伝統的」「伝統的な家族観」「伝統的な制度及び価値観」に色付けした。
〇 「自然生殖の可能性」に色付けした。
〇 「社会通念」に色付けした。
〇 「社会的な承認」「社会的に承認」「社会的承認」「承認」に色付けした。
〇 「人の尊厳」「個人の尊厳」に色付けした。
〇 「人格的生存」に色付けした。
〇 「人格的利益」に色付けした。
〇 「不利益」に色付けした。
〇 「婚姻及び家族」「婚姻及び家族に関する事項」「婚姻及び家族に関するその他の事項」を太字にした。
〇 主要な文に色付けしているところがある。
〇 リンクを加えた。
〇 読み取りにくい文
この判決には、似ているが少しずつ使われている言葉が違う文が登場する。
これらは、頭の中で同一のものを指していることを明快に描き出すことを難しくする原因となっている。
下記は、順番どおりである。
・男女の生活共同体として、その間に生まれた子の保護・育成、分業的共同生活の維持などの機能を通じ、家族の中核を形成するもの
・男女の生活共同体として、その間に生まれた子の保護・育成、分業的生活共同体の維持を通じ、家族の中核を形成するものである
・上記のような家族の中核としての機能を通じ、男女が共同生活を送りながら、子を産み育て、次世代へ承継していく営み
・男女が共同生活を送りながら、子を産み育て、次世代へ承継していく営み
・男女が共同生活を送りながら、子を産み育て、次世代へ承継していく営みがある
・子孫の生殖を伴う男女の結合関係とそれを中核とする家族関係の安定化
・子孫の生殖
・男女が共同生活を送りながら、子を産み育て、次世代に承継していく営み
・男女の結合関係(婚姻)を中核とし、その間に生まれた子の保護・育成を担うものである
・男女の生活共同体
・生殖と子の保護・育成
・男女の結合関係を中核としてその間に生まれた子の保護・育成の機能を担う
・男女の結合関係を中核とした
・男女の結合関係を中核としてその間に生まれた子の保護・育成の機能を担う
・男女の結合関係を中核としてその間に生まれた子の保護・育成の機能を担う
・法律によって具体化された法律婚制度を同性間に対しても及ぼすこと
・民法及び戸籍法等の法律によって具体化された法律婚制度を及ぼすこと
・同性間に対して現行の法律婚制度を及ぼすこと
・現行の法律婚制度が対象としてきた人的結合関係の範囲をそのまま拡張すること
・現行の法律婚制度をそのまま開放する
・現行の法律婚制度をそのまま開放すること
・同性間に対して現行の法律婚制度を及ぼすこと
・法律により具体化された現行の法律婚制度の対象をそのまま拡大させること
・同性間に対しても現行の法律婚制度を及ぼすこと
・現行の法律婚制度の開放を唯一の選択肢として、発生する効果に差を設けることを絶対に許さない
・現行の法律婚制度と発生させる効果を完全に一致させる
・現行の法律婚制度を同性間に対して及ぼすこと
・現行の法律婚制度をそのまま適用すること
・国による統一された制度によって公証
・国の制度により公証
・国の制度により公証
・国の制度によって公証
・国の制度によって公証
・国の制度によって公証
・国の制度として公証
・国の制度によって公証
・国の制度として公証
・国の制度によって公証
・国の制度によって公証
・国の制度によって公証
・その関係を保護するのにふさわしい効果の付与を受けるための枠組みが与えられる利益
・その関係を保護するのにふさわしい効果の付与を受けるための枠組みが与えられるという利益
・その関係を保護するのにふさわしい効果の付与を受けるための枠組み
・その関係を保護するのにふさわしい効果の付与を受けるための枠組み
・その関係を保護するのにふさわしい効果の付与を受けるための枠組み
・その関係を保護するのにふさわしい効果を付与するための枠組み
・その関係を保護するのにふさわしい効果を付与するための枠組み
・その関係を保護するのにふさわしい効果を付与するための枠組み
・…の関係を保護するのにふさわしい効果としていかなるものを付与するか
・その関係を保護するのにふさわしい効果を付与するための枠組み
・その関係を保護するのにふさわしい効果を付与するための枠組み
・その関係を保護するのにふさわしい効果を付与するための枠組み
◇ 「付与を受ける」
上記の上の五つの「付与を受ける」の文について、文法的には重言となって誤用である。
まず、「付与」の意味は「さずけ与えること」である。
「与える」が動詞であるのに対して、「付与」は名詞である。
その「与える」の意味は「自分のものを他に渡して、その人のものとする」である。
・ 人⇒(与える)⇒
次に「受ける」の意味は、「差し出されたものを自らの手に収める」である。
・ ⇒(受ける)⇒人
よって、「付与を受ける」の意味は、「与えるを受ける」と言っていることになる。
・ 人⇒(与えるを受ける)⇒人
これは同じ行為について「与える」という能動的な面と、「受ける」という受動的な面とを同時に用いるものとなっており、意味が重複していることから、重言となる。
そのため、「付与する」と書くか、「付与される」や「受ける」などの単語だけを使うことが正しいといえる。
◇ 「付与を受けるための枠組みが与えられる」
上記の上の二つの文は、「付与を受けるための枠組みが与えられる」となっている。
この文は、与えたり、受けたりする言葉が繰り返されており、意味不明になりやすい。
・「付与」 = 「与える」
・「受ける」 ⇒ 受動的な意味
・「与えられる」 = 「与える」の受動態
この文を「与える」に統一して表現すると「与えるを与えられるための枠組みが与えられる」となる。
このような内容は日本語の文法として適切ではないため、改めることが望ましいといえる。
【筆者】
インデント(字下げ)を加えて記載したところは、筆者の分析である。
令和5年5月30日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官
平成31年 第597号 国家賠償請求事件
口頭弁論終結日 令和4年12月2日
判 決
当事者等の表示 別紙1当事者目録記載のとおり
主文
1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第1 請求
被告は、原告らに対し、各100万円及びこれに対する平成31年3月6日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
1 本件は、同性カップルである原告らが、同性間の婚姻を認めていない民法及び戸籍法の規定は、憲法24条及び14条1項に違反するにもかかわらず、被告が必要な立法措置を講じていないため、婚姻をすることができない状態にあると主張して、国家賠償法1条1項に基づき、被告に対し、慰謝料各100万円及びこれに対する訴状送達の日である平成31年3月6日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
2 前提事実(当事者間に争いがないか後掲証拠(特に断らない限り枝番号を含む。以下同じ。)及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
⑴ 性的指向(Sexual Orientation)と性自認(Gender Identity)
性的指向とは、人が情緒的・感情的・性的な意味で、人に対して魅力を感じることを表す用語であり、性的指向が、異性の人に対して向くことを異性愛、同性の人に対して向くことを同性愛と呼ぶ(以下、異性愛の性的指向を有する者のことを「異性愛者」、同性愛の性的指向を有する者のことを「同性愛者」という。)。これに対し、性自認とは、自己の性別についての個人に内在化された感覚のことを指し、性的指向と併せてSOGIと呼ばれることがある。性自認が出生時に割り当てられた性別と異なる場合をトランスジェンダー(Transgender)と呼び、女性の同性愛者(Lesbian)、男性の同性愛者(Gay)及び同性愛と異性愛の双方の性的指向を有する者(Bisexual)と併せてLGBTと呼ばれることがある。また、LGBTは、身体上の性分化に関する特徴を表す用語であるインターセックス(Inter
Sex)と併せてLGBTIと呼ばれることがある(以下、LGBTI等の性的指向及び性自認における少数者を総称して「性的少数者」という。)。(争いがない事実、甲A2、5、114、弁論の全趣旨)
【筆者】
婚姻制度は「性愛」の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的とした制度ではないことから、この判決の中で「性的指向」と称する分類を持ち出していること自体が不適切である。
法律論としては、このような内心に基づいた分類を用いてはならない。
この段落では「性的指向」を取り上げているが、「恋愛的指向」と区別する考え方も存在する。
恋愛的指向 Wikipedia
この段落では「異性愛」と「同性愛」だけを挙げているが、他にも様々な分類が示されることがある。
性的同一性と性自認の一覧 Wikipedia
【セクシュアリティ辞典】性の多様性をまとめてみた 2020-05-20
このような思想の分類の中から一部分を取り出して何かを論じることができるわけではないし、法律論としてこれらの思想の分類を扱うことができるかのように論じていること自体が妥当でない。
世の中には下記のように法律論として扱うことのできない様々な思想がある。
気 Wikipedia
オーラ Wikipedia
四柱推命 Wikipedia
五行思想 Wikipedia
国や地方自治体が、このような思想の分類に関わるべきではないことと同様に、「性的指向」と称する内心の分類にも関わるべきではなく、これを論じること自体が誤りである。
ここでは「インターセックス(Inter Sex)」を取り上げ、「LGBTI等の性的指向及び性自認における少数者を総称して「性的少数者」という。」のように述べ、「LGBTI」を一括りにまとめている。
しかし、「インターセックス(Inter Sex)」については、「LGBT」の政治運動と一緒にされたくないとの意見もみられる。
私たちは「男女以外の第三の性別」を求めていません。(声明文) 2021年10月31日
このように、一括りにされたくないと考えている者もいることを看過してはならない。
政治的なグループの中でも様々な派閥があり、それらが連帯することもあれば、分断することもあることと同様に、もともとそれらに対して他者が勝手に一括りにまとめて論じることができるものではないのであり、数合わせをするかのように次々に分類を追加して一体のものであるかのように示そうとすること自体が適切ではない。
この論点については、当サイト「同性婚訴訟 東京地裁判決の分析」の同様の項目でも解説している。
我が国におけるLGBTの人口規模は、必ずしも明らかではないが、民間企業等により、全国の20歳ないし59歳を対象として、平成27年4月に行われた調査では調査対象約7万人中7.6%、平成28年5月に行われた調査では調査対象約10万人中約5.9%、同年6月に行われた調査では調査対象約1000人中4.9%であったことが報告されている(甲A237)。
【筆者】
「LGBT」と称するものは、客観的に判断できるものではなく、自己の思想、信条、信仰、感情を述べるに過ぎないものである。
そのため、これは「内心の自由」として捉えられるべき問題といえるものであり、その統計についての正確なデータが存在しないことは、そのような事情によるものである。
アメリカの調査の中には、アメリカの若者の30%以上が「自分はLGBTQ」であると認識している場合もある。
【参考】アメリカの若者の30%以上が「自分はLGBTQ」と認識していることが判明 2021年10月26日
このような「内心の自由」として扱われるものを論じることそのものが、法律論として妥当でない。
⑵ 原告ら
原告らは、いずれも男性であり、同性愛者である(弁論の全趣旨)。
【筆者】
ここで「同性愛者」であることが認定されているが、自己の思想、信条、信仰、感情を告白するものに過ぎず、このような事柄は法律論として区別して取扱うことのできる性質のものではない。
これは「同性愛者」に限られるものではなく、「異性愛者」を称する者も、「無性愛者」を称する者も、それ以外の「性愛」を持つと称する者も同じである。
そもそも「性愛」の分類を使っていない者もいるし、そのような分類で人を見ていない者もいるし、「性愛」を重視していない者もいるし、考えたことない者もいるのであり、「性愛」の存否や傾向を述べること自体が、特定の価値観で人を分類しようとする者の用いている一つの思想、信条、信仰に過ぎないものである。
それを公の機関が安易に受け入れて推進しようとしている状態となっており、極めて不適切である。
このような内心の告白を認定することになれば、「小児性愛者」を名乗る者が現れた場合には、同様の形で認定することを前提とするということになる。
【動画】家庭教師の時に… 子どもへの“性加害”10回以上くり返した男性の告白 政府なぜ見送り?「日本版DBS」【news23】 2023/09/26
【動画】「思春期前の男児にときめきを…」子どもへの“性加害”10回以上 小児性愛障害の男性が「実名」「顔出し」で証言【news23】 2023/10/08
法制度は内心に対して中立的でなければならず、「同性愛」だけを特別視して認定できるというものではないからである。
そのため、個人の内心に踏み込んで人を分類しようとするものとなっていることそのものが、国家による内心に対する不当な介入ということができ、これを前提として論じることそのものが妥当でない。
原告らは、●●●●●●●●●●●、双方が社会通念上の婚姻に相当する関係を築くことを目的とする結婚契約等公正証書を作成するとともに、任意後見契約公正証書を作成した(甲B1、2)。
原告らは、平成31年2月3日、居住地において、両名を当事者とする婚姻届を提出したが、同月7日、男性同士を当事者とする婚姻届は不適法であるとの理由により、これを不受理とされた(甲B3)。
3 婚姻制度に関する規定の内容
⑴ 民法及び戸籍法の規定
民法は、第四編第二章第一節において、婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずると規定するほか(同法739条1項)、婚姻の要件に関する規定を置き、戸籍法は、民法739条1項を受けて、婚姻をしようとする者は、夫婦が称する氏を届け出なければならない旨規定する(戸籍法74条1号)(以下、民法の規定は、昭和22年法律第222号による改正後の民法の家族法部分を総称して「現行民法」ということがあり、同改正前の家族法部分の規定を「明治民法」、同改正を「昭和22年民法改正」という。)。
そして、民法は、婚姻の効力に関し、氏の統一(同法750条)、夫婦の同居、協力及び扶助の義務(同法752条)等を、夫婦の財産に関し、婚姻費用の分担(同法760条)等を、離婚に関し、財産分与(同法768条)等を規定するほか、親子関係に関し、夫婦の子についての嫡出の推定(同法772条1項)、親権に関する規定(同法818条3項)を置き、相続に関し、配偶者の相続権(同法890条)を規定するなど、婚姻の重要な効果に関する規定を置いている。また、戸籍法では、婚姻の届出があったときは、夫婦について新戸籍を編製し(同法16条1項本文)、当該戸籍には、夫婦について夫又は妻である旨が記載され(同法13条6号)、子が出生した場合にはこれを届け出なければならず(同法49条1項)、子は親の戸籍に入ることとされており(同法18条)、戸籍の正本は市役所等に備え置くこととされて公証されている(同法8条2項)。
⑵ 同性間の婚姻についての解釈
民法及び戸籍法の諸規定は、同性間の婚姻を明文で禁止していないが、民法及び戸籍法が、婚姻をしたカップルを「夫婦」、その当事者を「夫」又は「妻」と呼称していることなどから、現在の実務では、同性間の婚姻は認められないものと解されている(以下、同性間の婚姻を認めていない民法及び戸籍法の諸規定を「本件諸規定」という。)。
【筆者】
ここでは、「民法及び戸籍法の諸規定は、同性間の婚姻を明文で禁止していない」と述べているが、「夫婦」、「夫」や「妻」の文言から「同性間の婚姻は認められない」と説明している。
この「禁止」という言葉は、様々な意味で用いられることがあるため、ここでいう「明文で禁止していない」の意味がどのような意味の「禁止」であるかを検討する。
① 義務文・否定文による禁止(命令文の禁止)
「義務文・否定文による禁止」とは、条文中に「禁止する」や「禁ずる」、「~~してはならない」、「~~しなければならない」のように記載されている場合のことをいう。
② 防ぐ意図の禁止(狭義の禁止)
「防ぐ意図の禁止」とは、何らかの対象を認識した上で、それを意図的に防ぐ意思を持って規定が設けられている場合のことをいう。
これは、何かを制限する意味、対象者を限定する意味、対象者専用とする意味も含まれる。
③ 上位法に反する禁止(広義の禁止)
「上位法に反する禁止」とは、何かを行った場合や下位の法令で制度を構築するなどした場合に上位法に違反する場合のことをいう。
この文は結論として「同性間の婚姻は認められない」としており、「禁止していない」ことと「認められない」ことを区別するものとなっている。
そのため、「認められない」ことについて「禁止」しているとは表現しない方針であることが明らかである。
よって、この「禁止していない」の文は、「認められない」ことに対応する③「上位法に反する禁止」の意味ではない。
次に、「夫婦」、「夫」や「妻」という文言があり、それ以外を許容していないことは明らかであるが、これについて「禁止」しているとは表現しない方針のようである。
よって、この「禁止していない」の文は、その範囲を限定していることに対応する②「防ぐ意図の禁止」の意味ではない。
これにより、残った「禁止」の意味は①「義務文・否定文による禁止」である。
① 「義務文・否定文による禁止」 ← (明文で禁止していない)
② 「防ぐ意図の禁止」 ← (夫婦、夫・妻)
③ 「上位法に反する禁止」 ← (認められない)
そのため、この文が「同性間の婚姻を明文で禁止していない」と表現する場合の「禁止」の意味は、①「義務文・否定文による禁止」を指していることになる。
しかし、問題は、上記の説明とこの判決の下記で24条1項を解釈する場面で「禁止されているとはいえない」と述べている場合とでは解釈の方法が異なることである。
24条1項について
・「2⑵ウ」:「禁止されていたとまではいえない」
・「2⑵ケ」:「禁止されているとはいえない」
・「2⑶ア」:「禁止されてはいない」
ここでは「禁止していない」と述べた上で、「夫婦」、「夫」や「妻」の文言が使われていることから、「同性間の婚姻は認められない」としているにもかかわらず、24条1項を解釈する場面では、同じように「禁止されているとはいえない」のように述べているものの、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とする法律を立法することが可能であるかのように述べているのである。
24条1項の文言でも「両性」「夫婦」の文言が用いられており、解釈の基準となる要素は同様であるにもかかわらず、一方は「認められない」として、もう一方は認めることができるとしているのである。
この部分で「禁止していない」が「認められない」と述べているのであるから、24条1項の解釈においても同様に「禁止されているとはいえない」と表現したとしても、結論としては「認められない」と論じることが整合的なのであり、それを認められるかのように説明していることは、整合性を欠くものとなっている。
この点は、この判決の内容が解釈の方法について一貫性のないことを明らかにするものであり、裁判官が特定の結論を導き出すために解釈の過程を歪め、恣意的な判断を行っていることを浮かび上がらせるものとなっている。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法を解釈することと、法を解釈していると思い込んでいることとを区別しうるためには、解釈は個人的・私的なものではなく、社会的な、つまり原理的には誰にも共通にアクセス可能な、公的活動でなければならないはずである。各人がそれぞれ異なった形で得心がいっただけでは、法解釈として十分とはいえない。解釈者は、他人を説得し、同じように既存の法源(判例・法令)を見るように議論を進める必要がある。もちろん、その結果、つねに同一の結論へと人々の意見が集約されるとは限らない。同じ程度に説得力を持つ複数の解釈が競合することは珍しいことではない。
解釈が解釈であるためには、つまり、それが原理的に誰もが参加しうる公的な活動であるためには、第一に、法源の核心的な意味の理解を可能とする共通の言語作用が背景として存在していなければならない。そして、第二に、解釈の目的は、例外的・病理的現象である法の意味の不明瞭化に対して、人々の合意をとりつけることで、正常な法の機能を回復すること、人々が再び疑いをもたずに法に従いうる状態を回復することになければならない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
憲法の理性 長谷部恭男 (P210) (下線は筆者)
もう一つ、この文には「同性間の婚姻」との文言があるか、「婚姻」は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた枠組みであり、「同性間の人的結合関係」についてはその間で「生殖」を想定することができないため「生殖と子の養育」の趣旨を満たすとはいえず、「婚姻」とすることはできない。
そのため、ここでは「夫婦」、「夫」や「妻」の文言から「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることが「認められない」と論じているが、「婚姻」という概念そのものによっても認められないことになる。
4 争点及び争点に関する当事者の主張
本件の争点は以下のとおりであり、これに関する当事者の主張は別紙2のとおりである。
⑴ 本件諸規定が憲法24条及び14条1項に違反するか(争点1)
⑵ 本件諸規定を改廃しないことが国家賠償法上違法であるか(争点2)
⑶ 原告らに生じた損害とその額(争点3)
第3 当裁判所の判断
1 認定事実
後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。
⑴ 性的指向等に関する知見
ア 現在の知見
性的指向が決定される原因や同性愛となる原因は、現在でも解明されていない。しかし、メンタルヘルス(精神衛生)に関わる大部分の専門家団体は、性的指向は、ほとんどの場合、人生の初期又は出生前に決定され、自ら選択するものではないと考えている。また、心理学の分野では、性的指向を自らの意思で変更することは不可能であるとするのが主たる見解となっているほか、精神医学の分野でも、同性愛者の中には性行動を変えられる者もいるが、それは性的指向自体の変化を意味するものではなく、性的指向が自らの意思や精神医学的な療法によって変わることはないであろうとの結論が大勢となっている。(甲A2、3、7、242、244)
【筆者】
婚姻制度は「性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いをするものではないし、「性愛」に基づいて婚姻制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもない。
よって、「性愛」を有する場合に、それがどのような対象に向かうかに関する「性的指向」と称するものを論じる必要そのものがないのであり、これを論じた上で判断しようとする前提そのものに誤りがある。
「性的指向を自らの意思で変更することは不可能であるとするのが主たる見解となっている」や「性的指向が自らの意思や精神医学的な療法によって変わることはないであろうとの結論が大勢となっている。」との部分であるが、「自らの意思」で「性的指向」を変えたいと望む者もいるにもかかわらず、それを「自らの意思で変更することは不可能である」や「変わることはない」と示すことは控えるべきものである。
たとえば、「異性愛から同性愛へ」「同性愛から異性愛へ」「小児性愛から成人性愛へ」「両性愛から多性愛へ」「全性愛から無性愛へ」など、様々な方面に「自らの意思」で変えたいと望む者が存在する。
この判決の次の項目の「イ 欧米諸国における知見の変遷」の「20世紀中頃以降の知見」でも「「自らの性的指向に悩み、葛藤し、変えたいと望む」同性愛者」について触れられている。
それに対して、「自らの意思で変更することは不可能である」や「変わることはない」と断じることは、その者の意思を否定することになるため、決して望ましいものではない。
もちろん、他者が本人の意思に反して無理に変えさせようと強制することは憲法19条の「思想良心の自由」の精神に反して許されないことは言うまでもない。
しかし、この判決が人の内心そのものを「自らの意思で変更することは不可能である」や「変わることはない」と断じることそのものも、憲法19条の「思想良心の自由」を侵す判断に他ならないことを理解する必要がある。
■ 司法権の範囲
「司法権の範囲」の論点を検討する。
司法(司法権の範囲) Wikipedia
「司法権の範囲」は、裁判所法3条の「法律上の争訟」に当たるか否かが問題となる。
裁判所法
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第三条(裁判所の権限) 裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。
② ……(略)……
③ ……(略)……
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「法律上の争訟」の意味は、判例で明らかとなっている。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
裁判所法三条によれば「裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する」ものであり、ここに「法律上の争訟」とは法令を適用することによつて解決し得べき権利義務に関する当事者間の紛争をいうのである。……
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「法律上の争訟」に関する判例を確認する。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
……(略)……第一に、法を適用することによっては解決しえない紛争は、法律上の争訟とは言えず、裁判所の審査権は及ばない。宗教上の教義に関する争い(最判昭和56・4・7民集35巻3号443頁〈板まんだら事件〉)、学問の真理性に関する争い(東京地判平成4・12・16判時1472号130頁)などが、このような事項の例として挙げられる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
司法権をめぐる論点 長谷部恭男 2004年9月 PDF (太字・下線は筆者)
憲法訴訟に関連する用語等の解説 衆議院憲法調査会事務局 平成12年5月 PDF
◇ 学問の真理性に関する争い
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
しかし、司法権の固有の内容として裁判所が審判しうる対象は、裁判所法三条にいう「法律上の争訟」に限られ、いわゆる法律上の争訟とは、「法令を適用することによつて解決し得べき権利義務に関する当事者間の紛争をいう」ものと解される(昭和二九年二月一一日第一小法廷判決、民集八巻二号四一九頁参照)。従つて、法令の適用によつて解決するに適さない単なる政治的または経済的問題や技術上または学術上に関する争は、裁判所の裁判を受けうべき事柄ではないのである。国家試験における合格、不合格の判定も学問または技術上の知識、能力、意見等の優劣、当否の判断を内容とする行為であるから、その試験実施機関の最終判断に委せられるべきものであつて、その判断の当否を審査し具体的に法令を適用して、その争を解決調整できるものとはいえない。この点についての原判決の判断は正当であつて、上告人は裁判所の審査できない事項について救済を求めるものにほかならない。……
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
国家試験合格変更又は損害賠償請求事件 昭和41年2月8日 (PDF)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
そこで検討するに、原告の主張する右先行権の意味は必ずしも明らかではないが、ある研究に関し、他者に先んじて当該研究を手掛けた研究者が、他者に対し先駆者としての地位を主張しうるとともに、学会等においても、当該研究の先駆者としての評価を受け、尊重されることをも意味するもののようである。そうすると、原告の主張するこのような先行権の存在を認めるには、まず比較されるべき二つ以上の研究の先後を評価ないし判定しなければならないことになるが、二つ以上の研究の先後の評価ないし判定は、当該対比されるべき研究における時間的な先後の一事のみならず、当該各研究の内容、程度、方法、結果の発表態様、学説若しくは見解の当否若しくは優劣等種々の要素を総合しなければ容易になしえないものであって、このような学問上の評価ないし判定は、その研究の属する分野の学者・研究者等に委ねられるべきものであり、裁判所において審査し、法令を適用して解決することのできる法律上の争訟ではないといわなければならない。したがって、本件において、原告の前記講演が被告佐伯論文よりなされたとして、先行権を有することを前提とする原告の主張は、既にこの点において理由がないというべきである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
この名古屋地裁判決は「性的指向」について「自らの意思で変更することは不可能である」や「変わることはない」などと述べている。
しかし、これは「技術上または学術上に関する争」のあるものについて、その当否の問題に踏み込んだ上で判断を試みようとしているものということができる。
上記の判例を参考にすれば、「学問または技術上の知識、能力、意見等の優劣、当否の判断を内容とする行為」については、「その判断の当否を審査し具体的に法令を適用して、その争を解決調整できるものとはいえない」ため、裁判所の審判できる「法律上の争訟」の範囲を超えるものである。
そのため、この名古屋地裁判決がこの点について特定の立場についての見解を正しいものであると認定した上で判断を試みていることは、「司法権の範囲」を超えた違法なものということになる。
◇ 宗教上の教義に関する争い
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
裁判所がその固有の権限に基づいて審判することのできる対象は、裁判所法三条にいう「法律上の争訟」、すなわち当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であつて、かつ、それが法令の適用により終局的に解決することができるものに限られる(最高裁昭和三九年(行ツ)第六一号同四一年二月八日第三小法廷判決・民集二〇巻二号一九六頁参照)。したがつて、具体的な権利義務ないし法律関係に関する紛争であつても、法令の適用により解決するのに適しないものは裁判所の審判の対象となりえない、というべきである。
……(略)……本件訴訟は、具体的な権利義務ないし法律関係に関する紛争の形式をとつており、その結果信仰の対象の価値又は宗教上の教義に関する判断は請求の当否を決するについての前提問題であるにとどまるものとされてはいるが、本件訴訟の帰すうを左右する必要不可欠のものと認められ、また、記録にあらわれた本件訴訟の経過に徴すると、本件訴訟の争点及び当事者の主張立証も右の判断に関するものがその核心となつていると認められることからすれば、結局本件訴訟は、その実質において法令の適用による終局的な解決の不可能なものであつて、裁判所法三条にいう法律上の争訟にあたらないものといわなければならない。�
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【動画】【憲法_重要判例】(司法権)【板まんだら事件】 2020/11/29
【動画】【行政書士 #3】憲法の統治で一番苦手?裁判所を簡単に攻略!判例の勉強方法もわかりやすく解説(講義 ゆーき大学) 2021/03/12
【動画】行政書士試験対策公開講座 憲法36「裁判所」 2016/03/15
【動画】2023年度前期・九大法学部「憲法1(統治機構論・後半)」第5回〜裁判所② 2023/07/01
【動画】2023年度前期・九大法学部「憲法1(統治機構論・後半)」第7回〜裁判所④ 2023/07/13 ①
【動画】2023年度前期・九大法学部「憲法1(統治機構論・後半)」第7回〜裁判所④ 2023/07/13 ②
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
そして、宗教団体における宗教上の教義、信仰に関する事項については、憲法上国の干渉からの自由が保障されているのであるから、これらの事項については、裁判所は、その自由に介入すべきではなく、一切の審判権を有しないとともに、これらの事項にかかわる紛議については厳に中立を保つべきであることは、憲法二〇条のほか、宗教法人法一条二項、八五条の規定の趣旨に鑑み明らかなところである(最高裁昭和五二年(オ)第一七七号同五五年四月一〇日第一小法廷判決・裁判集民事一二九号四三九頁、前記昭和五六年四月七日第三小法廷判決参照)。かかる見地からすると、特定人についての宗教法人の代表役員等の地位の存否を審理判断する前提として、その者の宗教団体上の地位の存否を審理判断しなければならない場合において、その地位の選任、剥奪に関する手続上の準則で宗教上の教義、信仰に関する事項に何らかかわりを有しないものに従ってその選任、剥奪がなされたかどうかのみを審理判断すれば足りるときには、裁判所は右の地位の存否の審理判断をすることができるが、右の手続上の準則に従って選任、剥奪がなされたかどうかにとどまらず、宗教上の教義、信仰に関する事項をも審理判断しなければならないときには、裁判所は、かかる事項について一切の審判権を有しない以上、右の地位の存否の審理判断をすることができないものといわなければならない(前記昭和五五年四月一〇日第一小法廷判決参照)。したがってまた、当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係に関する訴訟であっても、宗教団体内部においてされた懲戒処分の効力が請求の当否を決する前提問題となっており、その効力の有無が当事者間の紛争の本質的争点をなすとともに、それが宗教上の教義、信仰の内容に深くかかわっているため、右教義、信仰の内容に立ち入ることなくしてその効力の有無を判断することができず、しかも、その判断が訴訟の帰趨を左右する必要不可欠のものである場合には、右訴訟は、その実質において法令の適用による終局的解決に適しないものとして、裁判所法三条にいう「法律上の争訟」に当たらないというべきである(前記昭和五六年四月七日第三小法廷判決参照)。�
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
建物明渡、代表役員等地位確認請求事件 平成元年9月8日 (PDF)
【動画】2023年度前期・九大法学部「憲法1(統治機構論・後半)」第7回〜裁判所④ 2023/07/13 ③
「性的指向」と称しているものは個々人の内心にのみ存在する精神的なものであるから、その性質についていくつかの見解があるにもかかわらず、そのうちいずれかの見解が妥当なものであると認めた上での判断を求めるものとなっていることは、宗教的な教義が正しいものであることを裁判所に認めてもらおうとする主張とその本質において変わるものではない。
上記の判例を参考にすれば、「性的指向」と称するものについて自らの意思で変えることができるかどうかが問題となり、その性質の当否を前提としなければ判断を行うことができないような場合には、法令を適用することによって終局的に解決することができる問題ではないため、裁判所の審判できる「法律上の争訟」の範囲を超えるものである。
よって、これを前提として何らかの結論を導き出そうとしているこの判決の内容は、憲法76条1項の「司法権」や、裁判所法3条の「法律上の争訟」の範囲を超え、裁判所の有する権限を逸脱した違憲・違法な判断となる。
このように、「性的指向」と称するものの性質を前提として何らかの法制度の存否の当否を論じることは、そもそも裁判所法3条の「法律上の争訟」に該当せず、「司法権の範囲」を超えるものであるから、裁判所で判断することのできないものである。
そのため、この名古屋地裁判決が「性的指向」と称するものの性質がどういうものであるかという問題について特定の立場を採った上で、それを前提として法的な判断を行ったことは、「司法権の範囲」を超える違法があり、正当化することはできない。
【動画】【憲法_重要判例】(司法権)【板まんだら事件】 2020/11/29
【動画】【行政書士 #3】憲法の統治で一番苦手?裁判所を簡単に攻略!判例の勉強方法もわかりやすく解説(講義 ゆーき大学) 2021/03/12
【動画】行政書士試験対策公開講座 憲法36「裁判所」 2016/03/15
「司法権」については、当サイト「憲法の構成要素」でも触れている。
イ 欧米諸国における知見の変遷
20世紀中頃までの知見
欧米諸国では、19世紀末頃、精神医学の分野において、同性愛を精神的病理であるとする見解が主張されるようになり、アメリカ精神医学会は、1952(昭和27)年公刊の「精神障害のための診断と統計の手引き初版」(DSM(Diagnostic And Statistical Manual of Mental Disorders)-Ⅰ)において、「同性愛」を「性的逸脱」の一種とみなし、1968(昭和43)年公刊の第二版(DSM-Ⅱ)からは、独立した診断名として扱うようになった。また、世界保健機関(WHO)も、1975(昭和50)年公刊の「疾病及び関連保険問題の国際統計分類第九版」(ICD(International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems)-9)において、「性的逸脱及び障害」の項目に「同性愛」という診断名を掲げるようになった。(甲A24、27、29、48、273)
20世紀中頃以降の知見
これに対し、性科学や心理学の分野において、20世紀中頃、同性愛を精神的病理であるとする見解に疑問が呈されるようになった。そして、アメリカ精神医学会は、1973(昭和48)年、同性愛それ自体を精神障害として扱わないこととして、DSM-Ⅱの「同性愛」という診断名に代えて、「自らの性的指向に悩み、葛藤し、変えたいと望む」同性愛者のために「性的指向障害」という項目を新設する旨の決議を行ったところ、同診断名は、DSM-Ⅲにおいて「自我異和的同性愛」という名称に修正され、1987(昭和62)年公刊のDSM-Ⅲ-Rにおいて削除されるに至った。また、1975(昭和50)年以降、アメリカ心理学会やアメリカ行動療法促進学会等メンタルヘルス関連の主要な諸学会も上記決議を支持した。さらに、WHOは、1992(平成4)年公刊のICD-10において、「同性愛」の代わりに「自我異和的性志向」という分類名を採用するとともに、性指向自体は障害と考えられるべきではない旨を明らかにした。(甲A1、24、27ないし30、48)
【筆者】
婚姻制度は「性愛」を保護するための制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いをするものではないし、「性愛」に基づいて制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもない。
そのため、ここでこのような話を取り上げていることそのものが不適切である。
ここでは「アメリカ精神医学会」や「アメリカ心理学会やアメリカ行動療法促進学会等メンタルヘルス関連の主要な諸学会」のように「学会」が登場する。
しかし、学問の領域のことは学問の領域に任せるべきものであり、裁判所が特定の学会の意見を肯定したり否定したりするようなことをするべきではない。
【動画】第19回〜「思想・良心の自由」 2022/01/24
【動画】憲法 人権(学問の自由)ミニ講義【森Tの行政書士合格塾】 2022/04/30
ここでは「精神的病理」や「障害」であるか否かが問われているが、婚姻制度は「男女二人一組」などの要件を満たしたならば、「精神的病理」とされる者や「障害」を持つとされる者でも利用することができることから、そもそも「精神的病理」や「障害」である者を制度の対象から外すという発想が存在していない。
よって、このように何らかの精神状態が「精神的病理」や「障害」であるか否かを論じていること自体が不適切である。
ウ 我が国における知見の変遷
明治20年頃以降の知見
我が国でも、明治20年代に入ると、同性愛を精神的病理であるとする西欧の知見が導入されるようになり、明治39年には、同性愛は健康者と精神病者との中間にある「変質狂」の一種である色情感覚異常又は先天性の疾病であるとする知見が紹介されたほか、大正時代には、同性愛は「変態性欲」の一種であり、一種の伝染病であるとする知見も紹介された。また、平成5年当時においても、同性愛は、主要な精神医学の教科書において「性的異常」として紹介されていた。(甲A24、266、279、乙24ないし26)
さらに、青年期の同性愛については、昭和11年当時、ある程度を超えなければ心配する必要はないが、同性の者同士が愛情を深め、不純な同性愛に向くこともあり、このような場合には注意すべきことであって、絶対に禁止すべきものとされていたほか、昭和54年になっても、文部省の生徒の問題行動に関する基礎資料において、一般的に健全な異性愛の発達を阻害するおそれがあり、社会的にも、健全な社会道徳に反し、性の秩序を乱す行為となり得るものであり、是認されるものではないであろうとされていた(甲A26、乙27)。
平成7年頃以降の知見
日本精神神経学会は、平成7年、市民団体からの求めに応じ、ICD-10に準拠し、同性への性的指向それ自体を精神障害とみなさないとの見解を示した(甲A48、279)。
【筆者】
婚姻制度は「性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いを行うものではないし、「性愛」に基づいて制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもない。
よって、ここで「(⑴ 性的指向等に関する知見」と項目を立て、「ア 現在の知見」、「イ 欧米諸国における知見の変遷」、「ウ 我が国における知見の変遷」のように述べる必要そのものがないものである。
また、現在の婚姻制度についても、それは「異性愛」を保護することを目的とするものではないし、「異性愛者」を称する者を対象とするものでもないし、「異性愛」に基づいて制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもない。
現在の婚姻制度が「異性愛」という特定の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的としていたり、「異性愛者」を称する者を対象とするものとなっている場合には、それ自体で憲法違反となる。
よって、ここで「同性愛」の知見を述べたところで、婚姻制度に影響を及ぼすようなことはないし、影響を及ぼすようなことがあれば、その時点でその制度は憲法違反となることを押さえる必要がある。
⑵ 婚姻制度
ア 婚姻制度についての伝統的理解
人類は、男女の結合関係を営み、種の保存を図ってきたところ、婚姻制度は、この関係を規範によって統制するために生まれた。いかなる社会でも、当該社会における典型的な結合関係を法規範によって肯認し、その維持に努めた。その形態は、当該社会の経済的・政治的条件又は道徳的理念によって、時代や地域ごとに様々であるが、それぞれの社会において、正当な男女の結合関係を承認するものとして存在し、伝統的には、単純な男女の性関係ではなく、男女の生活共同体として、その間に生まれた子の保護・育成、分業的共同生活の維持などの機能を通じ、家族の中核を形成するものと捉えられてきた。(甲A247、乙1、2、21、22)
【筆者】
「人類は、男女の結合関係を営み、種の保存を図ってきたところ、婚姻制度は、この関係を規範によって統制するために生まれた。」との記載があるが、その通りである。
ただ、その「規範によって統制する」という背景には、「生殖」に関わって社会的な不都合が生じていることが原因である。
もし何らの不都合も存在しないのであれば、そもそも「規範によって統制する」ことも必要ないはずだからである。
よって、婚姻制度が「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として形成されていることは明らかである。
そして、それは下記のような経緯によるものである。
その国の中で「生殖と子の養育」に関する事柄について何らの制度も存在しない場合には、社会的な不都合が発生することがある。
例えば、「父親不明」の子供が増える、父親を特定できない子供が増える、父親が蒸発して行方不明になった子供が増える、それらにより「子の福祉」が減少する、父親を特定できないことにより近親者の範囲を把握できずに「近親交配」に至り潜性遺伝子を有する個体が高い確率で発現するようになる、一部の強者が多数人との生殖関係を独占することによって社会の中で「子を持ちたいと希望して相手を見つけようとする男女」の数の不均衡が生じて「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」が生まれる、低年齢での妊娠・出産により母体に危険が及ぶ、などの問題が生じることがある。
これらの不都合を解消するために、下記のような立法目的を有する枠組みを設けることが必要となる。
・「子の福祉」が実現される社会基盤を構築すること
・潜性遺伝子を有する個体が高い確率で発現することを抑制すること
・「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」を減らすこと
・母体を保護すること
そして、これらの目的を達成するためには、下記の要素を満たす枠組みを設けることが必要となる。
・子の遺伝的な父親を特定できる組み合わせとすること
・特定された子の父親にも子に対する責任を担わせること
・特定された子の父親を基に遺伝的な近親者を把握すること
・未婚の男女の数の不均衡を防止できる組み合わせに限定すること
これらの要素を満たすものとして「一人の男性」と「一人の女性」が選び出され、その間に「貞操義務」を設け、その関係を法的に結び付ける形を「婚姻」と呼んでいる。
そして、この「婚姻」に対して法的効果や一定の優遇措置を設けることで、婚姻制度を利用する者を増やし、これらの目的を達成することを目指すものとなっている。
このような「目的」と「その目的を達成するための手段」となる枠組みを定めることが、「婚姻」という概念が生じる経緯である。
これがここでいう「規範によって統制する」ことの意味であり、「男女の結合関係」としている理由である。
「いかなる社会でも、当該社会における典型的な結合関係を法規範によって肯認し、その維持に努めた。」との記載がある。
ここに「典型的な結合関係」とあるが、なぜ「社会」の中で「結合関係を法規範」によって定めるかという目的とその目的を達成するための手段の関係を検討することなく、「典型的」かどうかという評価を基にして論じようとしている部分が妥当でない。
上記でも説明したように、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で婚姻制度が設けられ、他の様々な人的結合関係や何らの制度も利用していない者との間で差異を設けることによって立法目的の達成を目指すものとなっている。
そのため、婚姻制度が「男女」の組み合わせを対象としていることは、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成するための手段として整合的な要素を満たすことによるものであり、これを離れて「典型的」か否かという何らかの評価を基にして「法規範」が設定されているわけではない。
「結合関係を法規範」で定めるか否かは、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的とその目的を達成するための手段によって決まるものであり、それを検討せずに何が「典型的」であるかが先に決まっているというものではないのである。
よって、ここで「典型的な結合関係」という評価を理由として、「法規範によって肯認」され「維持」されていると考えている部分は、判断の過程として必要となる根拠を欠くものであり、適当でない。
「その形態は、当該社会の経済的・政治的条件又は道徳的理念によって、時代や地域ごとに様々であるが、それぞれの社会において、正当な男女の結合関係を承認するものとして存在し、伝統的には、単純な男女の性関係ではなく、男女の生活共同体として、その間に生まれた子の保護・育成、分業的共同生活の維持などの機能を通じ、家族の中核を形成するものと捉えられてきた。」との記載がある。
「その形態は、当該社会の経済的・政治的条件又は道徳的理念によって、時代や地域ごとに様々であるが、」との部分であるが、おおよそその通りである。
「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成するための手段として整合的な形で、夫婦の財産関係や相続関係を定めるなどしているが、その夫婦の財産関係や相続関係などのあり方は「それぞれの時代、社会」によって方法が異なる場合がある。
「それぞれの社会において、正当な男女の結合関係を承認するものとして存在し、」との部分について検討する。
「正当な男女の結合関係」とあるが、このような表現を使うことは、「不当な男女の結合関係」というものが存在することを前提とするものとなるため妥当でない。
婚姻制度を利用する者は、単に「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度を利用しているというだけの者である。
そのため、法律論として考えれば、それは「正当な」ものであるか、「不当な」ものであるかという価値判断が入り込む余地はない。
もし「婚姻している者(既婚者)」が複数名との間で性的な接触を行った場合に、婚姻制度による法律関係を形成している「夫婦」である「男女」と、その「夫婦」の一方と性的接触を行った「夫婦」以外の者との間での「男女」との関係性が比較され、「夫婦」の場合は「貞操義務」に反するものではないが、その「夫婦」以外の者との間での性的接触は「貞操義務」に反するものとして「離婚の訴え」や「損害賠償」の対象となるという違いが生じる場合は考えられる。
しかし、これは制度を利用する者と利用しない者との間では、法律関係としては制度を利用した方が利用しない者よりは、「離婚の訴え」や「損害賠償」などの権利を得ることができる地位にあるという意味において有利になるというだけのことである。
この仕組みに着目して「正当な」と表現しているのかもしれないが、それは婚姻制度が存在することを前提としてその制度の仕組みに着目して後付けで評価を行っているものであり、初めに「正当な男女」とそうでない男女(不当な男女)というものが存在し、そのうちで「正当な男女」だけが選び出されて「承認する」などというものとは異なる。
そのため、ここで婚姻制度について「正当な男女の結合関係を承認するものとして存在し、」のように、「正当な男女の結合関係」というものを「承認する」というような立法目的が存在するかのように論じていることは誤りである。
「伝統的には、単純な男女の性関係ではなく、男女の生活共同体として、その間に生まれた子の保護・育成、分業的共同生活の維持などの機能を通じ、家族の中核を形成するものと捉えられてきた。」との部分について検討する。
「単純な男女の性関係ではなく、」との部分は、重要なことを述べている。
「婚姻」は、「性愛結社」とは異なることを明らかにしている点で、その通りということができる。
「性愛結社」は、憲法21条1項の「結社の自由」のような「自由権」によって形成することが可能であり、これは「婚姻」である必要もないことも押さえる必要がある。
「男女の生活共同体として、その間に生まれた子の保護・育成、分業的共同生活の維持などの機能を通じ、家族の中核を形成するものと捉えられてきた。」との部分であるが、婚姻制度がこのような人的結合関係を対象としている背景には、上記の「目的」と「その目的を達成するための手段」となる枠組み(必要となる要素)が存在する。
それを明らかにしないままに、「婚姻」の内容である「男女の生活共同体として、その間に生まれた子の保護・育成、分業的共同生活の維持などの機能を通じ、家族の中核を形成するもの」を説明したとしても、その形にどのような意図が含まれているのかを十分に説明しているものとは言えない。
そのため、これを「伝統的」と呼ぶかどうかは別として、婚姻制度が対象とする人的結合関係の範囲を論じる際には、「婚姻」の「目的」と「その目的を達成するための手段」となる枠組み(必要となる要素)を捉えることが必要となるのであり、「伝統的」な価値観を重視するか否かという価値観の対立によるものであるかのように考えることは誤りであることに注意が必要である。
イ 明治民法下での婚姻制度
明治民法の制定経過
我が国では、明治時代以前にも、婚姻に関する一定の慣習は存在していたが、統一的な法制度は存在しなかった。そこで、明治23年、同年法律第98号(以下「旧民法」という。)が公布された。その後、同法が施行されることはなかったが、部分的な修正が加えられ、明治31年、既存の慣習を踏襲しつつ、弊害のある事項や不明瞭な事項等の欠缺を補うものとして、明治民法が施行された。明治民法下では、婚姻とは終生の共同生活を目的とする一男一女の法律的結合関係をいうものであると捉えられていた。(甲A173、178、180、181、乙3)
制定過程における議論
旧民法の第1草案の起草過程においては、婚姻は男女の結合であるから、同性間の婚姻が不成立であることは当然であり、あえて婚姻の不成立事由として掲げる必要はないとされ、この立場は、明治民法にも踏襲された(甲A165、166)。
また、旧民法の第1草案においては、婚姻は両心の和合を性質とするものであり、生殖能力は婚姻にとって必要不可欠の条件であるとはいえないとして、老年等による生殖不能は婚姻障害事由として掲げられなかったところ、明治民法においても、同旨の立場が採用され、婚姻の無効もしくは取消原因又は離婚原因として、生殖不能が掲げられることはなかった(甲A172、173、178、179)。
【筆者】
ここには「両心の和合」との記載がある。
これについて、国(行政府)は、それが記載された文献の記述は「婚姻を生殖と結びついた男女間の結合と捉えつつ,このような理解を前提とした上で生殖能力のない者の婚姻の可否を論じているもの」であることを指摘している。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ア しかしながら,我が国の婚姻制度が伝統的に生殖と結びついて理解されてきたことは,被告第2準備書面第1の2(1)及び(2)(5ないし8ページ)において引用した文献の記載等からも明らかである。
イ この点,原告らは,「婚姻ハ兩心ノ和合ヲ以テ性質ト為スモノニシテ産子ノ能力ハ一般ニ具備スヘキ條件ナレドモ,必要欠ク可ラサル條件三アラズ」と説明する文献(熊野敏三ほか「民法正義入事編巻之壹(上下)」193ページ・甲A第186号証)を引用し,「我が国の婚姻制度は,必ずしも生殖を目的どしない親密な人格的結合(『両心ノ和合』)に基づく共同生活関係に対して法的保護を与えることを中心的な目的に据えてきたものであり,現在においてもそのような前提に変更はないものと解するのが適切である」と主張する(原告ら第6準備書面 22,40ページ)。
しかし,上記文献は,上記の引用部分の前に「産子ノ能力ヲ有セサル男女ト雖モ婚姻ヲ為スヲ得ヘキカ」という聞いが設けられているとおり(同号証192ページ),生殖能力が婚姻の必要条件か否かについて論じているのであって,我が国の婚姻制度が,伝統的に,必ずしも生殖を目的としない親密な人格的結合に基づく共同生活関係に対して法的保護を与えることを中心的な目的に据えてきた旨を述べるものではない。むしろ,「産子ノ能力ハ一般ニ具備スヘキ侠件」と明記されているととからすれば,上記文献は,婚姻を生殖と結びついた男女間の結合と捉えつつ,このような理解を前提とした上で生殖能力のない者の婚姻の可否を論じているものと解するのが自然であって,同文献は原告らの上記主張を補強するものではない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【札幌・第5回】被告第3準備書面 令和2年5月15日 (P6)
よって、具体的な婚姻制度の存在を前提として、その婚姻制度の効力が及ぶか否かを論じるものであり、この「両心の和合」というものが「国の立法目的」となっているわけではないし、この「両心の和合」というものによって、婚姻制度の枠組みを変更することができるとする理由になるものではないことを押さえる必要がある。
明治民法における婚姻制度の内容
明治民法においては、家を中心とする家族主義の理念に基づき、家長である戸主に家を統率するための戸主権が与えられ、婚姻は家のためにあるとの思想に基づき、一定の年齢(男は30歳、女は25歳)未満の子の婚姻には、戸主や親の同意が要件とされていた。また、男子及び男系尊重の封建武家的道徳に基づき、婚姻関係にも夫の妻に対する優越が認められ、相続についても、男子単独相続の家督相続が主眼とされ、女子は相続順位において男子より劣後的地位に置かれることとなった。(甲A19、142、179、180、181)
ウ 日本国憲法の制定
日本国憲法の制定過程
大日本帝国憲法においては、婚姻及び家族に関する規定が定められていなかったところ、連合国総司令部(GHQ)は、昭和21年2月、政府に対し、「家族ハ人類社会ノ基底ニシテ其ノ伝統ハ善カレ悪シカレ国民ニ滲透ス婚姻ハ男女両性(注・both sexes)ノ法律上及社会上争フ可カラサル平等ノ上ニ存シ両親ノ強要ノ代リニ相互同意ノ上ニ基礎ツケラレ且男性支配ノ代リニ協力ニ依リ維持セラルヘシ此等ノ原則ニ反スル諸法律ハ廃止セラレ配偶ノ選択、財産権、相続、住所ノ選定、離婚並ニ婚姻及家族ニ関スル其ノ他ノ事項ヲ個人ノ威厳及両性ノ本質的平等ニ立脚スル他ノ法律ヲ以テ之ニ代フヘシ」とするマッカーサー草案23条を提示した(甲A144、146ないし148、弁論の全趣旨)。
政府は、マッカーサー草案23条を受け、日本側の修正案として、昭和21年3月2日、「婚姻ハ男女相互ノ合意ニ基キテノミ成立シ、且夫婦ガ同等ノ権利ヲ有スルコトヲ基本トシ相互ノ協力ニ依リ維持セラルベキモノトス」とする案を、同月5日、同案を1項とし、2項に「配偶ノ選択、財産権、相続、住居ノ選定、離婚並ニ婚姻及家族ニ関スル其ノ他ノ事項ニ関シ個人ノ威厳及両性ノ本質的平等ニ立脚セル法律ヲ制定スヘシ」とする条項を加える案を作成した。同案は、同年4月、口語化され、帝国議会での審議とそれに基づく修正を経て、同年11月、憲法24条が制定された。(甲A146ないし148、151、弁論の全趣旨)
制定過程における議論
憲法24条の制定過程においては、帝国議会での審議の際に、伝統的な家族制度が維持されることになるかが論点となり、同条1項が「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」と規定している点について、司法大臣からは、明治民法が一定の年齢未満の子の婚姻につき戸主や親の同意を要件としていたのを排除し、両性の合意だけで成立させようとする趣旨である旨の説明がなされた。なお、同性間の婚姻に関して議論がなされた形跡は見当たらない。(甲A146、152、弁論の全趣旨)
エ 現行民法下における婚姻制度
昭和22年民法改正
昭和22年民法改正において、戸主権や家制度に関する規定が廃止されるとともに、戸主や親の婚姻同意権に関する規定が廃止され、未成年者の婚姻に限り父母の同意を要するものとされたほか、財産は夫婦が各自で管理収益するものとされ、配偶者(妻)にも常に相続権が与えられることとなった。(甲A19、180、181)
改正作業における議論
明治民法の改正に係る提案理由においては、明治民法、特に親族編及び相続編に、憲法13条、14条及び24条の基本原則に抵触する幾多の規定が置かれているため、これを改正する必要があるとされていたところ、改正作業は、日本国憲法に抵触する民法規定を中心に行われ、これに抵触しない規定についてはそのまま維持されることとなった。その過程で、同性間の婚姻について議論が行われた形跡は見当たらない。(甲A180、181、乙7、8、弁論の全趣旨)
⑶ 性的少数者の権利保護をめぐる各種国際機関等の動向
ア 国連の条約機関の動向
個人通報制度に基づく救済
市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)委員会は、1994(平成6)年、男性同士の性行為等を処罰する法律は、「私生活の尊重をうける権利」を保障する自由権規約17条に違反し、同規約2条1項及び26条が差別禁止分類として規定する「性(sex)」には性的指向も含まれるとして、同規約2条1項に違反するとの判断を示したほか、2003(平成15)年には、同性同士であることに基づき、同性パートナーに遺族年金の受給資格を与えないことは、同規約26条に違反するとの判断を示した。(甲A31、32、49)
規約の解釈の提示
経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約)委員会は、社会権規約の解釈等を示す一般的意見において、2009(平成21)年に、社会権規約2条2項が差別禁止分類として規定する「他の地位(other status)」には性的指向も含まれ、性的指向は遺族の年金受給権等規約上の権利を実現する上での障害とはならないことを明らかにした(甲A50、216)。
我が国に対する勧告
自由権規約委員会は、2008(平成20)年10月、我が国に対し、当時の公営住宅法や配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(以下「DV防止法」という。)等において、同性カップルが排除されていたことに対し、法改正を検討するよう勧告し、2014(平成26)年8月には、性的志向及び性自認等あらゆる理由に基づく差別を禁止する包括的な反差別法の制定等の勧告を行った(甲A38、95、96、192)。
イ 国連人権理事会の動向
SOGI決議の採択等
国連人権理事会は、2011(平成23)年、我が国を含む23か国の賛成を得て、世界各地での性的指向及び性自認を理由とした暴力や差別に重大な懸念を表明し、人権高等弁務官による人権状況に関する報告書の提出等を要請する決議(SOGI決議)(Human Rights, Sexual Orientation and Gender Identity)を採択し、2014(平成26)年にも、我が国を含む25か国の賛成を得て、同旨の決議を採択した。国連人権高等弁務官が2015(平成27)年に提出した報告書では、同性カップル及びその子供を法的に認知し、これらの者に対しても、結婚したパートナーに与えられてきた給付、年金、課税及び相続等に関する便益が差別なく付与されることが推奨された。(甲A31、34、199、208)
我が国に対する勧告
国連人権理事会が制度構築した普遍的定期的審査(UPR)の下で、我が国に対し、2008(平成20)年の第1回審査及び2012(平成24)年の第2回審査の過程で、複数諸国が、性的指向及び性自認に基づく差別の撤廃に向けた措置を講ずるよう勧告し、2017(平成29)年の第3回審査の過程では、スイスやカナダが、同性婚の公式な承認を国レベルに拡大するなど、地方自治体及び民間企業が性的指向及び性自認に基づく差別を撤廃するための努力を促進するよう勧告を行った。(甲A38、192、193、196ないし198)
ウ その他の動向
国際人権法ならびに性的指向及び性別自認に関する専門家国際委員会は、2006(平成18)年、「性的指向および性自認に関する国際人権法の適用に関連する原則(ジョグジャカルタ原則)」( Principles on the application of international human rights law in relation to sexual orientation and gender identity(THE YOGYAKARTA PRINCIPLES))を採択した。国連の公式文書や政府間の合意文書に属しない同原則は、国際人権法上の規範には該当しないが、既存の人権規定が性的指向や性自認に基づき差別されることなく適用可能であることを全29の原則を掲げて謳うものであり、その中では、家族を形成する権利として、性的指向及び性自認にかかわらず、家族を形成する権利を有することが明らかにされている。(甲A31、33、192)
【筆者】
「家族を形成する権利」とあるが、「家族」の意味の多義性について、当サイト「同性婚訴訟 東京地裁判決の分析」のポイントの部分で解説している。
⑷ 同性カップルの保護をめぐる諸外国の動向
ア 登録パートナーシップ制度による保護
導入国
デンマークは、1989(平成元)年、同性カップルの関係を法的に保護するための法制度として、世界で初めて登録パートナーシップ制度(以下、後記イの制度と併せて「登録パートナーシップ制度等」という。)を導入した。そして、制度の呼称や制度内容の詳細に違いはあるが、1993(平成5)年にはノルウェーが、1994(平成6)年にはスウェーデンが、1996(平成8)年にはアイスランドが、1998(平成10)年にはオランダが、2001(平成13)年にはフィンランド及びドイツが、2004(平成16)年にはルクセンブルク、イギリス、スイス及びニュージーランドが、2009(平成21)年にはオーストリアが、2010(平成22)年にはアイルランドが、2014(平成26)年にはマルタが、それぞれ同様の制度を導入した。(甲A98、140、141、249ないし251)
制度の具体的内容
オランダやルクセンブルク等の国を除き、登録パートナーシップ制度を採用する多くの国が、同性カップルのみを対象としている。そして、一般に、同制度は、同性カップルに対し、婚姻とほとんど同じ法的効果を付与するものであるとされており、前記 の諸外国では、同制度を利用した同性カップルに対し、相続や社会保障、税制上の優遇措置が認められている。(甲A98、140、141)
他方で、養子制度については、例えばオーストリアやイギリス、スウェーデンといった国では、異性カップルとほぼ同等の養子縁組が認められていた一方、ドイツでは、数次の法改正を経たものの、生活パートナー双方が第三者の子を同時に養子縁組することは認められず、アイルランド、ノルウェー等でも、共同養子縁組が認められていなかった。さらに、ニュージーランドでは、養子縁組法(Adoption Act 1955)において、養子縁組が「配偶者」にのみ認められていたため、そもそも登録パートナーカップルには養子縁組を利用する権利が認められていなかったほか、子ども身分法(Status of Children Act 1969)において、嫡出推定の規定の適用を婚姻している女性のみに限定していたことから、登録パートナーカップルが嫡出推定を受けることはできなかった。(甲A98、140、141)
その他にも、例えばイギリスでは、婚姻が性的であり宗教的な制度であるのに対し、パートナーシップ登録は非性的であり世俗的な制度であるとして、不貞行為を解消原因とせず、デンマークでも、登録パートナーカップルは宗教上の挙式を選択できないなど、同性間の婚姻との差異が設けられている。(甲A98、140、141)
【筆者】
上記では、外国の事例で「宗教的な制度」や「挙式」を行うものが挙げられている。
しかし、日本国の婚姻制度は宗教とは一切関係していないし、婚姻制度を利用する場合に「挙式」も必要ない。
この点でも、外国の制度とは性質を異にしており、外国の制度と同一の制度であるかのような前提で比較することは妥当でない。
また、日本国憲法24条の「婚姻」は「生殖と子の養育」に関わる制度を一元的に集約して規律していることから、「生殖と子の養育」に関わる制度を24条の「婚姻」を離れて立法することはできない。
そのため、外国の事例でその一国において「生殖と子の養育」に関わる制度が複数存在する場合があるとしても、日本国憲法24条の「婚姻」の下ではそのような形で制度を創設することはできない。
イ 法定同棲・PACS等による保護
法定同棲
登録パートナーシップ制度においては、財産法・身分法・社会保障法・税法等の広範囲にわたる法的な権利及び義務がパッケージとなって規定されている一方、このような強力な法的効果を望まないカップルのために、ベルギーやスウェーデンが、主として財産法上の法的効果を付与するものとして、法定同棲と呼ばれる制度を導入した。同制度は、同性カップルのみならず、異性カップルにおいても利用できるものとされており、ベルギーでは、兄弟姉妹間でも利用が認められていたほか、相続権や養子制度の利用も認められていた。(甲A98、140、141、249)
パックス(PACS)
フランスでは、当事者の契約によって権利及び義務を設定し公的機関に登録することで、第三者や国に対してカップルであることを対抗できるようにするものとして、パックス(PACS)と呼ばれる制度を導入している。同制度は、同性カップルのみならず、異性カップルにおいても利用できるものとされており、パックスの登録・公示により、民法のほか、労働法、税法、社会保障法上の効果が一体として付与されるものとされている。他方で、パックスの両当事者間では、相続権は認められていないほか、パックス当事者を養親とする養子縁組や生殖補助医療への権利も認められておらず、パックス当事者間に生まれた子は、非嫡出子として扱うものとされている。(甲A98、140、141、249)
民事的結合・事実上の共同生活
イタリアでは、憲法裁判所が、2014(平成26)年、「婚姻」は異性間の結合のみを指し、同性間の結合は婚姻と同質であるとは考えられない旨説示する一方で、同性間の結合について「(婚姻とは)別の形式(altra forma)」を設けておらず、法的に保護されたカップルの関係の維持が認められていないことが違憲である旨説示し、これを受けて2016(平成28)年に「同性間の民事的結合に関する規則及び共同生活の規律」が成立した。民事的結合に関する規定においては、貞操義務がないことや養子縁組に関する規定が存在しないなどの相違点もあるが、基本的には婚姻に関する規定が準用され、事実上の共同生活に関する規定においては、パートナーの処遇、疾病又は入院に際しての扶助、共同生活を営む住居への居住の継続等において一定の権利が認められるものとされている。(甲A98、140、141)
【筆者】
上記では、いくつか外国の事例が述べられている。
しかし、日本国の場合は、日本国憲法24条の「婚姻」は「生殖と子の養育」に関わる制度を一元的に集約して規律していることから、「生殖と子の養育」に関わる制度を憲法24条の「婚姻」を離れて立法することはできない。
そのため、外国の事例でその一国において「生殖と子の養育」に関わる制度が複数存在する場合があるとしても、日本国憲法24条の下ではそのような形で制度を創設することはできない。
また、ここでは「カップル」という「二人一組」に対して制度を設けることを述べるものがある。
しかし、日本国の場合は「三人一組」や「四人一組」、「それ以上の組み合わせ」を形成する者や、何らの制度も利用していない者との間で得られる利益の内容に合理的な理由を説明することができない差異を生じさせることとなるから、憲法14条1項の「平等原則」に抵触して違憲となる。
よって、外国の事例を日本国にもそのまま当てはめて考えることが可能となるわけではない。
ウ 婚姻制度による保護
同性間の婚姻を認めている諸外国
オランダは、2000(平成12)年、同性間の婚姻制度を世界で初めて導入し、2003(平成15)年にはベルギーが、2005(平成17)年にはスペイン及びカナダが、2006(平成18)年には南アフリカが、2008(平成20)年にはノルウェーが、2009(平成21)年にはスウェーデンが、2010(平成22)年にはポルトガル、アイスランド及びアルゼンチンが、2012(平成24)年にはデンマークが、2013(平成25)年にはフランス、ウルグアイ、ニュージーランド、ブラジル及びイギリス(イングランド及びウェールズ)が、2015(平成27)年にはルクセンブルク及びアイルランドが、2016(平成28)年にはコロンビアが、2017(平成29)年にはフィンランド、マルタ、ドイツ及びオーストラリアが、2019(平成31又は令和元)年には台湾、オーストリア及びエクアドルが、2020(令和2年)にはコスタリカが、それぞれ同性間の婚姻を容認するに至っている(甲A98、135ないし138、140、141、249ないし251)。
また、アメリカでは、連邦最高裁判所が、2015(平成27)年、オバーゲフェル判決(Obergefell v. Hodges)において、同性カップルに婚姻許可証を発給しないこと及び同性婚を承認しないことは、合衆国憲法修正第14条に違反するとの判断を示し、これによって、全ての州が、同性カップルと異性カップルとの区別なく婚姻を認めるとともに、他州において合法的に成立した婚姻を承認する義務を負うこととなった(甲A98、99、141)。
【筆者】
アメリカにおける婚姻は、日本国における婚姻制度とは性質が異なっている。
ただ、米国のObergefell判決を、日本国の法制度に照らし合わせて考えると、下記の論点で誤っていると考えられる。
⑤ 「カップル信仰論」になっていること
⑥ 「カップル間不平等論」になっていること
⑨ 婚姻制度は「性愛」を保護することを立法目的にはしていないこと
⑫ 「近親者」「三人以上の複数名」「婚姻適齢に満たない者」との間でも同様に語ることができること
(論点番号については、当サイト『同性婚訴訟 大阪地裁判決の分析』より)
同性間の婚姻の内容
前記 の諸外国では、同性婚と異性婚とでほとんど差異は生じていないものの、例えば、嫡出推定の規定について、スペインでは同性カップルに対し、オランダでは男性カップルに対し、その適用を排除するほか、生殖補助医療については、フランスでは同性カップルに対し、スペインでは男性カップルに対し、これを認めないなどの差異を設ける立法例も存在する。さらに、カナダや南アフリカ、ノルウェー、デンマークといった諸国では、宗教上の配慮に基づき、宗教者が同性カップルの婚姻の挙式を拒否する権利を認めている。また、同性カップルによる養子縁組については、オランダ、ベルギー及びポルトガルでは当初は認められず、後の改正を経て認められたという経過を辿っている。(甲A98、140、141)
【筆者】
上記では、「同性間の人的結合関係」をその国の法制度によって位置付けているものが取り上げられている。
(それぞれの国は、それぞれの国の社会事情に応じて、そこで生じる問題を解決することを目的として法制度を定めているだけであるから、ここで日本法のいう『婚姻』という概念と完全な対応関係にあるわけではない。そのため、『婚姻』という言葉を使って同一の概念であるかのように扱うことには抵抗がある。)
しかし、外国では、「一夫多妻型」の制度を立法している場合もあるのであり、「同性間の人的結合関係」のみを取り上げて論じようとすることは、特定の結論を導き出すために恣意的に視野を狭めようとするものとなるため妥当ではない。
【参考】「一夫多妻制が認められているところが世界にはあるって言ったらどうなる」 Twitter
【参考】一夫多妻制 Wikipedia
⑸ 性的少数者の権利保護に向けた我が国の動向
ア 国の施策等
性的志向に対する偏見や差別の解消に向けた施策
政府は、平成14年3月に人権教育及び人権啓発に関する基本計画を、平成22年12月及び平成27年12月に、それぞれ第3次男女共同参画基本計画及び第4次男女共同参画基本計画を閣議決定した。これらの基本計画においては、性的指向を理由とする差別や偏見の解消に向けた啓発活動等に取り組むこととされたところ、法務省人権擁護局において、主な人権課題の一つとして、啓発活動等が行われている。(甲A57ないし59、211、212、514ないし516、弁論の全趣旨)
性同一性障害特別措置法の制定
我が国では、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(性同一性障害特別措置法)(平成15年法律第111号)が、平成16年7月に施行され、一定の要件を満たす性同一性障害者について、戸籍上の性別の変更が認められるようになった。そして、平成20年6月には、性別変更に必要な要件として、同法3条1項3号が定めていた「現に子がいないこと」が「現に未成年の子がいないこと」と改正され(平成20年法律第70号)、性別変更に必要な要件の緩和が行われた。
【筆者】
この段落と関連する内容について、当サイト「性別と思想」で解説している。
国(行政府)の主張でも少し記載がある。
【札幌・第5回】被告第3準備書面 令和2年5月15日 (P7)
公営住宅法、DV防止法の改正
平成23年法律第37号による改正前の公営住宅法23条1項1号は、公営住宅の入居資格要件として、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があることを掲げていたところ、同年改正により、同号の規定は削除された。ただし、その経緯については、地方分権改革の中で、図らずも、要件が削除されたにすぎないとの評価がある(甲A192)。
また、DV防止法1条3項は、保護の対象となる「配偶者」について、「婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者」を含むと規定していたところ、平成25年法律第72号による改正により、「生活の本拠を共にする交際(婚姻関係における共同生活に類する共同生活を営んでいないものを除く。)」をする関係にある相手からの暴力について、準用規定が設けられた(同法28条の2)。ただし、同法が同性間へ適用されるかについては慎重に検討されるべきとの見解がある(甲A40)。
イ 各種政党の取組み
立憲民主党、共産党及び社民党の議員らは、令和元年6月、同性婚の法制化のため、民法739条1項を、「婚姻は、異性又は同性の当事者が戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる」と改正することを内容とする「民法の一部を開始する法律案要綱」を衆議院に提出した(甲A115、116、509)。
ウ 地方自治体の施策等
計画・指針等の策定
東京都は、平成12年11月に公表した人権施策推進指針の中で、性同一性障害を有する者や同性愛者をめぐる人権問題の解決に向けた議論を深める必要があることを指摘し、その後、複数の地方自治体において、性的指向及び性自認について言及した計画・指針等が定められるようになった(甲A66、67)。
条例等の制定等
複数の地方自治体において、性的指向の尊重又は差別の禁止を掲げる条例等が制定され、平成27年4月には、東京都渋谷区において、登録パートナーシップ制度が創設された。そして、同様の制度は、他の地方自治体にも拡大し、登録パートナーシップ制度を導入している地方自治体は、令和4年1月時点で147となった。また、登録パートナーシップ制度を導入している地方自治体の中には、相互に協定を取り交わすことにより、パートナーシップ登録の相互利用を可能とする取組みを行うものもある。(甲A67ないし91、303ないし355、395ないし436、477)
また、東京都世田谷区では、令和2年4月1日から、同性パートナーがいる区職員に対し、結婚休暇、出産支援休暇、看護休暇等を、異性パートナーがいる区職員と同等に認める取組みが行われており、鳥取県においても、同様の取組みが行われている。そして、東京都世田谷区では、新型コロナウイルスに対応した国民健康保険の特例措置をめぐり、同年6月、被保険者が死亡した場合に遺族に支給される傷病手当金を、同性パートナーにも支給することを明らかにした。(甲A356ないし358)
【筆者】
地方自治体の「登録パートナーシップ制度」について述べられている。
しかし、地方公共団体の制定する「条例」や「規則」、「要綱」などは、国会の制定する法律に違反してはならないため、民法に定められた婚姻制度に抵触するものとなっている場合には違法となる。
下記で条例制定権の限界に関する判例を読み取る。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
すなわち、地方自治法一四条一項は、普通地方公共団体は法令に違反しない限りにおいて同法二条二項の事務に関し条例を制定することができる、と規定しているから、普通地方公共団体の制定する条例が国の法令に違反する場合には効力を有しないことは明らかであるが、条例が国の法令に違反するかどうかは、両者の対象事項と規定文言を対比するのみでなく、それぞれの趣旨、目的、内容及び効果を比較し、両者の間に矛盾牴触があるかどうかによつてこれを決しなければならない。例えば、ある事項について国の法令中にこれを規律する明文の規定がない場合でも、当該法令全体からみて、右規定の欠如が特に当該事項についていかなる規制をも施すことなく放置すべきものとする趣旨であると解されるときは、これについて規律を設ける条例の規定は国の法令に違反することとなりうるし、逆に、特定事項についてこれを規律する国の法令と条例とが併存する場合でも、後者が前者とは別の目的に基づく規律を意図するものであり、その適用によつて前者の規定の意図する目的と効果をなんら阻害することがないときや、両者が同一の目的に出たものであつても、国の法令が必ずしもその規定によつて全国的に一律に同一内容の規制を施す趣旨ではなく、それぞれの普通地方公共団体において、その地方の実情に応じて、別段の規制を施すことを容認する趣旨であると解されるときは、国の法令と条例との間にはなんらの矛盾牴触はなく、条例が国の法令に違反する問題は生じえないのである。�
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
集団行進及び集団示威運動に関する徳島市条例違反、道路交通法違反 最高裁判所大法廷 昭和50年9月10日 (PDF) (徳島市公安条例事件)
この判例によれば、下記の場合には、「地方公共団体」において「登録パートナーシップ制度」を導入していることは、違法となる。
◇ 「国の法令中にこれを規律する明文の規定がない場合でも、当該法令全体からみて、右規定の欠如が特に当該事項についていかなる規制をも施すことなく放置すべきものとする趣旨であると解されるとき」
◇ 条例の「適用によつて」、国の法令「の規定の意図する目的と効果を」「阻害する」場合
そこで、民法上の婚姻制度の「趣旨、目的、内容及び効果」を検討すると婚姻制度の立法目的と、その達成手段は下記のように整理することができる。
〇 「子の福祉」が実現される社会基盤を構築すること
(→ 達成手段:嫡出子として父親を特定することができる状態で生まれることを重視)
〇 潜性遺伝子の発現した個体が高い確率で生じることを抑制すること
(→ 達成手段:貞操義務と嫡出推定、再婚禁止期間によって遺伝的な父親を極力特定し、それを基に遺伝的な近親者を把握し、近親婚を認めないことによって『近親交配』に至ることを防止)
〇 「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」を減らすこと
(→ 達成手段:未婚の男女の数の不均衡を防止できる組み合わせに限定。一夫一婦制。重婚や重婚状態、複婚や複婚状態の防止。)
〇 母体を保護すること
(→ 達成手段:婚姻適齢を設定)
「登録パートナーシップ制度」の内容が、これらの目的を達成することを阻害するものとなっている場合には、民法の婚姻制度に抵触して違法となる。
婚姻制度は遺伝上の父親を特定することにより、その者にも子に対する養育の責任を担わせることによって、「子の福祉」を実現しようとするものとなっていることから、父親を特定することができない人的結合関係に対して何らかの優遇措置を与えることは、この目的を達成することを阻害することになるから、婚姻制度に抵触して違法となる。
また、「登録パートナーシップ制度」の内容が「男女二人一組」の形であるとしても、そこに「貞操義務」が設けられていないのであれば、結局は制度の内容に従って適法な行動をしていたとしても、子の母親となる者は「登録パートナーシップ制度」を利用する相手方とは異なる他の男性との間で生殖を行っている可能性を排除することができないことから、父親を特定することができなくなるため、このような人的結合関係に対して何らかの優遇措置を与えることは、婚姻制度に抵触して違法となる。
婚姻制度は遺伝上の父親を特定することにより、その父親にも子に対する養育の責任を担わせることによって「子の福祉」を実現しようとするものであるから、婚姻制度を利用しない人的結合関係に対しては意図的に優遇措置を与えないことにより、「生殖」によって子供をつくる者が婚姻制度を利用することによって遺伝的な父親を特定できる人的結合関係を形成するようにインセンティブを与えるものとなっている。しかし、国民が「登録パートナーシップ制度」を利用することにより、婚姻制度を利用した場合と同様の優遇措置や類似した優遇措置を得られることを理由に、婚姻制度を利用するのではなく「登録パートナーシップ制度」を利用することに安住してしまうことになれば、婚姻制度が遺伝的な父親を特定することによって達成しようとした立法目的の達成を阻害することになる。よって、婚姻制度とは異なる選択肢として「登録パートナーシップ制度」を設け、婚姻制度と同様の優遇措置や類似した優遇措置を得られるようにすることは、婚姻制度に抵触して違法となる。
(ここで『婚姻制度とは異なる選択肢として』と記載している意味は、『企業間パートナーシップ』『商工業パートナーシップ』『貿易におけるパートナーシップ』など、婚姻とはまったく関わらない制度については、婚姻制度には抵触しないことを意味するものである。単に地方公共団体の政策担当者が『登録パートナーシップ制度』について『婚姻制度とは異なる制度である』と言い張るだけで、その『登録パートナーシップ制度』が民法の婚姻制度に違反しなくなって適法となるわけではなく、その『趣旨、目的、内容及び効果』が実質的に婚姻制度と競合したり、影響を与えることになるかどうかを判断することが必要である。)
婚姻制度には、遺伝上の父親を特定することによって近親者の範囲を把握し、それらの者との間で婚姻制度を利用できないことにすることで、「近親交配」に至ることを防ぎ、潜性遺伝子を有する個体が高い確率で発現することを防ぐ目的がある。この観点から、「女性同士の組み合わせ」に対して優遇措置を与えることは、遺伝的な父親を特定することができない関係の中で子供を産むことを促進する作用を持つものとなるから、遺伝的な近親者の範囲を把握することができなくなり、子供の世代において意図せずに「近親交配」に至る確率が高くなる。そうなれば、婚姻制度が潜性遺伝子を有する個体が高い確率で発現することを防ごうとする意図を達成することができなくなるのであり、婚姻制度の立法目的の達成を阻害することになる。よって、「登録パートナーシップ制度」の内容が、「女性同士の組み合わせ」(『女性三人以上の組み合わせ』であっても同様)に対して婚姻制度と同様の、あるいは類似する優遇措置を与えることは、婚姻制度に抵触して違法となる。
さらに、「登録パートナーシップ制度」においても婚姻制度と同様の、あるいは類似した優遇措置を得られることを理由として、同性間の人的結合関係を結んで「登録パートナーシップ制度」を利用する者が増えた場合には、制度を利用していない男女の数の不均衡が生じることにより、「子を持ちたくても相手が見つからずに子を持つ機会に恵まれない者」が増えることに繋がる。これは、婚姻制度が「男女二人一組」の形に限定することによって、「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」を減らそうとする立法目的の達成を阻害するものとなるから、婚姻制度に抵触して違法となる。
さらに、「登録パートナーシップ制度」の中には、「性愛(性的指向)」という特定の思想や信条、感情を保護することを目的としているものがあり、このような目的をもって制度を立法することは憲法20条1項後段・3項、89条の「政教分離原則」に抵触して違憲となる。
他にも、ある特定の人的結合関係の間に生じる「性愛(性的指向)」のみを制度の対象とし、それ以外の人的結合関係の間に生じる「性愛(性的指向)」を制度の対象としていないことは、個々人の内心に基づいて区別取扱いをするものであるから、憲法19条の「思想良心の自由」に抵触して違憲となるし、そのような区別取扱いは、憲法14条の「平等原則」に抵触して違憲となる。
加えて、憲法24条の「婚姻」の文言は、「生殖と子の養育」に関わる制度を一元的に集約して規律する趣旨を有しており、もし「生殖と子の養育」に関わる制度を24条の「婚姻」を離れて別の制度として立法した場合には、24条の「婚姻」の文言に抵触して違憲となる。
なぜならば、憲法24条が「婚姻」の内容に対して立法裁量の限界を画することによって、法律上の「婚姻」の制度を規律しているにもかかわらず、その憲法24条の制約を回避する形で制度を立法することができることになれば、憲法24条の規定そのものが有する効力が損なわれた状態となり、24条の規定が骨抜きとなるからである。
よって、「婚姻」が「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として、「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた枠組みである以上は、その「生殖と子の養育」に関わる制度については、24条の「婚姻」の文言が一元的に集約して規律する趣旨を有しており、これを離れて「生殖と子の養育」に関わる制度を立法することはできない。
そのため、ここでいう「登録パートナーシップ制度」の内容が「生殖と子の養育」に関わる制度となっている場合や、「生殖と子の養育」に影響を与えることが考えられる制度となっている場合には、そのこと自体で憲法24条の「婚姻」に抵触して違憲となる。
その他、「登録パートナーシップ制度」は「二人一組」を前提とするものとなっているが、婚姻制度のような「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的との関係で、一般的・抽象的にその間で「生殖」を想定することができる「男性」と「女性」の揃う「二人一組」を対象としてその目的の実現を目指すものとは異なるものであるから、そのような目的を有しない「二人一組」の間に何らかの制度を設けることは、「三人一組」や「四人一組」などの他の様々な人的結合関係との間で異なる取扱いをすることを正当化することのできる理由はないし、何らの制度も利用していない者との間でも合理的な理由を説明することのできない差異を生じさせることになる。
そのため、「二人一組」の人的結合関係のみを「登録パートナーシップ制度」の対象としていることについても、憲法14条の「平等原則」に抵触して違憲となる。
よって、このように「登録パートナーシップ制度」が民法上の婚姻制度や憲法上の規定に抵触するか否かの論点が存在するにもかかわらず、あたかも「パートナーシップ制度」が適法な制度であるかのような前提に基づいて論じていることは妥当でない。
「登録パートナーシップ制度」が法律に違反するか否かそのものが、婚姻制度の立法目的とそれを達成するための手段となる枠組みの当否の問題に直接的に関わっているにもかかわらず、これを論じずに「登録パートナーシップ制度」が適法に成立することができることを前提に話を進めている点で、十分な検討を行っているとはいえない。
詳しくは当サイト「パートナーシップ制度」で解説している。
国に対する提言
指定都市市長会は、平成30年7月、内閣府に対し、各府省が所管する性的少数者に係る様々な施策を総合的に調整し、一元管理する組織を明確にすることにより、国としての取組みを強化することのほか、性の多様性を認め合う社会の実現に向けて、先行自治体の取り組み事例や意見等を踏まえ、性的少数者への理解促進や取組みの強化に関する取組方針を示すよう要請した。また、令和2年12月には、大和郡山市議会及び東京都清瀬市議会が、それぞれ、衆参議院議長、内閣総理大臣及び法務大臣に対し、同性婚の法制化に関する議論の促進を要請する意見書を提出した。(甲A92、93、359、360)
エ その他の諸団体の提言・取組み等
民間企業等
一般社団法人日本経済団体連合会は、平成29年5月16日、ダイバーシティ・インクルージョン社会の実現に向けて、LGBTの人々に関する対応に経済界として初めて焦点を当てて、各企業の取り組み状況を紹介するとともに、どのような対応が考えられるかを提言するとし、同性パートナーに慶弔休暇や家族手当等を適用し、同性カップル及びその子に福利厚生を拡大するなどといった取組みを行う企業など、多数の日本を代表する企業による取組み例を紹介した。また、株式会社東洋経済新報社作成の「CSR企業総覧」によれば、LGBTに対しての基本方針(権利の尊重や差別の禁止等)を定めていると回答した会社は、平成28年1月4日時点で1325社中173社(約13%)であったのが、令和元年12月3日時点では1593社中364社(約22.8%)にまで増加した。(甲A94、291、292)
弁護士会
北海道弁護士会連合会は、平成30年7月、政府及び国会に対して同性間の婚姻を認める法制度の整備を求める旨を決議した。また、令和元年2月には、日本組織内弁護士協会が、同性カップルに婚姻の権利を認めるべきであるとする提言を行ったほか、令和元年7月には、日本弁護士連合会も、法務大臣、内閣総理大臣及び衆参議院議長に対し、同性婚を認めるための関連法令の改正を速やかに行うべきであるとの提言を行った。さらに、令和3年3月以降、複数の弁護士会が、同性間の婚姻を認める立法を直ちに整備するよう求める会長声明を発表した。(甲A113、134、153、154、383ないし393)
在日外国団体
在日米国商工会議所は、平成30年9月、政府に対し、LGBTカップルに婚姻の権利を認めることにより、人材の採用や維持、多様な従業員の公平な処遇において直面している障害を取り除くことができるとの提言を行い、在日オーストラリア・ニュージーランド商工会議所、在日英国商工会議所、在日カナダ商工会議所、在日アイルランド商工会議所のほか、在日デンマーク商工会議所が、同提言を支持した(甲A112、131ないし133)。
日本学術会議
日本学術会議法学委員会は、平成29年9月、我が国における顕著な家族の多様化と欧米諸国の動向に照らせば、婚姻の性中立化は必須であり、そのための民法改正が求められる旨の提言を発表した(甲A114)。
⑹ 同性婚の是非等に関する意識調査
ア 国民全体を対象とした意識調査
平成29年までの意識調査
同性婚を法的に認めることの可否について、日本世論調査会が平成26年に行った意識調査では、賛成派(賛成・やや賛成と回答した者。以下同じ。)は42.3%、反対派(反対・やや反対と回答した者。以下同じ。)は52.4%であった。また、毎日新聞社が平成27年に行った意識調査では、賛成は44%、反対は39%であり、河口和也広島修道大学教授(以下「河口教授」という。)らが同年に行った意識調査では、賛成派は51.2%、反対派は41.3%であった。さらに、NHKが平成29年に行った意識調査では、賛成は50.9%、反対は40.7%であり、朝日新聞社が同年に行った意識調査では、賛成は49%、反対は39%であった。(甲A104ないし109)
平成30年以降の意識調査
同性婚を法的に認めることの可否について、株式会社電通が平成30年に全国の20ないし50代のLGBT以外の男女を対象に行った意識調査では、賛成派は男性で69.2%、女性で87.9%であった。また、河口教授らが令和元(平成31)年に行った意識調査では、賛成派は64.8%、反対派は30.0%であったほか、朝日新聞社と東京大学の谷口将紀研究室が令和2年に実施した意識調査では、賛成派は46%、反対派は23%であり、NHKが令和3年に行った意識調査では、賛成派は56.7%、反対派は36.6%であった。(甲A110、368、441、479)
【筆者】
この「ア」の項目では二回「同性婚」との文言が出てくるが、この「婚」の意味である「婚姻」とは何かが問題となる。
「婚姻」は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度である。
「同性間の人的結合関係」については、その間で「生殖」を想定することができず、「生殖と子の養育」の趣旨を満たすとはいえないことから「婚姻」とすることはできない。
そのため、法律論としては「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることができないことから、「同性婚」という文言を用いていることは妥当でない。
よって、ここでは「同性婚を法的に認めることの可否」について「賛成派」と「反対派」を取り上げて論じようとしているが、それ以前の問題として法的には「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることはできない。
このことは、「独り者婚」を「法的に認めることの可否」について「賛成」か「反対」かを調査した場合においても、「独り者」を「婚姻」とすることはできないという点で妥当でないことと同様である。
イ 性的少数者を対象とした意識調査
平成27年の意識調査
NHKが平成27年に性的少数者を対象に行った意識調査では、地方自治体の行うパートナーシップ登録の申請を希望するかについて、申請したい(パートナーができたら申請したいを含む。)と回答した者は82.4%、申請したくないと回答した者は17.6%であり、申請したいと回答した者の半数以上が、その理由として「今後、法律上、家族として認めて欲しいのでその第一歩として」との理由を挙げたほか、同性婚を法的に認めることについて、賛成と回答した者は65.4%、結婚ではなくパートナー関係の登録制度を国が作ってほしいと回答した者は25.3%であった(甲A103)。
【筆者】
本人が「性的少数者」であるかどうかを第三者が外部から客観的に判断できるものはないのであり、このような「調査」と称するものも、すべて本人が「性的少数者」であると「自称」しているだけのものを根拠としたものである。
法律論を組み立てる際に、このような内容を取り上げて論じることはできないことに注意が必要である。
令和元年の意識調査
日高庸晴宝塚大学看護学部教授が令和元年に性的少数者を対象に行った意識調査では、異性婚と同じ法律婚を同性間にも適用してほしいと回答した者は60.4%、公的制度を作る必要はないが、社会の理解は今より浸透してほしいと回答した者は16.2%、その余の回答は、概ね、国レベル又は自治体レベルのパートナーシップを制定してほしいというものであった(甲A369)。
【筆者】
「性的少数者を対象に行った意識調査」との記載がある。
しかし、「性的少数者」であるか否かは、そもそも「内心の自由」に属する個々人の内心によるものであることから、本人が「性的少数者」であるか否かを明確に判断することのできる客観的な基準となるものは存在しない。
そのため、「性的少数者を対象に行った意識調査」としている内実は、本人が自らを「性的少数者」であると自称している者を対象にした調査に過ぎない。
【参考】アメリカの若者の30%以上が「自分はLGBTQ」と認識していることが判明 2021年10月26日
よって、法律論を組み立てる際に、このような内容を取り上げて論じることはできない
⑺ 婚姻に関する意識調査、統計
ア 婚姻に関する意識調査
内閣府の意識調査
内閣府の平成17年版国民生活白書によれば、結婚のメリットについて、家族や子供を持てると回答した者が最も多く(既婚者で63.5%、未婚者で58.2%)、2番目に多く選ばれた項目は、既婚者で、精神的な安定が得られることであり(61.9%)、未婚者で、好きな人と一緒にいられること(57.7%)であった。そして、結婚すると強く実感できる「家庭」の持つ価値については、既婚者では、家族の団らんの場と回答した者が最も多く(63.8%)、休息・安らぎの場と回答した者が2番目に多く(57.3%)、未婚者では、休息・安らぎの場と回答した者が最も多く(55.4%)、家族の団らんの場と回答した者が2番目に多かった(54.9%)。(甲A232)
次に、内閣府が平成23年に公表した結婚・家族形成に関する調査報告書によれば、既婚者が結婚した理由について、好きな人と一緒にいたかったと回答した者が61.0%、家族を持ちたかったと回答した者が44.2%、子供が欲しかったと回答した者が32.5%であった。また、平成27年の調査報告書によれば、未婚者が将来結婚したいと考える理由については、家族を持ちたいと回答した者、子供が欲しいと回答した者が共に70.0%であり、好きな人と一緒にいたいと回答した者が68.9%であった。(甲A233、234)
厚生労働省の意識調査
厚生労働白書によれば、結婚は個人の自由だから結婚してもしなくてもどちらでもよいと考え方について、平成21年調査では、賛成派は、平成4年の62.7%から70.0%にまで上昇したのに対し、反対派は、同年の31.0%から28.0%にまで減少した(甲A223)。
NHKの意識調査
NHKが実施する「日本人の意識」調査によれば、平成30年調査において、人は結婚するのが当たり前だと回答した者は、平成5年の45%から27%に減少した一方、必ずしも結婚する必要はないと回答した者は平成5年の51%から68%にまで上昇した。また、結婚したら子供を持つのが当たり前だと回答した者は、同年の54%から33%にまで減少した一方、結婚しても必ずしも子供を持たなくてもよいと回答した者は、同年の40%から60%にまで上昇した。(甲A228)
国立社会保障・人口問題研究所の意識調査
国立社会保障・人口問題研究所が実施する全国家庭動向調査によれば、夫婦は子供を持って初めて社会的に認められるとの考えについて、平成30年調査では、賛成派の既婚女性は、平成20年の35.8%から24.7%にまで減少した一方、反対派の既婚女性は、同年の64.2%から75.4%にまで上昇した(甲A229)。
上記研究所が平成27年に実施した意識調査によれば、未婚者(18歳ないし34歳。以下同じ。)のうち、いずれ結婚するつもりであると回答した者は、男性では85.7%、女性では89.3%であったほか、生涯独身で過ごすというのは望ましい生き方ではないとの考え方について、賛成は、男性では64.7%、女性では58.2%、反対は、男性では32.8%、女性では40.2%であった。また、未婚者で結婚することに利点があると感じている者は、昭和62年以降、男性で概ね6割台、女性で概ね7割台で推移しており、その具体的な利点については、平成27年時点で、男女ともに子供や家族を持てると回答した者が最も多く(男性で35.8%、女性で49.8%)、精神的安らぎの場が得られると回答した者が2番目に多かった(男性で31.1%、女性で28.1%)。また、子供を持つ理由について、結婚して子供を持つことは自然なことだからと回答した未婚者は、男性で48.4%、女性で39.0%であった。そして、結婚したら、子どもは持つべきだと回答した者は、未婚男性の75.4%、未婚女性の67.4%、既婚女性の66.6%であった。(甲A226、230)
イ 婚姻に関する統計
婚姻件数、婚姻率等
厚生労働省の調査によれば、我が国の婚姻件数は、昭和47年に110万組となり、その後は減少したが、平成28年でも62万0531組であった。また、婚姻率(全婚姻件数を総人口で除した上で1000を乗じた割合)は、昭和22年頃の約12から、平成28年には5にまで減少したものの、ヨーロッパ諸国(ただし、ロシア及びスウェーデンを除く。)に比べて高水準にある。なお、我が国の年間出生総数に占める非嫡出子の割合は、統計上の数値(大正9年から平成29年)によれば、最大でも8.25%(大正8年)、最小では0.78%(昭和51年)であり、平成29年時点でも2.23%であった。(甲A224、227の3)
また、我が国の50歳の未婚割合は、平成27年時点で、男性で23.4%、女性で14.1%であった(甲A226)。
【筆者】
日本国の「非嫡出子の割合」は他国とは大きく異なっており、婚姻制度の内容や機能が他国とは異なることは明らかである。
【参考】男女格差を失くすと豊かな一夫多妻的な社会になる 2016.10.05
【参考】表4-18 嫡出でない子の出生数および割合:1920~2015年
世帯人員の状況等
厚生労働省の調査によれば、平成30年時点で、全世帯総数のうち単独世帯が占める割合は、昭和61年の18.2%から27.7%にまで上昇し、夫婦のみ世帯が占める割合も、昭和61年の14.4%から24.1%にまで上昇した一方、夫婦と未婚の子のみの世帯は、昭和61年の41.4%から29.1%にまで減少した。(甲A225)
2 本件諸規定が憲法24条及び14条1項に違反するかについて(争点1)
⑴ 原告らは、憲法24条1項は、人と人の親密な関係に基づく、永続性をもった共同生活について、法律が要件と効果を定めて保護を与え承認・公証する制度である法律婚制度の存在を前提に、人が国家や第三者に干渉されることなく、望む相手との意思の合致のみにより婚姻をなし得る自由(婚姻の自由)を保障しており、このような婚姻の自由は同性間に対しても及ぶものと解すべきところ、同性間の婚姻を認めていない本件諸規定は同項に違反すると主張し、本件諸規定が、同性間の婚姻を認めていないことは、同性愛者の尊厳を毀損するものであり、かかる尊厳の毀損を許容できるほどの合理性や必要性を見出すことは不可能であるから、同条2項にも違反すると主張する。そして、仮に同性間の婚姻を求める権利利益が同条の保障する範囲でないとしても、婚姻により生じる諸々の法的利益を享受する権利は重大な法的利益であり、これが性的指向や性別により不合理な差別を受ける場合には、憲法14条1項違反となると主張する。
なお、原告らは、平成31年2月3日、両名を当事者とする婚姻届を提出し、同月7日、不受理とされたものであるが(前提事実⑵)、同性間に対して婚姻を認めるべきであるとする社会的要請が高まったことについて、同日以降の事実も併せて主張しており、現時点までに同性間の婚姻が認められていない状態に対する違法を主張する趣旨であると解される上、原告らにおいて改めて婚姻届を提出することが可能であり、その場合、現状においては不受理とされることが確実であると想定できるから、控訴審も事実審であることに鑑み、本件諸規定の憲法適合性判断に当たっては、当審の口頭弁論終結時までの事情を基礎として判断するのが相当である。
⑵ 憲法24条1項に違反するかについて
ア 憲法24条1項は、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」と規定しているところ、これは、婚姻をするかどうか、いつ誰と婚姻をするかについては、当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたものと解される。婚姻は、これにより、配偶者の相続権(民法890条)や夫婦間の子が嫡出子となること(同法772条1項等)などの重要な法律上の効果が与えられるものとされているほか、近年家族等に関する国民の意識の多様化が指摘されつつも、国民の中にはなお法律婚を尊重する意識が幅広く浸透していると考えられることを併せ考慮すると、上記のような婚姻をするについての自由は、憲法24条1項の規定の趣旨に照らし、十分尊重に値するものと解することができる。そして、同条2項は「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。」と規定している。婚姻及び家族に関する事項は、国の伝統や国民感情を含めた社会状況における種々の要因を踏まえつつ、それぞれの時代における夫婦や親子関係についての全体の規律を見据えた総合的な判断を行うことによって定められるべきものである。したがって、その内容の詳細については、憲法が一義的に定めるのではなく、法律によってこれを具体化することがふさわしいものと考えられる。同条2項は、このような観点から、婚姻及び家族に関する事項について、具体的な制度の構築を第一次的には国会の合理的な立法裁量に委ねるとともに、その立法に当たっては、同条1項も前提としつつ、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきであるとする要請、指針を示すことによって、その裁量の限界を画したものといえる。(最高裁平成25年 第1079号同27年12月16日大法廷判決・民集69巻8号2427頁(以下「再婚禁止期間大法廷判決」という。)、最高裁平成26年
第1023号同27年12月16日大法廷判決・民集69巻8号2586頁(以下「夫婦同氏制大法廷判決」という。)参照)
【筆者】
ここで示された判決は、下記の通りである。
・ 灰色で潰した部分は、最高裁の二つの「大法廷判決」とこの名古屋地裁判決とを合わせて三つの判決の間で共通する部分である。
・ 黄緑色で潰したの部分は、「再婚禁止期間大法廷判決」とこの名古屋地裁判決の間で共通する部分である。
・ 黄色で潰した部分は、「夫婦同氏制大法廷判決」とこの名古屋地裁判決の間で共通する部分である。
・ 潰していない残った部分が、それぞれの「大法廷判決」とこの名古屋地裁判決の上記の部分とは共通していないところである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ところで,婚姻及び家族に関する事項は,国の伝統や国民感情を含めた社会状況における種々の要因を踏まえつつ,それぞれの時代における夫婦や親子関係についての全体の規律を見据えた総合的な判断を行うことによって定められるべきものである。したがって,その内容の詳細については,憲法が一義的に定めるのではなく,法律によってこれを具体化することがふさわしいものと考えられる。憲法24条2項は,このような観点から,婚姻及び家族に関する事項について,具体的な制度の構築を第一次的には国会の合理的な立法裁量に委ねるとともに,その立法に当たっては,個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきであるとする要請,指針を示すことによって,その裁量の限界を画したものといえる。また,同条1項は,「婚姻は,両性の合意のみに基いて成立し,夫婦が同等の権利を有することを基本として,相互の協力により,維持されなければならない。」と規定しており,婚姻をするかどうか,いつ誰と婚姻をするかについては,当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたものと解される。婚姻は,これにより,配偶者の相続権(民法890条)や夫婦間の子が嫡出子となること(同法772条1項等)などの重要な法律上の効果が与えられるものとされているほか,近年家族等に関する国民の意識の多様化が指摘されつつも,国民の中にはなお法律婚を尊重する意識が幅広く浸透していると考えられることをも併せ考慮すると,上記のような婚姻をするについての自由は,憲法24条1項の規定の趣旨に照らし,十分尊重に値するものと解することができる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「再婚禁止期間大法廷判決」 (PDF)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2(1) 憲法24条は,1項において「婚姻は,両性の合意のみに基いて成立し,夫婦が同等の権利を有することを基本として,相互の協力により,維持されなければならない。」と規定しているところ,これは,婚姻をするかどうか,いつ誰と婚姻をするかについては,当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたものと解される。
本件規定は,婚姻の効力の一つとして夫婦が夫又は妻の氏を称することを定めたものであり,婚姻をすることについての直接の制約を定めたものではない。仮に,婚姻及び家族に関する法制度の内容に意に沿わないところがあることを理由として婚姻をしないことを選択した者がいるとしても,これをもって,直ちに上記法制度を定めた法律が婚姻をすることについて憲法24条1項の趣旨に沿わない制約を課したものと評価することはできない。ある法制度の内容により婚姻をすることが事実上制約されることになっていることについては,婚姻及び家族に関する法制度の内容を定めるに当たっての国会の立法裁量の範囲を超えるものであるか否かの検討に当たって考慮すべき事項であると考えられる。
(2) 憲法24条は,2項において「配偶者の選択,財産権,相続,住居の選定,離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては,法律は,個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して,制定されなければならない。」と規定している。
婚姻及び家族に関する事項は,関連する法制度においてその具体的内容が定められていくものであることから,当該法制度の制度設計が重要な意味を持つものであるところ,憲法24条2項は,具体的な制度の構築を第一次的には国会の合理的な立法裁量に委ねるとともに,その立法に当たっては,同条1項も前提としつつ,個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきであるとする要請,指針を示すことによって,その裁量の限界を画したものといえる。
3(1) 他方で,婚姻及び家族に関する事項は,国の伝統や国民感情を含めた社会状況における種々の要因を踏まえつつ,それぞれの時代における夫婦や親子関係についての全体の規律を見据えた総合的な判断によって定められるべきものである。特に,憲法上直接保障された権利とまではいえない人格的利益や実質的平等は,その内容として多様なものが考えられ,それらの実現の在り方は,その時々における社会的条件,国民生活の状況,家族の在り方等との関係において決められるべきものである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「夫婦同氏制大法廷判決」 (PDF)
この段落は、上記に挙げた「再婚禁止期間大法廷判決」の文面を中心としているが、憲法24条1項と2項を論じる順番については「夫婦同氏制大法廷判決」を参考としているようである。
しかし、このような形で最高裁判決を組み合わせたことによって、この段落では整合性に乱れが生じている。
まず、この段落の「憲法24条1項」について述べている部分では、「婚姻は、これにより、配偶者の相続権(民法890条)や夫婦間の子が嫡出子となること(同法772条1項等)などの重要な法律上の効果が与えられるものとされているほか、」のように、法律上の婚姻制度の効果について述べている。
しかし、これは本来、「再婚禁止期間大法廷判決」の中で「婚姻及び家族に関する事項」について「憲法が一義的に定めるのではなく,法律によってこれを具体化することがふさわしい」として、「憲法24条2項は,このような観点から,婚姻及び家族に関する事項について,具体的な制度の構築を第一次的には国会の合理的な立法裁量に委ねる」と述べた後に登場する文である。
このように、「法律によってこれを具体化することがふさわしい」として「具体的な制度」が「国会の合理的な立法裁量」によって立法されているからこそ、「配偶者の相続権(民法890条)や夫婦間の子が嫡出子となること(同法772条1項等)などの重要な法律上の効果」について論じることができるのであり、これを前提とせずに「憲法24条1項」の文言から急に「民法」における「法律上の効果」の話をしていることは不自然な文脈となっている。
その結果、この段落では「憲法24条1項」について述べる部分で「婚姻は、これにより、配偶者の相続権(民法890条)や夫婦間の子が嫡出子となること(同法772条1項等)などの重要な法律上の効果が与えられるものとされている」のように具体的な法律上の効果について触れた後に、「同条2項」について述べる部分で後からその法律上の効果の内容は「憲法が一義的に定めるのではなく、法律によってこれを具体化することがふさわしい」ものであったことが明らかとなるというものとなっており、読者を混乱させる文章となっている。
よって、このような形で複数の最高裁判決の文面を組み合わせる形で論じようとすることは、その意味の整合性を損なわせるものとなることから妥当でない。
この段落では、下記のような事柄が記載されている。
◇ 「婚姻をするについての自由は、憲法24条1項の規定の趣旨に照らし、十分尊重に値するものと解することができる。」
◇ 「婚姻及び家族に関する事項は、国の伝統や国民感情を含めた社会状況における種々の要因を踏まえつつ、それぞれの時代における夫婦や親子関係についての全体の規律を見据えた総合的な判断を行うことによって定められるべきものである。」
◇ 「婚姻及び家族に関する事項について、具体的な制度の構築を第一次的には国会の合理的な立法裁量に委ねるとともに、」
しかし、そこでいう「婚姻」や「婚姻及び家族」とは何かが問われることになる。
なぜならば、そもそも「婚姻」に含まれないのであれば「婚姻をするについての自由」が尊重される対象とならないし、「婚姻及び家族」の中に含まれないのであれば「婚姻及び家族」として「定められるべきもの」であるとはいえないし、「国会の合理的な立法裁量に委ねる」ことのできる対象でもないからである。
そして、「婚姻」は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度であり、「家族」はその「婚姻」と同一の目的を共有し、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす形で規律される枠組みである。
よって、「婚姻」は、その間で一般的・抽象的に自然生殖の可能性がある「男性」と「女性」の組み合わせを対象としており、「家族」は、その「婚姻」している「夫婦」と、「親子」による「血縁関係者」を指すものである。
そのことから、これに含まれない人的結合関係については、「婚姻」や「婚姻及び家族」の中には含まれない。
ここでは「婚姻」や「婚姻及び家族」の文言が出てくるが、それらはすべてこのような意味であることを押さえる必要がある。
そうすると、同条1項の「婚姻」とは、同条2項を通じて、民法及び戸籍法等の法律によって法律婚制度として具体化されるものであり、婚姻をするについての自由が同性間に対しても及ぶものであるか否かは、法律によって具体化された法律婚制度を同性間に対しても及ぼすことが、同条1項の趣旨に照らして要請されているかという観点から検討するのが相当である。原告らにおいても、法律によって具体化された現行の法律婚制度の内容それ自体を争っているわけではなく、当該法律婚制度が同性間にも適用されるかという適用対象の範囲を問題としているものである。
【筆者】
「同条1項の「婚姻」とは、同条2項を通じて、民法及び戸籍法等の法律によって法律婚制度として具体化されるものであり、婚姻をするについての自由が同性間に対しても及ぶものであるか否かは、法律によって具体化された法律婚制度を同性間に対しても及ぼすことが、同条1項の趣旨に照らして要請されているかという観点から検討するのが相当である。」との記載がある。
「同条1項の「婚姻」」が「同条2項を通じて、民法及び戸籍法等の法律によって法律婚制度として具体化される」ことはその通りである。
ただ、「同条1項」は「婚姻」を定めているのであるから、これは「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた枠組みであることは明らかであり、その「婚姻」という概念であることそれ自体によって、法律上で「婚姻」として立法することができる人的結合関係の範囲には内在的な限界がある。
そのことから、その内在的な限界を超える人的結合関係を「法律婚制度」として立法することはできないことに注意が必要である。
そして、ここでいう「同性間」については、その間で「生殖」を想定することができず、「生殖と子の養育」の趣旨を満たすとはいえないことから、「婚姻」とすることはできない。
よって、「法律によって具体化された法律婚制度を同性間に対しても及ぼすこと」はできない。
また、「婚姻をするについての自由が同性間に対しても及ぶものであるか否か」の答えは、「同性間」は「婚姻」とすることはできないことから、「婚姻をするについての自由」は「同性間」を対象とするものではなく、及ばないということができる。
よって、「同条1項の趣旨に照らして要請されているか」の答えは、そもそも「同性間」については「婚姻」とすることはできず、要請されていないということになる。
注意したいのは、「同性間」の人的結合関係を「婚姻」とすることができることを前提として「同性間」の人的結合関係を「婚姻」とすることを「同条1項」が「要請」しているか否かが問われているのではなく、そもそも「同条1項」の「婚姻」の中に「同性間」の人的結合関係を含めることはできないことから「同条1項」が「同性間」の人的結合関係を「婚姻」とすることを「要請」していないということである。
ここでは「同条1項」が「要請」しているか否かを問うものとなっているが、それ以前に「婚姻」の中に「同性間の人的結合関係」を含めることができるかという論点が含まれていることを見逃すことがあってはならない。
この点から検討することが必要である。
「法律によって具体化された現行の法律婚制度の内容それ自体を争っているわけではなく、当該法律婚制度が同性間にも適用されるかという適用対象の範囲を問題としているものである。」との記載がある。
ここでいう「当該法律婚制度」は、24条2項の要請に基づいて立法されており、その24条2項は24条1項の「婚姻」を前提とするものである。
そして、そこでいう「婚姻」とは、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた枠組みである。
そのため、「婚姻」の中に含めることのできる人的結合関係の範囲には内在的な限界があり、その内在的な限界を超える人的結合関係については、「婚姻」とすることはできない。
「同性間」については、その間で「生殖」を想定することができず、「生殖と子の養育」の趣旨を満たすものではないことから、「婚姻」とすることはできない。
よって、「法律によって具体化された現行の法律婚制度の内容それ自体」については、「男女二人一組」を対象とするものであり、「婚姻」であるといえるが、ここでいう「同性間」については「婚姻」とすることはできない。
そのことから、「当該法律婚制度が同性間にも適用されるかという適用対象の範囲を問題」は、「同性間」に対しては「適用」することはできないということになる。
「法律によって具体化された現行の法律婚制度」との表現であるが、「法律婚制度」自体が「法律によって具体化された」制度を指しているのであり、それに対して「法律によって具体化された」を加えて表現することは、同義反復となる。
これは、下記のように説明しているようなものである。
「法律により具体化された」「現行の」「法律により具体化された」婚姻制度
そのため、このような無用な言い回しをする必要はなく、「法律により具体化された」の部分は省略するべきである。
イ この点、憲法24条1項は、婚姻は、「両性」の合意のみに基づいて成立すると規定し、婚姻した当事者を「夫婦」と呼称しているほか、同条2項でも「両性」という文言が用いられている。そして、これらの「両性」、「夫婦」といった文言は、男性と女性の双方を表すのが通常の語義であり、憲法その他の法令において、同性同士をも含むものとしてこれらの文言を使用している例は見当たらない。
【筆者】
この段落については、特に述べることはない。その通りである。
また、人類は、男女の結合関係を営み、種の保存を図ってきたところ、婚姻制度は、この関係を規範によって統制するために生まれたものであり、伝統的には、正当な男女の結合関係を承認するために存在するものと捉えられてきた(認定事実⑵ア)。そして、我が国では、明治民法において、初めて婚姻に関する統一的な法制度が施行されたところ、同法の下では、婚姻とは終生の共同生活を目的とする一男一女の法律的結合関係をいうものであると捉えられており(認定事実⑵イ )、同性間の婚姻が無効であることは当然とされていた(認定事実⑵イ )。さらに、憲法24条の起草過程においても、同性間の結合が婚姻に含まれるかについての議論がなされた形跡は見当たらず(認定事実⑵ウ )、GHQ草案では「both sexes(男女両性)」との文言が用いられ、それを受けて起草された日本側草案でも「男女相互ノ」との文言が用いられていた(認定事実⑵ウ )。なお、憲法24条の要請に基づき行われた昭和22年民法改正の過程においても、同性間の結合が婚姻に含まれるかについての議論がなされた形跡は見当たらない(認定事実⑵エ )。
【筆者】
「人類は、男女の結合関係を営み、種の保存を図ってきたところ、婚姻制度は、この関係を規範によって統制するために生まれたものであり、伝統的には、正当な男女の結合関係を承認するために存在するものと捉えられてきた」との記載がある。
「人類は、男女の結合関係を営み、種の保存を図ってきたところ、婚姻制度は、この関係を規範によって統制するために生まれたものであり、」との部分であるが、その通りである。
ただ、その「規範によって統制する」という背景には、「生殖」に関わって社会的な不都合が生じていることが原因である。
もし何らの不都合も存在しないのであれば、そもそも「規範によって統制する」ことも必要ないはずだからである。
よって、婚姻制度が「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として形成されていることは明らかである。
「伝統的には、正当な男女の結合関係を承認するために存在するものと捉えられてきた」との部分について検討する。
「正当な男女の結合関係」から検討する。
まず、「男女の結合関係」の部分であるが、「婚姻制度」が「男女」を対象としていることは、「婚姻」が「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として、その間で一般的・抽象的に自然生殖を想定することができる「男性」と「女性」の間に「貞操義務」を設けるなど一定の形式で結び付けることによって、子供が産まれた場合にその父親を特定することができる関係を推進する仕組みとなっていることによるものである。
ここでは「男女の結合関係」について「正当な」としているが、このような表現を用いた場合には、「正当な」男女と、「不当な」男女が存在することを前提とするものであるから、法律論として適切であるとはいえない。
「婚姻制度」を利用する者は、単に「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度を利用しているというだけの者であり、法律論として考えれば、それは「正当な」ものであるか、「不当な」ものであるかという価値判断が入り込む余地はない。
もし「婚姻している者(既婚者)」が複数名との間で性的な接触を行った場合に、婚姻制度による法律関係を形成している「夫婦」である「男女」と、その「夫婦」の一方と性的接触を行った「夫婦」以外の者との間での「男女」との関係性が比較され、「夫婦」の場合は「貞操義務」に反するものではないが、その「夫婦」以外の者との間での性的接触は「貞操義務」に反するものとして「離婚の訴え」や「損害賠償」の対象となるという違いが生じる場合は考えられる。
しかし、これは制度を利用する者と利用しない者との間では、法律関係としては制度を利用した方が利用しない者よりは、「離婚の訴え」や「損害賠償」などの権利を得ることができる地位にあるという意味において有利になるというだけのことである。
この仕組みに着目して「正当な」と表現しているのかもしれないが、それはある制度が存在することを前提としてその制度の仕組みに着目して後付けで評価を行っているものであるから、その後付けで行われてた評価の部分を得るがために、その原因となっている制度の枠組みの方を自由に変えることができるとする根拠にはならないことに注意が必要である。
これは、「婚姻」が「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために設けられている枠組みであるにもかかわらず、その枠組みの妥当性によって支えられている評価の部分を得ようとするがために、その枠組みの目的とその目的を達成するための手段の関係を無視して、その枠組みを「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するものとして機能しないものに変えてしまったならば、そもそも「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために設けられている枠組みとしての妥当性が損なわれ、そこから生じていた評価も失われ、結果として得ようとしていた評価さえも手に入らない状態に陥るからである。
よって、この「婚姻制度」の枠組みを論じる判決において、その制度の枠組みの当否を論じるのではなく、その枠組みに対して結果として生じている評価の部分を持ち出して論じるような部分が見られることは、解釈の過程として適切ではないため、注意が必要である。
「正当な男女の結合関係を承認するために存在する」とあるが、「婚姻制度」を利用しているとしても、それを結果として「正当」と考えるかどうかは個々人の価値観の問題であるし、それを「承認」するか否かも個々人の価値観の問題であり、これは法律論を論じるものではない。
「婚姻制度を利用する者(既婚者)」が存在した場合に、それを「正当な」ものと認めなければならないだとか、「承認」しなければならないだとかを強制するようなことがあれば、個人の価値観に対して国家が介入するものとなるから、19条の「思想良心の自由」や20条1項前段の「信教の自由」に抵触して違憲となる。
よって、「婚姻制度」を利用する者がいるとしても、それを「正当な男女の結合関係」と考えるか否かは個々人の価値観によるものであるし、それを「承認」するか否かも個々人の価値観によるものであるから、このような説明を行って婚姻制度の枠組みを検討しようとすることは不適切であることに注意が必要である。
ただ、この判決を書いた裁判官個人の価値観としては、「婚姻制度」を利用していない「男女」については「不当」と考えており、「承認」もしていないようである。
「伝統的には、」と「男女の結合関係」との部分であるが、「婚姻制度」が「男女の結合関係」となっていることは、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度だからである。
それを「伝統的」と呼ぶかどうかは別として、「男女の結合関係」となっている背景には、立法目的とその立法目的を達成するための手段となる枠組みの関係が存在することについて触れているものということができる。
「我が国では、明治民法において、初めて婚姻に関する統一的な法制度が施行されたところ、同法の下では、婚姻とは終生の共同生活を目的とする一男一女の法律的結合関係をいうものであると捉えられており(…)、同性間の婚姻が無効であることは当然とされていた」(カッコ内省略)との記載がある。
「婚姻とは終生の共同生活を目的とする一男一女の法律的結合関係をいうものであると捉えられており」との部分について検討する。
まず、「目的」の多義性に注意が必要である。
「目的」の意味は、「① 国の立法目的」、「② 制度が機能することによって生じる結果(目的)」、「③ 個々人の利用目的」に分けることができる。
そして、ここでいう「目的」とは、婚姻制度が機能した場合に「一男一女」の間で「終生の共同生活」についての「法律的結合関係」が形成されるという結果を示すものであるから、「② 制度が機能することによって生じる結果(目的)」の意味にあたるものである。
これが「① 国の立法目的」の意味ではないかを検討するとしても、そもそも婚姻制度はどのような人的結合関係でも「共同生活」をしていれば「法律的結合関係」を形成するということを前提としていないことから、制度の枠組みを導き出す際の立法目的ということはできない。
そのため、ここで使われている「目的」の意味を、「① 国の立法目的」を示したものと考えることはできない。
このことから、このような「② 制度が機能することによって生じる結果(目的)」の意味の「目的」を理由として、婚姻制度の枠組みを変更するための理由とすることはできないことに注意が必要である。
「同性間の婚姻が無効であることは当然とされていた」との部分について検討する。
「同性間の婚姻」との文言があるが、「婚姻」は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度であり、「同性間」についてはその間で「生殖」を想定することができず、「生殖と子の養育」の趣旨を満たすとはいえないことから、「婚姻」とすることはできない。
そのため、「同性間」で「婚姻」することはできず、「同性間の婚姻」という言葉は成り立たない。
「無効」となる理由は、このような事情によるものである。
この文では、上記に解説しているように「② 制度が機能することによって生じる結果(目的)」を取り上げて、「同性間」の人的結合関係を「婚姻」とすることについて「無効」となると述べていることになるが、どちらかというと「婚姻」の対象となる枠組みを導き出すのは「① 国の立法目的」の方であり、「② 制度が機能することによって生じる結果(目的)」の部分は、それに付随して形成されるものであることをも認識するとよいのではないかと思われる。
「憲法24条の起草過程においても、同性間の結合が婚姻に含まれるかについての議論がなされた形跡は見当たらず(…)、GHQ草案では「both sexes(男女両性)」との文言が用いられ、それを受けて起草された日本側草案でも「男女相互ノ」との文言が用いられていた(…)。」(カッコ内省略)との記載がある。
「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度が「婚姻」であり、「生殖と子の養育」の趣旨を満たさない人的結合関係についてはもともと「婚姻」の中には含まれない。
「同性間の結合」についても、その間で「生殖」を想定することができないことから、「生殖と子の養育」の趣旨を満たすとはいえず、もともと「婚姻」の対象とすることができないものである。
よって、「憲法24条の起草過程において」「同性間の結合が婚姻に含まれるかについての議論がなされた形跡は見当たら」ないとしても、もともと「婚姻」の対象とすることができないものであるから当然であるともいえるものである。
「GHQ草案では「both sexes(男女両性)」との文言が用いられ、それを受けて起草された日本側草案でも「男女相互ノ」との文言が用いられていた」との部分についても、これは「生殖と子の養育」の趣旨を満たす人的結合関係として「男女」が挙げられているものということができる。
「なお、憲法24条の要請に基づき行われた昭和22年民法改正の過程においても、同性間の結合が婚姻に含まれるかについての議論がなされた形跡は見当たらない」との記載がある。
「同性間の結合」については、その間で「生殖」を想定することができず、「生殖と子の養育」の趣旨を満たさないことから、「婚姻」の中に含めることはできない。
そのため、もともと「婚姻」の中に含めることのできないものについては、「議論がなされた形跡は見当たらない」としても不思議ではない。
そのことから、「議論がなされた形跡は見当たらない」ことを理由として、その当時の判断に盲点があったということになるわけではないし、その後であれば「生殖と子の養育」の趣旨を満たさないものまでをも「婚姻」の中に含めることができるとする根拠となるわけではないことに注意が必要である。
以上に述べた憲法24条の文理や制定経過等によれば、少なくともその制定当時において、同性間に対して民法及び戸籍法等の法律によって具体化された法律婚制度を及ぼすことが、同条1項の趣旨に照らして要請されていたとは解し難い。
【筆者】
この段落の内容は、基本的にはその通りである。
ただ、「少なくともその制定当時において、」の部分は、「制定当時」とその後を区別しようとするものとなっているが、その後においても「婚姻」の背景にある「立法目的」と「その立法目的を達成するための手段」として必要となる要素が変化するものではないため、24条1項の意味か変わるということはない。
よって、憲法24条1項の「婚姻」の中に「同性間の人的結合関係」を含めることはできないことは「制定当時」もその後についても変わらない。
このため、その後についても当然、憲法24条1項が「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを「要請」しているということはない。
ウ これに対し、原告らは、仮に、制定当時において、憲法24条1項の趣旨に照らして、同性間に対して民法及び戸籍法等の法律によって具体化された法律婚制度を及ぼすことが要請されていなかったとしても、その後の社会情勢の変化等により、同性間の結合も「婚姻」に含まれるとする社会的な意識が確立し、同性間に対しても法律婚制度を及ぼすことが要請されるに至ったと主張する。
【筆者】
「婚姻」は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた枠組みである。
「同性間の人的結合関係」についてはその間で「生殖」を想定することができず、「生殖と子の養育」の趣旨を満たすものではないことから、「婚姻」とすることはできない。
そして、「憲法24条1項」は「婚姻」について定めていることから、その「婚姻」の中に「同性間の人的結合関係」を含めることはできない。
そのため、「憲法24条1項」は「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを「要請」しているということはない。
これは、「婚姻」の概念そのものが有している目的とその目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす枠組みによるものであり、国民の抱く「意識」によって左右されるというものではない。
確かに、GHQ草案23条が「婚姻ハ…両親ノ強要ノ代リニ相互同意ノ上ニ基礎ツケラレ且男性支配ノ代リニ協力ニ依リ維持セラルヘシ此等ノ原則ニ反スル諸法律ハ廃止セラレ…」と規定し(認定事実⑵ウ )、憲法24条1項が「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」と規定している点について、帝国議会での審議において、明治民法が一定の年齢未満の子の婚姻につき戸主や親の同意を要件としていたのを排除し、両性の合意だけで成立させようとする趣旨であるとの説明がなされていたこと(認定事実⑵ウ )等によれば、同条の主眼は、明治民法下の家制度を改め、戸主同意権を廃するなど、婚姻を含む家族生活について民主主義の基本原理である個人の尊厳と両性の本質的平等の原則を特に定める必要から設けられたものであると解される。そして、同性間の結合が「婚姻」に含まれるかについての議論がなされた形跡はないこと(認定事実⑵ウ)を考慮すれば、同性間に対して現行の法律婚制度を及ぼすことが、同条1項の趣旨に照らして禁止されていたとまではいえないと解される。
【筆者】
「確かに、GHQ草案23条が「婚姻ハ…両親ノ強要ノ代リニ相互同意ノ上ニ基礎ツケラレ且男性支配ノ代リニ協力ニ依リ維持セラルヘシ此等ノ原則ニ反スル諸法律ハ廃止セラレ…」と規定し(…)、憲法24条1項が「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」と規定している点について、帝国議会での審議において、明治民法が一定の年齢未満の子の婚姻につき戸主や親の同意を要件としていたのを排除し、両性の合意だけで成立させようとする趣旨であるとの説明がなされていたこと(…)等によれば、同条の主眼は、明治民法下の家制度を改め、戸主同意権を廃するなど、婚姻を含む家族生活について民主主義の基本原理である個人の尊厳と両性の本質的平等の原則を特に定める必要から設けられたものであると解される。」(カッコ内省略)との記載がある。
この段落の第一文は非常に長く読み取りづらいので、三つに分解して、(この)を加えると下記のようになる。
「GHQ草案23条が「婚姻ハ…両親ノ強要ノ代リニ相互同意ノ上ニ基礎ツケラレ且男性支配ノ代リニ協力ニ依リ維持セラルヘシ此等ノ原則ニ反スル諸法律ハ廃止セラレ…」と規定し(…)、憲法24条1項が「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」と規定している」
↓ ↓ ↓
(この)「点について、帝国議会での審議において、明治民法が一定の年齢未満の子の婚姻につき戸主や親の同意を要件としていたのを排除し、両性の合意だけで成立させようとする趣旨であるとの説明がなされていた」
↓ ↓ ↓
(この)「こと(…)等によれば、同条の主眼は、明治民法下の家制度を改め、戸主同意権を廃するなど、婚姻を含む家族生活について民主主義の基本原理である個人の尊厳と両性の本質的平等の原則を特に定める必要から設けられたものであると解される。」
上記の趣旨をさらに分かりやすくするために短くまとめると、下記のようにまとめることができる。
「憲法24条1項が「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」と規定している点について、」「婚姻を含む家族生活について民主主義の基本原理である個人の尊厳と両性の本質的平等の原則を特に定める必要から設けられたものであると解される。」
次に、この文の内容を検討する。
憲法24条1項に「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」と規定された経緯については、その通りであると考えられる。
しかし、憲法24条1項に定められているものが「婚姻」であることに違いはないのであるから、憲法24条1項の規定が設けられた背景にそのような意図があるとしても、そのことによって法制度が「婚姻」という枠組みそれ自体を設けている趣旨・目的そのものは何らの影響を受けるものではない。
そのため、そこでいう「婚姻」とは何かが問われるのであり、そのような制定経緯の一側面を持ち出したとしても、そのことが「婚姻」という概念そのものが有している内在的な限界を超える人的結合関係までをも「婚姻」の中に含めなければならないとする理由となるわけではない。
そして、「婚姻」は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として設けられた枠組みであり、その意味を離れて「婚姻」を観念することはできない。
また、憲法24条では「婚姻」について「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めている。
このことも、その目的を達成するための手段として整合的な枠組みとして記されているものである。
よって、憲法24条1項が設けられた制定経緯の一側面を持ち出したとしても、そこで記されている内容は常に「婚姻」であることに違いなく、その「婚姻」という概念そのものが有している趣旨・目的を失わせることまでをも、その制定経緯での一部の意図を用いて正当化することができることにはならず、それによって憲法24条の下で「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることができるとする理由を説明していることにはならない。
この点について、国(行政府)の主張も参考になる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
なお、原告らは、憲法制定時の審議過程において、憲法24条の趣旨につき、「今まで個人の尊重が足りなかつたと云ふことと、両性が不合理に差等をつけられて居つたと云ふ2點に着眼をして(中略)此の規定が出來た」との当時の国務大臣の発言を根拠に、憲法24条1項は同条2項を受けて、憲法の基本原理が確保されるための核心として婚姻の自由を保障しているとし、憲法24条1項の婚姻の自由が当事者の性別を問うのか否かの解釈においても、個人の尊厳などの憲法の基本原理に基づかなければならない旨主張する(原告ら第15準備書面11及び12ページ)。
しかし、上記発言は、「家督相續と云ふものが、此の憲法の趣意から云ふと、どう云ふものであるか」という質問に答えたものである。すなわち、明治民法における「家」の制度の下では子主権の相続たる家督相続の制度があり、家督相続においては原則として長男が独占的に相続するものとされていたところ、上記国務大臣の発言は、この「家」、「戸主権」、「家督相続」の制度が個人の尊厳と両性の平等に抵触する旨を指摘するものであって、正に憲法24条の趣旨の一つ(乙第31号証・415ページ)をいうものにほかならない。従って、上記国務大臣の発言は、憲法24条1項の「婚姻」が同性間の人的結合関係を含む趣旨であるとする原告らの主張の根拠になるものではない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【東京二次・第9回】被告第7準備書面 令和5年9月28日 PDF (P5~6)
このように、制定経緯での一部の意図を持ち出したとしても、「憲法24条1項の「婚姻」が同性間の人的結合関係を含む趣旨であるとする」「主張の根拠になるものではない。」ことは当然、それによって「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることができるとする理由を示していることにもならない。
そのため、その後、これができるかのような前提で論じている部分は誤りである。
もう一つ、「個人の尊厳と両性の本質的平等の原則を特に定める必要から設けられた」との部分であるが、これは「⑵ 憲法24条1項に違反するかについて」の項目の中で、「GHQ草案23条」の憲法24条1項に対応する部分を引用し、「憲法24条1項」の条文も引用した後に記載するものであるにもかかわらず、「個人の尊厳」や「両性の本質的平等」の文言そのものは24条2項に定められているものであることに注意が必要である。
「そして、同性間の結合が「婚姻」に含まれるかについての議論がなされた形跡はないこと(…)を考慮すれば、同性間に対して現行の法律婚制度を及ぼすことが、同条1項の趣旨に照らして禁止されていたとまではいえないと解される。」(カッコ内省略)との記載がある。
まず、「同性間の結合が「婚姻」に含まれるかについての議論がなされた形跡はない」との部分について検討する。
「同性間の結合が「婚姻」に含まれるか」という点について、「議論がなされた形跡はない」としても、そのことは「同性間の結合」を「婚姻」の中に含めることができるとする根拠となるものではない。
そのため、ここでは「含まれるか」のように述べているが、そもそも「同性間の結合」を「婚姻」の中に「含めることができるか」を先に検討することが必要である。
この点を検討することなく、「議論がなされた形跡」がないのであれば、「同性間の結合」を「婚姻」とすることが可能となるというものではないことに注意が必要である。
「同性間に対して現行の法律婚制度を及ぼすことが、同条1項の趣旨に照らして禁止されていたとまではいえないと解される。」との部分について検討する。
■ 「禁止」の意味
この「禁止」という言葉は、様々な意味で用いられる。
【動画】2023年度前期・九大法学部「法学入門」第2回〜法とは何か 2023/04/25 ①
【動画】2023年度前期・九大法学部「法学入門」第2回〜法とは何か 2023/04/25 ②
【動画】2023年度前期・九大法学部「法学入門」第2回〜法とは何か 2023/04/25 ③
【動画】【橋爪大三郎】憲法とは何か。他の法律との根本的な違いとは? 憲法の成り立ちや存在理由、9条問題についてなどを考えてみる 2021/05/03
そのため、その「禁止」の文言がどのような意味で使われているのかを更に検討する必要がある。
① 義務文・否定文による禁止(命令文の禁止)
「義務文・否定文による禁止」とは、条文中に「禁止する」や「禁ずる」、「~~してはならない」、「~~しなければならない」のように記載されている場合のことをいう。
② 防ぐ意図の禁止(狭義の禁止)
「防ぐ意図の禁止」とは、何らかの対象を認識した上で、それを意図的に防ぐ意思を持って規定が設けられている場合のことをいう。
これは、何かを制限する意味、対象者を限定する意味、対象者専用とする意味も含まれる。
③ 上位法に反する禁止(広義の禁止)
「上位法に反する禁止」とは、下位の法令で制度を構築した場合に憲法に違反する場合のことをいう。
この判決は、「禁止されていたとまではいえない」と述べているが、これら、①「義務文・否定文による禁止」、②「防ぐ意図の禁止」、③「上位法に反する禁止」のどれを指して「禁止されていたとまではいえない」と判断したかを検討する必要がある。
また、その「禁止されていたとまではいえない」との判断が憲法24条1項を解釈したものとして妥当な内容であるかも検討することが必要である。
■ 「婚姻」の中に含めることができるもの
この判決は、「禁止されていたとまではいえない」と述べ、その結果として「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることが可能であるかのように理解しているようである。
しかし、そもそも「婚姻」の中に「同性間の人的結合関係」を含めることができるのかどうかという部分から検討することが必要である。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
これらの学説を参照すると、憲法24条のいう「婚姻」の内実として同性カップルの「婚姻」というものが観念しうるのか、憲法上の「婚姻」とはそもそも男女が取り結ぶ一定の関係なのではないか、そして「同性」と「婚姻」を結びつけることが法的に可能なのかという問いが浮かぶ。
憲法24条が同性婚を想定していないのは確かだとして、憲法学説も民法学説も、従来、憲法24条の「婚姻」としては男女のカップルのそれを暗黙のうちに想定してきたと言える。「同性」という言葉と「婚姻」という言葉がそこでは結びついておらず、したがって「同性婚の自由」なるものが憲法上存在するかも定かではないのだ。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
生殖可能性のない同性婚を法律で認める理由はない…憲法学の専門家が「同性婚の法制化」にクギを刺す理由 2023/02/18
そこで、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」として扱うことができるかどうかを検討する。
■ いくつかの立場との関係性
憲法24条を解釈する際に、いくつかの立場がある。それらを検討する。
▼ 「婚姻」の由来
この立場は、「婚姻」という枠組みが形成された由来を遡り、「婚姻」という概念そのものが有している「目的」とその目的を達成するための「手段」とを整合的な形で考えるものである。
「婚姻」という枠組みが形成された由来を考えるため、「婚姻」という概念そのものが有している内在的な限界も考慮することになる。
これについて、後ほど「『婚姻』の概念による制約」の項目でも解説する。
◇ 存在しない説
この立場は、「婚姻」とは自然生殖可能性のある組み合わせを優遇する制度であることから、それを満たさない形の「婚姻」というものは存在しないと考えるものである。
「同性間」についても、その間で自然生殖を想定することができないことから、「婚姻」とは言えず、「同性間」の「婚姻」という概念は存在しないことになる。
国(行政府)の主張の中で、この立場に重なる部分は下記がある。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
イ しかしながら、法の解釈に際し、文言の日本語としての意味や文法が重視・尊重されなければならず、文言からかけ離れた解釈が許されないのは当然であるところ、前記2(2)
において述べたとおり、「両性」とは、両方の性、男性と女性又は二つの異なった性を意味し、「夫婦」とは、夫と妻又は適法の婚姻をした男女の身分を意味する文言であり、「両性」及び「夫婦」が男性又は女性のいずれかを欠き当事者双方の性別が同一である場合を含む概念であると理解する余地はなく、このような理解は、憲法24条1項の制定過程及び審議状況からも裏付けられている。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【東京一次・第1回】控訴答弁書 令和5年6月23日 PDF (P22~23)
◇ 成立条件説
この立場は、憲法24条1項の「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、」の文は「婚姻」の成立条件を示すものと考えるものである。
「婚姻」を成立させるためには「両性」である「男性」と「女性」の合意を必要とすると定めていることから、「同性間」で合意しても「婚姻」としては成立しないことになる。
国(行政府)は下記のように述べている。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
他方、同条2項は、婚姻等に関する事項について具体的な制度を構築するに当たっての立法上の要請及び指針を示したものであるが、上記のとおり、婚姻の成立については、同条1項により、両性の合意のみに基づいて成立する旨が明らかにされていることから、婚姻の成立要件等を定める法律は、かかる同条1項の規定に則した内容でなければならない。そのため、婚姻等に関する事項について立法上の要請及び指針を示した同条2項においては、同条1項の内容も踏まえ、配偶者の選択ないし婚姻等に関する法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならないとしたものである(憲法24条2項における配偶者の選択とは婚姻の相手の選択であるから、それについて、法律が個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならないということは、婚姻が当事者の自由な合意のみによって成立すべきことを意味し、同条1項の規定と同趣旨であると解されている(佐藤功「憲法(上)[新版]」414ページ。乙第33号証))。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【東京一次・第1回】控訴答弁書 令和5年6月23日 PDF
◇ 想定していない説
この立場は、憲法24条は「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを想定していないと考えるものである。
上記の三説と下記の三説のいずれの可能性もある。
国(行政府)は、下記のように「成立させること」と「想定していない」の両方を用いて説明している。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ア もっとも、前記(1) のとおり、憲法24条1項は、「両性」及び「夫婦」という文言を用いているところ、一般的に、「両性」とは、両方の性、男性と女性又は二つの異なった性を意味し、「夫婦」とは、夫と妻又は適法の婚姻をした男女の身分を意味するものとされている(新村出編・広辞苑第7版2526及び3095ページ)ことからすると、同項にいう「夫婦」や「両性」もこれと同義とみるべきであるから、憲法は、「両性」の一方を欠き当事者双方の性別が同一である場合に婚姻を成立させることをそもそも想定していないというべきである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【東京一次・第1回】控訴答弁書 令和5年6月23日 PDF (P14)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ア しかしながら、法の解釈に際し、文言の日本語としての意味や文法が重視・尊重されなければならず、文言からかけ離れた解釈が許されないのは当然であるところ、これまで繰り返し述べているとおり、憲法24条1項は、「両性」及び「夫婦」という文言を用いており、一般に、「両性」とは、両方の性、男性と女性又は二つの異なった性を意味し、「夫婦」とは、夫と妻又は適法の婚姻をした男女の身分を意味するものとされている(新村出編・広辞苑第7版2526及び3095ページ)ことからすると、同項にいう「夫婦」や「両性」もこれと同義とみるべきであるから、憲法は、「両性」の一方を欠き当事者双方の性別が同一である場合に婚姻を成立させることをそもそも想定していないというべきである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【東京二次・第9回】被告第7準備書面 令和5年9月28日 PDF (P5)
◇ 立法裁量の限界を画するもの
この立場は、憲法24条は立法裁量の限界を画する規定であることから、24条の文言に沿わない関係については、「婚姻」とすることができないと考えるものである。
憲法24条は「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めており、この形に限定して立法裁量の限界を画していることから、それ以外の人的結合関係を「婚姻」とすることはできない。
「同性間の人的結合関係」についても、これを満たさないため「婚姻」とすることはできないことになる。
◇ 禁止説
この立場は、憲法24条の規定は、何かを認知した上でそれを防ぐ意図をもって定められていることから、その規定に合わないものについては禁止されていると考えるものである。
「同性間の人的結合関係」についても、24条の規定が「両性」「夫婦」の文言を定めていることに合わないことから、24条は「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることの論点を認知した上で、それを防ぐ意図をもって禁止していることになる。
◇ 義務文・否定文による禁止説
この立場は、憲法24条1項の規定は「両性~に基づいて成立し、~なければならない。」(shall)という義務文・否定文による禁止の意味を有すると考えるものである。
これによれば、憲法24条1項は「両性」を満たさない人的結合関係を「婚姻」とすることを義務文・否定文によって禁止していることになる。
「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることについても、「両性」を満たさないため義務文・否定文によって禁止されていることになる。
どの説で考えることが妥当であるかを検討するためにも、「婚姻」という概念が形成されている由来を検討することが必要である。
そこで、下記ではさらに「婚姻」という概念が形成されている由来や、その目的と、その目的を達成するための手段となる枠組みについて検討する。
■ 「婚姻」の概念による制約
▼ 「婚姻」の概念に含まれる内在的な限界
「婚姻」は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために設けられた枠組みである。
これは、下記のような経緯によるものである。
その国の中で「生殖と子の養育」に関する事柄について何らの制度も存在しない場合には、社会的な不都合が発生することがある。
例えば、「父親不明」の子供が増える、父親を特定できない子供が増える、父親が蒸発して行方不明になった子供が増える、それらにより「子の福祉」が減少する、父親を特定できないことにより近親者の範囲を把握できずに「近親交配」に至り潜性遺伝子の発現した個体が高い確率で生じるようになる、一部の強者が多数人との生殖関係を独占することによって社会の中で「子を持ちたいと希望して相手を見つけようとする男女」の数の不均衡が生じて「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」が生まれる、低年齢での妊娠・出産により母体に危険が及ぶ、などの問題が生じることがある。
これらの不都合を解消するために、下記のような立法目的を有する枠組みを設けることが必要となる。
・「子の福祉」が実現される社会基盤を構築すること
・潜性遺伝子の発現した個体が高い確率で生じることを抑制すること
・「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」を減らすこと
・母体を保護すること
そして、これらの目的を達成するためには、目的との関係で整合的な下記の要素を満たす枠組みを設けることが必要となる。
・子の遺伝的な父親を特定できる組み合わせとすること
・特定された子の父親にも子に対する責任を担わせること
・特定された子の父親を基に遺伝的な近親者を把握すること
・未婚の男女の数の不均衡を防止できる組み合わせに限定すること
これらの要素を満たすものとして「一人の男性」と「一人の女性」が選び出され、その間に「貞操義務」を設け、その関係を法的に結び付ける形を「婚姻」と呼んでいる。
このことから、これらの要素は、「婚姻」という概念が他の様々な人的結合関係とは区別する形で成り立つための境界線となるものである。
そして、この「婚姻」に対して法的効果や一定の優遇措置を設けることによって、制度を利用する者を増やし、これらの立法目的の実現を目指す仕組みとなっている。
このような「生殖」に関わって生じる社会的な不都合(国民が「生殖」によって子供を産むことに関係して起き得る問題)を解決しようとする立法目的を離れて「婚姻」を観念することはできない。
そのため、「婚姻」という概念である以上は、国民が「生殖」によって子を産むことに関わる制度であることを前提としている。
よって、「婚姻」の文言の中には「生殖と子の養育」の趣旨が含まれている。
また、その社会の中で「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することが求められ、その目的を達成するための手段となる枠組みを「婚姻」という概念が担っている以上は、「婚姻」はそれを解消するものとして機能することが求められている。
そのため、「婚姻」の文言の中には、これらの目的を達成することを阻害する組み合わせを「婚姻」とすることはできないという内在的な限界が含まれている。
よって、これらの要素や「生殖と子の養育」の趣旨を満たさない人的結合関係については、「婚姻」とすることはできない。
このような差異が生じることは、「婚姻」という概念そのものが、目的を達成するための手段として形成されている枠組みである以上は当然のことである。
「同性間の人的結合関係」(同性三人以上の人的結合関係も同様)については、上記の要素や「生殖と子の養育」の趣旨を満たさないことから、「婚姻」の中に含めることはできない。
▼ 憲法24条の「婚姻」による限界
憲法24条の「婚姻」は、この意味の「婚姻」を引き継ぐ形で定められている。
憲法24条が定めているものが「婚姻」である以上は、その「婚姻」の文言の中には「生殖と子の養育」の趣旨が含まれている。
また、そこには「婚姻」の立法目的を達成することを阻害する組み合わせを「婚姻」とすることはできないという内在的な限界が含まれている。
よって、憲法24条の下で「生殖と子の養育」の趣旨を満たさない人的結合関係を「婚姻」とすることはできない。
もし、そのような人的結合関係を「婚姻」として立法しようとした場合には、憲法24条の「婚姻」に抵触して違憲となる。
また、憲法24条は「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて、一夫一婦制(男女二人一組)を定めている。
これは、「婚姻」の目的を達成するための手段として整合的な下記の要素を満たすからである。
・子の遺伝的な父親を特定できる組み合わせとすること
・特定された子の父親にも子に対する責任を担わせること
・特定された子の父親を基に遺伝的な近親者を把握すること
・未婚の男女の数の不均衡を防止できる組み合わせに限定すること
そのため、これらの要素を満たさない人的結合関係については、憲法24条の「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言の趣旨に当てはまらず、「婚姻」とすることはできない。
もし、これらの要素を満たさない人的結合関係を「婚姻」として扱う法律を立法しようとした場合には、憲法24条の許容する立法裁量の限界を超え、憲法24条に抵触して違憲となる。
「同性間の人的結合関係」については、一般的・抽象的にその間で「生殖」を想定することができず、「生殖と子の養育」の趣旨を満たすとはいえないし、これらの要素を満たすものではないため、「婚姻」とすることはできない。
そのため、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」として扱う法律を立法しようとした場合には、憲法24条の「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言に抵触して違憲となる。
▽ 憲法24条の「婚姻」が「生殖と子の養育」に関わる制度を一元的に集約していること
「婚姻」は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「生殖と子の養育」の観点から他の人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度である。
そして、憲法24条は「婚姻」の内容について、「両性の合意のみ」や「個人の尊厳」「両性の本質的平等」を満たすように求めている。
これは、「婚姻」という制度については特に注意を払い、憲法24条の統制に服させ、その内容に対して立法裁量の限界を画することが目的である。
この憲法24条の規定が有する意図を実現するためには、「生殖と子の養育」に関わる制度を憲法24条の「婚姻」の文言の中に一元的に集約する形で解釈することが必要であり、「生殖と子の養育」に関わる制度を24条の「婚姻」を離れて立法することはできない。
これは、下記が理由である。
仮に「生殖と子の養育」に関わる制度を、憲法24条の「婚姻」から離れて別の制度として立法することができるとする場合を考えてみる。
すると、「生殖と子の養育」に関わる制度でありながら、憲法24条によって統制(管理)することができない状態を許すことになる。
例えば、憲法24条のいう「婚姻」とは別に「生殖関連制度」や「三人以上の生殖結社制度」などが立法されることが考えられる。
そうなると、憲法24条は「婚姻」に対しては「両性の合意のみ」や「個人の尊厳」「両性の本質的平等」を満たすように求めて立法裁量の限界を画しているが、その「生殖と子の養育」に関わる制度は「婚姻」とは別の制度であることから、憲法24条の統制が及ばないことになる。
すると、その「生殖と子の養育」に関わる制度は「婚姻」ではないため、「両性の合意」以外の条件を設けるものでも、「個人の尊厳」や「両性の本質的平等」に立脚しないものでも構わないことになる。
例えば、戦前の明治民法のような「戸主」の同意を必要とする「戸主付き生殖関連制度」や「家制度的生殖関連制度」を立法することも可能となる。
また、その「婚姻」とは異なる「生殖と子の養育」に関わる制度に対して「婚姻」よりも充実した優遇措置を整備した場合には、人々の大半はその制度を利用することを選択し、次第に「婚姻」を利用しなくなっていくことが考えられる。
すると、「婚姻」という制度が衰退していき、「婚姻」が「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するための制度として機能しなくなることが考えられる。
これでは、憲法24条が「婚姻」に対して立法裁量の限界を画することによって、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために設けられた制度の内容が「両性の合意のみ」や「個人の尊厳」「両性の本質的平等」を満たすものとなるよう求める憲法上の立法政策としての目的を達成できない事態に陥る。
これでは、憲法24条の趣旨が損なわれ、何のために憲法24条が設けられているのか分からなくなる。
そのため、憲法24条の規定の効果が保たれるためには、「生殖と子の養育」に関わる制度は憲法24条の「婚姻」の文言が一元的に集約するものとして解釈することが必要となる。
このことから、「生殖と子の養育」に関わる制度を、憲法24条の「婚姻」を離れて別の制度として立法することはできない。
もし「生殖と子の養育」に関わる制度を、憲法24条の「婚姻」から離れて別の制度として立法しようとした場合には、憲法24条の「婚姻」に抵触して違憲となる。
この前提がある以上は、憲法24条の「婚姻」という文言の中には「生殖と子の養育」の趣旨が含まれており、この憲法24条の「婚姻」の文言から「生殖と子の養育」の趣旨を切り離して考えることはできない。
これにより、「生殖と子の養育」の趣旨を満たさない人的結合関係を24条の「婚姻」として扱うことはできない。
「同性間の人的結合関係」については「生殖と子の養育」の趣旨を満たすものではないため、「婚姻」とすることはできない。
▽ 憲法24条の「婚姻」から「生殖と子の養育」の趣旨が失われると24条の規定が有している目的を達成できないこと
仮に憲法24条の「婚姻」という概念から「生殖と子の養育」の趣旨を切り離して考えることができるとする前提に立つとする。
すると、憲法24条の「婚姻」の文言には「生殖と子の養育」の趣旨が含まれていないことになるから、憲法24条の「婚姻」の文言には「生殖と子の養育」に関わる制度を一元的に集約しようとする趣旨も含まれていないことになる。
そうなると、「生殖と子の養育」に関わる制度について、憲法24条の「婚姻」を離れて別の制度として立法することが可能となる。
「生殖と子の養育」に関わる制度が「婚姻」とは別の形で存在することを許すことになるから、「婚姻」が「生殖と子の養育」に関する様々な問題の発生を抑制しようとする機能を果たさなくなり、「婚姻」の政策効果が損なわれることになる。
また、その「生殖と子の養育」に関わる制度は、憲法24条の「婚姻」とは別の制度であることから、憲法24条の「両性の合意のみ」や「個人の尊厳」「両性の本質的平等」による統制が及ばないことになる。
つまり、その「生殖と子の養育」に関わる制度が、憲法24条の「両性の合意のみ」や「個人の尊厳」「両性の本質的平等」を満たさないものとなっていても、それがもともと憲法24条の「婚姻」ではないことを理由に、その制度の内容を是正することができなくなる。
これでは、本来「婚姻」を憲法24条の統制の下に置くことによって、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するための制度の内容に対して「両性の合意のみ」や「個人の尊厳」「両性の本質的平等」を満たすように求めるという憲法上の立法政策を実現することができない事態に陥る。
これでは、憲法24条の規定そのものが有する意図・目的を達成することができず、24条の規定が骨抜きとなる。
このような考えは解釈として妥当でない。
そのことから、「生殖と子の養育」に関わる制度については、憲法24条の「婚姻」に結び付けて考える必要があり、憲法24条の「婚姻」は「生殖と子の養育」に関わる制度を一元的に集約する趣旨を有している。
そのため、憲法24条の「婚姻」を「生殖と子の養育」の趣旨と切り離して考えることはできない。
よって、「生殖と子の養育」の趣旨を満たさない人的結合関係を、憲法24条の示している「婚姻」として扱うことはできない。
「同性間の人的結合関係」については「生殖と子の養育」の趣旨を満たすものではないため、「婚姻」とすることはできない。
▼ 言葉の置き換えを繰り返すことはできないこと
その国の中で「生殖と子の養育」に関する事柄について何らの制度も存在しない場合には、社会的な不都合が発生することがある。
例えば、「父親不明」の子供が増える、父親を特定できない子供が増える、父親が蒸発して行方不明になった子供が増える、それらにより「子の福祉」が減少する、父親を特定できないことにより近親者の範囲を把握できずに「近親交配」に至り潜性遺伝子の発現した個体が高い確率で生じるようになる、一部の強者が多数人との生殖関係を独占することによって社会の中で「子を持ちたいと希望して相手を見つけようとする男女」の数の不均衡が生じて「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」が生まれる、低年齢での妊娠・出産により母体に危険が及ぶ、などの問題が生じることがある。
「婚姻」は、これらの「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、他の人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度である。
そのため、「婚姻」には、下記の立法目的が存在すると考えられる。
・「子の福祉」が実現される社会基盤を構築すること
・潜性遺伝子の発現した個体が高い確率で生じることを抑制すること
・「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」を減らすこと
・母体を保護すること
このように、「婚姻」という枠組みが形成されている立法目的がある以上は、その「婚姻」という概念の中には、他の人的結合関係との間で区別するための要素が存在する。
それは、「婚姻」の立法目的を達成するための手段として整合的な要素であり、下記が不可欠である。
・子の遺伝的な父親を特定できる組み合わせとすること
・特定された子の父親にも子に対する責任を担わせること
・特定された子の父親を基に遺伝的な近親者を把握すること
・未婚の男女の数の不均衡を防止できる組み合わせに限定すること
もしこれらの要素を満たさない人的結合関係を「婚姻」の中に含めようとした場合には、その時点で、これらの要素を満たさないことから、「婚姻」の立法目的を達成することができなくなることを意味する。
すると、そもそもそのような制度に対して法的効果や優遇措置を行う意味も失われ、制度を継続する必要性がなくなり、その「婚姻」と呼んでいる制度を廃止することに行き着く。
また、その「婚姻」と呼んでいる枠組みによっては、既に立法目的を達成することができなくなっていることから、その目的を達成するために「婚姻」以外の新たな制度を立法することが求められることになる。
しかし、それは結局、それまで機能していた本来の「婚姻」とまったく同様の目的を達成することを意図して立法されることになるから、上記の要素を満たす人的結合関係を新たな枠組みとして他の様々な人的結合関係とは区別する形で設けることになるものである。
こうなると、それはもともと「婚姻」が有していた機能を、新たな枠組みの制度が担おうとするものとなることから、そもそも「婚姻」から新たな枠組みの制度へと言葉の入れ替えを行っているだけの状態となるのである。
このような言葉の置き換えという無意味なループを繰り返すことを防ぐためには、「婚姻」という枠組みが存在する時点で、そこには「婚姻」という枠組みを形成している立法目的が存在しており、その「婚姻」という枠組みそのものにその立法目的との間で整合性を保つことができる内在的な限界が含まれていることを捉える必要がある。
そして、その内在的な限界となる要素を満たさない人的結合関係を「婚姻」の中に含めようとする試みは、「婚姻」という概念そのものが有している本来の意味、内在的な機能を改変し、消失させようとするものとして排斥することが必要となる。
これによって、「婚姻」という概念そのものの枠組みを維持し、「婚姻」という概念そのものが消失することを防ぎ、「婚姻」という言葉の意味が成立する状態を保つことができるからである。
そのことから、「婚姻」という枠組みが形成されている背景にある立法目的が正当である以上は、その立法目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす人的結合関係については「婚姻」として扱うことができ、それを満たさない人的結合関係については「婚姻」として扱うことはできない。
このような差異が生じることは「婚姻」という枠組みが形成されている時点でもともと予定されていることである。
この差異を否定するのであれば、それはそもそも「婚姻」の立法目的を否定することになることを意味する。
「婚姻」の立法目的が正当と認められる以上は、その立法目的を達成するための手段として設けられている枠組みによって生じる差異は、法制度が政策的なものであることからくる誰もが甘受しなければならないものである。
そして、「同性間の人的結合関係」については、「婚姻」の目的を達成するための手段として必要となる上記の要素を満たすものではないため、「婚姻」とすることはできない。
▼ 主張の基盤を失わせる主張であること
憲法24条が定めている「両性の合意のみ」や「個人の尊厳」の文言を根拠として、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」の中に含めることができるはずであるとの主張がある。
しかし、この主張に従って「同性間の人的結合関係」を「婚姻」の中に含めた場合には、憲法24条の「婚姻」から「生殖と子の養育」の趣旨が失われることになる。
こうなると、憲法24条の「婚姻」の文言は「生殖と子の養育」に関わる制度を一元的に集約する趣旨を有していないことになる。
すると、「生殖と子の養育」に関わる制度を、憲法24条の「婚姻」を離れて別の制度として立法することが可能となる。
その「生殖と子の養育」に関わる制度は、「婚姻」ではないことから、24条の「両性の合意のみ」や「個人の尊厳」「両性の本質的平等」を満たさなくとも構わないことになる。
例えば、戦前の明治民法のような「戸主」の同意を必要とする「戸主付き生殖関連制度」や「家制度的生殖関連制度」を立法することも可能となる。
そして、その「婚姻」とは異なる「生殖と子の養育」に関わる制度に対して「婚姻」よりも充実した優遇措置を整備するようになった場合には、人々の大半はその制度を利用することを選択し、次第に「婚姻」を利用しなくなっていくことが考えられる。
この影響で、「婚姻」という制度が衰退していき、「婚姻」が「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するための制度として機能しなくなることが考えられる。
すると、実質的に憲法24条の規定が無意味なものとなり、憲法24条が「婚姻」に対して「両性の合意のみ」や「個人の尊厳」「両性の本質的平等」を満たすものとなるように立法裁量の限界を画している意味が希薄化してしまう。
そうなると、もともと憲法24条の「両性の合意のみ」や「個人の尊厳」を根拠として、「同性間の人的結合関係」を憲法24条の「婚姻」の中に含めることができると主張し、それによって「同性間の人的結合関係」についても優遇措置を得られると期待していたにもかかわらず、それをした場合には、そもそも「婚姻」から「生殖と子の養育」の趣旨が失われることから、結果として「生殖と子の養育」に関わる制度を「婚姻」とは別の制度として立法することを許すことに繋がり、その別の制度の優遇措置が増えるなどしてその制度が主流化し、もともと「婚姻」の中に「同性間の人的結合関係」を含めることによって得られると期待していただけの優遇措置を「婚姻」という制度からは得られない状態に陥ることになるのである。
そのため、憲法24条が定めている「両性の合意のみ」や「個人の尊厳」の文言を根拠として、「生殖と子の養育」の趣旨を満たさない人的結合関係についても「婚姻」の中に含めるべきであるとの主張は、結果として、自己の主張の基盤さえも失わせる主張となっているということができる。
よって、憲法24条の定める「両性の合意のみ」や「個人の尊厳」の文言を根拠として、憲法24条の「婚姻」の中に「生殖と子の養育」の趣旨を満たさない人的結合関係を含めることができるとの主張は成り立たない。
もし「生殖と子の養育」の趣旨を満たさない人的結合関係を「婚姻」とする法律を立法しようとした場合には、憲法24条の「婚姻」に抵触して違憲となる。
そのため、憲法24条の「婚姻」の下では「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることはできない。
これらを前提として、この判決が「同性間に対して現行の法律婚制度を及ぼすことが、同条1項の趣旨に照らして禁止されていたとまではいえないと解される。」と述べている部分を改めて検討する。
「婚姻」という概念は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために設けられた枠組みである。
そのため、「婚姻」という概念に含めることができる人的結合関係には、その概念が形成されている目的との関係で内在的な限界がある。
そして、「婚姻」の中には「生殖と子の養育」の趣旨が含まれており、これを満たさない人的結合関係を「婚姻」の中に含めることはできない。
また、24条が「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めていることも、この「生殖と子の養育」の趣旨と整合する形で定められたものとなっている。
「同性間の人的結合関係」については、一般的・抽象的にその間で「生殖」を想定することができないことから、「生殖と子の養育」の趣旨を満たすとはいえず、「婚姻」とすることはできない。
また、憲法24条の「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言の趣旨にも当てはまらないため、「婚姻」とすることはできない。
結果として、憲法24条は「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とする法律を立法することを認めていないことになる。
他にも、憲法24条は「婚姻」を定めていることから、この憲法24条の「婚姻」や「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言が、法律で立法される婚姻制度の意味や内容を「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するものとして機能しないものに変えてしまうことを許しているはずがない。
そのため、婚姻制度の中に「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することが不能となるような人的結合関係を含めようとする法律を立法することを、憲法24条の「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言に照らし合わせて考えた際に、これらの文言はそれを許容していない。
よって、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することが不能となるような人的結合関係を「婚姻」として扱おうとする法律を立法した場合には、憲法24条の「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言に抵触して違憲となる。
このことから、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とする法律を立法しようとした場合には、憲法24条の「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言に抵触して違憲となる。
これらの観点から、この判決が「同性間に対して現行の法律婚制度を及ぼすことが、同条1項の趣旨に照らして禁止されていたとまではいえないと解される。」と述べて、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることができるかのように論じていることは、「婚姻」という概念そのものに含まれている内在的な限界や、憲法24条の「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言の趣旨を考慮しないものであり、誤りとなる。
■ 「禁止」の意味との関係性
この判決は「禁止されていたとまではいえない」と述べるが、これは下記のように考えることになる。
① 義務文・否定文による禁止
24条1項の条文を確認すると、最後に「~なければならない。」と記載されている。
また、英語では「shall」の文言が2回使われており、「両性の合意のみに基いて成立し、」の部分についても「shall」で表現されている。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
Article 24. Marriage shall be based only on the mutual consent of both sexes and it shall be maintained through mutual cooperation with the equal rights of husband and wife as a basis.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
英文契約書における権利義務の定め方
そのことから、24条1項は「義務文・否定文による禁止」の意味を有していると考えることができる。
「同性間の人的結合関係」については、24条が「婚姻は、両性~に基いて成立し~なければならない。」(shall)と定めていることの「両性」の部分を満たさないことから禁止されている。
② 防ぐ意図の禁止(狭義の禁止)
憲法24条1項には「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」と記載されている。
憲法上に具体的な基準を示しており、また、いくつかの事項を満たすことを求めるものとなっている。
そのことから、憲法24条1項は「防ぐ意図の禁止」の意味を有していると考えることができる。
憲法24条は「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることの論点を認知した上で、それを防ぐ意図をもって規定されていることから禁止されている。
【参考】「24条は『両性の合意』に基づかない婚姻の成立を制限している。」 Twitter
【参考】「24条は『婚姻の自由の及ぶ範囲を規定している』」 Twitter
【参考】「範囲を規定している以上、その効果は範囲内に制限され、それ以外が除外される」 Twitter
【参考】「【男性禁止】だと不必要に攻撃的で印象が悪いので普通は【女性専用】を使うわな。」 Twitter
【参考】「24条は婚姻の成立条件を異性婚に限定しようという意図が含まれていると解するほうが、よほど論理的つながりがスムーズ」 Twitter
【参考】「『~せねばならない』なんて物言いは全く不要です。」 Twitter
【参考】「憲法で『禁ずる』と述べているのは36条のみ」 Twitter (憲法36条)
【参考】「【禁止】と銘打たなくても、対象を限定したり、それ以外を排除することは可能」 Twitter
【参考】「『禁止じゃなきゃ制限できない』なら、24条は『戸主による強制的な婚姻』すら制限できないことになるよね。」 Twitter
【参考】「24条は【戸主による婚姻の強制】を【制限】しているわけだし、」 Twitter
【参考】「ま、取り敢えず、『24条は一定の制限を画している』事実を認めたわけで、」 Twitter
【参考】「『24条は戸主による強制的な婚姻を制限している』を目的の一つと認めた時点で『禁止してないのに制限してる』事実を認めたことに他ならない。」 Twitter
【参考】「『禁止していない』だけ大声で叫んでも『許容している』ことにはならない」 Twitter
【参考】「『禁止を明示していなければ一切の制限は不可能』という公的な解釈を出して御覧なさい。」 Twitter
【参考】「例えば学校教育法2条で学校設置者が国、地方、学校法人のみとされてますが、禁止の文ではないのだから個人もOKと読んでいいのですか?」 Twitter (学校教育法2条)
③ 上位法に反する禁止(広義の禁止)
憲法24条1項には「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」の文言があり、一夫一婦制(男女二人一組)を定めている。
これらの文言の趣旨を満たさない形で法律を立法した場合には、上位法である憲法と下位法である法律の間に矛盾・衝突が生じることになる。
この場合、上位法である憲法を基準として、下位法である法律の内容の齟齬がある部分を是正することになる。
このため、憲法24条1項は「上位法に反する禁止」の意味を有していると考えることができる。
憲法24条の下で婚姻制度を「同性間の人的結合関係」を含む形で立法しようとした場合には憲法24条に違反するため、結果としてこれは禁止されている。
【参考】「婚姻の成立条件は両性の合意【のみ】だということです。」 Twitter
【参考】「「のみ」で「成立」なので反対解釈すると「両性の合意以外は不成立」になります。」 Twitter
【参考】「同性婚を婚姻の成立と認めていない」 Twitter
【参考】「そもそも同性は婚姻の対象にならない。」 Twitter
【参考】「結婚は異性同士でするもので差別とは全く関係ない」 Twitter
【参考】「そもそも婚姻は男女が一緒になることを意味していて、同性が一緒に暮らすことを婚姻とは言わないから。排除も禁止も必要もない。」 Twitter
【参考】「同性婚の概念が無く、従って同性婚を否定するネガティブ規定は、それを明文化する必要が無かった。」 Twitter
【参考】「違憲の条件は『禁止していること』ではなく『反していること』だからね。」 Twitter
【参考】「24条は禁じていないが、98条が『憲法に反した立法行為』を否定」 Twitter
憲法24条の下では「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることはできない。
そのため、憲法24条がそれを「禁止」する趣旨であるかどうかという点については、上記の①「義務文・否定文による禁止」、②「防ぐ意図の禁止」、③「上位法に反する禁止」のいずれの立場によって説明するものであるかという問題に過ぎないものとなる。
そして、これは➀②③が同時に成り立つ場合、②と③が同時に成り立つ場合、③だけに該当する場合の3つのパターンによって説明することが可能である。
この判決の「禁止されていたとまではいえない」の文についても、①ではない、①と②ではないという部分までは何とか意味が成り立つとしても、③ではないという意味までは成り立たない。
■ 結論
この判決は、「同条1項の趣旨に照らして禁止されていたとまではいえない」と述べて、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることができるかのように論じようとしている。
しかし、上記の点を考慮しておらず、その結論は正当化することができない。
憲法上の文言に従う解釈を行った場合に、そこに目的を達成するための手段として整合的な枠組みとなっていることを確認することができ、憲法上の規範としての意義を見出すことができる以上は、そこに規範的な力を認めることによって、憲法の規範性を保つことが求められる。
社会の根幹に関わる制度について、安易に憲法の規範力を損なわせる方向で考え、その制度の枠組みそのものを、その時々の政治的な事情や、国民のその時々の一時的な感情の振れ幅に委ねることができるかのように述べていることは適切ではない。
これら点を考慮せずに、「禁止されていたとまではいえない」というように憲法の規範力を損なわせるような説明を行っていることは、内容が不適切であるばかりか、法秩序の安定性まで損なわせるものとなっており、妥当であるとはいえない。
■ 論じる必要のない論点であること
この判決は、憲法24条1項について「同性間に対して現行の法律婚制度を及ぼすことが、同条1項の趣旨に照らして禁止されていたとまではいえないと解される。」と述べて、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることができるかのように論じている。
しかし、今回の事例は、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とする法律が存在していないことが憲法24条1項に違反するか否かが問われているのであって、憲法24条の下で「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とする法律を立法した場合に憲法24条に違反するか否かという意味において「禁止」しているか否かが問われているわけではない。
そのため、憲法24条の下で「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とする法律を立法した場合に、その法律が憲法24条に違反するか否かについてまで判断を示す必要がないものである。
解釈の方法について様々な論点が存在し、様々な立場から対立が見られるテーマについて、今回の事件の論点を超える形で裁判所が独断で方向性を示すことは控えるべきであると考える。
今回の事件の論点を超える形で判断を示すことは、別の事件が生じたときに、改めて別の角度から検討した結果、別の判断が下されることも起こり得る。
そのことから、他の立場の意見を網羅的に検討した上で異論が出ないほどまでに確立しているような十分な理由を示すこともなく、憲法24条の「婚姻」の下で「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とする法律を立法することが可能であるという意味において「禁止されていたとまではいえない」などと一方の意見のみを述べて何らかの方向性を与えようとすることは、この事例を解決するにあたって求められている法解釈の範囲を超える形で政治部門の特定の政策に対して支持、不支持、適当、不当を表明するものと受け止められかねないものとなっており、司法権の行使として適切な範囲を超えることになると考えられる。
国(行政府)の主張でも、この論点は今回の事例の争点ではないことについて指摘されている。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
なお、被控訴人原審第 2準備書面26ページにおいて述べたとおり、そもそも、憲法 24条との関係で木件立法不作為が違憲であることが明白であるといえるためには、同条が同性問の婚姻を法制化するととを国会に対して要請しているといえなければならず、同性婚が憲法上禁止されているか、又は許容されているのかという点は、原告らの憲法24条に関する主張の当否の判断において争点とはならないため、この点に関する回答は差し控える。また、憲法が同性問の婚姻を法制化することを国会に対して要請していないことは、控訴答弁書7ないし10ページにおいて述べたとおりである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【札幌・第2回】被控訴人回答書 令和4年3月4日 PDF
司法の謙抑性の観点からも、様々な論点が存在し、異論がないほどまでに解釈の方法が確立しているわけではない問題について、一定の方向性を与えるようなことを述べることは不適切ということができる。
司法権を行使する裁判所は、その事件を受け持った裁判官や裁判体の政治的な意見表明を行う場ではないことを心得る必要がある。
この文では、「そして」のように一つ前の文の憲法24条の制定経緯の文を繋ぎ、加えて「同性間の結合が「婚姻」に含まれるかについての議論がなされた形跡はないこと」を「考慮」することによって、「同性間の結合」を「婚姻」とすることが「禁止されていたとまではいえない」という結論を導き出そうとするものとなっている。
しかし、上記のように、憲法24条の制定経緯によっても、「議論がなされた形跡はないこと」によっても、「同性間の結合」を「婚姻」とすることができるとする理由を示すものにはならない。
よって、それを理由として「同性間の結合」を「婚姻」とすることについて「禁止されていたとまではいえない」のように述べて、「同性間の結合」を「婚姻」とすることができるかのような前提で論じようとしている部分は誤りとなる。
そして、近年多数の諸外国において同性婚制度が導入され(認定事実⑷ウ
)、我が国でも、地方自治体において、登録パートナーシップ制度の導入が進んでいること(認定事実⑸ウ )、諸団体から同性婚の法制化を求める声が上がっていること(認定事実⑸エ)などの事情に鑑みると、制定当時の理解が現時点でも妥当するものであるかについては、なお検討を要するところといわねばならない。
【筆者】
「近年多数の諸外国において同性婚制度が導入され」との記載がある。
ここに「同性婚制度」との文言があるが、外国語を翻訳する者が「諸外国」の法制度について「婚」という「婚姻」を指す言葉を充てて説明しているとしても、それは日本国の法制度における「婚姻」と同一のものを指していることにはならない。
なぜならば、「諸外国」の法制度は、それぞれの国の社会事情の中で生じている問題を解消することを意図して構築されたものであり、その立法目的やその立法目的を達成するための手段・方法には様々な違いがあるからである。
そのため、その「諸外国」の法制度と日本国の法制度との間に何らかの類似点を見出すことができる場合があるとしても、それはそれぞれの国の社会事情の中で形成された別個の制度であり、同一の制度を指していることにはならない。
よって、「諸外国」が「同性間の人的結合関係」を対象とした法制度を設けているとしても、日本国の法制度における「婚姻」と同一の制度について述べていることにはならないし、そのことが日本国の法制度に直接的な影響を与えることもない。
また、「諸外国」の事例を取り上げたとしても、そのことは日本国の法制度における「婚姻」の中に「同性間の人的結合関係」を含めることができるとする根拠にもならない。
「諸外国」の事例を取り上げる際には、この点に注意する必要がある。
「我が国でも、地方自治体において、登録パートナーシップ制度の導入が進んでいる」との記載がある。
まず、地方公共団体は、憲法や法律の範囲内でしか活動することはできない。
そのため、憲法や法律の解釈を行う際には、地方自治体の「登録パートナーシップ制度」のような憲法や法律の範囲内でしか運用することのできない事柄を持ち出して論拠を固めることはできない。
憲法や法律について解釈を行う際に、憲法や法律よりも下位の法令を持ち出すことは、その解釈の正当性を裏付けるものとはならない。
また、地方自治体の「登録パートナーシップ制度」は、憲法に定められた「婚姻」や法律上の婚姻制度に抵触している場合には、違法となる。
そのため、そもそも地方自治体の「登録パートナーシップ制度」が上位法である憲法や民法に抵触して違法となっている可能性があるにもかかわらず、このような制度が適法に成立することができることを前提として取り上げ、憲法上の規定の解釈を行うための参考となるかのような前提で論じていることは妥当でない。
この点について、詳しくは当サイト「パートナーシップ制度」で解説している。
「諸団体から同性婚の法制化を求める声が上がっている」との記載がある。
ここでいう「諸団体」とは(認定事実⑸エ)に挙げられている「民間企業等」「弁護士会」「在日外国団体」「日本学術会議」である。
それらの団体は、もともと様々な意見を表明する自由があり、実際に様々な意見を表明しながら活動を行っている。
ここで取り上げているものも、その自由の中で表明された一つの意見に過ぎない。
そのため、それらの団体が賛否を表明したとしても、それによって裁判所が法解釈を行う際に合憲・違憲の判断が変わることはない。
また、そのような事柄に影響を受けるようなこともあってはならない。
「制定当時の理解が現時点でも妥当するものであるかについては、なお検討を要するところといわねばならない。」との記載がある。
「婚姻」は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた枠組みである。
この立法目的を達成するための手段として必要となる要素を満たす人的結合関係は「婚姻」とすることができるが、それを満たさない人的結合関係は「婚姻」とすることはできない。
これは「婚姻」という概念そのものが有する内在的な限界である。
そのため、その要素を満たさない人的結合関係を「婚姻」とすることが可能であるかのような前提で検討を行おうとしていることは妥当でない。
エ もっとも、前記アのとおり、婚姻及び家族に関する事項は、国の伝統や国民感情を含めた社会状況における種々の要因を踏まえつつ、それぞれの時代における夫婦や親子関係についての全体の規律を見据えた総合的な判断を行うことによって定められるべきものであり、同条1項の「婚姻」は、同条2項を通じて、法律により具体化された法律婚制度であることを踏まえて検討しなければならない。
【筆者】
まず、ここでいう「婚姻及び家族に関する事項」とは、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた「婚姻」と、その「婚姻」と同一の目的を共有し、その目的を達成するための手段として「婚姻」の枠組みに付随する形で設けられている「家族」の枠組みをいうものである。
そのため、「同性間の人的結合関係」については、その間で一般的・抽象的に「生殖」を想定することができないことから、「婚姻」とすることはできないし、それが「親子」や「親子」の関係を基本とした「兄弟」「姉妹」などに含まれないのであれば「家族」の中にも含まれない。
そのことから、ここでは「婚姻及び家族に関する事項」について「国の伝統や国民感情を含めた社会状況における種々の要因を踏まえつつ、それぞれの時代における夫婦や親子関係についての全体の規律を見据えた総合的な判断を行うことによって定められるべきもの」としてその「同性間の人的結合関係」が「婚姻及び家族」の中に含まれる余地があるかのような前提で「検討」を行おうとするものなっているが、そもそもそれ以前にその「同性間の人的結合関係」が「婚姻及び家族」の中に含まれるか否かについての検討を行う必要があり、その検討を怠っている点で妥当でない。
「同条1項の「婚姻」は、同条2項を通じて、法律により具体化された法律婚制度であることを踏まえて検討しなければならない。」との部分について検討する。
ここでは「同条1項の「婚姻」」が「同条2項を通じて、法律により具体化された法律婚制度である」と述べているが、「同条1項の「婚姻」」そのものは憲法上の規定であり、「法律により具体化された法律婚制度」とはいえないため、誤りとなる。
「同条1項」を解釈したときに導き出される「婚姻をするについての自由」は、「同条2項を通じて、法律により具体化された法律婚制度」を利用するか否かに関する自由をいうという意味であれば最高裁判決が示した理解にも沿うものであり理解が可能であるが、それでも「同条1項」の「婚姻」そのものと、「同条1項」を解釈したときに導き出される「婚姻をするについての自由」は異なる概念であるため、これを区別できていない点で妥当でない。
もう一つ、この段落の「婚姻及び家族に関する事項は,国の伝統や国民感情を含めた社会状況における種々の要因を踏まえつつ、それぞれの時代における夫婦や親子関係についての全体の規律を見据えた総合的な判断(を行うこと)によって定められるべきもの」の部分は、最高裁判決の「再婚禁止期間大法廷判決」と「夫婦同氏制大法廷判決」で示された文面と重なるものとなっている。
(下記の灰色で潰した部分が、この名古屋地裁判決の上記の部分と重なる部分である。)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ところで,婚姻及び家族に関する事項は,国の伝統や国民感情を含めた社会状況における種々の要因を踏まえつつ,それぞれの時代における夫婦や親子関係についての全体の規律を見据えた総合的な判断を行うことによって定められるべきものである。……(略)……
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
損害賠償請求事件 最高裁判所大法廷 平成27年12月16日 (再婚禁止期間大法廷判決) (PDF)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3(1) 他方で,婚姻及び家族に関する事項は,国の伝統や国民感情を含めた社会状況における種々の要因を踏まえつつ,それぞれの時代における夫婦や親子関係についての全体の規律を見据えた総合的な判断によって定められるべきものである。……(略)……
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
損害賠償請求事件 最高裁判所大法廷 平成27年12月16日 (夫婦同氏制大法廷判決) (PDF)
そして、この段落ではそれを「踏まえて検討しなければならない。」述べている。
ここでいう「検討」の内容とは、この「⑵ 憲法24条1項に違反するかについて」の項目で問われている、24条1項が「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを「要請」しているか否かである。
このことは、この「⑵ 憲法24条1項に違反するかについて」の項目が下記のような文の流れとなっていることから確認することができる。
◇ 「ア」の第二段落
「法律によって具体化された法律婚制度を同性間に対しても及ぼすことが、同条1項の趣旨に照らして要請されているかという観点から検討するのが相当である。」
↓ ↓ ↓
◇ 「イ」の第三段落
「少なくともその制定当時において、同性間に対して民法及び戸籍法等の法律によって具体化された法律婚制度を及ぼすことが、同条1項の趣旨に照らして要請されていたとは解し難い。」
↓ ↓ ↓ (『イ』の結論を受けてもさらに加えて検討)
◇ 「ウ」の第一段落
「原告らは、」「その後の社会情勢の変化等により、同性間の結合も「婚姻」に含まれるとする社会的な意識が確立し、同性間に対しても法律婚制度を及ぼすことが要請されるに至ったと主張する。」
◇ 「ウ」の第三段落
「制定当時の理解が現時点でも妥当するものであるかについては、なお検討を要するところといわねばならない。」
この文の流れに従って、この「エ」の部分では「踏まえて検討しなければならない。」と述べているのである。
そして、これより以下で「オ」「カ」「キ」「ク」を検討した上で、「ケ」の部分で「憲法が一義的に、同性間に対しても現行の法律婚制度を及ぼすことを要請するに至ったとは解し難いといわざるを得ない。」と結論付けている。
さらに補足して、「コ」を検討した上で、「サ」の部分で「現時点においても、現行の法律婚制度を同性間に対して及ぼすことが、憲法24条1項の趣旨に照らして要請されていると解することは困難である」と結論付けるものとなっている。
しかし、最高裁判決がこの文面を示して述べていることは、「婚姻及び家族に関する事項は,国の伝統や国民感情を含めた社会状況における種々の要因を踏まえつつ、それぞれの時代における夫婦や親子関係についての全体の規律を見据えた総合的な判断(を行うこと)によって定められるべきもの」だから、基本的には「国会の合理的な立法裁量に委ねる」ことによって法律で具体化することがふさわしいということである。
(下記の灰色で潰した部分が、この名古屋地裁判決の上記の部分と重なる部分である。)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ところで,婚姻及び家族に関する事項は,国の伝統や国民感情を含めた社会状況における種々の要因を踏まえつつ,それぞれの時代における夫婦や親子関係についての全体の規律を見据えた総合的な判断を行うことによって定められるべきものである。したがって,その内容の詳細については,憲法が一義的に定めるのではなく,法律によってこれを具体化することがふさわしいものと考えられる。憲法24条2項は,このような観点から,婚姻及び家族に関する事項について,具体的な制度の構築を第一次的には国会の合理的な立法裁量に委ねるとともに,その立法に当たっては,個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきであるとする要請,指針を示すことによって,その裁量の限界を画したものといえる。また,同条1項は,「婚姻は,両性の合意のみに基いて成立し,夫婦が同等の権利を有することを基本として,相互の協力により,維持されなければならない。」と規定しており,婚姻をするかどうか,いつ誰と婚姻をするかについては,当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたものと解される。婚姻は,これにより,配偶者の相続権(民法890条)や夫婦間の子が嫡出子となること(同法772条1項等)などの重要な法律上の効果が与えられるものとされているほか,近年家族等に関する国民の意識の多様化が指摘されつつも,国民の中にはなお法律婚を尊重する意識が幅広く浸透していると考えられることをも併せ考慮すると,上記のような婚姻をするについての自由は,憲法24条1項の規定の趣旨に照らし,十分尊重に値するものと解することができる。
そうすると,婚姻制度に関わる立法として,婚姻に対する直接的な制約を課すことが内容となっている本件規定については,その合理的な根拠の有無について以上のような事柄の性質を十分考慮に入れた上で検討をすることが必要である。
そこで,本件においては,上記の考え方に基づき,本件規定が再婚をする際の要件に関し男女の区別をしていることにつき,そのような区別をすることの立法目的に合理的な根拠があり,かつ,その区別の具体的内容が上記の立法目的との関連において合理性を有するものであるかどうかという観点から憲法適合性の審査を行うのが相当である。以下,このような観点から検討する。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
損害賠償請求事件 最高裁判所大法廷 平成27年12月16日 (再婚禁止期間大法廷判決) (PDF)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 憲法24条は,2項において「配偶者の選択,財産権,相続,住居の選定,離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては,法律は,個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して,制定されなければならない。」と規定している。
婚姻及び家族に関する事項は,関連する法制度においてその具体的内容が定められていくものであることから,当該法制度の制度設計が重要な意味を持つものであるところ,憲法24条2項は,具体的な制度の構築を第一次的には国会の合理的な立法裁量に委ねるとともに,その立法に当たっては,同条1項も前提としつつ,個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきであるとする要請,指針を示すことによって,その裁量の限界を画したものといえる。
そして,憲法24条が,本質的に様々な要素を検討して行われるべき立法作用に対してあえて立法上の要請,指針を明示していることからすると,その要請,指針は,単に,憲法上の権利として保障される人格権を不当に侵害するものでなく,かつ,両性の形式的な平等が保たれた内容の法律が制定されればそれで足りるというものではないのであって,憲法上直接保障された権利とまではいえない人格的利益をも尊重すべきこと,両性の実質的な平等が保たれるように図ること,婚姻制度の内容により婚姻をすることが事実上不当に制約されることのないように図ること等についても十分に配慮した法律の制定を求めるものであり,この点でも立法裁量に限定的な指針を与えるものといえる。
3(1) 他方で,婚姻及び家族に関する事項は,国の伝統や国民感情を含めた社会状況における種々の要因を踏まえつつ,それぞれの時代における夫婦や親子関係についての全体の規律を見据えた総合的な判断によって定められるべきものである。特に,憲法上直接保障された権利とまではいえない人格的利益や実質的平等は,その内容として多様なものが考えられ,それらの実現の在り方は,その時々における社会的条件,国民生活の状況,家族の在り方等との関係において決められるべきものである。
(2) そうすると,憲法上の権利として保障される人格権を不当に侵害して憲法13条に違反する立法措置や不合理な差別を定めて憲法14条1項に違反する立法措置を講じてはならないことは当然であるとはいえ,憲法24条の要請,指針に応えて具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定が上記(1)のとおり国会の多方面にわたる検討と判断に委ねられているものであることからすれば,婚姻及び家族に関する法制度を定めた法律の規定が憲法13条,14条1項に違反しない場合に,更に憲法24条にも適合するものとして是認されるか否かは,当該法制度の趣旨や同制度を採用することにより生ずる影響につき検討し,当該規定が個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理性を欠き,国会の立法裁量の範囲を超えるものとみざるを得ないような場合に当たるか否かという観点から判断すべきものとするのが相当である。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
損害賠償請求事件 最高裁判所大法廷 平成27年12月16日 (夫婦同氏制大法廷判決) (PDF)
そして、その「婚姻及び家族に関する事項」が憲法上の規定に違反する場合とは、「その裁量の限界」を超えるものと見ざるを得ないような場合に限られることについて述べるものである。
これは、決して24条に違反するか否かの基準を「国の伝統や国民感情を含めた社会状況における種々の要因を踏まえつつ、それぞれの時代における夫婦や親子関係についての全体の規律を見据えた総合的な判断(を行うこと)によって」決めるべきと述べているものではない。
それにもかかわらず、この名古屋地裁判決は24条に違反するか否かの基準が「国の伝統や国民感情を含めた社会状況における種々の要因を踏まえつつ、それぞれの時代における夫婦や親子関係についての全体の規律を見据えた総合的な判断(を行うこと)によって」導き出されるものであるかのような理解を前提として、「オ」で「捉えられてきた」「否定し難い」「認められる。」「見るのは困難である。」、「カ」で「うかがわれる。」「無視し得ない事実である。」、「キ」で「評価できる。」「価値を失っているわけではない」「否定されたわけではない。」「避けられないと考えられる。」、「ク」で「ありうるところである。」と述べ、結論として24条1項が「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを「要請」していないと判断を下すものとなっている。
これは最高裁判決が、「婚姻及び家族に関する事項は,国の伝統や国民感情を含めた社会状況における種々の要因を踏まえつつ、それぞれの時代における夫婦や親子関係についての全体の規律を見据えた総合的な判断(を行うこと)によって定められるべきもの」だから、基本的には「国会の合理的な立法裁量に委ねる」ことによって法律で具体化することがふさわしいと述べている部分を、あたかも「婚姻及び家族に関する事項」が24条に違反するか否かの基準が「国の伝統や国民感情を含めた社会状況における種々の要因を踏まえつつ、それぞれの時代における夫婦や親子関係についての全体の規律を見据えた総合的な判断(を行うこと)によって」導き出されるかのように文面の意味を取り替えて論じるものであり、用い方を誤っている。
この点で、この名古屋地裁判決は最高裁判決の文面の意味を正しく理解しているものとはいえず、不正な手続きとなっている。
そのため、これ以降のこれを前提とした説明については、解釈の方法として正当化することができるものではない。
オ そこで検討すると、人類は、男女の結合関係を営み、種の保存を図ってきたところ、婚姻制度が、この関係を規範によって統制するために生まれたものであることは、前記イのとおりであり、その形態は、当該社会の経済的・政治的又は道徳的理念によって、時代や地域ごとに様々であるとしても、婚姻は、正当な男女の結合関係を承認するものとして存在し、男女の生活共同体として、その間に生まれた子の保護・育成、分業的生活共同体の維持を通じ、家族の中核を形成するものであると捉えられてきた(認定事実⑵ア)。
【筆者】
「人類は、男女の結合関係を営み、種の保存を図ってきたところ、婚姻制度が、この関係を規範によって統制するために生まれたものである」との部分であるが、その通りである。
ただ、その「規範によって統制する」という背景には、「生殖」に関わって社会的な不都合が生じていることが原因である。
もし何らの不都合も存在しないのであれば、そもそも「規範によって統制する」ことも必要ないはずだからである。
よって、婚姻制度が「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として形成されていることは明らかである。
「その形態は、当該社会の経済的・政治的又は道徳的理念によって、時代や地域ごとに様々であるとしても、」との部分であるが、おおよそその通りである。
「その形態」であるが、「婚姻制度」は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度であり、その目的を達成するための手段として整合的な範囲で、夫婦の財産関係や相続関係を定めるなどするものとなっている。
ただ、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的との関係で整合的な範囲で、夫婦の財産関係や相続関係などの付随して設けられている法的効果が「様々である」としても、「婚姻」そのものが「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成するための手段として設けられていることに違いはないのであり、その部分が変わるというものではないことに注意が必要である。
「婚姻は、正当な男女の結合関係を承認するものとして存在し、」との部分について検討する。
「婚姻」が「男女の結合関係」を対象としていることは、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として、その間で一般的・抽象的に自然生殖を想定することができる「男性」と「女性」の組み合わせに「貞操義務」を設けるなど一定の形式で法的に結び付けることによって、産まれてきた子供の父親を特定することができる関係を推進する仕組みとなっていることによるものである。
その婚姻制度を利用する者を「正当」と考えるか否かや、「承認」するか否かは、個々人の価値観の問題であり、法律論として論じることのできるものではない。
そのことから、婚姻制度を利用している者に対して、個々人が「正当」であるという価値観を抱く場合や、「承認」するという場合があるとしても、それを理由として婚姻制度の立法目的とその立法目的を達成するための手段となる枠組みの当否の問題を無視して、その婚姻制度の枠組みの方を変更しなければならないとする理由にはならないことに注意が必要である。
(婚姻は、)「男女の生活共同体として、その間に生まれた子の保護・育成、分業的生活共同体の維持を通じ、家族の中核を形成するものであると捉えられてきた」との部分について検討する。
「婚姻」が「男女の生活共同体として、その間に生まれた子の保護・育成、分業的生活共同体の維持を通じ、家族の中核を形成するものであると捉えられてきた」ことの理由は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消する必要性から、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」という目的が存在し、それらの目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす「男性」と「女性」の組み合わせを枠付けるところに「婚姻」が設けられているからである。
このように「立法目的」と「その立法目的を達成するための手段」となる枠組みの関係を示さずに、「捉えられてきた」と述べたところで、なぜ「婚姻」の枠組みが「男女」を対象としているのかを説明していることにはならないことに注意が必要である。
「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消する必要性
↓
「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」 …(目的)
↓
「男女」の組み合わせを枠付ける …(手段)
↓
「婚姻」
↓
「男女」と「捉えられてきた」
そして、我が国の年間出生総数に占める非嫡出子の割合は、統計上の数値(大正9年から平成29年)によれば、最大でも8.25%(大正8年)、最小では0.78%(昭和51年)であったのであり、平成29年時点でも2.23%であったこと(認定事実⑺イ )などからすると、法律婚制度が、我が国の社会において、上記のような家族の中核としての機能を通じ、男女が共同生活を送りながら、子を産み育て、次世代へ承継していく営みにおいて、重要かつ不可欠な役割を果たしてきた事実があることは、もとより否定し難いところである。また、近年家族等に関する国民の意識の多様化が指摘されつつも、平成27年時点でも、結婚する理由として子供を持ちたいと回答する者が70%であり、結婚したら子供を持つべきであると回答する者が60%以上であったとする結果が存在し(認定事実⑺ア )、国民の中には、子を産み育てることに婚姻の意義を見出す者が今なお少なからず存在していることが認められる。
【筆者】
「我が国の年間出生総数に占める非嫡出子の割合は、統計上の数値(大正9年から平成29年)によれば、最大でも8.25%(大正8年)、最小では0.78%(昭和51年)であったのであり、平成29年時点でも2.23%であった」との記載がある。
「非嫡出子の割合」は下記のようなデータがある。
【参考】男女格差を失くすと豊かな一夫多妻的な社会になる 2016.10.05
【参考】表4-18 嫡出でない子の出生数および割合:1920~2015年
これは、日本国の婚姻制度が「子の福祉」を実現するための手段として「嫡出子として生まれること」を重視した制度設計となっていることによるものと考えられる。
このように、日本国の中で婚姻制度に期待されているものは、他国の例とは比較にならないほどの背景の違いがある。
そのため、外国の法制度との間で比較する際にも、外国のある法制度に対して翻訳者が「婚姻」という言葉を充てて説明している場合があるとしても、それは日本国の法制度における「婚姻」と同一のものを指していることにはならない点に注意が必要である。
「法律婚制度が、我が国の社会において、上記のような家族の中核としての機能を通じ、男女が共同生活を送りながら、子を産み育て、次世代へ承継していく営みにおいて、重要かつ不可欠な役割を果たしてきた事実があることは、もとより否定し難いところである。」との記載がある。
この文は、この直前の部分で「我が国の年間出生総数に占める非嫡出子の割合」について述べられており、それを前提として説明するものであるから、「男女」が「法律婚制度」を利用することによって嫡出子として「子を産み育て」ている割合が多いことを示し、それを根拠として「法律婚制度」が「男女が共同生活を送りながら、子を産み育て、次世代へ承継していく営み」や「家族の中核としての機能」において「重要かつ不可欠な役割を果たしてきた」と論じるものとなっている。
ただ、これは「男女」が「子を産み育て、次世代へ承継していく営み」を行おうとした場合に、その多くが「法律婚制度」を利用することを選択して嫡出子として「子を産み育て」ようとする事実を示すものではあるが、なぜ「法律婚制度」が「男女」の枠組みとなっているのか、その理由を直接的に明らかにするものであるとはいえない。
そのため、この「法律婚制度」が「果たしてきた事実」を根拠として、24条1項の「婚姻」が「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを「要請」しているか否かを解釈するための原因とすることは妥当ではない。
よって、24条1項の「婚姻」が「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを「要請」しているか否かを検討するためには、「婚姻」の枠組みが果たしている機能よりも、「婚姻」の枠組みが設けられている立法目的について論じることが必要である。
具体的には、下記のような順序で論じることが妥当である。
「婚姻」は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消する必要性から、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」という立法目的を有している。
そして、その立法目的を達成するための手段として、一般的・抽象的にその間で自然生殖を想定することができる「男性」と「女性」の組み合わせが選び出され、そこに「貞操義務」を設けるなど一定の形式で法的に結び付けることによって、産まれてきた子供の父親を特定することができる関係となる状態を推進し、その立法目的の実現を目指すものとなっている。
この文が「男女」が「子を産み育て、次世代へ承継していく営み」を行おうとした場合に、その多くが「法律婚制度」を利用することを選択して嫡出子として「子を産み育て」ようとする事実を示していることは、婚姻制度の政策的な意図が十分に機能しており、その立法目的の実現に寄与するものとなっていることを裏付けるものということができる。
ただ、この立法目的を達成するための手段として設けられている枠組みが果たしている機能を根拠として、遡ってその制度の立法目的やその立法目的を達成するための手段として設けられている枠組みの方を変更することができるとする理由にはならない。
よって、この点を24条1項が「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを「要請」しているか否かを論じるものとして、このような事実を取り上げていることは、解釈の方法としては適切ではない。
「近年家族等に関する国民の意識の多様化が指摘されつつも、平成27年時点でも、結婚する理由として子供を持ちたいと回答する者が70%であり、結婚したら子供を持つべきであると回答する者が60%以上であったとする結果が存在し(…)、国民の中には、子を産み育てることに婚姻の意義を見出す者が今なお少なからず存在していることが認められる。」(カッコ内省略)との記載がある。
ここでは、「結婚する理由として子供を持ちたいと回答する者」「結婚したら子供を持つべきであると回答する者」を取り上げ、「国民の中には、子を産み育てることに婚姻の意義を見出す者が今なお少なからず存在している」と述べられている。
これは「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的(① 国の立法目的)として、「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた「婚姻」という制度を利用する場合に、個々人がどのように活用するかという「③ 個々人の利用目的」について述べるものである。
しかし、婚姻制度に対する「③ 個々人の利用目的」がどのような理由であるとしても、「① 国の立法目的」が変化することにはならない。
よって、このように「③ 個々人の利用目的」の統計を持ち出して、婚姻制度の「① 国の立法目的」を検討しようとすることは誤りである。
もう一つ、「国民の中には、子を産み育てることに婚姻の意義を見出す者が今なお少なからず存在している」ということは、国民の間で婚姻制度がどのような効果を有しているかが理解されており、実際に子を産む際に婚姻制度を利用する者が多数いるという関係にあるから、国が婚姻制度を設けるという政策的な意図が機能しており、立法目的の達成に寄与していることの現われと見ることができる。
この文章からは、この点を読み取ることができる。
以上のとおり、婚姻は、男女が共同生活を送りながら、子を産み育て、次世代へ承継していく営みにおいて、重要かつ不可欠な役割を果たしてきたものであり、国民の中には、子を産み育てることに婚姻の意義を見出す者が今なお少なからず存在していることに照らせば、諸外国で同性間の婚姻制度が導入され、我が国でも同性婚の法制化を求める声が高まっている事実があるとしても、依然として婚姻制度と自然生殖の可能性が完全に切り離されたと見るのは困難である。
【筆者】
「婚姻は、男女が共同生活を送りながら、子を産み育て、次世代へ承継していく営みにおいて、重要かつ不可欠な役割を果たしてきたものであり、」との記載がある。
「婚姻」は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消する必要性から、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」という立法目的を有しており、その立法目的を達成するための手段として、一般的・抽象的にその間で自然生殖を想定することができる「男性」と「女性」の組み合わせが選び出され、そこに「貞操義務」を設けるなど一定の形式で法的に結び付けることによって、その立法目的の達成を目指すものである。
「婚姻」が「男女」を対象としていることは、このような目的を達成するための手段として整合的な要素を満たすことが理由である。
ここでいう「男女が共同生活を送りながら、子を産み育て、次世代へ承継していく営み」とい部分も、このような目的を達成するための手段として整合的な形を満たす人的結合関係について述べているものとなる。
ただ、この「⑵ 憲法24条1項に違反するかについて」の項目では24条1項が「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを「要請」しているか否かが問われており、それを判断するための根拠としてこの「営み」が「重要かつ不可欠な役割を果たしてきた」ことを挙げようとしているが、その「営み」の内容を示すだけでは、それがなぜ「男女」の二人一組であるのかを明確に示すものであるとはいえない。
「男女が共同生活を送りながら、子を産み育て、次世代へ承継していく営み」それ自体は、「婚姻」の機能に対応するものであって、「① 国の立法目的」を説明するものとは異なるからである。
この点の説明は十分でないといえる。
「国民の中には、子を産み育てることに婚姻の意義を見出す者が今なお少なからず存在していることに照らせば、」との記載がある。
この「子を産み育てることに婚姻の意義を見出す者」の部分であるが、これは婚姻制度の枠組みを定める原因となっている「① 国の立法目的」について「子を産み育てること」に意義を見出す者を意味するものなのか、婚姻制度を利用する場合の「③ 個々人の利用目的」について「子を産み育てること」に意義を見出す者を意味するものなのかを特定することが必要である。
これは一つ前の段落に「国民の中には、子を産み育てることに婚姻の意義を見出す者が今なお少なからず存在している」と書かれていることを前提として、この文の冒頭で「以上のとおり、」と繋いだ上で記載されていることから、この内容は「③ 個々人の利用目的」について述べられたものということができる。
しかし、婚姻制度についての「③ 個々人の利用目的」についてどのような意見があるとしても、そのことは「① 国の立法目的」が変わるとする理由になるものではないため、これを婚姻制度の枠組みについて検討するための材料として取り上げることができるかのように論じていることは妥当でない。
「諸外国で同性間の婚姻制度が導入され、」との記載がある。
ここでいう「同性間の婚姻制度」との文言について、外国語を翻訳する者が「諸外国」の法制度について「婚姻」という言葉を使って翻訳しているからといって、それは日本国の法制度における「婚姻」と同一の制度を指していることにはならない。
それぞれの国の法制度は、それぞれの国の社会事情の中で生じる不都合を解消することを意図して構築された別個の制度であり、その立法目的やその立法目的を達成するための手段・方法には様々な違いがあるからである。
そのため、それらの「諸外国」の中で「同性間の人的結合関係」を対象とした何らかの法制度が存在するとしても、それは日本国の法制度における「婚姻」と同一の制度を指していることにはならないし、そのことは日本国の法制度における「婚姻」の中に「同性間の人的結合関係」を含めることができるとする理由となるものでもない。
よって、そのことを24条1項の「婚姻」の意味を理解するための根拠とすることはできない。
「我が国でも同性婚の法制化を求める声が高まっている事実があるとしても、」との記載がある。
まず、「同性婚」との文言があるが、そこでいう「婚」の意味である「婚姻」とは何かが問題となる。
「婚姻」は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度である。
そして、「同性間の人的結合関係」については、その間で「生殖」を想定することができないことから、「生殖と子の養育」の趣旨を満たすとはいえず、「婚姻」とすることはできない。
よって、「同性婚の法制化」とあるが、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることはできないという点で、「法制化」することはできないものである。
「声が高まっている事実がある」との部分であるが、上記のように「婚姻」とすることができないものについて「声が高まっている」ということになる。
これは、「独り者婚」に対する「声が高まっている」としても、「独り者」を「婚姻」とすることはできないことに変わりはないことと同様の状態といえる。
また、24条1項が「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを「要請」しているか否かについての法解釈を論じる文脈の中で、「声が高まっている事実がある」か否かを取り上げていることから、これはあたかも国民の賛成意見と反対意見の数によって24条1項の「婚姻」の意味が変わるかのような前提で論じるものとなっている。
しかし、ここでは法解釈が問われているのであるから、法の中に規範を見出さなければならないものであり、その法の条文に記された文言の意味そのものを国民の賛成意見が多いか反対意見が多いかという漠然としたその時々の国民意識に委ねることによって結論を導き出すことができるかのように論じていることは誤りである。
「依然として婚姻制度と自然生殖の可能性が完全に切り離されたと見るのは困難である。」との記載がある。
ここでは「依然として」との文言があることから、時が進めば「婚姻制度」と「自然生殖の可能性」が「完全に切り離された」状態となることもあり得るように論じるものとなっている。
しかし、物事の起こりを検討すれば、「婚姻制度」が先にあって、そこに後から「自然生殖の可能性」が結び付けられているわけではなく、「自然生殖」という営みが先にあって、そこに着目した枠組みとして「婚姻制度」が定められているものである。
そのことから、本来的に「婚姻制度」である以上は「自然生殖の可能性」を切り離して考えることはできないものである。
人間が「自然生殖」を行うことによって子孫を産む生き物であり、その活動によって生じる社会的な不都合を解消しようとする目的が存在している限りは、それを解決するための枠組みを定めることとなる。
そして、その枠組みのことを「婚姻」と呼んでいるのであり、この経緯を切り離した意味で「婚姻」という言葉を用いることはできない。
そのため、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消しようとする目的があり、その目的を達成するための手段として「婚姻」という枠組みが設けられているにもかかわらず、そこで使われている「婚姻」という言葉だけを刈り取って、その言葉が形成されている経緯から切り離して別の意味として用いることが可能となるわけではない。
よって、「完全に切り離された」のように、「婚姻制度」と「自然生殖の可能性」が「完全に切り離された」状態となることもあり得るかのような論じ方をしている部分は誤りである。
カ また、報道機関等が国民に対して行ったいくつかの意識調査結果によれば、同性婚を法的に認めることの可否について、平成30年以降は、賛成派が概ね過半数を超えてきているものの、依然として反対派も2割ないし3割程度を占めており(認定事実⑹ア )、なお、少なくない国民が反対の意見を有していることがうかがわれる。そして、この割合は、過去において医学心理学の専門家の知見として同性愛が精神病的なものであるとされていた時期が相当期間あり(認定事実⑴イ 、同ウ )、その後、これが改められた後にも(認定事実⑴イ 、同ウ )、なお国民の間でそのような認識が一定程度残り、上記意見形成に影響を及ぼしている可能性はあるものの、そればかりとは限らず、婚姻の重要な要素として、男女が共同生活を送りながら、子を産み育て、次世代へ承継していく営みがあると理解する伝統的な家族観に根差した結果が反映されているとも推察され、反対派が一定数を占めることは無視し得ない事実である。
【筆者】
「報道機関等が国民に対して行ったいくつかの意識調査結果によれば、同性婚を法的に認めることの可否について、平成30年以降は、賛成派が概ね過半数を超えてきているものの、依然として反対派も2割ないし3割程度を占めており(… )、なお、少なくない国民が反対の意見を有していることがうかがわれる。」(カッコ内省略)との記載がある。
ここで「同性婚」との文言があるが、この「婚」の意味である「婚姻」とは何かが問題となる。
「婚姻」は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度である。
「同性間の人的結合関係」については、その間で「生殖」を想定することができず、「生殖と子の養育」の趣旨を満たすとはいえないことから「婚姻」とすることはできない。
よって、ここで使われている「同性婚」という文言は、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることができないという点で法律論としては成り立たない。
また、ここでは「同性婚を法的に認めることの可否」について「賛成派」と「反対派」を取り上げて論じようとしているが、それ以前に法的には「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることはできない。
「平成30年以降は、賛成派が概ね過半数を超えてきているものの、依然として反対派も2割ないし3割程度を占めており(… )、なお、少なくない国民が反対の意見を有していることがうかがわれる。」との部分について検討する。
これは24条1項が「同性間の人的結合関係」を「婚姻」をすることを「要請」しているか否かについての法解釈が問われている文脈の中で、「賛成派」と「反対派」の意見を取り上げるものとなっている。
しかし、法の解釈を行う際には、法の中に規範を見出さなければならないのであり、規範の意味そのものを国民の賛成・反対の意見の数に委ねることはできない。
そのため、このような、あたかも国民の「賛成派」と「反対派」の数によって24条1項の「婚姻」の意味が変わるかのような前提を含む形で論じていることは誤りである。
「この割合は、過去において医学心理学の専門家の知見として同性愛が精神病的なものであるとされていた時期が相当期間あり(… )、その後、これが改められた後にも(… )、なお国民の間でそのような認識が一定程度残り、上記意見形成に影響を及ぼしている可能性はあるものの、」(カッコ内省略)との記載がある。
まず、婚姻制度は「性愛」の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いを行う制度ではないし、「性愛」に基づいて制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもない。
そのため、婚姻制度が「男女二人一組」の枠組みを定めているとしても、そのことは「異性愛」の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的とした制度であるということを意味しない。
もし「性愛」という特定の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的として何らかの制度を立法した場合には、20条1項後段・3項、89条の「政教分離原則」に抵触して違憲となるし、法制度を利用する者の内心に干渉するものとなるから、19条の「思想良心の自由」、20条1項前段の「信教の自由」に抵触して違憲となるし、国が保護する「性愛」と、保護しない「性愛」、あるいは、「性愛」以外の思想、信条、信仰、感情の間で差異を設けることになることから、14条の「平等原則」に抵触して違憲となる。
よって、ここでは「同性愛」を取り上げるのであるが、そもそも婚姻制度の立法目的に「性愛」の思想、信条、信仰、感情を保護することは含まれていないことから、このような事柄について取り上げて論じることそのものが適切ではない。
「そればかりとは限らず、婚姻の重要な要素として、男女が共同生活を送りながら、子を産み育て、次世代へ承継していく営みがあると理解する伝統的な家族観に根差した結果が反映されているとも推察され、反対派が一定数を占めることは無視し得ない事実である。」との記載がある。
ここでは「同性婚を法的に認めることの可否について、」の「反対派が一定数を占めること」の理由を述べようとするものとなっている。
ただ、この「⑵ 憲法24条1項に違反するかについて」の項目で問われているのは、憲法24条1項が「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを「要請」しているか否かであり、憲法上の条文の意味を問うものであるから、この条文の意味そのものを国民の意識調査の「賛成派」と「反対派」の数を考慮して決めようとする試みそのものが妥当でない。
よって、「賛成派」や「反対派」の意見を取り上げて、それを理由として24条1項の規範の意味を導き出そうとしていることそのものが誤りである。
次に、「婚姻の重要な要素として、男女が共同生活を送りながら、子を産み育て、次世代へ承継していく営みがある」との部分であるが、それだけではなぜ「婚姻」の枠組みが「男女」であるのかを十分に説明しているとは言い難い。
まず、「婚姻」は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために設けられた枠組みであり、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」という目的を有しており、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす「一人の男性」と「一人の女性」の組み合わせを法的に結び付けることによって、目的の実現を目指すものとなっている。
この枠組みが、ここでいう「男女が共同生活を送りながら、子を産み育て、次世代へ承継していく営み」という理解の前提となるものである。
これを「伝統的な家族観」と呼ぶかは別として、その理解の背景には「婚姻」という概念そのものが有している「目的」と、「その目的を達成するための手段」となる枠組みの関係が存在することは明らかである。
また、ここでいう「男女が共同生活を送りながら、子を産み育て、次世代へ承継していく営みがあると理解する伝統的な家族観」と称している理解からすれば、「同性間の人的結合関係」については、その間で「生殖」を想定することができないことから「生殖と子の養育」の趣旨を満たすとはいえず、「婚姻」とすることはできない。
よって、ここでいう「伝統的な家族観」と称している立場については、「賛成派」と「反対派」における「反対派」というよりも、「可能」と「不可能」における「不可能」にあたるものであり、これを「可能」であることを前提とした上での「反対派」であるかのようにカウントしていることは妥当ではない。
◇ 可能 (⇒ 賛成 or 反対 へ)
◇ 不可能 (⇒ 賛否を問う前提にない。)
法解釈を行う際には、「賛成派」と「反対派」を持ち出すことそのものが妥当でないため、このような論じ方をしていることそのものを正当化することはできない。
しかし、それとは別に、別の場面で何らかの統計を示す際には、「賛成」と「反対」の意見を集約するよりも以前の段階として「可能」と「不可能」の次元があり、その「不可能」という考え方を持つ者を、「可能」な場合における「反対派」であるかのように位置づけて論じようとすることは誤りであることに注意が必要である。
キ 次に、法律により具体化された現行の法律婚制度の規律内容を見ると、民法は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずるとし(同法739条1項)、婚姻の効力等に関し、氏の統一(同法750条)、同居、協力及び扶助の義務(同法752条)等を、夫婦の財産に関し、婚姻費用の分担(同法760条)、夫婦共有財産の推定(同法762条2項)等を、婚姻の解消に関して財産分与(同法768条)や裁判離婚の要件(同法770条)等の離婚制度を規定するほか、親子関係に関し、夫婦の子についての嫡出の推定(同法772条1項)、親権に関する規定(同法818条3項)、配偶者のある者の未成年者養子(同法795条)、特別養子における養親の夫婦共同縁組(同法817条の3)等を置き、親族に関し、三親等内の姻族を親族とし(同法725条3号)、三親等内の親族間の相対的扶養義務(同法877条2項)等を定め、相続に関し、配偶者の相続権(同法890条)、配偶者の法定相続分(同法900条)、配偶者居住権(同法1028条)、配偶者短期居住権(同法1037条)、遺留分(同法1042条)等を規定するなど、身分関係の創設、解消に関する規律を定め、婚姻に伴う様々な権利義務を発生させている。戸籍法は、婚姻の届出があったときに、夫婦について新戸籍を編製し(同法16条)、子又は養子は父母又は養親の戸籍に入り(同法18条)、戸籍に、夫婦については、夫又は妻である旨が(13条6号)、子については、実父母又は養親の氏名及び実父母又は養親との続柄が記載され(同条4号、5号)、戸籍の正本副本が、市役所、法務局等に保管され(同法8条)、戸籍謄抄本又は記載事項証明書の交付請求の手続(同法10条以下)が規定されており、身分関係を公証している。婚姻の効果には、民法が規定する上記の効果以外にも、税や社会保障等にかかわる制度など様々な社会政策的判断に基づき付与された効果が多数存在する。
【筆者】
「次に、法律により具体化された現行の法律婚制度の規律内容を見ると、」との記載があるが、24条1項の解釈を行う場面で根拠としてはならないものであり、これを持ち出していること自体が妥当でない。
まず、この「⑵ 憲法24条1項に違反するかについて」の項目で問われているのは、24条1項が「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを「要請」しているか否かである。
24条1項が「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを「要請」していれば違憲となり、「要請」していなければ合憲となる。
この24条1項が「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを「要請」しているか否かの結論を導き出すためには、憲法上の規定である24条1項の条文そのものの意味を解き明かすことによって規範を見出すことが必要となるのであり、憲法より下位の法令である「法律」を根拠としてその憲法24条1項の意味を明らかにすることはできない。
これは、法秩序は階層構造を有しており、何らかの条文の意味を解釈する際には、その条文よりも上位の法規範を辿ることによってその条文の意味を明らかにすることは可能であるが、その条文よりも下位の法規範を根拠として上位法にあたるその条文の意味を明らかにすることはできないからである。
それにもかかわらず、ここでは24条1項が「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを「要請」しているか否かを検討する際に、「法律により具体化された現行の法律婚制度の規律内容」という下位法を持ち出し、その上位法にあたる24条1項の意味の範囲を読み取ろうとするものとなっているのである。
これは、法秩序が階層構造を有していることを理解しないものであり、解釈の過程を誤っている。
よって、このような下位法である法律を根拠として、24条1項が「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを「要請」しているか否かを論じようとしている内容は正当化することができない。
この段落は、民法や戸籍法上の条文番号を具体的に列挙し、24条1項の解釈を検討しようとするものとなっている。
国(行政府)の主張の中でも、同様に民法や戸籍法の条文番号を具体的に列挙して説明している部分があるが、これは憲法24条を解釈するための根拠として持ち出されているものではない。
【名古屋・第12回】被告第5準備書面 令和4年5月31日 PDF (P29~31)
【東京一次・第1回】控訴答弁書 令和5年6月23日 PDF (P49~51)
そのため、このような形で下位法である民法や戸籍法の条文番号を具体的に列挙して、上位法である憲法24条1項の意味を明らかにしようとする試みは、この判決を書いた裁判体が独自に行おうとしているものということになる。
しかし、このような説明は、法秩序が階層構造を有しており、下位の法令を根拠として上位の法令の意味を確定することはできないという法学に対する初歩的な理解を欠くものとなっており、誤った手法である。
よって、このような下位法を持ち出してその上位法にあたる憲法24条1項の意味を理解しようと試み、その下位法を根拠として憲法24条1項が「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを「要請」しているか否かを検討していることは誤りとなる。
この段落の最初の「法律により具体化された現行の法律婚制度」の表現であるが、「法律婚制度」自体が「法律により具体化された」制度を指しているのであり、それに対して「法律により具体化された」の文言を加えることは同義反復となるため不要である。
このような表現は読み手を混乱さる原因となるため改めていくことが望ましいと言える。
これらの規定の中には、嫡出推定の規定(民法772条)が存し、同法は、嫡出否認のための手段を限定し(同法775条)、出訴期間を限定するほか(同法777条)、再婚禁止期間を設けるなどして(同法733条)、婚姻関係にある男女間に出生した子と父の関係について早期確定を図る制度を設け、男女間の婚姻関係を中核とする家族生活の安定を図っている。これらの規定の存在を考慮すると、民法は、法律婚制度の構築に当たり、子孫の生殖を伴う男女の結合関係とそれを中核とする家族関係の安定化を少なくともその目的の一つとしていたと評価できる。そして、平成27年の再婚禁止期間大法廷判決による違憲との判断を受けて再婚禁止期間の規定(民法733条、746条)について改正が行われたが、その際にも嫡出推定に関する規定群の存在が前提とされていたものであり、今なおこれらの規定群が価値を失っているわけではない(なお、我が国では、旧民法以来、一貫して生殖不能は婚姻障害事由に掲げられてこなかったが、この点は、上記評価を妨げるものではないというべきである。すなわち、旧民法の起草過程の議論によれば、生殖不能が婚姻障害事由に掲げられなかったのは、生殖能力が婚姻にとって必要不可欠の条件であるとまではいえないと考えられたからにすぎず(認定事実⑵イ )、婚姻の目的に子孫の生殖という側面があること自体が否定されたわけではない。)。
【筆者】
この段落では、第一文と第二文で民法上の規定が挙げられ、第三文で「今なおこれらの規定群が価値を失っているわけではない」と述べている。
しかし、それらの民法上の規定が「今なお」「価値を失っているわけではない」としても、そのことはこの「⑵ 憲法24条1項に違反するかについて」の項目で問われている24条1項が「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを「要請」しているか否かの結論を導き出す際に根拠とはならないものである。
これは、憲法24条1項の意味を理解するためには、憲法24条1項の文言を読み解くことによって基準を導き出すことが必要となるのであり、それを憲法よりも下位の法令である法律上の規定の趣旨を根拠として論じることはできないからである。
もしそのようなことが可能となった場合には、法律を制定することによって、その上位法である憲法の意味をいかようにでも書き替えることが可能となるのであり、違憲審査を行うことそのものが不可能となるため、妥当でない。
よって、この部分で民法上の規定を持ち出して、その後に24条1項が「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを「要請」しているか否かの判断を行おうとしていることは、解釈の手続きとして不当な内容であり、誤りである。
第二文の「子孫の生殖を伴う男女の結合関係とそれを中核とする家族関係の安定化を少なくともその目的の一つとしていた」との部分には「目的」の文言がある。
ここでいう「目的」の意味は、「② 制度が機能することによって生じる結果(目的)」にあたる意味である。
ただ、これは「民法」の「法律婚制度」について述べるものであり、「民法」の「法律婚制度」の内容は憲法24条の「婚姻」と同一の趣旨を有していることが前提ではあるが、下位法である「民法」の「法律婚制度」の趣旨を検討したことを根拠として、上位法にあたる憲法24条の「婚姻」の趣旨を検討しようとすることは妥当でないということに注意が必要である。
加えて、「婚姻」の概念に含まれる人的結合関係の範囲は「① 国の立法目的」を達成するための手段として整合的な要素を満たすものに限られる形で定まっているのであり、ここで述べられている「② 制度が機能することによって生じる結果(目的)」の意味から導くことは適当でないことにも注意が必要である。
第三文のカッコ内に、「なお、我が国では、旧民法以来、一貫して生殖不能は婚姻障害事由に掲げられてこなかったが、この点は、上記評価を妨げるものではないというべきである。すなわち、旧民法の起草過程の議論によれば、生殖不能が婚姻障害事由に掲げられなかったのは、生殖能力が婚姻にとって必要不可欠の条件であるとまではいえないと考えられたからにすぎず(…)、婚姻の目的に子孫の生殖という側面があること自体が否定されたわけではない。」(カッコ内省略)との記載がある。
この文はおおよそその通りであるといえる。
補足すると、この「生殖不能が婚姻障害事由に掲げられなかったのは、生殖能力が婚姻にとって必要不可欠の条件であるとまではいえないと考えられたからにすぎず」との部分は、個々人の個別特性として「生殖不能」な者がいるとしても「婚姻」を成立させることができることをいうものである。
そのため、この文をもって「婚姻」から「生殖と子の養育」の趣旨が失われるというものではないというものである。
ただ、これについても「法律」という憲法よりも下位の法令の内容について述べているものであり、これをもって憲法24条1項の規範の意味を導き出すことができることにはならず、憲法24条1項の解釈を検討する中で論じていることそのものは誤っている。
さらに、その他の規定による婚姻の効果を見ても、同居、協力及び扶助の義務等といった基本的に当事者間で完結する権利義務関係を発生させるもののみならず、養子制度を含む親子関係の規律や親族関係の発生といった第三者の地位、権利義務関係に影響を及ぼす事項のほか、様々な社会政策的判断により付与された権利義務に関わる事項など種々の効果の発生が一体的に予定されている。そうすると、現行の法律婚制度が対象としてきた人的結合関係の範囲をそのまま拡張することは、当事者間の規律の問題にとどまらず、これにより直接影響を受ける第三者が想定されるほか、既存の異性婚を前提に構築された婚姻制度全体についても見直す契機となり得るものであり、広く社会に影響を及ぼし、現行の法律婚制度全体の枠組みにも影響を生じさせることが避けられないと考えられる。
【筆者】
「その他の規定による婚姻の効果を見ても、同居、協力及び扶助の義務等といった基本的に当事者間で完結する権利義務関係を発生させるもののみならず、養子制度を含む親子関係の規律や親族関係の発生といった第三者の地位、権利義務関係に影響を及ぼす事項のほか、様々な社会政策的判断により付与された権利義務に関わる事項など種々の効果の発生が一体的に予定されている。」との記載がある。
まず、この「⑵ 憲法24条1項に違反するかについて」の項目で問われているのは、24条1項が「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを「要請」しているか否かである。
法秩序は階層構造を有していることから、条文を解釈する際には、その条文よりも上位の法源から根拠を導き出し、その条文の意味を明らかにすることは可能であるが、下位法を根拠としてその条文の意味を明らかにすることはできない。
それにもかかわらず、ここでは「その他の規定による婚姻の効果を見ても、」のように、憲法24条に従う形で定められた法律上の規定の効果を見た上で、それを理由としてその上位法である憲法24条1項が「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを「要請」しているか否かの判断を行おうとするものとなっている。
これは、法秩序は階層構造を有しているため、下位法は上位法に違反してはならないとの法則があり、下位法を用いて上位法の意味を検討することはできないことを認識できていない点で誤りである。
「現行の法律婚制度が対象としてきた人的結合関係の範囲をそのまま拡張することは、当事者間の規律の問題にとどまらず、これにより直接影響を受ける第三者が想定されるほか、既存の異性婚を前提に構築された婚姻制度全体についても見直す契機となり得るものであり、広く社会に影響を及ぼし、現行の法律婚制度全体の枠組みにも影響を生じさせることが避けられないと考えられる。」との記載がある。
「現行の法律婚制度が対象としてきた人的結合関係の範囲をそのまま拡張することは、」との部分について検討する。
ここでは、「法律婚制度」の範囲を「同性間の人的結合関係」を含める形に「拡張すること」ができることを前提として、その当否を論じようとするものとなっている。
しかし、「婚姻」は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた枠組みであり、一般的・抽象的に自然生殖を想定することができる「男性」と「女性」の間に「貞操義務」を設けるなど一定の形式で法的に結び付けることによって、立法目的を達成することを目指すものとなっている。
また、憲法24条はその「婚姻」について「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めており、この趣旨に対応するものとなっている。
それに対して、「同性間の人的結合関係」はその間で「生殖」を想定することができず、「生殖と子の養育」の趣旨を満たすものではないし、憲法24条が「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めている趣旨にも適合しないため、「婚姻」とすることはできない。
そのため、ここでいう「現行の法律婚制度」を「同性間の人的結合関係」を含む形に「そのまま拡張すること」はできないし、もしそれを行おうとした場合には、24条の「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言に抵触して違憲となる。
よって、ここで「法律婚制度」の対象とする人的結合関係の範囲を「同性間の人的結合関係」を含む形に「拡張すること」ができることを前提に論じている部分が誤りである。
「当事者間の規律の問題にとどまらず、これにより直接影響を受ける第三者が想定されるほか、」との部分について検討する。
まず、上記で述べたように「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることはできないため、これが可能であるかのような前提の下に「影響」の問題を想定している部分は妥当でない。
「既存の異性婚を前提に構築された婚姻制度全体についても見直す契機となり得るものであり、広く社会に影響を及ぼし、現行の法律婚制度全体の枠組みにも影響を生じさせることが避けられないと考えられる。」との部分について検討する。
上記で示したように、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることはできないため、これが可能であることを前提として「広く社会に影響を及ぼ」すか否かを検討しようとしていること自体が妥当でない。
また、「現行の法律婚制度全体の枠組みにも影響を生じさせることが避けられない」と考えているようであるが、そもそも24条の下で「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とする法律を立法することはできないため、それが可能であることを前提として「影響を生じさせる」か否かを検討しようとしていること自体が妥当でないし、もしそのような「法律婚制度」を立法しようとした場合には、24条の「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言に抵触して違憲となるため、「法律婚制度」の枠組みに「影響を生じさせる」ことはできないともいえるものである。
ここでは、「現行の法律婚制度が対象としてきた人的結合関係の範囲をそのまま拡張すること」についての「影響」を論じるものとなっている。
しかし、このような論じ方自体に誤りがある。
まず、この「⑵ 憲法24条1項に違反するかについて」の項目では、24条1項が「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを「要請」しているか否かが問われている。
そして、24条1項が「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを「要請」している場合には、その制度がないことは違憲となり、「要請」していない場合には、その制度が存在しないことは合憲となる。
この24条1項が「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを「要請」しているか否かは、憲法上の規定であるこの24条1項の意味を解釈することによって導き出されるものであり、下位の法令を根拠として上位法である憲法の意味を理解するための基準としたり、意味を確定するための材料とすることはできない。
これは、法秩序は階層構造を有しており、その条文の意味を解釈する際には、その条文よりも上位の法源を辿ることによってその意味を明らかにすることは可能であるが、その条文よりも下位の法規を根拠として上位法であるその条文の意味を解き明かすことはできないからである。
憲法
↓
法律
↓
命令
法解釈(上位法と下位法) Wikipedia
それにもかかわらず、ここでは「現行の法律婚制度が対象としてきた人的結合関係の範囲をそのまま拡張すること」の「影響」を論じており、これを基にして憲法24条1項の解釈を検討しようとするものとなっていることから、「現行の法律婚制度」を「拡張する」か否かという下位法の問題を根拠として、その上位法である憲法24条1項の意味を確定しようとするものとなっている。
このような判断は、法秩序の階層構造に従うものではなく、上位法と下位法の関係を覆そうとするものであるから、解釈の方法として誤っている。
この文には「異性婚」という文言があるが、これは法律用語として通用するものではないため注意が必要である。
また、「異性婚」という言葉を用いたとしても、「婚姻」であればもともと「男性」と「女性」の間の「異性」のものしか存在しないのであり、その「婚姻」の意味に「異性」を加えることは同義反復となって妥当でないことも押さえる必要がある。
その他、同義反復となることを無視して「異性婚」という言葉を使ったとしても、それに対する形で「同性婚」というものが法的に構成できることを意味することはなく、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることができることにはならない。
このような言葉が使われている背景に潜む意図に惑わされることがないようにする必要がある。
ク そして、自然生殖の可能性が存しない同性カップルに対して、いかなる保護を付与し、制度を構築するのが相当かについては、現行の法律婚制度をそのまま開放するのが唯一の方法とは限らず、当該制度とは別に、特別の規律を設けることによることも、立法政策としてはありうるところである。
【筆者】
まず、この「⑵ 憲法24条1項に違反するかについて」の項目で問われているのは、24条1項が「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを「要請」しているか否かである。
24条1項が「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを「要請」しているのであれば違憲、「要請」していないのであれば合憲である。
そして、この24条1項は憲法上の規定であるから、その意味を読み解く際には、その憲法上の規定の文言の中から意味を明らかにすることが必要となるのであり、その意味を読み解く際に憲法よりも下位の法令を根拠として考えることはできない。
これは、法秩序は段階構造を有しており、条文の意味を解釈するためには、その条文が書かれている法令よりも上位の法令を根拠として意味を明らかにすることはできるが、その条文が書かれている法令よりも下位の法令を根拠としてその条文の意味を明らかにしようとすることはできないからである。
もしそのような形で解釈を行おうとした場合には、上位法と下位法の立ち位置が逆転するものとなるため、下位法は上位法に違反してはならないという法則が成り立たなくなり、法秩序の階層構造を損なうことになるため妥当でない。
しかし、この段落では憲法24条1項の意味を明らかにする解釈の過程であるにもかかわらず、「現行の法律婚制度をそのまま開放するのが唯一の方法とは限らず、当該制度とは別に、特別の規律を設けることによることも、立法政策としてはありうる」のように、「立法政策」という憲法の規範の枠内でのみ行うことができる下位法にあたるものを持ち出した上で、それを根拠として上位法である憲法24条1項の解釈を確定しようとするものとなっている。
これは、24条1項よりも下位の法形式である法律上の「立法政策」について「ありうる」かどうかを検討し、その検討の結果「ありうる」という結論を先に出した上で、そこから遡ってそれよりも上位の法形式である憲法24条1項の意味について「要請」していないと判断することを根拠づけようとしているのである。
これは、下位法を基にして上位法を理解しようするものであるから、法秩序の階層性を損なうものであり、憲法24条1項の意味を解釈する手順として正当化することができるものではない。
よって、このような形で説明を試みているこの段落の内容は誤りである。
「自然生殖の可能性が存しない同性カップルに対して、いかなる保護を付与し、制度を構築するのが相当かについては、」との部分について検討する。
まず、ここでいう「同性カップル」という「同性間の人的結合関係」については、24条の「婚姻」ではないし、それが「親子」や「親子」の関係を基本とした「兄弟」「姉妹」などに含まれないのであれば、24条2項の「家族」にも含まれないことから、憲法は「いかなる保護を付与」することも「制度を構築する」ことも「要請」はしていない。
よって、「いかなる保護を付与し、制度を構築するのが相当か」のように、「保護」の「付与」や「制度」の「構築」を行うことを前提として論じている部分が妥当ではない。
また、憲法が「要請」していない事柄であるにもかかわらず、「保護」の「付与」や「制度」の「構築」を行うことについて論じていることは、国会の立法裁量に関する事柄について口出ししようとするものということができるから、司法権の行使として正当化することができず、越権行為である。
また、憲法24条の「婚姻」の文言は「生殖と子の養育」に関わる制度を一元的に集約して規律する趣旨を有しており、「生殖と子の養育」に関わる制度を24条の「婚姻」を離れて別に立法することはできない。
そのため、その「同性間の人的結合関係」に関する「保護」の「付与」や「制度」の「構築」の内容が「生殖と子の養育」に関わるものとなっている場合や、影響を与える場合には、24条の「婚姻」に抵触して違憲となる。
さらに、婚姻制度が「男女二人一組」の形となっていることについては、その社会の中で「生殖」に関わって生じる不都合を解消するという目的の実現に資することから、その「婚姻している者(既婚者)」は「婚姻していない者(独身者)」との間で優遇措置が与えられることが正当化されることになるが、そのような目的を有しない「同性間の人的結合関係」に対して「保護」の「付与」や「制度」の「構築」を行うことは、その制度を利用しておらず、何らの人的結合関係も形成していない者との間で、得られる利益の内容に合理的な理由のない差異を生じさせることになるから、憲法14条の「平等原則」に抵触して違憲となる。
このことから、そもそも「同性間の人的結合関係」についての「保護」の「付与」や「制度」の「構築」を行うことについては、国会であっても立法裁量を有しているということにはならない。
よって、この意味でも「同性間の人的結合関係」についての「保護」の「付与」や「制度」の「構築」を行うことができることを前提として論じている部分は妥当ではない。
「現行の法律婚制度をそのまま開放するのが唯一の方法とは限らず、」との部分について検討する。
まず、「婚姻」は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度であり、「同性間の人的結合関係」についてはその間で「生殖」を想定することができず「生殖と子の養育」の趣旨を満たすものではないことから「婚姻」とすることはできない。
そのため、「現行の法律婚制度」を「開放」する形で「同性間の人的結合関係」を「婚姻」として扱うことはできない。
もし「同性間の人的結合関係」を「法律婚制度」として立法しようとした場合には、24条の「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言に抵触して違憲となる。
そのため、「現行の法律婚制度をそのまま開放する」「方法」が選択肢として存在するかのように、「同性間の人的結合関係」についての「法律婚制度」を立法することができることを前提として論じていることは誤りとなる。
「当該制度とは別に、特別の規律を設けることによることも、立法政策としてはありうるところである。」との部分について検討する。
まず、「当該制度」の部分であるが、上記で述べたように、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることはできないため、「当該制度」にあたる「法律婚制度」の中に「同性間の人的結合関係」を含めることはできない。
次に、「同性間の人的結合関係」に対して「特別の規律を設けること」であるが、憲法24条の「婚姻」は「生殖と子の養育」に関わる制度を一元的に集約して規律する趣旨を有しており、「生殖と子の養育」に関わる制度を24条の「婚姻」を離れて立法することはできないことから、「特別の規律」の内容が「生殖と子の養育」に関わるものとなっている場合や、影響を与える場合には、憲法24条の「婚姻」に抵触して違憲となる。
また、「婚姻」が「男女二人一組」となっていることは「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的の実現に資することから、「婚姻している者(既婚者)」が一定の優遇措置を得られることを「婚姻していない者(独身者)」との間で正当化することができるが、そのような目的からは導かれない「同性間の人的結合関係」について「特別の規律」を設けることは、その制度を利用しない者との間で合理的な理由のない差異を生じさせることになるため、14条の「平等原則」に抵触して違憲となる。
よって、ここでは「立法政策としてはありうるところである。」のように述べるのであるが、「立法政策としてはありうるところ」とはいえない。
例えば、同性婚を肯定している国においても、パートナーシップ制度等を先行させた上で、後に同性婚制度に移行又は併存させる例も存在するところであり(認定事実⑷ウ )、現在においても、イタリアでは、同性カップルに対しては婚姻制度の適用を認めず、婚姻とは別の形式による保護を図ることとして、「同性間の民事的結合に関する規則及び共同生活の規律」が定められているし(認定事実⑷イ )、同性婚を認める諸外国の中でも、異性カップルと同性カップルとの間で、嫡出推定の規定や生殖補助医療について、差異を設ける立法例(スペイン、オランダ及びフランス)が存在するほか、宗教者が同性カップルの婚姻の挙式を拒否する権利を認める立法例(デンマーク、カナダ、南アフリカ、ノルウェー等)、養子縁組を認めるために段階的経過を経た立法例(オランダ、ベルギー、ポルトガル)も存在する(認定事実⑷ウ )。婚姻制度の内容は自国の伝統や宗教的背景等によって左右され得るものであり、諸外国の立法例が直ちに我が国の婚姻制度に妥当するわけではないが、諸外国ごとに多様な立法措置が講じられていることは、同性カップルに現行の法律婚制度をそのまま開放することが、唯一の保護形態であるというわけではないことを裏付けるものというべきである。
【筆者】
第一文は長文であるが、下記のようにまとめることができる。
◇ 「同性婚を肯定している国においても、パートナーシップ制度等を先行させた上で、後に同性婚制度に移行又は併存させる例も存在する」
◇ 「同性婚を認める諸外国の中でも、」
・「異性カップルと同性カップルとの間で、嫡出推定の規定や生殖補助医療について、差異を設ける立法例(スペイン、オランダ及びフランス)が存在する」
・「養子縁組を認めるために段階的経過を経た立法例(オランダ、ベルギー、ポルトガル)も存在する」
・「宗教者が同性カップルの婚姻の挙式を拒否する権利を認める立法例(デンマーク、カナダ、南アフリカ、ノルウェー等)」
◇ 「イタリアでは、同性カップルに対しては婚姻制度の適用を認めず、婚姻とは別の形式による保護を図ることとして、「同性間の民事的結合に関する規則及び共同生活の規律」が定められている」
まず、これら諸外国における「同性間の人的結合関係」についての法制度は、それぞれの国の社会事情の中で課題となる問題を解決することを意図して、それぞれの国の中で構築されたものであり、その立法目的やその立法目的を達成するための手段・方法は様々である。
そのため、これらの諸外国の法制度について、外国語を翻訳する者が何らかの類似性を見て「婚姻」という言葉を充てて説明しているとしても、それらは同一の制度のことを指していることにはならないし、当然、日本国の法制度における「婚姻」と同一の制度を指していることにはならない。
そのため、それぞれの国の法制度を「婚姻」という言葉を用いて統一的に理解することが可能なわけではない。
よって、諸外国のこれらの法制度が日本国の法制度における「婚姻」に対して影響を与えることはないし、これらの法制度は日本国の法制度における「婚姻」の中に「同性間の人的結合関係」を含めることができるとする理由になるものでもない。
その他、ここでは「同性間の人的結合関係」について法制度を定めている国のみを取り上げるのであるが、古くから「一夫多妻制」を採用している国々も存在しているのであり、それらを一切取り上げることなく、日本国の法制度との間で比較をしようとしている部分は、裁判官が特定の結論を導き出すために恣意的に視野を狭めようとするものとなっており、妥当でない。
この文の中では「カップル」という「二人一組」を示す言葉も使われているが、人的結合関係には「三人以上の組み合わせ」も存在するのであり、それを「二人一組」のみを検討すればそれで足りるかのような前提で論じている部分も妥当でない。
このような論じ方は、なぜ「二人一組」なのかその根拠を説明しないままに論じる「カップル信仰論」に陥っているものである。
「パートナーシップ制度等」や「婚姻とは別の形式による保護」の部分について検討する。
まず、日本国の法制度における「婚姻」は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度である。
そして、憲法24条の「婚姻」は「生殖と子の養育」に関わる制度を一元的に集約して規律する趣旨を有しており、「生殖と子の養育」に関わる制度をこの憲法24条の「婚姻」を離れて別の制度として立法することはできない。
もし24条の「婚姻」を離れて別の制度として「生殖と子の養育」に関わる制度を立法しようとした場合には、憲法24条の「婚姻」に抵触して違憲となる。
そのことから、ここでいう「パートナーシップ制度等」や「婚姻とは別の形式による保護」というものが、「生殖と子の養育」に関わる制度となっている場合や、影響を与える場合には、憲法24条の「婚姻」に抵触して違憲となる。
また、婚姻制度が「男女二人一組」に対して法的効果や一定の優遇措置を設けていることについては、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成するための手段として整合的な要素を満たすものであることから、「婚姻していない者(独身者)」との間での差異を正当化することができるが、「同性間の人的結合関係」についての「パートナーシップ制度等」や「婚姻とは別の形式による保護」というものは、そのような目的を有していないことから、何らの制度も利用していない者との間での差異を正当化することはできず、14条の「平等原則」に抵触して違憲となる。
よって、諸外国で「パートナーシップ制度等」や「婚姻とは別の形式による保護」を設けている場合があるとしても、そのことは日本国の法制度としてそのような制度を設けることができることを意味しないことを押さえることが必要である。
「婚姻制度の内容は自国の伝統や宗教的背景等によって左右され得るものであり、諸外国の立法例が直ちに我が国の婚姻制度に妥当するわけではないが、諸外国ごとに多様な立法措置が講じられていることは、同性カップルに現行の法律婚制度をそのまま開放することが、唯一の保護形態であるというわけではないことを裏付けるものというべきである。」との記載がある。
「婚姻制度の内容は自国の伝統や宗教的背景等によって左右され得るものであり、」との部分であるが、ここでいう「婚姻制度」と述べているものは、「諸外国」の中でその国の社会事情の中で生じている問題を解決することを目的として立法された別個の制度について、翻訳者が「婚姻制度」という言葉を使って翻訳しているだけものであり、それぞれの国の間で同一の制度のことを指していることにはならないものである。
よって、何らかの法制度が「自国の伝統や宗教的背景等」によって立法されていることは確かであるが、それらの国々の別個の法制度を「婚姻制度」という言葉によって同一の制度として把握することは必ずしも適切ではないことに注意が必要である。
「諸外国の立法例が直ちに我が国の婚姻制度に妥当するわけではないが、」との部分はその通りである。
「諸外国」と「我が国」では社会事情が異なっており、そこで生じている課題が異なるため、立法目的やその立法目的を解決するための手段・方法には様々な違いがあるからである。
また、日本国の法制度における「婚姻」という概念と、「諸外国」の法制度の内容(翻訳者が『婚姻』という言葉を充てて説明することのあるもの)との間では、使われている概念の意味もそれぞれ異なるという点も押さえる必要がある。
「諸外国ごとに多様な立法措置が講じられていることは、同性カップルに現行の法律婚制度をそのまま開放することが、唯一の保護形態であるというわけではないことを裏付けるものというべきである。」との部分であるが、「諸外国」で「同性カップル」という「同性間の人的結合関係」についての「立法措置」があるとしても、それを理由として日本国の法制度において「同性間の人的結合関係」に対する「立法措置」を行うことができることにはならない。
まず、「婚姻」は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するため「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度である。
そして、憲法24条の 「婚姻」の文言は、「生殖と子の養育」に関わる制度を一元的に集約して規律する趣旨を有しており、24条の「婚姻」を離れて別の制度として「生殖と子の養育」に関わる制度を立法することはできない。
そのため、「同性間の人的結合関係」についての「立法措置」を行うことは、「生殖と子の養育」に関わる制度となる場合や、それに影響を与えるものとなることが考えられることから、24条の「婚姻」に抵触して違憲となる。
次に、「婚姻」が「男女二人一組」を対象としていることは、一般的・抽象的にその間で自然生殖を想定することができる関係であることから、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的の実現に資するものである。
そのため、「婚姻している者(既婚者)」に対して一定の優遇措置が設けられていることは、「婚姻していない者(独身者)」との間で合理的な理由を説明することが可能である。
しかし、このような目的を有しない「同性間の人的結合関係」に対して優遇措置を設けることは、何らの制度も利用していない者との間で合理的な理由を説明することができない差異を生じさせることになることから、14条の「平等原則」に抵触して違憲となる。
よって、ここでは「諸外国」で「同性間の人的結合関係」についての「多様な立法措置が講じられていること」を持ち出すのであるが、日本国でそのような「立法措置」を行おうとした場合には、憲法に違反することになると考えられるため、このような「立法措置」が可能であることを前提として論じている部分は妥当でない。
「同性カップルに現行の法律婚制度をそのまま開放することが、唯一の保護形態であるというわけではないことを裏付けるものというべきである。」との部分について検討する。
まず、この「⑵ 憲法24条1項に違反するかについて」の項目で問われているのは、24条1項が「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを「要請」しているか否かである。
そして、この憲法24条1項を解釈するためには、憲法24条1項の条文の文言の中から意味を明らかにする必要があり、その憲法よりも下位の法令を持ち出して、その上位の法令にあたる憲法の条文の意味を明らかにすることはできない。
もしそのようなことができることになれば、下位法は上位法に違反してはならないとする法秩序の階層構造を保つための解釈の手続きを行うことが不可能となるため、上位法に違反するという下位法の問題点をその上位法を用いて是正することができなくなるのであり、妥当でない。
それにもかかわらず、ここでは「現行の法律婚制度をそのまま開放すること」や他の「保護形態」というように、憲法よりも下位の法令による立法政策に関する事柄を持ち出して、それを根拠として上位法である憲法24条1項の意味を明らかにしようと試みるものとなっている。
しかし、このような手続きは、上位法と下位法の関係性を逆転させるものであり、法秩序の階層構造を損なうものであるため、法解釈の手続きとして正当化することのできるものではない。
よって、憲法24条1項の解釈を行おうとしている説明の中で、憲法よりも下位の法令を持ち出している部分は、解釈の手続きとして誤っている。
ケ 確かに、同性間に対して現行の法律婚制度を及ぼすことが、憲法24条1項の趣旨に照らして禁止されているとはいえないし、国民の意識が同性婚を肯定する方向に変化しつつあるということはできる。
【筆者】
「同性間に対して現行の法律婚制度を及ぼすことが、憲法24条1項の趣旨に照らして禁止されているとはいえない」との記載がある。
この論点については、上記「⑵ウ」のところで解説している。
上記「⑵ウ」のところでは「禁止されていた」と過去形となっており、ここでは「禁止されている」と現在形となっているが、これによって解説した内容が変わるものではない。
よって、「同性間に対して現行の法律婚制度を及ぼすことが、憲法24条1項の趣旨に照らして禁止されているとはいえない」と述べて、あたかも「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることが可能であるかのように論じることは誤りとなる。
また、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることはできないことから、「婚姻」について定めている24条1項は「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを「要請」するものではない。
「国民の意識が同性婚を肯定する方向に変化しつつあるということはできる。」との部分について検討する。
「同性婚」との文言があるが、「婚姻」とは「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度であり、「同性間」についてはその間で「生殖」を想定することができず、「生殖と子の養育」の趣旨を満たすものではないため「婚姻」とすることはできない。
よって、「国民の意識が同性婚を肯定する方向に変化しつつある」と述べたとしても、そもそも「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることはできない。
また、ここで「国民の意識」を挙げているが、このような論じ方をするのであれば、調査の結果「国民の意識」が「否定する方向に変化」した場合には、また別の結論が導き出されることを前提とするものである。
そのため、このような形で法規範がどのような意味を有しているのかを「国民の意識」を基にして読み解こうとすることは、誤りである。
この「ケ」の第一段落は、「ウ」の第一段落の問いに対して応答する「ウ」の第二段落、第三段落を短くまとめて繰り返しているものに過ぎない。
ここで改めて繰り返す必要はなく、文の流れとしてはこれをカットしてそのまま次の段落の最後の結論に移る方が分かりやすい。
しかしながら、前記オないしキで詳述したところによれば、婚姻制度は伝統的には男女の結合関係を前提としてきたものであり、婚姻制度の趣旨に対する理解において、依然として、自然生殖の可能性と完全に切り離されたとはいえない状況にある(前記オ)。そして、伝統的な制度及び価値観を重視する立場の国民も一定の割合を占めている中で(前記カ)、法律により具体化された現行の法律婚制度の対象をそのまま拡大させることにより、婚姻当事者以外の者や既存の婚姻制度の適用対象者に影響が生じ得るにもかかわらず(前記キ)、同性カップルを保護するために現行の法律婚制度以外の方法を選択するという可能性を排除して、憲法が一義的に、同性間に対しても現行の法律婚制度を及ぼすことを要請するに至ったとは解し難いといわざるを得ない。
【筆者】
「婚姻制度は伝統的には男女の結合関係を前提としてきたものであり、婚姻制度の趣旨に対する理解において、依然として、自然生殖の可能性と完全に切り離されたとはいえない状況にある(…)。」(カッコ内省略)との記載がある。
「婚姻制度は伝統的には男女の結合関係を前提としてきたものであり、」との部分について検討する。
「婚姻制度」が「男女の結合関係」を前提としていることは、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」を目的として、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす「一人の男性」と「一人の女性」の組み合わせに対して「貞操義務」を設けるなど一定の形式で法的に結び付けるものとなっていることが理由である。
このため、「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度となっている。
そのことを「伝統的」と呼ぶかは別としても、「婚姻制度」の背景には立法目的とその立法目的を達成するための手段となる枠組みが存在していることを押さえる必要がある。
「婚姻制度の趣旨に対する理解において、依然として、自然生殖の可能性と完全に切り離されたとはいえない状況にある」との部分について検討する。
ここでは「依然として、」と述べていることから、時が経てば「婚姻制度の趣旨」から「自然生殖の可能性」が「完全に切り離された」状況になることもあり得ることを前提とするものとなっている。
しかし、物事の起こりの順序を見れば、「婚姻制度」に「自然生殖の可能性」が結び付いているというよりも、人間の「自然生殖」という営みが先にあって、そこに着目した枠組みとして「婚姻制度」を定めることになるものである。
そのことから、本来的に「婚姻制度」である以上は「自然生殖の可能性」を切り離して考えることはできないものである。
人間が「自然生殖」を行うことによって子孫を産む生き物であり、その活動によって生じる社会的な不都合を解消しようとする目的が存在している限りは、それを解決するための枠組みを定めることとなる。
その枠組みのことを「婚姻」と呼んでいることから、この経緯を切り離した意味で「婚姻」という言葉を用いることはできない。
そのため、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消しようとする目的があり、その目的を達成するための手段として「婚姻」という枠組みが設けられているにもかかわらず、そこで使われている「婚姻」という言葉だけを刈り取って、その言葉が形成されている経緯から切り離して別の意味として用いることができるというものではない。
よって、ここで「依然として、」のように、「婚姻制度の趣旨」と「自然生殖の可能性」が「完全に切り離された」状況となることがあり得るかのような前提で論じている部分は誤りである。
「伝統的な制度及び価値観を重視する立場の国民も一定の割合を占めている中で(…)、法律により具体化された現行の法律婚制度の対象をそのまま拡大させることにより、婚姻当事者以外の者や既存の婚姻制度の適用対象者に影響が生じ得るにもかかわらず(…)、同性カップルを保護するために現行の法律婚制度以外の方法を選択するという可能性を排除して、憲法が一義的に、同性間に対しても現行の法律婚制度を及ぼすことを要請するに至ったとは解し難いといわざるを得ない。」(カッコ内省略)との記載がある。
この文は、最後の部分で「憲法が一義的に、同性間に対しても現行の法律婚制度を及ぼすことを要請するに至ったとは解し難いといわざるを得ない。」と述べている。
このことから、この一文のその前の部分は、憲法24条1項が「同性間」の人的結合関係に対して「法律婚制度」を立法することを「要請」しているか否かを検討するものということになる。
そして、その結論は「要請するに至ったとは解し難い」ということであるから、憲法24条1項は「同性間」の人的結合関係に対して「法律婚制度」を立法することを「要請」していないというものである。
この一文がその結論を導き出すための判断で考慮した内容は、下記の通りである。
◇ 「伝統的な制度及び価値観を重視する立場の国民も一定の割合を占めている」
◇ 「法律により具体化された現行の法律婚制度の対象をそのまま拡大させることにより、婚姻当事者以外の者や既存の婚姻制度の適用対象者に影響が生じ得る」
◇ 「同性カップルを保護するために現行の法律婚制度以外の方法を選択するという可能性」
しかし、これらは憲法24条1項を解釈する際に考慮することのできるものではなく、解釈の過程で検討することは妥当でない。
まず、「伝統的な制度及び価値観を重視する立場の国民も一定の割合を占めている」の部分であるが、「国民」の「立場」の「割合」を述べるものとなっていることから、「国民」の賛成意見や反対意見の数によって、憲法24条1項の意味が揺れ動くものであるかのように論じていることになる。
しかし、法解釈は法の条文の中に規範を見出さなければならないのであり、国民のその時々の賛成・反対の意見の「割合」によって左右されるということはない。
このような解釈を許してしまうことになれば、法の支配、立憲主義、法治主義の精神に反することになるため、このことを根拠として憲法24条1項の意味を確定しようとする試みは正当化することはできず、誤りである。
次に、「法律により具体化された現行の法律婚制度の対象をそのまま拡大させることにより、婚姻当事者以外の者や既存の婚姻制度の適用対象者に影響が生じ得る」の部分について検討する。
「婚姻」は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度であり、「同性間の人的結合関係」はその間で「生殖」を想定することができず、「生殖と子の養育」の趣旨を満たすものではないため、「婚姻」とすることはできない。
そのため、「同性間の人的結合関係」に対して「法律により具体化された現行の法律婚制度の対象をそのまま拡大させること」は、そもそもできない。
もし「同性間の人的結合関係」に対して「法律により具体化された現行の法律婚制度の対象をそのまま拡大させること」を行おうとした場合には、24条の「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言に抵触して違憲となる。
そのことから、「同性間の人的結合関係」に対して「法律により具体化された現行の法律婚制度の対象をそのまま拡大させること」が可能であることを前提として、その「影響」を論じようとしている部分は誤りとなる。
「婚姻当事者以外の者や既存の婚姻制度の適用対象者に影響が生じ得る」との部分についても、そもそも「同性間の人的結合関係」に対して「法律により具体化された現行の法律婚制度の対象をそのまま拡大させること」はできないことから、この部分の検討を行うことができることを前提としている部分も誤りとなる。
さらに、この「⑵ 憲法24条1項に違反するかについて」で問われている内容は憲法24条1項が「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを「要請」しているか否かであり、それは憲法上の規定を読み解くことによって規範を明らかにしなければならないものである。
それにもかかわらず、ここでは「法律婚制度」という憲法よりも下位の法令を持ち出して、その法令を変更した場合の「影響」という立法政策に関することを検討した上で、上位法にあたる憲法24条1項の意味を明らかにしようとするものとなっている。
これは、下位法に基づいて上位法の意味を明らかにしようと試みるものであり、法秩序の階層性を理解しないものであるから、解釈の手続きとして正当化することができない。
よって、このような事柄を持ち出して憲法24条1項が「要請」しているか否かを論じようとしていることは誤りとなる。
「同性カップルを保護するために現行の法律婚制度以外の方法を選択するという可能性」との部分について検討する。
ここでいう「同性カップル」という「同性間の人的結合関係」を「保護するため」の「方法」や「可能性」であるが、憲法24条の「婚姻」は「生殖と子の養育」に関わる制度を一元的に集約して規律する趣旨を有しており、24条の「婚姻」を離れて別の制度として「生殖と子の養育」に関わる制度を立法することはできない。
よって、「同性間の人的結合関係」を「保護」する制度が「生殖と子の養育」に関わる制度となっている場合や、影響を与えることが考えられる制度となっている場合には、24条の「婚姻」に抵触して違憲となる。
また、婚姻制度の場合は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的により、「婚姻している者(既婚者)」が一定の優遇措置を得ることができることについて、「婚姻していない者(独身者)」との間で生じる差異を正当化することが可能であるが、そのような目的を有しない「同性間の人的結合関係」を「保護するため」の制度というものは、その制度を利用していない者との間で合理的な理由を説明することのできない差異を生じさせるものとなることから、14条の「平等原則」に抵触して違憲となる。
そのため、ここでは「同性カップル」という「同性間の人的結合関係」を「保護するため」の「方法」や「可能性」があり得るかのような前提で述べている部分は、この点を考慮しないものであり妥当でない。
その他、「現行の法律婚制度以外の方法を選択するという可能性」という憲法よりも下位の法令による立法政策を根拠として、その上位の法令である憲法24条1項の規範の意味を明らかにしようと試みていることは、上位法と下位法の立場を逆転させるものであり、法秩序の階層性を損なわせるものであるから、解釈の手続きとして誤っている。
よって、そのような下位法にあたる立法政策を持ち出して論じていることそのものが妥当でない。
「憲法が一義的に、同性間に対しても現行の法律婚制度を及ぼすことを要請するに至ったとは解し難いといわざるを得ない。」との部分について検討する。
まず、「婚姻」は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた枠組みである。
「同性間」の人的結合関係については、その間で「生殖」を想定することができないことから、「生殖と子の養育」の趣旨を満たすとはいえず、「婚姻」とすることはできない。
また、憲法24条は「婚姻」を定めており、「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言も、この「生殖と子の養育」の趣旨を満たすものとして定められているものである。
このことから、憲法24条は「同性間に対して」「現行の法律婚制度を及ぼすこと」を想定していない。
また、もし「同性間に対して」「現行の法律婚制度を及ぼすこと」を行おうとした場合には、憲法24条の「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言に抵触して違憲となる。
そのため、当然、憲法24条は「同性間に対して」「現行の法律婚制度を及ぼすこと」を「要請」するものではない。
もう一つ、ここでは「至ったとは」のように、時の経過によって「同性間に対して」「現行の法律婚制度を及ぼすこと」が「要請」される場合があり得ることを前提としているように見受けられる。
しかし、上記のように「婚姻」という概念であることそのものによって、もともと「同性間」の人的結合関係を含めることはできないため、時の経過を理由として「要請」される状態に「至」ることはない。
この「ケ」の項目は、「ウ」の第一段落で述べられている問いから始まって「ウ→エ→オ→カ→キ→ク→ケ」の流れに沿ってたどり着いた結論にあたるものである。
◇ 判断の「前提」
↓
◇ 判断の「過程」
↓
◇ 判断の「結論」
ただ、この「ケ」の第一段落は「ウ」の第一段落と第二段落の繰り返しであるし、この「ケ」の第二段落の「前記オないしキで詳述したところ」として挙げている(前記オ)(前記カ)(前記キ)についてもその部分を繰り返すものであるから、いずれも不要である。
この結論を述べる前に以前に述べた話を改めて繰り返していることは、「判断の前提」→「判断の過程」→「判断の結論」のような流れをストップさせ、「判断の前提」→「判断の過程」→「(判断の前提→判断の過程→)判断の結論」のように読み手を混乱させる原因となっている。
◇ 判断の「前提」
↓
◇ 判断の「過程」
↓
◇ 判断の「(前提)→(過程)→結論」
これを改善するためには、「ウ→エ→オ→カ→キ→ク」の順を追った後には、そのまま「ケ」の第二段落の最後の「憲法」が「要請」しているか否かの話に移ればよかったのである。
コ なお、原告らは、同性間の結合関係を保護するために、現行の法律婚制度とは別に、特別の規律を設けることは、同性カップルと異性カップルとを差別するものであるから、憲法24条1項は、そのような保護態様を予定していない旨主張する。
【筆者】
この文は読み取りづらいが、並べ替えて整理すると、「憲法24条1項は、」「現行の法律婚制度とは別に、」「同性間の結合関係を保護するため」の「特別の規律を設ける」という「保護態様を予定していない」との意味である。
これについては、その通りである。
ただ、その理由として「同性カップルと異性カップルとを差別するものであるから、」と考えているようであるが、この点については妥当でない。
まず、「憲法24条1項」は「婚姻」を定めており、その内容は法律によって具体化されることを予定しているが、この「婚姻」以外の制度については何ら述べていない。
そのため、「憲法24条1項」は、「法律婚制度」以外の、ここでいう「特別の規律」という「保護態様」を立法することを予定するものではない。
そのことから、「憲法24条1項は、」「現行の法律婚制度とは別に、」「同性間の結合関係を保護するため」の「特別の規律を設ける」という「保護態様を予定していない」ことになる。
その理由は、「同性カップルと異性カップルとを差別するものであるから、」というものではなく、そもそも「憲法24条1項」が「婚姻」以外の制度については何ら触れていないためである。
よって、この点の理由として挙げているものが誤っている。
これについて、国(行政府)の主張では、下記のように述べている部分にあたるものである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(オ)さらに、被控訴人原審第3準備書面第3の2(3)(15ないし17ページ)で述べたとおり、憲法24条が婚姻について異性間の人的結合関係のみを対象とするものとして明文で定め、婚姻に係る法制度の構築を法律に委ねているものの、それ以外の法制度の構築を明文で定めていないことからすると、憲法は、法律(本件諸規定)により異性間の人的結合関係のみを対象とする婚姻を制度化することを予定しているとはいえるものの、同性間の人的結合関係を対象とする婚姻制度を構築することを想定していないことはもとより、パートナーと家族になるための法制度を含め、同性間の人的結合関係を対象とする新たな婚姻に準じる法制度を構築することを具体的に想定しておらず、同制度の構築を立法府に要請しているものでもないから、同制度の不存在が憲法24条2項に違反する状態となることもないと解される。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【東京一次・第1回】控訴答弁書 令和5年6月23日 PDF (P34)
この論点について、別の角度からも検討する。
まず、「憲法24条1項」は「婚姻」について定めており、これは「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた枠組みである。
そして、この「憲法24条1項」の「婚姻」の文言は「生殖と子の養育」に関わる制度を一元的に集約して規律する趣旨を有しており、この24条2項の「婚姻」を離れて「生殖と子の養育」に関わる制度を立法することはできない。
もし「憲法24条1項」の「婚姻」を離れて別の制度として「生殖と子の養育」に関わる制度を立法した場合には、「憲法24条1項」の「婚姻」に抵触して違憲となる。
ここでいう「同性間の結合関係」について「特別の規律を設ける」という「保護態様」を立法しようとした場合には、それは「生殖と子の養育」に関わる制度か、影響を与える制度となることが考えられ、そのような制度は「憲法24条1項」の「婚姻」に抵触して違憲となる。
そのため、「憲法24条1項は、」「特別の規律を設ける」という「保護態様を予定していない」という意味の中には、単に「憲法24条1項」が「婚姻」以外の制度については何も述べていないという意味にとどまらず、そのような制度を立法することは「憲法24条1項」の「婚姻」に抵触して違憲となるという意味も同時に含まれていることになる。
この点も見逃さないように注意が必要である。
その他、「同性カップルと異性カップルとを差別するものであるから、」との部分について検討する。
ここでは「カップル」という「二人一組」を取り上げて比較を行おうとしているが、憲法は「個人の尊厳」を定めており、法主体としての地位を認められているのは「個人」であることから、比較の際には「個人」と別の「個人」との間で比較することが必要である。
よって、ここでいうように「カップル」という「二人一組」を取り上げて法的な比較を行うことができるかのように論じている部分が妥当でない。
国(行政府)の主張でも、憲法14条の「平等原則」の審査の場面について、その性質は「個人権」であり、「個人と個人の間の平等」をいうことを説明している。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ア しかしながら,憲法14条1項が規定する法の下の平等とは,個人と個人の間の平等をいい,同項が禁止する不合理な差別も,個人と他の個人との間の不合理な差別をいうものと考えられる(例えば,芦部信喜教授は,法の下の平等は「個人権」であり,「個人尊重の思想に由来」すると説明している(芦部信喜〔高橋和之補訂〕「憲法第七版」129 ページ)。)。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【大阪・第6回】被告第4準備書面 令和3年2月19日 PDF (P4) (下線は筆者)
【札幌・第7回】被告第4準備書面 令和2年10月21日 PDF (P4)
しかし、同性カップルと異性カップルとでは、個々人の個別特性を別に一般的類型的に見れば、自然生殖の可能性という点に差異があることは否定し難いのであり、前記オのとおり、我が国において、婚姻が、男女が共同生活を送りながら、子を産み育て、次世代に承継していく営みにおいて、重要かつ不可欠な役割を果たしてきており、国民の中には、子を産み育てることに婚姻の意義を見出す者が今なお少なからず存在していることは無視し得ない事実であって、憲法が、現行の法律婚制度の開放を唯一の選択肢として、発生する効果に差を設けることを絶対に許さないとまで要請していると解することはできない。現行の法律婚制度と発生させる効果を完全に一致させるのか、特別の規律を設けて発生させる効果ごとに吟味し差異を許容するのか、何らかの差異を許容した場合の制度にいかなる呼称を与えるのか(婚姻と呼ぶのかその他の呼称とするのか)など、なお検討されてよい課題が存在するはずであるし、仮に法律により何らかの特別の規律が設けられた場合においても、その後の実績に応じるなどして、時の経過とともに社会情勢は変化し、同性カップルを含む国民全体の意識も変動していくものと推測でき、一旦成立した法律を唯一絶対のものと見る必然はなく、不断の検証を経るべきものであって、将来的な改正も視野に入れて検討されてよいはずである。
【筆者】
「しかし、同性カップルと異性カップルとでは、個々人の個別特性を別に一般的類型的に見れば、自然生殖の可能性という点に差異があることは否定し難いのであり、前記オのとおり、我が国において、婚姻が、男女が共同生活を送りながら、子を産み育て、次世代に承継していく営みにおいて、重要かつ不可欠な役割を果たしてきており、国民の中には、子を産み育てることに婚姻の意義を見出す者が今なお少なからず存在していることは無視し得ない事実であって、憲法が、現行の法律婚制度の開放を唯一の選択肢として、発生する効果に差を設けることを絶対に許さないとまで要請していると解することはできない。」との記載がある。
この文章はやや読み取りづらいため、順番を替えて整理すると下記のようになる。
「しかし、」「前記オのとおり、我が国において、婚姻が、男女が共同生活を送りながら、子を産み育て、次世代に承継していく営みにおいて、重要かつ不可欠な役割を果たしてきており、」
↓ ↓
「国民の中には、子を産み育てることに婚姻の意義を見出す者が今なお少なからず存在していることは無視し得ない事実であって、」
↓ ↓
「同性カップルと異性カップルとでは、個々人の個別特性を別に一般的類型的に見れば、自然生殖の可能性という点に差異があることは否定し難いのであり、」
↓ ↓
「憲法が、現行の法律婚制度の開放を唯一の選択肢として、発生する効果に差を設けることを絶対に許さないとまで要請していると解することはできない。」
下記では、この並べ替えた順番で解説する。
「我が国において、婚姻が、男女が共同生活を送りながら、子を産み育て、次世代に承継していく営みにおいて、重要かつ不可欠な役割を果たしてきており、」との部分について検討する。
これは「婚姻」が「男女二人一組」の枠組みを定めていることを前提に、それが「重要かつ不可欠な役割を果たして」きたことを説明するものであるが、なぜ「男女二人一組」の枠組みであるのかその理由を説明するものとしては十分でない。
「婚姻」が「男女二人一組」の枠組みである理由は、「婚姻」には「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体保護」という立法目的が存在し、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす「男性」と「女性」の組み合わせが選び出され、「貞操義務」を設けるなど一定の形式で法的に結び付けることによってその目的を達成することを目指すものとなっているからである。
この点を説明しなければ、「婚姻」が「重要かつ不可欠な役割を果たして」きたとしても、その枠組みの当否を明らかにすることはできない。
「国民の中には、子を産み育てることに婚姻の意義を見出す者が今なお少なからず存在していることは無視し得ない事実であって、」との部分について検討する。
この文は上記の「⑵オ」のところに書かれている文と同様であるから、この「子を産み育てることに婚姻の意義を見出す者」の意味は「③ 個々人の利用目的」の意味である。
しかし、「③ 個々人の利用目的」について何らかの事柄に意義を見出す者がいるとしても、そのことは「① 国の立法目的」を根拠づけるものとはならない。
よって、婚姻制度の枠組みがどのような意図によって定められているかを論じる際に、このような事柄をその理由として取り上げていることは妥当でない。
「同性カップルと異性カップルとでは、個々人の個別特性を別に一般的類型的に見れば、自然生殖の可能性という点に差異があることは否定し難いのであり、」との部分について検討する。
ここでいう「異性カップル」という「異性間の人的結合関係」(男女二人一組)については「婚姻」とすることができ、ここでいう「同性カップル」という「同性間の人的結合関係」については「婚姻」とすることができないという「差異」が存在することは、下記のような経緯によるものである。
「婚姻」の立法目的として、下記を挙げることができる。
・「子の福祉」が実現される社会基盤を構築すること
・潜性遺伝子の発現した個体が高い確率で生じることを抑制すること
・「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」を減らすこと
・母体を保護すること
これらの目的を達成するためには、これらの目的との関係で整合的な下記の要素を満たす枠組みを設けることが必要となる。
・子の遺伝的な父親を特定できる組み合わせとすること
・特定された子の父親にも子に対する責任を担わせること
・特定された子の父親を基に遺伝的な近親者を把握すること
・未婚の男女の数の不均衡を防止できる組み合わせに限定すること
そして、これらの要素を満たす人的結合関係の間に対して「貞操義務」を設けるなど一定の形式で法的に結び付ける枠組みを「婚姻」と呼んでいる。
これにより、「異性間の人的結合関係」(男女二人一組)についてはこれらの要素を満たすことから「婚姻」とすることができるが、「同性間の人的結合関係」についてはこれらの要素を満たすものではないため「婚姻」とすることができないことになる。
このことは、ここで「一般的類型的に」「自然生殖の可能性という点に差異がある」と述べられていることと趣旨の重なる部分である。
ただ、ここでは「同性カップル」という「同性間の人的結合関係」のみを取り上げて比較しているのであるが、婚姻制度を利用することができない関係には、他にも「近親者との人的結合関係」、「三人以上の人的結合関係」、「婚姻適齢に満たない者との人的結合関係」がある。
そのため、ここで「同性間の人的結合関係」のみを比較対象として持ち出せば足りるかのような前提で論じていることは、網羅的な検討を行うものではなく、視野を狭めるものとなっているため妥当でない。
「憲法が、現行の法律婚制度の開放を唯一の選択肢として、発生する効果に差を設けることを絶対に許さないとまで要請していると解することはできない。」との部分について検討する。
この文は読み取りづらいが、要するに下記のようになる。
「憲法が、現行の法律婚制度の開放」(発生する効果に差を設けることを絶対に許さない)「を唯一の選択肢として」「要請している」「とまで」「と解することはできない。」
ただ、この「⑵ 憲法24条1項に違反するかについて」の項目で問われているのは、24条1項が「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを「要請」しているか否かであり、「現行の法律婚制度」を「開放」するか否かではない。
24条に基づいて「法律婚制度」が立法されているのであれば合憲であり、24条に基づいて「法律婚制度」が立法されていないのであれば違憲となるだけであり、その審査は24条に基づいて立法されているはずの「現行の法律婚制度」についてさらに24条に基づいて「開放」するか否かではない。
そのため、「開放」が「要請」されているか否かを問う論じ方をしている点は、24条1項で行うことのできる審査の内容を誤っており、妥当でない。
ここでは下記の二つの場合を想定するものとなっている。
◇ 「現行の法律婚制度の開放」(発生する効果に差を設けることを絶対に許さない)
◇ 「発生する効果に差を設けること」
しかし、そもそも24条1項は「現行の法律婚制度」に対して「開放」を「要請」する意味の規定ではないし、24条1項は「婚姻」以外の制度については何ら触れておらず、ここでいう創設を「発生する効果に差を設けること」という制度を創設することを「要請」するものではない。
よって、「発生する効果に差を設けること」という制度を挙げるのであるが、24条1項の解釈には関わらない事柄であり、これを取り上げて論じようとしている部分は妥当でない。
また、「発生する効果に差を設けること」という制度は、憲法よりも下位の法令の立法政策として検討されるものであり、その立法政策を根拠として上位法である憲法24条1項の意味を明らかにしようとする方法は、法秩序の階層性の上下関係を逆転させようとするものとなるから、解釈の方法として妥当でない。
もしかすると、「発生する効果に差を設けること」という制度の創設を24条1項が「要請」している可能性を検討しているのかもしれないが、24条1項は「婚姻」について触れているが、それ以外の制度については何ら触れていないため、24条1項はここでいう「発生する効果に差を設けること」という制度の創設を「要請」するものではない。
そのため、このような論じ方をしている点は、その全体としても誤っている。
「現行の法律婚制度と発生させる効果を完全に一致させるのか、特別の規律を設けて発生させる効果ごとに吟味し差異を許容するのか、何らかの差異を許容した場合の制度にいかなる呼称を与えるのか(婚姻と呼ぶのかその他の呼称とするのか)など、なお検討されてよい課題が存在するはずであるし、仮に法律により何らかの特別の規律が設けられた場合においても、その後の実績に応じるなどして、時の経過とともに社会情勢は変化し、同性カップルを含む国民全体の意識も変動していくものと推測でき、一旦成立した法律を唯一絶対のものと見る必然はなく、不断の検証を経るべきものであって、将来的な改正も視野に入れて検討されてよいはずである。」との記載がある。
この文章はたくさんの情報が詰め込まれており、読み取りづらいため、下記のように整理する。
◇ 「現行の法律婚制度と発生させる効果を完全に一致させる」
◇ 「特別の規律を設けて発生させる効果ごとに吟味し差異を許容する」
・ 「何らかの差異を許容した場合の制度にいかなる呼称を与えるのか(婚姻と呼ぶのかその他の呼称とするのか)など」
・ 「仮に法律により何らかの特別の規律が設けられた場合においても、」「将来的な改正も視野に入れて検討されてよいはずである。」
(その後の実績に応じるなどして、時の経過とともに社会情勢は変化し、同性カップルを含む国民全体の意識も変動していくものと推測でき、一旦成立した法律を唯一絶対のものと見る必然はなく、不断の検証を経るべきもの)
「など、なお検討されてよい課題が存在するはずである」
まず、「現行の法律婚制度と発生させる効果を完全に一致させるのか、」との部分について検討する。
「婚姻」は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた枠組みである。
「同性間の人的結合関係」については、その間で「生殖」を想定することができないことから、「生殖と子の養育」の趣旨を満たすものではなく、「婚姻」とすることはできない。
また、24条は「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めている。
そのため、「同性間の人的結合関係」については、24条の「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言の趣旨を満たさないため、「婚姻」とすることはできない。
もし「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とする法律を立法しようとした場合には、24条の「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言に抵触して違憲となる。
よって、ここでは「同性間の人的結合関係」について「現行の法律婚制度と発生させる効果を完全に一致させる」のように、「現行の法律婚制度」に「同性間の人的結合関係」を含めることができるかのような前提で論じているが、そもそも「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることはできず、「現行の法律婚制度」に「同性間の人的結合関係」を含めようとした場合には、24条の「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言に抵触して違憲となるため、それを行うことはできない。
もし「現行の法律婚制度」とは別に、「現行の法律婚制度と発生させる効果」が「完全に一致」する「婚姻」とは別の制度を設けることを検討するものであるとしても、24条の「婚姻」は「生殖と子の養育」に関わる制度を一元的に集約して規律する趣旨を有しており、24条の「婚姻」を離れて「生殖と子の養育」に関わる制度を立法することを許容していない。
そのため、「現行の法律婚制度と発生させる効果」が「完全に一致」する「婚姻」とは別の制度のようなものを立法しようとした場合には、24条の「婚姻」に抵触して違憲となる。
他にも、「婚姻」は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的との関係で、「婚姻している者(既婚者)」に対して一定の優遇措置を与えることは「婚姻していない者(独身者)」との間で生じる差異を正当化することができるが、そのような目的を有しない「現行の法律婚制度と発生させる効果」が「完全に一致」する「婚姻」とは別の制度については、その制度を利用していない者との間で合理的な理由を説明することのできない差異を生じさせることになることから、14条の「平等原則」に抵触して違憲となる。
よって、ここで述べているものが「現行の法律婚制度」とは別に「現行の法律婚制度と発生させる効果」が「完全に一致」する「婚姻」とは別の制度を設けることを検討するものであるとしても、その制度を立法することはできないため、その制度を立法することが可能であるかのような前提の下に論じていることは誤りである。
次に、「特別の規律を設けて発生させる効果ごとに吟味し差異を許容するのか、何らかの差異を許容した場合の制度にいかなる呼称を与えるのか(婚姻と呼ぶのかその他の呼称とするのか)など、」との部分について検討する。
「特別の規律」を設けることができることを前提に、「発生させる効果ごとに吟味し差異を許容する」方法を検討しているが、そもそも24条の「婚姻」は「生殖と子の養育」に関わる制度を一元的に集約して規律する趣旨を有しており、この24条の「婚姻」を離れて「生殖と子の養育」に関わる制度を立法することはできない。
そのため、ここでいう「特別の規律」が「生殖と子の養育」に関わる制度となっている場合や、影響を与える制度となっている場合には、24条の「婚姻」に抵触して違憲となる。
また、婚姻制度の場合には、「婚姻している者(既婚者)」が一定の優遇措置を得られることは「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成するための手段として合理的な範囲内でのみ「婚姻していない者(独身者)」との間の差異を正当化することができるが、ここでいう「特別の規律」はそのような目的を有するものではないため、そこで得られる利益は、その制度を利用していない者との間で合理的な理由を説明することのできない差異を生じさせるものとなることから、14条の「平等原則」に抵触して違憲となる。
よって、「特別の規律」という制度を設けることができることを前提に論じている部分が誤りである。
「何らかの差異を許容した場合の制度」に対して「いかなる呼称を与えるのか」についてであるが、そもそもそのような制度を立法することはできることにはならないため、それを立法することができることを前提に論じている部分が妥当でない。
「婚姻と呼ぶのかその他の呼称とするのか」との部分について、憲法24条は「婚姻」を定めており、その「婚姻」の内容を統制するものであるから、日本法の下での「婚姻」はすべてこの憲法24条の「婚姻」の効力が及ぶことになる。
そのため、24条の「婚姻」を離れる形で「婚姻」と称する制度を別に立法することはできない。
そのことから、24条の「婚姻」ではない制度について、「婚姻と呼ぶ」ことができることを前提に論じている部分は誤りである。
また、「その他の呼称」をする制度であるとしても、上記で述べたように、そのような制度の創設は24条の「婚姻」の趣旨や14条の「平等原則」に抵触して違憲となることが考えられるため、これを立法することができることを前提に論じている部分が妥当でない。
「なお検討されてよい課題が存在するはずであるし、」との部分について検討する。
上記のように、そもそも「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることはできないし、「特別の規律」を設けることができるわけでもないため、「検討されてよい課題が存在する」のではなく「検討」する前提を欠くものである。
この点を「検討」することができることを前提に論じている部分が誤りである。
「仮に法律により何らかの特別の規律が設けられた場合においても、その後の実績に応じるなどして、時の経過とともに社会情勢は変化し、同性カップルを含む国民全体の意識も変動していくものと推測でき、一旦成立した法律を唯一絶対のものと見る必然はなく、不断の検証を経るべきものであって、将来的な改正も視野に入れて検討されてよいはずである。」との部分について検討する。
ここでは「何らかの特別の規律」を「法律」で設ける場合について述べているが、先ほども述べたように、24条の「婚姻」の文言は「生殖と子の養育」に関わる制度を一元的に集約して規律していることから、24条の「婚姻」を離れて別の制度として「生殖と子の養育」に関わる制度を立法することはできない。
もし24条の「婚姻」を離れて「生殖と子の養育」に関わる制度や影響を与える制度を立法した場合には、24条の「婚姻」に抵触して違憲となる。
また、婚姻制度が「婚姻している者(既婚者)」に対して一定の優遇措置を講じることは「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成するための手段として整合的な範囲内で「婚姻していない者(独身者)」との間にある差異を正当化することができるが、そのような目的を有しない「何らかの特別の規律」については、その制度を利用しない者との間で合理的な理由を説明することのできない差異を生じさせることになるから、14条の「平等原則」に抵触して違憲となる。
よって、「何らかの特別の規律」を「法律」で定めることができることを前提に述べている部分が誤りである。
「その後の実績に応じるなどして、」とあるが、24条の「婚姻」や14条の「平等原則」に抵触して違憲となるため、そのような「実績」を積んだ場合は違法なものとなる。
「一旦成立した法律を唯一絶対のものと見る必然はなく、」との部分であるが、先ほども述べたように、24条の「婚姻」や14条の「平等原則」に抵触して違憲となる「法律」を立法することはできない。
「不断の検証を経るべきものであって、」との部分についても、それ以前にその「法律」が24条の「婚姻」や14条の「平等原則」に抵触して違憲となることについて「検証」することが必要なものである。
「将来的な改正も視野に入れて検討されてよいはずである。」との部分であるが、24条の「婚姻」や14条の「平等原則」に抵触して違憲となる「法律」は立法することはできないし、もし立法されたとしても違憲・無効となるため、これは「改正」ではなく、「廃止」となる。
また、「将来的な改正」によって、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを検討するものであるとしても、そもそも「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることはできないし、もしそれをしようとした場合には24条の「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言に抵触して違憲となる。
そのため、「改正」のように、そのような「法律」を立法することができることを前提に論じている部分が誤りとなる。
「同性カップル」のように「二人一組」の関係が出てくるが、人的結合関係の中には「三人一組」や「四人一組」などそれ以外の人的結合関係も存在するのであり、ここで「カップル」のように「二人一組」のみを取り上げて比較すればそれで足りるかのように述べている部分は妥当でない。
これは、なぜ「二人一組」であるのか、その根拠を説明しないままに論じる「カップル信仰論」に陥っているといえる。
この「⑵ 憲法24条1項に違反するかについて」の項目では、24条1項が「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを「要請」しているか否かが問われており、この文は、次の段落の「サ」で「憲法24条1項の趣旨に照らして要請されていると解することは困難である」と結論付けるまでの理由として示されているものである。
しかし、その理由として示しているものは、「現行の法律婚制度と発生させる効果を完全に一致させる」や「特別の規律を設けて発生させる効果ごとに吟味し差異を許容する」などについて「検討されてよい課題が存在するはずである」のように憲法の枠内でのみ立法することが許される法律の立法政策に関する事柄である。
これは、下位の法令を根拠としてその上位の法令の意味を明らかにしようとするものとなっており、上位法と下位法の上下関係を逆転させるものであり、法秩序の階層性を損なわせるものとなるから、解釈の方法として誤っている。
よって、このような憲法よりも下位の法令を根拠とすることによって、その上位の法令である憲法の意味を明らかにしようとする論じ方そのものが誤っており、この文が憲法上の規定の意味を明らかにするための理由として持ち出されていることそのものを正当化することができない。
他にも、結局「サ」の部分で「憲法24条1項の趣旨に照らして要請されていると解することは困難である」としているのであるから、この文は「憲法24条1項」が「要請」していない事柄について、「現行の法律婚制度と発生させる効果を完全に一致させる」や「特別の規律を設けて発生させる効果ごとに吟味し差異を許容する」、「将来的な改正」などと述べ、国会における立法政策に対して口出しするものであり、司法権の範囲を超えている。
よって、この文は憲法の許す範囲を超えている意味でも誤っており、憲法上の規定の意味を明らかにする手順としても誤っており、さらに、国会の立法政策に口出ししようとしている意味でも誤っている。
サ 以上によれば、現時点においても、現行の法律婚制度を同性間に対して及ぼすことが、憲法24条1項の趣旨に照らして要請されていると解することは困難であるから、婚姻をするについての自由が同性間に対して及ぶものであるとは認められず、同性間に婚姻を認めていない本件諸規定が、同条項に違反するものとはいえない。
【筆者】
「以上によれば、現時点においても、現行の法律婚制度を同性間に対して及ぼすことが、憲法24条1項の趣旨に照らして要請されていると解することは困難であるから、」との部分について検討する。
まず、「以上によれば、」として挙げられているのは、おおよそ下記のようにまとめることができる。
「イ」
・「「両性」、「夫婦」といった文言は、男性と女性の双方を表すのが通常の語義」
・「明治民法において、」「婚姻とは終生の共同生活を目的とする一男一女の法律的結合関係をいうものである」
・「憲法24条の起草過程においても、同性間の結合が婚姻に含まれるかについての議論がなされた形跡は見当たらず」
・「昭和22年民法改正の過程においても、同性間の結合が婚姻に含まれるかについての議論がなされた形跡は見当たらない」
「オ」
・「婚姻は、男女が共同生活を送りながら、子を産み育て、次世代へ承継していく営みにおいて、重要かつ不可欠な役割を果たしてきた」
・「国民の中に」「子を産み育てることに婚姻の意義を見出す者」
・「婚姻制度と自然生殖の可能性が完全に切り離されたと見るのは困難」
「カ」
・「少なくない国民が反対の意見を有している」
「キ」
・「民法は、法律婚制度の構築に当たり、子孫の生殖を伴う男女の結合関係とそれを中核とする家族関係の安定化を少なくともその目的の一つとしていた」
・「そのまま拡張することは、」「現行の法律婚制度全体の枠組みにも影響を生じさせることが避けられない」
「ク」
・「当該制度とは別に、特別の規律を設けることによることも、立法政策としてはありうる」
・「諸外国ごとに多様な立法措置が講じられている」
「ケ」
(おおよそ『オ』『カ』『キ』『ク』の繰り返し)
「コ」
・「自然生殖の可能性という点に差異があることは否定し難い」
・「仮に法律により何らかの特別の規律が設けられた場合においても、」「将来的な改正も視野に入れて検討されてよいはず」
しかし、この中には憲法解釈の過程では用いてはならないものが存在する。
これらの中の下記のような内容は、憲法上の規範の意味を明らかにするための解釈の過程において用いることはできない。
◇ 諸外国の立法例
◇ 国民の賛成意見・反対意見の数
◇ 婚姻制度を利用する者の「個々人の利用目的」
◇ 憲法よりも下位の法令やその立法政策
これらに関係するものを取り除くと、下記が残ることになる。
「イ」
・「「両性」、「夫婦」といった文言は、男性と女性の双方を表すのが通常の語義」
・「明治民法において、」「婚姻とは終生の共同生活を目的とする一男一女の法律的結合関係をいうものである」
・「憲法24条の起草過程においても、同性間の結合が婚姻に含まれるかについての議論がなされた形跡は見当たらず」
「オ」
・「婚姻は、男女が共同生活を送りながら、子を産み育て、次世代へ承継していく営みにおいて、重要かつ不可欠な役割を果たしてきた」
・「婚姻制度と自然生殖の可能性が完全に切り離されたと見るのは困難」
「コ」
・「自然生殖の可能性という点に差異があることは否定し難い」
(上記「イ」の「明治民法」については、憲法24条の制定に影響を与えていることから、大日本帝国憲法下での法形式としては「法律」であるが、ここでの議論としては取り除かずに残した。)
よって、この判決が「現行の法律婚制度を同性間に対して及ぼすことが、憲法24条1項の趣旨に照らして要請されていると解することは困難である」との結論に至るまでの解釈の過程において本来用いることのできる論拠は、上記に挙げた内容だけである。
ここで「現行の法律婚制度を同性間に対して及ぼすことが、憲法24条1項の趣旨に照らして要請されていると解することは困難である」という結論が導き出されるまでの根拠として、これ以前の段落では何度も「現行の法律婚制度とは別に、特別の規律を設けること」などが考えられることを述べるものとなっている。
しかし、これは憲法よりも下位の法令を根拠として、その上位の法令である憲法の意味を明らかにしようとするものであることから、法秩序の階層構造を損なわせるものであり、解釈の方法として正当化することはできない。
法秩序は階層構造を有しており、「憲法→法律→命令」のように法形式によって上下関係の順序が決められている。
憲法
↓
法律
↓
命令
そのため、「命令」で定められた内容を根拠として「法律」の意味を明らかにすることはできないし、「法律」で定められた内容を根拠として「憲法」の意味を明らかにすることもできない。
もしそれが可能となった場合には、上位の法令に定められた条文の意味を下位の法令によって書き替えることが可能となることを意味し、上位法と下位法の関係が逆転し、法秩序の階層構造が損なわれるからである。
こうなると、下位の法令の内容が上位の法令に違反するか否かを審査することができなくなるし、また、審査の結果として違反することが分かったとしても、それを是正することができなくなってしまうことになる。
そのため、下位の法令やその立法政策を根拠として、それよりも上位の法令の意味を明らかにしようとする方法は、解釈の手順として正当化することができるものではない。
この判決がそのような手順で解釈を試みている部分は、すべて誤りである。
このような手続きが妥当でないことについて、下記の動画も参考になる。
【動画】予備試験・司法試験で求められる「憲法のセンス」 2022/09/30
この名古屋地裁判決についても、これと同様のことが言える。
この名古屋地裁判決は、先に「婚姻」とは別の制度を創設する方法もあるという政策論を先行させた上で、その先行させた政策論を理由として後から憲法24条1項が「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを「要請」しているか否かを審査している。
これは逆立ちした議論である。
本来であれば憲法24条1項の意味を読み解くことによって基準を導き出して、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることが「要請」されているか否かという結論を論じるべきであったのに、そうではなくて、先に「婚姻」とは別の制度を創設する方法があるという政策論を論じた上で、後からそれを理由として憲法24条1項は「要請」していないとその結論について確認作業を行うものとなっており、逆立ちした議論となっている。
よって、この論証の仕方は誤りである。
「婚姻をするについての自由が同性間に対して及ぶものであるとは認められず、」との部分について検討する。
憲法24条1項を基にした「婚姻をするについての自由」のいう「婚姻」とは、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた枠組みである。
そして、この「婚姻をするについての自由」は、個々人に保障されているものであることから、ここでいう「同性間」のように人的結合関係を対象として保障しているものではない。
この意味で、「婚姻をするについての自由が同性間に対して及ぶものであるとは認められず、」との部分は正しいといえる。
その他、「同性間」の人的結合関係については、その間で「生殖」を想定することができず、「生殖と子の養育」の趣旨を満たすものではないことから、「婚姻」とすることはできない。
そのため、「婚姻をするについての自由」の意味は、「同性間」の人的結合関係を「婚姻」とすることを求める意味を有していないことも押さえる必要がある。
「同性間に婚姻を認めていない本件諸規定が、同条項に違反するものとはいえない。」との部分について検討する。
「同性間に婚姻を認めていない」とあるが、「婚姻」は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた枠組みであり、「同性間」については、その間で「生殖」を想定することができないことから、「生殖と子の養育」の趣旨を満たすとはいえず、「婚姻」とすることはできない。
よって、法律上の婚姻制度の内容が「同性間」を対象とするものとして定められていないことが憲法24条1項に違反することはなく、「同条項に違反するものとはいえない。」との部分はその通りである。
この判決の「⑵ 憲法24条1項に違反するかについて」の項目の「アイウエオカキクケコサ」の文章の流れは非常に読み取りづらいものとなっている。
これは、下記の原因を挙げることができる。
まず、下記のように【問い】を立てるタイミングと【結論】を述べるタイミングがまちまちとなっている。
◇ 「ア(第一段落)(第二段落【問い①】)」→「イ(第一段落)(第二段落)(第三段落【結論①】)」
↓ ↓
◇ 「ウ(第一段落【問い②】)(第二段落)(第三段落)」→「エ」→「オ」→「カ」→「キ」→「ク」→「ケ(ウの〔第二段落〕〔第三段落〕の繰り返し)【結論②】)」
↓ ↓
◇ 「コ(第一段落【問い③】)(第二段落〔オ→カ→キ→クの繰り返し〕)」
↓ ↓
◇ 「サ【結論①②③】」
上記のように、「ア」の途中で【問い①】を立て、「イ」の第三段落で【結論①】を述べている。
そして、「ウ」の第一段落で【問い②】を立て、「ウ」の第三段落で検討を宣言し、次の「エ」でも同じく検討を宣言し、そのまま「エ」、「オ」、「カ」、「キ」、「ク」を論じた後に、「ケ」で「ウ」の第二段落と第三段落を繰り返し、その後【結論②】を述べている。
さらに、「コ」の第一段落で【問い③】を立て、第二段落で以前に述べた「オ」、「カ」、「キ」、「ク」の話を繰り返し、「サ」で【結論】を述べている。
このように、【問い】を立てるタイミングと、【結論】を述べるタイミングに一貫性がないことが、読み取りづらくさせる原因となっている。
また、【結論】に至る直前の部分で無用に話を繰り返しているところがあり、それまで述べていた判断の過程と【結論】との関係性を確認しづらい点も読み取りづらくさせる原因となっている。
次に、「アイウエオカキクケコサ」の項目名を使う分量が【問い】ごとに違い過ぎる。
【問い①】 アイ (2項目)
【問い②】 ウエオカキクケ (7項目)
【問い③】 コ(サ) (1+1/3項目)
この点でも、項目をどのようなまとまりとして整理すればよいのか分かりづらくなっており、読者を混乱させるものとなっている。
三つ目に、【結論】の併用が存在する。
「サ」の【結論】については、直前の「コ」の【問い③】からの流れで読み取ると、【結論③】として述べられているように見える。
しかし、この「サ」の冒頭を見ると「現時点においても、」と書かれていることから、この文は、「ウ」で、「原告ら」が「憲法24条1項」について、「その後の社会情勢の変化等により、」「同性間に対しても法律婚制度を及ぼすことが要請されるに至った」と主張していることに応答するものであることが分かるため、「ウ」の【問い②】に応答するものとして【結論②】が述べられているように見える。
加えて、この「サ」の【結論】では、【結論①】や【結論②】でも示されている24条1項が「要請」しているか否かの判断だけでなく、その結果として24条1項に違反するか否かについてまで特別に明示していることから、この意味でこの「サ」の【結論】は、この「⑵ 憲法24条1項に違反するかについて」の項目を総括するものとなっているように見える。
◇ 「イ」:「同条1項の趣旨に照らして要請されていたとは解し難い。」
◇ 「ケ」:「要請するに至ったとは解し難いといわざるを得ない。」
◇ 「サ」:「憲法24条1項の趣旨に照らして要請されていると解することは困難である」⇒「同条項に違反するものとはいえない。」
そのため、この「サ」については、下記の役割を同時に有していることになる。
◇ 「コ」の【問い③】に対する【結論③】としての役割
◇ 「ウ」の【問い②】に対する【結論②】としての役割
◇ 「ア」の【問い①】、「ウ」の【問い②】、「コ」の【問い③】のすべてに対する【結論①②③】としての役割
このように、「サ」の【結論】を、「コ」の【問い③】に対する応答の意味だけでなく、「ウ」の【問い②】に対する応答の意味と、「⑵ 憲法24条1項に違反するかについて」の項目の全体をまとめる意味とを有しており、三つの意味において併用されている。
図にすると下記のようになる。
「ア」の【問い①】
↓ ↓
↓ 「イ」の【結論①】
↓
↓ 「ウ」の【問い②】
↓ ↓ ↓
↓ ↓ 「ケ」の【結論②】
↓ ↓
↓ ↓ 「コ」の【問い③】
↓ ↓ ↓
「サ」の【結論①②③】
これにより、文脈の前後を辿る際の対応関係を明快に認識することが困難となり、読者は混乱するのである。
このように、この「⑵ 憲法24条1項に違反するかについて」の項目の「アイウエオカキクケコサ」の文章の流れは構造的な問題を抱えており、これが原因となって、読み取りづらいものとなっている。
⑶ 憲法24条2項に違反するかについて
ア 前記⑵のとおり、現行の法律婚制度を同性間に対して及ぼすことは、憲法24条1項の趣旨に照らし、禁止されてはいないが、要請されているともいえない。そして、同条2項は、同条1項を前提として、法律による婚姻制度の具体化を国会の合理的な立法裁量に委ねるとともに、国会に要請、指針を示す規定と解されるから、同条2項も、現行の法律婚制度を同性間に対して及ぼすことを要請していないと解するのが整合的であり、本件諸規定が同性間に現行の法律婚制度をそのまま適用することを認めていないことは、同項に違反するものでもないというべきである。
【筆者】
「現行の法律婚制度を同性間に対して及ぼすことは、憲法24条1項の趣旨に照らし、禁止されてはいないが、要請されているともいえない。」との記載がある。
「現行の法律婚制度を同性間に対して及ぼすことは、憲法24条1項の趣旨に照らし、禁止されてはいない」との部分について検討する。
この論点については、上記「⑵ 憲法24条1項に違反するかについて」の「ウ」のところで解説している。
ここでは、先に出てきた上記の部分とは少しずつ文言が異なっている。
・上記「⑵ウ」:「禁止されていたとまではいえない」
・上記「⑵ケ」:「禁止されているとはいえない」
・この「⑶ア」:「禁止されてはいない」
しかし、これによって論点が変わることはなく、解説した内容が変わるということはない。
よって、ここで「現行の法律婚制度を同性間に対して及ぼすことは、憲法24条1項の趣旨に照らし、禁止されてはいない」のように述べて、「同性間」の人的結合関係を「婚姻」とすることができるかのような説明をしていることは誤りとなる。
「要請されているともいえない。」との部分について検討する。
その通り、「憲法24条1項」は「同性間」の人的結合関係を「婚姻」とすることを「要請」するものではない。
ただ、それは「同性間」の人的結合関係を「婚姻」とすることができることを前提として「憲法24条1項」がそれを「要請」していないというものではなく、「同性間」の人的結合関係を「婚姻」とすることができないことから「憲法24条1項」はそれを「要請」するものではないというものである。
この前提となっている論点を見逃すことがないように注意する必要がある。
「同条2項は、同条1項を前提として、法律による婚姻制度の具体化を国会の合理的な立法裁量に委ねるとともに、国会に要請、指針を示す規定と解されるから、同条2項も、現行の法律婚制度を同性間に対して及ぼすことを要請していないと解するのが整合的であり、本件諸規定が同性間に現行の法律婚制度をそのまま適用することを認めていないことは、同項に違反するものでもないというべきである。」との記載がある。
この文には、「要請していない」と「違反するものでもない」と記されている。
これは、この「⑶ 憲法24条2項に違反するかについて」の項目の中で、24条2項が「同性間」の人的結合関係を「婚姻」とすることを「要請」しているか否かの問題については、「要請していない」ことを示し、その結果、そのような法律が存在しないことについても、24条2項に違反するものではないと結論付けるものである。
これにより、24条2項の「婚姻及び家族」の文言の中の「婚姻」の部分については、この判決の中では判断が終了したことになる。
そのため、これより以下は、24条2項の「婚姻及び家族」の文言の「家族」の部分についての話に移ることになる。
イ ところで、原告らは、同性間の婚姻を求める権利利益が憲法24条の保障する範囲内でないとしても、婚姻により生じる諸々の法的利益を享受する権利は重大な法的利益であり、これが性的指向や性別により不合理な差別を受ける場合には、憲法14条1項違反となると主張している。その趣旨は、婚姻により生じる諸々の法的利益を享受する権利が原告らに保障されていないことが重大な法的利益の侵害であり、憲法に違反するというものであると解され、憲法24条においても考慮されるべきことを否定する趣旨ではないと解される。特に、家族に関する法制度の平等が問題となる場合においては、憲法14条1項と憲法24条2項の関係をどのように理解するかについては見解が分かれ得る問題であるとしても、両条項が保護しようとした法益に重なり合う部分が存することは否定できないと考えられるから、原告らが主張する重大な法的利益を享受できないことの違憲性については、憲法24条2項の問題ともなりうるものである。
【筆者】
「原告らは、同性間の婚姻を求める権利利益が憲法24条の保障する範囲内でないとしても、婚姻により生じる諸々の法的利益を享受する権利は重大な法的利益であり、これが性的指向や性別により不合理な差別を受ける場合には、憲法14条1項違反となると主張している。」との記載がある。
「同性間の婚姻を求める権利利益が憲法24条の保障する範囲内でないとしても、」との部分について検討する。
「憲法24条」は「婚姻」を定めており、これは「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度である。
「同性間」の人的結合関係については、その間で「生殖」を想定することができないことから、「生殖と子の養育」の趣旨を満たすとはいえず、「婚姻」とすることはできない。
よって、「同性間の婚姻を求める権利利益が憲法24条の保障する範囲内でない」との部分はその通りである。
「婚姻により生じる諸々の法的利益を享受する権利は重大な法的利益であり、これが性的指向や性別により不合理な差別を受ける場合には、憲法14条1項違反となると主張している。」との部分について検討する。
「婚姻により生じる諸々の法的利益を享受する権利は重大な法的利益であり、」とあるが、「婚姻」は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた枠組みであり、一般的・抽象的にその間で自然生殖を想定することができる「一人の男性」と「一人の女性」の組み合わせに対して「貞操義務」など一定の形式で法的に結び付けることにより、その目的を達成することを目指すものとなっている。
そして、その目的を達成するための手段として整合的な形で法的効果を設定し、一定の優遇措置を行うものとなっており、ここでいう「諸々の法的利益」についても、その目的を達成するための手段として合理的な範囲内で設定されるものである。
また、「婚姻」の中に含まれる人的結合関係と含まれない人的結合関係に区別することによって立法目的の達成を目指すものとなっていることから、「婚姻」の中に含まれる人的結合関係に対してのみ「諸々の法的利益」を与え、「婚姻」の中に含まれない人的結合関係については「諸々の法的利益」が与えられないことは当然に予定されている。
そのような中、この「男女二人一組」の婚姻制度を利用する意思を有しているにもかかわらず、行政府である行政機関や司法府である裁判所が婚姻制度に関する法律を適用する場面において、個々人の内心における「性愛」の有無や、「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかについての「性的指向」と称するものを審査し、その審査の結果に基づいて法令の適用を否定するようなことがあれば、それは「憲法14条1項」の「平等原則」における「法適用の平等」に違反することは考えられる。
しかし、今回の事例では、そのような事実は認められないから、「憲法14条1項」の「平等原則」における「法適用の平等」に違反するとはいえない。
また、「憲法14条1項」の「平等原則」における「法内容の平等」の論点を検討しようとしても、そもそも婚姻制度は「性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかについての「性的指向」と称するものを審査して区別取扱いをする制度ではないし、「性愛」に基づいて制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもない。
そのことから、婚姻制度が「性的指向」により「差別」しているという事実がないことから、当然、「憲法14条1項」の「平等原則」における「法内容の平等」に違反することもない。
これとは別の視点で、「婚姻している者(既婚者)」と「婚姻していない者(独身者)」との間の比較において、「婚姻している者(既婚者)」が婚姻制度の立法目的を達成するための手段としては不必要に過大な優遇措置(ここでいう『婚姻により生じる諸々の法的利益』)を得るものとなっていた場合には、その不必要に過大な優遇措置に関する規定が「憲法14条1項」の「平等原則」(法内容の平等)に抵触して違憲となり、その不必要に過大な優遇措置に関する規定が個別に失効することによって格差が是正されることになる。
「その趣旨は、婚姻により生じる諸々の法的利益を享受する権利が原告らに保障されていないことが重大な法的利益の侵害であり、憲法に違反するというものであると解され、憲法24条においても考慮されるべきことを否定する趣旨ではないと解される。」との記載がある。
「婚姻により生じる諸々の法的利益を享受する権利」との部分について検討する。
そこに「婚姻」と書かれているように、「婚姻」の中に含まれる人的結合関係に対してのみ「諸々の法的利益」を与えるものであるから、「婚姻」の中に含まれない人的結合関係に対しては「諸々の法的利益」は与えられないものである。
よって、「婚姻」の中に含まれない人的結合関係については、「婚姻により生じる諸々の法的利益を享受する権利」が保障されていないことは当然のことである。
ここでいう「原告ら」は、「同性間」であることから「婚姻」には含まれず、「婚姻により生じる諸々の法的利益を享受する権利」は与えられない。
「婚姻により生じる諸々の法的利益を享受する権利が原告らに保障されていないことが重大な法的利益の侵害であり、」との部分について検討する。
まず、「原告ら」の部分であるが、憲法は「個人の尊厳」の原理に基づいており、自然人は「個人主義」の基に各々「自律的な個人」として生存していくことを予定していることから、「原告ら」を法的な主体としての視点で見れば、一人一人として扱うことが必要となる。
また、民法上の法主体には「自然人」と「法人」があり、自然人の場合は出生によって「権利能力」を取得し、死亡することによって「権利能力」が消滅する。
民法
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第二章 人
第一節 権利能力
第三条 私権の享有は、出生に始まる。
2 外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
自然人 Wikipedia
法人 Wikipedia
人の始期 Wikipedia
権利能力 Wikipedia
「原告ら」は自然人であるから、「個人」として「権利能力」の主体となる。
よって、法律論上では、「原告ら」のようにまとめて一つの単位として扱うことができるわけではなく、その者たちが「二人一組」の人的結合関係を形成しているとしても、それは個人と個人が人的結合関係を形成しているという状態として扱う必要がある。
そのため、法的な主体としての地位を認識する場合には、すべて「個人」として扱われることとなる。
そして、その「原告ら」としている中の個々人について婚姻制度(男女二人一組)を利用することは可能である。
よって、「婚姻により生じる諸々の法的利益を享受する権利」は「保障」されており、「保障されていない」との部分は誤りである。
これにより、「婚姻により生じる諸々の法的利益を享受する権利が原告らに保障されていないこと」を前提として「重大な法的利益の侵害であり」と評価している部分も誤りとなる。
これとは別に、「同性間の人的結合関係」で「婚姻」することができるか否かを考える。
これについては、婚姻制度は「男女二人一組」となっていることから、これを満たさない以上は「婚姻」することはできない。
ただ、憲法は「個人の尊厳」の原理に基づいており、自然人は「個人主義」の下に各々「自律的な個人」として生存していくことを予定していることから、「婚姻していない者(独身者)」の状態で既に完全な状態である。
また、婚姻制度の対象でないとしても、単に優遇措置が得られないというだけであり、国家から個人に対して何らかの行為を制限したり、制裁を課すようなものではなく、個々人が有する「国家からの自由」という意味の「自由権」が侵害されることはない。
そのため、婚姻制度を利用していないとしても、そこに「重大な法的利益の侵害」とされる状態にはないため、それを「重大な法的利益の侵害」と評価している部分は誤りである。
「憲法に違反するというものであると解され、」との部分について検討する。
ここでは、一文前の「憲法14条1項違反となる」との主張の意味と、この文の「憲法24条」による審査の意味とが含まれていると考えられるため、それぞれの審査方法から検討する。
まず、「憲法14条1項違反となる」との主張の意味について検討する。
「婚姻」は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度である。
そして、この目的を達成するための手段として整合的な形で「諸々の法的利益」が設定されている。
「婚姻している者(既婚者)」が「婚姻していない者(独身者)」と比べて、これらの「諸々の法的利益」を得られる状態にあることは、「婚姻」の目的を達成するための手段として合理的な範囲内でのみ正当化することができるものである。
よって、「婚姻している者(既婚者)」が得ている「婚姻により生じる諸々の法的利益」の内容が、「婚姻」の立法目的を達成するための手段として不必要に過大なものとなっている場合には、「婚姻していない者(独身者)」との間で合理的な理由を説明することのできない差異を生じさせるものとして、憲法14条の「平等原則」に抵触して違憲となる。
その場合、その不必要に過大な「法的利益」に関する規定が個別に失効することによって、格差が是正されることになる。
ここでいう「原告ら」の個々人は「婚姻していない者(独身者)」であるから、「婚姻している者(既婚者)」が婚姻制度の立法目的を達成するための手段として不必要に過大な「法的利益」を得ている場合には、その不必要に過大な「法的利益」に関する規定が個別に失効することによって格差が是正されることになる。
しかし、その格差をもって「婚姻していない者(独身者)」である「原告ら」の個々人に対して「婚姻により生じる諸々の法的利益」を与えなければならないということになるわけではない。
この点に注意が必要である。
次に、「憲法24条」による審査の意味について検討する。
憲法24条は「婚姻」を定めており、これは「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた枠組みである。
そして、「生殖と子の養育」の趣旨から、一般的・抽象的にその間で自然生殖を想定することができる「男性」と「女性」の組み合わせを対象とするものであり、これに当てはまらない関係については、「婚姻」とすることはできない。
他にも、憲法24条は「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めており、この趣旨に当てはまらない場合には「婚姻」とすることはできない。
「同性間の人的結合関係」については、「婚姻」とすることはできないし、憲法24条の「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言が一夫一婦制(男女二人一組)を定めている趣旨を満たすものでもない。
そのため、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」としていないとしても、憲法24条に違反するということはない。
よって、その「婚姻」に含まれない関係について、「婚姻により生じる諸々の法的利益」が得られないことは当然予定されていることであり、このことをもって「憲法24条」に違反するということにはならない。
「憲法24条においても考慮されるべきことを否定する趣旨ではないと解される。」との部分について検討する。
これは「原告ら」が「憲法14条1項違反となると主張している。」ことについて、その「原告ら」の主張を「憲法24条においても考慮されるべきことを否定する趣旨ではないと解される。」のように別の条文に置き換えて検討を始めようとするものである。
しかし、ここでいう「原告ら」のような「同性間の人的結合関係」については、「婚姻」ではないし、「親子」や「親子」の関係を基本とした「兄弟」「姉妹」などでもないため「家族」にも含まれない。
そのため、「憲法24条」の「婚姻及び家族」の中に含まれるものではない。
ここでは「憲法24条においても考慮されるべきことを否定する趣旨ではないと解される。」のように述べて、「憲法24条」に関わる問題であることを前提としているが、そもそもここでいう「同性間の人的結合関係」については「憲法24条」の「婚姻及び家族」の中に含まれない。
よって、これを「憲法24条」を用いて審査することができる対象であるかのように考えている部分が誤りである。
「特に、家族に関する法制度の平等が問題となる場合においては、憲法14条1項と憲法24条2項の関係をどのように理解するかについては見解が分かれ得る問題であるとしても、両条項が保護しようとした法益に重なり合う部分が存することは否定できないと考えられるから、原告らが主張する重大な法的利益を享受できないことの違憲性については、憲法24条2項の問題ともなりうるものである。」との記載がある。
まず、「家族に関する法制度の平等が問題となる場合においては、」との部分について検討する。
この判決の事案である「同性間の人的結合関係」については、「婚姻」ではないし、「親子」や「親子」の関係を基本とした「兄弟」「姉妹」などでもないため「家族」にも当てはまらず、「家族に関する法制度」にも含まれない。
よって、この内容は「家族に関する法制度の平等が問題となる場合」には当たらないため、これに当てはまるかような前提で論じている部分が誤りである。
次に、「家族に関する法制度の平等が問題となる場合においては、憲法14条1項と憲法24条2項の関係をどのように理解するかについては見解が分かれ得る問題であるとしても、両条項が保護しようとした法益に重なり合う部分が存することは否定できないと考えられるから、」との部分について検討する。
これは「憲法14条1項」という「平等」に関わる条文を取り上げて「憲法24条2項」との関係を検討するものであるから、「憲法24条2項」の条文の中に記載されているいくつかの事柄の中でもとりわけ「両性の本質的平等」との関係を検討しようとするものと考えられる。
この関係について、「どのように理解するかについては見解が分かれ得る問題である」としているが、これは下記のようにまとめることができる。
◇ 「憲法14条1項」
「婚姻及び家族」の制度にかかわらず法制度全般に対して適用され、「両性」の間の「平等」以外の「平等」についても審査することが可能である。
◇ 「憲法24条2項」
「婚姻及び家族」の対象となっている場合にのみ適用されるものであり、その内容も「両性」の間の「平等」が問われる場合のみ審査を行うものである。
「両条項が保護しようとした法益に重なり合う部分が存することは否定できない」との部分について、その「重なり合う部分」とは、「婚姻及び家族」の対象となっている場合で、かつ「両性」の間の「平等」が問われる場合である。
この場合に、「憲法14条1項」の一般的な「平等」であることに対して、「憲法24条2項」の審査する「平等」の内容は、一般法と特別法の関係における特別法にあたると考える立場から、「憲法24条2項」の方が規律密度が高くなるとする見解が見られる。
ただ、これについて筆者は、「婚姻及び家族」の制度は、「生殖」に関わる問題が含まれており、これは自らの身体で子を産むことができるか否かなどの観点からもともと男女間で鮮明な違いが存在するため、その違いに基づいて男女間で差異を生じさせる不平等な立法が行われやすいという懸念があるため、特に注意的に定められているだけであるから、「憲法14条1項」よりも「憲法24条2項」の方が審査密度が高い(厳格)というわけではないと考えている。
つまり、筆者は「婚姻及び家族」の制度の内容の中で「両性」の間の「平等」が問われる場合には、「憲法14条1項」と「憲法24条2項」が「重なり合う部分」が存在するが、その審査密度が異なるということはなく、同じであると考えている。
三つ目に、「原告らが主張する重大な法的利益を享受できないことの違憲性については、憲法24条2項の問題ともなりうるものである。」との部分について検討する。
まず、「憲法24条2項」は「婚姻及び家族」を対象とするものであり、ここでいう「原告ら」の「同性間の人的結合関係」については「婚姻」ではないし、それが「親子」や「親子」の関係を基本とした「兄弟」「姉妹」などに当てはまらないのであれば「家族」にも含まれず、「憲法24条2項」は適用されない。
よって、このような「同性間の人的結合関係」について「憲法24条2項の問題ともなりうる」と述べている部分は誤りである。
そして、法律により具体化された現行の法律婚制度の概要は、前記⑵キで規定群を確認したとおりとなっており、両当事者及びその親族の身分関係を形成するとともに、戸籍制度によってその身分関係を公証し、民法及びその他の諸法令により、法律上、当事者間及びその他の第三者との間に様々な権利義務関係を生じさせるものとなっている。また、婚姻には、かかる法律上の効果にとどまらず、事実上の効果として、婚姻制度を利用することにより、社会的な信用が形成され、信任が得られるなどの社会的な効果のほか、そうした地位に立ったことによる精神的心理的効果をも生じさせるものである。異性カップルであれば、所定の要件を充たすことにより、法律婚制度の下で、法律上及び事実上の多彩な効果を一体のものとして享受することができる。
【筆者】
「法律により具体化された現行の法律婚制度の概要は、前記⑵キで規定群を確認したとおりとなっており、両当事者及びその親族の身分関係を形成するとともに、戸籍制度によってその身分関係を公証し、民法及びその他の諸法令により、法律上、当事者間及びその他の第三者との間に様々な権利義務関係を生じさせるものとなっている。」との記載がある。
「両当事者及びその親族の身分関係を形成するとともに、戸籍制度によってその身分関係を公証し、」との部分について検討する。
ここで「身分関係」とあるが、このように「身分関係」を明らかにする意味は、婚姻制度が「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するためである。
人間は有性生殖を行うことによって子孫を生むという身体機能を有しており、その男女の間で行われる「生殖」に関わって生じる不都合が社会的な課題となっていることから、「身分関係」を形成することによって、この問題の解決を図るのである。
そのため、この「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を切り離して「身分関係」を形成する意味を捉えることはできないことに注意が必要である。
「戸籍制度」についても、そのような目的との関係で形成されているものである。
「民法及びその他の諸法令により、法律上、当事者間及びその他の第三者との間に様々な権利義務関係を生じさせるものとなっている。」との部分について検討する。
これらの「権利義務関係」は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成するための手段として整合的な範囲で形成されるものであり、その目的との関係で整合的でないものについては、「法律婚制度」を利用していない者との間で合理的な理由のない差異を生じさせるものとなるから、正当化することはできない。
もともとこれらの「権利義務関係」の内容はこのような目的を離れて誰もが自由に形成することができるというものではないことを押さえる必要がある。
その他、「法律により具体化された現行の法律婚制度」との表現であるが、「法律婚制度」自体が「法律により具体化された」制度を指しているのであり、これに対して「法律により具体化された」の文言を加えることは同義反復となるため妥当でない。
そのため、「現行の法律婚制度」とするか、「法律により具体化された現行の婚姻制度」と表現することが妥当である。
「婚姻には、かかる法律上の効果にとどまらず、事実上の効果として、婚姻制度を利用することにより、社会的な信用が形成され、信任が得られるなどの社会的な効果のほか、そうした地位に立ったことによる精神的心理的効果をも生じさせるものである。」との記載がある。
ここでは「婚姻」には、「法律上の効果」と「事実上の効果」の二つがあると考えるものとなっている。
まず、「婚姻」は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度であり、ここでいう「法律上の効果」とは、その目的を達成するための手段として整合的な形で定められるものである。
次に、ここで「事実上の効果」としているものであるが、ここでは下記の二つを挙げるものとなっている。
「事実上の効果」と称するもの
◇ 社会的な信用が形成され、信任が得られるなどの社会的な効果
◇ そうした地位に立ったことによる精神的心理的効果
しかし、法律論として考えれば、婚姻制度を利用する者は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度を利用する者というだけであり、それ以外の何かを見出すことはできない。
もしそれ以外のものが見えているのであれば、それは法律論ではないことになる。
そのため、ここでは「婚姻制度を利用することにより、社会的な信用が形成され、信任が得られる」という「社会的な効果」が存在すると評価しているが、法律論ではないということができる。
このような評価は、この判決を書いた裁判官の個人的な認識として、「婚姻制度を利用している者(既婚者)」を「社会的な信用が形成され」ており「信任」することができる存在と見なし、「婚姻制度を利用していない者(独身者)」については「社会的な信用が形成」されておらず「信任」することのできない存在であると見なしているだけである。
この判決を書いた裁判官が「婚姻制度を利用している者(既婚者)」である場合には、自分自身は「婚姻制度を利用すること」によって「社会的な信用が形成され、信任が得られる」ようになったと考えていることを述べていることになるが、それは「婚姻制度を利用している者(既婚者)」の思い上がりというものである。
もしこの判決を書いた裁判官が「婚姻制度を利用していない者(独身者)」であるならば、「婚姻制度を利用している者(既婚者)」に対して「社会的な信用が形成」されており「信任が得られ」た存在であるかのように見なす必要はなく、自分自身について「社会的な信用が形成」されておらず「信任が得られ」ていないなどと卑下する必要はない。
謙虚な姿勢をもって物事に向き合うことが必要となる場合もあるかもしれないが、そのような個人的なスタンスを法律論の中に持ち込むことになっては、判断を誤ることになる。
また、そもそも法制度は政策的なものであることから、その制度の存在そのものに対して賛否があるのであって、当然、婚姻制度を廃止するべきと考えている者もいる。
婚姻制度を廃止するべきと考えている者からすれば、「婚姻制度を利用している者(既婚者)」を「信用」することはできず「信任」しないという場合もあるはずである。
よって、様々な考え方や立場が存在し、様々な評価がなされる制度に対して、それを利用した場合に「社会的な信用が形成され、信任が得られる」などと、特定の価値観に基づいた評価を持ち出して論じようとすることは妥当でない。
日本国内には「婚姻制度を利用していない者(独身者)」として生活している者がいるのであって、その者たちが「社会的な信用が形成され」ておらず「信任が得られ」ない者であるかのような前提の下に論じていること自体が誤った判断である。
「そうした地位に立ったことによる精神的心理的効果をも生じさせるものである。」との部分について検討する。
この「そうした地位」というのは、上記の「社会的な信用が形成され、信任が得られる」の部分を指すものである。
しかし、法律論として見れば、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度を利用しているというだけのことであり、それ以外の何かを見出しているのであれば、それは法律論ではなく、特定の宗教団体が信者を評価する際に用いている別の基準か何かであると考えられる。
そして、「そうした地位」に立つと「精神的心理的効果」を「生じさせる」と考えているようであるが、これも法律論としては関係ないものである。
日本国内には「婚姻していない者(独身者)」として生活している者がいるのであって、法制度を論じる際に「婚姻している者(既婚者)」のグループを持ち上げるような言説を前提にして論じるべきではない。
「異性カップルであれば、所定の要件を充たすことにより、法律婚制度の下で、法律上及び事実上の多彩な効果を一体のものとして享受することができる。」との記載がある。
「異性カップル」との部分であるが、法律論として考える場合には、「権利能力」を有して法主体としての地位を認められている個々の自然人が、制度を利用することができるか否かという視点で考える必要があり、「カップル」という「二人一組」を前提として論じることはできない。
よって、「法律婚制度」を利用することができるか否かを検討する際には、「二人一組」を基にして検討するのではなく、個々人を基にして検討することが必要である。
そのことから、個々の自然人が「法律上」の「効果を一体のものとして享受すること」ができるか否かを論じることが適切であり、ここで「カップル」という「二人一組」が「法律上」の「効果を一体のものとして享受すること」ができるか否かを論じていることは誤りである。
「事実上の多彩な効果」と称するものについては、上記で述べたように、法律論ではない。
この段落は読み取りづらいものとなっているが、内容を整理すると下記のようになる。
=======================================
「異性カップルであれば、所定の要件を充たすことにより、法律婚制度の下で、法律上及び事実上の多彩な効果を一体のものとして享受することができる。」
◇ 法律上の効果
「法律により具体化された現行の法律婚制度の概要は、前記⑵キで規定群を確認したとおりとなっており、両当事者及びその親族の身分関係を形成するとともに、戸籍制度によってその身分関係を公証し、民法及びその他の諸法令により、法律上、当事者間及びその他の第三者との間に様々な権利義務関係を生じさせるものとなっている。」
◇ 事実上の効果
「婚姻制度を利用することにより、社会的な信用が形成され、信任が得られるなどの社会的な効果のほか、そうした地位に立ったことによる精神的心理的効果をも生じさせるものである。」
=======================================
しかし、このようにまとめても内容が誤っていることは変わらない。
「カップル」という「二人一組」を前提に比較を試みることは誤りであり、「権利能力」を有し法主体としての地位を認められている個々の自然人が制度を利用することができるか否かによって論じる必要がある。
「事実上の効果」と称するものは法律論ではない。
他方、同性カップルは、本件諸規定が、同性カップルに対して法律婚制度の利用を認めず、他にこれを認める法令の規定が存しないことにより、法制度の下で、法律上及び事実上の多彩な効果を一体のものとして享受することができない状態となっており、異性カップルとの間に著しい乖離が生じている。同性カップルは、自然生殖の可能性が存しないという点を除けば、親密な関係に基づき永続性をもった生活共同体を構成しうるという実態において、異性カップルと何ら異なるところはなく(原告ら本人、弁論の全趣旨)、現在の医学心理学の知見によれば、性的指向及び性自認は、ほとんどの場合、人生の初期又は出生前に決定され、自らの意思や精神医学的な療法によって変更されるものではないとされている(認定事実⑴ア)点に照らせば、同性カップルが上記の状態に置かれている点が憲法上是認されるかどうかは、なお検討を要するというべきである。
【筆者】
「同性カップルは、本件諸規定が、同性カップルに対して法律婚制度の利用を認めず、他にこれを認める法令の規定が存しないことにより、法制度の下で、法律上及び事実上の多彩な効果を一体のものとして享受することができない状態となっており、異性カップルとの間に著しい乖離が生じている。」との記載がある。
ここでは「同性カップル」と「異性カップル」を取り上げて比較するものとなっている。
しかし、法律論上で比較することのできる対象は、「権利能力」を有して法主体としての地位を認められている者同士の間だけである。
そして、その法的な主体となることができるのは「自然人」と「法人」があるが、ここでいう「カップル」という「二人一組」の人的結合関係については、「自然人」ではないし、「法人」としての「権利能力」を取得していないのであれば「法人」ということもできない。
つまり、法的には、ここでいう「カップル」という「二人一組」を取り上げて比較して論じることはできない。
そのため、その「二人一組」については、法的な主体として認められている個々の「自然人」が人的結合関係を形成している状態として認識することが必要である。
そして、何かを比較するとしても、それはその「権利能力」を有して法主体としての地位を認められている個々の自然人が「法律婚制度」を利用することができるか否かという視点で捉えることが必要である。
そこで、「本件諸規定が、」「法律婚制度の利用を認めず、」としているか否かであるが、その個々の自然人については、婚姻制度(男女二人一組)の要件に従っているのであれば、適法に制度を利用することができることから、「法律婚制度の利用」は認められている。
そのため、「本件諸規定が、」「法律婚制度の利用を認めず、」と述べている部分は誤りとなる。
また、「法制度の下で、法律上」の「効果を一体のものとして享受することができない状態となっており、」との部分についても、「法律婚制度の利用」が認められていることから、「享受すること」は可能であるため、「法制度の下で、法律上」の「効果を一体のものとして享受することができない状態」となっているとの評価も誤りである。(『事実上の多彩な効果』と称してるものは、法律論ではないためここでは取り上げない。)
「著しい乖離が生じている。」との部分についても、個々人について「法律婚制度の利用」は認められていることから、「著しい乖離が生じている。」との事実は存在せず、誤りとなる。
これとは別に、「異性間の人的結合関係」が「法律婚制度」の対象となっており、「同性間の人的結合関係」が「法律婚制度」の対象となっていないことについて検討する。
まず、「婚姻」は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた枠組みである。
これは、その間で一般的・抽象的に自然生殖を想定することができる「男性」と「女性」の組み合わせに対して「貞操義務」を設けるなど一定の形式で法的に結び付け、子供が産まれた場合にその父親を特定することができる仕組みとなる状態を推進し、立法目的の実現を目指すものとなっている。
そのため、婚姻制度の対象となる場合とならない場合との間で差異を設け、子を持つことを望む者が婚姻制度を利用する形で子を持つに至るようにインセンティブを与えようとするものであるから、もともと「法律婚制度」の対象とならない場合があることは当然のことである。
「法律婚制度」の対象となっていない組み合わせについては、「近親者との人的結合関係」、「三人以上の人的結合関係」、「婚姻適齢に満たない者との人的結合関係」、「同性間の人的結合関係」を挙げることができる。
これらの組み合わせは、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的との関係で「婚姻」とすることができないもの(『法律婚制度』の対象とはならないもの)である。
これについて「法律上」の「効果を一体のものとして享受することができない状態」を「著しい乖離が生じている。」と考えることができるかについて検討する。
憲法は「個人の尊厳」の原理に基づいており、自然人は「個人主義」の下に各々「自律的な個人」として生存していくことを予定していることから、「婚姻していない者(独身者)」の状態で既に完全な状態であり、その状態が基準(スタンダード)となるべきものである。
そのような中で、「婚姻している者(既婚者)」が婚姻制度の立法目的を達成するための手段として不必要に過大な優遇措置を得るものとなっており、「婚姻していない者(独身者)」との間にここでいう「著しい乖離が生じている。」場合には、その過大な優遇措置に関する規定が14条の「平等原則」に抵触して違憲となり、その過大な優遇措置に関する規定が個別に失効することによって格差が是正されることになる。
よって、「法律婚制度」を利用している者と「法律婚制度」を利用していない者との間に何らかの差異があるとしても、「法律婚制度」を利用している者の得ている優遇措置が減らされる方向で差異が是正されることになるのであり、「法律婚制度」を利用している者が得ている優遇措置の内容に合わせる形で、「法律婚制度」の対象とはならない者に対してまで優遇措置を与えなければならないということにはならない。
この点に注意が必要である。
ここでは「カップル」という「二人一組」のみを取り上げて論じているものとなっている。
しかし、人的結合関係の中には「三人一組」や「四人一組」など、「三人以上の人的結合関係」も存在するのであり、それを取り上げることもせずに「二人一組」の人的結合関係だけを取り上げて論じればそれで済むかのような説明となっていることは、なぜ「二人一組」だけを取り上げるのかその根拠を説明しないままに論じる「カップル信仰論」に陥っている。
「同性カップルは、自然生殖の可能性が存しないという点を除けば、親密な関係に基づき永続性をもった生活共同体を構成しうるという実態において、異性カップルと何ら異なるところはなく(…)、現在の医学心理学の知見によれば、性的指向及び性自認は、ほとんどの場合、人生の初期又は出生前に決定され、自らの意思や精神医学的な療法によって変更されるものではないとされている(…)点に照らせば、同性カップルが上記の状態に置かれている点が憲法上是認されるかどうかは、なお検討を要するというべきである。」(カッコ内省略)との記載がある。
「同性カップルは、自然生殖の可能性が存しないという点を除けば、親密な関係に基づき永続性をもった生活共同体を構成しうるという実態において、異性カップルと何ら異なるところはなく」との部分について検討する。
ここでは「同性カップル」と「異性カップル」のように「カップル」という「二人一組」を取り上げて比較するものとなっている。
しかし、法律論として比較することができるのは「権利能力」を有して法主体としての地位を認められている者同士の間だけである。
ここでいう「カップル」という「二人一組」については、「自然人」ではないし、「法人」としての地位を取得しているものでもないため、「権利能力」を有しておらず法主体としての地位を認められていない。
そのため、この「カップル」という「二人一組」を取り上げて比較を行おうとしている部分は誤りである。
次に、「親密な関係に基づき永続性をもった生活共同体を構成しうるという実態」との部分について検討する。
「婚姻」は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、一般的・抽象的にその間で自然生殖を想定することができる「男性」と「女性」の組み合わせに対して「貞操義務」など一定の形式で法的に結び付け、それに対して法的効果や一定の優遇措置を与えることによって、その目的の実現を目指すものとして設けられている。
そのため、この「婚姻」の対象となるか否かは、ここでいう「親密な関係に基づき永続性をもった生活共同体を構成しうるという実態」であるか否かによって決まるものではない。
よって、「親密な関係に基づき永続性をもった生活共同体を構成しうるという実態」を取り上げることによって、婚姻制度に設定されている法的効果や一定の優遇措置の内容を得られるかのような前提で検討することは誤りである。
「何ら異なるところはなく」との部分であるが、「婚姻」は、社会の中に様々な人的結合関係が存在することを前提とした上で、その中から「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられている枠組みであり、一般的・抽象的にその間で「自然生殖の可能性」が有るか無いかは「婚姻」という概念の意味を定めるための根本的で不可欠の要素である。
よって、この点を切り離してその他の部分に「異なるところ」がないと強調したとしても、そもそもそのような人的結合関係とは区別する意味で「婚姻」が設けられている以上は、一般的・抽象的な「自然生殖の可能性」のない組み合わせを「婚姻」の中に含めることはできない。
「現在の医学心理学の知見によれば、性的指向及び性自認は、ほとんどの場合、人生の初期又は出生前に決定され、自らの意思や精神医学的な療法によって変更されるものではないとされている(…)点に照らせば、」との部分について検討する。
まず、「婚姻及び家族」の制度は、「性愛」の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いをする制度ではないし、「性愛」に基づいて制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもない。
また、法制度を立法する際には内心に中立的な内容でなければならないのであり、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかという「性的指向」と称するものを審査して区別取扱いを行ってはならない。
よって、「性的指向及び性自認」のような個人の内心にのみ存在する心理的・精神的なものを持ち出して、それに基づく形で法制度を立法することが可能であることを前提として法制度の存否を検討しようとしていること自体が誤りである。
また、「性的指向及び性自認は、ほとんどの場合、人生の初期又は出生前に決定され、自らの意思や精神医学的な療法によって変更されるものではないとされている」との説明についても、研究の中には「性的指向及び性自認」は後天的に形成されるとする立場や、「自らの意思や精神医学的な療法によって変更」することが可能であるとする立場も存在しており、それらを一方的に排してここで述べるような特定の立場を支持することを前提として、それに基づいて法規範の意味を論じようとすることも妥当でない。
もちろん、他者が本人の意思に反して無理やり「変更」させようとするようなことがあってはならないことは言うまでもない。
そのような他者が本人の意思に反して無理やり「変更」させようと強制するような事情がある場合には、それを行うことが妥当でないことを説明するために、「人生の初期又は出生前に決定され、自らの意思や精神医学的な療法によって変更されるものではない」という見解が必要とされ、そのような研究結果が強調される場合がある。
しかし同時に、本人が自らの意思で「変更」したいと望んだ場合には、「人生の初期又は出生前に決定され」るとは限らず、「自らの意思や精神医学的な療法」によって「変更」することも可能であるとする見解が必要とされることがあり、そのような研究結果が強調されるという場合もまたあり得るところである。
この判決でも「1 認定事実」の「⑴ 性的指向等に関する知見」の「イ 欧米諸国における知見の変遷」の「20世紀中頃以降の知見」の部分で、「「自らの性的指向に悩み、葛藤し、変えたいと望む」同性愛者」について触れており、これは実際に「変えたい」と望む者がいることを明らかにするものといえる。
もしその者が「自らの意思」で変えたいと望むのであれば、その可能性もまた開かれるのである。
そのため、これら内心における心理的・精神的な研究については、本来的に物理的な事象について外部から観測する場合のように誰もが共通の認識に至ることができるというような意味での客観性を有するものではなく、もともと様々な見解が存在しており、それを一つの見解に絞ることができるわけではないし、一つの見解に絞ることが適切であるともいえないものである。
そして、特定のグループや個人は、自己の置かれている事情の中で、そこで生じている課題を解決することを目的として、それらの様々な見解の中から特定の見解を引き出して論じている状況にあるというものである。
よって、人の内心にのみ存在する心理的・精神的なものについては、物理的に知覚することのできるものとは異なり、もともと外観から観測することによって誰もが共通した認識を持つことができるという意味での客観性を認めることができるものではないのであり、このような事柄に対して裁判所が特定の見解を拾い上げて支持・不支持を表明することは適切ではない。
また、このような「性的指向」と称しているものの性質についての見解の当否を前提としなければ判断を行うことができないような場合(つまり、『性的指向』と称しているものの性質について特定の立場に基づかなければ、この判決で述べられている論旨を正当化することができない場合)には、そもそも法令を適用することによって終局的に解決することができる問題であるとはいえないため、裁判所法3条の「法律上の争訟」の範囲を超えるものである。
よって、この判決が「性的指向及び性自認は、ほとんどの場合、人生の初期又は出生前に決定され、自らの意思や精神医学的な療法によって変更されるものではないとされている」という特定の見解を採用した上で、その特定の見解に基づく形で判断を行っていることは、裁判所法3条の「法律上の争訟」の解釈を誤ったものであり、結果として「司法権の範囲」を超えることになるため違法である。
この点については、上記「1 認定事実」の「⑴ 性的指向等に関する知見」の「ア 現在の知見」の部分でも解説している。
【参考】事実の存否、個人の主観的意見の当否、学術・技術上の争い 2006年04月14日
「同性カップルが上記の状態に置かれている点が憲法上是認されるかどうかは、なお検討を要するというべきである。」との部分について検討する。
まず、「同性カップル」の部分について検討する。
憲法は「個人の尊厳」の原理に基づいており、「個人主義」を採用するものとなっている。
そのため、ここでいう「同性カップル」については、法的な主体としての視点で見れば、一人一人として扱うことが必要となる。
また、民法上の法主体には「自然人」と「法人」があり、自然人の場合は出生によって「権利能力」を取得し、死亡することによって「権利能力」が消滅する。
民法
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第二章 人
第一節 権利能力
第三条 私権の享有は、出生に始まる。
2 外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
自然人 Wikipedia
法人 Wikipedia
人の始期 Wikipedia
権利能力 Wikipedia
ここでいう「同性カップル」は自然人の集まりであるから、それぞれ「個人」として「権利能力」の主体となっている。
そのため、法律論上では、「同性カップル」のように「二人一組」をまとめて一つの単位として扱うことはできず、個人と個人が人的結合関係を形成している状態として扱うことが必要である。
そして、その法的な主体としての地位を有する個々人について、「上記の状態に置かれている」といえるか否かであるが、「法律婚制度の利用」は認められているし、ここでいう「法制度の下で、法律上及び事実上の多彩な効果を一体のものとして享受すること」はできる状態といえることから、何らの「乖離」も生じていない。
よって、「法制度の下で、法律上及び事実上の多彩な効果を一体のものとして享受することができない状態」であることを前提として、「憲法上是認されるかどうか」について検討しようとしている部分が誤りである。
次に、「憲法上是認されるかどうか」の部分であるが、この「⑶ 憲法24条2項に違反するかについて」の項目で問われているのは、24条2項の「婚姻及び家族」が、「夫婦」や「親子」、「親子」の関係を基本とした「兄弟」「姉妹」などに含まれない人的結合関係を対象とする制度を立法することを「要請」しているか否かであり、ここでいうような比較を基にして「是認されるかどうか」を論じるものではない。
そのため、このような比較を基にする形で「憲法上是認されるかどうか」を検討しようとしている部分は、誤りである。
そして、憲法24条2項は、婚姻のほか、「家族」についても、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚した立法の制定を要請している。家族という概念は、憲法でも民法でも定義されておらず、その外縁は明確ではなく、社会通念上は、多義的なものである。上記のとおり、同性カップルにおいても、親密な関係に基づき永続性をもった生活共同体を構成しうることは、異性カップルと何ら異ならないのであるから、同性カップルの関係性について、家族の問題として検討することは十分に可能なはずである。同項は、「両性の本質的平等」との文言を用いているが、家族の問題については、例えば、家督相続制度の復活の是非を取り上げれば、両性間のみならず同性間の平等も問題となりうるのであり、「両性」の文言を「両当事者」と読み替えるまでもなく、同項は、両性が必ずしも関わらない家族の問題をも含めて規律していると理解することができると解される。
【筆者】
「憲法24条2項は、婚姻のほか、「家族」についても、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚した立法の制定を要請している。」との記載がある。
ここで述べられていることは、「憲法24条2項」に記されている「婚姻及び家族」の枠組みに従う形で定められた法律上の具体的な制度について「個人の尊厳」と「両性の本質的平等」を満たすものとなるように求め、国会の立法裁量の限界を画するものということである。
ただ、下記の意味とは異なることに注意が必要である。
まず、この「憲法24条2項」の「個人の尊厳」や「両性の本質的平等」の文言を根拠として、同じく「憲法24条2項」で定められている「婚姻及び家族」の枠組みそのものを変更することはできない。
そのため、この「個人の尊厳」や「両性の本質的平等」の文言によって、「憲法24条2項」の「婚姻及び家族」の枠組みの「要請」している内容そのものが変わることはなく、その「要請」に従って設けられる法律上の「婚姻及び家族」の制度の人的結合関係の枠組みそのものにも何らの影響を与えるものではない。
そのため、この「個人の尊厳」や「両性の本質的平等」の文言が存在することによって、もともと「婚姻及び家族」の枠組みの対象となっていない人的結合関係までをも「婚姻及び家族」の制度の中に含めなければならないということにはならない。
これは、「婚姻及び家族」の枠組みは、「婚姻」や「家族」という概念そのものであることによる内在的な限界が存在するにもかかわらず、その内在的な限界を超える人的結合関係をその中に含めようとした場合には、そもそも「婚姻」や「家族」の枠組みを設けることによって達成しようとしている目的を達成することができない状態に陥り、「婚姻及び家族」の枠組みそのものが破壊されることになるからである。
しかし、この「⑶ 憲法24条2項に違反するかについて」の項目は、結論として「ク」の第一段落の最後の部分で「上記の状態を継続し放置することについては、もはや、個人の尊厳の要請に照らして合理性を欠くに至っているものといわざるを得ず、国会の立法裁量の範囲を超えるものとみざるを得ないような場合に当たるというべきである。」と述べ、第二段落で「したがって、本件諸規定は、同性カップルに対して、その関係を国の制度によって公証し、その関係を保護するのにふさわしい効果を付与するための枠組みすら与えていないという限度で、憲法24条2項に違反するものである。」と述べている。
これは、「憲法24条2項」の「婚姻及び家族」の枠組みが「要請」している内容については、同じく「憲法24条2項」に定められている「個人の尊厳」の文言を用いて変更することはできないにもかかわらず、これを行うことができることを前提に「憲法24条2項」の「婚姻及び家族」の枠組みが「要請」している内容を変更した上で、その変更された「要請」に従う形で法律が定められていないことについて「憲法24条2項に違反するものである。」と述べるものとなっている。
このことは、「憲法24条2項」の「婚姻及び家族」の枠組みの「要請」する内容を同じく「憲法24条2項」に定められている「個人の尊厳」の文言によっていかようにも書き替えることができることを前提とするものであり、そもそも「個人の尊厳」の文言を適用することのできる対象の範囲(射程)を定めている「婚姻及び家族」の枠組みを内側から破壊しようと試みるものであり、解釈の手続きとして誤っている。
(その他、「婚姻及び家族」の概念が有する内在的な限界を考慮しない点でも誤りである。)
また、そもそもこの「ク」の第一段落の最後の部分で述べている「個人の尊厳の要請に照らして合理性を欠くに至っているものといわざるを得ず、国会の立法裁量の範囲を超えるものとみざるを得ないような場合」という基準は、「ウ」で示している「夫婦同氏制大法廷判決」の基準を用いようとするものであるが、この「夫婦同氏制大法廷判決」は、「憲法24条2項」の「婚姻及び家族」の枠組みに従って立法されている法律上の具体的な制度の内容が「個人の尊厳」を満たすものとなるか否かが問われている事例であり、この「個人の尊厳」を満たすか否かの基準を用いることができる事例とは、法律上の具体的な制度が存在することが前提となっている。
それに対して、この名古屋地裁判決で問われているのは、「憲法24条2項」の「婚姻及び家族」の枠組みが「要請」している内容であり、その「夫婦同氏制大法廷判決」とは事案が異なっている。
よって、「憲法24条2項」の「婚姻及び家族」の枠組みが「要請」しているか否かが問われており、「要請」がされていると判断された場合においてのみ「国会」の立法不作為が「憲法24条2項に違反する」ことになる事案に対して、「夫婦同氏制大法廷判決」の示した、法律上の具体的な制度が存在することを前提として、その制度の内容が「個人の尊厳」に照らして「合理性」を有するか否かが判断され、「国会の立法裁量の範囲を超えるものとみざるを得ないような場合」に当たるか否かが決まるという場合の基準を用いて結論を導き出すことができるかのように論じていること自体が誤りである。
以上から、ここで「憲法24条2項は、婚姻のほか、「家族」についても、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚した立法の制定を要請している。」と述べている部分は、文そのものの意味としてはその通りであるといえるとしても、その文意を上記のような意味で用いることはできないことに注意する必要がある。
「家族という概念は、憲法でも民法でも定義されておらず、その外縁は明確ではなく、社会通念上は、多義的なものである。」との記載がある。
この判決では、「家族という概念は、憲法でも民法でも定義されておらず、その外縁は明確ではなく、」と考えているようなので、24条2項の「婚姻及び家族」の枠組みと、その中の「家族」の枠組みについて、下記で詳しく検討する。
■ 「婚姻」と「家族」はそれ以外の概念ではないこと
「婚姻」や「家族」である以上は、「サークル」「部活」「組合」「雇用」「会社」「町内会」「宗教団体」「政党」など他の様々な人的結合関係とは異なる概念である。
当然、これは「意思表示」「代理」「物権」「即時取得」「売買」など、それとは別の概念を示すものでもない。
このように、「婚姻」や「家族」という概念が用いられている以上は、その概念そのものが有する意味を離れることはできないのであり、その概念が有する意味に拘束されることになる。
よって、「婚姻」や「家族」として扱うことができる範囲には、「婚姻」や「家族」という概念であることそのものによる内在的な限界が存在する。
言い換えれば、「婚姻」や「家族」という言葉それ自体を別の意味に変えてしまうことはできないのであり、これらの言葉に対して、その概念に含まれている内在的な限界を超える意味を与えることが解釈として可能となるわけではない。
もしその概念が有する内在的な限界(意味の範囲)を超える形で新たな枠組みを設けることを望む場合には、解釈によって導き出すことのできる範囲を超えることになるから、その規定を改正して文言を変更するか、その規定そのものを廃止することが必要となる。
■ 「婚姻」と「家族」は異なる概念であること
24条2項には「婚姻及び家族」と記載されている。
ここから分かることは、「婚姻」と「家族」はそれぞれ異なる概念であるということである。
このことから、下記の内容が導かれる。
〇 第一に、「婚姻」と「家族」を同一の概念として扱うことはできない。
〇 第二に、「婚姻」の概念を「家族」の概念に置き換えることや、「家族」の概念を「婚姻」の概念に置き換えることはできない。
〇 第三に、「婚姻」や「家族」という言葉の意味によって形成されている概念の境界線を取り払うことはできない。
〇 第四に、「婚姻」や「家族」という言葉の意味の範囲をどこまでも拡張することができるというものではない。
このように、「婚姻」と「家族」という文言が使われていることそのものによって、これを解釈する際に導き出すことのできる意味の範囲には内在的な限界がある。
それぞれの言葉には一定の意味があり、その意味そのものを同じものとして扱ったり、挿げ替えたり、混同したり、無制限に拡張したりすることはできないからである。
そのため、もし下記のような法律を立法した場合には、24条2項の「婚姻及び家族」の文言に抵触して違憲となる。
① 「婚姻」と「家族」の意味を同一の概念として扱うような法律を立法した場合
② 「婚姻」の意味と「家族」の意味を置き換えるような法律を立法した場合
③ 「婚姻」や「家族」の概念の境界線を取り払うような法律を立法した場合
④ 「婚姻」や「家族」という言葉の意味の範囲をどこまでも拡張することができることを前提とした法律を立法した場合
■ 「婚姻」と「家族」は整合的に理解する必要があること
24条2項の「家族」とは、法学的な意味の「家族」を指すものである。
そのため、社会学的な意味で使われる「家族」のように、どのような意味としてでも自由に用いることができるというわけではない。
24条2項には「婚姻及び家族」と記載されており、これら「婚姻」と「家族」の文言は、一つの条文の中に記されている。
24条2項では「A、B、C、D、E 並びに F」の形で順を追って説明するものとなっており、その中で「婚姻及び家族に関するその他の事項」が一つのまとまりとなっている。
この点で、「婚姻」と「家族」という二つの概念はまとめる形で定められている。
そして、「家族」の文言は、「婚姻及び家族」のように「婚姻」の文言のすぐ後に続く形で、「婚姻」と共に記されている。
そのことから、「家族」の概念は、「婚姻」の概念と結び付くものとして定められており、これらは切り離すことのできるものではない。
よって、「婚姻」と「家族」の意味を解釈する際には、それぞれの概念をまったく別個の目的を有した相互に関わり合いのない枠組みであるかのように考えることはできず、それらを整合的に読み解くことが求められる。
24条2項の「婚姻及び家族」の文言は、1項で「婚姻」について既に定められていることを前提として、それに続く形で「家族」についても触れるものとなっている。
そのため、「家族」の概念は「婚姻」を中心として定められる枠組みであることは明らかである。
これについて、国(行政府)は下記のように説明している。
◇ 「同項における立法上の要請及び指針は、形式的にも内容的にも、同条1項を前提とすることが明らかである。」
◇ 「このように、憲法24条2項が、同条1項の規定内容を踏まえ、これを前提として定められていることは、同条2項の内容面からしても明らかである。」
【東京一次・第1回】控訴答弁書 令和5年6月23日 PDF
国(行政府)は最高裁判決の記述も示している。
【東京二次・第9回】被告第7準備書面 令和5年9月28日 PDF (P14)
■ 「婚姻及び家族」の内在的な限界
「家族」の枠組みを検討するために、初めに、「婚姻」の目的と、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす枠組みから検討する。
▼ 「婚姻」の概念に含まれる内在的な限界
「婚姻」は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的とした形成された枠組みである。
これは、下記のような経緯によるものである。
その社会の中で何らの制度も設けられていない場合には、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合が発生する。
例えば、「父親不明」の子供が増える、父親を特定できない子供が増える、父親が蒸発して行方不明になった子供が増える、それらにより「子の福祉」が減少する、父親を特定できないことにより近親者の範囲を把握できずに「近親交配」に至り潜性遺伝子の発現した個体が高い確率で生じるようになる、一部の強者が多数人との生殖関係を独占することによって社会の中で「子を持ちたいと希望して相手を見つけようとする男女」の数の不均衡が生じて「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」が生まれる、低年齢での妊娠・出産により母体に危険が及ぶ、などの問題が生じることがある。
これらの不都合を解消するために、下記のような立法目的を有する枠組みを設けることが必要となる。
・「子の福祉」が実現される社会基盤を構築すること
・潜性遺伝子の発現した個体が高い確率で生じることを抑制すること
・「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」を減らすこと
・母体を保護すること
そして、これらの目的を達成するためには、下記の要素を満たす枠組みを設けることが必要となる。
・子の遺伝的な父親を特定できる組み合わせとすること
・特定された子の父親にも子に対する責任を担わせること
・特定された子の父親を基に遺伝的な近親者を把握すること
・未婚の男女の数の不均衡を防止できる組み合わせに限定すること
これらの要素を満たすものとして「一人の男性」と「一人の女性」が選び出され、その間に「貞操義務」を設け、その関係を法的に結び付ける形を「婚姻」と呼んでいる。
そして、この制度を利用した場合には一定の法的効果や優遇措置があるという差異を設けることによって、この制度を利用する者を増やし、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成することを目指すものとなっている。
このような「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解決しようとする目的を離れて「婚姻」を観念することはできない。
そのため、「婚姻」である以上は、これらの目的を達成することを阻害する組み合わせを「婚姻」とすることはできないという内在的な限界がある。
また、24条の「婚姻」は、「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めている。
これについても、上記の要素を満たす枠組みとして定められているものである。
よって、「婚姻」の中に含めることのできる人的結合関係の範囲は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成するための手段として整合的な上記の要素を満たす範囲に限られる。
▼ 「家族」の概念に含まれる内在的な限界
次に、「家族」の枠組みを検討する。
▽ 「婚姻」と「家族」の整合的な理解
上で述べたように、「家族」の枠組みは、「婚姻」という枠組みが存在することを前提としており、「婚姻」の枠組みから切り離して独立した形で存在することはできない。
そのため、もし「婚姻」の枠組みが有している目的の実現を「家族」の枠組みが阻害するものとなっている場合、「婚姻」と「家族」は同一の条文の中に記された文言であるにもかかわらず、その間に矛盾・抵触が生じていることとなり、その意味を整合的に読み解くことができていないことになるから、解釈の方法として妥当でない。
そのことから、「家族」の枠組みは、「婚姻」の枠組みが有している目的を達成することを阻害するような形で定めることはできず、「婚姻」の枠組みが有している目的との整合性を切り離して考えることはできない。
これにより、「婚姻」と「家族」は、同一の目的を共有し、その同一の目的に従って相互に矛盾することなく整合性を保った形で統一的に形成される枠組みということになる。
よって、「家族」の枠組みは、「婚姻」の立法政策に付随して同一の目的を共有し、「婚姻」の枠組みと結び付く形で位置付けられることになる。
▽ 「家族」の枠組み
「家族」の枠組みは、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として設けられた「婚姻」の枠組みと結び付いて定められている。
そのため、「家族」の枠組みは、「婚姻」の目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす枠組みが存在することを前提として、その「婚姻」と同一の目的を共有する形で、かつ、その「婚姻」の枠組みとの間で矛盾しない形で、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす形で定められることになる。
「婚姻」とするためには、下記の要素を満たすことが必要である。
・子の遺伝的な父親を特定できる組み合わせとすること
・特定された子の父親にも子に対する責任を担わせること
・特定された子の父親を基に遺伝的な近親者を把握すること
・未婚の男女の数の不均衡を防止できる組み合わせに限定すること
そして、「家族」の枠組みは、「婚姻」と同一の目的を共有し、この「婚姻」の枠組みと矛盾しない形で、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす形で定められることになる。
そのことから、「家族」とするためには、下記の要素を満たすことが必要である。
・「婚姻」と「家族」は異なる概念であること
・「婚姻」と同一の機能を「家族」の概念に担わせることはできないこと
・「生殖」を推進する関係は「婚姻」している夫婦の間に限られること
・「貞操義務」は夫婦の間に限られること
・夫婦以外の関係の間で「生殖」を推進する作用を生じさせないこと
・「生殖」によって子が生じるという生命活動の連鎖による血筋を明らかにすることが骨格となること
・「生殖」によって生じた子とその親による「親子」の関係を規律すること
・遺伝的な近親者とは「婚姻」することができないこと
これらの要素により、「家族」の中に含めることのできる人的結合関係と、含めることのできない人的結合関係が区別されることになる。
このように、「婚姻」が「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的としている以上は、その「婚姻」の目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす枠組みとの関係で、「家族」の枠組みも自ずと明らかとなる。
このことより、「家族」の中に含めることのできる人的結合関係の範囲は、「家族」という概念であることそれ自体による内在的な限界がある。
そのため、もし上記の要素を満たさない人的結合関係を「家族」の中に含めようとする法律を立法した場合には、24条2項の「家族」の文言に抵触して違憲となる。
∵ 「家族」の範囲
上記のように、「家族」は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として「婚姻」という枠組みが設けられていることを前提として、その立法政策に付随する形で同一の目的を共有し、その目的を達成するための手段として設けられる枠組みである。
そのため、「家族」の枠組みは、「生殖」によって「子」が生まれるという生物学的な因果関係を離れて観念することはできない。
よって、「家族」の中に含まれる人的結合関係の範囲は、下記の順に決まることになる。
① 婚姻している「男性」と「女性」の関係 (夫婦)
② 婚姻している「母親」から産まれた「子」とその「夫婦」との関係 (親子)
③ 婚姻していない「母親」から産まれた「子」とその「母親」との関係 (親子)
④ 婚姻している「母親」から産まれた「子」であるが、その「母親」の「夫」に嫡出否認された場合の「子」とその「母親」との関係 (親子)
⑤ 「子」の「父親」であると認知した者との関係〔あるいは『子』の親権を得た『父親』との関係〕 (親子)
このように、婚姻している「夫婦」と、自然生殖の過程を経て生まれてくる「子」とその「親」との関係を規律する「親子」による枠組みを骨格として範囲が決まることになる。
これは、「自然血族」である。
これらの関係が「家族」となるのは、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的によって「婚姻」という枠組みが設けられており、その「婚姻」と同一の目的を共有する形で、生物学上の血のつながりを持つ親子関係を明確にすることを意図した統一的な枠組みといえるからである。
⑥ 「自然血族」の「親子」の関係に擬制して位置付けられる「養子縁組」による「親子」の関係
自然生殖によって生じる「親子」の関係を規律する「自然血族」の枠組みを基本として、その骨格を維持したまま、その骨格に当てはめる形で法的に「親子」の関係として扱う制度が定められることがある。
これは、「法定血族」である。
∵ 結論
このように、24条2項の「家族」の中に含めることのできる人的結合関係の範囲は、「家族」の枠組みが「婚姻」と同一の目的を共有してその目的を達成するための手段として「婚姻」の枠組みとの間で整合性を保つ形で統一的に定められることによる内在的な限界がある。
そして、その限界は、「婚姻」している「夫婦」と、「生殖」によって子が生まれるという生物学的な因果関係を想定した「親子」の関係による「自然血族」と、その「自然血族」の枠組みを基本として、その骨格を維持したまま、その骨格に当てはめる形で位置付けられる「法定血族」までをいう。
まとめると、「家族」とは、「婚姻」している「夫婦」と、「親子」の関係によって結び付けられる「血縁関係者」のことを指す。
国(行政府)は下記のように述べている。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(イ)しかし、現行民法典には「家族」という言葉は存在せず、少なくとも民法の観点からは「家族」を厳密に定義することは困難であるが(大村敦志「家族法(第3版)」23ページ・乙第35号証)、一般的な用語としての「家族」は、「夫婦の配偶関係や親子・兄弟などの血縁関係によって結ばれた親族関係を基礎にして成立する小集団」を意味するものとされている(新村出編「広辞苑(第7版)」560ページ)。……(略)……
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【東京一次・第1回】控訴答弁書 令和5年6月23日 PDF
【参考】家族関係の基本知識 2022.12.19
【参考】血族について学ぼう!範囲や親族・姻族との違いを詳しく解説 2021.8.9
よって、この判決では「家族という概念は、憲法でも民法でも定義されておらず、その外縁は明確ではなく、」と述べているが、上記のように「夫婦」と「親子」の関係によるものに限られることから、「憲法でも民法でも定義されて」いないと言い切れるというものではないし、「その外縁は明確ではな」いとも言えない。
よって、「定義されて」いないと考えたり、「その外縁は明確」ではないと考えて、「家族」の概念を上記のような枠を離れてどのような意味としてでも用いることができるかのような前提で論じようとしている部分が誤りである。
「家族という概念は、……(略)……社会通念上は、多義的なものである。」との部分について検討する。
日常用語として「家族」という言葉が使われる場合、それは「共同生活者」などを示そうとするものであることが多い。
人によっては、犬、猫、鳥などのペットについても「家族」と呼んでいる場合もある。
これは、社会学的な意味で使われる「家族」であり、その意味はそれぞれの人の主観によるものである。
この部分では「社会通念上」と述べていることから、それが日常用語として使われる社会学的な意味の「家族」について述べるものであるのか必ずしも明らかではないが、「多義的なもの」としていることから、それについて述べているように見受けられる。
しかし、この判決で問われてるのは憲法24条2項に記された「家族」であり、これは法学的な意味の「家族」を指すものであるから、「多義的なもの」とはいえない。
また、この判決の文面では、この法学的な意味の「家族」について論じることが求められているのであり、この場面で社会学的な意味で使われる「家族」の意味について述べていることは適切であるとはいえない。
これが法学的な意味の「家族」でないのであれば、それは判決の文面の中で論じる必要のあるものではないし、それに基づいて何らかの結論を導き出すこともできないことを押さえる必要がある。
「同性カップルにおいても、親密な関係に基づき永続性をもった生活共同体を構成しうることは、異性カップルと何ら異ならないのであるから、同性カップルの関係性について、家族の問題として検討することは十分に可能なはずである。」との記載がある。
まず、「同性カップル」と「異性カップル」のように「カップル」という「二人一組」を取り上げて比較しようとしているが、人的結合関係の中には「三人一組」や「四人一組」、それ以上の組み合わせも存在するのであり、「カップル」のように「二人一組」のみを取り上げて比較すればそれで済むかのような前提で述べていることは、なぜ「二人一組」であるのかその根拠を説明しないままに論じる「カップル信仰論」に陥っており、妥当でない。
次に、「親密な関係に基づき永続性をもった生活共同体を構成しうる」との部分の共通性を下に「家族の問題として検討することは十分に可能」と考えているが、妥当でない。
憲法24条2項の「婚姻及び家族」のいう「家族」とは、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた枠組みとして存在する「家族」である。
この枠組みは「親密な関係に基づき永続性をもった生活共同体を構成しうる」ことを理由として設けられているわけではない。
そもそも憲法24条2項に定められている「婚姻及び家族」とは、「恋愛・性愛」などの個人の価値観に基づいて人的結合関係を形成している場合や、単に「共同生活」を営むために人的結合関係を形成している場合などの様々な人的結合関係が存在することを前提とする中において、その中でも特に「生殖と子の養育」の観点に着目して他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた枠組みである。
そのため、憲法24条2項の「婚姻及び家族」の枠組みは、単に「親密な関係に基づき永続性をもった生活共同体を構成しうる」人的結合関係を保護することを目的として設けられているわけではない。
そのことから、「生殖と子の養育」の趣旨によるものでない人的結合関係を「家族」の中に含めることはできず、ここで「親密な関係に基づき永続性をもった生活共同体を構成しうる」ことを理由として、「家族の問題として検討することは十分に可能」と述べている部分は誤りとなる。
「同項は、「両性の本質的平等」との文言を用いているが、家族の問題については、例えば、家督相続制度の復活の是非を取り上げれば、両性間のみならず同性間の平等も問題となりうるのであり、「両性」の文言を「両当事者」と読み替えるまでもなく、同項は、両性が必ずしも関わらない家族の問題をも含めて規律していると理解することができると解される。」との記載がある。
この文はやや長いため短くまとめると、要するに、24条2項の「両性の本質的平等」の文言は、「「両性」の文言を「両当事者」と読み替えるまでもなく」、「両性が必ずしも関わらない家族の問題をも含めて規律している」と考えているものである。
しかし、24条2項は「両性」における「本質的平等」を「規律」している条文であり、「両性」に当てはまらないものについては「規律」していない。
このような「両性」に当てはまらないものについては、14条1項の「平等原則」が適用されることになるが、24条2項はあくまでも「両性」の間の「平等」について「規律」するものである。
そのため、「「両性」の文言を「両当事者」と読み替える」ことは、24条2項の文言に反して許されないし、「両性」の適用対象は「男性」と「女性」の間を指すものであるから、これに当てはまらないものを「両性」に含めることができるかのように論じている部分は誤りである。
この名古屋地裁判決が多用している「再婚禁止期間大法廷判決」や「再婚禁止期間大法廷判決」でも、「両性の本質的平等」の「両性」の文言は「男性」と「女性」の間であることを前提としている。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 憲法24条は,2項において「配偶者の選択,財産権,相続,住居の選定,離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては,法律は,個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して,制定されなければならない。」と規定している。
婚姻及び家族に関する事項は,関連する法制度においてその具体的内容が定められていくものであることから,当該法制度の制度設計が重要な意味を持つものであるところ,憲法24条2項は,具体的な制度の構築を第一次的には国会の合理的な立法裁量に委ねるとともに,その立法に当たっては,同条1項も前提としつつ,個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきであるとする要請,指針を示すことによって,その裁量の限界を画したものといえる。
そして,憲法24条が,本質的に様々な要素を検討して行われるべき立法作用に対してあえて立法上の要請,指針を明示していることからすると,その要請,指針は,単に,憲法上の権利として保障される人格権を不当に侵害するものでなく,かつ,両性の形式的な平等が保たれた内容の法律が制定されればそれで足りるというものではないのであって,憲法上直接保障された権利とまではいえない人格的利益をも尊重すべきこと,両性の実質的な平等が保たれるように図ること,婚姻制度の内容により婚姻をすることが事実上不当に制約されることのないように図ること等についても十分に配慮した法律の制定を求めるものであり,この点でも立法裁量に限定的な指針を与えるものといえる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
損害賠償請求事件 最高裁判所大法廷 平成27年12月16日 (夫婦同氏制大法廷判決) (PDF)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
そうすると,婚姻制度に関わる立法として,婚姻に対する直接的な制約を課すことが内容となっている本件規定については,その合理的な根拠の有無について以上のような事柄の性質を十分考慮に入れた上で検討をすることが必要である。
そこで,本件においては,上記の考え方に基づき,本件規定が再婚をする際の要件に関し男女の区別をしていることにつき,そのような区別をすることの立法目的に合理的な根拠があり,かつ,その区別の具体的内容が上記の立法目的との関連において合理性を有するものであるかどうかという観点から憲法適合性の審査を行うのが相当である。以下,このような観点から検討する。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
損害賠償請求事件 最高裁判所大法廷 平成27年12月16日 (再婚禁止期間大法廷判決) (PDF)
よって、「同項は、両性が必ずしも関わらない家族の問題をも含めて規律していると理解することができると解される。」との認識は誤りである。
その他、「「両性」の文言を「両当事者」と読み替えるまでもなく、」との部分であるが、この「読み替え」の問題について検討する。
ここいう「読み替え」とは、「両性」という「男性」と「女性」を指している「両」の意味を、「両当事者」のように「二人一組」における「二つ」を指している「両」の意味に変換しようとするものであるが、そもそもこれが可能であるかという問題がある。
例えば、「この学校の3年2組のクラスは両性とも歌が上手い」との話題が出たときに、それは「この学校の3年2組のクラスは二人とも歌が上手い」ということを意味するわけではない。
クラスの中の「男性」と「女性」を取り上げる意味での「両」であるにもかかわらず、これがクラスの中に二人しかいないという意味での「両」に読み替えることは不正な手続きである。
他にも、「集まったメンバーは両性います」との報告を聴いた時には、それは「集まったメンバーは二人います」ということを意味するわけではない。
集まったメンバーの中に「男性」と「女性」がいることを示す意味の「両」であるにもかかわらず、これがメンバーが二人しかいないという意味での「両」に読み替えることは不正な手続きである。
そのため、ここで「「両性」の文言を「両当事者」と読み替える」との部分については、そもそもできるはずのない「読み替え」を行おうとしている点で誤りである。
よって、「「両性」の文言を「両当事者」と読み替えるまでもなく、」との部分については、そもそもそのように「読み替える」ことはできない。
「家督相続制度の復活の是非を取り上げれば、両性間のみならず同性間の平等も問題となりうるのであり、」との部分について検討する。
まず、憲法24条2項は、「婚姻及び家族」の制度について「両性」の間で「平等」が問われた場合については「両性の本質的平等」によって審査することができるが、「婚姻及び家族」の制度の問題でない場合や、「婚姻及び家族」の制度の問題であるとしても「両性」の間の「平等」が問題となっているわけではないのであれば、この「両性の本質的平等」によって審査することはできない。
ここでいう「家督相続制度」における「同性間の平等」が「問題」となる場合であるが、これは「同性間」であることから、24条2項の「両性の本質的平等」によって審査することのできる対象ではないことから、憲法24条2項の示す「婚姻及び家族」の制度ではない通常の一般的な法制度と同様に憲法14条1項の「平等原則」によって審査することになる。
上記の「イ」の第一段落の第三文には、「憲法14条1項と憲法24条2項の関係をどのように理解するかについては見解が分かれ得る問題であるとしても、両条項が保護しようとした法益に重なり合う部分が存することは否定できないと考えられるから、」との記載があるが、ここでいう「重なり合う部分」とは、憲法24条2項の「婚姻及び家族」の枠組みの「要請」に従って立法された法律上の具体的な制度(『婚姻及び家族』の制度)について、「両性」(男性と女性)の間での「平等」が問われた場合のみである。
この「家督相続制度」については、「両性間」ではないことから、憲法24条2項で審査することのできる対象ではないし、ここでいう「重なり合う部分」には該当しないものであり、単に憲法14条1項の「平等原則」によって審査されるものとなる。
この論点については、当ページ上記の「ポイント」のところでも解説している。
そこで、以下、同性カップルが上記の状態に置かれている点については、「家族」に関する事項として、憲法24条2項に違反しないかを検討する。
【筆者】
ここでいう「同性カップル」という「同性間の人的結合関係」については、一つ前の段落で解説したように、それが「親子」や、「親子」の関係を基本とした「兄弟」「姉妹」などに当てはまらないのであれば、24条2項の「家族」の中には含まれない。
そのため、ここでは「「家族」に関する事項として、憲法24条2項に違反しないかを検討する。」としているが、そもそも「家族」には含まれないという点で、そのような「検討」を行うことはできず、その「検討」を行おうとしている部分が誤りである。
加えて、24条2項は「婚姻及び家族」の制度の創設を「要請」するものであるが、それ以外の制度については何ら「要請」するものではない。
そのため、ここでいう「同性間の人的結合関係」については「婚姻」ではないし、「家族」の中にも含まれないことから、当然、これに対する何らかの制度の創設を24条2項が「要請」しているということはない。
よって、そのような制度が存在しないことについて、24条2項に違反するという結論が導き出されることもない。
このことから、この段落より以下の内容は、ここでいう「同性間の人的結合関係」が24条2項の「家族」に含まれることを前提として論じるものとなっているが、そもそも「家族」に含まれないという点で誤っているし、24条2項はそのような制度の創設を「要請」しているものでもないため、24条2項に違反するという結論が導き出されることもないのであり、これより以下で行っている検討やその結論はすべて正当化することはできず、誤っていることになる。
この「イ」の内容は、全体として読み取りづらいものとなっている。
これを整理してまとめると、下記のようになる。(カッコ内省略)
=======================================
「現在の医学心理学の知見によれば、性的指向及び性自認は、ほとんどの場合、人生の初期又は出生前に決定され、自らの意思や精神医学的な療法によって変更されるものではないとされている(…)」
↓ ↓
「同性カップルは、自然生殖の可能性が存しないという点を除けば、親密な関係に基づき永続性をもった生活共同体を構成しうるという実態において、異性カップルと何ら異なるところはなく(…)、」
↓ ↓
「異性カップルであれば、所定の要件を充たすことにより、法律婚制度の下で、法律上及び事実上の多彩な効果を一体のものとして享受することができる。」
◇ 法律上の効果
「法律により具体化された現行の法律婚制度」「は、」「両当事者及びその親族の身分関係を形成するとともに、戸籍制度によってその身分関係を公証し、民法及びその他の諸法令により、法律上、当事者間及びその他の第三者との間に様々な権利義務関係を生じさせるものとなっている。」
◇ 事実上の効果
「婚姻には、」「婚姻制度を利用することにより、社会的な信用が形成され、信任が得られるなどの社会的な効果のほか、そうした地位に立ったことによる精神的心理的効果をも生じさせるものである。」
↓ ↓
「他方、同性カップルは、本件諸規定が、同性カップルに対して法律婚制度の利用を認めず、他にこれを認める法令の規定が存しないことにより、法制度の下で、法律上及び事実上の多彩な効果を一体のものとして享受することができない状態となっており、異性カップルとの間に著しい乖離が生じている。」
↓ ↓
「同性カップルが上記の状態に置かれている点が憲法上是認されるかどうかは、なお検討を要するというべきである。」
↓ ↓
「原告らは、同性間の婚姻を求める権利利益が憲法24条の保障する範囲内でないとしても、婚姻により生じる諸々の法的利益を享受する権利は重大な法的利益であり、これが性的指向や性別により不合理な差別を受ける場合には、憲法14条1項違反となると主張している。」
↓ ↓
「その趣旨は、婚姻により生じる諸々の法的利益を享受する権利が原告らに保障されていないことが重大な法的利益の侵害であり、憲法に違反するというものであると解され、憲法24条においても考慮されるべきことを否定する趣旨ではないと解される。」
↓ ↓
「憲法24条2項は、婚姻のほか、「家族」についても、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚した立法の制定を要請している。」
↓ ↓
「家族という概念は、憲法でも民法でも定義されておらず、その外縁は明確ではなく、社会通念上は、多義的なものである。」
↓ ↓
「上記のとおり、同性カップルにおいても、親密な関係に基づき永続性をもった生活共同体を構成しうることは、異性カップルと何ら異ならないのであるから、同性カップルの関係性について、家族の問題として検討することは十分に可能なはずである。」
↓ ↓
「特に、家族に関する法制度の平等が問題となる場合においては、憲法14条1項と憲法24条2項の関係をどのように理解するかについては見解が分かれ得る問題であるとしても、両条項が保護しようとした法益に重なり合う部分が存することは否定できないと考えられる」
「同項は、「両性の本質的平等」との文言を用いているが、家族の問題については、例えば、家督相続制度の復活の是非を取り上げれば、両性間のみならず同性間の平等も問題となりうるのであり、「両性」の文言を「両当事者」と読み替えるまでもなく、同項は、両性が必ずしも関わらない家族の問題をも含めて規律していると理解することができると解される。」
↓ ↓
「原告らが主張する重大な法的利益を享受できないことの違憲性については、憲法24条2項の問題ともなりうるものである。」
↓ ↓
「そこで、以下、同性カップルが上記の状態に置かれている点については、「家族」に関する事項として、憲法24条2項に違反しないかを検討する。」
=======================================
しかし、このように並べ替えても、「イ」の内容が誤っていることは変わらない。
まず、法制度は内心に中立的な内容でなければならないことから、「性的指向及び性自認」と結び付く形で定めてはならない。
次に、婚姻制度は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度であり、「親密な関係に基づき永続性をもった生活共同体を構成しうる」ということを理由として設けられているものではない。
三つ目に、婚姻制度の「法律上の効果」は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成するための手段として整合的な形で設けられているものであり、その目的に沿わない場合に法的効果を与えなければならないことにはならない。
四つ目に、法律論上の比較対象とすることができるのは「権利能力」を有して法主体としての地位を認められている者同士であり、「カップル」という「二人一組」を取り上げて比較することはできない。
そして、個々人は婚姻制度を利用することが可能であることから、「著しい乖離」は生じていない。
五つ目に、「家族」の範囲は「夫婦」と「親子」によるものに限られており、それ以外は含まれない。
ここでいう「同性カップル」という「同性間の人的結合関係」については、「親子」や「親子」の関係を基本とした「兄弟」「姉妹」などではないため、「家族」には含まれない。
よって、ここでいう「同性間の人的結合関係」を「家族の問題として検討」することはできない。
六つ目に、憲法14条1項の「平等原則」と憲法24条2項の「両性の本質的平等」の「重なり合う部分」とは、憲法24条2項の「婚姻及び家族」に当てはまる場合で、かつ、「両性」(男性と女性)の間の差異が問題となる場合だけである。
今回の事例はそもそも憲法24条2項の「婚姻及び家族」には当てはまらないという点で憲法24条2項を適用することのできる対象ではなく、憲法14条1項との「重なり合う部分」には当たらない。
ウ 前記⑵アで見たとおり、憲法24条2項は「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。」と規定している。
婚姻及び家族に関する事項は、関連する法制度においてその具体的内容が定められていくものであることから、当該法制度の制度設計が重要な意味を持つものであるところ、同項は、具体的な制度の構築を第一次的には国会の合理的な立法裁量に委ねるとともに、その立法に当たっては、同条1項も前提としつつ、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきであるとする要請、指針を示すことによって、その裁量の限界を画したものといえる。
そして、同条が、本質的に様々な要素を検討して行われるべき立法作用に対してあえて立法上の要請、指針を明示していることからすると、その要請、指針は、単に、憲法上の権利として保障される人格権を不当に侵害するものでなく、かつ、両性の形式的な平等が保たれた内容の法律が制定されればそれで足りるというものではないのであって、憲法上直接保障された権利とまではいえない人格的利益をも尊重すべきこと、両性の実質的な平等が保たれるように図ること、婚姻制度の内容により婚姻をすることが事実上不当に制約されることのないように図ること等についても十分に配慮した法律の制定を求めるものであり、この点でも立法裁量に限定的な指針を与えるものといえる。
他方で、婚姻及び家族に関する事項は、国の伝統や国民感情を含めた社会状況における種々の要因を踏まえつつ、それぞれの時代における夫婦や親子関係についての全体の規律を見据えた総合的な判断によって定められるべきものである。特に、憲法上直接保障された権利とまではいえない人格的利益や実質的平等は、その内容として多様なものが考えられ、それらの実現の在り方は、その時々における社会条件、国民生活の状況、家族の在り方等との関係において決められるべきものである。
そうすると、同条の要請、指針に応えて具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定が上記のとおり国会の多方面にわたる検討と判断に委ねられているものであることからすれば、婚姻及び家族に関する法制度を定めた法律の規定が憲法24条に適合するものとして是認されるか否かは、当該法制度の趣旨や同制度を採用することにより生ずる影響につき検討し、当該規定が個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理性を欠き、国会の立法裁量の範囲を超えるものとみざるを得ないような場合に当たるか否かという観点から判断すべきものと解するのが相当である。
(夫婦同氏制大法廷判決参照)
【筆者】
ここで示された判決は、下記の通りである。
(灰色で潰した部分は、上記の記述と同様の文言が使われているところである。)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 憲法24条は,2項において「配偶者の選択,財産権,相続,住居の選定,離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては,法律は,個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して,制定されなければならない。」と規定している。
婚姻及び家族に関する事項は,関連する法制度においてその具体的内容が定められていくものであることから,当該法制度の制度設計が重要な意味を持つものであるところ,憲法24条2項は,具体的な制度の構築を第一次的には国会の合理的な立法裁量に委ねるとともに,その立法に当たっては,同条1項も前提としつつ,個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきであるとする要請,指針を示すことによって,その裁量の限界を画したものといえる。
そして,憲法24条が,本質的に様々な要素を検討して行われるべき立法作用に対してあえて立法上の要請,指針を明示していることからすると,その要請,指針は,単に,憲法上の権利として保障される人格権を不当に侵害するものでなく,かつ,両性の形式的な平等が保たれた内容の法律が制定されればそれで足りるというものではないのであって,憲法上直接保障された権利とまではいえない人格的利益をも尊重すべきこと,両性の実質的な平等が保たれるように図ること,婚姻制度の内容により婚姻をすることが事実上不当に制約されることのないように図ること等についても十分に配慮した法律の制定を求めるものであり,この点でも立法裁量に限定的な指針を与えるものといえる。
3(1) 他方で,婚姻及び家族に関する事項は,国の伝統や国民感情を含めた社会状況における種々の要因を踏まえつつ,それぞれの時代における夫婦や親子関係についての全体の規律を見据えた総合的な判断によって定められるべきものである。特に,憲法上直接保障された権利とまではいえない人格的利益や実質的平等は,その内容として多様なものが考えられ,それらの実現の在り方は,その時々における社会的条件,国民生活の状況,家族の在り方等との関係において決められるべきものである。
(2) そうすると,憲法上の権利として保障される人格権を不当に侵害して憲法13条に違反する立法措置や不合理な差別を定めて憲法14条1項に違反する立法措置を講じてはならないことは当然であるとはいえ,憲法24条の要請,指針に応えて具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定が上記(1)のとおり国会の多方面にわたる検討と判断に委ねられているものであることからすれば,婚姻及び家族に関する法制度を定めた法律の規定が憲法13条,14条1項に違反しない場合に,更に憲法24条にも適合するものとして是認されるか否かは,当該法制度の趣旨や同制度を採用することにより生ずる影響につき検討し,当該規定が個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理性を欠き,国会の立法裁量の範囲を超えるものとみざるを得ないような場合に当たるか否かという観点から判断すべきものとするのが相当である。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(PDF)
この名古屋地裁判決の内容は、この「夫婦同氏制大法廷判決」の文言から少し変えられている。
この名古屋地裁判決は、この「夫婦同氏制大法廷判決」で示された基準を用いて法的な判断を行おうとしているが、それが可能であるかを検討する。
まず、この名古屋地裁判決の「⑶ 憲法24条2項に違反するかについて」の項目で問われているのは、24条2項がここでいう「同性間の人的結合関係」に対する具体的な制度の創設を「要請」しているか否かである。
24条2項が「要請」しているのであればその制度がないことは違憲であるが、24条2項が「要請」していないのであればその制度がないことは合憲である。
24条2項には「婚姻及び家族」と記載されており、その中の「婚姻」については、上記「ア」の部分で「要請していないと解するのが整合的であり、」と述べていることから、「要請していない」と結論付けている。
そのため、今ここで問われているのはこの「ウ」の一段落前の部分(『イ』の第五段落)で示しているように、「「家族」に関する事項として、憲法24条2項に違反しないか」である。
24条2項の「家族」が「要請」しているのであればその制度がないことは違憲となるが、24条2項の「家族」が「要請」していないのであれば合憲となる。
24条2項の「家族」とは、上記「イ」の第四段落で解説したように、「夫婦」と「親子」の関係によるものに限られる。
このことから、24条2項の「家族」は、「夫婦」と「親子」に関する制度の創設を「要請」するものではあるが、それ以外の制度について「要請」していない。
よって、それ以外の制度が存在しないことについて、24条2項の「要請」に従っていないとは評価することができないことから、このことを理由として24条2項に違反することはない。
この名古屋地裁判決で取り上げている「同性間の人的結合関係」についても、「夫婦」には当たらないし、「親子」にも当たらないし、「親子」の関係を基本とした「兄弟」「姉妹」などにも当たらないため、24条2項の「家族」の中には含まれない。
そのため、ここでいう「同性間の人的結合関係」を対象とした制度が存在しないとしても、それは24条2項が「要請」するものではないため、そのことが24条2項に違反するということにはならない。
これに対して、この名古屋地裁判決の「ウ」の項目以下では、この「夫婦同氏制大法廷判決」が示した基準を用い、この「夫婦同氏制大法廷判決」が24条2項の「個人の尊厳」の文言に対応するものとして示した「人格的利益」の文言を拾い出し、具体的に存在する法制度の内容がこれを満たすか否かを検討することによって、ここでいう「同性間の人的結合関係」を対象とする制度を立法していないことについて24条2項に違反するか否かの結論を導き出そうとするものとなっている。
しかし、これは誤った理解である。
この「夫婦同氏制大法廷判決」で問われているのは、憲法24条2項が「婚姻及び家族」の制度を立法することを国会に対して「要請」していることに基づいて定められた法律上の「婚姻及び家族」の制度の内容が、憲法24条2項の「個人の尊厳」と「両性の本質的平等」に違反するか否かである。
これは、24条2項の「個人の尊厳」の文言を適用することができる対象は、24条2項の「婚姻及び家族」の枠組みに従って立法されている法律上の「婚姻及び家族」の制度のみであり、その審査の内容も「婚姻及び家族」の制度の内容について「個人の尊厳」に反する規定がある場合にそれを是正するというものだからである。
つまり、「婚姻及び家族」の枠組みの中で定められた事柄が「個人の尊厳」や「両性の本質的平等」の文言に違反するか否かが問われているものであって、「婚姻及び家族」という枠組みそのものの範囲が問われているものではない。
そのため、24条2項の「婚姻及び家族」の枠組みに従って立法されている法律上の「婚姻及び家族」の制度について「個人の尊厳」に違反するか否かを審査することは可能であるが、この「個人の尊厳」の文言を用いてその「個人の尊厳」が適用される対象の範囲を定めている「婚姻及び家族」の枠組みそのものを変更することはできない。
そのことから、この「夫婦同氏制大法廷判決」が示した基準を用いて、「婚姻及び家族」の枠組みそのものについて論じることはできない。
よって、これより以下の部分で、この名古屋地裁判決が「夫婦同氏制大法廷判決」の中で24条2項の「個人の尊厳」の文言に対応するものとして示されている「人格的利益」の文言を用いて「婚姻及び家族」の枠組みを変更することが可能であるかのような前提の下に、24条2項に違反するか否かを論じている部分は誤りである。
この点の切り分けを理解するためには、法律上の「婚姻及び家族」の制度が存在しない場合を検討すると分かりやすい。
法律上の「婚姻及び家族」の制度が存在しない場合には、憲法24条2項の「婚姻及び家族」の文言が有している「要請」に従って法制度が創設されていないことが違憲となるのであり、「個人の尊厳」や「両性の本質的平等」の部分に抵触して違憲と判断される場合とは性質が異なっている。
そのため、法律上の「婚姻及び家族」の制度が憲法24条2項の「婚姻及び家族」の枠組みに従って定められているかどうかという部分と、その憲法24条2項の「婚姻及び家族」の枠組みに従って立法されている法律上の「婚姻及び家族」の制度の内容が「個人の尊厳」や「両性の本質的平等」を満たすものとなっているかどうかは切り分けて考える必要がある。
当然、この「個人の尊厳」や「両性の本質的平等」を理由として、「婚姻及び家族」の枠組みそのものを変更することができることにはならないのである。
この点については、このページの上記「ポイント」のところでも解説しいる。
加えて、この「夫婦同氏制大法廷判決」においても「婚姻及び家族」の枠組みについては「夫婦や親子関係」と示していることにも注目すべきである。
この名古屋地裁判決では「夫婦同氏制大法廷判決」の文言から「人格的利益」を拾い出すことによって「婚姻及び家族」の枠組みの変更を試みるのであるが、その「夫婦同氏制大法廷判決」の内容は「婚姻及び家族」の枠組みについて「夫婦」と「親子」を前提とするものなのである。
そのため、「夫婦同氏制大法廷判決」が示している「人格的利益」の射程も「夫婦」と「親子」によるものに限られるのであり、この「人格的利益」の文言を用いてその枠そのものを変更することはそもそもできないものである。
これより以下の「エ」「オ」「カ」「キ」の項目では、下記のように文頭ですべて「前記ウの通り、」と記載されており、この「ウ」に記された「夫婦同氏制大法廷判決」の内容に基づいて判断を行うことを示すものとなっている。
◇ 「エ 前記ウのとおり、」
◇ 「オ 前記ウのとおり、」
◇ 「カ 前記ウのとおり、」
◇ 「キ 前記ウのとおり、」
しかし、先ほど解説したように、この名古屋地裁判決の事案において「夫婦同氏制大法廷判決」で示された内容を基準として用いることはできないのであり、これを基準として用いようとしているこれらすべての判断についての前提が誤っていることになるため、それらの検討の内容もすべて誤りとなる。
そしてその結果、その結論についても正当化することのできるものではなく、誤りとなる。
エ 前記ウのとおり、憲法24条2項は憲法上直接保障された権利とまではいえない人格的利益をも尊重すべきこと等についても十分に配慮した法律の制定を求めるものである。
【筆者】
まず、「憲法24条2項」は「婚姻及び家族」の対象となる場合について「個人の尊厳」に立脚するものとなるように求める規定であり、ここで「前記ウのとおり、」と示している「夫婦同氏制大法廷判決」の中で「人格的利益」について述べている部分は、この意味に基づくものとなっている。
しかし、そもそも「婚姻及び家族」の対象とならない場合については、「憲法24条2項」の「個人の尊厳」が適用される対象ではないため、これに基づく意味の「人格的利益」を尊重するべきか否かを論じることのできる前提にない。
この判決で取り上げている「同性間の人的結合関係」については、「婚姻」ではないし、「親子」や「親子」の関係を基本とした「兄弟」「姉妹」などでもないため「家族」にも含まれないことから、「憲法24条2項」の「家族」とはいえない。
そのため、「憲法24条2項」の「家族」に当てはまることを前提としてその制度の内容が「個人の尊厳」を満たすか否かを論じる前提にはなく、それに基づく意味での「人格的利益」を尊重するべきか否かについても検討することはできない。
この点に注意が必要である。
前記⑵アのとおり、同条1項は、婚姻をするかどうか、いつ誰と婚姻をするかについては、当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたものと解され、このような婚姻をするについての自由は、同項の規定の趣旨に照らし、十分尊重に値するものと解することができる。(再婚禁止期間大法廷判決参照)
【筆者】
ここで示された判決は、下記の通りである。
(灰色で潰した部分は、上記の記述と同様の文言が使われているところである。)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
……(略)……また,同条1項は,「婚姻は,両性の合意のみに基いて成立し,夫婦が同等の権利を有することを基本として,相互の協力により,維持されなければならない。」と規定しており,婚姻をするかどうか,いつ誰と婚姻をするかについては,当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたものと解される。婚姻
は,これにより,配偶者の相続権(民法890条)や夫婦間の子が嫡出子となること(同法772条1項等)などの重要な法律上の効果が与えられるものとされているほか,近年家族等に関する国民の意識の多様化が指摘されつつも,国民の中にはなお法律婚を尊重する意識が幅広く浸透していると考えられることをも併せ考慮すると,上記のような婚姻をするについての自由は,憲法24条1項の規定の趣旨に照らし,十分尊重に値するものと解することができる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(PDF)
24条1項について述べるものであるが、そこでいう「婚姻」とは、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた枠組みである。
そのため、24条1項が「婚姻をするかどうか、いつ誰と婚姻をするかについては、当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨」を有しているとしても、そこでいう「婚姻」の意味は常にこのような目的を達成するための手段として設けられた枠組みのことを指している。
そのため、この24条1項の解釈として導き出されている「婚姻をするかどうか、いつ誰と婚姻をするかについては、当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨」を根拠として、その「婚姻」という枠組みそのものを変更することができることにはならない。
この点も押さえる必要がある。
これについて、国(行政府)は下記のように述べている。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
したがって、憲法24条1項は、婚姻について異性間の人的結合関係のみを対象としており、「婚姻をするかどうか、いつ誰と婚姻をするか」を当事者で自由に意思決定し、故なくこれが妨げられないという意味における「婚姻をするについての自由」は、異性間の人的結合関係を対象とする婚姻についてのみ保障されていると解するのが相当である。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【東京二次・第9回】被告第7準備書面 令和5年9月28日 PDF
上記の婚姻をするについての自由は、同条2項を通じて、法律により具体化された法律婚制度を利用するについての自由であると解されるが、そのような法律婚制度を利用するについての自由が十分尊重に値するものとされるべき所以は、婚姻の本質が、両当事者において永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもって共同生活を営むことにあり、法律婚制度が、この本質に重要な価値を認め、これを具体化し実現し保護しようとしたことにあるためであると解される。そして、このような本質的な人間の営みは、法律婚制度が整えられる以前から歴史上自生的に生じたものと考えられる。したがって、法律婚制度を利用するについての自由が十分尊重に値するとされる背景にある価値は、人の尊厳に由来するものということができ、重要な人格的利益であるということができる。
【筆者】
「婚姻をするについての自由は、同条2項を通じて、法律により具体化された法律婚制度を利用するについての自由であると解されるが、そのような法律婚制度を利用するについての自由が十分尊重に値するものとされるべき所以は、婚姻の本質が、両当事者において永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもって共同生活を営むことにあり、法律婚制度が、この本質に重要な価値を認め、これを具体化し実現し保護しようとしたことにあるためであると解される。」との記載がある。
この文は、「婚姻をするについての自由」(法律婚制度を利用するについての自由)が「十分尊重に値するものとされるべき所以」について、「婚姻の本質が、両当事者において永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもって共同生活を営むことにあり、」「この本質に重要な価値を認め、これを具体化し実現し保護しようとしたことに」「法律婚制度が」「あるため」と考えているが、誤りである。
まず、この「婚姻をするについての自由」は、一段落前の「再婚禁止期間大法廷判決」について述べるものである。
しかし、その「再婚禁止期間大法廷判決」の中では、「婚姻をするについての自由」が「十分尊重に値するものと解することができる。」とする理由について、「配偶者の相続権(民法890条)や夫婦間の子が嫡出子となること(同法772条1項等)などの重要な法律上の効果が与えられるものとされている」ことを挙げている。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
……(略)……また,同条1項は,「婚姻は,両性の合意のみに基いて成立し,夫婦が同等の権利を有することを基本として,相互の協力により,維持されなければならない。」と規定しており,婚姻をするかどうか,いつ誰と婚姻をするかについては,当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたものと解される。婚姻
は,これにより,配偶者の相続権(民法890条)や夫婦間の子が嫡出子となること(同法772条1項等)などの重要な法律上の効果が与えられるものとされているほか,近年家族等に関する国民の意識の多様化が指摘されつつも,国民の中にはなお法律婚を尊重する意識が幅広く浸透していると考えられることをも併せ考慮すると,上記のような婚姻をするについての自由は,憲法24条1項の規定の趣旨に照らし,十分尊重に値するものと解することができる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
よって、この名古屋地裁判決が「婚姻をするについての自由」(法律婚制度を利用するについての自由)が「十分尊重に値するものとされるべき所以」について、「婚姻の本質」「に重要な価値を認め、これを具体化し実現し保護しようとしたこと」であると考えている部分は、前提として用いている最高裁判決の内容を読み取るものではないという点で誤っている。
「婚姻の本質が、両当事者において永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもって共同生活を営むことにあり、」との部分について検討する。
この「婚姻の本質」と称する説明は、下記の最高裁判決を参考としているものであるが、最高裁判決をそのまま抜き出したものとはなっていない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2 思うに、婚姻の本質は、両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもつて共同生活を営むことにあるから、夫婦の一方又は双方が既に右の意思を確定的に喪失するとともに、夫婦としての共同生活の実体を欠くようになり、その回復の見込みが全くない状態に至つた場合には、当該婚姻は、もはや社会生活上の実質的基礎を失つているものというべきであり、かかる状態においてなお戸籍上だけの婚姻を存続させることは、かえつて不自然であるということができよう。しかしながら、離婚は社会的・法的秩序としての婚姻を廃絶するものであるから、離婚請求は、正義・公平の観念、社会的倫理観に反するものであつてはならないことは当然であつて、この意味で離婚請求は、身分法をも包含する民法全体の指導理念たる信義誠実の原則に照らしても容認されうるものであることを要するものといわなければならない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
まず、最高裁判決においては明確に「両性」と書かれているが、この名古屋地裁判決では「両当事者」に変えられている。
この名古屋地裁判決が最高裁判決に示された文面を正確に引用していない背景には、この裁判官が「婚姻」の内容について「両性」という「男女」を意味する言葉を用いてその範囲が確定されている事実を意図的に排除することによって、「婚姻」が「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として設けられた枠組みであることを原因とした「婚姻」という概念そのものに含まれた内在的な限界を考慮することなく、それを超える人的結合関係を「婚姻」の中に含めるという特定の結論を導き出すために、恣意的に文言を変更している可能性が考えられる。
そのような意図に基づいて最高裁判決に示された「両性」の文言を「当事者」という文言に変更しているのであれば、「婚姻」という概念そのものに含まれた内在的な限界を何ら考慮することなく恣意的な形で結論を導き出そうとする不正であるし、最高裁判決で用いられた文面の意味を改竄するものということができ、解釈の過程を誤った違法なものというべきである。
法解釈は、論理的整合性の積み重ねによって結論を正当化することが可能となるのであり、解釈の過程で根拠となっている判例の文章の意味を読み替えたり、文言を勝手に変更したり、文章の内容を改竄することは、不正であり、違法な手続きということができる。
このような解釈の過程に不正、違法が含まれている場合には、根拠となっているもともとの条文や判例との間で完全に断絶するものとなるのであり、その結論は正当化することはできないことになる。
よって、この判決が「婚姻の本質」と称している説明を根拠として、何らかの解釈を行おうとしても、もともとの「婚姻の本質」と称している説明そのものが、具体的な条文やそれを基にして示された最高裁判決の文面の意味や内容から切り離された不当な内容であることになるから、それを根拠とした解釈や判断の枠組みについても、正当化することができないことになる。
下記の記事でも、最高裁判決では「両性」と示されていることや、「夫婦」の文言を前提としているものであることが説明されている。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
もっとも昭和62年9月2日の最高裁大法廷判決は、「婚姻の本質は、両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもつて共同生活を営むこと」としているが、この定義に続いて「夫婦」の言葉も見え、最高裁は、男女のカップルの共同生活を「婚姻」としているように読める〔最高裁判所大法廷 昭和61年(オ)260号 判決〕。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
生殖可能性のない同性婚を法律で認める理由はない…憲法学の専門家が「同性婚の法制化」にクギを刺す理由 2023/02/18
国(行政府)の主張においても「両性」と示されていることが述べられている。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
なお、控訴人らは、前記④のとおり、有責配偶者からの離婚請求の可否が争点となった事案において、最高裁昭和62年9月2日大法廷判決(民集41巻6号1423ページ)が、「婚姻の本質は、両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもって共同生活を営むことにある」と判示している点をとらえて、「カップル間の自然生殖可能性の有無は問題とされていない」旨主張するところ、同判決は、「両性」すなわち「一人の男性と一人の女性」を前提として判示しているものであることからすれば、控訴人らの主張のようには解されないところである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【東京一次・第1回】控訴答弁書 令和5年6月23日 PDF (P27)
このように、最高裁判決には、明確に「両性」と書かれており、「婚姻の本質」の意味についても「男女」であることを前提としているものであり、これを「両当事者」に書き替えている部分は誤りである。
この文で、「婚姻の本質が、両当事者において永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもって共同生活を営むことにあり、」「この本質に重要な価値を認め、これを具体化し実現し保護しようとした」ことにより「法律婚制度」があると考えていることについて検討する。
まず、最高裁判決が「婚姻の本質」について、「婚姻の本質は、両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもつて共同生活を営むことにある」と説明している根拠を検討する。
なぜならば、もし最高裁判所の裁判官が何らの根拠もなく独断で決めているとすれば、その時々の気分によって「婚姻の本質は、子供を産むことにある」や「婚姻の本質は、一夫多妻である」、「婚姻の本質は、親の決めた相手と結ばれることである」と述べてしまえば、それが絶対的な定義となってしまうことを意味するのであり、法の支配、法治主義を逸脱することになって妥当でないからである。
◇ 「両性」との部分は、婚姻制度が「男性」と「女性」を要件としていることから導かれる。
◇ 「永続的な」との部分は、婚姻制度には有効期限がなく、利用者が死亡するまで利用することができるという点から導かれる。
(もし婚姻制度が改正されて有効期限が定められることがあるとすれば、この『永続的な』との説明は根拠を失ってなくなることになる。)
◇ 「精神的及び肉体的結合を目的として」との部分は、婚姻制度が相互の協力を求めていることや、「貞操義務」があることから導かれる。
憲法
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
② (略)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
民法
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(『貞操義務』のある制度を読み解くことによって『肉体的結合』と表現しているのであり、もし『貞操義務』がなければ『肉体的結合』という表現は導かれないことになる。)
◇ 「共同生活を営む」との部分は、婚姻制度が「同居義務」を定めていることから導かれる。
民法
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(同居、協力及び扶助の義務)
第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
このように、最高裁判決の示す「婚姻の本質」と称する説明は、立法目的を達成するための手段として設けられた具体的な婚姻制度の枠組みが存在することを前提とし、その婚姻制度を利用する者の間で生じる法律関係について示されているものである。
立法目的:国の立法目的
↓
達成手段:婚姻制度の枠組み
↓
法律関係:「婚姻の本質」と称する説明
他にも、この「婚姻の本質」と称する説明の中には、「真摯な意思をもつて」との文言がある。
これは、法律上において具体的な婚姻制度が存在することを前提として、その婚姻制度を利用する者の間で法的拘束力を発生させることが妥当であるかどうかという問題において、「婚姻意思」を満たすものとして有効性を保つべきであるか否かに関係して論じられているものである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2 思うに、婚姻の本質は、両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもつて共同生活を営むことにあるから、夫婦の一方又は双方が既に右の意思を確定的に喪失するとともに、夫婦としての共同生活の実体を欠くようになり、その回復の見込みが全くない状態に至つた場合には、当該婚姻は、もはや社会生活上の実質的基礎を失つているものというべきであり、かかる状態においてなお戸籍上だけの婚姻を存続させることは、かえつて不自然であるということができよう。しかしながら、離婚は社会的・法的秩序としての婚姻を廃絶するものであるから、離婚請求は、正義・公平の観念、社会的倫理観に反するものであつてはならないことは当然であつて、この意味で離婚請求は、身分法をも包含する民法全体の指導理念たる信義誠実の原則に照らしても容認されうるものであることを要するものといわなければならない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「婚姻意思」に関する別の判例も確認する。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
しかし、右にいう「当事者間に婚姻をする意思がないとき」とは、当事者間に真に社会観念上夫婦であると認められる関係の設定を欲する効果意思を有しない場合を指すものと解すべきであり、したがつてたとえ婚姻の届出自体について当事者間に意思の合致があり、ひいて当事者間に、一応、所論法律上の夫婦という身分関係を設定する意思はあつたと認めうる場合であつても、それが、単に他の目的を達するための便法として仮託されたものにすぎないものであつて、前述のように真に夫婦関係の設定を欲する効果意思がなかつた場合には、婚姻はその効力を生じないものと解すべきである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
婚姻無効確認本訴並びに反訴請求 最高裁判所第二小法廷 昭和44年10月31日 (PDF)
このように、この最高裁判決で「婚姻の本質」として説明されている内容は、法律上の具体的な婚姻制度が存在することを前提として、その婚姻制度の法的な効果を発生させることが妥当であるか否かの「婚姻意思」の存否に関係する場面で論じられている説明である。
また、この「婚姻の本質」について説明している最高裁判決では、「裁判官佐藤哲郎の意見」の中で「離婚の本質」についても取り上げている。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
一 民法七七〇条一項五号は、同条の規定の文言及び体裁、我が国の離婚制度、離婚の本質などに照らすと、同号所定の事由につき専ら又は主として責任のある一方の当事者からされた離婚請求を原則として許さないことを規定するものと解するのが相当である。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
この「離婚の本質」についても、法律上の具体的な婚姻制度があることを前提として、「離婚」という法律行為をしようとする者に対して法的効果を及ぼすべき場合と、そうでない場合を区別する際の意味合いで用いられているものである。
同様に、「婚姻の本質」についても、法律上の具体的な婚姻制度の存在を前提として、その法的効果を及ぼすべき場合と、そうでない場合について論じる中で説明された文面である。
これらの理由で、最高裁判決の「両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもつて共同生活を営むことにある」という説明は、具体的な婚姻制度の枠組みが存在することを前提として、その制度を利用する者の間で生じる法律関係を示すために導かれた説明であり、これは具体的な婚姻制度の上位概念として位置付けられているものではないし、婚姻制度が形成される際の「国の立法目的」を示したものでもない。
ここでは「法律婚制度が、この本質に重要な価値を認め、これを具体化し実現し保護しようとしたことにあるためであると解される。」と述べているが、この「婚姻の本質」と称する説明は、具体的な「法律婚制度」を前提としてその制度を利用する者の法律関係について述べたものであるから、憲法上の「婚姻」の文言や「法律婚制度」の上位概念として位置付けられているわけではないし、この「婚姻の本質」と称する説明が「国の立法目的」となっているわけでもないため、この「婚姻の本質」「に重要な価値を認め、これを具体化し実現し保護しようとしたことに」「法律婚制度」があるかのような説明をしていることは、誤りである。
その他、この「婚姻の本質」と称する説明は、具体的な婚姻制度の上位概念として存在するものではないし、婚姻制度が形成される際の「国の立法目的」を示したものでもないことから、この「婚姻の本質」と称する説明を根拠として具体的な婚姻制度の枠組みを変更することはできないことに注意が必要である。
この一文は非常に読み取りづらいものとなっている。
その理由は、通常は「婚姻とは何か」という話が先にあり、その「婚姻」を前提として24条1項が「婚姻をするについての自由」について定めているという順序で論じられるところを、こここでは「再婚禁止期間大法廷判決」で述べられた「婚姻をするについての自由」についての文を先に持ってきた関係上、「婚姻」とは何かという話が後から遡る形で付け加えられているからである。
◇ 通常
「婚姻とは何か」
↓ ↓
「婚姻をするについての自由」
◇ この判決
「婚姻をするについての自由」
↓ ↓
「婚姻とは何か」
そのため、この文の前後を通常の形にして分かりやすく並べ替えると、下記のようになる。
「両当事者において永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもって共同生活を営むことに」「婚姻の本質が」「あり、」
↓ ↓
「この本質に重要な価値を認め、これを具体化し実現し保護しようとしたことに」「法律婚制度が」「あるため」
↓ ↓ (『所以』)
「法律婚制度を利用するについての自由が十分尊重に値するものとされるべき」
↓ ↓
「婚姻をするについての自由は、同条2項を通じて、法律により具体化された法律婚制度を利用するについての自由であると解される」
しかし、このように並べ替えたとしても、「婚姻の本質」と称する説明は、具体的な法律上の婚姻制度が存在することを前提としてその婚姻制度の内容を読み解いた際に「婚姻制度を利用している者」の法律関係の状態を簡潔に示したものであり、この判決がこれを「法律婚制度」を「具体化」する際の「① 国の立法目的」であるかのように考えていることが誤りであることは変わらない。
「このような本質的な人間の営みは、法律婚制度が整えられる以前から歴史上自生的に生じたものと考えられる。」との記載がある。
「このような本質的な人間の営みは、」との部分であるが、これが最高裁判決の示す「婚姻の本質」と称する説明について述べるものであるとすれば、それは具体的な婚姻制度の存在を前提として、その婚姻制度を利用する者の法律関係の状態を簡潔に示したものであるから、それを「人間の営み」と考えていることは誤りである。
また、その後の「法律婚制度が整えられる以前から歴史上自生的に生じたものと考えられる。」との部分についても、「婚姻の本質」と称する説明は、具体的な婚姻制度の存在を前提として、その婚姻制度を利用する者の法律関係の状態を示すものであるから、「法律婚制度」が「整えられる」ことによってその法律関係の状態を形成することが可能となるのであり、それを「法律婚制度が整えられる以前から歴史上自生的に生じたものと考えられる。」と認識していることも誤りである。
この名古屋地裁判決は最高裁判決が示した「婚姻の本質は、両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもつて共同生活を営むことにある」の文の「両性」の部分を「両当事者」に変えた上で、その示している内容について「人間の営み」や「歴史上自生的に生じたもの」と考えるものとなっている。
そのため、この「婚姻の本質」と称する説明の「精神的及び肉体的結合」の文言は、「恋愛・性愛」に対応するものであるかのように考え、これにより、「婚姻の本質」と称する説明は、「両性が永続的な」「恋愛・性愛」「を目的として真摯な意思をもつて共同生活を営むこと」を意味するものと読み取ろうとしている可能性が考えられる。
しかし、「婚姻の本質」と称する説明は、具体的な婚姻制度の存在を前提としてその制度を利用している者の法律関係の状態を簡潔に示したものであることから、その法律関係の意味を離れて、「永続的な精神的及び肉体的結合」や「真摯な意思」、「共同生活を営む」という文字だけを見て、その日本語としての語感を文学的な意味で捉えて、「それが婚姻である」、「婚姻の本質である」などと考えることはできない。
◇ 法学的な意味
・「両性」 ⇒ 「男性」と「女性」の要件を満たすこと。
・「永続的な」 ⇒ 有効期限がなく、利用者が死亡するまで利用することができること。
・「精神的……結合を目的として」 ⇒ 「相互の協力」が求められること
・「肉体的結合を目的として」 ⇒ 「貞操義務」があること。
・「真摯な意思をもつて」 ⇒ 「婚姻意思」があること。
・「共同生活を営む」 ⇒ 「同居義務」を定めていること。
◇ 文学的な語感で考える誤り
・「両性」 ⇒ 「両当事者」でもいいよね?(誤り)
・「永続的な」 ⇒ 「永遠」って何かロマンチックね!(誤り)
・「精神的……結合を目的として」 ⇒ 愛し合うことだよね!ロマンチック・ラブだ!(誤り)
・「肉体的結合を目的として」 ⇒ セックスのことだよね!(誤り)
・「真摯な意思をもつて」 ⇒ 真剣に考えてます!(誤り)
・「共同生活を営む」 ⇒ いつも一緒に居ようね!(誤り)
そのため、この「婚姻の本質」と称する説明について、法律関係の状態を指す法学的な意味を離れて、文学的な語感に基づいて理解しようとする試みは誤りである。
また、そもそも国が法制度として「恋愛・性愛」を保護する必要そのものがないのであり、婚姻制度の立法目的として「恋愛・性愛」を保護することが含まれているかのように考えている点でも誤りである。
もし「恋愛・性愛」という特定の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的とした制度が存在する場合には、20条1項後段・3項、89条の「政教分離原則」に抵触して違憲となるし、法制度を利用する者の内心に干渉するものとなるから、19条の「思想良心の自由」、20条1項前段の「信教の自由」に抵触して違憲となるし、国が保護する「恋愛・性愛」と、保護しない「恋愛・性愛」、あるいは、「恋愛・性愛」以外の思想、信条、信仰、感情(友情、友愛、絆などもそれにあたる)の間で差異を設けることになることから、14条の「平等原則」に抵触して違憲となる。
そのため、そもそも「恋愛・性愛」という特定の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的とした制度を立法することはできないのであり、「恋愛・性愛」を保護することを立法目的とする制度が存在することが許されることを前提として、婚姻制度と「恋愛・性愛」を結び付けて考えていることが誤りである。
これとは別に、「恋愛・性愛」という特定の思想、信条、信仰、感情に基づいて人的結合関係を形成することについては、憲法21条1項の「結社の自由」によって保障されることになる。
「法律婚制度を利用するについての自由が十分尊重に値するとされる背景にある価値は、人の尊厳に由来するものということができ、重要な人格的利益であるということができる。」との記載がある。
上記でも述べたように、「法律婚制度を利用するについての自由」とは最高裁の「再婚禁止期間大法廷判決」が示す「婚姻をするについての自由」に対応するものである。
そして、その最高裁判決は「婚姻をするについての自由」が「十分尊重に値するものと解することができる。」とする理由について、「配偶者の相続権(民法890条)や夫婦間の子が嫡出子となること(同法772条1項等)などの重要な法律上の効果が与えられるものとされている」ことを挙げているものである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
……(略)……また,同条1項は,「婚姻は,両性の合意のみに基いて成立し,夫婦が同等の権利を有することを基本として,相互の協力により,維持されなければならない。」と規定しており,婚姻をするかどうか,いつ誰と婚姻をするかについては,当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたものと解される。婚姻
は,これにより,配偶者の相続権(民法890条)や夫婦間の子が嫡出子となること(同法772条1項等)などの重要な法律上の効果が与えられるものとされているほか,近年家族等に関する国民の意識の多様化が指摘されつつも,国民の中にはなお法律婚を尊重する意識が幅広く浸透していると考えられることをも併せ考慮すると,上記のような婚姻をするについての自由は,憲法24条1項の規定の趣旨に照らし,十分尊重に値するものと解することができる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
よって、この名古屋地裁判決が「法律婚制度を利用するについての自由が十分尊重に値するとされる背景にある価値は、人の尊厳に由来するものということができ、」と述べている部分は、前提として用いている最高裁判決の内容を読み取るものではないという点で誤っている。
それとは別に、この段落全体を読み取って、この判決が言いたいであろうことを汲み取って検討すると、「歴史上自生的に生じた」「人の尊厳に由来する」「人間の営み」に「重要な人格的利益」があり、これに「重要な価値を認め、これを具体化し実現し保護しようとしたことに」「婚姻」があると考え、それを理由として「法律婚制度を利用するについての自由が十分尊重に値する」と述べようとしていると考えられる。
しかし、「歴史上自生的に生じた」「人の尊厳に由来する」「人間の営み」としての人的結合関係を形成する意思があるのであれば、それは「国家からの自由」という「自由権」の性質を持つ憲法21条1項の「結社の自由」によって保障されるものである。
そのため、個人が自己の意思で「性愛結社」を形成することを望む場合には、それによって保障されることになる。
それに対して、「婚姻」は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、それら他の様々な人的結合関係とは「生殖と子の養育」の観点から区別する意味で設けられた制度である。
そのとこから、この判決がいうような「恋愛・性愛」という営みがあるからといって、それを「婚姻」の中に含めることができるということにはならない。
よって、ここで「法律婚制度を利用するについての自由が十分尊重に値するとされる背景にある価値」について、この判決がいうような意味で「人の尊厳に由来するもの」と述べていることは誤りであるし、それについて「重要な人格的利益である」と述べていることも誤りである。
このような重要な人格的利益を実現するために制度化された法律婚制度は、既に見たように、両当事者等の身分関係を形成し、その関係を公証し、その身分関係を前提にこれを保護するのにふさわしい法律上の様々な効果を付与し、事実上も多彩な効果が生じるものとなっている。そして、人間が社会的な存在であり、その人格的生存に社会的な承認が不可欠であることを踏まえれば、上記多彩な効果において、とりわけ重要なのは、両当事者が安定して永続的な共同生活を営むために、両当事者の関係が正当なものであるとして社会的に承認されることが欠かせないということである。それゆえに、法律婚制度には、様々な効果が付与されるにとどまらず、身分関係を公に認め、これを公示し公証する制度が結び付けられているものと解されるのである。
【筆者】
「このような重要な人格的利益を実現するために制度化された法律婚制度は、既に見たように、両当事者等の身分関係を形成し、その関係を公証し、その身分関係を前提にこれを保護するのにふさわしい法律上の様々な効果を付与し、事実上も多彩な効果が生じるものとなっている。」との記載がある。
「このような重要な人格的利益を実現するために制度化された法律婚制度は、」との部分について検討する。
まず、この「人格的利益」の文言は、「エ」の第一文で「前記ウのとおり、憲法24条2項は憲法上直接保障された権利とまではいえない人格的利益をも尊重すべきこと等についても十分に配慮した法律の制定を求めるものである。」と述べていることに続くものであり、その「ウ」の「夫婦同氏制大法廷判決」の示している憲法24条2項の「個人の尊厳」から導かるものとしての「人格的利益」について述べているものである。
しかし、この「夫婦同氏制大法廷判決」では、憲法24条2項の「婚姻及び家族」の枠組みの「要請」に従って立法された法律上の具体的な制度が「個人の尊厳」を満たすか否かが問われているのに対して、この名古屋地裁判決で問われているのは、憲法24条2項の「家族」が、ここでいう「同性間の人的結合関係」を対象とした制度を立法することを「要請」しているか否かであり、これらの間では事案が異なっている。
「夫婦同氏制大法廷判決」では、憲法24条2項の「婚姻及び家族」の枠組みの「要請」に従って立法された法律上の具体的な制度が「個人の尊厳」を満たすか否かを問うものとして「人格的利益」について触れるものとなっているが、この段階で問われている審査の内容を、名古屋地裁判決で問われているそれ以前の憲法24条2項の「家族」が「要請」しているか否かの次元の問題に対して用いることはできない。
そのため、名古屋地裁判決の憲法24条2項の「家族」が「要請」しているか否かが問われ、「要請」していれば違憲となり、「要請」していないのであれば合憲となるという事案に対して、「夫婦同氏制大法廷判決」で問われた「人格的利益」の文言を根拠として、憲法24条2項に違反すると判断することはできない。
そのことから、これができることを前提として、この名古屋地裁判決の事案に対して「夫婦同氏制大法廷判決」で示された「人格的利益」を持ち出して、論じようとしている部分が誤りである。
上記の「夫婦同氏制大法廷判決」が示した24条2項の「個人の尊厳」に基づく「人格的利益」ではなく、13条によって保障されることのある「人格的利益」の観点から検討するとしても、これは国家から個人に対して具体的な侵害行為がある場合に、その侵害を排除するという「国家からの自由」という「自由権」として用いられることがあるというものであり、これによって具体的な制度の創設を国家に対して求めることはできない。
そのため、「国家からの自由」としての「自由権」の意味で「人格的利益」の意味を用いているのであれば、それによって具体的な制度の創設を国家に対して求めることはできないのであり、ここで「このような重要な人格的利益を実現するために制度化された法律婚制度」のように、「国家からの自由」という「自由権」を実現するために具体的に「法律婚制度」が「制度化された」かのように述べていることは、権利の性質を理解しないものであり、誤りとなる。
「法律婚制度」について、「両当事者等の身分関係を形成し、その関係を公証し、その身分関係を前提にこれを保護するのにふさわしい法律上の様々な効果を付与し、事実上も多彩な効果が生じるものとなっている。」と述べている部分を検討する。
「身分関係を形成し、」とあるが、婚姻制度が「身分関係」を形成するものとなっている理由は、婚姻制度が「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するためである。
人間は有性生殖を行うことによって子孫を生むという身体機能を有しており、その男女の間で行われる「生殖」に関わって生じる不都合が社会的な課題となっていることから、「身分関係」を形成することによって、この問題の解決を図るのである。
そのため、この「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を切り離して「身分関係」を形成する意味を捉えることはできないことに注意が必要である。
「その身分関係を前提にこれを保護するのにふさわしい法律上の様々な効果を付与し、」とあるが、婚姻制度は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成するための手段として整合的な効果を設定するものである。
「事実上も多彩な効果が生じるものとなっている。」との部分であるが、これは「イ」の第二段落の第二文で述べている「事実上の効果として、婚姻制度を利用することにより、社会的な信用が形成され、信任が得られるなどの社会的な効果のほか、そうした地位に立ったことによる精神的心理的効果をも生じさせるものである。」のことを述べているものと思われる。
しかし、これは「婚姻制度を利用する」者は「社会的な信用が形成され」ているだとか「信任が得られる」などと考え、反対に婚姻制度を利用していない者は「社会的な信用が形成され」ていないだとか「信任が得られ」ないという特定の価値観を抱く者の主張に過ぎない。
法律論として考えたならば、婚姻制度を利用していなくとも「社会的な信用」は「形成」されるし「信任」も得ることが可能である。
判決の文面において法律上の効果を論じる際に、このような特定の価値観を抱く者の主張に与する形で論じるべきではない。
他にも、この「⑶ 憲法24条2項に違反するかについて」の項目で問われているのは、憲法24条2項の「家族」が、「親子」や「親子」の関係を基本とした「兄弟」「姉妹」などに含まれない「同性間の人的結合関係」を対象とする制度を立法することを「要請」しているか否かである。
これは憲法24条2項の条文そのものから意味を明らかにしなければならないのであり、「法律婚制度」における「法律上の様々な効果」のように、下位の法令を検討することによって、その上位法である憲法24条2項の意味を明らかにすることはできない。
よって、ここで法律上の具体的な制度についての「効果」を検討することによって、それよりも上位法である憲法24条2項の意味を明らかにしようとしていることは、法秩序の階層構造を損なわせるものであり、解釈の方法として誤りである。
「人間が社会的な存在であり、その人格的生存に社会的な承認が不可欠であることを踏まえれば、上記多彩な効果において、とりわけ重要なのは、両当事者が安定して永続的な共同生活を営むために、両当事者の関係が正当なものであるとして社会的に承認されることが欠かせないということである。」との記載がある。
まず、「人間が社会的な存在であり、」との部分であるが、人間の中には無人島やジャングルの中で一人で生活している者もいることを無視しない方がいいと思われる。
次に、この文が下記について述べている部分を検討する。
◇ 「人間」の「人格的生存に社会的な承認が不可欠である」
◇ 「上記多彩な効果において、とりわけ重要なのは、両当事者が安定して永続的な共同生活を営むために、両当事者の関係が正当なものであるとして社会的に承認されることが欠かせない」
ここでは、「社会的な承認」と「社会的に承認」が登場する。
これは、「上記多彩な効果」によるものとしており、一文前で「事実上も多彩な効果が生じる」と述べていることから、これは「イ」の第二段落の第二文の「事実上の効果として、婚姻制度を利用することにより、社会的な信用が形成され、信任が得られるなどの社会的な効果のほか、そうした地位に立ったことによる精神的心理的効果をも生じさせるものである。」と述べている部分に対応するようである。
しかし、「イ」の第二段落の第二文を解説した部分でも述べたが、婚姻制度を利用したとしても「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するための制度を利用しているというだけのことであり、それによって「社会的な信用が形成され、信任が得られる」と考えることは個人の価値観によるものであって、法律論ではない。
法律論として考えれば、「婚姻制度を利用していない者(独身者)」であるとしても、その状態で既に完全な状態であるから、社会的な立場として完全に承認されているのであり、それがあたかも承認されていないかのような説明は誤りである。
もしこれが法律論を述べるものではないとすれば、「婚姻制度を利用していない者(独身者)」は「社会的な承認」が得られていないなどという特定の価値観に与する主張を裁判所が行っていることになるのであり、その内容からして不当である。
裁判所が「婚姻している者(既婚者)」のグループを持ち上げ、「婚姻していない者(独身者)」のグループを下に見るような言説を前提として論じることは不適切である。
「人間」の「人格的生存に社会的な承認が不可欠である」との部分について検討する。
ここでは「婚姻していない者(独身者)」は「社会的な承認」が存在しておらず、「人格的生存」が満たされていないことを前提に、制度によって「社会的に承認」されることが「不可欠である」や「欠かせない」と述べるものとなっている。
しかし、憲法は「個人の尊厳」に基づいており、自然人は「個人主義」の下に各々「自律的な個人」として生存していくことを予定していることから、「婚姻していない者(独身者)」の状態で既に完全である。
そのため、「婚姻していない者(独身者)」の状態でも何ら不完全でも不足した状態にあるわけでもなく、人が生命を維持し、生存し、生活していくために必要となる最低限のものを指す「人格的生存」は満たされている。
そのため、「婚姻制度を利用していない者(独身者)」が「人格的生存」が満たされていないとか、「社会的な承認」がないことを前提として論じていることは誤りである。
「それゆえに、法律婚制度には、様々な効果が付与されるにとどまらず、身分関係を公に認め、これを公示し公証する制度が結び付けられているものと解されるのである。」との記載がある。
「法律婚制度」は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として設けられた制度であり、「様々な効果」や「身分関係を公に認め、これを公示し公証する制度」と称するものはその目的を達成するための手段として定められているものである。
そして、それらについても、その目的を達成するための手段として合理的な範囲でのみ「法律婚制度」を利用していない者との間で生じる差異を正当化することができるものである。
しかし、ここではこれらの「様々な効果」や「身分関係を公に認め、これを公示し公証する制度」は、「人格的生存に社会的な承認が不可欠である」ために設けられていると考えているようであるが、「婚姻制度を利用していない者(独身者)」であっても、そのことによって「人格的生存」が損なわれているという事実はないし、「社会的な承認」が存在しないというわけでもないため、それを理由として「法律婚制度」が定められているとの理解は誤りである。
そうすると、永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもって共同生活を営むという重要な人格的利益を実現する上では、両当事者が正当な関係であると公証され、その関係を保護するのにふさわしい効果の付与を受けるための枠組みが与えられる利益が極めて重要な意義を有すると解されるのであり、単に、両当事者が共同生活を営むのを妨げられなければ事足りるとされるものではないというべきである。そして、こうした社会的承認は、様々な方法により与えられうるもので、歴史上も多様な方式、慣習が存在していたと考えられるが、わが国においては、国によって全国的に統一された均一の内容を持つ戸籍制度が完備されて久しくなり、国民の中にはなお法律婚を尊重する意識が幅広く浸透していることに鑑みると、国による統一された制度によって公証されることが、正当な関係として社会的承認を得たといえるための有力な手段になっていると理解することができる。
【筆者】
「永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもって共同生活を営むという重要な人格的利益を実現する上では、両当事者が正当な関係であると公証され、その関係を保護するのにふさわしい効果の付与を受けるための枠組みが与えられる利益が極めて重要な意義を有すると解されるのであり、単に、両当事者が共同生活を営むのを妨げられなければ事足りるとされるものではないというべきである。」との記載がある。
「永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもって共同生活を営むという重要な人格的利益を実現する上では、」との部分について検討する。
まず、「永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもって共同生活を営む」の部分は、最高裁判決(昭和62年9月2日・PDF)が「婚姻の本質は、両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもつて共同生活を営むことにある」と説明している部分から抜き出したようである。
しかし、この最高裁判決には「両性が」と書かれており、この名古屋地裁判決がこれを欠落させていることは、特定の結論を導き出すために恣意的に引用部分を限定していることが考えられ、不適切である。
次に、この最高裁判決の示す「婚姻の本質」と称する説明は、具体的な法律上の婚姻制度が存在することを前提として、その婚姻制度を利用する者の権利・義務の結び付きによる法律関係の状態を簡潔に示したものである。
これは、「両性」の部分は「男女」であること、「永続的な」の部分は死亡するまで有効期限がないこと、「精神的及び肉体的結合を目的」の部分は「相互の協力」や「貞操義務」を負うこと、「共同生活を営む」の部分は「同居義務」を負うことに対応するからである。
この最高裁判決の内容についても、具体的な法制度が存在することを前提として、その制度の要件に従う形で制度を利用する者について、その制度による法的な効果を及ぼすべきか否かが論点となっている事案である。
憲法24条の「婚姻」
↓
法律上の「婚姻」
↓
「婚姻の本質」と称する説明(法律関係)
↓
具体的に事例に法的効果を及ぼすべきかどうか
そのため、この「婚姻の本質」と称する説明は、婚姻制度よりも上位の概念として存在するものではないし、婚姻制度についての「① 国の立法目的」を示したものでもない。
よって、ここでは「永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもって共同生活を営む」の文に続く形で「という重要な人格的利益を実現する上では、」のように述べていることから、「婚姻の本質」と称する説明を基にして何らかの具体的な制度の創設を「実現する」かのような説明をしていることになるが、そもそも「婚姻の本質」と称する説明を基にして具体的な制度の内容を導き出すことはできないという点で誤っている。
三つ目に、「人格的利益」の文言であるが、これは、この「エ」の第一段落で「前記ウのとおり、憲法24条2項は憲法上直接保障された権利とまではいえない人格的利益をも尊重すべきこと等についても十分に配慮した法律の制定を求めるものである。」と述べているため、その「前記ウ」に記載された「夫婦同氏制大法廷判決」の中で示された「人格的利益」について述べようとするものと考えられる。
しかし、この「夫婦同氏制大法廷判決」では、憲法24条2項の「婚姻及び家族」の枠組みの「要請」に従って立法された法律上の具体的な制度の内容が「個人の尊厳」を満たすか否かが問われているのに対して、この名古屋地裁判決では、憲法24条2項の「家族」が「要請」しているか否かが問われており、これらは事案を異にしている。
そのため、「夫婦同氏制大法廷判決」の憲法24条2項の「婚姻及び家族」の枠組みの「要請」に従って立法された法律上の具体的な制度の内容が「個人の尊厳」を満たすか否かという次元の問題を用いて、この名古屋地裁判決で問われている憲法24条2項の「家族」が「要請」しているか否かについての結論を導き出すことはできない。
よって、この名古屋地裁判決で問われている内容に対しては、「夫婦同氏制大法廷判決」の中で「個人の尊厳」を満たすか否かの判断の中で示された「人格的利益」の文言が持ち出される前提を欠いており、これを持ち出して論じようとしていることそのものが誤りである。
四つ目に、「永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもって共同生活を営む」という文の「精神的及び肉体的結合」の部分を法学的な意味ではなく、文学的な語感に基づいて「恋愛・性愛」を意味するものと考えて、「永続的な」「恋愛・性愛」「を目的として真摯な意思をもって共同生活を営む」ことについて「重要な人格的利益」と考えて、それを「実現する」と考えている場合について検討する。
この場合、ここでいう「人格的利益」は、憲法13条を根拠とするものと考えられ、国家から個々人に対して具体的な侵害行為が存在し、そのような「営む」ことが制限されるようなことがあれば、「国家からの自由」という「自由権」の側面によって、その侵害を排除することが可能な場合が考えられる。
しかし、その憲法13条を根拠として具体的な制度の創設を国家に対して求めることはできないのであり、当然、憲法13条を基にした「人格的利益」によっても、具体的な制度の創設を国家に対して求めることはできない。
五つ目に、「恋愛・性愛」という特定の思想、信条、信仰、感情に基づいて法制度を立法してはならない。
もし「恋愛・性愛」という思想、信条、信仰、感情に基づいて制度を立法した場合には、憲法20条1項後段・3項、89条の「政教分離原則」に抵触して違憲となるし、法制度を利用する者の内心に干渉するものとなることから、憲法19条の「思想良心の自由」、20条1項前段の「信教の自由」に抵触して違憲となるし、他の思想、信条、信仰、感情との間で区別取扱いをすることになることから、14条の「平等原則」に抵触して違憲となる。
そのため、ここで「永続的な」「恋愛・性愛」「を目的として真摯な意思をもって共同生活を営む」ことについて「重要な人格的利益」と考えて、それを「実現する」ために法制度を立法しようとしているとしても、そのような「恋愛・性愛」という思想、信条、信仰、感情を保護するために制度を立法した場合には、それ自体で違憲となる。
よって、それが可能であるかのような前提の下に論じていることも、妥当でない。
「両当事者が正当な関係であると公証され、その関係を保護するのにふさわしい効果の付与を受けるための枠組みが与えられる利益が極めて重要な意義を有すると解されるのであり、単に、両当事者が共同生活を営むのを妨げられなければ事足りるとされるものではないというべきである。」との部分について検討する。
まず、「正当な関係」との部分であるが、このような表現を用いた場合には、反対に「不当な関係」というものが存在することを前提とするものとなるため、法律論として妥当ではない。
婚姻制度を利用する者は、単に「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度を利用しているというだけの者であり、法律論として考えれば、それは「正当な」ものであるか、「不当な」ものであるかという価値判断が入り込む余地はない。
もし「婚姻している者(既婚者)」が複数名との間で性的な接触を行った場合に、婚姻制度による法律関係を形成している「夫婦」である「男女」と、その「夫婦」の一方と性的接触を行った「夫婦」以外の者との間での「男女」との関係性が比較され、「夫婦」の場合は「貞操義務」に反するものではないが、その「夫婦」以外の者との間での性的接触は「貞操義務」に反するものとして「離婚の訴え」や「損害賠償」の対象となるという違いが生じるという場合は考えられる。
しかし、これは制度を利用する者と利用しない者との間では、法律関係としては制度を利用した方が利用しない者よりは、「離婚の訴え」や「損害賠償」などの権利を得ることができる地位にあるという意味において有利になるというだけのことである。
この仕組みに着目して「正当な」と表現しているのかもしれないが、それはある制度が存在することを前提としてその制度の仕組みに着目して後付けで評価を行っているものであるから、その後付けで行われてた評価の部分を得るがために、その原因となっている制度の枠組みの方を自由に変えることができるとする根拠にはならないことに注意が必要である。
なぜならば、「婚姻」が「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために設けられている枠組みであるにもかかわらず、その枠組みの妥当性によって支えられている評価の部分を得ようとするがために、その枠組みの目的とその目的を達成するための手段の関係を無視して、その枠組みを「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するものとして機能しないものに変えてしまったならば、そもそも「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために設けられている枠組みとしての妥当性が損なわれ、そこから生じていた評価も失われ、結果として得ようとしていた評価さえも手に入らない状態に陥るからである。
そのため、婚姻制度の枠組みが存在することを前提として、その枠組みに対して結果として生じている評価の部分を持ち出して、その枠組みに当てはまらない場合であっても同様の評価を得ることができるかのような認識の下に論じている部分は妥当でない。
よって、「正当な関係」のように「不当な関係」というものが存在することを前提とする表現は適切ではないし、婚姻制度における「夫婦」の「男女」と、その「夫婦」の一方と別の「異性」との間の「男女」とを区別する場合をいうのであれば、それは「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するための仕組みに依存するものであり、その枠組みに沿わない場合にまで同様の区別が可能となるわけではないという点で主張の根拠を欠くものであり、妥当でない。
「両当事者が正当な関係であると公証され、その関係を保護するのにふさわしい効果の付与を受けるための枠組みが与えられる利益が極めて重要な意義を有する」とあるが、ここでいう「両当事者」とは、この文の直前の「永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもって共同生活を営む」「両当事者」ということになる。
そして、この判決は「精神的及び肉体的結合」の部分を「恋愛・性愛」に対応するものと考えているようなので、「永続的な」「恋愛・性愛」「を目的として真摯な意思をもって共同生活を営む」「両当事者」に対して「公証」と「保護するのにふさわしい効果」「の枠組み」が「極めて重要」と述べていることになる。
しかし、「恋愛・性愛」という特定の思想、信条、信仰、感情を保護するために法制度を立法した場合には、憲法20条1項後段・3項、89条の「政教分離原則」に抵触して違憲となる。
また、制度を利用する者が「恋愛・性愛」という特定の思想、信条、信仰、感情を有することを前提とするものとなり、個々人の内心に対して国家が干渉するものとなるから、憲法19条の「思想良心の自由」、憲法20条1項前段の「信教の自由」に抵触して違憲となる。
さらに、「恋愛・性愛」という特定の思想、信条、信仰、感情を保護し、それ以外の思想、信条、信仰、感情を保護しないことになることから、憲法14条の「平等原則」に抵触して違憲となる。
そのため、「永続的な」「恋愛・性愛」「を目的として真摯な意思をもって共同生活を営む」「両当事者」に対して「公証」と「保護するのにふさわしい効果」「の枠組み」というものを立法することが許されるかのように述べている部分が誤りである。
もし「永続的な」「恋愛・性愛」「を目的として」「共同生活を営む」というのであれば、それは「国家からの自由」という「自由権」として、憲法21条1項の「結社の自由」によって保障されることになる。
「単に、両当事者が共同生活を営むのを妨げられなければ事足りるとされるものではないというべきである。」との部分であるが、「恋愛・性愛」という特定の思想、信条、信仰、感情を保護するために法制度を立法することはできないため、「恋愛・性愛」という特定の思想、信条、信仰、感情に基づく「共同生活を営む」ことは、基本的に憲法21条1項の「結社の自由」によって保障されるものとなり、それは「国家からの自由」という「自由権」の性質であるから、それが「妨げられな」いというものとなる。
国(行政府)の主張では、下記のように述べられている。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
しかしながら、被告第3準備書面第1の2(7ページ)で述べた通り、人は、一般に社会生活を送る中で、種々の、かつ多様な人的結合関係を生成しつつ、生きていくものであり、当該人的結合関係の構築、維持及び解消をめぐる様々な場面において幾多の自己決定を行っていくものと解されるが、そのような自己決定を故なく国家により妨げられているか否かということと、そのような自己決定の対象となる人的結合関係について国家の保護を求めることができるか否かということは、区別して検討されるべきものと解される。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【東京二次・第9回】被告第7準備書面 令和5年9月28日 PDF (P9~10)
「こうした社会的承認は、様々な方法により与えられうるもので、歴史上も多様な方式、慣習が存在していたと考えられるが、わが国においては、国によって全国的に統一された均一の内容を持つ戸籍制度が完備されて久しくなり、国民の中にはなお法律婚を尊重する意識が幅広く浸透していることに鑑みると、国による統一された制度によって公証されることが、正当な関係として社会的承認を得たといえるための有力な手段になっていると理解することができる。」との記載がある。
「こうした社会的承認は、様々な方法により与えられうるもので、歴史上も多様な方式、慣習が存在していたと考えられるが、」との部分について検討する。
まず、憲法は「個人の尊厳」の原理に基づいており、自然人は「個人主義」の下に各々自律的な個人」として生存していくことを予定していることから、「婚姻していない者(独身者)」の状態で既に完全な状態であり、そこに「社会的承認」がないなどということはない。
よって、「社会的承認」がないことを前提として、「社会的承認」を与えるために制度を立法しなければならないということにはならないのであり、「社会的承認」のために「様々な方法」や「歴史上」の「多様な方式、慣習」を検討していることは妥当でない。
「わが国においては、国によって全国的に統一された均一の内容を持つ戸籍制度が完備されて久しくなり、」との部分について検討する。
「戸籍制度」は「婚姻及び家族」に関することを定めた内容となっているが、これは「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するための手段として設けられているものである。
その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たさない場合には、「戸籍制度」の対象とはならないことは当然予定されているものである。
そのため、「国によって全国的に統一された均一の内容を持つ戸籍制度」が存在するとしても、その対象とはならない場合にまでこの中に含めなければならないということにはならない。
法制度は常に立法目的とその立法目的を達成するための手段として整合的な形で設けられるのであり、それを無視して制度の中に含めなければならないということにはならないからである。
「国民の中にはなお法律婚を尊重する意識が幅広く浸透していることに鑑みると、」との部分について検討する。
これは、「国民の中」で「法律婚」が「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するための手段として合理的な内容となっていることが知られていることによるものである。
しかし、その枠組みが変更された場合には「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するものとして十分に機能しなくなり、「法律婚を尊重する意識」が失われることも起こり得る。
そのため、「法律婚を尊重する意識」があることを理由として、その「法律婚」の枠組みを変更しようとする主張は、その「法律婚を尊重する意識」が生じている原因を損なうことにより、その「法律婚を尊重する意識」までも失わせるものとなるため妥当でないことに注意が必要である。
「国による統一された制度によって公証されることが、正当な関係として社会的承認を得たといえるための有力な手段になっていると理解することができる。」との部分について検討する。
まず、憲法は「個人の尊厳」の原理に基づいており、自然人は「個人主義」の下に各々「自律的な個人」として生存していくことを予定していることから、その状態で既に完全な状態といえるため、「社会的承認」を得ているといえる。
よって、「婚姻制度を利用していない者(独身者)」が「社会的承認」を得ていないことを前提に、婚姻制度を利用し「国による統一された制度によって公証されること」で「社会的承認」を得るかのような説明をしていることは妥当でない。
次に、「正当な関係」との部分について、このような表現を用いた場合には、反対に「不当な関係」というものが存在することを前提とするものとなるため妥当でない。
「婚姻している者(既婚者)」は、単に「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度を利用している者に過ぎず、それが「正当」であるか否かという認識は法律論として通用するものではない。
そのため、ここで「正当な関係」と述べている部分は、この判決を書いた裁判官の個人的な価値観が現れたものということになる。
世の中の様々な人的結合関係を「正当な関係」と「不当な関係」に分けた上で、その「正当な関係」として認めるべきか否かを論じようとしていることは、そもそも「不当な関係」というものが存在することを前提とするものであるため妥当でないし、法制度が単に政策目的を達成するための手段として設けられた枠組みであることとは別の次元の話であり、法律論とは異なるものであるため妥当でない。
こうした両当事者の関係が国の制度により公証され、その関係を保護するのにふさわしい効果の付与を受けるための枠組みが与えられるという利益は、憲法24条2項により尊重されるべき重要な人格的利益であると解される。
【筆者】
「こうした両当事者の関係が国の制度により公証され、その関係を保護するのにふさわしい効果の付与を受けるための枠組みが与えられるという利益は、」との部分について検討する。
この名古屋地裁判決で問われているのは、「憲法24条2項」の「家族」が、ここでいう「同性間の人的結合関係」を対象とした制度を立法することを「要請」しているか否かである。
そして、ここでいう「同性間の人的結合関係」については、「親子」や「親子」の関係に基づく「兄弟」「姉妹」などではないため、「家族」の中には含まれない。
そのことから、「憲法24条2項」の「家族」は、ここでいう「同性間の人的結合関係」を対象とした制度を立法することを「要請」していないことになる。
「憲法24条2項」は「婚姻及び家族」の制度については立法することを「要請」しているが、それ以外については何ら触れていないため、「憲法24条2項」はここでいう「両当事者の関係が国の制度により公証され、その関係を保護するのにふさわしい効果の付与を受けるための枠組み」と称するものを立法することを「要請」するものではない。
よって、「憲法24条2項」が「両当事者の関係が国の制度により公証され、その関係を保護するのにふさわしい効果の付与を受けるための枠組み」と称するものを立法することを「要請」していることを前提として、それが「与えられるという利益」というものが存在するかのように述べている部分が誤りである。
「憲法24条2項により尊重されるべき重要な人格的利益であると解される。」との部分について検討する。
これは「夫婦同氏制大法廷判決」が「憲法24条2項」の「婚姻及び家族」の枠組みの「要請」に従って立法された法律上の具体的な制度の内容について「個人の尊厳」を満たすか否かが問われている中において「人格的利益」について触れている部分から抜き出したものである。
しかし、この名古屋地裁判決で問われているのは「憲法24条2項」の「家族」が「親子」や「親子」の関係に基づく「兄弟」「姉妹」に含まれない「同性間の人的結合関係」を対象とした制度を立法することを「要請」しているか否かであり、「夫婦同氏制大法廷判決」とは事案が異なっている。
そのため、この名古屋地裁判決で問われている問題に対して、「夫婦同氏制大法廷判決」における「個人の尊厳」に基づく「人格的利益」を持ち出して論じることができるかのように考えている部分が誤りである。
しかしながら、同性カップルは、制度上、このような重要な人格的利益を享受できていないのである。
【筆者】
まず、「人格的利益」の部分であるが、これは、「夫婦同氏制大法廷判決」において憲法24条2項の「婚姻及び家族」の枠組みの「要請」に従って立法された法律上の具体的な制度の内容について「個人の尊厳」を満たすか否かが問われている中において「人格的利益」について触れている部分から抜き出したものとなっている。
しかし、その「夫婦同氏制大法廷判決」で問われているのは、憲法24条2項の「婚姻及び家族」の枠組みの「要請」に従って立法された法律上の具体的な制度の内容について「個人の尊厳」を満たすか否かであるのに対して、この名古屋地裁判決で問われているのは、憲法24条2項の「家族」が「親子」や「親子」の関係を基本とした「兄弟」「姉妹」などに含まれないここでいう「同性カップル」という「同性間の人的結合関係」を対象とした制度を立法することを「要請」しているか否かであり、これらは事案を異にしている。
そのため、名古屋地裁判決で問われている問題に対しては「夫婦同氏制大法廷判決」が「個人の尊厳」を基にして「人格的利益」を示している部分を用いることができるとする前提にない。
よって、ここでその「夫婦同氏制大法廷判決」で示された「人格的利益」を用いて論じようしていること自体が誤りである。
この「エ」の内容は読み取りづらいため、下記のように整理する。
=======================================
「両当事者において永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもって共同生活を営むことに」「婚姻の本質が、」「あり、」
↓ ↓
「このような本質的な人間の営みは、」「歴史上自生的に生じたものと考えられる。」(法律婚制度が整えられる以前から)
↓ ↓
「人の尊厳に由来するものということができ、重要な人格的利益であるということができる。」
↓ ↓
「そうすると、永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもって共同生活を営むという重要な人格的利益を実現する上では、」「単に、両当事者が共同生活を営むのを妨げられなければ事足りるとされるものではないというべきである。」
↓ ↓
「人間が社会的な存在であり、その人格的生存に社会的な承認が不可欠であることを踏まえれば、」「とりわけ重要なのは、両当事者が安定して永続的な共同生活を営むために、両当事者の関係が正当なものであるとして社会的に承認されることが欠かせないということである。」
↓ ↓
「両当事者が正当な関係であると公証され、その関係を保護するのにふさわしい効果の付与を受けるための枠組みが与えられる利益が極めて重要な意義を有すると解されるのであり、」
↓ ↓
「憲法24条2項は憲法上直接保障された権利とまではいえない人格的利益をも尊重すべきこと等についても十分に配慮した法律の制定を求めるものである。」
↓ ↓
「こうした両当事者の関係が国の制度により公証され、その関係を保護するのにふさわしい効果の付与を受けるための枠組みが与えられるという利益は、憲法24条2項により尊重されるべき重要な人格的利益であると解される。」
↓ ↓
「このような重要な人格的利益を実現するために」「法律婚制度は、」「制度化された」
「この本質に重要な価値を認め、これを具体化し実現し保護しようとしたことに」「法律婚制度が、」「あるためであると解される。」
↓ ↓
「それゆえに、法律婚制度には、」「上記多彩な効果において、」「様々な効果が付与されるにとどまらず、」「既に見たように、」
「身分関係を公に認め、これを公示し公証する制度が結び付けられているものと解されるのである。」
「両当事者等の身分関係を形成し、その関係を公証し、その身分関係を前提にこれを保護するのにふさわしい法律上の様々な効果を付与し、事実上も多彩な効果が生じるものとなっている。」
↓ ↓
「こうした社会的承認は、様々な方法により与えられうるもので、歴史上も多様な方式、慣習が存在していたと考えられる」
↓ ↓
「わが国においては、国によって全国的に統一された均一の内容を持つ戸籍制度が完備されて久しくなり、国民の中にはなお法律婚を尊重する意識が幅広く浸透している」
↓ ↓(鑑みると、)
「国による統一された制度によって公証されることが、正当な関係として社会的承認を得たといえるための有力な手段になっていると理解することができる。」
↓ ↓ ↑(背景にある価値)(所以)
「同条1項は、婚姻をするかどうか、いつ誰と婚姻をするかについては、当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたものと解され、」
「婚姻をするについての自由は、同条2項を通じて、法律により具体化された法律婚制度を利用するについての自由であると解されるが、」
↓ ↓
「このような婚姻をするについての自由は、同項の規定の趣旨に照らし、十分尊重に値するものと解することができる。(再婚禁止期間大法廷判決参照)」
「したがって、法律婚制度を利用するについての自由が十分尊重に値するとされる」
「そのような法律婚制度を利用するについての自由が十分尊重に値するものとされるべき」
↓ ↓
「しかしながら、同性カップルは、制度上、このような重要な人格的利益を享受できていないのである。」
=======================================
しかし、このようにまとめても「エ」の内容が誤っていることは変わらない。
一つ目に、「恋愛・性愛」など特定の価値観を抱くか否かは、憲法19条の「思想良心の自由」の範囲の問題であり、「婚姻」という枠組みとは関係がない。
「共同生活」についても、憲法21条1項の「結社の自由」の範囲の問題であり、これも「婚姻」という枠組みとは関係がない。
もしこれらが国家によって妨げられている場合には、「国家からの自由」という「自由権」としてその侵害を排除することが可能であるが、その「自由権」によって具体的な制度の創設を国家に対して求めることができることにはならない。
よって、そのような「人間の営み」があることを理由として、「法律婚制度」が存在するかのような理解は誤りである。
二つ目に、婚姻制度は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度であり、その内容は、その目的を達成するための手段として整合的な効果を設定しているものである。
そのため、「恋愛・性愛」などの特定の価値観を抱いていることを根拠として制度を設けているわけではないし、「共同生活」をしていることを根拠として制度を設けているものでもない。
よって、「恋愛・性愛」や「共同生活」を根拠として婚姻制度が設けられているかのような理解は誤りである。
三つ目に、憲法24条1項の「婚姻をするについての自由」とは、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度を利用することについての自由をいう。
そのため、そもそも「婚姻」の対象とならない場合には「婚姻をするについての自由」を適用する前提にない。
よって、「婚姻をするについての自由」を持ち出して「婚姻」の枠を変えることができるかのような理解は誤りである。
オ 前記ウのとおり、憲法24条の適合性を審査するためには、本件諸規定により具体化された現行の「家族」に関する法制度の趣旨を検討する必要がある。
【筆者】
上記「イ」の第四段落の第二文の解説として説明したように、24条2項の「家族」は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために設けられた「婚姻」の立法政策に付随する形で同一の目的を共有し、その立法目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす形で規律される枠組みであり、ここでいう「本件諸規定により具体化された現行の「家族」に関する法制度の趣旨」についても、この枠組みに重なる内容である。
もう一つ、この「⑶ 憲法24条2項に違反するかについて」の項目で問われているは、24条2項の「家族」が「親子」や「親子」の関係を基本とした「兄弟」「姉妹」などに含まれない「同性間の人的結合関係」に対して制度を立法することを「要請」しているか否かである。
「要請」している場合にはその制度がないことは違憲であり、「要請」していない場合にはその制度がないことは合憲となるというものである。
しかし、その憲法24条2項を解釈する際には、24条2項の文言そのものから意味を明らかにしなければならないのであり、この24条2項よりも下位法にあたる「本件諸規定により具体化された現行の「家族」に関する法制度の趣旨」を用いてその上位法に当たる憲法24条2項の意味を確定することはできない。
これは、法秩序は階層構造を有しており、下位法は上位法の許す範囲でのみ定めることが可能となっているにもかかわらず、下位法を根拠として上位法の意味が決まることになれば、上位法によって下位法を統制することができなくなり、法秩序の階層構造を損なわせることになるからである。
そのため、ここでは「憲法24条の適合性を審査するため」に、その下位法にあたる「本件諸規定により具体化された現行の「家族」に関する法制度」を持ち出し、その「趣旨を検討する」ことを述べるものとなっているが、このような下位法を基にして上位法の意味を解き明かそうとする試みは、法秩序の階層構造を損なわせるものであるから、解釈の手続きとして正当化することはできない。
よって、これより以下の「本件諸規定により具体化された現行の「家族」に関する法制度の趣旨を検討する」ことによって、その上位法である「憲法24条」に対する「適合性を審査」しようとしている部分は、すべて誤りである。
既に見たとおり、歴史上、家族は、男女の結合関係(婚姻)を中核とし、その間に生まれた子の保護・育成を担うものであると捉えられてきており、本件諸規定の制定当時も、このような伝統的な家族観が支配的であった。そして、その後の社会情勢を踏まえても、依然として、婚姻制度の理解において自然生殖の可能性が完全に切り離されたとはいえない状況にあって、伝統的な家族観を重視する立場の国民が一定の割合を占めていることからすれば、男女の生活共同体に対して法律婚制度により公証を与え、これを保護するための枠組みを設けることは、それ自体合理性を有するものではある。
【筆者】
「歴史上、家族は、男女の結合関係(婚姻)を中核とし、その間に生まれた子の保護・育成を担うものであると捉えられてきており、本件諸規定の制定当時も、このような伝統的な家族観が支配的であった。」との記載がある。
「婚姻及び家族」とは、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた枠組みであり、その内容が「男女の結合関係(婚姻)を中核とし、その間に生まれた子の保護・育成を担うもの」となっている理由は、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす形で枠組みを定めていることによるものである。
ここではそれを「伝統的な家族観」と呼んでいるが、そのような「伝統的な家族観」と呼んでいる形の背景には「目的」と「その目的を達成するための手段」の関係が存在するのであり、その「目的」と「その目的を達成するための手段」の関係を切り離して、単に「伝統的な家族観」と称する価値観を持つ国民が多いか少ないかというような国民意識の問題として「婚姻」の枠組みを論じることができるかのように考えることは誤りであることに注意が必要である。
「その後の社会情勢を踏まえても、依然として、婚姻制度の理解において自然生殖の可能性が完全に切り離されたとはいえない状況にあって、伝統的な家族観を重視する立場の国民が一定の割合を占めていることからすれば、男女の生活共同体に対して法律婚制度により公証を与え、これを保護するための枠組みを設けることは、それ自体合理性を有するものではある。」との記載がある。
「その後の社会情勢を踏まえても、依然として、婚姻制度の理解において自然生殖の可能性が完全に切り離されたとはいえない状況にあって、」との部分について検討する。
「その後の社会情勢」や「依然として、」との文言があることから、時が進めば「婚姻制度」と「自然生殖の可能性」が「完全に切り離された」状況となることもあり得るように論じるものとなっている。
しかし、物事の起こりを考えれば、「婚姻制度」が先にあって、そこに後から「自然生殖の可能性」が結び付けられているわけではなく、人間の「自然生殖」という営みが先にあって、そこに着目した枠組みとして「婚姻制度」を定めているものである。
そのことから、「婚姻制度」である以上は本来的に「自然生殖の可能性」を切り離して考えることはできないものである。
人間が「自然生殖」を行うことによって子孫を産む生き物であり、その活動によって生じる社会的な不都合を解消しようとする目的が存在している限りは、それを解決するための枠組みを定めることとなる。
そして、その枠組みのことを「婚姻」と呼んでいるのであり、この経緯を切り離した意味で「婚姻」という言葉を用いることはできない。
そのため、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消しようとする目的があり、その目的を達成するための手段として「婚姻」という枠組みが設けられているにもかかわらず、そこで使われている「婚姻」という言葉だけを刈り取って、その言葉が形成されている経緯から切り離して別の意味として用いることが可能となるわけではない。
よって、「完全に切り離された」のように、「婚姻制度」と「自然生殖の可能性」が「完全に切り離された」状況となることもあり得るかのような前提で論じている部分は誤りである。
「伝統的な家族観を重視する立場の国民が一定の割合を占めていることからすれば、」との部分について検討する。
ここで「伝統的な価値観」と称しているものは、一文前の「歴史上、家族は、男女の結合関係(婚姻)を中核とし、その間に生まれた子の保護・育成を担うものであると捉えられてきており、」との部分に対応するものである。
ただ、ここで「婚姻」が「男女の結合関係」となっている理由は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた枠組みが「婚姻」であるということによるものである。
この判決ではこの枠組みを「伝統的な価値観」と称するのであるが、これは「伝統的な価値観」とそれ以外の「価値観」が対立することによって「婚姻」という言葉の概念そのものがいかようにも変化するというものではないのであり、「伝統的価値観」とそれ以外の価値観が対立する関係にあるという認識に基づいて、そこで「伝統的な家族観を重視する立場の国民が一定の割合を占めていること」を理由として「婚姻」の意味が変わらなかったり、あるいは、価値観の変化によれば変わる余地があり得るかのように述べていることは誤りである。
そのため、「国民」の「割合」によって「婚姻」という枠組みの意味や内容が変わるかのような前提で論じている部分は妥当でない。
「男女の生活共同体に対して法律婚制度により公証を与え、これを保護するための枠組みを設けることは、それ自体合理性を有するものではある。」との部分について検討する。
まず、前提として人は様々な人的結合関係を形成、維持、解消しながら生活する自由を有している。
もちろん、この判決が触れるような意味での「恋愛・性愛」という個人の価値観に基づいて人的結合関係を形成したり、複数名で「共同生活」を行うなどしながら生活することも可能である。
そのような中、「生殖と子の養育」に関する事柄について何らの制度も存在しない場合には、社会的な不都合が発生することがある。
それらの問題を解決するために、他の様々な人的結合関係とは「生殖と子の養育」の観点から区別する意味で設けられた枠組みが「婚姻」である。
このような経緯により「男女」を対象とした「法律婚制度」が立法されている。
そして、ここで述べられている「公証を与え、これを保護するための枠組みを設ける」という部分についても、その目的を達成するための手段として整合的な範囲でのみ「婚姻」による「夫婦」や「親子」の身分関係を明らかにする制度を設けることが正当化され、その制度を利用する者に対して一定の優遇措置を設けることが正当化されるというものである。
これについて「それ自体合理性を有するものではある。」との部分は、そのような「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で「婚姻」という枠組みが存在し、それを「法律婚制度」として定めていることの「合理性」を認めるものということになる。
この点について、国(行政府)は、下記のように述べている。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(ア)以上の本件諸規定の立法経緯及びその規定内容からすると、本件諸規定に基づく婚姻は、人が社会生活を送る中で生成され得る種々の、かつ多様な人的結合関係のうち、一人の男性と一人の女性との人的結合関係とその間に産まれる子との人的結合関係を制度化し、夫婦に身分関係の発生に伴うものを含め、種々の権利を付与するとともに、これに応じた義務も負担させることによって、夫婦関係の長期にわたる円滑な運営及び維持を図ろうとするものである。すなわち、本件諸規定の目的は、一人の男性と一人の女性が子を産み育てながら共同生活を送るという関係に対して特に法的保護を与えることにあると解するのが相当である。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【東京一次・第1回】控訴答弁書 令和5年6月23日 PDF
しかしながら、婚姻の本質は、両当事者において永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもって共同生活を営むことにあるのであり、伝統的な家族観が支配的であった旧民法の起草過程という時期においてさえ、婚姻が両心の和合を性質とするものであるとされ、生殖不能が婚姻障害事由に掲げられなかったとおり(認定事実⑵イ )、婚姻の意義は、単に生殖と子の保護・育成のみにあるわけではなく、親密な関係に基づき永続性をもった生活共同体を構成することが、人生に充実をもたらす極めて重要な意義を有するものと理解されていたと解される。このような親密な関係に基づき永続性をもった生活共同体を構成することは、同性カップルにおいても成しうるはずのものである。
【筆者】
「婚姻の本質は、両当事者において永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもって共同生活を営むことにあるのであり、伝統的な家族観が支配的であった旧民法の起草過程という時期においてさえ、婚姻が両心の和合を性質とするものであるとされ、生殖不能が婚姻障害事由に掲げられなかったとおり(…)、婚姻の意義は、単に生殖と子の保護・育成のみにあるわけではなく、親密な関係に基づき永続性をもった生活共同体を構成することが、人生に充実をもたらす極めて重要な意義を有するものと理解されていたと解される。」(カッコ内省略)との記載がある。
最高裁判決が示している「婚姻の本質」と称する説明は、具体的な婚姻制度が存在することを前提として、その制度を利用する者の法律関係の状態を簡潔に示したものであり、また、その最高裁判決でもその具体的な婚姻制度が存在することを前提として、その法的効果を及ぼすことが妥当であるか否かがが問われている中で用いられた説明である。
そのため、具体的な婚姻制度が存在しない中では、この「婚姻の本質」と称する説明の根拠を欠く状態にあることから、「婚姻」の枠組みの範囲を論じるためにこの「婚姻の本質」と称する説明を用いることができることにはならない。
よって、この「婚姻の本質」と称する説明を持ち出して「婚姻」の枠組みを論じようとしている部分が誤りである。
「伝統的な家族観が支配的であった旧民法の起草過程という時期において」「婚姻が両心の和合を性質とするものであるとされ、生殖不能が婚姻障害事由に掲げられなかった」との部分であるが、これも具体的な婚姻制度が存在することを前提として、その制度を利用する意思がある場合に、個々人の個別特性として「生殖不能」な者がいた場合に、それが「婚姻障害自由」として婚姻制度の利用を否定するべきか否かの議論において、それを否定しなかったというものである。
これについても、具体的な婚姻制度が存在することを前提として、個別的な事例に対してその法的効果を及ぼすことができるか否かが論じられているものであり、婚姻制度の枠組みが導かれる際の「① 国の立法目的」について述べるものではないため、これを理由として「婚姻」の枠組みの範囲を変更することができるということにはならないし、別の制度を創設することができるとする理由になるものでもない。
その「両心の和合」の部分について、国(行政府)は下記のように説明している。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ア しかしながら,我が国の婚姻制度が伝統的に生殖と結びついて理解されてきたことは,被告第2準備書面第1の2(1)及び(2)(5ないし8ページ)において引用した文献の記載等からも明らかである。
イ この点,原告らは,「婚姻ハ兩心ノ和合ヲ以テ性質ト為スモノニシテ産子ノ能力ハ一般ニ具備スヘキ條件ナレドモ,必要欠ク可ラサル條件三アラズ」と説明する文献(熊野敏三ほか「民法正義入事編巻之壹(上下)」193ページ・甲A第186号証)を引用し,「我が国の婚姻制度は,必ずしも生殖を目的どしない親密な人格的結合(『両心ノ和合』)に基づく共同生活関係に対して法的保護を与えることを中心的な目的に据えてきたものであり,現在においてもそのような前提に変更はないものと解するのが適切である」と主張する(原告ら第6準備書面 22,40ページ)。
しかし,上記文献は,上記の引用部分の前に「産子ノ能力ヲ有セサル男女ト雖モ婚姻ヲ為スヲ得ヘキカ」という聞いが設けられているとおり(同号証192ページ),生殖能力が婚姻の必要条件か否かについて論じているのであって,我が国の婚姻制度が,伝統的に,必ずしも生殖を目的としない親密な人格的結合に基づく共同生活関係に対して法的保護を与えることを中心的な目的に据えてきた旨を述べるものではない。むしろ,「産子ノ能力ハ一般ニ具備スヘキ侠件」と明記されているととからすれば,上記文献は,婚姻を生殖と結びついた男女間の結合と捉えつつ,このような理解を前提とした上で生殖能力のない者の婚姻の可否を論じているものと解するのが自然であって,同文献は原告らの上記主張を補強するものではない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【札幌・第5回】被告第3準備書面 令和2年5月15日 (P6)
よって、「両心の和合」と書かれた文献は「婚姻を生殖と結びついた男女間の結合と捉えつつ,このような理解を前提とした上で生殖能力のない者の婚姻の可否を論じているもの」であり、「両心の和合」というものを理由として「婚姻」の枠組みを変えることができるとする理由になるものではない。
「婚姻の意義は、単に生殖と子の保護・育成のみにあるわけではなく、」との部分について検討する。
「婚姻の意義」とは、どのような意味で用いられているのかであるが、「意義」は、「意味」や「内容」、「価値」などに言い換えることができることから、これは「『目的』の多義性」を検討する場合に用いた「① 国の立法目的」、「② 制度が機能することによって生じる結果(目的)」、「③ 個々人の利用目的」の側面から検討することができると考えられる。
まず、「① 国の立法目的」であるが、これには「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」の目的が存在することから、「単に生殖と子の保護・育成のみにあるわけではなく、」との理解は、ある意味で正しいともいえる。
次に、これらの目的を達成するための手段として設けられる「婚姻」の枠組みの機能については、「生殖と子の保護・育成」を想定するものとなっていることから、「② 制度が機能することによって生じる結果(目的)」の意味では「単に生殖と子の保護・育成のみにあるわけではなく、」のように、別の機能を組み込むことが可能であるかのように述べることは正しいとはいえない。
三つ目に「③ 個々人の利用目的」であるが、これは個々人が婚姻制度を利用する場合に、どのような意味づけを行うかという問題であるから、「単に生殖と子の保護・育成のみにあるわけではなく、」と考える者もいることは想定されるものである。
このように、「婚姻の意義」と述べたとしても、その内容を詳しく検討した場合には、「① 国の立法目的」、「② 制度が機能することによって生じる結果(目的)」、「③ 個々人の利用目的」の側面から意味が異なるのであり、それを曖昧にしたまま「単に生殖と子の保護・育成のみにあるわけではなく、」のように何かを否定し、その否定したことを理由として別の「意義」を付け加えることができるかのように論じている部分が妥当でない。
「伝統的な家族観が支配的であった旧民法の起草過程という時期においてさえ、婚姻が両心の和合を性質とするものであるとされ、生殖不能が婚姻障害事由に掲げられなかったとおり(…)、婚姻の意義は、単に生殖と子の保護・育成のみにあるわけではなく、」(カッコ内省略)との部分について検討する。
ここでは、「生殖不能が婚姻障害事由に掲げられなかった」ことを理由に、「婚姻の意義」について「単に生殖と子の保護・育成のみにあるわけではな」いとしている。
しかし、この名古屋地裁判決の上記の「⑵ 憲法24条1項に違反するかについて」の項目の「キ」の部分では、「旧民法以来、一貫して生殖不能は婚姻障害事由に掲げられてこなかったが、この点は、」「子孫の生殖を伴う男女の結合関係とそれを中核とする家族関係の安定化を少なくともその目的の一つとしていた」との「評価を妨げるものではない」と述べている。
上記「⑵ 憲法24条1項に違反するかについて」の「キ」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
これらの規定の中には、嫡出推定の規定(民法772条)が存し、同法は、嫡出否認のための手段を限定し(同法775条)、出訴期間を限定するほか(同法777条)、再婚禁止期間を設けるなどして(同法733条)、婚姻関係にある男女間に出生した子と父の関係について早期確定を図る制度を設け、男女間の婚姻関係を中核とする家族生活の安定を図っている。これらの規定の存在を考慮すると、民法は、法律婚制度の構築に当たり、子孫の生殖を伴う男女の結合関係とそれを中核とする家族関係の安定化を少なくともその目的の一つとしていたと評価できる。そして、平成27年の再婚禁止期間大法廷判決による違憲との判断を受けて再婚禁止期間の規定(民法733条、746条)について改正が行われたが、その際にも嫡出推定に関する規定群の存在が前提とされていたものであり、今なおこれらの規定群が価値を失っているわけではない(なお、我が国では、旧民法以来、一貫して生殖不能は婚姻障害事由に掲げられてこなかったが、この点は、上記評価を妨げるものではないというべきである。すなわち、旧民法の起草過程の議論によれば、生殖不能が婚姻障害事由に掲げられなかったのは、生殖能力が婚姻にとって必要不可欠の条件であるとまではいえないと考えられたからにすぎず(認定事実⑵イ )、婚姻の目的に子孫の生殖という側面があること自体が否定されたわけではない。)。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
よって、この「生殖不能が婚姻障害事由に掲げられなかった」ことを理由として「婚姻の意義」について「単に生殖と子の保護・育成のみにあるわけではな」いのようにそれを否定していることは、この判決の内部でも整合性を欠くものとなっており、適当でない。
(個々人の個別特性として『生殖能力が婚姻にとって必要不可欠の条件であるとまではいえない』ことと、『婚姻の目的』〔[② 制度が機能することによって生じる結果(目的)]の意味〕や『婚姻の意義』として『子孫の生殖』や『生殖と子の保護・育成』があるということは区別して考える必要がある。)
もしかすると、ここでは「単に生殖と子の保護・育成のみにあるわけではな」いとの部分は、「③ 個々人の利用目的」について述べようとしているのかもしれないが、それは制度の枠組みを検討する中では論じる必要のないものであるし、「生殖不能が婚姻障害事由に掲げられなかった」こととは関係しないものであり、これを述べることは不自然である。
よって、「単に生殖と子の保護・育成のみにあるわけではな」いとの部分を「③ 個々人の利用目的」と考えるとしても誤りである。
「婚姻の意義は、」「親密な関係に基づき永続性をもった生活共同体を構成することが、人生に充実をもたらす極めて重要な意義を有するものと理解されていたと解される。」との部分について検討する。
まず、「婚姻」は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」という目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす人的結合関係を対象として設けられた枠組みである。
そのため、「親密な関係に基づき永続性をもった生活共同体を構成することが、人生に充実をもたらす極めて重要な意義を有する」ことを理由として設けられているものではない。
国(行政府)は下記のように述べている。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被告第5準備書面第2の2(3)ウ(ア)22ページにおいて述べたとおり、本件諸規定に基づく婚姻は、人が社会生活を送る中で生成され得る種々の、かつ多様な人的結合関係のうち、一人の男性と一人の女性との人的結合関係とその間に産まれる子との人的結合関係を制度化し、夫婦に身分関係の発生に伴うものを含め、種々の権利を付与するとともに、これに応じた義務も負担させることによって、夫婦関係の長期にわたる円滑な運営及び維持を図ろうとするものであり、本件諸規定の目的は、一人の男性と一人の女性が子を産み育てながら共同生活を送るという関係に対して特に法的保護を与えることにあると解するのが相当であって、個人の親密な関係を保護することが自己実現などの権利保護のために必要不可欠であるとして婚姻制度が創設されたものではない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【大阪・第12回】被告第6準備書面 令和4年2月21日 PDF (P25)
また、この文は下記の二つを挙げ、これを理由として「婚姻の意義は、」「親密な関係に基づき永続性をもった生活共同体を構成することが、人生に充実をもたらす極めて重要な意義を有するものと理解されていたと解される。」と考えるものとなっている。
◇ 婚姻の本質は、両当事者において永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもって共同生活を営むことにある
◇ 伝統的な家族観が支配的であった旧民法の起草過程という時期においてさえ、婚姻が両心の和合を性質とするものであるとされ、生殖不能が婚姻障害事由に掲げられなかった
しかし、上記で述べたように、その二つとも「婚姻」についての「① 国の立法目的」を示したものではないため、これを理由として「婚姻」の枠組みが変わることにはならないし、新たな制度を立法しなければならないことにもならない。
「このような親密な関係に基づき永続性をもった生活共同体を構成することは、同性カップルにおいても成しうるはずのものである。」との記載がある。
そもそも「婚姻」は単に「親密な関係に基づき永続性をもった生活共同体を構成すること」を理由として制度を設けているものではなく、それらの様々な人的結合関係とは「生殖と子の養育」の観点から区別する意味で設けられた制度である。
そのため、「親密な関係に基づき永続性をもった生活共同体を構成すること」ができることを理由として制度を立法しなければならないことにはならない。
ここでは「同性カップル」のように「同性間の人的結合関係」のみを取り上げて論じようとしているが、婚姻制度の対象となっていない人的結合関係の中には「近親者の人的結合関係」、「三人以上の人的結合関係」、「婚姻適齢に満たない者との人的結合関係」も存在しており、それらの人的結合関係が「親密な関係に基づき永続性をもった生活共同体を構成すること」ができるとしても、それを理由として婚姻制度の対象とはならないことは明らかである。
よって、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するための手段として設けられている「婚姻」という枠組みを利用している者の生活風景との類似性を述べることによって、その枠組みそのものを変更することができるとする理由にはならない。
そして、近年家族の多様化が指摘されており、平成30年時点で、全世帯総数のうち独身世帯が占める割合は、昭和61年の18.2%から27.7%にまで上昇し、夫婦のみ世帯が占める割合も、同年の14.4%から24.1%にまで上昇する一方、夫婦と未婚の子のみの世帯は、同年の41.4%から29.1%にまで減少するなど(認定事実⑺イ )、男女の結合関係を中核としてその間に生まれた子の保護・育成の機能を担うという伝統的な家族観が、唯一絶対のものであるというわけではなくなっていることが認められる。
【筆者】
「近年家族の多様化が指摘されており、」との部分であるが、「家族」が「多様化」しているとの認識は誤りである。
まず、法学的な意味の「家族」とは、憲法24条2項に定められた「婚姻及び家族」のいう「家族」であり、また、この憲法24条2項の要請に従う形で立法されている民法上の「家族」の制度(親族)のことである。
これは一つの制度であることから、これが「多様化」しているという事実はない。
この文の後に具体的な数字を示しながら説明している「割合」の話についても、そこで「全世帯総数のうち」と述べているように「世帯」の話をするものであり、これは法学的な意味の「家族」について述べるものではない。
よって、法学的な意味の「家族」が「多様化」しているという事実はないし、「世帯」の「多様化」について述べているのであれば「家族の多様化」と表現していることは誤りということになる。
その他、「世帯」が「多様化」したとしても、憲法24条2項の「婚姻及び家族」の枠組みやその機能が変わるということにはならない。
「男女の結合関係を中核としてその間に生まれた子の保護・育成の機能を担うという伝統的な家族観が、唯一絶対のものであるというわけではなくなっていることが認められる。」との部分について検討する。
まず、ここでは「伝統的な家族観が、唯一絶対のものであるというわけではなくなっている」との表現からは、「伝統的家族観」と、そうでない家族観というものがあり、その「家族観」の割合が変化することによって、「婚姻」あるいは「家族」の意味が変化するという考え方を前提とするものとなっている。
しかし、そもそも「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた枠組みが「婚姻」と「家族」の概念であり、その立法目的とその立法目的を達成するための手段の関係によって「男女の結合関係を中核としてその間に生まれた子の保護・育成の機能を担う」という枠組みが定められているのである。
これを「伝統的な家族観」と呼ぶかは別として、そもそも「婚姻」と「家族」の概念には立法目的とその立法目的を達成するための手段となる枠組みが存在するのであり、それを離れて「婚姻」と「家族」の概念を用いることはできないのであり、ここで「婚姻」と「家族」の概念をそのものを単なる音の響きに過ぎないものにまで言葉の意味を解体し、そこに「伝統的な価値観」を持つ国民とそうでない価値観を持つ国民の割合が変化することによって言葉の意味を自由に変化させることができるかのように述べていることは誤りである。
そのため、「伝統的な家族観」と呼ぶかどうかは別として、「婚姻」と「家族」の概念について、「男女の結合関係を中核としてその間に生まれた子の保護・育成の機能を担う」という枠組みについて、「唯一絶対のものであるというわけではなくなっている」のように述べて、それ以外の意味を付与することが可能であるかのような前提で論じていること自体が誤りである。
また、同性愛を精神的病理であるとする見解は、20世紀後半頃には否定されるに至り、性的指向それ自体は障害ではないとの知見が確立したことが認められる(認定事実⑴イ )。
【筆者】
「婚姻及び家族」の制度は「性愛」の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合それがどのような対象に向かうかを審査するものではないし、「性愛」に基づいて制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもない。
そのため、婚姻制度は「性愛」に関知していないのであり、ここで「同性愛」のように「性愛」と関係するかのように論じている点が妥当でない。
また、法制度は個々人の内心に対して中立的でなければならず、もし「性愛」の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的とした制度を立法した場合には、20条1項後段、3項、89条の「政教分離原則」に抵触して違憲となる。
他にも、「性愛」の思想、信条、信仰、感情を有するか否かを審査したり、「性愛」に基づいて制度を利用することを求めるものとなっていた場合には、19条の「思想良心の自由」や20条1項前段の「信教の自由」に抵触して違憲となる。
さらに、「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いをする場合には、14条の「平等原則」に抵触して違憲となる。
よって、そもそも法制度を「性愛」と関係するものとして立法してはならない。
そのことから、ここで「同性愛」に対する見解が変化したことを述べるのであるが、そもそも「同性愛」という特定の思想、信条、信仰、感情に基づく形で法制度を立法した場合には、そのこと自体が憲法違反の原因となるのであり、そのような「同性愛」という思想、信条、信仰、感情と関係する形で法制度を立法することが許されることを前提として論じていること自体が誤りである。
その他、「精神的病理」を取り上げて「性的指向それ自体は障害ではない」と述べている部分であるが、婚姻制度(男女二人一組)は「精神的病理」を有するとされる者であるとしても利用することができるのであり、何かが「精神的病理」であるか否か、「障害」であるか否かは関係がない。
よって、そもそも「同性愛」が「精神的病理」や「障害」であるとしても、それを理由として婚姻制度(男女二人一組)の利用が否定されているわけではないし、「同性愛」が「精神的病理」や「障害」でないとしても、婚姻制度(男女二人一組)を利用できることは変わらない。
そのため、ここで「同性愛」が「精神的病理」や「障害」であるか否かを論じていることは、そもそも「精神病理」や「障害」を持つ者に対して婚姻制度(男女二人一組)の利用を否定されているかのような前提を含む形で論じていることになるのであり、前提となる認識がそもそも不当である。
さらに、前記認定事実⑶によれば、各種国際機関は、20世紀後半以降、性的少数者の権利保護に向けた活動を行ってきたところ、こうした活動の中には、同性カップルに対して異性カップルに認められていた遺族年金の受給権を認めるもの(認定事実⑶ア 及び同 )のほか、同性カップル及びその子供を法的に認知し、異性カップルに与えられてきた法的利益が差別なく付与されることを推奨するもの(認定事実⑶イ )、性的指向及び性自認にかかわらず、家族を形成する権利を有することを宣明するもの(認定事実⑶ウ)など、同性カップルの生活共同体を保護するものが含まれている。
【筆者】
「各種国際機関は、20世紀後半以降、性的少数者の権利保護に向けた活動を行ってきたところ、こうした活動の中には、」との部分について検討する。
まず、この「⑶ 憲法24条2項に違反するかについて」で問われているのは憲法24条2項の「婚姻及び家族」の枠組みである。
そして、日本法における「婚姻及び家族」の枠組みは、「性愛」を保護することを目的とする制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いをするものではないし、「性愛」に基づいて「婚姻」することを求めるものでも勧めるものでもなく、個々人の内心には関知していない。
よって、ここで「性的少数者」を取り上げているのであるが、そもそも「婚姻及び家族」の枠組みを論じるにあたって関係しない事柄を持ち出すものであり、妥当でない。
「同性カップルに対して異性カップルに認められていた遺族年金の受給権を認めるもの」との部分について検討する。
ここでは「異性カップルに認められていた遺族年金の受給権」について「同性カップルに対して」も「認める」かどうかという論じ方をするものとなっており、「カップル」という「二人一組」が基準であるかのように論じるものとなっている。
しかし、「遺族年金」は単に「遺族年金」の制度の目的とその目的を達成するための手段として合理的な範囲の者を対象としているだけであり、例えば、死亡者の家族・親族にあたる配偶者・子・父・母・孫・祖父・祖父母・兄弟姉妹などを対象とするものである。
そのため、ここでいう「異性カップル」のように「異性間の人的結合関係」を形成していることのみを理由として、それだけで「遺族年金」の対象が定められているというものではない。
それにもかかわらず、このような範囲の中から、勝手に「二人一組」を絶対的な基準であるかのように打ち立てた上で、「異性があれば同性もあるだろう」などという安易な発想を基に「異性カップル」と「同性カップル」のように比較することができるかのように論じている部分は、誤りである。
このような論じ方は、なぜ「二人一組」であるのかその根拠を説明しないままに論じる「カップル信仰論」に陥っているということができる。
「同性カップル及びその子供を法的に認知し、異性カップルに与えられてきた法的利益が差別なく付与されることを推奨するもの」との部分について検討する。
ここでも「同性カップル」と「異性カップル」という「二人一組」を取り上げ、「差別なく」のように「二人一組」を前提として比較することができるかのように論じるものとなっている。
しかし、法律論としては、「権利能力」を有して法主体としての地位を認められている個々の自然人が「法的利益」を得ることができるか否かを比較することは可能であるが、「権利能力」を有しておらず法主体としての地位を認められていない「二人一組」を基にして比較することはできない。
そのため、「二人一組」を前提にして比較して論じようとすることは妥当でない。
また、ここでは「カップル」のように「二人一組」のみを取り上げているが、人的結合関係の中には「三人一組」や「四人一組」の場合も存在するのであり、それを検討することなく「二人一組」のみを取り上げればそれで済むかのように考えている部分は、なぜ「二人一組」なのかその根拠を説明しないままに論じる「カップル信仰論」に陥っており、この点でも妥当でない。
「性的指向及び性自認にかかわらず、家族を形成する権利を有することを宣明するもの」との部分について検討する。
「家族を形成する権利」とあるが、「家族」の意味の多義性について、当サイト「同性婚訴訟 東京地裁判決の分析」のポイントの部分で解説している。
「同性カップルの生活共同体を保護するものが含まれている。」との部分について検討する。
「生活共同体」については、憲法21条1項の「結社の自由」によって保障されるものである。
これについては、「カップル」という「二人一組」に限られず、「トリオ」である「三人一組」、「四人一組」、それ以上の人的結合関係についても同様に保障されている。
加えて、諸外国においては、1989(平成元)年にデンマークが登録パートナーシップ制度を導入して以降、世界各国において、同性カップルを公証するための制度(登録パートナーシップ制度等)が導入されるようになったほか(認定事実⑷ア及び同イ)、2000(平成12)年には、オランダが世界で初めて同性婚制度を導入し、現在までに、証拠上確認できるだけでも、28か国が同性婚制度を導入していることが認められる(認定事実⑷ウ)。
【筆者】
「1989(平成元)年にデンマークが登録パートナーシップ制度を導入して以降、世界各国において、同性カップルを公証するための制度(登録パートナーシップ制度等)が導入されるようになった」との部分について検討する。
日本国の場合、憲法24条に「婚姻」が定められており、これは「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度となっている。
そして、この24条は法律で定められる「婚姻」の内容について、立法裁量の限界を画するものとなっている。
このことから、もし「生殖と子の養育」に関わる制度を24条の規定が及ばない形で定めることが可能となると、24条の規定が法律で定められる「婚姻」に対して立法裁量の限界を画する意義が失われることになる。
よって、24条の「婚姻」の文言は、「生殖と子の養育」に関わる制度を一元的に集約して規律するものであり、この24条の「婚姻」を離れて「生殖と子の養育」に関わる制度を立法することはできない。
そのことから、ここで挙げられているように「デンマークが登録パートナーシップ制度を導入」したり、「世界各国において、同性カップルを公証するための制度(登録パートナーシップ制度等)」を「導入」しているとしても、日本国の場合では、それが「生殖と子の養育」に関わる制度となっている場合や、影響を与える制度となっている場合には、「婚姻」の立法目的の実現を阻害するものとして24条の「婚姻」に抵触して違憲となる。
また、「婚姻」が「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成するための手段として設けられている枠組みであるのに対して、そのような目的を有しない人的結合関係に対して何らかの法的効果や優遇措置を設けることは、何らの人的結合関係を形成していない者との間で合理的な理由を説明することができない差異を生じさせることになるから、14条の「平等原則」に抵触して違憲となる。
そのため、これらの点を検討せずに「諸外国」の事例を持ち出したとしても、そのことは日本国において類似の制度を創設することができるとする理由にはならない。
「2000(平成12)年には、オランダが世界で初めて同性婚制度を導入し、現在までに、証拠上確認できるだけでも、28か国が同性婚制度を導入していることが認められる」との部分について検討する。
まず、外国の法制度は、その国の社会事情の中で生じている不都合を解消することを目的として、その目的を達成するための手段として設けられたものであることから、その外国の法制度と自国の法制度に対して何らかの類似点を見出すことができる場合があるとしても、それはそれぞれの国の社会事情の中で形成された別個の制度である。
そのため、外国の法制度と日本国の法制度の間で何らかの類似点を見出すことができる場合があるとしても、それはそれぞれの国の社会事情の中で形成された別個の制度であり、同一の制度を指していることにはならない。
そのことから、外国語を翻訳する者がある制度に対して「婚姻」という言葉を当てて説明しているからといって、日本国の法制度における「婚姻」と同一のものを指していることにはならない。
よって、ここでは外国の法制度について「同性婚制度」のように「婚」の文字を使っていることから、「婚姻」という言葉を充てて説明していることになるが、それらの外国の制度と日本国の「婚姻」とは同一のものであるとはいえない。
そのため、日本国の法制度の内容に対して影響を与えることはないし、それらの外国の法制度に対して「婚姻」という言葉を充てて説明しているとしても、そのことは日本国の法制度における「婚姻」の中に「同性間の人的結合関係」を含めることができるとする根拠となるものではない。
その他、ここでは「同性婚制度」のように「同性間の人的結合関係」についての制度を導入している国の例のみを取り上げるのであるが、外国の中には古くから「男性一人と女性四人まで」の「一夫多妻制」を採用している国々も存在しているのであり、それらの事例を一切取り上げることなく、「同性間の人的結合関係」についての制度を導入している国の例のみを取り上げて論じようとしていることは、特定の結論を導き出すために意図的に「二人一組」であるという前提を先取りする形で論じようとしている可能性があり、適切ではない。
【参考】一夫多妻制 Wikipedia
このような形で特定の事例のみを取り上げて、それを結論を導き出すための根拠としようとすることは、特定の結論を導きたいがために恣意的に視野を狭めようとしていることが考えられる。
このような網羅性のない形で論じることは、統一的な理念に従って全体の整合性が保たれた制度を維持する視点を欠くものであることから、妥当でない。
我が国でも、平成12年頃以降、同性愛者等をめぐる人権問題の解決の必要性が指摘され(認定事実⑸ウ )、平成27年4月、地方自治体において初めて登録パートナーシップ制度が導入され、令和4年1月時点までに147の地方自治体がこれを導入しているほか、令和2年4月以降、同性パートナーがいる区職員に対しても結婚休暇等を認める取組みを行う地方自治体も現れ始めている(認定事実⑸ウ )。
【筆者】
「我が国でも、平成12年頃以降、同性愛者等をめぐる人権問題の解決の必要性が指摘され」との記載がある。
まず、「我が国」の「婚姻及び家族」の制度は、「性愛」の思想、信条、信仰、感情を保護するための制度ではないことから、一段落前からの続きの話題として「同性愛者等」のように「性愛」と関係するかのように取り上げていること自体が妥当でない。
また、一段落前で登場する外国が「性愛」と関係させる法制度を立法している場合があるとしても、日本国の「婚姻及び家族」の制度は「性愛」とは関わらない制度であることから、それらの制度とはまったく性質が異なっている。
よって、「我が国」の「婚姻及び家族」の制度を論じる場面で、「同性愛者等」のように、「性愛」の思想、信条、信仰、感情や、それを有すると称する者を取り上げていること自体が論じ方として誤っている。
「平成27年4月、地方自治体において初めて登録パートナーシップ制度が導入され、令和4年1月時点までに147の地方自治体がこれを導入しているほか、令和2年4月以降、同性パートナーがいる区職員に対しても結婚休暇等を認める取組みを行う地方自治体も現れ始めている」との記載がある。
地方自治体の「登録パートナーシップ制度」は、法律上の婚姻制度や憲法上の規定に抵触している場合には、違法となる。
数多くの地方自治体が導入しているとしても、違憲・違法となる場合にはそれを正当化することはできない。
また、地方自治体が「登録パートナーシップ制度」を設けているとしても、それよりも上位の法令である法律や憲法に対して影響を与えることはない。
詳しくは当サイト「パートナーシップ制度」で解説している。
そして、国においても、2008(平成20)年以降、国連の条約機関等からの勧告を受け(認定事実⑶ア 及び同イ )、平成14年以降、性的少数者に対する偏見等の解消に向けた啓発活動が行われたほか(認定事実⑸ア )、性同一性障害者の戸籍上の性別変更を認める法律の制定(認定事実⑸ア )が行われた。さらに、平成29年には、一部諸外国から、同性婚の公式な承認を国レベルに拡大するなどの施策等の勧告がなされ(認定事実⑶イ )、それ以降、地方自治体や各種団体から、同性間の婚姻を求める声明が発表されるに至っている(認定事実⑸ウ 及び同エ ないし )。
【筆者】
「国連の条約機関等からの勧告を受け」との部分であるが、条約は憲法に優越しないため、締結した条約や、条約によって設立された機関による何らかの意見があるとしてもそれによって憲法上の規範の意味が変わることはない。
よって、このような事柄は憲法上の規範の意味を解釈する中において影響を受けるものではないため、これによって24条2項の「婚姻及び家族」の枠組みの解釈が変わるということはない。
「性的少数者に対する偏見等の解消に向けた啓発活動が行われたほか」との部分であるが、それらの啓発活動が科学的な内容となっているかについて、当サイト「性別と思想」で検討している。
それとは別に、憲法24条2項の「婚姻及び家族」の枠組みは「性愛」に関わらない制度であるため、ここで「性的少数者」と関係するものとして取り上げていることそのものが妥当でない。
「性同一性障害者の戸籍上の性別変更を認める法律の制定(… )が行われた。」(カッコ内省略)との部分であるが、これと関連する内容について、当サイト「性別と思想」で解説している。
「一部諸外国から、同性婚の公式な承認を国レベルに拡大するなどの施策等の勧告がなされ」との部分であるが、「諸外国」から「勧告」がなされたことを理由として憲法24条2項の規範の意味が変わるというものではない。
「同性婚」との文言があるが、「婚姻」は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度であり、「同性間の人的結合関係」についてはその間で「生殖」を想定することができないため、「生殖と子の養育」の趣旨を満たすとはいえず、「婚姻」とすることはできない。
「地方自治体や各種団体から、同性間の婚姻を求める声明が発表されるに至っている」との部分について検討する。
「地方自治体」が「声明」を発表したとしても、そのことによって憲法24条2項の規範の意味が変わることにはならない。
「各種団体」についても、日本国内の様々な団体は自由に意見を表明する自由を有しており、実際に様々な意見を表明しながら活動を行っている。
その「各種団体」が「声明」を発表したとしても、そのことによって憲法24条2項の規範の意味が変わることにはならない。
よって、憲法24条2項の規範の意味を明らかにする解釈の過程において、このような「声明」を持ち出して論じようとすること自体が妥当でない。
その他、「同性間の婚姻」との文言があるが、「婚姻」は「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度であり、「同性間」ではその間で「生殖」を想定することができず、「生殖と子の養育」の趣旨を満たすものではないため、「婚姻」とすることはできない。
たとえ、「地方自治体」や「各種団体」が「同性間」の人的結合関係を「婚姻」とすることができることを前提に何らかの「声明」を発表しているとしても、そのことによって「同性間」の人的結合関係を「婚姻」として扱うことができることになるというわけではない。
以上のとおり、世界的に同性カップルの法的保護に向けた活動が活発化し、我が国でも、多数の地方自治体が登録パートナーシップ制度を導入するに至り、国レベルでの法制化の声が上がっていることに加え、民間企業においても、同性パートナーに家族手当等を適用するといった取組みを行う企業も現れ始め(認定事実⑸エ )、平成30年以降には、同性婚を法的に認めることに関する国民の意識調査において、賛成派が反対派を上回る結果が報告されるようになり、その中には賛成派が約6割半に及ぶとする結果や、20ないし50代の比較的若い層を対象としたものでは、賛成派が、男性の約7割、女性の9割弱を占める結果も存在している(認定事実⑹ア )。
【筆者】
「世界的に同性カップルの法的保護に向けた活動が活発化し、」との部分について検討する。
まず、世界の中には「男性一人と女性四人まで」の一夫多妻制を採用している国々も存在しており、それらを取り上げることなく、ここでいう「同性カップル」という「同性間の人的結合関係」のみを取り上げて何かを論じようとすること自体が妥当ではない。
このような説明は、なぜ「二人一組」なのかその根拠を説明しないままに論じる「カップル信仰論」に陥っている。
また、外国で「同性間の人的結合関係」についての法制度が存在するとしても、そのことは日本国の法制度における「婚姻」の中に「同性間の人的結合関係」を含めることができるとする理由にはならないし、「親子」や「親子」の関係を基本とした「兄弟」「姉妹」などに含まれない「同性間の人的結合関係」を「家族」とすることができるとする理由にはならない。
他にも、日本国で「同性間の人的結合関係」についての法制度を立法しようとした場合には、それが「生殖と子の養育」に関わる制度となっている場合や、影響を与える制度となっている場合には、24条の「婚姻」の文言が「生殖と子の養育」に関わる制度を一元的に集約して規律している趣旨に抵触して違憲となる。
さらに、「生殖と子の養育」の趣旨に関わらないとしても、そもそも「生殖と子の養育」の趣旨を有していない人的結合関係に対して何らかの法制度を設けることは、何らの制度も利用していない者との間で合理的な理由を説明することのできない差異を生じさせるものとなるから、それは14条1項の「平等原則」に抵触して違憲となる。
よって、「世界的に同性カップルの法的保護に向けた活動が活発化し、」ているとしても、そのことは日本国の法制度の解釈に対して影響を与えることはない。
「我が国でも、多数の地方自治体が登録パートナーシップ制度を導入するに至り、」との部分について検討する。
しかし、地方自治体の「登録パートナーシップ制度」が憲法上の規定に抵触している場合は違憲、法律上の婚姻制度に抵触している場合は違法となる。
そのため、そもそも憲法24条1項の「婚姻」や2項の「婚姻及び家族」、14条1項の「平等原則」、19条の「思想良心の自由」、20条1項前段の「信教の自由」、20条1項後段・3項、89条の「政教分離原則」に抵触して違憲、また、法律上の婚姻制度に抵触して違法となる問題を抱えている制度を持ち出して、それを根拠として24条2項の規範の意味を論じようとすることは正当化することができない。
また、そもそも下位法にあたる制度を持ち出して、その上位法である憲法上の規定の意味を明らかにしようとする試みていることについても、法秩序の階層構造を理解しないものであり、誤りである。
「登録パートナーシップ制度」について、詳しくは当サイト「パートナーシップ制度」で解説している。
「国レベルでの法制化の声が上がっていることに加え、」との部分について検討する。
「法制化の声が上がっていること」を理由として憲法上の規範の解釈が変わることになるのであれば、それは裁判所が法の論理に基づき理を突き詰めた結果として規範の意味を明らかにしているものとはいえないことになる。
つまり、単に外部からの圧力に屈する形で規範の意味を変更しようとしているか、裁判官が特定の結論を導き出したいと望む中において自己の恣意性を覆い隠す意図でこのような声を用いているかのどちらかということになる。
そのため、「法制化の声が上がっていること」などを取り上げることは、解釈の過程が不当な内容であることを自ら明らかにするものにしかならない。
「民間企業においても、同性パートナーに家族手当等を適用するといった取組みを行う企業も現れ始め」との部分について検討する。
民間企業の契約の内容については、憲法上の「公共の福祉」や民法上の「公序良俗」や「強行規定」に違反しないかを個別に検討しなければ、そのような扱いが適法となるかは判断することができない。
「愛人契約」が違法であることはよく知られていることであり、民間企業が「愛人契約」を制度化している場合には、その契約は違法となる。
そのため、これらの契約の内容を個別に検討することもなく、適法な制度であることを前提として取り上げていることは妥当とはいえない。
また、民間企業の契約の内容が、国の法制度の内容についての合憲・違憲の判断において影響を与えることはないのであり、このような事例を持ち出して論じることそのものについても妥当でない。
「平成30年以降には、同性婚を法的に認めることに関する国民の意識調査において、賛成派が反対派を上回る結果が報告されるようになり、その中には賛成派が約6割半に及ぶとする結果や、20ないし50代の比較的若い層を対象としたものでは、賛成派が、男性の約7割、女性の9割弱を占める結果も存在している」との部分について検討する。
まず、この「⑶ 憲法24条2項に違反するかについて」の項目の「イ」の第五段落の記述を受けて「ウ」以下で問われているのは、24条2項の「家族」が、「親子」や「親子」を基本とした「兄弟」「姉妹」などに含まれない「同性間の人的結合関係」に対して制度の創設を「要請」しているか否かである。
そして、「要請」しているのであればその制度がないことは違憲であり、「要請」していないのであればその制度がないことは合憲である。
この24条2項がそのような制度を立法することを「要請」しているか否かは、24条2項の条文そのものを読み解くことによってその規範の意味を明らかにすることが必要であり、その規範の意味そのものを「国民の意識調査」における「賛成派」や「反対派」の数に委ねることによって決することができるというものではない。
よって、24条2項がそのような制度を「要請」しているか否かの解釈の過程において、「国民の意識調査」における「賛成派」や「反対派」の割合を示すことは、解釈の方法として誤っている。
このような「国民の意識調査」における「賛成派」や「反対派」の数によって、憲法上の規範の意味が変わることになれば、「法の支配」、「法治主義」を損なわせることになるため、妥当でない。
また、その時々の国民意識によって条文に記された規範の意味が変わってしまうことになれば、そこにはそもそも「法」は存在しないも同然である。
よって、ここで「国民の意識調査」を持ち出して憲法24条2項の規範の意味を明らかにしようと試みていることは、解釈の方法として正当化することはできず、誤りである。
こうしてみると、家族の形態として、男女の結合関係を中核とした伝統的な家族観は唯一絶対のものであるというわけではなくなり、同性愛を精神的病理であるとする知見が否定されるに至った状況で、世界規模で同性カップルを保護するための具体的な制度化が実現してきており、わが国でも同性カップルに対する理解が進み、これを承認しようとする傾向が加速しているということができる。そうすると、現行の家族に関する法制度における現行の法律婚制度はそれ単体としては合理性があるように見えたとしても、そこで重視されるべき価値に対する理解の変化に伴い、その享有主体の範囲が狭きに失する疑いが生じてきており、結果として、同性愛者を法律婚制度の利用から排除することで、大きな格差を生じさせていながら、その格差に対して何ら手当てがなされていないことについて合理性が揺らいできているといわざるを得ず、もはや無視できない状況に至っていると考えられる。
【筆者】
「こうしてみると、家族の形態として、男女の結合関係を中核とした伝統的な家族観は唯一絶対のものであるというわけではなくなり、同性愛を精神的病理であるとする知見が否定されるに至った状況で、世界規模で同性カップルを保護するための具体的な制度化が実現してきており、わが国でも同性カップルに対する理解が進み、これを承認しようとする傾向が加速しているということができる。」との記載がある。
「こうしてみると、」の部分は、前の段落で述べている下記の内容をいうものである。
◇ 世界的に同性カップルの法的保護に向けた活動が活発化
◇ 我が国でも、多数の地方自治体が登録パートナーシップ制度を導入するに至り
◇ 国レベルでの法制化の声が上がっていること
◇ 民間企業においても、同性パートナーに家族手当等を適用するといった取組みを行う企業も現れ始め
◇ 平成30年以降には、同性婚を法的に認めることに関する国民の意識調査において、賛成派が反対派を上回る結果が報告される
しかし、これによって「家族の形態として、男女の結合関係を中核とした伝統的な家族観は唯一絶対のものであるというわけではなくなり、」との認識が導かれることにはならない。
まず、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の古兵」「母体の保護」という目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす「男性」と「女性」の組み合わせが選び出され、それに対して「貞操義務」などの一定の形式で結び付ける形で「婚姻」という枠組みが設けられている。
そして、この「婚姻」という政策に付随する形で、その「婚姻」と同一の目的を共有し、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす形で「家族」という枠組みが設けられている。
ここで「男女の結合関係を中核とした」と述べているものは、その「婚姻」と「家族」の枠組みについて述べるものとなっている。
ただ、ここではそれを「伝統的な家族観」と呼び、それが「唯一絶対のものであるというわけではなくなり、」としていることから、「伝統的な家族観」とそれ以外の家族観というものが別に存在することを前提とするものとなっている。
しかし、そのような理解は、「婚姻」と「家族」の概念そのものに含まれている立法目的とその立法目的を達成するための手段となる枠組みの関係から切り離し、「婚姻」と「家族」の概念を言葉の意味から切り離された音の響きに過ぎないものにまで解体した上で、その空箱となった音の響きに過ぎないものに対して、「伝統的な家族観」かそれ以外の家族観かのどちらかを当てはめることによって、「婚姻」と「家族」の意味が変化するものであるかのように説明するものとなっており、誤りである。
「家族」という概念が「男女の結合関係を中核」としているのは、「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた枠組みとして「男女の結合関係を中核」として「婚姻」と「家族」の枠組みが形成されているからであり、「婚姻」と「家族」という空箱が初めに存在していて、その後からその中に「男女の結合関係」を詰め込んでいるというものではない。
よって、「男女の結合関係を中核」としている枠組みについて、それを「伝統的な家族観」と呼ぶかは別としても、「伝統的な家族観」とそれ以外の家族観が対立し、その対立の結果によって「婚姻」と「家族」の言葉の意味が「男女の結合関係を中核とした」ものから別のものへと変わる余地があるかのような意味で「唯一絶対のものであるというわけではなくなり、」と述べていることは誤りである。
「同性愛を精神的病理であるとする知見が否定されるに至った状況で、」との部分について検討する。
「精神的病理」であればそれに対して行政が何らかのサポートを行う場合があるが、「同性愛」が「精神的病理」ではないということは、「同性愛」であることを理由として特別の保護や制度を設けることは、それを正当化することのできる理由がないことを意味する。
そのため、「同性愛」に対する特別の保護や制度を設けることは、憲法14条の「平等原則」に抵触して違憲となる。
「精神的病理」であれば特別の保護が与えられることを正当化することはできるとしても、「精神的病理」でないのであれば特別の保護を与えることは特権の付与となり、憲法14条の「平等原則」に抵触して違憲となるからである。
よって、地方自治体の行っている「同性愛」を理由とする「登録パートナーシップ制度」などの施策は、「同性愛を精神的病理であるとする知見が否定され」ていることによって初めから憲法14条の「平等原則」に抵触して違憲である。
詳しくは、当サイト「パートナーシップ制度」でも解説している。
その他、婚姻制度については「精神的病理」の者でも利用することができることから、「精神的病理」であることを理由として婚姻制度を利用することが否定されているという事実はない。
よって、あたかも「精神的病理」である者が婚姻制度を利用することができないかのような前提で論じている部分が妥当でない。
もう一つ、婚姻制度は「性愛」を保護することを目的とした制度ではないことも押さえる必要がある。
「世界規模で同性カップルを保護するための具体的な制度化が実現してきており、」との部分について検討する。
それぞれの国の制度は、それぞれの国の社会事情の中で課題となる問題を解決することを意図して構築されたものであり、その立法目的やその立法目的を達成するための手段・方法には様々な違いがある。
そのため、それら様々な国の法制度の間で何らかの類似点を見出すことができる場合があるとしても、それらは本来的にそれぞれ別個の制度であり、同一の制度を指していることにはならない。
そのため、外国で「同性間の人的結合関係」を対象とした法制度が存在するとしても、そのことは日本国の法制度の「婚姻」と同一の制度を指していることにはならない。
また、それは日本国の法制度における「婚姻」の中に「同性間の人的結合関係」を含めることができるとする理由になるものではないし、日本国の法制度における「家族」の中に「親子」や「親子」の関係を基本とした「兄弟」「姉妹」などに当てはまらない「同性間の人的結合関係」を含めることができるとする理由になるものでもない。
「同性愛を精神的病理であるとする知見が否定されるに至った状況で、世界規模で同性カップルを保護するための具体的な制度化が実現してきており、」との文脈を検討する。
この文によれば、「世界」の国々は「精神的病理」であることは法制度の利用を否定する理由となると考えていることになる。
しかし、日本法の下では「精神的病理」であるとしても制度の要件に従っているのであれば制度を利用することは可能であるため、「精神的病理」であることを理由に扱いを変えてはいない。
また、この文によれば「世界」の国々は「同性愛」という特定の思想、信条、信仰、感情に基づいて制度を構築していることになる。
しかし、日本法の下では、「同性愛」という特定の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的として制度を立法することは、20条1項後段・3項、89条の「政教分離原則」に抵触して違憲となる。
そのため、このような「世界」の国々と日本法ではもともと性質が異なっており、これを同じものであるかのような前提で論じようとしている部分が妥当でない。
「わが国でも同性カップルに対する理解が進み、これを承認しようとする傾向が加速しているということができる。」との部分について検討する。
ここでいう「同性カップル」という「同性間の人的結合関係」を形成することについては、憲法21条1項の「結社の自由」によって保障されている。
よって、これに対して「わが國」で「理解」がないことを前提に、「理解が進み」のように述べていることは妥当でない。
「これを承認しようとする傾向が加速している」との部分についても、そもそも「同性間の人的結合関係」を形成することは憲法21条1項の「結社の自由」で保障されており、「承認」されている。
よって、これが「承認」されていないことを前提に「これを承認しようとする傾向が加速している」と評価することは、前提を見誤っており妥当でない。
加えて、人的結合関係を形成していない者についても、そのまま「承認」されていることを理解することも重要である。
「現行の家族に関する法制度における現行の法律婚制度はそれ単体としては合理性があるように見えたとしても、そこで重視されるべき価値に対する理解の変化に伴い、その享有主体の範囲が狭きに失する疑いが生じてきており、結果として、同性愛者を法律婚制度の利用から排除することで、大きな格差を生じさせていながら、その格差に対して何ら手当てがなされていないことについて合理性が揺らいできているといわざるを得ず、もはや無視できない状況に至っていると考えられる。」との記載がある。
「現行の家族に関する法制度における現行の法律婚制度はそれ単体としては合理性があるように見えたとしても、」との部分について検討する。
まず、この「⑶ 憲法24条2項に違反するかについて」の項目の「イ」の内容により、「ウ」以下で問われているのは、24条2項の「家族」がここでいう「同性間の人的結合関係」に対して制度の創設を「要請」しているか否かである。
これは、憲法24条2項の意味そのものが問われており、憲法上の規定の意味を明らかにすることが必要となるものである。
しかし、ここで論じているのは「現行の家族に関する法制度における現行の法律婚制度」であり、これは憲法24条2項よりも下位の法形式である「法律」で定められている内容である。
そのため、この下位法である「法律」の内容の「合理性」が如何なるものであるとしても、そのことが上位法である憲法24条2項の条文の意味を読み解く際の基準となることはない。
よって、下位法である「法律婚制度」を理由として、上位法である憲法24条2項の意味を検討しようとすることは、法秩序が段階構造を有していることから上位法の意味を明らかにする際に下位法を用いてはならないということを理解しないものであり、解釈の方法として誤っている。
「そこで重視されるべき価値に対する理解の変化に伴い、その享有主体の範囲が狭きに失する疑いが生じてきており、」との部分について検討する。
これは直前で出てくる「現行の家族に関する法制度における現行の法律婚制度」の「それ単体」について、「そこで重視されるべき価値に対する理解の変化に伴い、」と述べているものである。
そのため、これは「現行の法律婚制度」を利用する者が抱く「③ 個々人の利用目的」について、「重視されるべき価値」が「変化」していることを示しているものということができる。
しかし、この婚姻制度を利用する者の抱く「③ 個々人の利用目的」について「重視されるべき価値」が変化したとしても、そのことは婚姻制度についての「① 国の立法目的」が変化するという理由になるものではない。
よって、「現行の法律婚制度」の「範囲」は「① 国の立法目的」から導き出されるにもかかわらず、その「範囲」を論じる際に「③ 個々人の利用目的」の話題を持ち出して、それを根拠として「狭きに失する疑い」をかけていることは、制度の立法目的や政策的な意図を無視して、制度を利用している者の抱いている価値観によって制度の枠組みそのものを変更することができるかのような前提で論じるものであり、誤っている。
また、婚姻制度の人的結合関係の「範囲」は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として、その目的を達成するための手段として定められているものである。
そのため、その目的との関係で整合的でない場合には、婚姻制度の中に含めることはできない。
ここで「享有主体」との文言があるが、法的な権利や利益を享有することのできる「主体」とは、「自然人」と「法人」があり、ここで「享有主体」という言葉を使うのであれば、それは「自然人」である個々人である。
そして、その個々人は「婚姻適齢」を満たしているのであれば婚姻制度を利用することは可能である。
よって、その個々人について婚姻制度の「享有主体の範囲が狭きに失する疑い」があるというのであれば、それは「婚姻適齢」を引き下げるか否かという話になるのであり、それと違うことを述べている部分は誤りとなる。
「結果として、同性愛者を法律婚制度の利用から排除することで、大きな格差を生じさせていながら、その格差に対して何ら手当てがなされていないことについて合理性が揺らいできているといわざるを得ず、もはや無視できない状況に至っていると考えられる。」との部分について検討する。
まず、「同性愛者を法律婚制度の利用から排除することで、」との部分を検討する。
「法律婚制度」は「性愛」を保護するための制度ではないし、個々人の「性愛』の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いを行う制度ではないし、「性愛」に基づいて制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもない。
そのため、「同性愛者」を称する者であるとしても、「法律婚制度」(男女二人一組)の要件に従って制度を利用する意思があるのであれば適法に利用することができるのであり、「同性愛者」を称する者を「法律婚制度の利用から排除」しているという事実はない。
よって、「結果として、同性愛者を法律婚制度の利用から排除することで、」と述べていることは誤りである。
次に、「大きな格差を生じさせていながら、」との部分を検討する。
そもそも「同性愛者」を称するものを「法律婚制度の利用から排除」しているという事実はないため、それによって「大きな格差」というものは生じていない。
三つ目に、「その格差に対して何ら手当てがなされていないことについて合理性が揺らいできているといわざるを得ず、」との部分を検討する。
上記で述べたように、「同性愛者」を称する者も「法律婚制度」を利用することができるため、利用することができないことを前提に「格差」が存在すると述べていることは誤りである。
これにより、その「格差」が存在することを前提として、「その格差に対して何ら手当てがなされていないこと」の「合理性」を論じようとしていることについても、その前提を欠くものであり、誤りである。
よって、「合理性が揺らいできているといわざるを得ず、」との部分も誤っている。
「もはや無視できない状況に至っていると考えられる。」との部分を検討する。
これは、「状況」の理解を誤っているため、「無視できない」と評価するか否かを論じる前提を欠いており、「無視できない」との評価を与えようとしている部分も妥当でない。
また、この「⑶ 憲法24条2項に違反するかについて」の項目の「イ」の内容により、「ウ」以下で問われているのは、24条2項の「家族」がここでいう「同性間の人的結合関係」に対して制度の創設を「要請」しているか否かであり、これは何かそれ以外のものについて「無視できない」と評価するか否かに左右されるものではないため、ここで「無視できない」と述べて何らかの結論を導き出すことができるかのように論じていることも妥当でない。
「オ」の内容は読み取りづらいので、下記のように整理する。
=======================================
「前記ウのとおり、憲法24条の適合性を審査するためには、本件諸規定により具体化された現行の「家族」に関する法制度の趣旨を検討する必要がある。」
↓ ↓
◇ 同性愛を精神的病理であるとする知見が否定されるに至った状況
「同性愛を精神的病理であるとする見解は、20世紀後半頃には否定されるに至り、性的指向それ自体は障害ではないとの知見が確立したことが認められる(…)。」
↓ ↓
◇ 世界的に同性カップルの法的保護に向けた活動が活発化
「各種国際機関は、20世紀後半以降、性的少数者の権利保護に向けた活動を行ってきたところ、こうした活動の中には、同性カップルに対して異性カップルに認められていた遺族年金の受給権を認めるもの(…)のほか、同性カップル及びその子供を法的に認知し、異性カップルに与えられてきた法的利益が差別なく付与されることを推奨するもの(…)、性的指向及び性自認にかかわらず、家族を形成する権利を有することを宣明するもの(…)など、同性カップルの生活共同体を保護するものが含まれている。」
↓ ↓
◇ 世界規模で同性カップルを保護するための具体的な制度化が実現
「諸外国においては、1989(平成元)年にデンマークが登録パートナーシップ制度を導入して以降、世界各国において、同性カップルを公証するための制度(登録パートナーシップ制度等)が導入されるようになったほか(…)、2000(平成12)年には、オランダが世界で初めて同性婚制度を導入し、現在までに、証拠上確認できるだけでも、28か国が同性婚制度を導入していることが認められる(…)。」
↓ ↓
◇ 我が国でも、多数の地方自治体が登録パートナーシップ制度を導入
「我が国でも、平成12年頃以降、同性愛者等をめぐる人権問題の解決の必要性が指摘され(…)、平成27年4月、地方自治体において初めて登録パートナーシップ制度が導入され、令和4年1月時点までに147の地方自治体がこれを導入しているほか、令和2年4月以降、同性パートナーがいる区職員に対しても結婚休暇等を認める取組みを行う地方自治体も現れ始めている(…)。」
↓ ↓
◇ 国レベルでの法制化の声が上がっている
「国においても、2008(平成20)年以降、国連の条約機関等からの勧告を受け(…)、平成14年以降、性的少数者に対する偏見等の解消に向けた啓発活動が行われたほか(…)、性同一性障害者の戸籍上の性別変更を認める法律の制定(…)が行われた。」
「平成29年には、一部諸外国から、同性婚の公式な承認を国レベルに拡大するなどの施策等の勧告がなされ(…)、それ以降、地方自治体や各種団体から、同性間の婚姻を求める声明が発表されるに至っている(…)。」
↓ ↓
◇ 民間企業においても、同性パートナーに家族手当等を適用するといった取組みを行う企業
↓ ↓
◇ わが国でも同性カップルに対する理解が進み、これを承認しようとする傾向が加速
「平成30年以降には、同性婚を法的に認めることに関する国民の意識調査において、賛成派が反対派を上回る結果が報告されるようになり、その中には賛成派が約6割半に及ぶとする結果や、20ないし50代の比較的若い層を対象としたものでは、賛成派が、男性の約7割、女性の9割弱を占める結果も存在している(…)。」
↓ ↓
◇ 家族の形態として、男女の結合関係を中核とした伝統的な家族観は唯一絶対のものであるというわけではなく
「近年家族の多様化が指摘されており、平成30年時点で、全世帯総数のうち独身世帯が占める割合は、昭和61年の18.2%から27.7%にまで上昇し、夫婦のみ世帯が占める割合も、同年の14.4%から24.1%にまで上昇する一方、夫婦と未婚の子のみの世帯は、同年の41.4%から29.1%にまで減少するなど(…)、男女の結合関係を中核としてその間に生まれた子の保護・育成の機能を担うという伝統的な家族観が、唯一絶対のものであるというわけではなくなっていることが認められる。」
↓ ↓
「婚姻の本質は、両当事者において永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもって共同生活を営むことにあるのであり、伝統的な家族観が支配的であった旧民法の起草過程という時期においてさえ、婚姻が両心の和合を性質とするものであるとされ、生殖不能が婚姻障害事由に掲げられなかったとおり(…)、婚姻の意義は、単に生殖と子の保護・育成のみにあるわけではなく、親密な関係に基づき永続性をもった生活共同体を構成することが、人生に充実をもたらす極めて重要な意義を有するものと理解されていたと解される。」
↓ ↓
「このような親密な関係に基づき永続性をもった生活共同体を構成することは、同性カップルにおいても成しうるはずのものである。」
↓ ↓
「歴史上、家族は、男女の結合関係(婚姻)を中核とし、その間に生まれた子の保護・育成を担うものであると捉えられてきており、本件諸規定の制定当時も、このような伝統的な家族観が支配的であった。」
↓ ↓
「その後の社会情勢を踏まえても、依然として、婚姻制度の理解において自然生殖の可能性が完全に切り離されたとはいえない状況にあって、伝統的な家族観を重視する立場の国民が一定の割合を占めていることからすれば、男女の生活共同体に対して法律婚制度により公証を与え、これを保護するための枠組みを設けることは、それ自体合理性を有するものではある。」
↓ ↓
「現行の家族に関する法制度における現行の法律婚制度はそれ単体としては合理性があるように見えたとしても、そこで重視されるべき価値に対する理解の変化に伴い、その享有主体の範囲が狭きに失する疑いが生じてきており、結果として、同性愛者を法律婚制度の利用から排除することで、大きな格差を生じさせていながら、その格差に対して何ら手当てがなされていないことについて合理性が揺らいできているといわざるを得ず、もはや無視できない状況に至っていると考えられる。」
=======================================
しかし、この説明は法解釈を述べるものではない。
まず、憲法24条2項の「家族」は、「夫婦」と「親子」による「血縁関係者」の範囲を指し、それ以外のものは含まれない。
次に、婚姻制度は「性愛」を保護するための制度ではないため、「同性愛」が「精神的病理」であるか否かを論じても、婚姻制度に何らの影響も与えない。
三つ目に、諸外国の法制度と日本国の法制度には様々な違いがあり、諸外国で制度が設けられているとしても、それは日本国で制度を設けることができるとする理由にはならない。
四つ目に、地方自治体のパートナーシップ制度は憲法よりも下位の法形式の制度であるか、そもそも法的な効力を持たないものであり、それを根拠として憲法24条2項の規範の意味を検討することはできない。
五つ目に、特定の団体の「声明」が発表されたとしても、それによって法解釈の結論が左右されることはない。
六つ目に、特定の民間企業の「契約」の内容が法制度の解釈に影響を与えることはない。
七つ目に、国民の賛成・反対の数によって法解釈の結論は左右されない。
八つ目に、「婚姻」という概念は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成するための手段として形成されているものであり、その目的を離れて「婚姻」という言葉を使うことはできず、この「婚姻」という言葉に対して後から「伝統的な家族観」というものが当てはめられているという性質のものではないため、それが「唯一絶対のもの」か否かを論じて何らかの結論を導き出すことができるというものではない。
九つ目に、「婚姻」は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度であり、「親密な関係」であることを理由として制度を設けているわけではない。
また、婚姻制度(男女二人一組)は「性愛」を保護するための制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査していないし、「性愛」に基づいて制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもない。
そのため、「同性愛者」を称する者を「排除」しているという事実はなく、それによって「格差」が生じているということはできない。
よって、これらを理由として憲法24条2項の規範の意味を検討しようとしていることは誤りである。
カ 前記ウのとおり、憲法24条の適合性を審査するためには、さらに、本件諸規定により具体化された現行の法律婚制度が採用されたことによる影響を検討する必要がある。
【筆者】
「前記ウのとおり、憲法24条の適合性を審査するためには、」との部分について検討する。
この「⑶ 憲法24条2項に違反するかについて」の項目の「イ」の第五段落の記述を受けて「ウ」以下で問われているのは、24条2項の「家族」が、「親子」や「親子」の関係を基本とした「兄弟」「姉妹」などに含まれない「同性間の人的結合関係」を対象とした制度を立法することを「要請」しているか否かである。
「要請」しているならばその制度がないことは違憲となり、「要請」していないのであればその制度がないことは「合憲」というものである。
そして、ここでは「前記ウのとおり、」と述べていることから、その「前記ウ」に記載された「夫婦同氏制大法廷判決」を持ち出し、それを基準として憲法24条2項に違反するか否かを検討しようとするものとなっている。
しかし、この「夫婦同氏制大法廷判決」で問われているのは、憲法24条2項の「婚姻及び家族」の枠組みの「要請」に従って立法された法律上の具体的な制度の内容が「個人の尊厳」と「両性の本質的平等」を満たすか否かであり、この名古屋地裁判決で24条2項の「家族」が、ここでいう「同性間の人的結合関係」を対象とした制度を立法することを「要請」しているか否かが問われているものとは事案を異にしている。
よって、この名古屋地裁判決で問われている内容について、「前記ウ」に記載された「夫婦同氏制大法廷判決」を用いて判断を行うことはできない。
また、「前記ウのとおり、」のように「夫婦同氏制大法廷判決」の基準に従う形で「本件諸規定により具体化された現行の法律婚制度が採用されたことによる影響を検討する必要がある。」と述べるものとなっているが、「夫婦同氏制大法廷判決」は「婚姻及び家族」に含まれるものについて審査を行うものであり、そもそも「婚姻及び家族」に含まれないものについて「憲法24条」に「適合」するか否かを審査することができるとしているものではない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) そうすると,憲法上の権利として保障される人格権を不当に侵害して憲法13条に違反する立法措置や不合理な差別を定めて憲法14条1項に違反する立法措置を講じてはならないことは当然であるとはいえ,憲法24条の要請,指針に応えて具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定が上記(1)のとおり国会の多方面にわたる検討と判断に委ねられているものであることからすれば,婚姻及び家族に関する法制度を定めた法律の規定が憲法13条,14条1項に違反しない場合に,更に憲法24条にも適合するものとして是認されるか否かは,当該法制度の趣旨や同制度を採用することにより生ずる影響につき検討し,当該規定が個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理性を欠き,国会の立法裁量の範囲を超えるものとみざるを得ないような場合に当たるか否かという観点から判断すべきものとするのが相当である。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
この「夫婦同氏制大法廷判決」の内容は、憲法24条2項の「婚姻及び家族」の枠組みの「要請」に従って立法された法律上の具体的な制度が存在することを前提として、その「法律」の内容が「個人の尊厳」と「両性の本質的平等」に違反するか否かが問われている。
これは、これは下位法にあたる「法律」の内容を論じるものである。
これに対して、この名古屋地裁判決の「⑶ 憲法24条2項に違反するかについて」の項目の「イ」の第五段落の記述を受けて「ウ」以下の内容は、24条2項の「家族」が、ここでいう「同性間の人的結合関係」を対象とした制度を立法することを「要請」しているか否かが問われている。
これは、「憲法(24条2項)」の内容それ自体を論じるものである。
そのため、これらの間では問われている事柄の次元が異なっており、同一の事案と見ることはできない。
◇ 「夫婦同氏制大法廷判決」
憲法24条2項の「婚姻及び家族」の枠組みの「要請」に従って立法された法律上の具体的な制度の内容が、「個人の尊厳」と「両性の本質的平等」を満たすか否かが問われている。
◇ 名古屋地裁判決
憲法24条2項の「家族」が「要請」しているか否かが問われている。
そのことから、この名古屋地裁判決で問われている内容を検討するための基準として、「夫婦同氏制大法廷判決」を用いることはできない。
よって、この名古屋地裁判決が憲法24条2項の「家族」が、ここでいう「同性間の人的結合関係」に対する制度を「要請」しているか否かの問題に対して、「夫婦同氏制大法廷判決」の基準を用いることができるかのような前提で論じていることは誤りである。
この点については、このページの上記「ポイント」の所でも解説している。
もう一つ、憲法24条2項の「家族」が、「親子」や「親子」の関係を基本とした「兄弟」「姉妹」などに含まれない「同性間の人的結合関係」に対する制度を立法することを「要請」しているか否かは、憲法24条2項の文言それ自体の意味を読み解くことによって判断を行うことが必要である。
しかし、ここではその憲法よりも下位の法令にあたる「本件諸規定により具体化された現行の法律婚制度」を持ち出し、それが「採用されたことによる影響」のように下位の法令における立法政策を根拠としてその上位の法令である憲法24条2項の意味を明らかにしようと試みるものとなっている。
これは上位法の意味を理解する際に下位法を根拠としようとするものであるから、法秩序の階層構造を損なわせるものであり、解釈の方法として正当化することができない。
そのため、「憲法24条の適合性を審査するため」に、「現行の法律婚制度」やその「影響」を検討しようとしていることは、誤りである。
よって、これより以下の検討内容についても、すべて「憲法24条の適合性を審査するため」に根拠とすることができないものを論じており、誤りである。
このように、この段落の内容は同時に複数の誤りを抱えるものとなっており、その主張の全体も誤りとなる。
同性カップルは、異性カップルと比較して、両当事者の関係が国の制度により公証され、その関係を保護するのにふさわしい効果の付与を受けるための枠組みを利用することができないという格差が生まれている。そして、かかる枠組みを利用することができるという価値は、単に法律によって付与された価値というにとどまらず、人の尊厳に由来する重要な人格的利益を基礎としているというべきである。永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもって共同生活を営もうとする同性カップルにおいて、婚姻に伴う個々の法的効果が付与されないのみならず、その関係が国の制度によって公証されず、その関係を保護するのにふさわしい効果の付与を受けるための枠組みすら与えられない不利益は甚大なものである。このことは、性的少数者を対象とするアンケートにおいて、結婚相当証明書申請をしたい理由として、「法律上、家族として認めてほしいのでその第一歩として」と回答した者が、全体の半数以上を占めていたこと(認定事実⑹イ )からも裏付けられる。
【筆者】
「同性カップルは、異性カップルと比較して、両当事者の関係が国の制度により公証され、その関係を保護するのにふさわしい効果の付与を受けるための枠組みを利用することができないという格差が生まれている。」との記載がある。
まず、「同性カップルは、異性カップルと比較して、」「格差」があるかないかを検討しようとしている部分について検討する。
法律論上として比較対象として取り上げることができる対象は、「権利能力」を有し法主体としての地位を認められている者同士だけである。
「権利能力」を有して法主体としての地位を認められるものには「自然人」と「法人」があり、ここでいう「カップル」という「二人一組」については法人格を取得していないため「権利能力」を有しておらず法主体としての地位を認められているものではないことから、これは個々の「自然人」である一人一人が人的結合関係を形成しているものとして認識することが必要である。
そのことから、法律論として比較を行う際には、「権利能力」を有して法主体としての地位を認められている個々の「自然人」を単位とすることが必要であり、ここで「同性カップル」や「異性カップル」のように「二人一組」を持ち出して「比較」を行うことができるかのような前提で「格差」を論じている部分は誤りである。
次に「両当事者の関係が国の制度により公証され、その関係を保護するのにふさわしい効果の付与を受けるための枠組みを利用することができないという格差が生まれている。」との部分について検討する。
ここでは「両当事者の関係」のように、ある人的結合関係を取り上げて論じようとするものとなっている。
しかし、「権利能力」を有して法主体としての地位を認められているのは「自然人」と「法人」であり、この「両当事者の関係」というものは「法人」としての法人格を取得しているものではないため、法律論としてこれを取り上げて比較することはできない。
そのことから、これは個々の「自然人」が人的結合関係を形成している状態として考える必要があり、「両当事者の関係」のような形で「二人一組」を取り上げて論じようとしている部分が誤りである。
ここでは婚姻制度が存在していることを前提とする文面であることから、その個々の自然人が婚姻制度を利用することができるか否かについて検討する。
個々の自然人は「婚姻適齢」を満たしているのであれば、婚姻制度を利用することができるのであり、そこに「婚姻」という「枠組み」について「利用することができないという格差」というものは生じていない。
よって、個々人が婚姻制度を「利用することができない」と論じることは誤りとなる。
「両当事者の関係が国の制度により公証され、その関係を保護するのにふさわしい効果の付与を受けるための枠組み」と称するものについて検討する。
憲法は「個人の尊厳」の原理に基づいており、自然人は「個人主義」の下に「自律的な個人」として生存していくことを予定している。
そして、その個々の自然人は人的結合関係を形成する自由を有しており、人的結合関係を生成、維持、解消を繰り返すなどしながら生活していくことになる。
これは「国の制度により公証」されるものではなく、各人の「国家からの自由」という「自由権」によって形成されるものである。
これにより、個々人が「恋愛・性愛」という特定の価値観に基づいて人的結合関係を形成することもできるし、共同生活のための人的結合関係を形成することも可能である。
これらの人的結合関係を形成することについては、「自由権」の範囲を超えて具体的な制度を設けて「保護」しなければならないということにはならないのであり、ここでいう「ふさわしい効果」と称する具体的な制度を「付与」しなければならないとの前提が存在していない。
あえて言うならば、その「自由権」を保障することが「保護」であり、「ふさわしい効果」ということができる。
このような中、「婚姻」は「生殖と子の養育」の観点からこれら他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度であり、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす形で枠組みを定めているものである。
この制度の対象となる場合とならない場合があることは、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成するための手段として設けられている差異であることから、制度そのものが政策目的を達成するための手段として設けられる性質のものである以上は当然のことである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
しかしながら、被告第3準備書面第1の2(7ページ)で述べた通り、人は、一般に社会生活を送る中で、種々の、かつ多様な人的結合関係を生成しつつ、生きていくものであり、当該人的結合関係の構築、維持及び解消をめぐる様々な場面において幾多の自己決定を行っていくものと解されるが、そのような自己決定を故なく国家により妨げられているか否かということと、そのような自己決定の対象となる人的結合関係について国家の保護を求めることができるか否かということは、区別して検討されるべきものと解される。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【東京二次・第9回】被告第7準備書面 令和5年9月28日 PDF
「そして、かかる枠組みを利用することができるという価値は、単に法律によって付与された価値というにとどまらず、人の尊厳に由来する重要な人格的利益を基礎としているというべきである。」との部分について検討する。
ここでいう「かかる枠組み」とは、一文前の「両当事者の関係が国の制度により公証され、その関係を保護するのにふさわしい効果の付与を受けるための枠組み」のことを指すものである。
しかし、そもそも憲法は「個人の尊厳」の原理に基づいており、自然人は「個人主義」の下に各々「自律的な個人」として生存していくことを予定していることから、その個々人が何らかの人的結合関係を形成したとしても、その状態に対して「枠組み」と称する具体的な制度を設けなければならないという前提が存在しない。
よって、「かかる枠組みを利用することができるという価値」のように、「かかる枠組み」と称する具体的な制度を国が設けなければならないかのような前提で論じている部分が誤りである。
また、「単に法律によって付与された価値というにとどまらず、」との部分についても、「法律」によって「かかる枠組み」と称する具体的な制度を創設しなければならないとの前提か存在しておらず、「法律によって付与された」のように、具体的な制度が「法律によって付与」されるかのような前提で論じている部分が誤りである。
「人の尊厳に由来する重要な人格的利益を基礎としているというべきである。」との部分を検討する。
「人の尊厳」とは、憲法13条で定められている「個人の尊重」の原理が「個人主義」の下に「個人」を尊重していることの意味が「全体主義」における「全体」との間で対比するものとなっていることの基底となる部分に、そもそも「人間」と「人間以外(物や動物)」との間を区別し、物や動物と対比して「人」としての尊厳が存在するという意味の言葉である。
人間〔人の尊厳〕 ⇒ <全体 ←→ 個人〔個人の尊重〕>
↑
↓
人間以外(物や動物)
(当サイト『人権と同じような言葉』でも解説している。)
しかし、憲法13条が「個人の尊重」を定めていることの前提には、既に「人の尊厳」の意味は含まれていることから、憲法13条の「個人の尊重」が存在する中で「人の尊厳」が実現されていないということにはならない。
また、憲法13条の「個人の尊重」によって具体的な制度を国家に対して求めることはできないのであり、当然、その基底にある「人の尊厳」によっても具体的な制度の創設を国家に対して求めることができることにはならない。
そして、この「人の尊厳」について「国家からの自由」という「自由権」の性質を見出して用いることを検討するとしても、これは「人間」と「人間以外(物や動物)」の間を区別する意味であることから、例えば人をライオンの餌として扱ったり、人を災いを防ぐための生贄として使ったり、人を家畜にして飼育したり、人を奴隷として売買したりするようなことがあった場合に、その侵害を排除するために用いられる概念である。
しかし、ここでいう「かかる枠組み」と称する具体的な制度が存在していないとしても、そのことは人を動物と同様の扱いをしたり、物のように扱ったりするものであるとはいえないことから、「人の尊厳」に反する状態にあるとはいえない。
よって、「かかる枠組みを利用することができるという価値」と称するものについて「人の尊厳に由来する」と述べていることは誤りである。
「重要な人格的利益を基礎としている」との部分であるが、この「人格的利益」の文言は「夫婦同氏制大法廷判決」を前提としているようである。
しかし、「夫婦同氏制大法廷判決」では、憲法24条2項の「婚姻及び家族」の枠組みの「要請」に従って立法された法律上の具体的な制度について「個人の尊厳」を満たすか否かが判断される中において「人格的利益」が述べられているものであり、そもそも憲法24条2項の「婚姻及び家族」に当てはまらない場合については「個人の尊厳」が適用される前提にはないため、「人格的利益」が登場する余地もない。
そして、ここでいう「同性間の人的結合関係」については、「親子」や「親子」の関係を基本とした「兄弟」「姉妹」などに当たらないため、憲法24条2項の「婚姻及び家族」には含まれておらず、「個人の尊厳」の文言を適用する前提になく、「夫婦同氏制大法廷判決」のいう「人格的利益」についての検討を行うこともできない。
よって、これについて「夫婦同氏制大法廷判決」を基にして「人格的利益」を持ち出しているのであれば誤りである。
これとは別に、憲法13条の「個人の尊重」の観点から「人格的利益」を述べようとしているとしても、憲法13条によって具体的な制度の創設を国家に対して求めることはできないことから、これによって「かかる枠組み」と称する具体的な制度の創設を求めることができるかのように述べている部分も誤りである。
「永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもって共同生活を営もうとする同性カップルにおいて、婚姻に伴う個々の法的効果が付与されないのみならず、その関係が国の制度によって公証されず、その関係を保護するのにふさわしい効果の付与を受けるための枠組みすら与えられない不利益は甚大なものである。」との記載がある。
「永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもって共同生活を営もう」との部分について、これは最高裁判決(昭和62年9月2日)の「婚姻の本質は、両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもつて共同生活を営むことにある」という文を抜き出したようであるが、この文は具体的な婚姻制度が存在することを前提として、その婚姻制度を利用する者の法律関係の状態を簡潔に示したものであり、具体的な婚姻制度の存在を前提とせずに法律関係の意味を離れて用いることができるものではなく、これを文学的な語感に基づいて意味を捉えようとしている部分が誤りである。
「同性カップルにおいて、婚姻に伴う個々の法的効果が付与されないのみならず、」との部分であるが、「婚姻」は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた枠組みであり、その制度の対象となる場合とならない場合があることは当然予定されていることである。
ここでいう「同性カップル」という「同性間の人的結合関係」についても、これはその間で「生殖」を想定することができず、「生殖と子の養育」の趣旨を満たすものではないため、「婚姻」とすることはできない。
よって、「婚姻に伴う個々の法的効果が付与されない」との部分は、制度の対象でないという意味でその通りである。
「同性カップル」について「その関係が国の制度によって公証されず、その関係を保護するのにふさわしい効果の付与を受けるための枠組みすら与えられない」と述べている部分について検討する。
憲法は「個人の尊厳」の原理に基づいており、自然人は「個人主義」の下に各々「自律的な個人」として生存していくことを予定している。
また、その中で個々人は自由に人的結合関係を生成、維持、解消することが可能であり、これに対して具体的な制度を必要とするものではない。
そのため、個々人が何らかの人的結合関係を形成したとしても、「国の制度によって公証
」しなければならないということにはならない。
個々人が人的結合関係を形成する自由があるという状態について「国家からの自由」という「自由権」によって「保護」されており、それについて「ふさわしい効果」と呼ぶことはできるとしても、「枠組み」と称する制度を立法しなければならないということにはならない。
よって、「枠組みすら与えられない」のように、具体的な制度の創設を国家に対して求めることができるかのような前提で論じている部分は妥当でない。
「不利益は甚大なものである。」との部分について検討する。
憲法は「個人の尊厳」の原理に基づいており、自然人は「個人主義」の下に各々「自律的な個人」として生存していくことを予定していることから、何らの制度も利用していない状態で既に完全な状態であり、そこに「不利益」は存在していない。
よって、ここでいう「枠組み」と称するような具体的な制度を利用していないことについて、「不利益は甚大なものである。」と評価している部分は、「不利益」のない状態であるにもかかわらず、それがあたかも「不利益」であるかのように述べるものであり、誤りである。
また、この「⑶ 憲法24条2項に違反するかについて」の項目の「イ」の内容により、「ウ」以下で問われているのは、24条2項の「家族」がここでいう「同性間の人的結合関係」に対して制度の創設を「要請」しているか否かであり、「不利益」であるか否かが論点となっているわけではない。
よって、「不利益」か否かを論じることによって何らかの結論を導き出そうとしている部分が誤りである。
「性的少数者を対象とするアンケートにおいて、結婚相当証明書申請をしたい理由として、「法律上、家族として認めてほしいのでその第一歩として」と回答した者が、全体の半数以上を占めていたこと(…)からも裏付けられる。」(カッコ内省略)との記載がある。
まず、「性的少数者」とは、この判決の「第2」の「2⑴」で述べているように「LGBTI等の性的指向及び性自認における少数者」のことを指している。
しかし、ここでいう「性的指向」、「性自認」、「I」である「インターセックス(Inter Sex)」であるか否かに関わらず、法律上の要件を満たすのであれば「婚姻及び家族」の制度を利用することはできることから、ここでいう「性的少数者」がそれを得られないかのような前提で論じている部分が誤りである。
「婚姻及び家族」の制度の対象となっていない組み合わせについては、それは「家族として認めてほしい」としても、ここでいう「家族」ではないことになる。
その他、「性的少数者」のうち「性的指向」と「性自認」については、心理的・精神的なものを勘案するものであるから、自己が「性的少数者」であると思えば「性的少数者」であると述べることができるものであり、その者を対象とする「アンケート」を実施しても、「性的少数者」を自称している者を対象とした「アンケート」に過ぎないものである。
このような明確な基準がないものを根拠として集計して論じようとしている部分も妥当ではないし、そもそも婚姻制度は「性愛」を保護することを目的とした制度ではないため、婚姻制度と関係のない事柄についてのアンケートを持ち出して論じている部分も妥当でない。
これは結局、「婚姻及び家族」の制度の枠を超えた新たな制度の創設を国家に対して求める主張に他ならず、一文前のいう「不利益は甚大なもの」であることを「裏付け」るものとはいえない。
よって、ここで「裏付けられる。」と述べている部分は誤りである。
確かに、同性カップルにおいても、原告らがそうであるように、結婚契約等公正証書を締結するなど、契約や遺言などの法律行為を行うことにより、一定程度、異性カップルに対するのと同等の効果を得ることが可能である。しかし、これらにより全てを賄えるものではないし、個々の法定効果の付与も大切ではあるが、それにとどまらず、同性カップルという関係が国の制度によって公証され、その関係を保護するのにふさわしい効果の付与を受けるための枠組みが与えられることに重大な価値があるのであり、これを享受できない不利益を解消することはできない。
【筆者】
「同性カップルにおいても、原告らがそうであるように、結婚契約等公正証書を締結するなど、契約や遺言などの法律行為を行うことにより、一定程度、異性カップルに対するのと同等の効果を得ることが可能である。」との記載がある。
まず、「同性カップル」と「異性カップル」という「二人一組」を取り上げて比較している部分であるが、法律論上は「権利能力」を有して法主体としての地位を認められている個々の自然人を単位として考えることが必要である。
そして、個々人は「契約や遺言などの法律行為」を行いながら生活していくことが基準(スタンダード)であり、既に完全な状態である。
ここでは「異性カップルに対するのと同等の効果を得ることが可能」か否かを論じているが、もともと個々人は「契約や遺言などの法律行為」を行いながら生活していくことが基準(スタンダード)であることから、何らかの制度(婚姻制度)を利用している者と比較してそれが「同等の効果」でなければならないということにはならない。
よって、「異性カップルに対するのと」のように、「婚姻制度を利用している者(既婚者)」を基準(スタンダード)として考えて、これと比較して「同等の効果を得ることが可能」か否かを論じることは、基準点を誤っており、妥当でない。
婚姻制度は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成するための手段としていくつかの法的効果をパッケージとしているだけであるから、そのパッケージを利用していない「婚姻していない者(独身者)」の状態を基準(スタンダード)として考える必要がある。
「これらにより全てを賄えるものではないし、個々の法定効果の付与も大切ではあるが、それにとどまらず、同性カップルという関係が国の制度によって公証され、その関係を保護するのにふさわしい効果の付与を受けるための枠組みが与えられることに重大な価値があるのであり、これを享受できない不利益を解消することはできない。」との記載がある。
「これらにより全てを賄えるものではないし、」との部分であるが、そもそも「婚姻していない者(独身者)」の状態が基準(スタンダード)であり、「婚姻している者(既婚者)」が婚姻制度から得ている法的な効果の「全てを賄える」かどうかというように、「婚姻している者(既婚者)」の状態が基準(スタンダード)であるかのように論じている部分が誤りである。
「個々の法定効果の付与も大切ではあるが、」との部分であるが、婚姻制度は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成するための手段として対象となる者を定め、それに対していくつかの法的効果を設けているものであることから、そもそも婚姻制度の対象とならない場合には、それによる法的な効果を与えないとしているものである。
そのため、ここで婚姻制度の対象となっていない場合であるにもかかわらず、それに「個々の法定効果」が「付与」されるかのように述べている部分は誤りである。
もしこの「個々の法定効果」というものが「契約や遺言などの法律行為」のことを指しているのであれば、それは婚姻制度の中から「個々の法定効果」が抜き出されて「付与」されるというものではなく、「契約」や「遺言」として単独で成立しているものであるから、婚姻制度の中から抜き出して「付与」するかのように述べている部分は誤りである。
「同性カップルという関係が国の制度によって公証され、その関係を保護するのにふさわしい効果の付与を受けるための枠組みが与えられることに重大な価値があるのであり、これを享受できない不利益を解消することはできない。」との部分について検討する。
まず、この「⑶ 憲法24条2項に違反するかについて」の項目で問われているのは、憲法24条2項の「家族」がここでいう「同性カップル」という「同性間の人的結合関係」を対象とした制度を立法することを「要請」しているか否かである。
ここでいう「同性間の人的結合関係」については、「親子」ではないし、「親子」の関係を基本とした「兄弟」「姉妹」などにも当たらないことから、「家族」には含まれない。
そのため、憲法24条2項はここでいう「同性間の人的結合関係」を対象とした制度を立法することを「要請」しておらず、その制度がないことが憲法24条2項に違反することはない。
よって、ここでは「同性カップルという関係が国の制度によって公証され、その関係を保護するのにふさわしい効果の付与を受けるための枠組みが与えられることに重大な価値がある」と述べているが、憲法24条2項の「家族」はそのような制度を立法することを「要請」していないため、その制度が存在しないことについて憲法24条2項に違反するということにはならない。
「これを享受できない不利益を解消することはできない。」との部分であるが、これは単に憲法24条2項の「婚姻及び家族」によって「要請」されていない制度であるにもかかわらず、その制度が存在しないことを取り上げて、何かを「享受」できると考えて「これを享受できない」と述べてみたり、「不利益」があることを前提として「不利益を解消することはできない。」と述べるなどして、そのことについて憲法24条2項を理由とする形で憲法違反を認めさせようとするものであり、論理的に意味の通らないものとなっている。
また、憲法は「個人の尊厳」の原理に基づいており、自然人は「個人主義」の下に各々「自律的な個人」として生存していくことを予定していることから、何らの制度も利用していない状態で既に完全な状態であり、そこに「不利益」といわれるものは存在していない。
そのため、その状態について「不利益」があると考えて、その「不利益」を「解消」しなければならないかのような前提で論じていること自体も誤りである。
そして、わが国におけるLGBTの人口規模は、必ずしも明らかではないが、平成27年及び平成28年に行われた調査では4.9%から7.6%であったというのであり(前提事実⑴)、少なく見ても百万人単位には達するものと推定できる。そして、医学心理学的知見によれば、性的指向は、ほとんどの場合、人生の初期又は出生前に決定され、自らの意思や精神医学的な療法によって変わるものではないとされており(認定事実⑴ア)、性的指向が生来的な特性であり、環境によって変動するものではないと考えられること、LGBTの人口規模が実数という意味において近年に激増したとの知見が見当たらないことなどからすれば、現行の法律婚制度が制定された当初からLGBTの人口が相当数に上っていたと推認できるのであり、医学心理学的知見の変遷や社会意識の変革が生ずる前の時期もあったとはいえ、70年以上の長期にわたって少なくない人口の同性カップルに対し、上記保護の枠組みが与えられていなかったものである。
【筆者】
「わが国におけるLGBTの人口規模は、必ずしも明らかではないが、平成27年及び平成28年に行われた調査では4.9%から7.6%であったというのであり(…)、少なく見ても百万人単位には達するものと推定できる。」(カッコ内省略)との記載がある。
まず、「LGBT」とは、内心にのみ存在する精神的なものによるものであるから、自らが「LGBT」であると名乗ることには何らの資格も必要としないものである。
ここでは「調査」の結果を示しているが、そこで「4.9%から7.6%であった」のようにはっきりとした数字を示すことができないことは、そのような事情によるものである。
アメリカでは下記のような調査結果も存在し、「LGBT」と称することに明確な基準があるわけではないことは明らかである。
【参考】アメリカの若者の30%以上が「自分はLGBTQ」と認識していることが判明 2021年10月26日
そのため、「LGBT」を名乗る者がいるとしても、それは客観性のある基準によるものではないのであり、このような「調査」と称するものを根拠として法律論を組み立てることはできない。
また、このような「調査」と称するものを根拠として法律論上の規範となる枠組みが左右されることはないし、それによって結論が変わるようなこともあってはならない。
「LGBT」であるか否かそれ自体がそれを名乗り出た者による自称でしかないことを押さえれば、それについての「調査」を前提として論じているこの判決の内容そのものも、説得的な説明を行っているものではないことが明らかとなる。
次に、婚姻制度は「性愛」の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的とする制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いをするものではないし、「性愛」に基づいて制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもない。
そのため、ここで「LGBT」のように「LGB」を取り上げて論じていること自体が、婚姻制度との間で関係性を認めることができないもので妥当でない。
三つ目に、「LGBT」を名乗る者の中にも、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを望んでいる者もいれば、望んでいない者もいる。
例えば、キリスト教においても様々な宗派があるし、仏教においても様々な宗派があることと同様に、「LGBT」を名乗る者にも様々な考え方が存在するのである。
また、「ホモ」を自称するが、「LGBT」というカテゴリーに加えられたくない、一緒にされたくない、「LGBT」を名乗る政治運動に加わりたくない、その者たちに利用されたくないと考えている者もいる。
それにもかかわらす、それらの中の一部の集団の意見だけを取り上げて、「LGBT」を名乗る者の意見が一つに集約されてまとまっているかのような前提で論じていること自体が妥当でない。
よって、すべての「LGBT」を名乗る者が「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることや何らかの制度を立法することを望んでいるかのような論じ方をすることは、前提を誤っている。
また、たとえその意見が一つに集約されているとしても、そのような内心の事柄と法制度は切り離して考えなければならないのであり、これを結び付けて論じることもしてはならない。
そのため、このような内心に基づいて人を分類しようとする一つの思想を持ち出して、法制度の存否の当否を論じようとしていることそのものが妥当でない。
四つ目に、そもそも「LGB」と「T」では性質が大きく違うにもかかわらず、これをまとめて説明することは妥当でないし、それをまとめたままの数字を示して根拠としようとしていることも疑問である。
「医学心理学的知見によれば、性的指向は、ほとんどの場合、人生の初期又は出生前に決定され、自らの意思や精神医学的な療法によって変わるものではないとされており(…)、性的指向が生来的な特性であり、環境によって変動するものではないと考えられること、」(カッコ内省略)との記載がある。
婚姻制度は「性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いをするものではないし、「性愛」に基づいて婚姻制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもない。
よって、「性愛」を有する場合に、それがどのような対象に向かうかに関する「性的指向」と称するものを論じる必要そのものがないのであり、これを論じた上で判断しようとする前提そのものに誤りがある。
また、法制度を立法する場合には、個々人の内心に中立的な内容でなければならないのであり、特定の「性愛」の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的として制度を立法した場合には、そのこと自体が違憲となる。
よって、「性的指向」と称するものを論じた上で、「保護の枠組み」と称する制度の立法について検討していること自体が妥当でない。
「自らの意思や精神医学的な療法によって変わるものではないとされており」との部分であるが、「自らの意思」で「性的指向」を変えたいと望む者もいるにもかかわらず、それを「変わるものではない」と示すことは控えるべきものである。
たとえば、「異性愛から同性愛へ」「同性愛から異性愛へ」「小児性愛から成人性愛へ」「両性愛から多性愛へ」「全性愛から無性愛へ」など、様々な方面に「自らの意思」で変えたいと望む者が存在する。
それに対して、「変わるものではない」と断じることは、その者の意思を否定することになるため、決して望ましいものではない。
もちろん、他者が本人の意思に反して無理に変えさせようと強制することは憲法19条の「思想良心の自由」の精神に反して許されないことは言うまでもない。
しかし、この判決が人の内心そのものを「変わるものではない」と断じることそのものも、憲法19条の「思想良心の自由」を侵す判断に他ならないことを理解する必要がある。
「性的指向は、ほとんどの場合、人生の初期又は出生前に決定され、自らの意思や精神医学的な療法によって変わるものではないとされており(…)、性的指向が生来的な特性であり、環境によって変動するものではないと考えられる」との部分について検討する。
研究の中には「性的指向」は後天的に形成され、「自らの意思や精神医学的な療法によって変わる」ものであり、「生来的な特性」ではなく、「環境によって変動する」と考える立場も存在する。
そのため、そのような別の研究の立場を一方的に排してここで述べるような特定の立場を支持することを前提として、それに基づいて法規範の意味を論じようとすることは妥当でない。
もちろん、他者が本人の意思に反して無理やり変えさせようと強制することは、「思想良心の自由」の精神に反して許されないことは言うまでもない。
そのような本人の意思に反して他者が無理やり変えさせようと強制するような事案があった場合には、そのような行動をとることが適切ではないことを説明するために、「人生の初期又は出生前に決定され、自らの意思や精神医学的な療法によって変更されるものではない」や「生来的な特性であり、環境によって変動するものではない」という見解が必要とされ、そのことを裏付ける研究の結果が強調されることがある。
しかし同時に、本人が自らの意思で変えたいと望んだ場合には、「人生の初期又は出生前に決定され」るとは限らず、「自らの意思や精神医学的な療法によって変更」することも可能でり、「生来的な特性」ではなく、「環境によって変動するもの」であるとする見解が必要とされ、そのことを裏付ける研究の結果が強調されることもあり得るものである。
もし本人が「自らの意思」で変えたいと望むのであれば、その可能性もまた開かれるということである。
そのような中、特定のグループや個人は、自己の置かれている事情の中で生じている課題を解決するために、それらの様々な見解の中から特定の見解を引き出して論じるなどしているに過ぎないのである。
そのため、これら人の内心にのみ存在する心理的・精神的な研究については、本来的に物理的な現象を外部から観測することによって誰もが共通した認識を持つことができるという意味での客観性を保つことができるものではないのであり、もともと様々な見解が存在しており、それを一つの見解に絞ることができるというものではないし、一つの見解に絞ることが適切であるともいえないものである。
そのことから、このような学術的な知見の当否の問題については、裁判所において審判することのできる範囲を超えるものである。
よって、このような事柄に対して裁判所が特定の見解だけを拾い上げて支持・不支持を表明するようなこととなっていることは適切ではない。
また、「性的指向」と称しているものの性質についての見解の当否を前提としなければ法的な判断を行うことができないような場合(『性的指向』と称しているものの性質について特定の立場に基づかなければこの判決を構成する論旨を正当化することができない場合)については、そもそも法令を適用することによって終局的に解決することができる問題とはいえない。
そのため、このような特定の見解を採用すること基づく形で判断を試みていることは、裁判所法3条の「法律上の争訟」の範囲を超えるものであり、裁判所で審査することのできる範囲を逸脱するものである。
よって、この判決が「性的指向」について、「人生の初期又は出生前に決定され、自らの意思や精神医学的な療法によって変わるものではない」や「生来的な特性であり、環境によって変動するものではない」という特定の見解を採用した上で、その見解に基づく形で判断を行っていることは、裁判所法3条の「法律上の争訟」の解釈を誤ったものであり、「司法権の範囲」を超えた違法なものというべきである。
この論点については、上記「1 認定事実」の「⑴ 性的指向等に関する知見」の「ア 現在の知見」の部分でも解説している。
「LGBTの人口規模が実数という意味において近年に激増したとの知見が見当たらないこと」との記載がある。
しかし、アメリカでは「激増」しているようである。
【参考】アメリカの若者の30%以上が「自分はLGBTQ」と認識していることが判明 2021年10月26日
イギリスやアメリカでは社会のブームに乗る形で増大しているようである。
【参考】トランス問題をどのように考えるべきか ――最初の一歩―― 2022年11月28日 (P12/2023年9月20日更新版)
それにもかかわらず、「近年に激増したとの知見が見当たらない」と断じていることは、知見を知らないというだけである。
ただ、そもそも「LGBT」と称しているものそのものが個人の内心にのみ存在する心理的・精神的なものであるから、そこに明確な境界線となるものはないのであり、数字によって正確な統計を取ることができないものである。
これらはすべて憲法19条の「思想良心の自由」や20条1項の「信教の自由」などの「内心の自由」として捉えられるべきものである。
「現行の法律婚制度が制定された当初からLGBTの人口が相当数に上っていたと推認できるのであり、医学心理学的知見の変遷や社会意識の変革が生ずる前の時期もあったとはいえ、70年以上の長期にわたって少なくない人口の同性カップルに対し、上記保護の枠組みが与えられていなかったものである。」との記載がある。
「現行の法律婚制度」は、「性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いをするものではないし、「性愛」に基づいて制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもない。
そのため、「現行の法律婚制度」は「異性愛者」を称する者を対象としているという事実はないため、それに対する形で「LGBTの人口」を取り上げて何かを論じようとしている部分は関係性を認めることができず、誤りである(Tの人口を含めている部分はさらに疑問である)。
「医学心理学的知見の変遷や社会意識の変革」との部分であるが、「法律婚制度」は「精神的病理」の者でも利用することはできるし、「性愛」に対する「社会意識の変革」があってもそもそも「法律婚制度」と「性愛」は関係がないため、それによって「法律婚制度」には何らの影響も与えるものではない。
「70年以上の長期にわたって少なくない人口の同性カップルに対し、上記保護の枠組みが与えられていなかったものである。」との部分について検討する。
まず、「性愛」の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的とした制度を立法した場合には、憲法20条1項後段・3項、89条の「政教分離原則」に抵触して違憲となる。
また、法制度を利用する者の内心に干渉するものとなるから、憲法19条の「思想良心の自由」、20条1項前段の「信教の自由」に抵触して違憲となる。
他にも、「性愛」以外の思想、信条、信仰、感情を抱く者との間で憲法14条の「平等原則」に抵触して違憲となる。
よって、「性愛」の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的とした「保護の枠組み」を立法することが可能であるかのような前提で論じている部分が誤りである。
次に、「同性カップル」という「同性間の人的結合関係」を対象とした「枠組みが与えられていなかった」ことについては、「法律婚制度」が「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度であり、「同性間の人的結合関係」はその間で「生殖」を想定することができず、「生殖と子の養育」の趣旨を満たすものではないことから、制度の対象ではないことが理由である。
「法律婚制度」の対象でない組み合わせとしては、他にも「近親者との人的結合関係」、「三人以上の人的結合関係」、「婚姻適齢に満たない者との人的結合関係」を挙げることができる。
このように個々の同性カップルが被る不利益を見ても、重大な人格的利益を享受できないものである上、その総体としての規模も期間も相当なものであるから、現行の法律婚制度が採用されつつ、同性カップルに対する保護がなされない影響は深刻なものである。
【筆者】
「個々の同性カップルが被る不利益を見ても、」との部分について検討する。
憲法は「個人の尊厳」の原理に基づいており、自然人は「個人主義」の下に各々「自律的な個人」として生存していくことを予定していることから、何らの制度も利用していない状態で既に完全な状態であり、そこに「不利益」は存在しない。
よって、その完全な状態である個々人がここでいう「同性カップル」のように「二人一組」の人的結合関係を形成したとしても、そこに「不利益」が存在することにはならないのであり、これについて「同性カップルが被る不利益」のように「不利益」が存在するかのように述べている部分が誤りである。
「重大な人格的利益を享受できない」との部分について検討する。
この「人格的利益」の文言は、「夫婦同氏制大法廷判決」で示された「人格的利益」の文言を前提としているようである。
しかし、「夫婦同氏制大法廷判決」では、憲法24条2項の「婚姻及び家族」の枠組みの「要請」に従って立法された法律上の具体的な制度について「個人の尊厳」を満たすか否かが判断される中において「人格的利益」に触れているものであり、そもそも憲法24条2項の「婚姻及び家族」に当てはまらない場合については「個人の尊厳」が適用される前提にはないため、「人格的利益」が登場する余地もない。
そして、ここでいう「同性カップル」という「同性間の人的結合関係」については、「婚姻」ではないし、「親子」や「親子」の関係を基本とした「兄弟」「姉妹」などにも当たらないため、憲法24条2項の「婚姻及び家族」には含まれておらず、「個人の尊厳」の文言を適用する前提にない。
そのことから、これについて「夫婦同氏制大法廷判決」で示された「人格的利益」を取り上げて検討を行うことはできないのであり、「夫婦同氏制大法廷判決」で示された「人格的利益」を持ち出して論じている部分が誤りである。
これとは別に、もしこれが憲法13条の「個人の尊重」の観点から「人格的利益」を述べようとしているものであるとしても、これは国家から個人に対して具体的な侵害行為があった場合に、その侵害を排除するために用いられるものであり、この「人格的利益を享受できない」状態とは、国家から個人に対して具体的な侵害行為が存在することになるが、婚姻制度の対象でないとしても、単に優遇措置がないというにとどまり、国家から個人に対して具体的な侵害行為が存在するものではないため、「人格的利益を享受できない」状態にあるとはいえない。
よって、それを「人格的利益を享受できない」状態にあるかのように論じている部分も誤りである。
「その総体としての規模も期間も相当なものであるから、」との部分について検討する。
上記で述べたように、そもそも「婚姻していない者(独身者)」の状態が基準(スタンダード)であり、そこに「不利益」は存在しないし、憲法24条2項の「婚姻及び家族」の対象ではない場合に24条2項の「個人の尊厳」の文言は適用されないためそれを基にした「人格的利益」を検討する前提にないし、国家から個人に対して具体的な侵害行為があるわけでもないため13条の観点からの「人格的利益を享受できない」状態にあるわけでもないため、「その総体としての規模」と「期間」を検討する前提を欠いており、それが「相当なもの」であるか否かという評価も行うことはできない。
よって、このように述べていることは誤りである。
「現行の法律婚制度が採用されつつ、同性カップルに対する保護がなされない影響は深刻なものである。」との部分について検討する。
「法律婚制度」は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度であり、この制度の対象となる場合とならない場合があることは当然に予定されている。
また、憲法は「個人の尊厳」の原理に基づいており、自然人は「個人主義」の下に各々「自律的な個人」として生存していくことを予定していることから、「法律婚制度」を利用していない状態で既に完全な状態であるということができ、「法律婚制度」を利用していない者がいるとしてもそこに不利益があるということにはならない。
よって、ここでいう「同性カップル」という「同性間の人的結合関係」が「法律婚制度」の対象でないとしても、その個々人が「婚姻していない者(独身者)」であるということに違いはなく、何らの不利益はないし、その「影響」が「深刻」ということもない。
「法律婚制度」の対象でないものとして、「同性間の人的結合関係」の他にも、「近親者との人的結合関係」、「三人以上の人的結合関係」、「婚姻適齢に満たない者との人的結合関係」が存在するが、それらも同様に不利益とされる状態にあるわけではないし、「影響」が「深刻」というわけでもない。
よって、「影響は深刻なものである。」と述べている部分は誤りである。
この「カ」の内容は、全体として読み取りづらいので、下記のように整理する。
=======================================
「前記ウのとおり、憲法24条の適合性を審査するためには、さらに、本件諸規定により具体化された現行の法律婚制度が採用されたことによる影響を検討する必要がある。」
↓ ↓
「医学心理学的知見によれば、性的指向は、ほとんどの場合、人生の初期又は出生前に決定され、自らの意思や精神医学的な療法によって変わるものではないとされており(…)、性的指向が生来的な特性であり、環境によって変動するものではないと考えられる」
↓ ↓
「わが国におけるLGBTの人口規模は、必ずしも明らかではないが、平成27年及び平成28年に行われた調査では4.9%から7.6%であったというのであり(…)、少なく見ても百万人単位には達するものと推定できる。」
「LGBTの人口規模が実数という意味において近年に激増したとの知見が見当たらない」
「現行の法律婚制度が制定された当初からLGBTの人口が相当数に上っていたと推認できる」
↓ ↓
「両当事者の関係が国の制度により公証され、その関係を保護するのにふさわしい効果の付与を受けるための枠組みを」「利用することができるという価値は、単に法律によって付与された価値というにとどまらず、人の尊厳に由来する重要な人格的利益を基礎としているというべきである。」
↓ ↓
「そして、」「永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもって共同生活を営もうとする」「同性カップルは、異性カップルと比較して、」「かかる枠組みを」「利用することができないという格差が生まれている。」
↓ ↓
「確かに、同性カップルにおいても、原告らがそうであるように、結婚契約等公正証書を締結するなど、契約や遺言などの法律行為を行うことにより、一定程度、異性カップルに対するのと同等の効果を得ることが可能である。」
↓ ↓
「しかし、これらにより全てを賄えるものではないし、個々の法定効果の付与も大切ではあるが、それにとどまらず、同性カップルという関係が国の制度によって公証され、その関係を保護するのにふさわしい効果の付与を受けるための枠組みが与えられることに重大な価値があるのであり、これを享受できない不利益を解消することはできない。」
↓ ↓
「このことは、性的少数者を対象とするアンケートにおいて、結婚相当証明書申請をしたい理由として、「法律上、家族として認めてほしいのでその第一歩として」と回答した者が、全体の半数以上を占めていたこと(…)からも裏付けられる。」
↓ ↓
「同性カップルにおいて、婚姻に伴う個々の法的効果が付与されないのみならず、その関係が国の制度によって公証されず、その関係を保護するのにふさわしい効果の付与を受けるための枠組みすら与えられない不利益は甚大なものである。」
↓ ↓
「医学心理学的知見の変遷や社会意識の変革が生ずる前の時期もあったとはいえ、70年以上の長期にわたって少なくない人口の同性カップルに対し、上記保護の枠組みが与えられていなかったものである。」
↓ ↓
「このように個々の同性カップルが被る不利益を見ても、重大な人格的利益を享受できないものである上、その総体としての規模も期間も相当なものであるから、現行の法律婚制度が採用されつつ、同性カップルに対する保護がなされない影響は深刻なものである。」
=======================================
しかし、このように整理したとしても、「カ」の内容が誤っていることは変わらない。
一つ目に、「憲法24条の適合性を審査するため」には、憲法24条の文言から意味を明らかにすることが必要であり、憲法よりも下位の法令を基にその上位法である憲法の意味を論じることはできない。
二つ目に、婚姻制度は「性愛」と関わるものではないことから、「性的指向」と称するものの性質を述べる必要そのものがない。
三つ目に、法制度は内心に対して中立的な内容でなければならず、「LGBTの人口規模」のような内心に関する調査を持ち出していることは適切ではない。
四つ目に、「人の尊厳」は「人間」と「人間以外(物や動物)」の対比の中で用いられる概念であるし、これを理由として具体的な制度の創設を国家に対して求めることができるというものではない。
五つ目に、「カップル」のような「二人一組」については「権利能力」を有しておらず法主体としての地位を認められていないことから、法律論として比較することはできない。
六つ目に、憲法は「個人の尊厳」の原理に基づいており、自然人は「個人主義」の下に各々「自律的な個人」として生存していくことを予定していることから、「婚姻していない者(独身者)」の状態で既に完全であり、何らの「不利益」も存在していない。
七つ目に、「婚姻している者(既婚者)」が婚姻制度の立法目的を達成するための手段として不必要に過大な優遇措置を得るものとなっている場合には、「婚姻していない者(独身者)」との間の比較において憲法14条1項の「平等原則」に抵触して違憲となり、その不必要に過大な優遇措置に関する規定が個別に失効することによって格差が是正されることになるのであり、「婚姻している者(既婚者)」が基準(スタンダード)となるかのように考えていることは妥当でない。
八つ目に、婚姻制度は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度であり、その目的を達成するための手段として整合的な枠組みを定めているものであることから、婚姻制度を利用することができる場合とできない場合があることはもともと予定されていることである。
キ 前記ウのとおり、他方で、婚姻及び家族に関する事項は、国の伝統や国民感情を含めた社会状況における種々の要因を踏まえつつ、それぞれの時代における夫婦や親子関係についての全体の規律を見据えた総合的な判断によって定められるべきものであることは確かである。
【筆者】
この文は、おおよそ「ウ」で示されている「夫婦同氏制大法廷判決」の文と同じである。
(灰色で潰した部分は、上記の記述と同様の文言が使われているところである。)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3(1) 他方で,婚姻及び家族に関する事項は,国の伝統や国民感情を含めた社会状況における種々の要因を踏まえつつ,それぞれの時代における夫婦や親子関係についての全体の規律を見据えた総合的な判断によって定められるべきものである。特に,憲法上直接保障された権利とまではいえない人格的利益や実質的平等は,その内容として多様なものが考えられ,それらの実現の在り方は,その時々における社会的条件,国民生活の状況,家族の在り方等との関係において決められるべきものである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
しかし、この「夫婦同氏制大法廷判決」を取り上げて論じるようとしていること自体が誤りである。
まず、この名古屋地裁判決の「⑶ 憲法24条2項に違反するかについて」の項目で問われているのは、憲法24条2項の「家族」が、ここでいう「同性間の人的結合関係」を対象とする制度を立法することを「要請」しているか否かである。
「要請」しているのであればその制度がないことは違憲であり、「要請」していないのであればその制度がないことは合憲であるというものである。
ここでいう「同性間の人的結合関係」については、「親子」や、「親子」の関係を基本とした「兄弟」「姉妹」などでもないため「家族」には含まれない。
そのため、憲法24条2項の「家族」は、ここでいう「同性間の人的結合関係」を対象とした制度を立法することを「要請」するものではない。
よって、その制度がないことについて憲法24条2項に違反することはない。
それに対して、この「夫婦同氏制大法廷判決」で問われている内容は、憲法24条2項の「婚姻及び家族」の枠組みの「要請」に従って立法された法律上の具体的な制度の存在を前提として、その具体的な制度の内容が「個人の尊厳」と「両性の本質的平等」を満たすか否かである。
憲法24条2項の「婚姻及び家族」の枠組みの「要請」に従って立法された法律上の具体的な制度の内容が、「個人の尊厳」と「両性の本質的平等」を満たさない場合には違憲となり、満たす場合には合憲となる。
これは、「婚姻及び家族」に当てはまる場合について審査するものであり、そもそも「婚姻及び家族」に当てはまらない場合については審査の対象としていないものである。
このように、「夫婦同氏制大法廷判決」とこの名古屋地裁判決とでは事案が異なっている。
そのため、この名古屋地裁判決で問われている事案に対して、「婚姻及び家族」に含まれる場合について審査するものとして示された「夫婦同氏制大法廷判決」の文面を用いて論じることが可能であるかのような前提で、「夫婦同氏制大法廷判決」の文面を持ち出していること自体が誤りである。
また、この段落の「夫婦同氏制大法廷判決」の文についても、これは憲法24条2項の「婚姻及び家族」の枠組みの「要請」に従って立法された法律上の具体的な制度について、その内容が「国の伝統や国民感情を含めた社会状況における種々の要因を踏まえつつ,それぞれの時代における夫婦や親子関係についての全体の規律を見据えた総合的な判断によって定められるべきものである。」ことを述べているものである。
これは憲法24条2項の「婚姻及び家族」の枠組みが「要請」している規範の意味(内容)そのものを説明しているものというわけではない。
◇ 憲法24条2項の「婚姻及び家族」 〔← 名古屋地裁判決で問われているもの)
↓ ↓ (要請)
◇ 法律上の「婚姻及び家族」の制度
(国の伝統や国民感情を含めた社会状況における種々の要因を踏まえつつ,それぞれの時代における夫婦や親子関係についての全体の規律を見据えた総合的な判断によって定められるべきものである。) 〔← 夫婦同氏制大法廷判決で問われている対象/『個人の尊厳』と『両性の本質的平等』を満たすか否か〕
そのため、憲法24条2項の「婚姻及び家族」の枠組みが「要請」している規範の内容そのものを明らかにすることが問われている名古屋地裁判決の手続きにおいて、憲法24条の「婚姻及び家族」の枠組みの「要請」に従って立法された法律上の具体的な制度についての判断の余地の話をしている「夫婦同氏制大法廷判決」の文を持ち出して論じようとすることは、下位法である法律上の具体的な制度についての判断の余地の話によって上位法である憲法の規範の意味を根拠づけようとするものであるから、法秩序の階層構造を損なわせるものであり、解釈の手続きとして誤っている。(下剋上解釈論)
しかしながら、同性カップルが国の制度によって公証されたとしても、国民が被る具体的な不利益は想定し難い。現に、地方自治体においては、登録パートナーシップ制度が創設された以降、これを導入する地方自治体が増加の一途を辿っているが(認定事実⑸ウ )、これにより弊害が生じたという証拠はなく、むしろ、国民の間に同性カップルを承認しようとする機運が高まっている証左とも捉えられる。そして、婚姻制度が男女の結合関係を中核としてその間に生まれた子の保護・育成の機能を担うという伝統的な家族観を重視する国民が一定数存在しており、その立場も尊重されるべきではあるものの、同性カップルを国の制度として公証したとしても、そのような伝統的家族観を直ちに否定することにはならず、共存する道を探ることはできるはずである。
【筆者】
「同性カップルが国の制度によって公証されたとしても、国民が被る具体的な不利益は想定し難い。」との記載がある。
「同性カップル」という「二人一組」を取り上げている部分であるが、人的結合関係の中には「トリオ」である「三人一組」や、「四人一組」、それ以上の組み合わせも存在するのであり、「二人一組」のみを取り上げている部分は、なぜ「二人一組」であるのかその根拠を説明しないまま論じる「カップル信仰論」に陥っているものであり、妥当でない。
ここでいう「同性カップル」という「同性間の人的結合関係」が「国の制度によって公証されたとしても、国民が被る具体的な不利益は想定し難い。」と述べている部分について検討する。
まず、憲法24条の「婚姻」の文言は「生殖と子の養育」に関わる制度を一元的に集約して規律する趣旨を有していることから、「生殖と子の養育」に関わる制度を憲法24条の「婚姻」を離れて立法することはできない。
もし「生殖と子の養育」に関わる制度を憲法24条の「婚姻」を離れて立法しようとした場合には、憲法24条の「婚姻」に抵触して違憲となる。
そのため、「同性間の人的結合関係」を対象とする制度を設けようとしても、それが「生殖と子の養育」に関わるものとなっている場合や、影響を与えるものとなっている場合には、憲法24条の「婚姻」に抵触して違憲となる。
よって、「同性間の人的結合関係」について「国の制度によって公証」することが可能であるかのように述べているが、憲法24条の「婚姻」との関係を十分に理解しているとはいえず、妥当でない。
次に、「婚姻制度を利用している者(既婚者)」と「婚姻制度を利用していない者(独身者)」との間の差異を検討する。
婚姻制度については、一般的・抽象的にその間で自然生殖を想定することができる「男性」と「女性」の組み合わせに対して「貞操義務」を設けるなど一定の形式で法的に結び付けるものとなっている。
これは、その間で自然生殖が行われた場合に、遺伝上の父親を特定することが可能となるという仕組みに着目したものであることから、「男性」と「女性」を組み合わせた「二人一組」てあることに必然性を見出すことができる。
また、父親を特定することによって、「近親交配」を回避することが可能となるし、「男女二人一組」の形に限定している場合においては、未婚の男女の数の不均衡を防止することが可能となるため、「生殖機会の公平」にも寄与することになる。
「婚姻適齢」を満たした者の間での「生殖と子の養育」であれば、「母体の保護」の観点や、「子育ての能力」の観点からも、一般には支障がないものと考えられる。
このような関係性を形成した者に対して一定の優遇措置を講じることは、その社会の中で「生殖」に関わって生じる不都合を解消するという目的に資することから、その「婚姻している者(既婚者)」は、「婚姻していない者(独身者)」との間で優遇措置が与えられることが正当化されることになる。
これに対して、「同性間の人的結合関係」については、その間で「生殖」を想定することができず、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する形で制度を設けるという目的からは導かれないものである。
そのため、「同性間の人的結合関係」に対して、何らかの制度を設けて優遇措置を講じることは、何らの人的結合関係も形成していない者との間で、合理的な理由を説明することのできない利益の差異を生じさせるものとなる。
よって、「同性間の人的結合関係」に対して、何らかの制度を設けて優遇措置を講じることは、その制度を利用しておらず、何らの人的結合関係も形成していない者との間で、得られる利益の内容に合理的な理由のない差異を生じさせるものとなることから、憲法14条の「平等原則」に抵触して違憲となる。
このように、憲法14条の「平等原則」に違反するということは国民の間に不平等が存在するということであるから、ここで「国民が被る具体的な不利益は想定し難い。」のように問題がないかのように述べている部分は、「想定」を十分に行うことができていないものであり、誤った理解であるということができる。
「現に、地方自治体においては、登録パートナーシップ制度が創設された以降、これを導入する地方自治体が増加の一途を辿っているが(…)、これにより弊害が生じたという証拠はなく、むしろ、国民の間に同性カップルを承認しようとする機運が高まっている証左とも捉えられる。」(カッコ内省略)との記載がある。
まず、「現に、地方自治体においては、登録パートナーシップ制度が創設された以降、これを導入する地方自治体が増加の一途を辿っているが」との部分であるが、地方自治体の「登録パートナーシップ制度」は、憲法上の規定に抵触して違憲、法律により定められている婚姻制度に抵触して違法となる部分があるため、このような制度を取り上げて論じようとしていること自体が妥当でない。
また、法の論理は導入した地方自治体の数によって左右されるものではないため、「これを導入する地方自治体が増加の一途を辿っている」のように「増加」していることを述べたとしても、それはその制度が違憲・違法でないことを示すものではない。
次に、「これにより弊害が生じたという証拠はなく、」との部分であるが、「登録パートナーシップ制度」の内容は違憲・違法となっていることから、「弊害」は生じている状態である。
また、「証拠はなく、」との部分であるが、この訴訟の中で具体的な「証拠」が提出されていないとしても、それはその制度に「弊害」がないことを意味するものではないし、その内容が違憲・違法でないことを証明すものでもない。
ここでいう「弊害」にあたるものについて、詳しくは当サイト「パートナーシップ制度」で解説している。
三つ目に、「⑶ 憲法24条2項に違反するかについて」の項目で問われているのは、憲法24条2項の「家族」が、「親子」や「親子」の関係を基本とした「兄弟」「姉妹」などに含まれない「同性間の人的結合関係」を対象とする制度を立法することを「要請」しているか否かであり、これは憲法上の文言から意味を明らかにすることが必要であり、その意味を憲法よりも下位の法形式で定められる制度を根拠とすることはできない。
そのことから、憲法24条2項の規範の意味を明らかにする過程において、憲法よりも下位の法形式で定められる地方自治体の「登録パートナーシップ制度」を取り上げて根拠としようとしていることは、法秩序の階層構造を理解しないものであり、解釈の過程として誤っている。
「国民の間に同性カップルを承認しようとする機運が高まっている証左とも捉えられる。」との部分について検討する。
ここでは「同性カップルを承認しようとする機運」と書かれていることから、現在、「同性カップル」という「同性間の人的結合関係」については「承認」されていないことを前提として考えていることになる。
しかし、「同性間」で人的結合関係を形成すること自体は憲法21条の「結社の自由」によって保障されているのであり、既に「承認」されているものである。
また、「婚姻制度を利用していない者」についても「婚姻していない人(独身者)」として「承認」されているのであるから、それが「承認」されていないということはない。
よって、「承認」されていないことを前提に「承認しようとする機運」のように論じている部分が誤りである。
「婚姻制度が男女の結合関係を中核としてその間に生まれた子の保護・育成の機能を担うという伝統的な家族観を重視する国民が一定数存在しており、その立場も尊重されるべきではあるものの、同性カップルを国の制度として公証したとしても、そのような伝統的家族観を直ちに否定することにはならず、共存する道を探ることはできるはずである。」との記載がある。
まず、「婚姻制度が男女の結合関係を中核としてその間に生まれた子の保護・育成の機能を担うという伝統的な家族観を重視する国民が一定数存在しており、その立場も尊重されるべきではあるものの、」との部分について検討する。
この文は、「国民」の中の「伝統的な家族観」と称するものとそれ以外の家族観が対立することによって、婚姻制度の内容をどのようにでも変えることができるかのような前提で述べるものとなっている。
しかし、婚姻制度は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成するための手段として設けられている枠組みであり、この目的を離れて「婚姻」を観念することができないことから、この立法目的とその立法目的を達成するための手段としての枠組みを超えて、「国民」の中の「伝統的な家族観」と称するものとそれ以外の家族観が対立することによって、婚姻制度の内容をどのようにでも変えることができるというものではない。
よって、「伝統的な家族観を重視する国民が一定数存在しており、」のように、「国民」の中の「家族観」と称するものの数の増減を勘案しようとしている部分が誤りである。
また、「男女の結合関係を中核としてその間に生まれた子の保護・育成の機能を担う」という部分は、婚姻制度が「生殖と子の養育」の趣旨を有していることに対応するものであり、その背景には「婚姻」という概念そのものが有している立法目的とその立法目的を達成するための手段となる枠組みが存在する。
そのため、これを「伝統的な家族観」と呼ぶかどうかは別として、この「男女の結合関係を中核としてその間に生まれた子の保護・育成の機能を担う」という部分は、それ以外の家族観と対立することによって「婚姻」の中から除外することのできるという性質のものではないため、「重視する国民」の数の増減によってこれを損なわせることができることを前提に論じている部分が誤りである。
「同性カップルを国の制度として公証したとしても、そのような伝統的家族観を直ちに否定することにはならず、共存する道を探ることはできるはずである。」との部分について検討する。
まず、「伝統的家族観」の部分であるが、上記で説明したようにこれは「国民」の中の数の増減によって変化するものであることを前提として考えることは誤りである。
次に、この「伝統的家族観」を「婚姻制度が男女の結合関係を中核としてその間に生まれた子の保護・育成の機能を担う」を意味するものとして考える。
つまり、この文を「同性カップルを国の制度として公証したとしても、」「婚姻制度が男女の結合関係を中核としてその間に生まれた子の保護・育成の機能を担う」こと「を直ちに否定することにはならず、」と述べているものとして検討する。
しかし、婚姻制度は「男女の結合関係を中核としてその間に生まれた子の保護・育成の機能を担う」制度を設け、それ以外に対しては制度を設けないという差異を設けることによって、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」という目的を達成することを予定しているのであり、それ以外の関係に対して制度を設けることは、この目的の達成を阻害する影響を与えることになる。
そのため、ここでいう「同性カップル」という「同性間の人的結合関係」に対して「国の制度によって公証」したとしても、「直ちに否定することにはならず、」のように、婚姻制度の政策効果を阻害しないかのように考えていることは誤りである。
また、憲法24条の「婚姻」の文言は「生殖と子の養育」に関わる制度を一元的に集約して規律する趣旨を有しており、「生殖と子の養育」に関わる制度を憲法24条の「婚姻」を離れて立法することはできない。
これは、もし「生殖と子の養育」に関わる制度を憲法24条の「婚姻」を離れて立法することが可能となると、憲法24条が「両性の合意のみ」や「個人の尊厳」「両性の本質的平等」を満たすように求めて立法裁量の限界を画しているにもかかわらず、この制約を回避する形で制度を設けることが可能となってしまい、実質的に憲法24条の条文が無意味なものとなってしまうからである。
そのため、ここでいう「同性カップル」という「同性間の人的結合関係」について「国の制度として公証」しようとした場合、それは「生殖と子の養育」に関わる制度や影響を与える制度となることが考えられ、憲法24条の「婚姻」の文言に抵触して違憲となる。
よって、そのような「同性間の人的結合関係」を「国の制度として公証」することが可能であるかのように考えていることも誤りである。
「共存する道を探ることはできるはずである。」との部分について検討する。
婚姻制度(男女二人一組)はそれ以外の関係との間に差異を設けることによって政策目的を達成することを目指す制度であることから、それ以外の関係に対して制度を設けることは婚姻制度の政策効果を阻害する影響を与えることになる。
そのため、婚姻制度が存在する中でそれ以外の関係に対して制度を設けることはできず、「共存」することはできない。
また、憲法24条の「婚姻」の文言は「生殖と子の養育」に関わる制度を一元的に集約して規律していることから、「生殖と子の養育」に関わる制度や影響を与える制度を憲法24条の「婚姻」を離れて立法することはできない。
もし立法しようとした場合には、憲法24条の「婚姻」に抵触して違憲となるため、「共存」することはできない。
よって、「共存する道を探ることはできるはずである。」と述べている部分は誤りである。
また、現行の法律婚制度に付与されている効果は多彩なものがあるが、同居、協力扶助義務や関係解消時に離婚手続を要することなど、親密な関係に基づく生活共同体に付与されるべき本質的な効果においても、基本的に両当事者間で完結するものも少なくなく、このような法的効果を同性カップルに付与した場合の具体的な弊害も観念しにくいものである。
【筆者】
「現行の法律婚制度に付与されている効果は多彩なものがあるが、」との部分であるが、「法律婚制度」は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために法的効果を設定しているものである。
「同居、協力扶助義務や関係解消時に離婚手続を要することなど、親密な関係に基づく生活共同体に付与されるべき本質的な効果においても、」との部分であるが、「法律婚制度」の内容に「同居、協力扶助義務や関係解消時に離婚手続を要することなど」の効果が設けられていることは、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために設けられているものであり、この目的を離れて単に「親密な関係に基づく生活共同体」であることを理由として設けられているものではない。
よって「法律婚制度」の法的効果の一部を抜き出して、勝手に「親密な関係に基づく生活共同体に付与されるべき本質的な効果」などと、「親密な関係に基づく生活共同体」であることを理由としてそれらの法的効果を得られると考えている部分が誤りである。
「親密な関係に基づく生活共同体」は、「国家からの自由」という「自由権」として憲法21条1項の「結社の自由」として保障されることになる。
「基本的に両当事者間で完結するものも少なくなく、このような法的効果を同性カップルに付与した場合の具体的な弊害も観念しにくいものである。」との部分について検討する。
「法律婚制度」というものは、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を離れて観念することはできないのであり、「両当事者間で完結する」のようにその制度の一部の効果を利用するだけの場合があるということを抜き出して、その部分だけを見て「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために「一人の男性」と「一人の女性」を枠づけることによって立法目的の実現を目指すという仕組みそのものを変えることができるとする理由にはならない。
よって、「男女二人一組」の「法律婚制度」の中から「両当事者間で完結する」という部分だけを取り出して、ここでいう「同性カップル」という「同性間の人的結合関係」にそれらの「法的効果」を「付与」することが可能であるかのように述べていることは誤りである。
「具体的な弊害も観念しにくいものである。」との部分であるが、「法律婚制度」は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するための制度であり、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす関係に対してのみ法的効果や一定の優遇措置を与え、それを満たさない場合には法的効果や優遇措置を与えないという差異を設けることによって立法目的の実現を目指すものであることから、その要素を満たさない人的結合関係に対して「法的効果」を「付与」することは立法目的の実現を阻害する影響を与えるものとなるため、「弊害」を観念することができる。
よって、「具体的な弊害」を「観念しにくい」のように、「具体的な弊害」が見られないかのように述べている部分は誤りとなる。
婚姻制度が「男女二人一組」を対象としていることは、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成するための手段として整合的であることから、「婚姻している者(既婚者)」が法的効果や一定の優遇措置が得られることは「婚姻していない者(独身者)」との間で正当化することができる。
しかし、そのような目的の実現からは導かれない人的結合関係に対して法的効果や優遇措置を与えることは、その制度を利用していない者の間で正当化することのできない差異を生じさせるものとなる。
そのため、そのような人的結合関係に対して法的効果や優遇措置を与えることは、合理的な理由を説明することのできない差異を生じさせるものとして憲法14条1項の「平等原則」に抵触して違憲となる。
よって、「具体的な弊害も観念しにくい」と述べていることは、この点についても理解しておらず、妥当でない。
その他、この「⑶ 憲法24条2項に違反するかについて」の項目で問われているのは、憲法24条2項の「家族」が、ここでいう「同性カップル」という「同性間の人的結合関係」を対象とした制度を立法することを「要請」しているか否かである。
これは憲法24条2項の文言から意味を明らかにしなければならないのであり、憲法よりも下位の法令によって「このような法的効果を同性カップルに付与した場合」に「具体的な弊害も観念しにくい」かどうかによって、憲法24条2項の規範の意味が明らかになるというものではない。
そのため、ここで下位の法令における立法政策の「弊害」を検討した上で、その上位法である憲法の条文の意味を明らかにしようとしていることは、法秩序の階層性を理解しないものであり、誤りである。
そして、契約や遺言等の法律行為によって、婚姻によって付与される効果を一定程度実現できるということは、そのような効果を同性カップルに付与することに法律は弊害を認めていないとも理解できるものである。
【筆者】
「契約や遺言等の法律行為によって、婚姻によって付与される効果を一定程度実現できる」との部分について検討する。
この文は、もともと「婚姻」という効果が存在することを前提に、その「婚姻によって付与される効果」を「契約や遺言等の法律行為」によって実現することが可能であるという発想に基づくものとなっている。
しかし、これは順序が逆である。
本来は、個々人が「契約や遺言等の法律行為」をしながら生活していくことが基準(スタンダード)である中で、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという立法目的を達成するための手段として「遺言等」のいくつかの法的効果を組み合わせて法制度のパッケージとしたものが「婚姻」である。
◇ この判決の発想
「婚姻」
↓ (婚姻によって付与される効果を一定程度実現できる)
「契約や遺言等の法律行為」
◇ 本来の考え方
「契約や遺言等の法律行為」
↓ (法制度のパッケージ)
「婚姻」
そのため、「契約や遺言等の法律行為」をしながら生活していくことが基準(スタンダード)であり、「婚姻によって付与される効果」を「婚姻制度を利用していない者(独身者)」に対しても与えなければならないという発想は基準点を見誤ったものである。
「そのような効果を同性カップルに付与することに法律は弊害を認めていないとも理解できるものである。」との部分について検討する。
ここでいう「同性カップル」という「同性間の人的結合関係」に対して「契約や遺言等の法律行為」の「効果」を与えることに「法律は弊害を認めていないとも理解できる」としているが、たとえ「契約」や「遺言」であるとしても、民法90条の「公序良俗」に反する場合は無効となるし、法律上の他の強行法規に抵触する場合には違法となるのであり、「同性間の人的結合関係」に対して「契約」や「遺言」などによって「婚姻によって付与される効果」と同様の効果を与えることができるとは限らない。
「契約」の内容によっては、婚姻制度の政策効果を阻害することになる場合が考えられることから、その場合には、民法90条の「公序良俗」や民法上の強行規定に抵触して無効となる。
そのため、「契約や遺言等の法律行為」ができる場合があるとしても、その内容が無制限に許されるというものではないのであり、それをもって「法律は弊害を認めていないとも理解できる」のように「弊害」が無いかのように論じている部分が誤りである。
また、憲法24条の「婚姻」の文言は「生殖と子の養育」に関わる制度を一元的に集約して規律する趣旨を有しており、その「同性間の人的結合関係」が「生殖と子の養育」に関わる制度となっている場合や「生殖と子の養育」に影響を与える制度となっている場合には、憲法24条の「婚姻」の文言に抵触して違憲となる。
よって、「同性間の人的結合関係」に対して「婚姻によって付与される効果」を与えることができることを前提に論じている部分も誤りである。
その他、この「⑶ 憲法24条2項に違反するかについて」の項目で問われているのは、憲法24条2項の「家族」が、ここでいう「同性間の人的結合関係」を対象とした制度を立法することを「要請」しているか否かである。
これは憲法24条2項の文言そのものの意味を明らかにすることによって結論を導き出すことが必要であり、「法律」という憲法よりも下位の法令が「弊害を認めていない」か否かという検討することによって、その上位法である憲法24条2項の規範の意味が明らかになるというものではない。
そのため、ここで下位の法令による「法律」が「弊害」を認めているか否かを根拠として、その上位法である憲法24条2項の条文の意味を明らかにしようとしていることは、法秩序の階層構造を損なわせるものであり、解釈の手続きとして誤っている。
確かに、婚姻に付与されるべき効果の中には、第三者の権利義務関係に影響を及ぼす事項のほか、様々な社会政策的判断により付与された権利義務に関わる事項もあり、同性カップルに付与する効果如何によっては、直接第三者に影響を及ぼし、あるいは、既存の異性婚に変容をもたらす可能性があるものもあり、これを付与するか否かについては、民主政の過程において慎重に審議が尽くされるべきものと考えられるし、諸外国の立法経緯や立法内容が一様でないことは先に見たとおりである。
【筆者】
この文は、下記のようにまとめることができる。
「婚姻に付与されるべき効果」
◇ 「第三者の権利義務関係に影響を及ぼす事項」
◇ 「様々な社会政策的判断により付与された権利義務に関わる事項」
↓ ↓
「同性カップルに付与する効果」
→ 「直接第三者に影響を及ぼし」
→ 「既存の異性婚に変容をもたらす可能性があるもの」
「これを付与するか否かについては、民主政の過程において慎重に審議が尽くされるべきものと考えられる」
(「諸外国の立法経緯や立法内容が一様でない」)
この文で四回登場する「付与」の部分を中心に検討する。
◇ 「婚姻に付与されるべき効果」
◇ 「様々な社会政策的判断により付与された権利義務に関わる事項」
◇ 「同性カップルに付与する効果」
◇ 「これを付与するか否か」
まず、「婚姻に付与されるべき効果」との部分であるが、「婚姻」に対して「付与されるべき効果」なのであれば、それは「婚姻」の立法目的を達成するための手段として整合的な形で法的な効果を設定しているものであり、そのような立法目的を達成するための手段として整合的でない人的結合関係に対しては「付与」しないことが前提である。
そのため、「婚姻に付与されるべき効果」であるにもかかわらず、その後、「婚姻」の対象とならないここでいう「同性カップル」という「同性間の人的結合関係」に対して「付与」するか否かを前提に論じている部分が妥当でない。
次に、「様々な社会政策的判断により付与された権利義務に関わる事項」の部分であるが、これは「婚姻に付与されるべき効果」の内容をとして挙げられているが、「付与されるべき」から「付与された」のように語句が変わっているのは疑問である。
これは、「べき」という義務づける意味のリストの中に「された」と受け身の過去形を入れるものとなっているため、一貫性がなく、どのような方向性をもって文脈を理解すればよいのか分からず、読者を混乱させる原因となっている。
三つ目に、「同性カップルに付与する効果」との部分であるが、「婚姻に付与されるべき効果」なのであるから、「婚姻」に含まれない「同性カップル」という「同性間の人的結合関係」に対しては「付与」しないものであり、「付与する効果」のように「付与」することを前提としている部分が妥当でない。
四つ目に、「これを付与するか否か」の部分であるが、「婚姻に付与されるべき効果」は「婚姻」の立法目的を達成するための手段として整合的な形で法的な効果を設定しているものであり、そのような目的を達成するための手段として整合的でない人的結合関係に対しては「付与」しないことが前提であるから、「これを付与するか否か」という問いの答えは「付与しない」ことになる。
この文でも「同性カップル」という「同性間の人的結合関係」に対して「効果」を設定することは、「直接第三者に影響を及ぼ」すことや「既存の異性婚に変容をもたらす可能性がある」ことを想定するものとなっている。
その通り、婚姻制度が存在する中では、婚姻制度の立法目的の実現を阻害する影響を与える制度を別に立法することはできず、それらを併存させることはできない。
また、憲法24条の「婚姻」の文言は、「生殖と子の養育」に関わる制度を一元的に集約して規律する趣旨を有しており、「同性間の人的結合関係」に対して制度を立法しようとした場合には「生殖と子の養育」に関わる制度や影響を与える制度となることが考えられ、憲法24条の「婚姻」の文言に抵触して違憲となる。
他にも、婚姻制度の場合は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的の実現に資するものとなっていることから、「婚姻している者(既婚者)」が「婚姻していない者(独身者)」との間の比較において法的効果や一定の優遇措置を得られることを正当化することができるが、そのような目的との関係で整合的でない「同性間の人的結合関係」に対して法的効果や優遇措置を与えることは、制度を利用しない者との間で合理的な理由を説明することのできない差異を生じさせることになることから、憲法14条1項の「平等原則」に抵触して違憲となる。
よって、「同性間の人的結合関係」に対して制度を設けることができることを前提に論じている部分が妥当でない。
「民主政の過程において慎重に審議が尽くされるべきものと考えられるし、」との部分についても、先に述べた通り、憲法24条の文言に抵触して違憲となる場合や、憲法14条1項の「平等原則」に抵触して違憲となる場合があり、これについては立法裁量の余地がないため、立法府を通す形で「民主制の過程」の「審議」を行うことができることを前提に論じている部分が妥当でない。
「諸外国の立法経緯や立法内容が一様でない」との部分についても、「諸外国」と日本法は異なっており、日本法には憲法24条の「婚姻」や憲法14条1項の「平等原則」による制約があるため、「諸外国」で「立法」されているとしても、同じように「立法」することができるというものではない。
その他、この「⑶ 憲法24条2項に違反するかについて」の項目で問われているのは、憲法24条2項の「家族」が、ここでいう「同性間の人的結合関係」を対象とした制度を立法することを「要請」しているか否かである。
これは憲法24条2項の文言そのものの意味を明らかにすることによって結論を導き出すことが必要であり、「法律」という下位の法令による立法政策として「民主政の過程において慎重に審議が尽くされるべきもの」であるとか、「直接第三者に影響を及ぼし、あるいは、既存の異性婚に変容をもたらす可能性がある」か否かを検討することによって、その上位法である憲法24条2項の規範の意味が明らかになるというものではない。
そのため、ここで「法律」という下位の法令による立法政策に関する事柄を根拠として、その上位法である憲法24条2項の条文の意味を明らかにしようとしていることは、法秩序の階層構造を損なわせるものであり、解釈の手続きとして誤っている。
しかし、そのような性質を有する効果が含まれているとしても、公証された関係に、その関係を保護するのにふさわしい効果を付与するための枠組み自体が与えられるべきことを否定すべきことにはならない。
【筆者】
「そのような性質を有する効果」の部分であるが、これは一段落前の「婚姻に付与されるべき効果」と称するものの中の「直接第三者に影響を及ぼし、あるいは、既存の異性婚に変容をもたらす可能性があるもの」と述べているものを指していると考えられる。
しかし、このような法律上の婚姻制度の内容となっている効果を検討をしていること自体が誤っている。
これは、下記が理由である。
この「⑶ 憲法24条2項に違反するかについて」の項目で問われているのは、憲法24条2項の「家族」が、ここでいう「同性間の人的結合関係」を対象とした制度を立法することを「要請」しているか否かである。
「要請」しているのであればその制度がないことは違憲であり、「要請」していないのであればその制度がないことは合憲というものである。
これは憲法24条2項の文言そのものの意味を明らかにすることによって結論を導き出すことが必要であり、「法律」という下位の法令の効果によって左右されるものではない。
そのため、ここで「法律」という下位の法令の効果について、「否定すべき」ものか否かを検討し、それを根拠として、その上位法である憲法24条2項の条文の意味を明らかにしようとしていることは、法秩序の階層構造を理解しないものであり、解釈の方法として誤っている。
そうすると、同性カップルに対し、その関係を国の制度によって公証し、その関係を保護するのにふさわしい効果を付与するための枠組み自体を存在させないようにするということと、存在を認めた上で、様々な立場や他の諸利益と調整するなどしながら、いかなる効果を付与すべきか検討し決定していくということとでは、自ずと立法裁量の広狭に差が生じるものであると解される。
【筆者】
この文は下記のようにまとめることができる。
「立法裁量の広狭に差が生じるものである」
◇ 「同性カップルに対し、その関係を国の制度によって公証し、その関係を保護するのにふさわしい効果を付与するための枠組み自体を存在させないようにするということ」
◇ 「同性カップルに対し、その関係を国の制度によって公証し、その関係を保護するのにふさわしい効果を付与するための枠組み自体」の「存在を認めた上で、様々な立場や他の諸利益と調整するなどしながら、いかなる効果を付与すべきか検討し決定していくということ」
しかし、これについて「立法裁量の広狭に差が生じる」のように「立法裁量の広狭」の問題と考えている部分が誤りである。
この「⑶ 憲法24条2項に違反するかについて」の項目で問われているのは、憲法24条2項の「家族」が、ここでいう「同性カップル」という「同性間の人的結合関係」を対象とした制度を立法することを「要請」しているか否かである。
「要請」しているのであればその制度がないことは違憲であり、「要請」していないのであればその制度がないことは合憲というものである。
これは、経済的自由権を規制した法律については、事後的に国民が民主制の過程を通してその規制を撤廃することが容易であるため、裁判所は規制の内容を尊重して緩やかな審査とすることが許されるが、これに対して、精神的自由権を規制した法律については、一度損なわれた場合に国民が民主制の過程を通してその規制を撤廃することが困難となることから、裁判所は積極的にその規制を取り除く形で審査を行うことが求められる、という「二重の基準論」のような形で事例ごとの「立法裁量の広狭」の比較が問われている事柄とは異なる。
そのため、「立法裁量の広狭」という話を持ち出していることは、この名古屋地裁判決の中で論点となっていないにもかかわらず、何らかの学問上で事例ごとの比較を行う際に登場した言い回しや、何か別の判例の言い回しのみを用いて違憲と結論付けようとするための材料として使われているものである可能性が高く、この名古屋地裁判決の事案には当てはまらないものであり、判断の過程を正当化することのできる内容であるとはいえない。
よって、「立法裁量の広狭に差が生じる」のように述べていることは、誤っている。
ク 以上によれば、本件諸規定が、異性間に対してのみ現行の法律婚制度を設け、その範囲を限定することで、同性間に対しては、国の制度として公証することもなく、その関係を保護するのにふさわしい効果を付与するための枠組み自体を与えない状態としているが、婚姻制度の趣旨に対する国民の意識の変化に伴い、同性カップルが法律婚制度に付与されている重大な人格的利益を享受することから一切排除されていることに疑問が生じており、累計的には膨大な数になる同性カップルが現在に至るまで長期間にわたってこうした重大な人格的利益の享受を妨げられているにもかかわらず、このような全面的に否定する状態を正当化するだけの具体的な反対利益が十分に観念し難いことからすると、同性カップルの関係を保護するのにふさわしい効果としていかなるものを付与するかという点においては、なお、国の伝統や国民感情を含めた社会状況における種々の要因を踏まえつつ、それぞれの時代における夫婦や親子関係についての全体の規律を見据えた総合的な判断によって定められるべく、国会の裁量に委ねられるべきものとしても、上記の状態を継続し放置することについては、もはや、個人の尊厳の要請に照らして合理性を欠くに至っているものといわざるを得ず、国会の立法裁量の範囲を超えるものとみざるを得ないような場合に当たるというべきである。
【筆者】
「本件諸規定が、異性間に対してのみ現行の法律婚制度を設け、その範囲を限定することで、同性間に対しては、国の制度として公証することもなく、その関係を保護するのにふさわしい効果を付与するための枠組み自体を与えない状態としているが、」との部分について検討する。
「本件諸規定が、異性間に対してのみ現行の法律婚制度を設け、その範囲を限定」している理由は、憲法24条が「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めており、これを前提とした同2項の「要請」に従って「現行の法律婚制度」が立法されているからである。
あらゆる法制度は何らかの立法目的を有しており、その立法目的を達成するための手段として枠組みを定め、その目的の実現を目指すものであるから、その枠組みに当てはまる場合と当てはまらない場合があることはもともと予定されていることである。
そのため、「その範囲を限定」していることは、制度が政策目的を達成するための手段として設けられているものである以上は当然のことである。
「同性間に対しては、国の制度として公証することもなく、その関係を保護するのにふさわしい効果を付与するための枠組み自体を与えない状態としているが、」との部分を検討する。
憲法24条が「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めており、これを前提とした同2項の「要請」に従って法律上の具体的な制度が立法されることを予定している以上は、その婚姻制度の対象となる場合とならない場合との間に差異が生じることは憲法上でもともと予定されているものである。
そのため、その婚姻制度の対象とならない場合に対して制度を設けなければならないということにはならない。
「本件諸規定」が憲法24条2項の「要請」に従って立法されている制度である以上は、「本件諸規定」の対象となる場合とならない場合があることも当然憲法上で予定されているものであり、その対象とならない場合に対して制度を設けなければならないということにはならない。
よって、「本件諸規定が、」「同性間に対して」「国の制度として公証することもなく、その関係を保護するのにふさわしい効果を付与するための枠組み自体を与えない状態としている」ことは、憲法24条2項によって「要請」されていない制度であるためその通りということができる。
むしろ、「本件諸規定」によって「同性間」に対して制度を設けようとした場合には、憲法24条が「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定め、立法目的を達成しようとしている趣旨を阻害することになり、憲法24条に抵触して違憲となる。
そのため、「本件諸規定」によって「同性間」に対して制度を設けてはならない性質のものである。
「婚姻制度の趣旨に対する国民の意識の変化に伴い、同性カップルが法律婚制度に付与されている重大な人格的利益を享受することから一切排除されていることに疑問が生じており、」との部分について検討する。
「人格的利益」の文言があるが、これは「夫婦同氏制大法廷判決」の中で述べられている「人格的利益」の文言から抜き出そうとしているものと考えられる。
この「夫婦同氏制大法廷判決」で問われたのは、憲法24条2項の「婚姻及び家族」の枠組みの「要請」に従って立法された法律上の具体的な制度の内容が「個人の尊厳」を満たすか否かであり、そこで「人格的利益」に触れられているものである。
しかし、この名古屋地裁判決で問われているのは、憲法24条2項の「家族」が、「親子」にも「親子」の関係を基本とした「兄弟」「姉妹」などに含まれないここでいう「同性カップル」という「同性間の人的結合関係」に対して制度を立法することを「要請」しているか否かである。
そのため、「夫婦同氏制大法廷判決」で問われている内容と、この名古屋地裁判決で問われている内容とでは論点が異なっており、この名古屋地裁判決で問われている内容に対して「夫婦同氏制大法廷判決」の「個人の尊厳」を満たすか否かについての論旨を用いることはできない。
よって、この名古屋地裁判決で問われている論点に対して、「夫婦同氏制大法廷判決」の中で「個人の尊厳」を基に「人格的利益」について触れている部分を用いることができるとする前提になく、ここで「人格的利益」の文言を述べていること自体が誤りである。
この「人格的利益」の文言を、「夫婦同氏制大法廷判決」の中で憲法24条2項の「個人の尊厳」を基にして触れられている形ではなく、憲法13条を根拠として示しているものと考えることができるかを検討する。
しかし、憲法13条は国家から個人に対して具体的な侵害行為が発生した場合に、その侵害を排除するという「国家からの自由」という「自由権」として用いることがあり、その場合に「人格的利益」が考慮されることは考えられるが、この憲法13条を根拠として具体的な制度の創設を国家に対して求めることはできない。
そのため、ここで「法律婚制度に付与されている重大な人格的利益」のように述べていることは、「法律婚制度」という具体的な制度によって、憲法13条を根拠とした「国家からの自由」という「自由権」として用いられる「人格的利益」が「付与」されるという意味の通じないことを述べるものとなる。
よって、「人格的利益」の文言を憲法13条を根拠として示したものと考えることも誤りとなる。
「婚姻制度の趣旨に対する国民の意識の変化に伴い、」との部分と、「一切排除されていることに疑問が生じており、」との部分を検討する。
ここでいう「国民の意識の変化」とは、婚姻制度についての「③ 個々人の利用目的」を述べているものと思われる。
しかし、婚姻制度についての「③ 個々人の利用目的」が変化しても、「① 国の立法目的」を達成するための手段として設けられている婚姻制度の枠組みが変化することにはならないのであり、その「国民の意識の変化」を持ち出して、婚姻制度の枠組みによって「一切排除されていることに疑問が生じて」いると述べていることは、婚姻制度の枠組みが「③ 個々人の利用目的」ではなく、「① 国の立法目的」を達成するための手段として設けられていることを理解しないために生じた「疑問」であるということができる。
この「疑問」を解消するためには「① 国の立法目的」と「③ 個々人の利用目的」の違いを理解することが必要であり、その「疑問」を解消するために婚姻制度の枠組みを変更しようとすることは「疑問」が生じている原因を正しく認知するものとはなっておらす、誤った方法である。
「累計的には膨大な数になる同性カップルが現在に至るまで長期間にわたってこうした重大な人格的利益の享受を妨げられているにもかかわらず、このような全面的に否定する状態を正当化するだけの具体的な反対利益が十分に観念し難いことからすると、」との部分について検討する。
上記でも述べたように、「人格的利益」の文言を「夫婦同氏制大法廷判決」で触れられている形で用いようとしていることは誤りであるし、憲法13条を根拠とするものと考えることも意味が通らないものである。
よって、「人格的利益」について述べていることは誤りである。
これにより、「重大な人格的利益の享受を妨げられている」という部分もそもそも意味を成しておらず、何も「妨げられて」いない。
そのため、何かが「妨げられて」いるかのように述べていることは誤りである。
また、その後の「このような全面的に否定する状態を正当化するだけの具体的な反対利益が十分に観念し難い」の部分についても、何も「否定」されていない。
そのため、「全面的に否定する状態」のように何かが「否定」されているかのように述べていることは誤りであるし、「否定」されていることを前提に「正当化するだけの具体的な反対利益」を「観念」できるか否かを論じようとしていることも誤りとなる。
この文全体についても、「累計的には膨大な数になる同性カップル」と称する「同性間の人的結合関係」は、「現在に至るまで長期間にわたって」何も「妨げられて」いないし、何も「否定」されていないため、「類型的」な「数」や「期間」について触れている部分も、それを持ち出す前提を欠くものである。
「同性カップルの関係を保護するのにふさわしい効果としていかなるものを付与するかという点においては、なお、国の伝統や国民感情を含めた社会状況における種々の要因を踏まえつつ、それぞれの時代における夫婦や親子関係についての全体の規律を見据えた総合的な判断によって定められるべく、国会の裁量に委ねられるべきものとしても、」との部分について検討する。
「同性カップルの関係を保護するのにふさわしい効果としていかなるものを付与するかという点においては、」との部分について検討する。
まず、この「⑶ 憲法24条2項に違反するかについて」の項目で問われているのは、憲法24条2項の「家族」が、「親子」や「親子」の関係を基本とした「兄弟」「姉妹」などに含まれないここでいう「同性カップル」という「同性間の人的結合関係」を対象とした制度を立法することを「要請」しているか否かである。
そして、「要請」していればその制度がないことは違憲であり、「要請」していないのであればその制度がないことは「合憲」というものである。
この「同性カップルの関係を保護するのにふさわしい効果としていかなるものを付与するか」との部分は、「いかなるものを付与するか」と述べているように、既に「付与する」という結論を前提として「いかなるもの」とするかを検討するものとなっている。
しかし、これは憲法24条2項の「家族」が、ここでいう「同性間の人的結合関係」を対象とした制度を「要請」していると結論付けられた場合においてしか検討することのできない事柄であり、未だ憲法24条2項の「家族」が「要請」しているか否かが明らかでない段階ではこれを検討する余地はない。
そのため、このような「いかなるものを付与するか」という憲法よりも下位法にあたる立法政策を根拠として上位法である憲法24条2項に違反するか否かを判断しようとしている部分は、法秩序の階層性を損なわせるものであり、解釈の手法として正当化することができず、誤っている。
「国の伝統や国民感情を含めた社会状況における種々の要因を踏まえつつ、それぞれの時代における夫婦や親子関係についての全体の規律を見据えた総合的な判断によって定められるべ」の文は、「キ」の第一段落の文と、その前提となっている「ウ」の「夫婦同氏制大法廷判決」の文と同一である。
(灰色で潰した部分は、上記の記述と同様の文言が使われているところである。)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3(1) 他方で,婚姻及び家族に関する事項は,国の伝統や国民感情を含めた社会状況における種々の要因を踏まえつつ,それぞれの時代における夫婦や親子関係についての全体の規律を見据えた総合的な判断によって定められるべきものである。特に,憲法上直接保障された権利とまではいえない人格的利益や実質的平等は,その内容として多様なものが考えられ,それらの実現の在り方は,その時々における社会的条件,国民生活の状況,家族の在り方等との関係において決められるべきものである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
そのため、この文は「夫婦同氏制大法廷判決」が示している文を用いて説明しようとするものとなっている。
しかし、この「夫婦同氏制大法廷判決」は、「婚姻及び家族に関する事項」に当てはまる場合について述べるものであり、そもそも「婚姻及び家族に関する事項」に当てはまらない場合については、この文が妥当する対象とはしていない。
ここでいう「同性カップル」という「同性間の人的結合関係」については、「婚姻」ではないし、「親子」や「親子」の関係を基本とした「兄弟」「姉妹」などではないため「家族」にも含まれず、「婚姻及び家族に関する事項」には当てはまらない。
よって、そもそも「婚姻及び家族に関する事項」に含まれる場合について「国の伝統や国民感情を含めた社会状況における種々の要因を踏まえつつ、それぞれの時代における夫婦や親子関係についての全体の規律を見据えた総合的な判断によって定められるべ」きことを述べている文を、「婚姻及び家族に関する事項」に含まれない場合についても用いることができることを前提として論じている部分が誤りである。
また、この文の中でも「夫婦や親子関係」の文言があるように、ここでいう「婚姻及び家族に関する事項」とは、「夫婦」と「親子」の関係によるものであることを前提としているのであり、ここでいう「同性カップル」という「同性間の人的結合関係」については、「夫婦」にも「親子」にも当たらないことから、この文言にも当てはまらないことを押さえる必要がある。
「国会の裁量に委ねられるべきものとしても、」との部分であるが、そもそも「国会」は「婚姻及び家族に関する事項」に含まれないものを「婚姻及び家族に関する事項」の中に含めるという権限を有しておらず、「国会の裁量」としてそのような権限が存在するかのように述べていることは誤りである。
よって、「国会の裁量に委ねられるべきもの」との理解も、「国会の裁量」に委ねられていないという点で誤りである。
「上記の状態を継続し放置することについては、もはや、個人の尊厳の要請に照らして合理性を欠くに至っているものといわざるを得ず、国会の立法裁量の範囲を超えるものとみざるを得ないような場合に当たるというべきである。」との部分について検討する。
この文は、「夫婦同氏制大法廷判決」の中で述べられた文と同じくするものである。
(灰色で潰した部分は、上記の記述と同様の文言が使われているところである。)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) そうすると,憲法上の権利として保障される人格権を不当に侵害して憲法13条に違反する立法措置や不合理な差別を定めて憲法14条1項に違反する立法措置を講じてはならないことは当然であるとはいえ,憲法24条の要請,指針に応えて具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定が上記(1)のとおり国会の多方面にわたる検討と判断に委ねられているものであることからすれば,婚姻及び家族に関する法制度を定めた法律の規定が憲法13条,14条1項に違反しない場合に,更に憲法24条にも適合するものとして是認されるか否かは,当該法制度の趣旨や同制度を採用することにより生ずる影響につき検討し,当該規定が個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理性を欠き,国会の立法裁量の範囲を超えるものとみざるを得ないような場合に当たるか否かという観点から判断すべきものとするのが相当である。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
この「夫婦同氏制大法廷判決」で問われているのは、憲法24条2項の「婚姻及び家族」の枠組みの「要請」に従って立法された法律上の具体的な制度の内容について「個人の尊厳」と「両性の本質的平等」を満たすか否かである。
これに対して、この名古屋地裁判決の「⑶ 憲法24条2項に違反するかについて」の項目で問われているのは、憲法24条2項の「家族」が、「親子」や「親子」の関係を基本とした「兄弟」「姉妹」などに含まれない「同性間の人的結合関係」を対象とした制度を立法することを「要請」しているか否かである。
これらは、問題となっている論点の次元が異なっている。
よって、この名古屋地裁判決では、憲法24条の「家族」が、ここでいう「同性間の人的結合関係」を対象とした制度を立法することを「要請」しているか否かについて問われているにもかかわらず、「夫婦同氏制大法廷判決」で示された憲法24条2項の「婚姻及び家族」の枠組みの「要請」に従って立法された法律上の具体的な制度の内容について「個人の尊厳」を満たすか否かが問われている場合と同様の論点であるかのような認識の下に、これを根拠として論じようとしていることは誤っている。
そして、ここでいう「同性間の人的結合関係」については、「親子」や「親子」の関係を基本とした「兄弟」「姉妹」などにも当たらないことから、憲法24条2項の「家族」には含まれない。
そのため、憲法24条2項の「家族」は、ここでいう「同性間の人的結合関係」を対象とした制度を立法することを「要請」していないことになる。
よって、その制度がないことについて、憲法24条2項に違反することはない。
加えて、憲法24条2項の「婚姻及び家族」の枠組みに当てはまる場合は、その「要請」に従って立法された法律上の具体的な制度が「個人の尊厳」を満たすか否かを審査することが可能であるが、そもそも「婚姻及び家族」の枠組みに当てはまらないことから、「要請」はされておらず、結果として法律上の具体的な制度の中にも含まれないものであるから、「個人の尊厳」を適用する前提になく、これを満たすか否かが審査されることはないことから、「個人の尊厳」に抵触することもない。
このことから、この判決が「個人の尊厳の要請に照らして合理性を欠くに至っているものといわざるを得ず、」と述べている部分は誤りである。
次に、「国会の立法裁量の範囲を超えるものとみざるを得ないような場合に当たるというべきである。」との部分を検討する。
これは、憲法24条2項の「婚姻及び家族」の枠組みの「要請」に従って法律上の具体的な制度を立法する際に「国会の立法裁量」があることを前提に、それが「個人の尊厳」を満たさない場合には「国会の立法裁量の範囲を超えるものとみざるを得ないような場合に当たる」とするものである。
しかし、この名古屋地裁判決の「⑶ 憲法24条2項に違反するかについて」の項目で問われているのは、憲法24条2項の「家族」が、ここでいう「同性間の人的結合関係」を対象とした制度を立法することを「要請」しているか否かであり、「要請」していればその制度がないことは違憲となり、「要請」していないのであればその制度がないことは合憲というものである。
この論点は、憲法24条2項によって「要請」されている場合であれば、そもそも「国会」は立法しないという選択をすることはできないため「国会の立法裁量」の余地は存在しないし、憲法24条2項によって「要請」されていないのであれば、そもそも「国会」に対して立法することを義務付けるものではないため「国会の立法裁量の範囲を超える」ことはなく、「国会の立法裁量の範囲を超えるものとみざるを得ないような場合に当たる」か否かを判断する前提にない。
そのため、いずれにせよここで問われているのは「国会の立法裁量」を検討する範疇の問題ではなく、「国会の立法裁量の範囲を超えるものとみざるを得ないような場合に当たる」か否かの論点とは異なっている。
よって、「国会の立法裁量の範囲を超えるものとみざるを得ないような場合に当たる」か否かが問われているかのように論じているが、もともと「国会の立法裁量」の範疇の問題ではないという点で誤りである。
この段落の内容は一文で書かれており、その一文が長すぎるという問題もあるが、文の内容のまとまりについても整理されておらず、読み取りづらく、解釈の過程も分かりづらくなっている。
そこで、下記のように文の内容のまとまりを区切り、順番を少し入れ替える。
=======================================
「本件諸規定が、異性間に対してのみ現行の法律婚制度を設け、その範囲を限定することで、同性間に対しては、国の制度として公証することもなく、その関係を保護するのにふさわしい効果を付与するための枠組み自体を与えない状態としている」(が、)
↓ ↓
「婚姻制度の趣旨に対する国民の意識の変化に伴い、同性カップルが法律婚制度に付与されている重大な人格的利益を享受することから一切排除されていることに疑問が生じており、累計的には膨大な数になる同性カップルが現在に至るまで長期間にわたってこうした重大な人格的利益の享受を妨げられているにもかかわらず、このような全面的に否定する状態を正当化するだけの具体的な反対利益が十分に観念し難い」(ことからすると、)
↓ ↓
「以上によれば、」
↓ ↓
「上記の状態を継続し放置することについては、もはや、個人の尊厳の要請に照らして合理性を欠くに至っているものといわざるを得ず、国会の立法裁量の範囲を超えるものとみざるを得ないような場合に当たるというべきである。」
↓ ↓
「同性カップルの関係を保護するのにふさわしい効果としていかなるものを付与するかという点においては、なお、国の伝統や国民感情を含めた社会状況における種々の要因を踏まえつつ、それぞれの時代における夫婦や親子関係についての全体の規律を見据えた総合的な判断によって定められるべく、国会の裁量に委ねられるべきもの」(としても、)
=======================================
上記の文を区切って説明している内容の第一文と第二文については、この段落よりも前に既に述べていることであり、それの繰り返しに過ぎない。
よって、上記の第四文における憲法解釈の結論を述べる前に改めて述べる必要はないものである。
上記の第五文については、この段落の一つ前の「キ」の内容の繰り返しである。
これは、憲法24条2項の「家族」の規範の意味が問われている中で、その下位の法令における立法政策について検討しているものということができ、それを根拠としてその上位法にあたる憲法24条2項の規範の意味を明らかにすることはできないものである。
よって、上記のように第四文のところで憲法解釈の結論を述べた後に配置することはできるとしても、その憲法解釈の結論を述べる前に取り上げて、それを根拠として憲法の規範の意味を論じようとすることは解釈の手続きとして誤りである。
そのことから、この「⑶ 憲法24条2項に違反するかについて」の項目の流れの中では、「カ」を述べた後に、そのまま上記の第三文の「以上によれば、」と繋ぎ、第四文の憲法解釈の結論だけを述べていれば、文章全体の構造としては分かりやすかったといえる。
この段落の内容をさらに細かく整理すると、下記のようになる。
=======================================
「異性間に対してのみ現行の法律婚制度を設け、その範囲を限定する」「本件諸規定」
↓ ↓
「同性間に対しては、国の制度として公証することもなく、その関係を保護するのにふさわしい効果を付与するための枠組み自体を与えない状態としている」
↓ ↓
「同性カップルが法律婚制度に付与されている重大な人格的利益を享受することから一切排除されている」
↓ ↓
「累計的には膨大な数になる同性カップルが現在に至るまで長期間にわたってこうした重大な人格的利益の享受を妨げられている」
↓ ↓
「婚姻制度の趣旨に対する国民の意識の変化に伴い、」「疑問が生じており、」
↓ ↓
「このような全面的に否定する状態を正当化するだけの具体的な反対利益が十分に観念し難い」
↓ ↓
「上記の状態を継続し放置することについては、もはや、個人の尊厳の要請に照らして合理性を欠くに至っているものといわざるを得ず、国会の立法裁量の範囲を超えるものとみざるを得ないような場合に当たるというべきである。」
↓ ↓
「同性カップルの関係を保護するのにふさわしい効果としていかなるものを付与するかという点においては、なお、国の伝統や国民感情を含めた社会状況における種々の要因を踏まえつつ、それぞれの時代における夫婦や親子関係についての全体の規律を見据えた総合的な判断によって定められるべく、国会の裁量に委ねられるべきもの」
=======================================
上記は長いので、憲法24条2項に違反すると結論付けるまでの判断の過程となっている部分だけを取り出すと下記のようになる。
「同性間に対しては、国の制度として公証することもなく、その関係を保護するのにふさわしい効果を付与するための枠組み自体を与えない状態としている」
↓ ↓
「同性カップルが法律婚制度に付与されている重大な人格的利益を享受することから一切排除されている」
↓ ↓
「上記の状態を継続し放置することについては、もはや、個人の尊厳の要請に照らして合理性を欠くに至っているものといわざるを得ず、国会の立法裁量の範囲を超えるものとみざるを得ないような場合に当たるというべきである。」
しかし、この説明は誤っている。
この「⑶ 憲法24条2項に違反するかについて」の項目で問われているのは、憲法24条2項の「家族」が、ここでいう「同性カップル」という「同性間の人的結合関係」を対象とした制度を立法することを「要請」しているか否かである。
そして、「人格的利益」の文言は、「夫婦同氏制大法廷判決」の中で憲法24条2項の「婚姻及び家族」の枠組みに従って立法された法律上の具体的な制度の内容が「個人の尊厳」を満たすか否かについての判断の中で触れられたものであり、そもそも「婚姻及び家族」の対象でない場合にはこれが検討される前提を欠くものである。
ここでいう「同性間の人的結合関係」については、「親子」ではないし、「親子」の関係を基本とした「兄弟」「姉妹」などではないため、憲法24条2項の「家族」の中に含まれず、結果として、憲法24条2項が「要請」しているものではない。
そのため、憲法24条2項の「婚姻及び家族」の対象とならないことから、「個人の尊厳」を満たすか否かを検討する前提になく、「人格的利益」に触れる機会もない。
よって、「同性間の人的結合関係」について「人格的利益」を検討することができるかのような前提で論じている部分が誤りである。
その後の「個人の尊厳」の文言についても、憲法24条2項の「婚姻及び家族」の対象となる場合にのみ検討することができるものであり、この対象とならない場合には検討する余地のないものである。
ここでいう「同性間の人的結合関係」は、「婚姻及び家族」の対象ではないことから、憲法24条2項の「個人の尊厳」を満たすか否かを検討する前提になく、「合理性を欠く」か否かを検討していること自体が誤りである。
また、その結果「国会の立法裁量の範囲を超えるものとみざるを得ないような場合に当たるというべきである。」との部分についても、検討する前提を欠くものについて検討しようとした結果であり、その結論を正当化することのできるものではない。
したがって、本件諸規定は、同性カップルに対して、その関係を国の制度によって公証し、その関係を保護するのにふさわしい効果を付与するための枠組みすら与えていないという限度で、憲法24条2項に違反するものである。
【筆者】
この「⑶ 憲法24条2項に違反するかについて」の項目で問われているのは、憲法24条2項の「家族」が、ここでいう「同性カップル」という「同性間の人的結合関係」を対象とした制度を立法することを「要請」しているか否かである。
「要請」しているのであればその制度がないことは違憲であり、「要請」していないのであればその制度がないことは合憲である。
ここでいう「同性間の人的結合関係」については、「親子」や「親子」の関係を基本とした「兄弟」「姉妹」などではないことから、「家族」の中に含まれない。
そのため、憲法24条2項の「家族」は、ここでいう「同性間の人的結合関係」を対象とした制度を立法することを「要請」しておらず、その制度がないことが憲法24条2項に違反することはない。
よって、その制度がないことについて「憲法24条2項に違反するものである。」と述べている部分は誤りである。
「同性カップルに対して、その関係を国の制度によって公証し、その関係を保護するのにふさわしい効果を付与するための枠組みすら与えていない」という部分についても、そもそも憲法24条2項の「家族」はそのような「枠組み」を立法することを「要請」していないのであり、これを「与えていない」ことが「憲法24条2項に違反する」ということはない。
そのため、これを「与えていないという限度で、憲法24条2項に違反するものである。」と述べていることについても誤りである。
24条2項が「要請」していない制度の不存在を理由として24条2項に違反するということにはならないことについて、国(行政府)の主張では下記の部分が対応するものである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(オ)さらに、被控訴人原審第3準備書面第3の2(3)(15ないし17ページ)で述べたとおり、憲法24条が婚姻について異性間の人的結合関係のみを対象とするものとして明文で定め、婚姻に係る法制度の構築を法律に委ねているものの、それ以外の法制度の構築を明文で定めていないことからすると、憲法は、法律(本件諸規定)により異性間の人的結合関係のみを対象とする婚姻を制度化することを予定しているとはいえるものの、同性間の人的結合関係を対象とする婚姻制度を構築することを想定していないことはもとより、パートナーと家族になるための法制度を含め、同性間の人的結合関係を対象とする新たな婚姻に準じる法制度を構築することを具体的に想定しておらず、同制度の構築を立法府に要請しているものでもないから、同制度の不存在が憲法24条2項に違反する状態となることもないと解される。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【東京一次・第1回】控訴答弁書 令和5年6月23日 PDF (P34)
「⑶ 憲法24条2項に違反するかについて」の項目の流れは分かりづらい。
そのため、項目と段落ごとに短くまとめると下記のようになる。
=========================================
「⑶ 憲法24条2項に違反するかについて」
【ア】
「同条2項も、現行の法律婚制度を同性間に対して及ぼすことを要請していないと解するのが整合的であり、」「同項に違反するものでもない」
↓ ↓
【イ】
「原告らは、」「憲法14条1項違反となると主張している。」「原告らが主張する」「違憲性については、憲法24条2項の問題ともなりうる」
「婚姻には、」「法律上の効果にとどまらず、事実上の効果」
「同性カップルは」「異性カップルとの間に著しい乖離が生じている。」「憲法上是認されるかどうかは、なお検討を要する」
「家族の問題として検討することは十分に可能なはず」
「「家族」に関する事項として、憲法24条2項に違反しないかを検討する。」
↓ ↓
【ウ】
(夫婦同氏制大法廷判決参照)
↓ ↓
【エ】
(エ 前記ウのとおり、)
「憲法24条2項は」「人格的利益をも尊重すべきこと等についても十分に配慮した法律の制定を求めるもの」
(再婚禁止期間大法廷判決参照)
「婚姻をするについての自由は、」「人の尊厳に由来するものということができ、重要な人格的利益である」
「とりわけ重要なのは、両当事者が安定して永続的な共同生活を営むために、両当事者の関係が正当なものであるとして社会的に承認されること」
「重要な人格的利益を実現する上では、両当事者が正当な関係であると公証され、その関係を保護するのにふさわしい効果の付与を受けるための枠組みが与えられる利益が極めて重要な意義を有する」
「両当事者の関係が国の制度により公証され、その関係を保護するのにふさわしい効果の付与を受けるための枠組みが与えられるという利益は、憲法24条2項により尊重されるべき重要な人格的利益である」
「同性カップルは、」「このような重要な人格的利益を享受できていない」
↓ ↓
【オ】
(オ 前記ウのとおり、)
「憲法24条の適合性を審査するためには、」「現行の「家族」に関する法制度の趣旨を検討する必要がある。」
「男女の生活共同体に対して法律婚制度により公証を与え、これを保護するための枠組みを設けることは、それ自体合理性を有する」
「親密な関係に基づき永続性をもった生活共同体を構成することは、同性カップルにおいても成しうるはずのもの」
「男女の結合関係を中核としてその間に生まれた子の保護・育成の機能を担うという伝統的な家族観が、唯一絶対のものであるというわけではなくなっている」
「性的指向それ自体は障害ではないとの知見が確立した」
「各種国際機関は、20世紀後半以降、性的少数者の権利保護に向けた活動を行ってきた」
「世界各国において、同性カップルを公証するための制度(登録パートナーシップ制度等)が導入されるようになった」「28か国が同性婚制度を導入している」
「地方自治体において」「登録パートナーシップ制度が導入」「同性パートナーがいる区職員に対しても結婚休暇等を認める取組み」
「国連の条約機関等からの勧告」「性同一性障害者の戸籍上の性別変更を認める法律の制定」「一部諸外国から、同性婚の公式な承認を国レベルに拡大するなどの施策等の勧告」「地方自治体や各種団体から、同性間の婚姻を求める声明」
「同性パートナーに家族手当等を適用するといった取組みを行う企業」「国民の意識調査において、賛成派が反対派を上回る結果が報告される」
「大きな格差」「もはや無視できない状況に至っている」
↓ ↓
【カ】
(カ 前記ウのとおり、)
「憲法24条の適合性を審査するためには、」「現行の法律婚制度が採用されたことによる影響を検討する必要がある。」
「同性カップルにおいて、」「その関係が国の制度によって公証されず、その関係を保護するのにふさわしい効果の付与を受けるための枠組みすら与えられない不利益は甚大なものである。」
「同性カップルという関係が国の制度によって公証され、その関係を保護するのにふさわしい効果の付与を受けるための枠組みが与えられることに重大な価値がある」
「長期にわたって」「同性カップルに対し、上記保護の枠組みが与えられていなかった」
「同性カップルに対する保護がなされない影響は深刻なものである。」
↓ ↓
【キ】
(キ 前記ウのとおり、)
(夫婦同氏制大法廷判決参照)
「同性カップルを国の制度として公証したとしても、」「伝統的家族観を直ちに否定することにはならず、共存する道を探ることはできるはず」
「このような法的効果を同性カップルに付与した場合の具体的な弊害も観念しにくい」
「そのような効果を同性カップルに付与することに法律は弊害を認めていない」
「既存の異性婚に変容をもたらす可能性があるものもあり、」「民主政の過程において慎重に審議が尽くされるべき」
「しかし、」「枠組み自体が与えられるべきことを否定すべきことにはならない。」
「枠組み自体を存在させないようにするということと、存在を認めた上で、」「いかなる効果を付与すべきか検討し決定していくということとでは、自ずと立法裁量の広狭に差が生じる」
↓ ↓
【ク】
「もはや、個人の尊厳の要請に照らして合理性を欠くに至っているものといわざるを得ず、国会の立法裁量の範囲を超えるものとみざるを得ない」
「同性カップルに対して、その関係を国の制度によって公証し、その関係を保護するのにふさわしい効果を付与するための枠組みすら与えていないという限度で、憲法24条2項に違反する」
=========================================
しかし、この内容は誤りである。
【ア】
ここでは特に述べることはない。
↓ ↓
【イ】
「カップル」という「二人一組」については、「権利能力」を有しておらず、法主体としての地位を認められていないことから、その間を法的に比較することはできない。
「親子」や「親子」の関係を基本とした「兄弟」「姉妹」などに含まれない「同性間の人的結合関係」については、憲法24条2項の「家族」には含まれないため、「家族」に関する事項として憲法24条2項に違反しないかを検討することは誤りである。
↓ ↓
【ウ】
この名古屋地裁判決の憲法24条2項の「家族」がここでいう「同性間の人的結合関係」を対象とする制度を立法することを「要請」しているかの問題と、「夫婦同氏制大法廷判決」が具体的な制度が存在することを前提としてその内容が「個人の尊厳」や「両性の本質的平等」に立脚しているかの問題では、異なる事案である。
そのため、この名古屋地裁判決で「夫婦同氏制大法廷判決」の基準を用いることはできない。
↓ ↓
【エ】
憲法24条2項は「婚姻及び家族」の制度を創設することを「要請」しているが、それ以外の制度の創設を「要請」していない。
また、「婚姻及び家族」の制度については、「個人の尊厳」を満たすか否かを審査することができるが、それ以外の制度に対しては24条2項の「個人の尊厳」は適用されないため、「婚姻及び家族」の制度に含まれない何らかの制度に対して「個人の尊厳」から導かれるとされる「人格的利益」を論じる余地はない。
↓ ↓
【オ】
問われているのは、24条2項の「家族」が、ここでいう「同性間の人的結合関係」を対象とした制度の創設を「要請」しているか否かであり、これは憲法上の条文そのものから意味を明らかにしなければならず、下位法である「家族」に関する法制度や「法律婚制度」を根拠として意味を明らかにすることはできない。
「婚姻」は「生殖」に関わって生じる社会吹きな不都合を解消するために「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度であり、単に「親密な関係」であることを理由として設けられているものではない。
婚姻制度は「性愛」を保護するための制度ではなく、「性的指向」と関係するかのように論じることは妥当でない。
外国の制度は日本国の「婚姻」と同一のものを指していることにならないし、日本法の解釈に影響を与えることはない。
地方自治体の登録パートナーシップ制度には違憲性、違法性が存在するし、下位法によって上位法である憲法の意味を明らかにすることはできない。
国民意識の賛成・反対の数によって憲法の規範の意味が変わることはない。
「婚姻している者(既婚者)」が「婚姻していない者(独身者)」との間で婚姻制度の立法目的を達成するための手段として不必要に過大な優遇措置を得ているのであれば、その過大な優遇措置に関する規定が個別に失効することによって格差が是正されることになる。
↓ ↓
【カ】
憲法24条2項の解釈を行う際に、「現行の法律婚制度」という下位の法令を基準とすることはできない。
憲法は「個人の尊厳」の原理に基づいており、自然人は「個人主義」の下に各々「自律的な個人」として生存していくことを予定しており、「婚姻していない者(独身者)」の状態で既に完全であるから、そこに「不利益」は存在していない。
婚姻制度は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために設けられており、その目的を達成するための手段として合理的な範囲で「婚姻している者(既婚者)」に対して優遇措置を与えることが正当化されるが、そのような目的を有しない制度を設けることは、憲法14条の「平等原則」に抵触して違憲となる。
「カップル」という「二人一組」については、「権利能力」を有しておらず、法主体としての地位を認められていないことから、法的に比較することはできないのであり、これを取り上げて論じている点で妥当でない。
憲法は「個人の尊厳」の原理に基づいており、自然人は「個人主義」の下に各々「自律的な個人」として生存していくことを予定していることから、その状態で既に完全であり、そこに不利益はない。
↓ ↓
【キ】
憲法24条の「婚姻」の文言は「生殖と子の養育」に関わる制度を一元的に集約して規律する趣旨を有していることから、24条の「婚姻」を離れて別の制度として「生殖と子の養育」に関わる制度を設けることはできない。
ここでいう「同性間の人的結合関係」に対して制度を設けることについても、「生殖と子の養育」に関わる制度や影響を与える制度であることが考えられるため、憲法24条の「婚姻」に抵触して違憲となる。
また、婚姻制度が「婚姻している者(既婚者)」に対して優遇措置を設けていることは、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成するための手段として合理的な範囲であれば、「婚姻していない者(独身者)」との間の差異を正当化することができるが、そのような目的を有しない「同性間の人的結合関係」に対して優遇措置を設けることは、制度を利用していない者との間で合理的な理由を説明することのできない差異を生じさせることになるから、憲法14条の「平等原則」に抵触して違憲となる。
「同性間の人的結合関係」に対して契約等によって法的効果を発生させることができるか否かであるが、法律上の強行規定や公序良俗に反する場合は無効となるため、法律は弊害を認めている場合もある。
24条の「婚姻」や「婚姻及び家族」の枠組みや憲法14条に抵触する場合には、国会の立法裁量の余地はない。
↓ ↓
【ク】
憲法24条2項の「婚姻及び家族」の枠組みに当てはまる場合には憲法24条2項の「個人の尊厳」が適用されるが、それに当てはまらない場合はこの「個人の尊厳」は適用されない。
ここでいう「同性間の人的結合関係」については、「婚姻及び家族」の枠組みに当てはまらないため、「個人の尊厳」を適用することのできる前提になく、この「個人の尊厳」を満たすか否かを判断することはできない。
よって、「国会の立法裁量の範囲」を超えるか否かの判断の前提を欠いており、これを「超えるもの」と論じていることは誤りである。
憲法24条2項は「婚姻及び家族」の制度の創設を「要請」しているが、それ以外の制度の創設は「要請」していないため、これに当てはまらない「同性間の人的結合関係」を対象する制度が存在しないことについて、憲法24条2項に違反することはない。
よって、憲法24条2項に違反すると述べていることも誤りである。
⑷ 憲法14条1項に違反するかについて
ア 憲法14条1項は、法の下の平等を定めており、この規定が、事柄の性質に応じた合理的な根拠に基づくものでない限り、法的な差別的取扱いを禁止する趣旨のものであると解すべきである(最高裁昭和37年 第1472号同39年5月27日大法廷判決・民集18巻4号676頁、最高裁昭和45年 第1310号同48年4月4日大法廷判決・刑集27巻3号265頁等)。
【筆者】
ここで示された判決は、下記の通りである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
……(略)……しかし、右各法条は、国民に対し絶対的な平等を保障したものではなく、差別すべき合理的な理由なくして差別することを禁止している趣旨と解すべきであるから、事柄の性質に即応して合理的と認められる差別的取扱をすることは、なんら右各法条の否定するところではない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
最高裁判所昭和39年5月27日大法廷判決 (PDF)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
よつて案ずるに、憲法一四条一項は、国民に対し法の下の平等を保障した規定であつて、同項後段列挙の事項は例示的なものであること、およびこの平等の要請は、事柄の性質に即応した合理的な根拠に基づくものでないかぎり、差別的な取扱いをすることを禁止する趣旨と解すべきことは、当裁判所大法廷判決(昭和三七年(オ)第一四七二号同三九年五月二七日・民集一八巻四号六七六頁)の示すとおりである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
最高裁判所昭和48年4月4日大法廷判決 (PDF)
この14条の「平等原則」を判断する際に必要となる視点は、下記の通りである。
◇ 「法適用の平等」と「法内容の平等」の違い
14条の「平等原則」における審査では、「法適用の平等」と「法内容の平等」を分けて考える必要がある。
【動画】シンポジウム 国葬を考える【The Burning Issues
vol.27】 2022/09/25
◇ 「法内容の平等」の審査
「法内容の平等」については、➀「区別(差別)」の存否と、②「区別(差別)」が存在した場合における「合理的な理由」の存否が問われることになる。
そして、②の「合理的な理由」の内容については、「立法目的」とその「達成手段」が問われることになる。
➀ 「区別(差別)」が存在するか否か
② 「区別(差別)」が存在する場合にその区別に「合理的な理由」が存在するか
「合理的な理由」の判断方法
・「立法目的」の合理性
・「立法目的を達成するための手段」の合理性
この判決の内容は、➀の「区別取扱い」が存在するか否かという判断から誤っているため、②の判断を行おうと試みている論旨についても、全面的に誤っている。
また、前記⑵ア及び⑶ウのとおり、憲法24条1項は、婚姻をするかどうか、いつ誰とするかについては、当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたものと解され、このような婚姻をするについての自由は、同項の趣旨に照らし、十分尊重に値するものと解することができ、同条2項は、婚姻及び家族に関する事項について、具体的な制度の構築を第一次的に国会の合理的な立法裁量に委ねるとともに、その立法に当たっては、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきであるとする要請、指針を示すことによって、その裁量の限界を画したものである(再婚禁止期間大法廷判決、夫婦同氏制大法廷判決参照)。
【筆者】
ここで示された判決は、下記の通りである。
対応関係を読み取る際には、24条の1項と2項を説明する順序が入れ替わっている部分があることに注意が必要である。
・ 灰色で潰した部分は、最高裁の二つの「大法廷判決」とこの名古屋地裁判決とを合わせて三つの判決の間で共通する部分である。
・ 黄緑色で潰したの部分は、「再婚禁止期間大法廷判決」とこの名古屋地裁判決の間で共通する部分である。
・ 潰していない残った部分が、それぞれの「大法廷判決」とこの名古屋地裁判決の上記の部分とは共通していないところである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ところで,婚姻及び家族に関する事項は,国の伝統や国民感情を含めた社会状況における種々の要因を踏まえつつ,それぞれの時代における夫婦や親子関係についての全体の規律を見据えた総合的な判断を行うことによって定められるべきものである。したがって,その内容の詳細については,憲法が一義的に定めるのではなく,法律によってこれを具体化することがふさわしいものと考えられる。憲法24条2項は,このような観点から,婚姻及び家族に関する事項について,具体的な制度の構築を第一次的には国会の合理的な立法裁量に委ねるとともに,その立法に当たっては,個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきであるとする要請,指針を示すことによって,その裁量の限界を画したものといえる。また,同条1項は,「婚姻は,両性の合意のみに基いて成立し,夫婦が同等の権利を有することを基本として,相互の協力により,維持されなければならない。」と規定しており,婚姻をするかどうか,いつ誰と婚姻をするかについては,当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたものと解される。婚姻は,これにより,配偶者の相続権(民法890条)や夫婦間の子が嫡出子となること(同法772条1項等)などの重要な法律上の効果が与えられるものとされているほか,近年家族等に関する国民の意識の多様化が指摘されつつも,国民の中にはなお法律婚を尊重する意識が幅広く浸透していると考えられることをも併せ考慮すると,上記のような婚姻をするについての自由は,憲法24条1項の規定の趣旨に照らし,十分尊重に値するものと解することができる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
再婚禁止期間大法廷判決 (PDF)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
婚姻及び家族に関する事項は,関連する法制度においてその具体的内容が定められていくものであることから,当該法制度の制度設計が重要な意味を持つものであるところ,憲法24条2項は,具体的な制度の構築を第一次的には国会の合理的な立法裁量に委ねるとともに,その立法に当たっては,同条1項も前提としつつ,個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきであるとする要請,指針を示すことによって,その裁量の限界を画したものといえる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
夫婦同氏制大法廷判決 (PDF)
しかし、この名古屋地裁判決で問われている論点に対して、これら「再婚禁止期間大法廷判決」と「夫婦同氏制大法廷判決」の内容を用いて何らかの結論を導き出そうとすることそのものが誤っている。
まず、この名古屋地裁判決で問われている内容は、下記の通りである。
第一に、憲法24条1項の「婚姻」や2項の「婚姻及び家族」が、「親子」や「親子」の関係を基本とした「兄弟」「姉妹」などに含まれない「同性間の人的結合関係」を対象とする制度を立法することを「要請」しているか否かである。
第二に、ここでいう「同性間の人的結合関係」を対象とする制度が存在しないことについて、憲法14条1項の「平等原則」に抵触するか否かである。
そして、憲法24条1項の「婚姻」については、この「⑵ 憲法24条1項に違反するかについて」の項目で「要請」していないと判断している。
憲法24条2項の「婚姻及び家族」の「婚姻」についても、「⑶ 憲法24条2項に違反するかについて」の項目の「ア」で「要請」していないと判断している。
憲法24条2項の「婚姻及び家族」の「家族」については、上記で解説しているように、「夫婦」と「親子」の関係による「血縁関係者」の範囲に限られる。
この名古屋地裁判決では憲法24条2項の「家族」が「要請」しているか否かが問われている事案に対して、「夫婦同氏制大法廷判決」で示された憲法24条2項の「婚姻及び家族」の枠組みの「要請」に従って立法された法律上の具体的な制度が「個人の尊厳」と「両性の本質的平等」を満たすか否かについての基準を持ち出し、いつの間にか憲法24条2項の「家族」が「要請」している内容の話から、「個人の尊厳」を満たすか否かに話が切り替わり、そのまま「個人の尊厳」に照らして合理性を欠くとして憲法24条2項に違反すると述べるものとなっており、論理的な欠陥を抱えた内容となっている。
これらを前提に、今ここで問われているのは、ここでいう「同性間の人的結合関係」を対象とする制度が存在しないことについて、憲法14条1項の「平等原則」に違反するか否かである。
しかし、そもそも憲法24条では「婚姻」について「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めていることから、この「婚姻」の枠組みが示す人的結合関係の範囲そのものを憲法14条1項の「平等原則」を用いて審査することはできない。
また、24条2項の「婚姻及び家族」の「家族」についても、「夫婦」と「親子」によるものに限られることから、この「家族」の枠組みが示す人的結合関係の範囲そのものを憲法14条1項の「平等原則」を用いて審査することはできない。
そのため、憲法14条1項の「平等原則」で審査することができる部分とは、24条の定める「婚姻及び家族」の枠組みが示す人的結合関係の範囲そのものに関わらない部分に限られる。
例えば、ここで取り上げている「再婚禁止期間大法廷判決」や「夫婦同氏制大法廷判決」、その他に「法定相続分」や「婚姻適齢」などを審査することが可能であると考えられる。
そして、今述べたように、ここで取り上げている「再婚禁止期間大法廷判決」と「夫婦同氏制大法廷判決」の内容は、憲法24条1項を踏まえて、憲法24条2項の「婚姻及び家族」が「要請」する法律上の具体的な制度が存在することを前提として、その法律上の具体的な制度の内容が「個人の尊厳」と「両性の本質的平等」を満たすか否かが問われている事案であり、また同時に憲法14条1項の「平等原則」の審査も行われたというものである。
しかし、この名古屋地裁判決で問われている論点は、憲法24条2項の「婚姻及び家族」の枠組みが示している人的結合関係の範囲そのものであり、そもそも憲法14条1項を用いて審査することのできる対象ではない。
そのことから、この名古屋地裁判決で問われている論点に対して、憲法24条2項の「婚姻及び家族」の枠組みに従って立法されている法律上の具体的な制度の内容について「個人の尊厳」と「両性の本質的平等」を満たすか否かが問われ、同時にその制度の内容が憲法14条の「平等原則」に違反しないか否かが問われている「再婚禁止期間大法廷判決」と「夫婦同氏制大法廷判決」の基準を用いて結論を導き出すことはできない。
よって、この名古屋地裁判決において、ここでいう「同性間の人的結合関係」を対象とする制度が存在しないことについて検討していることは、憲法24条が「要請」しておらず、憲法24条の「婚姻及び家族」の枠組みが示している人的結合関係の範囲そのものについては憲法14条1項の「平等原則」を用いて審査することはできないにもかかわらず、これを憲法14条1項の「平等原則」によって審査することが可能であるかのような前提で論じようとするものとなっており、誤りである。
また、その行うことのできない憲法14条1項の「平等原則」の審査においても、この名古屋地裁判決とは事案の異なる、憲法24条の「婚姻及び家族」の枠組みに従って立法された法律上の具体的な制度に対して「個人の尊厳」や「両性の本質的平等」を満たすか否かを判断する際に、同時にその制度に対して憲法14条1項の「平等原則」についても審査されているという、憲法24条の「婚姻及び家族」の枠組みの示す人的結合関係の範囲そのものに関わらない「再婚禁止期間大法廷判決」と「夫婦同氏制大法廷判決」の事案を持ち出すものとなっており、この点の論じ方についても誤っている。
これにより、この「⑷ 憲法14条1項に違反するかについて」の項目において、「再婚禁止期間大法廷判決」と「夫婦同氏制大法廷判決」を持ち出して論じようとしていることそのものが誤りである。
そうすると、婚姻及び家族に関する事項についての区別取扱いについては、立法府に与えられた上記の裁量権を考慮しても、そのような区別をすることに合理的な根拠が認められない場合には、当該区別は、憲法14条1項に違反するものということができる(最高裁平成24年 第984号、第985号同25年9月4日大法廷決定・民集67巻6号1320頁参照)。
【筆者】
ここで示された判決は、下記の通りである。
(灰色で潰した部分は、上記の記述と同様の文言が使われているところである。)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2 憲法14条1項適合性の判断基準について
憲法14条1項は,法の下の平等を定めており,この規定が,事柄の性質に応じた合理的な根拠に基づくものでない限り,法的な差別的取扱いを禁止する趣旨のものであると解すべきことは,当裁判所の判例とするところである(最高裁昭和37年(オ)第1472号同39年5月27日大法廷判決・民集18巻4号676頁,最高裁昭和45年(あ)第1310号同48年4月4日大法廷判決・刑集27巻3号265頁等)。
相続制度は,被相続人の財産を誰に,どのように承継させるかを定めるものであるが,相続制度を定めるに当たっては,それぞれの国の伝統,社会事情,国民感情なども考慮されなければならない。さらに,現在の相続制度は,家族というものをどのように考えるかということと密接に関係しているのであって,その国における婚姻ないし親子関係に対する規律,国民の意識等を離れてこれを定めることはできない。これらを総合的に考慮した上で,相続制度をどのように定めるかは,立法府の合理的な裁量判断に委ねられているものというべきである。この事件で問われているのは,このようにして定められた相続制度全体のうち,本件規定により嫡出子と嫡出でない子との間で生ずる法定相続分に関する区別が,合理的理由のない差別的取扱いに当たるか否かということであり,立法府に与えられた上記のような裁量権を考慮しても,そのような区別をすることに合理的な根拠が認められない場合には,当該区別は,憲法14条1項に違反するものと解するのが相当である。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(PDF)
「婚姻及び家族に関する事項についての区別取扱いについては、」との記載について検討する。
憲法24条2項は「婚姻及び家族」の枠組みを定めており、これは「夫婦」と「親子」による「血縁関係者」の範囲に限られる。
ここで述べている「婚姻及び家族に関する事項」についても、この憲法24条2項の「婚姻及び家族」が立法することを「要請」している法律上の具体的な制度を指すものであり、これと一致するものである。
そして、ここでいう「同性間の人的結合関係」については、「婚姻」ではないし、「親子」や「親子」の関係を基本とした「兄弟」「姉妹」などに当たらないことから「家族」にも含まれておらず、憲法24条2項の「婚姻及び家族」の中には含まれないし、当然、ここで述べている「婚姻及び家族に関する事項」の中には含まれない。
そのため、ここでいう「同性間の人的結合関係」を対象とした制度が存在しないことについては、そもそも「婚姻及び家族に関する事項」とはいえないため、これを「婚姻及び家族に関する事項についての区別取扱い」のように、「婚姻及び家族に関する事項」に含まれることを前提として、その中における「区別取扱い」が問題となっているかのような論じ方をしている部分が誤りである。
「立法府に与えられた上記の裁量権を考慮しても、そのような区別をすることに合理的な根拠が認められない場合には、当該区別は、憲法14条1項に違反するものということができる」の部分について検討する。
まず、この事案はそもそも「婚姻及び家族に関する事項」ではないため、「婚姻及び家族に関する事項」に含まれることを前提として「憲法14条1項」に違反するか否かを論じることができるかのように述べている部分が誤りである。
次に、憲法24条では「婚姻及び家族」の枠組みを定めており、これは「夫婦」と「親子」による「血縁関係者」の範囲に限られることから、これに含まれない「同性間の人的結合関係」を「婚姻及び家族に関する事項」として扱うことはできない。
よって、「婚姻及び家族に関する事項」の中にここでいう「同性間の人的結合関係」を含めることについては、そもそも「立法府」に「裁量権」は存在しておらず、その「裁量権」が「立法府」に与えられているかのような前提で論じている部分が誤りである。
三つ目に、「立法府」に「裁量権」が与えられていない事柄については、「憲法14条1項」によって「合理的な根拠が認められない場合」であるか否かを審査することはできないのであり、これができることを前提に「憲法14条1項に違反する」か否かを判断しようと試みている部分も誤りである。
イ 原告らは、本件諸規定は、異性との結婚を希望する者(異性カップル)には婚姻を認め、同性との結婚を希望する者(同性カップル)には婚姻を認めないという、婚姻を希望する者の性的指向に基づく別異取扱いを行うものであると主張し、被告は、本件諸規定は、性的指向それ自体に着目した区別を設けるためのものではなく、性的指向について中立的な規定であり、原告が主張する別異取扱いは、本件諸規定の適用の結果生じる事実上又は間接的な効果にすぎないと主張する。
【筆者】
「原告らは、本件諸規定は、異性との結婚を希望する者(異性カップル)には婚姻を認め、同性との結婚を希望する者(同性カップル)には婚姻を認めないという、婚姻を希望する者の性的指向に基づく別異取扱いを行うものであると主張し、」との記載がある。
まず、「異性との結婚」と「同性との結婚」との部分について検討する。
「婚姻」は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられている制度であり、一般的・抽象的にその間で自然生殖を想定することができる「男性」と「女性」の間に「貞操義務」を設けるなど一定の形式で結び付けるものとして形成されている。
「同性」間では生殖を想定することができず、「生殖と子の養育」の趣旨を満たすものではないことから、「婚姻」とすることができない。
そのため、「同性との結婚」のように「同性」間で「婚姻」が成立することを前提としている部分が妥当ではない。
次に、「異性カップル」と「同性カップル」との部分について検討する。
法律論上は「権利能力」を有して法主体としての地位を認められている者同士しか比較することはできず、ここでいう「カップル」のように「権利能力」を有しておらず、法主体としての地位を認められていない「二人一組」を取り上げて比較することはできない。
そのため、「異性カップル」と「同性カップル」のように「二人一組」を取り上げてその間の差異を検討しようとしている部分が誤りである。
三つ目に、「希望する者」との部分について検討する。
法制度は政策目的を達成するための手段として設けられ、その対象となる場合とならない場合との間に差異が生じることになるが、これは「希望する者」の「希望」が通るか否かという問題ではない。
「希望」していない者であっても、制度の対象となる場合はあるからである。
よって、「希望する者」のように「希望」する者だけを取り上げで論じようとしている部分も妥当でない。
「婚姻を希望する者の性的指向に基づく別異取扱いを行うものであると主張し、」との部分について検討する。
婚姻制度は「性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して区別するものではないし、「性愛」に基づいて婚姻制度を利用することを求めるものでも勧めるものではない。
そのため、「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかについての「性的指向」と称するものに基づいて「別異取扱い」を行っているという事実はない。
よって、「性的指向に基づく別異取扱いを行うものである」との主張は誤りである。
また、「性愛」という特定の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的として法制度を立法した場合には、憲法20条1項後段・3項、89条の「政教分離原則」に抵触して違憲となるし、制度を利用する者に「性愛」という特定の思想信条、信仰、感情を持つことを求めたり勧めるようなことをすれば国家による内心に対する不当な干渉となることから、憲法19条の「思想良心の自由」、憲法20条1項前段の「信教の自由」に抵触して違憲となるし、「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかという「性的指向」と称するものを審査して区別取扱いをするようなことがあれば、個人の内心に基づいて区別取扱いをすることになるから、憲法14条の「平等原則」に抵触して違憲となる。
そのことから、「性的指向に基づく別異取扱いを行うものである」との部分には、もともと婚姻制度が「性愛」を保護することを目的とする制度であったり、個人の内心に干渉するような制度として存在していても許されるかのように述べるものとなっているが、そのこと自体が誤った前提に立ったものということができる。
よって、「性的指向に基づく別異取扱いを行うものである」のように、「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかによって「別異取扱い」をすることが不当であるかという点よりも以前の問題として、「性愛」という特定の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的とした法制度を立法することや、個人の内心に干渉するような制度を立法することはできないという点で誤った主張である。
「被告は、本件諸規定は、性的指向それ自体に着目した区別を設けるためのものではなく、性的指向について中立的な規定であり、原告が主張する別異取扱いは、本件諸規定の適用の結果生じる事実上又は間接的な効果にすぎないと主張する。」
婚姻制度は「性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して区別するものではないし、「性愛」に基づいて婚姻制度を利用することを求めるものでも勧めるものではない。
そのため、被告(国)の主張として「本件諸規定は、性的指向それ自体に着目した区別を設けるためのものではなく、性的指向について中立的な規定であり、」と述べている部分は、その通りということができる。
「原告が主張する別異取扱いは、本件諸規定の適用の結果生じる事実上又は間接的な効果にすぎないと主張する。」との部分についても、もともと区別して扱っているという事実は存在しないし、婚姻制度は「性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、「性愛」に基づいて制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもないため、論じる必要のないものである。
この点、本件諸規定は、異性愛者であっても同性愛者であっても異性と婚姻することができるという意味で別異取扱いはなされていないが、婚姻の本質は、両当事者において永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもって共同生活を営むことにあるのであり、性的指向が向き合う者同士の婚姻をもって初めて本質を伴った婚姻といえるのであるから、性的指向が向かない相手との婚姻が認められるといっても、それは婚姻が認められないのと同義であって(異性愛者に同性との婚姻のみを認めるとしても意味がないのと同じことである。)、同性愛者にとって同性との婚姻が認められていないということは、性的指向により別異取扱いがなされていることに他ならず、原告らの主張は採用できるものであり、これに反する被告の主張は採用しない。
【筆者】
「本件諸規定は、異性愛者であっても同性愛者であっても異性と婚姻することができるという意味で別異取扱いはなされていないが、」の部分について検討する。
ここでは「異性愛者」と「同性愛者」が取り上げられているが、婚姻制度は「性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や、「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いをするものではないし、「性愛」に基づいて制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもないため、そもそも「異性愛者」や「同性愛者」を称する者を対象として設けられているわけでもない。
これは、婚姻制度は個々人の「性愛」には一切関知していないからである。
そのため、婚姻制度(男女二人一組)を適法に利用する意思があるのであれば、どのような思想、信条、信仰、感情を有する者であるとしても、婚姻制度を利用することが可能であり、当然、ここでいう「同性愛者」を称する者についても利用することが可能である。
そのため、「同性愛者」であることを理由として「別異取扱い」が行われているという事実はない。
これについては、「同性愛者」を称する者だけでなく、「異性愛者」、「両性愛者」、「全性愛者」、「近親性愛者」、「多性愛者」、「小児性愛者」、「老人性愛者」、「死体性愛者」、「動物性愛者」、「対物性愛者」、「対二次元性愛者」、「無性愛者」などを称する者であるとしても同様であるし、また、「キリスト教徒」、「イスラム教徒」、「ユダヤ教徒」、「ゾロアスター教徒」、「仏教徒」、「神道を信じる者」、「武士道を重んじる者」、「軍事オタク」、「鉄道オタク」、「アニメオタク」、「アイドルオタク」、「ADHD」、「アスペルガー」、「自閉症」、「サイコパス」、「統合失調症」を称する者であっても同様であり、それらを称する者であることを理由として「別異取扱い」をしているという事実はない。
よって、「別異取扱いはなされていない」との部分は妥当であるといえる。
「婚姻の本質は、両当事者において永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもって共同生活を営むことにあるのであり、性的指向が向き合う者同士の婚姻をもって初めて本質を伴った婚姻といえるのであるから、性的指向が向かない相手との婚姻が認められるといっても、それは婚姻が認められないのと同義であって(異性愛者に同性との婚姻のみを認めるとしても意味がないのと同じことである。)、同性愛者にとって同性との婚姻が認められていないということは、性的指向により別異取扱いがなされていることに他ならず、」との部分について検討する。
「婚姻の本質は、両当事者において永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもって共同生活を営むことにあるのであり、」との部分を検討する。
この文は、最高裁判決が「婚姻の本質は、両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもつて共同生活を営むことにある」(昭和62年9月2日・PDF)と説明していることを引用しているつもりのようである。
しかし、最高裁判決の文面では「両性」と明確に書かれているが、これが「両当事者」に変えられている。
これは、最高裁判決では「男女」であることを前提として「両性」の文字を使っているにもかかわらず、その「男女」の要素を意図的に無視し、「両当事者」のように「二人一組」の意味に変更しようとしているのである。
これは、最高裁判決の中で前提となっている事柄を無視し、文面を歪めて利用するものであり、この判決を書いた裁判官が望む特定の結論を導き出すために恣意的な判断を行っていることが考えられる。
このような引用元において前提となっている事柄から切り離して文を用いようとすることは、規範の意味を曖昧化させたり、流動化させることとなり、法的安定性を損なわせることとなるため不適切である。
法解釈は論理的整合性を積み重ねることによって結論を正当化することが可能となるのであり、このような恣意的に文言を変更するような手続きを経た上で何らかの結論を導き出そうとしても、その結論は前提となっている事柄から断絶することになり、その結論を正当化することはできない。
司法権を行使するにあたっては、その事件を担当している裁判官の個人的な思いや恣意的な判断によって内容が歪められるようなことがあってはならない。
ここでは最高裁判決の「両性」の文言が「両当事者」に変えられている。
「両性」の「両」の文字は、「男性と女性」の二つの性別を取り上げる意味として用いられているものであるにもかかわらず、これを「両当事者」に変えた場合には、「両」の文字の意味は「二人」の意味に変わることになる。
これは同じ「両」の文字が残っているとしても、指し示している対象が「性別」から「人数」の意味に変わっており、文字が持つ意味が変化させられている。
しかし、これは「両」の文字が残っているとしても、その文字の意味がもともと「人数」を示す意味で使われていたものではないにもかかわらず、漢字が残っていることを利用して別の意味に変えることができるかのような論じ方をするものであり、妥当でない。
このような「両」の文字を「性別」から「二人」の意味に変えてもよいと考えている背景には、なぜ「二人一組」であるのかその根拠を説明しないままに論じる「カップル信仰論」があると考えられる。
【参考】私たちは「重婚」を認められるか…?「同性婚」問題の先に浮かび上がる「多様性をめぐる根本的な難点」 2023.06.27
このような、理由もなく「二人一組」を前提として考えればそれで済むかのような認識に基づいて論じることは、特定の国々や文化圏、ロマンチック・ラブ・イデオロギーなどの法制度とは別に形成された何らかの文化、特定の宗教団体の教義などを前提に考えてしまっていると考えられ、法律論として妥当なものであるとはいえない。
最高裁判決が示している「婚姻の本質は、両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもつて共同生活を営むことにある」という文面は、具体的な法律上の婚姻制度の枠組みが存在することを前提として、その制度の内容を読み解いた際に、その制度を利用する者の法的な権利・義務の結び付きによる法律関係の状態を簡潔に示したものである。
その理由は、法律上の具体的な婚姻制度の枠組みと下記のように対応するからである。
◇ 「両性」との部分は、婚姻制度が「男性」と「女性」を要件としていることから導かれる。
◇ 「永続的な」との部分は、婚姻制度には有効期限がなく、利用者が死亡するまで利用することができるという点から導かれる。
(もし婚姻制度が改正されて有効期限が定められることがあるとすれば、この『永続的な』との説明は根拠を失ってなくなることになる。)
◇ 「精神的及び肉体的結合を目的として」との部分は、婚姻制度が相互の協力を求めていることや、「貞操義務」があることから導かれる。
(『貞操義務』のある制度を読み解くことによって『肉体的結合』と表現しているのであり、もし『貞操義務』がなければ『肉体的結合』という表現は導かれないことになる。)
◇ 「共同生活を営む」との部分は、婚姻制度が「同居義務」を定めていることから導かれる。
そのため、この「婚姻の本質」と称している説明は、具体的な婚姻制度の存在を前提とするものであり、「婚姻」という文言そのものから直ちに導かれるという性質のものではないし、婚姻制度よりも上位の概念として存在するものでもないし、婚姻制度についての「① 国の立法目的」を示したものでもない。
よって、この「婚姻の本質」と称する説明を用いて、婚姻制度の中に含めることのできる人的結合関係の範囲を導き出そうとすることは誤りである。
「性的指向が向き合う者同士の婚姻をもって初めて本質を伴った婚姻といえるのであるから、性的指向が向かない相手との婚姻が認められるといっても、それは婚姻が認められないのと同義であって」との部分について検討する。
「性的指向が向き合う者同士の婚姻をもって初めて本質を伴った婚姻といえるのであるから、」との部分を検討する。
この「本質」の文言は、上記の「婚姻の本質」の文言を指すものとして使われている。
そのため、ここで「性的指向が向き合う者同士の婚姻をもって初めて本質を伴った婚姻といえる」としている部分は、この判決の「婚姻の本質」と称する説明の中に「性的指向」と称するものと関係する内容が含まれていることを前提としていることになる。
このことから、この判決は、「婚姻の本質」と称する説明の中の「精神的及び肉体的結合」の部分を文学的な語感に基づいて読み解くことを試み、「恋愛・性愛」に対応するものであるかのように考えているようである。
そして、「婚姻の本質」と称する説明の意味を、「両当事者において永続的な」「恋愛・性愛」「を目的として真摯な意思をもって共同生活を営むことにある」と捉えているようである。
これにより、「性的指向が向き合う者同士」であることが「本質を伴った婚姻といえる」ための条件であると考えているようである。
しかし、そもそも婚姻制度は「恋愛・性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、個々人が「恋愛・性愛」の思想、信条、信仰、感情を有するか否かや、「恋愛・性愛」の思想、信条、信仰、感情を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いをするものではないし、「恋愛・性愛」の思想、信条、信仰、感情に従って制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもない。
婚姻制度は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として一般的・抽象的にその間で自然生殖の可能性のある「一人の男性」と「一人の女性」を法的に結び付け、その関係に対して一定の優遇措置を行うことにより、立法目的の達成を目指すものとしており、この法的な枠組みには「相互の協力」、「貞操義務」、「同居義務」が設定されているが、個々人の「恋愛・性愛」の有無や、「恋愛・性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかなど、一切関知していない。
これは、そもそも国家権力が人の内面に存在する「恋愛・性愛」の思想、信条、信仰、感情に対して干渉するものとして法制度を立法する必要そのものが存在しないからである。
また、もし個々人の内面である「恋愛・性愛」の思想、信条、信仰、感情に干渉する法律を立法した場合には、19条の「思想良心の自由」や、20条1項前段の「信教の自由」に抵触して違憲となる。
他にも、特定の「恋愛・性愛」の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的して法制度を立法することは、20条1項後段・3項、89条の「政教分離原則」に抵触して違憲となる。
よって、この判決は「婚姻の本質」と称する説明の「精神的及び肉体的結合」の部分を「恋愛・性愛」の意味であるかのように考えて説明しているようであるが、そもそも法制度が「恋愛・性愛」という特定の思想、信条、信仰、感情を保護するものとして存在しているとしてもそれが許されるかのような前提の下に論じていること自体が誤りとなる。
また、婚姻制度(男女二人一組)の要件を満たして制度を利用する意思があれば「性的指向」と称するものにかかわらず誰でも制度を利用することが可能である。
そのため、この判決が「性的指向が向き合う者同士」であることによって「本質を伴った婚姻といえる」のように述べていることは、婚姻制度(男女二人一組)を利用する者が法律上の要件を満たして制度を利用する意思を有しているにもかかわらず、それとは別にこの判決が独自に「性的指向が向き合う者同士」であるかという別の条件を加えるものとなっており、法律の内容に反した違法な判断であるといえる。
このような主張を前提とすれば、婚姻制度(男女二人一組)を利用する者について、個々人の「性的指向」によって「本質を伴った婚姻」と「本質を伴っていない婚姻」に区別することを前提とすることになり、「性的指向が向き合う者同士」でない場合には「本質を伴っていない婚姻」(男女二人一組)として扱われることを意味し、その者たちが適法な法律関係を形成することができていないかのように認定するものということになるから、明らかに不当である。
「同性愛者」を称する者が婚姻制度(男女二人一組)の要件を満たし、婚姻意思を有して適法に制度を利用しているとしても、それについて「性的指向が向き合う者同士」ではないことを理由に「本質を伴った婚姻」にはならないと述べていることを意味するのであり、法律論ではないことを述べる不当な説明となっている。
もしこれが法律論として述べたものではないとすれば、裁判官が個人的に「性的指向が向き合う者同士」で婚姻制度を利用している場合とそうでない場合との間に優劣を与えようとするものであり、不当な評価である。
実際、「同性愛者」を称する者であるとしても、「男女二人一組」の婚姻制度を利用している事実は認められる。
「同性愛者」を称する者であるとしても、婚姻制度の要件に従って、婚姻意思を有して適法に制度を利用しているのであれば、その法的な地位は完全なものであり、それを否定されるいわれはないのである。
このような「性的指向が向き合う者同士」でない場合には「本質を伴っていない」などという判断は、婚姻制度を利用する者の内心に干渉するものでもあるから、憲法19条の「思想良心の自由」、20条1項前段の「信教の自由」に抵触して違憲である。
裁判所が婚姻制度を利用する者の「性的指向」と称するものを問うことそのものが内心に対する不当な干渉といえるのである。
その他、上記でも述べたが、「婚姻の本質」と称する説明は、具体的な婚姻制度が存在することを前提として、その婚姻制度を利用する者の法律関係の状態を簡潔に述べたものである。
そのため、婚姻制度(男女二人一組)の要件を満たし、婚姻意思を有して婚姻関係を継続しているのであれば、最高裁判決が示した意味での「婚姻の本質」を満たしており、「本質を伴った婚姻」であるということができる。
そこでは、この判決がいうような「性的指向が向き合う者同士」であることは一切求められていない。
よって、婚姻制度(男女二人一組)を利用するに際して「性的指向が向き合う者同士」であるかどうかで思い悩む必要はないし、初めから「性的指向が向き合う者同士」でない場合や「性的指向」が途中で変わる場合があったとしても他者から「本質を伴っていない婚姻」などと非難されることもないし、婚姻制度を利用することによって自身の「性的指向」を審査されたりどれか一つに決めつけられたりする恐れもないし、裁判所から「性的指向が向き合う者同士」であるかどうかを問われることもない。
もし国家権力によって「性的指向が向き合う者同士」であることを問われた場合には、それは内心に対する不当な干渉であり、憲法19条の「思想良心の自由」、20条1項前段の「信教の自由」に抵触して違憲となるものである。
「性的指向が向かない相手との婚姻が認められるといっても、それは婚姻が認められないのと同義であって」との部分を検討する。
婚姻制度は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「生殖と子の養育」の観点から一般的・抽象的にその間で自然生殖を想定することができる「男性」と「女性」の組み合わせに対して「貞操義務」を設けるなど一定の形式で法的に結び付けるものとして設けられた制度である。
これは、「性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかという「性的指向」と称するものによって区別取扱いをする制度ではないし、「性愛」に基づいて制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもない。
よって、「性的指向が向かない相手との婚姻が認められる」ことは、そのまま「婚姻が認められ」ているものということができるのであり、それを「婚姻が認められないのと同義」と評価していることは、法律論として誤りである。
ここで、「性的指向が向かない相手との婚姻が認められる」ことについて「婚姻が認められないのと同義」と述べていることは、婚姻制度を利用する際に「性愛」を有していなければならず、かつ、「性的指向」と称するものが向く相手でなければならないという特定の価値観を前提とするものである。
これは、その価値観を有していなければ婚姻制度を利用することは認められないだとか、認めるべきではないだとか、「本質を伴った婚姻」ではなく正当でないなどと評価しようとするものであるから、婚姻制度を利用する者の内心に対して国家権力が介入しようとするものということができ、憲法19条の「思想良心の自由」、20条1項前段の「信教の自由」に抵触して違憲である。
よって、「婚姻」は「認められ」ているということができ、「婚姻が認められないのと同義」と述べている部分は誤りである。
「(異性愛者に同性との婚姻のみを認めるとしても意味がないのと同じことである。)、」との部分を検討する。
まず、「異性愛者」とあるが、これはこの判決が「同性愛者」と対比する形で持ち出しているものである。
しかし、「異性愛者」と「同性愛者」の二分論で考えるという前提そのものが特定の価値観に基づく分類に過ぎないし、そもそも人の内心を取り上げて分類し、その分類に基づいて区別して考えることが許されるかのように論じていることそのものが妥当でない。
そのため、個々人を内心に基づいて分類し、区別して考えていること自体が、法律論として誤りである。
「同性との婚姻」との部分であるが、「婚姻」は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために「生殖と子の養育」の観点からその間で自然生殖を想定することができる「男性」と「女性」の組み合わせに対して「貞操義務」などの一定の形式で法的に結び付けるものとして設けられており、「同性」間の人的結合関係については、その間で生殖を想定することができず、「生殖と子の養育」の趣旨を満たすものではないことから、「婚姻」とすることはできない。
そのため、「同性」との間では「婚姻」は成立せず、ここで「同性」との間で「婚姻」が成立することを前提として「同性との婚姻」と記載されている部分は誤りとなる。
この「異性愛者に同性との婚姻のみを認めるとしても意味がないのと同じことである。」との文は、「同じこと」と述べているように、「異性愛者」と「同性愛者」を対比する文脈の中で論じられているものである。
そのため、この「異性愛者に同性との」と書かれている部分は、もともと「同性愛者に異性との」を指していることを前提としている。
つまり、本来は「同性愛者に異性との婚姻のみを認めるとしても意味がない」という趣旨の文が存在することを前提として、「同性愛者に異性との」の部分を「異性愛者に同性との」に置き換えて、「同じこと」と述べているということである。
しかし、そのもともとの「同性愛者に異性との婚姻のみを認めるとしても意味がない」との理解には問題がある。
まず、「同性愛者」を称する者であるとしても、婚姻制度(男女二人一組)の要件を満たして婚姻意思を有しているのであれば、適法に婚姻することが可能である。
実際に、「同性愛者」を称する者であるとしても、婚姻制度(男女二人一組)を利用している事実は認められる。
それにもかかわらず、この判決では、「異性愛者に同性との婚姻のみを認めるとしても意味がないのと同じことである。」と述べることによって、それと対比する形で、暗に「同性愛者に異性との婚姻のみを認めるとしても意味がない」と述べており、「同性愛者」を称する者が婚姻制度(男女二人一組)を利用することや、利用している事実を指し示して「意味がない」と断じるものとなっている。
これは、婚姻制度(男女二人一組)を利用する者の内心に対して干渉し、それが「同性愛者」を称する者である場合には「意味がない」と評価するものであるから、憲法19条の「思想良心の自由」や20条1項前段の「信教の自由」に抵触して違憲である。
また、婚姻制度(男女二人一組)は法律上の要件を満たして婚姻意思を有しているのであれば、すべての者は平等に取り扱われるにもかかわらず、それが「同性愛者」を称する者である場合には「意味がない」と断じるものであるから、憲法14条1項の「平等原則」における「法適用の平等」に反して違憲である。
法制度を利用する者の内心を審査して、その審査の結果特定の内心を有する者を取り上げて「意味がない」などと断じることは、極めて不当である。
「同性愛者にとって同性との婚姻が認められていないということは、性的指向により別異取扱いがなされていることに他ならず、」(カッコ内省略)との部分であるが、誤りである。
まず、婚姻制度は「男女二人一組」などの要件を満たして婚姻意思を有しているのであれば、どのような思想、信条、信仰、感情を有しているものであるとしても利用することが可能である。
そのため、たとえ「同性愛者」を称する者であるとしても、婚姻制度(男女二人一組)の要件を満たして婚姻意思を有しているのであれば、適法に婚姻することが可能である。
よって、婚姻制度(男女二人一組)は、「性的指向」と称するものによって「別異取扱い」を行っているという事実は存在しない。
もし「同性愛者」を称する者が婚姻制度(男女二人一組)の要件を満たして婚姻意思を有して制度を利用しようとしているにもかかわらず、それを「同性愛者」を称する者であることを理由としてその利用を拒んだり、否定するようなこと(この判決が上記で暗に『意味がない』と述べている部分はこれに当たる)があれば、ここでいう「性的指向により別異取扱いがなされていることに他なら」ないということができ、憲法14条の「平等原則」における「法適用の平等」に抵触して違憲となるが、婚姻制度はそのような制度ではない。
これに対して、この文では、婚姻制度を利用する場合には「性愛」を抱いて利用しなければならないだとか、「性愛」に基づく形で利用するべきであるとか、「性愛」に基づく形で制度を利用することこそが正当であるという価値観を前提として、「同性愛者」を称する者は「男女二人一組」の婚姻制度を利用してはならないだとか、利用するべきではないだとか、利用することは正当でないと考え、その結果、「同性愛者」を称する者について「性的指向により別異取扱いがなされている」と認めようとするものとなっている。
しかし、婚姻制度は「性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査するものではないし、「性愛」に基づいて制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもない。
そのため、「同性愛者」を称する者を取り上げて「性的指向により別異取扱いがなされている」と認めようとしていることは、「同性愛者」を称する者が婚姻制度(男女二人一組)を利用しているはずがないとか、利用してはならないとか、利用することは正当ではないという価値観を基にするものであり、「同性愛者」を称する者が婚姻制度(男女二人一組)を利用することに対して否定的な意味合いを含むものとなっており、不当な主張である。
これは、「同性愛者」を称する者に対して特定の価値観を押し付けるものということができ、憲法19条の「思想良心の自由」、憲法20条1項の「信教の自由」に抵触して違憲である。
法制度は個々人の思想、信条、信仰、感情に対して中立的でなければならないのであり、特定の価値観に基づいて制度を利用することを求めるようなことがあってはならないし、勧めるようなこともしてはならない。
「原告らの主張は採用できるものであり、これに反する被告の主張は採用しない。」との部分であるが、「原告らの主張」が妥当でないことと、「被告の主張」が妥当であることは、一段落前で解説した通りである。
よって、「原告らの主張」を「採用できる」とし、「被告の主張」を「採用しない」とした判断は誤っているといえる。
そうすると、婚姻及び家族に関わる立法として、本件諸規定は、性的指向という、ほとんどの場合、生来的なもので、本人にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由として、婚姻に対する直接的な制約を課すことになっているのであり、その合理的な根拠の有無について以上のような事柄の性質を十分考慮に入れた上で検討をすることが必要である。
【筆者】
「婚姻及び家族に関わる立法として、」の部分について検討する。
ここでいう「同性間の人的結合関係」については、「婚姻」には含まれないし、「親子」や「親子」の関係を基本とした「兄弟」「姉妹」などにも当たらないため「家族」にも含まれない。
そのため、「婚姻及び家族に関わる立法」とはいえず、これが「婚姻及び家族に関わる立法」であるかのような前提で論じていること自体が誤りである。
「本件諸規定は、性的指向という、ほとんどの場合、生来的なもので、本人にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由として、婚姻に対する直接的な制約を課すことになっているのであり、」との部分について検討する。
婚姻制度は「性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかという「性的指向」と称するものを審査して区別取扱いするものではないし、「性愛」に基づいて制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもない。
よって、「性的指向」と称するものによって婚姻制度(男女二人一組)を利用することを「制約」しているという事実はなく、「婚姻に対する直接的な制約を課すことになっている」との認識は誤りである。
「ほとんどの場合、生来的なもので、本人にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由として、」との部分についても、そもそも「性的指向」と称するものによって婚姻制度(男女二人一組)を利用することを「制約」しているという事実がないことから、その性質がどのようなものであるかについても論じる必要のないものである。
「直接的な制約」の意味であるが、これは「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査し、その審査の結果に応じて何らかの制約を行う場合のことをいう。
例えば、「小児性愛」であるか否かを審査して、その審査の結果に応じて教員採用試験を受験することを禁じるなどして「職業選択の自由」を制約するなどの場合がこれに当たるということができる。
【参考】<わいせつ行為で処分された教員は9年連続200人以上>愛知医科大准教授が小児性愛障害診断テストを開発中「日本版DBSだけでは子どもへの性犯罪を防げない」 2023.09.28
しかし、婚姻制度については、「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかという「性的指向」と称するものについて一切審査しておらず、その審査の結果に基づいて区別取扱いをするものとはいえないため、「制約」は存在しておらず、それが「直接的」であるか否かについても、そもそも「制約」が存在しないという点によって検討する前提にないものである。
よって、「婚姻に対する直接的な制約を課すことになっている」との部分は、この意味でも誤りである。
「その合理的な根拠の有無について以上のような事柄の性質を十分考慮に入れた上で検討をすることが必要である。」との部分について検討する。
婚姻制度は「性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査するものではないし、「性愛」に基づいて婚姻制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもない。
そのため、「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかという「性的指向」と称するものによる「別異取扱い」は存在しない。
よって、「性的指向」と称するものによって「別異取扱い」があることを前提として、「その合理的な根拠の有無」を検討しようとしている部分は誤りである。
また、もし「性的指向」と称するものに基づいて「別異取扱い」を行っていることになれば、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して区別し、その区別に従う形で婚姻制度の利用の可否を決めていることになるが、それは個々人の内心に基づいて人を区別することになるから、憲法14条の「平等原則」に抵触して違憲となるし、国家権力が個々人の内心に対して干渉する制度ということになるから、憲法19条の「思想良心の自由」や憲法20条1項前段の「信教の自由」に抵触して違憲となるし、婚姻制度が「性愛」という特定の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的としていることになるから、20条1項後段・3項、89条の「政教分離原則」に抵触して違憲となる。
よって、もし「性的指向」と称するものに基づいて「別異取扱い」を行う法制度が存在している場合には、そのこと自体が違憲となるのであり、この部分で婚姻制度が「性的指向」と称するものに基づいて「別異取扱い」を行う制度であることを前提としてその「合理的な根拠の有無」を論じようとしている部分は、そもそも「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかという「性的指向」と称するものに基づいて「別異取扱い」を行う制度が存在していても許されるかのように論じている部分が誤りであるし、「性愛」という特定の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的とした制度が存在していても許されるかのように論じている部分が誤りである。
「以上のような事柄の性質を十分考慮に入れた上で」との部分についても、法制度は思想、信条、信仰、感情に対して中立的でなければならず、「性愛」を保護することを目的とした制度が存在した場合には、それ自体で憲法に違反するため、それを「考慮に入れた上で検討をすること」はしてはならないのであり、これを「以上のような事柄の性質を十分考慮に入れた上で検討をすることが必要である。」と述べていることは誤りとなる。
この段落の言い回しは、下記の「再婚禁止期間大法廷判決」を参考としたものと思われる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
そうすると,婚姻制度に関わる立法として,婚姻に対する直接的な制約を課すことが内容となっている本件規定については,その合理的な根拠の有無について以上のような事柄の性質を十分考慮に入れた上で検討をすることが必要である。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
損害賠償請求事件 最高裁判所大法廷 平成27年12月16日 (PDF) (再婚禁止期間大法廷判決)
しかし、「再婚禁止期間大法廷判決」が「男女二人一組」の「婚姻」に関するものであるため、「婚姻及び家族」に含まれる事案であったのに対し、この名古屋地裁判決のいう「同性間の人的結合関係」は「婚姻及び家族」には含まれないことから、この「再婚禁止期間大法廷判決」の示した基準を用いることができるとする前提にない。
そのため、これを持ち出して検討しようとしていること自体が誤りである。
ウ そして、こうした事柄の性質を踏まえ、国会の立法裁量の範囲を超えるものとみざるを得ないような場合に当たるか否かという点については、既に検討したとおり、本件諸規定が、同性カップルに対して、その関係を国の制度によって公証し、その関係を保護するのにふさわしい効果を付与するための枠組みすら与えていないという限度で、このような場合に当たるというべきであるから、その限度で、憲法24条2項に違反すると同時に、憲法14条1項にも違反するものといわざるを得ない。
【筆者】
「こうした事柄の性質を踏まえ、」との部分であるが、上記で述べたように「性的指向」と称するものによる「別異取扱い」は存在していないため、「事柄の性質」についての理解を誤っている。
そして、「別異取扱い」が存在しない場合には、そもそも憲法14条1項に違反することはないことから、「憲法14条1項にも違反するものといわざるを得ない。」と述べていることは誤りである。
「国会の立法裁量の範囲を超えるものとみざるを得ないような場合に当たるか否かという点については、既に検討したとおり、本件諸規定が、同性カップルに対して、その関係を国の制度によって公証し、その関係を保護するのにふさわしい効果を付与するための枠組みすら与えていないという限度で、このような場合に当たるというべきであるから、」との部分について検討する。
「既に検討したとおり、」としている「国会の立法裁量の範囲を超えるものとみざるを得ないような場合に当たるか否か」という文は、「夫婦同氏制大法廷判決」に記載された文と同じくするものである。
しかし、この「夫婦同氏制大法廷判決」とこの名古屋地裁判決とでは事案が異なっており、この名古屋地裁判決で問われている内容に対して「夫婦同氏制大法廷判決」の文面を用いて結論を導き出そうとすることは誤りである。
まず、「夫婦同氏制大法廷判決」で問われているのは、憲法24条2項の「婚姻及び家族」の枠組みの「要請」に従って立法された法律上の具体的な制度の内容が、「個人の尊厳」と「両性の本質的平等」を満たすか否かである。
そして、その法律上の具体的な制度の内容が、「個人の尊厳」と「両性の本質的平等」を満たすか否かを検討するものとして、「国会の立法裁量の範囲を超えるものとみざるを得ないような場合に当たるか否か」の判断が行われているものである。
法律上の具体的な制度の内容が、「個人の尊厳」や「両性の本質的平等」を満たさない場合には「国会の立法裁量の範囲を超えるものとみざるを得ないような場合に当たる」として違憲となり、法律上の具体的な制度の内容が、「個人の尊厳」や「両性の本質的平等」を満たす場合には「国会の立法裁量の範囲を超えるものとみざるを得ないような場合」には当たらず、合憲となるというものである。
これに対して、この名古屋地裁判決で問われているのは、憲法24条2項の「家族」が、「親子」や「親子」の関係を基本とした「兄弟」「姉妹」などに含まれない「同性間の人的結合関係」を対象とした制度を立法することを「要請」しているか否かである。
これは、「要請」していればその制度がないことは違憲となり、「要請」していないのであればその制度がないことは合憲となるものである。
これは、憲法24条の「婚姻及び家族」の枠組みそのものが問われており、その枠組みが有する規範を明らかにすることによって「要請」の有無を検討することが必要である。
ただ、検討の結果、もし「要請」していることになれば、その制度がないことは違憲となるため、「国会の立法裁量」の余地なくその制度を立法することが求められることになる。
すると、この場合には「国会の立法裁量の範囲を超えるものとみざるを得ないような場合に当たるか否か」の判断を行う余地もない。
逆に、検討の結果、「要請」していないのであれば、国会に対して何らの義務付けも行われていないため、その制度がないことが「国会の立法裁量」の範囲を超えるか否かを問う前提にない。
すると、やはり「国会の立法裁量の範囲を超えるものとみざるを得ないような場合に当たるか否か」を判断する余地はない。
このように、「要請」しているか否かを検討したとしても、そのいずれにせよこの名古屋地裁判決で問われている事案において、「国会の立法裁量」の問題は関わらないものである。
このため、この名古屋地裁判決の事案について、「国会の立法裁量」が関わるかのような前提で「国会の立法裁量の範囲を超えるものとみざるを得ないような場合に当たるか否か」の判断によって結論を導き出すことができるかのように述べている部分が誤りである。
よって、憲法24条2項の「婚姻及び家族」の枠組みの「要請」の内容が問われているこの名古屋地裁判決の事案に対して、憲法24条2項の「婚姻及び家族」の枠組みの「要請」に従って立法された法律上の具体的な制度の内容が「個人の尊厳」と「両性の本質的平等」を満たすか否かが審査され、それによって「国会の立法裁量の範囲を超えるものとみざるを得ないような場合に当たるか否か」の判断が導かれるという「夫婦同氏制大法廷判決」の事案を当てはめようとすることは、もともと解釈の次元が異なる問題を同一視して当てはめを行おうとしている点で、誤りである。
「本件諸規定が、同性カップルに対して、その関係を国の制度によって公証し、その関係を保護するのにふさわしい効果を付与するための枠組みすら与えていないという限度で、このような場合に当たるというべきであるから、」との部分を検討する。
この名古屋地裁判決で問われているのは、憲法24条2項の「婚姻及び家族」の枠組みがここでいう「同性間の人的結合関係」を対象とする制度を立法することを「要請」しているか否かである。
ここでいう「同性カップル」という「同性間の人的結合関係」については、「婚姻」ではないし、「親子」や「親子」の関係を基本とした「兄弟」「姉妹」などでもないことから「家族」にも含まれない。
この結果、憲法24条2項の「婚姻及び家族」の枠組みは、ここでいう「同性間の人的結合関係」を対象とした制度を立法することを「要請」していない。
また、憲法24条2項は「婚姻及び家族」の制度を立法することを「要請」するものではあるが、それ以外の制度を立法することを「要請」するものではない。
そのため、憲法24条2項は、ここでいう「同性カップルに対して、その関係を国の制度によって公証し、その関係を保護するのにふさわしい効果を付与するための枠組み」という制度を立法することを「要請」するものではない。
この文はその後、「国会の立法裁量の範囲を超えるものとみざるを得ないような場合に当たるか否か」の問いに答える形で「このような場合に当たるというべきである」と述べているが、上記でも解説したように、そもそもこの名古屋地裁判決の中で憲法24条2項の「婚姻及び家族」の枠組みの「要請」の有無が問われている論点では、「国会の立法裁量」は関わらないのであり、この「国会の立法裁量」があることを前提として、その「国会の立法裁量の範囲を超えるものとみざるを得ないような場合に当たるか否か」を論じていることそのものが論理的に誤っており、それを基にした「このような場合に当たるというべきである」との結論についても、意味を成さないものということができる。
よって、これを「要請」していることを意味する意図で「すら与えていないという限度で、このような場合に当たるというべきである」のように述べて、憲法24条2項に違反するという指摘を試みていることは誤りである。
「その限度で、憲法24条2項に違反すると同時に、憲法14条1項にも違反するものといわざるを得ない。」との部分について検討する。
「その限度で、」とあるが、これは「本件諸規定が、同性カップルに対して、その関係を国の制度によって公証し、その関係を保護するのにふさわしい効果を付与するための枠組みすら与えていないという限度」を指すものである。
◇ 憲法24条2項
まず、「憲法24条2項に違反する」との部分を検討する。
「憲法24条2項」に違反するといえるためには、前提として「憲法24条2項」の「婚姻及び家族」の枠組みが、「同性カップルに対して、その関係を国の制度によって公証し、その関係を保護するのにふさわしい効果を付与するための枠組み」という制度を立法することを「要請」していることが必要である。
しかし、ここでいう「同性カップル」という「同性間の人的結合関係」については、「婚姻」ではないし、「親子」や「親子」の関係を基本とした「兄弟」「姉妹」などでもないことから「家族」にも含まれず、「憲法24条2項」の「婚姻及び家族」には含まれない。
そのため、「憲法24条2項」の「婚姻及び家族」の枠組みは、ここでいう「同性カップルに対して、その関係を国の制度によって公証し、その関係を保護するのにふさわしい効果を付与するための枠組み」という制度を立法することを「要請」するものではない。
よって、「同性カップルに対して、その関係を国の制度によって公証し、その関係を保護するのにふさわしい効果を付与するための枠組み」と称する制度が存在しないことが「憲法24条2項に違反する」ということにはならない。
そのことから、「その限度で、憲法24条2項に違反する」のように、「本件諸規定が、同性カップルに対して、その関係を国の制度によって公証し、その関係を保護するのにふさわしい効果を付与するための枠組みすら与えていないという限度」「で、憲法24条2項に違反する」かのように述べていることは誤りとなる。
◇ 憲法14条1項
次に、「憲法14条1項にも違反するものといわざるを得ない。」との部分を検討する。
まず、この文が書かれている始めの部分では、「こうした事柄の性質を踏まえ、」とある。
そのため、この文は、この「⑷ 憲法14条1項に違反するかについて」の項目で問われている「別異取扱い」の存否について、「別異取扱い」が存在するとするこの判決の考えを前提としていることが示されている。
そして、その「別異取扱い」があることを前提として、「憲法14条1項」に違反するか否かについての「合理的な根拠の有無」を検討していくものとなっている。
しかし、その根拠として持ち出しているのは、この判決が「憲法24条2項」に違反するか否かの論点で検討することになると考えている「国会の立法裁量の範囲を超えるものとみざるを得ないような場合に当たるか否か」である。
そのため、その検討が行われている部分を見ると、「⑶ 憲法24条2項に違反するかについて」の項目の「ク」の第二段落で「憲法24条2項に違反するものである。」と結論付ける際に、「ク」の第一段落で「個人の尊厳の要請に照らして合理性を欠くに至っているものといわざるを得ず、国会の立法裁量の範囲を超えるものとみざるを得ないような場合に当たるというべきである。」と述べられていることから、ここで「国会の立法裁量の範囲を超えるものとみざるを得ないような場合に当たるか否か」について「当たるというべきである。」と判断する根拠となっているのは、「個人の尊厳」の文言である。
そのことから、この「憲法14条1項」に違反するか否かについての「合理的な根拠の有無」を判断する根拠としているものは、「憲法24条2項」の「個人の尊厳」の文言ということになる。
しかし、「憲法24条2項」の「個人の尊厳」の文言は、憲法24条2項の「婚姻及び家族」の対象となる場合にのみ適用されるものであり、そもそも「婚姻及び家族」に含まれていない場合には、この「個人の尊厳」が適用される前提にない。
ここでいう「同性カップル」という「同性間の人的結合関係」については、「婚姻」ではないし、「親子」や「親子」の関係を基本とした「兄弟」「姉妹」などでもないことから「家族」にも含まれず、「憲法24条2項」の「婚姻及び家族」には含まれないのであり、「個人の尊厳」が適用される前提にはない。
また、そもそもこの名古屋地裁判決で「⑶ 憲法24条2項に違反するかについて」の項目で問われているのは、「憲法24条2項」の「婚姻及び家族」が、ここでいう「同性カップル」という「同性間の人的結合関係」を対象とした制度を立法することを「要請」しているか否かであり、「夫婦同氏制大法廷判決」で問われたような、憲法24条2項の「婚姻及び家族」の枠組みの「要請」に従って立法された法律上の具体的な制度の内容が「個人の尊厳」と「両性の本質的平等」を満たすか否かではない。
そのため、「⑶ 憲法24条2項に違反するかについて」の項目において、「夫婦同氏制大法廷判決」の文面を用いて判断していることそのものが誤っており、結果として「個人の尊厳」を満たすか否かの判断を試みていることそのものが論点を見誤ったものとなっている。
よって、この「憲法14条1項」に違反するか否かの判断において、「⑶ 憲法24条2項に違反するかについて」の項目で「憲法24条2項」に違反するか否かについての判断として述べられている「個人の尊厳」を持ち出すことは、「憲法14条1項」の審査として憲法上の他の条文を用いることが妥当でないことに加えて、そもそもこの判決が論点を見誤って述べている文面を根拠として判断を試みるものということができ、誤りということになる。
ただ、これとは別に、そもそも今回の事例は「性的指向」と称するものによる「別異取扱い」は存在しないことから、「別異取扱い」が存在しないものを「憲法14条1項」で審査することはできないという点で、「憲法14条1項」に違反しないというものである。
これにより、「憲法14条1項にも違反するものといわざるを得ない。」と述べている部分は誤りとなる。
これは、「憲法14条1項」に違反するか否かを検討する際に、「別異取扱い」が存在する場合における「合理的な根拠の有無」についての判断を誤っているという論点ではなく、それ以前の「別異取扱い」の存否についての判断を誤ったことによって、結論を誤ったものである。
◇ 憲法24条2項と憲法14条1項
「憲法24条2項に違反すると同時に、憲法14条1項にも違反する」のように、「憲法24条2項」と「憲法14条1項」を並べて記載している。
ただ、このように並べて記載することによって、これら二つの規定をどのような関係性を持たせているのか読み解く必要がある。
まず、直前に「その限度で、」との文言があるが、これは「本件諸規定が、同性カップルに対して、その関係を国の制度によって公証し、その関係を保護するのにふさわしい効果を付与するための枠組みすら与えていないという限度」を指している。
そしてそれは、「国会の立法裁量の範囲を超えるものとみざるを得ないような場合に当たるか否かという点については、既に検討したとおり、」「このような場合に当たるというべきである」とする検討の中で述べられているものである。
このことから、この「憲法24条2項に違反する」という部分は、「既に検討した」ものとされていることから、この「⑷ 憲法14条1項に違反するかについて」の項目よりも前の「⑶ 憲法24条2項に違反するかについて」の項目で判断された事柄を述べているものということになる。
しかし、「⑶ 憲法24条2項に違反するかについて」の項目の「ク」の第二段落で「憲法24条2項に違反するものである。」と結論付ける際には、「ク」の第一段落で「個人の尊厳の要請に照らして合理性を欠くに至っているものといわざるを得ず、国会の立法裁量の範囲を超えるものとみざるを得ないような場合に当たるというべきである。」と述べているだけである。
ここには、「憲法14条1項」が規定している「平等」の観点と関わりのある文言は登場していない。
そのため、ここで「憲法14条1項にも違反する」と述べるとしても、「憲法24条2項に違反する」と述べる場合に根拠としているものとの間に重なり合う部分を見出すことができず、ここで「憲法24条2項に違反すると同時に、憲法14条1項にも違反する」のようにそれらを並べて記載していることに関連性は見られないことから、不必要であり、これを挙げていることそのものが妥当でない。
次に、「憲法24条2項」の「両性の本質的平等」の文言と、「憲法14条1項」の「平等原則」を関連させる意味で、「憲法24条2項に違反すると同時に、憲法14条1項にも違反する」のように述べているものであるかを検討する。
この判決でも、「⑶ 憲法24条2項に違反するかについて」の項目の「イ」の第一段落の第三文で、「憲法14条1項と憲法24条2項の関係をどのように理解するかについては見解が分かれ得る問題であるとしても、両条項が保護しようとした法益に重なり合う部分が存することは否定できないと考えられるから、」と述べられている部分は、これを検討する可能性について述べているものと考えられる。
しかし、「⑶ 憲法24条2項に違反するかについて」の項目で「憲法24条2項に違反するものである。」と結論を述べる際に用いられた根拠は「個人の尊厳の要請に照らして合理性を欠くに至っているものといわざるを得ず、国会の立法裁量の範囲を超えるものとみざるを得ないような場合に当たるというべきである。」という文であり、結局、判断の過程で「両性の本質的平等」には触れられていない。
そのため、「憲法24条2項」の「両性の本質的平等」の文言と「憲法14条1項」の「平等原則」を関連させようとする意図を見出すことはできない。
よって、この「⑷ 憲法14条1項に違反するかについて」の項目で、「憲法24条2項に違反すると同時に、」のように「憲法24条2項」を持ち出す必要そのものがないのであり、これを持ち出していることそのものが誤った論じ方であるといえる。
この「憲法24条2項に違反すると同時に、憲法14条1項にも違反するものといわざるを得ない。」の部分は、「再婚禁止期間大法廷判決」の言い回しを参考にしたものと思われる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3)以上の次第で,本件規定のうち100日超過部分が憲法24条2項にいう両性の本質的平等に立脚したものでなくなっていたことも明らかであり,上記当時において,同部分は,憲法14条1項に違反するとともに,憲法24条2項にも違反するに至っていたというべきである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
損害賠償請求事件 最高裁判所大法廷 平成27年12月16日 (PDF) (再婚禁止期間大法廷判決)
この「再婚禁止期間大法廷判決」の内容については、憲法24条2項の「婚姻及び家族」の枠組みに当てはまる事例であり、かつ、それが個人である「男性」と「女性」の間における「平等」が問われている問題であることから、憲法14条1項の「平等原則」と憲法24条2項の「両性の本質的平等」が同時に適用される事案であるということができる。
これに対して、この名古屋地裁判決の内容は、「同性間の人的結合関係」を対象とした制度が存在しないことが憲法に違反するか否かが問われている事案であり、これは「婚姻」ではないし、「親子」や「親子」の関係を基本とした「兄弟」「姉妹」などでもないため「家族」にも含まれず、そもそも憲法24条2項の「婚姻及び家族」の枠組みに当てはまらない事例である。
そのため、憲法24条2項の「両性の本質的平等」が適用される前提にはない。
よって、「再婚禁止期間大法廷判決」の言い回しを参考に述べることのできる前提になく、この言い回しと同様の形で憲法違反を述べるとしても、その内容は正当化することのできるものではない。
その他、国(行政府)は婚姻制度はパッケージとして定められているものであることから、その一部だけを切り出してそれを含む別の枠組みを設けていないことを憲法14条1項の「平等原則」に違反すると述べていることの誤りについて指摘している。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)このように、原判決は、本件諸規定が、同性カップルに対して、その関係を国の制度によって公証し、その関係を保護するのにふさわしい効果を付与するための枠組みすら与えていないことを殊更に問題視しているが、前記第4の3(2)で述べたとおり、そもそも控訴人らは、本件諸規定が同性婚を認めていないことが憲法14条1項に違反すると主張していたのであって、本件規定が、同性カップルに対して、その関係を国の制度によって公証し、その関係を保護するのにふさわしい効果を付与するための枠組みすら与えていないことを問題としていたわけではない。原判決のいう「同性カップルに対して、その関係を国の制度によって公証し、その関係を保護するのにふさわしい効果を付与するための枠組み」の立法不作為が憲法14条1項に違反するかについても、本来、控訴人の請求に理由があるか否かを判断するに当たって審理判断する必要のない事柄というべきである。
のみならず、本件諸規定は、憲法の定める婚姻を具体化するパッケージとして定められた規定であるから、その一部だけを切り出して、同性カップルに対して、その関係を国の制度によって公証し、その関係を保護するのにふさわしい効果を付与するための枠組みを設けるべきかということを本件諸規定と関連させて論じる性質のものではないと考えられる。これらの点で、原判決の問題の捉え方には根本的な誤りがあるというべきである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【名古屋・第1回】控訴答弁書 令和5年10月12日
この論点を整理して理解するためには、下記を踏まえる必要がある。
まず、憲法は「個人の尊厳」の原理に基づいており、自然人は「個人主義」の下に各々「自律的な個人」として生存していくことを前提としている。
それら個々人は、人的結合関係を形成、維持、解消するなどしながら自由に生活することが可能である。
そのような中、「婚姻」は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた枠組みであり、その法的効果や一定の優遇措置の内容は、その目的を達成するための手段として整合的な内容として定められている。
そして、憲法14条1項の「平等原則」によって制度の内容を審査する場合があるとしても、その審査の内容は、憲法14条1項は「個人権」であることから、第一に個人を基本とすることが必要であり、第二に何らの制度も利用していない状態を基準(スタンダード)として考えることが必要である。
よって、「婚姻制度を利用している者(既婚者)」が婚姻制度の立法目的を達成するための手段として不必要に過大な優遇措置を得ている場合には、「婚姻制度を利用していない者(独身者)」との間での比較において14条1項の「平等原則」に抵触して違憲となり、その不必要に過大な優遇措置に関する規定が個別に失効することによって格差が是正されることになる。
これに対して、この判決の内容は、憲法14条1項の「平等原則」の審査として比較する対象とすることのできない「カップル」という「二人一組」を取り上げている点で誤っているし、憲法14条1項に違反するとした場合においても、婚姻制度に設けられている法的効果や優遇措置の内容が個別に失効することによって格差が是正されるというものではなく、婚姻制度の内容を構成している一部分を切り出した別の枠組みを設けるべきであると述べるものとなっており、審査する際に前提となっている基準点(スタンダード)を見誤ったものということができる。
よって、国(行政府)の指摘は妥当である。
3 本件諸規定を改廃しないことが国家賠償法上違法であるかについて(争点2)
⑴ 国家賠償法1条1項は、国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が個々の国民に対して負担する職務上の法的義務に違反して当該国民に損害を加えたときに、国又は公共団体がこれを賠償する責任を負うことを規定するものであるところ、国会議員の立法行為又は立法不作為が同項の適用上違法となるかどうかは、国会議員の立法過程における行動が個々の国民に対して負う職務上の法的義務に違反したかどうかの問題であり、立法の内容の違憲性の問題とは区別されるべきものである。そして、上記行動についての評価は原則として国民の政治的判断に委ねられるべき事柄であって、仮に当該立法の内容が憲法の規定に違反するものであるとしても、そのゆえに国会議員の立法行為又は立法不作為が直ちに国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではない。
もっとも、法律の規定が憲法上保障され又は保護されている権利利益を合理的な理由なく制約するものとして憲法の規定に違反するものであることが明白であるにもかかわらず、国会が正当な理由なく長期にわたってその改廃等の立法措置を怠る場合などにおいては、国会議員の立法過程における行動が上記職務上の法的義務に違反したものとして、例外的に、その立法不作為は、国家賠償法1条1項の規定の適用上違法の評価を受けることがあるというべきである(最高裁昭和53年 第1240号同60年11月21日第一小法廷判決・民集39巻7号1512頁、最高裁平成13年 第82号、第83号、同年 第76号、第77号同17年9月14日大法廷判決・民集59巻7号2087頁、再婚禁止期間大法廷判決参照)。
【筆者】
そもそも憲法24条1項、2項、憲法14条に違反するものではないことから、「個々の国民に対して負う職務上の法的義務に違反」することはなく、国家賠償法上の問題を検討する必要はない。
前記2のとおり、本件諸規定は、同性カップルに対して、その関係を国の制度によって公証し、その関係を保護するのにふさわしい効果を付与するための枠組みを与えていないという限度で、憲法24条2項及び14条1項に違反するものである。そこで、以下、本件諸規定がこの限度で憲法の規定に違反するにもかかわらず、国会議員がその改廃等の立法措置を怠ったことが、例外的に国会賠償法1条1項の規定の適用上違法の評価を受けることがあるかについて、検討する。
【筆者】
「本件諸規定は、同性カップルに対して、その関係を国の制度によって公証し、その関係を保護するのにふさわしい効果を付与するための枠組みを与えていないという限度で、憲法24条2項及び14条1項に違反するものである。」との部分について検討する。
「憲法24条2項及び14条1項に違反するものである。」と述べていることから、「憲法24条2項」と「14条1項」をそれぞれ検討する。
◇ 憲法24条2項
まず、この訴訟で問われたのは、「憲法24条2項」の「家族」が、ここでいう「同性カップル」という「同性間の人的結合関係」を対象とする制度を立法することを「要請」しているか否かである。
そして、ここでいう「同性間の人的結合関係」については、「親子」や「親子」の関係を基本とした「兄弟」「姉妹」などではないことから、「家族」には含まれない。
そのため、「憲法24条2項」の「家族」は、ここでいう「同性間の人的結合関係」を対象とした制度を立法することを「要請」していないことから、その制度が立法されていないことが「憲法24条2項」に違反するということはない。
よって、この判決が「憲法24条2項」に「違反するものである」と述べていることは誤りである。
また、「同性カップルに対して、その関係を国の制度によって公証し、その関係を保護するのにふさわしい効果を付与するための枠組みを与えていないという限度で、」との部分についても、そもそも「憲法24条2項」の「家族」は、そのような制度を設けることを「要請」するものではないし、結果として「憲法24条2項」にも違反しないことから、「憲法24条2項」に違反する「限度」について述べようとしていることも誤りである。
◇ 憲法14条1項
次に、「14条1項」の「平等原則」に違反するか否かであるが、この判決は次の点で誤っている。
・「カップル」という「二人一組」を取り上げて比較することはできない
法律論上は、「権利能力」を有して法主体としての地位を認められている者同士しか比較することはできず、「二人一組」が「法人」としての法人格を取得していないのであれば、これらは個々の「自然人」が集まって人的結合関係を形成している状態として認識することが必要である。
よって、「自然人」の一人一人について、法制度を利用することができるか否かという観点から検討することは可能であるが、「二人一組」を取り上げて比較することが可能であるかのような前提で論じている部分は誤りである。
・「性的指向」と称するものによる区別取扱いは存在しない
「婚姻及び家族」の制度は、「性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査するものではないし、「性愛」に基づいて制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもない。
そのため、そもそも「性愛」に関わりのない制度であることから、「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかという「性的指向」と称するものによる区別取扱いをしているという事実がない。
そのことから、区別取扱いがある場合に「14条1項」の「平等原則」によって審査することが可能であるが、そもそも区別取扱いが無い場合には、その審査を行う前提を欠く状態となる。
よって、「14条1項」の「平等原則」に違反するということはない。
このことから、ここで「14条1項に違反するものである。」と述べていることは誤りである。
また、「同性カップルに対して、その関係を国の制度によって公証し、その関係を保護するのにふさわしい効果を付与するための枠組みを与えていないという限度で、」との部分についても、そもそも「14条1項」に違反しないことから、「14条1項」に違反する「限度」について述べようとしていることも誤りである。
その他、「14条1項」の「平等原則」に違反するか否かを検討するとしても、それは個々の自然人である「婚姻している者(既婚者)」と「婚姻していない者(独身者)」との比較において、「婚姻している者(既婚者)」が婚姻制度の立法目的を達成するための手段として不必要に過大な優遇措置を得ている場合には、その過大な優遇措置に関する規定が個別に失効することによって格差が是正されるという形で行われることになる。
この場合、「婚姻していない者(独身者)」が基準(スタンダード)となり、「婚姻している者(既婚者)」の得ている過大な優遇措置が減らされる方向で格差が是正されるのであり、この判決のいうような形で「婚姻していない者(独身者)」に対して何らかの「効果」を「付与」したり、「与え」たりするものではない。
よって、この判決が「14条1項に違反するものである。」と述べた上で、それを是正するための方法として「ふさわしい効果を付与するための枠組みを与えていない」のように、何らかの「効果」を「付与」したり、「与え」たりすることで解決しようとしていることについても、誤った理解となっている。
「本件諸規定がこの限度で憲法の規定に違反するにもかかわらず、国会議員がその改廃等の立法措置を怠ったことが、例外的に国会賠償法1条1項の規定の適用上違法の評価を受けることがあるかについて、検討する。」との部分について検討する。
上記のように、憲法24条1項、2項、14条1項に違反するものではないことから、「憲法の規定に違反するにもかかわらず、」と述べていることは誤りである。
「この限度で」の部分についても、憲法に違反しないことから、その「限度」について触れる前提にないものである。
「国会議員がその改廃等の立法措置を怠ったことが、」との部分についても、そもそも憲法に違反しないことから、立法措置についての怠りはない。
「国会賠償法1条1項の規定の適用上違法の評価を受けることがあるか」との部分についても、そもそも憲法に違反しないことから、これを検討する前提にないものである。
「検討する。」の部分についても、そもそも憲法に違反しないため、憲法に違反することを前提に「検討」をすることは誤りである。
その他、「国会賠償法1条1項」との記載があるが、これは「国家」とするべきところを「国会」と表記してしまった誤りである。
⑵ この点、国際機関の動向を見ると、1994(平成6)年には、自由権規約委員会が、男性同士の性行為等を処罰する法律が自由権規約に違反する旨の判断を示しているものの(認定事実⑶ア )、同性カップルに対する公証とそれに基づく効果を付与するための枠組みの必要性が明確にされたのは、2006(平成18年)年11月採択のジョグジャカルタ宣言において、性的指向及び性自認にかかわらず、家族を形成する権利を有することが謳われたのが初めてである(認定事実⑶ウ)。そして、2008(平成20)年には、自由権規約委員会やUPRの下で、性的少数者の人権問題に関する具体的な勧告が行われたものの、そこでは、公営住宅法やDV防止法が同性カップルを排除していることの問題等が指摘され、性的指向及び性自認を理由とする差別の撤廃に向けた措置を講ずることが求められていたにすぎず(認定事実⑶ア )、具体的に上記枠組みの必要性が勧告されたのは、2017(平成29)年のUPR第3回審査の過程で、スイスやカナダが、同性間の婚姻制度等の公式な承認を国レベルに拡大する措置を指摘したのが初めてである(認定事実⑶イ )。
【筆者】
「自由権規約委員会が、男性同士の性行為等を処罰する法律が自由権規約に違反する旨の判断を示しているものの」との部分であるが、日本国憲法の下で「男性同士の性行為等を処罰する法律」は存在しない。
また、これは「婚姻及び家族」の制度とは何らの関係もない事柄であり、これを取り上げていることそのものが妥当でない。
「ジョグジャカルタ宣言」とあるが、この判決で問われたのは、憲法24条2項の「家族」が、「親子」や「親子」の関係を基本とした「兄弟」「姉妹」などに含まれない「同性間の人的結合関係」を対象とした制度を立法することを「要請」しているか否かであり、これは憲法上の規定の意味を読み解くことによって明らかとなる事柄であることから、外部の団体が何かを宣言したところで、憲法上の規定の意味を書き替えることはなく、その解釈に影響を与えることはないし、影響を与えるようなことがあってはならない。
「家族を形成する権利」の部分について、日本国憲法の下で人的結合関係を形成することは憲法21条1項の「結社の自由」で保障されているし、「夫婦」(男女二人一組)と「親子」については憲法24条2項の「要請」に従った制度を利用することが可能である。
この自由を得ることやその制度を利用することについては、「性的指向及び性自認」を審査されるものではないことから、「性的指向及び性自認」に関わるものではない。
その他、国際機関や他国からの「指摘」があるとしても、その「指摘」そのものの当否を検討することが必要であって、それを無批判に自国の法制度に取り入れることが正しいというものではないし、そもそもそれらの「指摘」が憲法上の規定の意味を書き替えることはないため、その解釈に影響を与えることはないし、影響を与えるようなことがあってはならない。
また、そもそも憲法24条1項、2項、14条に違反しないことから、国家賠償法上の問題を検討する必要そのものがないものであり、その検討としてこれらを論じていることそのものが誤りである。
また、デンマークが1989(平成元)年に登録パートナーシップ制度を導入しているものの、登録パートナーシップ制度等や同性婚制度が世界的に広がりを見せたのは、2000(平成12)年頃以降のことであると認められ(認定事実⑷ア 及び同ウ
)、我が国において、地方自治体において登録パートナーシップ制度が初めて導入されたのは、平成27年4月のことである(認定事実⑸ウ )。そして、国に対して、地方自治体や民間企業、各種団体から、同性カップルの公証とそれに基づく法的利益を付与する枠組みの必要性が提言されるに至ったのも、平成28年頃以降のことであり(認定事実⑸ウ 及び同エ)、具体的な法案が国会に提出されるに至ったのは、令和元年6月のことであった(認定事実⑸イ)。
【筆者】
外国の法制度を取り上げているが、外国の法制度の中には日本国憲法の下で実施した場合には違憲となるものがあるため、諸外国の法制度を取り上げて何かを論じようとしていることそのものが妥当でない。
「地方自治体において登録パートナーシップ制度」についても、憲法違反や法律違反のものとなっており、これを基にして何かを論じようとしていることは妥当でない。
詳しくは、当サイト「パートナーシップ制度」で解説している。
何らかの「提言」をする団体があるとしても、憲法規定を解釈するにあたって影響を受けることはないし、影響を受けることがあってはならない。
また、そもそも憲法24条1項、2項、14条に違反しないことから、国家賠償法上の問題を検討する必要そのものがないものであり、その検討としてこれらを論じていることそのものが誤りである。
⑶ 前記⑵によれば、我が国において、同性カップルに対する公証とそれに基づく効果を付与するための枠組みの必要性が具体的に認識されるに至ったのは、比較的最近のことであったと認められる。そして、婚姻及び家族に関する事項については、その具体的な制度の構築が第一次的には国会の合理的な立法裁量に委ねられる事柄であるところ、男女の結合関係を中核としてその間に生まれた子の保護・育成の機能を担うという伝統的な家族観が存在し、このような家族観は、今日においても失われてはおらず、同性婚の是非に関し、令和2年時点での意識調査においても、一定数の反対派が存在したことにも照らせば、現時点において、本件諸規定が憲法24条2項及び14条1項に違反するものであることが明白であるにもかかわらず、国会が正当な理由なく長期にわたってその改廃等の立法措置を怠っていたと評価することはできない。
【筆者】
この段落は、「婚姻及び家族に関する事項」について「具体的な制度の構築が第一次的には国会の合理的な立法裁量に委ねられる事柄である」ことを前提に、「男女の結合関係を中核としてその間に生まれた子の保護・育成の機能を担うという伝統的な家族観」が「今日においても失われて」いないことから、「国会が正当な理由なく長期にわたってその改廃等の立法措置を怠っていたと評価することはできない。」と述べるものとなっている。
しかし、この判決で問われているのは、憲法24条2項の「家族」が、ここでいう「同性カップル」という「同性間の人的結合関係」を対象とした制度を立法することを「要請」しているか否かである。
これは、「要請」していればその制度がないことは違憲となり、「要請」していないのであればその制度がないことは合憲というものである。
これは憲法上の「要請」の有無の問題であるから、もし「要請」しているのであれば、その制度を立法しないことについて「国会」の「立法裁量」の余地はないし、もし「要請」していないのであれば、そもそも国会に対して立法することを義務付けられているものではないことから「国会」の「立法裁量」を超えるか否かを判断する前提にない。
そのため、いずれにせよ「国会」の「立法裁量」を検討することによって結論が導き出される問題ではない。
よって、「国会」の「立法裁量」を検討することによって結論が導き出される問題であることを前提として判断しようとしていること自体が誤りである。
また、そもそも憲法24条1項、2項、14条に違反しないことから、国家賠償法上の問題を検討する必要そのものがないものであり、その検討としてこれらを論じていることそのものが誤りである。
⑷ したがって、本件諸規定の改廃を怠ったことは、国会議員の立法過程における行動が上記職務上の法的義務に違反したものとはいえず、国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではないというべきである。
【筆者】
そもそも憲法24条1項、2項、14条に違反しないことから、国会は何も怠っていないのであり、「国会議員」が「職務上の法的義務に違反したものとはいえ」ない。
よって、結論として「国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではないというべきである。」との部分が妥当であるとしても、その判断の過程は誤っている。
第4 結論
よって、原告らの請求は、その余の争点について判断するまでもなく、理由がないことに帰するから、原告らの請求をいずれも棄却することとして主文のとおり判決する。
名古屋地方裁判所民事第8部
裁判長裁判官 西村修
裁判官 藤根康平
裁判官梁川将成は、転勤のため、署名押印することができない。
裁判長裁判官 西村修
<理解の補強>
私たちは「重婚」を認められるか…?「同性婚」問題の先に浮かび上がる「多様性をめぐる根本的な難点」 2023.06.27
【名古屋・第1回】控訴答弁書 令和5年10月12日
このページでは、この判決の内容に不備があることを憲法学者「南野森」の講義動画をいくつか用いて指摘している。
しかし、その憲法学者「南野森」の同性婚訴訟についての説明には不備があると考えられるため、それについてここで指摘しておく。
【動画】2023年度前期・九大法学部「法学入門」第3回〜法学とは何か 2023/05/10
婚姻制度は個々人の内心を審査して区別取扱いを行っている事実はないため、「異性愛者」を称する者も、「同性愛者」を称する者も、それ以外を称する者も、特に何も称しない者も分け隔てなく利用することができる。そのため、「異性愛者」を称する者にだけ制度の利用を認めているかのような説明は誤りである。また、そもそも人を内心に基づいて「異性愛者」と「同性愛者」に区別して論じることそのものが法律論として誤りである。
憲法は「個人の尊厳」の原理に基づいており、自然人は「個人主義」の下に各々「自律的な個人」として生存していくことを予定していることから、「婚姻していない者(独身者)」の状態で既に完全な状態であり、そこに「不利益」と称されるものはない。優遇措置に関しては、「婚姻している者(既婚者)」が婚姻制度の立法目的を達成するための手段として不必要に過大な優遇措置を得ている場合には、「婚姻していない者(独身者)」との比較において合理的な理由を説明することのできない差異を生じさせるものとして14条の「平等原則」に抵触して違憲となる。その場合、その過大な優遇措置に関する規定が個別に失効することによって格差が是正されることになる。病院での面会交流については、その病院の面会交流の制度の問題であり、「婚姻」の問題とはいえない。
憲法24条の規定が立法された意図について述べている部分であるが、そもそもそこでいう「婚姻」とは何かという問題については説明されていない。24条の規定が設けられた背景にそのような事実があるとしても、それは規定が設けられている理由の一部を説明するものに過ぎないのであり、24条の規定が有するすべての意味を説明したものとはいえない。そのため、そのような24条の規定が設けられた意図の一部を反対解釈したとしても、そこで24条の規定のすべての意味を読み出したことにはならない。そのため、そもそも24条のいう「婚姻」とは何かという論点を覆い隠す形で、24条の意味を確定することができるということにはならない。
その後、「禁止説」についての話を出しているが、上記で説明している通り、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることはできない。これを結果として「禁止」と表現するかどうかの問題に過ぎない。
14条の「平等原則」の話について、「同性カップル」と「異性カップル」とを持ち出して比較を試みるが、「権利能力」を有して法主体としての地位を有するのは個々の自然人であるから、「カップル」を持ち出して比較をすることは誤りである。
13条によって特定の制度の創設を国家に対して求めることはできない。
札幌地裁と東京地裁が憲法違反と言ったことについて「同性婚要請説」と説明しているが、いずれの判決も「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることについて述べているわけではなく、何らかの制度や法的効果について述べるものであり、論者が「同性婚要請説」と述べているものには含まれない。また、それらの判決の内容も当サイトで指摘しているように、内容に不備があり、誤っている。
「南野森さんにホモオカマ同性愛者当事者の私はブロックされてるわ」 Twitter
「異なる声の同性愛者は」 Twitter
判決の誤りを継承する解説
下記に挙げたこの名古屋地裁判決の記事や解説について、当サイトをお読みの方ならば、どの部分が妥当でないかを見抜くことができるはずである。
名古屋の違憲判決は国の主張を「真っ向からぶった切った」今まで以上に踏み込んだその内容とは【結婚の平等裁判】 2023年05月31日
歴史的なダブル違憲判決「婚姻の平等さらに前進」名古屋地裁判決を傍聴 2023/5/31
新局面を迎えた「同性婚訴訟」――有権者の投票行動にも影響 松田明 2023年6月2日
同性婚が実現しても「国民の不利益は想定しがたい」 名古屋地裁が判決で言い切った背景 2023年06月03日
第290号 同性婚を認める規定を設けていないことに関する名古屋地裁違憲判決 名古屋市立大学大学院 小林直三 2023年6月7日
同性カップルの婚姻が認められていないことは憲法24条2項に違反する 山下純司 2023年9月1日 PDF
【動画】熊澤美帆講師に聞く!「結婚の自由をすべての人に」訴訟 伊藤真 2023/06/21
同性婚認めない規定「違憲」 名古屋地裁で2例目判決 2023年5月30日
同性婚認めぬ規定「違憲」 名古屋地裁判決「国、現状を放置」…賠償は棄却 2023/05/31
<社説>同性婚訴訟判決 法制化に踏み出す時だ 2023年5月31日
「同性婚認めず」再び違憲 国は法制化に動くべきだ 2023/5/31
〈社説〉同性婚の不備 違憲受け止め法改正急げ 2023/05/31
<社説>同性婚判決 法整備は待ったなしだ 2023年6月1日
同性婚否定は違憲 婚姻の平等へ法制化を進めよ 2023年6月1日
社説:同性婚訴訟 違憲是正へ法制化急げ 2023年6月1日
【同性婚訴訟】権利擁護へ法整備急げ 2023.06.02
同性婚否定「違憲」判決 一刻も早く国は法整備を 2023/06/02
[社説]同性婚否定は違憲 法整備は社会の要請だ 2023年6月2日
同性婚訴訟/国に法整備迫る違憲判決 2023/06/02
<社説>同性婚不備「違憲」 当事者救済へ法整備を 2023年6月4日
(<社説>同性婚不備「違憲」 当事者救済へ法整備を 2023/06/04)
お読みいただきありがとうございました。