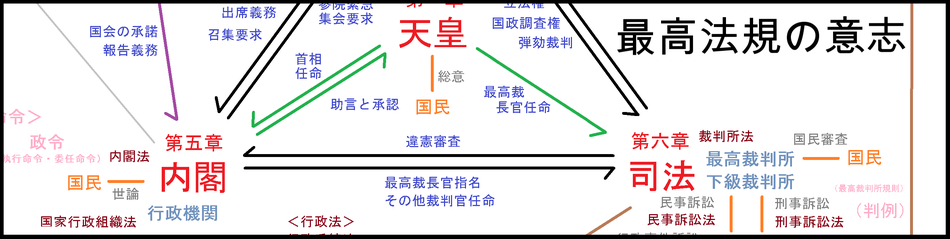天皇の地位
【目次】
〇 天皇とは何か
〇 天皇は必要か
〇 天皇を決める方法
天皇とは何か
Q 天皇とは何か。
これを説明するにはいくつかの方法がある。
◇ 公的な意味
A1 日本国の統治の作用のうち、「権威」と「権力」を分離した場合における「権威」の方である。
A2 日本国憲法がいう「日本国民の総意」(1条)である。
A3 そこに国家が存在していることを象徴するものである。国旗と同じ役割である。
A4 日本国のマスコットキャラクターである。地方自治体のマスコットキャラクターと同じ役割である。
A5 世襲制の公務員を中心に構成される劇団の長である。
「国家」という頭の中の合意事であり本来的に目に見えないものを、「見える化」して演じる者である。その者が演じることになっているものは常に「日本国」である。演目が「日本国」と定められた国家お抱えの劇団の長である。(ここで言いたいのは、役職であり、仕事であるということ。)
◇ その他
▽ 歴史的な意味
歴史的な文脈で天皇について論じられることがある。
しかし、これは現在の法体系のものとは性質が異なる場合があり、法学的な意味ではないことから、ここで取り扱うことはしない。
▽ 宗教的な意味
宗教的な意味で天皇について論じられることがある。
しかし、これも法学的な意味ではないことから、ここで取り扱うことはしない。
▽ 生物学的な意味
生物学的な意味では、天皇の役職を担う者は、ヒト科ヒト属のホモ・サピエンスの中の一人である。
この意味では、他の自然人(国民や外国人)と何ら変わるものではない。
そのため、天皇だけが生き物として根底から異なるものであるとか、ホモ・サピエンス以外のネアンデルタール人であるとか、神の種族のようなものが別に存在するとか、そういうものではない。
この意味で、他の一般人と何ら異なるものではない。
天皇とは、その社会の中で一定の役割を担うことが求められている仕事の一つであって、役職であって、地位である。
それを誰に担わせるかについて議論されることはあるが、生物学的な根底から他の者を圧倒する力があるとか、人知を超えた特別なパワーがあるとか、超能力を持っているとか、そのようなことは一切ない。
▽ 私的な意味
人はアイドルや芸能人などを慕うことがあり、中には信仰心まで抱く者もいる。同じように、天皇を慕い、信仰心を抱く者もいるかもしれない。
しかし、それはその者にとっての個人的な体験から来る価値であり、その者の中でその存在に対して意味づけを行っているものである。
それについては、公的な意味として取り扱うことはできないため、ここで個別に示すことはしない。
天皇について論じられる際に、そのような私的な意味づけが入り混じることが多いため、注意する必要がある。
これは、国会議員の法的な地位そのものと、「国会議員は偉い人・偉くない人」や「国会議員は頭が良い・悪い」などの私的に行う評価とを区別するべきことと同じである。
〇 「権威」と「権力」の分離について、イギリスの例を参考とする。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
バジョット(Bagehot,
W.)は、『イギリス憲政論』(1867)の中でイギリスの国家体制を分析する際、憲法の尊厳的部分と機能的部分とを区別した。
前者は、国民の崇敬と信従を喚起し、維持する部分であり、後者が実際の統治に携わる。
バジョットによれば、当時のイギリスの国家制度のうち王室や貴族院は前者であり、庶民院や内閣は後者にあたる(バジョット
[1970] 第1章)。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◇1.2.7 憲法の尊厳的部分と機能的部分 (下線・太字は筆者)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○長谷部参考人
(略)
首相公選制と天皇制との関係ということでございます。
これは、イギリスの昔の政治学者でバジョットという人がいますが、彼がイギリスの国政について指摘した議論の中に、憲法には尊厳的な部分と機能的な部分があるんだ、ある種、国家の威権というものを象徴して国民の信従を調達する部分と、実際に統治を担っていく部分が区別できるのであるということを指摘しているわけなんです。仮に、今首相公選制を採用した場合におきましても、天皇と公選首相の間には、やはり尊厳的な部分と機能的な部分の区分というものは当然成り立ち得ますので、制度としてどうしても両者が矛盾をするということではないのではないかと思います。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第153回国会 衆議院 憲法調査会 第3号 平成13年11月8日 (下線・太字は筆者)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○八木参考人
(略)
彼らが象徴天皇制度を考えるに当たって参照した文献があります。これがウォルター・バジョットの「イギリス憲政論」という本であります。一八六七年の著作であります。
一番下の黒丸をごらんください。このバジョットのイギリス憲政論の中にこういう部分があります。
国民は党派をつくって対立しているが、君主はそれを超越している。君主は表面上、政務と無関係である。そしてこのために敵意をもたれたり、神聖さをけがされたりすることがなく、神秘性を保つことができるのである。またこのため君主は、相争う党派を融合させることができ、教養が不足しているためにまだ象徴を必要とする者に対しては、目に見える統合の象徴となることができるのである
こういうことですね。まさに国民統合の象徴という言葉は、このバジョットの中で使われているわけであります。
バジョットの考えをまとめてみます。
バジョットは、君主の役割を、党派をつくって対立している国民を融合させる、目に見える統合の象徴であることに見出したわけです。それは、君主が政務、つまり実際政治と無関係で、それを超越しているがゆえに可能なのだというように考えているわけです。国民統合の象徴とは、バジョットの文脈でいいますと、立憲君主の有する機能を言った表現であります。
さて、バジョットの立憲君主制論について若干説明をしておきたいと思います。
バジョットは、政治を二つの部分から成るものと考えます。一つは尊厳的部分、もう一つは実効的部分。尊厳的部分を担うのが君主、王室であるということ、実効的部分を担うのが内閣その他であるということであります。
(略)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第154回国会 衆議院 憲法調査会政治の基本機構のあり方に関する調査小委員会 第5号 平成14年7月4日
【参考】英連邦オーストラリアに英国王は必要か? 2019年5月25日
【動画】特番「「女性天皇」と「女系天皇」はどう違うのか」谷田川 惣 倉山満【チャンネルくらら】 2020/03/08
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○角田(礼)政府委員
(略)
憲法上、天皇が国家機関として行為をされるその場合としては、憲法の定めるいわゆる国事行為に限るということは、憲法の四条二項、六条及び第七条に明記されているところでありまして、このことについては明らかであろうと思います。ただいま申し上げたのは、天皇が国家機関として行為をされる場合のことについてのことでございますが、憲法というのは、言うまでもなく国の国家構造というものを決めている基本法でございますから、わが国におきましては立法、行政、司法の三権についてそれぞれ決めていると同時に、天皇という特別の地位を持っておられる方も広い意味の国家構造の一部として国事行為を行われる、これが国家機関としての天皇の地位であろうと思います。そういう意味で、その点については憲法の性質からいつて明文の規定があるわけでございます。
(略)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第75回国会 衆議院 内閣委員会 第6号 昭和50年3月14日
国民の信従を調達する機能としての役割を担うに当たって、下記のような方法を採用していることが多い。
・品位を感じられること
・人々の模範となること
・人々と共にあろうとすること
・政治的に無色であること
・人々が国政を考える際の基盤となること
・国政の安定が普遍的なものとなるよう努めること
・
など
これらは、演目の具体的な内容、あるいは、イメージ戦略にあたるものである。
これらは行為の外形として現れる部分であることから、法的な側面としては職務専念義務にあたるものと位置付けることができると考えられる。
ただ、法的な側面としては、これ以上のことを求めることはできないと考えられる。
法的な側面とは別に、私的な活動として倫理的な考慮をしたり、宗教的な行為によって精神的な側面まで統制されることを求められ、何らかの勤めをしていることは考えられる。
天皇は必要か
国の制度として天皇という地位を設けていることについて、必要と考える意見と、必要ないと考える意見の両方がある。
〇 不要説
必要ないと考える意見がある。
必要ないと考える場合に注意すべきことについて下記の動画が参考になる。
【動画】天皇と合理性。伝統は伝統であるが故に尊い!合理性という浅知恵と何世代も培った伝統という叡智|竹田恒泰チャンネル2 2024/04/04
〇 必要説
必要であると考える意見がある。
必要性については、下記のような説が考えられる。
◇ 政治的中立性説
憲法改正・法律・政令・条約の公布、国会の召集、議会の解散、選挙の公示、権力者の任命など、政治的に無色の者が担うことが相応しい事柄、政治的に無色であることが求められる事柄、政治的に無色である者にしかできない事柄がある。
これを担わせるための存在として必要と考える。
◇ 対外的国家代表説
外国の大使や公使を接受するなどの場面において、政治的に無色な立場にある者が国家を代表して対外的な関係を構築する機能を果たすことには意味があると考えられる。
また、その役割を行政府の長などの権力を担う者に対して同時に担わせることは、現実の政治的な対立からくる緊張状態の中でその職務を同時に行わなければならないこととなることから、不必要に過大な負担が生じることになり得る。
このように役割を分担することによって、権力を担う者の負担を軽減し、質の高い国政運営を実現することに集中できる環境を整える意味合いも考えられる。
【動画】【ひろゆき】天皇・皇族についてタブー度外視ひろゆき【切り抜き】 2020/11/25
◇ 究極のバリアフリー説
法学の勉強を極めていない人、法学の勉強が嫌いな人、法学の勉強を途中で諦めた人、もともと法学を学んでいない人、文字が読めない人、知識の少ない人、精神的に弱っている人、子供たちであっても、「国」という存在を確かに感じ取ることのできる形に表現された究極のバリアフリーとしての機能である。
国政の複雑な統治作用を一切理解できていないとしても、国という存在の確からしさを示し、人々を法の秩序の下に結び付けることのできる役割である。
【動画】天皇を生で見たJKの反応 2019/10/22
◇ 安全安心保証説
「権力」と「権威」を分離してそれぞれの役割を分けていることは、「安全」と「安心」を区別する考え方と似たようなイメージを持つことができる。
【音声】豊田章男の“本音”を特別公開|トヨタイムズニュース 2024/02/12
両者は一見似ているのであるが、やはり違うものである。
特に、命に関わる問題については「安全」だけでなく「安心」まで実現することが望ましいといえる。
同様に、この点の違いまで意識して国家運営を行った方が、よりきめ細かいところまで手が届く質の高い国家運営を実現することができると考えられる。
その意味で、「権力」によって「安全」を実現するというだけでなく、「権威」によって国民が「安心」できるところまでしっかりと目を配る形で国政運営を行うことの方が、そうでないよりも良いと考えられる。
◇ 共同幻想説
民族のまとまりを作るものとして機能するとの考え方である。
【動画】【扶桑社プレゼンツ】左右激突!「天皇・憲法9条」立憲民主党米山隆一衆議院議員 皇室史学者倉山満【チャンネルくらら】 2024/03/07
◇ 国政安定説
国の象徴としての機能を行政府の長などの権力を有する機関が担うことになると、その者の任期によって数年ごとに国を象徴する人物が入れ替わることになる。
また、国の象徴としての機能を行政府の長などの権力を有する機関が担うことになると、そこに法秩序が存在すること示す国の基盤となる目印(象徴)そのものが政争の対象となって政治的な攻撃を受けることになる。
その政争の結果として、国の象徴としての機能を担う人物が短い期間で頻繁に入れ替わることになる。
こうなると、法秩序そのものが存在することを示す目印がいつまでも安定しないことから、政争が行われる基盤(前提)となっている法秩序そのものがその時々に形成される一時期の民意の振れ幅によって揺るがされる危機に何度も見舞われることとなる。
すると、政権が変わるごとに法秩序の連続性が断ち切られ、あたかも革命が起きて別の国に変わったかのような状態にも陥りやすくなる。
これでは、長期的な視野に立った安定的な国家運営を行うことが困難となり、国政の平穏さを維持することができなくなる。
そのため、権力とは切り離された存在として別に権威を配置し、そこに法の秩序が存在することを示す目印(象徴)を置くことは、国政の安定に資すると考えられる。
◇ 法の実効性確保説
⇒ 当サイト「前文の世界観」のページで解説している。
◇ 憲法保障説
憲法保障の機能として「権力」と分離された形で「権威」を配置することには意味があると考えられる。
⇒ 当サイト「憲法の体系」のページで解説している。
◇ 非常事態統治機能回復説
戦争や事変などで、内閣を構成する大臣や国会を構成する議員の大半が失われて統治機能が麻痺した場合など、通常の憲法秩序を維持することができないほどの非常事態が発生した場合において、統治権を行使する者を選出して一時的に任命したり、一時的に統治権を行使するなどして憲法秩序を回復させる機能を担う可能性が考えられる。
立法、行政、司法の三権を担う者以外の「憲法尊重擁護義務」を課せられた存在として、非常時での統治権の代替や統治機能の回復を担う可能性が考えられる。(最終手段説)
国の制度として天皇の地位を設けていることに関して様々な説明がなされることがある。
ただ、そこで注意するべきなのは、制度設計として耐えられる説明と、そうでない説明を区別することである。
これを区別する視点について、下記の動画が参考になる。
【動画】【模擬講義】工学院大学/工学部 機械工学科 ~飛行機は なぜ空を飛べるのか?翼のはたらき~ 2020/09/02
ここで述べられていることは、下記のような内容である。
なぜ飛行機は空を飛べるのかについて、翼の形状との関係を基に様々な説明がなされている。
ただ、その中には既に実際に飛ぶことができている翼の形状が存在することを前提として、それについて後から解釈して説明しているだけのものが存在する。
しかし、そのような知識では、新しい翼の形状を設計する際に、事前に飛べる形状となっているのか、飛べない形状となっているのかを予測することができず、工学的な技術の知識としては使えないという問題がある。
同様に、天皇の地位の存在についても、様々な説明がなされていることがあるが、その中には、既に天皇の地位が存在することを前提とした上でそれを後から理由付けをしているものや、天皇の地位が存在することを前提としてそれに対する信仰心が入り混じったような説明がなされていることがある。
しかし、そのような知識では、統治に関する制度を設計するという場面では、事前に制度として機能するのか、機能しないのかを予測することができず、法学的な知識としては使えないという問題がある。
そのため、国の制度として天皇という地位を設けていることについても、制度設計として通用する説明と、天皇の存在を前提として後からその理由について解釈した一断片の説明とを区別する視点を持つことが必要である。
<理解の補強>
【動画】【皇室】女性・女系天皇って何だ?「国論を二分しかねない議論に」なぜ男系男子にこだわる?皇室にもジェンダー平等は必要?EXITが憲法学者に学ぶ 2021/04/09
天皇を決める方法
〇 「必要説」を採る場合に誰がやるのか
天皇の役割を誰が担うのかを決める際に、揉めたり、争いが起きたりしないルールが設けられていることが望ましいといえる。
そこで、どのような方法が考えられるかを検討する。
◇ 勉強が一番できる者
何を基準に勉強ができると評価するのかという評価方法の対立を避けることができない。勉強できる者と勉強ができない者の間で優劣関係が生じることによる紛争も避けられない。
◇ 納税額が最高額の者
営利的な対立や紛争から離れられない。後に不正が発覚するなど紛争が起きやすい。
◇ 選挙
政治的な対立が生じることを回避することができない。
◇ くじ引き
人材の質を保証することができない。本人にとってもその立場に立つことに対して予測可能性がない。
◇ 世襲
そこそこマシ。
◇ (他にもっと良い方法はあるか……。)
これらのいろいろな方法を考えた結果、他の選択肢よりもマシだから、一応「世襲」でやっている。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第2条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
皇室典範によれば、「男系の男子」が継承することになっている。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第一条 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「男系の男子」が継承するものとして定めている理由は、下記のような考え方によるものである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
皇位継承の順序の変更
皇位継承の順序がかく典範によって厳重に一定せられたことは、後世に長く紛争の源を絶ち禍(わざわい)を未然に防がんとする遠大の聖旨に出たものでありまして、この順序は決して濫(みだ)りにこれを動かすことはできないのであります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
憲法講話 美濃部達吉著(岩波文庫) (P110) (下線は筆者)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
宮台━━社会学の答えははっきりしています。正統な継承線をきわめて限定することで、継承線をめぐる鍔迫りあいの混乱を回避する。それが社会学的に見た「男系原理」や「女系原理」の機能になります。実際、正統性と訳されるレジティマシー(legitimacy)とは、もともとの語源は「正統な継承線」という意味です。社会学の伝統的思考によれば、正統性=レジティマシーとは、社会的承認可能性━━正確にいえば「皆が承認するだろうと皆が思えること」━━にすぎません。社会的承認が期待可能であれば、科学的根拠を含めた合理的根拠が、あろうがなかろうが関係ない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
天皇と日本のナショナリズム_神保・宮台マル激トーク・オン・デマンドIV 神保哲生 宮台真司 2006/11/1 amazon (P34) (下線は筆者)
【動画】講師:作家 竹田恒泰 氏/テーマ:「日本を楽しく学ぼう」(公家の政権700年)【第2期まなびと夜間塾開講講座】 2021.2.19
【動画】参院選SP ゼロから分かる皇位継承と男系男子。そして保守と保守モドキを見分ける重要なポイントを分かりやすく解説! ゲスト:竹田恒泰 2022/07/08
【動画】【日本の窮状】男系継承の秘密 2024/03/29
この「揉めたり、争いが起きたりしないためのルールがあればよい」という考え方は、下記の考え方と同じである。
・ 現在の道路交通法は、自動車を「左側通行」としている。
・ しかし、これは「右側通行」であっても特に問題はない。
・ ただ、左側と決めた以上はよほどのことがない限りは変えるべきではない。 その理由は、可変的なものであることを前提とすると、混乱したり、紛争を招くからである。
・ このように、揉めないためのルールとして存在していることに意味があるというものである。
憲法学者「長谷部恭男」は、この考え方を下記のように説明している。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
これを如実に示すのが車両は左側を通行せよ(道路交通法17条4項)というルールです。これが普遍的なものではないことはご存じのとおりです。その意味で車両の通行は左右いずれでも本質的に関係ないということになるのですが、これは「どちらか」に決まっていることが重要です。このような「どちら(どのよう)でも良いが、どちらか(どのようにか)が決まっていることが重要」な問題を「調整問題」だとするものがあります(長谷部恭男『憲法』〔第5版〕(新世社・2011)8ページ)。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定観念? ―あるいは調整問題― 2014-03-16 (下線は筆者)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
実定法は権威であると自己主張することがしばしばある。「あなた方、自分で判断するのはやめて、私の言う通りにして下さい。そうした方が、あなた方が本来すべき行動をよりよくとることになりますから」と主張するものである。大多数の人々が、大多数の人々と同じ行動をとろうと考えている調整問題状況では、実定法を権威として受け止め、その通りにすることで、本来すべき行動をとることのできる場合が多いであろう。実定法が、自動車は道路の左側を通るように指示している社会で、左側を通るようにすれば、事故を起こすこともなく、スムーズに、かつ、安全に自動車を運行することができる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
その16 憲法より大切なもの 2018/7/4 (下線は筆者)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
たとえば、自動車は道路の左側を通るべきだと道路交通法が定めれば(道路交通法17条4項参照)、人はいずれの側を通るべきか自分で判断する必要はありません。法律の求めるように左側を通れば、事故を起こすこともなく、スムーズに自動車を運行することができます。つまり法律は、本来各自が行うべき実践理性の判断を不要とし、ショートカットするための便利な道具です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【視点】憲法とは何か 長谷部 恭男 2019年12月16日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
一方、いわゆる道路交通法や手形小切手法といった普通の法律は、「自分で判断しないで言う通りにしてくれ」という法です。左側通行がよいか悪いか、各人が自分で考えて判断したら大混乱になるわけです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
理想の生き方は、人それぞれで異なります 2020/07/31
【動画】憲法 守るべきものは何か 長谷部恭男×石川健治【春の立憲デモクラシー講座」 2022/04/22
【動画】衆議院 憲法審査会 2023年5月18日
【動画】おしえて長谷部先生!「法の支配」ってなぁに? 2024/02/03
(憲法カフェ第3弾 おしえて長谷部先生!「法の支配」ってなぁに? 2024.2.13)
(憲法と法の支配 パルシステム東京 2024年2月3日 PDF)
このような問題と同様に、現在、天皇の地位を「男系の男子」としていることも、それは揉めないためのルールとして機能しているところに価値があるというものである。
「男系の男子」にあたる人物が他の人物よりも能力が優れているとか、遺伝的に特別なパワーを有した存在であるとか、そういう話ではない。
〇 天皇の世襲制について
どれだけ天皇の地位が世襲によって成り立っていることの素晴らしさを唱えたとしても、それらはすべて嘘になると考えられる。
それよりは、下記のように考えることが妥当であると思われる。
① 代々、必要とされる役職がある。
② その役職を誰が担うかについて、すべての人に可能性を開くと、揉めることになる。
③ 一番揉めにくい方法を選択した結果、世襲制に行き着いた。
そうやって紛争の起きない方法を選択し、すべての人が平穏でいられる状態を確保しようとしているだけである。
もっと良い方法があるのであれば、それに変える可能性は常にあるはずである。
天皇の男系継承というルールは、継承者を選出する際に揉めないためのルールとしてやっているだけである。
もし揉めないための手段(それも将来に渡って永続的に)が別にあるとすれば、それを採用することは可能であるはずである。
そのため、「男系継承であることそのものに価値があり、そのルールを信じて守り抜くことだけが正しい選択であり、天皇という価値を守ることに繋がる」などというものではないはずである。
その社会の中で天皇という価値を体現することが必要とされており、それを担う人物を選出するために作られた「揉めないためのルール」に過ぎないものを、あたかもそれが天皇という価値そのものであるかのように考えることは誤解であると考えられる。
こういう過程で決められているだけである。
そのため、天皇家のDNAに不思議なパワーがあるとか、通常の人間では有していない特別な力があるとか、そういうものではない。
そういう話は信仰の領域であり、科学的な根拠はない。
この意味で、世襲制が素晴らしいというものではなく、消去法で行き着いた結果として世襲制を定めているというものである。
このように、制度は制度としてドライに理解した方がよいと思われる。
〇 国の権威を司る役職と世襲制の親和性
世襲制であれば、その国の最高の権威である天皇となる人物は予め定められている。
そのため、その者以外は、その国の中でどれだけ勉強しても、どれだけ運動しても、どれだけ真面目に働いても、どれだけお金を稼いでも、どれだけ部下を従えても、どれだけ人気を集めても、どれだけ人々から尊敬を集めても、どれだけ修行しても、どれだけ努力しても、その国の最高の地位(トップ)に立つことはできない。
これにより、知力や体力、財力などを用いて国の根幹を奪い取ることはできず、結果として国家の法秩序の存在そのものが政争の対象となることを防ぐことが可能となり、国家を私物化することを試みる権力者や国家の転覆を図る権力者が現れることが抑制され、国政の安定に寄与することになる。
この点で国の権威という価値を体現する者を決める方法として、世襲制には親和性が高いと考えられる。
ただ、反対に天皇の地位にある者は権力を行使することができないという制限が徹底的に加えられることになる。
【動画】④竹田恒泰「天皇家の血筋と人格形成の関係」を語る! 2020/02/03
【動画】【歴史のタブー】幕府もGHQも天皇を倒さなかった理由|小名木善行 2022/09/05
【動画】Q.日本の総理って、最大何年までやれるんですか? 2024/05/13
〇 国家を構成する要素と世襲制の親和性
国家の要素は、「領土」「人」「統治権」の三つによって構成されると考えることが一般的である。
これが国家としての基盤であり、普遍的な性質である。
この点で、天皇を誰が担うかを決める際に、「勉強ができる」や「納税額が高い」など、その時々の価値観や社会制度を基に決めようとすると、価値観の変化や社会制度の変更によって、それまで機能していた判断基準が機能しなくなる。
すると、また新たな価値観や社会制度を基にして基準を見つけ出さなければならないという事態が生じ、その過程で紛争が起こることが考えられる。
その点、世襲制であれば、人間がいれば、その人間は誰か別の人間から産まれていることは明白であり、そのことを基準として継承者を選出するのであれば、国家の要素として「領土」「人」「統治権」の中の「人」に基づくものであることから、いつの時代においても通用する普遍的なものとして機能することになる。
この点でも、国家の根幹となる役職を担う者は、世襲制で決められることには合理性があると考えられる。
〇 世襲制の復元力の高さ
宇宙から飛来した巨大な隕石が東京駅に直撃し、その爆風で東京駅を中心に半径5キロの範囲で街がすべて破壊されたとする。
これにより、国会議事堂、首相官邸、最高裁判所などの建物が失われ、職務中であった国会議員の大半、すべての大臣、行政機関の幹部職員の大半、すべての最高裁判所裁判官が失われたとする。
同様に、皇居にいた天皇や皇族もすべて失われたか行方不明となり、現在の日本国の統治作用を担う主要な人物がほぼ失われてしまった場合を考える。
ただ、そもそも国家というものは人々の頭の中の合意事であり、その合意事が失われていない限りは、国家は存続し続けるといえるものである。
そのため、このような場合においても、やはり日本国憲法やこれまで用いられてきたルールに則って解決が図られることになる。
つまり、戸籍などを用いて日本国民の中からそれまで天皇の地位にあった者と最も近い男系の男子にあたる人物を探し出してきて、その人物に皇位が継承されたことにして統治機能を回復させるということである。
その人物が天皇として即位し、壊滅した東京の街に代わって京都あたりに首都機能を移転させ、国会議員の選挙を公示して国会を召集し、内閣総理大臣と最高裁判所長官を任命することで、通常の統治作用へと回復させるのである。
そこでまた新たに巨大な隕石が飛来し、再開した京都での統治作用が壊滅的な打撃を受けたとしても、やはり日本国民の中から男系の男子にあたる人物を探し出してきて、その者に皇位が継承されたことにして統治機能を回復させていくという流れによって処理されていくことになるのである。
これを繰り返すことにより、結局は男系の男子にあたる人物が日本国内から完全にいなくなるまで、これまで続いてきた形の日本国の統治作用を失わせることはできないのである。
この点で、世襲制は統治作用を復元させる力が非常に高く、非常時においても混乱なく統治の作用を継続することが可能である。
これは、危機に乗じる形で国家の統治権を独占しようとする者や、統治機能を壊乱しようとする者、国家の転覆を図ろうとする者、革命を起こして別の国につくり替えようとする者が現れることが抑制されるという意味において安定性が高く、合理性があるといえる。
【動画】【対談 大塚耕平 参議院議員】ためになる皇位継承の歴史 2022/03/15
<理解の補強>
象徴天皇:時代とともに移り変わる国民統合の意味 2021.09.21
(フォーラム)象徴天皇の未来は 2024年2月11日
「象徴」って何だろう 2024年1月25日
【動画】戦争を経て過去には反発も…“皇室外交”で取り戻した“特別な関係”両陛下訪英【報道ステーション】 2024年6月25日
(戦争を経て過去には反発も…“皇室外交”で取り戻した“特別な関係”両陛下訪英 2024/06/25)
◇ 統治が安定していない場合のイメージ
【動画】マリでクーデターか 大統領拘束され辞意 2020/08/19
【動画】【襲撃】ギニアで大統領拘束 軍によるクーデターか 2021/09/06
【動画】西アフリカ・ギニアでクーデターか 「貧困と汚職のまん延」で大統領排除 2021/09/06
【動画】ブルキナファソでクーデター 軍が大統領排除 イスラム過激派対応への支援不足に不満 2022/01/25
【動画】ミャンマー軍事クーデターから1年 抵抗が流血の内戦へ 2022/02/03
【動画】【解説】 ブラジルの襲撃事件、なぜ起きたのか 2023/01/11
【動画】西アフリカ・ニジェールの軍事クーデターで忍び寄るロシア・プーチン大統領の影 2023年8月4日
【動画】ガボンでクーデター 現職大統領の3選発表後 軍高官グループ「政権を掌握した」と反発 アフリカ中部 2023/08/31
【動画】ブラジル前大統領支持者ら数千人がデモ 23年議会襲撃は「クーデターではない」 2024/02/26
【動画】南米ボリビア 軍がクーデターか 大統領官邸に装甲車 2024年6月27日
【動画】南米ボリビアで軍が大統領官邸を包囲 クーデターを企てるも撤退 2024/06/27
統治の仕組みが十分でない場合には、このような混乱や暴動が起こりやすい状態となる。統治の仕組みとは、このような問題を防ぐところに主要な目的があるのであり、現在の制度がある程度このような問題を防ぐことができているにもかかわらず、このような問題が起き得ることを考えないままに安易に制度を変更してしまうことは危険である。統治の仕組みを考える上では、この点に注意が必要である。