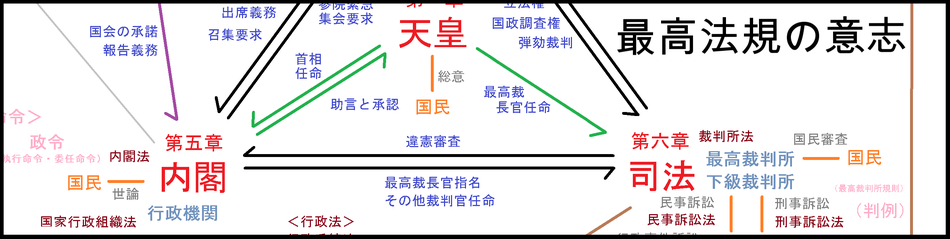同性婚訴訟 札幌高裁判決の分析
【このページの目次】
はじめに
ポイント
〇 「性愛」を論じる誤り
〇 「人格」とはどういう意味か
〇 13条で特定の制度の創設を国家に対して求めることはできないこと
〇 個人と婚姻の関係
〇 「婚姻」のある社会を選択する意図
〇 婚姻が成立するための「条件」
〇 「同性婚」は法律用語ではない
〇 解釈の方法と限界
〇 「目的」の意味の混同
〇 24条2項の「個人の尊厳」と「両性の本質的平等」の適用対象
〇 「個人の尊厳」とは何か
〇 内心による区別取扱いの違憲性
〇 「性愛」による区別取扱いは存在しないこと
〇 司法権の範囲
札幌高裁判決の内容
判決の誤りを継承する解説
はじめに
「同性婚訴訟 札幌高裁判決」の内容を分析する。
判決
━ 令和6年3月14日 (PDF)
【札幌高裁】判決全文 PDF
判決要旨
【札幌高裁】判決要旨 PDF
【判決要旨全文】札幌高裁が「違憲」と判断した理由は?(結婚の平等裁判) 2024年03月14日
この判決文の内容は、誤った前提認識や、法律論でない部分、判例引用の間違いなど、問題が多岐にわたる。複数ヵ所の誤りを同時に解きほぐすことが必要となるため、初学者には難解であると思われる。
ここでは、その誤りを丁寧に確認していきたい。
ポイント
判決の誤りを理解するために、前提として必要となる知識を整理する。
「性愛」を論じる誤り
この判決は「異性愛者」と「同性愛者」の二分論で考えることを前提としているようである。(『対象が異性と同性の双方の場合』は出てくるが、『異性』と『同性』を前提としていることは変わらない。)
しかし、その他にも様々なバリエーションが存在する。
例えば、「両性愛者」「全性愛者」「近親性愛者」「多性愛者」「小児性愛者」「老人性愛者」「死体性愛者」「動物性愛者」「対物性愛者」「対二次元性愛者」などが議論されている。
個々人が「性愛」を抱く場合の対象は様々であり、「性別」という視点に限られるものではなく、「年齢」「身長」「体型」「外見」「部位」「性格」など様々な視点も存在している。
また、「性愛」を抱く対象が「自分自身」に向かう者もいる。
他にも、「性愛」を抱かない「無性愛者」とされる者もいるし、自分の年齢や時期、その時々の気分やタイミング、環境、対象との関係性などによっても、個々人が「性愛」を抱く場合や抱かない場合は様々である。
それにもかかわらず、「性愛」の対象の向かう対象の範囲を「人」に限り、その上でさらに「性別」の視点に限り、「性的指向」と称するものも「異性」あるいは「同性」に二分できることを前提とし、すべての人間を「異性愛者/同性愛者」の二分論で区別することができるかのような論じ方をしている部分は、「性愛」に対する理解を誤っている。
また、この判決では「性的指向」のみを取り上げるのであるが、「性的指向」と「恋愛的指向」を区別するべきであるとの考え方も存在する。
「恋愛」を抱くが、それが「性愛」に結び付くとは限らず、「恋愛」していれば相手を性欲を満たすための対象であるかのように捉えることは、重大な誤認であり、著しく不適切であるとするものである。
他にも、「性愛」を「性的欲求」の側面に限られない意味で使っているのであれば、「愛」の取り上げ方には「友愛」「親子愛」「兄弟愛」「姉妹愛」「会社愛」「宗教愛」などいくらでもある。
さらに、「性愛」であっても、「恋愛」であっても、「友愛」であっても、「兄弟姉妹愛」であっても、「親子愛」であっても、「孫への愛」てあっても、「子孫への愛」であっても、「会社への愛」であっても、「宗教的な愛」であっても、「国家への愛(愛国心)」であっても、「人類愛」であっても、「生命愛」であっても、すべて個々人の内心にのみ存在する精神的なものであることから、これらの様々な「愛」などと称される感情をそれぞれの間で明確に区別することができるという性質のものではない。
そのため、これらはすべて「内心の自由」によって捉えられるべきものである。
また、「愛」などと称される感情もあれば、「嫌悪」など不快な感情も存在する。
そのどちらの感情であっても、そこに法律論上の優劣はないのであり、殊更に「愛」を正当化して法制度を立法することができるという性質のものではない。
一人の人間の中でも、感情は様々な要素を有している。
【イメージの参考】脳内メーカー
このような個々人の有する内心の一側面のみを切り取って、その者を「異性愛者」や「同性愛者」などと明確に区別することができるわけではないのであり、法律論を論じる際に「異性愛者」や「同性愛者」などと区別して考えることができるかのような前提で論じていること自体が誤りである。
これと関連して、この判決が「男女二人一組」の婚姻制度を利用している者をすべて「異性愛者」と考えている点でも誤りである。
婚姻制度は「性愛」の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にどのような対象に向かうかを審査するものではないし、「性愛」に基づいて「婚姻」することを求めるものでも勧めるものでもない。
そのため、法律論としては法制度を利用する者の内心には立ち入ってはならないのであり、「男女二人一組」の婚姻制度を利用する者を「異性愛者」と称する者であるかのような理解を前提として論じるようなこともしてはならない。
「人格」とはどういう意味か
この分野の判決では、下記のように「人格」に関する文言を根拠として法的審査を行おうとしている場合がある。
・人格的尊厳 (大阪地裁判決)(名古屋地裁判決では『人の尊厳』が登場)
・人格的自律 (福岡地裁判決〔人格的自律権として登場〕)
・人格的生存 (東京地裁判決)(名古屋地裁判決)
・人格的利益 (東京地裁判決)(大阪地裁判決)(名古屋地裁判決)(福岡地裁判決)(札幌高裁判決〔最高裁判決の引用として登場〕)
・人格権 (大阪地裁判決)(東京地裁判決〔最高裁判決の引用として登場〕)(名古屋地裁判〔最高裁判決の引用として登場〕)(札幌高裁判決)
しかし、その意味を理解して使っているのか疑わしい。
そこで、「人格的尊厳」、「人格的自律」、「人格的生存」、「人格的利益」、「人格権」の意味を下記でまとめる。
◇ 人格的尊厳
人間として尊重されること、あるいは、個人として尊重されることを指す。(個人の尊重・個人の尊厳)
これは、すべての人が持っている普遍的で不可侵のものであり、他人に譲渡したり放棄したりすることはできない性質である。
◇ 人格的自律
個人が自分の意思に基づいて行動し、自分の人生を自分自身で決めること、また、その自己決定する能力を指す。(自己決定権)
◇ 人格的生存
人が生命を維持し、生存し、生活していくために必要となる(最低限の)ものを指す。
例えば、生命、身体、健康、住居、食料、衣服などがある。
・身体的側面:生命・身体・健康・自由・貞操など
・精神的側面:名誉・信用・氏名・肖像・プライバシーなど
◇ 人格的利益
個人の人格的生存に不可欠な利益であり、他者から侵害されることなく確保されるべきものを指す。
・身体的側面:生命・身体・健康・自由・貞操など
・精神的側面:名誉・信用・氏名・肖像・プライバシーなど
◇ 人格権
個人が社会生活の上で有する人格的利益を保護するための権利を指す。
・身体的側面:生命・身体・健康・自由・貞操など
・精神的側面:名誉・信用・氏名・肖像・プライバシーなど
・名誉:人の価値に対する社会の評価
・プライバシー:社会的評価にかかわりのない私的領域
これらの「人格」に関するものは、憲法13条と関わるものである。
「人格的尊厳」は、法律論上において、人間が権利・義務を結び付けることができる法主体としての地位を認められるかに関わるものであるが、それ以上に何か具体的な内容を引き出すことができるものではない。
「人格的自律」は、個人が自由な意思に基づいて意思決定を行うことを正当化する場合に用いられるが、具体的な制度の創設を求めることができるものではない。
「人格的生存」は、個人が生存していくために必要となる最低限のものを指し、その不可欠な利益を「人格的利益」、その利益を保護するための権利を「人格権」と呼んでおり、国家から個人に対する具体的な侵害行為が生じた場合などに用いることがあるが、具体的な制度の創設を国家に対して求めることができるものではない。
よって、これら「人格」に関する文言を根拠として、具体的な制度の創設を国家に対して求めることができるかのような論旨は誤りとなる。
そして、本来、このような「人格権」を用いることができる場面とは、下記のような場合である。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【北京共同】人工知能(AI)で生成された自身の声を模した音声が文章読み上げソフトに無断で使用されたとして、中国の女性ナレーターが関連企業5社に損害賠償を求めた訴訟で、北京市の裁判所は4月下旬、人格権の侵害を認め、一部企業に25万元(約540万円)の支払いを命じた。国営中央テレビによると「AI音声」の権利侵害を巡る判決は中国で初めて。
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4月23日の判決は「本件音声と原告の声色や語調はほぼ一致しており、本人と識別できる」と認定。人物特定ができる前提下で「声の権利」はAI音声にまで及ぶとの判断を示した。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
AI音声の無断使用は違法 中国初、人格権侵害を認定 2024年5月2日 (下線は筆者)
これに対して、この札幌高裁判決では「性的指向、さらには同性間の婚姻の自由が人格権の一内容を構成し得る」などという形で「人格権」を持ち出すものとなっている。
しかし、「性的指向」や「人的結合関係」を形成すること、「婚姻をするについての自由」にあたるものは、下記のように憲法上の別の条文によって捉えられるものであり、「人格権」として論じることのできるものではない。
◇ 「性的指向」
⇒ 憲法19条「思想良心の自由」
◇ 「人的結合関係」を形成すること
⇒ 憲法21条1項「結社の自由」
◇ 「婚姻をするについての自由」
⇒ 憲法24条1項を解釈した場合に導かれているもの
よって、これらの事柄を「人格権」として論じようとしていることは誤りである。
また、この札幌高裁判決では、「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」の示した「人格権」についての文面を用いて論じようとしている部分もある。
しかし、「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」で論じられているは、下図のように法律上の具体的な制度が存在することを前提として、その制度に基づく「人格権」について触れているものである。
上図のように「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」は、具体的な制度を前提として論じられているものである。
これ対して、この札幌高裁判決で論じている内容は具体的な制度によって定められている事柄を論じているものではない。
下図で、具体的な法制度の存在を前提とする「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」の「氏名」についての事例と、具体的な法制度の存在を前提としないこの札幌高裁判決の事例を比較する。
このように、「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」とこの札幌高裁判決で論じている内容の間には対応関係がなく、関連性が見られないことから、この札幌高裁判決の中で「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」を持ち出して、それに重ね合わせる形で同一の文面を用いることによって結論が導き出されるかような論じ方をしていることは誤りである。
13条で特定の制度の創設を国家に対して求めることはできないこと
憲法13条で特定の制度の創設を国会に対して求める権利が保障されているとはいえない。
これについて、国(行政府)は下記のように説明している。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
……(略)……このように,被告は,現行の法制度が憲法の要請に従って構築されたものであることを前提に,かかる法制度を超える上記の新たな制度の創設を求める権利が憲法13条における自己決定権に含まれるものではないと主張しているのであって,国家の制度を前提にするか否かによって憲法上の保障に値するか否かが決定されると主張しているのではない。
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
そして,婚姻の自由が憲法13条によって保障されるとの見解についてみれば,被告第3準備書面第2の2 (2)イ(ア)(7,8ページ)で述べたとおり,婚姻は,必然的に一定の法制度の存在を前提としている以上,仮に婚姻に関する自己決定権を観念できるとしても,その自己決定権は憲法の要請に従って構築された法制度の枠内で保障されるものにとどまると考えられる。しかるところ,上記見解のいう「婚姻の自由」が,性別を問わず配偶者を選択する自由を含む権利であるとすると,それは,「両性」の本質的平等に立脚すぺきことを規定する憲法24条2項の要請に従って創設された現行の法制度の枠を超えて,同性の者を婚姻相手として選択できることを含む内容の法制度の創設を求めるものにほかならない。……(略)……
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【東京・第6回】被告第4準備書面 PDF (P9~12)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ア(ア)しかしながら、被告第4準備書面第2の2 (8及び9ページ)及び同3(2) (13ないし16ページ)で述ぺたとおり、婚姻及び家族に関する事項については、憲法24条2項に基づき、法律によって具体的な内容を規律するものとされているから、婚姻及び家族に関する権利利益等の内容は、憲法の趣旨を踏まえつつ、法律によって定められる制度に基づき初めて具体的に捉えられるものである。そうすると、婚姻の法的効果を享受する利益や、「婚姻をするかどうか、いつ誰と婚姻をするか」を当事者間で自由に意思決定し、故なくこれを妨げられないという婚姻をするについての自由は、憲法の定める婚姻を具体化する法律(本件規定)に基づく制度によって初めて個人に与えられる、あるいはそれを前提とした自由であり、法制度を離れた生来的、自然権的な自由権として憲法上保障されていると解することはできない。
そうすると、原告らの「婚姻の自由」に関する主張について、自由権の侵害を問題とするものとしては前提を欠いているというぺきである。
(イ)原告らは、上記(1)のとおり、同性力ップルにおいても婚姻の自由は憲法13条により保障されている旨及ぴ同性カップルを婚姻から排除することが違憲である旨主張するが、原告らの主張の本質は、同性間の人的結合関係についても、異性間の人的結合関係を対象とする婚姻と同様の積極的な保護や法的な利益の供与を認める法制度の創設を国家に対して求めるものにほかならない。このような内実のものにすぎない個々の権利若しくは利益又はその総体が憲法13
条の規定する幸福追求権の一内容を構成するものと解することはできず、これは、同性間の人的結合関係を婚姻の対象に含めることが、同性間の婚姻を指向する当事者の自由や幸福追求に資する面があるとしても変わるものではないことは被告第4 準備書面第2の2 (8及び9ページ)で述べたとおりである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【九州・第11回】被告第6準備書面 令和4年11月30日 PDF (P7~8)
このように、憲法13条を根拠として「新たな法制度」の創設を国家に対して求めることはできない。
個人と婚姻の関係
憲法は「個人の尊厳」の原理に基づいており、自然人は「個人主義」の下に「自律的な個人」として生存していくことを予定している。
そのため、何らの制度も利用していない「個人」の状態で既に完全な状態ということができ、それがすべての法制度を検討する際の基準(スタンダード)となる状態である。
そのような中、それらの個々人は、人的結合関係を形成、維持、解消するなどしながら生活していくことになる。
もちろん、個々人が「共同生活」を営むことも可能である。
このような行為は、「国家からの自由」という「自由権」の性質として、憲法21条1項の「結社の自由」によって保障される。
ただ、国民が「生殖」することによって社会的な不都合が発生することを抑制するために、国家の政策的な要請として「生殖と子の養育」の観点から一定の人的結合関係を選び出し、その枠組みを「婚姻」として扱うことを制度化している。
これが、「結社の自由」で保障される他の様々な人的結合関係から区別する意味で「婚姻」という枠組みを設けている理由である。
この点について、国(行政府)は下記のように理解している。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)ア しかしながら、人は、一般に、社会生活を送る中で、種々の、かつ多様な人的結合関係を生成しつつ、生きていくものであり、当該人的結合関係の構築、維持及び解消をめぐる様々な場面において幾多の自己決定を行っていくものと解されるが、そのような自己決定を故なく国家により妨げられているか否かということと、そのような自己決定の対象となる人的結合関係について国家の保護を求めることができるか否かということとは、少なくとも憲法13条の解釈上は区別して検討されるべきものと解される。そして、被告第2準備書面第5の2(3)イ(ア)(42及び43ページ)で述べたとおり、本件規定に基づく婚姻は、人が社会生活を送る中で生成され得る種々の、かつ多様な人的結合関係のうち、一人の男性と一人の女性との人的結合関係とその間に産まれる子との人的結合関係を制度化し、夫婦の身分関係の発生に伴うものを含め、種々の権利を付与するとともに、これに応じた義務も負担させることによって、夫婦関係の長期にわたる円滑な運営及び維持を図ろうとするものであり、本件規定の目的は、一人の男性と一人の女性が子を産み育てながら共同生活を送るという関係に対して特に法的保護を与えることにあると解するのが相当であって、個人の親密な関係を保護することが自己実現などの権利保護のために必要不可欠であるとして婚姻制度が創設されたものではない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【東京二次・第5回】被告第3準備書面 令和4年6月20日 PDF
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(ア)以上の本件諸規定の立法経緯及びその規定内容からすると,本件諸規定に基づく婚姻は,人が社会生活を送る中で生成され得る種々の,かつ多様な人的結合関係のうち,一人の男性と一人の女性との人的結合関係とその間に産まれる子との人的結合関係を制度化し,夫婦に身分関係の発生に伴うものを含め,種々の権利を付与するとともに,これに応じた義務も負担させることによって,夫婦関係の長期にわたる円滑な運営及び維持を図ろうとするものである。すなわち,本件諸規定の目的は,一人の男性と女性が子を産み育てながら共同生活を送るという関係に対して特に法的保護を与えることにあると解するのが相当である。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【大阪・第9回】被告第5準備書面 令和3年9月24日 PDF
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(ア)婚姻は「伝統的に生殖と子の養育を目的とする男女の結合であった。したがって,同性の性的結合関係や共同生活関係は婚姻たりえないとされてきた」ところ,「国ないし社会が婚姻に法的介入をするのは,婚姻が社会の次世代の構成員を生産し,育成する制度として社会的に重要なものであったからである」(乙第1号証)などと指摘されている。このように,伝統的に,婚姻は,生殖と密接に結び付いて理解されてきており,それが異性間のものであることが前提とされてきた。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【大阪・第9回】被告第5準備書面 令和3年9月24日 PDF
もし「婚姻」という制度を立法する目的から「生殖と子の養育」の趣旨が失われた場合には、その時点で他の人的結合関係とは区別することができなくなり、「婚姻」という概念そのものが消失することになる。
「婚姻」のある社会を選択する意図
その社会の中で何らの制度も設けられていない場合には、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合が発生する。
例えば、「父親不明」の子供が増える、父親を特定できない子供が増える、父親が蒸発して行方不明になった子供が増える、それらにより「子の福祉」が減少する、父親を特定できないことにより近親者の範囲を把握できずに「近親交配」に至り潜性遺伝子の発現した個体が高い確率で生じるようになる、一部の強者が多数人との生殖関係を独占することによって社会の中で「子を持ちたいと希望して相手を見つけようとする男女」の数の不均衡が生じて「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」が生まれる、低年齢での妊娠・出産により母体に危険が及ぶ、などの問題が生じることがある。
これらの不都合を解消するために、下記のような立法目的を有する枠組みを設けることが必要となる。
・「子の福祉」が実現される社会基盤を構築すること
・潜性遺伝子の発現した個体が高い確率で生じることを抑制すること
・「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」を減らすこと
・母体を保護すること
そして、これらの目的を達成するためには、下記の要素を満たす枠組みを設けることが必要となる。
・子の遺伝的な父親を特定できる組み合わせとすること
・特定された子の父親にも子に対する責任を担わせること
・特定された子の父親を基に遺伝的な近親者を把握すること
・未婚の男女の数の不均衡を防止できる組み合わせに限定すること
これらの要素を満たすものとして「一人の男性」と「一人の女性」が選び出され、その間に「貞操義務」を設け、その関係を法的に結び付ける形を「婚姻」と呼んでいる。
そして、この「婚姻」に対して法的効果や一定の優遇措置を設けることで、婚姻制度を利用する者を増やし、これらの目的を達成することを目指すものとなっている。
このように、「婚姻」は国民が「生殖」によって子供を産むことに関係して起き得る問題を抑制することを目的として、「生殖と子の養育」の観点に着目して他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた枠組みである。
このような「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解決しようとする目的を離れて「婚姻」を観念することはできない。
よって、「婚姻」の文言には、これらの目的を達成することを阻害する組み合わせを「婚姻」の中に含めることはできないという内在的な限界が含まれており、その限界を超えるものについては「婚姻」とすることはできない。
また、憲法24条は「婚姻」を規定しており、「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めている。
これについても、上記の要素を満たす枠組みとして定められているものである。
この24条の定める形が「婚姻」であり、これらの要素を満たさないものについては「婚姻」とすることはできない。
婚姻が成立するための「条件」
ある組み合わせにおいては「婚姻」することができるが、ある組み合わせにおいては「婚姻」することができない。
これは、婚姻を成立させるための要件が定められていることによるものであり、「条件」ということができる。
下図は、立法目的を達成するための手段として設けられた「婚姻」という制度を利用する場合の「条件」である。
「同性婚」は法律用語ではない
この判決では、「同性婚」という言葉が使われている。
しかし、これは法律用語ではないし、法律論としてこの言葉を使うことには問題がある。
もし「~~婚」と名付けるだけで、それを「婚姻」とすることができるのであれば、「親子婚」「兄弟婚」「姉妹婚」「親戚婚」「師弟婚」「集団婚」「家族婚」「子供婚」「クラス婚」「サークル婚」「宗教団体婚」「組合婚」「会社婚」「政党婚」「不動産婚」「独り者婚」などと、どのような形でも「婚姻」とすることができることになってしまう。
このような考えは妥当でないため、「婚」を付けるだけで何でも「婚姻」とすることができることにはならない。
仮に「~~婚」という言葉を用いたとしても、その「~~婚」という言葉は、「~~」の部分を法的な意味における「婚姻」として扱うことができるとする理由を示すものではない。
そのため、そもそも「~~」の部分について、法的な意味における「婚姻」とすることができるか否かという論点を回避することはできない。
よって、「~~婚」という表現を用いたとしても、常にその「婚」の意味である「婚姻」とは何か、「婚姻」のそのものがどのような枠組みであるかという部分が問われることになる。
そこで、「婚姻」という概念に内在的に含まれている限界について下記で検討する。
「婚姻」は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として設けられた枠組みである。
これは、下記のような経緯によるものである。
その社会の中で何らの制度も設けられていない場合には、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合が発生する。
例えば、「父親不明」の子供が増える、父親を特定できない子供が増える、父親が蒸発して行方不明になった子供が増える、それらにより「子の福祉」が減少する、父親を特定できないことにより近親者の範囲を把握できずに「近親交配」に至り潜性遺伝子の発現した個体が高い確率で生じるようになる、一部の強者が多数人との生殖関係を独占することによって社会の中で「子を持ちたいと希望して相手を見つけようとする男女」の数の不均衡が生じて「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」が生まれる、低年齢での妊娠・出産により母体に危険が及ぶ、などの問題が生じることがある。
これらの不都合を解消するために、下記のような立法目的を有する枠組みを設けることが必要となる。
・「子の福祉」が実現される社会基盤を構築すること
・潜性遺伝子の発現した個体が高い確率で生じることを抑制すること
・「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」を減らすこと
・母体を保護すること
そして、これらの目的を達成するためには、下記の要素を満たす枠組みを設けることが必要となる。
・子の遺伝的な父親を特定できる組み合わせとすること
・特定された子の父親にも子に対する責任を担わせること
・特定された子の父親を基に遺伝的な近親者を把握すること
・未婚の男女の数の不均衡を防止できる組み合わせに限定すること
これらの要素を満たすものとして「一人の男性」と「一人の女性」が選び出され、その間に「貞操義務」を設け、その関係を法的に結び付ける形を「婚姻」と呼んでいる。
そして、この「婚姻」に対して法的効果や一定の優遇措置を設けることで、婚姻制度を利用する者を増やし、これらの目的を達成することを目指すものとなっている。
このように、「婚姻」は国民が「生殖」によって子供を産むことに関係して起き得る問題を抑制することを目的として、「生殖と子の養育」の観点に着目して他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた枠組みである。
このような「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解決しようとする目的を離れて「婚姻」を観念することはできない。
よって、「婚姻」の文言には、これらの目的を達成することを阻害する組み合わせを「婚姻」の中に含めることはできないという内在的な限界が含まれており、その限界を超えるものについては「婚姻」とすることはできない。
また、憲法24条は「婚姻」を規定しており、「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めている。
これについても、上記の要素を満たす枠組みとして定められているものである。
この憲法24条の定める形が「婚姻」であり、これらの要素を満たさないものについては「婚姻」とすることはできない。
そのため、法律論として論じる際には、この点を考えないままに「~~婚」のように、あたかも「~~」の部分を「婚姻」とすることができるかのような前提を含む形で論じることは適切ではない。
この判決では「同性婚」という言葉を使っているが、「同性間の人的結合関係」についても、これらの要素を満たさないことから、「婚姻」とすることはできない。
「同性婚」のように、あたかも「婚姻」として扱うことができるかのような誤解を生む表現を用いていることは妥当であるとはいえない。
「~~婚」という言葉は法律用語として通用するものではないことを押さえ、このような言葉のトリックに惑わされることがないように注意する必要がある。
解釈の方法と限界
法令を解釈する方法と、その限界について検討する。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○政府委員(大出峻郎君) 一般論として申し上げますというと、憲法を初め法令の解釈といいますのは、当該法令の規定の文言とか趣旨等に即して、立案者の意図なども考慮し、また、議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定されるべきものであると考えられるわけであります。
政府による憲法解釈についての見解は、このような考え方に基づき、それぞれ論理的な追求の結果として示されてきたものと承知をいたしており、最高法規である憲法の解釈は、政府がこうした考え方を離れて自由に変更することができるという性質のものではないというふうに考えておるところであります。
特に、国会等における論議の積み重ねを経て確立され定着しているような解釈については、政府がこれを基本的に変更することは困難であるということでございます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第134回国会 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第3号 平成7年11月27日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
憲法を始めとする法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、また、議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定されるべきものであり、政府による憲法の解釈は、このような考え方に基づき、それぞれ論理的な追求の結果として示されてきたものであって、諸情勢の変化とそれから生ずる新たな要請を考慮すべきことは当然であるとしても、なお、前記のような考え方を離れて政府が自由に憲法の解釈を変更することができるという性質のものではないと考えている。仮に、政府において、憲法解釈を便宜的、意図的に変更するようなことをするとすれば、政府の憲法解釈ひいては憲法規範そのものに対する国民の信頼が損なわれかねないと考えられる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書 平成16年6月18日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
また、お尋ねの「法的安定性」とは、法の制定、改廃や、法の適用を安定的に行い、ある行為がどのような法的効果を生ずるかが予見可能な状態をいい、人々の法秩序に対する信頼を保護する原則を指すものと考えている。仮に、政府において、論理的整合性に留意することなく、憲法解釈を便宜的、意図的に変更するようなことをするとすれば、法的安定性を害し、政府の憲法解釈ひいては憲法規範そのものに対する国民の信頼が損なわれかねないと考えられる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
七・一閣議決定の法的安定性と論理的整合性の意味等に関する質問に対する答弁書 平成29年6月27日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法を解釈することと、法を解釈していると思い込んでいることとを区別しうるためには、解釈は個人的・私的なものではなく、社会的な、つまり原理的には誰にも共通にアクセス可能な、公的活動でなければならないはずである。各人がそれぞれ異なった形で得心がいっただけでは、法解釈として十分とはいえない。解釈者は、他人を説得し、同じように既存の法源(判例・法令)を見るように議論を進める必要がある。もちろん、その結果、つねに同一の結論へと人々の意見が集約されるとは限らない。同じ程度に説得力を持つ複数の解釈が競合することは珍しいことではない。
解釈が解釈であるためには、つまり、それが原理的に誰もが参加しうる公的な活動であるためには、第一に、法源の核心的な意味の理解を可能とする共通の言語作用が背景として存在していなければならない。そして、第二に、解釈の目的は、例外的・病理的現象である法の意味の不明瞭化に対して、人々の合意をとりつけることで、正常な法の機能を回復すること、人々が再び疑いをもたずに法に従いうる状態を回復することになければならない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
憲法の理性 長谷部恭男 (P210) (下線は筆者)
「目的」の意味の混同
「目的」の意味には多義性がある。どのような文脈で使われているかによって、その意味するところは異なっているため、注意して読み解く必要がある。
① 「国の立法目的」の意味
概念や制度の枠組みが導かれ、定められる際の立法目的にあたるもの。
例
・「会社法」の立法目的
・「宗教法人法」の立法目的
・婚姻制度の立法目的 ⇒ 「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消すること
② 「制度が機能することによって生じる結果(目的)」の意味
ある制度が機能すると、何らかの結果が生じることになるが、その結果の部分を「目的」と表現することがある。
制度 ⇒(機能すると)⇒ 結果(目的)
例
・「会社」は、営利を目的として事業を行う社団法人である。【動画】
→ 会社が機能すると、営利(経済的な利益)が生じる。
・「宗教法人法」は、宗教団体に法人格を与えることを目的として作られた法律である。
→ 宗教法人法が機能すると、宗教団体に法人格が与えられる。
・婚姻制度の目的は、次世代再生産の可能性のある組み合わせを優遇することである。
→ 婚姻制度が機能すると、次世代再生産の可能性のある組み合わせが優遇される。
この機能面に着目することによって、ある制度を、他の様々な制度との間で区別して理解することが可能となる。
これは、同じ機能を持ち、同じ結果を生じさせる制度であれば、異なる名前を付けている意味がないからである。
そのため、この意味で「目的」という言葉が使われている場合には、その制度を他の制度との間で区別して理解しようとする文脈であることを意味する。
③ 「個々人の利用目的」の意味
個々人がどのような意思をもって制度を利用・活用するかに関するもの。
例
・私の「会社」は営利を目的としているわけではなく、社会貢献が目的である。
・この「宗教団体」は人を幸せにすることを目的としている。
・私は子供をつくることを目的として婚姻する。
下図は、婚姻制度についての、「① 国の立法目的」と、「② 制度が機能することによって生じる結果(目的)」と、「③ 個々人の利用目的」の位置づけである。
この札幌高裁判決の「3 本件規定が憲法24条に違反する旨の主張について」の項目の「(2)ウ」の第二段落で下記のように述べている。
「(2)ウ」の第二段落
◇ 「法令の解釈をする場合には、文言や表現のみでなく、その目的とするところを踏まえて解釈することは一般的に行われており、」
◇ 「仮に立法当時に想定されていなかったとしても、社会の状況の変化に伴い、やはり立法の目的とするところに合わせ、改めて社会生活に適する解釈をすることも行われている。」
これは、法令を解釈する場合において、①「国の立法目的」が検討されることについて述べるものということができる。
そのため、憲法を解釈する過程の部分では、この①「国の立法目的」の内容が検討されるはずである。
しかし、その後の「(2)ウ」の第三段落において、この解釈の過程として挙げられているものは、下記の内容である。
「(2)ウ」の第三段落
A 「性的指向及び同性間の婚姻の自由は、現在に至っては、憲法13条によっても、人格権の一内容を構成する可能性があり、十分に尊重されるべき重要な法的利益であると解される」
B 「憲法24条1項は、婚姻をするかどうか、いつ誰と婚姻をするかについては、 当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたものと解され、このような婚姻をするについての自由は、同項の規定に照らし、十分尊重に値するものと解することができる(再婚禁止期間制度訴訟大法廷判決参照)。」
C 「憲法24条2項は、婚姻及び家族に関する事項についての立法に当たっては、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきと定めている。」
上記「A」の憲法13条の説明については、憲法24条とは別の条文であり、憲法24条が「婚姻」の枠組みを定めている根拠となるようなものではない。
また、「B」の憲法24条1項や「C」の24条2項の説明についても、その条文が意図する機能(その条文が下位の法令に対してどのような影響を与えることが意図されているか)について述べているだけである。
(「B」は、憲法24条1項の条文が存在することを前提として、その意味を解釈した結果として導き出されたものであり、24条1項の条文よりも上位にある規範として示されたものではない。)
(「C」も、憲法24条2項の条文が存在することを前提として、その意味について説明するものであり、24条の条文よりも上位にある規範が示されているわけではない。)
そのため、これも、①の「国の立法目的」にあたる説明をしているものではない。
このように、これらの説明は、憲法24条が「婚姻」の枠組みを定め、その内容を「両性」「夫婦」「相互」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)としていることの背景にある①『国の立法目的』について述べているものではない。
そのことから、これらの説明は、最初に示された法令を解釈する場合において検討される①の「国の立法目的」を示したものであるとはいえず、憲法24条1項が「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めている規範の意味を書き換えることができるとする根拠とはならないものである。
よって、この札幌高裁判決は、前提として示している「目的」(国の立法目的)にあたるものが示されていないままに憲法24条1項の条文に記された文言の意味を変更し、特定の結論だけを述べて正当化を試みるものとなっていることから、結論に至るまでの判断の過程において正当化することができる論理的な筋道のある手続き踏むものとなっておらず、その結論も正当化することはできない。
24条2項の「個人の尊厳」と「両性の本質的平等」の適用対象
憲法24条2項の「個人の尊厳」と「両性の本質的平等」の文言が適用される対象を検討する。
〇 憲法24条2項の読み方と意味
初めに、憲法24条2項の条文の読み方と意味から検討する。
憲法24条2項の「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項」の部分の「並びに」と「及び」の読み方を整理する。
・ A、B、C、D、E 並びに F
・ F = x 及び y に関するその他の事項
この部分の意味を図にすると、下図のようになる。
〇 「個人の尊厳」と「両性の本質的平等」の適用対象
次に、憲法24条2項の「個人の尊厳」と「両性の本質的平等」の文言が適用される対象を検討する。
憲法24条2項の「個人の尊厳」と「両性の本質的平等」の文言は、「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項」に対して適用される。
そのため、この範囲に含まれない場合については、憲法24条2項の「個人の尊厳」と「両性の本質的平等」の文言は適用されない。
「個人の尊厳」とは何か
「個人の尊厳」とは、基本的人権を享有する主体を定義する起点となる概念である。
【動画】宍戸常寿「憲法の運用と「この国のかたち」」(2013年度学術俯瞰講義「この国のかたち−日本の自己イメージ」第10回) 2020/04/26
具体的には、下記のように整理することができる。
〇 自然人とそれ以外との関係
まず、「個人の尊厳」は、自然人であれば誰もが持つとされている。
この意味では「個人の尊厳」の背景に「人間の尊厳」があることを前提に、人間以外のものとの対比に主眼を置いて使われている。
(例:家畜のように扱われてはならない。物のように扱われてはならない。)
【動画】【司法試験】2021年開講!塾長クラス体験講義~伊藤塾長の最新講義をリアルタイムで体験しよう~<体系マスター憲法1-3> 2021/02/06
自然人 Wikipedia
そのため、人間であるにもかかわらず法的に自然人として扱われていない状態、例えば、人が物や動物のように扱われたり、奴隷のように扱われたりしている場合には、この意味の「個人の尊厳」を用いて是正することができる。
〇 個人主義と全体主義との関係
また、「個人の尊厳」は、「全体主義」との対比において「個人主義」に根差すという文脈で使われている。
(例:全体の中の一部として扱われてはならない。全体のための存在として扱われてはならない。)
【自民党憲法改正案の問題点:第13条】個人を「人」にして支配 2020.10.18
そのため、個人が全体の中の一部として扱われたり、個々人が何者かの付属物として扱われたりすることがあれば、この意味の「個人の尊厳」を用いて是正することができる。
〇 権利能力・意思能力・行為能力との関係
他にも、「個人の尊厳」は、権利や義務を結び付けることのできる法的な主体としての地位を指すものである。
民法3条:権利能力とは?わかりやすく解説【権利能力平等の原則】 2021年2月21日
権利能力 Wikipedia
【動画】基本講義「民法」単元3後半 権利能力・意思能力・行為能力 2020/03/22
【動画】〔独学〕司法試験・予備試験合格講座 民法(基本知識・論証パターン編)第8講:権利能力と胎児 〔2021年版・民法改正対応済み〕 2021/05/28
【動画】【行政書士試験対策】権利能力//権利・義務の主体となれるのは? 2023/03/25
【動画】民法本論1 01権利能力 2011/04/11
【動画】2021応用インプット講座 民法5(総則5 権利能力) 2020/11/20
【動画】民法入門1 民法の全体像 2021/04/29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
民法は我々の生活関係を権利と義務に分解して規定し、規律するが、この権利及び義務の帰属主体となりうる資格を権利能力という。民法は、権利能力はあらゆる自然人が平等に有するとしているが、このことは近代法によって確立された原則であり、近代法が発達する以前の時代、すなわち奴隷制が存在した時代や、封建時代には、人によっては権利能力を認められない自然人も存在したのである。人は権利能力があって初めて法律的に自由な経済活動が可能となるのであり、その権利能力を自然人に平等に認めるのは、憲法の要請でもある。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第15課 民法―権利義務の主体(自然人その1) (下線・太字は筆者)
そのため、「権利能力」を喪失させられたり、「意思能力」を否定されたり、「行為能力」を制限されるようなことがあった場合に、この意味の「個人の尊厳」を用いてそれを是正することができる。
しかし、このような意味を離れて「個人の尊厳」という言葉を用いることはできないことに注意が必要である。
内心による区別取扱いの違憲性
特定の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的とした制度を立法した場合には違憲になる。
また、人の内心に着目して区別取扱いを行う制度を立法することも違憲になる。
上図のように、特定の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的として制度を立法すると違憲になる。
そのため、婚姻制度を立法する際にも、特定の思想・信条・感情を保護することを目的とする場合には、違憲になる。
この札幌高裁判決は、婚姻制度が特定の「性愛」を保護することを目的とした制度であるかのような前提で論じている部分があるが、そのような立法目的に基づいて法制度が定められていた場合には、そのこと自体で違憲となる。
法制度は思想、信条、信仰、感情に対して中立性を保たなければならない。
「性愛」による区別取扱いは存在しないこと
婚姻制度は「性愛」を保護することを目的とする制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いをする制度ではないし、「性愛」に基づいて制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもない。
そのため、婚姻制度は「性愛」による区別取扱いをする制度であるとはいえない。
「性愛」による区別取扱いを行う制度とは、例えば下記のようなものが該当する。
【参考】<わいせつ行為で処分された教員は9年連続200人以上>愛知医科大准教授が小児性愛障害診断テストを開発中「日本版DBSだけでは子どもへの性犯罪を防げない」 2023.09.28
これは、個々人の「性愛」の有無や、「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して、その審査の結果によって区別取扱いを行うものということができる。
これは、人の内心を審査した結果に応じて不利益を課すものであるから、「内心の自由」を侵害するものであり、憲法19条の「思想良心の自由」や20条1項の「信教の自由」に抵触して違憲となる。
しかし、今回の事例は、このような性質のものではなく、「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかについての「性的指向」と称するものによる区別取扱いは存在しない。
司法権の範囲
裁判所が「司法権」の範囲を超える判断を行うことはできないことについて検討する。
〇 「司法権」の範囲を逸脱してはならないこと
日本国憲法は、国家の作用を「立法権」「行政権」「司法権」の三権に分割している。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○味村政府委員 三権分立と申しますと、委員がただいま述べられましたように、国家作用を立法、司法、行政の三つに分かちまして、そのおのおのを担当いたします機関を相互に分離、独立させ、それらの機関を相互に牽制させるという統治組織の原理であると心得ております。この原理は、委員御指摘のような理念に基づきまして、近代民主主義国家におきまして広く採用されているところでございまして、日本国憲法の定めております統治組織もこの原理を基本原理としておる次第でございます。
(略)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第109回国会 衆議院 予算委員会 第3号 昭和62年7月14日
これら三権の中で「司法権」しか有していない裁判所が、他の機関の有する権限を行使したり、干渉したりすることは許されない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○味村政府委員 日本国憲法は三権分立の制度をとっておりまして、立法、司法、行政はそれぞれ独立してその職務を遂行するということに相なっておるわけでございます。もちろん、その間に相互の関連が生じないというわけではございません。たとえば立法につきまして、法律が成立いたしました後でそれが憲法に違反するかどうかということの違憲立法審査権は、これは裁判所が持っておるというように、その相互に関連はございます。
しかし、立法は国会の専権事項でございまして、どのような法律を制定するかということは国会の専権事項になっておりまして、それに関しましては司法は介入することができない、このように存じます。
(略)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第80回国会 衆議院 地方行政委員会 第21号 昭和52年5月13日
〇 国民の賛否を集約することは「政治部門」の役割であること
特定の政策に対する国民の賛成意見や反対意見を集約し、憲法の枠内で政策を選択することは、政治部門である国会や内閣以下の行政機関の役割である。
そのため、裁判所が国民の賛否を勘案するなどして判断を行うことはできない。
また、司法権の行使においては、法令に違反するかという合法・違法の判断のみしか行うことはできない。
そして、法令に記された規範の意味は国民の賛否によって変化するものではないことから、国民の賛否を勘案することによって結論を導き出すことができるというものではない。
そのため、政治部門の政策的な議論に任せるべき領域の事柄を勘案して判断を行うことは、司法権の範囲を逸脱するものとなる。
また、政治部門の政策的な議論に任せるべき領域の事柄に対して裁判所が意見を述べることも、司法権の範囲を逸脱するものである。
〇 裁判所で判断できるのは「法律上の争訟」に限られること
裁判所で判断することができるのは裁判所法3条の「法律上の争訟」の範囲に限られる。
裁判所法
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第三条(裁判所の権限) 裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。
② ……(略)……
③ ……(略)……
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
そのため、この「法律上の争訟」の範囲に含まれない事柄について、判断してはならない。
札幌高裁判決の内容
具体的に、判決の誤りを確認する。
〇 原判決である札幌地裁判決と、この札幌高裁判決を融合した形で記載する。
この札幌高裁判決の内容は、原判決である札幌地裁判決が存在することを前提として、その内容を「引用」し、部分的に「読み替える」、「補正」、「改める」、「加える」などを行う形で論じられている。
しかし、この札幌高裁判決に記された指示を示すだけでは、この判決の全体を見渡すことはできず、全体を把握することは困難である。
そのため、ここではこの札幌高裁判決の文面をそのまま記載するのではなく、原判決である札幌地裁判決をベースとし、この札幌高裁判決の指示に従う形で、その原判決である札幌地裁判決を修正した状態で読み取ることができるように記載し、札幌高裁判決の全体を見渡せる形で記載することにする。
原判決である札幌地裁判決の内容は、次の通りである。
損害賠償請求事件 札幌地方裁判所 令和3年3月17日 (PDF)
下記では、この原判決である札幌地裁判決の内容(黄緑色で潰した部分)を前提とし、札幌高裁判決の指示に従って文面を修正した形で記載している。
〇 項目のタイトルの文字サイズを拡大したところと、太字にしたところがある。
〇 「性愛」「異性愛」「同性愛」「異性愛者」「同性愛者」「同性愛者等」に色付けをした。
〇 「同性の者との間の婚姻の自由」「同性の者との婚姻の自由」「性的指向及び同性間の婚姻の自由」「性的指向と同性間の婚姻の自由」「同性間の婚姻」「同性者間の婚姻」に色付けした。
〇 「同性婚」に色付けした。
〇 「パートナーシップ認定制度」に色付けした。
〇 「個人の尊重」に色付けした。
〇 「個人の尊厳」に色付けした。
〇 「人格権」に色付けした。
〇 「不利益」に色付けした。
〇 この判決で頻出する「合理」に関する部分に色付けした。
「合理的な立法裁量」
「合理性」
「合理性」
「合理的に区別する理由」
「合理的な理由」
「合理的な理由」
「合理性」
「合理的な根拠」
「合理的な裁量」
「合理的理由」
「合理的な根拠」
「合理的根拠」
「合理的な理由」
「合理的な根拠」
「合理的な区別の理由」
「合理的な根拠」
〇 下記を太字にした。
「婚姻及び家族に関するその他の事項」
「婚姻及び家族に関する事項」
「婚姻及び家族に関する法制度」
「婚姻と家族に係る法制度等」
「婚姻や家族に関する制度」
「婚姻及び家族の法制度」
「婚姻と家族の制度」
「家族制度」
〇 主要な文に色付けしているところがある。
〇 リンクを加えた。
【筆者】
インデント(字下げ)を加えて記載したところは、筆者の分析である。
令和6年3月14日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官
令和3年(ネ)第194号 損害賠償請求控訴事件
(原審・札幌地方裁判所平成31年(ワ)第267号)
口頭弁論終結日 令和5年10月31日
判決
当事者及び代理人の表示
別紙「当事者目録」の記載のとおり
主 文
1 本件控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
事実及び理由
第1 控訴の趣旨
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人は、控訴人らに対し、各100万円及びこれに対する平成31年2月28日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
1 本件は、同性愛者である控訴人らが、民法及び戸籍法が同性者間の婚姻を許容していないのは憲法24条、13条、14条1項に違反すること、国会は必要な立法措置を講じるべき義務があるのにこれを怠っていること(立法不作為)、これにより控訴人らは婚姻することができず、精神的苦痛を被っていることを主張して、被控訴人に対し、国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づく損害賠償として、各人につき100万円及びこれに対する平成31年2月28日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
原審は、民法及び戸籍法の婚姻に関する諸規定(本件規定)が同性者間の婚姻を許容していないことは、憲法24条と13条には違反しないものの、憲法14条1項には違反するとしたが、そのことを国会において直ちに認識することは容易ではなかったから、国賠法1条1項の適用上違法の評価を受けないとして、控訴人らの請求を棄却した。
控訴人らは、これを不服として本件控訴を提起した。
2 前提事実(いずれも当事者間に争いがない。)
⑴ 性的指向
性的指向とは,人が情緒的,感情的,性的な意味で,人に対して魅力を感じることであり,このような恋愛・性愛の対象が異性に対して向くことが異性愛,同性に対して向くことが同性愛である(以下,性的指向が異性愛である者を「異性愛者」,性的指向が同性愛である者を「同性愛者」という。)。
⑵ 控訴人らの関係等
ア 控訴人1及び控訴人2は,いずれも男性であり,同性愛者である。
控訴人1及び控訴人2は,平成31年1月,居住地において婚姻届を提出したが,両者が同性であることを理由に不受理とされた。
イ 控訴人3及び控訴人4は,いずれも男性であり,同性愛者である。
控訴人3及び控訴人4は,平成31年1月,居住地において婚姻届を提出したが,両者が同性であることを理由に不受理とされた。
ウ 控訴人5及び控訴人6は,いずれも女性であり,同性愛者である。
控訴人5及び控訴人6は,平成31年1月,居住地において婚姻届を提出したが,両者が同性であることを理由に不受理とされた。
3 民法及び戸籍法の関連規定
民法739条1項は,婚姻は戸籍法の定めるところにより届け出ることによってその効力を生ずるとし,同法74条1号は,婚姻をしようとする者は,夫婦が称する氏を届け出なければならない旨規定するなど,婚姻制度を定める民法及び戸籍法の諸規定が全体として異性間の婚姻(以下「異性婚」という。)のみを認めることとし,同性間の婚姻(以下「同性婚」という。)を認める規定を設けておらず,これら民法及び戸籍法の婚姻に関する諸規定(以下,総称して「本件規定」という。)は,婚姻は,異性間でなければすることができない旨規定している。
4 争点及び争点に対する当事者の主張の要旨
本件の争点は次のとおりであり,争点に対する当事者の主張の要旨は,原判決別紙2のとおりである。なお,同原判決別紙で定義した用語は,本文においても用いる。
⑴ 本件規定は憲法13条,14条1項又は24条に違反するものであるか
⑵ 本件規定を改廃しないことが国家賠償法1条1項の適用上違法であるか
⑶ 控訴人らの損害額
3 当審における控訴人らの補充主張
(1) 憲法24条、13条違反について
婚姻の自由の憲法上の保障の根拠は、第一次的には憲法24条にあるが、その背後には憲法13条が基盤とする国民の自由・幸福追求の権利が存するのであり、本件規定の憲法適合性の検討に当たっては、両条を併せて考慮すべきものである。憲法24条の「婚姻」の解釈は社会状況の変化により変動し得るものであり、「両性」、「夫婦」という同条の文言や制定時の理解にとらわれることなく、婚姻によって国民が享受し得る利益の重要性を踏まえた上、憲法13条の自由・幸福追求の権利の観念を背景に、国民に対し、婚姻をするかどうか、いつ誰と婚姻するかについての自由を認めた趣旨(最高裁平成25年(オ)第1079号同27年12月16日大法廷判決・民集69巻8号2427頁〔以下「再婚禁止期間制度訴訟大法廷判決」という。〕)に立ち返れば、国民が同性パートナーを婚姻の相手に選択する自由も憲法24条1項の規定上保障ないし保護されるものと解するのが適切である。
また、憲法が同性カップルに婚姻や家族関係の形成を認める立法を禁止していないことからすると、同性カップルに婚姻等を認めることは国会の立法裁量の問題となるところ、憲法24条2項は、個人の尊厳等の観点から婚姻及び家族に関する事項についての国会の立法裁量の限界を画し、憲法上の権利に至らない国民の人格的利益をも尊重し、婚姻制度の内容により婚姻が事実上不当に制約されることのないこと等についても十分に配慮した法律の制定を要請しているから(最高裁平成26年(オ)第1023号同27年12月16日大法廷判決・民集69巻8号2586頁〔以下「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」という。〕)、婚姻及び家族に関する法制度として同性カップルに婚姻等を認めない本件規定を改廃しないことは、国会の立法裁量の範囲を逸脱したものとして違憲である。
社会情勢としても、令和5年1月時点で、同性婚を認める国・地域は34か国に増え、世界のGDPに占める同性婚を認める国の割合は52%であり、パートナーシップ認定制度を導入した地方公共団体は264に増え、総人口カバー率も65%を超えている。世論調査で同性婚を認めるべきとする意見は令和5年1月時点では5~7割に増えている。弁護士会等の弁護士団体や学術団体、福祉系団体の決議や宣言、会長声明、提言等も多く出ている。これに対し、同性カップルに対する差別・偏見に基づく発言は、むしろ内閣総理大臣や首相秘書官、国会議員や地方議会議員、一部の政治団体等から発せられており、国会では、法制化に向けた議論や審議すら行われていない。
なお、同性カップルに婚姻や家族形成を認めるか否かという問題と、認めるとした場合にいかなる形式及び内容とするかという問題とは別問題であるから、仮に後者につき立法裁量が認められるとしても、それによって前者につき同性カップルに婚姻や家族関係の形成を全く認めない現状の合理性が肯定されることにはならない。また、上記の区別ないし事態は、現存する本件規定によって生じているものであるから、仮に、同性カップルにつき婚姻類似の制度を創設することが可能であるとしても、それによって現に存在する本件規定の違憲性が否定されることになるものではない。諸外国のように婚姻制度とほぼ同じ法的効果を有する登録パートナーシップ制度が制定されたとしても、婚姻と婚姻類似の制度とが法律上区別されているとすれば、それらを利用するカップルの関係も同等のものではなく、婚姻類似の制度を利用した同性カップルの関係は、婚姻制度を利用した異性カップルの関係と同等の重要性や意義を持つものでなく、婚姻の名に値しないような劣ったものであると社会に受け止められることとなりかねないし、婚姻類似の制度を利用できるのは同性カップルのみということになれば、婚姻類似の制度を利用していることを明らかにすることが、性的指向や性自認のカミングアウトにつながってしまうこととなり、むしろ差別の再生産につながるから相当でない。
そもそも、共同生活の保護を目的とする規定である夫婦財産制(民法755条以下)、夫婦相互の同居・協カ・扶助義務(同法752条)、配偶者の相続権(同法890条)等につき、異性カップルと同性カップルに異なる規定を設ける理由はない。また、生殖関係や親子関係に関する規定である嫡出推定(同法772条)、認知(同法779条以下)、親権(同法818条以下)、養子縁組(同法795条、817条の3)等についても、男女を前提とする文言を改正するだけで同性・カップルにそのまま適用することに支障はない。嫡出推定は女性カップル固有の問題であるが、一方の女性が出産した場合に、他方の女性の嫡出子として共同親権を認めればよく、認知の問題も生じない。このことは、遺伝学上の父親となりえないはずの性別変更をしたトランスジェンダー男性につき、懐胎した妻の子に関する嫡出推定を認めた最高裁平成25年(許)第5号同年12月10日第三小法廷決定・民集67巻9号1847頁で解決済みである。さらに、同性カップルに対する社会的承認の進んでいる現状において、同性カップルに婚姻制度の利用を承認する前に、登録パートナーシップ制度を創設し運用するといった段階を踏まなければならない理由はなく、多大なコストと労力をかけて戸籍と異なる独自の登録簿制度を設ける必要もない。
よって、国会には、現行の婚姻制度の対象に同性カップルも含める以外の立法を選択する余地はない。
(2) 憲法14条1項違反について
本件規定の憲法14条1項適合性の判断に当たって、同性婚に対する否定的な意見や価値観を持つ国民が少なからずいることを、立法府が裁量権の行使に当たって勘酌し得るものとすることは、結局、合理的な理由を欠いた差別的な意見や価値観をもって区別取扱いの合理的根拠とすることとなるから相当でなく、むしろ、このような意見や価値観があることを考慮して、同性婚を社会的差別から守るための特別の制度を構築することが必要であるというべきである。
また、本件規定が憲法14条1項に適合的な制度となるためには、同性婚のカップルにも異性婚のカップルと同様の婚姻によって生ずる法的効果が与えられるべきであって、同性婚のカップルに婚姻によって生ずる法的効果の一部でも共有する法的手段を提供すれば足りるというものではない。諸外国の例にあるような登録パートナーシップ制度をあえて異性婚とは別の法制度として設けることは、合理的理由を欠いた差別的なものであるとしてアメリカの判例法理でも否定された「分離すれど平等」の誤りを繰り返すものとして当然に否定されるべきものである。
(3) 立法不作為の国賠法上の違法性について
法律の規定が憲法に違反することの明白性の有無の判断に当たっては、まず、違憲とされる憲法上の権利の性質や当該法律の規定によるその侵害の内容・程度が考慮要素となるところ、婚姻によって生ずる法的効果を享受する利益は、憲法24条がその実現のための婚姻を制度として保障していることに照らしても、重要な法的利益であるということができる。しかるところ、本件規定は、同性愛者に対しては、そのような重要な利益である婚姻によって生ずる法的効果を享受する法的手段を提供しないとしているものであり、また、それは本件規定の改正がなされるまで継続するものである。そして、このような利益侵害は、控訴人らを含む日本の全人口の5.9~8.0%に及ぶものであるから、本件規定は、国民の重要な利益に対する極めて重大な侵害を生じさせるものであることが明らかである。
また、デンマークにおける最初の登録パートナーシップ制度の導入は1989年(平成元年)であり、2000年(平成12年)から2010年(平成22年)までの10年間に限っても10か国で同性婚制度が導入されていること、この間、同性婚を含む性的指向に基づく差別の解消が、法律問題あるいは憲法問題として、国会においても絶えず議論の対象とされてきたことに鑑みれば、国会議員においては、本件規定が今日においてなお合理性を有するものであるか否かについて自ら検討し、あるいは、議員の活動を補佐するために設置されている衆参両議院の事務局及び議院法制局に対し調査・検討の助力を求めたり、外部の専門家から見解を仰いだりするなどの手段を用いて検討を深めることにより、本件規定がもはや合理性を欠くものとして憲法に違反するとの認識に達することも十分に可能な状況であったというべきである。
したがって、国会議員は、その職務上の法的義務として、自ら率先して上記のような検討を行い、本件規定の合理性を不断に吟味すべき能動的な義務を負っていたものと解すべきである。
それにもかかわらず、国会が依然として本件規定を改正しないことから、地方公共団体において、直接的な法的効果は生じないパートナーシップ認定制度の導入が急速に広まったのであり、このような事情は、同性婚制度に関する立法不作為の明白な違法性を肯定する方向に働く積極的要素の1つとして考慮されるべきである。
第3 当裁判所の判断
1 当裁判所も、控訴人らの請求はいずれも理由がないと判断する。
1 認定事実
後掲証拠等によれば,次の事実を認めることができる。
⑴ 性的指向等
ア 性的指向
性的指向とは,人が情緒的,感情的,性的な意味で,人に対して魅力を感じることであり,このような恋愛・性愛の対象が異性に対して向くことが異性愛,同性に対して向くことが同性愛である。性的指向が決定される原因,又は同性愛となる原因は解明されておらず,遺伝的要因,生育環境等複数の要因が組み合わさって作用している可能性が指摘されているが,精神医学に関わる大部分の専門家団体は,ほとんどの人の場合,性的指向は,人生の初期か出生前に決定され,選択するものではないとしており,心理学の主たる見解も,性的指向は意思で選ぶものでも,意思により変えられるものでもないとしている。同性愛者の中には,性行動を変える者もいるが,それは性的指向を変化させたわけではなく行動を変えたにすぎないものであり,自己の意思や精神医学的な療法によっても性的指向が変わることはない。(前提事実⑴,甲A2〔枝番号を含む〕,7〔枝番号を含む〕,231,233,235,控訴人1~2,4~6本人)
イ 性的指向別の人口
我が国における異性愛以外の性的指向を持つ者の人口は明らかではないが,いわゆるLGBT(男性及び女性の各同性愛者,同性愛と異性愛の双方の性的指向を有する両性愛者及び心の性と体の性が一致していないトランスジェンダーの総称)に該当する人が,人口の7.6%とする調査,5.9%とする調査,8%とする調査などがあり,いずれの調査においても異性愛者の割合は9割を超えている(甲A350)。
⑵ 明治期における同性愛に関する知見
明治期においては,同性愛は,健康者と精神病者との中間にある変質狂の1つである色情感覚異常又は先天性の疾病であるとされていた。色情感覚異常の著明な症状は,色情倒錯又は同性的色情であり,男子は年少の男子に対して色情を持ち,「鶏姦」(男性間の性的行為)をするものとされ,女子は女子を愛してしまうものであり,これらが変質徴候の第一とされていた。このような色情感覚異常者に対する治療法として,催眠術を施すほか,臭素剤を投与する,身体的労働をさせる,冷水浴をさせる,境遇を変化させるなどが行われていた。(甲A187,189)
また,青年期における同性愛は,愛情に対する欲求が極めて強いために起こることであり,ある程度を超えなければ心配する必要がないが,同性同士の愛情を深め,不純な同性愛に向くこともあり,そのような場合はすこぶる注意すべきことであって,絶対に禁止すべきものとされていた(甲A190)。
このような考え方は、明治31年の明治民法制定以前からみられる考え方であった。(甲A485、486)
⑶ 昭和22年法律第222号による改正(以下「昭和22年民法改正」という。)前の民法の家族法部分(以下「明治民法」という。)における婚姻制度等
ア 明治民法の起草
明治民法の起草に当たっては,フランス民法,イタリア民法,ベルギー民法など8か国の外国法を参照するところから始まったが,その起草過程においては,婚姻は当然に男女がするものであることが前提とされており,同性婚の許否について議論がされた形跡は見当たらない。当時の外国法においては,同性婚を明示的に禁止するものもみられたが,起草者は,同性婚が認められないことは当然であって,あえて民法に規定を置くまでもないと考えていた。(甲A184,186,188)。
イ 明治民法における婚姻
明治民法が制定される以前から,婚姻は,人生における重要な出来事の1つとされ,かつ,既に一定の慣習が存在した。明治民法は,そのような慣習を直ちに改めるのではなく,慣習を踏襲しつつも,慣習の中には,そのまま認めれば弊害となる事柄があったり,慣習によっては決められない不明な点もあったりしたことから,そのような事柄について法により規律するものとして制定された。(乙3)
明治民法においては,家を中心とする家族主義の観念から,家長である戸主に家を統率するための戸主権を与え,婚姻は家のためのものであるとして戸主や親の同意が要件とされ,当事者間の合意のみによってはできないものとされた上,夫の妻に対する優位が認められていた。このような明治民法における婚姻は,終生の共同生活を目的とする,男女の,道徳上及び風俗上の要求に合致した結合関係であり,又は,異性間の結合によって定まった男女間の生存結合を法律によって公認したものであるとされた。したがって,婚姻が男女間におけるものであることはいうまでもないことであるとされ,よって,同性婚を禁じる規定は置かれていなかった。同性婚は,学問を妻とするとか,書籍を配偶者とするなどの比喩を用いる場合と同様に,婚姻意思を全く欠くものとして否認されなければならないとされた。(甲A19、183、188、193、194、乙4、5)
ウ 明治民法における婚姻制度の目的
明治民法においては,その起草時から,子をつくる能力を持たない男女であっても婚姻をすることができるかという検討・議論がされていた。婚姻の性質を,男女が種族を永続させるとともに,人生の苦難を共有して共同生活を送ることと解すべしとの見解があった一方で,男女が種族を永続させるとの定義は,老齢等の理由により子をつくることができない夫婦がいることを説明できないとの反対の見解が示された。また,子をつくる能力がない男女は,婚姻の材料を欠き,その目的を達し得ないから婚姻し得ないとの見解が示された一方で,そのように婚姻を理解するのは明治民法の趣旨に沿ったものではなく,婚姻とは両者の和合にその本質があり,子をつくる能力は婚姻に必要不可欠の条件ではないとの反対の見解が示された。
このような議論を経て,明治民法においては,婚姻とは,男女が夫婦の共同生活を送ることであり,必ずしも子を得ることを目的とせず,又は子を残すことのみが目的ではないと考えられるに至り,したがって,老年者や生殖不能な者の婚姻も有効に成立するとの見解が確立された。
(以上につき,甲A186,196,199,乙4)
⑷ 戦後初期(昭和20年頃)から昭和55年頃までの間における同性愛に関する知見等
ア 医学,心理学領域における同性愛に関する知見
戦後初期においても,鶏姦又は女子相姦は,変態性欲の1つとされた。すなわち,鶏姦や女子相姦は,陰部暴露症などと並んで精神異常者や,色欲倒錯者に多くみられるものであり,病理とされた。
心理学の分野においても,同性愛は,古来より存在し,民族や階級等にかかわらず存在する,性欲の質的異常とされていた。同性愛は,異性愛への心理的成熟以前に,精神的又は肉体的な同性愛を経験しそれが定着した場合に生じることがあるとされ,その後,異性愛者となり,健康な結婚生活を営めるようになる場合が一般的ではあるものの,外的要因によって同性愛に病的に定着してしまうことがあり,それは一般の健康な親愛とは違って,性的不適応の一種であるとされた。そのように病的に同性愛が定着してしまった場合の心理療法として,自己暗示,自己観察,原因の探求などを行うものとされ,異性愛に対する障害を取り去ることが根本的対策であるともされていた。
(以上につき,甲A201~205)
イ 外国における同性愛に関する知見
米国精神医学会が,1952年(昭和27年)に刊行した精神障害のための診断と統計の手引き第1版(DSM-Ⅰ)及び1968年(昭和43)年に刊行した同第2版(DSM-Ⅱ)においては,同性愛は,病理的セクシュアリティーを伴う精神病質人格又は人格障害とされていた(甲A48,215)。
また,世界保健機関が公表した国際疾病分類(ICD)においても,1992年(平成4年)に改訂第10版(ICD-10)が公表されるまでの改訂第9版(ICD-9)以前においては,同性愛は性的偏倚と性的障害の項目に位置付けられていた(甲A29)。
ウ 教育領域における同性愛の扱い
昭和54年1月,当時の文部省が発行した中学校,高等学校の生徒指導のための資料である「生徒の問題行動に関する基礎資料」には,性非行の中の倒錯型性非行として同性愛が示されており,正常な異性愛が何らかの原因によって異性への嫌悪感となったりすること,年齢が上がるに従い正常な異性愛に戻る場合が多いが成人後まで続くこともあること,一般的に健全な異性愛の発達を阻害するおそれがあり,また社会的にも健全な社会道徳に反し,性の秩序を乱す行為となり得るもので,現代社会にあっても是認されるものではないことなどが示されていた(甲A26)。
⑸ 昭和22年民法改正後の民法の家族法(以下「現行民法」という。)における婚姻
ア 昭和22年民法改正
昭和22年民法改正は,明治民法を改正するものであったが,これは次の理由による。
憲法13条及び14条は,全て国民は個人として尊重され,法の下に平等であって,性別その他により経済的又は社会的関係において差別されないことを明らかにし,同法24条では,婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し,夫婦が同等の権利を有することを基本として,相互の協力により維持されなければならないこと,及び配偶者の選択,財産権,相続,住居の選定,離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては,法律は個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならないことを宣言しているが,明治民法には,この憲法の基本原則に抵触する規定があるので,これを改正する必要があるとされた。すなわち,明治民法においては,家を中心とする家族主義の観念から,家長である戸主に家を統率するための戸主権を与え,婚姻も家のためのものであるとされ,戸主や親の同意が要件とされ,当事者間の合意のみによってはできないものとされ,また,夫の妻に対する優位が認められていたことから,これを,婚姻の自主性を宣言し,個人を自己目的とする個人主義的家族観に基づいた家族基盤の法律的規制に改めるためにされたものである。
もっとも,昭和22年民法改正は,明治民法のうち憲法に抵触する規定を中心に行われ,憲法に抵触しない規定については明治民法の規定を踏襲したものであり,この際に同性婚については議論された形跡はない。
(以上につき,甲A19,142,143,145,146,152,177,乙6,7,弁論の全趣旨)
イ 昭和22年民法改正当時に考えられていた婚姻
昭和22年民法改正によっても,婚姻は引き続き男女の当事者のみができるものとされ,夫婦関係とは,社会で一般に夫婦関係と考えられているような,社会通念による夫婦関係を築く男女の精神的・肉体的結合であるとされていた。また,婚姻意思とは,当事者に社会の風俗によって定まる夫婦たる身分を与え,将来当事者間に生まれた子に,社会の風習によって定める子たる身分を取得させようとする意思,又は,その時代の社会通念に従って婚姻とみられるような関係を形成する意思であるなどと解されていた。(甲A206,207,乙8,9)
ウ 同性婚に対する理解
昭和22年民法改正が行われた頃は,上記イのとおり,夫婦関係とは,社会で一般に夫婦関係と考えられているような,社会通念による夫婦関係を築く男女の精神的・肉体的結合であるとされていたため,同性婚はその意味で婚姻ではないとされた。また,明治民法下と同様に,同性婚は,学問を妻とするとか,芸術と結婚するなどと比喩する場合と同様に,婚姻意思を全く欠くものとして否認されなければならないとされた。(甲A206,207,乙9)
⑹ 昭和48年頃以降における同性愛に関する知見
ア 外国における同性愛に関する知見の変化
米国精神医学会は,1973年(昭和48年),同性愛を同学会の精神障害のリストから取り除くとの決議を行い,1975年(昭和50年)には,米国心理学会も,上記米国精神医学会の決議を支持し,同性愛それ自体では,判断力,安定性,信頼性,一般的な社会的能力又は職業遂行における障害を意味しないとの決議を採択した(甲A1〔枝番号を含む〕,3〔枝番号を含む〕)。
米国精神医学会は,1980年(昭和55年)に刊行した精神障害のための診断と統計の手引き第3版(DSM-Ⅲ)において,同性愛は,同性愛者である患者が,同性愛的興奮の持続したパターンが嫌で,持続的な苦悩の源泉であったと訴える場合のみが精神疾患に当たるものと改訂したが,これも,1987年(昭和62年)に刊行された第3版の改訂版(DSM-Ⅲ-R)においては削除され,同性愛は精神疾患とはされなくなった(甲A27の1~28の2,48,215,217)。
世界保健機関は,1992年(平成4年),同性愛を疾病分類から削除した国際疾病分類改訂第10版(ICD-10)を発表した。世界保健機関は,併せて,同性愛はいかなる意味でも治療の対象とならない旨宣明した。(甲A30の2、甲A48、180、217)
イ 我が国における同性愛に関する知見の変化
我が国においても,昭和56年頃には,同性愛は,当事者が普通に社会生活を送っている限り,精神医学的に問題にすべきものではなく,当事者が精神的苦痛を訴えるときにだけ治療の対象とすれば足りるとの知見が広まり,その後,我が国の精神医学上,精神疾患とはみなされなくなった(甲A48,216,217)。
⑺ 諸外国及び地域における同性婚等に関する状況
ア 諸外国及び地域における法制度等の状況
(ア) 1989年(平成元年),デンマークにおいて,同性婚とは異なるものの,同性の二者間の関係を公証し,又は一定の地位を付与する登録制度(導入した主体によって制度の内容は異なるが,以下,総称して「登録パートナーシップ制度」という。)が導入され,2001年(平成13年)にはドイツ及びフィンランド,2004年(平成16年)にはルクセンブルク、2009年(平成21年)にはオーストリア、2010年(平成22年)にはアイルランド、2016年(平成28年)にはイタリアにおいて登録パートナーシップ制度が導入された(甲A141)。
(イ) また、次の国・地域では、次に掲げる年に同性婚を可能とする法律が成立し、又は裁判所が同性婚の禁止を憲法違反とするなどして同性婚を認める判断が出ており、これにより、同性婚が可能となった国・地域は、下記以外にも一部の州で同性婚が可能となったメキシコを含めて34か国、世界のGDPに占める同性婚を認める国の割合は52%となった(甲A98、137、141、354、565~572)。
2000年(平成12年) オランダ
2003年(平成15年) ベルギー
2005年(平成17年) スペイン、カナダ
2006年(平成18年) 南アフリカ
2008年(平成20年) ノルウェー
2009年(平成21年) スウェーデン
2010年(平成22年) ポルトガル、アイスランド、アルゼンチン
2012年(平成24年) デンマーク
2013年(平成25年) ウルグアイ、ニュージーランド、フランス、ブラジル、英国(イングランド、ウェールズ)
2014年(平成26年) ルクセンブルク
2015年(平成27年) フィンランド、アイルランド、アメリカ
2016年(平成28年) コロンビア
2017年(平成29年) 台湾、マルタ、ドイツ、オーストリア、オーストラリア
2018年(平成30年) コスタリカ
2019年(令和元年) エクアドル、英国(北アイルランド)
2021年(令和 3年) スイス、チリ
2022年(令和 4年) スロベニア、キューバ
2023年(令和 5年) アンドラ公国
(……削る……)
(ウ) 一方、同性婚の容認以外の動きがあった国として、ロシアは,2013年(平成25年),同性愛行為は禁止しないが,同性愛を宣伝する活動を禁止するための法改正を行い,2014年(平成26年),憲法裁判所は、同性愛の宣伝行為の禁止は同国憲法に違反しない旨の判断をした。
ベトナムにおいては,2014年(平成26年),それまで禁止の対象となっていた同性との間で結婚式をすることを禁止事項から除く法改正を行ったが,同時に,婚姻は男性と女性との間のものと明記し,法律は同性婚に対する法的承認や保護を提供しないとされた。
また,韓国においては,2016年(平成28年),地方裁判所に相当する地方法院において,同性婚を認めるかは立法的判断によって解決されるべきであり,司法により解決できる問題ではないとの判断をした。同国の2013年(平成25年)の調査においては,同性婚を法的に認めるべきとする者が25%だったのに対し,認めるべきではないとする者が67%に上っていた。
(以上につき,甲A141)
イ 日本に所在する外国団体の動向
在日米国商工会議所は,平成30年9月,日本を除くG7参加国においては同性婚又は登録パートナーシップ制度が認められているにもかかわらず,日本においてはこれらが認められていないことを指摘し,外国で婚姻した同性愛者のカップルが,我が国においては配偶者ビザを得られないなど同性愛者の外国人材の活動が制約されているなどとして,婚姻の自由をLGBTカップルにも認めることを求める意見書を公表した。また,同月,在日オーストラリア・ニュージーランド商工会議所,在日英国商業会議所,在日カナダ商工会議所及び在日アイルランド商工会議所も上記意見書に対する支持を表明し,その後,在日デンマーク商工会議所も支持を表明した。
(甲A112,131,132)
この意見書への賛同は、多数の企業、法律事務所等に広がっており、賛同団体は135に及んでいる(甲A757、758)。
⑻ 我が国の状況
ア 我が国においては,平成27年10月に東京都渋谷区が,同年11月に東京都世田谷区がパートナーシップ認定制度を導入したのをはじめとして,パートナーシップ認定制度を導入する地方公共団体が増加し、令和4年10月1日時点で導入した地方公共団体数が60となり,そのような地方公共団体に居住する人口は合計で約3700万人を超えた(甲A75~91,98,119~129,164~170,271~292,311~322,325)。
また、その後もパートナーシップ認定制度を導入する地方公共団体は増え続け、令和5年1月時点で264に増え、総人ロカバー率は65.2%となった(甲A734)。また、同性婚に関する意見書を採択し、衆参議院各議長や内閣総理大臣、法務大臣等にこれを提出した地方議会も6つある(甲A332、750~754)。なお、国連自由権規約人権委員会は、市民的及び政治的権利に関する国際規約の実施状況に関する第7回日本政府報告書に対し、総括所見として、レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル及びトランスジェンダーの人々が、特に公営住宅、戸籍の性別変更、法律的な結婚へのアクセス及び矯正施設での処遇において、差別的な扱いに直面していることを示す報告に懸念を抱いているとした上、締結国が行うべきこととして、同性カップルが公営住宅へのアクセスや同性婚を含め、規約に規定されたすべての権利を締約国の領域のすべてで享受できるようにすることを指摘した(甲A574の1・2)。
イ 我が国における,権利の尊重や差別の禁止などLGBTに対する基本方針を策定している企業数の調査において,平成28年の調査結果では173社であったが,令和元年の調査結果では364社であった(甲A387,388)。
ウ 令和2年11月18日、同性婚の法制化に賛同する企業を可視化するキャンペーン「Business for Marriage Equality」が発足し、これに加わる企業・団体は、令和5年3月6日時点で362である(甲A759~762)。
エ 日本弁護士連合会や複数の弁護士連合会、複数の弁護士会(単位会)、日本組織内弁護士協会は、平成30年7月から令和5年3月にかけて、同性婚法制化に関する意見書や決議、宣言、会長声明等を発表した(甲A113、130、134、153、154、407~410、461~467、769~782)。
また、日本家族〈社会と法〉学会や日本学術会議は、同性婚規定の新設提案や民法改正の提言を発表するなどした(甲A114、425)。
オ 国会においては、次のような機会に、国会議員や参考人から、同性婚の法制化に関する発言がされ、又は国会議員からの質問主意書に対し、内閣が答弁書により回答した(甲All、12、60~62、229、261、267、432、437、439、441、442) 。
平成12年 5月25日 参議院:法務委員会
平成16年 2月19日 衆議院:憲法調査会(基本的人権の保障に関する調査小委員会)
平成17年 2月16日 参議院:少子高齢社会に関する調査会
平成19年 2月15日 参議院:厚生労働委員会
平成21年 4月 3日 衆議院:法務委員会
平成22年 5月20日 衆議院:青少年問題に関する特別委員会
平成27年 2月18日 参議院:本会議
平成27年 4月 1日 参議院:予算委員会
平成30年 5月11日 質問主意書に対する答弁書
平成30年 6月13日 衆議院:法務委員会
平成30年 6月19日 衆議院:本会議
平成30年 7月 3日 参議院:法務委員会
⑼ 婚姻・結婚に関する統計
ア 婚姻に対する意識調査の結果
(ア) 内閣府による平成17年版国民生活白書によれば,独身のときに子供ができたら結婚した方が良いかとの質問に対し,15歳~49歳のいずれの年齢層においても,そう思うとの回答がおおむね6割となり,そう思わないとの回答は1割に満たなかった。また,いずれ結婚するつもりであると回答した男女は,昭和57年から平成14年までの各年の調査を通じてそれぞれ9割を超えていた。(甲A236)
(イ) 厚生労働省が行った平成21年の調査では,「結婚は個人の自由であるから,結婚してもしなくてもどちらでもよい」という考え方に賛成又はどちらかといえば賛成する者は70%であったが,同省が平成22年に20~49歳を対象として行った調査によれば,「結婚は必ずするべきだ」又は「結婚はしたほうがよい」との意見を持つ者は合計で64.5%に上り,米国(53.4%),フランス(33.6%),スウェーデン(37.2%)を上回った(甲A238)。
(ウ) 国立社会保障・人口問題研究所が行った平成27年の調査によれば,結婚することに利点があると思う未婚の者は,男性で64.3%,女性で77.8%であり,その理由として回答が多かったもの(2つまで選択可の選択肢式による調査)は,次のとおりである(甲A345)。
「子供や家族をもてる」(男性35.8%,女性49.8%)
「精神的な安らぎの場が得られる」(男性31.1%,女性28.1%)
「親や周囲の期待に応えられる」(男性15.9%,女性21.9%)
「愛情を感じている人と暮らせる」(男性13.3%,女性14%)
「社会的信用や対等な関係が得られる」(男性12.2%,女性7%)
(エ) 国立社会保障・人口問題研究所が行った平成27年の調査によれば,未婚者に対する「生涯を独身で過ごすというのは,望ましい生き方ではない」との質問には男性の64.7%,女性の58.2%が賛成し,「男女が一緒に暮らすなら結婚すべきである」との質問には男性の74.8%,女性の70.5%が賛成と回答をした(甲A345)。
イ 婚姻に関する統計
(ア) 厚生労働省が行った平成30年の我が国の人口動態に関する調査によれば,平成28年の婚姻件数は,最も多かった昭和47年の110万組と比較すると約半分となって減少傾向ではあるものの,62万0531組であった(甲A239)。
(イ) 厚生労働省が行った平成30年の上記調査によれば,我が国の婚姻率(年間婚姻件数を総人口で除した上で1000を乗じた割合)は,昭和47年以降,増減がありつつも減少傾向にあり,平成28年には5%となったが,イタリア(3.2%),ドイツ(4.9%),フランス(3.6%),オランダ(3.8%)等のヨーロッパ諸国を上回っている。また,出生に占める嫡出でない子の出生割合は,日本は2.3%であり,米国(40.3%),フランス(59.1%),ドイツ(35%),イタリア(30%),英国(47.9%)などよりもはるかに低い割合となっている。(甲A239)
(ウ) 厚生労働省が昭和61年から平成30年までに行った調査によれば,昭和61年以降の児童のいる世帯が全世帯に占める割合は年々減少し,昭和61年には46.2%であったものが,平成30年には22.1%まで減少した(甲A240)。
⑽ 同性婚の賛否等に関する意識調査の統計
ア 河口和也広島修道大学教授を研究代表者とするグループが行った平成27年の調査によれば,男性の44.8%,女性の56.7%が同性婚に賛成又はやや賛成と回答したが,男性の50%,女性の33.8%は同性婚に反対又はやや反対と回答した。この調査においては,20~30代の72.3%,40~50代の55.1%は同性婚に賛成又はやや賛成と回答したが,60~70代の賛成又はやや賛成の回答は32.3%にとどまり,同年代の56.2%は同性婚に反対又はやや反対と回答した。(甲A104の2)
イ 毎日新聞社が平成27年に行った調査によれば,同性婚について,男性の38%,女性の50%が賛成と回答したのに対し,男性の49%,女性の30%が反対と回答した(甲A105)。
ウ 日本放送協会が平成27年に行った調査によれば,同性同士が婚姻することを認めるべきかとの質問に対し,51%がそう思うと回答し,41%がそうは思わないと回答した(甲A107)。
エ 朝日新聞社が平成27年に行った調査によれば,同性婚を法律で認めるべきかとの質問に対し,49%が認めるべきだと回答し,39%が認めるべきではないと回答した。同回答においては,18~29歳及び30代においては,認めるべきだとの回答が7割に上ったが,60代では認めるべきだ,認めるべきではないのいずれの回答も42%であり,70歳以上では,認めるべきではないとの回答が63%を占めた。(甲A109)
オ 国立社会保障・人口問題研究所が平成30年に行った全国家庭動向調査によれば,同性愛者のカップルにも何らかの法的保障が認められるべきだとの調査項目に対し,全く賛成又はどちらかといえば賛成と回答した者は75.1%であり,全く反対又はどちらかといえば反対と回答した者は25.0%であった。また,同性婚を法律で認めるべきだとの調査項目については,全く賛成又はどちらかといえば賛成と回答した者は69.5%であり,全く反対又はどちらかといえば反対と回答した者は30.5%であった。(甲A174)
カ 令和元年に、アと同様の方法で行われた全国調査の結果によれば、平成27年からの4年間の間に、全世代平均で賛成及びやや賛成との回答が51.2%から64.8%へと増加し、反対及びやや反対との回答が41.3%から20.0%へと減少しており、令和5年に入ってから行われた共同通信社及び複数の新聞社が行った世論調査においては、同性婚を認めるべきである旨の回答が最低でも54%、最高で72%であった(甲A786、789~792)。
2 本件規定が憲法13条に違反する旨の主張について(争点⑴関係)
この「2 本件規定が憲法13条に違反する旨の主張について」の項目で述べられている内容は、「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」(平成27年12月16日)の「第2 上告理由のうち本件規定が憲法13条に違反する旨をいう部分について」の項目の構成や文言をテンプレートとして用い、その内容を今回の事案に当てはめようとして改変を試みた形跡が見受けられる。
その根拠は、下記の通りである。
(論理を展開しようとする進み方の構成が似通っている。また、色を付けたところは文言が全く同じである。)
夫婦同姓制度訴訟大法廷判決
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第2 上告理由のうち本件規定が憲法13条に違反する旨をいう部分について
1 論旨は,本件規定が,憲法上の権利として保障される人格権の一内容である「氏の変更を強制されない自由」を不当に侵害し,憲法13条に違反する旨をいうものである。
2(1) 氏名は,社会的にみれば,個人を他人から識別し特定する機能を有するものであるが,同時に,その個人からみれば,人が個人として尊重される基礎であり,その個人の人格の象徴であって,人格権の一内容を構成するものというべきである(……参照)。
(2) しかし,氏は,婚姻及び家族に関する法制度の一部として法律がその具体的な内容を規律しているものであるから,氏に関する上記人格権の内容も,憲法上一義的に捉えられるべきものではなく,憲法の趣旨を踏まえつつ定められる法制度をまって初めて具体的に捉えられるものである。
したがって,具体的な法制度を離れて,氏が変更されること自体を捉えて直ちに人格権を侵害し,違憲であるか否かを論ずることは相当ではない。
(3) そこで,民法における氏に関する規定を通覧すると,……。………。
………。……合理性があるといえる。
(4) 本件で問題となっているのは,婚姻という身分関係の変動を自らの意思で選択することに伴って夫婦の一方が氏を改めるという場面であって,……。
………。
(5) 以上のような現行の法制度の下における氏の性質等に鑑みると,婚姻の際に「氏の変更を強制されない自由」が憲法上の権利として保障される人格権の一内容であるとはいえない。本件規定は,憲法13条に違反するものではない。
3 もっとも,上記のように,氏が,……,……,人が個人として尊重される基礎であり,その個人の人格を一体として示すものでもあることから,氏を改める者にとって,そのことによりいわゆるアイデンティティの喪失感を抱いたり,……,個人の信用,評価,名誉感情等にも影響が及ぶという不利益が生じたりすることがあることは否定できず,……婚姻に伴い氏を改めることにより不利益を被る者が増加してきていることは容易にうかがえるところである。
これらの婚姻前に築いた個人の信用,評価,名誉感情等を婚姻後も維持する利益等は,憲法上の権利として保障される人格権の一内容であるとまではいえないものの,後記のとおり,氏を含めた婚姻及び家族に関する法制度の在り方を検討するに当たって考慮すべき人格的利益であるとはいえるのであり,憲法24条の認める立法裁量の範囲を超えるものであるか否かの検討に当たって考慮すべき事項であると考えられる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
損害賠償請求事件 最高裁判所大法廷 平成27年12月16日 (PDF)
この札幌高裁判決
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2 本件規定が憲法13条に違反する旨の主張について(争点⑴関係)
(1) 控訴人らは、本件規定が憲法13条に違反すると主張し、憲法上の権利として保障される人格権の一内容である「同性の者との間の婚姻の自由」を不当に侵害し、又は「同性の者との間の婚姻の自由」の根拠であり、人格権の一内容でもある「性的指向」を不当に侵害する旨を主張する趣旨と解される。………。………。
(2)ア 性的指向とは、……。………。
………。………。したがって、性的指向は、重要な法的利益であるということができる。………。
……同時に、その個人からみれば、人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の象徴であって、人格権の一内容を構成し得るものというべきである。
イ しかし、このように性的指向、さらには同性間の婚姻の自由が人格権の一内容を構成し得るとしても、……、婚姻の制度は、法制度の一部として法律がその具体的な内容を規律しているものであるから、性的指向及び同性間の婚姻の自由に係る人格権の内容は、憲法上一義的に捉えられるべきものではなく、憲法の趣旨を踏まえつつ定められている法制度との関係で初めて具体的に捉えられるものであると解すべきである(夫婦同姓制度訴訟大法廷判決参照)。
したがって、具体的な法制度を離れて、同性間で婚姻することができないこと自体を捉えて直ちに人格権を侵害し、違憲であるか否かを論ずることは相当ではない。
ウ そこで、異性婚を定め、同性婚を許していない本件規定について検討すると、……。……異性間の婚姻については、違憲の問題は生じない。
ところが、本件で問題となっているのは、……婚姻という身分関係の変動における社会的な制度を享受させるべきかどうかということであって、……。そうすると、……、このような観点からすると、憲法13条が人格権として性的指向及び同性間の婚姻の自由を保障しているものということは直ちにできず、本件規定が憲法13条に違反すると認めることはできない。
(3) もっとも、……。性的指向は、……、人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の一要素でもあることから、社会の制度上取扱いに不利益があれば、そのことによりいわゆるアイデンティティの喪失感を抱き、人としての存在を否定されたとの思いに至ってしまうことは容易に理解できることである。
………。
したがって、性的指向及び同性間の婚姻の自由は、憲法上の権利として保障される人格権の一内容を構成し得る重要な法的利益として、後記のとおり、本件規定が同性婚を許していないことが憲法24条の定める立法裁量の範囲を超えるものであるか否かの検討に当たって考慮すべき事項であると考えられる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
論理を展開しようとする構成や文言がこれだけ似通っていることから、この札幌高裁判決は「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」の内容をテンプレートとして利用しようとするものといえる。(テンプレート論法)
しかし、法律論は、論理的な整合性を積み重ねることによって結論を正当化することが可能となるのであり、何らかの訴訟の判決で示された構成や文言をテンプレートとして用いたとしても、その内容が他の事案と対応するものであるかどうかは別の問題である。
そのため、たとえ何らかの訴訟の判決の内容をテンプレートとして用いようとしても、今回問われている事柄と内容が対応していない場合には、法的に意味の通ったものとして成り立つことはない。
そして、「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」とこの札幌高裁判決とでは、下記の点で取り上げている事柄が異なっている。
◇ 「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」で取り上げている「氏」は、婚姻制度の一部として定められており、具体的な制度の存在を前提とするものである。
それに対して、この札幌高裁判決で取り上げている「性的指向」と称するものは、個人の内心における心理的・精神的なものであり、具体的な制度の存在を前提とするものではない。
当然、これは法制度の要件として定められているものではない。
また、婚姻制度は「性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いをする制度ではないし、「性愛」に基づいて制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもない。
そのことから、婚姻制度を「性的指向」と結び付くものとして考える前提そのものも誤っている。
そのことから、この札幌高裁判決で取り上げている事柄について、「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」の構成や論旨を用いることができるとする前提にない。
そのため、「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」で示された内容が意味の通ったものであるとしても、それとは事案が異なるこの札幌高裁判決を論じる際にそれを用いたとしても、同じように意味が通るものとして文章を構成することができるということにはならず、その論旨も正当化することができるものとはならない。
よって、この札幌高裁判決がこのように「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」をテンプレートとして用いて論じようとしていることは、論じ方として誤っている。
(1) 控訴人らは、本件規定が憲法13条に違反すると主張し、憲法上の権利として保障される人格権の一内容である「同性の者との間の婚姻の自由」を不当に侵害し、又は「同性の者との間の婚姻の自由」の根拠であり、人格権の一内容でもある「性的指向」を不当に侵害する旨を主張する趣旨と解される。この点、控訴人らは、本件規定が憲法13条及び憲法24条に違反すると主張するところ、性的指向にかかる差別の禁止と人権の保障を主張しており、同性の者との婚姻の自由はその一場面であると考えられることから、まずは憲法13条違反の主張について検討し、憲法24条違反の主張については後述する。なお、控訴人らの主張は、憲法違反をいう前提として、本件規定について、異性間の婚姻を定めているが、同性間の婚姻は許していないとの解釈を前提として、このような定めが憲法の各条項に違反するとの趣旨と解され、以下このような理解のもとに判断する。
【筆者】
この段落は控訴人らの主張をまとめたものなので、解説はしない。
(2)ア 性的指向とは、人が情緒的、感情的、性的な意味で、人に対して魅力を感じることであり、このような恋愛、性愛の対象が異性に対して向くことが異性愛、同性に向くことが同性愛である。性的指向が決定される原因、又は同性愛となる原因は解明されておらず、遣伝的要因、生育環境等複数の要因が組み合わさって作用している可能性が指摘されているが、精神医学に関わる大部分の専門家団体は、ほとんどの人の場合、性的指向は、人生の初期か出生前に決定され、選択するものではないとしており、心理学の主たる見解も、性的指向は意思で選ぶものでも、意思により変えられるものでもないとしている。性的指向が障害や疾患の一つであるという考えは受け入れられなくなった(認定事実(1)ア)。
【筆者】
━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━
この段落の文面は、非常に読み取りづらいものとなっている。
その原因は下記の通りである。
この段落全体の内容について、文を区切って整理し、構造上の問題を明らかにする。
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
① 性的指向とは、人が情緒的、感情的、性的な意味で、人に対して魅力を感じることであり、
② このような恋愛、性愛の対象が異性に対して向くことが異性愛、同性に向くことが同性愛である。
③ 性的指向が決定される原因、又は同性愛となる原因は解明されておらず、遣伝的要因、生育環境等複数の要因が組み合わさって作用している可能性が指摘されているが、
④ 精神医学に関わる大部分の専門家団体は、ほとんどの人の場合、性的指向は、人生の初期か出生前に決定され、選択するものではないとしており、
⑤ 心理学の主たる見解も、性的指向は意思で選ぶものでも、意思により変えられるものでもないとしている。
⑥ 性的指向が障害や疾患の一つであるという考えは受け入れられなくなった(…)。
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
この段落の文面が読み取りづらい理由として、下記を挙げることができる。
◇ ①の「性的指向」についての定義が誤っていること
①では「性的指向とは、」と文が始まることから、その後に続く部分では、「性的指向」について説明しているはずである。
しかし、その後に続く文は、「人が情緒的、感情的、性的な意味で、人に対して魅力を感じること」である。
これは、一般的にはおおよそのところ「恋愛」や「性愛」などと表現されることのある人の内心における思想、信条、信仰、感情の一側面を示すものであり、「性的指向」について説明するものではない。
「性的指向」と称しているものは、人が「性愛」を有するとされる場合にそれがどのような対象に向かうかについて用いられている言葉であり、単に「人が情緒的、感情的、性的な意味で、人に対して魅力を感じること」をいうものとは異なるものである。
よって、「性的指向」について「人が情緒的、感情的、性的な意味で、人に対して魅力を感じること」と説明していることは誤りである。
この点、福岡地裁判決で述べられている説明の方が正確性が高いといえる。
同性婚訴訟 福岡地裁判決 (同性婚訴訟 福岡地裁判決の分析)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 性的指向
性的指向とは、人の恋愛・性愛がどういう対象に向かうのかを示す概念をいい、恋愛・性愛の対象が異性に向かう異性愛、同性に向かう同性愛、男女両方に向かう両性愛を指す(以下、性的指向が異性愛である者を「異性愛者」、性的指向が同性愛である者を「同性愛者」という。)。……(略)……
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「結婚の自由をすべての人に」訴訟事件 福岡地方裁判所 令和5年6月8日 (PDF)
ただ、これらは人の内心における精神的なものであることから、「内心の自由」として捉えられるものであり、法律論としてこのような内心における思想、信条、信仰、感情の一側面を取り上げて論じることができるというものではないし、それをその他の思想、信条、信仰、感情との間で区別して扱うことができるというものでもない。
◇ ②の「このような」が指し示す対象が誤った定義の説明を前提としていること
②の「このような」の部分であるが、これは「性的指向」を説明する文の中で、「人が情緒的、感情的、性的な意味で、人に対して魅力を感じること」と説明されているものを拾い上げ、「このような恋愛、性愛」と説明するものである。
しかし、そもそも「性的指向」を説明しているはずの文の中から、「恋愛、性愛」を示す文を拾い上げて説明を続けようとしている点で、この文の中で前提となっている「性的指向」の話とは関係のない話を続けるものとなっており、文脈として不自然である。
また、結局はその後「恋愛、性愛の対象が異性に対して向くことが異性愛、同性に向くことが同性愛」のように、本来の「性的指向」の意味に対応する説明をしようとしており、その直前の文はやはり「恋愛、性愛」を説明するものであり、「性的指向」の説明ではないことが明らかとなっている。
これにより、「このような」の文が指すものは、「恋愛、性愛」を説明するものであり、「性的指向」の説明をしているという前提が自ら覆されている点で、混乱するものとなっている。
・ 「性的指向とは、」 → 「人が情緒的、感情的、性的な意味で、人に対して魅力を感じることであり、」
・ 「人が情緒的、感情的、性的な意味で、人に対して魅力を感じること」 → 「このような恋愛、性愛」
この構造から見ると、この文では「性的指向」と「恋愛、性愛」が同じ意味ということになるのである。
・ 「性的指向」⇒「人が情緒的、感情的、性的な意味で、人に対して魅力を感じること」
・ 「恋愛、性愛」⇒「人が情緒的、感情的、性的な意味で、人に対して魅力を感じること」
しかし、「性的指向」と「恋愛、性愛」は異なる意味で用いられる概念であることから、これらを同じ意味で扱っている点で誤りである。
◇ ③の「又は」の文言が前後の二者のうち一つを選ぶという意味で使われているというより、実質的には同様の事柄をどのような言葉で表現するかについての言葉の言い換えを示すものとなっていること。
③の「性的指向が決定される原因、又は同性愛となる原因は解明されておらず、」の部分では、「又は」の文言で、「性的指向が決定される原因」と「同性愛となる原因」が繋げられている。
しかし、これは、その後に続く「解明されておらず、」との部分との文脈との関係性を検討すると、「A又はB」のようにAとBという選択肢の中から二者択一で検討する事案として示されているものではなく、単に同様の事柄についてどのような言葉で表現するかについて「性的指向が決定される原因」や「同性愛となる原因」のように言葉の言い換えの事例を示をしているだけである。
文章を作成する際に、言葉の置き換えの事例を示すことそのものはあり得るとしても、ここでは前後の文脈やこの文の中では「解明されて」いるか否かが中心的な話題となっているのであり、その中で唐突に「又は」の文言を用いながら言葉の言い換えの例示を行うことは、不自然な展開であり、読者を混乱させるものとなっている。
◇ この段落の第二文(③④⑤)は文を区切るべきところを区切っておらず、意味の関係性を読み取りづらいこと。
この段落の第二文(③④⑤)は、下記である。
「性的指向が決定される原因、又は同性愛となる原因は解明されておらず、遣伝的要因、生育環境等複数の要因が組み合わさって作用している可能性が指摘されているが、精神医学に関わる大部分の専門家団体は、ほとんどの人の場合、性的指向は、人生の初期か出生前に決定され、選択するものではないとしており、心理学の主たる見解も、性的指向は意思で選ぶものでも、意思により変えられるものでもないとしている。」
この文を上記のように③④➄の部分に区切ると分かりやすくなる。
③ 性的指向が決定される原因、又は同性愛となる原因は解明されておらず、遣伝的要因、生育環境等複数の要因が組み合わさって作用している可能性が指摘されているが、
④ 精神医学に関わる大部分の専門家団体は、ほとんどの人の場合、性的指向は、人生の初期か出生前に決定され、選択するものではないとしており、
⑤ 心理学の主たる見解も、性的指向は意思で選ぶものでも、意思により変えられるものでもないとしている。
そして、③の最後の部分の「が、」の文言は、逆説の意味や後に示す事柄を強調する意味で用いられているようである。
しかし、この「が、」によって繋ぐことのできる意味の転換の対応関係が、非常に分かりづらい。
まず、「が、」の直前を見て「指摘されているが、」を拾い、これに逆接するものとして後の「選択するものではない」と「変えられるものでもない」に繋がると考えようとする場合を検討する。
しかし、「指摘されている」ものとは、「遣伝的要因、生育環境等複数の要因が組み合わさって作用している可能性」であり、これは「選択するものではない」と「変えられるものでもない」という結論と意味が直接的に対応していない。
よって、「指摘されている」の部分に対して逆接を繋ぎ、「選択するものではない」と「変えられるものでもない」と結論付ける方法で読み解くことは不自然である。
次に、「が、」の直前ではなく、それよりさらに前の「原因は解明されておらず、」の部分を拾い、これに逆接するものとして後の「選択するものではない」と「変えられるものでもない」に繋がると考えようとする場合を検討する。
この場合、「原因は解明されて」いない「が、」、「選択するものではない」and「変えられるものでもない」と結論を述べようとするものであるから、意味を自然に読み解くことができる。
ただ、そのように意味を繋ぐのであれば、③の部分の語順を並べ替えた上で、その③の部分を文を区切って完結させ、元の文で③④⑤の文全体の中で逆接で繋ぐ役割を持っている「が、」の言葉の役割を次の文となる④⑤の部分の前に「しかし、」を加えるなどして表現した方が読み取りやすいものとなっていたはずである。
③ 「性的指向が決定される原因、又は同性愛となる原因は」、「遣伝的要因、生育環境等複数の要因が組み合わさって作用している可能性が指摘されているが、」「解明されて(おらず、)」いない。
しかし、
④ 精神医学に関わる大部分の専門家団体は、ほとんどの人の場合、性的指向は、人生の初期か出生前に決定され、選択するものではないとしており、
⑤ 心理学の主たる見解も、性的指向は意思で選ぶものでも、意思により変えられるものでもないとしている。
この判決の文面は、文面に詰め込みたい情報と、その文をどのように接続して表現するかという点について、熟考された形跡を見て取ることができず、意味が不明瞭となっている。
このような悪文をそのままにして論じることは、解釈の過程において明確な理解を得ることを困難とし、誤った結論を導き出す原因となる。
また、読み手との間でも一文一文についての明確な理解を共有することを不能とし、解釈の過程について読み手との間で合意を形成することができなくなるし、後にその論理展開を検証することも困難となることから、適切ではない。
◇ この段落の第一文(①②)と第二文(③④⑤)の流れからして、第三文(⑥)の内容が唐突であること。
⑥の内容は「性的指向が障害や疾患の一つであるという考えは受け入れられなくなった(…)。」である。
この文は、これより前に示された第一文(①②)と第二文(③④⑤)との間で脈絡がなく、突然挿入されたような印象を受けるものとなっている。
「その他、」や「また、」などの接続の言葉もないことから、通常読み手は前の文との間で連続性のある内容として読み取ろうとするが、一文前の結論である「選択するものではない」と「変えられるものでもない」という趣旨から導かれる内容であるとはいえず、直接の繋がりを見出すことができない。
第二文の③の部分について、先ほど筆者が語順を並べ替えた上で、その③の部分を文を区切って完結させている部分に逆接を加えた形で繋げようとしているのかもしれない。
③ 「性的指向が決定される原因、又は同性愛となる原因は」、「遣伝的要因、生育環境等複数の要因が組み合わさって作用している可能性が指摘されているが、」「解明されて(おらず、)」いない。
しかし、
⑥ 「性的指向が障害や疾患の一つであるという考えは受け入れられなくなった(…)。」
ただ、この第二文の③の部分を前提として、それを逆接で繋ぐという方法は、第二文の③の部分を第二文の④➄の部分とは切り離して文を区切ったからこそ、その後の文として繋ぐことができるものであり、そもそも第二文の③の部分が④➄の部分と繋がったまま一つの文として構成されている以上は、その第二文の③の部分だけを拾い上げて第三文(⑥)にも同様に繋ぐように読み取るというのは困難である。
そのため、このような読み手を混乱させる文章は悪文であるということができる。
◇ この段落の第三文(⑥)には「受け入れられなくなった」とあるが、主語がなく、誰に「受け入れられなくなった」の分からないこと。
第三文(⑥)には「受け入れられなくなった」とあるが、誰に「受け入れられなくなった」のか、その主語となるものが書かれていない。
たとえ、何者かに「受け入れられなくなった」としても、それがどのような範囲で、どのような意味として「受け入れられなくなった」のか説明するものではないことから、それが精神科医の下に通う患者にとってなのか、民間の企業にとってなのか、宗教団体にとってなのか、政府なのか、この判決を書いた裁判官にとってなのかも分からないものとなっている。
一文前の第二文を見て、その中の④の部分の「精神医学に関わる大部分の専門家団体」や⑤の部分の「心理学の主たる見解」として「受け入れられなくなった」と説明しようとしている可能性は考えられる。
しかし、先ほども述べたように、この第三文(⑥)は唐突に持ち出されており、前の文との間で文の接続の関係が明瞭ではない。
また、第二文の③の部分を前提に、それを逆接で繋ぐ形ならば意味が通じるものとして把握することは可能となるが、第二文そのものは③の部分で文を区切っているわけでもないため、そのような前提で読み取ることは困難である。
そして、たとえ第二文を③の部分で区切って、それを逆接で繋ぐ形で理解しようとしても、そこに④の文で示された「精神医学に関わる大部分の専門家団体」や⑤の文で示された「心理学の主たる見解」は登場しない。
よって、このような形で試行錯誤して読み取ろうとしたとしても、そこに「精神医学に関わる大部分の専門家団体」と「心理学の主たる見解」は登場しないのであり、それが主語であることを読者に自然に読み取らせることは困難である。
そのため、このような形で説明していることは、悪文であるということができる。
━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━
「性的指向とは、人が情緒的、感情的、性的な意味で、人に対して魅力を感じることであり、このような恋愛、性愛の対象が異性に対して向くことが異性愛、同性に向くことが同性愛である。」との記載がある。
婚姻制度は「性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いを行うものではないし、「性愛」に基づいて制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもない。
そのため、この訴訟の中で、「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかについての「性的指向」と称するものについて論じる必要そのものがないものである。
よって、ここで「性的指向」と称するものを取り上げて、それを前提として法制度の内容について論じようとする試みそのものが誤っている。
「性的指向とは、人が情緒的、感情的、性的な意味で、人に対して魅力を感じることであり、」との部分について検討する。
「性的指向」とは、ここで「人が情緒的、感情的、性的な意味で、人に対して魅力を感じること」と示しているように、人の内心における精神的なものである。
そのため、これは「内心の自由」として捉えられるものであり、憲法上の具体的な条文としては、19条の「思想良心の自由」や20条1項前段の「信教の自由」として保障されるものである。
また、この「性的指向」と称するものは、精神的なものであるから、その性質上、もともと明確に割り切ることができるというものではない。
そのため、持続的で明確な確信を有している者から、曖昧な認識の者、その認識がそもそも存在しない者まで様々である。
他にも、ここでは「性的指向」を取り上げているが、これを「恋愛的指向」と区別するべきという考え方も存在する。
恋愛的指向 Wikipedia
しかし、法律論としては、このような人の内心における思想、信条、信仰、感情の一部分を取り出して自然人を分類することはできない。
また、もし法制度がこのような人の内心を審査して、その審査の結果に応じて人を分類し、その分類に応じて区別取扱いをするようなことがあれば、憲法14条の「平等原則」に違反するし、国家による内心に対する不当な干渉として憲法19条の「思想良心の自由」にも違反する。
よって、法律論としては、このように人の内心を取り上げて何かを論じることができるかのような前提で論じていることそのものが誤っている。
「このような恋愛、性愛の対象が異性に対して向くことが異性愛、同性に向くことが同性愛である。」との部分について検討する。
ここでは、「異性愛」と「同性愛」を取り上げるのみであるが、このような人の内心における心理状態についての分類は、他にも様々な分類が議論されていることを忘れてはならない。
・ 恋愛、性愛の対象が両性に対して向くことが「両性愛」
・ 恋愛、性愛の対象が全てに対して向くことが「全性愛」
・ 恋愛、性愛の対象が近親者に対して向くことが「近親性愛」
・ 恋愛、性愛の対象が多方に対して向くことが「多性愛」
・ 恋愛、性愛の対象が子供に対して向くことが「小児性愛」
・ 恋愛、性愛の対象が老人に対して向くことが「老人性愛」
・ 恋愛、性愛の対象が死体に対して向くことが「死体性愛」
・ 恋愛、性愛の対象が動物に対して向くことが「動物性愛」
・ 恋愛、性愛の対象が物に対して向くことが「対物性愛」
・ 恋愛、性愛の対象が二次元に対して向くことが「対二次元性愛」
・ 恋愛、性愛の対象が無い者を「無性愛」
・ 愛の対象が「国家」に対して向くことが「愛国」
・ 信仰の対象がキリスト教に対して向くことが「キリスト教信仰」
・ 信仰の対象がイスラム教に対して向くことが「イスラム教信仰」
・ 信仰の対象がユダヤ教に対して向くことが「ユダヤ教信仰」
・ 信仰の対象がゾロアスター教に対して向くことが「ゾロアスター教信仰」
・ 信仰の対象が仏教に対して向くことが「仏教信仰」
・ 信仰の対象が神道に対して向くことが「神道信仰」
・ 信仰の対象が武士道に対して向くことが「武士道信仰」
・ 脳の機能が一定の状態にある場合を「ADHD」
・ 脳の機能が一定の状態にある場合を「アスペルガー」
・ 脳の機能が一定の状態にある場合を「自閉症」
・ 脳の機能が一定の状態にある場合を「強迫神経症」
・ 脳の機能が一定の状態にある場合を「妄想症」
・ 脳の機能が一定の状態にある場合を「境界性パーソナリティー障害」
・ 脳の機能が一定の状態にある場合を「解離性同一性障害」
・ 脳の機能が一定の状態にある場合を「統合失調症」
・ 脳の機能が一定の状態にある場合を「サイコパス」
・ 迷える心を「煩悩」
・ 迷いのない心を「解脱」
・ 解脱した心を「悟り」
他にも、下記を挙げることができる。
性的同一性と性自認の一覧 Wikipedia
【セクシュアリティ辞典】性の多様性をまとめてみた 2020-05-20
ただ、これらは人の心理状態について、特定の視点から分類したものに過ぎない。
法律論として、このような思想の分類の中から一部分を取り出して何かを論じることができるわけではない。
世の中には法律論として扱うことのできない様々な思想がある。
気 Wikipedia
オーラ Wikipedia
四柱推命 Wikipedia
五行思想 Wikipedia
国や地方自治体が、このような思想の分類に関わるべきではないことと同様に、「性的指向」と称する特定の思想における内心の分類にも関わるべきではない。
そのため、法律論として「異性愛」や「同性愛」などと特定の思想の分類を扱うことができるかのような前提で取り上げていること自体が妥当でない。
「性的指向が決定される原因、又は同性愛となる原因は解明されておらず、遣伝的要因、生育環境等複数の要因が組み合わさって作用している可能性が指摘されているが、精神医学に関わる大部分の専門家団体は、ほとんどの人の場合、性的指向は、人生の初期か出生前に決定され、選択するものではないとしており、心理学の主たる見解も、性的指向は意思で選ぶものでも、意思により変えられるものでもないとしている。」との記載がある。
まず、婚姻制度は「性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いをするものではないし、「性愛」に基づいて婚姻制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもない。
よって、「性愛」を有する場合に、それがどのような対象に向かうかに関する「性的指向」と称するものを論じる必要そのものがないのであり、これを論じた上で判断しようとする前提そのものに誤りがある。
また、法制度を立法する場合には、個々人の内心に対して中立的な内容でなければならないのであり、特定の「性愛」の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的として制度を立法した場合には、そのこと自体が違憲となる。
よって、「性的指向」と称するものを論じた上で、法制度を検討しようとしていること自体が妥当でない。
「精神医学に関わる大部分の専門家団体は、ほとんどの人の場合、性的指向は、人生の初期か出生前に決定され、選択するものではないとしており、心理学の主たる見解も、性的指向は意思で選ぶものでも、意思により変えられるものでもないとしている。」との部分について検討する。
まず、「性的指向」を「意思により」変えたいと望む者もいるにもかかわらず、それを「意思により変えられるものでもない」と示すことは控えるべきものである。
たとえば、「異性愛から同性愛へ」「同性愛から異性愛へ」「小児性愛から成人性愛へ」「両性愛から多性愛へ」「全性愛から無性愛へ」など、様々な方面に「意思により」で変えたいと望む者が存在する。
それに対して、「意思により変えられるものでもない」と断じることは、その者の意思を否定することになるため、決して望ましいものではない。
もちろん、他者が本人の意思に反して無理に変えさせようと強制することは憲法19条の「思想良心の自由」の精神に反して許されないことは言うまでもない。
しかし、この判決が国家権力の行使として人の内心そのものを「意思により変えられるものでもない」と断じることそのものも、憲法19条の「思想良心の自由」を侵す判断に他ならないことを理解する必要がある。
次に、「精神医学」や「心理学」の見解とあるが、学問の領域のことは学問の領域に任せるべきものであり、裁判所が特定の学説を肯定したり否定したりするような形で取り上げるべきではない。
【動画】第19回〜「思想・良心の自由」 2022/01/24
【動画】憲法 人権(学問の自由)ミニ講義【森Tの行政書士合格塾】 2022/04/30
国家が特定の学説を肯定したり否定したりすると、下記のように、特定の学問分野についての意見が裁判所の権威を用いる形で肯定されたり否定されたりするような論争を招くこととなる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
同委員会は松村氏が副委員長を務めており、委員会では20日の発言への批判が上がった。「台東にじいろの会(立憲・れいわ)」の風沢純子区議は「同性婚訴訟を通じて(性的指向は)意思によって変えられないとの判決が札幌地裁で出ている。一般質問を通じて誤解を広めた責任は極めて重い」と指摘。同会派は、発言の撤回と謝罪を求める申し入れ書を松村氏と自民会派の石塚猛幹事長宛てに提出し、委員会の場で発言を求めたが、松村氏は応じなかった。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
台東区教委、性的指向の誘導を否定 「偏った教材で同性愛」発言巡り 2023/10/2 (下線は筆者)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
同委員会は松村氏が副委員長を務めており、委員会では20日の発言への批判が上がった。「台東にじいろの会(立憲・れいわ)」の風沢純子区議は「同性婚訴訟を通じて(性的指向は)意思によって変えられないとの判決が札幌地裁で出ている。一般質問を通じて誤解を広めた責任は極めて重い」と指摘。……(略)……
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「教育で誘導」否定 自民区議の同性愛発言に 台東区教委 /東京 2023/10/3 (下線は筆者)
このように、特定の学説や見解が学問上でどのように位置づけられているかを問うものではなく、その特定の学説や見解が裁判所からお墨付きを得ているか否かという形で用いられ、学問の内容が国家権力によって歪められることも引き起こされる。
そのため、裁判所は特定の学問分野の意見について肯定したり否定したりするような形で拾い上げて論じるようなことはするべきではない。
憲法
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第23条 学問の自由は、これを保障する。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「遣伝的要因、生育環境等複数の要因が組み合わさって作用している可能性が指摘されているが、」との部分について検討する。
ここで述べられているように、「性的指向」は「遣伝的要因、生育環境等複数の要因が組み合わさって作用している可能性が指摘されている」ことから、研究の中には「性的指向」は変動するものであり、「選択する」ことも可能であり、「意思で選ぶ」ことや「意思により変えられる」と考える立場も存在する。
そのため、そのような別の研究の立場を一方的に排してここで述べるような「性的指向は、人生の初期か出生前に決定され、選択するものではない」や「性的指向は意思で選ぶものでも、意思により変えられるものでもない」という特定の立場を支持することを前提として、それに基づいて法規範の意味を論じようとすることは妥当でない。
もちろん、他者が本人の意思に反して無理やり変えさせようと強制することは、「思想良心の自由」の精神に反して許されないことは言うまでもない。
そのような本人の意思に反して他者が無理やり変えさせようと強制するような事案があった場合には、そのような行動をとることが適切ではないことを説明するために、「性的指向は、人生の初期か出生前に決定され、選択するものではない」や「性的指向は意思で選ぶものでも、意思により変えられるものでもない」という見解が必要とされ、そのことを裏付ける研究の結果が強調されることがある。
しかし同時に、本人が自らの意思で変えたいと望んだ場合には、「性的指向は、人生の初期か出生前に決定され」るとは限らず、「選択する」こともや「意思で選ぶ」ことも可能であり、「意思により変えられる」とする見解が必要とされ、そのことを裏付ける研究の結果が強調されることもあり得るものである。
もし本人が自らの「意思」で変えたいと望むのであれば、その可能性もまた開かれるということである。
そのような中、特定のグループや個人は、自己の置かれている事情の中で生じている課題を解決するために、それらの様々な見解の中から特定の見解を引き出して論じるなどしているに過ぎないのである。
そのため、これら人の内心にのみ存在する心理的・精神的な研究については、本来的に物理的な現象を外部から観測することによって誰もが共通した認識を持つことができるという意味での客観性を保つことができるものではないのであり、もともと様々な見解が存在しており、それを一つの見解に絞ることができるというものではないし、一つの見解に絞ることが適切であるともいえないものである。
そのことから、このような学術的な知見の当否の問題については、裁判所において審判することのできる範囲を超えるものである。
よって、このような事柄に対して裁判所が特定の見解だけを拾い上げて支持・不支持を表明するようなこととなっていることは適切ではない。
また、「性的指向」と称しているものの性質についての見解の当否を前提としなければ法的な判断を行うことができないような場合(『性的指向』と称しているものの性質について特定の立場に基づかなければこの判決を構成する論旨を正当化することができない場合)については、そもそも法令を適用することによって終局的に解決することができる問題とはいえない。
そのため、このような特定の見解を採用すること基づく形で判断を試みていることは、裁判所法3条の「法律上の争訟」の範囲を超えるものであり、裁判所で審査することのできる範囲を逸脱するものである。
よって、この判決が「性的指向」について、「性的指向は、人生の初期か出生前に決定され、選択するものではない」や「性的指向は意思で選ぶものでも、意思により変えられるものでもない」という特定の見解を採用した上で、その見解に基づく形で判断を行っていることは、裁判所法3条の「法律上の争訟」の解釈を誤ったものであり、「司法権の範囲」を超えた違法なものというべきである。
【参考】事実の存否、個人の主観的意見の当否、学術・技術上の争い 2006年04月14日
下記で、「司法権の範囲」、「法律上の争訟」の意味を確認する。
■ 司法権の範囲
「司法権の範囲」の論点を検討する。
司法(司法権の範囲) Wikipedia
「司法権の範囲」は、裁判所法3条の「法律上の争訟」に当たるか否かが問題となる。
裁判所法
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第三条(裁判所の権限) 裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。
② ……(略)……
③ ……(略)……
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「法律上の争訟」の意味は、判例で明らかとなっている。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
裁判所法三条によれば「裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する」ものであり、ここに「法律上の争訟」とは法令を適用することによつて解決し得べき権利義務に関する当事者間の紛争をいうのである。……
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「法律上の争訟」に関する判例を確認する。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
……(略)……第一に、法を適用することによっては解決しえない紛争は、法律上の争訟とは言えず、裁判所の審査権は及ばない。宗教上の教義に関する争い(最判昭和56・4・7民集35巻3号443頁〈板まんだら事件〉)、学問の真理性に関する争い(東京地判平成4・12・16判時1472号130頁)などが、このような事項の例として挙げられる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
司法権をめぐる論点 長谷部恭男 2004年9月 PDF (太字・下線は筆者)
憲法訴訟に関連する用語等の解説 衆議院憲法調査会事務局 平成12年5月 PDF
◇ 学問の真理性に関する争い
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
しかし、司法権の固有の内容として裁判所が審判しうる対象は、裁判所法三条にいう「法律上の争訟」に限られ、いわゆる法律上の争訟とは、「法令を適用することによつて解決し得べき権利義務に関する当事者間の紛争をいう」ものと解される(昭和二九年二月一一日第一小法廷判決、民集八巻二号四一九頁参照)。従つて、法令の適用によつて解決するに適さない単なる政治的または経済的問題や技術上または学術上に関する争は、裁判所の裁判を受けうべき事柄ではないのである。国家試験における合格、不合格の判定も学問または技術上の知識、能力、意見等の優劣、当否の判断を内容とする行為であるから、その試験実施機関の最終判断に委せられるべきものであつて、その判断の当否を審査し具体的に法令を適用して、その争を解決調整できるものとはいえない。この点についての原判決の判断は正当であつて、上告人は裁判所の審査できない事項について救済を求めるものにほかならない。……
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
国家試験合格変更又は損害賠償請求事件 昭和41年2月8日 (PDF)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
そこで検討するに、原告の主張する右先行権の意味は必ずしも明らかではないが、ある研究に関し、他者に先んじて当該研究を手掛けた研究者が、他者に対し先駆者としての地位を主張しうるとともに、学会等においても、当該研究の先駆者としての評価を受け、尊重されることをも意味するもののようである。そうすると、原告の主張するこのような先行権の存在を認めるには、まず比較されるべき二つ以上の研究の先後を評価ないし判定しなければならないことになるが、二つ以上の研究の先後の評価ないし判定は、当該対比されるべき研究における時間的な先後の一事のみならず、当該各研究の内容、程度、方法、結果の発表態様、学説若しくは見解の当否若しくは優劣等種々の要素を総合しなければ容易になしえないものであって、このような学問上の評価ないし判定は、その研究の属する分野の学者・研究者等に委ねられるべきものであり、裁判所において審査し、法令を適用して解決することのできる法律上の争訟ではないといわなければならない。したがって、本件において、原告の前記講演が被告佐伯論文よりなされたとして、先行権を有することを前提とする原告の主張は、既にこの点において理由がないというべきである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
この札幌高裁判決は「性的指向は、人生の初期か出生前に決定され、選択するものではない」や「性的指向は意思で選ぶものでも、意思により変えられるものでもない」などと述べている。
しかし、これは「技術上または学術上に関する争」のあるものについて、その当否の問題に踏み込んだ上で判断を試みようとしているものということができる。
上記の判例を参考にすれば、「学問または技術上の知識、能力、意見等の優劣、当否の判断を内容とする行為」については、「その判断の当否を審査し具体的に法令を適用して、その争を解決調整できるものとはいえない」ため、裁判所の審判できる「法律上の争訟」の範囲を超えるものである。
そのため、この札幌高裁判決がこの点について特定の立場についての見解を正しいものであると認定した上で判断を試みていることは、「司法権の範囲」を超えた違法なものということになる。
◇ 宗教上の教義に関する争い
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
裁判所がその固有の権限に基づいて審判することのできる対象は、裁判所法三条にいう「法律上の争訟」、すなわち当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であつて、かつ、それが法令の適用により終局的に解決することができるものに限られる(最高裁昭和三九年(行ツ)第六一号同四一年二月八日第三小法廷判決・民集二〇巻二号一九六頁参照)。したがつて、具体的な権利義務ないし法律関係に関する紛争であつても、法令の適用により解決するのに適しないものは裁判所の審判の対象となりえない、というべきである。
……(略)……本件訴訟は、具体的な権利義務ないし法律関係に関する紛争の形式をとつており、その結果信仰の対象の価値又は宗教上の教義に関する判断は請求の当否を決するについての前提問題であるにとどまるものとされてはいるが、本件訴訟の帰すうを左右する必要不可欠のものと認められ、また、記録にあらわれた本件訴訟の経過に徴すると、本件訴訟の争点及び当事者の主張立証も右の判断に関するものがその核心となつていると認められることからすれば、結局本件訴訟は、その実質において法令の適用による終局的な解決の不可能なものであつて、裁判所法三条にいう法律上の争訟にあたらないものといわなければならない。�
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【動画】【憲法_重要判例】(司法権)【板まんだら事件】 2020/11/29
【動画】【行政書士 #3】憲法の統治で一番苦手?裁判所を簡単に攻略!判例の勉強方法もわかりやすく解説(講義 ゆーき大学) 2021/03/12
【動画】行政書士試験対策公開講座 憲法36「裁判所」 2016/03/15
【動画】2023年度前期・九大法学部「憲法1(統治機構論・後半)」第5回〜裁判所② 2023/07/01
【動画】2023年度前期・九大法学部「憲法1(統治機構論・後半)」第7回〜裁判所④ 2023/07/13 ①
【動画】2023年度前期・九大法学部「憲法1(統治機構論・後半)」第7回〜裁判所④ 2023/07/13 ②
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
そして、宗教団体における宗教上の教義、信仰に関する事項については、憲法上国の干渉からの自由が保障されているのであるから、これらの事項については、裁判所は、その自由に介入すべきではなく、一切の審判権を有しないとともに、これらの事項にかかわる紛議については厳に中立を保つべきであることは、憲法二〇条のほか、宗教法人法一条二項、八五条の規定の趣旨に鑑み明らかなところである(最高裁昭和五二年(オ)第一七七号同五五年四月一〇日第一小法廷判決・裁判集民事一二九号四三九頁、前記昭和五六年四月七日第三小法廷判決参照)。かかる見地からすると、特定人についての宗教法人の代表役員等の地位の存否を審理判断する前提として、その者の宗教団体上の地位の存否を審理判断しなければならない場合において、その地位の選任、剥奪に関する手続上の準則で宗教上の教義、信仰に関する事項に何らかかわりを有しないものに従ってその選任、剥奪がなされたかどうかのみを審理判断すれば足りるときには、裁判所は右の地位の存否の審理判断をすることができるが、右の手続上の準則に従って選任、剥奪がなされたかどうかにとどまらず、宗教上の教義、信仰に関する事項をも審理判断しなければならないときには、裁判所は、かかる事項について一切の審判権を有しない以上、右の地位の存否の審理判断をすることができないものといわなければならない(前記昭和五五年四月一〇日第一小法廷判決参照)。したがってまた、当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係に関する訴訟であっても、宗教団体内部においてされた懲戒処分の効力が請求の当否を決する前提問題となっており、その効力の有無が当事者間の紛争の本質的争点をなすとともに、それが宗教上の教義、信仰の内容に深くかかわっているため、右教義、信仰の内容に立ち入ることなくしてその効力の有無を判断することができず、しかも、その判断が訴訟の帰趨を左右する必要不可欠のものである場合には、右訴訟は、その実質において法令の適用による終局的解決に適しないものとして、裁判所法三条にいう「法律上の争訟」に当たらないというべきである(前記昭和五六年四月七日第三小法廷判決参照)。�
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
建物明渡、代表役員等地位確認請求事件 平成元年9月8日 (PDF)
【動画】2023年度前期・九大法学部「憲法1(統治機構論・後半)」第7回〜裁判所④ 2023/07/13 ③
「性的指向」と称しているものは個々人の内心にのみ存在する精神的なものであるから、その性質についていくつかの見解があるにもかかわらず、そのうちいずれかの見解が妥当なものであると認めた上での判断を求めるものとなっていることは、宗教的な教義が正しいものであることを裁判所に認めてもらおうとする主張とその本質において変わるものではない。
上記の判例を参考にすれば、「性的指向」と称するものについて自らの意思で変えることができるかどうかが問題となり、その性質の当否を前提としなければ判断を行うことができないような場合には、法令を適用することによって終局的に解決することができる問題ではないため、裁判所の審判できる「法律上の争訟」の範囲を超えるものである。
よって、これを前提として何らかの結論を導き出そうとしているこの判決の内容は、憲法76条1項の「司法権」や、裁判所法3条の「法律上の争訟」の範囲を超え、裁判所の有する権限を逸脱した違憲・違法な判断となる。
例えば、「性的指向は自らの意思で変えられる」とする宗教団体Aと、「性的指向は自らの意思で変えられない」とする宗教団体Bが現れ、それぞれがその見解を争った場合に、裁判所は特定の宗教団体の主張や教義を前提として判断することは適切ではない。
その場合には、その紛争が裁判所法3条の「法律上の争訟」ではないとして退けることが必要である。
この事例も「性的指向は自らの意思で変えられるかどうか」を問題として扱い、そのどちらかの立場や見解を採用して判断を行うということそのものが、既に「法律上の争訟」の範囲を超えるものである。
このように、「性的指向」と称するものの性質を前提として何らかの法制度の存否の当否を論じることは、そもそも裁判所法3条の「法律上の争訟」に該当せず、「司法権の範囲」を超えるものであるから、裁判所で判断することのできないものである。
そのため、この札幌高裁判決が「性的指向」と称するものの性質がどういうものであるかという問題について特定の立場を採った上で、それを前提として法的な判断を行ったことは、「司法権の範囲」を超える違法があり、正当化することはできない。
【動画】【憲法_重要判例】(司法権)【板まんだら事件】 2020/11/29
【動画】【行政書士 #3】憲法の統治で一番苦手?裁判所を簡単に攻略!判例の勉強方法もわかりやすく解説(講義 ゆーき大学) 2021/03/12
【動画】行政書士試験対策公開講座 憲法36「裁判所」 2016/03/15
「司法権」については、当サイト「憲法の構成要素」でも触れている。
「性的指向が障害や疾患の一つであるという考えは受け入れられなくなった」との記載がある。
ここでは、「性的指向」について、それが「障害や疾患の一つである」か否かを問うものとなっている。
しかし、「性的指向」とは、「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかに関するものであり、個人の内心における思想、信条、信仰、感情そのものを指し示すというよりも、その内心を分類する場合における分類方法を指す概念として用いられている。
そのため、特定の「性愛」の思想、信条、信仰、感情が「障害や疾患」であるか否かという論じ方をしている場合には意味が通じるといえるが、ここで「性的指向」そのものを指して、それが「障害や疾患」であるか否かを論じることは不自然であり、意味が通じない。
そのことから、この判決は「性的指向」の意味を的確に理解できていないようである。
「障害や疾患の一つであるという考えは受け入れられなくなった」とあるが、心理的・精神的なものについては、それを「障害や疾患」と評価するか否かには難解な論点がある。
基本的には、その精神状態が社会生活を送る上で支障があるとすれば、それは「障害や疾患」と評価することも可能である。
しかし、それを「障害や疾患」と評価することによって本人が社会生活を送る上で支障が生じる場合には、それを「障害や疾患」とは評価しないという場合もある。
そのため、本人がある一定の精神状態にあるとしても、それが社会生活を送る上で支障が生じるか否かが重要な要素となるものであり、その精神状態そのものが否定されたり、肯定されたりするような意味で「障害や疾患」か否かを評価することができるという性質のものではないのである。
精神的なものについては、それが内心にとどまる限りは「内心の自由」として絶対的に保障されるのであり、そのこと自体が「障害や疾患」であるか否かという評価を受けて否定されたり、肯定されたりするようなことはない。
その内心が外部的な行為に現れるに至ったときに、それが「公共の福祉」に反する場合には、法的な規制の対象となる場合は考えられるが、内心にとどまる限りは何者にも侵されるものではないし、否定されることもないのである。
そのため、ここでは「性的指向が障害や疾患の一つであるという考えは受け入れられなくなった」と述べているのであるが、「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかという内心における心理的・精神的なものについては、それが内心に留まる限りは「内心の自由」として保障されており、「障害や疾患」か否かという評価の対象ではない。
社会生活を送る上で支障があり、それを「障害や疾患」として扱うことが本人にとって望ましい場合には、「障害や疾患」として考えることも可能であるが、「障害や疾患」として考えなければならないものとして定義されているものではないのである。
ただ、「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかという内心における心理的・精神的なものによって社会生活を送る上で支障があり、それを「障害や疾患」として扱うことが本人にとって望ましい場合には、それを「障害や疾患」として考えることも可能なものである。
そのため、「障害や疾患」であるか否かについてはこのような論点を検討しなければならず、「障害や疾患の一つであるという考えは受け入れられなくなった」のように「障害や疾患」ではないかのように述べたところで、それが本人にとって望ましいとはいえない場合もあるし、その一定の精神状態を「障害や疾患」として扱うことを前提として治療することを望む者にとっては、「障害や疾患」ではないとされることは治療の妨げになるという場合もある。
そのため、このような論点を踏まえずに「性的指向が障害や疾患の一つであるという考えは受け入れられなくなった」のように、「障害や疾患」ではないということに決めてかかることによって何らかの結論を導き出そうとする発想そのものが妥当ではない。
それとは別に、婚姻制度(男女二人一組)は、「性愛」を保護するための制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかによって区別取扱いをする制度ではないし、「性愛」に基づいて制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもないことから、ここで「性的指向が障害や疾患の一つであるという考えは受け入れられなくなった」などと述べたところで婚姻制度に何らの影響も与えるとする理由にはならず、これを理由として何らかの法制度を立法しなければならないとする根拠とはならない。
また、婚姻制度(男女二人一組)は「障害や疾患」の者でも利用することができることから、何らかの精神状態が「障害や疾患」でないと示したとしても、そのことと婚姻制度を利用できるか否かの間には何らの関わり合いも認めることができないものである。
以上のような性的指向の性質を踏まえると、人は生物学的に男か女かのどちらかで出生するけれども、どちらであっても、生物学的な機能の存在とは別に性的指向を有することがあるのだから、異性を愛する場合と同性を愛する場合を比べると、生まれながらの指向の違いがあるにすぎないといえる。そうすると、恋愛や性愛は個人の尊重における重要な一要素であり、これに係る性的指向は、生来備わる人としてのアイデンティティであるのだから、個人の尊重に係わる法令上の保護は、異性愛者が受けているのであれば、同性愛者も同様に享受されるべきである。したがって、性的指向は、重要な法的利益であるということができる。なお、同性愛のみならず、対象が異性と同性の双方の場合、自身の性を自認できない場合なども同じように考えることができるが、本件では、控訴人らの主張に基づき、同性愛と異性愛、同性婚と異性婚について検討する。
【筆者】
━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━
この段落の文面は、文脈の連続性を捉えることが困難であり、非常に読み取りづらいものなっている。
その原因は、下記の二つの話が同時並行で論じられているからである。
◇ 「性的指向」の性質
◇ 「異性愛者」と「同性愛者」を区別するべきではないこと
下記でそれぞれの内容ごとに文を追うことができるようにした。
◇ 「性的指向」の性質
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
以上のような性的指向の性質を踏まえると、人は生物学的に男か女かのどちらかで出生するけれども、どちらであっても、生物学的な機能の存在とは別に性的指向を有することがあるのだから、異性を愛する場合と同性を愛する場合を比べると、生まれながらの指向の違いがあるにすぎないといえる。そうすると、恋愛や性愛は個人の尊重における重要な一要素であり、これに係る性的指向は、生来備わる人としてのアイデンティティであるのだから、個人の尊重に係わる法令上の保護は、異性愛者が受けているのであれば、同性愛者も同様に享受されるべきである。したがって、性的指向は、重要な法的利益であるということができる。なお、同性愛のみならず、対象が異性と同性の双方の場合、自身の性を自認できない場合なども同じように考えることができるが、本件では、控訴人らの主張に基づき、同性愛と異性愛、同性婚と異性婚について検討する。
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
◇ 「異性愛者」と「同性愛者」を区別するべきではないこと
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
以上のような性的指向の性質を踏まえると、人は生物学的に男か女かのどちらかで出生するけれども、どちらであっても、生物学的な機能の存在とは別に性的指向を有することがあるのだから、異性を愛する場合と同性を愛する場合を比べると、生まれながらの指向の違いがあるにすぎないといえる。そうすると、恋愛や性愛は個人の尊重における重要な一要素であり、これに係る性的指向は、生来備わる人としてのアイデンティティであるのだから、個人の尊重に係わる法令上の保護は、異性愛者が受けているのであれば、同性愛者も同様に享受されるべきである。したがって、性的指向は、重要な法的利益であるということができる。なお、同性愛のみならず、対象が異性と同性の双方の場合、自身の性を自認できない場合なども同じように考えることができるが、本件では、控訴人らの主張に基づき、同性愛と異性愛、同性婚と異性婚について検討する。
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
この段落では、この二つの話を一つの意味の通った文面としてまとめることに失敗している。
その理由として大きな要素を占めるものは、第一文と第二文を繋いでいる「そうすると、」と、第二文と第三文を繋いでいる「したがって、」の用い方に連続性がなく、接続詞の使い方を誤っているからである。
通常、文面全体の意味を捉える際には、接続詞を中心に内容のまとまりを捉え、文の構造の論理展開を把握することになる。
そのため、意味を理解することが難しい場合に、接続詞を目印にして、検討することになる。
しかし、この文面は下記の点でその試みを断念させるものとなっている。
◇ 第一文と第二文を繋ぐ「そうすると、」の文言を中心に文面の骨格を検討しようとすると、この文面は「『異性愛者』と『同性愛者』を区別するべきではないこと」の話を中心に論理展開が行われていることになる。
しかし、そうなると、第二文と第三文を繋ぐ「したがって、」の文言が「『性的指向』の性質」の話を中心として論理展開をしようとしていることと辻褄が合わなくなる。
◇ 逆に、第二文と第三文を繋ぐ「したがって、」の文言を中心に文面の骨格を検討しようとすると、この文面は「『性的指向』の性質」の話を中心に論理展開をしようとしていることになる。
しかし、そうなると、第一文と第二文を繋ぐ「そうすると、」の文言が「『異性愛者』と『同性愛者』を区別するべきではないこと」の話を中心として論理展開をしようとしていることと辻褄が合わなくなる。
このように、これら二つの話が同時並行で行われており、かつ、その混在した内容の文と文を繋ぐ接続詞についても、文面全体の論理構造を明らかにするための基準としても役立つものとなっていないのである。
そのため、読者はこの文面の全体を意味の通った形で理解することが困難となり、読み取りづらく感じるのである。
そのため、このような読み取りづらい文面となることを防ぐためには、下記のように二つの話を分離し、順を追って説明することが適切であるといえる。
◇ 「性的指向」の性質
「以上のような性的指向の性質を踏まえると、人は生物学的に男か女かのどちらかで出生するけれども、どちらであっても、生物学的な機能の存在とは別に性的指向を有することがある」
↓ ↓
「恋愛や性愛は個人の尊重における重要な一要素であり、これに係る性的指向は、生来備わる人としてのアイデンティティである」
↓ ↓
「したがって、性的指向は、重要な法的利益であるということができる。」
↓ ↓
「なお、同性愛のみならず、対象が異性と同性の双方の場合、自身の性を自認できない場合なども同じように考えることができる」
◇ 「異性愛者」と「同性愛者」を区別するべきではないこと
「異性を愛する場合と同性を愛する場合を比べると、生まれながらの指向の違いがあるにすぎないといえる。そうすると、」
↓ ↓
「個人の尊重に係わる法令上の保護は、異性愛者が受けているのであれば、同性愛者も同様に享受されるべきである。」
↓ ↓
「本件では、控訴人らの主張に基づき、同性愛と異性愛、同性婚と異性婚について検討する。」
━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━
「以上のような性的指向の性質を踏まえると、人は生物学的に男か女かのどちらかで出生するけれども、どちらであっても、生物学的な機能の存在とは別に性的指向を有することがあるのだから、異性を愛する場合と同性を愛する場合を比べると、生まれながらの指向の違いがあるにすぎないといえる。」との記載がある。
━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━
この文が読み取りづらい原因は、下記の通りである。
〇 第一文の「けれども、」の使い方が文脈に沿うものではない。
◇ 「人は生物学的に男か女かのどちらかで出生するけれども、どちらであっても、生物学的な機能の存在とは別に性的指向を有することがある」
これは文が長くて分かりづらいので、短くすると、下記のようになる。
◇ 「男か女かのどちらかで出生するけれども、」「性的指向を有することがある」
「けれども」とは、対比的な関係にある二つの事柄を結び付ける意味で用いられる。
しかし、この「性的指向」と称するものを論じる中において、「男か女かのどちらかで出生する」という事柄は、対比的な関係にある事柄であるとはいえず、ここで取り上げることに意味を見出すことができない。
そのため、この「けれども、」の使い方は意味が通じるものとはいえない。
この点が、読み手を惑わせるものなっている。
〇 第一文の「だから、」の文言が、文脈に沿うものではない。
◇ 「人は生物学的に男か女かのどちらかで出生するけれども、どちらであっても、生物学的な機能の存在とは別に性的指向を有することがあるのだから、異性を愛する場合と同性を愛する場合を比べると、生まれながらの指向の違いがあるにすぎないといえる。」
この文は長くて分かりづらいので、短くすると、下記のようになる。
◇ 「男か女かのどちらかで出生するけれども、」「性的指向を有することがあるのだから、異性を愛する場合と同性を愛する場合を比べると、生まれながらの指向の違いがあるにすぎないといえる。」
「だから」とは、前に述べたことを理由としてその帰結を述べる言葉である。
ただ、ここで「性的指向」とは、「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを指すものであり、それを「有することがある」と述べた後に、それに続いて「のだから、」と繋ぎ、「異性を愛する場合と同性を愛する場合」を述べることは内容を繰り返すものとなっている。
これについては、「だから」という言葉で前に述べたことを理由としてその帰結を述べるものではないといえる。
また、「性的指向を有することがある」と述べた後に、それに続いて「のだから、」と繋ぎ、「生まれながらの指向の違いがあるにすぎないといえる。」と述べているものと考えるとしても、「性的指向」という「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかについて、それを「有する」ことを理由として、「生まれながら」という帰結に繋がるとはいえない。
また、「指向の違いがあるにすぎない」という文も、既に「性的指向」の中に含まれている意味であり、同じ事柄を繰り返して述べているだけとなる。
その他、「けれども、」の部分の不自然さを無視して、「男か女かのどちらかで出生する」という「出生」の部分と結んで、「出生」の時から「性的指向を有することがある」と述べようとしているのであれば、それを「のだから、」と繋いで「生まれながらの指向の違いがあるにすぎないといえる。」と述べようとしていることが考えられる。
しかし、「出生」の時から「性的指向を有する」ことを理由として、その帰結として「生まれながらの指向の違いがあるにすぎない」と述べていることは、やはり内容を繰り返しているだけとなり、意味のある内容を形成しているとはいえない。
また、「生まれながらの指向の違い」と述べている部分は、一段落前で「性的指向が決定される原因、又は同性愛となる原因は解明されておらず、遣伝的要因、生育環境等複数の要因が組み合わさって作用している可能性が指摘されている」と自ら述べている通り、「性的指向が決定される原因」は「解明されて」いるわけではなく、「遣伝的要因」や「生育環境」等の「複数の要因が組み合わさって作用している可能性」も「指摘されている」ものである。
そのため、「生まれながら」のものであるかは「解明されて」いるわけではないにもかかわらず、ここで「生まれながらの指向の違い」と述べていることは、未だ「原因」が「解明されて」いない部分について、特定の立場を基にして断定するものとなっており、適切ではない。
これらの言い回しは、文脈の内容と噛み合うものとなっておらず、読み手を混乱させるものとなっている。
━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━
上記の文脈の問題とは別に、この文の意味を検討する。
「以上のような性的指向の性質を踏まえると、」との部分について検討する。
「性的指向」とは、「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかに関するものであり、個人の内心おける精神的なものである。
これは「内心の自由」として、憲法19条の「思想良心の自由」によって保障されるものである。
この憲法19条の「思想良心の自由」は、「国家からの自由」という「自由権」の性質であり、国家から個人に対して具体的な侵害行為があった場合に、それを排除する場面で用いられることがある。
しかし、この憲法19条を根拠として特定の制度の創設を国家に対して求めることができるというものではない。
よって、「性愛」という人の内心における精神的なものを理由として特定の制度の創設を国家に対して求めることができるということにはならないことに注意が必要である。
「人は生物学的に男か女かのどちらかで出生するけれども、どちらであっても、生物学的な機能の存在とは別に性的指向を有することがあるのだから、」との部分について検討する。
ここで登場する「どちらであっても、」の「どちら」が指し示すものを検討する。
この文の冒頭で「性的指向の性質を踏まえると、」と書かれていることや、一つ前の段落で「異性愛」と「同性愛」について触れていることから、「性的指向」における「異性愛」と「同性愛」を指しているのではないかと混乱しやすいものとなっている。
しかし、この部分の直前で「生物学的に男か女かのどちらか」と書かれていることから、この「どちら」が指し示すものは「生物学的」な「男」と「女」であると考えることが妥当である。
そして、その「生物学的」な「男」と「女」の「どちらであっても、生物学的な機能の存在」としていることから、ここでいう「生物学的な機能」とは、「男」と「女」の「生物学的な機能」の差異を示すものと考えられる。
また、「出生するけれども、」のように、「出生」と結び付けていることから、「生殖」との関係についても意識させるものとなっていることから、「男」と「女」の「生物学的な機能」とは、「生殖」における「男」と「女」の「生物学的な機能」の違いについて意識させるものとなっているように見受けられる。
ただ、「性愛」を有する場合に、それがどのような対象に向かうかについての「性的指向」と称しているものは、人の心の中の事柄であり、個人の内心における心理的・精神的なものであ。
それについて論じる中で、わざわざ「生殖」における「男」と「女」の「生物学的な機能」の違いを意識させる必要があるのか疑問である。
そのため、この段落の第一文で「性的指向」について論じる際に、この部分はカットした方が意味が通じるように思われる。
下記に、この部分をカットした場合の文を記載する。
◇ 「以上のような性的指向の性質を踏まえると、」→「異性を愛する場合と同性を愛する場合を比べると、生まれながらの指向の違いがあるにすぎないといえる。」
「性的指向を有することがあるのだから、」との文について検討する。
「性的指向」とは、「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかについて分類する際に用いられている概念である。
つまり、個人の内心において「性愛」を有するか否かという問題が先にあって、その後、「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかに着目して、その向かう先に応じて区別した場合の分類のことを指す言葉である。
そのため、「性的指向」そのものは、個々人の内心にある思想、信条、信仰、感情を指し示すものではない。
よって、「性的指向」そのものについては、「人」が「有する」とか「有しない」とかいう性質のものではなく、これを「人」は「性的指向を有する」と表現している部分は素直に意味が通るものにはなっていない。
「異性を愛する場合と同性を愛する場合を比べると、生まれながらの指向の違いがあるにすぎないといえる。」との部分について検討する。
ここでは「異性を愛する場合と同性を愛する場合」とある。
この「愛する」の意味は多義的に使われることがあるため注意が必要である。
外国の事例を紹介したニュースの記事の中で「同性愛は禁じられている」などと表現されていることがあるが、それは「内心で抱かれる同性に対する思い」を禁じているわけではなく、「同性愛行為」などと表現されることもある「同性間での性交類似行為」あるいは「同性間での性的な接触」が禁じられているという意味であることが多い。
イラク、同性愛に禁錮刑 最長15年、欧米は批判 2024/4/28
イラク、同性愛に禁錮刑 最長15年、欧米は批判 2024年4月28日
この札幌高裁判決の基になっている札幌地裁判決の「1 認定事実」の「⑺ア(エ)」の部分でも、下記のように「同性愛行為」について触れている。
「(エ) ロシアは,2013年(平成25年),同性愛行為は禁止しないが,同性愛を宣伝する活動を禁止するための法改正を行い,2014年(平成26年),憲法裁判所も同性愛行為が同国憲法に違反しない旨の判断をした。」
そのため、ここで「愛する」などと表現している部分を見ると、法制度は内心に対して中立的な内容でなければならないことから、法律論としては内心について述べているはずはないという前提でこの文を見ると、法律論として取り扱うことのできる自然人の「行為」に着目した形で「同性間での性交類似行為」あるいは「同性間での性的な接触」について、「愛する」と表現しているのではないかと思わせるものとなっている。
すると、この文は法律論としてと扱うことのできる問題として認識しようとすると、下記のようになる。
「性的指向の性質を踏まえると、……(略)……異性を愛する場合と同性を愛する場合を比べると、生まれながらの指向の違いがあるにすぎないといえる。」
↓ ↓ ↓
「性的指向の性質を踏まえると、……(略)……『異性との性行為をする場合』と『同性と性交類似行為をする場合』を比べると、生まれながらの指向の違いがあるにすぎないといえる。」
しかし、ある者の「行為」に着目してそれを「生まれながら」と論じることは、刑法学や刑事政策の場面において犯罪という「行為」を行う者についても同じように「生まれながら」のものであると論じることに繋がるため適切ではない。
そのような論理は、犯罪行為を行った者に対する再教育を不能にさせるものとなるため妥当な理解ではない。
そのため、ある「行為」を行っている者に対して、それが「生まれながら」であるかということを安易に決めてかかるようなことをするべきではない。
機会的同性愛 Wikipedia
ただ、このような「行為」に着目した議論をしているとすれば、それまで「性的指向」や「恋愛、性愛」について「人が情緒的、感情的、性的な意味で、人に対して魅力を感じること」とのように個々人の内心における心理的・精神的な事柄について述べていた部分から、その者の外部的な行為の話に変わっており、文脈として不自然な点もある。
そこで、ここで「愛する」と述べているものが、個人の内心における心理的・精神的なものとしての「性愛」について述べている場合をさらに検討する。
ここでは「異性を愛する場合」と「同性を愛する場合」とが書かれており、「異性愛」と「同性愛」の二分論で考えるものとなっている。
しかし、他にも「両性愛」「全性愛」「近親性愛」「多性愛」「小児性愛」「老人性愛」「死体性愛」「動物性愛」「対物性愛」「対二次元性愛」など様々なバリエーションが存在することが議論されている。
性的同一性と性自認の一覧 Wikipedia
【セクシュアリティ辞典】性の多様性をまとめてみた 2020-05-20
また、個々人が「性愛」を抱く場合の対象は様々であり、「性別」という視点に限られるものではなく、「年齢」「身長」「体型」「外見」「部位」「性格」など様々な視点も存在している。
他にも、「性愛」を抱く対象が「自分自身」に向かう者もいるし、自分の年齢や時期、その時々の気分やタイミング、環境、対象との関係性などによっても、個々人が「性愛」を抱く場合や抱かない場合は様々である。
さらに、「性愛」を抱かない「無性愛」とされる者もいる。
それにもかかわらず、「性愛」の対象の向かう対象の範囲を「人」に限り、その上でさらに「性別」の視点に限り、「性的指向」と称するものも「異性愛」や「同性愛」などと明確に区別できることを前提とし、すべての人間が「性愛」を有するかのような論じ方をしている部分は、「性愛」に対する理解を誤っている。
また、この判決では「性的指向」のみを取り上げるのであるが、「性的指向」と「恋愛的指向」を区別するべきであるとの考え方も存在する。
恋愛的指向 Wikipedia
これは、「恋愛」を抱くが、それが「性愛」に結び付くとは限らず、「恋愛」していれば相手を性欲を満たすための対象であるかのように捉えることは、重大な誤認であり、著しく不適切であると考えるものである。
他にも、「性愛」を「性的欲求」の側面に限られない意味で使っているのであれば、「愛」の取り上げ方には「友愛」「親子愛」「兄弟愛」「姉妹愛」「会社愛」「宗教愛」などいくらでもある。
さらに、「性愛」であっても、「恋愛」であっても、「友愛」であっても、「兄弟姉妹愛」であっても、「親子愛」であっても、「孫への愛」てあっても、「子孫への愛」であっても、「会社への愛」であっても、「宗教的な愛」であっても、「国家への愛(愛国心)」であっても、「人類愛」であっても、「生命愛」であっても、すべて個々人の内心にのみ存在する精神的なものであることから、これらの様々な「愛」などと称される感情をそれぞれの間で明確に区別することができるという性質のものではない。
また、「性愛」の感情そのものが、生活の中の一側面としてそのような心理状態が現れるというだけのものであり、常にそのような心理状態を感じ続けているわけでもない。
もともと「異性愛」や「同性愛」といっても、「少しばかり異性愛」「少しばかり同性愛」から、「強度の異性愛」「強度の同性愛」など、その心理は様々である。
一人の人間の中でも、感情は様々な要素を有している。
また、「愛」などと称される感情もあれば、「嫌悪」など不快な感情も存在する。
そのどちらの感情であっても、そこに法律論上の優劣はないのであり、殊更に「愛」を正当化して法制度を立法することができるという性質のものではない。
これらはすべて「内心の自由」によって捉えられるべきものである。
そのため、このような個々人の有する内心の一側面のみを切り取って、その者を「異性愛者」や「同性愛者」などと明確に区別することができるわけではないのであり、法律論を論じる際に「異性愛者」や「同性愛者」などと区別して考えることができるかのような前提で論じていること自体が誤りである。
また、そもそも法制度は個々人の内心に対して中立的な内容でなければならないのであり、個人の内心に踏み込む形で何かを論じようとしていることそのものが誤っている。
法律論として「愛」を論じることはできない。
隣人愛 Wikipedia
自己愛 Wikipedia
愛 Wikipedia
よって、この「異性を愛する場合と同性を愛する場合」の文の「愛する」の意味について、「行為」を指すものと考えても、「内心」を指すものと考えても、いずれの意味でも妥当でない。
「そうすると、恋愛や性愛は個人の尊重における重要な一要素であり、これに係る性的指向は、生来備わる人としてのアイデンティティであるのだから、個人の尊重に係わる法令上の保護は、異性愛者が受けているのであれば、同性愛者も同様に享受されるべきである。」との記載がある。
━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━
この文が読み取りづらい原因は下記の通りである。
「そうすると、」とあるが、この文言がどの部分に係っているのか明確でない。
そのため、この文のどこに焦点を当てて読み取るべきなのか分かりづらいものとなっている。
◇ 「そうすると、」 → 「恋愛や性愛は個人の尊重における重要な一要素であ」る。
◇ 「そうすると、」 → 「恋愛や性愛(は個人の尊重における重要な一要素であり、これ)に係る性的指向は、生来備わる人としてのアイデンティティである」
◇ 「そうすると、」 → 「個人の尊重に係わる法令上の保護は、異性愛者が受けているのであれば、同性愛者も同様に享受されるべきである。」
また、「そうすると、」という文言が用いられているということは、これよりも以前に示された部分を理由として、これらのいずれかの結論を導いていることになるが、それぞれの結論に対応する根拠がこれよりも以前の部分に存在するといえるかは疑問である。
そこで、それぞれの部分を結論として考えた場合に、それ以前で示された部分にその結論を導くための根拠となるものが存在するかを検討する。
◇ まず、「そうすると、」の文言が「恋愛や性愛は個人の尊重における重要な一要素であ」るという部分に係ると考えた場合、これを結論とする根拠がこれよりも以前に書かれているはずである。
そこで、この文の書かれている「(2)ア」の第一段落から一文前の第二段落の第一文までの範囲の内容をまとめると、下記の通りである。
「(2)ア」の第一段落
① 性的指向とは、人が情緒的、感情的、性的な意味で、人に対して魅力を感じること
② 恋愛、性愛の対象が異性に対して向くことが異性愛、同性に向くことが同性愛である。
③ 性的指向が決定される原因、又は同性愛となる原因は解明されておらず、遣伝的要因、生育環境等複数の要因が組み合わさって作用している可能性が指摘されている
④ 精神医学に関わる大部分の専門家団体は、ほとんどの人の場合、性的指向は、人生の初期か出生前に決定され、選択するものではないとしており、
⑤ 心理学の主たる見解も、性的指向は意思で選ぶものでも、意思により変えられるものでもないとしている。
⑥ 性的指向が障害や疾患の一つであるという考えは受け入れられなくなった
「(2)ア」の第二段落の第一文
⑦ 以上のような性的指向の性質を踏まえる
⑧ 人は生物学的に男か女かのどちらかで出生するけれども、どちらであっても、生物学的な機能の存在とは別に性的指向を有することがある
⑨ 異性を愛する場合と同性を愛する場合を比べると、生まれながらの指向の違いがあるにすぎないといえる。
初めに、この文の書かれている一文前である第二段落第一文の⑦⑧⑨から検討する。
⑦は、それよりも以前の内容を受けているだけなので、「恋愛や性愛は個人の尊重における重要な一要素であ」ると考えることの根拠とはならないことは明らかである。
⑧は、「性的指向を有することがある」として「性的指向」を有すると述べているだけであるから、それが「恋愛や性愛は個人の尊重における重要な一要素であ」ると考えることの根拠とはならない
(『性的指向』は『性愛』を有する場合にそれがどのような対象に向かうかに関する分類をいうものであり、『性愛』を有するか否かを答えることができても、『性的指向』そのものは『有する』とか『有しない』とかいう性質のものではないため、言葉の用い方として適切であるとはいえない。)
また、この札幌高裁判決では「(2)ア」の第一段落の第一文では、「性的指向」の意味について、「性的指向とは、人が情緒的、感情的、性的な意味で、人に対して魅力を感じることであり、このような恋愛、性愛の対象が……(略)……。」と述べている。
ただ、この札幌高裁判決の「性的指向」についての説明は誤っていると考えられるため、「同性婚訴訟 福岡地裁判決」の説明を取り上げて補足するが、そこでも「性的指向とは、人の恋愛・性愛がどういう対象に向かうのかを示す概念をいい、」と述べられている。
そのため、「恋愛、性愛」を前提として意味を成している「性的指向」と称する概念を取り上げ、その「性的指向を有する」ことを理由として、ここでいう「恋愛や性愛は個人の尊重における重要な一要素であ」ると説明することは、根拠としている事柄よりも後に派生したことを示して論じようとするものであり、妥当な文章とはならなくなる。
・「恋愛、性愛」 → 「性的指向」
・「性的指向を有する」 → 「そうすると、」「恋愛や性愛は個人の尊重における重要な一要素であ」る (?)
このように、⑧の部分が「恋愛や性愛は個人の尊重における重要な一要素であ」るとする結論を導くための根拠とはならない。
⑨についても、⑧と同様に、「異性を愛する場合と同性を愛する場合」や「生まれながらの指向の違い」ように「恋愛、性愛」を前提とした「性的指向」と称するものを取り上げているだけである。
よって、「恋愛や性愛」の性質について「個人の尊重」と結び付けて論じることの理由になるものではなく、「恋愛や性愛は個人の尊重における重要な一要素であ」るとする結論を導くための根拠とはならない。
そこで、更に遡って「(2)ア」の第一段落を検討する。
①も②も、先ほど⑧で説明したように「恋愛、性愛」を前提とする「性的指向」と称するものを取り上げているだけなので、この「恋愛、性愛」について論じている「恋愛や性愛は個人の尊重における重要な一要素であ」るとする結論を導くための根拠とはならない。
③もやはり「恋愛、性愛」を前提とする「性的指向」と称するものの性質が「解明」されていないことを述べているだけである。
④と⑤も、「恋愛、性愛」を前提とする「性的指向」と称するものについての「精神医学に関わる大部分の専門家団体」や「心理学の主たる見解」を取り上げているだけである。
⑥についても、「恋愛、性愛」を前提とする「性的指向」と称するものを「障害や疾患」と考えるか否かを問題にしているだけである。
よって、③④⑤⑥の内容が「恋愛や性愛は個人の尊重における重要な一要素であ」るとする結論を導くための根拠とはならない。
このように、「恋愛や性愛は個人の尊重における重要な一要素であ」るとする根拠は、これよりも以前に登場しておらず、「そうすると、」の文言は、この部分には係っていないことになる。
ただ、それが明らかになると、今度は、この文が当然「恋愛や性愛は個人の尊重における重要な一要素であ」ると断定していることは、これ以前の文脈と関連性がなく唐突なものであり、そのように理解するに至った経緯について何らの根拠も示していないということになる。
よって、「恋愛や性愛は個人の尊重における重要な一要素であ」ると述べていることそのものについての妥当性を別途検討する必要がある。
◇ 次に、「そうすると、」の文言が「恋愛や性愛(…)に係る性的指向は、生来備わる人としてのアイデンティティである」という部分に係ると考えた場合、これを結論とする根拠がこれよりも以前に書かれているはずである。
そこで、先ほど示した「(2)ア」の第一段落から一文前の第二段落の第一文までの範囲の内容を確認する。
「(2)ア」の第一段落
① 性的指向とは、人が情緒的、感情的、性的な意味で、人に対して魅力を感じること
② 恋愛、性愛の対象が異性に対して向くことが異性愛、同性に向くことが同性愛である。
③ 性的指向が決定される原因、又は同性愛となる原因は解明されておらず、遣伝的要因、生育環境等複数の要因が組み合わさって作用している可能性が指摘されている
④ 精神医学に関わる大部分の専門家団体は、ほとんどの人の場合、性的指向は、人生の初期か出生前に決定され、選択するものではないとしており、
⑤ 心理学の主たる見解も、性的指向は意思で選ぶものでも、意思により変えられるものでもないとしている。
⑥ 性的指向が障害や疾患の一つであるという考えは受け入れられなくなった
「(2)ア」の第二段落の第一文
⑦ 以上のような性的指向の性質を踏まえる
⑧ 人は生物学的に男か女かのどちらかで出生するけれども、どちらであっても、生物学的な機能の存在とは別に性的指向を有することがある
⑨ 異性を愛する場合と同性を愛する場合を比べると、生まれながらの指向の違いがあるにすぎないといえる。
初めに、この文の書かれている一文前である第二段落第一文の⑦⑧⑨から検討する。
⑦は、それよりも以前の内容を受けているだけなので、「恋愛や性愛(…)に係る性的指向は、生来備わる人としてのアイデンティティである」と考えることの根拠とはならないことは明らかである。
⑧は、「人は生物学的に男か女かのどちらかで出生するけれども、どちらであっても、生物学的な機能の存在とは別に性的指向を有することがある」と述べている。
この文は読み取りづらく、「生物学的な機能」とは何を意味しているのか分かりづらいため、下記のように整理する。
「人は生物学的に男か女かのどちらかで出生する」
↓ ↓ (けれども、)
(男か女かの)「どちらであっても、」(男か女かの)「生物学的な機能の存在とは別に性的指向を有することがある」
ここでは、個人の「男か女かの」「生物学的な機能の存在」について話題にしているにもかかわらず、これとは「別に」として個人の内心における精神的なものである「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかという「性的指向」と称するものに話が変わっている。
しかし、「性的指向」と称するものを論じる際に、「男か女かの」「生物学的な機能の存在」を取り上げて論じることに直接的な関係性を認めることができず、これを持ち出して論じていること自体が疑問である。
この点は無視して⑧の内容を見ると、「性的指向を有することがある」と述べているだけである。
③で示された「遣伝的要因」の「可能性」の「指摘」と、④で示された「精神医学に関わる大部分の専門家団体」が「性的指向は、人生の初期か出生前に決定され、」と述べていることと関係して、この⑧の「人」の「出生」と関係させようとしているのかもしれないが、素直に読めるものとはなっていない。
また、③や④で示された内容も「可能性」の「指摘」や学問上の意見の一つであり、断定できるというものではないことにも注意が必要である。
そのため、この点を拾うとしても、「人」の「出生」から「性的指向を有することがある」と述べているだけである。
これが「恋愛や性愛(…)に係る性的指向は、生来備わる人としてのアイデンティティである」と結論付けるための根拠となるかを検討する。
まず、「恋愛や性愛(…)に係る性的指向は、」の部分は、⑧の「性的指向」と同じことを述べているだけである。
「生来備わる人としての」の部分も「人」の「出生」の部分と同じことを述べているだけである。
最後に「アイデンティティである」との部分が残る。
しかし、「アイデンティティ」という言葉の意味は、環境や時間の変化の中でも連続性をもってある特定のものをその他のものとの間で区別することを可能する事柄についていうものである。
このような個人を識別する機能や個人を特定する機能について、法制度としては「氏名」や「マイナンバー」がその役割を果たしているといえる。
「氏名」や「マイナンバー」については、「出生」と結び付いて記録されることになるため、「アイデンティティ」と表現する場合も考えられる。
しかし、「性的指向」とは、個人の内心における心理的・精神的なものであることから、そのような識別機能を有するものではないし、「出生」と結び付いて記録されているものでもないことから、「アイデンティティ」という言葉に対応するものはない。
そのため、「アイデンティティである」と述べている部分も、「人」の「出生」や「性的指向」と関係するものではない。
よって、⑧の部分が「恋愛や性愛(…)に係る性的指向は、生来備わる人としてのアイデンティティである」という結論を導くための根拠とはならない。
⑨は、「異性を愛する場合と同性を愛する場合を比べると、生まれながらの指向の違いがあるにすぎないといえる。」と述べている。
この「恋愛や性愛(…)に係る性的指向は、」との部分は、「異性を愛する場合と同性を愛する場合を比べると、」や「指向の違いがあるにすぎないといえる。」との部分とほぼ同じことを述べているだけである。
「生来備わる人としての」との部分は、「生まれながらの」との部分と同じことを述べているだけである。
最後に「アイデンティティである」との部分が残るが、「アイデンティティ」の意味は特定のものをその他のものとの間で区別することを可能とする事柄についていうものであるから、「異性を愛する場合と同性を愛する場合」などという個人の内心における心理的・精神的な事柄と関係するものではない。
そのため、「アイデンティティである」と述べている部分が、「異性を愛する場合と同性を愛する場合を比べると、生まれながらの指向の違いがあるにすぎないといえる。」の部分と関係するものではない。
よって、⑨の部分が「恋愛や性愛(…)に係る性的指向は、生来備わる人としてのアイデンティティである」という結論を導くための根拠とはならない。
このように、「恋愛や性愛(…)に係る性的指向は、生来備わる人としてのアイデンティティである」とする根拠は、これよりも以前に登場しておらず、「そうすると、」の文言は、この部分には係っていないことになる。
◇ 三つ目に、「そうすると、」の文言が「個人の尊重に係わる法令上の保護は、異性愛者が受けているのであれば、同性愛者も同様に享受されるべきである。」という部分に係ると考えた場合、これを結論とする根拠がこれよりも以前に書かれているはずである。
ただ、この「個人の尊重に係わる法令上の保護は、」の部分であるが、先ほど示したように、この第二文の「恋愛や性愛は個人の尊重における重要な一要素であ」るという部分について「恋愛や性愛」が「個人の尊重」と結び付くという根拠は何ら示されないままに唐突に述べられているものであり、当然、「恋愛や性愛」や「性的指向」と称するものが「個人の尊重に係わる」とする根拠もない。
よって、ここで「個人の尊重に係わる法令上の保護は、」のように、「恋愛や性愛」や「性的指向」と称するものが「個人の尊重に係わる」ものとして「法令上の保護」を受けているかのように論じていることは妥当でない。
また、婚姻制度についても、「恋愛や性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「恋愛や性愛」の有無や「恋愛や性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いをする制度ではないし、「恋愛や性愛」に基づいて制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもない。
この点にも注意が必要である。
これを前提に、先ほど示した「(2)ア」の第一段落から一文前の第二段落の第一文までの範囲の内容を確認する。
「(2)ア」の第一段落
① 性的指向とは、人が情緒的、感情的、性的な意味で、人に対して魅力を感じること
② 恋愛、性愛の対象が異性に対して向くことが異性愛、同性に向くことが同性愛である。
③ 性的指向が決定される原因、又は同性愛となる原因は解明されておらず、遣伝的要因、生育環境等複数の要因が組み合わさって作用している可能性が指摘されている
④ 精神医学に関わる大部分の専門家団体は、ほとんどの人の場合、性的指向は、人生の初期か出生前に決定され、選択するものではないとしており、
⑤ 心理学の主たる見解も、性的指向は意思で選ぶものでも、意思により変えられるものでもないとしている。
⑥ 性的指向が障害や疾患の一つであるという考えは受け入れられなくなった
「(2)ア」の第二段落の第一文
⑦ 以上のような性的指向の性質を踏まえる
⑧ 人は生物学的に男か女かのどちらかで出生するけれども、どちらであっても、生物学的な機能の存在とは別に性的指向を有することがある
⑨ 異性を愛する場合と同性を愛する場合を比べると、生まれながらの指向の違いがあるにすぎないといえる。
初めに、この文の書かれている一文前である第二段落第一文の⑦⑧⑨から検討する。
⑦は、それよりも以前の内容を受けているだけなので、「(個人の尊重に係わる)法令上の保護は、異性愛者が受けているのであれば、同性愛者も同様に享受されるべきである。」と考えることの根拠とはならないことは明らかである。
⑧と⑨は、「性的指向を有することがある」や「異性を愛する場合と同性を愛する場合を比べると、生まれながらの指向の違いがあるにすぎないといえる。」と述べているものである。
「(個人の尊重に係わる)法令上の保護は、異性愛者が受けているのであれば、同性愛者も同様に享受されるべきである。」との結論に繋がる部分があるように思われる。
ただ、この結論が導かれる理由として、この部分を挙げるとしても、それは法制度は内心に対して中立的な内容でなければならないという前提の下に、「性的指向」と称するものが個人の内心における精神的なものであることを理由に、その「性的指向」を審査して区別取扱いをするような法制度を立法することはできないことにより、「法令上の保護は、異性愛者が受けているのであれば、同性愛者も同様に享受されるべきである。」という結論が導かれるというものである。
これは、この判決が考えるように、あたかも「恋愛や性愛」を保護することを目的とした制度が存在していたり、「恋愛や性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかという「性的指向」と称するものを審査して区別取扱いをする制度が存在していたり、「恋愛や性愛」に基づいて制度を利用することを求めたり進めたりする制度が存在しているとしても許されるかのような前提で考えて、その中でも「異性愛者が受けているのであれば、同性愛者も同様に享受されるべきである。」などと考えるものとは異なる。
よって、ここで文面上は話が噛み合っているとしても、法的に正当化することのできる意味として考えると、この札幌高裁判決の前提とている認識を基にして意味が対応しているわけではないことに注意が必要である。
①②③④⑤⑥についても、「恋愛や性愛」を前提とする「性的指向」と称するものが個人の内心における精神的なものであることを明らかにしており、法制度は内心に対して中立的な内容でなければならないことから、「(個人の尊重に係わる)法令上の保護は、異性愛者が受けているのであれば、同性愛者も同様に享受されるべきである。」という結論が対応するといえる部分はある。
ただ、先ほども述べたように、この札幌高裁判決の前提としている認識を基にして意味が対応しているわけではないことに注意が必要である。
このように、それぞれの結論について、これを根拠づける内容がこれよりも以前に明確に示されているといえるか疑問なところが多く、「そうすると、」に続く形で結論を正当化することができているとまではいえない。
この点で、読み手を混乱させるものとなっている。
━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━
「恋愛や性愛は個人の尊重における重要な一要素であり、」との部分について検討する。
まず、「恋愛や性愛」とは、個人の内心における心理的・精神的なものである。
このような事柄は、「内心の自由」として憲法19条の「思想良心の自由」によって保障されるものである。
ここでは「個人の尊重における重要な一要素であり、」のように述べて、「個人の尊重」という言葉を使っていることから、憲法13条前段の「すべて国民は、個人として尊重される。」との部分と関係するかのように論じているように見受けられる。
しかし、この13条の「個人の尊重」とは、「全体主義」との対比における「個人主義」に基づくことを示すものであり、法主体としての地位を有する対象となるのは「個人」であることを意味するものである。
そのため、この「個人の尊重」の文言が、個人の内心における心理的・精神的なものと直接的に結び付くことはない。
そのことから、「恋愛や性愛」は、個人の内心における心理的・精神的なものとして憲法19条の「思想良心の自由」によって保障されるのであり、憲法13条の「個人の尊重」と関係させて論じていることは誤りである。
よって、「個人の尊重における重要な一要素であり、」のように、「個人の尊重」と関係することを前提として、「重要な一要素」と述べている部分も誤りとなる。
上記の文脈における問題点について解説したところでも説明したが、この「恋愛や性愛は個人の尊重における重要な一要素であ」ると理解するに至る経緯については、これよりも以前の文面の中に登場していない。
そのため、このように「恋愛や性愛」が「個人の尊重における重要な一要素であ」るとする根拠は何ら示されていない。
よって、法律論としては、唐突に「恋愛や性愛は個人の尊重における重要な一要素であ」るとの理解を前提に論じていることも妥当でなく、誤っている。
「これに係る性的指向は、生来備わる人としてのアイデンティティであるのだから、」との部分について検討する。
「これに係る性的指向」の部分の「これ」とは、「恋愛や性愛」を指している。
そのため、これは「恋愛や性愛」「に係る性的指向は、」と述べている文ということになる。
この「性的指向」とは、「恋愛や性愛」という個人の内心における心理的・精神的なものに「係る」ものであり、「内心の自由」として憲法19条の「思想良心の自由」によって保障されるものである。
ここでは、「性的指向」について「生来備わる」としている。
しかし、この判決は、一段落前で「性的指向が決定される原因、又は同性愛となる原因は解明されておらず、遣伝的要因、生育環境等複数の要因が組み合わさって作用している可能性が指摘されている」と自ら述べているように、「性的指向が決定される原因」は「解明されて」おらず、「遣伝的要因」や「生育環境」等の「複数の要因が組み合わさって作用している可能性」も「指摘されている」。
そのため、「生来備わる」ものであるかは「解明されて」いないのであり、ここで「生来備わる」と述べていることは、未だ「原因」が「解明されて」いない部分について、特定の立場を基にして断定するものとなっていることから、適切ではない。
ここでは、「性的指向」について「人としてのアイデンティティである」としている。
まず、「アイデンティティ」とは、環境や時間の変化の中でも連続性をもってある特定のものをその他のものとの間で区別することを可能する事柄についていうものである。
そのため、これを「人」と関係させて考えると、個人を識別する機能や個人を特定する機能にあたるものをいうのであり、法制度としては「氏名」や「マイナンバー」、「生年月日」、「住所」などの個人情報がその役割を果たすものであるといえる。
「氏名」や「マイナンバー」、「生年月日」、「住所」などについては、「アイデンティティ」と表現される場合が考えられる。
しかし、「性的指向」とは、個人の内心における心理的・精神的なものであることから、そのような個人を識別するための機能を有するものではないことから、「アイデンティティ」という言葉に対応するものはない。
そのため、「性的指向」について、「アイデンティティである」と述べている部分は法律論としては誤っている。
「個人の尊重に係わる法令上の保護は、異性愛者が受けているのであれば、同性愛者も同様に享受されるべきである。」との部分について検討する。
「個人の尊重に係わる法令上の保護」とある。
ここで「個人の尊重に係わる法令上の保護」と述べているということは、「法令上の保護」が「個人の尊重に係わる」ものとそうでないものとに区別しようとする発想によるものとなっている。
しかし、「個人の尊重」がなされていない状態とは、人が奴隷のように売買される対象となっていたり、人が集団の中の一部として扱われたりするなど、「個人」が法的な主体として認められていない場合をいうものである。
具体的にそのような状態が生じていないにもかかわらず、「個人の尊重」と特定の法令を結び付けて考えていることは妥当でない。
また、ここでは何らかの状態を「個人の尊重」と結び付けて論じようというのであるが、「個人の尊重」を理由として特定の制度の創設を国家に対して求めることができるというものではない。
そのため、「個人の尊重」を根拠として「法令上の保護」という具体的な制度が設けらているかのように考えているのであれば誤りである。
この文の始めで「恋愛や性愛は個人の尊重における重要な一要素であり、」と述べていることから、「個人の尊重に係わる法令上の保護」との部分と合わせて、「恋愛や性愛」と「法令上の保護」を関係させている部分について検討する。
まず、「恋愛や性愛」とは、個人の内心における心理的・精神的なものである。
このような事柄は、「内心の自由」として憲法19条の「思想良心の自由」によって保障されるものである。
そのことから、「恋愛や性愛」に係わる「法令上の保護」とは何かを考えると、憲法19条の「思想良心の自由」ということになる。
その他、「恋愛や性愛」に基づく行為についての「法令上の保護」は、下記のように整理されることになる。
・「恋愛や性愛」が外部的な行為に現れた場合には、憲法21条1項の「表現の自由」として保障される。
・「恋愛や性愛」に基づいて集会をする場合には、憲法21条1項の「集会の自由」として保障される。
・「恋愛や性愛」に基づいて人的結合関係を形成する場合には、憲法21条1項の「結社の自由」として保障される。
・「恋愛や性愛」に基づいてある場所に住む場合には、憲法22条1項の「居住の自由」として保障される。
・「恋愛や性愛」に基づいて場所を移すことがあった場合には、憲法22条1項の「移転の自由」として保障される。
・「恋愛や性愛」に基づいて活動をする場合、憲法20条1項前段の「信教の自由」によって「信仰の自由」、「宗教的行為の自由」、「宗教的結社の自由」として保障される。
・「恋愛や性愛」の動機に基づいて財産を移転したり、処分したりする場合には、憲法29条1項の「財産権」として保障される。
・「恋愛や性愛」の動機に基づいて職業をしたり、「恋愛や性愛」に関わる職業を営む場合には、憲法22条1項の「職業選択の自由」によって「営業の自由」として保障される。
・「恋愛や性愛」に基づいて外国に移住する場合には、憲法22条2項の「外国移住の自由」として保障される。
・「恋愛や性愛」に基づいて日本国の国籍を離脱する場合には、憲法22条2項の「国籍離脱の自由」として保障される。
よって、ここでは「恋愛や性愛は個人の尊重における重要な一要素であり、」と述べて、「個人の尊重に係わる法令上の保護」としていることから、「恋愛や性愛」が「個人の尊重」について書かれている憲法13条前段によって保障されているかのように述べているが、「恋愛や性愛」そのものは憲法19条の「思想良心の自由」によって保障され、その行為は上記のように憲法上の個別の規定によって保障されることになることから、直ちに憲法13条を持ち出すことは適切ではない。
また、「恋愛や性愛」を憲法13条後段の「幸福追求権」として論じる余地はあるが、これは憲法13条後段であり、憲法13条前段の「個人の尊重」の部分ではない。
そのため、ここで「個人の尊重」のように憲法13条前段の部分を述べていることは誤っていることになる。
その他、「恋愛や性愛」を憲法13条後段の「幸福追求権」によって保障されることを検討するとしても、これは憲法13条は「国家からの自由」という「自由権」の性質であることから、これによって特定の制度の創設を国家に対して求めることができるということにはならない。
また、法制度は内心に対して中立的な内容でなければならないことから、「恋愛や性愛」という特定の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的として制度を設けた場合には、憲法20条1項後段・3項、89条の「政教分離原則」に違反するし、「恋愛や性愛」という特定の思想、信条、信仰、感情を保護してそれ以外の思想、信条、信仰、感情を保護しないことになることから、憲法14条1項の「平等原則」に違反するし、制度を利用する者の内心に対して国家が干渉するものとなることから、憲法19条の「思想良心の自由」にも違反することになる。
そのため、「恋愛や性愛」を「保護」するという形で法律を立法することはできないのであり、ここでいう「法令上の保護」というものが、憲法上で「国家からの自由」という「自由権」として保障されるという意味を超えて、「恋愛や性愛」を「保護」する形の具体的な法制度について述べようとしているのであれば、そのような法制度は定められていないし、もし定められていた場合にはその法律そのものが違憲となって失効することになるものである。
よって、そのような法制度が定められているとか、定められているとしても構わないかのように述べていることは誤りである。
「異性愛者が受けているのであれば、同性愛者も同様に享受されるべきである。」とある。
まず、「異性愛者」と「同性愛者」という文言について検討する。
これは、「異性愛者」や「同性愛者」などと区別して考えることが可能であるかのような前提で取り上げるものとなっている。
しかし、「異性愛者」であるか「同性愛者」であるかというのは、個人の内心における精神的なものによるものであり、その者が「異性愛」や「同性愛」の思想、信条、信仰、感情を有しているか否かなど、その者の内心の中でしか分からないものである。
そのため、「異性愛者」や「同性愛者」であると称する者がいるとしても、それは外部から客観的に判定することができるという性質のものではなく、それを証明することは不可能である。
そのことから、これらの「異性愛者」や「同性愛者」と区別しているものは、結局のところ、自己の思想、信条、信仰、感情を告白するものに過ぎない。
よって、このような客観性を有しないものを根拠とする形で法律論を組み立てることはできない。
また、一度「異性愛者」や「同性愛者」などと区別して考えたとしても、「性的指向」と称するものは変わることもあるとされている。
そのため、このような内心の事柄を基にして論じることは、「性的指向」と称するものが途中で変わった場合や、そもそも「性愛」を失った場合などにおいて、その区別に基づく議論はすべて意味を成さなくなるものである。
そのことから、このような事柄は法制度との関係において整合的な説明をすることが不可能なものであり、法律論として区別して取扱うことのできる性質のものではない。
これは「異性愛者」や「同性愛者」に限られるものではなく、「両性愛者」を称する者も、「無性愛者」を称する者も、それ以外の「性愛」を持つと称する者も同じである。
よって、ここで「異性愛者」や「同性愛者」などと分類した上で、それを基に人を区別することが可能であるかのような前提で論じていること自体が法律論として妥当でない。
次に、「異性愛者が受けているのであれば、同性愛者も同様に享受されるべきである。」との文の意味について検討する。
まず、憲法は20条1項後段・3項、89条で「政教分離原則」を定めていることから、特定の思想、信条、信仰、感情を保護するために制度を設けることはできない。
また、憲法は14条1項で「平等原則」を定めていることから、特定の思想、信条、信仰、感情を有するか否かを審査して区別取扱いをすることはできないし、特定の思想、信条、信仰、感情を抱く者のために制度を設け、それ以外の思想、信条、信仰、感情を抱く者との間で区別することも許されない。
他にも、憲法は19条で「思想良心の自由」、20条1項前段で「信教の自由」を定めて「内心の自由」を保障していることから、個々人の内心を規制する法律を定めることはできないし、法制度を利用する者に対して内心の告白を強制することはできないし、特定の思想、信条、信仰、感情を抱くことを求めたり、勧めるようなこともしてはならない。
このように、法制度は内心に対して中立的な内容でなければならないのであり、法制度が特定の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的として定められている場合や、法制度が個々人の内心に基づいて区別取扱いを行うようなものとして定められている場合、法制度を利用する者の内心に干渉するようなものとして定められている場合には、そのこと自体で違憲となる。
そのため、法制度の内容が上記のような事柄に抵触している場合には違憲となる。
また、法制度を適用する場面についても、「異性愛者」や「同性愛者」などと人をその内心に基づいて区別し、ある特定の内心を有する者に対して法制度の適用を否定することがあった場合には、憲法14条1項の「平等原則」における「法適用の平等」に違反することになる。
このような意味において、「異性愛者が受けているのであれば、同性愛者も同様に享受されるべきである。」との意味は、その通りであるということができる。
ここでは「異性愛者」と「同性愛者」の二分論で論じるものとなっているが、これに限られるものではなく、「両性愛者」、「全性愛者」、「多性愛者」、「小児性愛者」、「老人性愛者」、「死体性愛者」、「動物性愛者」、「対物性愛者」、「対二次元性愛者」、「無性愛者」であっても「同様に享受されるべきである。」といえる。
また、「キリスト教徒」、「イスラム教徒」、「ユダヤ教徒」、「ゾロアスター教徒」、「仏教徒」、「神道を信じる者」、「武士道を重んじる者」、「軍事オタク」、「鉄道オタク」、「アニメオタク」、「アイドルオタク」であっても、「ADHD」、「アスペルガー」、「自閉症」、「強迫神経症」、「妄想症」、「境界性パーソナリティー障害」、「解離性同一性障害」、「統合失調症」を有すると称する者であっても「同様に享受されるべきである。」といえる。
これらは、人の内心における心理的・精神的なものであるという意味でまったく変わりないものであり、法律論としては、それらを有すると称する者であることを理由として区別取扱いをすることはできないからである。
この点、婚姻制度(男女二人一組)については、「性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いをする制度ではないし、「性愛」に基づいて制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもない。
また、婚姻制度(男女二人一組)を適用する場面においても、個々人の内心を審査し、その中で特定の内心を有する者に対して制度の適用を否定しているという事実もない。
そのことから、婚姻制度(男女二人一組)について、「異性愛者」を称する者も、「同性愛者」を称する者も、「同様に享受」することが可能である。
よって、婚姻制度(男女二人一組)の内容が憲法に違反しているということはないし、その適用の場面において憲法に違反しているという事実もない。
これに対して、この判決では「2 本件規定が憲法13条に違反する旨の主張について」の項目の「(2)ウ」で「これまで社会上、法令上想定されてきた異性愛者による婚姻の制度に」と述べているように、婚姻制度(男女二人一組)が「異性愛者」を対象とした制度であるかのような前提で論じている部分がある。
そのため、この判決のいうような意味でこの文を読み解くと、「異性愛者が受けている」との部分の意味は、「異性愛」を保護することを目的とした制度が存在していたり、「異性愛者」を有するか否かによって区別取扱いをする制度が存在していたり、国家が個人の内心に対して干渉するような制度が存在しているとしても許されるかのような前提を含む意味で述べるものとなっている。
しかし、もし「異性愛」という特定の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的とした制度が存在した場合には、憲法20条1項後段・3項、89条の「政教分離原則」に違反するし、「異性愛」という特定の思想、信条、信仰、感情を保護し、それ以外の「性愛」や、「性愛」以外の思想、信条、信仰、感情を保護しないということになることから、憲法14条1項の「平等原則」に違反するし、制度を利用する者の内心に干渉するものとなることから、憲法19条の「思想良心の自由」に違反することになる。
そのため、この判決の前提とする考え方の下に「異性愛者が受けている」のように「異性愛者」を称する者を対象とした法制度が存在するとすれば、その法制度自体が違憲となる。
よって、その違憲となる法制度の効果を「同性愛者も同様に享受されるべきである。」のように論じることは、その違憲な法制度をさらに進めようとするものであるから、同じく違憲であり、誤りであるということになる。
「法令上の保護」が「同様に享受されるべきである。」ことについて、ここでは「恋愛や性愛は個人の尊重における重要な一要素であり、これに係る性的指向は、生来備わる人としてのアイデンティティである」ことが理由であるとしている。
「恋愛や性愛は個人の尊重における重要な一要素であり、これに係る性的指向は、生来備わる人としてのアイデンティティである」
↓ ↓
「のだから、」
↓ ↓
「個人の尊重に係わる法令上の保護は、異性愛者が受けているのであれば、同性愛者も同様に享受されるべきである。」
しかし、法律論上は、「法令上の保護」が「同様に享受されるべきである。」とする理由は、法制度は個人の内心に対して中立的な内容でなければならないことから、内心に基づいて人を区別して、その区別に従う形で取扱う制度を定めていけないし、その区別に従う形で制度の適用の可否を決してはいけないからである。
そのため、ここでは「法令上の保護」が「同様に享受されるべきである。」という結論に至る理由について、「恋愛や性愛は個人の尊重における重要な一要素であり、これに係る性的指向は、生来備わる人としてのアイデンティティである」ことを挙げているが、その理由付けは誤っている。
「したがって、性的指向は、重要な法的利益であるということができる。」との記載がある。
━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━
まず、「したがって、」の文言があることから、「性的指向は、重要な法的利益である」という結論を述べる前に、その結論が導き出されるまでの理由が、この文よりも前に記されているはずである。
そこで、この文よりも前を遡り、この結論が導き出される根拠となるものが存在するかを検討する。
「(2)ア」の第一段落
① 性的指向とは、人が情緒的、感情的、性的な意味で、人に対して魅力を感じること
② 恋愛、性愛の対象が異性に対して向くことが異性愛、同性に向くことが同性愛である。
③ 性的指向が決定される原因、又は同性愛となる原因は解明されておらず、遣伝的要因、生育環境等複数の要因が組み合わさって作用している可能性が指摘されている
④ 精神医学に関わる大部分の専門家団体は、ほとんどの人の場合、性的指向は、人生の初期か出生前に決定され、選択するものではないとしており、
⑤ 心理学の主たる見解も、性的指向は意思で選ぶものでも、意思により変えられるものでもないとしている。
⑥ 性的指向が障害や疾患の一つであるという考えは受け入れられなくなった
「(2)ア」の第二段落
⑦ 以上のような性的指向の性質を踏まえる
⑧ 人は生物学的に男か女かのどちらかで出生するけれども、どちらであっても、生物学的な機能の存在とは別に性的指向を有することがある
⑨ 異性を愛する場合と同性を愛する場合を比べると、生まれながらの指向の違いがあるにすぎないといえる。
⑩ 恋愛や性愛は個人の尊重における重要な一要素であり、これに係る性的指向は、生来備わる人としてのアイデンテイティである
⑪ 個人の尊重に係わる法令上の保護は、異性愛者が受けているのであれば、同性愛者も同様に享受されるべきである。
①~⑨については、「恋愛、性愛」や「性的指向」の性質について述べているだけである。
この「恋愛、性愛」や「性的指向」とは、個人の内面における精神的なものであることから、「内心の自由」として憲法19条の「思想良心の自由」として保障されることは考えられる。
ただ、ここからは、ここで「したがって、」とそれよも前から何らかの理由を繋いだ上で、「性的指向は、重要な法的利益である」との結論を示す際に、「法的」な問題として扱うことについての根拠を示すものではないし、それを「重要な」のように他の事柄と区別し、その性質を強調することに繋がるような内容も見つけ出すことができない。
そこで、この文の直前の文である⑩と⑪の部分を検討する。
この⑩と⑪の部分は、この判決の文面では「そうすると、恋愛や性愛は個人の尊重における重要な一要素であり、これに係る性的指向は、生来備わる人としてのアイデンテイティであるのだから、個人の尊重に係わる法令上の保護は、異性愛者が受けているのであれば、同性愛者も同様に享受されるべきである。」のように一つの文として記載されている。
このため、通常の文章の構成から考えると、この文の後半の⑪に記載された「同様に享受されるべきである。」との結論部分を受け、次の文で「したがって、」と繋ぎ、「性的指向は、重要な法的利益である」という結論に至ると読み取ることになる。
そこで、その⑪の部分に対応する形で文脈を検討する。
⑪ 「個人の尊重に係わる法令上の保護は、異性愛者が受けているのであれば、同性愛者も同様に享受されるべきである。」
↓ ↓
「したがって、性的指向は、重要な法的利益であるということができる。」
しかし、「個人の尊重に係わる法令上の保護は、異性愛者が受けているのであれば、同性愛者も同様に享受されるべきである。」との内容は、単に個々人の内心に基づいて「法令上」の区別取扱いをするべきではないということを述べているに過ぎない。
これは、憲法14条1項の「平等原則」における「法適用の平等」に関わる論点について説明しているものであるということは理解できるが、それがその後、「したがって、」と繋げられ、「性的指向」そのものについて「重要な法的利益」であるか否かについての結論を論じる際の原因となる事情を示すものであるとはいえない。
よって、通常文書が構成される際には、「したがって、」のように前の文から意味を繋ぐ形で結論を述べる際には、直前の文の最後に書かれている結論部分を受ける形で表現されるはずであるが、この判決の文面においてはそのような読み取り方をすると意味が通じないため、その読み方はできないことになる。
そこで別の読み方を改めて検討することが必要である。
先ほど挙げた文の前半の⑩の部分を受けて、次の文として「したがって、」と繋がり、「性的指向は、重要な法的利益である」との結論に至るものとして読み取ることができるかを検討する。
そこで、その⑩の部分に対応する形で文脈を整理すると、下記のようになる。
⑩ 「恋愛や性愛は個人の尊重における重要な一要素であり、これに係る性的指向は、生来備わる人としてのアイデンテイティである」
↓ ↓
「したがって、性的指向は、重要な法的利益であるということができる。」
これは、法的な意味として正しいかどうかは別して、文脈の流れとしては、意味が繋がるように思われる。
ただ、このように意味を読み取ろうとすると、この文はもともと「恋愛や性愛は個人の尊重における重要な一要素であり、これに係る性的指向は、生来備わる人としてのアイデンテイティである」の後に「のだから、」と繋ぎ、「個人の尊重に係わる法令上の保護は、異性愛者が受けているのであれば、同性愛者も同様に享受されるべきである。」という結論に至るまでの過程として示されている内容であることを無視することになる。
そのため、このような読み方は、下記の対立を引き起こすことになる。
◇ 「したがって、」を重視して文の前後関係を読み取ろうとすると、一文の中で⑩の部分と⑪の部分を繋いでいる「のだから、」の接続を無視することとなる。
◇ 逆に「のだから、」を重視して文の前後関係を読み取ろうとすると、「したがって、」の接続詞が意味の通じないものとなる。
このように、「したがって、」と「のだから、」のどちらを採っても、これら全体を意味の通ったものと把握することができないのである。
よって、国家権力の行使として行われる裁判所の判決の文面において、このような問題を抱えた意味の通じない文面で論じていることは、適切であるとはいえない。
━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━
文脈の問題とは別に、この文面が、法的な意味において正当化できるものとなっているかを検討する。
⑩ 「恋愛や性愛は個人の尊重における重要な一要素であり、これに係る性的指向は、生来備わる人としてのアイデンテイティである」
↓ ↓
「したがって、性的指向は、重要な法的利益であるということができる。」
まず、「恋愛や性愛」は個々人の内心における精神的なものであることから、「内心の自由」として憲法19条の「思想良心の自由」、あるいは、憲法20条1項前段の「信教の自由」として保障されるものである。
また、個々人が「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかという「性的指向」と称するものについても、同様である。
ここでは、個々人の内心における様々な精神活動の中から、「恋愛や性愛」のみを取り上げているのであるが、「友愛」「友情」「絆」「慈悲」「御心」「悟り」「不快感」「嫌悪感」など、他の様々な精神活動についても同様である。
ただ、このような内心における精神的なものを取り上げて、ここでは「個人の尊重における重要な一要素であり、」と述べるのであるが、内心の問題は憲法19条の「思想良心の自由」として保障されるものであり、憲法13条前段に記載されている「すべて国民は、個人として尊重される。」の文を基にした「個人の尊重」と結び付けて論じることには飛躍がある。
憲法上の条文として示されているすべての権利については、すべて法主体としての地位を認められている「個人」に属するものであることを前提としており、その意味で個人の内心を保障している19条の「思想良心の自由」についても、「個人」として保障されるものであるということができ、13条の示す「個人の尊重」に繋がるものとなっているといえる側面はある。
しかし、「恋愛や性愛」という個々人の内心における精神活動の一部分を取り上げるだけでは、それは「内心の自由」として扱われる以上の意味を見出すことはできないのであり、それを憲法19条の「思想良心の自由」を離れて、それとは区別する意味で「個人の尊重」と繋げることは因果関係の道筋を示すものはなく、論理的に飛躍しており、「個人の尊重」という文言によって事象を捉えることについて正当化することができる内容を持つものではない。
そのため、「恋愛や性愛は個人の尊重における重要な一要素であり、」との文は、そもそも適用される条文の選択を誤っているし、「恋愛や性愛」という個々人の内心における精神活動について、どのように扱うことが「個人」を「尊重」したことになるのかという説明もないままに、「個人の尊重における重要な一要素であり、」と結論付けている(その結論を前提に論じようとしている)ことは、憲法上の条文の存在を前提とし、その条文との対応関係を検討する中において法的な視点によって論理を構成していくという営みの中では、条文の根拠に裏付けられる形での意味の通ったものとしては理解することができない。
よって、「恋愛や性愛は個人の尊重における重要な一要素であり、」と述べていることは、誤った説明であるといえる。
次に、「これに係る性的指向は、生来備わる人としてのアイデンテイティである」と述べている部分を検討する。
この「これ」の指し示すものは、「性的指向」と「係る」ものであることを述べていることから、この文の中の少し前の「恋愛や性愛」のことである。
そのため、この文は「恋愛や性愛」「に係る性的指向は、生来備わる人としてのアイデンテイティである」と述べていることになる。
この「恋愛や性愛」やそれを有する場合にどのような対象に向かうかについての「性的指向」と称しているものは、個人の内心における心理的・精神的なものであり、憲法19条の「思想良心の自由」として保障されるものである。
そして、「性的指向」が「生来備わる」かどうかであるが、これはこの判決が一段落前の「(2)ア」の第二文で「性的指向が決定される原因、又は同性愛となる原因は解明されておらず、遣伝的要因、生育環境等複数の要因が組み合わさって作用している可能性が指摘されている」と述べている通り、「性的指向が決定される原因」は「解明されて」いるわけではなく、「遣伝的要因」や「生育環境」等の「複数の要因が組み合わさって作用している可能性」も「指摘されている」ものである。
そのため、「生来備わる」のものであるかは「解明されて」いるわけではないにもかかわらず、ここで「生来備わる」と述べていることは、未だ「原因」が「解明されて」いない部分について、特定の立場を基にして断定するものとなっており、適切ではない。
「性的指向」が「アイデンティティ」であるかどうかであるが、「アイデンティティ」とは、環境や時間の変化の中でも連続性をもってある特定のものをその他のものとの間で区別することを可能する事柄についていうものであり、これを「人」と関係させて考えると、個人を識別する機能や個人を特定する機能にあたるものをいうことから、法制度としては「氏名」や「マイナンバー」、「生年月日」、「住所」などの個人情報がその役割を果たすものであるといえる。
そのため、「氏名」や「マイナンバー」、「生年月日」、「住所」などについては、「アイデンティティ」と表現される場合が考えられる。
しかし、「性的指向」とは、個人の内心における心理的・精神的なものであることから、そのような個人を識別するための機能を有するものではなく、「アイデンティティ」という言葉に対応するものはない。
そのため、「性的指向」について、「アイデンティティである」と述べている部分は法律論としては誤っている。
このことから、「恋愛や性愛は個人の尊重における重要な一要素であり、」との部分や「性的指向」については、これを捉えるための条文の根拠を誤っているし、「性的指向」と称しているものが「生来備わる」かどうかは「解明されて」いるものではないし、「性的指向」が法的な意味で「アイデンティティ」という言葉に対応するともいえないものである。
よって、この「恋愛や性愛は個人の尊重における重要な一要素であり、これに係る性的指向は、生来備わる人としてのアイデンテイティである」との文に対して、「したがって、」という接続詞を用いて、これを原因として「性的指向は、重要な法的利益であるということができる。」のように「性的指向」が「重要な法的利益である」という結論を導き出すことができるかのように論じていることは、論理的に意味が通じるものとなっていない。
よって、「したがって、」のようにそれ以前の文面を繋ぐ形で「性的指向は、重要な法的利益である」という結論を述べている部分は、その結論に至るまでの理由となるものが示されているとはいえず、「したがって、」の接続詞は意味が通じるものとなっていないし、そこで示されている「性的指向は、重要な法的利益である」との結論についても、その内容を正当化できるだけの理由に支えられているものではない。
その他、国家が個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかについての「性的指向」と称するものを審査して、その審査の結果、特定の「性愛」を有する者がいた場合に、それを強制的に変えさせようとするなど、国家から個人に対する具体的な侵害行為が存在する場合には、「国家からの自由」という「自由権」として憲法19条の「思想良心の自由」によってその侵害を排除することが考えられる。
この意味で、「性的指向」は、憲法19条の「思想良心の自由」によって法的な保障の対象となるものである。
ただ、個々人の内心を「国家からの自由」という「自由権」の性質として保障している憲法19条の「思想良心の自由」によって、特定の制度の創設を国家に対して求めることはできない。
そのため、ここで「性的指向は、重要な法的利益である」と述べて、法的な保障が及ぶことについて触れているとしても、それは「国家からの自由」という「自由権」として憲法19条の「思想良心の自由」の中で保障されるものであり、具体的な制度の創設を国家に対して求めることができるというものではないし、自らの望む内容の法制度が定められていない場合に、それを自らの望む形に内容を形成することを求めることができるというものでもない。
そのため、「重要な法的利益」と述べている部分を、このような「国家からの自由」という「自由権」の性質を離れて理解することはできないのであり、これをその後の文の中で「国家からの自由」という「自由権」の性質を超えて、特定の制度の創設を国家に対して求めたり、自らの望む法制度が定められていない場合に、それを自らの望む形に内容を形成することを求めることができるとする根拠として扱うことまで含まれるかのような前提の下に論じようとしていることは誤っている。
「同性愛のみならず、対象が異性と同性の双方の場合、自身の性を自認できない場合なども同じように考えることができるが、本件では、控訴人らの主張に基づき、同性愛と異性愛、同性婚と異性婚について検討する。」との記載がある。
「同性愛のみならず、対象が異性と同性の双方の場合、自身の性を自認できない場合なども同じように考えることができるが、」との部分について検討する。
ここでいう「対象が異性と同性の双方の場合」や「自身の性を自認できない場合」とは、個人の内心における心理的・精神的なものであることから、「内心の自由」として憲法19条の「思想良心の自由」によって保障されるという意味では「同じように考えることができる」ということができる。
しかし、この札幌高裁判決では、法制度は個人の内心に対して中立的な内容でなければならないにもかかわらず、個人の内心における心理的・精神的なものを保護するために法制度が定められているとしても許されるかのような前提で論じ初め、ここで「対象が異性と同性の双方の場合、自身の性を自認できない場合なども同じように考えることができる」と述べるものとなっていることから、その意味では誤っている。
その他、「自身の性を自認できない場合」とあるが、この「性を自認」と述べている部分には科学的な面から議論のあるものである。
トランス問題をどのように考えるべきか ――最初の一歩―― 2022年11月28日
ただ、この「自認」というものも個人の内心における心理的・精神的なものであるから、その個人の内心における心理的・精神的なものを特定の価値観に基づいて分類してその分類に従う形で法制度として区別して扱うことができるものではないことから、これを取り上げて論じていること自体が法律論として誤りである。
「本件では、控訴人らの主張に基づき、同性愛と異性愛、同性婚と異性婚について検討する。」との部分について検討する。
ここには「同性婚」や「異性婚」とあるが、これは法律用語ではないし、法律論としてこの言葉を使うことには問題がある。
もし「~~婚」と名付けるだけで、それを「婚姻」とすることができるのであれば、「親子婚」「兄弟婚」「姉妹婚」「親戚婚」「師弟婚」「集団婚」「家族婚」「子供婚」「クラス婚」「サークル婚」「宗教団体婚」「組合婚」「会社婚」「政党婚」「不動産婚」「独り者婚」などと、どのような形でも「婚姻」とすることができることになってしまう。
このような考えは妥当でないため、「婚」を付けるだけで何でも「婚姻」とすることができるということにはならない。
仮に「~~婚」という言葉を用いたとしても、その「~~婚」という言葉は、「~~」の部分を法的な意味における「婚姻」として扱うことができるとする理由を示すものではない。
そのため、そもそも「~~」の部分について、法的な意味における「婚姻」とすることができるか否かという論点を回避することはできない。
よって、「~~婚」という表現を用いたとしても、常にその「婚」の意味である「婚姻」とは何か、「婚姻」のそのものがどのような枠組みであるかという部分が問われることになる。
そこで、「婚姻」という概念に内在的に含まれている限界について下記で検討する。
「婚姻」は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として設けられた枠組みである。
これは、下記のような経緯によるものである。
その社会の中で何らの制度も設けられていない場合には、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合が発生する。
例えば、「父親不明」の子供が増える、父親を特定できない子供が増える、父親が蒸発して行方不明になった子供が増える、それらにより「子の福祉」が減少する、父親を特定できないことにより近親者の範囲を把握できずに「近親交配」に至り潜性遺伝子の発現した個体が高い確率で生じるようになる、一部の強者が多数人との生殖関係を独占することによって社会の中で「子を持ちたいと希望して相手を見つけようとする男女」の数の不均衡が生じて「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」が生まれる、低年齢での妊娠・出産により母体に危険が及ぶ、などの問題が生じることがある。
これらの不都合を解消するために、下記のような立法目的を有する枠組みを設けることが必要となる。
・「子の福祉」が実現される社会基盤を構築すること
・潜性遺伝子の発現した個体が高い確率で生じることを抑制すること
・「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」を減らすこと
・母体を保護すること
そして、これらの目的を達成するためには、下記の要素を満たす枠組みを設けることが必要となる。
・子の遺伝的な父親を特定できる組み合わせとすること
・特定された子の父親にも子に対する責任を担わせること
・特定された子の父親を基に遺伝的な近親者を把握すること
・未婚の男女の数の不均衡を防止できる組み合わせに限定すること
これらの要素を満たすものとして「一人の男性」と「一人の女性」が選び出され、その間に「貞操義務」を設け、その関係を法的に結び付ける形を「婚姻」と呼んでいる。
そして、この「婚姻」に対して法的効果や一定の優遇措置を設けることで、婚姻制度を利用する者を増やし、これらの目的を達成することを目指すものとなっている。
このように、「婚姻」は国民が「生殖」によって子供を産むことに関係して起き得る問題を抑制することを目的として、「生殖と子の養育」の観点に着目して他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた枠組みである。
このような「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解決しようとする目的を離れて「婚姻」を観念することはできない。
そのため、「婚姻」の文言には、これらの目的を達成することを阻害する組み合わせを「婚姻」の中に含めることはできないという内在的な限界が含まれており、その限界を超えるものについては「婚姻」とすることはできない。
また、憲法24条は「婚姻」を規定しており、「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めている。
これについても、上記の要素を満たす枠組みとして定められているものである。
この憲法24条の定める形が「婚姻」であり、これらの要素を満たさないものについては「婚姻」とすることはできない。
そのため、法律論として論じる際には、この点を考えないままに「~~婚」のように、あたかも「~~」の部分を「婚姻」とすることができるかのような前提を含む形で論じることは適切ではない。
ここでは「同性婚」という言葉が使われているが、「同性間の人的結合関係」についても、これらの要素を満たすものではないことから、「婚姻」とすることはできない。
よって、「同性婚」のように、あたかも「婚姻」として扱うことができるかのような表現をしていることは誤りとなる。
ここでは「異性婚」という言葉も使われているが、上記のように「婚姻」そのものが「男女二人一組」という「異性」間を前提とする概念として形成されているのであり、その「婚姻」の意味である「婚」に「異性」を加えて「異性婚」と表現することは、文法上は同義反復となるため適切な表現ではない。
このように、「~~婚」という言葉は法律用語として通用するものではないことを押さえ、その「婚姻」とは何かという部分を踏まえずに語感だけで論じようとすることは適切でない。
ここでは「同性愛と異性愛、同性婚と異性婚について検討する。」のように、「性愛」と「婚姻」を結び付けて論じようとするものとなっている。
このことからすると、この札幌高裁判決は、婚姻制度が「異性」間である「男女二人一組」を対象としていることを捉えて、それは「異性愛」という特定の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的とした制度であり、「異性愛者」を称する者を対象とした制度であり、「異性愛」に基づいて制度を利用することを求めたり勧めたりする制度であると考えているように思われる。
その上で、「異性愛者」を称する者は婚姻制度(男女二人一組)を利用することができるが、「同性愛者」を称する者は婚姻制度(男女二人一組)を利用することができないとの認識を前提として、新たに「同性愛」という特定の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的とし、「同性愛者」を称する者を対象とし、「同性愛」に基づいて利用することを求めたり勧めたりする制度を定めるべきかどうかを「検討」しようとするものとなっている。
しかし、そもそも法制度は個人の内心に対して中立的な内容でなければならないのであり、もし「性愛」という特定の思想、信条、信仰、感情を保護するための制度が存在した場合には、憲法20条1項後段・3項、89条の「政教分離原則」に違反するし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いをしたり、特定の「性愛」を有する者を対象とした制度を設けたりした場合には、個人の内心に基づいて人を区別するものとなるから、憲法14条1項の「平等原則」に違反するし、制度を利用する者の内心に対して国家が干渉するものとなることから、憲法19条の「思想良心の自由」に違反することになる。
よって、「性愛」という個人の内心における心理的・精神的なものと、「婚姻」という法制度における法律関係の問題を関連させて考えることは、法律論として誤りである。
そして、婚姻制度は、「性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いを行うものではないし、「性愛」に基づいて制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもない。
そのため、婚姻制度(男女二人一組)は「異性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、「異性愛者」を称する者を対象とした制度でもないし、「異性愛」に基づいて制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもない。
そのことから、「同性愛者」を称する者であるとしても、婚姻制度(男女二人一組)の要件を満たして制度を利用する意思があるのであれば、適法に制度を利用することが可能である。
実際、「同性愛者」を称する者であるとしても、婚姻制度(男女二人一組)を利用している事実は認められる。
よって、「同性愛者」を称する者が婚姻制度(男女二人一組)を利用することができないことを前提として論じていることは誤りとなる。
この判決の述べるように婚姻制度と「性愛」とを結び付けて論じることになれば、他の法制度についても「性愛」やその他の思想、信条、信仰、感情とを結び付けて論じることに繋がることになる。
すると、「養子縁組」を行って「親子」となることについても、「小児性愛」を保護するための制度であり、「小児性愛者」を対象とする制度であり、「小児性愛」に基づいて制度を利用することを求めたり勧めたりする制度であると同様に考えることに繋がることになる。
そのため、法制度と個人の内心における心理的・精神的なものを結び付けて考える発想そのものが誤っているのであり、婚姻制度の中に「性愛」という思想、信条、信仰、感情を持ち込んで論じることは誤りである。
以上のとおり、性的指向は生来備わる性向であり、社会的には異性愛者と同性愛者それぞれの取扱いを変える本質的な理由がないといえ、同時に、その個人からみれば、人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の象徴であって、人格権の一内容を構成し得るものというべきである。
【筆者】
━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━
この文は、読み取りづらいものとなっている。
その原因は、下記の通りである。
この文は、「以上のとおり、」のように、これよりも前の文の内容を受けて、それをまとめるものとなっている。
そして、その「以上のとおり、」としてまとめている内容は、「同時に、」の文言で繋いであることから、二つの内容が含まれていると予測することができる。
そのため、「同時に、」の前後の部分をそれぞれのまとまりとして捉えようとすると、それぞれの部分がどの範囲でまとまりを形成しているかを考えることになる。
ここで、「同時に、」の前後を分けると、下記のようになる。
「同時に、」の前後の文
◇ 「以上のとおり、性的指向は生来備わる性向であり、社会的には異性愛者と同性愛者それぞれの取扱いを変える本質的な理由がないといえ、」
◇ 「その個人からみれば、人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の象徴であって、人格権の一内容を構成し得るものというべきである。」
ただ、「以上のとおり、」の部分は、前の段落を受けていることを示すものであるが、「同時に、」の文言よりも前の部分だけに係る語句とは思われず、この文が示す結論の全体に係るものと思われるので、これを外して考える。
すると、下記のように、「~~であり、~~といえ、(同時に、)~~であり、~~である。」のように、二つの文の中で「~~であり、」という同一の文言を登場させ、「同時に、」の文言の前後が並列の関係で同じようなまとまりとして記載されていることを予測させるものとなっている。
「~~であり、」の文言が連続的に使われていることに注目する読み方
◇ 「性的指向は生来備わる性向であり、社会的には異性愛者と同性愛者それぞれの取扱いを変える本質的な理由がないといえ、」
◇ 「その個人からみれば、人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の象徴であって、人格権の一内容を構成し得るものというべきである。」
しかし、このような読み取り方をすると、前半は意味が通じるが、後半の部分には主語が存在しておらず、突然、「その個人からみれば、人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の象徴であって、人格権の一内容を構成し得るものというべきである。」と述べていることになる。
この文が一つのまとまりとして、「以上のとおり、」とこれよりも前の段落を受けて、その結論を示すものであるとすれば、この文の主語となる部分がこの段落よりも前に記載されていることになるが、前の段落は下記の二つの内容を同時並行で混在させたままに論じているだけである。
◇ 「性的指向」の性質
◇ 「異性愛者」と「同性愛者」を区別するべきではないこと
そのため、これよりも前の段落の中で、この文の主語となるものを見つけ出すことができない。
すると、先ほど挙げた「~~であり、」を二回用いて、「同時に、」の文言の前後を並列の関係で同じようなまとまりとして記載したものと考える読み方が誤っているとの可能性が浮上する。
そこで検討すると、この文は「以上のとおり、A、同時に、B。」のように構成しているわけではなく、「性的指向は生来備わる性向であり、」の部分が「同時に、」の前と後の二つの部分にそれぞれ係る形で主語となっているという読み方に行き着く。
× 「以上のとおり、A、同時に、B。」
○ 「以上のとおり、性的指向は生来備わる性向であり、A、同時に、B。」
すると、この文は、「同時に、」の前後で分けるとしても、下記の二つの内容を持っていることになる。
◇ 「性的指向は生来備わる性向であり、社会的には異性愛者と同性愛者それぞれの取扱いを変える本質的な理由がない」の部分
◇ (性的指向は生来備わる性向であり、)「その個人からみれば、人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の象徴であって、人格権の一内容を構成し得るものというべきである」
このように、この文は読み取る際に妥当な読み方をいくつか探ることが必要となっており、これが原因となって、読者を混乱させるものとなっている。
次に、この文の「以上のとおり、」の文言は、前の段落を受ける形で説明するものとなっているが、この前の段落のどの部分が、先ほど挙げた二つのまとまりと関わるのかを検討する。
前の段落の内容は、下記の通りである。
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
以上のような性的指向の性質を踏まえると、人は生物学的に男か女かのどちらかで出生するけれども、どちらであっても、生物学的な機能の存在とは別に性的指向を有することがあるのだから、異性を愛する場合と同性を愛する場合を比べると、生まれながらの指向の違いがあるにすぎないといえる。そうすると、恋愛や性愛は個人の尊重における重要な一要素であり、これに係る性的指向は、生来備わる人としてのアイデンテイティであるのだから、個人の尊重に係わる法令上の保護は、異性愛者が受けているのであれば、同性愛者も同様に享受されるべきである。したがって、性的指向は、重要な法的利益であるということができる。なお、同性愛のみならず、対象が異性と同性の双方の場合、自身の性を自認できない場合なども同じように考えることができるが、本件では、控訴人らの主張に基づき、同性愛と異性愛、同性婚と異性婚について検討する。
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
上記の最後の文である第四文は、「なお、」と始まり「検討する。」で文が締められている。
ただ、「検討する。」としていることは、この判決全体での「検討」の仕方について触れるものであり、「以上のとおり、」のように前の段落の内容を繋ぐ形で結論を述べようとしているこの文の内容と対応するものではない。
そのため、通常であれば、このような「なお、」以下の文は、(カッコ)で括って文面全体の流れに沿わないものであるが内容を補足するものとして記載していることを読者に伝わるように記載するか、あるいは、文章の構成そのものを見直してこの内容についても別の文脈の中で自然に読み取ることができるように書き換えることが必要なものである。
しかし、この判決では、そのような配慮をしないままに文面の一連の流れとしてそのまま記載していることから、自然に意味を読み取ることができず、読者を混乱させることになっている。
そこで、上記の「なお、」以下の部分をカットして改めて検討する。
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
以上のような性的指向の性質を踏まえると、人は生物学的に男か女かのどちらかで出生するけれども、どちらであっても、生物学的な機能の存在とは別に性的指向を有することがあるのだから、異性を愛する場合と同性を愛する場合を比べると、生まれながらの指向の違いがあるにすぎないといえる。そうすると、恋愛や性愛は個人の尊重における重要な一要素であり、これに係る性的指向は、生来備わる人としてのアイデンテイティであるのだから、個人の尊重に係わる法令上の保護は、異性愛者が受けているのであれば、同性愛者も同様に享受されるべきである。したがって、性的指向は、重要な法的利益であるということができる。……(略)……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
第一文の冒頭の「以上のような性的指向の性質を踏まえると、」の部分は、前の段落を受けていることを説明するものであり、ここで「以上のとおり、」として結論を示すに至るまでの理由になるものではないため、対応関係を検討する候補からは外すことになる。
すると、二つの話が同時並行で混在したまま説明されているため、非常に分かりづらいが、下記のように対応しているように思われる。
◇ 「人は生物学的に男か女かのどちらかで出生するけれども、どちらであっても、生物学的な機能の存在とは別に性的指向を有することがあるのだから、異性を愛する場合と同性を愛する場合を比べると、生まれながらの指向の違いがあるにすぎないといえる」
◇ 「個人の尊重に係わる法令上の保護は、異性愛者が受けているのであれば、同性愛者も同様に享受されるべきである。」
↓ ↓ ↓
「性的指向は生来備わる性向であり、社会的には異性愛者と同性愛者それぞれの取扱いを変える本質的な理由がない」の部分
◇ 「恋愛や性愛は個人の尊重における重要な一要素であり、これに係る性的指向は、生来備わる人としてのアイデンテイティである」
◇ 「性的指向は、重要な法的利益であるということができる。」
↓ ↓ ↓
(性的指向は生来備わる性向であり、)「その個人からみれば、人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の象徴であって、人格権の一内容を構成し得るものというべきである」の部分
そこで、以下では、この文が、前の段落に記載されたこのような内容を繋ぐ形で論じられているものであることを前提に検討する。
━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━
「性的指向は生来備わる性向であり、」との部分について検討する。
この判決は、一段落前で「性的指向が決定される原因、又は同性愛となる原因は解明されておらず、遣伝的要因、生育環境等複数の要因が組み合わさって作用している可能性が指摘されている」と自ら述べている。
そのため、「性的指向が決定される原因」は「解明されて」いるわけではなく、「遣伝的要因」や「生育環境」等の「複数の要因が組み合わさって作用している可能性」も「指摘されている」。
よって、「性的指向」が「生来備わる」のものであるかは「解明されて」いるわけではないのであり、ここで「生来備わる」と述べることは、未だ「原因」が「解明されて」いない事柄について、様々な見解の中から特定の立場を基にして断定するものとなっており、適切ではない。
また、「性的指向」は変わることもあるとされており、一度「備わ」ったからといって、それが生涯変わらないといえるものではない。
実際、下記の動画のように「私自身は10年ぐらい前から人間女性はもう恋愛対象ではなくなっていた」と述べる者もいる。
【動画】初音ミクと“結婚”した男性「母と妹に理解してもらえなかった」なぜ結婚したのか?結婚生活は? 2023/05/13
一般社団法人フィクトセクシュアル協会 Twitter
他にも、「性的指向」が定まらないと称する者もいるのであり、確定的なものではない。
よって、この意味でも「性的指向は生来備わる性向であり、」と述べていることは誤りである。
結局、このような事柄は個人の内心における精神的なものであり、「内心の自由」として憲法19条の「思想良心の自由」として保障されることにはなるが、それ以外のものではない。
「社会的には異性愛者と同性愛者それぞれの取扱いを変える本質的な理由がないといえ、」との部分について検討する。
ここでは、「異性愛者」と「同性愛者」との文言が登場する。
これは人の内心における精神的なものを取り上げた上で、それを異なるものに分類し、その分類に基づいて人を区別するものということができる。
しかし、「性愛」の存否や傾向について述べていること自体が、特定の価値観で人を分類しようとする者の用いている一つの思想、信条、信仰に過ぎないものである。
もともと「性愛」の分類を使っていない者もいるし、そのような分類で人を見ていない者もいるし、「性愛」を重視していない者もいるし、そもそも考えたことない者もいる。
また、「同性愛者」や「異性愛者」というような人の内心に基づいた区別はいずれ無くなるべきだと考えている者もいる。
それにもかかわらず、この判決で「異性愛者」や「同性愛者」などという言葉を使い、「性愛」の有無やその「性愛」がどのような対象に向かうかという視点で人を区別して見ていること自体が、既に「性愛」によって人を分類するという特定の価値観に基づいて、その主張に与する形で論じるものとなっており、不適切である。
裁判所が個々人の内心に基づいて人を分類するようなことをするべきではないし、自己の内心を告白するに過ぎない者の主張をそのまま取り上げて認定することも妥当でない。
恐らくこの判決を書いた裁判官は、自分自身についても、何らかの「性愛」に基づいて「〇〇性愛者」であると認識しているのだと思われる。
しかし、そのような「性愛」に基づいた分類で人を区別して考えていること自体が、特定の思想や信条、信仰を抱く者の中でのみ通用する価値観でしかないものである。
このような心理的・精神的なもので、客観性を有しないものについては、下記のような様々な分類方法がある。
「草食系・肉食系」という分類がある。
「理系・文系」という分類がある。
文系と理系 Wikipedia
人のタイプの分け方には、様々な方法がある。
エニアグラム性格診断【無料/90問式】あなたは9タイプのどれ?
あなたは何系女子? 〇〇系女子診断! 2017/05/01
これらはすべて心理的・精神的なものであり、「内心の自由」として扱われるものである。
「性愛」の分類の話も、「内心の自由」として保障される分類方法の一つに過ぎないものである。
これらは法律論として区別して扱うことができるものではないし、これらを基にして法制度を立法することができるということにもならない。
そのため、個々人を取り上げる際に、個々人の抱く内心に踏み込む形で論じるようなことをしてはならない。
それにもかかわらず、ここで「異性愛者と同性愛者」のように取り上げていることは、人をその内心に基づいて区別するという思想の一つを公の機関が安易に受け入れて推進しようとしている状態となっており、極めて不適切である。
よって、人の内心を取り上げて区別して考えることが可能であることを前提として論じること自体が誤りである。
この論点について、当サイト「性別と思想」でも解説している。
「性的指向は生来備わる性向であり、社会的には異性愛者と同性愛者それぞれの取扱いを変える本質的な理由がないといえ、」とある。
「社会的には」との部分であるが、「社会」の中の私的な団体においては、個々人が「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかによって人を区別しようとする思想の下に、連絡を取り合ったり、集会をしたり、人的結合関係を形成、維持、解消するなどする場合がある。
これは、政党A、政党B、政党C、政党D、政党Eが、それぞれの思想や信条の下に連絡を取り合ったり、集会をしたり、人的結合関係を形成、維持、解消するなどしていることと同様である。
そのため、中には「性的指向」と称するものによってメンバーを集めたり、団体やグループを形成するなどしていることはあり得るのであり、「取扱いを変える本質的な理由がない」とはいえない。
よって、「社会的には異性愛者と同性愛者それぞれの取扱いを変える本質的な理由がない」と述べていることは誤りとなる。
これに対して、法的には、法制度は個人の内心に中立的な内容でなければならないことから、「異性愛者と同性愛者それぞれの取扱いを変える」ことはできない。
もし「性愛」を保護することを目的とした制度が存在した場合には、憲法20条1項・3項、89条の「政教分離原則」に違反するし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いをする制度が存在した場合には、憲法14条1項の「平等原則」に違反するし、「性愛」に基づいて制度を利用することを求めたり勧めたりする制度が存在した場合には、憲法19条の「思想良心の自由」に違反することになる。
また、法制度を適用する場面で、個々人の内心を審査して特定の思想、信条、信仰、感情を有する者に対して適用を否定することがあった場合には、憲法14条の「平等原則」における「法適用の平等」に違反することになる。
ここでは「異性愛者と同性愛者それぞれの取扱いを変え」ないことについて、「性的指向は生来備わる性向であ」ることが理由であるかのように述べているが、法的には、上記のように法制度は個人の内心に中立的な内容でなければならないことが理由であり、「性的指向は生来備わる性向であ」ることが理由となっているわけではない。
しかし、この判決は、「性的指向は生来備わる性向であ」ることを理由として、「異性愛者と同性愛者それぞれの取扱いを変える本質的な理由がない」と述べるものとなっている。
そのため、これは特定の「性愛」を保護することを目的とした制度が存在していたり、個々人が「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いをする制度が存在していたり、「性愛」に基づいて制度利用することを求めたり勧めたりする制度が存在しても許されるかのような前提で考えていることになる。
また、その特定の「性愛」を有する者を対象とした制度が存在することを前提に、「性的指向」と称するものによって「それぞれの取扱いを変える本質的な理由がない」と述べるものとなっている。
このような主張は、そもそも法制度は内心に対して中立的な内容でなければならず、特定の「性愛」を有する者を対象とした制度を設けることはできないという点で誤った主張である。
よって、「異性愛者と同性愛者それぞれの取扱いを変える本質的な理由がない」という部分の文面それ自体が法的に意味が通るとしても、その前提となっている法制度に対する認識が異なっていることにより、この論旨を正当化できるということにはならないことに注意が必要である。
(性的指向は生来備わる性向であり、)「その個人からみれば、人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の象徴であって、人格権の一内容を構成し得るものというべきである。」との部分について検討する。
この文は「謝罪広告等請求事件」と「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」が「氏名」についての「人格権」について述べている部分を参考としているようである。
下記の灰色で潰した部分が、この札幌高裁判決の文と重なる部分である。
謝罪広告等請求事件
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
氏名は、社会的にみれば、個人を他人から識別し特定する機能を有するものであるが、同時に、その個人からみれば、人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の象徴であつて、人格権の一内容を構成するものというべきであるから、人は、他人からその氏名を正確に呼称されることについて、不法行為法上の保護を受けうる人格的な利益を有するものというべきである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
謝罪広告等請求事件 最高裁判所第三小法廷 昭和63年2月16日 (PDF)
夫婦同姓制度訴訟大法廷判決
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2(1) 氏名は,社会的にみれば,個人を他人から識別し特定する機能を有するものであるが,同時に,その個人からみれば,人が個人として尊重される基礎であり,その個人の人格の象徴であって,人格権の一内容を構成するものというべきである(最高裁昭和58年(オ)第1311号同63年2月16日第三小法廷判決・民集42巻2号27頁参照)。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
損害賠償請求事件 最高裁判所大法廷 平成27年12月16日 (PDF)
ただ、「謝罪広告等請求事件」では論じられていないが、「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」では、その後に、この「氏名」としている「氏」の性質について、「法律がその具体的な内容を規律しているもの」であることを説明している。
夫婦同姓制度訴訟大法廷判決
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2(1) 氏名は,社会的にみれば,個人を他人から識別し特定する機能を有するものであるが,同時に,その個人からみれば,人が個人として尊重される基礎であり,その個人の人格の象徴であって,人格権の一内容を構成するものというべきである(最高裁昭和58年(オ)第1311号同63年2月16日第三小法廷判決・民集42巻2号27頁参照)。
(2) しかし,氏は,婚姻及び家族に関する法制度の一部として法律がその具体的な内容を規律しているものであるから,氏に関する上記人格権の内容も,憲法上一義的に捉えられるべきものではなく,憲法の趣旨を踏まえつつ定められる法制度をまって初めて具体的に捉えられるものである。
したがって,具体的な法制度を離れて,氏が変更されること自体を捉えて直ちに人格権を侵害し,違憲であるか否かを論ずることは相当ではない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
損害賠償請求事件 最高裁判所大法廷 平成27年12月16日 (PDF)
この札幌高裁判決では、「謝罪広告等請求事件」と「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」で示された「氏名」についての「人格権の一内容を構成するもの」という文面を用いる形で、「性的指向」について論じようと試みている。
しかし、「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」の事案については、「謝罪広告等請求事件」で取り上げるように、「氏名」については「人格権の一内容を構成するもの」として「人は、他人からその氏名を正確に呼称されることについて、不法行為法上の保護を受けうる人格的な利益を有する」ことが前提となるが、それとは異なって、「氏」の仕組みそのものを問うものであって、その「氏」の仕組みは「法律がその具体的な内容を規律しているもの」であることから「具体的な法制度を離れて,氏が変更されること自体を捉えて直ちに人格権を侵害し,違憲であるか否かを論ずることは相当ではない。」とし、結論としても「憲法上の権利として保障される人格権の一内容であるとはいえない。」と述べているものである。
これに対して、この札幌高裁判決で論じている「性的指向」とは、個々人が「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかに関わるものであり、その性質は個人の内心における心理的・精神的なものであることから、「国家からの自由」という「自由権」の性質のものであり、具体的な法制度の存在を前提とするものではない。
また、このような個人の内心については、「内心の自由」として憲法19条の「思想良心の自由」によって保障されるものであり、憲法13条に関わる「人格権」として捉えられるものではない。
そのため、そもそも「謝罪広告等請求事件」と「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」で論じられた「人格権」についての論点と、この札幌高裁判決で問われている事柄は、もともと性質が異なっている。
そのことから、「謝罪広告等請求事件」と「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」が国家によって定められる具体的な法制度の存在を前提とし、その法制度を基にして形成される「人格権」についての説明を行っているにもかかわらず、この札幌高裁判決が具体的な法制度の存在を前提としない個人の「内心の自由」として捉えられる「性的指向」と称するものを取り上げた上で、具体的な法制度の存在を前提とする形で論じられている「謝罪広告等請求事件」と「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」における「人格権」についての説明を用いて同様の論理の中に当てはめて考えることができるかのよう論じようと試みていることは誤りである。
よって、これらの性質の違いを無視して、この札幌高裁判決の中で、「謝罪広告等請求事件」と「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」を参照する形で同一の論じ方によって問題を処理することができるかのように考えていることは誤りである。
また、「性的指向」とは、「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかに関するものであり、個人の内心における心理的・精神的なものであることから、「内心の自由」として憲法19条の「思想良心の自由」として保障されるものであり、これについて、憲法13条の「人格権」と結び付けて論じていることも誤りである。
次に、「その個人からみれば、人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の象徴であって、人格権の一内容を構成し得るものというべきである。」との文は、「謝罪広告等請求事件」と「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」が「氏名」の性質について述べた文と同じくするものである。
灰色の部分が、この文と同じ文言である。
謝罪広告等請求事件
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
氏名は、社会的にみれば、個人を他人から識別し特定する機能を有するものであるが、同時に、その個人からみれば、人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の象徴であつて、人格権の一内容を構成するものというべきであるから、人は、他人からその氏名を正確に呼称されることについて、不法行為法上の保護を受けうる人格的な利益を有するものというべきである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
謝罪広告等請求事件 最高裁判所第三小法廷 昭和63年2月16日 (PDF)
夫婦同姓制度訴訟大法廷判決
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2(1) 氏名は,社会的にみれば,個人を他人から識別し特定する機能を有するものであるが,同時に,その個人からみれば,人が個人として尊重される基礎であり,その個人の人格の象徴であって,人格権の一内容を構成するものというべきである(最高裁昭和58年(オ)第1311号同63年2月16日第三小法廷判決・民集42巻2号27頁参照)。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
損害賠償請求事件 最高裁判所大法廷 平成27年12月16日(PDF)
しかし、「謝罪広告等請求事件」と「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」では、「氏名」の性質について、「個人からみれば」という「個人」から見た場合だけでなく、「社会的にみれば」という「社会的」に見た場合について検討しており、これらを「同時に、」の文言で繋ぎ、二つの意味を対比させる形で論じられている。
◇ 「社会的にみれば,個人を他人から識別し特定する機能を有するものであるが,」
◇ 「その個人からみれば,人が個人として尊重される基礎であり,その個人の人格の象徴であって,」
しかし、この札幌高裁判決では、「個人からみれば」の部分だけを抜き出し、「社会的にみれば」の部分を欠落させるものとなっている。
その代わりに、「社会的には異性愛者と同性愛者それぞれの取扱いを変える本質的な理由がないといえ、」の文言を加えているが、「謝罪広告等請求事件」と「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」の中で使われている「氏名」の性質について述べている文脈に対応するものであるとはいえない。
「謝罪広告等請求事件」と「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」では、「氏名」の性質について、「社会的に」見た場合と「個人から」見た場合を対比させる文脈として説明されている。
つまり、先に「社会的に」見た場合の「氏名」の性質を検討し、その後に「個人から」見た場合の「氏名」の性質について検討するものとなっている。
ここで注意したいのは、「個人から」見た場合の「氏名」の性質については、先に「社会的に」見た場合の「氏名」の性質である個人識別機能を前提として論じられていることである。
これは、「社会的に」見た場合に、「氏名」には個人識別機能があり、その個人識別機能の存在によって、全体の一部として扱われたり、他者との間で混同されたりすることはないという意味で、「人が個人として尊重される基礎」となっており、「その個人の人格の象徴」として機能するのように、「個人から」見た場合の説明に繋がっているのである。
(『象徴』とは、抽象的な観念を具体的な形象に託して表現することを意味する。つまり、ここではある人の人格を示す際に、本人の身体をそのまま取り上げるのではなく、氏名という形に置き換えて表現する機能を指していることになる。)
しかし、この札幌高裁判決は、「氏名」について説明する文脈の中で「社会的に」見た場合についての説明を切り落としていることから、その後の「個人から」見た場合について取り上げるとしても、それは個人識別機能についての説明を前提とするものとなっていない。
すると、個人識別機能とは異なる意味として、どのような意味で「性的指向」が「人が個人として尊重される基礎であり,その個人の人格の象徴」であるのか理解することが不可能であり、意味が通じないものとなっているのである。
そもそも、「性的指向」と称しているものは、「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかについて示すものであり、個人の内心における精神的なものであることから、「内心の自由」として憲法19条の「思想良心の自由」によって保障されるものであり、「個人として尊重される」こととは直接的に関係するものであるとはいえない。
また、「個人の人格」を示す際にその本人の身体をそのまま取り上げるのではなく別の簡易な形に置き換えて表現するという「象徴」としての機能を果たすものであるともいえない。
そのため、このような差し替えによって、この札幌高裁判決が抜き出している「個人から」見た場合についてのもともとの説明の意味をも改変させるものとなるため、誤った参照方法であるといえる。
よって、「性的指向」について、「人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の象徴であって、」と述べていることは意味が通じておらず、誤りということになる。
「その個人の人格の象徴であって、」との部分について、これは「パブリシティ権」に関わる意味で用いられることがあるが、ここでそのような意味とは違うことを述べている点は誤っている。
人格権 Wikipedia
パブリシティ権 Wikipedia
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4月23日の判決は「本件音声と原告の声色や語調はほぼ一致しており、本人と識別できる」と認定。人物特定ができる前提下で「声の権利」はAI音声にまで及ぶとの判断を示した。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
AI音声の無断使用は違法 中国初、人格権侵害を認定 2024年5月2日 (下線は筆者)
イ しかし、このように性的指向、さらには同性間の婚姻の自由が人格権の一内容を構成し得るとしても、同性愛者が婚姻という制度の適用を受けられるかどうかについて検討すると、婚姻の制度は、法制度の一部として法律がその具体的な内容を規律しているものであるから、性的指向及び同性間の婚姻の自由に係る人格権の内容は、憲法上一義的に捉えられるべきものではなく、憲法の趣旨を踏まえつつ定められている法制度との関係で初めて具体的に捉えられるものであると解すべきである(夫婦同姓制度訴訟大法廷判決参照)。
【筆者】
この文は、文尾で「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」を取り上げている。
そこで、「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」を確認すると、この文は「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」の「第2 上告理由のうち本件規定が憲法13条に違反する旨をいう部分について」の項目の「人格権」について説明している文面を参考とし、その議論に重ね合わせる形で説明しようと試みているようである。
(灰色で潰した部分が、上記の記述と文面が重なる部分である。)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2(1) 氏名は,社会的にみれば,個人を他人から識別し特定する機能を有するものであるが,同時に,その個人からみれば,人が個人として尊重される基礎であり,その個人の人格の象徴であって,人格権の一内容を構成するものというべきである(最高裁昭和58年(オ)第1311号同63年2月16日第三小法廷判決・民集42巻2号27頁参照)。
(2) しかし,氏は,婚姻及び家族に関する法制度の一部として法律がその具体的な内容を規律しているものであるから,氏に関する上記人格権の内容も,憲法上一義的に捉えられるべきものではなく,憲法の趣旨を踏まえつつ定められる法制度をまって初めて具体的に捉えられるものである。
したがって,具体的な法制度を離れて,氏が変更されること自体を捉えて直ちに人格権を侵害し,違憲であるか否かを論ずることは相当ではない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
損害賠償請求事件 最高裁判所大法廷 平成27年12月16日 (PDF)
しかし、この文は「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」における「人格権」について説明している部分の意味を適切に理解するものではなく、誤っている。
まず、この「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」の内容は、下記の段階を踏んで説明するものである。
◇ 「氏名」は、「人格権の一内容を構成するもの」
↓ ↓
◇ 「氏」は、「法律がその具体的な内容を規律しているもの」
↓ ↓
◇ 「氏に関する」「人格権の内容も,」「法制度をまって初めて具体的に捉えられるもの」
↓ ↓
◇ 「具体的な法制度を離れて,氏が変更されること自体を捉えて直ちに人格権を侵害し,違憲であるか否かを論ずることは相当ではない。」
これは、「氏名」は「人格権の一内容を構成する」としながらも、その「氏名」とは何か、「氏」とは何かという問題について遡って検討すると、「氏」は「法律がその具体的な内容を規律しているもの」であるから、「氏に関する上記人格権の内容」についても「法制度をまって初めて具体的に捉えられるもの」であり、「具体的な法制度を離れて,」論じることはできないという意味である。
これは、「氏名」が「人格権の一内容を構成する」という話を先に出し、その「氏名」における「氏」とは何かという前提に遡って検討するものとなっている。
この遡る形の説明が原因となって、その文面全体を理解することを難しくしている。
そのため、順序を入れ替えて説明すると、下記のようになる。
◇ 「氏は,」「法律がその具体的な内容を規律しているものである」
↓ ↓
◇ 「氏に関する」「人格権の内容」は「法制度をまって初めて具体的に捉えられるものである。」
↓ ↓
◇ 「氏名は,」「人格権の一内容を構成するものというべきである」
↓ ↓
◇ 「具体的な法制度を離れて,氏が変更されること自体を捉えて直ちに人格権を侵害し,違憲であるか否かを論ずることは相当ではない。」
このように順序を入れ替えて検討すると、読み取りやすくなる。
つまり、法律上の具体的な制度によって「氏」が定められており、その「氏」に関する「人格権」の内容も、その「氏」について定めた制度の仕組みを前提として形成されているものであることから、その制度の仕組みを離れて「氏」についての「人格権」を主張する基盤はないし、「氏」について定めた制度の仕組みそのものの変更を求めることができるという意味まで含む形で「氏」についての「人格権」を主張することができるという基盤はないということを説明しているものである。
簡単に言えば、「氏」について定めた法制度の予定する範囲でしか、「氏」についての「人格権」を主張する余地はないということである。
この「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」の構造を前提に、この札幌高裁判決が述べている文を読み解くと、その内容は整合性の乱れが生じており、意味が通じていない。
まず、「性的指向」について検討する。
◇ 「性的指向」は個人の内心における精神的なものであり、法制度により定められているものではない。
この時点で、既に「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」とは事案が異なっており、同様の論旨を採用できるとする前提にない。
↓ ↓
◇ 具体的な法制度が存在しないことから、具体的な法制度が存在することに基づいて論じられる「人格権」を捉える前提にない。
↓ ↓
◇ 「性的指向」は「内心の自由」として憲法19条の「思想良心の自由」により保障されるが、「人格権」として捉えられるものではない。
↓ ↓
◇ 憲法19条の「思想良心の自由」は「国家からの自由」という「自由権」の性質であり、これによって特定の制度の創設を国家に対して求めることはできない。
次に、「同性間の婚姻」についても検討する。
▼ 「同性間の婚姻」の意味が「同性間の人的結合関係」を形成することを指す場合
◇ 「同性間の婚姻」が「同性間の人的結合関係」を形成することを指すのであれば、憲法21条1項の「結社の自由」によって保障される。
これは、「国家からの自由」という「自由権」の性質であることから、具体的な法制度を前提とするものではない。
この時点で、既に「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」とは事案が異なっており、同様の論旨を採用できるとする前提にない。
↓ ↓
◇ 具体的な法制度が存在しないことから、具体的な法制度が存在することに基づいて論じられる「人格権」を捉える前提にない。
↓ ↓
◇ 「同性間の人的結合関係」を形成することは、憲法21条1項の「結社の自由」によって保障されるが、「人格権」として捉えられるものではない。
↓ ↓
◇ 憲法21条1項の「結社の自由」は「国家からの自由」という「自由権」の性質であり、これによって特定の制度の創設を国家に対して求めることはできない。
▼ 「同性間の婚姻」の意味が「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを指す場合
◇ 「同性間の婚姻」が「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを指すのであれば、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることができるかから検討する必要がある。
「婚姻」は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」を目的として、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす「一人の男性」と「一人の女性」の組み合わせに対して「貞操義務」を設けるなど一定の形式で法的に結び付け、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によってそれらの目的の達成を目指す枠組みである。
憲法24条はその「婚姻」について規定しており、「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めている。
これも、上記の趣旨に対応するものとして定められているものである。
そして、憲法24条の「婚姻」の枠組みの「要請」に従う形で法律上の婚姻制度が一夫一婦制(男女二人一組)で定められることになる。
これに対して、「同性間の人的結合関係」については、上記の趣旨に当てはまるものではないことから、「婚姻」の中に含めることはできない。
そして、「同性間の人的結合関係」については、それを「婚姻」とすることはできないことから、それについての具体的な法制度は存在していない。
この時点で、既に「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」とは事案が異なっており、同様の論旨を採用できるとする前提にない。
↓ ↓
◇ 具体的な法制度が存在しないことから、具体的な法制度が存在することに基づいて論じられる「人格権」を捉える前提にない。
このように、「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」で使われている文面を用いて説明しようとしても、そもそも「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」で問題となっている事柄とこの札幌高裁判決で問題となっている事柄は性質が異なっており、これに当てはめて論じることができるとする前提にないものである。
これを無理やり「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」の論じ方に当てはめて論じようとすることにより、この札幌高裁判決の内容は文面全体として意味の通ったものとして成立しておらず、法的な枠組みを整合的に理解することができる内容となっていない。
「このように性的指向、さらには同性間の婚姻の自由が人格権の一内容を構成し得るとしても、」との部分について検討する。
ここでは、「性的指向」と「同性間の婚姻の自由」という言葉が登場し、それが「人格権の一内容を構成し得る」という結論と結び付けられている。
しかし、これらが「人格権の一内容を構成し得る」といえるのかどうか、それぞれ詳しく検討する。
まず、「性的指向」が「人格権の一内容を構成し得る」と述べていることについて検討する。
「性的指向」とは、個々人が「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかについて示すものであることから、その性質は個人の内心における精神的なものである。
そのため、これは「内心の自由」として憲法19条の「思想良心の自由」により保障されるものである。
そのことから、「性的指向」と称している個人の内心における精神的なものを「人格権の一内容を構成し得る」のように「人格権」と結び付けて論じていることは妥当でない。
また、個人の内心における精神的なものについては、具体的な制度の存在を前提としているものではないことから、具体的な制度の存在を前提として論じている「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」を参照し、それと同様の論理で論じることができるかのように述べていることも妥当でない。
次に、「同性間の婚姻の自由が人格権の一内容を構成し得る」と述べている部分について検討する。
ここでいう「同性間の婚姻」の意味が問題となる。
この「同性間の婚姻」の意味が「同性間の人的結合関係」を形成することを指す場合と、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを指す場合とに分けて検討する。
まず、「同性間の婚姻」の意味が「同性間の人的結合関係」を指しているとすれば、「同性間の婚姻の自由」の意味は「同性間の人的結合関係」を形成する「自由」という意味となる。
これについては、「国家からの自由」という「自由権」の性質によって憲法21条1項の「結社の自由」として保障されるものである。
そのため、この文がそれについて「人格権の一内容を構成し得る」と述べて、「人格権」として検討しようとしていることは誤りである。
また、「同性間の人的結合関係」を形成する「自由」については、「国家からの自由」という「自由権」の性質であることから、これは具体的な法制度の存在を前提とするものではない。
よって、これについて、具体的な法制度の存在を前提とする「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」の議論と対応するものであるかのように論じていることも誤りである。
次に、「同性間の婚姻」の意味が「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを指しているとすれば、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることができるかという部分から検討することが必要である。
「婚姻」は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた枠組みである。
具体的には、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」を目的として、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす形で、その間で自然生殖を想定することができる「一人の男性」と「一人の女性」を選び出し、その間に「貞操義務」を設けるなど一定の形式で法的に結び付け、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によってそれらの目的の達成を目指すものとして形成されている。
「婚姻」は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために設けられた枠組みであり、この機能を果たすことが求められていることから、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たさない人的結合関係については「婚姻」の中に含めることはできないという内在的な限界がある。
「同性間の人的結合関係」については、その間で「生殖」を観念することができず、この「生殖と子の養育」の趣旨を満たすものではないため、「婚姻」の中に含めることはできない。
よって、「同性間の婚姻」と述べている部分は、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることができないことから、法的な意味として成立しないものである。
その後の「婚姻の自由」と述べている部分だけを見ると、これは「再婚禁止期間制度訴訟大法廷判決」が示した「婚姻をするについての自由」について述べるものと考えられる。
ただ、「再婚禁止期間制度訴訟大法廷判決」の内容は、上記のような意味で「婚姻」そのものが「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた枠組みであり、その内容も「男女二人一組」を対象とするものであることが前提である。
そのため、そこで述べられた「婚姻をするについての自由」と述べているものについても、このような「男女二人一組」を対象としている婚姻制度を利用するか否かについての「自由」について述べられているものであり、この「婚姻をするについての自由」には「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを求めることができるという意味は含まれていない。
よって、「同性間の婚姻の自由」のように、これを一続きに述べたとしても、「婚姻」そのものによって「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることができることにはならないし、ここでいう「自由」についても、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として定められている「婚姻」という枠組みを利用するか否かに関する「自由」をいうものであることから、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」の中に含めることを国家に対して求めることができるという意味を有するものではない。
その他、「人格権の一内容を構成し得る」と述べている部分は、「謝罪広告等請求事件」や「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」で「氏名」について、「人格権の一内容を構成するものというべきである」と述べている部分と重ねる形で論じようとするものである。
謝罪広告等請求事件
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
氏名は、社会的にみれば、個人を他人から識別し特定する機能を有するものであるが、同時に、その個人からみれば、人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の象徴であつて、人格権の一内容を構成するものというべきであるから、人は、他人からその氏名を正確に呼称されることについて、不法行為法上の保護を受けうる人格的な利益を有するものというべきである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
謝罪広告等請求事件 最高裁判所第三小法廷 昭和63年2月16日 (PDF)
夫婦同姓制度訴訟大法廷判決
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2(1) 氏名は,社会的にみれば,個人を他人から識別し特定する機能を有するものであるが,同時に,その個人からみれば,人が個人として尊重される基礎であり,その個人の人格の象徴であって,人格権の一内容を構成するものというべきである(最高裁昭和58年(オ)第1311号同63年2月16日第三小法廷判決・民集42巻2号27頁参照)。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
損害賠償請求事件 最高裁判所大法廷 平成27年12月16日 (PDF)
しかし、「謝罪広告等請求事件」や「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」において、「人格権の一内容を構成するもの」と述べている理由は、「氏名」の性質が、「個人を他人から識別し特定する機能を有する」ものであり、また、その機能によって「人が個人として尊重される基礎」となり「その個人の人格の象徴」となるからである。
これに対して、「性的指向」と称するものは、個人の内心における精神的なものであることから、「内心の自由」として憲法19条の「思想良心の自由」によって保障されるものではあるが、個人を他者との間で識別する機能を有しているわけではないことから、「謝罪広告等請求事件」や「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」で述べられているような意味の「人格権」に対応するものではない。
また、「謝罪広告等請求事件」や「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」において、「人格権の一内容を構成するもの」と述べている部分は、「氏名」についての具体的な法制度の存在を前提として論じているものであるが、この札幌高裁判決の述べている「性的指向」と称するものについては、個人の内心における精神的なものであり、具体的な法制度の存在を前提とするものではない。
この点でも、「謝罪広告等請求事件」や「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」で述べられているような意味の「人格権」に対応するものではない。
また、この札幌高裁判決のいう「同性間の婚姻」についても、これが「同性間の人的結合関係」を形成することを意味するのであれば、それは「国家からの自由」という「自由権」の性質として憲法21条1項の「結社の自由」として保障されることから、具体的な法制度の存在を前提とするものではないし、これが「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを意味するのであれば、そもそも「婚姻」は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する形て設けられた制度であり、この「生殖と子の養育」の趣旨を満たさない「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることはできず、それを対象とした婚姻制度を立法することはできず、やはり具体的な法制度は存在していない。
そのため、この札幌高裁判決の事例では具体的な法制度が存在していないことから、「謝罪広告等請求事件」や「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」において「氏名」についての具体的な法制度が存在することを前提として「人格権」を論じている場合とは性質が異なっており、これを重ね合わせる形で「人格権」を論じることができるというものではない。
よって、これと重ね合わせて論じようとしていることは誤りということになる。
この文は、「このように」とこれ以前の文を受けて「人格権の一内容を構成し得る」という結論を導き出しているかのように示している。
しかし、これ以前に示された文面の中では、「性的指向」について一文前で「人格権の一内容を構成し得るものというべきである。」と述べているだけである。
そして、その文の内容や、その文よりも以前に書かれている文面を見ても、「性的指向」と称するものが「人格権の一内容を構成し得る」と結論付けるだけの説得的な根拠となるものは示されていない。
まして、これ以前に示された文面を見ても、「同性間の婚姻の自由」と称するものが「人格権の一内容を構成し得る」などとは一切示されていない。
そのため、「このように」と述べてこれ以前の部分を受ける形で論じていることは、文脈として意味が通じていない。
よって、これらを「人格権の一内容を構成し得る」と結論付けようとしている部分も正当化することはできない。
これらの論点について、国(行政府)の主張は、下記のように述べられている。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
しかしながら、被告第3準備書面第1の2(7ページ)で述べた通り、人は、一般に社会生活を送る中で、種々の、かつ多様な人的結合関係を生成しつつ、生きていくものであり、当該人的結合関係の構築、維持及び解消をめぐる様々な場面において幾多の自己決定を行っていくものと解されるが、そのような自己決定を故なく国家により妨げられているか否かということと、そのような自己決定の対象となる人的結合関係について国家の保護を求めることができるか否かということは、区別して検討されるべきものと解される。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【東京二次・第9回】被告第7準備書面 令和5年9月28日 PDF
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
しかしながら,人は,一般に,社会生活を送る中で,種々の かつ多様な人的結合関係を生成しつつ,生きていくものであり,当該人的結合関係の構築,維持及び解消をめぐる様々な場面において幾多の自己決定を行っていくものと解されるが,そのような自己決定を故なく国家により妨げられているか否かということと,そのような自己決定の対象となる人的結合関係について国家の保護を求めることができるか否かということとは,少なくとも憲法13条の解釈上は区別して検討されるべきものと解される。
前記2で述べたとおり,婚姻が一定の法制度を前提としている以上,「婚姻をするかどうか,いつ誰と婚姻をするか」を当事者間で自由に意思決定し,故なくこれを妨げられないという「婚姻をするについての自由」は,法制度を離れた生来的,自然権的な自由権として憲法で保障されているものと解することはできない。前記1で述べたとおり,憲法24条1項は,婚姻について異性間の人的結合関係のみを対象とし,同性間の人的結合関係を対象とすることを想定しておらず,同条2項も,飽くまで婚姻が異性間の人的結合関係のみを対象とするものであることを前提としてこれを具体化する制度の整備を立法府に要請するものであり,これを受けて定められた本件規定も,婚姻が異性間の人的結合関係のみを対象とするものであることを前提に定められている。
そうすると,原告らが「婚姻の自由」として主張するものの内実は,「両性」の本質的平等に立脚すべきことを規定する憲法24条2項の要請に従って創設された現行の婚姻制度の枠を超えて,同性間の人的結合関係についても婚姻と同様の積極的な保護や法的な利益の供与を認める法制度の創設を国家に対して求めるものにほかならないのであって,国家からの自由を本質とするものではないから,このような自由が憲法13条の幸福追求権の一内容を構成するものと解することはできない。
また,本件規定が同性婚を定めていないことは,同性間の人的結合関係について本件規定による特別の法的保護が与えられていないことを意味するにとどまり,これによって,同性間において婚姻類似の人的結合関係を構築して維持したり,共同生活を営んだりする自由が制約されるものではない。
なお,原告らは,要旨,婚姻をするかどうかの選択及び誰と婚姻するかの意思決定の自由(婚姻の自由)は憲法13条で保障されると解すべきであり,かつ,婚姻が重要であることはパートナーが同性である場合と異性である場合とで異ならないから,そのような意思決定の自由(婚姻の自由)は,婚姻相手が同性の場合も当然に含むものであると主張するが(原告第13準備書面14ないし17ページ),異性間の婚姻については既に法制度が存在し,その法制度の中で婚姻をするか否か及び誰と婚姻するかの選択が妨げられているかどうかが問題となる一方で,同性間の人的結合関係について婚姻に相当する法制度は存在しないのであるから,原告らの主張する同性間の人的結合関係における婚姻の自由は,上記のとおり,同性間の人的結合関係についても婚姻と同様の積極的な保護や法的な利益の供与を認める法制度の創設を求めるものと解されるのであって,これらは次元を異にする問題である。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【九州・第6回】被告第4準備書面 令和3年l0月29日 PDF
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
すなわち、異性間の婚姻については既に法制度が存在し、その法制度の中で婚姻をするか否か及び誰と婚姻するかの選択が妨げられているかどうかが問題となる一方で、同性間の人的結合関係についての婚姻に相当する法制度は存在しないのであるから、原告らの主張する同性間の人的結合関係における婚姻の自由は、上記のとおり、同性間の人的結合関係についても婚姻と同様の積極的な保護や法的な利益の供与を認める法制度の創設を求めるものと解されるのであって、これらは次元を異にする問題である。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【東京二次・第5回】被告第3準備書面 令和4年6月20日 PDF
「同性愛者が婚姻という制度の適用を受けられるかどうかについて検討すると、」との部分について検討する。
「同性愛者」とあるが、法律論としては、人を内心に基づいて分類しようとする一つの思想を持ち出して人を区別して考えることはできない。
そのため、人の内心における精神的なものを取り上げて分類し、その分類に基づいて区別して考えることが許されるかのように論じていることそのものが妥当でない。
それとは別に、婚姻制度は「性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いをする制度ではないし、「性愛」に基づいて制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもない。
そのことから、「同性愛者」を称する者であるとしても、婚姻制度(男女二人一組)の要件を満たして制度を利用する意思があるのであれば、適法に制度を利用することができる。
実際、「同性愛者」を称する者であるとしても、婚姻制度を利用している事実は認められる。
よって、「同性愛者が婚姻という制度の適用を受けられるかどうか」という問いに対する答えは、「適用を受けられる」といえる。
「婚姻の制度は、法制度の一部として法律がその具体的な内容を規律しているものであるから、性的指向及び同性間の婚姻の自由に係る人格権の内容は、憲法上一義的に捉えられるべきものではなく、憲法の趣旨を踏まえつつ定められている法制度との関係で初めて具体的に捉えられるものであると解すべきである」との部分について検討する。
この文は「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」の下記の部分と重なる形で表現されている。
灰色で潰した部分が、同一の文言である。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) しかし,氏は,婚姻及び家族に関する法制度の一部として法律がその具体的な内容を規律しているものであるから,氏に関する上記人格権の内容も,憲法上一義的に捉えられるべきものではなく,憲法の趣旨を踏まえつつ定められる法制度をまって初めて具体的に捉えられるものである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
損害賠償請求事件 最高裁判所大法廷 平成27年12月16日(PDF)
しかし、「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」の中で「氏は,婚姻及び家族に関する法制度の一部として」と書かれている部分が、この札幌高裁判決では「婚姻の制度は、法制度の一部として」に変えられている。
この変更により、「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」の意図する文面から意味の性質が変わっており、同一の論旨として対応関係にあるものと見ることができないものに変わってしまっている。
具体的には、下記の通りである。
「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」では「氏」について論じていることから、その「氏」について定めた規定について「氏は,婚姻及び家族に関する法制度の一部として法律がその具体的な内容を規律している」と述べるものである。
「婚姻及び家族に関する法制度」
↓ (一部)
「氏」 (法律がその具体的な内容を規律している)
これに対して、この札幌高裁判決では、「婚姻の制度は、法制度の一部として」に変わっており、「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」の示している枠組みとは大幅に次元が異なるものとなっている。
「法制度」
↓ (一部)
「婚姻の制度」 (法律がその具体的な内容を規律している)
ここでいう「法制度」は、いかなる範囲の「法制度」であるのか特定されておらず、日本法のすべての「法制度」を対象として論じるものと考えてよいのかもよく分からない。
「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」では、下記のように述べている。
◇ 「氏は,婚姻及び家族に関する法制度の一部として法律がその具体的な内容を規律しているものであるから,」
◇ 「氏に関する上記人格権の内容も,憲法上一義的に捉えられるべきものではなく,……(略)……」
ここでは下線部のように、どちらの部分も「氏」が主題となっている。
これに対して、この札幌高裁判決では「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」で初めの「氏は,」となっていたところを「婚姻の制度は、」に変えているが、次の「氏に」のところを「性的指向及び同性間の婚姻の自由に」に変えている。
◇ 「婚姻の制度は、法制度の一部として法律がその具体的な内容を規律しているものであるから、」
◇ 「性的指向及び同性間の婚姻の自由に係る人格権の内容は、憲法上一義的に捉えられるべきものではなく、……(略)……」
ここでは「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」を参照していることを示しているのであるから、通常は、「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」において「氏は,」としている部分を「婚姻の制度は、」に変えて論じようとするのであれば、「氏に」としている部分も同様の形で「婚姻の制度に」と変えることによって、「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」の内容と対応するものとして論じていることを明らかにするはずである。
しかし、ここではそのような形で論じておらず、変則的な改変が行われており、もともとの文面においては文言や意味が対応していた部分の構造まで変えるものとなっている。
これにより、「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」を引用して論じようとする趣旨からも逸脱するものとなっており、また、文面の意味も整合的に理解することができないものとなっている。
他にも、「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」では「氏」という「法律がその具体的な内容を規律しているもの」について論じていることに対して、この札幌高裁判決では「性的指向」という個人の内心における精神的なものを取り上げており、これは法律上の要件として定められているものではない。
また、この札幌高裁判決の「同性間の婚姻」と称してる部分についても、「同性間の人的結合関係」を対象とした具体的な法制度が存在しているわけではないことから、やはり法律上の具体的な制度について論じているものでもない。
そのため、「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」で論じられている内容に重ねる形で「人格権」について論じることができるとする前提になく、この札幌高裁判決の事案を「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」に当てはめて論じようとしていることそのものが誤りである。
「性的指向及び同性間の婚姻の自由に係る人格権の内容は、」との部分について検討する。
「性的指向」とは、「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかに関わるものであり、個人の内心における精神的なものである。
そのため、「内心の自由」として憲法19条の「思想良心の自由」によって保障されるものである。
よって、これについて「人格権」として説明していることは誤りである。
「同性間の婚姻」の意味が「同性間の人的結合関係」を形成することを指すのであれば、それは憲法21条1項の「結社の自由」によって保障されるものである。
よって、これを「人格権」と「係る」かのように述べていることは誤りである。
「同性間の婚姻」の意味が「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを指すのであれば、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」の中に含めることができるかから検討することが必要である。
「婚姻」は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた枠組みである。
具体的には、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」を目的として、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす「一人の男性」と「一人の女性」の組み合わせを選び出し、その間に「貞操義務」を設けるなど一定の形式で法的に結び付け、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によってそれらの目的の達成を目指すものである。
「同性間の人的結合関係」については、この趣旨を満たすものではないことから、「婚姻」の中に含めることはできない。
そのため、ここで「同性間の婚姻」と述べている部分は、法的には成立しないものである。
よって、これが「人格権」と「係る」と考えることはできない。
その後の「婚姻の自由」と述べている部分だけを見ると、これは「再婚禁止期間大法廷判決(平成27年12月16日)」が示した「婚姻をするについての自由」について述べるものと考えられる。
しかし、その「再婚禁止期間大法廷判決」では、「婚姻をするについての自由」について憲法24条1項の解釈として導かれているものであり、「人格権」として論じられているものではない。
よって、この「婚姻の自由」(婚姻をするについての自由)が「人格権」と「係る」かのように考えることは妥当でない。
また、その「再婚禁止期間大法廷判決」の内容は、上記で解説したように「婚姻」そのものが「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた枠組みであり、その内容も「男女二人一組」を対象とするものであることが前提となっている。
そのため、そこで述べられた「婚姻をするについての自由」と述べているものについても、このような「男女二人一組」を対象としている婚姻制度を利用するか否かについての「自由」について述べているものである。
この「婚姻をするについての自由」の中に「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを求めることができるという意味は含まれていない。
そのため、ここで「同性間の婚姻の自由」のように、これを一続きに述べたとしても、「婚姻」そのものによって「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることができることにはならないし、ここでいう「自由」についても、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として定められている「婚姻」という枠組みを利用するか否かに関する「自由」をいうものであることから、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」の中に含めることを国家に対して求めることができるという意味を有するものではない。
最高裁判決の示した「婚姻をするについての自由」について、国(行政府)は下記のように述べている。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
すなわち、およそ人同士がどうつながりを持って暮らし、生きていくかは、当人らが自由に決めて然るべき事柄であり、このような自由自体は異性間であっても同性間であっても、等しく憲法13条において尊重されるべきものと解されるが、前記3で述べたとおり、婚姻が一定の法制度を前提としている以上、「婚姻をするかどうか、いつ誰と婚姻をするか」を当事者間で自由に意思決定し、故なくこれを妨げられないという意味における「婚姻をするについての自由」は、憲法の定める婚姻を具体化する法律(本件諸規定)に基づく制度によって初めて個人に与えられる、あるいはそれを前提とした自由であり、生来的、自然権的な権利又は利益、人が当然に享受すべき権利又は利益ということはできない。このように、婚姻をすることについての自由は、法制度を離れた生来的、自然権的な権利又は利益として憲法で保障されているものではないというべきである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【九州・第1回】被控訴人(被告)答弁書 令和6年1月31日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
もっとも、婚姻及び家族に関する事項については、前記2(1)のとおり、憲法24条2項に基づき、法律によって具体的な内容を規律するものとされているから、婚姻及び家族に関する権利利益等の内容は、憲法上一義的に捉えられるべきものではなく、憲法の趣旨を踏まえつつ、法律によって定められる制度に基づき初めて具体的に捉えられるものである。そうすると、婚姻の法的効果(例えば、民法の規定に基づく、夫婦財産制、同居・協力・扶助の義務、財産分与、相続、離婚の制限、嫡出推定に基づく親子関係の発生、姻族の発生、戸籍法の規定に基づく公証等)を享受する利益や、「婚姻をするかどうか、いつ誰と婚姻をするか」を当事者間で自由に意思決定し、故なくこれを妨げられないという婚姻をすることについての自由は、憲法の定める婚姻を具体化する法律(本件諸規定)に基づく制度によって初めて個人に与えられる、あるいはそれを前提とした自由であり、生来的、自然権的な権利又は利益、人が当然に享受すべき権利又は利益ということはできない。このように、婚姻の法的効果を享受する利益や婚姻をすることについての自由は、法制度を離れた生来的、自然権的な権利又は利益として憲法で保障されているものではないというべきである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【九州・第1回】被控訴人(被告)答弁書 令和6年1月31日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
まず、被控訴人原審第6準備書面第3の1(2)(19・及び20ページ)並びに控訴答弁書第2の2(10及び11ページ)で述べたとおり、控訴人らが、本件諸規定が法律上同性のカップルを「排除」しているとする前提として主張する「婚姻の自由」の内実は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきことを規定する憲法24条2項の要請に従って創設された現行の婚姻制度の枠を超えて、同性間の人的結合関係についても婚姻と同様の積極的な保護や法的な利益の供与を認める法制度の創設を国家に対して求めるものにほかならないのであって、国家からの自由を本質とするものとい うこともできないものである。したがって、本件事案の本質的な問題は、現行の婚姻制度に加えて同性間の婚姻を認める法制度を創設しないことの憲法適合性であり、同性間の人的結合関係につき控訴人らがいうところの「婚姻の自由」が保障されていることを前提に、本件諸規定から同性愛者等を排除していることの憲法適合性を問題とする控訴人らの視点は誤りである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【東京一次・第3回】被控訴人第2準備書面 令和6年2月29日
よって、「性的指向及び同性間の婚姻の自由」と称するものに「人格権」が「係る」かのように述べていることは誤りである。
「憲法上一義的に捉えられるべきものではなく、憲法の趣旨を踏まえつつ定められている法制度との関係で初めて具体的に捉えられるものであると解すべきである」とある。
しかし、上記でも述べたように、この判決のいう「性的指向及び同性間の婚姻の自由」と称しているものについては、具体的な法制度が存在しておらず、法律上の要件として定められているものではないことから、「法制度との関係で初めて具体的に捉えられるもの」であると論じる前提を欠くものである。
よって、具体的な法制度の存在を前提として論じている「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」の文面に当てはめる形で論じようとしていることは誤りである。
「憲法上一義的に捉えられるべきものではなく、」とある。
これについて、「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」では「氏」について問われていたことから、この「氏」について憲法上で具体的に指定している文言は存在しないため、「憲法上一義的に捉えられるべきものではなく、」といえるものであった。
しかし、この札幌高裁判決では、この「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」の「氏は,」の部分を「婚姻の制度は、」に変えており、「婚姻の制度」を問うものとなっている。
そうなると、憲法上では24条で「婚姻」について定めており、具体的に「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)の枠組みを指定していることから、「憲法上一義的に捉えられる」ものであるということができる。
そのため、「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」の「氏は,」の部分を「婚姻の制度は、」に変えているにもかかわらず、その「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」で述べている「憲法上一義的に捉えられるべきものではなく、」の部分をそのまま用いることができると考えて、「婚姻の制度」についてまで「憲法上一義的に捉えられる」ものではないかのように述べていることは誤りである。
したがって、具体的な法制度を離れて、同性間で婚姻することができないこと自体を捉えて直ちに人格権を侵害し、違憲であるか否かを論ずることは相当ではない。
【筆者】
この文は、一段落前の文の最後に「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」が取り上げられていることに続いて、同じように「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」の文に重ね合わせる形で論じようと試みるものとなっている。
下記の、灰色で塗りつぶした部分が、この文と同様の文言が使われている部分である。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2(1) 氏名は,社会的にみれば,個人を他人から識別し特定する機能を有するものであるが,同時に,その個人からみれば,人が個人として尊重される基礎であり,その個人の人格の象徴であって,人格権の一内容を構成するものというべきである(最高裁昭和58年(オ)第1311号同63年2月16日第三小法廷判決・民集42巻2号27頁参照)。
(2) しかし,氏は,婚姻及び家族に関する法制度の一部として法律がその具体的な内容を規律しているものであるから,氏に関する上記人格権の内容も,憲法上一義的に捉えられるべきものではなく,憲法の趣旨を踏まえつつ定められる法制度をまって初めて具体的に捉えられるものである。
したがって,具体的な法制度を離れて,氏が変更されること自体を捉えて直ちに人格権を侵害し,違憲であるか否かを論ずることは相当ではない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
損害賠償請求事件 最高裁判所大法廷 平成27年12月16日(PDF)
しかし、この「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」で論じられているのは、上記にあるようにその判決の中で参照されている「謝罪広告等請求事件」の中で、「氏名は、」「人格権の一内容を構成するもの」であるから「人は、他人からその氏名を正確に呼称されることについて、不法行為法上の保護を受けうる人格的な利益を有する」と判断したが、この「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」の事案ではそれとは異なり、「氏は,」そのものは「法律がその具体的な内容を規律しているものである」ため「具体的な法制度を離れて,氏が変更されること自体を捉えて直ちに人格権を侵害し,違憲であるか否かを論ずることは相当ではない。」とし、結論としても「憲法上の権利として保障される人格権の一内容であるとはいえない。」としているものである。
◇ 謝罪広告等請求事件(昭和63年2月16日)
「氏名は、」「人格権の一内容を構成するもの」
↓ ↓
「人は、他人からその氏名を正確に呼称されることについて、不法行為法上の保護を受けうる人格的な利益を有する」
◇ 夫婦同姓制度訴訟大法廷判決
「氏名は、」「人格権の一内容を構成するもの」
↓ ↓
「氏は,」「法律がその具体的な内容を規律しているもの」
↓ ↓
「具体的な法制度を離れて,氏が変更されること自体を捉えて直ちに人格権を侵害し,違憲であるか否かを論ずることは相当ではない。」
↓ ↓
「憲法上の権利として保障される人格権の一内容であるとはいえない。」
この両者は、「氏名は、」「人格権の一内容を構成するもの」という部分は同じであるが、一方は「その氏名を正確に呼称されること」についての「人格的な利益」を認めるものであるが、もう一方はそもそも「氏」を定めている「具体的な法制度」の仕組みに遡り、「氏が変更されること自体」については、「憲法上の権利として保障される人格権の一内容であるとはいえない。」としているものである。
ただ、この両者は、「氏名」の制度という「具体的な法制度」の存在を前提として論じられているものである。
そして、この札幌高裁判決では、「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」の文面を取り上げて、それと重ね合わせる形で文章を作成している。
◇ 夫婦同姓制度訴訟大法廷判決
「したがって,具体的な法制度を離れて,氏が変更されること自体を捉えて直ちに人格権を侵害し,違憲であるか否かを論ずることは相当ではない。」
◇ 札幌高裁判決
「したがって、具体的な法制度を離れて、同性間で婚姻することができないこと自体を捉えて直ちに人格権を侵害し、違憲であるか否かを論ずることは相当ではない。」
しかし、この両者では、前提となっている事情が異なっており、これらを同一視して論じることができるものではない。
まず、「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」については、「氏」についての「具体的な制度」が存在している事例である。
「具体的な法制度を離れて,氏が変更されること自体を捉えて直ちに」憲法上で保障される権利としての「人格権を侵害し,違憲であるか否かを論ずることは相当ではない。」と述べているのは、この後に、前提として示した「謝罪広告等請求事件」とは異なる展開で論じることを事前に明らかにするためである。
そして、その「具体的な制度」である「氏」についての仕組みを検討し、「氏が,」「身分関係の変動に伴って改められることがあり得ることは,その性質上予定されている」ことから、「氏が変更されること自体」について「憲法上の権利として保障される人格権の一内容であるとはいえない。」としているものである。
これは、「具体的な制度」が存在することを前提とし、その「具体的な制度」の仕組みを検討した結果、「氏が変更されること自体」について「憲法上の権利として保障される人格権の一内容であるとはいえない。」と結論付けるものである。
これに対して、この札幌高裁判決では「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」の文の中で「氏が変更されること自体」と書かれている部分を、「同性間で婚姻することができないこと自体」の文言に置き換えて論じるものとなっているが、そもそも「同性間で婚姻すること」については「具体的な制度」は存在していない。
そのため、ここでは「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」の文面と重ね合わせる形で、「したがって、具体的な法制度を離れて、」と述べているのであるが、そもそも「同性間で婚姻すること」についての「具体的な法制度」が存在しないことから、「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」の事案と重ね合わせて論じることのできる前提にないものである。
ウ そこで、異性婚を定め、同性婚を許していない本件規定について検討すると、本件規定は、憲法24条により婚姻の制度として定められているが、従来、憲法24条は異性間の婚姻を定めたものと解されてきた。したがって、本件規定は、憲法24条の考え方を踏まえ、婚姻及び家族に関する法制度の一部としてその具体的な内容を定めたものであって、異性間の婚姻については、違憲の問題は生じない。
【筆者】
━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━
まず、この段落の文章が読み取りづらい理由から検討する。
◇ 第一文は、「そこで、」という接続詞を用いて一段落前の「具体的な法制度を離れて、」「論ずることは相当ではない。」との結論を受けるものとなっている。
これを前提として、この文は「本件規定について検討すると、」のように「本件規定」について検討することを述べている。
しかし、この文は始めに「本件規定について検討すると、」と述べているにもかかわらず、その後の結論では「従来、憲法24条は異性間の婚姻を定めたものと解されてきた。」と述べている。
これは、「本件規定」ではなく「憲法24条」について説明するものに変わってしまっているのである。
そのため、「本件規定について検討する」という前提が維持されておらず、突然、話の主題が変わってしまっていることから、読み手は混乱するのである。
◇ 次の第二文では、「したがって、」という接続詞を使って第一文の内容を受けるものなっている。
そのため、一文前の「検討する」と述べた後に、具体的に検討している部分を受けて、この第二文ではその検討の結果となる結論について述べることになるはずである。
しかし、「したがって、」に続く文は、「憲法24条の考え方を踏まえ、婚姻及び家族に関する法制度の一部としてその具体的な内容を定めたものであって、」であり、一文前で検討している過程の部分を繰り返すものとなっており、結論について述べているものではない。
この点が、読み手を混乱させる原因となっている。
そして、その後「異性間の婚姻については、違憲の問題は生じない。」という結論を述べることになる。
そのため、この段落は、「したがって、」の接続詞を述べた後に、前の文で触れている内容に重なることを繰り返している点で、読み手の素直な期待に沿う文面となっておらず、読み取りにくく感じるものとなっている。
・ 通常の文章
「検討する」→「検討過程」→「【したがって、】⇒結論」
・ この文章
「検討する」→「検討過程」→「【したがって、】⇒(検討過程)→結論」
━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━
「そこで、異性婚を定め、同性婚を許していない本件規定について検討すると、本件規定は、憲法24条により婚姻の制度として定められているが、従来、憲法24条は異性間の婚姻を定めたものと解されてきた。」との記載がある。
「異性婚を定め、同性婚を許していない」との部分について検討する。
「異性婚」や「同性婚」とあるが、これは法律用語ではなく、法律論としてこの言葉を使うことには問題がある。
もし「~~婚」と名付けるだけで、それを「婚姻」とすることができるとすれば、「親子婚」「兄弟婚」「姉妹婚」「親戚婚」「師弟婚」「集団婚」「家族婚」「子供婚」「クラス婚」「サークル婚」「宗教団体婚」「組合婚」「会社婚」「政党婚」「不動産婚」「独り者婚」などと、どのような形でも「婚姻」とすることができることになってしまう。
このような考えは妥当でない。
そのため、「婚」を付けるだけで何でも「婚姻」とすることができるということにはならない。
仮に「~~婚」という言葉を用いたとしても、その「~~婚」という言葉は、「~~」の部分を法的な意味における「婚姻」として扱うことができるとする根拠を示すものではないことから、そもそも「~~」の部分について、法的な意味における「婚姻」とすることができるか否かという論点を回避することはできない。
よって、「~~婚」という表現を用いたとしても、常にその「婚」の意味である「婚姻」とは何か、「婚姻」のそのものがどのような枠組みであるかという部分が問われることになる。
そして、「婚姻」そのものが有する内在的な限界を超えるものについては、たとえ「~~婚」という表現を用いたとしても、それを法的に「婚姻」として扱うことができるということにはならない。
そして、「婚姻」とは、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた枠組みである。
具体的には、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」を目的として、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす「一人の男性」と「一人の女性」の組み合わせを選び出し、その間に「貞操義務」を設けるなど一定の形式で法的に結び付け、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によってそれらの立法目的の達成を目指すものとなっている。
そのため、ここでいう「異性婚」の部分について、「異性」間の人的結合関係は「婚姻」の対象となっているということができる。
しかし、そもそも「婚姻」は、様々な人的結合関係の中から産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる関係を選び出して形成されている枠組みであり、「婚姻」であればそれは「男性」と「女性」の両方が揃う関係しか存在しないことから、その「男性」と「女性」の組み合わせによって形成される概念に対してさらに「異性」を加えて「異性婚」と表現することは同義反復となるため適切な表現であるとはいえない。
ここでいう「同性婚」の部分について、「同性間の人的結合関係」はその間で「生殖」を想定することができないことから、上記の「生殖と子の養育」の趣旨を満たすものではなく、「婚姻」の中に含めることはできない。
そのため、「同性婚」という語感は、あたかも「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることができるかのような前提で論じるものとなっているが、法的な意味の「婚姻」の中に「同性間の人的結合関係」を含めることはできないことから、法律論としては「同性婚」という言葉は成立しないことになる。
このため、「異性婚」や「同性婚」という言葉には問題があり、裁判所が判決の中で法律論として厳密に論じることが求められている中では、「~~婚」という表現を用いることは適切ではない。
「同性婚を許していない本件規定」との表現について検討する。
まず、この「同性婚」の意味が「同性間の人的結合関係」を形成することを指している場合について検討する。
「同性間の人的結合関係」を形成することについては、「国家からの自由」という「自由権」の性質として憲法21条1項の「結社の自由」によって保障されるものである。
また、その「同性間の人的結合関係」を形成することについて、それが法的な規制の対象となっているという事実はないし、「本件規定」もそれを規制するものではないため、それについて「許されていない」と理解していることは誤りである。
次に、この「同性婚」の意味が「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを指している場合について検討する。
「本件規定」は、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを定めていないということができる。
ただ、これは法制度が定められているか否かの問題であることから、むやみに「許していない」のように「許す・許さない」という意味の表現を用いることは適切であるとは思われない。
これは、ある個人が特定の法制度を利用しようと考えた場合に、自己の望む形で法制度が定められていないことを理由として望み通りとならず、利用することを控えるという視点から、その者個人の受け止め方として「許していない」などと表現しているものを述べるものである。
しかし、法制度は政策的なものであり、何らかの立法目的を達成するための手段として定められているものであることから、それが自らの望む形で定められていないという場合は当然に起こり得ることである。
そのことを客観的な視点から捉える場合には、「許していない」という表現は適切であるとはいえない。
そのため、ある特定の形の法制度が定められていないことについて、敢えて「許していない」という表現を用いることは、別の個所の「不利益」などの文言と相まって、法制度の性質について客観的な視点から説明するものとはなっておらず、訴訟の当事者の一方の見方や意見、感じ方に与する形で論じるものとなっていることが考えられる。
裁判所は法制度の性質について客観的な視点から論じることが求められており、このような訴訟の当事者の一方が現在の法制度をどのように受け止めているかという主観的な立ち位置から見た場合の言葉遣いをそのまま受け入れ、客観性や中立性を欠く表現を用いていることは適切ではない。
「そこで、……(略)……本件規定について検討すると、」とある。
ここでは、「そこで、」とこれ以前に述べた内容を繋ぎ、それを「本件規定」と繋ぐものとして示そうとするものとなっている。
このことから、これ以前の部分で述べているものを確認すると、下記を述べているだけである。
◇ 「(2)ア」
「恋愛や性愛」、「性的指向」、「異性愛」、「同性愛」、「異性愛者」、「同性愛者」の性質
◇ 「(2)イ」
「性的指向、さらには同性間の婚姻の自由が人格権の一内容を構成し得る」が「具体的な法制度を離れて、同性間で婚姻することができないこと自体を捉えて直ちに人格権を侵害し、違憲であるか否かを論ずることは相当ではない。」
しかし、「本件規定」が定めている婚姻制度は、「性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかという「性的指向」と称するものによって区別取扱いをする制度ではないし、「性愛」に基づいて制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもない。
また、「(2)イ」の「同性間の婚姻」の意味が「同性間の人的結合関係」を形成することを指しているとすれば、憲法21条1項の「結社の自由」で保障され、これは「国家からの自由」という「自由権」の性質であることから「具体的な法制度」を前提とするものではない。
他にも、「(2)イ」の「同性間の婚姻」の意味が「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを指しているとすれば、そもそも「婚姻」は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた枠組みであり、この趣旨を満たさない「同性間の人的結合関係」を「婚姻」の中に含めることはできないし、「同性間の人的結合関係」について定めた「具体的な法制度」が別に存在しているわけでもない。
そのため、これらの話をこの文が「そこで、」と繋いで「本件規定」と関わるものとして「検討」しようと考えていることそのものが誤りである。
よって、「そこで、……(略)……本件規定について検討すると、」と述べていることは誤りである。
「本件規定は、憲法24条により婚姻の制度として定められているが、従来、憲法24条は異性間の婚姻を定めたものと解されてきた。」との部分について検討する。
「本件規定は、憲法24条により婚姻の制度として定められている」とあるが、これは「本件規定」が憲法24条の「要請」に従って法律上の「婚姻の制度」として定められていることを述べるものである。
「憲法24条」は「婚姻」を規定しており、「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて、一夫一婦制(男女二人一組)を定めている。
ここで「憲法24条は異性間の婚姻を定めたもの」と述べていることも、このことを指しているといえる。
そして、この「憲法24条」の「婚姻」の枠組みの「要請」に従って法律上の「婚姻の制度」が立法されることになるが、そこで「要請」されている「婚姻」とは、今示したように、一夫一婦制(男女二人一組)の枠組みである。
そのため、法律上の「婚姻の制度」の内容も、一夫一婦制(男女二人一組)で定められることとなる。
この文は、これについて述べているものといえる。
「従来、憲法24条は異性間の婚姻を定めたものと解されてきた。」とあるが、ここで「従来、」と述べて「解されてきた。」のように過去形で表現することにより、現在や将来は異なるかのような含みを持たせようとしているように見受けられる。
しかし、この考え方は妥当でない。
「婚姻」とは、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」を目的として、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす「一人の男性」と「一人の女性」を選び出し、その間に「貞操義務」を設けるなど一定の形式で法的に結び付け、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によってそれらの立法目的の達成を目指すものとして形成されている概念である。
「憲法24条」が「婚姻」について規定しており、「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めていることは、この仕組みに対応する意味のものである。
そして、この「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的が存在する限りは、「婚姻」という枠組みはその社会的な不都合を解消するための制度として機能することが求められており、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす一夫一婦制(男女二人一組)の枠組みは、「従来、」も、現在も、将来も、それが変わるということはない。
よって、この点の制度の根幹部分を維持する視点を持たないままに、「憲法24条は異性間の婚姻を定めたもの」という「男女二人一組」の枠そのものを、「従来、」のものと位置付けて、現在や将来は変わることがあるかのような前提を含む形で述べようとしているとすれば、誤った認識ということになる。
ここで「異性間の婚姻」という文言があるが、これはあたかも「異性間」の「婚姻」と、それ以外の「婚姻」が存在するかのような言葉遣いとなっており、正しい説明であるとは言い難い。
まず、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」を目的として、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす「一人の男性」と「一人の女性」を選び出し、その間に「貞操義務」を設けるなど一定の形式で法的に結び付け、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によってそれらの目的の達成を目指す概念を「婚姻」と呼んでいる。
憲法24条が「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めていることについても、すべてこの意味に対応するものとして用いられている。
そのため、「婚姻」であることそれ自体において、「男性」と「女性」の組み合わせしか存在しないのであり、ここで述べているような「憲法24条は異性間の婚姻を定めたものと解されてきた。」どころか、「婚姻」であれば、それはそもそも「異性間」について述べるものということである。
このことから、「異性間の婚姻」という言葉は、「異性間」という「男性」と「女性」を指す言葉と、「婚姻」という「男性」と「女性」の組み合わせを指す概念とを同時に用いるものとなっており、文法上は「同義反復」(同語反復/トートロジー)となるため誤用ということになる。
また、「同義反復」となることを無視して、この判決のように「異性間の婚姻」という言葉を使ったとしても、「婚姻」であることそれ自体で既に「男性」と「女性」の組み合わせによる「異性間」しか存在しないのであり、それに対する形で「同性間の婚姻」というものが存在することにはならない。
そのため、「異性間の婚姻」という言葉に対する形で、それ以外の「婚姻」というものが成立するという余地はない。
よって、「男性」と「女性」の組み合わせを備えない形で「婚姻」という概念は成立し得ないのであり、その「婚姻」という言葉だけを刈り取ってその概念が形成されている目的から切り離して考えて「婚姻」という空の箱(言葉の意味から切り離された『音の響き』に過ぎないもの)の中に何らかの人的結合関係を詰め込むことができるという性質のものではない。
◇ 本来の意味
「男性」と「女性」の組み合わせ ⇒ 法的に結び付ける形を「婚姻」とする
◇ この判決の言葉の使い方
「婚姻」は空箱 ⇒ どのような人的結合関係でも詰め込むことができる
そのことから、「異性間の婚姻」のように、「婚姻」という概念そのものを、その概念が形成されている目的との間で切り離して、どのような意味としてでも用いることができるような前提を含む形で論じることは、言葉の表現として適切であるとはいえない。
「本件規定は、憲法24条の考え方を踏まえ、婚姻及び家族に関する法制度の一部としてその具体的な内容を定めたものであって、異性間の婚姻については、違憲の問題は生じない。」との記載がある。
この「法制度の一部として」との表現は、上記「(2)イ」の第一段落で述べられている「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」を参照するものとして、その「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」の「氏は,婚姻及び家族に関する法制度の一部として」と述べている部分を「婚姻の制度は、法制度の一部として」と述べている部分の「法制度の一部として」から用いようとしているように見受けられる。
◇ 夫婦同姓制度訴訟大法廷判決
「氏は,婚姻及び家族に関する法制度の一部として法律がその具体的な内容を規律しているものであるから,」
◇ 「(2)イ」
「婚姻の制度は、法制度の一部として法律がその具体的な内容を規律しているものであるから、」
◇ この部分
「婚姻及び家族に関する法制度の一部としてその具体的な内容を定めたものであって、」
しかし、その「(2)イ」の部分では、「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」で「氏は,」と述べている部分を、「婚姻の制度は、」に変えていることは、「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」が「婚姻及び家族に関する法制度の一部」である「氏」について述べている文を「婚姻及び家族に関する法制度の一部」ではなく、「婚姻の制度」そのものを論じるものに意味を変えてしまうものとなっている。
このような「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」の意図する文面の射程そのものを変更する形で論じていることは、文面に同一の言葉が使われているとしても、実質的には「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」を参照する形で論じているのものではなく、まったく別の文を創作しているものと見るべきものである。
そのため、このような新たな文面を創作したものについて、「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」を参照しているかのように示すことは不正な手続きである。
そのことから、その不正な手続きを前提としている「(2)イ」の部分を引き継ぐものとして、ここで同様に「法制度の一部として」と述べているのであれば、この部分も「(2)イ」の部分と同様に誤っていることになる。
また、ここでは「(2)イ」が単に「法制度」と述べていることとは異なり、「婚姻及び家族に関する法制度」と述べていることは、「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」が「婚姻及び家族に関する法制度」と述べていることと同じである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) しかし,氏は,婚姻及び家族に関する法制度の一部として法律がその具体的な内容を規律しているものであるから,氏に関する上記人格権の内容も,憲法上一義的に捉えられるべきものではなく,憲法の趣旨を踏まえつつ定められる法制度をまって初めて具体的に捉えられるものである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
損害賠償請求事件 最高裁判所大法廷 平成27年12月16日 (PDF)
そのため、ここで述べていることは「(2)イ」よりも、「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」の文面を前提とするものとして示そうとしている可能性が考えられる。
しかし、「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」が「婚姻及び家族に関する法制度の一部」である「氏」について論じているのに対して、ここでは「本件規定」を論じるものとなっており、この「本件規定」とは、「第2」の「1」で書かれているように「民法及び戸籍法の婚姻に関する諸規定」を指していることから、「婚姻及び家族に関する法制度の一部」ではなく、「婚姻及び家族に関する法制度」そのものを論じるものと考える方が適切である。
そのため、「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」が「婚姻及び家族に関する法制度の一部」と論じている部分とは意味が対応する関係になく、結局、ここで「婚姻及び家族に関する法制度の一部として」のように述べていることは、「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」の文面を前提とするものとして示そうとしているとしても、意味の通じるものではなく、誤っていることになる。
「異性間の婚姻については、違憲の問題は生じない。」について検討する。
「異性間の婚姻」とあるが、「婚姻」であることそのものによって「男女」のものしか存在しないのであり、その「婚姻」の文言に「異性間」という「男女」を指す言葉を付けることは、文法上は同義反復となるため誤用である。
「憲法24条」は「婚姻」について「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めており、この「憲法24条は異性間の婚姻を定めたものと解され」、その「憲法24条の考え方を踏まえ、」て「本件規定」が「異性間」を対象として設けられていることについて、「違憲の問題は生じない。」という点はその通りである。
これに対して、「本件規定」である法律上の婚姻制度を「同性間」の人的結合関係を対象として設けようとした場合について検討する。
「憲法24条」は「婚姻」を定めており、これは「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」を目的として、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす「一人の男性」と「一人の女性」を選び出し、その間に「貞操義務」を設けるなど一定の形式で法的に結び付け、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によってそれらの目的の達成を目指すものである。
また、「憲法24条」は「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)の枠組みを定めており、この趣旨に対応するものとなっている。
このことから、この「憲法24条の考え方を踏まえ、」ると、「同性間」の人的結合関係はその間で「生殖」を想定することができず、上記の趣旨を満たすものではないし、「憲法24条」が「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)の枠組みを定めている趣旨にも沿うものではないことから、「違憲の問題」が生じることになる。
ところが、本件で問題となっているのは、異性愛者のみならず、同性愛者にも婚姻という身分関係の変動における社会的な制度を享受させるべきかどうかということであって、さらには、歴史上の様々な事象や考え方を踏まえ、憲法の解釈上、これまで社会上、法令上想定されてきた異性愛者による婚姻の制度に同性婚を含めて容認するかという観点を含むところがある。そうすると、憲法13条のみならず、憲法24条、さらには各種の法令、社会の状況等を踏まえて検討することが相当であり、このような観点からすると、憲法13条が人格権として性的指向及び同性間の婚姻の自由を保障しているものということは直ちにできず、本件規定が憲法13条に違反すると認めることはできない。
【筆者】
「本件で問題となっているのは、異性愛者のみならず、同性愛者にも婚姻という身分関係の変動における社会的な制度を享受させるべきかどうかということであって、さらには、歴史上の様々な事象や考え方を踏まえ、憲法の解釈上、これまで社会上、法令上想定されてきた異性愛者による婚姻の制度に同性婚を含めて容認するかという観点を含むところがある。」との記載がある。
「本件で問題となっているのは、異性愛者のみならず、同性愛者にも婚姻という身分関係の変動における社会的な制度を享受させるべきかどうかということであって、」との部分について検討する。
まず、「本件で問題となっているのは、」憲法24条の「婚姻」の枠組みが「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とする法律の立法を「要請」しているか否かであり、また、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とする法律が存在しないことについて憲法13条、憲法14条に違反するか否かである。
そのため、ここで「本件で問題となっているのは、」と述べながら、この意味ではなく、「異性愛者のみならず、同性愛者にも婚姻という身分関係の変動における社会的な制度を享受させるべきかどうか」が論点であるかのように述べていることは誤りである。
次に、もし「本件」が「婚姻という身分関係の変動における社会的な制度を」「異性愛者のみならず、同性愛者にも」「享受させるべきかどうかということ」が「問題となっている」のであれば、これは憲法14条1項の「平等原則」における「法適用の平等」の論点である。
【動画】シンポジウム 国葬を考える【The Burning Issues vol.27】 2022/09/25
この「法適用の平等」が問題となっているのであれば、「絶対的平等」でなければならず、「婚姻という身分関係の変動における社会的な制度」(男女二人一組)は「異性愛者のみならず、同性愛者にも」「享受させるべき」ということになる。
これは、法制度は個々人の内心に基づいて「異性愛者」や「同性愛者」などと区別して取扱うことはしてはならないからである。
ただ、「本件」では、行政機関が婚姻制度を適用する場面において、個々人の内心を理由として制度の適用を否定したという事案でないため、「本件で問題となっている」ものであるとはいえない。
これとは別に、この判決が「男女二人一組」の「婚姻という身分関係の変動における社会的な制度」について、あたかも「異性愛」を保護することを目的とし、「異性愛者」を称する者を対象とし、「異性愛」に基づいて利用することを求めたり勧めたりする制度であるかのように考え、これと同様の「同性愛」を保護することを目的とし、「同性愛者」を称する者を対象とし、「同性愛」に基づいて利用することを求めたり勧めたりする制度を立法するべきかどうかが「本件で問題となっている」かのように考えている場合について検討する。
まず、法制度は内心に対して中立的な内容でなければならないのであり、人をその内心に基づいて「異性愛者」や「同性愛者」などと区別して取扱うようなことをしてはならない。
そのため、ここで「異性愛者」と「同性愛者」など人をその内心における心理的・精神的なものに基づいて区別することが可能であるかのように論じていること自体が誤りである。
次に、「異性愛」という特定の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的とした制度が存在する場合には、憲法20条1項後段・3項、89条の「政教分離原則」に違反するし、「異性愛」という特定の思想、信条、信仰、感情を有する者を対象とし、それ以外の「性愛」や、「性愛」以外の思想、信条、信仰、感情を有する者を対象としない制度が存在した場合には、憲法14条1項の「平等原則」に違反するし、個々人が「異性愛」という特定の思想、信条、信仰、感情を有するか否かに干渉する制度を設けることは、憲法19条の「思想良心の自由」に違反する。
そのため、そもそも法制度が「異性愛」を保護することを目的としていたり、「異性愛者」を称する者を対象としていたり、「異性愛」に基づいて利用することを求めたり勧めたりする制度が存在していること自体で違憲となるのであり、そのような制度が存在するとしても許されるかのように考えていることが誤りである。
そのことから、このような認識を前提として、新たに「同性愛」を保護することを目的とし、「同性愛者」を称する者を対象とし、「同性愛」に基づいて利用することを求めたり勧めたりする制度を設けるべきかどうかを論じていることは、その違憲な内容をさらに積み重ねるかどうかを論じているものということができ、その土台となる認識の部分から既に誤っている。
これに対して、婚姻制度は「性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いをする制度ではないし、「性愛」に基づいて制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもない。
そのため、婚姻制度は「異性愛者」を称する者を対象として設けられている制度ではなく、婚姻制度(男女二人一組)の要件に従って制度を利用する意思があるのであれば、どのような内心を有している者であっても、分け隔てなく利用を認めている。
当然、「同性愛者」を称する者であるとしても、適法に制度を利用することができ、実際、「同性愛者」を称する者も婚姻制度(男女二人一組)を利用している事実は認められる。
よって、「婚姻適齢」などの要件を満たしているのであれば、「男女二人一組」の「婚姻という身分関係の変動における社会的な制度」は誰もが「享受」することができるのであり、それを「享受」することができない者がいることを前提に、「婚姻という身分関係の変動における社会的な制度を享受させるべきかどうか」のように「享受させるべきかどうか」を論じていることは「問題」を適切に捉えることができていないといえる。
「婚姻という身分関係の変動における社会的な制度」とある。
ここでいう「身分関係」とは、「婚姻」という制度を利用する者としての「身分関係」を指すものである。
つまり、これは「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成するための手段として設けられた制度を利用する者としての「身分関係」であり、例えば「公務員」としての身分など「婚姻」とは別の制度についての身分関係とは全く関係がないものである。
そして、その「婚姻」という制度は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす人的結合関係に対してのみ制度の利用を認めることによって、その目的の実現を目指すものであるから、その目的との関係で整合的でない場合には、「婚姻」という制度による「身分関係」を形成することができないことはもともと予定されていることである。
「婚姻」という制度そのものが、このような差異を設けることによって立法目的を達成することを目指す仕組みとして形成されているものであるから、「婚姻」の持つこのような機能を無視して適用対象となる人的結合関係の範囲を拡大させることができるというものではない。
「さらには、歴史上の様々な事象や考え方を踏まえ、憲法の解釈上、これまで社会上、法令上想定されてきた異性愛者による婚姻の制度に同性婚を含めて容認するかという観点を含むところがある。」との部分について検討する。
「歴史上の様々な事象や考え方を踏まえ、憲法の解釈上、これまで社会上、法令上想定されてきた異性愛者による婚姻の制度」とある。
しかし、「歴史上」も「憲法の解釈上」も「社会上」も「法令上」も、「婚姻の制度」は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」を目的として、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす「一人の男性」と「一人の女性」の組み合わせを「貞操義務」など一定の形式で法的に結び付け、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によってそれらの目的の達成を目指す仕組みである。
そのため、「歴史上」、「憲法の解釈上」、「社会上」、「法令上」において、「異性愛者による婚姻の制度」などと、「婚姻の制度」が「異性愛者」を称する者を対象とするものとして設けられているという事実はない。
そもそも法制度は個々人の内心に対して中立的な内容でなければならないのであり、個々人をその内心に基づいて「異性愛者」や「同性愛者」などと区別して取扱ってはならないのであり、これまでの間に「婚姻の制度」が「異性愛者」を称する者であるか否かなどと人を内心において区別しているという事実は存在しない。
これに対して、この札幌高裁判決では、「異性愛者による婚姻の制度」のように「婚姻の制度」をあたかも「異性愛」を保護することを目的とした制度であり、「異性愛者」を称する者を対象とした制度であり、「異性愛」に基づいて制度を利用することを求めたり勧めたりする制度であるとしていることは、法制度が個々人の内心を審査して区別取扱いをするものとして存在するとしても許されるかのように述べていることになる。
これは、「婚姻の制度」を「異性愛」という特定の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的とした制度としようとするものであるから、憲法20条1項後段・3項、89条の「政教分離原則」に違反するものである。
また、「婚姻の制度」を「異性愛者」を称する者を対象とし、それ以外の者を対象としない制度ということになり、個人の内心に基づいて区別する制度としようとするものであるから、憲法14条1項の「平等原則」に違反するものである。
さらに、「婚姻の制度」を利用する者の内心に対して国家が干渉するものとしようとするものであるから、憲法19条の「思想良心の自由」に違反するものである。
そのため、ここで「異性愛者による婚姻の制度」と述べていることは誤りである。
また、「婚姻の制度」を利用している者をすべて「異性愛者」を称する者であるかのような前提で論じていることも誤りである。
実際、「婚姻の制度」は、「異性愛者」を称する者以外の者でも利用することができるのであり、「同性愛者」を称する者や、特に何も称しない者が利用している事実を認めることができる。
よって、「歴史上の様々な事象や考え方を踏まえ、憲法の解釈上、これまで社会上、法令上想定されてきた異性愛者による婚姻の制度に同性婚を含めて容認するかという観点を含むところがある。」との部分は、「歴史上」、「憲法の解釈上」、「社会上」、「法令上」において「異性愛者」を称する者を対象とした「婚姻の制度」が存在するかのように述べている点で誤りであるし、「異性愛者」を称する者を対象とした「婚姻の制度」が存在するとしても許されるかのように述べている点でも誤りである。
「婚姻の制度に同性婚を含めて容認するかという観点を含むところがある。」とある。
しかし、「婚姻」は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた枠組みである。
具体的には、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」を目的として、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす「一人の男性」と「一人の女性」を選び出し、その間に「貞操義務」を設けるなど一定の形式で法的に結び付け、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によってそれらの目的を達成することを目指すものである。
そのため、この趣旨との関係で「婚姻」の中に含めることができる人的結合関係の範囲には内在的な限界がある。
これは、もしどのような人的結合関係でも「婚姻」の中に含めることができることになれば、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成することができない状態となり、「婚姻」という枠組みを設けている意味がなくなってしまうからである。
そのため、ここでは「同性婚」のように、「婚姻」の中に「同性」間の人的結合関係を含めることができるかのような前提の下に説明するものとなっているが、そもそも「同性」間の人的結合関係については、その間で「生殖」を想定することができないことから、上記の趣旨を満たすとはいえず、「婚姻」という概念の中に含まれない。
よって、この文は「婚姻の制度に同性婚を含めて容認するか」と記載されているが、「婚姻」の中に「同性」間の人的結合関係を含めることはできないし、その「婚姻の制度」の部分についても「同性」間の人的結合関係を含めることはできない。
「そうすると、憲法13条のみならず、憲法24条、さらには各種の法令、社会の状況等を踏まえて検討することが相当であり、このような観点からすると、憲法13条が人格権として性的指向及び同性間の婚姻の自由を保障しているものということは直ちにできず、本件規定が憲法13条に違反すると認めることはできない。」との記載がある。
「そうすると、」の部分は、一文前の内容を引き継ぐものとなっているが、上記で説明したように、一文前の内容は前提となる認識に誤りがあり、これを引き継ぐことそのものが誤りである。
「憲法13条のみならず、」とある。
しかし、これより以前の文の中で、「控訴人ら」の主張としてではなく、この判決を書いた裁判体の見解として「憲法13条」についての説明は登場していない。
それにもかかわらず、「憲法13条のみならず、」のように、突然「憲法13条」について取り上げ、加えて「のみならず、」のように「憲法13条」について既に論じられていることを前提としているかのように述べていることは適切ではない。
その他、一文前の「異性愛者のみならず、同性愛者にも婚姻という身分関係の変動における社会的な制度を享受させるべきかどうかということ」については、法令の適用に関するものであり、憲法上の条文としては憲法14条の「平等原則」における「法適用の平等」に関するものである。
そのため、「憲法13条」が関わるものではなく、「憲法13条のみならず、」のように、「憲法13条」の「検討」をすることは誤りである。
一文前の「婚姻の制度に同性婚を含めて容認するかという観点」については、憲法24条の「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言が一夫一婦制(男女二人一組)を定めていることとの関係を検討するものであることから、憲法24条で検討されるものである。
そのため、「憲法13条」が関わるものではなく、「憲法13条のみならず、」のように、「憲法13条」の「検討」をすることは誤りである。
「そうすると、……(略)……憲法24条、さらには各種の法令、社会の状況等を踏まえて検討することが相当であり、」とある。
これは、「そうすると、」として一文前で述べたことを理由として「憲法24条、さらには各種の法令、社会の状況等を踏まえて検討することが相当であ」るとの結論を述べようとするものである。
しかし、一文前の内容が誤っていることから、その誤った内容を理由として「憲法24条、さらには各種の法令、社会の状況等を踏まえて検討することが相当であ」るとの結論が導き出されるかのように考えていることも誤りである。
「憲法24条」「を踏まえて検討する」のであれば、憲法24条は「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めており、この枠組みによって「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成することを目指す制度を設けることを「要請」するものであるから、この趣旨を満たさない「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とする法律を立法することを「要請」しているものではなく、その「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とする法律が存在しないことが「憲法24条」に違反するということにはならない。
「各種の法令」「を踏まえて検討する」との部分であるが、憲法以外の「各種の法令」が存在するか否かという問題は、憲法24条の「婚姻」の枠組みが「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とする法律の立法を「要請」しているか否かという憲法上の規定に適合するか否かに関わりのないことである。
そのため、憲法に違反するか否かが問われている憲法解釈の場面で、憲法以外の「各種の法令」「を踏まえて検討する」ことは妥当でない。
「社会の状況等を踏まえて検討する」との部分であるが、裁判所は法令の規定に違反するか否かという合憲・違憲、あるいは、合法・違法しか判断することはできず、法令上の規範は「社会の状況等」によって左右されるものではないし、左右されるようなことがあってはならないものであることから、それが「社会の状況等を踏まえて検討する」ことによって結論が変わるかのような前提で論じていることは誤りである。
また、「社会の状況等を踏まえて検討する」ことは、憲法の枠内で政治部門である国会や内閣以下の行政機関の役割である。
そのため、法令に違反するか否かしか判断することのできない裁判所で検討することができる問題ではないし、それを検討して特定の結論を導き出そうとすることは司法権の範囲を逸脱した越権行為であり、違法である。
よって、「憲法13条のみならず、憲法24条、さらには各種の法令、社会の状況等を踏まえて検討することが相当であり、」と述べている部分は、「相当」であるとはいえず、誤りである。
「このような観点からすると、」とあるが、「このような観点」の指しているものが明確ではない。
これが直前の「憲法13条のみならず、憲法24条、さらには各種の法令、社会の状況等を踏まえて検討することが相当であり、」の部分を指しているのであれば、その「憲法24条、さらには各種の法令、社会の状況等を踏まえて検討」した結果として、この「2 本件規定が憲法13条に違反する旨の主張について」の項目の「憲法13条」に違反するか否かの結論が示されるはずである。
しかし、そのような「憲法24条、さらには各種の法令、社会の状況等を踏まえて検討」を行っているという形跡はなく、この部分のすぐ後で「憲法13条が人格権として性的指向及び同性間の婚姻の自由を保障しているものということは直ちにできず、本件規定が憲法13条に違反すると認めることはできない。」のように「憲法13条」に違反するか否かの結論を述べていることは不自然である。
また、「憲法13条のみならず、憲法24条、さらには各種の法令、社会の状況等を踏まえて検討することが相当であり、」との部分は、上記で述べたようにそもそも誤った内容であり、「このような観点」を検討して結論を導き出そうとしていることそのものが誤りとなるという問題もある。
そのため、「このような観点からすると、」の部分は、一文前の「婚姻の制度に同性婚を含めて容認するかという観点」の部分を指している可能性がある。
ただ、そうなると、「そうすると、」の部分で一文前の「婚姻の制度に同性婚を含めて容認するかという観点」を既に引き継いでいることから、そこで改めて「このような観点」のように一文前を引き継いでいることを更に繰り返す必要はなかったはずである。
この点で、非常に読み取りづらいものとなっている。
「憲法13条が人格権として性的指向及び同性間の婚姻の自由を保障しているものということは直ちにできず、本件規定が憲法13条に違反すると認めることはできない。」
ここでは「憲法13条が人格権として性的指向及び同性間の婚姻の自由を保障しているものということは直ちにできず、」との結論が導き出される理由として、「憲法13条のみならず、憲法24条、さらには各種の法令、社会の状況等を踏まえて検討することが相当であり、」や「このような観点」と述べている部分を挙げるものとなっている。
しかし、「憲法13条が人格権として性的指向及び同性間の婚姻の自由を保障しているものということ」が「でき」ない理由は、下記の理由である。
まず、「性的指向」と称しているものは個人の内心における心理的・精神的なものであり、このような内心に関することは「内心の自由」として憲法19条の「思想良心の自由」によって保障される事柄であり、「憲法13条」の「人格権」として捉えられるものではない。
次に、ここでいう「同性間の婚姻」の意味が「同性間の人的結合関係」を形成すること指すのであれば、それは憲法21条1項の「結社の自由」として保障されるものであり、「憲法13条」の「人格権」として捉えられるものではない。
三つ目に、ここでいう「同性間の婚姻」の意味が「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを指すのであれば、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることができるかどうかという点から検討することが必要である。
「婚姻」は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」を目的として、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす「一人の男性」と「一人の女性」の組み合わせを「貞操義務」などの一定の形式で法的に結び付け、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によってそれらの目的の達成を目指す枠組みである。
「同性間の人的結合関係」については、その間で「生殖」を想定することができず、この趣旨を満たすものではないことから、「婚姻」の中に含めることはできない。
そのため、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることをはできない。
四つ目に、「婚姻の自由」との部分は、「再婚禁止期間制度訴訟大法廷判決」の述べる「婚姻をするについての自由」にあたるものとして述べられていると考えられる。
しかし、これは憲法24条1項の趣旨を解釈したものとして示されたものであり、「憲法13条」や「人格権」で保障されるものとして示されたものではない。
よって、この札幌高裁判決が「憲法13条が人格権として性的指向及び同性間の婚姻の自由を保障しているものということ」が「でき」ないとの結論が導き出される理由として、「憲法13条のみならず、憲法24条、さらには各種の法令、社会の状況等を踏まえて検討することが相当であり、」や「このような観点」と述べている部分を挙げていることは誤りである。
「直ちに」の文言であるが、この部分に配置することは文法的に意味を読み取りづらく、その意味も曖昧なものとなるため表現として適切ではない。
「本件規定が憲法13条に違反すると認めることはできない。」との部分であるが、この結論そのものは正しいといえる。
しかし、判断の過程の部分が誤っているため、それを前提としてこの結論を述べているという文脈として考えると、この結論の正当性を支える理由があるとはいえないものとなっている。
この「憲法13条」の論点について、国(行政府)の主張では下記のように述べられている。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(イ)しかしながら,およそ人同士がどうつながりを持って暮らし,生きていくかは,当人らが自由に決めて然るべぎ事柄であり,このような自由自体は異性間であっても同性間であっても,等しく憲法13条において尊重されるべきものと解されるが,前記3で述べたとおり,婚姻が一定の法制度を前提としている以上,「婚姻をするかどうか,いつ誰と婚姻をするか」を当事者間で自由に意思決定し,故なくこれを妨げられないという「婚姻をするについての自由」は,法制度を離れた生来的, 自然権的な自由権として憲法で保障されているものと解することはできない。前記2で述べたとおり,憲法24条1項は,婚姻について異性間の人的結合関係のみを対象とし,同性間の人的結合関係を対象とすることを想定しておらず,同条2項も,飽くまで婚姻が異性間の人的結合関係のみを対象とするものであることを前提としてこれを具体化する制度の整備を立法府に要請するものであり,これを受けて定められた本件規定も,婚姻が異性間の人的結合関係のみを対象とするものであることを前提に定められている。
そうすると,控訴人らが「婚姻をするについての自由」として主張するものの内実は,「両性」の本質的平等に空脚すべきことを規定する憲法24条2項の要請に従って創設された現行の婚姻制度の枠を超えて,同性間の人的結合関係についても婚姻と同様の積極的な保護や法的な利益の供与を認める法制度の創設を国家に対して求めるものにほかならないのであって,国家からの自由を本質とするものではないから,このような自由が憲法13条の幸福追求権の一内容を構成するものと解することはできない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【札幌・第1回】被控訴人答弁書 令和3年9月30日 PDF (P14~)
(3) もっとも、性的指向及び同性間の婚姻の自由は、人格権の一内容を構成し得る重要な法的利益ということができる。性的指向は、社会的には異性愛者と同性愛者を本質的に区別する理由がなく、人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の一要素でもあることから、社会の制度上取扱いに不利益があれば、そのことによりいわゆるアイデンティティの喪失感を抱き、人としての存在を否定されたとの思いに至ってしまうことは容易に理解できることである。
【筆者】
「性的指向及び同性間の婚姻の自由は、人格権の一内容を構成し得る重要な法的利益ということができる。」との記載がある。
「性的指向及び同性間の婚姻の自由」との部分を検討する。
まず、「性的指向」とは、「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかに関するものであり、個人の内心における精神的なものであることから、「内心の自由」として憲法19条の「思想良心の自由」によって保障されるものである。
そのため、「性的指向」と称するものについては、「人格権」として捉えられるものではない。
よって、「性的指向……(略)……は、人格権の一内容を構成し得る」と述べていることは誤りである。
次に、「同性間の婚姻」の意味が「同性間の人的結合関係」を指しているのであれば、「同性間の人的結合関係」を形成することについては、「国家からの自由」という「自由権」の性質として憲法21条1項の「結社の自由」によって保障されるものである。
そのため、「同性間の人的結合関係」を形成する「自由」について、「人格権」として捉えられるものではない。
よって、「同性間の婚姻の自由は、人格権の一内容を構成し得る」と述べていることは誤りである。
「同性間の婚姻」の意味が「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを指しているのであれば、そもそも「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることができるかという部分ら検討することが必要である。
「婚姻」とは、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた枠組みである。
具体的には、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」を目的として、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす「一人の男性」と「一人の女性」の組み合わせを選び出し、その間に「貞操義務」を設けるなど一定の形式で法的に結び付けることで産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によってそれらの目的の達成を目指すものである。
しかし、「同性間の人的結合関係」については、その間で「生殖」を想定することができず、この「生殖と子の養育」の趣旨に沿うものではないことから、「婚姻」の中に含めることはできない。
よって、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることはできないのであり、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることができることを前提として論じていることは誤りとなる。
また、「婚姻の自由」(『再婚禁止期間制度訴訟大法廷判決』の述べている『婚姻をするについての自由』にあたるもの)についても、憲法24条が「婚姻」を規定しており、また、「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めており、その憲法24条の「婚姻」の枠組みの「要請」に従って立法された法律上の婚姻制度を利用するか否かについての自由をいうものである。
そのため、この「婚姻の自由」(婚姻をするについての自由)を根拠として、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを求めることができるというものではない。
よって、この「婚姻の自由」(婚姻をするについての自由)を理由として「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることが可能であるかのように述べようとしているのであれば、それも誤りである。
その他、たとえこれが「男女二人一組」の「婚姻」について述べているとしても、その「婚姻をするについての自由」とは、「再婚禁止期間制度訴訟大法廷判決」で述べられているように、憲法24条1項を解釈することにより導かれているものである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
……(略)……また,同条1項は,「婚姻は,両性の合意のみに基いて成立し,夫婦が同等の権利を有することを基本として,相互の協力により,維持されなければならない。」と規定しており,婚姻をするかどうか,いつ誰と婚姻をするかについては,当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたものと解される。婚姻は,これにより,配偶者の相続権(民法890条)や夫婦間の子が嫡出子となること(同法772条1項等)などの重要な法律上の効果が与えられるものとされているほか,近年家族等に関する国民の意識の多様化が指摘されつつも,国民の中にはなお法律婚を尊重する意識が幅広く浸透していると考えられることをも併せ考慮すると,上記のような婚姻をするについての自由は,憲法24条1項の規定の趣旨に照らし,十分尊重に値するものと解することができる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
そのため、この「婚姻をするについての自由」は、憲法24条1項に基づくものであり、「人格権」として捉えられるものではない。
よって、ここでいう「婚姻の自由」(婚姻をするについての自由)について、「人格権の一内容を構成し得る」のように、「人格権」として説明しようとしていることは誤りである。
これとは別に、「人格権の一内容を構成し得る」との説明は、「謝罪広告等請求事件」や「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」で「氏名」について、「人格権の一内容を構成するものというべきである」と述べている部分と重ねる形で論じようとするものである。
謝罪広告等請求事件
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
氏名は、社会的にみれば、個人を他人から識別し特定する機能を有するものであるが、同時に、その個人からみれば、人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の象徴であつて、人格権の一内容を構成するものというべきであるから、人は、他人からその氏名を正確に呼称されることについて、不法行為法上の保護を受けうる人格的な利益を有するものというべきである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
謝罪広告等請求事件 最高裁判所第三小法廷 昭和63年2月16日 (PDF)
夫婦同姓制度訴訟大法廷判決
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2(1) 氏名は,社会的にみれば,個人を他人から識別し特定する機能を有するものであるが,同時に,その個人からみれば,人が個人として尊重される基礎であり,その個人の人格の象徴であって,人格権の一内容を構成するものというべきである(最高裁昭和58年(オ)第1311号同63年2月16日第三小法廷判決・民集42巻2号27頁参照)。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
損害賠償請求事件 最高裁判所大法廷 平成27年12月16日 (PDF)
しかし、「謝罪広告等請求事件」や「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」において、「人格権の一内容を構成するもの」と述べている理由は、上記のように、「氏名」の性質が、「個人を他人から識別し特定する機能を有する」ものであり、また、その機能によって「人が個人として尊重される基礎」となり「その個人の人格の象徴」となるからである。
これに対して、「性的指向」と称するものは、個人の内心における精神的なものであることから、「内心の自由」として憲法19条の「思想良心の自由」によって保障されるものではあるが、個人を他者との間で識別する機能を有しているわけではないことから、「謝罪広告等請求事件」や「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」で述べられているような意味の「人格権」に対応するものではない。
また、「謝罪広告等請求事件」や「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」において、「人格権の一内容を構成するもの」と述べている部分は、「氏名」についての具体的な法制度の存在を前提として論じているものであるが、この札幌高裁判決の述べている「性的指向」と称するものについては、個人の内心における精神的なものであり、具体的な法制度の存在を前提とするものではない。
この点でも、「謝罪広告等請求事件」や「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」で述べられているような意味の「人格権」に対応するものではない。
「同性間の婚姻」の意味が「同性間の人的結合関係」を形成することを指すのであれば、それは「国家からの自由」という「自由権」の性質として憲法21条1項の「結社の自由」として保障されるものであることから、具体的な法制度の存在を前提とするものではない。
また、「同性間の婚姻」の意味が「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを指すのであれば、そもそも「婚姻」は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する形て設けられた制度であり、この趣旨を満たさない「同性間の人的結合関係」を「婚姻」として立法することをはできず、やはり具体的な法制度は存在していない。
そのため、この札幌高裁判決の事例では具体的な法制度が存在していないことから、「謝罪広告等請求事件」や「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」において「氏名」についての具体的な法制度が存在することを前提として「人格権」を論じている場合とは性質が異なっており、これらの判決に重ね合わせる形で「人格権」を論じることができるというものではない。
よって、これと重ね合わせて論じようとしていることは誤りである。
「性的指向は、社会的には異性愛者と同性愛者を本質的に区別する理由がなく、人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の一要素でもあることから、社会の制度上取扱いに不利益があれば、そのことによりいわゆるアイデンティティの喪失感を抱き、人としての存在を否定されたとの思いに至ってしまうことは容易に理解できることである。」との記載がある。
━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━
この文は非常に読み取りづらいものとなっている。
その理由から検討する。
◇ 「性的指向は、社会的には異性愛者と同性愛者を本質的に区別する理由がなく、」とある。
しかし、「性的指向」とは「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを示す際に使われている言葉である。
そのため、「性的指向は、」と述べて性的指向を主題としているにもかかわらず、そこで「性愛」を有する場合にどのような対象に向かうかについて述べるのではなく、「異性愛者」と「同性愛者」のように「性愛」を有する本人について述べるものとなっており、主題との間で対応するものとなっていない。
そのため、読み手を混乱させるものとなっている。
「人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の一要素でもある」との部分は、「性的指向は、」という主題に対応するものとして述べようとしているようである。
ただ、その内容の当否については別に検討する必要がある。
「社会の制度上取扱いに不利益があれば、」との部分は、主語が何か分からないものとなっている。
また、この部分の直前を見ても「社会の制度上」においてどのような「取扱い」によって「不利益」が生じたのかも明らかでない。
そのため、読み手は主語や「取扱い」の内容について明確なイメージを掴むことができず、読み取りにくく感じるものとなっている。
ただ、この文の主題が「性的指向は、」となっており、「社会的には異性愛者と同性愛者を本質的に区別する理由がなく、」と述べている部分があることから、これを前提として個人の「性的指向」と称するものによって「社会制度上」で「区別」「取扱い」を受け、「不利益」が生じた場合のことを述べようとしているようにも見受けられる。
そうであば、下記のように文の中身を並べ替えたほうが読み取りやすいはずである。
・ 「性的指向は、」「人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の一要素でもあることから、」「社会的には異性愛者と同性愛者を本質的に区別する理由がなく、」「社会の制度上取扱いに不利益があれば、そのことによりいわゆるアイデンティティの喪失感を抱き、人としての存在を否定されたとの思いに至ってしまうことは容易に理解できることである。」
ただ、読み取りやすくしたとしても、内容が妥当であるかどうかは別の問題として検討する必要がある。
━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━
「性的指向は、」との部分について検討する。
「性的指向」と称しているものは、「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかについて分類するものであり、個人の内心における精神的なものについて述べるものである。
ただ、そもそも法制度は内心に対して中立的な内容でなければならないことから、法律論としては人をその個人の内心における精神的なものに基づいて区別するようなことをしてはならないのであり、ここで「性的指向」などと個人の内心における精神的なものを分類しようとする特定の思想を持ち出して人を区別することが可能であるかのように論じていることそのものが妥当でない。
「社会的には異性愛者と同性愛者を本質的に区別する理由がなく、」との部分について検討する。
ここでは、「異性愛者」と「同性愛者」との文言が登場する。
これは人の内心における心理的・精神的なものを取り上げて、それを異なるものに分類し、その分類に基づいて人を区別するものということができる。
しかし、「性愛」の存否や傾向について述べていること自体が、特定の価値観で人を分類しようとする者の用いている一つの思想、信条、信仰に過ぎないものである。
もともと「性愛」の分類を使っていない者もいるし、そのような分類で人を見ていない者もいるし、「性愛」を重視していない者もいるし、そもそも考えたことない者もいる。
また、「同性愛者」や「異性愛者」というような人の内心に基づいた区別はいずれ無くなるべきだと考えている者もいる。
それにもかかわらず、この判決で「異性愛者」や「同性愛者」などという言葉を使い、「性愛」の有無やその「性愛」がどのような対象に向かうかという視点で人を区別して見ていること自体が、既に「性愛」によって人を分類するという特定の価値観に基づいて、その主張に与する形で論じるものとなっており、不適切である。
そもそも、「性愛」そのものが個人の内心における心理的・精神的なものであることから、それが常に明確であるというものではない。
例えば「異性愛」や「同性愛」などと取り上げることがあるとしても、人によって「少しばかり異性愛」、「少しばかり同性愛」という者から、「強度の異性愛」、「強度の同性愛」など、その心理状態は様々である。
また、「性愛」の感情についても、生活の中で抱かれる様々な心理状態の中の一側面として現れるというだけのものであり、生活の中で常にそのような心理状態を感じ続けているわけではない。
ある一時期に感じていた「性愛」についても、別の時期には異なる形で感じられることもあるだろうし、便宜的に「異性愛」や「同性愛」などと述べている傾向についても、途中で変わることもある。
また、相手を異性であると認識していたが、外見による判断は誤っており、後に同性であることが確認されるという場合もあり得るものである。
こうなると、「異性愛」や「同性愛」などという区別も、外見や特定の記号に対する心理的な反応を伝えるために使っている便宜的な説明に過ぎないものであることは明らかである。
そのため、「異性愛」や「同性愛」、「その他の性愛」などの個人の内心における心理的・精神的なものについては、常に「内心の自由」として捉えられるものであり、これを法的な議論の中で人を区別して取扱うための基準として用いることができるということにはならない。
そのことから、個々人を取り上げる際に、個々人の抱く内心に踏み込む形で論じるようなことはしてはならない。
これらは法律論として区別して扱うことができるものではないし、これらを基にして法制度を立法することができることにもならない。
よって、このような内心を取り上げて人を区別することが可能であるかのような前提で論じていること自体が妥当でない。
裁判所が人をその内心に基づいて分類するようなことをするべきではなく、ここで人を内心に基づいて区別しようとする者の主張を安易に受け入れ、実際に「異性愛者と同性愛者」のように取り上げて、人をその内心に基づいて区別することが可能であることを前提として論じていることは誤りである。
この論点について、当サイト「性別と思想」でも解説している。
「性的指向は、社会的には異性愛者と同性愛者を本質的に区別する理由がなく、」とある。
「社会的には」との部分であるが、「社会」の中の私的な団体においては、個々人が「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかによって人を区別しようとする思想の下に、その特定の内心を有する者との間で連絡を取り合ったり、集会をしたり、人的結合関係を形成、維持、解消するなどする場合がある。
これは、宗教団体A、宗教団体B、宗教団体C、宗教団体D、宗教団体Eが、それぞれの思想や信条、信仰の下に連絡を取り合ったり、集会をしたり、人的結合関係を形成、維持、解消するなどしていることと同様である。
そのため、中には「性的指向」と称するものによってメンバーを集めたり、団体やグループを形成することはあり得るのであり、「本質的に区別する理由がな」いとはいえない。
もし「社会的に」「区別する」ことを不可とした場合には、これらのすべての交流や集会、結合は違法として禁じられることになるが、そのような措置は「国家からの自由」という「自由権」の性質である憲法21条1項の「集会の自由」や「結社の自由」などに違反することになる。
よって、「社会的には異性愛者と同性愛者を本質的に区別する理由がなく、」と述べていることは誤りとなる。
これに対して、法的には、法制度は個人の内心に対して中立的な内容でなければならず、「異性愛者」や「同性愛者」などと人をその内心に基づいて区別して取扱うことはできない。
もし「性愛」を保護することを目的とした制度が存在した場合には、憲法20条1項・3項、89条の「政教分離原則」に違反することになるし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いをする制度が存在した場合には、憲法14条1項の「平等原則」に違反することになるし、「性愛」に基づいて制度を利用することを求めたり勧めたりする制度が存在した場合には、憲法19条の「思想良心の自由」に違反することになる。
また、法制度を適用する場面で、個々人の内心を審査して特定の思想、信条、信仰、感情を有する者に対して適用を否定することがあった場合には、憲法14条1項の「平等原則」における「法適用の平等」に違反することになる。
そのため、法的には「異性愛者と同性愛者を本質的に区別する」ことはできない。
これとは別の論点で、ここでこの判決が「異性愛者と同性愛者を本質的に区別する理由がなく、」のように述べていることは、現在の法制度の中に個々人の内心を審査して「異性愛者」と「同性愛者」に区別して取扱う制度が存在することを前提として論じるものとなっている。
しかし、もし人を内心に基づいて「異性愛者」と「同性愛者」に区別して取扱う制度が存在するのであれば、そのこと自体が違憲となり、その法制度は無効となる。
そのため、個人の内心における精神的なものに基づいて人を区別する法制度が存在した場合に、そのような法制度の存在そのものを違憲として失効させるのではなく、その対象となっている特定の内心以外の内心も対象とすることによって問題の解決を図ることは、法制度の違憲性に重ねる形で、新たに同様の違憲性を持つ法制度の整備することを意味するのであり、方法として誤りである。
この点に注意する必要がある。
その他、婚姻制度(男女二人一組)は、「性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いをする制度ではないし、「性愛」に基づいて制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもない。
そのため、婚姻制度(男女二人一組)は憲法に違反するものではない。
しかし、この判決が婚姻制度(男女二人一組)が「性愛」(その中でも特に『異性愛』)を保護することを目的とした制度であり、「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうか(特に『異性愛』であるか)を審査して区別取扱いをする制度であり、「性愛」(その中でも特に『異性愛』)に基づいて制度を利用することを求めたり勧めたりするものであるとの前提で論じていることは、その解釈そのものが憲法に違反するものである。
そのため、この判決は婚姻制度(男女二人一組)の違憲性について論じようとしているが、むしろこの判決の婚姻制度(男女二人一組)に対する理解こそが違憲となるものである。
また、法制度は内心に対して中立的な内容でなければならないことから、「異性愛者と同性愛者を本質的に区別する理由がなく、」といえるところを、むしろ、この判決が人をその内心に基づいて「異性愛者」と「同性愛者」などと個人の内心における精神的なものに基づいて人を区別して論じていることそのものが、ここで自ら「区別する理由がなく、」と述べていることと矛盾していることになるのであり、妥当でない。
さらに、ここで「異性愛者と同性愛者を本質的に区別する理由がなく、」のように述べているのであれば、地方自治体の実施する「パートナーシップ認定制度」の内容が「同性愛」を保護することを目的とした制度となっていたり、「同性愛者」を称する者を対象とした制度となっていたり、「同性愛」に基づいて制度を利用することを求めたり勧めたりするものとなっていることについて、憲法に違反するものであることは理解できるはずである。
そのため、この判決の立場からは、地方自治体の「パートナーシップ認定制度」が個人の内心における精神的なものに基づいて人を区別する制度となっていることの違憲性を指摘することが必要である。
それにもかかわらず、この判決では、このような「パートナーシップ認定制度」が適法であるかのような前提で取り上げて、それを根拠として、逆に「性愛」とは関りがなく違憲性も存在しない婚姻制度(男女二人一組)の方を違憲であると結論付けようとするものとなっており、これは、自らが打ち立てた「異性愛者と同性愛者を本質的に区別する理由がなく、」という基準にさえ背くものということができ、この判決の矛盾を明らかにするものであるといえる。
「性的指向」について「人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の一要素でもあることから、」と述べている部分について検討する。
この文は、上記の「(2)ア」の第三段落でもよく似た文が登場している。
◇ 「(2)ア」の第三段落
「その個人からみれば、人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の象徴であって、人格権の一内容を構成し得るものというべきである。」
ただ、「(2)ア」の第三段落で「人格の象徴」と述べていた部分は、ここでは「人格の一要素」となっており、文言がやや異なる。
この「人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の」の文言は、「謝罪広告等請求事件」と「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」における「氏名」の性質について述べている部分の言い回しと同じくするものとなっている。
謝罪広告等請求事件
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
氏名は、社会的にみれば、個人を他人から識別し特定する機能を有するものであるが、同時に、その個人からみれば、人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の象徴であつて、人格権の一内容を構成するものというべきであるから、人は、他人からその氏名を正確に呼称されることについて、不法行為法上の保護を受けうる人格的な利益を有するものというべきである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
謝罪広告等請求事件 最高裁判所第三小法廷 昭和63年2月16日 (PDF)
夫婦同姓制度訴訟大法廷判決
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2(1) 氏名は,社会的にみれば,個人を他人から識別し特定する機能を有するものであるが,同時に,その個人からみれば,人が個人として尊重される基礎であり,その個人の人格の象徴であって,人格権の一内容を構成するものというべきである(最高裁昭和58年(オ)第1311号同63年2月16日第三小法廷判決・民集42巻2号27頁参照)。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
損害賠償請求事件 最高裁判所大法廷 平成27年12月16日 (PDF)
しかし、「謝罪広告等請求事件」と「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」では、「氏名」の性質について、「個人からみれば」という「個人」から見た場合だけでなく、「社会的にみれば」という「社会的」に見た場合について検討しており、これらを「同時に、」の文言で繋ぎ、二つの意味を対比させる形で論じられている。
◇ 「社会的にみれば,個人を他人から識別し特定する機能を有するものであるが,」
◇ 「その個人からみれば,人が個人として尊重される基礎であり,その個人の人格の象徴であって,」
しかし、この札幌高裁判決では、「個人からみれば」の部分だけを抜き出し、「社会的にみれば」の部分を欠落させるものとなっている。
その代わりに、「社会的には異性愛者と同性愛者を本質的に区別する理由がなく、」の文言を加えているが、「謝罪広告等請求事件」と「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」の中で使われている「氏名」の性質について述べている文脈に対応するものであるとはいえない。
「謝罪広告等請求事件」と「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」では、「氏名」の性質について、「社会的に」見た場合と「個人から」見た場合を対比させる文脈として説明されている。
つまり、先に「社会的に」見た場合の「氏名」の性質を検討し、その後に「個人から」見た場合の「氏名」の性質について検討するものとなっている。
ここで注意したいのは、「個人から」見た場合の「氏名」の性質については、先に「社会的に」見た場合の「氏名」の性質である個人識別機能を前提として論じられていることである。
これは、「社会的に」見た場合に、「氏名」には個人識別機能があり、その個人識別機能の存在によって、全体の一部として扱われたり、他者との間で混同されたりすることはないという意味で、「人が個人として尊重される基礎」となっており、「その個人の人格の象徴」として機能するのように、「個人から」見た場合の説明に繋がっているのである。
しかし、この札幌高裁判決は、「氏名」について説明する文脈の中で「社会的に」見た場合についての説明を切り落としていることから、その後の「個人から」見た場合について取り上げるとしても、それは個人識別機能についての説明を前提とするものとなっていない。
すると、個人識別機能とは異なる意味として、どのような意味で「性的指向」が「人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の」であるのか理解することが不可能であり、意味が通じないものとなっているのである。
そもそも、「性的指向」と称しているものは、「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかについて示すものであり、個人の内心における精神的なものであることから、「内心の自由」として憲法19条の「思想良心の自由」によって保障されるものであり、「個人として尊重される」こととは直接的に関係するものであるとはいえない。
よって、「性的指向」について、「人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の」と述べていることは意味が通じておらず、誤りということになる。
「社会の制度上取扱いに不利益があれば、そのことによりいわゆるアイデンティティの喪失感を抱き、人としての存在を否定されたとの思いに至ってしまうことは容易に理解できることである。」との部分について検討する。
「社会の制度上取扱い」との部分であるが、ここではどのよう「取扱い」がなされているのか明確に記載されていないため、意味を読み取りしづらいものとなっている。
ただ、これよりも前の部分で「性的指向」や「異性愛者と同性愛者を本質的に区別する理由がなく、」と述べていることから、「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかという事柄によって、「社会の制度上」で「取扱い」が変えられている場合について述べているようである。
「社会の制度」の中には、例えば宗教団体のように、自らが特定の内心を有すると告白したり宣言したりすることによって(信仰告白)、その宗教団体に所属することを可能としている場合がある。
また、会社組織や政党の中でも、特定の思想、信条、信仰を有していることを前提としていたり、特定の思想、信条、信仰に賛同していることを宣言することを条件としている場合などがある。
そのため、私的な団体において、個人の内心における精神的なものに基づいて「社会の制度上取扱い」が変えられるということはあり得るものである。
これに対して、法的には、個人の内心に対して中立的な内容でなければならないことから、個人の内心における精神的なものに基づいて「取扱い」を変えてはならない。
そのため、個人の内心における精神的なものを理由として人を区別して扱っているという事実はない。
もし法制度が特定の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的とした制度となっていた場合には、憲法20条1鋼・3項、89条の「政教分離原則」に違反することになる。
また、特定の思想、信条、信仰、感情を有する者を対象として、それ以外の思想、信条、信仰、感情を有する者を対象としないことや、個人の内心における精神的なものに基づいて人を区別して取扱うような制度が存在した場合には、憲法14条1項の「平等原則」に違反することになる。
他にも、法制度が個人の内心に対して干渉するものとなることから、憲法19条の「思想良心の自由」にも違反することになる。
さらに、法制度を適用する場面において、個人の内心を審査して特定の内心を有する者に対してその法制度を適用しないということがあれば、憲法14条1項の「平等原則」における「法適用の平等」に違反することになる。
そのため、個人の内心における精神的なものに基づいて、法的な「制度上」の「取扱い」を変えた場合は、違憲となる。
また、この札幌高裁判決で問われている婚姻制度(男女二人一組)については、「性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いをするものではないし、「性愛」に基づいて制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもない。
そのため、婚姻制度(男女二人一組)が「異性愛者と同性愛者」などと「性的指向」と称するものに基づいて法的な取り扱いを変えているという事実はない。
よって、この文が、婚姻制度(男女二人一組)が法的な「制度上」において「取扱い」を変えているかのような認識を前提として論じているのであれば誤りである。
「不利益があれば、」との部分であるが、婚姻制度(男女二人一組)は、個人の内心における精神的なものに基づいて人を区別するものではないことから、特定の内心を有する者に対して法制度の適用を否定しているという事実はなく、そのような区別取扱いが存在することを前提として「不利益」を論じることは誤りである。
また、憲法は「個人の尊厳」の原理に基づいており、自然人は「個人主義」の下に各々「自律的な個人」として生存していくことを予定していることから、何らの制度も利用していない状態で既に完全な状態ということができ、そこに「不利益」と称されるものはない。
よって、ここで「婚姻制度を利用していない者(独身者)」の状態について、「不利益」などと論じようとしているのであれば、誤りである。
「そのことによりいわゆるアイデンティティの喪失感を抱き、人としての存在を否定されたとの思いに至ってしまうことは容易に理解できることである。」とある。
まず、婚姻制度(男女二人一組)は「性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いをする制度ではないし、「性愛」に基づいて制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもない。
そのため、婚姻制度(男女二人一組)が「異性愛者と同性愛者」などと「性的指向」と称するものに基づいて法的な「取扱い」を変えているという事実はない。
よって、婚姻制度(男女二人一組)が「異性愛者と同性愛者」などと「性的指向」と称するものに基づいて法的な「取扱い」を変えていることを前提として、「いわゆるアイデンティティの喪失感を抱き、人としての存在を否定されたとの思いに至ってしまうこと」が生じているとの認識は誤りである。
「いわゆるアイデンティティの喪失感」との部分であるが、「アイデンティティ」とは、特定のものをその他のものとの間で区別することを可能とする事柄についていうものである。
そのため、個人を識別する機能や個人を特定する機能にあたるものをいうのであり、法制度としては「氏名」や「マイナンバー」、「生年月日」、「住所」などの個人情報がその役割を果たすものであるといえる。
もし自己が他人と混同された扱いを受けたり、法制度上で記録されている「氏名」や「マイナンバー」、「生年月日」、「住所」などの情報を理由もなく違法に抹消されることがあれば、その不当性を主張するために「アイデンティティ」という言葉で論じることは考えられる。
しかし、「異性愛者と同性愛者」などという「性的指向」と称するものについては、個人の内心における心理的・精神的なものであり、個人を識別する機能や個人を特定する機能を果たすものではないし、個人の身分関係を証明するものでもないため、「アイデンティティ」という言葉に対応するものではない。
そのため、そもそも法制度が「異性愛者と同性愛者」などという「性的指向」と称するものによって、「取扱い」を変えている事実はないことが前提であるが、ここで「異性愛者と同性愛者」などという「性的指向」と称するものに対して「アイデンティティ」という言葉を用いて表現していることも、法律論としては意味の通じるものではなく、妥当でない。
よって、「いわゆるアイデンティティの喪失感」と述べている部分も誤りである。
「人としての存在を否定されたとの思いに至ってしまうことは容易に理解できることである。」とある。
しかし、そもそも「異性愛者」や「同性愛者」などと「性的指向」と称するものに基づいて人を区別して取扱っている法制度は存在しない。
そのため、「取扱い」に「区別」があることを前提として、「人としての存在を否定されたとの思いに至ってしまうことは容易に理解できる」などと述べているとすれば誤りである。
その他、法制度が自らの思い通りに定められていないことに対する不満や憤りの感情(憤慨)については、下記が参考になる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
このように、原告らの主張は、結局のところ、自らの思想、信条、政治的見解等と相容れない内容である本件各行為が行われたことにより、精神的な苦痛を感じたというものであるところ、多数決原理を基礎とする代表民主制を採用している我が国においては、多様な意見を有する国民が、表現の自由、政治活動の自由、選挙権等の権利を行使し、それぞれの立場・方法で国や政府による立法や政策決定過程に参画した上で、最終的には、全国民の代表者として選出された議員により組織される国会において個々の法令が制定されるのであるから、その結果として、ある個人の思想、信条、政治的見解等とは相容れない内容の法令が制定されることは、全国民の意見が一致しているというおよそ想定し難い場面以外では、不可避的に発生する事態である。そうすると、自らの思想、信条、政治的見解等とは相容れない行為が行われたことで精神的苦痛を感じたとしても、そのような精神的苦痛は社会的に受忍しなければならないものというほかない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
国家賠償請求事件 高知地方裁判所 令和6年3月29日 (PDF)
このように、民主主義の下では自らの望む形で法制度が定められていないという事態が生じることは予定されていることであり、これについて述べたとしても、それは憲法上の条文を用いて下位の法令の内容を無効としたり、特定の制度を創設することを国家に対して求めることができるとする根拠となるものではない。
控訴人らは、人として、同じく人である同性パートナーを愛し、家族としての営みを望んでいるにもかかわらず、パートナーが異性でなく、同性であるという理由から、当事者以外の家族の間で、職場において、社会生活において、自身の存在の意義を失うという喪失感に苛まれているのであって(甲B4~9、原審原告番号1、2、4、5及び6の各本人尋問の結果)、個人の尊重に対する意識の高まった現在において、性的指向による区別を理由に、このような扱いを受けるいわれはなく、これは憲法が保護する個人の尊厳にかかわる問題であるということができる。
【筆者】
━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━
この文は、文構造として問題を抱えている。
まず、この文の前半について、主語は「控訴人らは、」であり、述語は「望んでいる」と「苛まれている」の二つである。
そのため、主語と述語の関係で文を分けると、下記のようになる。
◇ 「控訴人らは、人として、同じく人である同性パートナーを愛し、家族としての営みを望んでいる」
◇ (控訴人らは、)「パートナーが異性でなく、同性であるという理由から、当事者以外の家族の間で、職場において、社会生活において、自身の存在の意義を失うという喪失感に苛まれている」
そして、この文は、これらの二つの部分を「にもかかわらず、」で繋いでいる。
この「にもかかわらず、」の意味は、「前に述べた事柄を受けて、それに反する行動をとる意を表す。」ものである。
しかし、「望んでいる」→「にもかかわらず、」→「苛まれている」との文脈は、自然な文章として読み取ることができない。
その理由は、下記の通りである。
この「望んでいる」→「にもかかわらず、」→「苛まれている」という文の構成から見ると、「望んでいる」ことによって起こる状態がまずあり、それに対して「にもかかわらず、」の文言を繋ぐことで、それに反すること状態が生じていることを予見させ、その内容は「苛まれている」状態というのである。
このことから見ると、「望んでいる」ことによって通常は、「苛まれ」ることはないという認識が前提となっていることを意味する。
ただ、その前提となる認識を詳しく見ると、「家族としての営みを望んでいる」ことによって「自身の存在の意義を失うという喪失感に苛まれ」ることはないと考えているということになるが、このことに因果関係を認めることができない。
◇ 「家族としての営みを望んでいる」 →(ならば)→ 「自身の存在の意義を失うという喪失感に苛まれ」ない
憲法は「個人の尊厳」の原理に基づいており、自然人は「個人主義」の下に各々「自律的な個人」として生存していくことを予定している。
そのため、何らの人的結合関係も形成していない「個人」の状態で既に完全な状態である。
そのことから、ここでいう「家族」の意味が、法学的な意味の「家族」であるとしても、社会学的な意味の「家族」であるとしても、何らの人的結合関係も形成していない「個人」の状態が基準(スタンダード)となるのであり、その状態について「自身の存在」が「失われる」だとか、何かを「喪失」するなどという状態にあるとはいえない。
よって、法的な意味としては、この文脈を理解することは不能である。
その他、法的な意味としてではなく、個々人の受け止め方や感想について述べるものであるとすれば、何をすることによって「自身の存在の意義」を感じるかという極めて個人的な内容を述べていることになる。
しかし、そのような事柄を法的な判断の過程で述べることは不適切であるし、それを基にして法的な判断を行うことができるというものではない。
よって、この「望んでいる」→「にもかかわらず、」→「苛まれている」との文脈は、法的に意味の通ったものとして理解することができない。
━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━
「控訴人らは、人として、同じく人である同性パートナーを愛し、家族としての営みを望んでいる」との部分について検討する。
「控訴人らは、人として、」とあるが、「控訴人ら」が「人」であることは、誰もが理解していることであり、ここで「人」であることを強調する意味を見出すことができない。
「人として、同じく人である」とあるが、法的な視点から見れば、これは自然人と自然人との関係を指すものと捉えることができる。
このような自然人と自然人による人的結合関係については、憲法21条1項の「結社の自由」によって保障されることになる。
「同性パートナー」とあるが、これは法律用語ではないため、使う人によってそれぞれ意味するところが異なるものである。
このような言葉は、何らかの思想や信条、宗教的な信仰を抱いていることを前提とした用語であることもあるし、訴訟の当事者の一方が自らの望む結論を導き出すことを目的として前提を先取りするために敢えて用いられているという場合もある。
そのため、法律論として論じる際に、このような言葉を安易に用いてはならない。
「愛し、」とあるが、これは個人の内心におる精神的なものであるため、思想、信条、信仰、感情の一つとして憲法19条の「思想良心の自由」で保障されるものである。
また、「愛」を基にする活動については憲法20条1項前段の「信教の自由」で保障され、「愛」を基にした人的結合関係については憲法21条1項の「結社の自由」で保障されることになる。
「家族としての営みを望んでいる」とある。
この「家族」の意味が社会学的な意味の「家族」であれば、何らかの人的結合関係をいうものと考えられることから、それは憲法21条1項の「結社の自由」によって保障されることになる。
この「家族」の意味が法学的な意味の「家族」であれば、憲法24条2項の「婚姻及び家族」として示されている「家族」であることから、「夫婦」と「親子」による「血縁関係者」の範囲を指すものとなる。
そのため、ここでいう「同性」の自然人と自然人の組み合わせが「親子」や「親子」の関係を基本とした「兄弟」「姉妹」などに当たらないのであれば、「家族」とすることはできない。
「パートナーが異性でなく、同性であるという理由から、当事者以外の家族の間で、職場において、社会生活において、自身の存在の意義を失うという喪失感に苛まれているのであって」との部分について検討する。
「パートナー」とあるが、これは法律用語ではないため、使う人によってそれぞれ意味するところが異なるものである。
他者との関係性を示す言葉には、他にも 「デュオ」、「コンビ」、「バディ」、「ダブルス」、「トリオ」、「相棒」、「仲間」、「ソウルメイト」などの言葉があるが、法的な議論の中では、これらも同様に用いることはできない。
このような言葉は、何らかの思想や信条、宗教的な信仰を抱いていることを前提とした用語であることもあるし、訴訟の当事者の一方が自らの望む結論を導き出すことを目的として前提を先取りするために敢えて用いられているという場合もある。
そのため、法律論として論じる際に、このような言葉を安易に用いてはならない。
「パートナーが異性でなく、同性であるという理由から、」との部分であるが、ここ「パートナー」と称している何らかの関係性を形成するか否かは個々人の自由の範囲の問題である。
そのため、「異性でなく、同性である」との部分についても、個々人が人的結合関係を形成する自由の範囲のことであることから、そもそも「異性」との間で人的結合関係を形成しなければならないなどという前提は存在しておらず、「異性」や「同性」などと性別を取り上げて論じる必要のないものである。
また、そもそも他者との間でそのような関係性を形成しないままに生活している者もいる。
よって、この部分で「異性でなく、同性であるという理由から、」「自身の存在の意義を失うという喪失感に苛まれている」との認識を述べていることは、人的結合関係を形成する自由が憲法21条1項の「結社の自由」で保障されていることを理解していないことによるものか、人は他者との間で人的結合関係を形成しなければならず、また、その他者は「異性」でなければならないなどという特定の価値観を前提とした上で、それとは異なる状態にある者は劣位にあると考えるという特定の価値観を基にして形成された認識ということができる。
しかし、法律論としては、そもそもそのような特定の価値観を支持することを前提として、その価値観に沿うか否かという観点から論じることは適切ではない。
憲法は「個人の尊厳」の原理に基づいており、自然人は「個人主義」の下に各々「自律的な個人」として生存していくことを予定していることから、何らの人的結合関係も形成していない状態で既に完全な状態である。
そのため、法的な観点から見れば、何らの人的結合関係も形成していないとしても、そのことについて何かが欠落しているなどということはないし、不当に不利に扱われているということもない。
そのような中、個人が他者との間で人的結合関係を形成・維持・解消することは自由であり、そのことが否定されるということはない。
よって、「同性」との人的結合関係を形成する者が、自身が、人は他者との間で人的結合関係を形成しなければならず、また、その他者は「異性」でなければならないという特定の価値観を抱いていることにより、その状態とは異なる状態にあることを理由として「自身の存在の意義を失うという喪失感に苛まれている」としても、それは個人の抱いている特定の価値観を前提とする主張に過ぎないということができる。
これを法的な視点から客観的に考えると、「自身の存在の意義を失うという喪失感」と述べていることに対応する意味での何かを失うというようなものを見出すことはできないのであり、法的な問題として取り扱うことのできるものでない。
「個人の尊重に対する意識の高まった現在において、性的指向による区別を理由に、このような扱いを受けるいわれはなく、これは憲法が保護する個人の尊厳にかかわる問題であるということができる。」との部分について検討する。
「個人の尊重に対する意識の高まった現在において、」とある。
しかし、憲法制定時より憲法13条で「すべて国民は、個人として尊重される。」と定められており、この条文の下で運用されていることから、「現在において、」のように、憲法制定からそれまでの間に「個人の尊重」がなされていなかったかのような前提で論じていることは妥当でない。
また、憲法学における「個人の尊重」とは、「全体主義」ではなく「個人主義」に根差すことをいうものである。
そして、「個人の尊重に対する意識の高まった」というのであれば、自然人は「個人主義」の下に各々「自律的な個人」として生存していくことを予定していることについて述べていることになるから、何らの人的結合関係も形成していない状態が基準(スタンダード)となることを意味しているといえる。
そのため、この「個人の尊重」の文言が、個々人が人的結合関係を形成することについての何らかの根拠となることはないし、人的結合関係について定めた特定の制度の創設を国家に対して求めることができるとする理由となるものでもない。
「性的指向による区別を理由に、このような扱いを受けるいわれはなく、」とある。
まず、婚姻制度は「性愛」を保護するための制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いをする制度ではないし、「性愛」に基づいて制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもない。
そのため、婚姻制度を利用することができないという理由は、「男女二人一組」という条件を満たしていないことによるものであり、決して個々人の内心における「性的指向」と称するものが原因となっているわけではない。
そのことから、「性的指向による区別を理由に、」のように、「性的指向」と称するものによって「区別」がなされていることを前提として論じていることは誤りである。
「このような扱いを受けるいわれはなく、」との部分についても、婚姻制度を利用することができていない理由は、「男女二人一組」の条件を満たしていないことによるものであり、「性的指向」と称するものが原因となっているものではない。
この点は、法律上の要件に適合しているか否かの問題であるにもかかわらず、あたかも個々人の内心が原因となって「区別」が行われているかのように考えてしまっている点で、法律上の要件を満たした場合に一定の効果を生じさせることとするという法律の条文を適用する仕組みについての事実を的確に認知することができていないといえる。(認知の歪み)
「これは憲法が保護する個人の尊厳にかかわる問題であるということができる。」とある。
まず、憲法は「個人の尊厳」の原理に基づいて形成されている。
ただ、「個人の尊厳」という文言そのものは、憲法24条2項に定められており、これは憲法24条2項の「婚姻及び家族」の枠組みの「要請」に従って立法された法律上の「婚姻及び家族」の制度に対してのみ適用されるものである。
そのため、この憲法24条2項の「個人の尊厳」の文言が、「婚姻及び家族」の枠組みに当てはまらない場合に対してまで適用されるかのような前提の下に「憲法が保護する個人の尊厳にかかわる問題」と述べているとすれば誤りである。
また、この意味を憲法13条の「個人の尊重」について述べていると考えるしても、憲法13条では「個人として尊重される。」と書かれているが、「個人の尊厳」という文言が使われているわけではない。
そのため、「個人の尊厳」が憲法上の具体的な権利として定められているかのような説明となっていることは誤りである。
他にも、「個人の尊厳にかかわる問題である」とあるが、「個人の尊厳」とは、権利や義務を結び付けることのできる法的な主体としての地位をいうものであるから、これに「かかわる問題」とは、「権利能力」や「意思能力」、「行為能力」の喪失や制限に「かかわる問題」について論じようとしていることになる。
しかし、ある者が婚姻制度を利用していない状態にあるとしても、その者は物や動物のように扱われているわけではないし、奴隷のように売買される対象となっているわけではないし、人が集団の中の一部として扱われるなど「個人」が法的な主体として認められておらず、「権利能力」を有しない存在となっているわけでもない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
民法は我々の生活関係を権利と義務に分解して規定し、規律するが、この権利及び義務の帰属主体となりうる資格を権利能力という。民法は、権利能力はあらゆる自然人が平等に有するとしているが、このことは近代法によって確立された原則であり、近代法が発達する以前の時代、すなわち奴隷制が存在した時代や、封建時代には、人によっては権利能力を認められない自然人も存在したのである。人は権利能力があって初めて法律的に自由な経済活動が可能となるのであり、その権利能力を自然人に平等に認めるのは、憲法の要請でもある。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第15課 民法―権利義務の主体(自然人その1) (下線・太字は筆者)
【動画】〔独学〕司法試験・予備試験合格講座 民法(基本知識・論証パターン編)第8講:権利能力と胎児 〔2021年版・民法改正対応済み〕 2021/05/28
【動画】【行政書士試験対策】権利能力//権利・義務の主体となれるのは? 2023/03/25
【動画】民法本論1 01権利能力 2011/04/11
【動画】2021応用インプット講座 民法5(総則5 権利能力) 2020/11/20
また、ある者が婚姻制度を利用していない状態にあるとしても、それは婚姻制度を利用していないことが原因となって「意思能力」を認められないとか、否定されるというわけではない。
他にも、ある者が婚姻制度を利用していない状態にあるとしても、それは婚姻制度を利用していないことが原因となって「行為能力」が制限されるというわけでもない。
そのため、婚姻制度を利用していないことが原因となって「権利能力」を喪失したり、「意思能力」を否定されたり、「行為能力」が制限されるということはないことから、そのことが「個人の尊厳」に「かかわる問題である」とはいえない。
よって、ここで「個人の尊厳にかかわる問題であるということができる。」と述べていることは誤りである。
したがって、性的指向及び同性間の婚姻の自由は、憲法上の権利として保障される人格権の一内容を構成し得る重要な法的利益として、後記のとおり、本件規定が同性婚を許していないことが憲法24条の定める立法裁量の範囲を超えるものであるか否かの検討に当たって考慮すべき事項であると考えられる。
【筆者】
「性的指向及び同性間の婚姻の自由は、憲法上の権利として保障される人格権の一内容を構成し得る重要な法的利益として、」との部分について検討する。
まず、「性的指向及び同性間の婚姻の自由」について検討する。
「性的指向」とは、「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかに関するものであり、個人の内心における精神的なものである。
そのため、これは「内心の自由」として憲法19条の「思想良心の自由」によって保障されるものである。
よって、これについて「憲法上の権利として保障される人格権の一内容を構成し得る」のように、「人格権」として説明しようとしていることは誤りである。
ここでいう「同性間の婚姻」の意味が「同性間の人的結合関係」を形成することを指している場合には、それは「国家からの自由」という「自由権」の性質として憲法21条1項の「結社の自由」によって保障されるものである。
そのため、その「同性間の人的結合関係」を形成する「自由」について、「憲法上の権利として保障される人格権の一内容を構成し得る」のように、「人格権」として説明していることは誤りである。
ここでいう「同性間の婚姻」の意味が「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを指している場合は、そもそも「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることができるかという部分から検討することが必要である。
「婚姻」は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度である。
具体的には、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」を目的として、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす「一人の男性」と「一人の女性」の間を「貞操義務」などの一定の形式で法的に結び付け、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によってそれらの目的の達成を目指す仕組みとなっている。
「同性間の人的結合関係」については、この趣旨を満たすものではないことから、「婚姻」の中に含めることはできない。
そのため、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることができるかのような前提で論じていることは誤りとなる。
また、「婚姻の自由」(『再婚禁止期間制度訴訟大法廷判決』の述べている『婚姻をするについての自由』にあたるもの)についても、憲法24条1項が「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めていることを前提として、その憲法24条の「婚姻」の枠組みの「要請」に従って定められている法律上の婚姻制度を利用するか否かに関する自由をいうものである。
そのため、「婚姻の自由」(憲法24条1項を基に導かれている『婚姻をするについての自由』)には、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを求めることができるとする根拠となるものではない。
よって、この「婚姻の自由」(婚姻をするについての自由)を理由として「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることが可能であるかのように述べているのであれば、それも誤りである。
また、その「婚姻をするについての自由」とは、「再婚禁止期間制度訴訟大法廷判決」で述べられているように、憲法24条1項を解釈することにより導かれているものであることから、「憲法上の権利として保障される人格権の一内容を構成し得る」のように、「人格権」として説明しようとしていることは根拠を欠くものであり、妥当でない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
……(略)……また,同条1項は,「婚姻は,両性の合意のみに基いて成立し,夫婦が同等の権利を有することを基本として,相互の協力により,維持されなければならない。」と規定しており,婚姻をするかどうか,いつ誰と婚姻をするかについては,当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたものと解される。婚姻は,これにより,配偶者の相続権(民法890条)や夫婦間の子が嫡出子となること(同法772条1項等)などの重要な法律上の効果が与えられるものとされているほか,近年家族等に関する国民の意識の多様化が指摘されつつも,国民の中にはなお法律婚を尊重する意識が幅広く浸透していると考えられることをも併せ考慮すると,上記のような婚姻をするについての自由は,憲法24条1項の規定の趣旨に照らし,十分尊重に値するものと解することができる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
次に、「憲法上の権利として保障される人格権の一内容を構成し得る重要な法的利益として、」について検討する。
ここでは「憲法上の権利として保障される人格権の一内容を構成し得る」とあるが、「憲法上の権利として保障される」のあれば、「(2)ウ」の第二段落の第二文で「憲法13条が人格権として性的指向及び同性間の婚姻の自由を保障しているものということは直ちにできず、本件規定が憲法13条に違反すると認めることはできない。」と述べている部分と矛盾するものとなっている。
◇ 「(2)ウ」
「憲法13条が人格権として性的指向及び同性間の婚姻の自由を保障しているものということは直ちにできず、本件規定が憲法13条に違反すると認めることはできない。」
◇ この文
「性的指向及び同性間の婚姻の自由は、憲法上の権利として保障される人格権の一内容を構成し得る重要な法的利益」
「(2)ウ」のように「憲法13条が人格権として性的指向及び同性間の婚姻の自由を保障しているものということは直ちにできず、本件規定が憲法13条に違反すると認めることはできない。」というのであれば、「憲法上の権利として保障」されていないことになる。
すると、この文が「憲法上の権利として保障される」との文言を用いて「憲法上の権利として保障される人格権の一内容を構成し得る重要な法的利益」と述べている部分とは矛盾する。
逆に、この文が「憲法上の権利として保障される人格権の一内容を構成し得る重要な法的利益」であれば、「憲法13条に違反する」はずである。
すると、「(2)ウ」で「本件規定が憲法13条に違反すると認めることはできない。」と述べている部分とは矛盾する。
このような矛盾が生じている原因を検討する。
まず、下記の違いを押さえる必要がある。
◇ 謝罪広告等請求事件(昭和63年2月16日)
「氏名は、」「人格権の一内容を構成するもの」であるから、「人は、他人からその氏名を正確に呼称されることについて、不法行為法上の保護を受けうる人格的な利益を有する」
◇ 夫婦同姓制度訴訟大法廷判決
「氏名は、」「人格権の一内容を構成するもの」であるが、「氏は,」「法律がその具体的な内容を規律しているものであるから,」「具体的な法制度を離れて,氏が変更されること自体を捉えて直ちに人格権を侵害し,違憲であるか否かを論ずることは相当ではない。」
「謝罪広告等請求事件」の場合は、「氏名は、」「人格権の一内容を構成するもの」であることを理由に、「氏名を正確に呼称されること」は「不法行為法上の保護を受けうる人格的な利益」であるとする論理である。
それに対して、「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」では、「氏名は、」「人格権の一内容を構成するもの」であるが、「氏が変更されること」については「具体的な法制度」の内部の問題であるから、その仕組みについて「直ちに人格権を侵害し,違憲であるか否かを論ずることは相当ではない。」として、結論においても「人格権の一内容であるとはいえない。」とする論理である。
この両判決の内容は、「氏名は、」「人格権の一内容を構成するもの」との部分までは共通しているものの、一方は、「具体的な制度」の存在を前提としてそれを基に対外的な意味で「人格権」が形成されることを認めるものであるが、もう一方は、「具体的な制度」の内部の仕組みの問題であってその仕組みそのものを取り上げて直ちに「人格権」を侵害するか否かを論じること相当ではないとし、結論においても「人格権の一内容であるとはいえない。」とするものである。
これらは、まったく性質を異にするものである。
この札幌高裁判決では、「人格権の一内容を構成し得る」や「人格権の一内容を構成し得る重要な法的利益」と述べながら、「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」を示している。
しかし、「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」では、「謝罪広告等請求事件」において「氏名は、」「人格権の一内容を構成するもの」であることを理由に「氏名を正確に呼称されること」は「不法行為法上の保護を受けうる人格的な利益」と示したこととは異なり、「氏が変更されること自体」については、結論として「憲法上の権利として保障される人格権の一内容であるとはいえない。」と述べるものである。
そのため、「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」を前提に考えると、「具体的な法制度」の仕組みそのものについては、「人格権の一内容を構成するもの」とは述べていないのであり、この札幌高裁判決が「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」を取り上げる形で「人格権の一内容を構成し得る」や「人格権の一内容を構成し得る重要な法的利益」と述べていることは、「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」の論理そのもの正確に読み解くことができていないことによって生じたものと言わざるを得ない。
その他にも、「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」は、「氏」について論じているものであることから、その「氏」についての「具体的な制度」の存在を前提とするものであるが、この札幌高裁判決では「性的指向」という個人が「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかという個々人の内心における精神的なものを論じるものであることから、「具体的な制度」の存在を前提とするものではない。
よって、このような「具体的な制度」の存在を前提としないものについては、「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」だけでなく、「謝罪広告等請求事件」において「人格権の一内容を構成するもの」であることを理由に、「不法行為法上の保護を受けうる人格的な利益」を認める論理を導く部分とも整合しないものであり、このような「人格権の一内容を構成し得る」や「人格権の一内容を構成し得る重要な法的利益」が存在することを前提として論じていることそのものが、これまでの判例の論理とはまったく次元の異なる内容を述べるものであり、それらの判例を前提として論じる試みそのものが誤りである。
「本件規定が同性婚を許していないことが憲法24条の定める立法裁量の範囲を超えるものであるか否かの検討に当たって考慮すべき事項であると考えられる。」との部分について検討する。
「本件規定が同性婚を許していない」とある。
この「同性婚」の意味が「同性間の人的結合関係」を形成することを指しているのであれば、それは憲法21条1項の「結社の自由」で保障されているものである。
「本件規定」はそれを規制するものではないことから、「同性間の人的結合関係」を形成することを「許していない」との認識は誤りとなる。
この「同性婚」の意味が「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを指しているのであれば、「本件規定」は「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを定めていないということができる。
ただ、これは法制度が定められているか否かの問題であるから、むやみに「許す・許さない」という意味での「許していない」という表現を用いることは適切であるとは思われない。
このような表現は、別の個所の「不利益」などの文言と相まって、法制度の性質について客観的な視点から説明するものとして用いられる言葉遣いではなく、訴訟の当事者の一方の見方や意見、感じ方に与する形で論じるものとなっていることが考えられる。
そのため、敢えてこのような表現を用いて論じていることは、公的な性質を持つ裁判所の立場で用いる言葉の選択として適切なものであるとはいえない。
「憲法24条の定める立法裁量の範囲を超えるものであるか否かの検討に当たって考慮すべき事項であると考えられる。」とある。
しかし、憲法24条の解釈で問われるのは、憲法24条の「婚姻」の枠組みが「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とする法律を立法することを「要請」しているか否かである。
憲法24条の「婚姻」の枠組みがこれを「要請」しているのであればその制度が存在しないことは違憲となり、憲法24条の「婚姻」の枠組みがこれを「要請」していないのであればその制度が存在しないことは合憲というものである。
これは憲法24条の「婚姻」の枠組みが「要請」している場合には、その法律を定めないという選択をすることはできないことから、国会に「立法裁量」は存在しておらず、「立法裁量の範囲を超えるものであるか否か」を検討する前提にない。
逆に、憲法24条の「婚姻」の枠組みが「要請」していないのであれば、そもそも国会に対して立法することが義務付けられているわけではないことから、やはり「立法裁量の範囲を超えるものであるか否か」を検討する前提にない。
そのため、いずれにせよ、この憲法24条の「婚姻」の枠組みが「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とする法律を立法することを「要請」しているか否かの問題に対して、「立法裁量の範囲を超えるものであるか否か」という問題は関わらないものである。
よって、この札幌高裁判決の事案について、「立法裁量の範囲を超えるものであるか否か」を検討することによって結論を導き出すことができるかのように述べていることは誤りとなる。
この段落の「後記のとおり、本件規定が同性婚を許していないことが憲法24条の定める立法裁量の範囲を超えるものであるか否かの検討に当たって考慮すべき事項であると考えられる。」という言い回しは、「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」の文に重ねる形で用いようとしているものと考えられる。
灰色で潰した部分が文言が重なる部分である。
夫婦同姓制度訴訟大法廷判決
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
これらの婚姻前に築いた個人の信用,評価,名誉感情等を婚姻後も維持する利益等は,憲法上の権利として保障される人格権の一内容であるとまではいえないものの,後記のとおり,氏を含めた婚姻及び家族に関する法制度の在り方を検討するに当たって考慮すべき人格的利益であるとはいえるのであり,憲法24条の認める立法裁量の範囲を超えるものであるか否かの検討に当たって考慮すべき事項であると考えられる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
損害賠償請求事件 最高裁判所大法廷 平成27年12月16日 (PDF)
しかし、その「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」では、「憲法24条の認める立法裁量の範囲を超えるものであるか否かの検討に当たって考慮すべき事項であると考えられる。」のように、「認める」と書かれているのに対して、この札幌高裁判決では、「定める」となっており、文言が異なる。
◇ 「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」
「憲法24条の認める立法裁量の範囲」
◇ この札幌高裁判決
「憲法24条の定める立法裁量の範囲」
この点、憲法24条は「婚姻及び家族」について規定しており、その「婚姻及び家族」の枠組みの「要請」に従って立法された法律上の「婚姻及び家族」の制度の内容に対して立法裁量の限界を画することを規定しているものである。
このため、立法裁量の限界を画するということは、その前提として立法裁量の余地があることを意味し、その趣旨より「立法裁量の範囲」を「認める」ものであると理解することが妥当といえる。
よって、「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」の「認める」の表現は正確であると考える。
これに対して、この札幌高裁判決では、「憲法24条の定める立法裁量の範囲」となっており、あたかも「憲法24条」が国会の「立法裁量」について積極的に定めた規定であるかのような印象を受ける言葉の使い方となっている。
この札幌高裁判決では、結論として「本件規定」である婚姻制度について違憲であるとの判断を行っているため、この「憲法24条」が国会に対して積極的に「立法裁量」を認めているという前提が存在した方が、違憲であるとの結論を導くために有利であると考え、この点を「定める」という文言を用いようとしているように見受けられる。
これは、「憲法24条の認める立法裁量の範囲」という文言では、「憲法24条」が「立法裁量の範囲」として認めていない部分が存在することを前提とすることになり、それが「婚姻及び家族」の枠組みが「夫婦」と「親子」による「血縁関係者」の範囲に限られており、この範囲を超えて「同性間の人的結合関係」をも「婚姻」の中に含めることは「立法裁量の範囲」として認められていないことについての指摘を回避したいとの思惑を感じさせるものとなっている。
この点で、この札幌高裁判決が「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」の言い回しを用いながらその文言を変更していることは、自らの望む結論を導き出すために、前提として用いている判決の文面の意味を恣意的に変更する意図が含まれていることが考えられ、不適切である。
3 本件規定が憲法24条に違反する旨の主張について(争点⑴関係)
(1) 控訴人らは、本件規定が、異性間で婚姻をすることができると定めているのに、同性間で婚姻することを許していないことは、実質的に婚姻の自由を侵害するものであり、また、国会の立法裁量の存在を考慮したとしても、本件規定が個人の尊厳を侵害するものとして、憲法24条に違反する旨をいうものである。
【筆者】
この段落は控訴人らの主張をまとめたものなので、解説はしない。
(2)ア 憲法24条は、1項において「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」と規定しているところ、これは、両性の間で、つまり男女の間で、婚姻をするかどうか、いつ誰と婚姻をするかについては、当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたものと解される(再婚禁止期間制度訴訟大法廷判決参照)。
【筆者】
ここで示された判決は、下記の通りである。
(灰色で潰した部分が、上記の記述と文面が重なる部分である。)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ところで,婚姻及び家族に関する事項は,国の伝統や国民感情を含めた社会状況における種々の要因を踏まえつつ,それぞれの時代における夫婦や親子関係についての全体の規律を見据えた総合的な判断を行うことによって定められるべきものである。したがって,その内容の詳細については,憲法が一義的に定めるのではなく,法律によってこれを具体化することがふさわしいものと考えられる。憲法24条2項は,このような観点から,婚姻及び家族に関する事項について,具体的な制度の構築を第一次的には国会の合理的な立法裁量に委ねるとともに,その立法に当たっては,個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきであるとする要請,指針を示すことによって,その裁量の限界を画したものといえる。また,同条1項は,「婚姻は,両性の合意のみに基いて成立し,夫婦が同等の権利を有することを基本として,相互の協力により,維持されなければならない。」と規定しており,婚姻をするかどうか,いつ誰と婚姻をするかについては,当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたものと解される。婚姻は,これにより,配偶者の相続権(民法890条)や夫婦間の子が嫡出子となること(同法772条1項等)などの重要な法律上の効果が与えられるものとされているほか,近年家族等に関する国民の意識の多様化が指摘されつつも,国民の中にはなお法律婚を尊重する意識が幅広く浸透していると考えられることをも併せ考慮すると,上記のような婚姻をするについての自由は,憲法24条1項の規定の趣旨に照らし,十分尊重に値するものと解することができる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(PDF)
上記では、参照として「再婚禁止期間制度訴訟大法廷判決」を挙げるのみであるが、この文の内容そのものは「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」の文面の方により近いものとなっている。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2(1) 憲法24条は,1項において「婚姻は,両性の合意のみに基いて成立し,夫婦が同等の権利を有することを基本として,相互の協力により,維持されなければならない。」と規定しているところ,これは,婚姻をするかどうか,いつ誰と婚姻をするかについては,当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたものと解される。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
この札幌高裁判決の文面では「これは、両性の間で、つまり男女の間で、」と書かれているが、「再婚禁止期間制度訴訟大法廷判決」の中にそのような記述はない。
憲法24条が「婚姻」を規定しており、「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めており、「再婚禁止期間制度訴訟大法廷判決」の内容もその憲法24条の「婚姻」について「両性の間で、つまり男女の間」で成立するものであることを前提として、憲法24条1項の趣旨について説明していることは確かであるとしても、この札幌高裁判決の中で「(再婚禁止期間制度訴訟大法廷判決参照)」のように「参照」と示してほとんどの部分で同一の文面で引用しているのであるから、そこで「再婚禁止期間制度訴訟大法廷判決」の中で書かれていない内容を勝手に加えて示すことは不適切である。
このような形でもともとの判決文の内容に付け加える形で表現することは、法律の専門家や、この家族法の法分野に精通した者であれば、「再婚禁止期間制度訴訟大法廷判決」と同じ文面で書かれておらず、引用が不正確であり、この「これは、両性の間で、つまり男女の間で、」との部分は「再婚禁止期間制度訴訟大法廷判決」の内容についてこの札幌高裁判決を書いた裁判官が読み解いた内容であることに気付くこともあるかもしれないが、法律の初学者や法律の深い知識を持ち合わせていない一般人がそこまで注意深く読み取ることは困難であり、その影響で読み手を誤った理解へと導くものとなりやすいため不適切である。
「再婚禁止期間制度訴訟大法廷判決」の内容について「これは、両性の間で、つまり男女の間で、」と説明するのであれば、「再婚禁止期間制度訴訟大法廷判決」の文面をそのまま引用した後の段階で、その意味を解説する場所を別に設けて表現することが適切であり、引用している文面に(カッコ)を付けるなどして読み手が分かるようにする配慮もないままに勝手に文を加える形で表現するべきものではない。
この段落に関係する内容について、国(行政府)は、下記のように説明している。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
したがって、憲法24条1項は、婚姻について異性間の人的結合関係のみを対象としており、「婚姻をするかどうか、いつ誰と婚姻をするか」を当事者で自由に意思決定し、故なくこれが妨げられないという意味における「婚姻をするについての自由」は、異性間の人的結合関係を対象とする婚姻についてのみ保障されていると解するのが相当である。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【東京二次・第9回】被告第7準備書面 令和5年9月28日 PDF
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
また,前記2で述べたとおり,婚姻の法的効果(例えば,民法の規定に基づく,夫婦財産制,同居・協力・扶助の義務,財産分与,相続,離婚の制限,嫡出推定に基づく親子関係の発生,姻族の発生,戸籍法の規定に基づく公証等)を享受する利益や婚姻をすることについての自由は,憲法の定める婚姻を具体化する法律(本件規定)に基づく制度によって初めて個人に与えられる,あるいはそれを前提とした自由であり,生来的,自然権的な権利又は利益,人が当然に享受すべき権利又は利益ということはできないのであるから,異性間における婚姻の効果を享受する利益や婚姻の自由と同性間のそれらとの間には,憲法を含めた我が国の法制上,本質的な差異があるものと解さざるを得ない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【九州・第6回】被告第4準備書面 令和3年10月29日 PDF (P13)
本件規定は、憲法24条を受け、両性つまり異性間の婚姻を定めたものと解されている。したがって、この点では本件規定が憲法24条1項の趣旨に沿わないなどと評価することはできない。ある法制度の内容により婚姻をすることが制約されることになっていることについては、婚姻及び家族に関する法制度の内容を定めるに当たっての国会の立法裁量の範囲を超えるものであるか否かの検討に当たって考慮すべき事項であると考えられる(夫婦同姓制度訴訟大法廷判決参照)。
【筆者】
「本件規定は、憲法24条を受け、両性つまり異性間の婚姻を定めたものと解されている。」との記載がある。
「本件規定は、憲法24条を受け、」との部分について検討する。
「本件規定」は、「憲法24条」が「婚姻」について規定しており、「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めていることを前提に、その「婚姻」の枠組みの「要請」に従って制定されているものである。
この「憲法24条」の「婚姻」は、法令として定められているものである。
そのため、宗教上の婚姻を指すものではないし、特定の地域でのみ婚姻と称して通用していた何らかの人的結合関係などを指すものでもない。
それらとは区別する意味で設けられている法学的な意味の法制度としての「婚姻」を指すものである。
そのことから、この憲法24条の「婚姻」は、法制度を前提としない何らかの人的結合関係を指しているものではない。
そして、「憲法24条」が「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めていることから、「憲法24条」が「要請」する内容は、法律上で一夫一婦制(男女二人一組)の婚姻制度を立法することである。
よって、「憲法24条を受け」て法律上の具体的な制度を定めると、当然、婚姻制度の内容は「男女二人一組」を対象とした形となる。
この意味で、「本件規定は、憲法24条を受け、両性つまり異性間の婚姻を定めたものと解されている。」との理解はその通りである。
「両性つまり異性間の婚姻」との部分について検討する。
「婚姻」とは、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」を目的として、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす「一人の男性」と「一人の女性」を選び出し、その間に「貞操義務」を設けるなど一定の形式で法的に結び付け、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によってそれらの目的の達成を目指す枠組みである。
そのため、「婚姻」であれば、「両性つまり異性間」のものしか存在しておらず、これを満たさない人的結合関係で「婚姻」を成立させることはできない。
そのことから、ここで「両性つまり異性間の婚姻」と述べていることは、「両性つまり異性間」という「男女」を指す言葉と、「婚姻」という「男女」によって構成される概念の言葉とを同時に用いるものとなっており、文法上は同義反復となるため誤用である。
また、この「両性つまり異性間の婚姻」との表現は、「婚姻」そのものが「両性つまり異性間」で成立する概念であることを示す意味で用いているとすれば意味は通じるが、「両性つまり異性間の婚姻」に対する形でそれ以外の「婚姻」というもの(例えば『同性間の婚姻』と称するもの)が成立する余地があることを前提として敢えて「両性つまり異性間の婚姻」と述べているとすれば誤った理解に基づく表現ということになる。
「したがって、この点では本件規定が憲法24条1項の趣旨に沿わないなどと評価することはできない。」との記載がある。
これについては、その通りである。
国(行政府)は下記のように述べている。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ア しかしながら、法の解釈に際し、文言の日本語としての意味や文法が重視・尊重されなければならず、文言からかけ離れた解釈が許されないのは当然であるところ、これまで繰り返し述べているとおり、憲法24条1項は、「両性」及び「夫婦」という文言を用いており、一般に、「両性」とは、両方の性、男性と女性又は二つの異なった性を意味し、「夫婦」とは、夫と妻又は適法の婚姻をした男女の身分を意味するものとされている(新村出編・広辞苑第7版2526及び2095ページ)ことからすると、同項にいう「夫婦」や「両性」もこれと同義とみるべきであるから、憲法は、「両性」の一方を欠き当事者双方の性別が同一である場合に婚姻を成立させることをそもそも想定していないというべきである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【東京二次・第9回】被告第7準備書面 令和5年9月28日 PDF
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
他方、同条2項は、婚姻等に関する事項について具体的な制度を構築するに当たっての立法上の要請及び指針を示したものであるが、上記のとおり、婚姻の成立については、同条1項により、両性の合意のみに基づいて成立する旨が明らかにされていることから、婚姻の成立要件等を定める法律は、かかる同条1項の規定に則した内容でなければならない。そのため、婚姻等に関する事項について立法上の要請及び指針を示した同条2項においては、同条1項の内容も踏まえ、配偶者の選択ないし婚姻等に関する法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならないとしたものである(憲法24条2項における配偶者の選択とは婚姻の相手の選択であるから、それについて、法律が個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならないということは、婚姻が当事者の自由な合意のみによって成立すべきことを意味し、同条1項の規定と同趣旨であると解されている(佐藤功「憲法(上)[新版]」414ページ。乙第33号証))。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【東京一次・第1回】控訴答弁書 令和5年6月23日 PDF
「ある法制度の内容により婚姻をすることが制約されることになっていることについては、婚姻及び家族に関する法制度の内容を定めるに当たっての国会の立法裁量の範囲を超えるものであるか否かの検討に当たって考慮すべき事項であると考えられる(…)。」(カッコ内省略)との記載がある。
ここで示された判決は、下記の通りである。
(灰色で潰した部分が、上記の記述と文面が重なる部分である。ここでは、この札幌高裁判決の一段落前の部分も灰色で潰した。)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2(1) 憲法24条は,1項において「婚姻は,両性の合意のみに基いて成立し,夫婦が同等の権利を有することを基本として,相互の協力により,維持されなければならない。」と規定しているところ,これは,婚姻をするかどうか,いつ誰と婚姻をするかについては,当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたものと解される。
本件規定は,婚姻の効力の一つとして夫婦が夫又は妻の氏を称することを定めたものであり,婚姻をすることについての直接の制約を定めたものではない。仮に,婚姻及び家族に関する法制度の内容に意に沿わないところがあることを理由として婚姻をしないことを選択した者がいるとしても,これをもって,直ちに上記法制度を定めた法律が婚姻をすることについて憲法24条1項の趣旨に沿わない制約を課したものと評価することはできない。ある法制度の内容により婚姻をすることが事実上制約されることになっていることについては,婚姻及び家族に関する法制度の内容を定めるに当たっての国会の立法裁量の範囲を超えるものであるか否かの検討に当たって考慮すべき事項であると考えられる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
夫婦同姓制度訴訟大法廷判決 (PDF)
この札幌高裁判決では、最高裁判決の「事実上」の文言が抜けている。
このような不正確な引用を行うことは、この判決を書く裁判官が自らの望む結論を導き出すことを意図して、その判決文に示された内容の本来の意味を恣意的に変更しようとすることを引き起こしやすくなる。
そのため、司法判断として判決の内容を引用する際には、このような不正な手続きが行われることを極限まで排除するために、より厳格な形での引用を行うように徹底することが望ましいということができる。
このような不正確な引用によって、もともとの判決文の解釈の過程で示されている規範の意味が曖昧化したり、変更されたり、別の裁判体が判決を積み重ねていくうちに規範の内容が流動化するようなことがあってはならないと考える。
「ある法制度の内容により婚姻をすることが制約されることになっていることについては、」との部分について検討する。
ここで論じているのは「婚姻をすること」とあるように、「婚姻」をすることができるか否かである。
そして、その「婚姻」とは、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」を目的として、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす「一人の男性」と「一人の女性」を選び出し、その間「貞操義務」を設けるなど一定の形式で法的に結び付け、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によってそれらの立法目的の達成を目指す法制度としての枠組みのことである。
また、憲法24条では「婚姻」を規定し、「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めており、これも上記の趣旨と対応するものとなっている。
その婚姻制度を利用することについて、婚姻制度の一部の規定であるここでいう「ある法制度」によって「制約されることになっている」か否かが問われているのである。
しかし、上記のような経緯によって形成されている「婚姻」という概念の中に、その目的との間で整合的な要素を満たさない人的結合関係までをも「婚姻」の中に含めるべきであるとの主張について、それを「婚姻をすること」についての「制約」と考えて論じることはできないことに注意する必要がある。
これは、「婚姻」という概念そのものが「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成するための手段として形成されていることから、一般的・抽象的に「生殖」の営みとの対応関係において定義される「男性」と「女性」の両方を満たすことが内在的に求められており、この意味で機能している「婚姻」という法制度を利用することについての「婚姻をすること」が「制約されることになっている」か否かの問題と、この「男性」と「女性」の両方を満たさない人的結合関係を「婚姻」という法制度の中に含めることができるか否かという問題を「婚姻をすること」に対する「制約」と呼んで説明するか否かの問題は、「婚姻」という枠組みが「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために形成されているという経緯や、その目的を達成するための手段として必要となる要素との整合性、その目的を達成するための手段として機能する枠組みであるか否かという点で根本的な違いがあるからである。
そして、この「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」についても、上記の趣旨で形成されている「男女二人一組」の婚姻制度を利用するか否かについて述べているものであり、その文面で用いられている「ある法制度の内容により婚姻をすることが事実上制約されることになっている」との部分も、「男女二人一組」を枠として形成されている婚姻制度を利用することが「事実上制約されることになっている」か否かが問われており、これを「男性」と「女性」の両方を満たさない人的結合関係が「婚姻」の中に含まれていないことについてまで「制約」と呼んで、それを憲法24条1項の趣旨との間で審査することができるとする意味まで含む形で述べられているものではない。
そのことから、この札幌高裁判決の中で「婚姻」という概念そのものや憲法24条の「婚姻」の中に「同性間の人的結合関係」を含めるべきであるとの主張を取り扱う中においては、そもそも憲法24条が「婚姻」について規定し、「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めており、それに基づいて「婚姻」が「男女二人一組」の枠組みであることを前提として判断されている「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」の中で述べられた婚姻制度(男女二人一組)を利用することができるか否かに関わる「婚姻をすることが制約されることになっている」か否かについての文面を持ち出して論じることができるというものではない。
よって、この札幌高裁判決で問われている論点に対して、この「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」で示された文を用いて論じようとしていること自体が誤りである。
「婚姻及び家族に関する法制度の内容を定めるに当たっての国会の立法裁量の範囲を超えるものであるか否かの検討に当たって考慮すべき事項であると考えられる」との部分について検討する。
ここでいう「婚姻及び家族に関する法制度」とは、憲法24条2項の「婚姻及び家族」の枠組みの「要請」に従って立法される法律上の具体的な制度のことである。
憲法24条2項の「婚姻及び家族」とは、「夫婦」と「親子」による「血縁関係者」の範囲を指すものであり、これを定めた制度の内容について「国会」は「立法裁量」を有しているといえる。
しかし、この「夫婦」と「親子」による「血縁関係者」の範囲を超える人的結合関係を「婚姻及び家族」の中に含めるという権限は、「国会」であっても「立法裁量」として有しているわけではない。
そして、憲法24条が「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めており、この枠組みによって立法目的の達成を目指すことを「要請」するものであることから、ここでいう「婚姻」についても「男女二人一組」であることを前提とするものであり、この文が「国会の立法裁量の範囲」と述べている部分についても、この「男女二人一組」の枠組みを前提として形成されている「婚姻及び家族に関する法制度」についての「国会の立法裁量の範囲」を述べるものである。
そのため、この「男女二人一組」を満たさない人的結合関係を「婚姻」の中に含めることについてまで「国会の立法裁量の範囲」の中にあることを前提として述べられているものではない。
よって、この「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」の判断の射程が、「男女二人一組」によって形成されている「婚姻」という枠組みそのものを改変することまでをも「国会の立法裁量の範囲」に含まれるかのような前提で論じることはできないのであり、この札幌高裁判決の中で、婚姻」という概念そのものや、憲法24条の「婚姻」の中に「同性間の人的結合関係」を含めるべきであるとの主張を取り扱う中において、この文面を持ち出して論じていること自体が誤っている。
「国会の立法裁量の範囲を超えるものであるか否かの検討」とある。
しかし、この憲法24条の論点で問われているのは、憲法24条の「婚姻」の枠組みが「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とする法律の立法を「要請」しているか否かである。
これは、憲法24条の「婚姻」の枠組みが「要請」しているのであればその制度がないことは違憲であり、「要請」していないのであればその制度がないことは合憲というものである。
そして、憲法24条の「婚姻」の枠組みが「要請」しているのであれば、その制度を立法しないという選択をすることはできないことから、国会に「立法裁量」は存在しておらず、「国会の立法裁量の範囲を超えるものであるか否か」を判断する余地はない。
逆に、憲法24条の「婚姻」の枠組みが「要請」していないのであれば、その制度を立法することが国会に対して義務付けられているわけではないため、「国会の立法裁量の範囲を超えるものであるか否か」を判断する余地もない。
そのため、この憲法24条の論点において「国会の立法裁量の範囲を超えるものであるか否か」を「検討」する前提にないのであり、ここで「国会の立法裁量の範囲を超えるものであるか否か」を「検討」することによって結論が導き出される問題であるかのように考え、この「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」の文面を引用して論じていることそのものが誤りである。
イ 憲法24条は、2項において「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。」と規定している。
婚姻及び家族に関する事項は、関連する法制度においてその具体的内容が定められていくものであることから、当該法制度の制度設計が重要な意味を持つものであるところ、憲法24条2項は、具体的な制度の構築を第一次的には国会の合理的な立法裁量に委ねるとともに、その立法に当たっては、同条1項も前提としつつ、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきであるとする要請、指針を示すことによって、その裁量の限界を画したものといえる。
そして、憲法24条が、本質的に様々な要素を検討して行われるべき立法作用に対してあえて立法上の要請、指針を明示していることからすると、その要請、指針は、単に、憲法上の権利として保障される人格権を不当に侵害するものでなく、かつ、両性の形式的な平等が保たれた内容の法律が制定されればそれで足りるというものではないのであって、憲法上直接保障された権利とまではいえない人格的利益をも尊重すべきこと、両性の実質的な平等が保たれるように図ること、婚姻制度の内容により婚姻をすることが事実上不当に制約されることのないように図ること等についても十分に配慮した法律の制定を求めるものであり、この点でも立法裁量を限定する指針を与えるものといえる(夫婦同姓制度訴訟大法廷判決参照)。
【筆者】
ここで示された判決は、下記の通りである。
(灰色で潰した部分が、上記の記述と文面が重なる部分である。)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 憲法24条は,2項において「配偶者の選択,財産権,相続,住居の選定,離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては,法律は,個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して,制定されなければならない。」と規定している。
婚姻及び家族に関する事項は,関連する法制度においてその具体的内容が定められていくものであることから,当該法制度の制度設計が重要な意味を持つものであるところ,憲法24条2項は,具体的な制度の構築を第一次的には国会の合理的な立法裁量に委ねるとともに,その立法に当たっては,同条1項も前提としつつ,個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきであるとする要請,指針を示すことによって,その裁量の限界を画したものといえる。
そして,憲法24条が,本質的に様々な要素を検討して行われるべき立法作用に対してあえて立法上の要請,指針を明示していることからすると,その要請,指針は,単に,憲法上の権利として保障される人格権を不当に侵害するものでなく,かつ,両性の形式的な平等が保たれた内容の法律が制定されればそれで足りるというものではないのであって,憲法上直接保障された権利とまではいえない人格的利益をも尊重すべきこと,両性の実質的な平等が保たれるように図ること,婚姻制度の内容により婚姻をすることが事実上不当に制約されることのないように図ること等についても十分に配慮した法律の制定を求めるものであり,この点でも立法裁量に限定的な指針を与えるものといえる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(PDF)
最後の部分で、「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」では「限定的な指針」となっているにもかかわらず、この札幌高裁判決では「限定する指針」に変えられており、引用を誤っている。
◇ 夫婦同姓制度訴訟大法廷判決
「この点でも立法裁量に限定的な指針を与えるものといえる。」
◇ 札幌高裁判決
「この点でも立法裁量を限定する指針を与えるものといえる」
これにより、「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」で示された内容の意味を変えるものとなっている。
しかし、司法権を行使するにあたっては、その事件を担当している裁判官の個人的な思いや恣意的な判断によって内容が歪められるようなことがあってはならない。
この札幌高裁判決が最高裁判決に示された文面を正確に引用せず、文面を歪めて利用している背景に、最高裁判決で前提となっている事柄を意図的に無視することで、この判決を書いた裁判官が望む特定の結論を導き出すために恣意的な判断を行うものとなっていないか注意する必要がある。
もしそのような意図に基づいて文言を変更しているとすれば、恣意的な形で結論を導き出そうとする不正であるし、最高裁判決で用いられた文面の意味を改竄するものであり、解釈の過程を誤った違法なものということになる。
法解釈は、論理的整合性の積み重ねによって結論を正当化することが可能となる。
解釈の過程で根拠となっている判例の文言を勝手に変更したり、文章の内容を改竄したり、文章の意味を読み替えたり、その文面で用いられている文意の理解や前提となっている事柄から離れる形で用いることは、その判決の文面が前提としている憲法や法律などの具体的な条文や、その背景にある立法目的とその立法目的を達成するための手段となる枠組みとの関係から切り離されたものとなる。
そのような前提となっている条文や判決の文面の意味や内容から切り離された単なる文面を利用して何らかの結論を導き出そうとしても、その文面そのものが既に根拠となる法源から論理的な過程の積み重ねによって導き出されたものとはいえないことから、法的に正当化することのできる基盤を失っており、その文面を理由とした解釈や判断の枠組みについても法的な効力を有することにはならず、当然、そこで示された結論を正当化することもできない。
よって、このような文言上の操作を行うことは、不正であり、前提となっている事柄から断絶させるものとして違法な手続きということになる。
また、裁判所が、裁判体ごとにこのような誤った引用を繰り返していけば、判例の体系的な整合性が損なわれていき、規範の意味を曖昧化させたり、流動化させることとなり、裁判体ごとに別々の結論が下されてしまうことに繋がる。
そうなれば、同様の事件であれば誰が裁判を行っても同様の結論が導き出されるはずであるとの公平性や公正性への期待感が損なわれ、法的安定性も損なわれ、国民の抱く司法への信頼も失われることになる。
そのため、司法判断として判決の内容を引用する際には、このような不正な手続きが行われることを極限まで排除するために、より厳格な形での引用を行うように徹底することが望ましいといえる。
もともとの判決文を切り貼りする行為によって、そのもともとの判決文の解釈の過程で示されている規範の意味が変更されたり、曖昧化したり、別の裁判体が判決を積み重ねていくうちに規範の内容が流動化するようなことがあってはならない。
その他、この最高裁判決のいう「婚姻」は、「男女二人一組」の枠組みを前提とするものである。
これについて、国(行政府)は下記のように説明している。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
イ 憲法24条2項は同条1項を前提とした規定であり、同条2項における立法上の要請及び指針も、婚姻が異性間の人的結合関係を対象とするものであることを前提としていること
控訴答弁書第3の2(1)(12及び13ページ)及び (3)(16ないし19ページ)で述べたとおり、憲法24条2項は、婚姻及び家族に関する事項について、具体的な制度の構築を第一次的には国会の合理的な立法裁量に委ねるとともに、その立法に当たっては、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきであるとする要請、指針を示すことによって、その裁量の限界を画したものであるところ(再婚禁止期間違憲判決)、同項における立法上の要請及び指針は、形式的にも内容的にも、同条1項の存在及び内容を前提とすることが明らかである(平成27年夫婦別姓訴訟最高裁判決も同旨の判示をしているところである。)。
そして、前記アのとおり、憲法24条1項が、婚姻について異性間の人的結合関係のみを対象としていることに加え、同条2項においても、同条1項と同じく「両性」といった男性と女性の両方の性を意味する文言が用いられていることからすれば、同条2項も、飽くまで婚姻が異性間の人的結合関係を対象とするものであることを前提として、これを具体化する制度の整備を立法府に要請するものであることが明らかである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【東京一次・第3回】被控訴人第2準備書面 令和6年2月29日 PDF
この「男女二人一組」を前提とした「婚姻」について述べている最高裁判決の文面を用いても、「婚姻」の中に「同性間の人的結合関係」を含めることができるとする根拠にはならないものである。
また、この最高裁判決の文面は、憲法上の条文が存在することを前提とし、その条文の意味を解釈したものとして生じたいわば下位法にあたるものとして示されているものである。
そのことから、この下位法にあたる解釈の内容について、これを憲法よりも上位の規範として用いることはできない。
そのため、この最高裁判決の文面は、その上位法にあたる憲法上の条文に記されている規範の意味を書き換えることができるとする根拠とはならないものである。
よって、憲法24条の「婚姻」の中に「同性間の人的結合関係」を含めることができるかという問題が問われているこの札幌高裁判決の中で、この最高裁判決の文面を持ち出して論じようとすることは誤りである。
さらに、この最高裁判決が述べているのは、憲法24条2項の「婚姻及び家族」の枠組みの「要請」に従って定められた法律上の「婚姻及び家族」の制度の内容が「個人の尊厳」と「両性の本質的平等」を満たすか否かについてである。
しかし、この札幌高裁判決で問われているは、そもそも憲法24条の「婚姻」の枠組みが「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とする法律を立法することを「要請」しているか否かである。
これらは解釈の対象となっている事柄の次元が異なっており、この最高裁判決で論じられている内容を用いて、この札幌高裁判決で問われている憲法24条の「婚姻」の枠組みが「同性間の人的結合関係」を対象とした制度の創設を「要請」しているか否かを判断することはできない。
よって、この札幌高裁判決で問わている事柄を論じる際に、この最高裁判決を持ち出して論じようとすることは誤りである。
ウ ここで、憲法24条が異性間の婚姻のみならず、同性間の婚姻まで保障しているかについて検討する。
【筆者】
ここでいう「異性間の婚姻」と「同性間の婚姻」の意味が、それぞれ「異性間の人的結合関係」を形成することと「同性間の人的結合関係」を形成することを指している場合には、それは憲法21条1項の「結社の自由」によって保障されるものである。
また、憲法21条1項の「結社の自由」が「国家からの自由」という「自由権」の性質によって個々の自然人が人的結合関係を形成することを保障していることに対して、「憲法24条」は国の法制度としての「婚姻」について定めたものであり、「国家からの自由」という「自由権」の性質の生来的、自然権的な権利を保障したものではない。
そのため、「異性間の人的結合関係」や「同性間の人的結合関係」を形成することそのものを「憲法24条」が「保障している」とはいえないということができる。
ここでいう「異性間の婚姻」と「同性間の婚姻」の意味が、それぞれ「異性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることと「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを指している場合には、それは「婚姻」の概念の意味を検討することが必要である。
まず、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」を目的として、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす「一人の男性」と「一人の女性」の組み合わせを選び出し、その間に「貞操義務」を設けるなど一定の形式で法的に結び付け、子供が産まれた場合にその子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によって立法目的の達成を目指す概念を「婚姻」と呼んでいる。
また、憲法24条は「婚姻」を規定しており、「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めていることも、この意味に対応するものである。
この「異性間の婚姻」との部分について、「異性間」の人的結合関係は上記の趣旨を満たすものであることから、「婚姻」として成立することになる。
ただ、「異性間の婚姻」という表現は、あたかも「異性間」の「婚姻」に対して、それ以外の「婚姻」というものが存在するかのような言葉遣いであるが、上記のように「婚姻」であることそれ自体において、「男性」と「女性」の組み合わせによるものしか存在しないのであり、「婚姻」であればそもそも「異性間」について述べているものである。
このため、「異性間の婚姻」という言葉は、「異性間」という「男女」を指す言葉と、「婚姻」という「男女」の組み合わせを指す概念を同時に用いるものとなっており、文法上は「同義反復」となるため誤用ということになる。
また、「同義反復」となることを無視して、「異性間の婚姻」という言葉を使ったとしても、「婚姻」であることそれ自体で既に「男性」と「女性」の組み合わせによる「異性間」を指す意味しか存在しないことから、この「異性間の婚姻」という言葉に対する形で、それ以外の「婚姻」というものが成立するという余地はない。
そのことから、仮に「異性間の婚姻」という言葉を使ったとしても、それに対する形で「同性間の婚姻」というものを法的に構成することができるということにはならない。
そのため、その「婚姻」という言葉だけを刈り取ってその概念が形成されている目的から切り離して考えて「婚姻」という空の箱(言葉の意味から切り離された『音の響き』に過ぎないもの)の中にどのような人的結合関係でも詰め込むことができるかのような前提を含む形で論じていることは、正しい説明であるとはいえない。
◇ 本来の意味
「男性」と「女性」の組み合わせ ⇒ 法的に結び付ける形を「婚姻」とする
◇ この判決の言葉の使い方
「婚姻」は空箱 ⇒ どのような人的結合関係でも詰め込むことができる
よって、「異性間の婚姻」のように、「婚姻」という概念そのものをその概念が形成されている目的との間で切り離して、どのような意味としてでも用いることができるような前提を含む形で論じていることは、言葉の表現として適切であるとはいえない。
次に、「同性間の婚姻」との部分であるが、「同性間」の人的結合関係はその間で「生殖」を想定することができず、上記の「生殖と子の養育」の趣旨を満たすものではないことから、「婚姻」の中に含めることはできない。
そのため、「同性間の婚姻」のように、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることができるかのように述べていることは誤りとなる。
「憲法24条が異性間の婚姻のみならず、同性間の婚姻まで保障しているかについて検討する。」とある。
この文は「憲法24条が」「同性間の婚姻まで保障しているかについて検討する。」ものであることから、当然、「憲法24条が異性間の婚姻」を「保障している」ことを前提としているといえる。
そこで、この「憲法24条が異性間の婚姻」を「保障している」という表現の問題点について検討する。
まず、憲法は「個人の尊厳」の原理に基づいており、自然人は「個人主義」の下に各々「自律的な個人」として生存していくことを予定している。
そして、その個々の自然人が人的結合関係を形成、維持、解消することは自由である。
これは、憲法21条1項の「結社の自由」により「国家からの自由」という「自由権」の性質として保障される。
・憲法21条1項:「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」
憲法上では、他にも「保障する。」という文言が使われている条文がある。
・憲法20条1項前段:「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。」
・憲法23条:「学問の自由は、これを保障する。」
これらも「国家からの自由」という「自由権」の性質として「保障」しているといえる。
これに対し、憲法24条の条文の中に「保障する。」という文言は書かれていない。
そのため、「憲法24条」について「保障している」と表現される場合があるとしても、それは「憲法24条」の条文の文言をそのまま用いて説明しているものではなく、憲法24条の条文の趣旨を読み取った者の一人がそのような表現を用いて解説しているというだけのものである。
そのことから、憲法24条の条文そのものを読み解くことによって憲法24条の規範の意味を明らかにすることはできるが、憲法24条の条文の趣旨を読み取った者の中の一人が「保障している」と表現していることを根拠にして、そこから遡って憲法24条の条文の意味や性質を導き出そうとする試みは誤りである。
次に、憲法24条が定めている「婚姻」は、宗教的な意味として用いられる婚姻や、特定の地域の中でのみ通用していた婚姻を指すものではなく、それらとは区別されたものとして、国の法制度としての「婚姻」を指すものである。
これは、大日本帝国憲法下で定められていた法律上の婚姻制度(明治民法)を前提としており、その法律上の婚姻制度(明治民法)は、その制度が定められる以前に存在した伝統や慣習、宗教上の婚姻とは区別するものとして公的な制度として整理されたものである。
そのため、この意味で用いられている法制度としての「婚姻」の意味を、その制度としての意味を離れて「国家からの自由」という「自由権」としての人的結合関係を形成している状態を指すものであるかのように考えることは妥当でない。
他にも、「婚姻」とは、一定の枠組みを定めることによって「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的の達成を目指すものであることから、本来的に一定の枠が存在することを前提とするものであり、この概念の中に「国家からの自由」という「自由権」の意味は含まれていない。
そのため、この憲法24条の「婚姻」の意味は、憲法21条1項の「結社の自由」が個々の自然人に対して「国家からの自由」という「自由権」を保障していることとは性質が異なっている。
・憲法21条1項「結社の自由」 ⇒ 「国家からの自由」という「自由権」の性質
・憲法24条「婚姻」 ⇒ 法制度
そのことから、憲法24条1項が「婚姻」を「保障している」と表現される場合があるとしても、その意味は、「国家からの自由」という「自由権」の意味は含まれておらず、憲法24条の「婚姻」の枠組みが法律によって婚姻制度(男女二人一組)を立法することを「要請」していることから、当然、その婚姻制度(男女二人一組)を利用することが可能となるという意味のものである。
つまり、憲法24条は「婚姻」について定めており、この「要請」に従って法律上の婚姻制度(男女二人一組)を設けることになっていることから、国民がその制度を利用することを望む場合にはその制度を利用することができる状態にあるため、それを憲法24条の規定が存在しない場合と比べる意味で、憲法上で「保障されている」と表現しているものである。
当サイトでも「保障している」と表現している場合があるが、これも憲法上で立法することが「要請」されていることから、その制度が存在しない状態とはならず、国民はその制度を利用することを望むのであれば利用することができるというこの意味で用いている。
そのため、この意味を離れて「保障している」との表現を用いることは適切ではない。
しかし、この判決では、その憲法24条の条文の趣旨を読み取った者の一人が「憲法24条は、婚姻を保障している」のように説明している場合における「保障している」との表現を拾い上げ、「『保障している』のであれば、それは『国家からの自由』という『自由権』の性質なのだろう」という誤った推測を働かせ、憲法24条の「婚姻」の意味を憲法21条1項の「結社の自由」と同様の「国家からの自由」という「自由権」の性質として読み解こうとしているように見受けられる。
この傾向は、この札幌高裁判決が「(2)ウ」の第三段落の第四文で憲法24条1項について「人と人との間の自由な結びつき」と説明しているところからも感じ取ることができる。
そのため、ここで「憲法24条」について「保障している」と表現している部分についても、憲法24条の「婚姻」の枠組みの「要請」に従って立法された法律上の婚姻制度を利用することが可能となるという意味を離れて用いていることが考えられる。
◇ この札幌高裁判決の理解
憲法24条の「婚姻」 ← (『国家からの自由』という『自由権』の性質と考える)
↓ (誰かの解説) ↑ (逆算)
「憲法24条は、婚姻を保障している。」
◇ 本来の意味
憲法24条の「婚姻」 ⇒ (法制度)
↓ (要請)
法律上の婚姻制度 ← (24条の『要請』で定められ、利用することが可能となる。)
よって、ここで「憲法24条」について「保障している」と表現している部分は、「憲法24条」は法制度としての「婚姻」について定めたものであり、「国家からの自由」という「自由権」を保障するものとは性質が異なることを理解していない表現と考えられ、適切な表現であるとはいえない。
国(行政府)も、この点については「保障している」とは表現しておらず、「要請」しているか否かの問題であることを示している。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
なお、被控訴人原審第2準備書面26ページにおいて述べたとおり、そもそも、憲法24条との関係で本件立法不作為が違憲であることが明白であるといえるためには、同条が同性問の婚姻を法制化することを国会に対して要請しているといえなければならず、同性婚が憲法上禁止されているか、又は許容されているのかという点は、原告らの憲法24条に関する主張の当否の判断において争点とはならないため、この点に関する回答は差し控える。また、憲法が同性問の婚姻を法制化することを国会に対して要請していないことは、控訴答弁書7ないし10ページにおいて述べたとおりである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【札幌・第2回】被控訴人回答書 令和4年3月4日 PDF
同条は、その文言上、異性間の婚姻を定めており、制定当時も同性間の婚姻までは想定されていなかったと考えられる。婚姻と家族の制度において、旧憲法下の家制度の制約を改め、対等な当事者間の自由な意思に基づく婚姻を定める趣旨により、両性との文言が採用されたと解される。また、当時は、いまだ同性愛については、疾患や障害と認識されていたとの事情もあったと思われる。しかしながら、法令の解釈をする場合には、文言や表現のみでなく、その目的とするところを踏まえて解釈することは一般的に行われており、これは、法人や外国人の人権が問題となる場合をはじめとして(最高裁昭和41年(オ)第444号同45年6月24日大法廷判決・民集24巻6号625頁、最高裁昭和50年(行ツ)第120号同53年10月4日大法廷判決・民集32巻7号1223頁等参照)、憲法の解釈においても変わるところはないと考えられる。さらに、仮に立法当時に想定されていなかったとしても、社会の状況の変化に伴い、やはり立法の目的とするところに合わせ、改めて社会生活に適する解釈をすることも行われている。したがって、憲法24条についても、その文言のみに捉われる理由はなく、個人の尊重がより明確に認識されるようになったとの背景のもとで解釈することが相当である。
【筆者】
━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━
この段落が読み取りづらい理由は、下記のとおりである。
◇ 第四文の「しかしながら、」についても、その前提となる事情から話が切り替わることが明らかであることから、改行を加えたほうが分かりやすいといえる。
また、第六文の「したがって、」の結論部分も、その前の部分から話が切り替わるため、改行を加えたほうが分かりやすいといえる。
◇ 第五文の始めでは「さらに、」のように、以前に述べていることを前提とした上で別の根拠や理由を加える言葉が付いている。
それにもかかわらず、その後その文の中で「やはり」のようにそれまでに述べたことを繰り返す意味の言葉を用いており、一貫性がないものとなっている。
そのため、この第五文の始めの「さらに、」という言葉と、同じく第五文の「やはり」という言葉のどちらが誤っているかを検討するために、内容を読み取ると、一文前の第四文で述べた「その目的とするところを踏まえて解釈すること」と、この第五文の「立法の目的とするところに合わせ、」では同じことを述べていることから、「さらに、」の方が誤っていることになる。
もしかすると、「法人や外国人の人権が問題となる場合をはじめとして」に続く形で判例を二つ挙げていることから、この根拠に加える形で「さらに、」と述べたかったのかもしれないが、そうであれば、第四文は「一般的に行われており、これは、」と続いている文を「一般的に行われて」『いる。』の形で一度文を区切り、新たな文として「これは、」と続けて「法人や外国人の人権が問題となる場合」の事例を挙げ、その後、「さらに、」と別の根拠を加える形で構成した方が読み取りやすかったはずである。
━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━
「同条は、その文言上、異性間の婚姻を定めており、制定当時も同性間の婚姻までは想定されていなかったと考えられる。」との記載がある。
この文には「異性間の婚姻」と「同性間の婚姻」の文言がある。
この意味がそれぞれ「異性間の人的結合関係」と「同性間の人的結合関係」を指しているのであれば、そのような人的結合関係を形成することは憲法24条1項の「結社の自由」によって保障されているものであり、ここでいう「同条」である憲法24条によって保障されているかのように述べていることは誤りとなる。
この意味が「異性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることと「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを指しているのであれば、一段落前で解説したように、「異性間の婚姻」という表現はあたかも「婚姻」という概念の中に「異性間」を対象とするもの以外のものが存在し得るかのような前提で論じるものとなるため妥当ではないし、「同性間の婚姻」という表現はそもそも「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることはできないため妥当ではない。
よって、いずれの意味でも「異性間の婚姻」や「同性間の婚姻」との表現は適切ではない。
「同条は、その文言上、異性間の婚姻を定めており、」との部分について検討する。
憲法24条が「その文言上、異性間」の人的結合関係を対象として「婚姻を定めて」いる理由は、下記の通りである。
「婚姻」は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた枠組みである。
具体的には、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」という目的の下に、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす組み合わせとなる「一人の男性」と「一人の女性」を選び出し、その間に「貞操義務」を設けるなど一定の形式で法的に結び付け、子供が産まれた場合にその子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によってそれら目的の達成を目指すものである。
「同条」である憲法24条は「婚姻」を規定しており、「その文言上」、「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めている。
これは、上記の目的と、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす組み合わせであることに対応するものである。
このことから、ここでいうように「同条は、その文言上、異性間の婚姻を定めて」いるといえる。
「制定当時も同性間の婚姻までは想定されていなかったと考えられる。」との部分について検討する。
「想定されていなかった」ことには、それが「想定されていなかった」なりの事情が存在するはずである。
その理由を遡って検討しなければ、「婚姻」という概念そのものや、憲法24条の「婚姻」の文言や「両性」「夫婦」の文言が、「同性間」の人的結合関係をどのように扱っているのかを理解することはできないし、憲法24条の下で「同性同士の組み合わせ」を「婚姻」とする法律を立法することが可能であるか否かも判断することはできない。
そこで、その理由を下記で検討する。
「婚姻」は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられている枠組みである。
具体的には、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」という目的の下に、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす組み合わせとなる「一人の男性」と「一人の女性」を選び出し、その間に「貞操義務」を設けるなど一定の形式で法的に結び付け、子供が産まれた場合にその子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によってそれらの目的の達成を目指す仕組みとして形成されている。
このような経緯から、「婚姻」は「生殖と子の養育」の趣旨を有しており、これらの目的を達成するための手段として、下記の要素を満たす人的結合関係を対象とする制度である。
・子の遺伝的な父親を特定できる組み合わせとすること
・特定された子の父親にも子に対する責任を担わせること
・特定された子の父親を基に遺伝的な近親者を把握すること
・未婚の男女の数の不均衡を防止できる組み合わせに限定すること
「同性間」の人的結合関係については、その間で「生殖」を観念することができず、「生殖と子の養育」の趣旨や上記の要素を満たすものではないことから、「婚姻」として「想定されていなかった」といえる。
つまり、制度の趣旨に沿わない関係であれば、もともと「婚姻」ではないことから、「婚姻」として「想定されていなかった」ということである。
このように、「想定されていなかった」ことには、「想定されていなかった」だけの理由がある。
そのため、この「想定されていなかった」との文言だけを見て、それを単に立法者がうっかり忘れていたかのような安易な発想によるものであると意味を限定して認識し、それを反対解釈すれば「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることができるということにはならないことに注意が必要である。
【参考】「想定していないということは、同性婚は24条の【婚姻】と認められないということ」 Twitter
【参考】「想定してないモノはそもそも【婚姻】じゃない」 Twitter
【参考】「想定していないことは禁じてることにはならないが、想定していなければ認められない。」 Twitter
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「24条は同性婚を想定していない」
①だから同性婚を禁止していない
②だから同性婚を許可していない
どちらも正解。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「想定してない」「触れてない」「定めてない」
そんなモノがどうして【婚姻】と言えるのだ?
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【参考】「同性婚を想定したものじゃないから関係ない。 これ言い始めたら憲法条文に意味がなくなる。」 Twitter
「婚姻と家族の制度において、旧憲法下の家制度の制約を改め、対等な当事者間の自由な意思に基づく婚姻を定める趣旨により、両性との文言が採用されたと解される。」との記載がある。
この文は、直前の文で「同条」と書かれており、さらにその直前の一段落前の「ウ」の第一段落の文でも「憲法24条」とあることから、「憲法24条」について説明するものである。
憲法制定の過程において「憲法24条」が設けられた背景に、ここでいう「旧憲法下の家制度の制約を改め、対等な当事者間の自由な意思に基づく婚姻を定める趣旨」があったとの認識はその通りであると思われる。
しかし、ここではその「趣旨」により、「両性との文言が採用されたと解される。」と述べているが、これは誤りである。
まず、明治民法では、「婚姻」する際に「戸主」の同意が求められる場合があり、「婚姻」する当事者だけでなく「戸主」の意向に左右されるものとなっていた。
これを改めるために、「憲法24条」に「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、」と定められ、ここでいう「当事者間の自由な意思に基づく婚姻を定める趣旨」が含まれていると解されることになるのである。
そのため、「当事者間の自由な意思」に基づく「婚姻」を定める趣旨に対するものは、「戸主」による同意が求められ、「婚姻」する者の「合意」だけでは「婚姻」が成立しないという事実である。
よって、「当事者間の自由な意思に基づく婚姻を定める趣旨」に対応する「憲法24条」の文言は、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、」の中の「合意のみ」の部分である。
そのため、ここで「対等な当事者間の自由な意思に基づく婚姻を定める趣旨により、両性との文言が採用されたと解される。」のように、「当事者間の自由な意思に基づく婚姻を定める趣旨」に対応する部分が「両性」の部分であるかのように述べていることは誤りである。
この札幌高裁判決が示す「両性」とは、当然に「男女」であることを意味するものである。
そして、その「婚姻」する「男女」(ここでは『当事者』と述べているもの)の間の「合意のみ」の部分こそが、戸主の反対などの他者からの干渉を防ぐものとして機能する部分である。
そのため、これを「両性」の部分を取り上げて、それが「対等な当事者間の自由な意思に基づく婚姻を定める趣旨」と述べることは誤りである。
また、「対等な当事者間の自由な意思に基づく婚姻を定める趣旨」の部分も、それぞれ憲法24条との条文との関係を読み解くと、下記のようになる。
・「対等な」
⇒ 24条1項「夫婦が同等の権利を有することを基本として、」
⇒ 24条2項「両性の本質的平等」
・「当事者間の」
⇒ 24条1項「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」
⇒ 24条2項「婚姻」「両性の本質的平等」
・「自由な意思に基づく」
⇒ 24条1項「合意のみ」
・「婚姻を定める趣旨」
⇒ 24条1項「婚姻」(両性)(夫婦)(相互)(配偶者)
⇒ 24条2項「婚姻」
そのため、この「対等な当事者間の自由な意思に基づく婚姻を定める趣旨」という文の意味のすべてを「両性」の文言だけに読み込むことは不可能である。
よって、「両性との文言が採用されたと解される。」と述べていることは誤りである。
「また、当時は、いまだ同性愛については、疾患や障害と認識されていたとの事情もあったと思われる。」との記載がある。
まず、婚姻制度は「性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や、「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いをする制度ではないし、「性愛」に基づいて制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもない。
そのため、婚姻制度について論じる場面で「性愛」を取り上げる必要がないのであり、その中の一つとされる「同性愛」の性質について述べる必要はない。
法制度は個々人の内心に対して中立的な内容でなければならず、もし「性愛」という特定の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的とした制度を立法した場合には、憲法20条1項後段・3項、89条の「政教分離原則」に違反する。
他にも、「性愛」の思想、信条、信仰、感情を有するか否かを審査したり、「性愛」に基づいて制度を利用することを求めるものとなっていた場合には、憲法19条の「思想良心の自由」や憲法20条1項前段の「信教の自由」に違反する。
さらに、「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いをする場合には、憲法14条1項の「平等原則」に違反する。
また、「性愛」の思想、信条、信仰、感情を保護し、「性愛」以外の「友情」、「友愛」、「絆」など他の様々なの思想、信条、信仰、感情を保護しないことになるから、その点でも憲法14条1項の「平等原則」に違反する。
そのため、そもそも法制度を「性愛」と関係するものとして立法してはならない。
このことから、ここで「当時は、いまだ同性愛については、疾患や障害と認識されていた」のように述べて、現在は「疾患や障害」との認識とは異なることを示すのであるが、そもそも「性愛」という特定の思想、信条、信仰、感情に基づく形で法制度を立法した場合には、そのこと自体が憲法違反の原因となるのであり、そのような「同性愛」という思想、信条、信仰、感情と関係する形で法制度を立法することが許されることを前提として論じていること自体が誤りである。
また、「男女二人一組」の枠組みを定めている婚姻制度についても、それは「異性愛」という思想、信条、信仰、感情を保護することを目的とした制度ではないし、「異性愛者」を称する者を対象としているものでもないし、「異性愛」に基づいて制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもない。
そのため、「男女二人一組」の枠組みを定める婚姻制度が「異性愛」を保護するための制度であることを前提として、これに対する形で「同性愛」を取り上げているものであるとしても、そもそもの前提認識からして誤りである。
その他、婚姻制度(男女二人一組)は「疾患や障害」を持つ者でも利用することができることから、「疾患や障害」ではないことを理由にして婚姻制度の中に含めるべきであるとの主張は、そもそも「疾患や障害」を持つ者は婚姻制度(男女二人一組)を利用することができないかのような認識を前提として論じていることになるのであり、その前提となる認識そのものが不当である。
「しかしながら、法令の解釈をする場合には、文言や表現のみでなく、その目的とするところを踏まえて解釈することは一般的に行われており、これは、法人や外国人の人権が問題となる場合をはじめとして(…)、憲法の解釈においても変わるところはないと考えられる。」(カッコ内省略)との記載がある。
「しかしながら、法令の解釈をする場合には、」とある。
これは、これ以前の「(2)ア」と「イ」での部分で「再婚禁止期間制度訴訟大法廷判決」と「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」を示しており、これらの内容も憲法24条の「婚姻」が「男女二人一組」を前提とした解釈となっていることを踏まえ、ここで「しかしながら、」と逆接を述べて、これらの最高裁判決の示した解釈をこの札幌高裁判決が新たな解釈を示すことによって否定しようとすることを述べるものといえる。
ただ、その後「ウ」の第三段落第二文で「憲法24条1項は、婚姻をするかどうか、いつ誰と婚姻をするかについては、 当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたものと解され、このような婚姻をするについての自由は、同項の規定に照らし、十分尊重に値するものと解することができる(再婚禁止期間制度訴訟大法廷判決参照)。」と述べて、改めて憲法24条の「婚姻」について「男女二人一組」を前提としている「再婚禁止期間制度訴訟大法廷判決」の文面が示されている。
そして、これを根拠の一つとして「憲法24条1項は、……(略)……同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障していると考えることが相当である。」との結論を導き出そうとするものとなっている。
しかし、この論じ方は、ここで先に自ら否定したはずの最高裁判決の内容を用いて結論を導き出そうとするものとなっている点で誤っている。
また、その内容についても、「男女二人一組」を前提とする最高裁判決を前提として、この「男女」を満たさない人的結合関係も「同じ程度に保障していると考えることが相当である。」とする結論を導き出そうとするものとなっており、その結論を導くための根拠とはならないものを用いているという点でも誤っている。
よって、ここで「しかしながら、」と逆接で説明しようとしていることは妥当でない。
「法令の解釈をする場合には、文言や表現のみでなく、その目的とするところを踏まえて解釈することは一般的に行われており、」との部分について検討する。
一般論としてはその通りといえる場合がある。
しかし、法令の「文言や表現」から乖離する形での解釈が無制限に許されるわけではない。
国(行政府)の主張では、下記のように説明されている。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
イ しかし、控訴答弁書第3の3(2)イ(22及び23ページ)で述べたとおり、法の解釈に際し、文言の日本語としての意味や文法が重視・尊重されなければならないのは当然のことであり、文言からかけ離れた解釈は許されない。そして、前記 (2)アで述べたとおり、「両性」とは、一般に、両方の性、男性と女性を意味する文言であり、「両性」が男性又は女性のいずれかを欠き当事者双方の性別が同一である場合を含む概念であると理解する余地はなく、憲法24条1項及び2項における「両性」の意味もこのように理解すべきことは、憲法24条の制定過程及び審議状況からも裏付けられている。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【東京一次・第3回】被控訴人第2準備書面 令和6年2月29日 PDF
解釈の内容についても、その法令の趣旨や目的により拘束されることになる。
行政府の答弁では、解釈の方法やその限界について、下記のように説明している。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○政府委員(大出峻郎君) 一般論として申し上げますというと、憲法を初め法令の解釈といいますのは、当該法令の規定の文言とか趣旨等に即して、立案者の意図なども考慮し、また、議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定されるべきものであると考えられるわけであります。
政府による憲法解釈についての見解は、このような考え方に基づき、それぞれ論理的な追求の結果として示されてきたものと承知をいたしており、最高法規である憲法の解釈は、政府がこうした考え方を離れて自由に変更することができるという性質のものではないというふうに考えておるところであります。
特に、国会等における論議の積み重ねを経て確立され定着しているような解釈については、政府がこれを基本的に変更することは困難であるということでございます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第134回国会 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第3号 平成7年11月27日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
憲法を始めとする法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、また、議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定されるべきものであり、政府による憲法の解釈は、このような考え方に基づき、それぞれ論理的な追求の結果として示されてきたものであって、諸情勢の変化とそれから生ずる新たな要請を考慮すべきことは当然であるとしても、なお、前記のような考え方を離れて政府が自由に憲法の解釈を変更することができるという性質のものではないと考えている。仮に、政府において、憲法解釈を便宜的、意図的に変更するようなことをするとすれば、政府の憲法解釈ひいては憲法規範そのものに対する国民の信頼が損なわれかねないと考えられる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書 平成16年6月18日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
また、お尋ねの「法的安定性」とは、法の制定、改廃や、法の適用を安定的に行い、ある行為がどのような法的効果を生ずるかが予見可能な状態をいい、人々の法秩序に対する信頼を保護する原則を指すものと考えている。仮に、政府において、論理的整合性に留意することなく、憲法解釈を便宜的、意図的に変更するようなことをするとすれば、法的安定性を害し、政府の憲法解釈ひいては憲法規範そのものに対する国民の信頼が損なわれかねないと考えられる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
七・一閣議決定の法的安定性と論理的整合性の意味等に関する質問に対する答弁書 平成29年6月27日
解釈は、紛争を招くことのない公共的な合意に至ることのできる法的安定性を有した規範を導くものであることが求められる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法を解釈することと、法を解釈していると思い込んでいることとを区別しうるためには、解釈は個人的・私的なものではなく、社会的な、つまり原理的には誰にも共通にアクセス可能な、公的活動でなければならないはずである。各人がそれぞれ異なった形で得心がいっただけでは、法解釈として十分とはいえない。解釈者は、他人を説得し、同じように既存の法源(判例・法令)を見るように議論を進める必要がある。もちろん、その結果、つねに同一の結論へと人々の意見が集約されるとは限らない。同じ程度に説得力を持つ複数の解釈が競合することは珍しいことではない。
解釈が解釈であるためには、つまり、それが原理的に誰もが参加しうる公的な活動であるためには、第一に、法源の核心的な意味の理解を可能とする共通の言語作用が背景として存在していなければならない。そして、第二に、解釈の目的は、例外的・病理的現象である法の意味の不明瞭化に対して、人々の合意をとりつけることで、正常な法の機能を回復すること、人々が再び疑いをもたずに法に従いうる状態を回復することになければならない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
憲法の理性 長谷部恭男 (P210) (下線は筆者)
法を解釈するに当たっては、このような作法を踏まえることが必要である。
そこで、「その目的とするところを踏まえて解釈すること」について詳しく検討する。
条文の意味を解釈する際には、その条文に記された文言がどのような意味を持っているかを検討することが必要である。
また、単にその条文の文言から意味を読み取るというだけでなく、その条文に関連する他の規定が存在するのであれば、その関連する規定と照らし合わせて整合的に読み解くことが必要である。
それでもまだ意味が不明瞭な部分については、その条文を含む制度の枠組みの全体を整合的に読み解くことができる目的を特定することが求められる。
これは、その制度の全体をその目的に照らし合わせて整合的な形で統一的に理解することにより、一つ一つの条文の意味を正確に読み解くことが可能となるからである。
このように制度の全体を整合的に読み解くことができる理解を基にして考えることで、条文に記された一つ一つの文言が持つ意図を正確に導き出すことが可能となり、その文言の持つ意味の射程を把握することが可能となる。
これにより、具体的な事例に対してその条文を適用することができる場合であるか否かや、その条文の下で定められている制度(下位法)があればその制度の形を変更することができるか否か、また、その限界を判断することが可能となる。
しかし、その判断の過程でこの目的を特定する作業に失敗すると、その誤った目的に従って制度の枠組みを変更したことによって、その制度が本来予定していた機能が損なわれたり、その制度全体を整合的に理解することが不可能となって制度そのものが成り立たなくなるなど、制度そのものが破壊されてしまうことが起こり得る。
また、一度その「目的」を見誤って、その「手段」となっている制度の枠組みを変えてしまった場合には、その誤った「目的」が別の事案においても主張され続けることとなり、次々にその「手段」となっている制度の枠組みが突き崩されていくことに繋がる。
すると、その制度が本来予定していた機能を果たさない状態に変わってしまうことになる。
そのため、「目的」を特定するにあたっては、このような事態に陥ることがないように、断片的な判断を行うのではなく、制度の全体を見渡してすべての規定の意味を整合的に理解することができる状態を保つことができるように注意深く検討することが必要である。
特に、その制度がもたらす個別の効果のみに着目して、その個別の効果を生じさせている個別の規定が有している目的を基にして考えてしまうことで、その制度の全体が存在していることそのものが有している目的を見失うようなことがあってはならない。
また、目的を特定する際に注意するべきなのは、現在の制度がよく機能しており、その制度が有している目的が十分に達成されていることから、現在の社会の中で問題が表面化していないという場合を見逃してはならないことである。
これについて、下記の動画が参考になる。
【動画】天皇と合理性。伝統は伝統であるが故に尊い!合理性という浅知恵と何世代も培った伝統という叡智|竹田恒泰チャンネル2 2024/04/04
このように、その制度が有する目的が十分に達成されており、社会的な不都合に出くわす場面が少ない中では、逆にその制度が存在しない場合に起こり得る問題を十分に想定することができなくなってしまい、その制度が有する目的を正確に捉えることができていない者が現れることがある。
そして、その制度が有している立法目的を捉え間違えた者によって国家権力(立法権、行政権、司法権)が行使されることで、むやみに制度の内容が変更されたり、制度そのものが廃止されたりすることによって、今までその制度が存在する中では表面化していなかった問題が後に顕在化するということが起こり得る。
そのため、そもそも何を目的として定められた制度なのかを十分に捉えることができなくなっている場合や、制度の有している目的とその目的を達成するための手段となる具体的な枠組みとの関係にどのような意図が含まれているのかを忘れてしまっている場合に制度を変更しようとすることは危険である。
そのことから、安易に制度の目的を理解したかのように思い込んでしまい、その目的であると思い込んだ事柄を理由にして制度を変更することができると結論付けてしまうようなことがあってはならない。
そのため、その制度全体が有している目的が定まるまでの背景にある社会的な不都合を解消しようとする事実を見ないままに、安易に目的を理解したと思い込んでしまっていないか、常々点検しながら検討することが必要である。
このため、この目的を特定する作業を失敗しないためには、その制度が機能している以前の状態の中で、何が求められ、どのような目的をもって形成されたのか、その原点に立ち戻って検討することが必要である。
つまり、その社会の中でその制度が存在しない状態にまで遡り、その状態で起こり得る問題を勘案し、そこで生じる不都合を解消するという視点を基にして目的となっているものを導き出すことが必要である。
この過程で、制度の全体を整合的に理解することができなくなったり、制度を機能しないものに変えてしまうような一線を損なわせることに繋がる事柄については、それをその制度の目的として理解することはできないことになる。
つまり、そのような事柄をその制度の「目的」として考えることを正当化することはできず、そのような事柄は退けられるということである。
また、このように、その社会の中でその制度が存在しない状態で起こり得る問題を勘案することによって、その制度の目的とその目的を達成するための手段となっている具体的な条文との関係を特定することが可能となる。
そして、その条文が、その目的を達成するための手段としてどのような関係の下に位置付けられているかを明らかにすることにより、その条文に記された一つ一つの文言の意味を正確に読み解くことが可能となり、その文言に含まれる規範の意味を導き出すことが可能となる。
これを前提に、「婚姻」についても、法が「婚姻」という制度を設けることによって、何を実現しようとしているのかを考え、その目的を特定することが必要である。
これは、その目的と照らし合わせて考えることによって、「婚姻」という制度について定めた条文や、その条文に記された一つ一つの文言の意味を正確に読み解くことが可能となり、制度を変更することの可否やその限界を見出すことが可能となるからである。
ここで注意するべきなのは、現在の婚姻制度がよく機能していることによって、婚姻制度の有する目的が十分に達成されており、現在の社会の中で不都合な問題が表面化していないという場合を見逃してはならないことである。
そのため、その社会の中で婚姻制度が存在しない状態にまで遡り、その状態で起こり得る問題を勘案し、そこで生じる不都合を解消するという視点を基にしてその目的を導き出すことが必要である。
この過程で、「婚姻」の枠組みが予定している機能が損なわれるような事柄や、「婚姻」の枠組みを整合的に理解することができない事柄、今回の事案では直ちに何らかの影響が見られないとしても、その後、他の訴訟が提起された場合などに、そこで用いられた目的と称しているものを理由として制度の変更がなされると「婚姻」の枠組みが予定している機能が損なわれてしまうような整合性のないものについては、それを「婚姻」という枠組みの目的として理解することはできない。
そこで、「婚姻」という概念が担っている事柄を検討し、その目的と、その目的を達成するための手段となる枠組みとの関係を検討する。
その社会の中で何らの制度も設けられていない場合には、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合が発生する。
例えば、「父親不明」の子供が増える、父親を特定できない子供が増える、父親が蒸発して行方不明になった子供が増える、それらにより「子の福祉」が減少する、父親を特定できないことにより近親者の範囲を把握できずに「近親交配」に至り潜性遺伝子の発現した個体が高い確率で生じるようになる、一部の強者が多数人との生殖関係を独占することによって社会の中で「子を持ちたいと希望して相手を見つけようとする男女」の数の不均衡が生じて「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」が生まれる、低年齢での妊娠・出産により母体に危険が及ぶ、などの問題が生じることがある。
これらの不都合を解消するために、下記のような立法目的を有する枠組みを設けることが必要となる。
・「子の福祉」が実現される社会基盤を構築すること
・潜性遺伝子の発現した個体が高い確率で生じることを抑制すること
・「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」を減らすこと
・母体を保護すること
そして、これらの目的を達成するためには、下記の要素を満たす枠組みを設けることが必要となる。
・子の遺伝的な父親を特定できる組み合わせとすること
・特定された子の父親にも子に対する責任を担わせること
・特定された子の父親を基に遺伝的な近親者を把握すること
・未婚の男女の数の不均衡を防止できる組み合わせに限定すること
これらの要素を満たすものとして「一人の男性」と「一人の女性」が選び出され、その間に「貞操義務」を設け、その関係を法的に結び付ける形を「婚姻」と呼んでいる。
そして、この「婚姻」に対して法的効果や一定の優遇措置を設けることで、婚姻制度を利用する者を増やし、これらの目的を達成することを目指すことになる。
憲法24条はこの「婚姻」について規定しており、「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めている。
これも、上記の要素と対応するものとして定められている。
これが「婚姻」という概念が有している目的とその目的を達成するための手段として導かれる枠組みとの関係である。
このように、「婚姻」は、人間が有性生殖を行うことによって子孫を産むという身体機能を有しており、その男女の間で行われる「生殖」の営みに関わって生じる不都合が社会的な課題となっていることから、その不都合を解消するために設けられている枠組みである。
つまり、人間の有性生殖の営みに着目して設けられている枠組みということである。
そして、この「婚姻」という枠組みが形成された当初から現在までの間に、人類が有性生殖の機能を失ったり、人類が無性生殖をする生き物に進化したりしたという事情は認められない。
そのため、その「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することの必要性は「婚姻」という枠組みが形成された当初から現在においてまで何ら変わるものではない。
このため、その社会の中で「婚姻」という枠組みがその不都合を解消するものとして機能することが求められていることにも変わりはない。
そのことから、「婚姻」の概念が「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消する仕組みとしての役割を担っていることに変わりはなく、これをこの機能を果たさない別の概念へと変えてしまうということはできない。
もしそのようなことをすれば、それはここでいう「その目的とするところを踏まえて解釈」したものであるともいうことができなくなり、不当な内容となることは明らかだからである。
そのため、「婚姻」という枠組みが形成された当初から現在においてまで、上記で示した「婚姻」の枠組みが有している目的と、その目的を達成するための手段として整合的な要素との関係に何らの変わりはない。
よって、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的と、憲法24条の「婚姻」という文言それ自体や「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言との対応関係を照らし合わせて考えた場合に、これらの文言は一夫一婦制(男女二人一組)の婚姻制度を定めることによってその目的を達成することを予定しているものであるということができる。
このように目的との間で対応関係の見られる文言が条文の中に具体的に存在している以上は、その文言を意味を無視することは許されず、この憲法24条の「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言の意味を自由に変更することができるということにはならない。
このことから、憲法24条が「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)の枠組みを定めており、この枠組みに従う形で法律を立法することを「要請」していることから、これらの文言は婚姻制度の内容を一夫一婦制(男女二人一組)で定めることを「要請」しているということができる。
そして、この「要請」に従って定められる法律上の婚姻制度の内容も、一夫一婦制(男女二人一組)で定められることになる。
そのため、この「要請」に従って法律上の婚姻制度を一夫一婦制(男女二人一組)で立法していることは、ここでいう「文言や表現のみでなく、その目的とするところを踏まえて解釈」したものであるということができる。
これに対して、この札幌高裁判決が示している解釈の過程や、そこから導き出したとする結論の内容は、上記の法令を解釈する方法やその限界を踏まえたものであるとはいえない。
この札幌高裁判決では、憲法24条について、この段落の第一文で「同条は、その文言上、異性間の婚姻を定めており、制定当時も同性間の婚姻までは想定されていなかったと考えられる。」との前提を述べた上で、ここで「しかしながら、法令の解釈をする場合には、文言や表現のみでなく、その目的とするところを踏まえて解釈することは一般的に行われており、」のように、「しかしながら、」と逆接を用いてその前提を覆し、別の結論が導き出されることを予測させるものとなっている。
そして、ここでいう「文言や表現のみでなく、その目的とするところを踏まえて解釈」したことを理由として、その後この「ウ」の第三段落の第四文で「憲法24条1項は、……(略)……同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障していると考えることが相当である。」との結論を導き出そうとするものとなっている。
しかし、上記で説明したように、そもそも法律上の婚姻制度が一夫一婦制(男女二人一組)の形で立法されていることは、憲法24条の「文言や表現のみでなく、その目的とするところを踏まえて解釈」した結果として導き出されているものである。
つまり、法律上の婚姻制度が一夫一婦制(男女二人一組)の形で立法されていることは、単に「文言や表現のみ」に基づくものというわけではないし、「その目的とするところを踏まえて解釈」していないものであるというわけではない。
そのことから、この札幌高裁判決では、憲法24条が「異性間」を対象としているとの理解について、「文言や表現のみ」に基づくものであり「その目的とするところを踏まえて解釈」していないとの前提の下に、これを否定することを試みるのであるが、そもそも憲法24条が「異性間」を対象としているとの理解は、「文言や表現」に沿うものとなっていることに加えて、その内容も「その目的とするところを踏まえて解釈」したものであることから、それを否定しようとする前提となる認識の部分から既に誤っていることになる。
よって、ここで「法令の解釈をする場合には、文言や表現のみでなく、その目的とするところを踏まえて解釈することは一般的に行われており、」と述べてはいるものの、そのように憲法24条の「婚姻」について「その目的とするところを踏まえて解釈」したとしても、その「婚姻」の中に「同性間の人的結合関係」を含めることができることに繋がるわけではないのであり、ここで「その目的とするところを踏まえて解釈」することによって、後に「ウ」の第三段落の第四文のところで「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることが可能となるかのような前提の下に「憲法24条1項は、……(略)……同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障していると考えることが相当である。」と述べていることは誤りとなる。
その他、この札幌高裁判決が後に「目的」の内容として挙げている内容も誤っている。
上記で論じられている条文を解釈する場合における「目的」とは、その制度の枠組みを構成するに至っている原因となるものであり、その条文よりも上位にある概念である。
しかし、この札幌高裁判決では、後に「(2)ウ」の第三段落において、この「目的」に当たるものとして下記の内容を挙げるものとなっている。
「(2)ウ」の第三段落
A 「性的指向及び同性間の婚姻の自由は、現在に至っては、憲法13条によっても、人格権の一内容を構成する可能性があり、十分に尊重されるべき重要な法的利益であると解される」
B 「憲法24条1項は、婚姻をするかどうか、いつ誰と婚姻をするかについては、 当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたものと解され、このような婚姻をするについての自由は、同項の規定に照らし、十分尊重に値するものと解することができる(再婚禁止期間制度訴訟大法廷判決参照)。」
C 「憲法24条2項は、婚姻及び家族に関する事項についての立法に当たっては、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきと定めている。」
上記「A」の憲法13条の説明については、憲法24条とは別の条文であり、憲法24条が「婚姻」の枠組みを定めている根拠となるようなものではない。
また、「B」の憲法24条1項や「C」の憲法24条2項の説明についても、その条文が意図する機能(その条文が下位の法令に対してどのような影響を与えることが意図されているか)について述べているだけである。
(「B」は、憲法24条1項の条文が存在することを前提として、その意味を解釈した結果として導き出されたものであり、憲法24条1項の条文よりも上位にある規範として示されたものではない。)
(「C」も、憲法24条2項の条文が存在することを前提として、その意味について説明するものであり、憲法24条の条文よりも上位にある規範が示されているわけではない。)
そのため、これも、上記で論じている「目的」(国の立法目的)にあたる説明をしているものではない。
このように、これらの説明は、憲法24条が「婚姻」の枠組みを定め、その内容を「両性」「夫婦」「相互」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)としていることの背景にある「目的」(国の立法目的)について述べているものではない。
そのことから、これらの説明は、上記で論じている法令の文言を解釈する場合において検討される「目的」(国の立法目的)を示したものであるとはいえず、憲法24条1項が「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めている規範の意味を書き換えることができるとする根拠とはならないものである。
よって、この札幌高裁判決がこれらを「目的」の内容として挙げていることは誤っており、これを根拠として結論を導き出そうとすることも誤りであり、そこで生じたとする結論の内容も誤りとなる。
「法人や外国人の人権が問題となる場合」について検討する。
「婚姻」は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、国家の政策の手段として設けられた制度である。
このような目的を離れて「婚姻」を観念することはできないことから、この目的との関係により「婚姻」として扱うことのできる範囲には内在的な限界がある。
これを前提に、「法人」と「法人」との間で「婚姻」が成立するかどうかであるが、「婚姻」そのものが「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を基にして形成されている概念であり、「法人」と「法人」との間では「生殖」を想定することができず、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的に沿うものではないことから、「婚姻」として扱うことはできない。
また、「法人」については、憲法24条の「婚姻」の文言それ自体が有する内在的な限界や「両性」「夫婦」「配偶者」などの文言に沿うものではないことから、「婚姻」とすることはできない。
もし「法人」を「婚姻」の対象として扱う法律を立法しようとした場合には、憲法24条の「婚姻」「両性」「夫婦」「配偶者」などの文言に抵触して違憲となる。
「外国人」については、自然人であるため、婚姻制度の要件に従って制度を利用する意思を有しているのであれば、「婚姻」することが可能である。
「さらに、仮に立法当時に想定されていなかったとしても、社会の状況の変化に伴い、やはり立法の目的とするところに合わせ、改めて社会生活に適する解釈をすることも行われている。」との記載がある。
「仮に立法当時に想定されていなかったとしても、」との部分について検討する。
「立法当時に想定されていなかった」とあるが、今回の事案において「立法当時に想定されていなかった」といえるかどうかについては、読み方に検討の余地がある。
まず、憲法は「個人の尊厳」の原理に基づいており、自然人は「個人主義」の下に各々「自律的な個人」として生存していくことを予定している。
そして、その個々の自然人は他者との間で人的結合関係を形成、維持、解消する自由を有しており、これは「国家からの自由」という「自由権」の性質として、憲法21条1項の「結社の自由」によって保障されている。
そのような中、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するための枠組みを設けることが求められ、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」を目的として、他の様々な人的結合関係の中から、それらの目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす「一人の男性」と「一人の女性」の組み合わせが選び出され、その間に「貞操義務」を設けるなど一定の形式で法的に結び付け、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によってそれらの目的を達成するものとして形成されたものを「婚姻」と呼んでいる。
そのため、「立法当時」から、他の様々な人的結合関係とは区別する意味で「男女二人一組」の組み合わせが選び出されているのであり、その他の人的結合関係が存在し得ることそのものは「想定されて」いるといえる。
よって、「男女二人一組」ではない、その他の人的結合関係の一つとして「同性間の人的結合関係」が存在することそのものについては、「想定されて」いる事案であるといえる。
その点で、「立法当時に想定されていなかった」とはいえない点に注意が必要である。
次に、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを「立法当時に想定されていなかった」と考える場合について検討する。
先ほども述べたように、「婚姻」という概念は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた枠組みである。
具体的には、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」を目的として、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす「一人の男性」と「一人の女性」の組み合わせに「貞操義務」を設けるなど一定の形式で法的に結び付け、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によってそれらの目的の達成を目指すものとして形成されている。
そのため、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」として「想定されていなかった」ことは、この趣旨を満たすものではないことにより、意図して「想定」していないものといえる。
この点で、「立法当時に想定されていなかった」との意味はその通りであるといえる。
「社会の状況の変化に伴い、」との部分について検討する。
まず、その時々の「社会の状況の変化に伴い、」法規範を改正したり、廃止したりして制度を変更することができるのは、立法府の国会である。
そのため、「社会の状況の変化」を受け止めて、法令を立法するか、改正するか、廃止するかを選択することは立法府の国会の役割であり、司法府の裁判所がこれにあたる行為を行ってはならない。
よって、司法府の裁判所が「社会の状況の変化」を受け止める形で法令に定められている規範の意味を変更することができるかのような前提で論じていることは誤りとなる。
また、法令は予め言語によって規範を定め、その規範に従う形で具体的な事案を処理することで紛争を解決しようとするものであり、その規範の意味が「社会の状況の変化」を勘案することによって揺れ動くということはない。
それまで不明確だった部分が、学術的な理解が進むにつれて明確となり、新たな規範が発見されるという形でより普遍性の高い基準が見出されるということはあり得るが、それは「社会の状況の変化」に合わせる形で規範の意味を読み替えることが可能となるという性質のものではない。
この点について、下記の記事が参考になる。
この記事の内容は、憲法改正について論じているものであるが、解釈を変更することができるかどうかを検討する場面においても共通性を見ることができる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
このように、学問の目的はおしなべて「真理の探究」という点にあるわけですが、先ほども述べたように、憲法も「法」であり学問の一つである以上、その論理は当てはまります。
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
この点、「真理」とは物事の本質であり「矛盾がない」状態を言い、またこの宇宙が存在する限り「普遍的」にゆるぎないものを言いますので、憲法の真理は「矛盾のない普遍的なもの」と言い換えることができます。
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
そこで考えられたのが「法」です。「法」は形而上の世界の絶対的な価値観である「哲学」や「宗教」などによって導き出される命題を、形而下にある現実世界で具現化させるために用いられますので、「法」の根源(真理)には「哲学」や「宗教(神学)」などによって導き出される絶対的・普遍的な命題が内在されているといえます(※ちなみに法学は「形而下学」と呼ばれます)。
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ですから、現代に生きる我々は、哲学的命題という絶対的普遍的な価値観と矛盾しない憲法を追求することが求められているのであり、その哲学的命題という宇宙の真理に矛盾しない憲法を求めるために日々議論を重ねなければならないと言えるのです。
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
「憲法は時代に合わせて変えるべき」とか「実態社会に適合しなくなった憲法は変えるべきだ」という主張はもっともらしく聞こえますが、実はもっともな主張とは言えません。
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
このように、「憲法は時代に合わせて変えるべき」という主張は本来的にファシズムや極右思想や全体主義を呼び込む危険性を包含していることを考えれば妥当な思想ではありません。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
憲法は何を目的として改正されるべきなのか 2018.12.29
このように、解釈の変更は、より普遍性の高い規範が発見された場合に限り認められるべきものであり、そうでない場合に「社会の状況の変化」を理由として変更を認めることは適切ではない。
もし「社会の状況の変化」を理由として変更を認めた場合には、そのような変更は法的安定性を損なうものとなるし、国会の立法権や憲法改正の手続きを侵害するものとして司法権により正当化することのできないものとなる。
よって、「社会の状況の変化に伴い、」のように、「社会の状況の変化」を勘案することによって、法規範の意味が揺れ動き、その揺れ動いた意味に合わせて解釈を変更することができるかのような前提で論じていることは誤りである。
「社会の状況の変化に伴い、」とあるが、そもそも「社会の状況」が「変化」しているといえるかを検討する。
これについて、一般には、毎年、あるいは日々、様々な分野において「社会の状況」は「変化」しているといえる。
例えば、インターネット通信の技術の発達、電子マネーの普及、消費税の増額などを挙げることができる。
しかし、ここで問われているのは、婚姻制度が存在していることの目的との関係において「社会の状況」が「変化」しているかどうかである。
これについて、婚姻制度の「立法当時」から現在においてまで、 人間が有性生殖を行うことによって子孫を産む身体機能を有しており、その「生殖」の営みによって社会的な不都合が生じ得るという事情には何らの変わりもない。
そして、婚姻制度が「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消する制度として機能しなくなった場合には、その社会的な不都合が生じることになることから、婚姻制度がその不都合を解消するための制度として機能することが求められているという事情にも何らの変わりはない。
そのため、婚姻制度が存在している目的との関係において「社会の状況」に「変化」があるとはいえない。
婚姻制度が存在している目的との関係で「社会の状況」に「変化」があるといえる場合とは、人類が有性生殖によって子孫を産むという身体機能を喪失した場合や、進化の過程を経るなどして異なる性別の生殖細胞が融合することのないままに子孫を産むという無性生殖が可能となるなど、生物学的な身体機能において根本的な変化が生じた場合などがこれに当たるといえる。
しかし、婚姻制度の「立法当時」から現在においてまで、そのような状況が生じているという事実はない。
よって、「社会の状況の変化に伴い、」のように婚姻制度が存在していることの目的との関係において「社会の状況」に「変化」が存在するかのような前提で論じることは妥当な認識ではない。
これらのことから、この札幌高裁判決で問われている事案に対して「社会の状況の変化」を挙げることは正当化することができない。
「やはり立法の目的とするところに合わせ、改めて社会生活に適する解釈をすることも行われている。」との部分について検討する。
「やはり立法の目的とするところに合わせ、」とある。
条文を解釈する際に「立法の目的とするところに合わせ」て解釈する場合があるということはその通りである。
しかし、一文前のところで解説したように、条文に記された内容から離れることが無制限に許されるわけではない。
また、そもそも「立法の目的とするところに合わせ」て条文の意味を読み解いたとしても、今回の事案においては結論が変わるということはない。
このため、今回の事案が「立法の目的とするところに合わせ」て解釈されていないことを前提として、「立法の目的とするところに合わせ」て解釈することによって結論が変わるかのように述べていることは誤りである。
「改めて社会生活に適する解釈をすることも行われている。」とある。
まず、この「社会生活に適する解釈」というものが、裁判官の恣意に流れるようなものであってはならない。
そのため、公共的な合意として機能する基準となるものを見出せることが必要である。
憲法24条は「婚姻」を規定し、「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)の枠組みを具体的に示している。
これについて、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することが必要とされていおり、それを達成するための手段として「婚姻」という枠組みが設けられている以上は、それを達成するための手段として機能する枠組みについて示したものと読み解くことが「社会生活に適する解釈」に当たるものであるといえる。
そのことから、これらの文言は、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」を目的として、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす「一人の男性」と「一人の女性」の組み合わせを選び出し、その間に「貞操義務」を設けるなど一定の形式で法的に結び付け、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によってそれらの目的を達成することを目指すという手段を採用しているものと読み取ることが妥当である。
そのため、憲法24条が「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)の枠組みを定めていることは、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的と対応するものとして定められているものであることから、それはそのまま一夫一婦制(男女二人一組)の枠組みを定めたものと読み解くことこそが、「社会生活に適する解釈をする」ことにより導き出される結論であるといえる。
このため、この「社会生活に適する解釈」というものを前提として考えたとしても、これとは異なる結論を導き出すことができるということにはならない。
よって、この「社会生活に適する解釈」というものを根拠として、これとは異なる結論が導き出されるかのように論じることは誤りである。
「したがって、憲法24条についても、その文言のみに捉われる理由はなく、個人の尊重がより明確に認識されるようになったとの背景のもとで解釈することが相当である。」との記載がある。
「憲法24条についても、その文言のみに捉われる理由はなく、」とある。
「憲法24条」は「婚姻」を規定しており、これは「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」を目的として、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす「一人の男性」と「一人の女性」を選び出し、その間に「貞操義務」を設けるなど一定の形式で法的に結び付け、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によって立法目的の達成を目指すものである。
「憲法24条」がその「婚姻」について「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)の枠組みを示していることも、この趣旨に対応するものである。
そのため、この「憲法24条」が「婚姻」を規定し、「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めており、その枠組みの「要請」に従って法律上の婚姻制度が一夫一婦制(男女二人一組)で立法されていることについては、「憲法24条」の「文言」に沿うものとなっているが、これは単に「その文言のみに捉われ」ているというものではなく、「婚姻」の枠組みが有する上記の趣旨との対応関係を前提として、「婚姻」という枠組みそのものの「目的とするところを踏まえて」、「立法の目的とするところに合わせ」て導き出されているものである。
そのため、「憲法24条」の下で法律上の婚姻制度が一夫一婦制(男女二人一組)で立法されていることについて、単に「文言のみに捉われ」ているものであり、「その目的とするところを踏まえて」おらず「立法の目的とするところに合わせ」て考えるものとなっていないという認識の下に、「その文言のみに捉われる理由はなく、」と述べていることは、そもそもの前提となる認識の部分において誤っているといえる。
「憲法24条についても、……(略)……個人の尊重がより明確に認識されるようになったとの背景のもとで解釈することが相当である。」とある。
この「個人の尊重」の文言は、憲法13条前段の「すべて国民は、個人として尊重される。」の部分を前提として述べているものと考えらる。
しかし、憲法13条と「憲法24条」は共に憲法上の規定であることから、それらは相互に矛盾するものではない。
そのため、この憲法13条の「個人の尊重」が「明確に認識される」とか、さなれないとかいうことによって、「憲法24条」の規範の意味が変わるということはない。
よって、「憲法24条」について「個人の尊重がより明確に認識されるようになった」のように憲法13条を根拠として「その文言のみに捉われる理由」がなくなり、それを原因として「解釈」が変更されることがあり得るかのように述べていることは誤りである。
◇ この札幌高裁判決の誤った説明
13条の「個人の尊重」
↓
↓
24条の「婚姻」 ←←← 24条の「個人の尊厳」で枠を改変
↓ ↓
↓(保障) ↓(合理性)
↓ ↓
自由な結びつき → ? → 法律上の婚姻制度
(自由権?)
◇ 本来の整合性のある説明 (再婚禁止期間制度や夫婦同姓制度の大法廷判決)
24条の「婚姻」 ← (矛盾なし) → 13条「個人の尊重」
↓ |
↓ |
↓ 24条の「個人の尊厳」の審査
↓ ↓
↓(要請) ↓
↓ ↓
法律上の婚姻制度 ←←←
その他、憲法制定当初より「個人の尊重」はなされているのであり、それが現在初めて「個人の尊重がより明確に認識されるようになった」かのような理解は誤りである。
むしろ、この裁判官は今まで「個人の尊重」がなされていなかったかのような理解を有しているようであるが、憲法制定当初より「個人の尊重」はなされていることを認識できていないものであり、誤っている。
他にも、「個人の尊重」を述べているということは、それは自然人は「個人主義」の下で各々「自律的な個人」として生存していくことが基準(スタンダード)であることを示しているものである。
そのため、この「個人の尊重」を持ち出したしても、ここから何らかの人的結合関係を対象とした制度を設けなければならないという特定の結論を導き出すことに繋がるものではない。
そのことから、「個人の尊重」を理由とすることで、婚姻制度を含め、あらゆる法制度を自由に書き換えることができるということにはならないし、まして、「個人の尊重」について触れている13条と同様に憲法上の規定として定められている24条の意味を書き換えることまで正当化することができるとする根拠となるものではない。
よって、「個人の尊重がより明確に認識されるようになったとの背景のもとで解釈することが相当である。」のように述べて、結論を導くために「個人の尊重」を理由としていることは誤りである。
その上で、性的指向及び同性間の婚姻の自由は、現在に至っては、憲法13条によっても、人格権の一内容を構成する可能性があり、十分に尊重されるべき重要な法的利益であると解されることは上記のとおりである。憲法24条1項は、婚姻をするかどうか、いつ誰と婚姻をするかについては、当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたものと解され、このような婚姻をするについての自由は、同項の規定に照らし、十分尊重に値するものと解することができる(再婚禁止期間制度訴訟大法廷判決参照)。そして、憲法24条2項は、婚姻及び家族に関する事項についての立法に当たっては、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきと定めている。そうすると、性的指向及び同性間の婚姻の自由は、個人の尊重及びこれに係る重要な法的利益であるのだから、憲法24条1項は、人と人との間の自由な結びつきとしての婚姻をも定める趣旨を含み、両性つまり異性間の婚姻のみならず、同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障していると考えることが相当である。
【筆者】
━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━
この段落の内容が読み取りづらい原因は、下記の通りである。
◇ 第一文は「その上で、」と前の文から繋ぐものとなっている。
この「その」の部分が前の文の「個人の尊重がより明確に認識されるようになったとの背景のもとで解釈することが相当である。」との部分を指していると考えると、この文の「憲法13条」に対応するものとして示そうとしていることまでは意味を読み取ることができる。
ただ、その後、この段落では第二文、第三文、第四文と話が続くが、この第一文の「その上で、」という部分は第一文だけに係るものとしてまとまっており、第二文、第三文とは切り離されており、そこに係っているわけではない。
しかし、この第二文、第三文についても、第一文と同様に、一段落前の最後の文である「個人の尊重がより明確に認識されるようになったとの背景のもとで解釈することが相当である。」との前提の中で説明されている事柄であることは同じであり、第一文と並列の関係にあるものとして示された後に、第四文で「そうすると、」と示された後にこの段落の結論が導かれるものとなっている。
そのため、この第一文の「その上で、」の使い方は、第一文のみを一段落前の最後の文と接続するものであるかのように見せながら、その後の第二文、第三文も一段落前の最後の文を前提として話が続くものであることは同じであるという状態となるため、話の流れに対応するものとなっていない。
よって、「その上で、」の言葉の使い方は、一文前である一段落前の最後の文とこの段落の第二文、第三文との間の接続の関係を明確なものとして読み取ることが困難であり、適切な表現であるとはいえない。
◇ 第四文の「そうすると、」以下は、検討の結果としての「結論」を述べるものとなっている。
しかし、その「結論」を述べる中で「性的指向及び同性間の婚姻の自由は、個人の尊重及びこれに係る重要な法的利益であるのだから、」のように、この段落の第一文で登場した検討の過程の説明が繰り返されており、内容が重複するものとなっている。
・通常の構成
「解釈の前提」→「解釈の過程」→「解釈の結論」
・この文
「解釈の前提」→「解釈の過程」→「(解釈の過程の一つ)→解釈の結論」
これにより、読み手は「結論」をはっきりと認識することが困難となり、読み都づらく感じることとなる。
◇ 第四文の「そうすると、」以下は、第一文、第二文、第三文での検討の過程ではなく、解釈の結論を述べる部分である。
そのため、第四文は、第一文、第二文、第三文とは性質の異なる文であることを明らかにするために、改行を加えて別のまとまりとして示した方が分かりやすかったといえる。
━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━
「性的指向及び同性間の婚姻の自由は、現在に至っては、憲法13条によっても、人格権の一内容を構成する可能性があり、十分に尊重されるべき重要な法的利益であると解されることは上記のとおりである。」との記載がある。
━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━
この文が読み取りづらい原因は下記の通りである。
◇ 「憲法13条によっても、」とあるが、この「よっても」の言葉に続く形でどのような扱いがなされているのかその結果が説明されておらず、そのまま文が終わっている。
これにより、読み手はこの「よっても」が何に係っているのか未解決のまま放置されることになり、意味を掴むことができなくなるのである。
━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━
「性的指向及び同性間の婚姻の自由」との部分について検討する。
「性的指向」とは、「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかに関するものであり、個人の内心における精神的なものである。
このような事柄は「内心の自由」として憲法19条の「思想良心の自由」として保障されるものである。
ここでは「憲法13条」や「人格権」を持ち出しているが、憲法19条の「思想良心の自由」として保障されるものであるため、誤りである。
「人格権の一内容を構成する可能性があり、」とあるが、憲法19条の「思想良心の自由」として保障されるものであることから、「人格権の一内容を構成する」というものではない。
ここでいう「同性間の婚姻」の意味が、これが「同性間の人的結合関係」を形成することを指しているのであれば、それは憲法21条1項の「結社の自由」によって保障されるものである。
ここでは、「憲法13条」や「人格権」を持ち出しているが、人的結合関係を形成することについての具体的な条文が憲法21条1項の「結社の自由」として存在しているのであるから、「憲法13条」として説明することは適切ではないし、「人格権」と結び付けて考えていることも誤りである。
ここでいう「同性間の婚姻」の意味が「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを指しているのであれば、「婚姻」という概念の中に「同性間の人的結合関係」を含めることができるかどうかという点から検討することが必要である。
「婚姻」とは、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた枠組みである。
具体的には、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」を目的として、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす「一人の男性」と「一人の女性」の組み合わせを「貞操義務」などの一定の形式で法的に結び付け、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によって立法目的の達成を目指すものである。
また、憲法24条はその「婚姻」を規定し、「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めていることも、この趣旨に対応するものである。
「同性間の人的結合関係」については、その間で「生殖」を想定することができず、この「生殖と子の養育」の趣旨を満たすものではないし、憲法24条が「婚姻」について「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めている趣旨にも沿うものではないため、「婚姻」の中に含めることはできない。
よって、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることができることを前提に、「同性間の婚姻」と述べていることは誤りとなる。
その後に続く「婚姻の自由」との部分だけを見ると、これは「再婚禁止期間大法廷判決(平成27年12月16日)」が示した「婚姻をするについての自由」について述べようとしているものと考えられる。
ただ、「再婚禁止期間大法廷判決(平成27年12月16日)」の内容は、憲法24条1項が「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めていることを前提として、その憲法24条の「要請」に従って定められている法律上の婚姻制度を利用するか否かに関する自由をいうものである。
そのため、そこで述べられた「婚姻をするについての自由」と述べているものについても、このような「男女二人一組」を対象としている婚姻制度を利用するか否かについての「自由」について述べられているものである。
そのことから、この「婚姻をするについての自由」の中には、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを求めることができるという意味は含まれていない。
よって、「同性間の婚姻の自由」のように、これを一続きに述べたとしても、「婚姻」そのものによって「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることができることにはならないし、ここでいう「自由」についても、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として定められている「婚姻」という枠組みを利用するか否かに関する「自由」をいうものであることから、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」の中に含めることを国家に対して求めることができるという意味を有するものではない。
また、その「婚姻をするについての自由」とは、「再婚禁止期間制度訴訟大法廷判決」で述べられているように、憲法24条1項を解釈することにより導かれているものであることから、「憲法13条」から導き出しているものではないし、「人格権」として理解するものでもない。
よって、「婚姻をするについての自由」が「憲法13条」や「人格権」から導かれるかのように論じていることは誤りである。
この「人格権の一内容を構成する可能性があり、」との記述は、「2 本件規定が憲法13条に違反する旨の主張について」の項目の「(2)イ」の第一段落で「このように性的指向、さらには同性間の婚姻の自由が人格権の一内容を構成し得る」と述べて、最後に参照として「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」を示している部分と同じ趣旨である。
よって、この「人格権の一内容を構成する可能性があり、」という説明についても、「(2)イ」の第一段落と同様に「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」に裏付けられる形で論じようとするものということになる。
しかし、「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」で論じているのは、「氏名」については「謝罪広告等請求事件」で「人格権の一内容を構成するもの」であり、「人は、他人からその氏名を正確に呼称されることについて、不法行為法上の保護を受けうる人格的な利益を有する」と述べた通りであるが、そこから遡って、その「氏名」を構成している「氏」の制度の仕組みそのものについては「法律がその具体的な内容を規律しているもの」であるから「具体的な法制度を離れて,氏が変更されること自体を捉えて直ちに人格権を侵害し,違憲であるか否かを論ずることは相当ではない。」としており、結論としても「氏が,」「身分関係の変動に伴って改められることがあり得ることは,その性質上予定されている」ことなどを理由に「婚姻の際に「氏の変更を強制されない自由」が憲法上の権利として保障される人格権の一内容であるとはいえない。」としているものである。
この点、この「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」では、「氏名」について定めた具体的な法制度の存在を前提として論じているのに対して、この札幌高裁判決が取り上げる「性的指向」とは、「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを示すものであり、個々人の内心における心理的・精神的なものであることから、具体的な法制度の存在を前提とするものではない。
そのため、「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」とこの札幌高裁判決では事案の性質を異にするものである。
また、下記の点でも性質が異なっている。
「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」では、「氏名は,社会的にみれば,個人を他人から識別し特定する機能を有するものであるが,同時に,その個人からみれば,人が個人として尊重される基礎であり,その個人の人格の象徴であって,」と述べている。
このように、「氏名」を「社会的」に見た場合に個人識別機能を有していることを認め、その後、その個人識別機能の存在を前提として考えれば、全体の一部として扱われたり、他者と混同されることはないという意味において、「人が個人として尊重される基礎」となり「その個人の人格」を「象徴」することができるという点で、「人格権の一内容を構成するもの」という権利の性質を捉えるものとなっている。
これに対して、この札幌高裁判決で述べている「性的指向」と称するものは、「性愛」を抱く場合に、それがどのような対象に向かうかに関するものであり、これは個人の内心における精神的なものとして捉えられる以上の機能や役割を果たすものではないし、ある人を他者との間で識別し、本人を特定することができるという機能を持つものでもないため、これを「人格権」として捉える基礎を欠くものである。
また、ここでいう「同性間の婚姻」の意味が「同性間の人的結合関係」を指すものであれば、それを形成する「自由」は、「国家からの自由」という「自由権」の性質により、憲法21条1項の「結社の自由」として保障されるものであるため、これも「人格権」を持ち出す前提に前提にないものである。
他にも、ここでいう「同性間の婚姻」の意味が「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを指すのであれば、そもそも「同性間の人的結合関係」はその間で「生殖」を想定することができず、「生殖と子の養育」の趣旨に従って統一的に形成される枠組みとして整合性がないことから、「婚姻」の中に含めることはできないものである。
さらに、「婚姻の自由」と述べている部分も、これは「再婚禁止期間制度訴訟大法廷判決」の示した「婚姻をするについての自由」をいうものと考えられ、これは憲法24条1項から導かれたものであり、憲法13条を根拠とするものではないし、「人格権」して説明されるものでもない。
よって、「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」とこの札幌高裁判決では事案の性質が異なるにもかかわらず、この「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」の文面に記されている言葉遣いだけを真似る形で同様に論じることができるかのような前提で「人格権の一内容を構成する可能性があり、」と述べていることは誤りである。
「十分に尊重されるべき重要な法的利益であると解される」という部分であるが、「法的」な保障の仕方は下記のようになる。
「性的指向」は、個人の内心における精神的なものであることから、憲法19条の「思想良心の自由」によって保障される。
この憲法19条の「思想良心の自由」は、「国家からの自由」という「自由権」の性質であることから、もし国家から個人の内心に対して具体的な侵害行為があった場合には、それを排除する場面で用いられることになる。
しかし、この憲法19条の「思想良心の自由」を用いて、特定の制度の創設を国家に対して求めることはできない。
「同性間の婚姻」の意味が「同性間の人的結合関係」を形成することを指しているのであれば、 それは、憲法21条1項の「結社の自由」によって保障される。
この憲法21条1項の「結社の自由」についても、「国家からの自由」という「自由権」の性質であることから、もし国家から個人に対して人的結合関係を形成することを禁止するような具体的な侵害行為があった場合には、それを排除することができる場合が考えられる。
しかし、この憲法21条1項の「結社の自由」を用いて、特定の制度の創設を国家に対して求めることはできない。
「同性間の婚姻」の意味が「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを指しているのであれば、上記で説明したように、そもそも「婚姻」の中に含めることのできる人的結合関係の範囲には内在的な限界があり、「同性間の人的結合関係」はその間で「生殖」を想定することができず、「生殖と子の養育」の趣旨を満たすものではないことから、「婚姻」とすることはできない。
そのため、「婚姻」の中にどのような人的結合関係でも含めることができるなどという自由は保障されているものではない。
「再婚禁止期間制度訴訟大法廷判決」が示した「婚姻をするについての自由」については、その判決の中で「配偶者の相続権(民法890条)や夫婦間の子が嫡出子となること(同法772条1項等)などの重要な法律上の効果が与えられるものとされている」ことから「十分尊重に値するものと解することができる。」と述べているものである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
……(略)……また,同条1項は,「婚姻は,両性の合意のみに基いて成立し,夫婦が同等の権利を有することを基本として,相互の協力により,維持されなければならない。」と規定しており,婚姻をするかどうか,いつ誰と婚姻をするかについては,当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたものと解される。婚姻は,これにより,配偶者の相続権(民法890条)や夫婦間の子が嫡出子となること(同法772条1項等)などの重要な法律上の効果が与えられるものとされているほか,近年家族等に関する国民の意識の多様化が指摘されつつも,国民の中にはなお法律婚を尊重する意識が幅広く浸透していると考えられることをも併せ考慮すると,上記のような婚姻をするについての自由は,憲法24条1項の規定の趣旨に照らし,十分尊重に値するものと解することができる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ただ、この「婚姻をするについての自由」は、憲法24条1項が「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めている中において、その「要請」に従って立法されている法律上の婚姻制度を利用するか否かについての自由について、この憲法24条1項を解釈したものとして導かれているものである。
そのため、この憲法24条1項を解釈した結果として導かれているいわば下位法に当たるものを用いて、憲法24条1項が「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めている枠組みそのものを変更することができるとする根拠とはならない。
上位法:憲法24条1項
↓(解釈)
下位法:「婚姻をするについての自由」
このようにいわば下位法として示された解釈を用いてその上位法である憲法24条1項の枠組みを変更することはできない。
よって、この「婚姻をするについての自由」を用いて、憲法24条の定める一夫一婦制(男女二人一組)の枠組みそのものを変更することができるという根拠とすることはできず、この「婚姻をするについての自由」は、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」の中に含めることができるというような自由を保障するものであるとはいえない。
このように、これらについて「法的」に保障できるとは限らないし、「法的」な保障を検討する場合があるとしても、それはここでいう「憲法13条」や「人格権」として保障されるものではない。
よって、「憲法13条」や「人格権」によって「法的」な保障について検討できるかのように述べていることは誤りとなる。
この文は、最後に「上記のとおりである。」と述べているように、これよりも前の部分で「憲法13条によっても、人格権の一内容を構成する可能性があり、十分に尊重されるべき重要な法的利益であると解される」ことについて触れていることを前提としている。
そこで、同様の趣旨の文を探すと、下記のような記載を見つけることができる。
「2 本件規定が憲法13条に違反する旨の主張について」の項目
◇ 「(2)ア」第二段落の第三文
「したがって、性的指向は、重要な法的利益であるということができる。」
◇ 「(2)ア」第三段落
「以上のとおり、性的指向は生来備わる性向であり、……(略)……その個人からみれば、人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の象徴であって、人格権の一内容を構成し得るものというべきである。」
◇ 「(2)イ」第一段落第一文
「しかし、このように性的指向、さらには同性間の婚姻の自由が人格権の一内容を構成し得るとしても、」
◇ 「(3)」第一段落第一文
「もっとも、性的指向及び同性間の婚姻の自由は、人格権の一内容を構成し得る重要な法的利益ということができる。」
◇ 「(3)」第三段落
「したがって、性的指向及び同性間の婚姻の自由は、憲法上の権利として保障される人格権の一内容を構成し得る重要な法的利益として、」
しかし、「性的指向」とは、「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを指すものであり、個人の内心における精神的なものであることから、「内心の自由」として憲法上の条文では19条の「思想良心の自由」によって保障されるものである。
そのため、これについて「憲法13条」を持ち出したり、「人格権の一内容を構成する」などと論じていることは誤りである。
また、「同性間の婚姻」の意味が「同性間の人的結合関係」を指す場合であれば、その「同性間の人的結合関係」を形成する「自由」については、「国家からの自由」という「自由権」の性質として憲法21条1項の「結社の自由」として保障されるものである。
そのため、これについても「憲法13条」を持ち出したり、「人格権の一内容を構成する」などと論じていることは誤りである。
「同性間の婚姻」の意味が「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを指すとしても、「同性間の人的結合関係」はその間で「生殖」を想定することができず、「生殖と子の養育」の趣旨を満たすものではないことから、「婚姻」とすることはできない。
「婚姻の自由」についても、憲法24条1項が一夫一婦制(男女二人一組)を定めていることを前提として、その憲法24条の「要請」に従って立法された法律上の婚姻制度を利用するか否かについての自由をいうものであることから、憲法24条1項の解釈として導かれるいわば下位法として述べられているものであり、この下位法を理由としてその上位法である憲法24条1項が一夫一婦制(男女二人一組)の枠組みを定めていることを変更することができるとする根拠とはならない。
よって、この「婚姻の自由」と称しているものを理由として、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを求めることができることにはならない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
……(略)……このように,被告は,現行の法制度が憲法の要請に従って構築されたものであることを前提に,かかる法制度を超える上記の新たな制度の創設を求める権利が憲法13条における自己決定権に含まれるものではないと主張しているのであって,国家の制度を前提にするか否かによって憲法上の保障に値するか否かが決定されると主張しているのではない。
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
そして,婚姻の自由が憲法13条によって保障されるとの見解についてみれば,被告第3準備書面第2の2 (2)イ(ア)(7,8ページ)で述べたとおり,婚姻は,必然的に一定の法制度の存在を前提としている以上,仮に婚姻に関する自己決定権を観念できるとしても,その自己決定権は憲法の要請に従って構築された法制度の枠内で保障されるものにとどまると考えられる。しかるところ,上記見解のいう「婚姻の自由」が,性別を問わず配偶者を選択する自由を含む権利であるとすると,それは,「両性」の本質的平等に立脚すぺきことを規定する憲法24条2項の要請に従って創設された現行の法制度の枠を超えて,同性の者を婚姻相手として選択できることを含む内容の法制度の創設を求めるものにほかならない。……(略)……
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【東京・第6回】被告第4準備書面 PDF (P9~12)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ア(ア)しかしながら、被告第4準備書面第2の2 (8及び9ページ)及び同3(2) (13ないし16ページ)で述ぺたとおり、婚姻及び家族に関する事項については、憲法24条2項に基づき、法律によって具体的な内容を規律するものとされているから、婚姻及び家族に関する権利利益等の内容は、憲法の趣旨を踏まえつつ、法律によって定められる制度に基づき初めて具体的に捉えられるものである。そうすると、婚姻の法的効果を享受する利益や、「婚姻をするかどうか、いつ誰と婚姻をするか」を当事者間で自由に意思決定し、故なくこれを妨げられないという婚姻をするについての自由は、憲法の定める婚姻を具体化する法律(本件規定)に基づく制度によって初めて個人に与えられる、あるいはそれを前提とした自由であり、法制度を離れた生来的、自然権的な自由権として憲法上保障されていると解することはできない。
そうすると、原告らの「婚姻の自由」に関する主張について、自由権の侵害を問題とするものとしては前提を欠いているというぺきである。
(イ)原告らは、上記(1)のとおり、同性力ップルにおいても婚姻の自由は憲法13条により保障されている旨及ぴ同性カップルを婚姻から排除することが違憲である旨主張するが、原告らの主張の本質は、同性間の人的結合関係についても、異性間の人的結合関係を対象とする婚姻と同様の積極的な保護や法的な利益の供与を認める法制度の創設を国家に対して求めるものにほかならない。このような内実のものにすぎない個々の権利若しくは利益又はその総体が憲法13 条の規定する幸福追求権の一内容を構成するものと解することはできず、これは、同性間の人的結合関係を婚姻の対象に含めることが、同性間の婚姻を指向する当事者の自由や幸福追求に資する面があるとしても変わるものではないことは被告第4準備書面第2の2
(8及び9ページ)で述べたとおりである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【九州・第11回】被告第6準備書面 令和4年11月30日 PDF (P7~8)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
しかしながら,人は,一般に,社会生活を送る中で,種々の かつ多様な人的結合関係を生成しつつ,生きていくものであり,当該人的結合関係の構築,維持及び解消をめぐる様々な場面において幾多の自己決定を行っていくものと解されるが,そのような自己決定を故なく国家により妨げられているか否かということと,そのような自己決定の対象となる人的結合関係について国家の保護を求めることができるか否かということとは,少なくとも憲法13条の解釈上は区別して検討されるべきものと解される。
前記2で述べたとおり,婚姻が一定の法制度を前提としている以上,「婚姻をするかどうか,いつ誰と婚姻をするか」を当事者間で自由に意思決定し,故なくこれを妨げられないという「婚姻をするについての自由」は,法制度を離れた生来的,自然権的な自由権として憲法で保障されているものと解することはできない。前記1で述べたとおり,憲法24条1項は,婚姻について異性間の人的結合関係のみを対象とし,同性間の人的結合関係を対象とすることを想定しておらず,同条2項も,飽くまで婚姻が異性間の人的結合関係のみを対象とするものであることを前提としてこれを具体化する制度の整備を立法府に要請するものであり,これを受けて定められた本件規定も,婚姻が異性間の人的結合関係のみを対象とするものであることを前提に定められている。
そうすると,原告らが「婚姻の自由」として主張するものの内実は,「両性」の本質的平等に立脚すべきことを規定する憲法24条2項の要請に従って創設された現行の婚姻制度の枠を超えて,同性間の人的結合関係についても婚姻と同様の積極的な保護や法的な利益の供与を認める法制度の創設を国家に対して求めるものにほかならないのであって,国家からの自由を本質とするものではないから,このような自由が憲法13条の幸福追求権の一内容を構成するものと解することはできない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【九州・第6回】被告第4準備書面 令和3年l0月29日 PDF
「憲法24条1項は、婚姻をするかどうか、いつ誰と婚姻をするかについては、当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたものと解され、このような婚姻をするについての自由は、同項の規定に照らし、十分尊重に値するものと解することができる(再婚禁止期間制度訴訟大法廷判決参照)。」との記載がある。
この文が参照している「再婚禁止期間制度訴訟大法廷判決」と文言が重なる部分は下記の通りである。
(灰色で潰した部分が、上記と文言が重なっている。)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ところで,婚姻及び家族に関する事項は,国の伝統や国民感情を含めた社会状況における種々の要因を踏まえつつ,それぞれの時代における夫婦や親子関係についての全体の規律を見据えた総合的な判断を行うことによって定められるべきものである。したがって,その内容の詳細については,憲法が一義的に定めるのではなく,法律によってこれを具体化することがふさわしいものと考えられる。憲法24条2項は,このような観点から,婚姻及び家族に関する事項について,具体的な制度の構築を第一次的には国会の合理的な立法裁量に委ねるとともに,その立法に当たっては,個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきであるとする要請,指針を示すことによって,その裁量の限界を画したものといえる。また,同条1項は,「婚姻は,両性の合意のみに基いて成立し,夫婦が同等の権利を有することを基本として,相互の協力により,維持されなければならない。」と規定しており,婚姻をするかどうか,いつ誰と婚姻をするかについては,当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたものと解される。婚姻は,これにより,配偶者の相続権(民法890条)や夫婦間の子が嫡出子となること(同法772条1項等)などの重要な法律上の効果が与えられるものとされているほか,近年家族等に関する国民の意識の多様化が指摘されつつも,国民の中にはなお法律婚を尊重する意識が幅広く浸透していると考えられることをも併せ考慮すると,上記のような婚姻をするについての自由は,憲法24条1項の規定の趣旨に照らし,十分尊重に値するものと解することができる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
再婚禁止期間制度訴訟大法廷判決 (PDF)
まず、「婚姻」とは、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」を目的として、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす「一人の男性」と「一人の女性」を選び出し、その間に「貞操義務」を設けるなど一定の形式で法的に結び付け、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によって立法目的の達成を目指す枠組みのことである。
また、憲法24条が「婚姻」について「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めていることも、この趣旨に対応するものである。
この「再婚禁止期間制度訴訟大法廷判決」についてもこれを前提とした「婚姻」について述べるものであり、その文面においても、上記の下線部で「夫婦や親子関係」や「夫婦間」の文言を用いており、一夫一婦制(男女二人一組)であることを前提とするものとなっている。
そのため、「憲法24条1項」が、「婚姻をするかどうか、いつ誰と婚姻をするかについては、当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたものと解され、」るとしても、そこでいう「婚姻」の意味は、常にこのような目的とその目的を達成するための手段として設けられた一夫一婦制(男女二人一組)の枠組みのことを指すものである。
これについて、国(行政府)は下記のように述べている。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
したがって、憲法24条1項は、婚姻について異性間の人的結合関係のみを対象としており、「婚姻をするかどうか、いつ誰と婚姻をするか」を当事者で自由に意思決定し、故なくこれが妨げられないという意味における「婚姻をするについての自由」は、異性間の人的結合関係を対象とする婚姻についてのみ保障されていると解するのが相当である。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【東京二次・第9回】被告第7準備書面 令和5年9月28日 PDF
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
かえって、同判決が、婚姻制度における男女の区別の合理性が争われ、その区別が憲法14条1項及び「両性の本質的平等」を定めた憲法24条2項に違反すると判断された事案であることからすれば、同判決における判事が、憲法24条2項の「両性」をまさに男女を表すものとして理解していることは明らかであって、「両性の合意」によって成立するとされる同条1項の婚姻についても、男女を当事者とするものであることを当然の前提にしていると見るほかない。同判決における判示が、原告らの主張するような異性間か同性間かを捨象した婚姻の自由を保障することを前提とするものであると解することは到底できない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【東京二次・第5回】被告第3準備書面 令和4年6月20日
そのため、この「男女二人一組」を前提とした「婚姻」について述べている「再婚禁止期間制度訴訟大法廷判決」の文面を用いても、「婚姻」の中に「同性間の人的結合関係」を含めることができるとする根拠とはならないものである。
つまり、「再婚禁止期間制度訴訟大法廷判決」の文面は、「男女二人一組」を満たさない人的結合関係についてまで判断しているものではないことから、そこで「男女二人一組」を前提として説明されている「婚姻をするについての自由」の文言を基にして、これを満たさない人的結合関係を「婚姻」の中に含めることができるとする根拠とすることはできないし、これを満たさない人的結合関係についても同様に「婚姻をするについての自由」を得られるとする根拠となるものでもないということである。
よって、ここでこの「再婚禁止期間制度訴訟大法廷判決」の「憲法24条1項は、婚姻をするかどうか、いつ誰と婚姻をするかについては、当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたものと解され、このような婚姻をするについての自由は、同項の規定に照らし、十分尊重に値するものと解することができる」との文面を持ち出したとしても、これはこの段落の第四文で「憲法24条1項は、……(略)……同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障していると考えることが相当である。」という結論を導き出す根拠となるものではなく、これを理由してその結論を正当化することができるということにはならない。
次に、この「婚姻をするについての自由」の意味について検討する。
これは「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、他の様々な人的結合関係とは区別する形で、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」を目的として、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす「一人の男性」と「一人の女性」を選び出し、その間に「貞操義務」を設けるなど一定の形式で法的に結び付け、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によって立法目的の達成を目指す仕組みとして形成されている「婚姻」という枠組みが存在することを前提とし、これを「する」か否かの「自由」について述べるものである。
つまり、婚姻制度を利用するか否かについての「自由」をいうものである。
そのことから、これは、具体的な制度を前提とするものではない、国家から個人に対して侵害行為がある場合にそれを排除する場面で用いる「国家からの自由」という「自由権」(生来的,自然権的な権利)について述べるものではない。
これについて、国(行政府)は下記のように述べている。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
もっとも,婚姻及び家族に関する事項については,前記1 (1)のとおり,憲法24条2項に基づき,法律によって具体的な内容を規律するものとされているから,婚姻及び家族に関する権利利益等の内容は,憲法上一義的に捉えられるべきものではなく,憲法の趣旨を踏まえつつ,法律によって定められる制度に基づき初めて具体的に捉えられるものである。そうすると,婚姻の法的効果(例えば,民法の規定に基づく,夫婦財産制,同居・協力・扶助の義務,財産分与,相続,離婚の制限,嫡出推定に基づく親子関係の発生,姻族の発生,戸籍法の規定に基づく公証等)を享受する利益や,「婚姻をするかどうか,いつ誰と婚姻をするか」を当事者間で自由に意思決定し,故なくこれを妨げられないという婚姻をすることについての自由は,憲法の定める婚姻を具体化する法律(本件規定)に基づく制度によって初めて個人に与えられる,あるいはそれを前提とした自由であり,生来的,自然権的な権利又は利益,人が当然に享受すべき権利又は利益ということはできない。このように,婚姻の法的効果を享受する利益や婚姻をすることについての自由は,法制度を離れた生来的,自然権的な権利又は利益として憲法で保障されているものではないというべきである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【九州・第6回】被告第4準備書面 令和3年10月29日 PDF (P8)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
前記2で述べたとおり,婚姻が一定の法制度を前提としている以上,「婚姻をするかどうか,いつ誰と婚姻をするか」を当事者間で自由に意思決定し,故なくこれを妨げられないという「婚姻をするについての自由」は,法制度を離れた生来的,自然権的な自由権として憲法で保障されているものと解することはできない。前記1で述べたとおり,憲法24条1項は,婚姻について異性間の人的結合関係のみを対象とし,同性間の人的結合関係を対象とすることを想定しておらず,同条2項も,飽くまで婚姻が異性間の人的結合関係のみを対象とするものであることを前提としてこれを具体化する制度の整備を立法府に要請するものであり,これを受けて定められた本件規定も,婚姻が異性間の人的結合関係のみを対象とするものであることを前提に定められている。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【九州・第6回】被告第4準備書面 令和3年l0月29日 PDF
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
しかしながら、被告第2準備書面第4の2(2)および(3)(14ないし16ページ)で述べたとおり、憲法24条1項は、婚姻について異性間の人的結合関係のみを対象とし、同性間の人的結合関係を対象とすることを想定しておらず、同条2項も、飽くまで婚姻が異性間の人的結合関係を対象とするものであることを前提として、これを具体化する制度の整備を立法府に要請しているのであり、本件規定は、かかる要請に基づき、婚姻について、異性間の人的結合関係のみを対象とするものとしてその具体的な内容を定めているということができる。また、被告第2準備書面第4の2(4)イ(ア)(16ないし18ページ)で述べたとおり、婚姻が一定の法制度を前提としている以上、「婚姻をするかどうか、いつ誰と婚姻をするか」を当事者間で自由に意思決定し、故なくこれを妨げられないという「婚姻をするについての自由」は、法制度を離れた生来的、自然権的な自由権として憲法で保障されているものと解することはできない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【東京二次・第5回】被告第3準備書面 令和4年6月20日 (P11)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ア(ア)しかしながら、被告第4準備書面第2の2 (8及び9ページ)及び同3(2) (13ないし16ページ)で述ぺたとおり、婚姻及び家族に関する事項については、憲法24条2項に基づき、法律によって具体的な内容を規律するものとされているから、婚姻及び家族に関する権利利益等の内容は、憲法の趣旨を踏まえつつ、法律によって定められる制度に基づき初めて具体的に捉えられるものである。そうすると、婚姻の法的効果を享受する利益や、「婚姻をするかどうか、いつ誰と婚姻をするか」を当事者間で自由に意思決定し、故なくこれを妨げられないという婚姻をするについての自由は、憲法の定める婚姻を具体化する法律(本件規定)に基づく制度によって初めて個人に与えられる、あるいはそれを前提とした自由であり、法制度を離れた生来的、自然権的な自由権として憲法上保障されていると解することはできない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【九州・第11回】被告第6準備書面 令和4年11月30日 PDF (P7~8)
また、この「婚姻をするについての自由」は、「婚姻」という枠組みが存在することを前提とするものであり、これは「婚姻」という概念の意味を保つことのできる枠組みが存在している状態の中での「自由」について述べるものであることから、「婚姻」という枠組みが形成されている原因となっている上記の「生殖と子の養育」の趣旨を満たさない人的結合関係を「婚姻」という概念の中に含めることができるとする根拠として用いることができるものではない。
つまり、「婚姻」の枠組みは、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的との関係により、その間で自然生殖を想定することができ、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となる状態を推進し、血縁関係を明確にする機能によって立法目的の達成を目指すという仕組みに制度の根幹部分があることから、この枠組みを失わせた場合には、それは既に「婚姻」という概念で把握することができる対象が存在しない状態となり、「婚姻をするについての自由」という言葉の中の「婚姻」という枠組みが存在することを前提とする中での「自由」について述べているという前提さえも覆すものとなることから、この「婚姻をするについての自由」との文言を、「婚姻」が「男女二人一組」の枠組みで形成されていることそのものを自由に変更することができるする根拠とすることはできないということである。
そのため、この「婚姻をするについての自由」を持ち出したとしても、これは「婚姻」の中に「同性間の人的結合関係」を含めることができるとする根拠とはならないものである。
よって、この「婚姻をするについての自由」を持ち出したとしても、これはこの段落の第四文で「憲法24条1項は、……(略)……同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障していると考えることが相当である。」という結論を導き出す根拠となるものではなく、これを理由してその結論を正当化することができるということにはならない。
他にも、この「再婚禁止期間制度訴訟大法廷判決」の文面は、憲法上の条文が存在することを前提とし、その条文の意味を解釈したものとして導き出されたいわば下位法にあたるものとして示された説明である。
そのため、このような「憲法24条1項」が一夫一婦制(男女二人一組)を定めていることを前提として、その「憲法24条1項」を解釈した結果して導き出される説明を基にして、その説明の根拠となっている「憲法24条1項」の枠組みの方を変更することができるということにはならない。
つまり、この「再婚禁止期間制度訴訟大法廷判決」の「婚姻をするかどうか、いつ誰と婚姻をするかについては、当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたもの」や「婚姻をするについての自由」という説明を持ち出しても、それは「憲法24条1項」を解釈した結果として導き出されているいわば下位法にあたる説明であり、それはその上位法である「憲法24条1項」の「婚姻」が一夫一婦制(男女二人一組)の枠組みとなっていることそのものを変更することができるとする根拠にはならないものである。
よって、憲法24条の「婚姻」の中に「同性間の人的結合関係」を含めることができるかが問題となっているこの札幌高裁判決の中で、この「再婚禁止期間制度訴訟大法廷判決」の文面を持ち出して論じようとすることは誤りである。
さらに、一つ前の段落で「目的とするところを踏まえて解釈すること」や「立法の目的とするところに合わせ、改めて社会生活に適する解釈をすること」のように述べて、「目的」とするところから解釈するべきと述べて、ここで「再婚禁止期間制度訴訟大法廷判決」の文面を取り上げるものとなっている。
しかし、この「再婚禁止期間制度訴訟大法廷判決」の文面は憲法24条の条文が存在することを前提として、その条文に記された文言を読み解いた結果として導き出されているものであることから、憲法上の条文を上位法として捉え、いわば下位法として導き出されている説明である。
そのため、これは憲法24条が定めている「婚姻」という枠組みそのものが形成されていることの原因となっている「国の立法目的」について示したものではない。
つまり、この憲法24条1項の条文を解釈した結果として導かれている説明は、憲法24条の条文そのものが有している意味に優越するものとして位置付けられているものではなく、憲法24条の条文に記されている文言の意味を書き換えることが可能であると主張される場合に持ち出される憲法24条の条文よりも上位にある「国の立法目的」であるとはいえない。
そのため、この憲法24条1項の条文を解釈した場合に導かれているいわば下位法にあたる説明は、憲法よりも下位の法令である法律の内容がその説明を満たすか否かについて検討し、その説明を満たさない場合にはその法律の内容を是正することができるという場合の基準として用いることは可能であるとしても、この説明を用いて、憲法24条の条文に記された文言の意味を書き換えることができるとする根拠となるものではない。
そのため、この憲法24条1項の条文を解釈した結果として導かれている説明を持ち出したとしても、これは憲法24条の「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言に含まれていない「同性間の人的結合関係」をこの「婚姻」の中に含むとする結論を導き出すための根拠とはならないものである。
よって、この「再婚禁止期間制度訴訟大法廷判決」の文面を、この札幌高裁判決が法令を解釈する際の前提として示した「目的とするところを踏まえて解釈すること」や「立法の目的とするところに合わせ、改めて社会生活に適する解釈をすること」という場合における「目的」(条文よりも上位にある『国の立法目的』)にあたるものであるかのように位置付けて論じていることは誤りである。
「そして、憲法24条2項は、婚姻及び家族に関する事項についての立法に当たっては、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきと定めている。」との記載がある。
この文は、「憲法24条2項」の「婚姻及び家族」の枠組みの「要請」に従って立法された法律上の「婚姻及び家族」の制度について、「個人の尊厳」と「両性の本質的平等」を満たす必要があることを述べるものである。
24条2項の「婚姻及び家族」
↓ |
↓ 24条の「個人の尊厳」と「両性の本質的平等」の審査
↓ ↓
↓(要請) ↓
↓ ↓
法律上の「婚姻及び家族」の制度 ←←←←
そこで、この「個人の尊厳」と「両性の本質的平等」を適用する対象として示さている「婚姻及び家族」とはどのような枠組みを指しているのかが問題となる。
そのことから、下記で憲法24条2項の「婚姻及び家族」の枠組みについて詳しく検討する。
■ 「婚姻」と「家族」はそれ以外の概念ではないこと
「婚姻」や「家族」である以上は、「サークル」「部活」「組合」「雇用」「会社」「町内会」「宗教団体」「政党」など他の様々な人的結合関係とは異なる概念である。
当然、これは「意思表示」「代理」「物権」「即時取得」「売買」など、それとは別の概念を示すものでもない。
このように、「婚姻」や「家族」という概念が用いられている以上は、その概念そのものが有する意味を離れることはできないのであり、その概念が有する意味に拘束されることになる。
よって、「婚姻」や「家族」として扱うことができる範囲には、「婚姻」や「家族」という概念であることそのものによる内在的な限界が存在する。
言い換えれば、「婚姻」や「家族」という言葉それ自体を別の意味に変えてしまうことはできないのであり、これらの言葉に対して、その概念に含まれている内在的な限界を超える意味を与えることが解釈として可能となるわけではない。
もしその概念が有する内在的な限界(意味の範囲)を超える形で新たな枠組みを設けることを望む場合には、解釈によって導き出すことのできる範囲を超えることになるから、その規定を改正して文言を変更するか、その規定そのものを廃止することが必要となる。
■ 「婚姻」と「家族」は異なる概念であること
24条2項には「婚姻及び家族」と記載されている。
ここから分かることは、「婚姻」と「家族」はそれぞれ異なる概念であるということである。
このことから、下記の内容が導かれる。
〇 第一に、「婚姻」と「家族」を同一の概念として扱うことはできない。
〇 第二に、「婚姻」の概念を「家族」の概念に置き換えることや、「家族」の概念を「婚姻」の概念に置き換えることはできない。
〇 第三に、「婚姻」や「家族」という言葉の意味によって形成されている概念の境界線を取り払うことはできない。
〇 第四に、「婚姻」や「家族」という言葉の意味の範囲をどこまでも拡張することができるというものではない。
このように、「婚姻」と「家族」という文言が使われていることそのものによって、これを解釈する際に導き出すことのできる意味の範囲には内在的な限界がある。
それぞれの言葉には一定の意味があり、その意味そのものを同じものとして扱ったり、挿げ替えたり、混同したり、無制限に拡張したりすることはできないからである。
そのため、もし下記のような法律を立法した場合には、24条2項の「婚姻及び家族」の文言に抵触して違憲となる。
① 「婚姻」と「家族」の意味を同一の概念として扱うような法律を立法した場合
② 「婚姻」の意味と「家族」の意味を置き換えるような法律を立法した場合
③ 「婚姻」や「家族」の概念の境界線を取り払うような法律を立法した場合
④ 「婚姻」や「家族」という言葉の意味の範囲をどこまでも拡張することができることを前提とした法律を立法した場合
■ 「婚姻」と「家族」は整合的に理解する必要があること
24条2項の「家族」とは、法学的な意味の「家族」を指すものである。
そのため、社会学的な意味で使われる「家族」のように、どのような意味としてでも自由に用いることができるというわけではない。
24条2項には「婚姻及び家族」と記載されており、これら「婚姻」と「家族」の文言は、一つの条文の中に記されている。
24条2項では「A、B、C、D、E 並びに F」の形で順を追って説明するものとなっており、その中で「婚姻及び家族に関するその他の事項」が一つのまとまりとなっている。
この点で、「婚姻」と「家族」という二つの概念はまとめる形で定められている。
そして、「家族」の文言は、「婚姻及び家族」のように「婚姻」の文言のすぐ後に続く形で、「婚姻」と共に記されている。
そのことから、「家族」の概念は、「婚姻」の概念と結び付くものとして定められており、これらは切り離すことのできるものではない。
よって、「婚姻」と「家族」の意味を解釈する際には、それぞれの概念をまったく別個の目的を有した相互に関わり合いのない枠組みであるかのように考えることはできず、それらを整合的に読み解くことが求められる。
24条2項の「婚姻及び家族」の文言は、1項で「婚姻」について既に定められていることを前提として、それに続く形で「家族」についても触れるものとなっている。
そのため、「家族」の概念は「婚姻」を中心として定められる枠組みであることは明らかである。
これについて、国(行政府)は下記のように説明している。
◇ 「同項における立法上の要請及び指針は、形式的にも内容的にも、同条1項を前提とすることが明らかである。」
◇ 「このように、憲法24条2項が、同条1項の規定内容を踏まえ、これを前提として定められていることは、同条2項の内容面からしても明らかである。」
【東京一次・第1回】控訴答弁書 令和5年6月23日 PDF
国(行政府)は最高裁判決の記述も示している。
【東京二次・第9回】被告第7準備書面 令和5年9月28日 PDF (P14)
【九州・第1回】被控訴人(被告)答弁書 令和6年1月31日 (P15)
■ 「婚姻及び家族」の内在的な限界
「家族」の枠組みを検討するために、初めに、「婚姻」の目的と、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす枠組みから検討する。
▼ 「婚姻」の概念に含まれる内在的な限界
「婚姻」は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的とした形成された枠組みである。
これは、下記のような経緯によるものである。
その社会の中で何らの制度も設けられていない場合には、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合が発生する。
例えば、「父親不明」の子供が増える、父親を特定できない子供が増える、父親が蒸発して行方不明になった子供が増える、それらにより「子の福祉」が減少する、父親を特定できないことにより近親者の範囲を把握できずに「近親交配」に至り潜性遺伝子の発現した個体が高い確率で生じるようになる、一部の強者が多数人との生殖関係を独占することによって社会の中で「子を持ちたいと希望して相手を見つけようとする男女」の数の不均衡が生じて「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」が生まれる、低年齢での妊娠・出産により母体に危険が及ぶ、などの問題が生じることがある。
これらの不都合を解消するために、下記のような立法目的を有する枠組みを設けることが必要となる。
・「子の福祉」が実現される社会基盤を構築すること
・潜性遺伝子の発現した個体が高い確率で生じることを抑制すること
・「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」を減らすこと
・母体を保護すること
そして、これらの目的を達成するためには、下記の要素を満たす枠組みを設けることが必要となる。
・子の遺伝的な父親を特定できる組み合わせとすること
・特定された子の父親にも子に対する責任を担わせること
・特定された子の父親を基に遺伝的な近親者を把握すること
・未婚の男女の数の不均衡を防止できる組み合わせに限定すること
これらの要素を満たすものとして「一人の男性」と「一人の女性」が選び出され、その間に「貞操義務」を設け、その関係を法的に結び付ける形を「婚姻」と呼んでいる。
そして、この制度を利用した場合には一定の法的効果や優遇措置があるという差異を設けることによって、この制度を利用する者を増やし、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成することを目指すものとなっている。
このような「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解決しようとする目的を離れて「婚姻」を観念することはできない。
そのため、「婚姻」である以上は、これらの目的を達成することを阻害する組み合わせを「婚姻」とすることはできないという内在的な限界がある。
また、24条の「婚姻」は、「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めている。
これについても、上記の要素を満たす枠組みとして定められているものである。
よって、「婚姻」の中に含めることのできる人的結合関係の範囲は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成するための手段として整合的な上記の要素を満たす範囲に限られる。
▼ 「家族」の概念に含まれる内在的な限界
次に、「家族」の枠組みを検討する。
▽ 「婚姻」と「家族」の整合的な理解
上で述べたように、「家族」の枠組みは、「婚姻」という枠組みが存在することを前提としており、「婚姻」の枠組みから切り離して独立した形で存在することはできない。
そのため、もし「婚姻」の枠組みが有している目的の実現を「家族」の枠組みが阻害するものとなっている場合、「婚姻」と「家族」は同一の条文の中に記された文言であるにもかかわらず、その間に矛盾・抵触が生じていることとなり、その意味を整合的に読み解くことができていないことになるから、解釈の方法として妥当でない。
そのことから、「家族」の枠組みは、「婚姻」の枠組みが有している目的を達成することを阻害するような形で定めることはできず、「婚姻」の枠組みが有している目的との整合性を切り離して考えることはできない。
これにより、「婚姻」と「家族」は、同一の目的を共有し、その同一の目的に従って相互に矛盾することなく整合性を保った形で統一的に形成される枠組みということになる。
よって、「家族」の枠組みは、「婚姻」の立法政策に付随して同一の目的を共有し、「婚姻」の枠組みと結び付く形で位置付けられることになる。
▽ 「家族」の枠組み
「家族」の枠組みは、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として設けられた「婚姻」の枠組みと結び付いて定められている。
そのため、「家族」の枠組みは、「婚姻」の目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす枠組みが存在することを前提として、その「婚姻」と同一の目的を共有する形で、かつ、その「婚姻」の枠組みとの間で矛盾しない形で、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす形で定められることになる。
「婚姻」とするためには、下記の要素を満たすことが必要である。
・子の遺伝的な父親を特定できる組み合わせとすること
・特定された子の父親にも子に対する責任を担わせること
・特定された子の父親を基に遺伝的な近親者を把握すること
・未婚の男女の数の不均衡を防止できる組み合わせに限定すること
そして、「家族」の枠組みは、「婚姻」と同一の目的を共有し、この「婚姻」の枠組みと矛盾しない形で、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす形で定められることになる。
そのことから、「家族」とするためには、下記の要素を満たすことが必要である。
・「婚姻」と「家族」は異なる概念であること
・「婚姻」と同一の機能を「家族」の概念に担わせることはできないこと
・「生殖」を推進する関係は「婚姻」している夫婦の間に限られること
・「貞操義務」は夫婦の間に限られること
・夫婦以外の関係の間で「生殖」を推進する作用を生じさせないこと
・「生殖」によって子が生じるという生命活動の連鎖による血筋を明らかにすることが骨格となること
・「生殖」によって生じた子とその親による「親子」の関係を規律すること
・遺伝的な近親者とは「婚姻」することができないこと
これらの要素により、「家族」の中に含めることのできる人的結合関係と、含めることのできない人的結合関係が区別されることになる。
このように、「婚姻」が「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的としている以上は、その「婚姻」の目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす枠組みとの関係で、「家族」の枠組みも自ずと明らかとなる。
このことより、「家族」の中に含めることのできる人的結合関係の範囲は、「家族」という概念であることそれ自体による内在的な限界がある。
そのため、もし上記の要素を満たさない人的結合関係を「家族」の中に含めようとする法律を立法した場合には、24条2項の「家族」の文言に抵触して違憲となる。
∵ 「家族」の範囲
上記のように、「家族」は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として「婚姻」という枠組みが設けられていることを前提として、その立法政策に付随する形で同一の目的を共有し、その目的を達成するための手段として設けられる枠組みである。
そのため、「家族」の枠組みは、「生殖」によって「子」が生まれるという生物学的な因果関係を離れて観念することはできない。
よって、「家族」の中に含まれる人的結合関係の範囲は、下記の順に決まることになる。
① 婚姻している「男性」と「女性」の関係 (夫婦)
② 婚姻している「母親」から産まれた「子」とその「夫婦」との関係 (親子)
③ 婚姻していない「母親」から産まれた「子」とその「母親」との関係 (親子)
④ 婚姻している「母親」から産まれた「子」であるが、その「母親」の「夫」に嫡出否認された場合の「子」とその「母親」との関係 (親子)
⑤ 「子」の「父親」であると認知した者との関係〔あるいは『子』の親権を得た『父親』との関係〕 (親子)
このように、婚姻している「夫婦」と、自然生殖の過程を経て生まれてくる「子」とその「親」との関係を規律する「親子」による枠組みを骨格として範囲が決まることになる。
これは、「自然血族」である。
これらの関係が「家族」となるのは、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的によって「婚姻」という枠組みが設けられており、その「婚姻」と同一の目的を共有する形で、生物学上の血のつながりを持つ親子関係を明確にすることを意図した統一的な枠組みといえるからである。
⑥ 「自然血族」の「親子」の関係に擬制して位置付けられる「養子縁組」による「親子」の関係
自然生殖によって生じる「親子」の関係を規律する「自然血族」の枠組みを基本として、その骨格を維持したまま、その骨格に当てはめる形で法的に「親子」の関係として扱う制度が定められることがある。
これは、「法定血族」である。
∵ 結論
このように、24条2項の「家族」の中に含めることのできる人的結合関係の範囲は、「家族」の枠組みが「婚姻」と同一の目的を共有してその目的を達成するための手段として「婚姻」の枠組みとの間で整合性を保つ形で統一的に定められることによる内在的な限界がある。
そして、その限界は、「婚姻」している「夫婦」と、「生殖」によって子が生まれるという生物学的な因果関係を想定した「親子」の関係による「自然血族」と、その「自然血族」の枠組みを基本として、その骨格を維持したまま、その骨格に当てはめる形で位置付けられる「法定血族」までをいう。
まとめると、「家族」とは、「婚姻」している「夫婦」と、「親子」の関係によって結び付けられる「血縁関係者」のことを指す。
国(行政府)は下記のように述べている。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(イ)しかし、現行民法典には「家族」という言葉は存在せず、少なくとも民法の観点からは「家族」を厳密に定義することは困難であるが(大村敦志「家族法(第3版)」23ページ・乙第35号証)、一般的な用語としての「家族」は、「夫婦の配偶関係や親子・兄弟などの血縁関係によって結ばれた親族関係を基礎にして成立する小集団」を意味するものとされている(新村出編「広辞苑(第7版)」560ページ)。……(略)……
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【東京一次・第1回】控訴答弁書 令和5年6月23日 PDF
【参考】家族関係の基本知識 2022.12.19
【参考】血族について学ぼう!範囲や親族・姻族との違いを詳しく解説 2021.8.9
上記の通り、「憲法24条2項」の「婚姻及び家族」とは、「夫婦」と、「親子」による「血縁関係者」のことを指している。
そのため、「憲法24条2項」の「婚姻及び家族」の枠組みが法律上の制度として立法することを「要請」しているのは、この「夫婦」と「親子」による「血縁関係者」を対象とした制度である。
そのことから、ここでいう「憲法24条2項は、婚姻及び家族に関する事項についての立法に当たっては、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきと定めている。」という文の意味は、上記の意味の「婚姻及び家族」の枠組みの「要請」に従って定められた法律上の「婚姻及び家族」の制度が存在することを前提として、その「夫婦」と「親子」による「血縁関係者」の枠組みに付随する形で規定される細目的な内容について「個人の尊厳」と「両性の本質的平等」を満たすことが必要である旨を述べているものということになる。
しかし、問題はこの文そのものではなく、この文がこの札幌高裁判決の論旨の中でどのような文脈の中に位置付けられているかというところにある。
これについて、さらに検討する。
まず、一つ前の段落で「目的とするところを踏まえて解釈すること」や「立法の目的とするところに合わせ、改めて社会生活に適する解釈をすること」のように述べて、「目的」とするところから解釈するべきと述べている。
そして、ここで憲法24条2項の条文を取り上げるのであるが、この文は憲法24条2項の条文が下位の法令に対して指示している内容について説明したものに過ぎず、憲法24条の条文や、憲法24条が定めている「婚姻」という枠組みそのものが形成されていることの原因となっている「目的」(国の立法目的)について示したものではない。
そのため、特定の条文が下位の法令に対して指示している内容そのものが、その条文や、その条文の中に記されている言葉の概念の枠組みが形成されていることの原因となっている「目的」(国の立法目的)となることはないし、これによってその条文に記されている文言の意味を書き換えることができるとする理由になるものでもない。
そのため、これを基にして憲法24条の「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言に含まれない「同性間の人的結合関係」を「婚姻」の中に含めることができるとする結論を導き出すための根拠とすることはできない。
よって、先に「目的とするところを踏まえて解釈すること」や「立法の目的とするところに合わせ、改めて社会生活に適する解釈をすること」と述べ、その後、その「目的」や「立法の目的」にあたるものとしてこの憲法24条の条文が下位の法令に対して指示している内容についての説明を持ち出し、これを基にして憲法24条の「婚姻」の中に「同性間の人的結合関係」が含まれるとする結論を導き出そうとしていることは誤りである。
その他、「婚姻及び家族」の枠組みが対象としている人的結合関係の範囲を、ここで登場する「個人の尊厳」の文言を用いて変更することができるかのような理解の下にこの文を持ち出しているつもりの場合について検討する。
まず、憲法24条2項は、憲法24条2項の「婚姻及び家族」の枠組みの「要請」に従って立法される法律上の具体的な制度としての「婚姻及び家族」の制度について、「個人の尊厳」を満たすよう求めるものである。
そのため、憲法24条2項は「婚姻及び家族」の枠組みに当てはまる対象について「個人の尊厳」を満たすことを求めるものといえるが、そもそも「婚姻及び家族」の枠組みに当てはまらない場合については「個人の尊厳」を満たすことを求めるものではない。
まして、この憲法24条2項の「個人の尊厳」の文言を根拠として、その「個人の尊厳」の文言を適用する対象の範囲を定めている「婚姻及び家族」の枠組みそのものをも変更することまで可能となるということはない。
これは、憲法24条2項の条文は、憲法24条2項の示す「婚姻及び家族」の枠組みが存在することを前提として、その枠組みを対象として「個人の尊厳」が適用されることについて定めるものであって、「個人の尊厳」の文言が「婚姻及び家族」の枠組みそのものを形成するという関係にあるわけではないからである。
これについて、下記で詳しく述べる。
「婚姻及び家族」とは、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、血縁関係を明確にする機能によって立法目的の達成を目指す枠組みである。
これは、一定の枠を設けて他の様々な人的結合関係との間で区別することにより、その目的の達成を目指す仕組みとして設けられているものである。
そのため、当然、このような一定の枠が存在することを前提として「婚姻」や「家族」という概念が形成されていることを意味しており、この枠組みがその機能を果たすことが求められている。
そのことから、もしその枠組みを形成している境界線を取り払った場合には、そもそもその枠組みそのものが立法目的を達成するための手段として機能しないものに変わってしまうこととなり、その枠組みが有している立法目的を達成しようとする機能が損なわれ、その枠組みが制度として成り立たなくなる。
よって、このような枠組みそのものを失わせることはできない。
そのことから、この「婚姻及び家族」の枠組みの対象となる人的結合関係の範囲は、「婚姻及び家族」の枠組みが有している立法目的との関係で内在的な限界があり、その立法目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす場合に限られる。
そして、憲法24条では「婚姻及び家族」と定めて他の様々な人的結合関係やそれ以外の概念との間で区別する形でその枠を指定しており、その対象となる範囲を具体的に特定するものとなっている。
そのため、憲法24条2項の規定の内容も、「婚姻及び家族」と呼ぶことのできる一定の目的を達成するための手段となっている枠が存在することを前提としており、その枠が保たれた中で形成される、その枠に付随する形で定められる個別の効果を定めた細目的な内容の規定について、「個人の尊厳」を満たすように求めるものであるといえる。
このことから、「婚姻及び家族」と呼ぶことのできる枠組みが存在することを前提として、その枠組みに対して適用される「個人の尊厳」の文言を用いて、その「個人の尊厳」が適用される範囲を指定している「婚姻及び家族」の枠組みそのものを変更することができるということにはならない。
それは、法が一定の枠組みを定めて範囲を指定し、その中でのみ適用されることが予定されている事柄を用いて、それを適用する範囲そのものを変えることができることになれば、いわば下位の規範によって上位の規範の意味を書き換えて変更しようとする試み(下剋上解釈論)と同様に、条文に記された論理的な構造そのものを損なわせることになるからである。
そのため、憲法24条2項に記されている「個人の尊厳」の文言は、その「婚姻及び家族」という枠組み自体が有している目的とその目的を達成するための手段として整合的な要素によって形成される枠組みそのものを変えることまで趣旨として含むものではない。
このことから、憲法24条2項の「個人の尊厳」の文言を根拠として、憲法24条2項の「婚姻及び家族」の枠組みを、このような目的を達成するための手段として機能しないものに変えてしまうことができるということにはならない。
そのため、「婚姻及び家族」の枠組みが有している目的との整合性の観点から「婚姻及び家族」の中に含めることのできる人的結合関係の範囲は定まっているのであり、その「婚姻及び家族」を対象として適用される「個人の尊厳」の文言を持ち出して、それを遡って「婚姻及び家族」の中に含めることのできる人的結合関係の範囲を形成している境界線の方を取り払うことを主張することはできない。
よって、憲法24条2項の「個人の尊厳」の文言を根拠として「婚姻及び家族」の枠組みそのものを書き換えることができるとの主張は正当化することができず、この「個人の尊厳」の文言を理由として「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることができるかのように論じることは誤りである。
これについて、国(行政府)は下記のように述べている。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
また、前記2のとおり、憲法24条2項は、飽くまで婚姻が異性間の人的結合関係を対象とするものであることを前提として、これを具体化する制度の整備を立法府に要請するものであり、憲法解釈としては、同項の「個人の尊厳」をこのような規定の在り方と切り離して解釈することは相当でなく、本件諸規定は、このような同項の要請に従って制定されたものである。……(略)……
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【大阪・第12回】被告第6準備書面 令和4年2月21日 PDF (P14)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3)また、前記1(2)及び(3)のとおり、憲法24条2項は、飽くまで婚姻が異性間の人的結合関係を対象とするものであることを前提として、これを具体化する制度の整備を立法府に要請するものであり、同性間の人的結合関係をも対象として婚姻を認める立法措置を執ることを立法府に要請していると解することはできない。そして、被控訴人原審第5準備書面第3の1(3)(10ないし12ページ)において述べたとおり、憲法24条1項の定める婚姻が異性間の人的結合関係のみを対象とするものとして本件諸規定により制度化され、同性間の人的結合関係を対象とするものとして制度化されない事態(差異)が生じることは、憲法24条が婚姻について異性間の人的結合関係のみを対象とすることを明文で定め、婚姻に係る法制度の構築を法律に委ねていることの当然の帰結にすぎない。
そうすると、同性間では本件諸規定に基づき婚姻をすることができないことは、憲法自体が予定し、かつ許容するものであるのであるから、憲法24条2項の「個人の尊厳」をこのような規定の在り方と切り離して解釈することは相当でない(なお、前記1(3)ウのとおり、同項が、配偶者の選択ないし婚姻等に関する事項について「個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。」と規定している意味は、同条1項と同様、婚姻が、夫婦となろうとする両性当事者の自由な合意のみによって成立すべきことを意味するものとされているところである(乙第31号証)。)。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【名古屋・第1回】控訴答弁書 令和5年10月12日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
イ しかし、控訴答弁書第3の3(2)イ(22及び23ページ)で述べたとおり、法の解釈に際し、文言の日本語としての意味や文法が重視・尊重されなければならないのは当然のことであり、文言からかけ離れた解釈は許されない。そして、前記 (2)アで述べたとおり、「両性」とは、一般に、両方の性、男性と女性を意味する文言であり、「両性」が男性又は女性のいずれかを欠き当事者双方の性別が同一である場合を含む概念であると理解する余地はなく、憲法24条1項及び2項における「両性」の意味もこのように理解すべきことは、憲法24条の制定過程及び審議状況からも裏付けられている。
また、控訴答弁書第3の3(6)イ(29ないし31ページ)で述べたとおり、憲法24条1項の定める婚姻が異性間の人的結合関係のみを対象とするものとして本件諸規定により制度化され、同性間の人的結合関係を対象とするものとして制度化されない事態が生じることは、憲法自体が予定し、かつ許容するものであるから、憲法24条2項の「個人の尊厳」をこのような規定の在り方と切り離して解釈することは相当でない(なお、同項が、配偶者の選択ないし婚姻等に関する事項について「個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。」と規定している意味は、同条1項と同様、婚姻が、夫婦となろうとする両性当事者の自由な合意のみによって成立すべきことを意味するものとされている(乙第33号証)。)。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【東京一次・第3回】被控訴人第2準備書面 令和6年2月29日 PDF
「そうすると、性的指向及び同性間の婚姻の自由は、個人の尊重及びこれに係る重要な法的利益であるのだから、憲法24条1項は、人と人との間の自由な結びつきとしての婚姻をも定める趣旨を含み、両性つまり異性間の婚姻のみならず、同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障していると考えることが相当である。」との記載がある。
「性的指向及び同性間の婚姻の自由は、個人の尊重及びこれに係る重要な法的利益であるのだから、」との部分について検討する。
「性的指向」については、「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかに関するものであり、個人の内心における精神的なものであることから、憲法19条の「思想良心の自由」によって保障される。
そのため、ここで「個人の尊重」という文言を使い、この段落の第一文でも示されているように憲法13条で捉えられるものであるかのように述べていることは、権利の性質に関する分類を誤っており、適切ではない。
また、「これに係る重要な法的利益」との部分についても、「これに係る」のように憲法13条の「個人の尊重」と結び付けて考えていることは適切ではない。
「重要な法的利益」との部分について、国家から個人に対してその内心を侵害するような具体的な行為があった場合には、「国家からの自由」という「自由権」の性質として憲法19条の「思想良心の自由」を用いてその侵害を排除することが可能な場合があり、その意味で個人の内心における精神的なものは法的に保護されているということができる。
しかし、これは憲法19条の「思想良心の自由」によって保障されるものであるから、憲法13条の「個人の尊重」との部分に結び付けて考えることは適切ではない。
よって、「性的指向」と称するものについて、「個人の尊重及びこれに係る重要な法的利益」のように憲法13条と結び付けて説明していることは誤りである。
その他、「性的指向」と称する個人の内心における精神的なものが憲法19条の「思想良心の自由」によって保障されるとしても、これは「国家からの自由」という「自由権」の性質であることから、これによって特定の制度の創設を国家に対して求めることができるというものではない。
そのため、「性的指向」と称している個人の内心における精神的なものが憲法上の具体的な条文によって保障されるとしても、国家から個人に対しての侵害行為を排除する意味を超えて、具体的な制度を形成することを求めることができるとする理由にはならない。
「同性間の婚姻」の意味が「同性間の人的結合関係」を形成することを指すのであれば、それは憲法21条1項の「結社の自由」によって保障されるものである。
そのため、ここで「個人の尊重」という文言を使い、この段落の第一文でも示されているように憲法13条で捉えられるものであるかのように述べていることは、権利の性質に関する分類を誤っており、適切ではない。
よって、「同性間の人的結合関係」を形成することを指して「個人の尊重及びこれに係る重要な法的利益」と述べているとすれば誤りである。
また、憲法21条1項の「結社の自由」は、「国家からの自由」という「自由権」の性質のものであり、国家から個人に対する侵害があった場合にそれを排除することは可能であるが、その意味を超えて、特定の制度の創設を国家に対して求めることができるとする根拠とはならない。
もう一つ、憲法13条が包括的基本権として用いられる場合について述べようとしている可能性があるが、それは通常憲法13条後段の「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」の部分から導き出されるとするものである。
しかし、ここでは憲法13条前段の「すべて国民は、個人として尊重される。」の部分の「個人の尊重」を持ち出して説明していることは不自然である。
ただ、今回の事案は、やはり憲法21条1項の「結社の自由」により保障されることになることから、憲法13条後段の「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」によって捉えられるものでもない。
「同性間の婚姻」の意味が「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを指している場合であれば、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることができるかどうかから検討することが必要である。
「婚姻」とは、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた枠組みである。
具体的には、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」を目的として、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす「一人の男性」と「一人の女性」の組み合わせに対して「貞操義務」を設けるなど一定の形式で法的に結び付け、子供が産まれた場合にその子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によって立法目的の達成を目指すものとなっている。
「同性間の人的結合関係」については、その間で「生殖」を想定することができず、この「生殖と子の養育」の趣旨により導かれるものではないことから、「婚姻」の中に含めることはできない。
そのため、「同性間の婚姻」のように、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることができるかのように述べていることは誤りとなる。
「婚姻の自由」とあるが、これは「再婚禁止期間大法廷判決(平成27年12月16日)」が示した「婚姻をするについての自由」について述べようとしているものと考えられる。
ただ、「再婚禁止期間大法廷判決(平成27年12月16日)」の内容は、憲法24条1項が「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めていることを前提として、その憲法24条の「要請」に従って定められている法律上の婚姻制度を利用するか否かに関する自由をいうものである。
そのため、そこで述べられた「婚姻をするについての自由」についても、このような「男女二人一組」を対象としている婚姻制度を利用するか否かについての「自由」を指すものである。
そのことから、この「婚姻をするについての自由」の中には、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを求めることができるという意味は含まれていない。
よって、「同性間の婚姻の自由」のように、これを一続きに述べたとしても、「婚姻」そのものによって「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることができることにはならないし、ここでいう「自由」についても、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として定められている「婚姻」という枠組みを利用するか否かに関する「自由」をいうものであることから、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」の中に含めることを国家に対して求めることができるという意味を有するものではない。
また、その「婚姻をするについての自由」とは、「再婚禁止期間制度訴訟大法廷判決」で述べられているように、憲法24条1項を解釈することにより導かれているものである。
そのため、ここで「個人の尊重」という文言を使い、この段落の第一文でも示されているように憲法13条で捉えられるものであるかのように述べていることは誤りである。
「憲法24条1項は、人と人との間の自由な結びつきとしての婚姻をも定める趣旨を含み、両性つまり異性間の婚姻のみならず、同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障していると考えることが相当である。」との部分について検討する。
「憲法24条1項は、人と人との間の自由な結びつきとしての婚姻をも定める趣旨を含み、」とある。
まず、「婚姻」とは、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」を目的として、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす「一人の男性」と「一人の女性」の組み合わせに対して「貞操義務」を設けるなど一定の形式で法的に結び付け、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によってそれらの目的の達成を目指す枠組みである。
そのため、その「婚姻」という枠組みの条件となっている「男女二人一組」を満たす形で、「男性」と「女性」の間の合意によって「婚姻」が成立することを指して、「人と人との間の自由な結びつき」と表現しているのであれば、「憲法24条1項」では「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、」と書かれていることから、その「趣旨」を「定める」ものといえる。
ただ、この意味の場合、「憲法24条1項」には「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、」と記されているのであるから、「憲法24条1項」は「両性」という「男性」と「女性」を前提とした合意によるものとしての「人と人との間の自由な結びつきとしての婚姻を」「定める趣旨」の規定であるという部分が主要な内容である。
そのため、ここで「をも定める趣旨を含み、」のように、一見主要な内容として定めているようには見えないが、意味を検討すると別の意味「をも」「含」むものと読み取ることができるというような場合の表現を用いていることは不自然である。
そこで、別の読み方を検討する。
「人と人との間の自由な結びつき」の部分について、「人と人との間の」「結びつき」の意味を、法的な意味で法律関係について示したものと認識すると、「契約」のことを指しているものと考えることができる。
「契約」とは、相対する二人以上の当事者の意思表示の合致(合意すること)によって、権利義務の関係をつくり出す法律行為のことである。
そして、その「人と人との間の」「結びつき」が、「自由な」ものであるというのであるから、これは全体として「契約の自由」のことを指しているといえる。
契約の自由 Wikipedia
近代私法の三大原則 Wikipedia
契約自由の原則 2023.06.26
「契約の自由」の内容には、下記のような要素があるとされている。
・契約を締結するかしないかの自由
・契約相手を選択する自由
・契約の内容決定の自由
・契約の方式の自由
そのため、人は他者との間で「契約を締結するかしないかの自由」、「契約相手を選択する自由」、「契約の内容決定の自由」、「契約の方式の自由」を有しており、民法90条の「公序良俗」や他の法律の規定に違反しない場合には、自由な「契約」を行うことが可能である。
民法では下記のように規定されている。
民法
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(契約の締結及び内容の自由)
第五百二十一条 何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。
2 契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
このように、「人と人との間の自由な結びつき」の意味は、「契約の自由」のことを指しているということができる。
しかし、ここでは「人と人との間の自由な結びつきとしての婚姻」のように、その「契約の自由」のことを「婚姻」と表現しており、言葉の意味に反するものとなっているため誤りである。
また、ここでは「憲法24条1項」がこの「契約の自由」を「定める趣旨」の規定であるかのように述べていることになるが、「憲法24条1項」は「婚姻」について定めたものであり、「契約の自由」について定めたものではないことから、このように述べていることも誤りとなる。
その他、「人と人との間の自由な結びつき」との部分を「人的結合関係」を形成することを指しているとすれば、これは「国家からの自由」という「自由権」の性質として憲法21条1項の「結社の自由」によって保障されるものである。
国(行政府)の主張では、「憲法13条において尊重されるべきもの」と説明している。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(イ)しかしながら,およそ人同士がどうつながりを持って暮らし,生きていくかは,当人らが自由に決めて然るべぎ事柄であり,このような自由自体は異性間であっても同性間であっても,等しく憲法13条において尊重されるべきものと解されるが,前記3で述べたとおり,婚姻が一定の法制度を前提としている以上,「婚姻をするかどうか,いつ誰と婚姻をするか」を当事者間で自由に意思決定し,故なくこれを妨げられないという「婚姻をするについての自由」は,法制度を離れた生来的, 自然権的な自由権として憲法で保障されているものと解することはできない。前記2で述べたとおり,憲法24条1項は,婚姻について異性間の人的結合関係のみを対象とし,同性間の人的結合関係を対象とすることを想定しておらず,同条2項も,飽くまで婚姻が異性間の人的結合関係のみを対象とするものであることを前提としてこれを具体化する制度の整備を立法府に要請するものであり,これを受けて定められた本件規定も,婚姻が異性間の人的結合関係のみを対象とするものであることを前提に定められている。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【札幌・第1回】被控訴人答弁書 令和3年9月30日 PDF (P14~)
しかし、このような「人的結合関係」を形成することについては、そのような様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられている「婚姻」とは異なるものであることから、それは「婚姻」であるとはいえない。
この点について、国(行政府)は下記のように述べている。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
このように,婚姻は,必然的にー定の法制度の存在を前提としている以上,仮に婚姻に関する自己決定の側面を観念することができるとしても,その自己決定は,憲法の要請に従って構築された法制度の枠内で保障されるものにとどまると考えられる。すなわち,前記(2)で述べたとおり,憲法24条1項の「両性」が男女を指すことは明らかであるから,同項は婚姻について異性閲の人的結合関係のみを対象としており,また,同条2項は飽くまで婚姻が異性間の人的結合関係を対象とするものであるととを前提として,これを具体化する制度の整備を立法府に要請するものである。そうすると,原告らが「望む相手と意思の合致のみにより自律的に法律婚をなしうる自由」や「婚姻をするかどうか,いつ誰と婚姻をするか」の自由として主張するものの内実は,「両性」の本質的平等に立脚すべきことを規定する憲法24条2項の要請に従って創設された現行の法制度の枠を超えて,同性間の人的結合関係についても婚姻と同様の積極的な保護や法的な利益の供与を認める法制度の創設を国家に対して求めるものにほかならないのであって,このような内実をもつ「自由」が憲法24条1項の「婚姻の自由」を構成するものと解することはできない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【東京二次・第3回】被告第2準備書面 令和3年11月30日 PDF (P17~)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
しかしながら、被告第2準備書面第4の2(2)および(3)(14ないし16ページ)で述べたとおり、憲法24条1項は、婚姻について異性間の人的結合関係のみを対象とし、同性間の人的結合関係を対象とすることを想定しておらず、同条2項も、飽くまで婚姻が異性間の人的結合関係を対象とするものであることを前提として、これを具体化する制度の整備を立法府に要請しているのであり、本件規定は、かかる要請に基づき、婚姻について、異性間の人的結合関係のみを対象とするものとしてその具体的な内容を定めているということができる。また、被告第2準備書面第4の2(4)イ(ア)(16ないし18ページ)で述べたとおり、婚姻が一定の法制度を前提としている以上、「婚姻をするかどうか、いつ誰と婚姻をするか」を当事者間で自由に意思決定し、故なくこれを妨げられないという「婚姻をするについての自由」は、法制度を離れた生来的、自然権的な自由権として憲法で保障されているものと解することはできない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【東京二次・第5回】被告第3準備書面 令和4年6月20日 (P11)
そのため、ここで「人と人との間の自由な結びつきとしての婚姻」のように、「人と人との間の自由な結びつき」という「人的結合関係」を形成することについて、それを「婚姻」と表現している場合であっても、その意味は誤りである。
よって、「憲法24条1項は、人と人との間の自由な結びつきとしての婚姻をも定める趣旨を含み、」と述べている部分は、どのように読み解いても全体として意味が成立しておらず誤りである。
「両性つまり異性間の婚姻のみならず、同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障していると考えることが相当である。」との部分について検討する。
━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━
この文が読み取りづらい原因は、「保障している」ことと、その「程度」について一文の中で同時に述べるものとなっているからである。
また、その関係で「異性間」の文言が二回繰り返されており、文を区切ることのできるまとまりを捉えることができなくなっているからである。
◇ 「両性つまり異性間の婚姻のみならず、同性間の婚姻についても、」「保障していると考えることが相当である。」
◇ 「同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障していると考えることが相当である。」
この文は、これよりも前の部分との関係性から見ても、文を区切ることのできるまとまりが異なる。
◇ 「憲法24条1項は、人と人との間の自由な結びつきとしての婚姻をも定める趣旨を含み、両性つまり異性間の婚姻のみならず、同性間の婚姻についても、」「保障していると考えることが相当である。」
◇ 「憲法24条1項は、」「同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障していると考えることが相当である。」
このように、この文は、一つの文の中で複数の事柄を説明しようとするものとなっており、論理的な枠組みを正確に捉えることが困難となり、全体として意味を掴みづらいものとなっている。
━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━
「両性つまり異性間の婚姻のみならず、」とある。
この「両性つまり異性間の婚姻」の意味が、「異性間の人的結合関係」を形成することを指しているのであれば、それは「国家からの自由」という「自由権」として憲法21条1項の「結社の自由」によって保障されているものである。
そのため、「憲法24条1項」が、「国家からの自由」という「自由権」として「異性間の人的結合関係」を「保障している」との前提で論じていることは誤りである。
この「両性つまり異性間の婚姻」の意味が、「異性間の人的結合関係」による「婚姻」について述べているとすれば、「婚姻」という概念そのものが「男女」を前提とするものであることから、これに対して「両性つまり異性間」のように「男女」を指す言葉を加えて表現することは、文法上は同義反復となるため誤用である。
その他、「憲法24条1項」がそれを「保障している」ことを前提として表現している部分には問題がある。
まず、憲法は「個人の尊厳」の原理に基づいており、自然人は「個人主義」の下に各々「自律的な個人」として生存していくことを予定している。
そして、その個々の自然人が人的結合関係を形成、維持、解消することは自由である。
これは、憲法21条1項の「結社の自由」により「国家からの自由」という「自由権」の性質として保障される。
・憲法21条1項:「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」
憲法上では、他にも「保障する。」という文言が使われている条文がある。
・憲法20条1項前段:「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。」
・憲法23条:「学問の自由は、これを保障する。」
これらも「国家からの自由」という「自由権」の性質として「保障」しているといえる。
これに対し、憲法24条の条文の中に「保障する。」という文言は書かれていない。
そのため、「憲法24条1項」について「保障している」と表現される場合があるとしても、それは「憲法24条1項」の条文の文言をそのまま用いて説明しているものではなく、憲法24条の条文の趣旨を読み取った者の一人がそのような表現を用いて解説しているというだけのものである。
そのことから、憲法24条の条文そのものを読み解くことによって憲法24条の規範の意味を明らかにすることはできるが、憲法24条の条文の趣旨を読み取った者の中の一人が「保障している」と表現していることを根拠にして、そこから遡って憲法24条の条文の意味や性質を導き出そうとする試みは誤りである。
そして、憲法24条の定めている「婚姻」は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「生殖と子の養育」の観点から、他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた枠組みである。
また、憲法24条に定められた「婚姻」は、宗教的な意味として用いられる婚姻や、特定の地域の中でのみ通用していた婚姻を指すものではなく、それらとは区別する意味で国の法制度として設けられる「婚姻」を指すものである。
そのため、この憲法24条の「婚姻」の規定は、憲法21条1項の「結社の自由」が個々の自然人に対して「国家からの自由」という「自由権」を保障していることとは性質が異なっている。
・憲法21条1項の「結社の自由」 ⇒ 「国家からの自由」という「自由権」の性質
・憲法24条の「婚姻」 ⇒ 法制度
そのことから、「憲法24条1項」が「婚姻」を「保障している」と表現される場合があるとしても、その意味は、憲法21条の「結社の自由」のように個々の自然人に対して生来的・自然権的な権利としての「国家からの自由」という「自由権」を保障しているという意味を含むものではなく、憲法24条の「婚姻」の枠組みの「要請」に従って設けられる法律上の婚姻制度(男女二人一組)を利用することが可能となるという意味に留まるものである。
つまり、憲法24条の「婚姻」の枠組みが法律により婚姻制度(男女二人一組)を立法することを「要請」していることから、当然、その婚姻制度(男女二人一組)を利用することが可能となるという意味のものである。
しかし、この判決では、その憲法24条の条文の趣旨を読み取った者の一人が「憲法24条は、婚姻を保障している」のように説明している場合における「保障している」との表現を拾い上げ、「『保障している』のであれば、それは『国家からの自由』という『自由権』の性質なのだろう」という誤った推測を働かせ、憲法24条の「婚姻」の意味を憲法21条1項の「結社の自由」と同様の「国家からの自由」という「自由権」の性質として読み解こうとしているように見受けられる。
この傾向は、この札幌高裁判決が「(2)ウ」の第三段落の第四文で「憲法24条1項」について「人と人との間の自由な結びつき」と説明しているところからも感じ取ることができる。
そのため、ここで「憲法24条1項」について「保障している」と表現している部分についても、この判決が「憲法24条1項」について「人と人との間の自由な結びつき」のように「国家からの自由」という「自由権」の性質に裏付けられているかのように考えている部分と相まって、憲法24条の「婚姻」の枠組みの「要請」に従って立法された法律上の婚姻制度を利用することが可能となるという意味を離れて用いていると考えられる。
◇ この札幌高裁判決の理解
憲法24条の「婚姻」 ← (『国家からの自由』という『自由権』の性質と考える)
↓ (誰かの解説) ↑ (逆算)
「憲法24条は、婚姻を保障している。」
◇ 本来の意味
憲法24条の「婚姻」 ⇒ (法制度)
↓ (要請)
法律上の婚姻制度 ← (24条の『要請』で定められ、利用することが可能となる。)
よって、ここで「憲法24条1項」について「保障している」と表現している部分については、「憲法24条1項」は法制度としての「婚姻」について定めたものであり、「国家からの自由」という「自由権」を保障するものとは性質が異なることを理解していないことから生じた表現であるということができ、妥当なものではない。
「婚姻」が制度であることについて、国(行政府)は下記のように説明している。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
また,被告が,被告第3準備書面第1の2 (3,4ページ)において民法及び憲法の学説を引用した趣旨は,伝統的に,婚姻は,生殖や子の養育と結びついて理解されてきたところ,明治民法における婚姻が我が国の従来の慣習を制度化したものであり,男女間のものであることが前提とされていたという点を,当時の学説を引用するなどして明らかにした上で(被告第2準備書面第2の1〔3,4ページ〕),日本国憲法が制定され,その制定に伴って現行民法が制定された際にも,婚姻が男女問のものであるという上記の前提に変わりはなかったという点を,改正案の提案理由や改正時の国会審議の状況に加え,関連する学説を引用するなどして明らかにし(同第2の2〔4,5ページ〕),ひいては,現在においてもなお,婚姻の当事者が男女であるという理解が一般的なものであって,本件規定の合理性が失われているわけでもなければ,憲法に反するとの見解が支配的なわけでもない旨を明らかにする(被告第3準備書面第1の2〔3,4ページ〕参照)ことにある。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【東京・第6回】被告第4準備書面 令和3年2月24日 PDF (P10~11)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(イ)しかしながら、被告第5準備書面第3の4 (3)イ(32ないし35 ぺージ)で述べたとおり、明治民法制定当時、一部の学問分野において同性愛が精神疾患であるとする知見が存在していたとしても、それが明治民法制定時の立法事実として存在していたものではなく、むしろ、明治民法において同性婚が定められなかったのは、被告第4準備書面第3の2(3)ア(34及び35ページ)で述べたとおり、婚姻が生殖と子の養育を目的とする男女の結合であるとの我が国の伝統、慣習を制度化したものであり、男女間のものであることが前提とされていたからにすぎない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【九州・第11回】被告第6準備書面 令和4年11月30日 PDF (P20)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
また、本件規定は、異性間の婚姻を前提とする憲法24条の規定を受けて定められたものである上、本件規定の淵源は、被告第2準備書面第5の2(3)イ(ア)(42及び43ページ)で述べたとおり、我が国において、一人の男性と一人の女性の人的結合関係が、今後の社会を支える次世代の子を産み、育みつつ、我が国の社会を構成し、支える自然的かつ基礎的な集団単位である家族をその中心となって形成しているという実態があって、当該実態に対して歴史的に形成されてきた社会的承認が存在していることを背景に、男女間の結合としての婚姻の慣習が法制度化されたことにあるところ、そのような経緯で成立した本件規定の立法目的である「一人の男性と一人の女性が子を産み育てながら共同生活を送るという関係に対して特に法的保護を与えること」は、それ自体、性自認や性的指向に着目して法的な差別取扱いを生じさせることを趣旨として含むものではなく本件規定が性自認や性的指向について中立的なものであることは明らかである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【東京二次・第5回】被告第3準備書面 令和4年6月30日 PDF
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1 憲法及び民法は、婚姻が生殖と子の養育を目的とする男女の結合であるとの我が国の伝統、慣習が制度化されたものであること
(1) 控訴答弁書第4の2(3)(36ないし43ページ)で述べたとおり、伝統的に、婚姻は、生殖と密接に結び付いて理解されてきており、それが異性聞のものであることが前提とされ、現行民法における婚姻も、我が国の従来の慣習を制度化したものであって、男女間のものであることが前提とされていたのであり、本件規定の目的は、一人の男性と一人の女性が子を産み育てながち共同生活を送るという関係に対して特に法的保護を与えることにあると解される。
(略)
(2) しかしながら、被控訴人が本件規定の立法経緯を主張した趣旨は、異性問の人的結合関係が婚姻として法制度化される前から、伝統的に、婚姻は生殖と密接に結び付いて理解されてきており、それが異性聞のものであることが前提とされ、現行民法における婚姻も、我が国のこのような慣習を制度化したものであることを示すとともに、このような法制度化された背景に、一人の男性と一人の女性という具性聞の人的結合関係が、今後の社会を支える次世代の子を産み、育みつつ、我が園の社会を構成して支える自然的かつ基礎的な集団単位である家族をその中心となって形成しているという社会的な実態及び慣習があることを示したものであって、控訴人らがいうように「従来の慣習の制度化それ自体が婚姻立法の目的と説いたもの」ではない。控訴人らの前記(1)の主張は、このような被控訴人の主張を正解しないものであり、失当である。
そして、控訴人らの主張を前提としても、異性聞の人的結合関係が婚姻として法制度化される前から、婚姻は男女聞のものであるとする慣習が存在していたことは明らかであり、控訴人らの挙げる文献によっても、婚姻が同性聞の人的結合関係をも含むものであるとの慣習が我が国に存在した事実や、立法過程において同性聞の人的結合関係を婚姻に含めることが議論された形跡もうかがわれない。
また、伝統的に、婚姻は、生殖と密接に結び付いて理解されてきたことは、「男と女との性的結合は、人類の永続の基礎である。いかなる社会でも、当該社会における典型的な結合関係を法規範によって肯認し、その維持につとめた。(中略)近代文明諸国の法は、ほとんど例外なしに、この結合を一人の男と一人の女との平等な立場における結合とする。そして、その聞の未成熟の子を含む夫婦・親子の団体をもって、社会構成の基礎とする。わが新法の態度もそうである。」(我妻栄「親族法」9ページ・乙第21号証)と説明されたり、「婚姻とは、男と女との共同生活関係であって、社會的制裁(sanction)によって保障されているところの社會的制度たる意味をもつもの、である。婚姻は、子の出生の社會制度的基礎でもあり、したがって、婚姻は、家族的生活の構成部分、しかも重要な構成部分である。」(中川善之助「註注釈親族法(上)」90ページ・乙第24号証)と説明されたりしていることからも裏付けられている。
したがって、このような本件規定の立法経緯及び後記2の本件規定の内容に照らせば、本件規定の目的が一人の男性と一人の女性が子を産み育てながら共同生活を送るという関係に対して特に法的保護を与えることにあると解するのが相当である。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【札幌・第2回】被控訴人第1準備書面 令和4年3月4日 PDF
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
この点,後記のとおり,婚姻は,憲法を含めた我が国の法制上,異性間の一定の人的結合関係について特に法的保護を与える法制度という性質を有するもので,それ自体が憲法に根拠を持つ立法政策のーつとして位置づけられるものであり,その余の人的結合関係において,法律上の根拠もなく当然に同じ特別の保護が与えられるはずであるという関係には立たないこと,本件諸規定の改正という方法も,同性間の人的結合関係に対し,婚姻に認められている法的効果の全部又は一部を付与するという立法政策を執ることとした場合に,当該立法政策を実現するための方法のーつと位置づけられることからすると,本件事案の本質は,同性婚の制度を創設していないことを憲法との関係でどのように解すべきであるかということにあると解される。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【大阪・第9回】被告第5準備書面 令和3年9月24日 PDF
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
そして,婚姻の自由が憲法13条によって保障されるとの見解についてみれば,被告第3準備書面第2の2 (2)イ(ア)(7,8ページ)で述べたとおり,婚姻は,必然的に一定の法制度の存在を前提としている以上,仮に婚姻に関する自己決定権を観念できるとしても,その自己決定権は憲法の要請に従って構築された法制度の枠内で保障されるものにとどまると考えられる。……(略)……
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【東京・第6回】被告第4準備書面 令和3年2月24日 PDF (P12)
憲法24条1項が「国家からの自由」という「自由権」ではないことについて、国は下記のように説明している。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ア(ア)しかしながら、被告第4準備書面第2の2(8及び9ページ)及び同3(2) (13ないし16ページ)で述ぺたとおり、婚姻及び家族に関する事項については、憲法24条2項に基づき、法律によって具体的な内容を規律するものとされているから、婚姻及び家族に関する権利利益等の内容は、憲法の趣旨を踏まえつつ、法律によって定められる制度に基づき初めて具体的に捉えられるものである。そうすると、婚姻の法的効果を享受する利益や、「婚姻をするかどうか、いつ誰と婚姻をするか」を当事者間で自由に意思決定し、故なくこれを妨げられないという婚姻をするについての自由は、憲法の定める婚姻を具体化する法律(本件規定)に基づく制度によって初めて個人に与えられる、あるいはそれを前提とした自由であり、法制度を離れた生来的、自然権的な自由権として憲法上保障されていると解することはできない。
そうすると、原告らの「婚姻の自由」に関する主張について、自由権の侵害を問題とするものとしては前提を欠いているというぺきである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【九州・第11回】被告第6準備書面 令和4年11月30日 PDF (P7~8)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
前記2で述べたとおり,婚姻が一定の法制度を前提としている以上,「婚姻をするかどうか,いつ誰と婚姻をするか」を当事者間で自由に意思決定し,故なくこれを妨げられないという「婚姻をするについての自由」は,法制度を離れた生来的,自然権的な自由権として憲法で保障されているものと解することはできない。前記1で述べたとおり,憲法24条1項は,婚姻について異性間の人的結合関係のみを対象とし,同性間の人的結合関係を対象とすることを想定しておらず,同条2項も,飽くまで婚姻が異性間の人的結合関係のみを対象とするものであることを前提としてこれを具体化する制度の整備を立法府に要請するものであり,これを受けて定められた本件規定も,婚姻が異性間の人的結合関係のみを対象とするものであることを前提に定められている。
そうすると,原告らが「婚姻の自由」として主張するものの内実は,「両性」の本質的平等に立脚すべきことを規定する憲法24条2項の要請に従って創設された現行の婚姻制度の枠を超えて,同性間の人的結合関係についても婚姻と同様の積極的な保護や法的な利益の供与を認める法制度の創設を国家に対して求めるものにほかならないのであって,国家からの自由を本質とするものではないから,このような自由が憲法13条の幸福追求権の一内容を構成するものと解することはできない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【九州・第6回】被告第4準備書面 令和3年l0月29日 PDF
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
しかしながら、被告第2準備書面第4の2(2)及び(3)(14ないし16ページ)で述べたとおり、憲法24条1項は、婚姻について異性間の人的結合関係のみを対象とし、同性間の人的結合関係を対象とすることを想定しておらず、同条2項も、飽くまで婚姻が異性間の人的結合関係を対象とするものであることを前提として、これを具体化する制度の整備を立法府に要請しているのであり、本件規定は、かかる要請に基づき、婚姻について、異性間の人的結合関係のみを対象とするものとしてその具体的な内容を定めているということができる。また、被告第2準備書面第4の2(4)イ(ア)(16ないし18ページ)で述べたとおり、婚姻が一定の法制度を前提としている以上、「婚姻するかどうか、いつ誰と婚姻をするか」を当事者間で自由に意思決定し、故なくこれを妨げられないという「婚姻をするについての自由」は、法制度を離れた生来的、自然権的な自由権として憲法で保障されているものと解することはできない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【東京二次・第5回】被告第3準備書面 令和4年6月30日 PDF
「同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障していると考えることが相当である。」について検討する。
この「同性間の婚姻」の意味が「同性間の人的結合関係」を形成することを指しているのであれば、それは「国家からの自由」という「自由権」として憲法21条1項の「結社の自由」によって保障されているものである。
これについては、憲法21項1項がここでいう「異性間の場合と同じ程度に保障していると考えることが相当である。」といえるものである。
しかし、これを憲法21項1項ではなく「憲法24条1項」が「国家からの自由」という「自由権」として「同性間の人的結合関係」を形成することを「保障している」かのような前提で論じていることについては誤りである。
この「同性間の婚姻」の意味が「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを指しているのであれば、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることができるかという部分から検討する必要がある。
これについて、下記で詳しく検討する。
■ 「婚姻」の中に含めることができるもの
この札幌高裁判決は、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることが可能であるかのように理解しているようである。
しかし、そもそも「婚姻」という概念の中に「同性間の人的結合関係」を含めることができるのかどうかという部分から検討することが必要である。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
これらの学説を参照すると、憲法24条のいう「婚姻」の内実として同性カップルの「婚姻」というものが観念しうるのか、憲法上の「婚姻」とはそもそも男女が取り結ぶ一定の関係なのではないか、そして「同性」と「婚姻」を結びつけることが法的に可能なのかという問いが浮かぶ。
憲法24条が同性婚を想定していないのは確かだとして、憲法学説も民法学説も、従来、憲法24条の「婚姻」としては男女のカップルのそれを暗黙のうちに想定してきたと言える。「同性」という言葉と「婚姻」という言葉がそこでは結びついておらず、したがって「同性婚の自由」なるものが憲法上存在するかも定かではないのだ。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
生殖可能性のない同性婚を法律で認める理由はない…憲法学の専門家が「同性婚の法制化」にクギを刺す理由 2023/02/18
そこで、「婚姻」という概念が形成されている由来や、「婚姻」が有している目的とその目的を達成するための手段となる枠組みについて検討する。
■ 「婚姻」の概念による制約
▼ 「婚姻」の概念に含まれる内在的な限界
「婚姻」は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために設けられた枠組みである。
これは、下記のような経緯によるものである。
その国の中で「生殖と子の養育」に関する事柄について何らの制度も存在しない場合には、社会的な不都合が発生することがある。
例えば、「父親不明」の子供が増える、父親を特定できない子供が増える、父親が蒸発して行方不明になった子供が増える、それらにより「子の福祉」が減少する、父親を特定できないことにより近親者の範囲を把握できずに「近親交配」に至り潜性遺伝子の発現した個体が高い確率で生じるようになる、一部の強者が多数人との生殖関係を独占することによって社会の中で「子を持ちたいと希望して相手を見つけようとする男女」の数の不均衡が生じて「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」が生まれる、低年齢での妊娠・出産により母体に危険が及ぶ、などの問題が生じることがある。
これらの不都合を解消するために、下記のような立法目的を有する枠組みを設けることが必要となる。
・「子の福祉」が実現される社会基盤を構築すること
・潜性遺伝子の発現した個体が高い確率で生じることを抑制すること
・「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」を減らすこと
・母体を保護すること
そして、これらの目的を達成するためには、目的との関係で整合的な下記の要素を満たす枠組みを設けることが必要となる。
・子の遺伝的な父親を特定できる組み合わせとすること
・特定された子の父親にも子に対する責任を担わせること
・特定された子の父親を基に遺伝的な近親者を把握すること
・未婚の男女の数の不均衡を防止できる組み合わせに限定すること
これらの要素を満たすものとして「一人の男性」と「一人の女性」が選び出され、その間に「貞操義務」を設け、その関係を法的に結び付ける形を「婚姻」と呼んでいる。
そして、この「婚姻」に対して法的効果や一定の優遇措置を設けることによって、制度を利用する者を増やし、これらの立法目的の実現を目指す仕組みとなっている。
これが、「婚姻」という概念が生じる経緯である。
このように「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという「目的」に従って、「その目的を達成するための手段」となる枠組みを定めるところに「婚姻」という概念が生じているのである。
これは、これらの目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす人的結合関係を、他の様々な人的結合関係との間で区別する形で枠づけることの必要性に基づいて形成されている。
そのため、このような国民が「生殖」によって子供を産むことに関係して起き得る問題を解決しようとする目的を離れて「婚姻」を観念することはできない。
つまり、 このような「目的」と、「その目的を達成するための手段」として整合的な要素を満たす枠組みとの関係を切り離して「婚姻」を観念することはできない。
そのことから、「婚姻」という概念である以上は、国民が「生殖」によって子を産むことに関わる制度であることを前提としている。
これにより、「婚姻」は、上記の要素と対応する形で「生殖と子の養育」の趣旨により統一的な理念に従って定められ、他の様々な人的結合関係との間で区別する意味で設けられている枠組みであるといえる。
また、その社会の中で「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することが求められ、その目的を達成するための手段となる枠組みを「婚姻」という概念が担っている以上は、「婚姻」はそれを解消するものとして機能することが求められている。
そのため、「婚姻」の文言の中には、これらの目的を達成することを阻害する組み合わせを「婚姻」とすることはできないという内在的な限界が含まれている。
よって、「婚姻」という概念の中に含めることができる人的結合関係は、これらの目的を達成するための手段として整合的な上記の要素を満たす範囲に限られる。
もし「婚姻」の中にこれらの要素を満たさない人的結合関係を含めようとした場合には、その時点で、これらの要素を満たさないことが理由となって 「婚姻」の立法目的を達成することができなくなる。
そのことから、これらの要素は、「婚姻」という枠組みが機能するために最低限必要となるものであり、「婚姻」という概念そのものが他の様々な人的結合関係とは区別して成り立つための境界線となるものである。
よって、これらの要素を満たさないものについては、「婚姻」という枠組みそのものを他の様々な人的結合関係との間で区別するための境界線となっている一線を損なうこととなり、「婚姻」という枠組みそのものを他の様々な人的結合関係との間で区別することができなくなり、「婚姻」という概念自体が成り立たなくなり、「婚姻」という概念そのものを雲散霧消させてしまうことになることから、「婚姻」とすることはできない。
このため、「婚姻」が「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために設けられた枠組みである以上、その目的との関係により、「婚姻」の中に含めることができる人的結合関係の範囲は自ずと画されることになる。
そのことから、どのような人的結合関係でも「婚姻」の中に含めることができるというわけではない。
そして、このような差異が生じることは、「婚姻」という概念そのものが目的を達成するための手段として形成されている枠組みである以上は、もともと予定されていることである。
▼ 憲法24条の「婚姻」による限界
憲法24条の「婚姻」は、この意味の「婚姻」を引き継ぐ形で定められている。
そのため、憲法24条の「婚姻」の文言の中には「生殖と子の養育」の趣旨が含まれている。
また、憲法24条が定めているものが「婚姻」である以上は、そこにはこれらの目的を達成することを阻害する組み合わせを「婚姻」とすることはできないという内在的な限界が含まれている。
よって、憲法24条の下では、先ほど挙げた下記の要素を満たさない人的結合関係を「婚姻」とすることはできない。
・子の遺伝的な父親を特定できる組み合わせとすること
・特定された子の父親にも子に対する責任を担わせること
・特定された子の父親を基に遺伝的な近親者を把握すること
・未婚の男女の数の不均衡を防止できる組み合わせに限定すること
また、憲法24条は「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて、一夫一婦制(男女二人一組)を定めている。
その理由は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成するための手段として整合的な上記の要素を満たすからである。
そのため、これらの要素を満たさない人的結合関係については、憲法24条の「婚姻」の文言そのものや、「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言の趣旨に当てはまらず、「婚姻」とすることはできない。
もし、これらの要素を満たさない人的結合関係を「婚姻」として扱う法律を立法しようとした場合には、憲法24条の「婚姻」の文言そのものや「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言に抵触して違憲となる。
よって、憲法24条「婚姻」は、上記の要素と対応する形で「生殖と子の養育」の趣旨により統一的な理念に従って定められる枠組みであり、この憲法24条の下でこの趣旨を満たさない人的結合関係を「婚姻」とすることはできない。
▽ 憲法24条の「婚姻」が「生殖と子の養育」に関わる制度を一元的に集約していること
「婚姻」は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「生殖と子の養育」の観点から他の人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度である。
そして、24条は「婚姻」の内容について、「両性の合意のみ」や「個人の尊厳」「両性の本質的平等」を満たすように求めている。
これは、「婚姻」という制度については特に注意を払い、24条の統制に服させ、その内容に対して立法裁量の限界を画することが目的である。
この24条の規定が有する意図を実現するためには、「生殖と子の養育」に関わる制度を24条の「婚姻」の文言の中に一元的に集約する形で解釈することが必要であり、「生殖と子の養育」に関わる制度を24条の「婚姻」を離れて立法することはできない。
これは、下記が理由である。
仮に「生殖と子の養育」に関わる制度を、24条の「婚姻」から離れて別の制度として立法することができるとする場合を考えてみる。
すると、「生殖と子の養育」に関わる制度でありながら、24条によって統制(管理)することができない状態を許すことになる。
例えば、24条のいう「婚姻」とは別に「生殖関連制度」や「三人以上の生殖結社制度」などが立法されることが考えられる。
そうなると、24条は「婚姻」に対しては「両性の合意のみ」や「個人の尊厳」「両性の本質的平等」を満たすように求めて立法裁量の限界を画しているが、その「生殖と子の養育」に関わる制度は「婚姻」とは別の制度であることから、24条の統制が及ばないことになる。
すると、その「生殖と子の養育」に関わる制度は「婚姻」ではないため、「両性の合意」以外の条件を設けるものでも、「個人の尊厳」や「両性の本質的平等」に立脚しないものでも構わないことになる。
例えば、戦前の明治民法のような「戸主」の同意を必要とする「戸主付き生殖関連制度」や「家制度的生殖関連制度」を立法することも可能となる。
また、その「婚姻」とは異なる「生殖と子の養育」に関わる制度に対して「婚姻」よりも充実した優遇措置を整備した場合には、人々の大半はその制度を利用することを選択し、次第に「婚姻」を利用しなくなっていくことが考えられる。
すると、「婚姻」という制度が衰退していき、「婚姻」が「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するための制度として機能しなくなることが考えられる。
これでは、24条が「婚姻」に対して立法裁量の限界を画することによって、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために設けられた制度の内容が「両性の合意のみ」や「個人の尊厳」「両性の本質的平等」を満たすものとなるよう求める憲法上の立法政策としての目的を達成できない事態に陥る。
これでは、24条の趣旨が損なわれ、何のために24条が設けられているのか分からなくなる。
そのため、24条の規定の効果が保たれるためには、「生殖と子の養育」に関わる制度は24条の「婚姻」の文言が一元的に集約するものとして解釈することが必要となる。
このことから、「生殖と子の養育」に関わる制度を、24条の「婚姻」を離れて別の制度として立法することはできない。
もし「生殖と子の養育」に関わる制度を、24条の「婚姻」から離れて別の制度として立法しようとした場合には、24条の「婚姻」に抵触して違憲となる。
この前提がある以上は、24条の「婚姻」という文言の中には「生殖と子の養育」の趣旨が含まれており、この24条の「婚姻」の文言から「生殖と子の養育」の趣旨を切り離して考えることはできない。
これにより、「生殖と子の養育」の趣旨を満たさない人的結合関係を24条の「婚姻」として扱うことはできない。
▽ 憲法24条の「婚姻」から「生殖と子の養育」の趣旨が失われると24条の規定が有している目的を達成できないこと
仮に24条の「婚姻」という概念から「生殖と子の養育」の趣旨を切り離して考えることができるとする前提に立つとする。
すると、24条の「婚姻」の文言には「生殖と子の養育」の趣旨が含まれていないことになるから、24条の「婚姻」の文言には「生殖と子の養育」に関わる制度を一元的に集約しようとする趣旨も含まれていないことになる。
そうなると、「生殖と子の養育」に関わる制度について、24条の「婚姻」を離れて別の制度として立法することが可能となる。
「生殖と子の養育」に関わる制度が「婚姻」とは別の形で存在することを許すことになるから、「婚姻」が「生殖と子の養育」に関する様々な問題の発生を抑制しようとする機能を果たさなくなり、「婚姻」の政策効果が損なわれることになる。
また、その「生殖と子の養育」に関わる制度は、24条の「婚姻」とは別の制度であることから、24条の「両性の合意のみ」や「個人の尊厳」「両性の本質的平等」による統制が及ばないことになる。
つまり、その「生殖と子の養育」に関わる制度が、24条の「両性の合意のみ」や「個人の尊厳」「両性の本質的平等」を満たさないものとなっていても、それがもともと24条の「婚姻」ではないことを理由に、その制度の内容を是正することができなくなる。
これでは、本来「婚姻」を24条の統制の下に置くことによって、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するための制度の内容に対して「両性の合意のみ」や「個人の尊厳」「両性の本質的平等」を満たすように求めるという憲法上の立法政策を実現することができない事態に陥る。
これでは、24条の規定そのものが有する意図・目的を達成することができず、24条の規定が骨抜きとなる。
このような考えは解釈として妥当でない。
そのことから、「生殖と子の養育」に関わる制度については、24条の「婚姻」に結び付けて考える必要があり、24条の「婚姻」は「生殖と子の養育」に関わる制度を一元的に集約する趣旨を有している。
そのため、24条の「婚姻」を「生殖と子の養育」の趣旨と切り離して考えることはできない。
よって、「生殖と子の養育」の趣旨を満たさない人的結合関係を、24条の示している「婚姻」として扱うことはできない。
▼ 言葉の置き換えを繰り返すことはできないこと
上記のように、「婚姻」という枠組みが形成されている立法目的がある以上は、その「婚姻」という概念の中には、他の様々な人的結合関係との間で区別するための要素が存在する。
それは、「婚姻」の立法目的を達成するための手段として整合的な要素であり、下記が不可欠である。
・子の遺伝的な父親を特定できる組み合わせとすること
・特定された子の父親にも子に対する責任を担わせること
・特定された子の父親を基に遺伝的な近親者を把握すること
・未婚の男女の数の不均衡を防止できる組み合わせに限定すること
もしこれらの要素を満たさない人的結合関係を「婚姻」の中に含めようとした場合には、その時点で、これらの要素を満たさないことから、「婚姻」の立法目的を達成することができなくなることを意味する。
すると、そもそもそのような制度に対して法的効果や優遇措置を行う意味も失われ、制度を継続する必要性がなくなるし、制度を利用していない者との間でも不平等を生じさせるものとなることから、その「婚姻」と呼んでいる制度を廃止することに行き着く。
また、その「婚姻」と呼んでいる枠組みによっては、既に立法目的を達成することができなくなっていることから、その目的を達成するために「婚姻」以外の新たな制度を立法することが求められることになる。
しかし、それは結局、それまで機能していた本来の「婚姻」とまったく同様の目的を達成することを意図して立法されることになるから、上記の要素を満たす人的結合関係を新たな枠組みとして他の様々な人的結合関係とは区別する形で設けることになるものである。
こうなると、それはもともと「婚姻」が有していた機能を、新たな枠組みの制度が担おうとするものとなることから、そもそも「婚姻」から新たな枠組みの制度へと言葉の入れ替えを行っているだけの状態となるのである。
このような言葉の置き換えという無意味なループを繰り返すことを防ぐためには、「婚姻」という枠組みが存在する時点で、そこには「婚姻」という枠組みを形成している立法目的が存在しており、その「婚姻」という枠組みそのものにその立法目的との間で整合性を保つことができる内在的な限界が含まれていることを捉える必要がある。
そして、その内在的な限界となる要素を満たさない人的結合関係を「婚姻」の中に含めようとする試みは、「婚姻」という概念そのものが有している本来の意味、内在的な機能を改変し、消失させようとするものとして排斥することが必要となる。
これによって、「婚姻」という概念そのものの枠組みを維持し、「婚姻」という概念そのものが消失することを防ぎ、「婚姻」という言葉の意味が成立する状態を保つことができるからである。
そのことから、「婚姻」という枠組みが形成されている背景にある立法目的が正当である以上は、その立法目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす人的結合関係については「婚姻」として扱うことができ、それを満たさない人的結合関係については「婚姻」として扱うことはできない。
このような差異が生じることは「婚姻」という枠組みが形成されている時点でもともと予定されていることである。
この差異を否定するのであれば、それはそもそも「婚姻」の立法目的を否定することになることを意味する。
「婚姻」の立法目的が正当と認められる以上は、その立法目的を達成するための手段として設けられている枠組みによって生じる差異は、法制度が政策的なものであることからくる誰もが甘受しなければならないものである。
▼ 主張の基盤を失わせる主張であること
24条が定めている「両性の合意のみ」や「個人の尊厳」の文言を根拠として、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」の中に含めることができるはずであるとの主張がある。
しかし、この主張に従って「同性間の人的結合関係」を「婚姻」の中に含めた場合には、24条の「婚姻」から「生殖と子の養育」の趣旨が失われることになる。
こうなると、24条の「婚姻」の文言は「生殖と子の養育」に関わる制度を一元的に集約する趣旨を有していないことになる。
すると、「生殖と子の養育」に関わる制度を、24条の「婚姻」を離れて別の制度として立法することが可能となる。
その「生殖と子の養育」に関わる制度は、「婚姻」ではないことから、24条の「両性の合意のみ」や「個人の尊厳」「両性の本質的平等」を満たさなくとも構わないことになる。
例えば、戦前の明治民法のような「戸主」の同意を必要とする「戸主付き生殖関連制度」や「家制度的生殖関連制度」を立法することも可能となる。
そして、その「婚姻」とは異なる「生殖と子の養育」に関わる制度に対して「婚姻」よりも充実した優遇措置を整備するようになった場合には、人々の大半はその制度を利用することを選択し、次第に「婚姻」を利用しなくなっていくことが考えられる。
この影響で、「婚姻」という制度が衰退していき、「婚姻」が「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するための制度として機能しなくなることが考えられる。
すると、実質的に24条の規定が無意味なものとなり、24条が「婚姻」に対して「両性の合意のみ」や「個人の尊厳」「両性の本質的平等」を満たすものとなるように立法裁量の限界を画している意味が希薄化してしまう。
そうなると、もともと24条の「両性の合意のみ」や「個人の尊厳」を根拠として、「同性間の人的結合関係」を24条の「婚姻」の中に含めることができると主張し、それによって「同性間の人的結合関係」についても優遇措置を得られると期待していたにもかかわらず、それをした場合には、そもそも「婚姻」から「生殖と子の養育」の趣旨が失われることから、結果として「生殖と子の養育」に関わる制度を「婚姻」とは別の制度として立法することを許すことに繋がり、その別の制度の優遇措置が増えるなどしてその制度が主流化し、もともと「婚姻」の中に「同性間の人的結合関係」を含めることによって得られると期待していただけの優遇措置を「婚姻」という制度からは得られない状態に陥ることになるのである。
そのため、24条が定めている「両性の合意のみ」や「個人の尊厳」の文言を根拠として、「生殖と子の養育」の趣旨を満たさない人的結合関係についても「婚姻」の中に含めるべきであるとの主張は、結果として、自己の主張の基盤さえも失わせる主張となっているということができる。
よって、24条の定める「両性の合意のみ」や「個人の尊厳」の文言を根拠として、24条の「婚姻」の中に「生殖と子の養育」の趣旨を満たさない人的結合関係を含めることができるとの主張は成り立たない。
もし「生殖と子の養育」の趣旨を満たさない人的結合関係を「婚姻」とする法律を立法しようとした場合には、24条の「婚姻」に抵触して違憲となる。
■ 整合的な理解
これらを前提として、改めて検討する。
「婚姻」という概念は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために設けられた枠組みである。
そのため、「婚姻」という概念に含めることができる人的結合関係には、その概念が形成されている目的との関係で内在的な限界がある。
そして、「婚姻」の中には「生殖と子の養育」の趣旨が含まれており、これを満たさない人的結合関係を「婚姻」の中に含めることはできない。
また、憲法24条が「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めており、これもこの「生殖と子の養育」の趣旨と整合する形で定められたものとなっている。
「同性間の人的結合関係」については、その間で「生殖」を想定することができず、この「生殖と子の養育」の趣旨を満たすとはいえないことから、「婚姻」の中に含めることはできない。
また、憲法24条の「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言の趣旨にも当てはまらないため、「婚姻」とすることはできない。
結果として、憲法24条は「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とする法律を立法することを認めていないことになる。
他にも、憲法24条は「婚姻」を定めていることから、この憲法24条の「婚姻」や「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言が、法律で立法される婚姻制度の意味や内容を「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するものとして機能しないものに変えてしまうことを許しているはずがない。
そのため、婚姻制度の中に「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することが不能となるような人的結合関係を含めようとする法律を立法することを、憲法24条の「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言に照らし合わせて考えた際に、これらの文言はそれを許容していない。
よって、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することが不能となるような人的結合関係を「婚姻」として扱おうとする法律を立法した場合には、憲法24条の「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言に抵触して違憲となる。
このことから、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とする法律を立法しようとした場合には、憲法24条の「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言に抵触して違憲となる。
■ 生殖関係を整理するために性別は不可欠であること
「婚姻」は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられている枠組みである。
「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することは不可欠の目的であり、法制度として「婚姻」以外にこれを担うものは存在していない。
また、そもそも「婚姻」は、婚姻制度を利用した場合に法的効果や一定の優遇措置を得られるようにし、婚姻制度を利用しない場合との間に差異を設けることにより、婚姻制度を利用することに対してインセンティブを働かせ、婚姻制度を利用する者を増やすことによって目的の達成を目指す仕組みのものである。
そのため、その「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するための枠組みを規律するものとして唯一の制度となっていることがその機能を果たすための本質的な要素であるということができる。
このことから、この「婚姻」が排他的にその機能を担うことが本来的に求められている。
そして、その機能を担うものとして「生殖」との間で定義される「男性」と「女性」の「性別」を区別することを予定し、その区別に従った組み合わせを法的に結び付けることで、その目的を達成することを目指すものとして定められている。
そのため、このように「性別」によって区別され、その「性別」に基づいた形で制度を利用できる組み合わせを指定することは、その目的を達成するための手段として不可欠の要素として設けられる枠組みであるといえる。
そして、憲法24条は「婚姻」を規定し、この規範を「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)として定めているのであるから、「生殖」の関係において定義される「男性」と「女性」を組み合わせ、その間で子供が産まれた場合に遺伝的な父親を特定することができるというところにその枠組みを定めていることの意義を見出すことができるといえる。
このように、その目的を達成するための手段として整合的な枠組みとなっていることを確認することができる以上は、そこに規範的な意味を見出し、その枠に従った形で法制度を運用することにより、立法目的を達成することが予定されている。
このことから、憲法24条の「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言が、目的を達成するための手段となる枠組みに対応するものとして意味を構成している事実を確認できる以上は、その文言が示している枠組みに含まれている趣旨や、目的とその目的を達成するための手段の関係を無視することは解釈として正当化することのできるものではない。
そのため、憲法24条が「婚姻」について「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めることによって立法目的を達成しようとしている枠組みを変えることはできない。
これにより、憲法24条が「婚姻」を規定し、「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)の枠組みを定めていることについて、これをそれ以外の人的結合関係を指すものとして読み解くことはできない。
よって、これらの文言の中に「同性間」の人的結合関係が含まれるかのように考えることは誤りとなる。
■ 男女を区別する制度として定められていること
憲法24条1項には「両性」「夫婦」の文言が定められている。
これらの文言は「男性」と「女性」を区別することを前提としていることから、「性別」を区別することによって立法目的を達成することを意図するものであることは明らかである。
また、その「性別」による区別を前提とした上で、「男性」のグループと「女性」のグループのように同じ「性別」の者を集めてグループにするわけではなく、敢えて「男性」と「女性」という異なる性別の者同士を組み合わせることによって立法目的を達成することを意図していることも明らかである。
このように、異なる性別の二者を法的に結び付ける枠組みを設ける意図は、生物学的な因果関係から見て「男性」と「女性」の間に「貞操義務」を設けた場合に、産まれてきた子供の遺伝的な父親を特定することができる関係になるというところにある。
これは、人間が生命体として有性生殖を行う仕組みに着目し、人間の性質を「生殖」との関係において定義される「精子を生成し、陰茎を有するタイプ」の「男性」と、「卵子を生成し、妊娠し、子を産む機能を備え、膣を有するタイプ」の「女性」とに区別した上で、女性の子宮の中で「精子」と「卵子」が結合することによって子が生じるという状態に至る際に、その女性の「卵子」と、どの男性の「精子」が結合したかが明らかであるならば、そこで産まれてきた子に対して責任を担う者を特定することができる状態となるというところに意図があるといえる。
このため、「両性」「夫婦」という文言が使われていることの意味は、「男性」と「女性」を区別するものであることを前提とし、かつ、その区別を前提に敢えてその異なる性別の者同士を法的に結び付けることを意図していることは明らかである。
このような枠組みを設けることによって、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目指すものとして定められていることから、「両性」「夫婦」の文言を「生殖」との関係から切り離して用いることはできない。
そのことから、「婚姻」における「両性」「夫婦」などの文言は、「生殖」という営みと対応するものとして位置付けられている言葉であり、これを「男性」と「女性」の意味を離れて理解することは不可能である。
そのため、このような意図を達成することを阻害するものを、この「両性」「夫婦」の文言と照らし合わせて考えた場合には、その制度が「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するものとして機能するか否かという点で根本的に異なるものであり、相いれないものということになる。
そのようなものについては「両性」「夫婦」の中に含まれないこととなる。
このことから、「婚姻」とすることができる人的結合関係の範囲は、これらの意図を満たす「男性」と「女性」の両方が揃うことが必要であり、それを満たさない組み合わせについては「婚姻」とすることができない。
よって、「同性間の人的結合関係」が「両性」「夫婦」の文言の中に含まれると考えることはできず、「同性間の人的結合関係」がここに含まれるかのように述べることは誤りとなる。
■ 「法の支配」との関係
文字によって記されている言葉があり、その言葉の意味を理解し、その言葉が示す通りの行動を行った場合に、何らかの紛争を解決する機能を有しているのであれば、そこには法としての規範性を見出すことができるものとなっていることを意味する。
これを無視して、その文言の意味に沿わない制度の創設を許すことになれば、言語(文字)によって規範を設定し、予め基準を示すことによって、為政者の恣意的な権力行使を防ごうとする法の支配や立憲主義、法治主義を採用して国家運営を行っていることにはならない。
もしこれが可能となった場合には、法の条文にどのような文字を定めたとしても、その意味をその時々に権力を行使する者がいかようにでも無効化することができてしまうこととなり、法の支配、立憲主義、法治主義を採用している意味そのものが失われることになる。
つまり、条文を定める際にどんなに丁寧に言葉を選んだとしても意味がなくなるということである。
これでは、紛争の解決を法によって、つまり、客観性・明確性を持つ形で言語化された公のものとして示された基準に従って紛争を解決する作用によって行おうとする姿勢に反するものとなる。
そのため、日本国憲法を掲げ、法という秩序によって国家運営を行っている以上は、言葉が示す規範を歪める形で運用することは行ってはならないことである。
憲法24条に「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」という言葉が使われているのであれば、それは制度の枠組みについて具体的に基準を示していることを意味するのであって、その文言の意味に沿わない制度を立法することはできない。
そのため、憲法24条の「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言が一夫一婦制(男女二人一組)を定めていることの趣旨に沿わない人的結合関係がこの中に含まれているかのように主張することは誤りである。
■ 法解釈の限界との関係
「法の支配」とは、予め言語を用いて規範を示すことで将来起こる紛争を解決するための基準とするものであることから、法を解釈する過程の中で言葉の意味や定義そのものを変更することはできない。
もしそれをしようとすることは法解釈の限界を超えるものとして、そこで解釈しようとした条文そのものに反して違法となる。
そのため、その領域に踏み込む問題については、立法府によって条文を改正あるいは廃止するか、憲法改正の手続きによって憲法上の条文を改正あるいは廃止することによって対応することが必要である。
憲法は改正する手続きを用意しており、これによって憲法上の規定を改廃することが可能である以上は、憲法上の文言の意味そのものを別の意味に変えようとすることは、解釈の限界を超えるものである。
「婚姻」の文言の中に「男女」を満たさない人的結合関係が含まれているとか、含まれるべきであるとの主張は、「婚姻」という言葉を単なる「音の響き」に過ぎないものにまで解体し、言葉の意味そのものを改変して新たな意味を付与しようと試みるものということになる。
これは、言葉の意味を読み取って規範の意味を明らかにしようとするものとはいえないことから、法を解釈するという営みの中で正当化することができる範囲を超えており、法解釈としての限界を超えるものである。
これは、憲法上の規定を改廃する手続きによってしか行うことのできない領域に踏み込むものであり、解釈として妥当性を有しておらず、規範の意味から逸脱した違法な解釈となる。
このような解釈の限界を超えた判断を行うことは、後に別の角度から訴訟が起こされた場合に、その解釈そのものが否定され、その解釈が憲法に違反すると判断されることを導くことになる。
そのため、法の条文の中に具体的な定義について逐一触れていないとしても、その文言そのものが有する意味や条文の構造、条文の持つ趣旨や目的に拘束されるのであり、裁判所がそれを超える意味を新たに加えることが可能となるわけではない。
つまり、言葉の意味が歪められるようなことがあってはならないということである。
よって、憲法24条の「婚姻」の概念が有する内在的な限界を考慮せずに、どのような人的結合関係でも「婚姻」に含まれる余地があるかのように主張することは誤りである。
もし憲法24条の「婚姻」の範囲を超える制度が設けられたとしても、後に訴訟が起こされた場合には、憲法上の文言に含まれているものではないことから、これが含まれるとした裁判所の判決の違法性が発見され、その内容が見直され、その判決の内容が無効化されることになる。
■ いくつかの立場との関係性
上記のような理解について、憲法24条の条文の意味を読み取る際のいくつかの立場との関係は下記のように整理することができる。
▼ 「婚姻」の由来
この立場は、「婚姻」という枠組みが形成された由来を遡り、「婚姻」という概念そのものが有している「目的」とその目的を達成するための「手段」とを整合的な形で考えるものである。
「婚姻」という枠組みが形成された由来を考えるため、「婚姻」という概念そのものが有している内在的な限界も考慮することになる。
これについては、上記で解説した通りである。
◇ 存在しない説
この立場は、「婚姻」とは自然生殖可能性のある組み合わせを優遇する制度であることから、それを満たさない形の「婚姻」というものは存在しないと考えるものである。
「同性間」についても、その間で自然生殖を想定することができないことから、「婚姻」とはいえず、「同性間」の「婚姻」という概念は存在しないことになる。
国(行政府)の主張の中で、この立場に重なる部分は下記がある。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
イ しかしながら、法の解釈に際し、文言の日本語としての意味や文法が重視・尊重されなければならず、文言からかけ離れた解釈が許されないのは当然であるところ、前記2(2)
において述べたとおり、「両性」とは、両方の性、男性と女性又は二つの異なった性を意味し、「夫婦」とは、夫と妻又は適法の婚姻をした男女の身分を意味する文言であり、「両性」及び「夫婦」が男性又は女性のいずれかを欠き当事者双方の性別が同一である場合を含む概念であると理解する余地はなく、このような理解は、憲法24条1項の制定過程及び審議状況からも裏付けられている。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【東京一次・第1回】控訴答弁書 令和5年6月23日 PDF (P22~23)
◇ 成立条件説
この立場は、憲法24条1項の「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、」の文は「婚姻」の成立条件を示すものと考えるものである。
「婚姻」を成立させるためには「両性」である「男性」と「女性」の合意を必要とすると定めていることから、「同性間」で合意しても「婚姻」としては成立しないことになる。
国(行政府)は下記のように述べている。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
他方、同条2項は、婚姻等に関する事項について具体的な制度を構築するに当たっての立法上の要請及び指針を示したものであるが、上記のとおり、婚姻の成立については、同条1項により、両性の合意のみに基づいて成立する旨が明らかにされていることから、婚姻の成立要件等を定める法律は、かかる同条1項の規定に則した内容でなければならない。そのため、婚姻等に関する事項について立法上の要請及び指針を示した同条2項においては、同条1項の内容も踏まえ、配偶者の選択ないし婚姻等に関する法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならないとしたものである(憲法24条2項における配偶者の選択とは婚姻の相手の選択であるから、それについて、法律が個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならないということは、婚姻が当事者の自由な合意のみによって成立すべきことを意味し、同条1項の規定と同趣旨であると解されている(佐藤功「憲法(上)[新版]」414ページ。乙第33号証))。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【東京一次・第1回】控訴答弁書 令和5年6月23日 PDF
◇ 想定していない説
この立場は、憲法24条は「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを想定していないと考えるものである。
上記の三説と下記の三説のいずれの可能性もある。
国(行政府)は、下記のように「成立させること」と「想定していない」の両方を用いて説明している。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ア もっとも、前記(1) のとおり、憲法24条1項は、「両性」及び「夫婦」という文言を用いているところ、一般的に、「両性」とは、両方の性、男性と女性又は二つの異なった性を意味し、「夫婦」とは、夫と妻又は適法の婚姻をした男女の身分を意味するものとされている(新村出編・広辞苑第7版2526及び3095ページ)ことからすると、同項にいう「夫婦」や「両性」もこれと同義とみるべきであるから、憲法は、「両性」の一方を欠き当事者双方の性別が同一である場合に婚姻を成立させることをそもそも想定していないというべきである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【東京一次・第1回】控訴答弁書 令和5年6月23日 PDF (P14)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ア しかしながら、法の解釈に際し、文言の日本語としての意味や文法が重視・尊重されなければならず、文言からかけ離れた解釈が許されないのは当然であるところ、これまで繰り返し述べているとおり、憲法24条1項は、「両性」及び「夫婦」という文言を用いており、一般に、「両性」とは、両方の性、男性と女性又は二つの異なった性を意味し、「夫婦」とは、夫と妻又は適法の婚姻をした男女の身分を意味するものとされている(新村出編・広辞苑第7版2526及び3095ページ)ことからすると、同項にいう「夫婦」や「両性」もこれと同義とみるべきであるから、憲法は、「両性」の一方を欠き当事者双方の性別が同一である場合に婚姻を成立させることをそもそも想定していないというべきである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【東京二次・第9回】被告第7準備書面 令和5年9月28日 PDF (P5)
◇ 立法裁量の限界を画するもの
この立場は、憲法24条は立法裁量の限界を画する規定であることから、24条の文言に沿わない関係については、「婚姻」とすることができないと考えるものである。
憲法24条は「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めており、この形に限定して立法裁量の限界を画していることから、それ以外の人的結合関係を「婚姻」とすることはできない。
「同性間の人的結合関係」についても、これを満たさないため「婚姻」とすることはできないことになる。
◇ 禁止説
この立場は、憲法24条の規定は、何かを認知した上でそれを防ぐ意図をもって定められていることから、その規定に合わないものについては禁止されていると考えるものである。
「同性間の人的結合関係」についても、憲法24条の規定が「両性」「夫婦」の文言を定めていることに合わないことから、憲法24条は「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることの論点を認知した上で、それを防ぐ意図をもって禁止していることになる。
◇ 義務文・否定文による禁止説
この立場は、憲法24条1項の規定は「両性~に基づいて成立し、~なければならない。」(shall)という義務文・否定文による禁止の意味を有すると考えるものである。
これによれば、憲法24条1項は「両性」を満たさない人的結合関係を「婚姻」とすることを義務文・否定文によって禁止していることになる。
「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることについても、「両性」を満たさないため義務文・否定文によって禁止されていることになる。
■ 結論
憲法上の文言に従う解釈を行った場合に、そこに目的を達成するための手段として整合的な枠組みとなっていることを確認することができ、憲法上の規範としての意義を見出すことができる以上は、そこに規範的な力を認めることによって、憲法の規範性を保つことが求められる。
そのため、この判決では「同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障していると考えることが相当である。」のように述べて、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることができるかのように論じようとしているが、上記の点を考慮しないものであり、その結論は正当化することができない。
よって、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることができることを前提に論じていることは誤りとなる。
その他、この段落では、結論に至るまでの間に論理的な過程が示されていないことの問題について検討する。
一つ前の「ウ」の第二段落では「その目的とするところを踏まえて解釈することは一般的に行われており、」や「やはり立法の目的とするところに合わせ、」と述べられている。
しかし、この段落で解釈の過程としてこの「目的」に当たるものとして挙げられているものは、下記の内容である。
A 「性的指向及び同性間の婚姻の自由は、現在に至っては、憲法13条によっても、人格権の一内容を構成する可能性があり、十分に尊重されるべき重要な法的利益であると解される」
B 「憲法24条1項は、婚姻をするかどうか、いつ誰と婚姻をするかについては、 当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたものと解され、このような婚姻をするについての自由は、同項の規定に照らし、十分尊重に値するものと解することができる(再婚禁止期間制度訴訟大法廷判決参照)。」
C 「憲法24条2項は、婚姻及び家族に関する事項についての立法に当たっては、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきと定めている。」
上記「A」の憲法13条の説明については、憲法24条とは別の条文であり、憲法24条が「婚姻」の枠組みを定めている根拠となるようなものではない。
また、「B」の憲法24条1項や「C」の憲法24条2項の説明についても、その条文が意図する機能(その条文が下位の法令に対してどのような影響を与えることが意図されているか)について述べているだけである。
(「B」は、憲法24条1項の条文が存在することを前提として、その意味を解釈した結果として導き出されたものであり、憲法24条1項の条文よりも上位にある規範として示されたものではない。)
(「C」も、憲法24条2項の条文が存在することを前提として、その意味について説明するものであり、憲法24条の条文よりも上位にある規範が示されているわけではない。)
そのため、これも「ウ」の第二段落で論じている「目的」にあたる説明をしているものではない。
これらは、憲法24条1項の条文を解釈した結果として導かれるとする「婚姻をするについての自由」と、憲法24条2項が法律の内容に対して「個人の尊厳」と「両性の本質的平等」を満たすことを求めているものである。
これは憲法24条が機能することによって下位の法令に対してどのような影響を与えるかに関するものであり、これは「ウ」の第二段落で論じている「目的」に対応するものではない。
このように、これらの説明は、憲法24条が「婚姻」の枠組みを定め、その内容を「両性」「夫婦」「相互」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)としていることの背景にある「目的」(国の立法目的)について述べているものではない。
そのことから、これらの説明は、法令を解釈する場合において検討される「目的」(国の立法目的)を示したものであるとはいえず、憲法24条1項が「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めている規範の意味を書き換えることができるとする根拠とはならないものである。
よって、この札幌高裁判決は、前提として示している「目的」(国の立法目的)にあたるものが示されていないままに憲法24条1項の条文に記された文言の意味を変更し、特定の結論だけを述べて正当化を試みるものとなっていることになる。
結果として、結論に至るまでの判断の過程において正当化することができる論理的な筋道のある手続き踏むものとなっていないことを意味し、根拠を示さないままに結論だけを述べていることになることから、その結論も正当化することはできない。
このような解釈の過程において論理的な筋道が示されておらず、公共的な合意を形成するものとして成り立っていないことの不当性については、下記が参考になる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法を解釈することと、法を解釈していると思い込んでいることとを区別しうるためには、解釈は個人的・私的なものではなく、社会的な、つまり原理的には誰にも共通にアクセス可能な、公的活動でなければならないはずである。各人がそれぞれ異なった形で得心がいっただけでは、法解釈として十分とはいえない。解釈者は、他人を説得し、同じように既存の法源(判例・法令)を見るように議論を進める必要がある。もちろん、その結果、つねに同一の結論へと人々の意見が集約されるとは限らない。同じ程度に説得力を持つ複数の解釈が競合することは珍しいことではない。
解釈が解釈であるためには、つまり、それが原理的に誰もが参加しうる公的な活動であるためには、第一に、法源の核心的な意味の理解を可能とする共通の言語作用が背景として存在していなければならない。そして、第二に、解釈の目的は、例外的・病理的現象である法の意味の不明瞭化に対して、人々の合意をとりつけることで、正常な法の機能を回復すること、人々が再び疑いをもたずに法に従いうる状態を回復することになければならない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
憲法の理性 長谷部恭男 (P210) (下線は筆者)
(3)ア 他方で、婚姻及び家族に関する事項は、国の伝統や国民感情を含めた社会状況における種々の要因を踏まえつつ、それぞれの時代における夫婦や親子関係についての全体の規律を見据えた総合的な判断によって定められるべきものである。特に、憲法上明記されていない権利、又は直接保障された権利とまではいえない人格的利益や実質的平等は、その内容として多様なものが考えられ、それらの実現の在り方は、その時々における社会的条件、国民生活の状況、家族の在り方等との関係において決められるべきものである。
イ そうすると、憲法上の権利として保障される人格権を不当に侵害して憲法13条に違反する立法措置を講じてはならないことは当然であるとはいえ、憲法24条の要請、指針に応えて具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定が上記アのとおり国会の多方面にわたる検討と判断に委ねられているものであることからすれば、婚姻及び家族に関する法制度を定めた法律の規定が憲法24条に適合するものとして是認されるか否かは、当該法制度の趣旨や同制度を採用することにより生ずる影響につき検討し、当該規定が個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理性を欠き、国会の立法裁量の範囲を超えるものとみざるを得ないような場合に当たるか否かという観点から判断すべきものとするのが相当である(夫婦同姓制度訴訟大法廷判決参照)。
【筆者】
ここで示された判決は、下記の通りである。
(灰色で潰した部分が、上記の記述と文面が重なる部分である。)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3(1) 他方で,婚姻及び家族に関する事項は,国の伝統や国民感情を含めた社会状況における種々の要因を踏まえつつ,それぞれの時代における夫婦や親子関係についての全体の規律を見据えた総合的な判断によって定められるべきものである。特に,憲法上直接保障された権利とまではいえない人格的利益や実質的平等は,その内容として多様なものが考えられ,それらの実現の在り方は,その時々における社会的条件,国民生活の状況,家族の在り方等との関係において決められるべきものである。
(2) そうすると,憲法上の権利として保障される人格権を不当に侵害して憲法13条に違反する立法措置や不合理な差別を定めて憲法14条1項に違反する立法措置を講じてはならないことは当然であるとはいえ,憲法24条の要請,指針に応えて具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定が上記(1)のとおり国会の多方面にわたる検討と判断に委ねられているものであることからすれば,婚姻及び家族に関する法制度を定めた法律の規定が憲法13条,14条1項に違反しない場合に,更に憲法24条にも適合するものとして是認されるか否かは,当該法制度の趣旨や同制度を採用することにより生ずる影響につき検討し,当該規定が個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理性を欠き,国会の立法裁量の範囲を超えるものとみざるを得ないような場合に当たるか否かという観点から判断すべきものとするのが相当である。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(PDF)
「ア」の第二文の冒頭の「特に、憲法上明記されていない権利、又は」との部分は、「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」とは異なっている。
◇ 「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」
「特に,憲法上直接保障された権利とまではいえない人格的利益や実質的平等は,」
◇ この札幌高裁判決
「特に、憲法上明記されていない権利、又は直接保障された権利とまではいえない人格的利益や実質的平等は、」
ここで「憲法上明記されていない権利」との文言が追加されているが、これにより、「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」で示された内容を変えるものとなっている。
しかし、司法権を行使するにあたっては、その事件を担当している裁判官の個人的な思いや恣意的な判断によって参照している判例の内容が歪められるようなことがあってはならない。
この札幌高裁判決が最高裁判決で示されている文面を正確に引用せずに文面を歪めて利用している背景には、最高裁判決の中で前提となっている事柄を意図的に無視することにより、この判決を書いた裁判官が望む特定の結論を導き出すために恣意的な判断が行われていないか注意する必要がある。
もしそのような意図に基づいて文言を変更しているとすれば、論理的な整合性を積み重ねることによって結論を導き出すのではなく、恣意的な形で特定の結論を導き出そうとする不正な手続きであるし、最高裁判決で用いられた文面に記された意味を改竄するものであり、解釈の過程を誤った違法なものとなる。
法解釈は、論理的整合性を積み重ねることによって結論を正当化することが可能となる。
解釈の過程で根拠となっている判例の文言を勝手に変更したり、恣意的に文言を変更したり、文章の内容を改竄したり、文章の意味を読み替えたり、その文面で用いられている文意の理解や前提となっている事柄から離れる形で用いた場合には、その判決の文面が前提としている憲法や法律などの具体的な条文や、その背景にある立法目的とその立法目的を達成するための手段となる枠組みとの関係から切り離されたものとなる。
そのような前提となっている条文や判決の文面に記された意味や内容から切り離された単なる文面を利用して何らかの結論を導き出そうとしても、その文面そのものが既に根拠となる法源から論理的な過程を積み重ねることによって導き出されたものとはいえないものとなっていることから、法的に正当化することのできる基盤を失っていることになる。
すると、その文面を理由とした解釈や判断の枠組みについても法的な効力を有することにはならず、当然、そこで示された結論も正当化することはできない。
よって、このような文言上の操作を行うことは、不正であり、前提となっている事柄から断絶させるものとして違法な手続きということになる。
また、裁判所が、裁判体ごとにこのような誤った引用を繰り返していけば、判例の体系的な整合性が損なわれていき、規範の意味が曖昧化したり、流動化することとなり、裁判体ごとに別々の結論が下されてしまうことに繋がる。
そうなれば、同様の事件であれば誰が裁判を行っても同様の結論が導き出されるはずであるとの公平性や公正性への期待感が損なわれ、法的安定性も損なわれ、国民の抱く司法への信頼も失われることになる。
そのため、司法権を行使するという法的な判断において別の裁判で示された判決の内容を引用する際には、このような不正な手続きが行われることを極限まで排除するために、より厳格な形での引用を行うように徹底することが望ましいといえる。
もともとの判決文を切り貼りする行為によって、そのもともとの判決文の解釈の過程で示されている規範の意味が変更されたり、曖昧化したり、別の裁判体が判決を積み重ねていくうちに規範の内容が流動化するようなことがあってはならない。
他にも、この札幌高裁判決が新たに文言を加えた文は、構造的曖昧文を形成するものとなっており、読み取りが困難である。
そのため、日本語の文法表現としても問題がある。
◇ 夫婦同姓制度訴訟大法廷判決
「憲法上直接保障された権利とまではいえない人格的利益や実質的平等」
上記の読み方は一つしかないため、文の意味を理解することが可能である。
◇ この札幌高裁判決
「憲法上明記されていない権利、又は直接保障された権利とまではいえない人格的利益や実質的平等」
読み方 1
「憲法上明記されていない権利、」(又は)「直接保障された権利とまではいえない人格的利益や実質的平等」
読み方 2
「『憲法上明記されていない権利、』(又は)『直接保障された権利』とまではいえない人格的利益や実質的平等」
読み方 3
「憲法上『明記されていない権利、』(又は)『直接保障された権利とまではいえない人格的利益や実質的平等』」
読み方 4
「憲法上『明記されていない権利、』(又は)『直接保障された権利』とまではいえない人格的利益や実質的平等」
「、」の位置から考えると、「読み方 1」や「読み方 2」ではないかとの推測を導くものとなっているように見える。
しかし、「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」で「憲法上直接保障された……」のように、「憲法上」と「直接保障された」の文言が繋がっていたところに、後から割り込む形でその間に「明記されていない権利、」と入れていることから、「憲法上」の文字を「憲法上直接保障された……」にもかかるものとして読み取ることが正しいのかもしれないと思わせるものとなっている。
すると、「又は」の文言は、「読み方 4」のように、「又は」の文言の前後の「憲法上明記されていない権利」と「(憲法上)直接保障された権利」のように「権利」を基にした形でそれらを並列の関係で示すものではないかと思わせるものとなる。
これにより、「憲法上」の文言は、「明記されていない権利」と「直接保障された権利」の両方に掛かり、また、これら両方をまとめる形で「とまではいえない人格的利益や実質的平等」が加えられているのではないかと思わせるものとなっている。
また、この読み方においては、「又は」の文言の前後の部分は、それぞれ別の意味を持つ言葉ではなく、「憲法上明記されていない権利」ということは「(憲法上)直接保障された権利」ではないという類似した関係から、同じもの指しており、「又は」の文言は言葉の言い換えを示すものとして使われているのではないかと推測させるものとなっている。
ただ、そうなると、「憲法上明記されていない権利」「とまではいえない人格的利益や実質的平等」とは何かという問題に行き着く。
他にも、通常は「(憲法上)直接保障された権利」のような典型的な事例を先に示した後で、「憲法上明記されていない権利」のような非典型的な事例を示すという流れで説明するはずであるが、ここでは非典型的な事例から先に説明していることになり、読み手を混乱させる順序で説明していることになる。
また、この典型的な事例と非典型的な事例を別々に示すものであるとすれば、先ほど「又は」の文言は前後で同じ意味の事柄について言葉を言い換えていることを示すために用いられているのではないかとの推測は外れていたということになる。
上記のように、この札幌高裁判決の文面は、日本語の文法として構造的に曖昧性を含むものとなっており、読み手に正しい理解を伝えることができないものとなっている。
そのため、「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」の文面を勝手に変更している点で引用の方法として誤っているし、その内容の表現も文法上の問題を抱えたものとなっており、不適切であるといえる。
このような構造的な曖昧性を持つ文の問題点については、当サイト「構造的曖昧文の克服」で解説している。
「ア」の部分の冒頭に 「他方で、」とある。
これは「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」の中で使わている文言をそのまま用いているものであるが、この判決では「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」とは異なり、これよりも前の段落では、別の事柄について説明するものとなっている。
よって、この札幌高裁判決の内容の文脈との対応関係を見ないままに、このような別の判決の中で示された「他方で、」の文言をそのまま引用していることは、この札幌高裁判決を読み取る読者にとって意味の通じない文章となるため妥当でない。
この「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」のこの部分が述べているのは、憲法24条2項の「婚姻及び家族」の枠組みの「要請」に従って法律上の「婚姻及び家族」の制度(婚姻及び家族に関する法制度を定めた法律の規定)が立法されていることを前提として、その法律上の「婚姻及び家族」の制度の内容を構成している細目的な規定に関しては基本的に国会の立法裁量の範囲の事柄であるが、その細目的な規定が「個人の尊厳」と「両性の本質的平等」を満たしていない場合には国会の立法裁量の範囲を超えるとされる場合があるということである。
そこで、「個人の尊厳」と「両性の本質的平等」を満たすか否かを検討する際の前提となっている「婚姻及び家族」の枠組みについて検討する。
「婚姻」とは、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」を目的として、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす「一人の男性」と「一人の女性」を選び出し、その間に「貞操義務」を設けるなど一定の形式で法的に結び付け、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によって立法目的の達成を目指す枠組みのことである。
憲法24条が「婚姻」について「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めていることも、この趣旨に対応するものである。
この「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」の文面の上記の下線部でも「夫婦や親子関係」と記されており、「婚姻」の枠組みが一夫一婦制(男女二人一組)であることを前提としていることを読み取ることができる。
この点、国(行政府)は下記のように説明している。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
イ 憲法24条2項は同条1項を前提とした規定であり、同条2項における立法上の要請及び指針も、婚姻が異性間の人的結合関係を対象とするものであることを前提としていること
控訴答弁書第3の2(1)(12及び13ページ)及び (3)(16ないし19ページ)で述べたとおり、憲法24条2項は、婚姻及び家族に関する事項について、具体的な制度の構築を第一次的には国会の合理的な立法裁量に委ねるとともに、その立法に当たっては、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきであるとする要請、指針を示すことによって、その裁量の限界を画したものであるところ(再婚禁止期間違憲判決)、同項における立法上の要請及び指針は、形式的にも内容的にも、同条1項の存在及び内容を前提とすることが明らかである(平成27年夫婦別姓訴訟最高裁判決も同旨の判示をしているところである。)。
そして、前記アのとおり、憲法24条1項が、婚姻について異性間の人的結合関係のみを対象としていることに加え、同条2項においても、同条1項と同じく「両性」といった男性と女性の両方の性を意味する文言が用いられていることからすれば、同条2項も、飽くまで婚姻が異性間の人的結合関係を対象とするものであることを前提として、これを具体化する制度の整備を立法府に要請するものであることが明らかである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【東京一次・第3回】被控訴人第2準備書面 令和6年2月29日 PDF
また、「家族」とは、「(2)ウ」の第三段落のところで解説したように、「夫婦」と「親子」による「血縁関係者」のことをいう。
この「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」の文面の上記の下線部で「夫婦や親子関係」と述べているのは、この意味に対応するものである。
そのため、「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」は、この「婚姻及び家族」の枠組みの対象とする人的結合関係の範囲が存在することを前提として、その枠組みの「要請」に従って立法される法律上の「婚姻及び家族」の対象とする人的結合関係の枠組みに付随して設けられる細目的な規定について「国会の立法裁量」があることを述べているものである。
そのことから、これは「婚姻及び家族」の枠組みが対象としている人的結合関係の範囲そのものまでをも「国会の立法裁量」の範囲に含まれるとしているわけではない。
このことから、この「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」が「国会の立法裁量」の範囲の中にあるものに対して「個人の尊厳」と「両性の本質的平等」を満たすか否かを判断することができる旨を述べている部分を持ち出したとしても、これを根拠として「婚姻及び家族」の対象とする人的結合関係の範囲そのものを変更することができるということにはならない。
当然、「婚姻及び家族」の対象とする人的結合関係の範囲は、「国会の立法裁量」の範囲に含まれているわけではないことから、裁判所によって「国会の立法裁量」が存在する部分について「個人の尊厳」と「両性の本質的平等」に照らしてその「立法裁量」の範囲を超えるか否かを審査する対象になるものでもない。
そのため、この「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」のこの部分の説明を持ち出したとしても、これを根拠として「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることができることにはならないし、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とする法律が存在しないことが憲法に違反するとの結論にも繋がらないものである。
よって、後に「(4)キ」の部分で「本件規定は、憲法24条に違反する。」と結論付けるまでの根拠としてこの「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」のこの部分の説明を持ち出していることは誤りである。
その他、国会であっても「婚姻及び家族」の中に含まれない人的結合関係を「婚姻及び家族」の中に含めるという権限を有しているわけではない。
まず、「婚姻及び家族」の枠組みは、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」という目的を共有し、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす形で統一的に形成されるものである。
そのため、「婚姻及び家族」の中に含めることのできる人的結合関係の範囲には内在的な限界がある。
そのことから、どのような人的結合関係でも「婚姻及び家族」の中に含めることができるというものではない。
また、もし国会が法律上の「婚姻及び家族」の制度の中に「夫婦」と「親子」による「血縁関係者」の範囲に含まれない人的結合関係を含めようとした場合には、それは「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成するための手段として整合的な要素を満たすものではないことから、その目的の達成を阻害する影響を生じさせることになる。
こうなると、実質的に憲法24条2項の示す「婚姻及び家族」ではないものを「婚姻及び家族」という名前で呼ぼうと試みるものであるということになる。
それは結局、憲法24条の「婚姻」や憲法24条2項の「婚姻及び家族」の枠組みが、一夫一婦制(男女二人一組)による「婚姻」と、「家族」である「夫婦」と「親子」による「血縁関係者」について定めた法律を立法することによって「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的の達成を目指すことを「要請」しているにもかかわらず、その「要請」に従った内容の法律が存在しない(定められていない)状態となっていることを意味し、憲法24条に違反することになる。
よって、国会は「婚姻及び家族」の中に含まれない人的結合関係を「婚姻及び家族」の中に含めるという権限を有していない。
この点でも、この「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」が「国会の立法裁量」について触れているとしても、その「国会の立法裁量」の対象となっている事柄は、あくまで憲法24条2項の「婚姻及び家族」の対象とする人的結合関係の枠組みが存在することを前提として、その枠組みの「要請」に従って立法される法律上の「婚姻及び家族」の対象とする人的結合関係の枠組みに付随して設けられる細目的な規定の内容だけである。
そのため、「国会の立法裁量」の中に「婚姻及び家族」の枠組みの対象となっている人的結合関係の範囲そのものを変更する権限は含まれておらず、当然、「国会の立法裁量」があることを前提として、その「立法裁量」の範囲を超えるか否かという点について司法権の行使として判断することができるとする部分には当たらないことから、これによって憲法に違反するという結論が導き出されることもない。
もう一つ、この「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」で述べられている「当該規定が個人の尊厳」「の要請に照らして合理性を欠き,国会の立法裁量の範囲を超えるものとみざるを得ないような場合に当たる」とは、具体的にどのような場合であるかを検討する。
まず、「個人の尊厳」は、自然人であれば誰もが持つとされている。
そのため、人間であるにもかかわらず法的に自然人として扱われていない状態、例えば、人が物や動物のように扱われたり、奴隷のように扱われたりしている場合には、この意味の「個人の尊厳」を用いて是正することができる。
また、「個人の尊厳」は、「全体主義」との対比において「個人主義」に根差すという文脈で使われている。
そのため、個人が全体の中の一部として扱われたり、個々人が何者かの付属物として扱われたりすることがあれば、この意味の「個人の尊厳」を用いて是正することができる。
他にも、「個人の尊厳」は、権利や義務を結び付けることのできる法的な主体としての地位を指すものである。
そのため、「権利能力」を喪失させられたり、「意思能力」を否定されたり、「行為能力」を制限されるようなことがあった場合には、この意味の「個人の尊厳」を用いてそれを是正することができる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
民法は我々の生活関係を権利と義務に分解して規定し、規律するが、この権利及び義務の帰属主体となりうる資格を権利能力という。民法は、権利能力はあらゆる自然人が平等に有するとしているが、このことは近代法によって確立された原則であり、近代法が発達する以前の時代、すなわち奴隷制が存在した時代や、封建時代には、人によっては権利能力を認められない自然人も存在したのである。人は権利能力があって初めて法律的に自由な経済活動が可能となるのであり、その権利能力を自然人に平等に認めるのは、憲法の要請でもある。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第15課 民法―権利義務の主体(自然人その1) (下線・太字は筆者)
【動画】〔独学〕司法試験・予備試験合格講座 民法(基本知識・論証パターン編)第8講:権利能力と胎児 〔2021年版・民法改正対応済み〕 2021/05/28
【動画】【行政書士試験対策】権利能力//権利・義務の主体となれるのは? 2023/03/25
【動画】民法本論1 01権利能力 2011/04/11
【動画】2021応用インプット講座 民法5(総則5 権利能力) 2020/11/20
権利主体とは?権利能力の発生要件・意思能力や行為能力との違い・事業者の注意点などを分かりやすく解説! 2023.05.26
このため、もし「権利能力」を喪失させたり、「意思能力」を否定したり、「行為能力」を制限したりする法律が立法された場合には、その内容について、立法目的の合理性と、その立法目的を達成するための手段の合理性を審査し、その立法目的に合理的な根拠がなく、又はその手段・方法の具体的内容が立法目的との関連において著しく不合理なものといわざるを得ないような場合であって、立法府に与えられた裁量の範囲を逸脱し又は濫用するものであることが明らかである場合には、その要件が「個人の尊厳」に反するものとして是正されることは考えられる。
ただ、「個人の尊厳」を用いることができる場合があるとしても、これらを是正することができるということに留まるものである。
また、「個人の尊厳」というだけでは、何らの規範的な枠組みを示すものではないことから、この「個人の尊厳」を用いて特定の制度を創設することを国家に対して求めることができるとする根拠となることはないし、当然、これによって具体的な制度の内容を形成することができるというものでもない。
そして、憲法24条2項には「個人の尊厳」が定められている。
これは、憲法24条2項の「婚姻及び家族」の枠組みの「要請」に従って立法される法律上の「婚姻及び家族」の制度の内容が「個人の尊厳」を満たすものとなるよう求めるものである。
この「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」のこの部分で「個人の尊厳」に違反するか否かを論じていることも、この点について述べるものである。
ただ、現行の婚姻制度を利用したとしても、その者が自然人としての地位を失って物や動物のように扱われるということはないし、奴隷のように売買される対象となるようなこともない。
また、その者が集団の中の一部として扱われたり、何者かの付属物として扱われたりすることもない。
他にも、「権利能力」を喪失したり、「意思能力」が否定されたり、「行為能力」が制限されたりするということもない。
戦前の明治民法においては、婚姻した場合に妻が「無能力者」(制限行為能力者)となっていたが、この点は新憲法であるこの24条2項の「個人の尊厳」に抵触すると考えられたことから、民法改正の過程で既に改められている。
そのことから、もし「権利能力」を喪失させたり、「意思能力」を否定したり、「行為能力」を制限したりする要件を持つ婚姻制度が立法された場合には、その内容について、立法目的の合理性と、その立法目的を達成するための手段の合理性を審査し、その立法目的に合理的な根拠がなく、又はその手段・方法の具体的内容が立法目的との関連において著しく不合理なものといわざるを得ないような場合であって、立法府に与えられた裁量の範囲を逸脱し又は濫用するものであることが明らかである場合には、その要件が憲法24条2項の「個人の尊厳」に違反するものとして無効となり、是正されることは考えられるが、現行の婚姻制度を利用したとしても、上記のような事態は生じておらず、「個人の尊厳」が損なわれている状態にあるとはいえないことから、憲法24条2項の「個人の尊厳」に違反するということはない。
また、「個人の尊厳」というだけでは、何らの規範的な枠組みを示すものではないことから、この「個人の尊厳」を用いて特定の制度を創設することを国家に対して求めることができるとする根拠になるものではなく、当然、これによって具体的な制度の内容を形成することができるということにもならない。
そのため、この憲法24条2項の「個人の尊厳」の文言を用いて婚姻制度(男女二人一組)の中に存在しない特定の制度を創設するように求めたり、制度の内容を特定の形に形成しようとすることはできない。
もしそれをするための根拠として用いようとした場合には、憲法24条2項の「個人の尊厳」の文言を用いて是正することができるとする役割の範囲を超えるものとなるため、その結論を正当化することはできない。
そのことから、この憲法24条2項の「個人の尊厳」の文言を、婚姻制度(男女二人一組)の中に存在しない具体的な制度の創設を求めたり、制度の内容を特定の形に形成しようとする根拠として用いることができるかのように論じることは誤りである。
よって、この憲法24条2項の「個人の尊厳」の文言を用いて「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とする法律を立法することを根拠付けようとすることは誤りであるし、「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」の述べている「個人の尊厳」の審査についても、それを正当化することができることを前提として述べられているものではないことから、これを用いて「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とする法律を立法することを根拠付けようとすることも誤りである。
ウ 上記ア及びイの点につき、憲法24条1項が同性婚をも保障していると解するとしても、文言上は異性間の婚姻を定めていることから、異性間の婚姻のみを定める本件規定が憲法24条に違反するかどうかを判断するに当たっても、同様の検討が必要と考えられる。
【筆者】
━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━
この文が読み取りづらい原因は下記の通りである。
◇ この文は「上記ア及びイの点につき、」のように、前の文を受けて説明を始めている。
そのため、その後には「上記ア及びイの点」に関係する内容を説明することが通常予想される文の流れである。
しかし、この文では、その後に「憲法24条1項が同性婚をも保障していると解するとしても、」と述べており、これは三段落前の「(2)ウ」の第三段落の第四文の説明を引き継ぐものであり、「上記ア及びイの点」の内容を説明するものではない。
また、これに続いて「文言上は異性間の婚姻を定めていることから、」の部分も、やはり「(2)ウ」の説明、あるいは、それよりさらに前に遡って「(2)ア」の第一段落の説明を引き継ぐ内容であり、「上記ア及びイの点」の内容を説明するものではない。
これにより、読者はこの文が、この判決の全体との対応関係においてどの部分と結び付くものとして説明されているのか把握することがむずかしく、読み取ることが困難となるのである。
◇ 「文言上は異性間の婚姻を定めていることから、」との「文言」は、この文の中ではこの部分よりも先に「憲法24条1項」が登場しており、その「憲法24条1項」も「婚姻」について定め、「両性」「夫婦」との文言が使われていることから、「憲法24条1項」の「文言」について説明するものと考えることが普通である。
・ 憲法上の規定の「文言」を指すと考える場合
「憲法24条1項が同性婚をも保障していると解するとしても、文言上は異性間の婚姻を定めていることから、」
↓ ↓
「異性間の婚姻のみを定める本件規定が憲法24条に違反するかどうかを判断するに当たっても、」「上記ア及びイの点につき、」「同様の検討が必要と考えられる。」
しかし、この文は「上記ア及びイの点につき、」「同様の検討が必要」として「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」における「検討」と「同様」と考えており、「憲法24条に違反するかどうか」が問われていることを見ると、この「文言」とは、法律上の規定のことを指していると考えることも可能であるように思われる。
・ 法律上の規定の「文言」を指すと考える場合
「憲法24条1項が同性婚をも保障していると解するとしても、」
↓ ↓
「文言上は異性間の婚姻を定めていることから、異性間の婚姻のみを定める本件規定が憲法24条に違反するかどうかを判断するに当たっても、」「上記ア及びイの点につき、」「同様の検討が必要と考えられる。」
ただ、このように読み取ると、「文言上は異性間の婚姻を定めていることから、異性間の婚姻のみを定める本件規定が」の部分は、「文言上は異性間の婚姻を定めている」と「異性間の婚姻のみを定める本件規定」とで、同じ法律上の規定のことを繰り返して述べていることになり、不自然である。
この不自然さを避けるため、下記のような並べ替えも考えられる。
「憲法24条1項が同性婚をも保障していると解するとしても、」
↓ ↓
「異性間の婚姻のみを定める本件規定が」「文言上は異性間の婚姻を定めていることから、」「憲法24条に違反するかどうかを判断するに当たっても、」「上記ア及びイの点につき、」「同様の検討が必要と考えられる。」
この場合、少し読み取りやすくはなったが、本来の語順の中でこの判決が述べようとしていることとは異なると考えられる。
すると、やはりここで登場する「文言」とは、「憲法24条1項」の「文言」について述べているものと考えることが妥当であるように思わる。
「憲法24条1項が……(略)……文言上は異性間の婚姻を定めていることから、」
↓ ↓
「異性間の婚姻のみを定める本件規定が憲法24条に違反するかどうかを判断するに当たっても、」「上記ア及びイの点につき、」「同様の検討が必要と考えられる。」
しかし、そうなると、この文は「憲法24条1項が」「文言上は異性間の婚姻を定めていることから、」「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」と「同様の検討が必要と考えられる。」と述べていることになる。
「憲法24条1項が」「文言上」において「異性間の人的結合関係」を対象とするものとして「婚姻」を定めていることを理由として、「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」と「同様の検討」によって「憲法24条に違反するかどうかを判断する」ことができると述べているということである。
しかし、「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」は、「憲法24条1項」の「婚姻」が「異性間の人的結合関係」を対象としていることを前提として判断されたものであることは確かであるが、この札幌高裁判決はその前提を「憲法24条1項が同性婚をも保障していると解する」として覆そうとしているのであるから、「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」の中で論じられていることとは前提が異なっている。
そのため、これについて「同様の検討」を行うことができると考えていることは誤りである。
また、「憲法24条1項」が「文言上は異性間の婚姻を定めている」ことを理由にして、「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」の中のここで「上記ア及びイ」で示された部分と「同様の検討が必要」となると述べているが、この理由と結論との間に因果関係を見出すことができない。
そのため、この説明そのものが論理的に成り立つものではない。
これにより、読み手は意味の分からないままに「検討」が進められる状態となり、この判決の内容を理解することができなくなるのである。
━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━
「上記ア及びイの点につき、」との部分について検討する。
「上記ア及びイ」を解説した部分で述べたように、この「上記ア及びイ」で示されている「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」は、「婚姻及び家族」が「夫婦」と「親子」による「血縁関係者」によって形成されている枠組みであることを前提としたものである。
また、この「婚姻及び家族」の枠組みに含まれない人的結合関係をここに含めるという権限は国会であっても有していない。
そのため、この「婚姻及び家族」の枠組みに含まれない人的結合関係をここに含めることは国会の立法裁量の範囲にあるものではないため、この国会の立法裁量の範囲を超えるか否かという点において憲法に違反するか否かを司法権として審査することができるとする前提にないものである。
よって、ここで「上記ア及びイの点につき、」のように、「上記ア及びイの点」を検討することによって憲法に違反するか否かについての結論を導き出すことができるかのように論じていることは誤りである。
「憲法24条1項が同性婚をも保障していると解するとしても、」との部分について検討する。
ここでいう「同性婚」の意味が「同性間の人的結合関係」を形成することを指しているのであれば、それは憲法21条1項の「結社の自由」によって保障されるものである。
そのため、「同性間の人的結合関係」を形成することを「憲法24条1項」が「保障している」かのように解していることは誤りとなる。
ここでいう「同性婚」の意味が「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを指しているのであれば、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることができるかという点から検討することが必要である。
「婚姻」とは、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」を目的として、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす「一人の男性」と「一人の女性」の組み合わせを選び出し、その間に「貞操義務」を設けるなど一定の形式で法的に結び付け、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によって立法目的の達成を目指す枠組みである。
「同性間の人的結合関係」については、この趣旨から導かれるものではないため、「婚姻」とすることはできない。
よって、「憲法24条1項」は「同性間の人的結合関係」について定めたものであるとはいえず、「憲法24条1項が同性婚をも保障している」と解していることは誤りとなる。
その他、ここで「憲法24条1項」について「保障している」という表現を用いていることの問題点について検討する。
憲法24条が定めている「婚姻」は、宗教的な意味の婚姻や特定の地域の中でのみ通用していた婚姻とは区別されたものとして、国の法制度としての「婚姻」を指すものである。
そのため、この「婚姻」の意味には、憲法21条1項の「結社の自由」が個々の自然人の自由な結合を保障していることとは意味が異なっており、そこには「国家からの自由」という「自由権」の性質の意味を含むものではない。
そのことから、憲法24条1項が「婚姻」を「保障している」と表現される場合があるとしても、その意味は、憲法24条の「婚姻」の枠組みが法律によって婚姻制度(男女二人一組)を立法することを「要請」していることから、当然、その婚姻制度(男女二人一組)を利用することが可能となるという意味に留まるものである。
よって、このような憲法24条の「婚姻」の枠組みが法律上で婚姻制度(男女二人一組)を立法することを「要請」しているという意味を超えて、国民個人が「国家からの自由」という「自由権」の性質の具体的な権利を憲法24条1項によって保障されているかのように考えることは誤りである。
この判決では、憲法24条の条文の中に、憲法23条で「学問の自由は、これを保障する。」のように明確に「保障する。」と記載されているわけではないにもかかわらず、その24条の条文の趣旨を読み取った者の一人が「憲法24条は、婚姻することについて保障している規定である」と解釈して表現した場合における「保障している」との表現を拾い上げ、「『保障している』のであれば、それは『国家からの自由』という『自由権』の性質なのだろう」という推測により、憲法24条の「婚姻」を「国家からの自由」という「自由権」の性質として読み解こうとしているように思われる。
しかし、そもそも憲法24条の条文の中に「保障する。」という文言は含まれていないのであり、憲法24条の趣旨を読み取った者の中の一人が「保障している」などと表現していることを根拠にして、そこから遡って条文の意味や性質を考えることは誤りである。
そして、ここで「憲法24条1項」について「保障している」と表現している部分についても、この判決が「憲法24条1項」について「人と人との間の自由な結びつき」のように「国家からの自由」という「自由権」の性質に裏付けられているかのように考えている部分と相まって、やはり「憲法24条1項」が法制度としての「婚姻」について定めているものであることを理解しないままに表現しているものということができ、誤りとなる。
「文言上は異性間の婚姻を定めていることから、異性間の婚姻のみを定める本件規定が憲法24条に違反するかどうかを判断するに当たっても、同様の検討が必要と考えられる。」との部分について検討する。
ここでは「異性間の婚姻」の文言が二回登場する。
しかし、この文言はあたかも「異性間」の「婚姻」と、それ以外の「婚姻」が存在するかのような言葉遣いとなっており、正しい説明であるとは言い難い。
まず、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」を目的として、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす「一人の男性」と「一人の女性」の組み合わせが選び出され、その間に「貞操義務」を設けるなど一定の形式で法的に結び付け、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によってそれらの目的の達成を目指す概念を「婚姻」と呼んでいる。
憲法24条1項の「両性」や「夫婦」の文言についても、すべてこの意味に対応するものとして用いられている。
そのため、「婚姻」であることそれ自体において、「男性」と「女性」の組み合わせによるものしか存在しないのであり、この判決が述べるような「異性間の婚姻を定めている」や「異性間の婚姻のみを定める本件規定」どころか、「婚姻」であれば、それはそもそも「異性間」について述べるものということである。
このことから、「異性間の婚姻」という言葉は、「異性間」という「男性」と「女性」を指す言葉と、「婚姻」という「男性」と「女性」の組み合わせを指す概念を同時に用いるものとなっており、文法上は「同義反復」(同語反復/トートロジー)となるため誤用ということになる。
また、「同義反復」となることを無視して、この判決のように「異性間の婚姻」という言葉を使ったとしても、「男性」と「女性」の組み合わせを備えない形で「婚姻」という概念は成立し得ないため、「婚姻」であることそれ自体で既に「男性」と「女性」の組み合わせによる「異性間」を指す意味しか存在しないのであり、「異性間の婚姻」という言葉に対する形で、それ以外の「婚姻」というものが成立するという余地はなく、「同性間の婚姻」というものが存在することにはならない。
よって、その「婚姻」という言葉だけを刈り取ってその概念が形成されている目的から切り離して考えて「婚姻」という空の箱(言葉の意味から切り離された『音の響き』に過ぎないもの)の中に何らかの人的結合関係を詰め込むことができるという性質のものではない。
◇ 本来の意味
「男性」と「女性」の組み合わせ ⇒ 法的に結び付ける形を「婚姻」とする
◇ この判決の言葉の使い方
「婚姻」は空箱 ⇒ どのような人的結合関係でも詰め込むことができる
そのことから、ここで「異性間の婚姻」のように、「婚姻」という概念そのものを、その概念が形成されている目的との間で切り離して、どのような意味としてでも用いることができるような前提を含む形で表現していることは適切ではない。
「異性間の婚姻のみを定める本件規定が憲法24条に違反するかどうかを判断するに当たっても、」「上記ア及びイの点につき、」「同様の検討が必要と考えられる。」との旨を述べていることについて検討する。
「上記ア及びイの点につき、」で述べているのは、憲法24条2項の「婚姻及び家族」の枠組みの「要請」に従って法律上の「婚姻及び家族」の制度が立法されていることを前提として、その法律上の「婚姻及び家族」の制度の内容を構成している細目的な規定に関しては基本的に国会の立法裁量の範囲の事柄であるが、その細目的な規定が「個人の尊厳」と「両性の本質的平等」を満たしていない場合には国会の立法裁量の範囲を超えるとされる場合があるということである。
そして、この「婚姻及び家族」とは、「夫婦」と「親子」による「血縁関係者」によって形成される枠組みである。
このような「婚姻及び家族」という概念に一定の枠組みがあることは、この「上記ア及びイ」が示している「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」の文面の中で「夫婦や親子関係」と述べられていることからも読み取ることができる。
そのため、この「上記ア及びイ」が示している「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」の内容は、あくまで憲法24条2項の「婚姻及び家族」が対象とする人的結合関係の枠組みが存在することを前提として、その枠組みの「要請」に従って立法される法律上の「婚姻及び家族」が対象とする人的結合関係に付随して設けられる細目的な規定について「国会の立法裁量」があることを述べているものである。
そのことから、これは「婚姻及び家族」の枠組みが対象としている人的結合関係の範囲そのものまでも「国会の立法裁量」の範囲に含まれるものとしているわけではない。
このため、この「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」が「国会の立法裁量」の範囲の中にあるものに対して「個人の尊厳」と「両性の本質的平等」を満たすか否かを判断することができる旨を述べている部分を持ち出したとしても、これを根拠として「婚姻及び家族」の対象とする人的結合関係の範囲そのものを変更することができるということにはならない。
当然、「婚姻及び家族」の対象とする人的結合関係の範囲は、「国会の立法裁量」の範囲に含まれているわけではないことから、裁判所によって「国会の立法裁量」が存在する部分について、「個人の尊厳」と「両性の本質的平等」に照らしてその範囲を超えるか否かを審査する対象になるものでもない。
そのため、この「上記ア及びイ」と示している「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」のこの部分の説明を持ち出したとしても、これを根拠として「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることができることにはならないし、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とする法律が存在しないことが憲法に違反するとの結論を導き出すことができるとする根拠にもならないものである。
よって、「異性間の婚姻のみを定める本件規定が憲法24条に違反するかどうかを判断する」ことについて、「上記ア及びイ」と示している「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」と「同様の検討」によって結論を導き出すことができるかのように考えていることは誤りである。
(4) 以上の観点から、本件規定の憲法24条適合性について検討する。
【筆者】
ここでは、これより以前の「(3)」の「ア」と「イ」の部分で「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」を挙げ、それに続く「ウ」で「同様の検討が必要と考えられる。」とし、それを受けて「以上の観点から、本件規定の憲法24条適合性について検討する。」と述べるものとなっている。
また、この文は「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」の中の「第4 上告理由のうち本件規定が憲法24条に違反する旨をいう部分について」の項目の「4」で述べられている「以上の観点から,本件規定の憲法24条適合性について検討する。」という言い回しと同じである。
しかし、この札幌高裁判決で問われている事柄と「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」で問われている事柄は論点が異なっており、この札幌高裁判決で問われている事柄を「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」と「同様の検討」によって結論を導き出すことができるものではなく、同じ言い回しを使って論じることができるとする前提にないものである。
まず、憲法24条の「婚姻」の規定は、「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)の枠組みを定めており、この枠組みによって「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的の達成を目指すことを「要請」しており、この「要請」に従って法律上の具体的な制度として婚姻制度が定められることになるが、憲法24条2項では、その婚姻制度の枠組みに付随して設けられる細目について「個人の尊厳」と「両性の本質的平等」を満たすようを求めるものとなっている。
そして、「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」は、憲法24条が「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)の枠組みを定めており、その「要請」に従って法律上で婚姻制度が一夫一婦制(男女二人一組)で定められていることを前提とし、その婚姻制度(男女二人一組)の枠組みに付随する形で設けられている「夫婦同氏制」に関する規定が「個人の尊厳」と「両性の本質的平等」を満たすか否かについて問われた事案である。
この点で、「国会の立法裁量の範囲を超えるものとみざるを得ないような場合に当たるか否か」が問われたものである。
そして、「国会の立法裁量の範囲を超えるものとみざるを得ないような場合に当たる」といえるためには、その「規定の立法目的に合理的な根拠がなく、又はその手段・方法の具体的内容が立法目的との関連において著しく不合理なものといわざるを得ないような場合であって、立法府に与えられた裁量の範囲を逸脱し又は濫用するものであることが明らかである場合に限られる」(参考となる部分:【東京一次・第3回】被控訴人第2準備書面 令和6年2月29日)と考えられる。
これに対して、この札幌高裁判決で問われている事柄は、憲法24条の「婚姻」の枠組みが、そもそも「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とする法律を立法することを「要請」しているか否かである。
これは「婚姻」という枠組みが対象とする人的結合関係の範囲そのものが問われている問題であり、2項が「婚姻」の枠組みに付随して設けられる細目的な内容について定めた規定が「個人の尊厳」と「両性の本質的平等」を満たすものとなるよう求めている部分によっては変えることのできないものである。
なぜならば、「個人の尊厳」と「両性の本質的平等」の適用対象の範囲を定めている部分が「婚姻」の枠組みであるにもかかわらず、その「個人の尊厳」と「両性の本質的平等」の文言によってその適用対象の範囲を変えることができることになれば、そもそも適用対象が指定されていないこととなり、その「婚姻」を対象として「個人の尊厳」と「両性の本質的平等」を満たすように求めるという条文の構造そのものを覆すことになるし、実質的に「婚姻」という言葉の意味を解体させ、「婚姻」という概念を成り立たない状態とし、「婚姻」という概念そのものを雲散霧消させることを許すこととなり、「婚姻」という名前をもって意味を指定し、条文という形で予め見えるものとして規範を描き出し、将来起こり得る紛争を解決しようとする「法の支配」という営みそのものを否定することになってしまうからである。
よって、札幌高裁判決で問われている事柄と「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」で問われている事柄は論点が異なっており、これらを同一視して論じることができるとする前提になく、これより以前の「(3)」の「ア」と「イ」の部分で「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」を挙げ、それに続く「ウ」で「同様の検討が必要と考えられる。」とし、それを受けて「以上の観点から、本件規定の憲法24条適合性について検討する。」のように「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」と同じ言い回しを使って結論を導き出すことができるかのような論じ方をしていることは誤っている。
その他、この札幌高裁判決で問われているものは、憲法24条の「婚姻」の枠組みが「同性間の人的結合関係」を対象とした制度を立法することを「要請」しているか否かである。
憲法24条の「婚姻」の枠組みが「要請」しているのであればその制度が存在しないことが違憲となり、反対に「要請」していないのであればその制度が存在しないことは合憲となるというものである。
これは、「本件規定」という現在定められている法制度の内容そのものが合憲・違憲の対象となるというものではなく、憲法24条の「婚姻」の枠組みが「要請」する制度が存在するか否かを問うものである。
よって、これを「本件規定」そのものが対象となって「憲法24条適合性」が問われている問題であるかのような前提で論じようとしていることは、憲法24条の「婚姻」の枠組みの「要請」に従う形で法律上の婚姻制度が存在することを前提として、その枠組みに付随して設けられている細目的な規定の内容が「個人の尊厳」と「両性の本質的平等」を満たすか否かが問われるという場合の「憲法24条適合性」の議論と混同するものとなっており、これらを区別できていない点で誤っている。
ア 本件規定は、憲法24条を受け、異性間の婚姻を定める我が国の法制度として採用され、我が国の社会に定着してきたものである。本件規定は、異性間の夫婦としての家族を、社会の自然かつ基礎的な集団単位と捉えているが、このことには合理性が認められてきたということができる。
【筆者】
「本件規定は、憲法24条を受け、異性間の婚姻を定める我が国の法制度として採用され、我が国の社会に定着してきたものである。」との記載がある。
「本件規定は、憲法24条を受け、」との部分について検討する。
「本件規定」は、「憲法24条」の1項が「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めていることを前提に、同2項が「婚姻及び家族」について法律で制定することを定めていることに基づいて制定されているものである。
そのため、憲法が定めている「婚姻」は、法制度として定められる形態のものを指す概念であり、法制度を前提としない何らかの人的結合関係について述べているものではない。
そして、「憲法24条」は「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めていることから、「憲法24条」の「要請」の内容は、この一夫一婦制(男女二人一組)の枠組みを定める趣旨(意図)を満たす法制度を定めることである。
よって、「憲法24条を受け」て法律上の具体的な制度を定める場合には、当然、「男女二人一組」という「異性間の人的結合関係」を対象とした婚姻制度を定めることになる。
この意味で、「本件規定は、憲法24条を受け、異性間の婚姻を定める我が国の法制度として採用され、」との部分は、その通りである。
「異性間の婚姻」との文言があるが、これはあたかも「異性間」の「婚姻」と、それ以外の「婚姻」が存在するかのような言葉遣いとなっており、正しい説明であるとは言い難い。
「婚姻」は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた枠組みである。
具体的には、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」を目的として、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす「一人の男性」と「一人の女性」の組み合わせに対して「貞操義務」を設けるなど一定の形式で法的に結び付け、子供が産まれた場合にその子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によって立法目的の達成を目指すものである。
憲法24条が「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めていることも、この趣旨に対応するものである。
そのため、「婚姻」であることそれ自体において、「異性間」のものしか存在しないのであり、ここでいうように「異性間の婚姻を定める」どころか、そもそも「婚姻」であれば「異性間」について述べるものということになる。
「異性間の婚姻」という言葉は、「異性間」という「男性」と「女性」を指す言葉と、「婚姻」という「男性」と「女性」の組み合わせを指す概念を同時に用いるものとなっており、文法上は「同義反復」となるため誤用となる。
また、「同義反復」となることを無視して、「異性間の婚姻」という言葉を使ったとしても、「男性」と「女性」の組み合わせを備えない形で「婚姻」という概念は成立し得ず、「婚姻」であることそれ自体で既に「男性」と「女性」の組み合わせによる「異性間」を指す意味しか存在しないことから、「異性間の婚姻」という言葉に対する形で、それ以外の「婚姻」というものが成立するということはない。
そのため、「異性間の婚姻」のように、「婚姻」という概念そのものを、その概念が形成されている目的との間で切り離して、どのような意味としてでも用いることができるような前提を含む形で表現していることは適切ではない。
ここでは、その「婚姻」という言葉だけを刈り取って、その概念が形成されている目的から切り離して考えることができるかのような前提の下に、「婚姻」という空の箱(言葉の意味から切り離された『音の響き』に過ぎないもの)の中にどのような人的結合関係を詰め込むことができるかのように論じるものとなっている。
◇ 本来の意味
「男性」と「女性」の組み合わせ ⇒ 法的に結び付ける形を「婚姻」とする
◇ この判決の言葉の使い方
「婚姻」は空箱 ⇒ どのような人的結合関係でも詰め込むことができる
このような理解は、実質的に「婚姻」という言葉の意味そのものを解体して無意味なものとすることを前提とするものであり、言語によって規範を描き出し、秩序を形成するという「法の支配」という営みそのものを否定するものであることから、誤りである。
「本件規定は、異性間の夫婦としての家族を、社会の自然かつ基礎的な集団単位と捉えているが、このことには合理性が認められてきたということができる。」との記載がある。
まず、この札幌高裁判決で問われている論点は、憲法24条の「婚姻」の枠組みが「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とする法律の立法を「要請」しているか否かである。
憲法24条の「婚姻」の枠組みがそれを「要請」しているのであればその制度がないことは違憲となり、それを「要請」していないのであればその制度がないことは合憲となる。
これは、憲法24条の条文の意味を読み解くことによって結論を導き出すことが必要なものであり、「本件規定」という下位の法令に「合理性」が認められるか否かによって結論が導き出されるというものではない。
そして、「婚姻」という概念は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」を目的として、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす「一人の男性」と「一人の女性」の組み合わせを「貞操義務」などの一定の形式で法的に結び付けるものとして形成されており、憲法24条はその「婚姻」について規定しており、その内容も「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めるものである。
そのことから、憲法24条の「婚姻」の枠組みは、法律上の婚姻制度を一夫一婦制(男女二人一組)として定めることを「要請」する内容となっており、それ以外の人的結合関係を「婚姻」とする法律を立法することを「要請」するものではない。
「同性間の人的結合関係」についても、憲法24条が一夫一婦制(男女二人一組)の婚姻制度を立法することによって立法目的の達成を目指すことを「要請」している内容に当てはまるものではないため、憲法24条の「婚姻」の枠組みが「要請」しているものではない。
よって、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とする法律が存在しないことは、憲法24条に違反することはない。
それとは別に、ここでは「本件規定」が「異性間の夫婦」という枠組みを定めていることについての「合理性」を認めるものとなっている。
「異性間」という「男女」の組み合わせを法的に結び付けることの「合理性」を認めているということであるから、そこには子が生まれた場合にその子供の遺伝上父親を特定することができる状態となることを政策として推進することの「合理性」を認めているということになる。
この子供が産まれた場合にその子供の遺伝上父親を特定することができる状態となることを政策として推進することの意図は、父親を特定することによって、その者にも子に対する責任を担わせることによって「子の福祉」の充実を目指すことにある。
また、遺伝上の父親を特定することができるということは、近親者の範囲を把握することが可能となり、その者との間で「婚姻」することができない仕組みとすることにより、近親交配に至ることを未然に防ぐことが可能となる。
他にも、「異性間」の「男女二人一組」を法的に結び付けるという形であれば、その制度を利用していない男女(未婚の男女)の数に不均衡が生じることはないため、その制度を利用していない男女(未婚の男女)の「生殖機会の公平」が保たれ、「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」が生じることを抑制することが可能である。
このような仕組みの「合理性」に着目して「男女二人一組」の間を「貞操義務」などの一定の形式で法的に結び付けるものとして「婚姻」という概念が形成されており、憲法24条はその「婚姻」について規定し、「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めていることから、これもまたその「合理性」に着目して枠組みを定めているものということができる。
よって、この判決も「異性間」という「男女」の組み合わせを法的に結び付けることの「合理性」を認めているのであるから、憲法24条が「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めていることの「合理性」についても認めていることになるのであり、それにもかかわらず、この判決が憲法24条の「婚姻」という枠組みの中に「同性間の人的結合関係」も含まれるかのように述べている部分は、自ら述べている「異性間」という「男女」の組み合わせを法的に結び付けることの「合理性」の背景にある仕組みを損なうものとなっており、妥当ではない。
しかし、性的指向及び同性間の婚姻の自由は、憲法13条によっても、人格権と同様に、重要な法的利益と解される。そして、憲法24条は、憲法13条を受けて定められており、同条1項が同性間の婚姻を文言上は直接的に保障していないとしても、同条2項が定めるとおり、個人の尊厳が家族を単位とする制度的な保障によって社会生活上実現可能であることを踏まえると、同条1項は人の人との間の婚姻の自由を定めたものであって、同性間の婚姻についても、異性間の婚姻と同程度に保障する趣旨であるというべきである。このことは上記のとおりである。
【筆者】
「しかし、性的指向及び同性間の婚姻の自由は、憲法13条によっても、人格権と同様に、重要な法的利益と解される。」との記載がある。
━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━
この文が読み取りづらい原因は、下記の通りである。
◇ 「憲法13条によっても、」とあるが、この「よっても」の言葉に続く形でどのような扱いがなされているのかその結果が説明されておらず、そのまま文が終わっている。
これにより、読み手はこの「よっても」が何に係っているのか未解決のまま放置されることになり、意味を掴むことができなくなるのである。
◇ 「性的指向及び同性間の婚姻の自由は、……(略)……人格権と同様に、」とあるが、「人格権と同様」ということは、「性的指向及び同性間の婚姻の自由」と称するものは「人格権」が別個に存在している中で、それと「同様」と考える位置付けのものということになる。
すると、下記のようにこれまで「人格権の一内容」のように「人格権」と結び付けて論じようとしている部分とは整合しないことを述べていることになる。
「2 本件規定が憲法13条に違反する旨の主張について」
・「(2)イ」の第一段落:「このように性的指向、さらには同性間の婚姻の自由が人格権の一内容を構成し得るとしても、」
・「(3)」の第一段落:「性的指向及び同性間の婚姻の自由は、人格権の一内容を構成し得る重要な法的利益ということができる。」
・「(3)」の第三段落:「性的指向及び同性間の婚姻の自由は、憲法上の権利として保障される人格権の一内容を構成し得る重要な法的利益として、」
「3 本件規定が憲法24条に違反する旨の主張について」
・「(2)ウ」の第三段落:「性的指向及び同性間の婚姻の自由は、現在に至っては、憲法13条によっても、人格権の一内容を構成する可能性があり、十分に尊重されるべき重要な法的利益であると解される」
この点で、読み手は整合性のないことを述べていることに混乱させられるものとなっている。
━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━
「性的指向」とは、「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかに関するものであり、個々人の内心における精神的なものである。
そのため、これは「内心の自由」として憲法19条の「思想良心の自由」によって保障されるものである。
よって、これについて「憲法13条」で保障されると考えたり、「憲法13条」の「人格権」と結び付けて考えるものであるかのように述べていることは誤りである。
「同性間の婚姻」の部分について、これが「同性間の人的結合関係」を指す場合には、「同性間の人的結合関係」を形成する「自由」は、憲法21条1項の「結社の自由」によって保障されるものである。
そのため、これについて「憲法13条」の「人格権」と結び付けて考えるものであるかのように述べていることは妥当でない。
「同性間の婚姻」の部分について、これが「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを指す場合には、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることができるかどうかから検討することが必要である。
「婚姻」は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消する必要性の下に、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」という目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす「一人の男性」と「一人の女性」を選び出し、その間に「貞操義務」を設けるなど一定の形式で法的に結び付け、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によってそれらの立法目的の達成を目指す枠組みである。
「同性間の人的結合関係」については、この趣旨を満たすものではないことから、「婚姻」という概念の中に含めることはできない。
よって、「同性間の婚姻」の部分について、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることができることを前提として論じようとしていることは誤りとなる。
その後に続く「婚姻の自由」との部分だけを見ると、これは「再婚禁止期間大法廷判決(平成27年12月16日)」が示した「婚姻をするについての自由」について述べようとしているものと考えられる。
ただ、「再婚禁止期間大法廷判決(平成27年12月16日)」の内容は、憲法24条1項が「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めていることを前提として、その憲法24条の「要請」に従って定められている法律上の婚姻制度を利用するか否かに関する自由をいうものである。
そのため、そこで述べられた「婚姻をするについての自由」と述べているものについても、このような「男女二人一組」を対象としている婚姻制度を利用するか否かについての「自由」について述べられているものである。
そのことから、この「婚姻をするについての自由」の中には、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを求めることができるという意味は含まれていない。
よって、「同性間の婚姻の自由」のように、これを一続きに述べたとしても、「婚姻」そのものによって「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることができることにはならないし、ここでいう「自由」についても、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として定められている「婚姻」という枠組みを利用するか否かに関する「自由」をいうものであることから、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」の中に含めることを国家に対して求めることができるという意味を有するものではない。
また、その「婚姻をするについての自由」とは、「再婚禁止期間制度訴訟大法廷判決」で述べられているように、憲法24条1項を解釈することにより導かれているものであることから、「憲法13条」から導き出しているものではないし、「人格権」として理解するものでもない。
よって、「婚姻をするについての自由」が「憲法13条」や「人格権」から導かれるかのように論じることは誤りである。
「重要な法的利益と解される。」という部分であるが、「法的」な保障の仕方は下記のようになる。
「性的指向」は、個人の内心における精神的なものであることから、憲法19条の「思想良心の自由」によって保障される。
この憲法19条の「思想良心の自由」は、「国家からの自由」という「自由権」の性質であることから、もし国家から個人の内心に対して具体的な侵害行為があった場合には、それを排除する場面で用いられることになる。
しかし、この憲法19条の「思想良心の自由」を用いて、特定の制度の創設を国家に対して求めることはできない。
「同性間の婚姻」の意味が「同性間の人的結合関係」を形成することを指しているのであれば、 それは、憲法21条1項の「結社の自由」によって保障される。
この憲法21条1項の「結社の自由」についても、「国家からの自由」という「自由権」の性質であることから、もし国家から個人に対して人的結合関係を形成することを禁止するような具体的な侵害行為があった場合には、それを排除することができる場合が考えられる。
しかし、この憲法21条1項の「結社の自由」を用いて、特定の制度の創設を国家に対して求めることはできない。
「同性間の婚姻」の意味が「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを指しているのであれば、上記で説明したように、そもそも「婚姻」の中に含めることのできる人的結合関係の範囲には内在的な限界があり、「同性間の人的結合関係」は「生殖と子の養育」の趣旨を満たすものではないことから、「婚姻」とすることはできない。
そのため、「婚姻」の中にどのような人的結合関係でも含めることができるなどという自由は保障されているものではない。
「再婚禁止期間制度訴訟大法廷判決」が示した「婚姻をするについての自由」については、その判決の中で「配偶者の相続権(民法890条)や夫婦間の子が嫡出子となること(同法772条1項等)などの重要な法律上の効果が与えられるものとされている」ことから「十分尊重に値するものと解することができる。」と述べられている。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
……(略)……また,同条1項は,「婚姻は,両性の合意のみに基いて成立し,夫婦が同等の権利を有することを基本として,相互の協力により,維持されなければならない。」と規定しており,婚姻をするかどうか,いつ誰と婚姻をするかについては,当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたものと解される。婚姻は,これにより,配偶者の相続権(民法890条)や夫婦間の子が嫡出子となること(同法772条1項等)などの重要な法律上の効果が与えられるものとされているほか,近年家族等に関する国民の意識の多様化が指摘されつつも,国民の中にはなお法律婚を尊重する意識が幅広く浸透していると考えられることをも併せ考慮すると,上記のような婚姻をするについての自由は,憲法24条1項の規定の趣旨に照らし,十分尊重に値するものと解することができる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ただ、この「婚姻をするについての自由」は、憲法24条1項が「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めている中において、その「要請」に従って立法されている法律上の婚姻制度を利用するか否かについての自由について、この憲法24条1項を解釈したものとして導かれているものである。
そのため、この憲法24条1項を解釈した結果として導かれているいわば下位法に当たるものを用いて、憲法24条1項が「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めている枠組みそのものを変更することができるとする根拠とはならない。
上位法:憲法24条1項
↓(解釈)
下位法:「婚姻をするについての自由」
このようにいわば下位法として示された解釈を用いてその上位法である憲法24条1項の枠組みを変更することはできない。
よって、この「婚姻をするについての自由」を用いて、憲法24条の定める一夫一婦制(男女二人一組)の枠組みそのものを変更することができるという根拠とすることはできず、この「婚姻をするについての自由」は、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」の中に含めることができるというような自由を保障するものではない。
このように、これらについて「法的」に保障できるとは限らないし、「法的」な保障を検討する場合があるとしても、それはここでいう「憲法13条」や「人格権」として保障されるものではない。
よって、「憲法13条」や「人格権」によって「法的」な保障について検討できるかのように述べていることは誤りとなる。
その他、「人格権」を用いることができる場合とは、下記のような場合である。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4月23日の判決は「本件音声と原告の声色や語調はほぼ一致しており、本人と識別できる」と認定。人物特定ができる前提下で「声の権利」はAI音声にまで及ぶとの判断を示した。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
AI音声の無断使用は違法 中国初、人格権侵害を認定 2024年5月2日 (下線は筆者)
この札幌高裁判決は、上記のような事案ではないことから、「人格権」を用いることのできるものではない。
「そして、憲法24条は、憲法13条を受けて定められており、同条1項が同性間の婚姻を文言上は直接的に保障していないとしても、同条2項が定めるとおり、個人の尊厳が家族を単位とする制度的な保障によって社会生活上実現可能であることを踏まえると、同条1項は人の人との間の婚姻の自由を定めたものであって、同性間の婚姻についても、異性間の婚姻と同程度に保障する趣旨であるというべきである。」との記載がある。
「憲法24条は、憲法13条を受けて定められており、」との部分について検討する。
憲法は「個人の尊厳」の原理に基づいて形成されていることから、当然「憲法24条」もそれを前提として定められているといえる。
しかし、ここでいうように「憲法24条」が「憲法13条を受けて定められて」いるという直接的な関係性を示す手がかりとなるようなものは存在しない。
むしろ、「憲法13条」と「憲法24条」はどちらも憲法上規定であり、相互に矛盾しないものとして定められていることから、「憲法24条」が「婚姻」について定め、その「文言上」で「同性間」の人的結合関係を対象としていないということは、そのことが「憲法13条」に違反しないことを裏付けるものであるといえる。
そのため、その後、この「憲法24条は、憲法13条を受けて定められており、」との論旨を前提として「憲法24条」の規範の意味を書き換えようとするのであるが、そもそも「憲法13条」と「憲法24条」は相互に矛盾しないものであることから、この「憲法13条」を理由として「憲法24条」に定められた規範の意味を書き換えることができるかのように述べていることは誤りである。
◇ この札幌高裁判決の誤った説明
13条の「個人の尊重」
↓
↓
24条の「婚姻」 ←←← 24条の「個人の尊厳」で枠を改変
↓ ↓
↓(保障) ↓(合理性)
↓ ↓
自由な結びつき → ? → 法律上の婚姻制度
(自由権?)
◇ 本来の整合性のある説明 (再婚禁止期間制度や夫婦同姓制度の大法廷判決)
24条の「婚姻」 ← (矛盾なし) → 13条「個人の尊重」
↓ |
↓ |
↓ 24条の「個人の尊厳」の審査
↓ ↓
↓(要請) ↓
↓ ↓
法律上の婚姻制度 ←←←
「同条1項が同性間の婚姻を文言上は直接的に保障していないとしても、」との部分について検討する。
ここでいう「同性間の婚姻」の意味が「同性間の人的結合関係」を指している場合には、それは憲法21条1項の「結社の自由」によって保障されるものである。
そのため、ここでいう「憲法24条」を指す意味での「同条1項」が「文言上は直接的に保障していない」と述べている部分については、「文言上」どころか条文そのものが「保障していない」し、当然、「直接的に」どころか「間接的」にも「保障していない」といえる。
ここでいう「同性間の婚姻」の意味が、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを指している場合には、「同条1項」は「婚姻」について規定し、「両性」「夫婦」「相互」との文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)の枠組みを定めていることから、ここでいう「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることについて定めているものではないという意味でその通りである。
ただ、そもそも「同性間の人的結合関係」は「婚姻」とすることができないという点で、「文言上」とか、「直接的」であるかという論点を回避すれば、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることができるということになるというものではないことに注意が必要である。
「同条2項が定めるとおり、個人の尊厳が家族を単位とする制度的な保障によって社会生活上実現可能であることを踏まえると、」との部分について検討する。
この文は、意味を読み取ることが非常に困難である。
この文面が述べようとしていることを、この文の文節を区切って並び替える形で推測する。
並び替えるとしても、何かが「実現可能である」という結論に行き着くことは読み取ることができるため、これを固定して考える。
① 「個人の尊厳が」「社会生活上」「家族を単位とする制度的な保障によって」「実現可能である」
② 「家族を単位とする制度的な保障によって」「個人の尊厳が」「社会生活上」「実現可能である」
③ 「家族を単位とする制度的な保障によって」「社会生活上」「個人の尊厳が」「実現可能である」
④ 「社会生活上」「家族を単位とする制度的な保障によって」「個人の尊厳が」「実現可能である」
⑤ 「社会生活上」「個人の尊厳が」「家族を単位とする制度的な保障によって」「実現可能である」
これらの例から読み取ると、①か④が比較的読み取りやすいと思われる。
よって、④の「社会生活上」「家族を単位とする制度的な保障によって」「個人の尊厳が」「実現可能である」を基に検討する。
まず、この文は「同条2項が定めるとおり、……④……ことを踏まえると、」と述べるものであることから、「同条2項が」、「社会生活上」「家族を単位とする制度的な保障によって」「個人の尊厳が」「実現可能である」こと「定め」ていることを前提としている。
しかし、憲法24条2項は、「婚姻及び家族」の枠組みの「要請」に従って立法された法律上の「婚姻及び家族」の制度について「個人の尊厳」と「両性の本質的平等」を満たすことを求めるものである。
そのため、憲法24条2項は、「家族を単位とする制度的な保障によって」「個人の尊厳が」「実現可能である」などとは一切述べていない。
よって、「同条2項が定めるとおり、」のように、「同条2項」に、もともとの文でいう「個人の尊厳が家族を単位とする制度的な保障によって社会生活上実現可能である」と「定め」られているかのように述べていることは誤りである。
次に、この➀や④の意味を検討する。
① 「個人の尊厳が」「社会生活上」「家族を単位とする制度的な保障によって」「実現可能である」
④ 「社会生活上」「家族を単位とする制度的な保障によって」「個人の尊厳が」「実現可能である」
この文の意味は、後ほど「(4)工」の第三段落の第三文で「人が生まれながらに由来する自由と権利、これに係る個人の尊厳の実現には、家族とこれに対する社会的な制度の保障が不可欠であるといえる」と述べられている部分と同様の意味と思われる。
しかし、この「個人の尊厳」を「実現」するために「家族を単位とする制度的な保障」が必要であるとする理解は誤りである。
まず、「家族」とは、「(2)ウ」の第三段落で説明したように、「夫婦」と「親子」による「血縁関係者」のことをいう。
そして、ここでは「家族を単位とする制度的な保障」を得ていない場合には、「個人の尊厳」が「実現」されていないという認識を前提として、「家族を単位とする制度的な保障」を得ることによって初めて「個人の尊厳」が「実現」されると考えるものとなっている。
しかし、このような考えは「夫婦」や「親子」による「血縁関係者」がいない者について、「個人の尊厳」が「実現」されていないという認識を前提とし、そこで「家族を単位とする制度的な保障」と称するものによって初めて「個人の尊厳」が「実現」されると述べていることになる。
これは、前提として「家族」のいない者について「個人の尊厳」が「実現」されていないとの考えに基づくものとなっていることから、「家族」のいない者を、物や動物、奴隷などと同様の「人」ではないものとして扱っていることを意味し、極めて不当な認識である。
「家族」のいない者であっても、その者は「人」であり、「個人の尊厳」を有しており、それは「実現」されている状態にあるといえる。
この札幌高裁判決は「家族」のいない者を「人」として扱わず、「個人の尊厳」を有しておらず、それが「実現」されていない対象と見なすものとなっているという点で、誤っている。
また、憲法は「個人の尊厳」の原理に基づいており、自然人は「個人主義」の下に各々「自律的な個人」として生存していくことを予定している。
そのため、何らの人的結合関係も形成していない者の状態で既に完全な状態ということができ、その状態で「個人の尊厳」を有しており、それが「実現」されていない状態にあるとはいえない。
よって、ここで「家族を単位とする制度的な保障」と称するものによって「個人の尊厳」が「実現」されるという理解を前提としていることは、その前提となる認識の部分において誤っているといえる。
これとは別に、ここでは「個人の尊厳」の文言を、ある特定の制度を設けることが政策として望ましいと考える意味で用いようとしていることが考えられる。
しかし、どのような制度を設けることが政策として望ましいかということについては、「個人の尊厳」と述べるだけで、何らかの結論を導き出すことができるというものではない。
もしこのような意味で「個人の尊厳」という言葉を用いようとしているのであれば、同様に、「個人の尊厳」の実現のために一夫多妻制とするべきであるとか、「個人の尊厳」の実現のために婚姻制度を廃止するべきであるなど、様々な政策を「個人の尊厳」と述べるだけで正当化することができてしまうことに繋がる。
すると、下記のようにあらゆる制度や政策について「個人の尊厳」と結び付けて論じることが可能となる。
・ 「個人の尊厳」の実現のため、近親者との婚姻を認めるべきである。
・ 「個人の尊厳」の実現のため、一夫多妻制を認めるべきである。
・ 「個人の尊厳」の実現のため、婚姻適齢を廃止するべきである。
・ 「個人の尊厳」の実現のため、一夫一婦制(男女二人一組)とするべきである。
・ 「個人の尊厳」の実現のため、離婚後は共同親権にするべきである。
・ 「個人の尊厳」の実現のため、離婚後は単独親権にするべきである。
・ 「個人の尊厳」の実現のため、選択的個人名制(夫婦別氏制)とするべきである。
・ 「個人の尊厳」の実現のため、好きな芸能人と同じ氏に変えられるべきである。
・ 「個人の尊厳」の実現のため、氏を廃止するべきである。
・ 「個人の尊厳」の実現のため、名も廃止するべきである。
・ 「個人の尊厳」の実現のため、貞操義務を廃止するべきである。
・ 「個人の尊厳」の実現のため、愛人を解禁するべきである。
・ 「個人の尊厳」の実現のため、婚姻制度は廃止するべきである。
・ 「個人の尊厳」の実現のため、戸籍制度を廃止するべきである。
・ 「個人の尊厳」の実現のため、自動車運転を免許制で規制するのは止めるべきである。
・ 「個人の尊厳」の実現のため、安楽死は認められるべきである。
・ 「個人の尊厳」の実現のため、銃器の所持は認められるべきである。
・ 「個人の尊厳」の実現のため、ドラッグは合法化するべきである。
・ 「個人の尊厳」の実現のため、ヘイト表現は規制するべきでない。
・ 「個人の尊厳」の実現のため、ヘイト表現は規制するべきである。
・ 「個人の尊厳」の実現のため、窃盗を犯罪化するべきではない。
・ 「個人の尊厳」の実現のため、窃盗を犯罪とするべきである。
・ 「個人の尊厳」の実現のため、仇討ちは許されるべきである。
・ 「個人の尊厳」の実現のため、………。
上記で示した中には、それぞれ政策として両立しないものが含まれており、これらの対立する政策を「個人の尊厳」という同一の理由を持ち出すことによって一つの結論に収束するという性質のものではない。
そのため、「個人の尊厳」を理由とする形で、特定の結論を導き出すことができるということにはならない。
そのことから、ここで「個人の尊厳」を持ち出したとしても、それを理由として「同性間の婚姻」と称する特定の制度を立法することについて正当化できるということにはならない。
そもそも、望ましい政策を考えた結果として、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」を目的し、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす「一人の男性」と「一人の女性」を選び出し、その間に「貞操義務」など一定の形式で法的に結び付け、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によってそれらの目的を達成することを目指すこととし、「婚姻」という枠組みを形成しているのである。
そのため、「個人の尊厳」という言葉を望ましい政策と考える旨として用いているのであれば、むしろ望ましい政策という意味で憲法上の立法政策として一夫一婦制(男女二人一組)による「婚姻」という枠組みを定め、他の様々な人的結合関係やその制度を利用していない者との間で一定の差異を設けることにより立法目的の達成を目指す仕組みを採用していることになるのであり、この枠を超える人的結合関係を「婚姻」とすることをその望ましい政策を意味する「個人の尊厳」という言葉によって正当化することができるとする理由にはならないものである。
そのことから、このような望ましい政策がなされた状態とは何かを考えた結果として憲法上の立法政策として一夫一婦制(男女二人一組)の枠組みが定められているという問題を差し置いて、それとは異なる特定の制度を定めることについて、それを望ましい政策を意味する「個人の尊厳」という言葉と結び付けて論じることができるというものではない。
そのため、このような意味で「個人の尊厳」と述べているのであれば、それを基にここでいう「同性間の婚姻」と称する特定の制度を立法することを根拠付けることはできない。
よって、ここで「個人の尊厳」を持ち出して、その後、これを根拠として「同性間の婚姻」と称する制度を立法していないことについて憲法に違反すると結論付けようとしていることは誤りである。
さらに、「個人の尊厳」についてある特定の制度を設けることが政策として望ましいと考える意味で用いようとしているのであれば、そもそもどのような政策が望ましいかという問題については、憲法の枠内で政治部門である立法府の国会で議論される事柄である。
これについては、法令の合憲・違憲、あるいは、合法・違法しか判断することのできない司法府の裁判所の立場で論じてはならないものである。
この点について裁判所の立場から口出しをすることは、その主張そのものが越権行為であり、司法権の逸脱・濫用として違法となる。
よって、この札幌高裁判決を書いた裁判官が特定の政策を実施することが望ましいと考える旨として「個人の尊厳」という言葉を用いているとしても、そこで示された内容や結論は正当化することができず、誤った判断ということになる。
これらのことから、「個人の尊厳が家族を単位とする制度的な保障によって社会生活上実現可能である」と述べている部分は誤りである。
「踏まえると、」とある。
しかし、この「踏まえると、」よりも以前の部分で述べていることは、上記のように誤っている。
そのため、この誤った理解を「踏まえる」ことによって結論を導き出すことはできず、これを「踏まえる」形で、「同条1項は人の人との間の婚姻の自由を定めたものであって、同性間の婚姻についても、異性間の婚姻と同程度に保障する趣旨であるというべきである。」との結論が導き出されるかのように述べていることは誤りである。
その他、そもそも「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることはできないことから、ここでこれを「踏まえる」か否かにかかわらず、その結論として述べられている部分の内容についても誤りである。
「同条1項は人の人との間の婚姻の自由を定めたものであって、同性間の婚姻についても、異性間の婚姻と同程度に保障する趣旨であるというべきである。」
「同条1項は人の人との間の婚姻の自由を定めたものであって、」とある。
まず、「婚姻」とは、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」を目的として、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす「一人の男性」と「一人の女性」を選び出し、その間に「貞操義務」を設けるなど一定の形式で法的に結び付け、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によってそれらの目的の達成を目指す枠組みである。
そして、この「人の人との間の婚姻の自由」との部分の「婚姻の自由」についても、これは「同条1項」が「婚姻」を規定し、「両性」「夫婦」「相互」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)の枠組みを定めていること前提として、その枠組みの「要請」に従って立法された法律上の婚姻制度を利用するか否かの自由をいうものである。
「再婚禁止期間制度訴訟大法廷判決」では、この「同条1項」の趣旨を「婚姻をするについての自由」と表現している。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
……(略)……また,同条1項は,「婚姻は,両性の合意のみに基いて成立し,夫婦が同等の権利を有することを基本として,相互の協力により,維持されなければならない。」と規定しており,婚姻をするかどうか,いつ誰と婚姻をするかについては,当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたものと解される。婚姻は,これにより,配偶者の相続権(民法890条)や夫婦間の子が嫡出子となること(同法772条1項等)などの重要な法律上の効果が与えられるものとされているほか,近年家族等に関する国民の意識の多様化が指摘されつつも,国民の中にはなお法律婚を尊重する意識が幅広く浸透していると考えられることをも併せ考慮すると,上記のような婚姻をするについての自由は,憲法24条1項の規定の趣旨に照らし,十分尊重に値するものと解することができる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
この意味について、国(行政府)は下記のように述べている。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
かえって、同判決が、婚姻制度における男女の区別の合理性が争われ、その区別が憲法14条1項及び「両性の本質的平等」を定めた憲法24条2項に違反すると判断された事案であることからすれば、同判決における判事が、憲法24条2項の「両性」をまさに男女を表すものとして理解していることは明らかであって、「両性の合意」によって成立するとされる同条1項の婚姻についても、男女を当事者とするものであることを当然の前提にしていると見るほかない。同判決における判示が、原告らの主張するような異性間か同性間かを捨象した婚姻の自由を保障することを前提とするものであると解することは到底できない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【東京二次・第5回】被告第3準備書面 令和4年6月20日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(イ)しかしながら,およそ人同士がどうつながりを持って暮らし,生きていくかは,当人らが自由に決めて然るべぎ事柄であり,このような自由自体は異性間であっても同性間であっても,等しく憲法13条において尊重されるべきものと解されるが,前記3で述べたとおり,婚姻が一定の法制度を前提としている以上,「婚姻をするかどうか,いつ誰と婚姻をするか」を当事者間で自由に意思決定し,故なくこれを妨げられないという「婚姻をするについての自由」は,法制度を離れた生来的, 自然権的な自由権として憲法で保障されているものと解することはできない。前記2で述べたとおり,憲法24条1項は,婚姻について異性間の人的結合関係のみを対象とし,同性間の人的結合関係を対象とすることを想定しておらず,同条2項も,飽くまで婚姻が異性間の人的結合関係のみを対象とするものであることを前提としてこれを具体化する制度の整備を立法府に要請するものであり,これを受けて定められた本件規定も,婚姻が異性間の人的結合関係のみを対象とするものであることを前提に定められている。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【札幌・第1回】被控訴人答弁書 令和3年9月30日 PDF (P14~)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
したがって、憲法24条1項は、婚姻について異性間の人的結合関係のみを対象としており、「婚姻をするかどうか、いつ誰と婚姻をするか」を当事者で自由に意思決定し、故なくこれが妨げられないという意味における「婚姻をするについての自由」は、異性間の人的結合関係を対象とする婚姻についてのみ保障されていると解するのが相当である。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【東京二次・第9回】被告第7準備書面 令和5年9月28日 PDF
そのため、「婚姻」という枠組みそのものが有している内在的な条件や「同条1項」が「両性」「夫婦」「相互」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)の枠組みを定めていることを前提とし、その「男女二人一組」を満たす形での婚姻制度を利用するか否かの自由について、ここで「人の人との間の婚姻の自由」と表現しているのであれば、「同条1項」はそれを「定めたもの」と解釈することができる。
ただ、これはあくまで「男女二人一組」を対象としている「婚姻」について述べるものであることから、これを根拠として「同性間の人的結合関係」を「婚姻」の中に含めることができるする理由にはならないことに注意が必要である。
「同性間の婚姻についても、異性間の婚姻と同程度に保障する趣旨であるというべきである。」とある。
ここでいう「同性間の婚姻」の意味が、「同性間の人的結合関係」を形成することを指すのであれば、それは憲法21条1項の「結社の自由」によって保障されるため、「同条1項」のように「憲法24条」と関わるかのように述べていることは誤りである。
ここでいう「異性間の婚姻」の意味についても、これが「異性間の人的結合関係」を形成することを指すのであれば、それは憲法21条1項の「結社の自由」によって保障されるのであり、「同条1項」のように「憲法24条」と関わるかのように述べていることは誤りである。
そして、憲法21条1項の「結社の自由」については、「異性間の人的結合関係」についても、「同性間の人的結合関係」についても、「同程度に保障する趣旨であるというべきである。」といえる。
ここでいう「同性間の婚姻」の意味が、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」することを指しているのであれば、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることができるかどうかという点から検討することが必要である。
「婚姻」は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「生殖と子の養育」の観点から、他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度である。
具体的には、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」を目的として、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす「一人の男性」と「一人の女性」を選び出し、その間に「貞操義務」を設けるなど一定の形式で法的に結び付け、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によってそれらの目的の達成を目指す枠組みである。
「同性間の人的結合関係」については、その間で「生殖」を想定することができず、この「生殖と子の養育」の趣旨を満たすものではないことから、「婚姻」の中に含めることはできない。
そのため、「同性間の婚姻」のように、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることができるかのように述べていることは誤りとなる。
これにより、「同条1項」について「同性間の婚姻についても、異性間の婚姻と同程度に保障する趣旨であるというべきである。」と述べている部分についても、そもそも「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることはできないし、「同条1項」も「同性間の人的結合関係」を対象として定めているものではないことから、誤りである。
その他、この部分の直前の「同条1項は人の人との間の婚姻の自由を定めたものであって、」と述べている部分は、先ほど述べたように「男女二人一組」の条件を満たす形での婚姻制度を利用するか否かの自由について定めている趣旨であるし、これは「同条1項」の条文が存在することを前提として、その条文の意味を解釈した結果として生じたいわば「同条1項」よりも下位の規範として導かれているものである。
そのため、この部分を根拠として「同条1項」が「同性間の婚姻についても、異性間の婚姻と同程度に保障する趣旨であるというべきである。」のように「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることができることを前提とした結論を導き出すことができることにはならない。
そのことから、「同性間の婚姻についても、異性間の婚姻と同程度に保障する趣旨であるというべきである。」との結論を述べているとしても、その結論を裏付けるための根拠として挙げている理由は、その結論との間で論理的な関係性が見られず、その結論を正当化することができるものであるとはいえない。
よって、「同条1項は人の人との間の婚姻の自由を定めたものであって、同性間の婚姻についても、異性間の婚姻と同程度に保障する趣旨であるというべきである。」と述べている部分は、全体としても誤っている。
もう一つ、この文は、直前の「同条2項が定めるとおり、個人の尊厳が家族を単位とする制度的な保障によって社会生活上実現可能であることを踏まえると、」の部分を「踏まえ」た上で結論として述べられているものである。
しかし、上記で述べたように、「家族を単位とする制度的な保障によって」「個人の尊厳が」「実現可能である」との認識は誤った認識であり、この誤った認識を基にして結論を導き出そうとしても、その結論の正当性を支えることはできない。
よって、「同条2項が定めるとおり、個人の尊厳が家族を単位とする制度的な保障によって社会生活上実現可能であることを踏まえると、同条1項は人の人との間の婚姻の自由を定めたものであって、同性間の婚姻についても、異性間の婚姻と同程度に保障する趣旨であるというべきである。」と述べている部分は、その全体としても誤っている。
その他、ここで「同条1項」について「保障する趣旨である」という表現を用いていることの問題点について検討する。
憲法24条の定めている「婚姻」は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「生殖と子の養育」の観点から、他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた枠組みである。
また、憲法24条が定めている「婚姻」は、宗教的な意味として用いられる婚姻や、特定の地域の中でのみ通用していた婚姻を指すものではなく、それらとは区別されたものとして、国の法制度としての「婚姻」を指すものである。
そのため、この「婚姻」の意味は、憲法21条1項の「結社の自由」が個々の自然人に対して「国家からの自由」という「自由権」を保障していることとは性質が異なっている。
そのことから、憲法24条1項が「婚姻」を「保障している」と表現される場合があるとしても、その意味は、「国家からの自由」という「自由権」の性質の意味を含むものではなく、憲法24条の「婚姻」の枠組みが法律によって婚姻制度(男女二人一組)を立法することを「要請」していることから、当然、その婚姻制度(男女二人一組)を利用することが可能となるという意味に留まるものである。
つまり、憲法24条の「婚姻」の枠組みの「要請」に従って立法されている法律上の婚姻制度(男女二人一組)を利用することが可能となるという意味で、「保障する趣旨である」と表現されるということである。
そのことから、このような24条の「婚姻」の枠組みが法律上で婚姻制度(男女二人一組)を立法することを「要請」しているという意味を超えて、国民個人が「国家からの自由」という「自由権」の性質の具体的な権利を憲法24条1項によって保障されているかのように考えることは誤りである。
この判決では、憲法24条の条文の中に、憲法23条で「学問の自由は、これを保障する。」のように明確に「保障する。」と記載されているわけではないにもかかわらず、その憲法24条の条文の趣旨を読み取った者の一人が「憲法24条は、婚姻することについて保障している規定である」と解釈して表現した場合における「保障している」との表現を拾い上げ、「『保障している』のであれば、それは『国家からの自由』という『自由権』の性質なのだろう」という推測により、憲法24条の「婚姻」を「国家からの自由」という「自由権」の性質として読み解こうとしているように思われる。
しかし、そもそも憲法24条の条文の中に「保障する。」という文言は含まれていないのであり、憲法24条の趣旨を読み取った者の中の一人が「保障している」などと表現していることを根拠にして、そこから遡って条文の意味や性質を考えることは誤りである。
そして、ここで「憲法24条1項」について「保障する趣旨である」と表現している部分についても、この判決が「憲法24条1項」について「人と人との間の自由な結びつき」のように「国家からの自由」という「自由権」の性質に裏付けられているかのように考えている部分と相まって、やはり「憲法24条1項」が法制度としての「婚姻」について定めているものであることを理解しないままに表現しているものということができ、誤りとなる。
◇ この札幌高裁判決の誤った説明
13条の「個人の尊重」
↓
↓
24条の「婚姻」 ←←← 24条の「個人の尊厳」で枠を改変
↓ ↓
↓(保障) ↓(合理性)
↓ ↓
自由な結びつき → ? → 法律上の婚姻制度
(自由権?)
◇ 本来の整合性のある説明 (再婚禁止期間制度や夫婦同姓制度の大法廷判決)
24条の「婚姻」 ← (矛盾なし) → 13条「個人の尊重」
↓ |
↓ |
↓ 24条の「個人の尊厳」の審査
↓ ↓
↓(要請) ↓
↓ ↓
法律上の婚姻制度 ←←←
「このことは上記のとおりである。」の部分について検討する。
「このことは」との部分であるが、その「このこと」が指しているこの段落の内容は、この段落で解説してきたように誤っている。
「上記のとおり」との部分であるが、その「上記」が指している部分についも、その部分で解説したように誤っている。
よって、「このことは上記のとおりである。」との内容は、「このこと」についても「上記」についてもいずれも誤っていることから、ここで「このこと」と「上記」が同様の趣旨であることを確認したとしても、その内容を正当化することができるものではない。
ところが、本件規定は、同性間の婚姻を許しておらず、同性愛者は婚姻による社会生活上の制度の保障を受けられない。このことにより、社会生活上の不利益を受け、その程度も著しいということだけでなく、アイデンティティの喪失感を抱いたり、自身の存在の意義を感じることができなくなったり、個人の社会的な信用、評価、名誉感情等を維持することが困難になったりするなど、個人の尊厳を成す人格が損なわれる事態となってしまっている。
【筆者】
「本件規定は、同性間の婚姻を許しておらず、同性愛者は婚姻による社会生活上の制度の保障を受けられない。」との記載がある。
「本件規定は、同性間の婚姻を許しておらず、」との部分について検討する。
ここでいう「同性間の婚姻」の意味が「同性間の人的結合関係」を形成することについて述べているのであれば、それは「国家からの自由」という「自由権」として憲法21条1項の「結社の自由」によって保障されている。
「本件規定」についても、それを制限する内容のものではないことから、「許しておらず、」のようにそれが許されていないかのような認識は誤りである。
ここでいう「同性間の婚姻」の意味が「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることについて述べているのであれば、「本件規定」は「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを定めていないということができる。
ただ、これは法制度が定められているか否かの問題であるから、むやみに「許す・許さない」という意味での「許しておらず、」という表現を用いることは適切ではない。
このような表現は、別の個所の「不利益」などの文言と相まって、法制度の性質について客観的な視点から説明するものとして用いられる言葉遣いではなく、訴訟の当事者の一方の見方や意見、感じ方に与する形で論じるものとなっていることが考えられる。
そのため、敢えてこのような表現を用いて論じていることは、公的な性質を持つ裁判所の立場で用いる言葉の選択として中立性がなく、適切ではない。
「同性愛者は婚姻による社会生活上の制度の保障を受けられない。」とある。
まず、婚姻制度は「性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いをする制度ではないし、「性愛」に基づいて制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもない。
そのため、個々人がどのような思想、信条、信仰、感情を抱いているとしても、婚姻制度(男女二人一組)の要件を満たして制度を利用する意思があるのであれば、誰でも適法に制度を利用することができる。
当然、「同性愛者」を称する者も婚姻制度(男女二人一組)の要件を満たして制度を利用する意思があるのであれば、適法に制度を利用することができる。
それにもかかわらず、ここでは「同性愛者は婚姻による社会生活上の制度の保障を受けられない。」と論じるものとなっている。
これは、個々人の内心を審査して、それが「同性愛者」を称する者であった場合には婚姻制度(男女二人一組)の適用を否定するものであることから、憲法14条1項の「平等原則」における「法適用の平等」に違反する説明である。
○ 「無性愛者」 → 婚姻制度を利用することは可能である。
○ 「近親性愛者」 → 婚姻制度を利用することは可能である。
○ 「多性愛者」 → 婚姻制度を利用することは可能である。
○ 「小児性愛者」 → 婚姻制度を利用することは可能である。
× 「同性愛者」 → 「婚姻による社会生活上の制度の保障を受けられない。」
「同性愛者」を称する者に対するこのような評価は、法的にはまったく整合性がないものであり、不当な主張である。
【参考】「何言っているの、ゲイでもレズでも結婚できる。私もゲイだったが結婚した。」 Twitter
よって、「同性愛者」を称する者も、婚姻制度(男女二人一組)を利用することは可能であり、ここで「同性愛者は婚姻による社会生活上の制度の保障を受けられない。」と述べていることは誤りである。
「このことにより、社会生活上の不利益を受け、その程度も著しいということだけでなく、アイデンティティの喪失感を抱いたり、自身の存在の意義を感じることができなくなったり、個人の社会的な信用、評価、名誉感情等を維持することが困難になったりするなど、個人の尊厳を成す人格が損なわれる事態となってしまっている。」との記載がある。
「このことにより、社会生活上の不利益を受け、その程度も著しいということだけでなく、」との部分について検討する。
まず、「不利益」という文言について検討する。
憲法は「個人の尊厳」の原理に基づいており、自然人は「個人主義」の下に「自律的な個人」として生存していくことを予定している。
そのため、何らの制度も利用していない者の状態で既に完全な状態であり、「婚姻制度を利用していない者(独身者)」の状態が基準(スタンダード)となるものである。
そのことから、「婚姻制度を利用していない者(独身者)」の状態について、何らの「不利益」と称されるものはない。
よって、ここではある特定の形の法制度が定められていないという状態について、「不利益」という言葉で表現していることは、法律論として客観的な視点から説明しているものであるとはいえない。
これは、ある個人が特定の法制度を利用しようと考えた場合に、その個人にとってその法制度が自らの望む形で定められていないことを理由に、望み通りとはならず、その法制度の利用を控えるという視点により、その者個人の受け止め方として「不利益」などと表現しているものを述べているものである。
しかし、法制度は立法目的を達成するための手段として定められるものであり、制度が政策的なものである以上は、その制度が自らの望む形で定められていないという事態が起こり得ることはもともと予定されていることである。
そのことを客観的な視点から捉える場合には、その者個人が「不利益」を受けていることになるわけではない。
そのため、ここで「不利益」という表現を用いている背景には、法制度が自らの望む形で定められている状態を完全な状態と捉えた上で、現在の法制度がその状態に至っていないという認識を基にして、その完全な状態と設定したゴールまでの距離(その間の差の部分)を「不利益」と呼ぼうとする動機が含まれていることになる。
◇ この判決の認識
自らの望む法制度(ゴール)
↑
↑ (この差異を『不利益』と表現している。)
↑
現在地点
しかし、法的な視点から見れば、憲法は「個人の尊厳」の原理に基づいており、自然人は「個人主義」の下に各々「自律的な個人」として生存していくことを予定していることから、法制度を利用していない状態で既に完全な状態ということができ、「不利益」は存在してない。
◇ 法律論として客観的な視点
現在地点 ← (法制度がない状態で既に完全であり、『不利益』は存在しない)
そのため、その者が「不利益」と表現している場合があるとしても、それは自らの望む形で法制度が定められている状態をゴールと考えることを前提とした上での、そのゴールと現在地点との間の距離について述べているものであり、その者個人が抱いている理想の法制度を前提とする主観的な思いを表現しているに過ぎないものである。
しかし、そのことを法的な視点から客観的に考えると、そこには「不利益」と称されるものを認めることはできないものである。
この点、裁判所は法制度の性質について客観的な視点から論じることが必要であり、このような訴訟の当事者の一方が現在の法制度をどのように受け止めているかという主観的な立ち位置から見た場合の言葉遣いをそのまま受け入れて表現していることは適切ではない。
また、その言葉そのものの中には、その訴訟の当事者の一方が抱いている理想の法制度が定められている状態を完全な状態(目標地点・ゴール)として設定することを受け入れるか否かという隠れた論点が含まれている。
それにもかかわらず、その言葉を用いることは、その隠れた論点が表出しないままに、その訴訟の当事者の一方が抱いている理想の法制度が定められている状態を完全な状態(目標地点・ゴール)として設定することを受け入れることを前提として論じていることとなる。
しかし、そのような前提となる状況認識の設定そのものが、自らの主張を通そうとする訴訟の当事者の一方によって意図的に仕組まれたものであり、それを客観的な視点から見抜くことができないままに、その言葉を安易に受け入れてしまうことは、前提となる状況認識の設定について法的な視点からの客観性を保つことができていないこととなるため、結論を導くまでの判断の過程における中立性が損なわれていることとなる。
よって、裁判所の立場でこのような訴訟の当事者の一方が自己の主張を通すために行っている前提となる基準点(スタンダード)を移し替えた上で論じる表現を用いることは適切ではない。
この問題について、国(行政府)の主張では下記のように説明されている。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
そうすると、原告らが本件規定により侵害されていると主張する権利又は利益は、憲法24条2項の要請に基づき、異性間の人的結合関係を対象とする婚姻について具体的な内容として定められた権利又は利益であり、結局のところ、これらが侵害されたとする原告らの主張の本質は、同性間の人的結合関係についても、異性間の人的結合関係を対象とする婚姻と同様の積極的な保護や法的な利益の供与を認める法制度の創設を国家に対して求めるものに他ならない。
従って、本件規定が「婚姻の自由」ないし婚姻に伴う種々の権利及び利益を奪うものとはいえないから、原告らの主張は理由がない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【東京二次・第5回】被告第3準備書面 令和4年6月20日
よって、法律論としては、婚姻制度を利用していない状態について何ら「不利益」と称されるものはないのであり、ここで「社会生活上の不利益を受け、」のように「不利益を受け」ていることを前提として論じていることは誤りである。
「その程度も著しいということだけでなく、」との部分についても、そもそも「不利益」と称されるものはないことから、その「程度」を論じる前提になく、「その程度も著しい」と述べていることも誤りである。
「アイデンティティの喪失感を抱いたり、自身の存在の意義を感じることができなくなったり、個人の社会的な信用、評価、名誉感情等を維持することが困難になったりするなど、個人の尊厳を成す人格が損なわれる事態となってしまっている。」との部分について検討する。
この文は、「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」の下記の部分の言い回しを参考にしていると思われる。
(憲法13条に違反する旨をいう部分)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3 もっとも,上記のように,氏が,名とあいまって,個人を他人から識別し特定する機能を有するほか,人が個人として尊重される基礎であり,その個人の人格を一体として示すものでもあることから,氏を改める者にとって,そのことによりいわゆるアイデンティティの喪失感を抱いたり,従前の氏を使用する中で形成されてきた他人から識別し特定される機能が阻害される不利益や,個人の信用,評価,名誉感情等にも影響が及ぶという不利益が生じたりすることがあることは否定できず,特に,近年,晩婚化が進み,婚姻前の氏を使用する中で社会的な地位や業績が築かれる期間が長くなっていることから,婚姻に伴い氏を改めることにより不利益を被る者が増加してきていることは容易にうかがえるところである。
これらの婚姻前に築いた個人の信用,評価,名誉感情等を婚姻後も維持する利益等は,憲法上の権利として保障される人格権の一内容であるとまではいえないものの,後記のとおり,氏を含めた婚姻及び家族に関する法制度の在り方を検討するに当たって考慮すべき人格的利益であるとはいえるのであり,憲法24条の認める立法裁量の範囲を超えるものであるか否かの検討に当たって考慮すべき事項であると考えられる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(憲法24条に違反する旨をいう部分)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
イ これに対して,夫婦同氏制の下においては,婚姻に伴い,夫婦となろうとする者の一方は必ず氏を改めることになるところ,婚姻によって氏を改める者にとって,そのことによりいわゆるアイデンティティの喪失感を抱いたり,婚姻前の氏を使用する中で形成してきた個人の社会的な信用,評価,名誉感情等を維持することが困難になったりするなどの不利益を受ける場合があることは否定できない。……(略)……
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
損害賠償請求事件 最高裁判所大法廷 平成27年12月16日 (PDF)
このように、この札幌高裁判決の「アイデンティティの喪失感を抱いたり、」や「個人の社会的な信用、評価、名誉感情等を維持することが困難になったりするなど、」との部分は、「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」の文言と重なっている。
そこで、これらの文の中で使われている文言が、「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」の中ではどのような前提の下に用いられているかを確認する。
「アイデンティティ」という言葉の意味は、環境や時間の変化の中でも連続性をもってある特定のものをその他のものとの間で区別することを可能する事柄についていうものである。
そのため、これを「人」と関係させて考えると、他者から見て個人を識別することができる機能を有するものや個人を特定することができる機能を有するものがこれに当たり、法制度としては「氏名」や「マイナンバー」、「生年月日」、「住所」などがその役割を果たしているといえる。
「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」において「アイデンティティの喪失感を抱いたり,」と述べられている部分については、その前に「氏が,名とあいまって,個人を他人から識別し特定する機能を有する」と書かれており、この「個人を他人から識別し特定する機能を有する」ことに対応して「アイデンティティ」という言葉が使われているといえる。
また、この「個人を他人から識別し特定する機能を有する」ことは、個人を他者との間で混同したり、同一視したり、集団全体の中の一部として見たりするのではなく、「個人」として扱うことを可能とするための前提を形成するものとなることから、これに結び付く形で「人が個人として尊重される基礎であり,その個人の人格を一体として示すものでもある」という説明が導かれているといえる。
(そのことから、ここで使われている使われている『個人として尊重』や『個人の人格』との文言を、このような意味を離れて用いることはできないものである。この札幌高裁判決では『個人として尊重』や『人格』を強調する部分が見られるが、『夫婦同姓制度訴訟大法廷判決』ではこの意味で用いられており、これとは事案の異なる札幌高裁判決で同様に論じることができるとする前提にないことに注意が必要である。)
この「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」において「個人の信用,評価,名誉感情等」や「個人の社会的な信用,評価,名誉感情等」と述べられている部分も、この「個人を他人から識別し特定する機能を有する」こととの関係を前提として検討するものとなっている。
これに対して、この札幌高裁判決の中では、一文前で「本件規定は、同性間の婚姻を許しておらず、同性愛者は婚姻による社会生活上の制度の保障を受けられない。」と述べて、この文の冒頭で「このことにより、」とそれを引き継ぎ、これを理由に「アイデンティティの喪失感を抱いたり、」や「個人の社会的な信用、評価、名誉感情等を維持することが困難になったりするなど、」と述べるものとなっている。
しかし、「本件規定」である婚姻制度は、他者から見て個人を識別することができる機能を有するものや個人を特定することができる機能を有するものではないことから、「アイデンティティ」という言葉に対応する事柄であるとはいえない。
そのため、これを「アイデンティティ」という言葉と結び付けて「アイデンティティの喪失感」と述べている部分は、この事案における事柄を描写しているものとはいえず、この事案に対して用いる表現としての妥当性を欠いている。
「個人の社会的な信用、評価、名誉感情等を維持することが困難になったりするなど、」との部分も、「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」の中では「個人を他人から識別し特定する機能を有する」こととの関係において述べられているものであり、この札幌高裁判決で問われている事案とは異なるし、そもそも「同性間の婚姻を許しておらず、」や「婚姻による社会生活上の制度の保障を受けられない。」と述べている部分から「婚姻制度を利用していない者の状態」としての法的な地位に変動は生じておらず、「維持することが困難になったりする」のような変化の存在を前提として論じられている文脈との間でも対応関係にないものであり、この事案における事柄を捉えた内容となっているとはいえない。
よって、この札幌高裁判決が「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」の文言に重ねる形で表現していることは妥当でないし、その内容も今回の事案に当てはまるものではないことから、表現としても妥当なものではない。
「自身の存在の意義を感じることができなくなったり、」とある。
これは、一文前で「本件規定は、同性間の婚姻を許しておらず、同性愛者は婚姻による社会生活上の制度の保障を受けられない。」と述べて、この文の冒頭で「このことにより、」とそれを引き継ぎ、これを理由に「自身の存在の意義を感じることができなくなったり、」と述べるものとなっている。
しかし、「同性間の婚姻を許しておらず、」や「婚姻による社会生活上の制度の保障を受けられない。」と述べている部分の状態とは、単に「婚姻制度を利用していない者(独身者)」の状態を指しているものといえる。
婚姻制度が定められている以上は、一定の枠組みを設けることによって立法目的の達成を目指すことになるのであり、その制度の対象となる場合とならない場合があることは始めから予定されていることである。
そして、婚姻制度を利用していないとしても、何らの不利益と称される状態にはないことから、その状態を理由として「自身の存在の意義を感じることができなくなったり、」と述べたとしても、それは個人の感じ方の一つについて述べるものということになる。
このような法制度が自らの思い通りに定められていないことに対する不満や憤りの感情(憤慨)については、下記が参考になる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
このように、原告らの主張は、結局のところ、自らの思想、信条、政治的見解等と相容れない内容である本件各行為が行われたことにより、精神的な苦痛を感じたというものであるところ、多数決原理を基礎とする代表民主制を採用している我が国においては、多様な意見を有する国民が、表現の自由、政治活動の自由、選挙権等の権利を行使し、それぞれの立場・方法で国や政府による立法や政策決定過程に参画した上で、最終的には、全国民の代表者として選出された議員により組織される国会において個々の法令が制定されるのであるから、その結果として、ある個人の思想、信条、政治的見解等とは相容れない内容の法令が制定されることは、全国民の意見が一致しているというおよそ想定し難い場面以外では、不可避的に発生する事態である。そうすると、自らの思想、信条、政治的見解等とは相容れない行為が行われたことで精神的苦痛を感じたとしても、そのような精神的苦痛は社会的に受忍しなければならないものというほかない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
国家賠償請求事件 高知地方裁判所 令和6年3月29日 (PDF)
国(行政府)の主張の中では、下記のように整理されるものである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
控訴人らが本件規定により侵害されていると主張する権利又は利益の本質は、結局のところ、同性間の人的結合関係についても異性間の人的結合関係を対象とする婚姻と同様の積極的な保護や法的な利益の供与を認める法制度の創設を国家に対して求めるものにほかならず、法制度を離れた生来的、自然権的な権利又は人格的生存に不可欠の利益として憲法で保障されているものではないから、このような内実のものが憲法13条の規定する幸福追求権の一内容を構成すると解することはできない。……(略)……
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【札幌・第4回】被控訴人第2準備書面 令和5年6月8日 PDF
そのことから、このような感覚を抱くことについては、自身の望む法制度が定められていないことに対する不満や憤りの感情(憤慨)と考えるべきものであり、民主主義の下では当然、そのような自らの望む形で法制度が定められていないという事態が生じることは予定されているといえる。
よって、このような事柄を述べたとしても、憲法上の条文を用いて下位の法令の内容を無効としたり、特定の制度を創設するように国家に対して求めることができるとする根拠となるものではなく、これを取り上げて、それを憲法24条に違反すると結論付けるための根拠として論じようとしていることは誤りであるといえる。
「個人の尊厳を成す人格が損なわれる事態となってしまっている。」とある。
ここで「個人の尊厳」との文言を用いていることについて、一段落前の「ア」の第二段落の第二文において、「憲法24条」について「同条2項が定めるとおり、」と示し、その後に「個人の尊厳」を示していることから、その次の段落であるこの段落においても、この憲法24条2項の「個人の尊厳」と関係するものであるかのように論じようとしている可能性が考えられる。
しかし、そもそも憲法24条2項の「個人の尊厳」の文言は、憲法24条2項の「婚姻及び家族」を対象として適用されるものであり、その内容である「夫婦」と「親子」による「血縁関係者」に含まれない場合には適用されるという前提にないものである。
そのことから、「同性間」の人的結合関係については、「夫婦」ではないし、「親子」や「親子」を基本とした「血縁関係者」に当たらないのであれば、この憲法24条2項の「個人の尊厳」を適用できるとする前提にないことから、ここで「個人の尊厳」を持ち出して論じることができるかのように述べていることは誤りとなる。
今述べたように、この札幌高裁判決の事案では憲法24条2項の「個人の尊厳」を用いることができるとする前提にはない。
ただ、憲法は「個人の尊厳」の原理に基づいていることから、下記では憲法24条2項の「個人の尊厳」を適用する場面とは異なる意味における「個人の尊厳」を基に検討する。
「個人の尊厳を成す人格が損なわれる事態」とある。
この「個人の尊厳を成す人格が損なわれる事態」の部分を読み解くと、「個人の尊厳」を「成」している、人の「人格」が「損なわれる」という「事態」について述べているものといえる。
これは、自然人は誰もが「個人の尊厳」を有しているとの前提より、その「個人の尊厳」を適用する主体としての地位を「成す」ものである「人格」が「損なわれ」、「個人の尊厳」を「成す」状態ではなくなることを指していることになる。
このため、この部分の意味は、その自然人が「死亡」した状態について述べていることになる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
権利能力の喪失時期、つまり死亡の時期については、心臓停止説、つまり、心臓が不可逆的に停止した時を基準とする説が通説である。最近では、脳死を基準とすべきであるという説も有力であるが、倫理や遺族感情などの問題とも絡み合い、脳死を基準とするのは困難であることが指摘されている。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第15課 民法―権利義務の主体(自然人その1) (下線・太字は筆者)
人の終期 Wikipedia
しかし、婚姻制度を利用していないとしても、その者が「死亡」した状態にあるというわけではない。
よって、「婚姻制度を利用していない者(独身者)」の状態ついて、「個人の尊厳を成す人格が損なわれる事態」と述べていることは誤りである。
上記とは別に、「を成す人格」の部分を省略し、「個人の尊厳」「が損なわれる事態」という意味として改めて検討してみる。
「個人の尊厳」とは、自然人であれば誰もが持つとされているものである。
そのため、この意味で「個人の尊厳」「が損なわれる事態」とは、自然人として認められていない状態を指すことになり、人が、奴隷のように扱われたり、物や動物と同様の扱いをされたり、そもそも生きた人間として扱われていない場合について述べていることになる。
また、「個人の尊厳」の意味は、「全体主義」との対比における「個人主義」に根差すという文脈で使われているものである。
そのため、この意味で「個人の尊厳」「が損なわれる事態」とは、全体の中の一部として扱われたり、何者かの付属物として扱われたりする場合について述べていることになる。
他にも、「個人の尊厳」の意味は、権利や義務を結び付けることのできる法的な主体としての地位との関係で使われるものである。
そのため、この意味で「個人の尊厳」「が損なわれる事態」とは、「権利能力」を喪失したり、「意思能力」を否定されたり、「行為能力」を制限される場合について述べていることになる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
民法は我々の生活関係を権利と義務に分解して規定し、規律するが、この権利及び義務の帰属主体となりうる資格を権利能力という。民法は、権利能力はあらゆる自然人が平等に有するとしているが、このことは近代法によって確立された原則であり、近代法が発達する以前の時代、すなわち奴隷制が存在した時代や、封建時代には、人によっては権利能力を認められない自然人も存在したのである。人は権利能力があって初めて法律的に自由な経済活動が可能となるのであり、その権利能力を自然人に平等に認めるのは、憲法の要請でもある。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第15課 民法―権利義務の主体(自然人その1) (下線・太字は筆者)
しかし、「婚姻制度を利用していない者(独身者)」の状態であるとしても、それはその者が奴隷として扱われたり、物や動物として扱われたり、生きた人間として扱われていないというわけではない。
また、「婚姻制度を利用していない者(独身者)」の状態であるとしても、それはその者が独裁者のための存在や、国などの全体のための存在として扱われているわけではない。
他にも、「婚姻制度を利用していない者(独身者)」の状態であるとしても、そのことが理由となって「権利能力」を喪失したり、「意思能力」が否定されたり、「行為能力」が制限されたりしているわけではない。
そのため、婚姻制度を利用していない状態について、「個人の尊厳」「損なわれる事態」であるとはいえない。
よって、この文が「個人の尊厳」「損なわれる事態となってしまっている。」という意味を述べようとしているものであるとしても、その内容は誤りである。
イ 他方、同性間の婚姻について社会的な法制度を定めた場合の不利益・弊害を検討すると、社会的な影響を含め、社会上の不利益・弊害が生じることがうかがえない。
【筆者】
━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━
この文の意味が読み取りづらい理由は、下記のとおりである。
◇ 前の文を受けて、「他方、」と繋ぐのであるが、文脈から考えて接続の仕方が適切とは言い難い。
◇ 「社会」の文字が三回登場する。ここまで繰り返す必要はないはずである。
これにより文字数が増えている割には中身が重なっていることから、明確なイメージを掴むことができず、読み手を躓かせるものとなっている。
━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━
憲法24条の論点で問われるのは、憲法24条の「婚姻」の枠組みが「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とする法律を立法することを「要請」しているか否かである。
そして、憲法24条の「婚姻」の枠組みがそれを「要請」しているのであればその制度がないことは違憲となり、「要請」していないのであればその制度がないことは合憲となる。
これは、憲法24条1項の「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」の文言や、2項の「配偶者」「離婚」「婚姻及び家族」の文言など、憲法上の条文に記された文言そのものを手掛かりとして、「要請」の有無を判断することが必要である。
しかし、ここで「社会的な法制度を定めた場合の不利益・弊害を検討する」と述べていることから、これは「社会的な法制度」という憲法よりも下位の法令を持ち出してその「不利益・弊害」を検討し、その検討の結果に基づいて遡ってその上位の法令にあたる憲法24条の規範の意味を明らかにしようとするものとなっている。
これは、法秩序は階層構造を有しており、下位法を根拠として上位法の意味を明らかにすることはできないことを理解しないものであり、誤りである。(下剋上解釈論)
「同性間の婚姻について社会的な法制度を定めた場合の不利益・弊害を検討すると、」との部分について検討する。
ここでいう「同性間の婚姻」の意味について、「同性間の人的結合関係」を指す場合と、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを指す場合とに分けて検討する。
まず、ここでいう「同性間の婚姻」の意味が「同性間の人的結合関係」を指す場合、これについて婚姻制度とは別に「社会的な法制度を定めた場合」について検討する。
■ 婚姻制度の概要
「婚姻」は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために設けられた枠組みである。
これは、下記のような経緯によるものである。
その国の中で「生殖と子の養育」に関する事柄について何らの制度も存在しない場合には、社会的な不都合が発生することがある。
例えば、「父親不明」の子供が増える、父親を特定できない子供が増える、父親が蒸発して行方不明になった子供が増える、それらにより「子の福祉」が減少する、父親を特定できないことにより近親者の範囲を把握できずに「近親交配」に至り潜性遺伝子の発現した個体が高い確率で生じるようになる、一部の強者が多数人との生殖関係を独占することによって社会の中で「子を持ちたいと希望して相手を見つけようとする男女」の数の不均衡が生じて「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」が生まれる、低年齢での妊娠・出産により母体に危険が及ぶ、などの問題が生じることがある。
これらの不都合を解消するために、下記のような立法目的を有する枠組みを設けることが必要となる。
・「子の福祉」が実現される社会基盤を構築すること
・潜性遺伝子の発現した個体が高い確率で生じることを抑制すること
・「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」を減らすこと
・母体を保護すること
そして、これらの目的を達成するためには、目的との関係で整合的な下記の要素を満たす枠組みを設けることが必要となる。
・子の遺伝的な父親を特定できる組み合わせとすること
・特定された子の父親にも子に対する責任を担わせること
・特定された子の父親を基に遺伝的な近親者を把握すること
・未婚の男女の数の不均衡を防止できる組み合わせに限定すること
これらの要素を満たすものとして「一人の男性」と「一人の女性」が選び出され、その間に「貞操義務」を設け、その関係を法的に結び付ける形を「婚姻」と呼んでいる。
そして、この「婚姻」に対して法的効果や一定の優遇措置を設けることによって、制度を利用する者を増やし、これらの立法目的の実現を目指す仕組みとなっている。
憲法24条でも「婚姻」について「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて、一夫一婦制(男女二人一組)を定めている。
憲法24条が一夫一婦制(男女二人一組)を定めている理由は、「婚姻」が有している目的を達成するための手段として整合的な上記の要素を満たすからである。
そして、憲法24条の「婚姻」の枠組みの「要請」に従って、法律上で具体的な婚姻制度が定められることになる。
■ 婚姻制度の「趣旨・目的・内容・効果」
婚姻制度は、「男性」と「女性」の間に「貞操義務」を設けることによって、その「女性」から生まれてくる子供の遺伝的な父親を特定することを重視するものとなってる。
これは、産まれてくる子供に対して、母親だけでなく、父親にも責任を担わせることによって、「子の福祉」の充実を期待するものとなっているからである。
子は何らの因果関係もなく突然「女性」の腹から生まれてくるわけではないため、その子が生じるという因果関係の一旦を担う父親に対してその子に対する責任を担わせる仕組みとすることは、逃れることのできない責任を有する者として合理的ということができるからである。
また、遺伝上の父親を特定できることは、遺伝上の近親者を把握することが可能となるため、その近親者との間で「婚姻」することができない仕組みを導入することで、「近親交配」に至ることを防止することが可能となる。
これによって、産まれてくる子供に潜性遺伝子が発現することを抑えることが可能となり、産まれてくる子に遺伝上の障害が生じるリスクを減らすこともできるからである。
他にも、婚姻制度の枠組みが「男女二人一組」となっていることは、その社会の中に男女がほぼ同数生まれているという前提の下では、未婚の男女の数に不均衡が生じることはないため、より多くの者に「子を持つ機会」を確保することを可能とするものとなっている。
その他、婚姻制度のもつ子供の遺伝上の父親を特定することができる形での「生殖」を推進する仕組みからは、婚姻制度を利用する形で子供を妊娠し、出産することを期待する(インセンティブを与える)ものとなっているが、その妊娠、出産に関して母体の保護の観点からリスクのある状態を推奨することはできないし、親となる者が低年齢のままに子を持つという責任を担う立場に置かれることを推進することも望ましくないことから、婚姻制度の利用に対して「婚姻適齢」という形で一定の年齢制限を設けるものとなっている。
これらの意図を満たす形で「男女二人一組」という枠組みを設定し、その婚姻制度の枠組みに従う者に対して、一定の優遇措置を講じることによって、婚姻制度の利用者を増やし、その立法目的を達成することを目指すものとなっている。
このことから、婚姻制度の立法目的とその立法目的を達成するための手段は下記のように整理することができる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
① 「子の福祉」が実現される社会基盤を構築すること
(→ 嫡出子として父親を特定することができる状態で生まれることを重視)
② 潜性遺伝子の発現した個体が高い確率で生じることを抑制すること
(→ 貞操義務と嫡出推定〔、再婚禁止期間〕によって遺伝的な父親を極力特定し、それを基に遺伝的な近親者を把握し、近親婚を認めないことによって『近親交配』に至ることを防止)
③ 「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」を減らすこと
(→ 未婚の男女の数の不均衡を防止できる組み合わせに限定。一夫一婦制。重婚や重婚状態、複婚や複婚状態の防止。)
④ 母体を保護すること
(→ 婚姻適齢を設定)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
このような婚姻制度の「趣旨・目的・内容・効果」を前提として、婚姻制度とは別に「同性間の人的結合関係」を対象とした制度を設けた場合に、ここでいう「社会的な影響を含め、社会上の不利益・弊害が生じることがうかがえない。」といえるかどうかを検討する。
■ 婚姻制度との間で生じる齟齬
▼ 婚姻制度の政策効果を阻害すること
▽ 子の福祉
婚姻制度は、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によって立法目的の達成を目指すものである。
つまり、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定し、母親だけでなくその者にも子に対する養育の責任を担わせることにより、「子の福祉」の実現を目指す仕組みとなっている。
また、子供にとって遺伝上の父親を特定することができることによる利益を得られるように配慮するものとなっている。
そのため、「生殖」によって子供をつくろうとする者が婚姻制度を利用することによって遺伝上の父親を特定することができる人的結合関係を形成するようにインセンティブ(動機付け)を与えるものとなっている。
しかし、「同性間の人的結合関係」を対象とした制度を設けた場合は、その制度によって婚姻制度を利用した場合と同様、あるいは類似した優遇措置を得られることが原因となって、婚姻制度を利用することに対してインセンティブが働かなくなる。
また、「女性同士の組み合わせ」を形成して子供を産むことに対してインセンティブが働くことになり、遺伝上の父親を特定することができない状態で子供を産むことを推進する作用が生じることとなる。
これは、子供にとって遺伝上の父親を特定することができない状態となることから、「子の福祉」の充実に沿わないことが考えられる。
そのため、「同性間の人的結合関係」を対象とした制度を設け、婚姻制度と同様、あるいは類似した優遇措置を得られるようにすることは、婚姻制度の政策的な効果を弱める影響を与えることとなり、婚姻制度の立法目的の実現が阻害され、婚姻制度との間で矛盾するものとなる。
▽ 近親交配の回避
婚姻制度は、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によって立法目的の達成を目指すものである。
その中に、遺伝上の父親を特定することによって近親者の範囲を把握し、その近親者との間では「婚姻」することができないことにすることで、「近親交配」に至ることを防ぎ、潜性遺伝子の発現した個体が高い確率で生じることを防ぐ仕組みがある。
しかし、「同性間の人的結合関係」を対象とした制度を設け、法的効果や一定の優遇措置を与えた場合には、「女性同士の組み合わせ」を形成することに対してインセンティブが働くことになり、遺伝上の父親を特定することができない関係の中で子供を産むことを促進する作用が生じ、近親者の範囲を把握することができない状態を推進することになる。
そうなると、婚姻制度を設けることによって「近親交配」に至ることを回避することができる社会環境を整備しているにもかかわらず、その仕組みに沿わない制度が別に存在することによって、婚姻制度を設けることによって「近親交配」に至ることを防ぐという一貫性のある政策を行うという前提が成り立たなくなる。
つまり、婚姻制度が近親者の範囲を把握することを前提とした上でその近親者との間では「婚姻」することができないことにすることで「近親交配」に至ることを未然に防ぐ仕組みとしているにもかかわらず、その仕組みが十分に機能しなくなり、その社会の中で「近親交配」に至ることを十分に防止することができなくなるということである。
すると、婚姻制度が潜性遺伝子の発現した個体が高い確率で生じることを防ごうとする意図を達成することができなくなり、子供の世代において意図せずに「近親交配」に至る確率が高くなる。
そして、実際に「近親交配」に至ってしまった場合には、子供は潜性遺伝子が発現するリスクが高くなり、遺伝上の障害を抱えやすくなる。
これは、婚姻制度を設けていること自体の価値を損なわせ、人々が婚姻制度に対して抱いている信頼感を失わせることに繋がる。
そのため、「同性間の人的結合関係」(特に女性同士の組み合わせ〔女性三人以上の組み合わせであっても同様〕)を対象とした制度を設け、婚姻制度と同様、あるいは類似した優遇措置を得られるようにすることは、婚姻制度の政策的な効果を弱める影響を与えることとなり、婚姻制度の立法目的の達成が阻害され、婚姻制度との間で矛盾するものとなる。
▽ 生殖機会の公平
婚姻制度は、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によって立法目的の達成を目指すものである。
その中に、一夫一婦制(男女二人一組)とすることにより、未婚の男女の数の不均衡が生じることを防止し、未婚の男女にとっての「生殖機会の公平」が保たれるように配慮し、その社会の中で「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」が生じることを抑制しようとする仕組みがある。
しかし、「同性間の人的結合関係」を対象とした制度を設けた場合には、その制度を利用することによって婚姻制度と同様、あるいは類似の法的効果や優遇措置を得られることを理由として、「同性間の人的結合関係」を形成する者が増えることが考えられる。
すると、その社会の中で未婚の男女の数(制度を利用しない男女の数)に不均衡が生じることに繋がることから、その社会環境が未婚の男女(制度を利用しない男女)にとって「子を持つ機会」の公平性が保たれなくなり、「子を持ちたくても相手が見つからずに子を持つ機会に恵まれない者」が増えることに繋がる。
そのような社会の中で生活することを強いることになることは、「公共の福祉」の観点からも障害となると考えられる。
そのため、「同性間の人的結合関係」を対象とした制度を設け、婚姻制度と同様、あるいは類似した優遇措置を得られるようにすることは、婚姻制度が「男女二人一組」の形に限定することによって「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」を減らそうとする立法目的の達成を阻害するものとなるから、婚姻制度との間で矛盾するものとなる。
▽ インセンティブの減少
婚姻制度は、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によって立法目的の達成を目指すものである。
このことから、婚姻制度を利用しない人的結合関係に対しては意図的に優遇措置を設けないことにより、「生殖」によって子供をつくろうとする者が婚姻制度を利用することによって遺伝的な父親を特定することができる人的結合関係を形成するようにインセンティブを与えるものとなっている。
つまり、婚姻制度を利用する者に対して法的効果や一定の優遇措置を与え、婚姻制度を利用していない者にはそれを与えないという差異を設けることによって、婚姻制度を利用することに対してインセンティブを働かせ、婚姻制度を利用する者を増やし、その立法目的を達成することを目指すものである。
そのことから、婚姻制度を利用しない人的結合関係に対しては意図的に法的効果や優遇措置を与えないということを予定しているものである。
しかし、「同性間の人的結合関係」を対象とした制度を設けた場合には、国民がその制度を利用することにより、婚姻制度を利用した場合と同様、あるいは類似した優遇措置を得られることを理由に、婚姻制度を利用するのではなくその制度を利用することを選択する者が増加していくこととなる。
すると、婚姻制度が遺伝的な父親を特定することができる状態を推進することによって達成しようとした立法目的の達成を阻害する影響を与えることになる。
そのため、「同性間の人的結合関係」を対象とした制度を設け、婚姻制度と同様、あるいは類似した優遇措置を得られるようにすることは、婚姻制度の政策的な効果を弱める影響を与えるものとなることから、婚姻制度との間で矛盾するものとなる。
▽ 母体の保護
上記のような問題により、婚姻制度が「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するための制度として十分に機能しないものとなると、その社会の中で人々が抱いている婚姻制度に対する信頼性が損なわれることになる。
すると、その社会の中で子を産むことを希望する者が次第に婚姻制度を利用しなくなっていき、婚姻制度が存在している意義そのものが希薄化していくことになる。
そうなると、婚姻制度を利用して子を持つという形を求める者が減少し、反対に、婚姻制度を利用しない形で「生殖」をしたり、子を持つ者が増加していくことになる。
すると、それまでは婚姻制度を利用する形で子供を妊娠し、出産することに対してインセンティブを与えていたことから、婚姻制度を利用して子を持つという形を求める者が多く、婚姻適齢に満たない者が「生殖」の営みに誘引される機会がそれなりに少ない社会状況を維持することができていたが、婚姻制度の価値や信頼性が損なわれている結果、婚姻制度を利用することについて十分なインセンティブが働かない状態となっていることから、婚姻制度を利用しない中で「生殖」を営み、子を持つ者が増加していくこととなり、その影響で婚姻適齢に満たない者が「生殖」の営みに誘引される機会も増加していくことに繋がる。
その結果、婚姻適齢に満たない若年の女性が「生殖」(性的な接触や性行為)に続いて、妊娠、出産のリスクを背負うことが増加し、「母体の保護」の観点から見れば望ましくない状態で妊娠、出産に至ることが抑制されなくなる。
また、低年齢のままに親として子を持つという責任を担う立場に置かれることも増加し、婚姻制度の政策的な効果が十分に機能していないことから父親が特定されていなかったり、知識レベルや経済力が十分でないままに子を育てるという過酷な状況に陥ることが抑制されなくなる。
このことは、「母体の保護」の観点や、倫理的な観点、望ましい社会の在り方を考える上で問題となる。
このように、「同性間の人的結合関係」に対して制度を設けることは、婚姻制度の政策効果を阻害することに繋がり、その結果、それまで人々が婚姻制度を利用することに対して魅力を感じていたことにより抑制されていた問題が表出することになる。
▼ 24条の「婚姻」を離れて「生殖と子の養育」に関わる制度を立法することはできないこと
憲法24条の「婚姻」の文言は、「生殖と子の養育」に関わる制度を一元的に集約して規律する趣旨を有していることから、もし「生殖と子の養育」に関わる制度を憲法24条の「婚姻」を離れて別の制度として立法した場合には、憲法24条の「婚姻」の文言に抵触して違憲となる。
なぜならば、憲法24条が「婚姻」の内容に対して立法裁量の限界を画することによって、法律上の「婚姻」の制度を規律しているにもかかわらず、その憲法24条の制約を回避する形で制度を立法することができることになれば、憲法24条の規定そのものが有する効力が損なわれた状態となり、憲法24条の規定が骨抜きとなるからである。
よって、「婚姻」が「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として、「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた枠組みである以上は、その「生殖と子の養育」に関わる制度については、憲法24条の「婚姻」の文言が一元的に集約して規律する趣旨を有しており、これを離れて「生殖と子の養育」に関わる制度を立法することはできない。
そのため、ここでいう「同性間の人的結合関係」について制度を設けた場合に、その内容が「生殖と子の養育」に関わる制度となっている場合や、「生殖と子の養育」に影響を与えることが考えられる制度となっている場合には、そのこと自体で憲法24条の「婚姻」に抵触して違憲となる。
▼ 制度を利用していない者との間の差異を正当化できないこと
一般的・抽象的にその間で自然生殖を想定することができる「一人の男性」と「一人の女性」の組み合わせに対して「貞操義務」など一定の形式で法的に結び付けることは、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的の実現に資することから、必然性を見出すことができる。
つまり、「男女二人一組」については、その間で自然生殖が行われた場合に、遺伝的な父親を特定することができる関係となることから、その特定された父親に対しても子に対する責任を担わせることができる。
また、父親を特定することによって「近親交配」に至ることを回避することも可能となる。
他にも、「男女二人一組」の制度であれば、未婚の男女の数の不均衡を防止することが可能となるため、その社会全体の中で「生殖機会の公平」を実現することに寄与するものとなる。
「婚姻適齢」を満たした者の間での「生殖と子の養育」に関する制度であれば、「母体の保護」の観点や、「子育ての能力」の観点からも一般には支障がないものと考えられる。
これらは、結果として「子の福祉」を目指す仕組みとして合理的であるということができる。
そのため、「男女二人一組」の関係性に対して制度を設けてその制度を利用する者に対して一定の優遇措置を与えるとしても、それはその制度を利用していない者との間で生じる差異を正当化することが可能である。
しかし、「同性間の人的結合関係」については、その間で「生殖」を想定することができないことから、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する形で制度を設けるという目的からは導かれないものである。
そのため、「同性間の人的結合関係」に対して制度を設けることは、その制度を利用していない者との間で合理的な理由を説明することのできない差異を生じさせるものとなり、「平等原則」に反することになる。
▼ 他の人的結合関係との間の差異を正当化できないこと
「同性間の人的結合関係」を対象とする制度は「二人一組」を対象とすることが想定されている。
しかし、「同性間の人的結合関係」については、婚姻制度のように「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的との関係により一般的・抽象的にその間で「生殖」を想定することができる「男性」と「女性」の揃う「二人一組」を対象として枠組みを定めるという意図からは導き出されないものである。
そのため、その内容を「二人一組」とする必然性もないのであり、理由なく「二人一組」としていることは、「カップル信仰論」に基づくものとなっている。
人的結合関係には、「三人一組」や「四人一組」、「それ以上の人的結合関係」も存在するのであり、「二人一組」だけを特別視して制度を設けること自体についても、合理的な理由を説明することができないものとなっており、妥当でない。
■ 結論
このように、もし「同性間の人的結合関係」を対象とした制度を設けた場合には、婚姻制度の立法目的の実現を阻害し、婚姻制度の政策効果を弱めることに繋がる。
また、「同性間の人的結合関係」を対象とした制度を立法した場合には、憲法24条の「婚姻」の文言が「生殖と子の養育」に関わる制度を一元的に集約して規律している趣旨や、憲法14条1項の「平等原則」の関係で違憲となることが考えられ、そのような制度を立法することはできない。
そのため、上記のような問題点を何ら検討することもなく「社会的な影響を含め、社会上の不利益・弊害が生じることがうかがえない。」のように、「社会的な影響」や「社会上の不利益・弊害」が生じないかのような説明をしていることは、婚姻制度の有している機能や果たしている役割、婚姻制度の立法目的とその立法目的を達成するための手段となっている枠組みとの整合性を理解していないものであり、誤りである。
次に、ここでいう「同性間の婚姻」の意味が「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを指す場合について検討する。
まず、「婚姻」とは、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた枠組みである。
具体的には、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」を目的として、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす「一人の男性」と「一人の女性」を選び出し、その間に「貞操義務」を設けるなど一定の形式で法的に結び付け、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によってそれらの目的の達成を目指すものである。
また、憲法24条は「婚姻」を規定し、具体的に「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)の枠組みを定めており、上記の趣旨に対応するものとなっている。
「同性間の人的結合関係」については、その間で「生殖」を想定することができず、上記の「生殖と子の養育」の趣旨を満たすものではないし、憲法24条が一夫一婦制(男女二人一組)の枠組みを定めている趣旨にも沿わないことから、「婚姻」の中に含めることはできない。
そのため、ここで「同性間の婚姻」のように、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることができるかのように述べていることは誤りである。
むしろ、同性愛者は割合的には社会的に少数である(認定事実(1)イ)。同性婚を認めることが、社会の状況に大きな変化をもたらすものであって、その影響を考慮する必要があるとの的確な根拠があるとはうかがえない。もっとも、同性愛者は、割合的には少数であっても、人数的には相応の対象者が想定される。したがって、同性婚を認めることは、現存の制度の例外を定め、少数の割合であるが、相応の人数に達する同性愛者に対する権利を保障し、個人として尊重することに意義を有するものと考えられる。
【筆者】
━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━
この段落の文書が読み都づらい理由は、下記の通りである。
◇ 第一文の「むしろ、」の言葉の使い方が適切ではないこと
第一文では、「むしろ、」と述べていることから、前の段落を受けるものとなっている。
この「むしろ」の文法上の意味は、「二つのうち、あれよりもこれを選ぶという気持ちを表す」や「これのほうがよりよいという気持ちを表す」ものである。
しかし、前の段落で示した内容よりもこの文の「同性愛者は割合的には社会的に少数である」ということを強調しようとしていることになるが、前の段落で述べているのは「同性間の婚姻について社会的な法制度を定めた場合」に「社会的な影響を含め、社会上の不利益・弊害が生じることがうかがえない。」というものであり、このことと、この文が示す「少数である」との結論との間に、「むしろ」という言葉で繋ぐことができるとする関係性を認めることができない。
よって、このような意味の通らない形で文を繋いでいることは適切ではない。
◇ 第二文は一段落前の文の繰り返しであること
一段落前と、この段落の第二文は、内容が重なっている。
・一段落前
「同性間の婚姻について社会的な法制度を定めた場合」に「社会的な影響を含め、社会上の不利益・弊害が生じることがうかがえない。」
・この段落の第二文
「同性婚を認めることが、社会の状況に大きな変化をもたらすものであって、その影響を考慮する必要があるとの的確な根拠があるとはうかがえない。」
しかし、この両者の間には、この段落の第一文の「むしろ、同性愛者は割合的には社会的に少数である(…)。」という文があるため、連続していない。
これにより、同様の趣旨の文が不規則に登場するため、読み手はどのような意図で説明したいのか理解することが困難となり、読み取りづらく感じるのである。
◇ 「同性愛者」の性質について説明する文が三回登場すること
この段落では、「同性愛者」の性質についての説明が三回登場する。
・「同性愛者は割合的には社会的に少数である」
・「同性愛者は、割合的には少数であっても、人数的には相応の対象者が想定される。」
・「少数の割合であるが、相応の人数に達する同性愛者」
しかし、どれも同じようなことを述べており、これらをわざわざ散りばめる形で記載していることに意味を見出すことができない。
◇ 第四文の「したがって、」の文で述べる結論に対応する根拠が適切でないこと
第四文の始めに「したがって、」と書かれており、それまでに述べた部分を受ける形で結論を述べるものとなる。
ただ、第四文の「少数の割合であるが、相応の人数に達する」の部分は、「同性愛者」の性質について述べているだけであるから、「同性愛者」の意味を補足するものであり、直接的に結論を示す文脈の意味に対応するものではない。
そのため、この第四文の結論は、下記を述べるものである。
・「したがって、同性婚を認めることは、現存の制度の例外を定め、」「同性愛者に対する権利を保障し、個人として尊重することに意義を有するものと考えられる。」
この文を見ると、「現存の制度の例外を定め、」の部分が何を意味しているのか分からないため、「同性婚を認めることは、」の部分と語順を入れ替えて分かりやすくすると下記のようになる。
・「したがって、」「現存の制度の例外を定め、」「同性婚を認めることは、」「同性愛者に対する権利を保障し、個人として尊重することに意義を有するものと考えられる。」
これが、この段落の結論として述べようとしているものとなる。
しかし、これを遡って、この結論を導くための理由となっているものを検討しても、この結論を導き出すに至る理由となるものを見つけることができない。
まず、先ほど示したこの第四文の「少数の割合であるが、相応の人数に達する」の部分は、「同性愛者」の性質について補足して述べているだけであり、結論を導き出すための理由として論じられているものではない。
よって、これと同様のことを述べている第一文と第三文の「同性愛者」の性質について述べている文は、この第四文がこの段落の結論として示す内容を導くための理由となるものではない。
そのため、それらを除外して、最後に残った文を見ると、第二文で「同性婚を認めることが、社会の状況に大きな変化をもたらすものであって、その影響を考慮する必要があるとの的確な根拠があるとはうかがえない。」と述べられているだけである。
しかし、「同性婚を認めることが、社会の状況に大きな変化をもたらすものであって、その影響を考慮する必要があるとの的確な根拠があるとはうかがえない。」ことを理由として、「同性婚を認めることは、」「同性愛者に対する権利を保障し、個人として尊重することに意義を有する」との結論を述べるというのは、論理的な関係性を示すものは存在していない。
この点で、結論とその結論を導くための根拠との間に関係性を認めることができず、読み手はこの判決が示す結論を意味の通ったものとして受け入れることができなくなるのである。
━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━
「むしろ、同性愛者は割合的には社会的に少数である」との記載がある。
「同性愛者」とあるが、法律論としては、人を内心に基づいて分類しようとする一つの思想を持ち出して人を区別して考えることはできないのであり、人の内心を取り上げて分類し、その分類に基づいて区別して考えることが許されるかのように論じていることそのものが妥当でない。
また、婚姻制度は「性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いをする制度ではないし、「性愛」に基づいて制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもない。
そのため、「同性愛者」を称する者であるとしても、婚姻制度(男女二人一組)の要件を満たして制度を利用する意思があるのであれば、適法に婚姻制度を利用することができる。
実際、「同性愛者」を称する者であるとしても、婚姻制度を利用している事実は認められる。
それにもかかわらず、ここで人を内心に基づいて区別して考え、その中の「同性愛者」を称する者を取り上げているということは、「同性愛者」を称する者が婚姻制度(男女二人一組)を利用することができないかのような前提で論じるものであり、妥当でない。
また、もし「同性愛者」を称する者であるとしても婚姻制度(男女二人一組)を利用することは可能であることを理解した上で述べているとすれば、ここで「同性愛者」を称する者を取り上げて論じているということの背景には、「同性愛者」を称する者が婚姻制度(男女二人一組)を利用しているはずがないとか、利用してはならないとか、利用することは正当ではないという価値観を基にする主張であるということになる。
これは、「同性愛者」を称する者が婚姻制度(男女二人一組)を利用することに対して否定的な意味合いを含むものとなっており、不当な主張である。
このような理解の下に国家権力が行使されるということは、「同性愛者」を称する者に対して特定の価値観を押し付けるものということができ、憲法19条の「思想良心の自由」、憲法20条1項の「信教の自由」に違反するものである。
法制度は個々人の思想、信条、信仰、感情に対して中立的でなければならないのであり、特定の価値観に基づいて制度を利用することを求めるようなことがあってはならないし、勧めるようなこともしてはならない。
よって、「同性愛者」などと人の内心に踏み込む形で論じていること自体が誤りである。
「割合的には社会的に少数である」との部分についても、そもそも婚姻制度を利用することについては「性愛」と関りがないことから、「同性愛者」を称する者の数が多いか少ないかという問題に関係しないのであり、これを述べていること自体が妥当でない。
「同性婚を認めることが、社会の状況に大きな変化をもたらすものであって、その影響を考慮する必要があるとの的確な根拠があるとはうかがえない。」との記載がある。
ここでいう「同性婚」の意味が「同性間の人的結合関係」を形成することを指すのであれば、それは憲法21条1項の「結社の自由」で保障されている。
そのため、これが認められていないことを前提として「認めることが、」と述べていることは、前提となる認識を誤っていることになる。
ここでいう「同性婚」の意味が「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを指すのであれば、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることができるかという点から検討する必要がある。
「婚姻」は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」を目的として、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす「一人の男性」と「一人の女性」の組み合わせに対して「貞操義務」を設けるなど一定の形式で法的に結び付け、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によってそれらの目的の達成を目指す枠組みである。
また、憲法24条は「婚姻」を規定し、具体的に「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)の枠組みを定めていることも、この趣旨に対応するものである。
「同性間の人的結合関係」については、上記の「生殖と子の養育」の趣旨を満たすものではないし、憲法24条の文言の趣旨にも沿うものではないことから、「婚姻」の中に含めることができない。
よって、ここで「同性婚」のように「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることができることを前提として論じていることは誤りである。
「社会の状況に大きな変化をもたらすものであって、その影響を考慮する必要がある」か否かを検討している部分であるが、そもそも「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることはできないことから、これができることを前提として「社会の状況に大きな変化をもたらすものであって、その影響を考慮する必要がある」か否かを検討しようとしていることは、その前提を欠くものである。
また、「的確な根拠があるとはうかがえない。」との評価についても、その当否を論じる前提にないものである。
「もっとも、同性愛者は、割合的には少数であっても、人数的には相応の対象者が想定される。」との記載がある。
これは「同性愛者」と称する者を取り上げて、その者を対象とした制度を設けることを検討するものとなっている。
しかし、「同性愛」という特定の思想、信条、信仰、感情を保護するために制度を設けることは、憲法は20条1項後段・3項、89条で「政教分離原則」に違反する。
また、「同性愛」という特定の思想、信条、信仰、感情を抱く者のために制度を設け、それ以外の「性愛」の思想、信条、信仰、感情や、「性愛」以外の思想、信条、信仰、感情を抱く者との間で区別するものとなることから、憲法14条1項の「平等原則」に違反する。
他にも、「同性愛」という特定の思想、信条、信仰、感情を抱くことを求めたり勧めたりするものとなることから、個人の内心に対して干渉するものとなり、憲法19条の「思想良心の自由」、憲法20条1項前段で「信教の自由」に違反する。
このように、法制度は内心に中立的な内容でなければならないのであり、法制度が特定の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的として定められている場合や、法制度が個々人の内心に基づいて区別取扱いを行うようなものとして定められている場合、法制度を利用する者の内心に干渉するようなものとして定められている場合には、そのこと自体で違憲となる。
そのため、ここで「同性愛者」などと人の内心における心理的・精神的なものを取り上げて人を区別し、その区別に応じる法制度を設けることが可能であるかのように論じていること自体が誤りである。
「したがって、同性婚を認めることは、現存の制度の例外を定め、少数の割合であるが、相応の人数に達する同性愛者に対する権利を保障し、個人として尊重することに意義を有するものと考えられる。」との記載がある。
ここでいう「同性婚」の意味が、「同性間の人的結合関係」を形成することを指すのであれば、それは憲法21条1項の「結社の自由」で保障されていることから、それが認められていないということはない。
そのため、それが認められていないことを前提に「認めること」と述べていることは誤りである。
ここでいう「同性婚」の意味が、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを指すのであれば、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることができるかという部分から検討することが必要である。
「婚姻」とは、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた枠組みである。
具体的には、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」を目的として、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす「一人の男性」と「一人の女性」の組み合わせを選び出し、その間を「貞操義務」を設けるなど一定の形式で法的に結び付け、子供が産まれた場合にその遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によって立法目的の達成を目指すものである。
「同性間の人的結合関係」については、その間で「生殖」を想定することができず、この「生殖と子の養育」の趣旨を満たすものではないことから、「婚姻」の中に含めることはできない。
よって、ここで「同性婚」のように、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることができるかのように述べていることは誤りとなる。
ただ、ここでは「同性婚を認めることは、現存の制度の例外を定め、」としていることから、「現存の制度」である婚姻制度の「例外」として「同性婚」を位置付けていることから、ここでいう「同性婚」と称しているものは、「婚姻」ではないように思われる。
ただ、「婚姻」ではないものを「~~婚」と表現することは、「~~婚」の「婚」の語源が「婚姻」であることからすると、「婚姻」でないものを「婚姻」と呼んで指し示そうとしていることになるのであり、言葉の使い方として正しいとはいえない。
そのため、「婚姻」とは何かが厳密に問われているこの訴訟の中において、「~~婚」のような言葉を用いて表現することは不適切である。
「同性婚を認めることは、現存の制度の例外を定め、少数の割合であるが、相応の人数に達する同性愛者に対する権利を保障し、」との部分について検討する。
ここでいう「同性婚」とは「現存の制度の例外」とされており、その「同性婚を認めること」が「同性愛者に対する権利を保障」することになると述べていることから、この札幌高裁判決は、「現存の制度」は「同性愛者」を称する者を制度の対象から外していると考えているようである。
しかし、「現存の制度」である婚姻制度は、「性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いをする制度ではないし、「性愛」に基づいて制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもない。
そのため、個々人がどのような内心を有しているとしても分け隔てなく利用することができるのであり、「同性愛者」を称している者を婚姻制度(男女二人一組)の対象から外しているという事実は存在しない。
よって、ここで「現存の制度」である婚姻制度(男女二人一組)が「同性愛者」を称する者を制度の対象から外しているかのような前提に基づき、「同性愛者に対する権利」が「保障」されていないと考えた上で、ここでいう「同性婚を認めること」によって初めて「同性愛者に対する権利」が「保障」されるかのように論じていることは誤りである。
また、ここで「同性婚を認めることは、」「同性愛者に対する権利を保障」することになると論じていることからすれば、ここでいう「同性婚」としている法制度は、「同性愛」を保護することを目的とし、「同性愛者」を称する者を対象とし、「同性愛」に基づいて利用することを求めたり勧めたりする制度いうことになる。
しかし、法制度は個々人の内心に対して中立的な内容でなければならないことから、「同性愛者」を称するものを取り上げて法制度を設けることは違憲となる。
具体的には、「同性愛」という特定の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的とした制度を設けることは、憲法20条1項後段・3項、89条の「政教分離原則」に違反する。
「同性愛者」を称する者を対象とした制度を設けることは、個々人の内心に基づいて区別取扱いをすることになることから、憲法14条1項の「平等原則」に違反する。
「同性愛」に基づく制度を設けることは、制度を利用する者の内心に対して国家が干渉するものとなることから、憲法19条の「思想良心の自由」に違反する。
そのため、「同性愛」に基づく制度や、「同性愛者」を称する者を対象とした制度を設けることはできない。
よって、ここで「同性愛者に対する権利を保障」するための「同性婚」という法制度を立法することが可能であるかのように論じていること自体が誤りである。
「同性婚を認めることは、……(略)……相応の人数に達する同性愛者に対する権利を保障し、個人として尊重することに意義を有するものと考えられる。」と述べている部分を検討する。
まず、憲法は「個人の尊厳」の原理に基づいており、自然人は「個人主義」の下に「自律的な個人」として生存していくことを予定している。
そのため、何らの制度も利用していない状態で既に完全な状態ということができ、何らの制度も利用していない者の状態が「個人として尊重」されていないということにはならない。
また、「同性愛者」を称する者も自然人であることから、憲法上の人としての地位を有しているのであり、憲法13条前段のいう「すべて国民は、個人として尊重される。」という条文の適用を受けており、「個人として尊重」されている。
これに対して、ここでは「同性愛者」を称する者が「個人として尊重」されていないという前提認識から出発し、ここでいう「同性婚を認めること」という特定の制度を設けることによって初めて「個人として尊重」されることになると説明するものとなっている。
しかし、このような特定の制度が設けられていなければ「同性愛者」を称する者は「個人として尊重」されていないという認識を前提とすることは、「同性愛者」を称する者は自然人ではなく、憲法上の主体としての地位を有しておらず、「権利能力」も存在しないということになることから、明らかに不当である。
「同性愛者」を称する者も自然人であり、憲法13条前段の「すべて国民は、個人として尊重される。」との条文の適用を受けており、「個人として尊重」されているし、憲法上の主体としての地位を有しており、「権利能力」も存在する。
そのことから、札幌高裁判決が前提とする「同性愛者」を称する者が「個人として尊重」されていないという理解は誤りである。
そのため、「同性愛者」と称する者が何らの制度も利用していないことについて、あたかも「権利」が「保障」されていないだとか、「個人として尊重」されていないかのような前提を基に、制度を設けることによって初めて「権利」が「保障」されるとか、「個人として尊重」されるなどという認識の下に論じていることは、前提としている認識において誤っている。
これは、その主張そのものの中に、「同性愛者」と称する者が自然人として認められておらず、何か劣った存在であり、法的に「個人として尊重」されていない扱いを受けているかのような認識を前提として論じていることになるのであり、不当な主張である。
よって、特定の制度を設けることによって初めて「同性愛者」を称する者の「権利」が「保障」され、「個人として尊重する」ことになるかのような意味で、「権利を保障し、個人として尊重することに意義を有する」と述べていることは誤りである。
他にも、この「個人として尊重」の文言は、憲法13条前段の「すべて国民は、個人として尊重される。」との部分を意識していると考えられるが、この憲法13条は「国家からの自由」という「自由権」の性質であり、国家から個人に対する具体的な侵害行為があった場合に、その侵害を排除する場合に用いられることがあるが、これを根拠として特定の制度の創設を国家に対して求めることができるというものではない。
よって、憲法13条の「個人として尊重」の部分を持ち出したとしても、それによって特定の制度の創設を国家に対して求めることはできないのであり、ここで「個人として尊重することに意義を有するもの」として「同性婚を認めること」を挙げて、特定の制度の創設を求めることが可能であるかのように論じていることは誤りである。
その他、そもそも憲法24条は「婚姻」を規定しており、これは「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」を目的とし、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす「一人の男性」と「一人の女性」を選び出し、その間に「貞操義務」を設けるなど一定の形式で法的に結び付け、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によって立法目的の達成を目指す枠組みである。
憲法24条が「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めていることについても、この趣旨に対応するものである。
そのため、法律上において一夫一婦制(男女二人一組)の婚姻制度が定められ、それ以外の人的結合関係を対象とした制度が定められないという事態は、もともと憲法上で予定されていることである。
そして、憲法上で定められている事柄が、憲法上の他の規定との間で矛盾するということにはならないことから、憲法24条が「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めており、その規定の「要請」に従って法律上の婚姻制度が一夫一婦制(男女二人一組)で立法され、それ以外の人的結合関係はその制度の対象なっていないことが、同じ憲法上の規定である憲法13条との間で矛盾するということにはならない。
よって、一夫一婦制(男女二人一組)の婚姻制度が定められていることを前提として、それに対する意味として「同性婚」と称する何らかの制度を持ち出し、その制度が存在しないことを理由に憲法13条の「個人として尊重」がなされていないという認識の下に論じていることは誤りであるし、その認識の下に、その制度を立法することによって初めて「個人として尊重」されると考え、「個人として尊重することに意義を有する」と述べていることは、そもそも憲法24条と13条の内容が矛盾することはないという点で、憲法13条による審査を行う前提にない事柄であるという点で誤っている。
これとは別に、「個人として尊重することに意義を有するものと考えられる。」との部分の「個人として尊重」について、ある特定の制度を設けることが政策として望ましいと考える意味で用いようとしていることが考えられる。
しかし、どのような制度を設けることが政策として望ましいかということについては、「個人として尊重」と述べるだけでは何らの結論を導き出すことのできるものではない。
そのため、「個人として尊重」を理由として「同性婚」と称する特定の制度を立法することを正当化できるということにはならない。
このような意味として「個人として尊重」という言葉を用いているのであれば、同様に、一夫多妻制は「個人として尊重することに意義を有する」だとか、婚姻制度は廃止することが「個人として尊重することに意義を有する」など、様々な政策を「個人として尊重」と述べるだけで同様に正当化することができてしまうことに繋がるものである。
そのため、「個人として尊重」を理由とする形で、特定の結論を導き出すことができるということにはならないのであり、これを述べたとしても、ここでいう「同性婚」と称する制度を設けることについて正当化できるということにはならない。
そもそも、望ましい政策を考えた結果として、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」を目的として、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす「一人の男性」と「一人の女性」の組み合わせに対して「貞操義務」を設けるなど一定の形式で法的に結び付け、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によってそれらの目的の達成を目指すものとして「婚姻」という枠組みが形成されているものである。
そのため、「個人として尊重」という言葉を望ましい政策と考える旨として用いているのであれば、むしろ望ましい政策という意味で憲法上の立法政策として一夫一婦制(男女二人一組)による「婚姻」という枠組みを定めているということになるのであり、この枠を超える人的結合関係を「婚姻」とすることをその望ましい政策を意味する「個人として尊重」という言葉によって正当化することができるとする理由にはならないものである。
もう一つ、この「個人として尊重することに意義を有するものと考えられる。」との意味が、憲法13条の「個人として尊重」の部分とは何ら関係なく、この札幌高裁判決を書いた裁判官が特定の政策を実施することが望ましいと考える旨を述べている可能性が考えられる。
しかし、どのような政策が望ましいかという問題は憲法の枠内で政治部門である国会で議論される事柄であり、法令の合憲・違憲、合法・違法しか判断することのできない裁判所の立場で論じてはならないものである。
それについて裁判所の立場で口出しをしようとすることは、その主張そのものが越権行為であり、司法権の逸脱・濫用にあたるものである。
そのため、この札幌高裁判決を書いた裁判官が特定の政策を実施することが望ましいと考える旨を述べているとすれば、誤った判断であるといえる。
ここでは「同性婚を認めること」が「個人として尊重することに意義を有する」か否かを論じるものとなっている。
しかし、憲法24条の論点において問われているのは、憲法24条の「婚姻」の枠組みが「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とする法律を立法することを「要請」しているか否かであり、「同性婚を認めること」が「個人として尊重することに意義を有する」か否かではない。
そのため、ここで「同性婚を認めること」のように、憲法よりも下位の法令である法律上の立法政策の問題を取り上げて、それが「個人として尊重することに意義を有する」か否かを考えることによって、憲法24条に違反するか否かの結論が導き出されるかのような前提で論じていることは誤りである。
「相応の人数に達する」とあるが、「達する」とは、どこかの地点からある地点にたどり着くことを意味する言葉であるが、特にこの文脈である地点からどこかに到達するという説明の中で用いられているわけではないことから、言葉の選択が妥当であるとはいえない。
ウ 昨今の社会の流れとしては、次のような事情を挙げることができる。
【筆者】
ここでは「昨今の社会の流れ」を取り上げているが、憲法上の条文を解釈するにあたって、このような事柄を根拠としてはならない。
「昨今の社会の流れ」を理由とすることの不当性について、日本国憲法の制定に関わった「鈴木義男」の述べた下記の内容が参考になる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
有澤廣巳の裁判 弁護要旨より
(鈴木義男)
裁判がその時の政治的勢力に左右された形跡ありと見られる事例は
歴史の法廷に於いては常に醜いものとして再批判されます
学問が政権から超然としておらねばならぬやうに
裁判も常に政権政治的な動きからは超然でなければならぬと信じます
裁判は政治ではない
一切の政治的勢力乃至影響から超然として
法によってのみ為さるる所に司法の尊厳があり
国家を盤石の安きに置く保障があるのであります
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
NHK ETV特集「義男さんと憲法誕生」 初回放送日:2020年5月2日 (50分20秒頃より)
このように、裁判所の判断は「法によってのみ為さるる」ことが必要であり、「その時の政治的勢力」や「政治的な動きからは超然でなければならぬ」ものであるといえる。
そのため、条文の内容が「昨今の社会の流れ」を理由として歪められるようなことがあってはならない。
よって、このような「昨今の社会の流れ」を取り上げ、これを考慮することによって憲法上の条文に記された規範の意味が左右されるかのような前提で論じようとしていることは誤りである。
また、この「ウ」で「昨今の社会の流れ」として次の段落より以下で取り上げている内容を先にまとめて示すと、下記のようになる。
ウ
「昨今の社会の流れ」
・「同性婚が可能となった国・地域は30を超えている」
・「国連自由権規約人権委員会は、」「指摘した」
・「同性婚の制度や判例法理を確立させ、あるいはこれに準ずる登録パートナーシップ制度を導入する諸外国が多数ある」
・「地方公共団体」「においてパートナーシップ認定制度を導入し、その人ロカバー率は65%に達している」
・「同性婚の法制化に賛同する企業の可視化に加わる企業や団体は、現在360を超えている」
・「日本家族〈社会と法〉学会や日本学術会議は、同性婚規定の新設提案や民法改正の提言を発表している」
・「国民に対する各種調査においても、同性婚を認める回答が増加しており、最近では、ほぼ半数を超える国民が同性間の婚姻を容認すると回答している」
・「最新の新聞社による世論調査では、同性婚を容認するとの回答は最低54%から、最高は72%に達しており」
・「国会においても同性婚の法制化につき議論がされるようになってきている」
これらのいずれについても、法解釈として憲法上の条文の意味そのものを読み取る過程で用いてはならないものであり、これらを考慮することによって憲法上の条文の規範の意味を論じようとしていることは、法解釈の方法として誤っている。
同性婚が可能となった国・地域は30を超えている(認定事実(7)ア(イ))。国連自由権規約人権委員会は、日本政府報告書において、レズビアン、ゲイ等の人々が、法律的な婚姻等へのアクセスにおいて差別的な扱いに直面し、同性婚を含め、市民的及び政治的権利に関する国際規約に規定された全ての権利を締結国の領域の全てで享受できるようにすることを指摘した(認定事実(8)ア)。また、同性婚の制度や判例法理を確立させ、あるいはこれに準ずる登録パートナーシップ制度を導入する諸外国が多数ある中(認定事実(7)ア)、我が国においても、地方公共団体(全国での数はおよそ1700)のうち、260を超える団体においてパートナーシップ認定制度を導入し、その人ロカバー率は65%に達している(認定事実(8)ア)。
【筆者】
━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━
この文が読み取りづらい原因は、下記の通りである。
◇ 第一文で「同性婚が可能となった国・地域」について述べて、第二文で「国連自由権規約人権委員会」の話に移っている。
そして、第三文で「我が国」の「地方自治体」の話を出すことによって順番に説明するものかと思いきや、この第三文の前半ではまた「諸外国」の話をするものとなっている。
「国・地域」 → 「国連自由権規約人権委員会」 → 「諸外国 ⇒ 地方自治体」
そのため、読み手は話の道筋をスムーズに読み取ることができず、混乱するのである。
◇ 第二文の「国連自由権規約人権委員会は、日本政府報告書において、レズビアン、ゲイ等の人々が、法律的な婚姻等へのアクセスにおいて差別的な扱いに直面し、同性婚を含め、市民的及び政治的権利に関する国際規約に規定された全ての権利を締結国の領域の全てで享受できるようにすることを指摘した(…)。」(カッコ内省略)の文は、「レズビアン、ゲイ等の人々が、~~直面し、」のように、「し、」の後に続いて「レズビアン、ゲイ等の人々が、」を主語とした形で何らかの出来事があること予想されるものとなっている。
しかし、その後、続く文は、「~~で享受できるようにすることを指摘した」となっており、「国連自由権規約人権委員会」が主語となる文が述べられているだけである。
そのため、「レズビアン、ゲイ等の人々が、~~直面し、」の後に、その「レズビアン、ゲイ等の人々」がどうなったのかが分からないままとなっている。
この点で、読み手は疑問を抱えたまま放置されることとなり、読み取りづらく感じるのである。
◇ 第三文について「同性婚の制度……(略)……、あるいはこれに準ずる登録パートナーシップ制度を導入する諸外国が多数ある中」という文ならば意味を読み取ることができる。
しかし、ここでは「同性婚の制度」の後に、「や判例法理を確立させ」との文言がある。
その「判例法理を確立させ」との部分には、「確立させ」たことによってその後どのような結果が生じたのか明らかになっておらず、そのまま文が終わってしまう。
そのため、読み手は「判例法理を確立させ」た話はその後どう決着したのか分からないままとなり、文の意味を飲み込むことができなくなり、読み取りづらく感じるものとなっている。
◇ 第三文は「また、~~を導入する諸外国が多数ある中(…)、我が国においても、~~を導入し、その人ロカバー率は65%に達している(…)。」との文なっている。
これは、「また、」から始まり、「諸外国が多数ある中」のように「諸外国」のことを出し、その後「我が国においても、」のように「我が国」のことを出しているのであるから、これは「諸外国」と「我が国」のことを対比する形で論じていることを想定させるものとなっている。
しかし、「~~を導入する諸外国が多数ある中(…)、」に続いて結論を述べるのであるから、「我が国」についても「導入」するか否かを論じて締められるはずであるが、ここでは「我が国」について「~~を導入し、」と述べた後にもまだ文が続き、「その人ロカバー率は65%に達している(…)。」と述べて文を閉めている。
このように、この文は、対比させたい事柄だけでなく、それに別の情報を加えていることから、話の筋道が途中で変わっており、読み取りづらく感じるのである。
◇ 第三文の「我が国においても、地方公共団体(全国での数はおよそ1700)のうち、260を超える団体においてパートナーシップ認定制度を導入し、その人ロカバー率は65%に達している(…)。」との文であるが、「のうち、260を」の部分の「、」は不要であると考える。
この点で文を区切ることにより、読み手を無駄に一呼吸させるものとなり、この一文を飲み込みにくいものとしている。
━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━
「同性婚が可能となった国・地域は30を超えている」との記載がある。
ここでは、他の「国・地域」の法制度について、「同性婚」という文言を用いて説明するものとなっている。
しかし、外国語を翻訳する者が外国の法制度について「婚」のように「婚姻」を指す言葉を充てて説明しているとしても、それは日本国の法制度における「婚姻」と同一のものを指していることにはならない。
なぜならば、外国の法制度は、それぞれの国の社会事情の中で生じている問題を解消することを意図して構築されたものであり、その立法目的やその立法目的を達成するための手段・方法には様々な違いがあるからである。
そのため、その外国の法制度と日本国の法制度との間に何らかの類似点を見出すことができる場合があるとしても、それはそれぞれの国の社会事情の中で形成された別個の制度であり、同一の制度を指していることにはならない。
そのことから、外国で「同性間の人的結合関係」を対象とした何らかの法制度が存在するとしても、それは日本国の法制度における「婚姻」と同一の制度について述べているということにはならない。
このため、外国の事例を取り上げたとしても、そのことが日本国の法制度に直接的な影響を与えることはないし、日本国の法制度における「婚姻」の中に「同性間の人的結合関係」を含めることができるとする根拠にもならない。
また、この判決では外国の法制度の中でも、「同性」間の「二人一組」の人的結合関係を対象とした法制度のみを取り上げて論じるものとなっている。
しかし、外国の中には「男性一人」と「女性四人まで」の「一夫多妻型」の法制度を採用している国も存在しているのであり、それらを一切取り上げることなく、「二人一組」の人的結合関係のみを比較対象として取り上げれば何らかの結論を導き出せるのではないかとの前提で論じている点は妥当でない。
外国の法制度との間で比較をする際には、比較対象の選択が恣意的なものとなってはならない。
そのため、もしこのように「同性婚が可能となった国・地域」を取り上げて論じたいのであれば、「近親者との人的結合関係」を制度にしている「国・地域」や、一夫多妻制など「三人以上の人的結合関係」を制度にしている「国・地域」、日本法の基準から見て「婚姻適齢に満たない者との人的結合関係」を制度にしている「国・地域」など、様々な事例を網羅的に論じることが必要である。
そのような検討をせずに、制度の一断片のみを切り取って論じるだけでは、統一的な理念に基づいて全体の整合性を保った制度を維持しようとする視点を欠いているため、誤った結論を導き出す原因となる。
裁判官が取り上げたいものだけを議論の前提として使うということになれば、公平性・公正性が保たれているとはいえない。
他にも、外国の中には「性愛」の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的とした法制度を定めているものが考えられるところ、日本国の法制度においては特定の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的とした法制度を立法した場合には、憲法20条1項後段・3項、89条の「政教分離原則」に違反することになる。
そのため、外国の法制度においてそのような制度が存在するとしても、日本法においては立法することができない点にも注意する必要がある。
外国の法制度との間で比較をする際には、このような点も押さえる必要がある。
「国連自由権規約人権委員会は、日本政府報告書において、レズビアン、ゲイ等の人々が、法律的な婚姻等へのアクセスにおいて差別的な扱いに直面し、同性婚を含め、市民的及び政治的権利に関する国際規約に規定された全ての権利を締結国の領域の全てで享受できるようにすることを指摘した」との記載がある。
「レズビアン、ゲイ等の人々が、法律的な婚姻等へのアクセスにおいて差別的な扱いに直面し、」との部分について検討する。
「法律的な婚姻等へのアクセス」とあるが、婚姻制度は「男女二人一組」などの要件を満たして制度を利用する意思を有するのであれば、誰にでも制度の利用を認めている。
そのため、「レズビアン、ゲイ等の人々」であっても、その個々人が「男女二人一組」などの要件を満たして制度を利用する意思を有するのであれば、適法に婚姻制度を利用することができる。
よって、「レズビアン、ゲイ等の人々」に対して「法律的な婚姻等へのアクセスにおいて差別的な扱い」をしているとの事実はない。
これについては、「レズビアン、ゲイ等の人々」に限らず、「異性愛者」、「同性愛者」、「両性愛者」、「全性愛者」、「多性愛者」、「小児性愛者」、「老人性愛者」、「死体性愛者」、「動物性愛者」、「対物性愛者」、「対二次元性愛者」、「無性愛者」を称する者であっても、特に何も称しない者であっても同様である。
婚姻制度は個々人の「性愛」の有無や、「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いを行うような制度ではないからである。
よって、「レズビアン、ゲイ等の人々が、法律的な婚姻等へのアクセスにおいて差別的な扱いに直面し、」との説明は誤りである。
「同性婚を含め、市民的及び政治的権利に関する国際規約に規定された全ての権利を締結国の領域の全てで享受できるようにすることを指摘した」との部分について検討する。
「同性婚」との部分について検討する。
憲法24条に定められている「婚姻」は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた枠組みである。
具体的には、これは「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」を目的として、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす「一人の男性」と「一人の女性」の組み合わせに対して「貞操義務」を設けるなど一定の形式で法的に結び付け、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によってそれらの目的の達成を目指すものである。
「同性間の人的結合関係」については、その間で「生殖」を想定することができず、この「生殖と子の養育」の趣旨を満たすものではないことから、「婚姻」の中に含めることはできない。
よって、ここで「同性婚」とあるが、日本法の下では「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることはできないことになる。
また、ここでいう「同性婚」の意味が「同性間の人的結合関係」を対象とした何らかの制度を指しているとしても、日本国の場合は、憲法24条の「婚姻」の文言が「生殖と子の養育」に関わる制度を一元的に集約して規律していることから、それが「生殖と子の養育」に関わる制度や影響を与える制度となっている場合には、憲法24条の「婚姻」に抵触して違憲となる。
他にも、婚姻制度が「男女二人一組」に対して法的効果や一定の優遇措置を設けていることについては、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成するための手段として整合的な要素を満たすものであることから、「婚姻していない者(独身者)」との間での差異を正当化することができるが、「同性間の人的結合関係」を対象とした制度の場合は、そのような目的を有していないことから、何らの制度も利用していない者との間での差異を正当化することはできず、憲法14条1項の「平等原則」に違反することになる。
よって、何らかの「指摘」を受けたとしても、日本国で「同性間の人的結合関係」を対象とした制度を設けることができるということにはならない。
また、国際機関や他国からの「指摘」があるとしても、その「指摘」そのものの当否を検討することが必要である。
その「指摘」を無批判に自国の法制度に取り入れることが正しいというものではない。
他にも、それらの「指摘」が憲法上の規定の意味を書き替えることはないため、憲法の解釈に影響を与えることはないし、影響を受けるようなこともあってはならない。
「同性婚の制度や判例法理を確立させ、あるいはこれに準ずる登録パートナーシップ制度を導入する諸外国が多数ある中」との記載がある。
ここでは、「諸外国」の「同性婚の制度」について述べている。
ただ、外国語を翻訳する者が「諸外国」のある法制度について「同性婚」の「婚」のように「婚姻」という言葉をあてて説明しているとしても、それは日本国の法制度における「婚姻」と同一の制度を指していることにはならない。
なぜならば、外国の法制度は、それぞれの国の社会事情の中で生じている問題を解消することを意図して構築されたものであり、その立法目的やその立法目的を達成するための手段・方法には様々な違いがあるからである。
そのため、外国の法制度と日本の法制度の間で何らかの類似点を見出すことができる場合があるとしても、それはそれぞれの国の社会事情の中で形成された別個の制度であり、同一の制度を指していることにはならない。
そのことから、このような「諸外国」の事例を取り上げたとしても、そのことが日本国の法制度に対して直接的な影響を与えることはないし、日本国の法制度における「婚姻」の中に「同性間の人的結合関係」を含めることができるとする根拠にもならない。
よって、「諸外国」の「同性婚の制度」と述べたところで、日本国の法制度における「婚姻」の中に「同性間の人的結合関係」を含めることができるとすることにはならない。
また、ここでは「諸外国」の「同性婚の制度」のように「同性間の人的結合関係」を対象とした制度を設けている国について取り上げているのであるが、「諸外国」の中には「一人の男性と四人の女性まで」の「一夫多妻制」を採用している国もあるのであり、そのような国を一切取り上げることなく、「同性間の人的結合関係」を対象とした制度を設けている国だけを取り上げて論じれば何らかの結論を導き出せるかのように考えているところも妥当でない。
このような比較対象の取り上げ方には、この判決を書いた裁判官が特定の結論を導き出すために恣意的な判断が含まれていることが考えられる。
このため、「二人一組」であることを前提とする論じ方は、なぜ「二人一組」であるのかその根拠を説明しないままに論じる「カップル信仰論」に陥っているということができる。
【参考】「advocating polygamy to solve Japan's declining birthrate.」 Twitter
【参考】「【公約】 「一夫多妻制(多夫多妻制)」の実現」 Twitter
「判例法理を確立させ、」の部分は、上記の「読み取りづらい原因」のところでも説明したが、「判例法理を確立させ」たことにより、どのような結論を導いたのか書かれておらず、意味の分からないものなっており、妥当でない。
また、その「判例法理」の内容も分からず、その結論を正当化することのできる理由があるのかどうかも不明である。
「諸外国」の「同性婚の制度」「に準ずる登録パートナーシップ制度」について述べている。
しかし、「諸外国」で「同性間の人的結合関係」を対象とした「登録パートナーシップ制度」が存在するとしても、それは日本国の法制度において「同性間の人的結合関係」を対象とした制度を立法することができるとする根拠にはならない。
まず、日本国の法制度における「婚姻」は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度である。
そして、憲法24条の「婚姻」の文言は「生殖と子の養育」に関わる制度を一元的に集約して規律する趣旨を有しており、「生殖と子の養育」に関わる制度をこの憲法24条の「婚姻」を離れて別の制度として立法することはできない。
そのため、もし憲法24条の「婚姻」を離れて別の制度として「生殖と子の養育」に関わる制度を立法しようとした場合には、憲法24条の「婚姻」に抵触して違憲となる。
そのことから、「同性間の人的結合関係」を対象とした制度を立法しようとした場合、それは「生殖と子の養育」に関わる制度や影響を与える制度となることが考えられ、憲法24条の「婚姻」の文言に抵触して違憲となる。
また、たとえ「生殖と子の養育」に関わらないとしても、そもそも「生殖と子の養育」の趣旨を有していない人的結合関係に対して何らかの法制度を設けることは、何らの制度も利用していない者との間で合理的な理由を説明することのできない差異を生じさせるものとなるから、憲法14条1項の「平等原則」に違反することになる。
よって、「諸外国」で「同性間の人的結合関係」を対象とした「登録パートナーシップ制度」を設けているとしても、それは日本法の下では「同性間の人的結合関係」を対象とした制度を設けることができるとする根拠にはならない。
「我が国においても、地方公共団体(全国での数はおよそ1700)のうち、260を超える団体においてパートナーシップ認定制度を導入し、その人ロカバー率は65%に達している」との記載がある。
地方自治体の「パートナーシップ認定制度」は、憲法上の規定に抵触して違憲、法律により定められている婚姻制度に抵触して違法となる部分があるため、このような制度を取り上げて論じようとしていること自体が妥当でない。
これについて、詳しくは当サイト「パートナーシップ制度」で解説している。
また、法の論理は導入した地方自治体の数によって左右されるものではないことから、「全国での数」や「人ロカバー率」を述べたとしても、そのことはその制度が違憲・違法でないことを示すものではない。
他にも、「3 本件規定が憲法24条に違反する旨の主張について」の項目で問われているのは、憲法24条の「婚姻」の枠組みが「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とする法律を立法することを「要請」しているか否かであり、これは憲法上の条文の文言を読み解くことによって規範の意味を明らかにすることが必要であり、その意味を憲法よりも下位の法形式の制度を根拠とすることはできない。
そのことから、憲法24条の規範の意味を明らかにする過程において、憲法よりも下位の法形式か、あるいは法的な効力を持たない形で定められる地方自治体の「パートナーシップ認定制度」を取り上げて根拠としようとしていることは、法秩序の階層構造を理解しないものであり、解釈の過程として誤っている。
同性婚の法制化に賛同する企業の可視化に加わる企業や団体は、現在360を超えている(認定事実(8)ウ)。日本家族〈社会と法〉学会や日本学術会議は、同性婚規定の新設提案や民法改正の提言を発表している(認定事実(8)エ)。
【筆者】
「同性婚の法制化に賛同する企業の可視化に加わる企業や団体は、現在360を超えている」との部分について検討する。
ここでいう「企業や団体」は、もともと様々な意見を表明する自由があり、実際に様々な意見を表明しながら活動を行っている。
ここで取り上げているものも、その自由の中で表明された一つの意見に過ぎない。
そのため、それらの団体が賛否を表明したとしても、それによって裁判所が法解釈を行う際に合憲・違憲の判断が変わることはない。
また、そのような事柄に影響を受けるようなことがあってはならない。
「日本家族〈社会と法〉学会や日本学術会議は、同性婚規定の新設提案や民法改正の提言を発表している」との記載がある。
しかし、「日本家族〈社会と法〉学会」や「日本学術会議」が何らかの「提言」を行ったとしても、そのことによって憲法24条の規範の意味が変わるということにはならない。
日本国内には様々な団体があり、それぞれの団体は意見を表明する自由を有しており、実際に様々な意見を表明しながら活動を行っている。
よって、憲法24条2項の規範の意味を明らかにする解釈の過程において、このような「提言」を持ち出して論じようとすること自体が妥当でない。
この段落では、「同性婚の法制化」や「同性婚規定」のように「同性婚」という言葉が使われている。
しかし、「婚姻」とは、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」を目的として、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす「一人の男性」と「一人の女性」を選び出し、その間「貞操義務」を設けるなど一定の形式で法的に結び付け、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によって立法目的の達成を目指す枠組みである。
また、憲法24条が「婚姻」を規定しており、「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めていることも、この趣旨に対応するものとなっている。
そのため、「同性」間ではその間で「生殖」を想定することができず、「生殖と子の養育」の趣旨を満たすものではないし、憲法24条の「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言が一夫一婦制(男女二人一組)を定めている趣旨にも沿うものではないことから、「婚姻」の中に含めることはできない。
そのことから、たとえ「企業や団体」や「日本家族〈社会と法〉学会や日本学術会議」が「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることができることを前提に何らかの活動を行ったり、「提言」を発表しているとしても、そのことによって「同性間の人的結合関係」を法的な意味で「婚姻」として扱うことができるということにはならない。
よって、ここで「同性婚」のように、「同性」間の人的結合関係を「婚姻」とすることができるかのような言葉を用いていることは適切ではない。
そして、国民に対する各種調査においても、同性婚を認める回答が増加しており、最近では、ほぼ半数を超える国民が同性間の婚姻を容認すると回答している(認定事実(10)ア~オ)。最新の新聞社による世論調査では、同性婚を容認するとの回答は最低54%から、最高は72%に達しており(認定事実(l0)力)、国会においても同性婚の法制化につき議論がされるようになってきている(認定事実(8)オ)。
【筆者】
「国民に対する各種調査においても、同性婚を認める回答が増加しており、最近では、ほぼ半数を超える国民が同性間の婚姻を容認すると回答している」との記載がある。
まず、ここでいう「同性婚」や「同性間の婚姻」の意味について検討する。
この意味が「同性間の人的結合関係」を形成することを指しているのであれば、それは憲法21条1項の「結社の自由」で保障されているものである。
この意味が「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを指しているのであれば、そもそも「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることができるかから検討する必要がある。
「婚姻」とは、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた枠組みである。
具体的には、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」を目的として、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす「一人の男性」と「一人の女性」の組み合わせを選び出し、その間に「貞操義務」を設けるなど一定の形式で法的に結び付けるものとして形成されている。
これは、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によって立法目的の達成を目指すところに意図がある。
「同性間の人的結合関係」については、その間で「生殖」を想定することができず、上記の「生殖と子の養育」の趣旨を満たすものではないことから、「婚姻」の中に含めることはできない。
よって、ここでは「同性婚を認める回答が増加しており、」や「同性間の婚姻を容認すると回答している」と述べているが、これは「婚姻」とすることができないものについて「認める」や「容認する」と「回答」するものということになる。
これは、「独り者婚」を「認める」や「容認する」と「回答」する者がいるとしても、「独り者」を「婚姻」とすることはできないことに変わりはないことと同様の状態といえる。
これとは別に、ここでは「国民に対する各種調査」を取り上げていることから、あたかも国民の賛成意見と反対意見の数によって、憲法24条に違反するか否かが変わることを前提として論じていることになる。
しかし、憲法24条に違反するか否かは法解釈の問題であるから、法の中に規範を見出さなければならないものであり、憲法24条の条文の文言そのものを読み解くことによって規範の意味を明らかにし、結論を導き出すことが必要なものである。
そのため、「国民に対する各種調査」を取り上げて、法の条文に記された文言の意味そのものが、その時々の国民の賛成意見や反対意見の数という漠然とした国民意識によって左右され、これによって結論が導き出されるかのような前提で論じていることは誤りである。
「最新の新聞社による世論調査では、同性婚を容認するとの回答は最低54%から、最高は72%に達しており」との記載がある。
「同性婚」とあるが、これが「同性間の人的結合関係」を形成することを指すのであれば、憲法21条1項の「結社の自由」で保障されている。
「同性婚」の意味が「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを指すのであれば、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることができるかという部分から検討することが必要である。
「婚姻」とは、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた枠組みである。
具体的には、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」を目的として、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす「一人の男性」と「一人の女性」の組み合わせを選び出し、その間に「貞操義務」を設けるなど一定の形式で法的に結び付けるものとして形成されている。
これは、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によってそれらの目的の達成を目指すところに意図があるものである。
「同性間の人的結合関係」については、その間で「生殖」を想定することができず、上記の「生殖と子の養育」の趣旨を満たすものではないことから、「婚姻」の中に含めることはできない。
そのため、この意味で「同性婚を容認するとの回答」があるとしても、そもそも「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることはできない。
これとは別に、このような「世論調査」を根拠として持ち出しているということは、国民の賛成意見と反対意見の数によって、憲法24条に違反するか否かが変わることを前提として論じていることになる。
しかし、憲法24条に違反するか否かは法解釈の問題であるから、国民の「賛成」や「反対」の数というその時々の調査によって結論が変わるような資料を根拠として規範の意味を論じることは不適切である。
「国会においても同性婚の法制化につき議論がされるようになってきている」との記載がある。
しかし、「国会」で「議論」が行われていることを理由として、憲法上の規範の意味が変わることはないのであって、それによって法解釈の結論が変わることはない。
そのため、裁判所が判決文における法解釈を導く際の根拠としてこのような事柄を取り上げていること自体が不適切である。
工 同性間の婚姻に反対する立場の意見を検討する。
【筆者】
この憲法24条を解釈する場面で問われているのは、憲法24条の「婚姻」の枠組みが「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とする法律を立法することを「要請」しているか否かである。
憲法24条の「婚姻」の枠組みがこれを「要請」しているのであればその制度が存在しないことは違憲となり、憲法24条の「婚姻」の枠組みがこれを「要請」していないのであればその制度が存在しないことは合憲というものである。
これは、憲法上の条文の意味が問われているものであることから、その条文そのものから規範の内容を導き出すことが必要である。
しかし、ここでは憲法24条の規範の意味を明らかにする解釈の過程において、「反対する立場の意見」を取り上げ、それを「検討」することによって結論を導き出そうとするものとなっている。
これは、あたかも国民の「賛成派」や「反対派」の意見によって憲法24条の規範の意味が変わるかのように論じるものであり、法を解釈しているものとはいえない。
そのため、国民の意見によって規範の意味が変わるかのような前提で論じていることは誤りである。
法を解釈する過程の中においては、国民の賛成意見と反対意見を当否を論じることは不要である。
ここでは「同性間の婚姻」のように「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることが可能であることを前提としている。
そして、「賛成」と「反対」の意見を検討することによって結論を導き出すことを試みようとするものとなっている。
しかし、「婚姻」は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた枠組みである。
具体的には、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」を目的として、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす「一人の男性」と「一人の女性」の組み合わせに対して「貞操義務」を設けるなど一定の形式で法的に結び付け、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によってそれらの目的の達成を目指すものである。
そのため、この「生殖と子の養育」の趣旨を満たさない人的結合関係を「婚姻」の中に含めることはできない。
「同性間の人的結合関係」については、その間で「生殖」を想定することができず、この「生殖と子の養育」の趣旨を満たすものではないことから、「婚姻」とすることはできない。
これは、「賛成」と「反対」という次元の問題として導き出されているものではなく、それ以前の「可能」と「不可能」の次元の問題として導き出されているものである。
◇ 可能 (⇒ 賛成 or 反対 へ)
◇ 不可能 (⇒ 賛否を問う前提にない。)
よって、一段落前で「国民に対する各種調査」や「世論調査」における「賛成」と「反対」の数を取り上げ、その中の「賛成意見」と「反対意見」について検討したならば法解釈としての結論を導き出すことができるかのように考えて論じていること自体が妥当でない。
一つは、歴史及び制度上、一般的に、長らく異性間の婚姻が存続し、生殖機能の違いを有する男女の夫婦を基本的な単位とする家族制度が続いてきたことから、これと異なる同性間の婚姻について、同性愛に対する違和感、これが高じた嫌悪感、偏見を持つ場合があると考えられる。もっとも、この点は、感覚的、感情的な理由にとどまるものといえ、現在も実施されているように、啓蒙活動によって、同性愛は、生まれながらの器質、性質に由来し、合理的に区別する理由がないことを説いていくことによって解消していく可能性がある。
【筆者】
「一つは、歴史及び制度上、一般的に、長らく異性間の婚姻が存続し、生殖機能の違いを有する男女の夫婦を基本的な単位とする家族制度が続いてきたことから、これと異なる同性間の婚姻について、同性愛に対する違和感、これが高じた嫌悪感、偏見を持つ場合があると考えられる。」との記載がある。
━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━
この文が読み取りづらい原因は下記の通りである。
◇ 一段落前で「反対する立場の意見を検討する。」と述べていることから、この段落の第一文では、その「意見」の「一つ」が紹介されるはずである。
しかし、この段落の第一文は、「嫌悪感、偏見を持つ場合があると考えられる。」と結んでおり、「反対する立場の意見」そのものを述べているものではなく、何らかの意見の背景にあると考えるものについて述べるものとなっている。
このため、一段落前で「意見を検討する。」としている部分と内容が対応しておらず、読み手を混乱させるものとなっている。
◇ 「生殖機能の違いを有する男女の夫婦」とあるが、この文は構造的曖昧性を含むものとなっている。
・読み方1:「生殖機能の違いを有する男女」の夫婦
この読み方であれば、「男性」と「女性」の「生殖機能の違い」に着目して述べられていることになる。
・読み方2:生殖機能の違いを有する「男女の夫婦」
この読み方であれば、「男女の夫婦」と、それ以外の組み合わせとの間では、「生殖機能」という点において違いがあることを述べていることになる。
この文脈においては、この「生殖機能の違いを有する」の部分が、どちらの意味で使われているのか判断することができず、読み手を混乱させるものとなっている。
構造的な曖昧性を含む文の問題点については、当サイト「構造的曖昧文の克服」で解説している。
━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━
「一つは、」の部分であるが、一段落前で「反対する立場の意見を検討する。」と述べていることから、これは反対意見の「一つ」として取り上げてようとしているものということになる。
しかし、この憲法24条の解釈が問われている場面では、憲法24条の条文そのものから意味を読み取って規範の内容を明らかにしなければならないのであり、賛成意見と反対意見を比べて憲法24条の規範の意味を明らかにしようとしていることは誤りである。
また、反対意見を持つ者の「一つ」の意見を取り出して、その「一つ」の意見に対して反論したからといって、反対意見を持つ者のすべての意見に対して反論したことになるわけではない。
そのため、反対意見の「一つ」取り出して、それに対して反論したからといって、それがそのまま賛成意見を正当化することに繋がるということはないし、賛成意見の方が正しいということになるわけでもない。
よって、ここで反対意見を持つ者の「一つ」の意見を取り出して、その「一つ」の意見に対して反論したことを理由に憲法24条の規範の意味が決まるかのような前提で論じていることは誤りである。
ここでは「異性間の婚姻」と「同性間の婚姻」との文言が登場する。
まず、「異性間の婚姻」の意味であるが、ここでは「歴史及び制度上」や「男女の夫婦を基本的な単位とする家族制度」と書かれていることから、「同性間の人的結合関係」を指す意味ではなく、「異性間の人的結合関係」を対象としている「婚姻」の制度のことを指しているようである。
ただ、「婚姻」は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」を目的として、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす「一人の男性」と「一人の女性」を選び出し、その間に「貞操義務」を設けるなど一定の形式で法的に結び付け、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によって立法目的の達成を目指す枠組みである。
そのため、「婚姻」であれば、それは「異性間」のものしか存在しないのであり、ここで「異性間の婚姻」のように「異性間」という「男女」を指す言葉と「婚姻」という「男女」によって形成される概念を同時に用いることは、同義反復となるため文法上は誤用となる。
また、同義反復となることを無視して「異性間の婚姻」という言葉を用いたとしても、そもそも「男性」と「女性」の組み合わせを備えない形で「婚姻」という概念は成立し得ないことから、「異性間の婚姻」という言葉に対する形で、この「異性間」を満たさない「~~の婚姻」というものが別に成立するという余地はない。
そのため、この「異性間の婚姻」という言葉に対する形で、「同性間の婚姻」というものを法的に構成することができるかのように論じることは誤りであることに注意が必要である。
次に、「同性間の婚姻」の意味であるが、ここでは「同性間の人的結合関係」を指す意味として使われているとしても不自然ではないと考えられる。
しかし、「同性間の人的結合関係」を指すのであれば、そこで敢えて「婚姻」という法制度を指す言葉を用いる必要はないのであり、それを「同性間の婚姻」という言葉で表現していることは誤っているといえる。
この「同性間の婚姻」の意味が、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを指すのであれば、「同性間」ではその間で「生殖」を想定することができず、上記の「生殖と子の養育」の趣旨を満たすものではないため、「婚姻」の中に含めることはできない。
よって、「同性間の婚姻」のように「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることができるかのように述べていることは誤りとなる。
「歴史及び制度上、一般的に、長らく異性間の婚姻が存続し、生殖機能の違いを有する男女の夫婦を基本的な単位とする家族制度が続いてきたことから、」との部分について検討する。
これは、「歴史及び制度上」において、「生殖機能の違い」に着目して「男女」という「異性間」を組み合わせるものとして「婚姻」という制度が「長らく」「存続し」「続いてきた」ことを述べているものである。
この点で間違ってはいけないのは、物事の起こりを考えれば、「婚姻」という制度が先にあって、そこに後から「生殖機能の違いを有する男女」を結び付けているわけではなく、人間の「生殖」という営みが先にあって、そこに着目した枠組みとして「婚姻」という制度を定めているということである。
人間が「生殖」を行うことによって子孫を産む生き物であり、その活動によって生じる社会的な不都合を解消しようとする目的が存在している限りは、それを解決するための枠組みを定めることとなる。
そして、その枠組みのことを「婚姻」と呼んでいるのであり、この経緯を切り離した意味で「婚姻」という言葉を用いることはできない。
そのため、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消しようとする目的があり、その目的を達成するための手段として「婚姻」という枠組みが設けられているにもかかわらず、そこで使われている「婚姻」という言葉だけを刈り取って、その言葉が形成されている経緯から切り離して別の意味として用いることが可能となるわけではない。
「婚姻」という概念が形成される際の「目的」と「その目的を達成するための手段」となる枠組みの関係を切り離して、「婚姻」の意味そのものを単なる「音の響き」に過ぎないものにまで解体した上で、その空箱となった「音の響き」に過ぎないものに対してどのような人的結合関係でも詰め込むことができるということにはならない。
そのような論じ方は、条文に記された文言の意味を解体して無意味なものとし、法律上の規範としての意味を失わせるものとなるから、法解釈として不適切である。
よって、「長らく異性間の婚姻が存続し、」ていたが、時が経てば、この「婚姻」の中に「異性間」(男女)を満たさない人的結合関係までもを含めることができるとする余地が生まれるかのような前提で論じることは誤りとなる。
もう一つ、ここで「歴史及び制度上、一般的に、長らく異性間の婚姻が存続し、生殖機能の違いを有する男女の夫婦を基本的な単位とする家族制度が続いてきた」としても、これは「性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いをする制度ではないし、「性愛」に基づいて制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもない。
そのため、ここで「異性間の婚姻」や「生殖機能の違いを有する男女の夫婦を基本的な単位とする家族制度」と述べているものは、「異性愛」に基づく制度というわけではないし、「異性愛者」を称する者を対象とした制度というわけでもない。
そのことから、この部分の後で、これに対する形で「これと異なる同性間の婚姻について、同性愛に対する」のように、「同性愛」に基づいた「同性間の人的結合関係」を対象とする制度を取り上げようとしているが、そもそもここでいう「異性間の婚姻」や「生殖機能の違いを有する男女の夫婦を基本的な単位とする家族制度」は、「異性愛」に基づいた制度ではないという点で前提となる認識を誤っているといえる。
「これと異なる同性間の婚姻について、同性愛に対する違和感、これが高じた嫌悪感、偏見を持つ場合があると考えられる。」との部分について検討する。
ここでは「同性愛」を取り上げているが、法制度は個々人の内心に対して中立的な内容でなければならないのであり「性愛」を保護することを目的とした制度や、特定の「性愛」を有する者を対象とした制度、「性愛」に基づいて利用することを求めた勧めたりする制度を立法してはならない。
そのため、ここで「同性愛」という個人の内心における心理的・精神的なものを取り上げて、それを法制度と結び付けることが可能であるかのような前提で論じていることは誤りである。
また、ここでは、ここでいう「同性間の婚姻」という「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることに反対する理由は「同性愛に対する違和感、これが高じた嫌悪感、偏見」であると述べるものとなっている。
しかし、「同性愛者」を称している者であるとしても、ここでいう「同性間の婚姻」という「同性間の人的結合関係」を「婚姻」することに反対している場合もあるのであり、その反対する理由を「同性愛に対する違和感、これが高じた嫌悪感、偏見」であることを前提として論じることは不適切である。
【参考】「ゲイだけど、同性婚など一連の運動に反対。」 Twitter
【参考】「同性婚を反対している同性愛者は同性愛者とはどういう人たちなのかをよーく知っていて反対している。 」 Twitter
【参考】「同性婚に反対している同性愛者も大勢いる」 Twitter
【参考】「私も同性愛者ですが同性婚に反対です。私も同性愛者差別者になるんでしょうかね(笑)おかしな話ですよね。」 Twitter
【参考】「同性愛者でありながら、同性婚の「法制度化」に首尾一貫して反対している私は、自分自身を差別する「同性愛者差別者」ということになりますが、なんのことやら訳がわかりませんね。」 Twitter
【参考】「何故に、私達、市井の性的マイノリティーも同性婚と代理母出産に大反対なのか…。 解ってもらえていない」 Twitter
これは、別の意見を持つ「同性愛者」を称する者の意見を無視するものといえるのであり、この札幌高裁判決の前提とする「同性愛者」を称する者に対する理解の方が、むしろ「偏見」であるといえるものである。
また、法律論は、論理的な整合性を積み重ねることによって結論を正当化することが可能となるのであり、弱者を救おうとする正義感のある態度をどれだけ示すことができるかという「正義感レース」や「救済感レース」を行っているわけではない。
そのことから、「弱者であると称する者は、弱者なのだろう」と決めてかかり、そこに寄り添う態度を示せば問題が解消されるという性質のものではない。
そのため、反対の意見を持つ者を「同性愛に対する違和感、これが高じた嫌悪感、偏見」であると切り捨てることによって、弱者であると称する者に対して寄り添う態度を示したならば、そこで述べられる結論を正当化することができるということにはならない。
よって、ここで反対の意見を持つ者を「同性愛に対する違和感、これが高じた嫌悪感、偏見」によるものと決めてかかり、それを否定する態度を示したことによって結論を正当化することができるかのような前提で論じていることは誤りである。
このような、どれだけ弱者に寄り添う態度を示すことができるかという「正義感レース」や「救済感レース」は、宗教学の分野でしばしば見られるものである。
これは、より「正義感」が強い言動や、より「救済感」の高い言動を行った者が称えられ、尊敬されるという価値観を基にして、その言動を競い合うというもの(レース)である。
そして、宗教的指導者にあたる者は、そのような姿勢が特に感じられる傾向にあるとして上位のランクに位置付けられ、人々に称えられ、尊敬を集めていることがある。
しかし、このような価値観は法律論の中に持ち込むことができるものではない。
また、そのような「正義感レース」や「救済感レース」に基づく言動によって法的な規範を描き出すことができるということにはならない。
裁判所は純粋に法的な視点のみによって理を突き詰めた形で判断することが必要とされているのであり、何らかの敵を想定することによって、その仮想した敵を攻撃する態度を示して弱者に寄り添っていることをアピールすれば、そこで述べる結論の正しさを保証することができるというものではない。
そのため、「違和感」であるとか、「嫌悪感」であるとか、「偏見」であるとかいう敵を仮想して、それを攻撃したからといって、自らの述べる結論の正しさを支えることができるということになるわけではない。
よって、ここで反対する意見を持つ者について「同性愛に対する違和感、これが高じた嫌悪感、偏見」であると決めてかかり、それを否定する言動を示したことをもって結論を正当化できるかのような前提で論じていることは、論じ方として誤っている。
むしろ、法律論として考えれば、このような言動によって「弱者であると称する者」をそのまま「弱者である」と決めてかかって論じていることそのものが、その者を「弱者である」というレッテルを貼って他の者とは別物であるかのように扱っていることになるのであり、不平等を生じさせる原因となることを理解する必要がある。
その他、ここでは憲法上の条文の解釈が問われているのであるから、ここで国民の中の賛成意見や反対意見の数や考え方を取り上げて論じていることは誤りである。
法解釈の結論は、国民の中の賛成意見や反対意見の数や考え方によって左右されるものではないし、左右されるようなことがあってはならない。
「もっとも、この点は、感覚的、感情的な理由にとどまるものといえ、現在も実施されているように、啓蒙活動によって、同性愛は、生まれながらの器質、性質に由来し、合理的に区別する理由がないことを説いていくことによって解消していく可能性がある。」との記載がある。
これは、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とする制度に反対する理由について、「感覚的、感情的な理由にとどまるもの」として、「啓蒙活動によって、」「合理的に区別する理由がないことを説いていくことによって解消していく可能性」を述べている。
しかし、「同性愛者」を称する者であるとしても「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とする制度を設けることについて反対する者もいるのであり、これを「感覚的、感情的な理由にとどまるものといえ、」ると述べたり、「啓蒙活動」によって「解消」するべき対象であるなどという説明をすることは不適切である。
また、特定の思想を押し付けている点でも不適切である。
【参考】「同性愛者当事者ですが、同性婚には反対です。そういう人たちの声もよく聞いてくださいよね。」 Twitter
【参考】「同性婚に反対する同性愛者は沢山いますね。」 Twitter
【参考】「俺は、ホモ当事者として、ゲイ当事者として、現行憲法下で法律制定又は法律改正だけで、同性婚を認めることこそ日本国憲法に憲法違反だと考えています。」 Twitter
【参考】「愛し合っていることを国に認めてもらうために同性婚を推進しているのだとしたら、内心の自由の侵害に道を開く」 Twitter
また、そもそも婚姻制度は「性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いをする制度ではないし、「性愛」に基づいて制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもない。
そのため、「性愛」に基づいて「区別」がされているという前提が存在しないのであり、ここで「区別」されていることを前提として、「合理的に区別する理由がないことを説いていくこと」を述べていることは、そもそも「区別」がされていないという点で誤っているものである。
また、ここでは「合理的に区別する理由がないことを説いていく」ことについて、「現在」、「啓蒙活動」が「実施されている」と述べるものとなっているが、そもそも婚姻制度は「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いをする制度ではないことから、「性愛」に基づいて「区別」されていることを前提として「合理的に区別する理由がないことを説いていく」「啓蒙活動」を「現在」「実施」しているとすれば、その「啓蒙活動」は誤った前提に基づくものである。
そのため、そのような「現在」「実施されている」とする「啓蒙活動」については、逆に、婚姻制度は「性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いをする制度ではないし、「性愛」に基づいて制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもないことを「啓蒙」される必要があるといえるものである。
他にも、婚姻制度は「性愛」と結び付かないことから、「性愛」についての誤解を解消したところで、それは婚姻制度の枠組みや内容を変更することができるとする理由に繋がるものではない。
これについて分かりやすく言えば、法制度としての婚姻制度に乗っかる形で婚姻制度を利用する場合の教義を発行している宗教団体があるとして、何らかの活動によってその宗教団体が発行している教義の内容を変更するように求め、実際にその教義が変更されたとしても、法制度としての婚姻制度そのものには何らの影響を及ぼすものではないということである。
これと同様に、法制度としての婚姻制度は「性愛」と関わりのない形で定められていることから、婚姻制度と「性愛」を結び付けて考える者の思想信条や主義主張が「啓蒙活動」など何らかの活動によって変容することがあったとしても、そのことが法制度としての婚姻制度に対して何らかの影響を及ぼすというものではないのである。
よって、ここで「啓蒙活動によって、」「解消していく可能性」について述べるのであるが、そもそも婚姻制度と「性愛」を結び付ける者の価値観が変容したとしても、そのことが婚姻制度の枠組みや内容を変更することができるとする理由に繋がるというものではない。
逆に、この判決が婚姻制度と「性愛」を結び付けて考えていること自体が、法制度は個々人の内心に対して中立的な形で定めなければならないことを理解していないものであり、「解消」されるべきものである。
「同性愛は、生まれながらの器質、性質に由来し、」とある。
しかし、「同性愛」が「生まれながらの器質、性質に由来」するものであるかどうかについては、「2 本件規定が憲法13条に違反する旨の主張について」の項目の「(2)ア」の第一段落で「同性愛となる原因は解明されておらず、遣伝的要因、生育環境等複数の要因が組み合わさって作用している可能性が指摘されている」と述べている通り、「原因は解明されて」いないし、「遣伝的要因、生育環境等複数の要因が組み合わさって作用している可能性」も「指摘されている」ものである。
機会的同性愛 Wikipedia
それにもかかわらず、ここで「生まれながらの器質、性質に由来し、」のように述べていることは、未だ「原因は解明されて」いないにもかかわらず、特定の立場を前提として論じるものとなっており、不適切である。
「合理的に区別する理由がない」とある。
通常、「区別」がある場合には、そこで「区別する『合理的な』理由」があるかないかが問われ、その結果「区別する『合理的な』理由がない」のように判断されることはあり得る。
しかし、ここでいうような「合理的に区別する理由」があるかないかが問われることはない。
前者の「区別する『合理的な』理由」があるかないかについては、区別が存在した場合に、その合理性が問われ、その理由が妥当であるかが問われるというものである。
これに対して、ここでいう「合理的に区別する理由」があるかないかについては、「合理的に区別する」という基準が存在していて、その基準を用いて区別することについて理由があるか否かを問うものとなっている。
この両者は、「区別に『合理性』があるか否かを問うもの」であるか、「『合理的に区別する』という一定の基準を用いるか否かを問うもの」であるかという点で異なるものといえる。
そのため、ここでは「合理的に区別する理由がない」と述べられているが、この文脈の中でこの言葉を使っていることは、これら両者の意味の違いを識別できていない点で説明を誤っていると考えられる。
その他、ここでは憲法上の条文の解釈が問われているのであるから、憲法上の条文を読み解くことによって規範の内容を明らかにしなければならないのであり、国民の中の賛成意見や反対意見の数や考え方によって結論が左右されるというものではない。
よって、ここで国民の中の反対意見を取り上げて、それに対して反論することによって、憲法上の条文の意味を解釈する作業に影響を与え、結論が左右されるかのような前提で論じていることは誤りである。
また、ここで反対意見を持つ者に対して「啓蒙活動」をすることを述べるものとなっているが、そもそも法解釈は国民の中の賛成意見や反対意見を勘案することによって結論が左右されるというものではないのであり、反対意見を持つ者に対する「啓蒙活動」を論じることによって、法解釈の結論が変わることがあり得るかのような前提で論じていることも誤りである。
もう一つは、生殖機能に相違がある男女間の婚姻についてのみ、次世代に向けての子の育成の観点から、社会的な制度保障をすることが相当であり、そうではない同性間の婚姻についてはその保障が必要ないとする意見が考えられる。社会の制度については様々な意見があるところである。しかし、人が生まれながらに由来する自由と権利、これに係る個人の尊厳の実現には、家族とこれに対する社会的な制度の保障が不可欠であるといえるのであって、同性間で婚姻ができない不利益を解消する必要性は非常に高い。そうすると、婚姻の制度について様々な考え方があり、生殖機能に相違がある男女間の婚姻について一定の意義を認めるにせよ、これを理由に、同性間の婚姻を許さないということにはならないというべきである。
【筆者】
「もう一つは、生殖機能に相違がある男女間の婚姻についてのみ、次世代に向けての子の育成の観点から、社会的な制度保障をすることが相当であり、そうではない同性間の婚姻についてはその保障が必要ないとする意見が考えられる。」との記載がある。
二段落前で「反対する立場の意見を検討する。」と述べていることから、これは反対意見の「一つ」として取り上げようとしているものである。
しかし、ここでは憲法24条の条文の意味が問われており、それは憲法24条の条文そのものを読み解くことによって結論を導き出すことが必要であることから、特定の政策に対する賛成意見や反対意見を検討することによって憲法24条の規範の意味を導き出すことができるかのように論じていることは誤りである。
また、ここでは「反対する立場の意見」の一つを取り出し、それに反論することで憲法24条の規範の意味を導き出そうとするものとなっているが、賛成意見や反対意見に対して反論することで自らの主張の内容を強化することによって意思決定を行うことは、立法府や行政府がその裁量の範囲の中で行うことのできるいくつかの選択肢が存在する場合に、どの選択肢がよいと考えるかを政治的な議論の中で行う場合に用いられるものである。
しかし、司法府の裁判所においては、法令について合法・違法、あるいは合憲・違憲の判断のみしか行うことはできないのであり、ある特定の政策についての国民の議論の賛成意見と反対意見を取り出して、その意見の当否を論じたり、反論したとしても、それは法令を解釈する際の合法・違法、あるいは合憲・違憲の判断をする際の根拠とすることのできるものではない。
よって、このような「反対する立場の意見」を取り出して、それに対して反論したことを理由として憲法24条の規範の意味を明らかにするための根拠とすることができるかのように論じていることは誤りである。
政治部門の立法府と行政府の役割と、司法府である裁判所が司法権を行使するという権限の中で判断することのできる範囲のものとを区別することが必要である。
ここでは「男女間の婚姻」と「同性間の婚姻」との文言がある。
まず、「婚姻」とは、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」を目的として、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす「一人の男性」と「一人の女性」を選び出し、その間に「貞操義務」を設けるなど一定の形式で法的に結び付け、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によって立法目的の達成を目指す枠組みである。
そのため、「男女間の婚姻」との部分について、「婚姻」であればそもそも「男女間」のものを指していることから、この「婚姻」という言葉に「男女間の」という言葉を加えることは、「婚姻」の内容を示しているものとしては意味が通じるとしても、「男女間の婚姻」に対する形で、この「男女」を満たさないそれ以外の「婚姻」というものを法的に構成することができることを前提として用いているとすれば誤りである。
次に、この「男女間の婚姻」に対する形で用いられていると考えられる「同性間の婚姻」であるが、「同性間」ではその間で「生殖」を想定することができず、上記の「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的の下に形成される枠組みとして整合的な要素を満たすものではないことから、「婚姻」の中に含めることはできない。
そのことから、「同性間」の人的結合関係を「婚姻」とすることができるかのような前提で「同性間の婚姻」と述べている部分は誤りとなる。
この「同性間の婚姻」の文言は、「反対する立場の意見」の一つとして述べられているものであるが、この「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることができるか否かの論点は、「賛成・反対」における「反対」の問題ではなく、「可能・不可能」における「不可能」の問題であることに注意が必要である。
ここでは「同性間の婚姻に反対する立場の意見」として、「生殖機能に相違がある男女間の婚姻についてのみ、次世代に向けての子の育成の観点から、社会的な制度保障をすることが相当であり、そうではない同性間の婚姻についてはその保障が必要ないとする意見」を「考えられる。」として取り上げるものとなっている。
ここでは、「同性間の婚姻」のように、「同性間」の人的結合関係を「婚姻」とすることができることを前提に、「反対する立場の意見」を「考え」るものとなっている。
しかし、そもそも「婚姻」の中に「同性間」の人的結合関係を含めることができるかどうかから検討することが必要である。
まず、「婚姻」という言葉を用いている以上は、「婚姻」という概念によって指し示される対象と、それ以外の物事とが区別されていることを意味する。
また、この「婚姻」という言葉を用いて法制度を定めている以上は、他の様々な人的結合関係との間で区別する意味で「婚姻」という人的結合関係の枠組みを設けていることになる。
そのため、その「婚姻」にあたる人的結合関係と、「婚姻」ではない人的結合関係とが存在することはもともと予定されている。
また、言葉には一定の意味が存在することから、この「婚姻」という言葉を別の意味に変えてしまうことはできないし、「婚姻」の中にどのような人的結合関係でも自由に含めることができるということにもならない。
そして、人間は有性生殖を行うことによって子孫を生むという身体機能を有しており、その男女の間で行われる「生殖」に関わって生じる不都合が社会的な課題となっていることから、この問題の解決を図るために、この「生殖」の仕組みに着目する形で一定の枠組みを設けることが求められ、その機能を持つ制度のことを「婚姻」と呼んでいる。
ここで「生殖機能に相違がある男女間」や「次世代に向けての子の育成の観点」と述べているものも、この意味に対応するものであるといえる。
そのことから、その社会の中で「生殖」に関わって生じる不都合を解消することが求められている以上は、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす枠組みを定めることになるのであり、その機能を「婚姻」という概念が担っている以上は、その「婚姻」という概念をその機能を果たさないものに変えてしまうことはできない。
そのため、「婚姻」の概念の中に含めることのできる人的結合関係の範囲は、「婚姻」という概念が担っている「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的との関係で内在的な限界がある。
具体的には、下記の目的とその目的を達成するための手段として整合的な要素によって導き出されることになる。
目的
・「子の福祉」が実現される社会基盤を構築すること
・潜性遺伝子の発現した個体が高い確率で生じることを抑制すること
・「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」を減らすこと
・母体を保護すること
これらの目的を達成するためにの手段として整合的な要素
・子の遺伝的な父親を特定できる組み合わせとすること
・特定された子の父親にも子に対する責任を担わせること
・特定された子の父親を基に遺伝的な近親者を把握すること
・未婚の男女の数の不均衡を防止できる組み合わせに限定すること
そのため、これらの要素を満たさない人的結合関係を「婚姻」の中に含めることはできない。
「同性間」の人的結合関係については、これらの要素を満たすものではないことから、「婚姻」とすることはできない。
ここでは「同性間の婚姻に反対する立場の意見」を取り上げて、それに反論することによって、「同性間」の人的結合関係を「婚姻」とする法律を立法していないことについて憲法24条に違反するという結論に繋げようとするものとなっているが、そもそも「同性間」の人的結合関係を「婚姻」とすることについては「賛成・反対」以前に、「可能・不可能」の次元の問題があり、「同性間」の人的結合関係を「婚姻」とすることは「婚姻」という概念そのものが持つ内在的な限界によって「不可能」である。
よって、「同性間」の人的結合関係を「婚姻」とすることができることを前提として論じていること自体が誤りである。
「生殖機能に相違がある男女間の婚姻についてのみ、次世代に向けての子の育成の観点から、社会的な制度保障をすることが相当であり、そうではない同性間の婚姻についてはその保障が必要ない」との説明であるが、これは「同性間の婚姻に反対する立場の意見」というよりも、「婚姻」という枠組みを設けていることそれ自体による内在的なものである。
まず、人は何らの人的結合関係も形成しない中で各々が自由に生活している状態が基本となる。
そのような中、人間は有性生殖を行うことによって子孫を生むという身体機能を有しており、その男女の間で行われる「生殖」に関わって生じる不都合が社会的な課題となっていることから、この問題の解決を図るために、この「生殖」の仕組みに着目する形で一定の枠組みを設けることになる。
そして、その「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するための機能を持つ枠組みのことを「婚姻」と呼び、他の様々な人的結合関係との間で区別している。
これが、ここでいう「次世代に向けての子の育成の観点」も含む意味で「生殖機能に相違がある男女間」を対象とした制度として設けている理由である。
ただ、この「婚姻」という枠組みは、この婚姻制度を利用する場合に対して法的効果や一定の優遇措置(ここでいう『社会的な制度保障』)を設け、婚姻制度を利用しない場合には法的効果や優遇措置を与えないという差異を設けることによって、婚姻制度を利用することに対してインセンティブを生じさせ、それにより婚姻制度を利用する者を増やし、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成することを目指すものである。
そのため、婚姻制度の対象となっていない人的結合関係(『生殖』に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成するための手段として整合的な要素を満たさない人的結合関係)に対して同様の、あるいは類似の法的効果や優遇措置を設けた場合には、婚姻制度を利用することに対するインセンティブを低下させることに繋がり、婚姻制度を利用する者が減少する影響が生じ、婚姻制度の立法目的の達成を阻害する影響を与えることになる。
そのことから、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために婚姻制度という形で法的効果や一定の優遇措置を設けている以上は、婚姻制度を利用しない者や婚姻制度の対象となっていない人的結合関係には法的効果や優遇措置を与えないという差異が生じることはもともと予定されており、この差異によって婚姻制度を利用することに対してインセンティブを生じさせることを含む意味のものであることから、その差異を失わせる形で制度を組み立てたり、別の制度を設けることは本来的にできないものである。
よって、「生殖機能に相違がある男女間の婚姻についてのみ、次世代に向けての子の育成の観点から、社会的な制度保障をすることが相当であり、そうではない同性間の婚姻についてはその保障が必要ない」との説明の内容は、法制度として「婚姻」という枠組みを設けていることそれ自体を理由とする内在的なものであり、「同性間の婚姻に反対する立場の意見」のように、「賛成・反対」における「反対する立場の意見」の一つという位置づけで認識していることは誤りであるといえる。
「社会の制度については様々な意見があるところである。」との記載がある。
まず、裁判所は、立法府である国会や行政府である内閣以下の行政機関のように、国民の意見を集約する機関ではない。
裁判所は、法令の内容が合法であるか違法であるか、あるいは、合憲であるか違憲であるかしか判断する権限を有しておらず、その判断は条文に記された文言の意味を読み解くことによって規範の意味を明らかにし、結論を導き出すことが求められている。
それにもかかわらず、ここでは「社会の制度については様々な意見がある」のように、特定の政策や制度についての「意見」について論じ、その「意見」に対して反論することで、憲法24条の規範の意味を導き出そうとするものとなっている。
しかし、「社会の制度について」の「様々な意見」を集約することによって政策を行うのは立法府である国会や行政府である内閣以下の行政機関の役割であって、司法府である裁判所において判断することのできる対象ではない。
また、「社会の制度について」の「様々な意見」の中から「一つ」を取り出して、それに反論したとしても、そのことが法令を解釈する際の根拠となるというものではないのであり、それを根拠として憲法24条の規範の意味を明らかにすることができるかのように論じていることも誤りである。
「しかし、人が生まれながらに由来する自由と権利、これに係る個人の尊厳の実現には、家族とこれに対する社会的な制度の保障が不可欠であるといえるのであって、同性間で婚姻ができない不利益を解消する必要性は非常に高い。」との記載がある。
━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━
この文が読み取りづらい原因は下記の通りである。
◇ 「人が生まれながらに由来する自由と権利」との部分について、一見、主語は「人が」の部分であるように見える。
しかし、この文の中に「人が」の部分に対応する述語にあたるものが存在しない。
よって、「人が」に繋がる言葉が存在しておらず、意味を成さないものであることから、文の構造上は不要である。
その他、この文は、「人が生まれながらに『有する』自由と権利」と表記しようとしたところ、誤って「由来する」と表記してしまった可能性が考えられる。
ただ、いずれの読み方にせよ、この文の内容が誤っていることにより、読者は読み取りづらく感じるのである。
━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━
「人が生まれながらに由来する自由と権利」とある。
ここで示されている「自由と権利」は、「生まれながら」としていることから、「自然権」、「前国家的な権利」、あるいは「国家からの自由」という意味の「自由権」について述べるものといえる。
「人が生まれながらに由来する自由と権利、これに係る個人の尊厳」との部分について検討する。
まず、「個人の尊厳」とは、法的な主体となることのできる単位(『権利能力』を取得する単位)が「個人」を基本とすることを指す言葉である。
そして、人は「生まれながら」に「個人」であり、「個人の尊厳」を有している。
そのため、「人が生まれながらに由来する自由と権利」に「係る」(結び付く)形で「個人の尊厳」が存在するというのではなく、「人が生まれ」た時点でその者は法的な主体となる地位を取得して「個人」として扱われるという意味で「個人の尊厳」を有することになり、その「個人の尊厳」を起点として「自然権」や「前国家的権利」などと呼ばれる「国家からの自由」という「自由権」としての「生まれながらに由来する自由と権利」を得ていることになるという流れのものである。
そのため、「人が生まれながらに由来する自由と権利、これに係る個人の尊厳」のように、「生まれながらに由来する自由と権利」の後に「個人の尊厳」が結び付いてくるかのような説明は適切でない。
「人が生まれながらに由来する自由と権利」に「係る」形で「個人の尊厳」を位置付けることは、「自由と権利」が結び付く主体となる地位のことを「個人の尊厳」と述べているということを理解しないものであり、順序を誤っている。
よって、「人が生まれながらに由来する自由と権利、これに係る個人の尊厳」との説明は誤りである。
「人が生まれながらに由来する自由と権利、これに係る個人の尊厳の実現には、家族とこれに対する社会的な制度の保障が不可欠であるといえる」との部分について検討する。
ここでは「生まれながら」の「自由と権利」や「個人の尊厳」を実現するために、「家族とこれに対する社会的な制度の保障が不可欠である」と述べるものとなっている。
しかし、「生まれながら」の「自由や権利」とは、「自然権」や「前国家的権利」などと呼ばれる性質のものであり、国家による具体的な法制度の存在を前提としないものである。
また、この「生まれながら」の「自由と権利」の性質を適用する場面においても、これは「国家からの自由」という「自由権」の性質として、国家から個人に対して具体的な侵害行為があった場合に、その侵害を排除する場面において用いられるものである。
そのため、これによって具体的な制度の創設を国家に対して求めることができるというものではない。
それにもかかわらず、「生まれながら」の「自由や権利」を「実現」するために、「家族とこれに対する社会的な制度」による「保障が不可欠である」などと、具体的な制度によって「保障」することが「不可欠である」と述べていることは、「生まれながら」の「自由や権利」の性質そのものを理解していないものであり、誤った説明である。
「人が生まれながらに由来する自由と権利、これに係る個人の尊厳の実現には、家族とこれに対する社会的な制度の保障が不可欠である」とある。
まず、「家族」とは、「(2)ウ」の第三段落で説明したように、「夫婦」と「親子」による「血縁関係者」のことをいう。
そして、ここでは「家族とこれに対する社会的な制度の保障」を得ていない場合には、「人が生まれながらに由来する自由と権利」や「個人の尊厳」が「実現」されていないという認識を前提として、「家族とこれに対する社会的な制度の保障」を得ることによって初めて「人が生まれながらに由来する自由と権利」や「個人の尊厳」が「実現」されると考え、それが「不可欠である」と述べるものとなっている。
しかし、このような考えは「夫婦」や「親子」による「血縁関係者」がいない者について、「人が生まれながらに由来する自由と権利」を有しておらず「個人の尊厳」が「実現」されていないという認識を前提とし、そこで「家族とこれに対する社会的な制度の保障」と称するものによって初めて「人が生まれながらに由来する自由と権利」を取得し「個人の尊厳」が「実現」されると述べていることになる。
このような認識は、前提として「家族」のいない者について「人が生まれながらに由来する自由と権利」を有しておらず、「個人の尊厳」が「実現」されていないとの考えに基づくものとなっていることから、「家族」のいない者を物や動物、奴隷などと同様の「人」ではないものとして扱っていることになるのであり、極めて不当な認識である。
「家族」のいない者であるとしても、その者は「人」であり、「人が生まれながらに由来する自由と権利」を有しており、「個人の尊厳」も有しており、それは「実現」されている状態にあるといえる。
この札幌高裁判決は「家族」のいない者を「人」として扱わず、「人が生まれながらに由来する自由と権利」を有しておらず、「個人の尊厳」も有しておらず、それが「実現」されていない対象と見なすものとなっているという点で、誤りである。
また、憲法は「個人の尊厳」の原理に基づいており、自然人は「個人主義」の下に各々「自律的な個人」として生存していくことを予定していることから、何らの人的結合関係も形成していない者であっても「人が生まれながらに由来する自由と権利」を完全な状態で有しているし、「個人の尊厳」も有しており、それが「実現」されていない状態にあるとはいえない。
よって、ここで「家族とこれに対する社会的な制度の保障」と称するものによって「人が生まれながらに由来する自由と権利」を有することになるとか、「個人の尊厳」が「実現」されるという理解を前提としていることは、その前提となる認識を誤っている。
これとは別に、ここでは「個人の尊厳」の文言を、ある特定の制度を設けることが政策として望ましいと考える意味で用いようとしていることが考えられる。
しかし、どのような制度を設けることが政策として望ましいかということについては、「個人の尊厳」と述べるだけでは何らの結論を導き出すことができるものではない。
そのため、「個人の尊厳」を理由としてここでいう「同性間で婚姻」と称する特定の制度を立法することを正当化できるということにはならない。
このような意味で「個人の尊厳」という言葉を用いようとしているのであれば、同様に、一夫多妻制は「個人の尊厳」の実現に意義があるとか、婚姻制度を廃止することは「個人の尊厳」の実現に意義があるなど、様々な政策を「個人の尊厳」と述べるだけで同様に正当化することができてしまうことに繋がる。
すると、下記のようにあらゆる制度や政策について「個人の尊厳」と結び付けて論じることが可能となる。
・ 「個人の尊厳」の実現のため、近親者との婚姻を認めるべきである。
・ 「個人の尊厳」の実現のため、一夫多妻制を認めるべきである。
・ 「個人の尊厳」の実現のため、婚姻適齢を廃止するべきである。
・ 「個人の尊厳」の実現のため、一夫一婦制(男女二人一組)とするべきである。
・ 「個人の尊厳」の実現のため、離婚後は共同親権にするべきである。
・ 「個人の尊厳」の実現のため、離婚後は単独親権にするべきである。
・ 「個人の尊厳」の実現のため、選択的個人名制(夫婦別氏制)とするべきである。
・ 「個人の尊厳」の実現のため、好きな芸能人と同じ氏に変えられるべきである。
・ 「個人の尊厳」の実現のため、氏を廃止するべきである。
・ 「個人の尊厳」の実現のため、名も廃止するべきである。
・ 「個人の尊厳」の実現のため、貞操義務を廃止するべきである。
・ 「個人の尊厳」の実現のため、愛人を解禁するべきである。
・ 「個人の尊厳」の実現のため、婚姻制度は廃止するべきである。
・ 「個人の尊厳」の実現のため、戸籍制度を廃止するべきである。
・ 「個人の尊厳」の実現のため、自動車運転を免許制で規制するのは止めるべきである。
・ 「個人の尊厳」の実現のため、安楽死は認められるべきである。
・ 「個人の尊厳」の実現のため、銃器の所持は認められるべきである。
・ 「個人の尊厳」の実現のため、ドラッグは合法化するべきである。
・ 「個人の尊厳」の実現のため、ヘイト表現は規制するべきでない。
・ 「個人の尊厳」の実現のため、ヘイト表現は規制するべきである。
・ 「個人の尊厳」の実現のため、窃盗を犯罪化するべきではない。
・ 「個人の尊厳」の実現のため、窃盗を犯罪とするべきである。
・ 「個人の尊厳」の実現のため、仇討ちは許されるべきである。
・ 「個人の尊厳」の実現のため、………。
そのため、「個人の尊厳」を理由とする形で、特定の結論を導き出すことができるということにはならないのであり、これを述べたとしても、ここでいう「同性間で婚姻」と称する制度を設けることについて正当化できるということにはならないものである。
そもそも、望ましい政策を考えた結果として、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」を目的として、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす「一人の男性」と「一人の女性」の組み合わせを「貞操義務」など一定の形式で法的に結び付け、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によってそれらの目的の達成を目指すこととし、「婚姻」という枠組みが形成されているのである。
そのため、「個人の尊厳」という言葉を望ましい政策と考える旨として用いているのであれば、むしろ望ましい政策という意味で憲法上の立法政策として一夫一婦制(男女二人一組)による「婚姻」という枠組みを定めているということになるのであり、この枠を超える人的結合関係を「婚姻」とすることをその望ましい政策を意味する「個人の尊厳」という言葉によって正当化することができるとする理由にはならないものである。
よって、このような意味で「個人の尊厳」と述べているのであれば、それを基にここでいう「同性間で婚姻」と称する特定の制度を立法することを根拠付けることはできないのであり、その制度を立法していないことを指して憲法に違反すると結論付けようとしていることは誤りである。
さらに、「個人の尊厳」についてある特定の制度を設けることが政策として望ましいと考える意味で用いようとしているのであれば、そもそもどのような政策が望ましいかという問題については憲法の枠内で政治部門である国会で議論される事柄であり、法令の合憲・違憲、合法・違法しか判断することのできない裁判所の立場で論じてはならないものである。
この点について裁判所の立場で口出ししようとすることは、その主張そのものが越権行為であり、司法権の逸脱・濫用にあたるものといえる。
よって、この札幌高裁判決を書いた裁判官が特定の政策を実施することが望ましいと考える旨として「個人の尊厳」という言葉を用いているとしても、そこで示された内容や結論は正当化することができず、誤った判断であるといえる。
「同性間で婚姻ができない不利益を解消する必要性は非常に高い。」との部分について検討する。
まず、憲法は「個人の尊厳」の原理に基づいており、自然人は「個人主義」の下に「自律的な個人」として生存していくことを予定していることから、何らの制度も利用していない者の状態で既に完全な状態ということができ、「婚姻制度を利用していない者(独身者)」の状態が基準(スタンダード)となるものである。
そのため、「婚姻制度を利用していない者(独身者)」の状態について、何らの「不利益」と称されるものはない。
よって、ここで「婚姻ができない不利益」のように、「婚姻制度を利用していない者(独身者)」の状態について「不利益」があるとしていることは誤りである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
厚生労働省の調査によりますと、一人暮らしの世帯数は去年6月時点で1849万5000世帯と全体の34%を占めていて、統計を始めた1986年以来、過去最多となりました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「子どもいる世帯」約983万世帯で過去最少 「一人暮らし」は過去最多 厚生労働省 2024年7月5日
また、「不利益」があることを前提としてそれを「解消する必要性は非常に高い。」と述べている部分についても、そもそも「不利益」と称される状態にないことから、何も「解消する必要」はないし、その「必要性」が「高い」か低いかについても検討する前提を欠くものである。
ここである特定の形の法制度が定められていないという状態について「不利益」という言葉で表現している部分は、ある個人が特定の法制度を利用しようと考えた場合に、その個人にとってその法制度が自らの望む形で定められていないことを理由に思い通りとはならず、その法制度の利用を控えるという場合について、その者個人の受け止め方として「不利益」などと表現しているものを述べているものである。
しかし、法制度そのものは立法目的を達成するための手段として定められるものであり、制度が政策的なものである以上は、その制度が自らの望む形で定められていないことは当然起こり得ることである。
その状態を法的な視点から客観的に捉えた場合には、その者個人が「不利益」を受けているということになるわけではない。
そのため、このような言葉が用いられる背景には、法制度が自らの望む形で定められている状態を完全な状態として設定した上で、現在の法制度がその状態に至っていないという認識に基づいて、その完全な状態と設定したゴールまでの距離(その間の差の部分)を「不利益」と呼ぼうとする動機が含まれていることになる。
◇ この判決の認識
自らの望む法制度(ゴール)
↑
↑ (この差異を『不利益』と表現している。)
↑
現在地点
しかし、法的な視点から見れば、憲法は「個人の尊厳」の原理に基づいており、自然人は「個人主義」の下に各々「自律的な個人」として生存していくことを予定していることから、法制度を利用していない状態で既に完全な状態ということができ、そこに「不利益」は存在してない。
◇ 法律論として客観的な視点
現在地点 ← (法制度がない状態で既に完全であり、『不利益』は存在しない)
そのため、その者が「不利益」と表現している場合があるとしても、それは自らの望む形で法制度が定められている状態をゴールと考えることを前提とした上での、そのゴールと現在地点との間の距離について述べているものであり、その者個人が抱いている理想の法制度を前提とする主観的な思いを表現しているに過ぎないものである。
これについて、裁判所は法制度の性質について客観的な視点から論じることが必要であり、このような訴訟の当事者の一方が現在の法制度をどのように受け止めているかという主観的な立ち位置から見た場合の言葉遣いをそのまま受け入れて表現していることは適切ではない。
また、このような言葉を用いるか否かの判断の中には、その訴訟の当事者の一方が抱いている理想の法制度が定められている状態を完全な状態(目標地点・ゴール)として設定することを受け入れるか否かという隠れた論点が含まれている。
それを見抜くことができないままに、安易にこのような言葉を用いることは、その隠れた論点が表出しないままに、その訴訟の当事者の抱いている理想の法制度が定められている状態を完全な状態(目標地点・ゴール)として設定することを受け入れることを前提として論じていることになってしまう。
しかし、そのような前提となる状況認識の設定そのものが、法的な視点から客観性を保つ形で論じることのできていないものなのであり、これを前提として結論を導こうとすることは、判断の過程における中立性が損なわれていることとなる。
よって、裁判所の立場では、このような訴訟の当事者の一方が自己の主張を通すために行っている前提となる基準点(スタンダード)を移し替えた上で論じる表現をそのまま受け入れて用いることは適切ではない。
この論点について、国(行政府)の主張では下記のように説明されている。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
そうすると、原告らが本件規定により侵害されていると主張する権利又は利益は、憲法24条2項の要請に基づき、異性間の人的結合関係を対象とする婚姻について具体的な内容として定められた権利又は利益であり、結局のところ、これらが侵害されたとする原告らの主張の本質は、同性間の人的結合関係についても、異性間の人的結合関係を対象とする婚姻と同様の積極的な保護や法的な利益の供与を認める法制度の創設を国家に対して求めるものに他ならない。
従って、本件規定が「婚姻の自由」ないし婚姻に伴う種々の権利及び利益を奪うものとはいえないから、原告らの主張は理由がない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【東京二次・第5回】被告第3準備書面 令和4年6月20日
この札幌高裁判決では、このような前提となる状況認識の設定を誤ったことにより、誤った判断を導くこととなり、その結論も正当化できないものとなっている。
「そうすると、婚姻の制度について様々な考え方があり、生殖機能に相違がある男女間の婚姻について一定の意義を認めるにせよ、これを理由に、同性間の婚姻を許さないということにはならないというべきである。」との記載がある。
「そうすると、」とあるが、これは一文前の文を繋ぎ、その文の内容を理由としてこの文の示す結論が導き出されていることを示すものである。
しかし、一文前の文は、上記で述べたように、誤った認識を基にした説明となっている。
そのため、この誤った認識を「そうすると、」の文言で繋いだとしても、正しい結論を導き出すことができることにはならず、結果として、この文で示された結論を正当化することもできない。
「婚姻の制度について様々な考え方があり、」との部分について検討する。
まず、「婚姻」という名をもって指し示されている対象が存在する以上は、「婚姻」とそうでない物事が区別されていることを意味する。
そして、人間は有性生殖を行うことによって子孫を生むという身体機能を有しており、その男女の間で行われる「生殖」に関わって生じる不都合が社会的な課題となっていることから、この問題の解決を図るために一定の枠組みを設けることが求められ、その機能を持つ制度のことを「婚姻」と呼んでいる。
そのため、「婚姻」は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的と切り離して考えることはできない。
その具体的な内容は、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」を目的として、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす「一人の男性」と「一人の女性」を選び出し、その間に「貞操義務」を設けるなど一定の形式で法的に結び付け、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によってそれらの目的の達成を目指すものとなっている。
そのため、この「婚姻」という名をもって指し示されている対象について、氏の制度の在り方、財産関係の制度の在り方、扶養の制度の在り方、親権の制度の在り方などの個別の効果については「様々な考え方」があることはその通りであるといえる部分はあるとしても、この札幌高裁判決が論じている「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とする法律を立法することができるかという点については、そもそも「婚姻」という枠組みは「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた枠組みであり、その性質上内在的に一般的・抽象的に「生殖」の営みとの関係において定義される「男性」と「女性」の両方を必要としており、これを満たさない「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることができるというものではない。
よって、ここで「婚姻の制度について様々な考え方があり、」と述べている部分については、本来的に「婚姻」という「男性」と「女性」の両方を満たす人的結合関係についての枠組みが保たれている中において、氏の制度の在り方、財産関係の制度の在り方、扶養の制度の在り方、親権の制度の在り方などの個別の効果について「様々な考え方」があるとしても、この「婚姻」の中に「同性間の人的結合関係」を含めることができることを前提として、それを含めるか否かについてまで「様々な考え方」の中にあるものとして扱うことができるかのような前提で論じていることは誤りである。
言葉には一定の意味があるのであり、「婚姻」という言葉の意味を変えることまでをも、「様々な考え方」の中に含めて論じることができるというわけではない。
「生殖機能に相違がある男女間の婚姻について一定の意義を認めるにせよ、これを理由に、同性間の婚姻を許さないということにはならないというべきである。」との部分について検討する。
「生殖機能に相違がある男女間の婚姻について一定の意義を認める」とある。
まず、これは「生殖機能」という点に着目して法制度を定めることの「意義」を認めるものということができる。
つまり、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することの必要性に基づいて法制度が定められることの「意義」を認めるものといえる。
そして、「生殖機能に相違がある男女間」のように、「男女間」の「生殖機能」の「相違」に着目していることから、その「男女間」で「生殖」が行われることを想定する法制度を定めることの「意義」を認めるものである。
これは、単に女性が子供を出産するという点にのみ着目して法制度を定めるのではなく、女性が子供を産むことの原因となる子供の遺伝上の父親となる男性を特定することができる関係性に着目した形で、「男女間」を結び付ける法制度を定めることの「意義」を認めるものである。
このことから、この「生殖機能に相違がある男女間の婚姻について一定の意義を認める」という意味の中には、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によって立法目的の達成を目指す法制度を定めることの「意義」を認めるものということができる。
このようにして法制度が「生殖機能に相違がある男女間」という産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進する理由は、血縁関係を明確にする機能によって「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」という目的を達成することを目指すためである。
そしてこの仕組みを持つ法制度は、「生殖機能に相違がある男女間」に対して制度を設け、それ以外に対しては制度を設けないという差異を生じさせることによって、その制度を利用することに対してインセンティブを働かせ、その制度を利用する者を増やし、これらの目的を達成することを予定するものである。
そのため、「生殖機能に相違がある男女間の婚姻について一定の意義を認める」ことの内容として、「生殖機能に相違がある男女間」に対して制度を設け、それ以外の人的結合関係には制度を設けないという差異を生じさせることによって、その「男女間」の法制度を利用することに対してインセンティブを働かせ、その制度を利用する者を増やし、「生殖」により子供を持つことを希望する者が産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によって「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」という目的の実現を目指すという意味も含まれている。
そのことから、「生殖機能に相違がある男女間の婚姻について一定の意義を認める」ことの意味の中には、内在的に「生殖機能に相違がある男女間」とそれ以外の人的結合関係との間で差異を生じさせるために、「生殖機能に相違がある男女間」以外の人的結合関係には制度を設けないという意味まで含まれている。
よって、ここでは「生殖機能に相違がある男女間の婚姻について一定の意義を認めるにせよ、これを理由に、同性間の婚姻を許さないということにはならないというべきである。」と述べているが、「生殖機能に相違がある男女間の婚姻について一定の意義を認める」ことそのものによって、「生殖機能に相違がある男女間」以外の、その間で「生殖」を想定することができない「同性間」の人的結合関係に対して制度を設けないことの「理由」になるものであり、ここで「これを理由に、同性間の婚姻を許さないということにはならないというべきである。」と述べていることは、自ら述べている前提との間でも矛盾するものとなっており、誤りであるといえる。
オ 一部の自治体では同性間の婚姻についての不利益を緩和するためにパートナーシップ認定制度が設けられ、普及が進んでいる(認定事実(8)ア)。このことは、同性間で婚姻することができない場合に生じる不利益を一定程度緩和し、国民の間で同性婚に対して許容する程度が高まっていると評価することができる。しかし、パートナーシップ認定制度は、当該自治体による制度という制約があり、本件規定が異性間の婚姻以外について一切手当をしていないことに鑑みると、パートナーシップ認定制度により、同性婚ができないことによる不利益が解消されているということはできない。したがって、パートナーシップ認定制度の普及により、本件規定の見直しが不要になると解することはできない。
【筆者】
「一部の自治体では同性間の婚姻についての不利益を緩和するためにパートナーシップ認定制度が設けられ、普及が進んでいる」との記載がある。
ここでいう「同性間の婚姻」との文言は、前後に「一部の自治体」や「不利益を緩和する」や「パートナーシップ認定制度」との文言があることから、「同性間の人的結合関係」を形成することについて述べているものと思われる。
しかし、これを前提としてこの文を読み解いても、憲法は「個人の尊厳」の原理に基づいており、自然人は「個人主義」の下に各々「自律的な個人」として生存していくことを予定していることから、何らの制度も利用していない状態で既に完全な状態ということができ、その状態に「不利益」と称されるものは存在しない。
当然、その何らの制度も利用していない個々人が集まって人的結合関係を形成したとしても、そこに「不利益」が生じるということにはならない。
よって、「同性間の人的結合関係」を形成していることについて、「不利益」が存在することを前提として論じていることは誤りである。
また、「不利益」は存在しないため、その存在しない「不利益」は「緩和」することができないことから、「緩和するために」と述べていることも誤りとなる。
「一部の自治体では」「パートナーシップ認定制度が設けられ、普及が進んでいる」とある。
そこで、地方自治体の権限の範囲を確認し、この「パートナーシップ認定制度」の違法性について検討する。
憲法94条に定められている通り、地方自治体の「条例」は「法律の範囲内」でしか制定することができない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
〔地方公共団体の権能〕
第94条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
条例(条例の限界) Wikipedia
上乗せ条例 Wikipedia
横出し条例 Wikipedia
「国と地方の在り方(地方自治等)」に関する資料 衆議院憲法審査会事務局 平成29年4月 PDF (P15からは『条例制定権の限界』について)
そのため、地方公共団体の制定する「条例」や「規則」、「要綱」などを定める際には、国会の制定する法律の内容に違反してはならない。
下記で条例制定権の限界について示した判例を確認する。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
すなわち、地方自治法一四条一項は、普通地方公共団体は法令に違反しない限りにおいて同法二条二項の事務に関し条例を制定することができる、と規定しているから、普通地方公共団体の制定する条例が国の法令に違反する場合には効力を有しないことは明らかであるが、条例が国の法令に違反するかどうかは、両者の対象事項と規定文言を対比するのみでなく、それぞれの趣旨、目的、内容及び効果を比較し、両者の間に矛盾牴触があるかどうかによつてこれを決しなければならない。例えば、ある事項について国の法令中にこれを規律する明文の規定がない場合でも、当該法令全体からみて、右規定の欠如が特に当該事項についていかなる規制をも施すことなく放置すべきものとする趣旨であると解されるときは、これについて規律を設ける条例の規定は国の法令に違反することとなりうるし、逆に、特定事項についてこれを規律する国の法令と条例とが併存する場合でも、後者が前者とは別の目的に基づく規律を意図するものであり、その適用によつて前者の規定の意図する目的と効果をなんら阻害することがないときや、両者が同一の目的に出たものであつても、国の法令が必ずしもその規定によつて全国的に一律に同一内容の規制を施す趣旨ではなく、それぞれの普通地方公共団体において、その地方の実情に応じて、別段の規制を施すことを容認する趣旨であると解されるときは、国の法令と条例との間にはなんらの矛盾牴触はなく、条例が国の法令に違反する問題は生じえないのである。�
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
集団行進及び集団示威運動に関する徳島市条例違反、道路交通法違反 最高裁判所大法廷 昭和50年9月10日 (PDF) (徳島市公安条例事件)
この判例によれば、下記の場合には、違法となる。
◇ 「国の法令中にこれを規律する明文の規定がない場合でも、当該法令全体からみて、右規定の欠如が特に当該事項についていかなる規制をも施すことなく放置すべきものとする趣旨であると解されるとき」
◇ 条例の「適用によつて」、国の法令「の規定の意図する目的と効果を」「阻害する」場合
このことから、地方自治体の実施している「パートナーシップ認定制度」の内容が、民法で定められている婚姻制度に抵触している場合には違法となる。
そのため、婚姻制度の内容について検討する。
■ 婚姻制度の概要
「婚姻」は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために設けられた枠組みである。
これは、下記のような経緯によるものである。
その国の中で「生殖と子の養育」に関する事柄について何らの制度も存在しない場合には、社会的な不都合が発生することがある。
例えば、「父親不明」の子供が増える、父親を特定できない子供が増える、父親が蒸発して行方不明になった子供が増える、それらにより「子の福祉」が減少する、父親を特定できないことにより近親者の範囲を把握できずに「近親交配」に至り潜性遺伝子の発現した個体が高い確率で生じるようになる、一部の強者が多数人との生殖関係を独占することによって社会の中で「子を持ちたいと希望して相手を見つけようとする男女」の数の不均衡が生じて「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」が生まれる、低年齢での妊娠・出産により母体に危険が及ぶ、などの問題が生じることがある。
これらの不都合を解消するために、下記のような立法目的を有する枠組みを設けることが必要となる。
・「子の福祉」が実現される社会基盤を構築すること
・潜性遺伝子の発現した個体が高い確率で生じることを抑制すること
・「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」を減らすこと
・母体を保護すること
そして、これらの目的を達成するためには、目的との関係で整合的な下記の要素を満たす枠組みを設けることが必要となる。
・子の遺伝的な父親を特定できる組み合わせとすること
・特定された子の父親にも子に対する責任を担わせること
・特定された子の父親を基に遺伝的な近親者を把握すること
・未婚の男女の数の不均衡を防止できる組み合わせに限定すること
これらの要素を満たすものとして「一人の男性」と「一人の女性」が選び出され、その間に「貞操義務」を設け、その関係を法的に結び付ける形を「婚姻」と呼んでいる。
そして、この「婚姻」に対して法的効果や一定の優遇措置を設けることによって、制度を利用する者を増やし、これらの立法目的の実現を目指す仕組みとなっている。
■ 婚姻制度の「趣旨・目的・内容・効果」
婚姻制度は、「男性」と「女性」の間に「貞操義務」を設けることによって、その「女性」から生まれてくる子供の遺伝的な父親を特定することを重視するものとなってる。
これは、産まれてくる子供に対して、母親だけでなく、父親にも責任を担わせることによって、「子の福祉」の充実を期待するものとなっているからである。
子は何らの因果関係もなく突然「女性」の腹から生まれてくるわけではないため、その子が生じるという因果関係の一旦を担う父親に対してその子に対する責任を担わせる仕組みとすることは、逃れることのできない責任を有する者として合理的ということができるからである。
また、遺伝上の父親を特定できることは、遺伝上の近親者を把握することが可能となるため、その近親者との間で「婚姻」することができない仕組みを導入することで、「近親交配」に至ることを防止することが可能となる。
これによって、産まれてくる子供に潜性遺伝子が発現することを抑えることが可能となり、産まれてくる子に遺伝上の障害が生じるリスクを減らすこともできるからである。
他にも、婚姻制度の枠組みが「男女二人一組」となっていることは、その社会の中に男女がほぼ同数生まれているという前提の下では、未婚の男女の数に不均衡が生じることはないため、より多くの者に「子を持つ機会」を確保することを可能とするものとなっている。
その他、婚姻制度のもつ子供の遺伝上の父親を特定することができる形での「生殖」を推進する仕組みからは、婚姻制度を利用する形で子供を妊娠し、出産することを期待する(インセンティブを与える)ものとなっているが、その妊娠、出産に関して母体の保護の観点からリスクのある状態を推奨することはできないし、親となる者が低年齢のままに子を持つという責任を担う立場に置かれることを推進することも望ましくないことから、婚姻制度の利用に対して「婚姻適齢」という形で一定の年齢制限を設けるものとなっている。
これらの意図を満たす形で「男女二人一組」という枠組みを設定し、その婚姻制度の枠組みに従う者に対して、一定の優遇措置を講じることによって、婚姻制度の利用者を増やし、その立法目的を達成することを目指すものとなっている。
このことから、婚姻制度の「趣旨、目的、内容及び効果」を検討すると、婚姻制度の立法目的とその立法目的を達成するための手段の関係は下記のように整理することができる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
① 「子の福祉」が実現される社会基盤を構築すること
(→ 嫡出子として父親を特定することができる状態で生まれることを重視)
② 潜性遺伝子の発現した個体が高い確率で生じることを抑制すること
(→ 貞操義務と嫡出推定〔、再婚禁止期間〕によって遺伝的な父親を極力特定し、それを基に遺伝的な近親者を把握し、近親婚を認めないことによって『近親交配』に至ることを防止)
③ 「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」を減らすこと
(→ 未婚の男女の数の不均衡を防止できる組み合わせに限定。一夫一婦制。重婚や重婚状態、複婚や複婚状態の防止。)
④ 母体を保護すること
(→ 婚姻適齢を設定)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(婚姻制度の立法目的については、当サイト「同性婚について」で解説している。)
「パートナーシップ認定制度」の内容が、婚姻制度のこれらの目的を達成することを阻害する影響を与えるものとなっている場合には、民法の婚姻制度に抵触して違法となる。
■ 矛盾・抵触
▼ 婚姻制度の政策効果を阻害すること
▽ 子の福祉
婚姻制度は、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によって立法目的の達成を目指すものである。
つまり、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定し、母親だけでなくその者にも子に対する養育の責任を担わせることにより、「子の福祉」の実現を目指す仕組みとなっている。
しかし、産まれた子供の遺伝上の父親を特定することができない人的結合関係に対して何らかの優遇措置を設けた場合、婚姻制度の産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進する仕組みと矛盾することになり、この目的の達成を阻害する影響を与えることになる。
そのため、生まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができない人的結合関係に対して「パートナーシップ認定制度」を設けることは、婚姻制度に抵触して違法となる。
∵ 貞操義務
たとえ「パートナーシップ認定制度」の内容が「男女二人一組」の形であり、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる組み合わせとなっているとしても、そこに「貞操義務」が設けられていないのであれば、その制度を利用する女性は制度の内容に従って適法な行動をしたとしても、その制度を共に利用している相手方の男性とは異なる男性との間で「生殖」を行っている可能性を排除できていない状態ということになる。
これは結局、その女性から生まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができない状態であることに変わりはないことから、このような人的結合関係に対して何らかの優遇措置を設けることは、婚姻制度の立法目的を達成することを阻害する影響を与えるものとして、婚姻制度に抵触して違法となる。
▽ 近親交配の回避
婚姻制度は、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によって立法目的の達成を目指すものである。
その中に、遺伝上の父親を特定することによって近親者の範囲を把握し、その近親者との間では「婚姻」することができないことにすることで、「近親交配」に至ることを防ぎ、潜性遺伝子の発現した個体が高い確率で生じることを防ぐ仕組みがある。
しかし、「女性同士の組み合わせ」に対して何らかの優遇措置を設けた場合、遺伝的な父親を特定することができない関係の中で子供を産むことを促進する作用が生じ、遺伝的な近親者の範囲を把握することができない状態を推進することとなる。
そうなれば、子供の世代において意図せずに「近親交配」に至る確率が高くなり、婚姻制度が潜性遺伝子の発現した個体が高い確率で生じることを防ごうとする意図を達成することができなくなるのであり、婚姻制度の立法目的の達成を阻害することになる。
そのため、「パートナーシップ認定制度」を設けて、「女性同士の組み合わせ」(『女性三人以上の組み合わせ』であっても同様)が婚姻制度と同様、あるいは類似する優遇措置を得られるようにすることは、婚姻制度に抵触して違法となる。
【動画】【禁忌】近親相姦という聖域に踏み入った者たちの末路… 2022/03/11
▽ 生殖機会の公平
婚姻制度は、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によって立法目的の達成を目指すものである。
その中に、制度の内容を「男女二人一組」の形に限定することにより、「子を持ちたくても相手が見つからずに子を持つ機会に恵まれない者」が生じる子を抑制しようとする仕組みがある。
しかし、「パートナーシップ認定制度」を利用することで婚姻制度と同様、あるいは類似した優遇措置を得られることを理由として、同性間で「パートナーシップ認定制度」を利用する者が増えた場合には、制度を利用していない男女の数に不均衡が生じることとなり、「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」が増えることに繋がる。
これは、婚姻制度が「男女二人一組」の形に限定することによって、「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」を減らそうとする立法目的の達成を阻害する影響を与えることから、婚姻制度に抵触して違法となる。
▽ インセンティブの減少
婚姻制度は、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によって立法目的の達成を目指すものである。
このことから、婚姻制度を利用しない人的結合関係に対しては意図的に優遇措置を設けないことにより、「生殖」によって子供をつくろうとする者が婚姻制度を利用することによって遺伝的な父親を特定することができる人的結合関係を形成するようにインセンティブを与えるものとなっている。
しかし、国民が「パートナーシップ認定制度」を利用することにより、婚姻制度を利用した場合と同様、あるいは類似した優遇措置を得られることを理由に、婚姻制度を利用するのではなく「パートナーシップ認定制度」を利用することに安住してしまうことになれば、婚姻制度が遺伝的な父親を特定することができる状態を推進することによって達成しようとした立法目的の達成を阻害する影響を与えることになる。
そのため、婚姻制度の他に「パートナーシップ認定制度」を設け、婚姻制度と同様、あるいは類似した優遇措置を得られるようにすることは、婚姻制度の政策的な効果を弱める影響を与えるものとなることから、婚姻制度に抵触して違法となる。
▽ 母体の保護
上記のような問題により、婚姻制度が「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するための制度として十分に機能しないものとなると、その社会の中で人々が抱いている婚姻制度に対する信頼性が損なわれることになる。
すると、その社会の中で子を産むことを希望する者が次第に婚姻制度を利用しなくなっていき、婚姻制度が存在している意義そのものが希薄化していくことになる。
そうなると、婚姻制度を利用して子を持つという形を求める者が減少し、反対に、婚姻制度を利用しない形で「生殖」をしたり、子を持つ者が増加していくことになる。
すると、それまでは婚姻制度を利用する形で子供を妊娠し、出産することに対してインセンティブを与えていたことから、婚姻制度を利用して子を持つという形を求める者が多く、婚姻適齢に満たない者が「生殖」の営みに誘引される機会がそれなりに少ない社会状況を維持することができていたが、婚姻制度の価値や信頼性が損なわれている結果、婚姻制度を利用することについて十分なインセンティブが働かない状態となっていることから、婚姻制度を利用しない中で「生殖」を営み、子を持つ者が増加していくこととなり、その影響で婚姻適齢に満たない者が「生殖」の営みに誘引される機会も増加していくことに繋がる。
その結果、婚姻適齢に満たない若年の女性が「生殖」(性的な接触や性行為)に続いて、妊娠、出産のリスクを背負うことが増加し、「母体の保護」の観点から見れば望ましくない状態で妊娠、出産に至ることが抑制されなくなる。
また、低年齢のままに親として子を持つという責任を担う立場に置かれることも増加し、婚姻制度の政策的な効果が十分に機能していないことから父親が特定されていなかったり、知識レベルや経済力が十分でないままに子を育てるという過酷な状況に陥ることが抑制されなくなる。
このことは、「母体の保護」の観点や、倫理的な観点、望ましい社会の在り方を考える上で問題となる。
このように、「パートナーシップ認定制度」を設けることは、婚姻制度の政策効果を阻害することに繋がり、その結果、それまで人々が婚姻制度を利用することに対して魅力を感じていたことにより抑制されていた問題が表出することになる。
▼ 人の内心に着目した制度は立法することができないこと
「パートナーシップ認定制度」の中には、「性愛」という特定の思想や信条、信仰、感情を保護することを目的とするものや、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかによって区別取扱いをするものが存在する。
しかし、法制度は個々人の内心に対して中立的な内容でなればならないのであり、このような制度を設けることは許されない。
まず、「性愛」という特定の思想、信条、信仰を感情を保護することや、それを普及すること、また、理解を促進させるという目的をもって「パートナーシップ認定制度」を設けていることは、憲法20条1項後段・3項、89条の「政教分離原則」に違反することになる。
また、ある特定の「性愛」の思想、信条、信仰、感情を有する者を対象とし、それ以外の「性愛」を有する者や、「性愛」以外の思想、信条、信仰、感情を有する者を制度の対象としないというのであるから、個々人の内心に基づいて区別取扱いをする制度であるということになり、憲法14条1項の「平等原則」に違反することになる。
他にも、このような制度は、制度を利用する者の内心に干渉するものとなることから、憲法19条の「思想良心の自由」や憲法20条1項の「信教の自由」に違反することになる。
よって、個々人の内心に着目する形で定められている「パートナーシップ認定制度」は違憲となる。
▼ 24条の「婚姻」を離れて「生殖と子の養育」に関わる制度を立法することはできないこと
憲法24条の「婚姻」の文言は、「生殖と子の養育」に関わる制度を一元的に集約して規律する趣旨を有しており、もし「生殖と子の養育」に関わる制度を憲法24条の「婚姻」を離れて別の制度として立法した場合には、憲法24条の「婚姻」の文言に抵触して違憲となる。
なぜならば、憲法24条が「婚姻」の内容に対して立法裁量の限界を画することによって、法律上の「婚姻」の制度を規律しているにもかかわらず、その憲法24条の制約を回避する形で制度を立法することができることになれば、憲法24条の規定そのものが有する効力が損なわれた状態となり、憲法24条の規定が骨抜きとなるからである。
よって、「婚姻」が「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として、「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた枠組みである以上は、その「生殖と子の養育」に関わる制度については、憲法24条の「婚姻」の文言が一元的に集約して規律する趣旨を有しており、これを離れて「生殖と子の養育」に関わる制度を立法することはできない。
そのため、ここでいう「パートナーシップ認定制度」の内容が「生殖と子の養育」に関わる制度となっている場合や、「生殖と子の養育」に影響を与えることが考えられる制度となっている場合には、そのこと自体で憲法24条の「婚姻」に抵触して違憲となる。
▼ 制度を利用していない者との間の差異を正当化できないこと
婚姻制度が「男女二人一組」の形となっていることは、「一人の男性」と「一人の女性」の間に「貞操義務」を設けることで、その間で自然生殖が行われた場合に産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる組み合わせであることが理由である。
そして、父親を特定することによって「近親交配」に至ることを回避することが可能となるし、「男女二人一組」の形に限定している場合においては、未婚の男女の数に不均衡が生じることを防止することが可能となるため「生殖機会の公平」にも寄与することになる。
他にも、「婚姻適齢」を満たした者の間での「生殖と子の養育」であれば、「母体の保護」や「子育ての能力」の観点からも、一般には支障がないものと考えられる。
このため、「生殖と子の養育」の観点から「男性」と「女性」を「二人一組」の形で組み合わせることには必然性を見出すことができる。
よって、このような関係性を形成した者に対して一定の優遇措置を講じることは、その社会の中で「生殖」に関わって生じる不都合を解消するという目的の実現に資することから、「婚姻制度を利用している者(既婚者)」に一定の優遇措置を与えることについて「婚姻制度を利用していない者(独身者)」との間で生じる差異を正当化することができる。
しかし、「同性間の人的結合関係」については、その間で「生殖」を想定することができず、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で制度を設けるという目的からは導かれないものである。
そのため、「同性間の人的結合関係」に対して何らかの優遇措置を講じることは、その制度を利用しておらず、何らの人的結合関係も形成していない者との間で、得られる利益の内容に合理的な理由を説明することのできない差異を生じさせることになる。
よって、「同性間の人的結合関係」に対して「パートナーシップ認定制度」を設けることは、憲法14条の「平等原則」に抵触して違憲となる。
▼ 他の人的結合関係との間の差異を正当化できないこと
「パートナーシップ認定制度」は「二人一組」を対象とするものとなっている。
しかし、「同性間の人的結合関係」については、婚姻制度のように「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的との関係により一般的・抽象的にその間で自然生殖を想定することができる「男性」と「女性」の揃う「二人一組」を対象として枠組みを定めるという意図によって導き出されるものではない。
そのため、その内容を「二人一組」とする必然性もないのであり、なぜ「二人一組」であるのかその根拠を説明しない「カップル信仰論」に基づくものとなっている。
人的結合関係の中には、「三人一組」や「四人一組」、「それ以上の人的結合関係」も存在するのであり、「二人一組」だけを特別視して制度を設けていること自体についても、合理的な理由を説明することができないものであり、妥当でない。
■ 結論
上記のように、地方自治体の「パートナーシップ認定制度」の内容は、民法上の婚姻制度に抵触して違法、憲法上の規定に抵触して違憲な内容となっている。
よって、このような民法上の婚姻制度や憲法上の規定に抵触する論点を見ないままに、あたかも「パートナーシップ認定制度」が適法な制度であることを前提として論じていることは妥当でない。
詳しくは当サイト「パートナーシップ制度」で解説している。
その他、「パートナーシップ認定制度」は、憲法よりも下位の法形式として定められているか、あるいは法的な効力のないものであり、ここで憲法上の規定である24条の条文の意味を明らかにする解釈の過程で根拠とすることはできないものである。
よって、憲法24条の規定の意味を明らかにする解釈の過程で、「パートナーシップ認定制度」を持ち出していることそのものが誤りである。
「このことは、同性間で婚姻することができない場合に生じる不利益を一定程度緩和し、国民の間で同性婚に対して許容する程度が高まっていると評価することができる。」との記載がある。
「同性間で婚姻することができない場合に生じる不利益を一定程度緩和し、」との部分について検討する。
まず、憲法は「個人の尊厳」の原理に基づいており、自然人は「個人主義」の下に各々「自律的な個人」として生存していくことを予定している。
そのため、「婚姻していない者(独身者)」の状態で既に完全な状態ということができ、「婚姻していない者(独身者)」が基準(スタンダード)となるべきものである。
よって、「婚姻していない者(独身者)」の状態について「不利益」と称されるものは存在していない。
そのことから、「婚姻することができない場合」のように、「婚姻していない者(独身者)」がいるとしても、その状態について「不利益」と称されるものは存在していない。
また、「婚姻していない者(独身者)」が、ここでいう「同性間」のように何らかの人的結合関係を形成したとしても、その個々人が「婚姻していない者(独身者)」であることに違いはなく、そこに「不利益」と称されるものは存在していない。
よって、ここで「同性間で婚姻することができない場合に生じる不利益」のように、「婚姻していない者(独身者)」について「不利益」が生じているとの理解を前提とした説明は誤りとなる。
ここである特定の形の法制度が定められていないという状態について「不利益」という言葉で表現している背景には、ある者にとって法制度が自らの望む形で定められている状態を完全な状態と設定した上で、現在の法制度がその状態に至っていないという認識の下に、その完全な状態と設定したゴールまでの距離(その間の差の部分)を「不利益」と呼ぼうとする動機が含まれているといえる。
◇ この判決の認識
自らの望む法制度(ゴール)
↑
↑ (この差異を『不利益』と表現している。)
↑
現在地点
しかし、法的な視点から見れば、憲法は「個人の尊厳」の原理に基づいており、自然人は「個人主義」の下に各々「自律的な個人」として生存していくことを予定していることから、法制度を利用していない状態で既に完全な状態ということができ、「不利益」と称されるものは存在してない。
◇ 法律論として客観的な視点
現在地点 ← (法制度がない状態で既に完全であり、『不利益』は存在しない)
このことから、ある者が「不利益」と表現している場合があるとしても、それは自らの望む形で法制度が定められている状態をゴールと考えることを前提とした上での、そのゴールと現在地点との間の距離について述べているものであり、その者個人が抱いている理想の法制度を前提とする主観的な思いを表現しているに過ぎないものということになる。
しかし、そのことを法的な視点から客観的に考えると、そこに「不利益」と称されるものを認めることはできないのであり、ここである特定の形の法制度が定められていないという状態について「不利益」という言葉で表現していることは、法律論として客観的な視点から論じるものとはいえないものである。
よって、裁判所の立場では法制度の性質について客観的な視点から論じることが必要とされており、このような訴訟の当事者の一方が現在の法制度をどのように受け止めているかという主観的な立ち位置から見た場合の言葉遣いをそのまま受け入れて表現していることは適切ではない。
この判決の内容は、このような誤った前提認識を基にして論じていることにより、誤った結論を導くものとなっている。
その他、憲法は「個人の尊厳」の原理に基づいており、自然人は「個人主義」の下に各々「自律的な個人」として生存していくことを予定しており、その中で個々人が人的結合関係のを形成、維持、解消するなどしながら生活していくこと基本とし、その状態を基準(スタンダード)とするものとなっている。
そのような中、「婚姻」は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「生殖と子の養育」の観点からそれら他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度である。
具体的には、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」を目的とし、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす「一人の男性」と「一人の女性」の組み合わせに対して「貞操義務」を設けるなど一定の形式で法的に結び付け、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によってそれらの目的の達成を目指すものである。
そのため、婚姻制度の対象となる場合とならない場合の間に差異が生じることはもともと予定されていることである。
つまり、他の様々な人的結合関係の中から、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす人的結合関係を選び出し、その機能を果たすものとして対象となる範囲が予め指定されている枠組みのことを「婚姻」という名前でもって区別して把握している時点で、その対象となる場合とならない場合の間に差異が生じることはもともと予定されていることである。
また、もし「婚姻している者(既婚者)」と「婚姻していない者(独身者)」とを比べた場合に、「婚姻している者(既婚者)」が婚姻制度の立法目的を達成するための手段として不必要に過大な優遇措置を得るものとなっている場合には、「婚姻していない者(独身者)」が基準(スタンダード)となって、「婚姻している者(既婚者)」が得ている不必要に過大な優遇措置について定めた規定が個別に失効することによって格差が是正されることになる。
そのことから、「婚姻している者(既婚者)」と「婚姻していない者(独身者)」との間に差異がある場合には、「婚姻している者(既婚者)」の得ている優遇措置が減らされる方向で差異が是正されるのであり、「婚姻していない者(独身者)」に対して制度を設けなければならないということにはならない。
よって、ここで「婚姻している者(既婚者)」と「婚姻していない者(独身者)」との間に差異があることに着目して、それを「婚姻していない者(独身者)」に対して新たに「パートナーシップ認定制度」を設けることによって解決しようとする発想の下に論じていることは誤りである。
もう一つ、「男女二人一組」の婚姻制度については、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的との間で整合的な要素を満たすものとなっていることから、「婚姻している者(既婚者)」と「婚姻していない者(独身者)」との間で差異が生じることを正当化することができるといえる。
しかし、そのような目的によって導かれるものではない「同性間」の人的結合関係についての制度を設けることは、その制度を利用する者とその制度を利用していない者との間で生じる差異を正当化することができず、憲法14条1項の「平等原則」に違反することになる。
よって、「婚姻していない者(独身者)」については「不利益」といわれるものがないことは前提であるが、ここで「一定程度緩和し、」と述べている部分で「婚姻している者(既婚者)」と「婚姻していない者(独身者)」との間で生じている何らかの差異に着目してその差異を無くそうとする方法として「同性間」の人的結合関係を対象とした「パートナーシップ認定制度」を設けていることについても、その差異を解消する手段として誤った方法であり、結果として、「パートナーシップ認定制度」を利用していない者との間で生じる差異を正当化することができないものとして憲法14条1項の「平等原則」に違反するものとなっていることから、方法として誤っている。
「国民の間で同性婚に対して許容する程度が高まっていると評価することができる。」との部分について検討する。
ここでいう「同性婚」の意味が「同性間の人的結合関係」を形成することを指す場合には、それは憲法21条1項の「結社の自由」として保障されるものである。
これについては、「国民の間」でも「許容」されていると考えられる。
ここでいう「同性婚」の意味が「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを指すのであれば、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることができるかという部分から検討することが必要である。
「婚姻」とは、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた枠組みである。
具体的には、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」を目的として、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす「一人の男性」と「一人の女性」の組み合わせに対して「貞操義務」を設けるなど一定の形式で法的に結び付け、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によってそれらの目的の達成を目指すものである。
また、憲法24条は「婚姻」について「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めており、上記の趣旨に対応するものとなっている。
「同性間の人的結合関係」については、その間で「生殖」を想定することができず、上記の「生殖と子の養育」の趣旨を満たすものではなく、「婚姻」の中には含めることはできない。
また、憲法24条が「婚姻」について「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めている趣旨にも沿うものではないことから、「婚姻」とすることはできない。
よって、ここで「同性婚」のように「同性間の人的結合関係」を法的な意味で「婚姻」とすることができるかのような前提で論じていることは誤りである。
ここでは、「国民の間で同性婚に対して許容する程度が高まっている」と述べているが、法的な意味において「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることができないことはその時々の国民の意識の高まりや低下よって左右されるというものではないため、「国民の間」で「許容」する意識が「高まっている」としても、この結論が変わるということはない。
その他、憲法上の条文を解釈する過程では、憲法の条文の文言を読み解くことによって規範の意味を明らかにしなければならないのであって、「国民の間」で何かを「許容」する意識が「高まっている」かそうでないかという事柄によって左右されるものではないし、左右されるようなことがあってはならない。
よって、憲法24条の条文の解釈の過程で「国民の間で同性婚に対して許容する程度が高まっていると評価することができる。」などと、「国民の間で」「許容する程度」について論じていること自体が誤りである。
「しかし、パートナーシップ認定制度は、当該自治体による制度という制約があり、本件規定が異性間の婚姻以外について一切手当をしていないことに鑑みると、パートナーシップ認定制度により、同性婚ができないことによる不利益が解消されているということはできない。」との記載がある。
━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━
この文が読み取りづらい理由は、下記の通りである。
◇ この文は、「パートナーシップ認定制度」の話→「本件規定」の話→「パートナーシップ認定制度」の話のように、「パートナーシップ認定制度」の話が二回登場するが、それがまとめられていない。
これにより、意味を整理して読み取ることが難しくなっている。
そのため、下記のように並べ替える。
「しかし、」「本件規定が異性間の婚姻以外について一切手当をしていないことに鑑みると、」「パートナーシップ認定制度は、当該自治体による制度という制約があり、」「パートナーシップ認定制度により、同性婚ができないことによる不利益が解消されているということはできない。」
◇ この文は、「パートナーシップ認定制度は、当該自治体による制度という制約があり、」との文に続いて「本件規定が異性間の婚姻以外について一切手当をしていないことに鑑みると、」のように述べている。
これは、始めに「パートナーシップ認定制度」について「当該自治体による制度という制約」と述べていることから、その制度が適用される地域について説明するものとなっている。
そのため、それに続く話としては、その地域による制約と対比する形で「本件規定」が法律規定であることから全国で適用されることを述べようとしているのではないかと予想されるものとなっている。
しかし、「本件規定」について述べている部分を見ても、「本件規定が異性間の婚姻以外について一切手当をしていないこと」を述べているだけであり、ここでは「異性間の婚姻以外」の「手当」の存否に焦点が当たっているとはいえるが、具体的に「本件規定」が適用さる地域の話をしている部分はない。
よって、「当該自治体による制度という制約」という制度が適用される地域の話については未解決のままに話が進む印象を受けるものとなっている。
これにより、読み手はこの文がどの部分に焦点を当てて説明しようとしているのか掴むことができず、理解することができなくなってしまうのである。
━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━
まず、「パートナーシップ認定制度は、当該自治体による制度という制約があり、」との部分について検討する。
まず、地方自治体が実施する制度は、その地域の中で適用されるものとして定められる。
それぞれの自治体がそれぞれの自治体の事情に応じて制度を定めているだけであるから、その状態を法的な視点から客観的に見た場合には、「制約」という言葉を用いるような性質のものではない。
そのため、ここで「制約」という言葉を使って表現していることの背景には、ある者にとって法制度が自らの望む形で定められている状態を完全な状態と設定した上で、現在の法制度がその状態に至っていないという認識の下に論じようとする動機が含まれていると考えられる。
自らは、その地方自治体の地域を超えて制度を利用できることを望むが、そうなっていない状況を個人の受け止め方として「制約」と感じているから「制約」と表現しようというものである。
しかし、裁判所の立場では法制度の性質について客観的な視点から論じることが必要とされており、このような訴訟の当事者の一方が現在の法制度をどのように受け止めているかという主観的な立ち位置から見た場合の言葉遣いをそのまま受け入れて表現していることは適切ではない。
次に、「本件規定が異性間の婚姻以外について一切手当をしていないことに鑑みると、」との部分について検討する。
「異性間の婚姻」との文言がある。
ここでいう「異性間の婚姻」の意味が「異性間の人的結合関係」について述べているのであれば、「本件規定」は「異性間の人的結合関係」「以外」は対象としていないということができる。
ここでいう「異性間の婚姻」が「異性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを指しているのであれば、「婚姻」の意味との整合性が問われることになる。
「婚姻」とは、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」を目的として、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす「一人の男性」と「一人の女性」の間に「貞操義務」を設けるなど一定の形式で法的に結び付け、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によって立法目的の達成を目指すものとして形成されている。
そのため、「男性」と「女性」の組み合わせを備えない形で「婚姻」という概念は成立し得ない。
そのことから、「婚姻」であれば、そもそも「男女」という「異性間」のものを指すものということになる。
よって、この「異性間の婚姻」という言葉からは、あたかも「異性間の婚姻」と、「異性間」ではないそれ以外の「婚姻」というものが存在するかのような印象を受けるが、法的には「異性間」以外の「婚姻」は構成することができないものである。
また、「異性間の婚姻」という文言は、「異性間」という「男女」を指す言葉と、「婚姻」という「男女」間を指す言葉が同時に用いられていることになり、文法上は同義反復となるため誤用ということになる。
「本件規定」である婚姻制度は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」という目的の下に、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす「一人の男性」と「一人の女性」を選び出し、その間に「貞操義務」を設けるなど一定の形式で法的に結び付け、子供が産まれた場合にその子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によって立法目的の達成を目指すものである。
このため、婚姻制度は、その制度を利用する場合と利用しない場合との間に差異を設けることによって立法目的の達成を目指す仕組みであることから、この制度の意図する枠組みに当てはまらない場合に制度を設けないことはもともと予定されていることである。
そのため、ここでいう「異性間の婚姻」という「男女二人一組」の枠組み以外について「一切手当をしていないこと」は、もともと予定されているものである。
よって、「一切手当をしていないこと」のように、婚姻制度を定めている「本件規定」が、その婚姻制度の目的を達成するための手段として整合的でない人的結合関係に対してまで「手当」をしなければならないかのような前提で論じていることは誤った認識である。
「パートナーシップ認定制度は、当該自治体による制度という制約があり、本件規定が異性間の婚姻以外について一切手当をしていないことに鑑みると、パートナーシップ認定制度により、同性婚ができないことによる不利益が解消されているということはできない。」との部分を検討する。
この内容を読み解いても、憲法24条の解釈において関係性を認めることができないため、これを論じていること自体が誤りである。
まず、憲法24条の解釈において問われているのは、憲法24条の「婚姻」の枠組みが「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とする法律の立法を「要請」しているか否かである。
憲法24条の「婚姻」の枠組みがそれを「要請」しているのであればその制度がないことは違憲となり、憲法24条の「婚姻」の枠組みがそれを「要請」していないのであればその制度がないことは合憲となる。
そして、その解釈を行う際には、憲法の条文そのものを読み取ることによって、規範の意味を明らかにすることが必要である。
その解釈の過程において、地方自治体が実施する「パートナーシップ認定制度」という憲法よりも下位の法形式で定められている制度を持ち出して、それを根拠として憲法24条の規定の意味を明らかにすることはできない。
そのため、憲法24条の解釈が求められている中において、「パートナーシップ認定制度」を取り上げて論じていること自体が誤りである。
次に、「同性婚ができないことによる不利益が解消されているということはできない。」との部分であるが、憲法24条の解釈において問われているのは、憲法24条の「婚姻」の枠組みが「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とする法律を立法することを「要請」しているか否かであり、ここでいう「同性婚ができないこと」に「不利益」があるかが問われているわけではない。
そのため、ここで「不利益」があるかないかが問われているかのような前提で、「不利益が解消されている」か否かを判断することによって、結論を導き出すことができるかのように述べていることは誤りである。
三つ目に、憲法は「個人の尊厳」の原理に基づいており、自然人は「個人主義」の下に各々「自律的な個人」として生存していくことを予定していることから、「婚姻していない者(独身者)」の状態で既に完全な状態ということができ、そこに「不利益」と称されるものは存在していない。
そのため、ここで「同性婚ができないことによる不利益」のように、あたかも「婚姻していない者(独身者)」の状態について「不利益」が存在するかのような前提で論じていることは誤りである。
また、「不利益」は存在しないことから、それを「解消」しなければならないかのように述べている部分も誤りである。
その他、地方自治体の「パートナーシップ認定制度」は、憲法上の規定に抵触して違憲、法律により定められている婚姻制度に抵触して違法となる部分がある。
そのため、憲法の解釈が問われている中において、このような違憲・違法となる制度を取り上げて論じようとしていること自体が妥当でない。
「したがって、パートナーシップ認定制度の普及により、本件規定の見直しが不要になると解することはできない。」との記載がある。
まず、「したがって、」とあることから、前の文の「不利益が解消されているということはできない。」との部分を受けていることになる。
しかし、上記で述べたが、憲法は「個人の尊厳」の原理に基づいており、自然人は「個人主義」の下に「自律的な個人」として生存していくことを予定していることから、「婚姻制度を利用していない者(独身者)」の状態で既に完全な状態ということができる。
そのため、「婚姻していない者(独身者)」の状態が基準(スタンダード)であり、その「婚姻していない者(独身者)」の状態について「不利益」と称されるものはない。
また、「不利益」と称されるものは存在しないことから、「不利益」と称されるものがあることを前提とした上で、それを「解消」しなければならないとする部分も、その前提を欠くものである。
そして、この文は「したがって、」と前の文から繋ぐものとなっているが、前の文で「不利益」があることを前提に論じている部分が誤っていることから、その「不利益」を理由として「本件規定の見直し」が必要であることを前提とした上での、それが「パートナーシップ認定制度の普及」によって「不要になる」場合に当たるか否かを論じている部分は、そもそも「不利益」は存在しないため「本件規定の見直し」が必要であるという前提が誤っているため、それが「パートナーシップ認定制度の普及」によって「不要になる」場合に当たるか否かを論じる前提にないという点で誤っていることになる。
他にも、この憲法24条の解釈で問われているのは憲法24条の「婚姻」の枠組みが「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とする法律の立法を「要請」しているか否かである。
これは、憲法24条の「婚姻」の枠組みが「要請」しているのであればその制度が存在しないことは違憲であり、「要請」していないのであればその制度が存在しないことは合憲というものである。
これは憲法24条の条文そのものを読み解くことによって規範の意味を明らかにしなければならないものであり、「本件規定」である法律上の婚姻制度と、別の制度の効果を検討することによって憲法24条の「要請」の有無が変化するというものではない。
よって、ここで「パートナーシップ認定制度の普及により、本件規定の見直しが不要になる」か否かを論じることによって、合憲・違憲の結論を導き出すことができるかのように論じていることは誤りである。
地方自治体の「パートナーシップ認定制度」が憲法上の規定に抵触している場合は違憲、法律上の婚姻制度に抵触している場合は違法となる。
そのため、そもそも憲法24条1項の「婚姻」や2項の「婚姻及び家族」、14条1項の「平等原則」、19条の「思想良心の自由」、20条1項前段の「信教の自由」、20条1項後段・3項、89条の「政教分離原則」に抵触して違憲、また、法律上の婚姻制度に抵触して違法となる問題を抱えている制度を持ち出して、それを根拠として憲法24条の規範の意味を論じようとすることは正当化することができない。
また、「パートナーシップ認定制度」という下位法にあたる制度を持ち出して、その上位法である憲法上の規定の意味を明らかにしようとする試みていることについても、法秩序の階層構造を理解しないものであり、誤りである。
ここでは「パートナーシップ認定制度の普及により、本件規定の見直し」が必要か否かを論じるものとなっている。
しかし、「パートナーシップ認定制度」は「本件規定」である民法上の婚姻制度の立法目的の達成を阻害する影響を与えるものとなっており、婚姻制度に抵触して違法となる。
そのため、「本件規定」と「パートナーシップ認定制度」とを比較した場合、「本件規定」が上位法となることから、「見直し」が必要となるのは「本件規定」の方ではなく、「パートナーシップ認定制度」の方である。
よって、「パートナーシップ認定制度の普及により、本件規定の見直し」が必要などと、下位の法令によってその上位の法令を「見直し」させることができるかのように論じていることは誤りである。
カ 同性間で婚姻を認める場合であっても、制度の設計にはいくつかの考え方があり得るところである。例えば、パートナーシップ認定制度を設けたうえで、その状況を確認し、婚姻制度を設けるという考え方があるかもしれない。婚姻の制度は、夫婦のみならず、親子、相続等の民法の諸規定、これに関連する各種法令に及び、婚姻制度を設けるとしても、男女間の婚姻と全く同じにするか、さらには婚姻及び家族の法制度における数多くの個別の定めをどのように設計するかなど、検討すべき事項は多い。これらの事項は、法律の制定によるところであり、国会の裁量に委ねられることになり、その検討の過程を考慮する必要がある。しかしながら、同性間で婚姻ができないことによる著しい不利益が生じ、国民の多くが同性婚を容認し、海外でも同性婚を制度として定める国が多いという現状に鑑みれば、上記の制度設計について検討の過程が必要であることは、後述の国賠法1条1項の適用における事情としては考慮されるとしても、憲法違反に当たるかどうかという点では、本件規定が同性婚を一切許していない合理的な理由にはならないと解される。
【筆者】
「同性間で婚姻を認める場合であっても、制度の設計にはいくつかの考え方があり得るところである。」との記載がある。
ここでいう「同性間の婚姻」の意味が、「同性間の人的結合関係」を形成することを指すのであれば、それは憲法21条1項の「結社の自由」で保障されるものである。
これは憲法21条1項の「結社の自由」によって保障されている事柄であり、これが認められていないことを前提として「認める場合」について検討することは前提認識として誤りである。
その他、この憲法21条1項の「結社の自由」は、「国家からの自由」という「自由権」の性質であり、国家から個人に対する具体的な侵害行為があった場合に、その侵害を排除する場面で用いることはできるが、これを基にして特定の制度の創設を国家に対して求めることはできない。
そのため、憲法21条1項の「結社の自由」は、国会に対して「制度の設計」をするよう「要請」するものではなく、「制度の設計」をしなければならないとの前提が存在しない。
よって、「制度の設計にはいくつかの考え方があり得るところである。」のように、「制度の設計」をしなければならないかのような前提で論じていることは誤りとなる。
ここでいう「同性間の婚姻」の意味が、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを指すのであれば、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることができるかどうかから検討することが必要である。
「婚姻」とは、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた枠組みである。
具体的には、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」を目的として、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす「一人の男性」と「一人の女性」の組み合わせに対して「貞操義務」などの一定の形式で法的に結び付け、子供が産まれた場合にその遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によって立法目的の達成を目指すものである。
「同性間の人的結合関係」については、その間で「生殖」を想定することができず、この「生殖と子の養育」の趣旨を満たすものではないことから、「婚姻」とすることはできない。
よって、「同性間で婚姻を認める」ことができるかのように述べていることは誤りとなる。
また、その「同性間で婚姻を認める」ことができることを前提とした「制度の設計」をすることが可能であるかのように述べている部分も誤りとなる。
「例えば、パートナーシップ認定制度を設けたうえで、その状況を確認し、婚姻制度を設けるという考え方があるかもしれない。」との記載がある。
まず、ここでいう「パートナーシップ認定制度」が地方自治体の制度を指すのであれば、一段落前で説明したように、その制度は法律上の婚姻制度に抵触して違法、憲法24条の「婚姻」、20条1項後段・3項、89条の「政教分離原則」、19条の「思想良心の自由」、20条1項前段の「信教の自由」、14条1項の「平等原則」に抵触して違憲となるものである。
そのため、このような制度を設けることはできない。
よって、「パートナーシップ認定制度を設けたうえで、その状況を確認し、婚姻制度を設ける」のように、「パートナーシップ認定制度」を設けることができるかのように述べていることは誤りとなる。
ここでいう「パートナーシップ認定制度」が法律上の制度である場合には、法律上の婚姻制度が「生殖」によって子を持つことを希望する者が婚姻制度(男女二人一組)を利用する形で子を妊娠して出産することに対してインセンティブを与えることにより、遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によって「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」という目的を達成することを目指しているにもかかわらず、この「パートナーシップ認定制度」を設けたことによってその制度を利用することに対するインセンティブが働くこととなり、婚姻制度(男女二人一組)を利用しようするインセンティブが十分に働かなくなる影響を与えることになる。
これにより、婚姻制度(男女二人一組)が有する「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」という目的を達成しようとする機能を弱め、婚姻制度の政策的な効果を阻害する影響を与えることになる。
また、そもそも憲法24条の「婚姻」は「生殖と子の養育」に関わる制度を一元的に集約して規律する趣旨を有しており、憲法24条の「婚姻」を離れて別の制度として「生殖と子の養育」に関わる制度を立法することはできない。
そのため、ここでいう「パートナーシップ認定制度」を設けた場合には、「生殖と子の養育」に関わる制度や影響を与える制度となることが考えられ、それは憲法24条の「婚姻」が「生殖と子の養育」に関わる制度を「婚姻」として一元的に集約して規律する趣旨に反するものとなり、憲法24条の「婚姻」に抵触して違憲となる。
他にも、婚姻制度(男女二人一組)の場合には、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するための「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」という目的の実現に資することから、法的な効果や一定の優遇措置を設けているとしても、「婚姻制度を利用していない者(独身者)」との間で生じる差異を正当化することができるが、ここでいう「パートナーシップ認定制度」については、このような「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的の下に形成されるものではないことから、その制度を利用していない者との間で生じる差異を正当化することができず、憲法14条の1項の「平等原則」に違反することになる。
そのため、ここで「パートナーシップ認定制度を設けたうえで、その状況を確認し、婚姻制度を設ける」のように、「パートナーシップ認定制度」を設けることができるかのように述べているが、「パートナーシップ認定制度」を設けることは、婚姻制度(男女二人一組)の政策効果を阻害する影響を与えることになるため立法政策として矛盾のある制度を導入することはできないし、そもそも憲法24条の「婚姻」が「生殖と子の養育」に関わる制度を一元的に集約して規律している趣旨に反して違憲となるし、その制度を利用する者と利用しない者との間で生じる差異を正当化することもできないことから憲法14条1項の「平等原則」に違反することになるため、設けることはできない。
よって、「パートナーシップ認定制度」を設けることができることを前提に論じていることは誤りとなる。
「その状況を確認し、」との部分であるが、「パートナーシップ認定制度」を設けることは上記のように違憲・違法となるため、そのような制度を設けることはできず、「その状況を確認」することができるとする前提にないものである。
「婚姻制度を設けるという考え方があるかもしれない。」とあるが、ここでいう「婚姻制度」とは、「同性間の人的結合関係」を含む意味で用いようとしていると考えられる。
しかし、「婚姻」とは、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」を目的として、この目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす「一人の男性」と「一人の女性」の組み合わせを「貞操義務」などの一定の形式で法的に結び付け、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によって立法目的の達成を目指すものである。
そのため、この趣旨から導かれない「同性間の人的結合関係」は「婚姻」とすることはできない。
また、憲法24条は「婚姻」を規定しており、その内容も「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めている。
これも、上記の目的と、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たすことによるものである。
「同性間の人的結合関係」はこの趣旨を満たすものではないことから、「婚姻」とすることはできないし、もし法律上の婚姻制度の中に「同性間の人的結合関係」を含めようとした場合には、憲法24条が「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)の枠組みを定めることによって立法目的を達成することを定めている趣旨に反して違憲となる。
よって、「同性間の人的結合関係」を含む形で「婚姻制度を設ける」ことはできず、ここで「婚姻制度を設けるという考え方があるかもしれない。」のように「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることができるかのように述べていることは誤りとなる。
「婚姻の制度は、夫婦のみならず、親子、相続等の民法の諸規定、これに関連する各種法令に及び、婚姻制度を設けるとしても、男女間の婚姻と全く同じにするか、さらには婚姻及び家族の法制度における数多くの個別の定めをどのように設計するかなど、検討すべき事項は多い。」との記載がある。
「婚姻の制度」とあるが、それが「婚姻」である以上は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」を目的とし、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす「一人の男性」と「一人の女性」を選び出し、その間に「貞操義務」を設けるなど一定の形式で法的に結び付け、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によって立法目的の達成を目指す制度である。
ここで「夫婦のみならず、親子、相続等の民法の諸規定、これに関連する各種法令」と述べているものについても、その一夫一婦制(男女二人一組)によって立法目的の達成を目指す枠組みを前提とするものである。
これに対して、「同性間の人的結合関係」については、上記の「生殖と子の養育」の趣旨によって導かれるものではないことから、「婚姻」の中に含めることはできない。
そのため、その後「婚姻制度を設けるとしても、」のように、この「男性」と「女性」の両方が揃わない「同性間の人的結合関係」について「婚姻制度」として扱うことができることを前提として、この「夫婦のみならず、親子、相続等の民法の諸規定、これに関連する各種法令」との関係を検討し、「男女間の婚姻と全く同じにするか、さらには婚姻及び家族の法制度における数多くの個別の定めをどのように設計するかなど」を「検討すべき」としているが、そもそも「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることはできないため、「同性間の人的結合関係」を含む形で「婚姻制度を設ける」ことができるかのような前提で「婚姻制度を設けるとしても、」と述べていることは誤りである。
これにより、「同性間の人的結合関係」を含む形で「婚姻制度を設ける」ことができることを前提として「男女間の婚姻と全く同じにするか、さらには婚姻及び家族の法制度における数多くの個別の定めをどのように設計するかなど」を「検討すべき」としている部分についても誤りとなる。
「これらの事項は、法律の制定によるところであり、国会の裁量に委ねられることになり、その検討の過程を考慮する必要がある。」との記載がある。
まず、「婚姻」とは、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」を目的とし、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす「一人の男性」と「一人の女性」を選び出し、その間に「貞操義務」を設けるなど一定の形式で法的に結び付け、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によって立法目的の達成を目指す枠組みである。
憲法24条が「婚姻」を規定し、「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)の枠組みを定めていることについても、この趣旨に対応するものである。
そのため、「婚姻」という概念をこのような趣旨を離れて理解することはできなし、このような趣旨を離れて用いることもできないことから、この趣旨を満たさない人的結合関係を「婚姻」の中に含めることはできない。
「同性間の人的結合関係」についても、上記の趣旨を満たすものではないことから、「婚姻」とすることはできない。
もし「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とする法律を立法した場合には、「婚姻」という文言そのものに反するし、憲法24条の「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言に抵触して違憲となる。
ここでは「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とする法律を立法することができることを前提として、「法律の制定によるところ」や「国会の裁量に委ねられること」のように述べている。
しかし、「国会」であっても言葉の意味に反する法律を立法することはできないし、憲法24条が「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めている趣旨を満たさない人的結合関係を「婚姻」とする法律を立法する権限は有していない。
そのため、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」する法律を立法することについては、「国会の裁量に委ねられ」ているとはいえないし、その「法律の制定」は行うことができない。
よって、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とする法律を立法することができることを前提に「法律の制定によるところであり、国会の裁量に委ねられることになり、」と述べていることは誤りである。
他にも、憲法24条の「婚姻」の文言は、「生殖と子の養育」に関わる制度を一元的に集約して規律する趣旨を有しており、憲法24条の「婚姻」を離れて別の制度として「生殖と子の養育」に関わる制度を立法することはできない。
そのため、憲法24条の「婚姻」を離れて別の制度として「生殖と子の養育」に関わる制度を設けることは、憲法24条の「婚姻」に抵触して違憲となる。
そのことから、「同性間の人的結合関係」についての制度を設けた場合には、それは「生殖と子の養育」に関わる制度や影響を与える制度となることが考えられ、「国会」であってもそのような制度を立法することはできないため、これについて「国会の裁量に委ねられ」ているとはいえず、「法律の制定」をすることはできない。
さらに、婚姻制度(男女二人一組)については、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的との間で整合的な要素を満たすことから、「婚姻制度を利用している者(既婚者)」に対して法的効果や一定の優遇措置を設けることについて「婚姻制度を利用していない者(独身者)」との間で生じる差異を正当化することができるが、「同性間の人的結合関係」を対象とした制度については、そのような目的により導かれるものではないため、その制度を利用しない者との間で生じる差異を正当化することができず、憲法14条1項の「平等原則」に違反することになる。
そのため、このような問題が生じる「同性間の人的結合関係」を対象とした制度については、「国会」であっても立法する権限を有しておらず、これについて「国会の裁量に委ねられ」ているとはいえないし、「法律の制定」をすることができることにもならない。
よって、このような制度を立法することができるかのような前提で、「法律の制定によるところであり、国会の裁量に委ねられることになり、」と述べていることは誤りである。
「その検討の過程を考慮する必要がある。」との部分についても、そもそもそのような制度を立法することはできないことから、それができることを前提とした「検討の過程」について「考慮」する前提にないものである。
よって、「その検討の過程を考慮する必要がある。」と述べている部分も誤りである。
「しかしながら、同性間で婚姻ができないことによる著しい不利益が生じ、国民の多くが同性婚を容認し、海外でも同性婚を制度として定める国が多いという現状に鑑みれば、上記の制度設計について検討の過程が必要であることは、後述の国賠法1条1項の適用における事情としては考慮されるとしても、憲法違反に当たるかどうかという点では、本件規定が同性婚を一切許していない合理的な理由にはならないと解される。」との記載がある。
「同性間で婚姻ができないことによる著しい不利益が生じ、」との部分について検討する。
憲法は「個人の尊厳」の原理に基づいており、自然人は「個人主義」の下に「自律的な個人」として生存していくことを予定している。
そのため、何らの制度も利用していない状態で既に完全な状態ということができ、「婚姻制度を利用していない者(独身者)」の状態が基準(スタンダード)となるものである。
そのことから、「婚姻制度を利用していない者(独身者)」の状態について、それが何らかの「不利益」が生じている状態であるとはいえない。
よって、ここで「同性間で婚姻ができないことによる著しい不利益」のように、「婚姻制度を利用していない者(独身者)」の状態について「不利益」があるかのように述べていることは誤りである。
ここである特定の形の法制度が定められていないという状態について「不利益」という言葉で表現している部分は、ある個人が特定の法制度を利用しようと考えた場合に、その個人にとってその法制度が自らの望む形で定められていないことを理由に思い通りとはならず、その法制度の利用を控えるという場合について、その者個人の受け止め方として「不利益」などと表現しているものを述べているものである。
しかし、法制度は何らかの立法目的を達成するための手段として定められているものであり、その制度が自らの望む形で定められていないという事態は、制度が政策的なものである以上は当然起こり得ることである。
その状態を法的な視点から客観的に捉えた場合には、その者個人が「不利益」を受けているということにはならない。
結局、このような言葉が用いられる背景には、法制度が自らの望む形で定められている状態を完全な状態として設定した上で、現在の法制度がその状態に至っていないという認識に基づき、その完全な状態と設定したゴールまでの距離(その間の差の部分)を「不利益」と呼ぼうとする動機が含まれていることになる。
◇ この判決の認識
自らの望む法制度(ゴール)
↑
↑ (この差異を『不利益』と表現している。)
↑
現在地点
しかし、法的な視点から見れば、憲法は「個人の尊厳」の原理に基づいており、自然人は「個人主義」の下に各々「自律的な個人」として生存していくことを予定していることから、法制度を利用していない状態で既に完全な状態ということができ、そこに「不利益」と称されるものは存在してない。
◇ 法律論として客観的な視点
現在地点 ← (法制度がない状態で既に完全であり、『不利益』は存在しない)
そのため、その者が「不利益」と表現している場合があるとしても、それは自らの望む形で法制度が定められている状態をゴールと考えることを前提とした上での、そのゴールと現在地点との間の距離について述べているものであり、その者個人が抱いている理想の法制度を前提とする主観的な思いを表現しているに過ぎないものである。
これについて、裁判所は法制度の性質について客観的な視点から論じることが必要であり、このような訴訟の当事者の一方が現在の法制度をどのように受け止めているかという主観的な立ち位置から見た場合の言葉遣いをそのまま受け入れて表現していることは適切ではない。
また、このような言葉の中には、その訴訟の当事者の一方が抱いている理想の法制度が定められている状態を完全な状態(目標地点・ゴール)として設定することを受け入れるか否かという論点が隠されて含まれている。
それを見抜くことができないままに、安易にこのような言葉を用いることは、その隠された論点が表出しないままに、その訴訟の当事者の抱いている理想の法制度が定められている状態を完全な状態(目標地点・ゴール)として設定することをそのまま受け入れることを前提として論じていることになってしまう。
しかし、そのような前提となる状況認識の設定そのものが、法的な視点から客観性を保つ形で論じているものではないのであって、そのような認識を前提として結論を導こうとすることは、判断の過程における中立性が損なわれていることを意味する。
そのため、裁判所の立場では、このような訴訟の当事者の一方が自己の主張を通すために行っている前提となる基準点(スタンダード)を移し替えた上で論じる表現をそのまま受け入れて論じることは適切ではない。
この点で、言葉の選択に中立性が見られず、法的な視点で論じるというよりも、政治運動(社会運動)の中で用いられるような色の付いた言葉が残ったまま論じるものとなっており、法的な議論としてまとめる際に必要となる脱色がなされておらず、妥当でない。
この札幌高裁判決では、このような前提となる状況認識の設定を誤ったことにより、誤った結論を導くものとなっている。
「国民の多くが同性婚を容認し、」との部分について検討する。
「国民の多く」は「同性間の人的結合関係」を形成することそのものについては「容認」していると考えられる。
これは憲法21条1項の「結社の自由」によって保障されていることでもある。
しかし、「婚姻」とは、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」を目的として、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす「一人の男性」と「一人の女性」を「貞操義務」など一定の形式で法的に結び付け、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によって立法目的の達成を目指す枠組みである。
この「婚姻」の中にこの趣旨を満たさない「同性間の人的結合関係」を含めることはできない。
このことは、これは「国民」の賛否の数によって左右されるものではないことから、「国民の多く」が「容認」と述べたところでこの結論が左右されるということはない。
「海外でも同性婚を制度として定める国が多いという現状に鑑みれば、」との部分について検討する。
それぞれの国の法制度は、それぞれの国の社会事情の中で生じている不都合を解消することを目的として、その目的を達成するための手段として定められているものである。
そのため、外国の法制度と日本の法制度の間で何らかの類似点を見出すことができる場合があるとしても、それはそれぞれの国の社会事情の中で形成された別個の制度であり、同一の制度を指していることにはならない。
なぜならば、外国の法制度は、それぞれの国の社会事情の中で生じている問題を解消することを意図して構築されたものであり、その立法目的やその立法目的を達成するための手段・方法には様々な違いがあるからである。
ここでは「同性婚を制度として定める国」と述べられているが、外国語を翻訳する者が外国のある制度に対して「婚姻」という言葉を充てて説明しているとしても、それは日本国の法制度における「婚姻」と同一の制度を指していることにはならない。
そのため、外国の事例を取り上げたとしても、そのことが日本国の法制度に直接的な影響を与えることはないし、日本国の法制度における「婚姻」の中に「同性間の人的結合関係」を含めることができるとする根拠にもならない。
よって、「同性婚を制度として定める国が多い」と述べたところで、日本国の法制度における「婚姻」の中に「同性間の人的結合関係」を含めることができるとする根拠とはならない。
また、ここでは「同性婚」のように「同性間の人的結合関係」を対象とした法制度を設けている国を取り上げるのであるが、外国の中には「一人の男性と四人の女性まで」の「一夫多妻制」を採用している国もあるのであり、それらを出すことなく、「同性間の人的結合関係」を対象とした法制度を設けている国だけを持ち出して論じるものとなっていることも妥当でない。
「上記の制度設計について検討の過程が必要であることは、後述の国賠法1条1項の適用における事情としては考慮されるとしても、憲法違反に当たるかどうかという点では、本件規定が同性婚を一切許していない合理的な理由にはならないと解される。」との部分について検討する。
この文は読み取りづらいため、下記のように整理して考えると分かりやすい。
◇ 「後述の国賠法1条1項の適用における事情としては」「上記の制度設計について検討の過程が必要であることは、」「考慮されるとしても、」
◇ 「憲法違反に当たるかどうかという点では、」「上記の制度設計について検討の過程が必要であることは、」「本件規定が同性婚を一切許していない合理的な理由にはならないと解される。」
「上記の制度設計について検討の過程が必要であることは、……(略)……憲法違反に当たるかどうかという点では、本件規定が同性婚を一切許していない合理的な理由にはならないと解される。」と述べている。
これは、前提として「本件規定が同性婚を一切許していない」ことについて、「上記の制度設計について検討の過程が必要であること」を根拠として「憲法違反に当た」らないとの主張が存在していることを前提とし、それに対して反論する形で論じるものとなっている。
しかし、憲法24条の解釈における「憲法違反に当たるかどうか」の論点は、憲法24条の「婚姻」の枠組みが「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とする法律を立法することを「要請」しているか否かである。
これは、憲法24条の「婚姻」の枠組みがそれを「要請」しているのであればその制度がないことは違憲となり、憲法24条の「婚姻」の枠組みがそれを「要請」していないのであればその制度がないことは合憲というものである。
国(行政府)の説明では、下記の部分である。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
なお、被控訴人原審第2準備書面26ページにおいて述べたとおり、そもそも、憲法24条との関係で本件立法不作為が違憲であることが明白であるといえるためには、同条が同性問の婚姻を法制化することを国会に対して要請しているといえなければならず、同性婚が憲法上禁止されているか、又は許容されているのかという点は、原告らの憲法24条に関する主張の当否の判断において争点とはならないため、この点に関する回答は差し控える。また、憲法が同性問の婚姻を法制化することを国会に対して要請していないことは、控訴答弁書7ないし10ページにおいて述べたとおりである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【札幌・第2回】被控訴人回答書 令和4年3月4日 PDF
そして、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とする法律を立法することを「要請」していないため「憲法違反に当た」らないというものであり、そもそも「上記の制度設計について検討の過程が必要であること」を根拠として「憲法違反に当た」らないとの主張はなされておらず、それを前提として、それに対する反論を試みていること自体が誤りである。
そのため、「上記の制度設計について検討の過程が必要であることは、……(略)……憲法違反に当たるかどうかという点では、本件規定が同性婚を一切許していない合理的な理由にはならないと解される。」と述べていることは誤りとなる。
また、ここでは「合理的な理由にはならないと解される。」との結論を導き出す根拠として、「同性間で婚姻ができないことによる著しい不利益が生じ、国民の多くが同性婚を容認し、海外でも同性婚を制度として定める国が多いという現状」を「鑑み」るものとなっているが、そもそも「上記の制度設計について検討の過程が必要であること」を根拠として「憲法違反に当た」らないというものではないため、それが論点であることを前提として反論しようとしていることそのものが誤っているため、「鑑み」る前提を欠いており、これを論じていることも誤りである。
「本件規定が同性婚を一切許していない」とある。
この「同性婚」の意味が「同性間の人的結合関係」を形成することを指しているのであれば、それは憲法21条1項の「結社の自由」で保障されており、「本件規定」もそれを規制するものではないことから、それを「一切許していない」との説明は誤りである。
この「同性婚」の意味が「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを指しているのであれば、「本件規定」は「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを定めていないということができる。
ただ、これは法制度が定められているか否かの問題であるから、むやみに「許す・許さない」という意味での「許していない」という表現を用いることは適切ではない。
このような言葉遣いは、法制度の性質について客観的な視点から論じるものとして用いられる表現ではなく、別の個所で使われている「不利益」という文言などと相まって、訴訟の当事者の一方の見方や意見、感じ方に与する形で論じるものとなっていることが考えられる。
そのため、敢えてこのような表現を用いていることは、公的な性格を持ち、中立性が求められている裁判所の立場で論じる際の言葉の選択として妥当であるとはいえない。
「上記の制度設計について検討の過程が必要であることは、後述の国賠法1条1項の適用における事情としては考慮される」と述べている。
これは、「憲法違反に当たる」場合について、「国賠法1条1項の適用における事情として」「上記の制度設計について検討の過程が必要であること」が「考慮される」ことを述べるものである。
しかし、そもそも「婚姻」とは「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」を目的として、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす「一人の男性」と「一人の女性」に「貞操義務」を設けるなど一定の形式で法的に結び付け、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によって立法目的の達成を目指す枠組みである。
そして、憲法24条は「婚姻」を規定し、その内容も「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めており、この趣旨と対応するものとなっている。
そのことから、憲法24条の「婚姻」の枠組みは法律上の婚姻制度について一夫一婦制(男女二人一組)で定めることを「要請」するものであるが、それ以外の人的結合関係を「婚姻」とする法律を立法することを「要請」していない。
「同性間の人的結合関係」についても、憲法24条の「婚姻」の枠組みが「要請」するものではないため、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とする法律が存在しないことについて、憲法24条に違反するということにはならない。
よって、そもそも「憲法違反に当たる」とはいえないため、「国賠法1条1項」を「適用」する前提になく、「国賠法1条1項」が「適用」されることを前提として、「国賠法1条1項の適用における事情として」「上記の制度設計について検討の過程が必要であること」が「考慮される」ことを述べていることも誤りである。
婚姻と家族に係る法制度等は多種多様にわたり、法令上又は社会上定められている一部の規定においては、婚姻について、異性間の婚姻のみならず、同性間の婚姻を含むものと解することによって、同性婚ができない不利益を一定程度解消することができる。しかし、これも、個々の規定により保護されるにすぎず、本件規定が同性婚を許さないことの合理的な理由になるとは認められない。
【筆者】
「婚姻と家族に係る法制度等は多種多様にわたり、法令上又は社会上定められている一部の規定においては、婚姻について、異性間の婚姻のみならず、同性間の婚姻を含むものと解することによって、同性婚ができない不利益を一定程度解消することができる。」との記載がある。
「婚姻と家族に係る法制度等は多種多様にわたり、」との部分について検討する。
この「婚姻と家族」とは、裁判所が判決文の中で述べているものであることから、法的な意味で用いられる法制度としての「婚姻」と「家族」を指すものであり、これは憲法24条2項が定める「婚姻及び家族」の枠組みに対応するものといえる。
そして、この「婚姻と家族」の意味は、「(2)ウ」の第三段落で説明したように、「夫婦」と、「親子」による「血縁関係者」のことである。
そのため、「夫婦」と「親子」による「血縁関係者」に当てはまらない場合については、この「婚姻と家族」の中に含めることはできない。
「異性間の婚姻」との部分について検討する。
ここでは、「婚姻について、異性間の婚姻のみならず、」という文となっていることから、この「異性間の婚姻」の意味は、全体として「異性間の人的結合関係」を指しているように思われる。
しかし、「婚姻」の中に「異性間の人的結合関係」を含めることができるか否かを論じることは可能であるとしても、その「異性間の人的結合関係」のことを「異性間の婚姻」と表現することは、文面上は「婚姻」の中に「~~の婚姻」のように更に「婚姻」を含めることができるか否かを論じていることになるから、論理的に意味が通じないものとなる。
そのため、これは「異性間の人的結合関係」を「異性間の婚姻」と表現しているのであれば、それは端的に「婚姻」とはいえないという点で言葉の意味に反するものであり、言葉の置き換えを誤っているということができ、言語表現として不適切である。
また、仮に文言を誤っているわけではないという前提で内容を読み取ろうとすると、「婚姻」の中に「婚姻」を含めることができるか否かという意味の通じないことを述べていることになるのであり、論理的に誤っていることになる。
よって、いずれにせよ、この文は誤りであるということになる。
「同性間の婚姻」との部分について検討する。
ここでは「婚姻について、異性間の婚姻のみならず、同性間の婚姻を含むものと解することによって、」のように、「婚姻」の中に含めることができるか否かを論じる文となっていることから、「同性間の婚姻」の意味は「同性間の人的結合関係」を指しているように思われる。
しかし、「婚姻」の中に「同性間の人的結合関係」を含めることができるか否かを論じることそのものは可能であるとしても、文面上は「婚姻」の中に「~~の婚姻」を含めることができるか否かについて論じるものとなっていることから、「婚姻」の中に更に「婚姻」を含めることができるか否かを問うものとなっており、論理的に考えると意味の通じない文章となっている。
そのため、これは「同性間の人的結合関係」のことを「同性間の婚姻」と表現しているのであれば、それは端的に「婚姻」とはいえないものであって、言葉の意味に反するものであり、言葉の置き換えとして誤っているということができ、言語表現として不適切である。
また、仮に文言を誤っているわけではないという前提で文を読み取ろうとすると、「婚姻」の中に「婚姻」を含めることができるか否かという意味の通じないことを述べていることになり、論理的な部分が誤っていることになる。
よって、いずれにせよ、この文は誤りであるということになる。
その他、ここで「同性間の婚姻」と述べたり、「婚姻」の中に「同性間の人的結合関係」を「含むものと解すること」ができるかのように述べているが、その前に「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることができるかという点を検討することが必要である。
「婚姻」は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた枠組みである。
具体的には、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」を目的として、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす「一人の男性」と「一人の女性」の組み合わせに対して「貞操義務」を設けるなど一定の形式で法的に結び付け、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によって立法目的の達成を目指すものである。
「同性間の人的結合関係」については、その間で「生殖」を想定することができず、この「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成するための手段として整合的な要素を満たすものではないことから、「婚姻」の中に含めることはできない。
よって、「同性間の婚姻」のように「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることができるかのような論じ方をしている部分や、「婚姻」の中に「同性間の人的結合関係」を「含むものと解すること」が可能であるかのような論じ方をしていることは、誤りである。
「婚姻と家族に係る法制度等は多種多様にわたり、法令上又は社会上定められている一部の規定においては、婚姻について、異性間の婚姻のみならず、同性間の婚姻を含むものと解することによって、」との部分について検討する。
まず、「婚姻と家族に係る法制度等」として「法令上又は社会上定められている」「規定」は、「婚姻」の立法目的を達成するための手段として整合的な形で定められているものである。
また、これは「婚姻」の立法目的を達成するための手段として整合的な範囲内でのみ正当化することが可能なものである。
なぜならば、もし「婚姻」の立法目的を達成するための手段として不必要に過大な優遇措置を与えるものとなっていた場合には、「婚姻制度を利用していない者(独身者)」との間で合理的な理由を説明することのできない差異を生じさせるものとして、憲法14条1項の「平等原則」に違反し、その不必要に過大な優遇措置について定めている「規定」が個別に失効することによって格差が是正されることになるからである。
そのため、「婚姻と家族に係る法制度等」として「法令上又は社会上定められている」「規定」であれば、「婚姻と家族」の枠組みに含まれている「夫婦」と「親子」による「血縁関係者」を対象とした「規定」なのであり、その「婚姻」に対して設けられている「法令上又は社会上定められている」「規定」を「婚姻」の中に含めることのできない「同性間の人的結合関係」に対して適用することはできない。
もし「婚姻と家族」を対象とした「規定」をその「婚姻と家族」に含まれない場合にも適用しようとした場合には、法令の内容に違反するものであるから、違法となるものである。
よって、ここで「同性間の人的結合関係」に対して、「婚姻と家族に係る法制度等」の「婚姻」として「法令上又は社会上定められている一部の規定」を適用することができるかのような論じ方をしていることは誤りである。
「同性婚ができない不利益を一定程度解消することができる。」との部分について検討する。
「同性婚」の意味が「同性間の人的結合関係」を形成することを指しているのであれば、それは憲法21条1河野「結社の自由」として保障されている。
そのため、これが「できない」ということはなく、これが「できない」と述べていることは誤りとなる。
また、それが「できない」ことを前提として「不利益」と考えたり、それを「解消することができる。」か否かを検討することも誤りである。
「同性婚」の意味が「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを指しているのであれば、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることができるかどうかという点から検討する必要がある。
「婚姻」は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」を目的として、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす「一人の男性」と「一人の女性」を選び出し、その間に「貞操義務」を設けるなど一定の形式で法的に結び付け、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によってその目的の達成を目指す枠組みである。
「同性間の人的結合関係」は、その間で「生殖」を想定することができず、この「生殖と子の養育」の趣旨を満たすものではないことから、「婚姻」の中に含めることはできない。
そのため、ここでいう「同性婚」の文言は、法的には「同性間の人的結合関係」を「婚姻」として構成することはできないことから、法律論としては成立しないものである。
よって、「同性婚ができない」という部分は、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることはできないという意味ではその通りであるとしても、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることができるかのような前提で「同性婚」という言葉を用いているとすれば誤りとなる。
「同性婚ができない不利益」とある。
憲法は「個人の尊厳」の原理に基づいており、自然人は「個人主義」の下に「自律的な個人」として生存していくことを予定していることから、何らの制度も利用していない者の状態で既に完全な状態ということができる。
そのため、その何らの制度も利用していない者の状態について、「不利益」と称されるものは存在しない。
そのことから、ここで「同性婚ができない不利益」と述べているが、これは単に何らの制度も利用していない者の状態について述べているに過ぎないのであり、そこに「不利益」と称されるものは一切存在しない。
よって、「同性婚ができない不利益」と述べていることは、何らの制度も利用していない者の状態について「不利益」と考えるものとなっている点で誤りである。
その後、「不利益を一定程度解消することができる。」と述べている部分についても、そもそも「不利益」な状態にあるとはいえないことから、それを「解消する」という前提にないものであり、「一定程度解消することができる。」か否かを論じていることそのものが誤りである。
その他、婚姻制度は、人が何らの人的結合関係も形成しておらず、何らの制度も利用していない状態を基準(スタンダード)となっている中で、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」を目的として、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす「一人の男性」と「一人の女性」を選び出し、その間に「貞操義務」を設けるなど一定の形式で法的に結び付け、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によってその目的を達成することを目指すものとして形成されているものである。
そのため、「婚姻している者(既婚者)」と「婚姻していない者(独身者)」とを比べて、「婚姻している者(既婚者)」が婚姻制度の立法目的を達成するための手段として不必要に過大な優遇措置を得ている場合には、何らの制度も利用していない者である「婚姻していない者(独身者)」を基準(スタンダード)として、婚姻制度における過大な優遇措置に関する規定を個別に失効させることによって格差を是正することになるものである。
そのことから、「婚姻している者(既婚者)」と「婚姻していない者(独身者)」との間で何らかの差異があるとしても、それは「婚姻していない者(独身者)」が基準(スタンダード)となって、「婚姻している者(既婚者)」の得ている法的効果や優遇措置が減らされる方向で差異が是正されるのであり、「婚姻していない者(独身者)」に対して制度を設けなければならないということにはならない。
よって、ここで「法令上又は社会上定められている一部の規定」を「婚姻していない者(独身者)」に対して適用することによって差異を解消しようとする方法について論じていることは誤りである。
「しかし、これも、個々の規定により保護されるにすぎず、本件規定が同性婚を許さないことの合理的な理由になるとは認められない。」との記載がある。
これは一つ前の文との関係で、「本件規定が同性婚を許さないこと」が憲法に違反しないことの理由として、「婚姻について」の「法令上又は社会上定められている一部の規定」を「異性間の婚姻のみならず、同性間の婚姻を含むものと解することによって、同性婚ができない不利益を一定程度解消することができる。」と述べられていることを前提として、それに反論する形で論じるものである。
しかし、そもそも「婚姻について」の「法令上又は社会上定められている一部の規定」を「異性間の婚姻のみならず、同性間の婚姻を含むものと解することによって、同性婚ができない不利益を一定程度解消することができる。」ことを理由として憲法に違反しないとの主張は存在しておらず、そのような主張が存在することを前提として、それに対して反論を試みていることそのものが誤りである。
また、「婚姻について」の「法令上又は社会上定められている一部の規定」を「異性間の婚姻のみならず、同性間の婚姻を含むものと解すること」は、婚姻制度(異性間)を対象とした「法令上又は社会上定められている」「規定」であるにもかかわらず、その対象ではない「同性間」に対しても適用しようとするものであるから、条文の内容に反する形で法制度を適用しようとするものであり、違法な手続きである。
そのため、「法令上又は社会上定められている」「規定」が「婚姻」(異性間)を対象として定められている以上は、それを「同性間」を「含むものと解すること」はできない。
そのことから、その違法な手続きが行われた上で憲法に違反しないとする主張が存在していることを前提として、それに対して反論を試みるものとなっているが、そもそも法の支配、法治主義の観点から、違法な手続きを行うことはできないという点を指摘する必要があり、それを無視して「これも、個々の規定により保護されるにすぎず、」のようにそのような不正な手続きにより「保護される」ことを前提に論じていることは、不正な手続きに加担するものとなっており、この点でも誤りである。
他にも、婚姻制度は、何らの制度も利用していない者を基準(スタンダード)となっている中で、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために形成された枠組みであり、もし「婚姻制度を利用している者(既婚者)」が婚姻制度の目的を達成するための手段として不必要に過大な優遇措置を得ている場合には、何らの制度も利用していない「婚姻制度を利用していない者(独身者)」を基準(スタンダード)として、その不必要に過大な優遇措置に関する規定が個別に失効することによって格差が是正されることになるものである。
そのため、「婚姻制度を利用している者(既婚者)」と「婚姻制度を利用していない者(独身者)」との間で何らかの差異があるとしても、その差異を是正する場合には「婚姻制度を利用していない者(独身者)」が基準(スタンダード)となって、「婚姻制度を利用している者(既婚者)」の得ている法的効果や優遇措置が減らされる方向で格差が是正されることになるものである。
よって、ここで「個々の規定により保護されるにすぎず、」のように、「婚姻していない者(独身者)」に対して「個々の規定により保護」することによって差異を解消しようとする方法について論じていることは誤りである。
また、その誤った方法を根拠として、それが「合理的な理由になる」か否かを論じていることも、そもそも基準(スタンダード)を誤った議論に基づくものであるから誤りである。
さらに、憲法24条の解釈で問われているのは、憲法24条の「婚姻」の枠組みが「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とする法律を立法することを「要請」しているか否かであり、「合理的な理由」の存否が問われるというものではないため、ここで「合理的な理由」の存否について検討していることそのものが誤っており、これを述べたとしてもこれによって憲法に違反するか否かの結論を導き出すことには繋がらないものである。
キ 以上の点を総合的に考慮すると、本件規定は、異性間の婚姻のみを定め、同性間の婚姻を許さず、これに代わる措置についても一切規定していないことから、個人の尊厳に立脚し、性的指向と同性間の婚姻の自由を保障するものと解される憲法24条の規定に照らして、合理性を欠く制度であり、少なくとも現時点においては、国会の立法裁量の範囲を超える状態に至っていると認めることが相当である。
【筆者】
「以上の点を総合的に考慮すると、」との部分について検討する。
憲法24条の論点で問われるのは、憲法24条の「婚姻」の枠組みが「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とする法律を立法することを「要請」しているか否かである。
憲法24条の「婚姻」の枠組みがそれを「要請」しているのであればその制度が存在しないことは違憲となり、憲法24条の「婚姻」の枠組みがそれを「要請」していないのであればその制度が存在しないことは合憲というものである。
そして、憲法24条の「婚姻」とは、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた枠組みである。
具体的には、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」を目的として、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす「一人の男性」と「一人の女性」の組み合わせを「貞操義務」など一定の形式で法的に結び付け、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態とすることを推進し、血縁関係を明確にする機能によって立法目的の達成を目指すものである。
また、憲法24条でも「婚姻」について「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いており、このような目的とその目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす一夫一婦制(男女二人一組)を定めるものとなっている。
しかし、「同性間の人的結合関係」については、その間で「生殖」を想定することができず、この「生殖と子の養育」の趣旨を満たすものとはいえないことから、「婚姻」とすることはできない。
そのため、憲法24条の「婚姻」という概念そのものや、そこで「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言が一夫一婦制(男女二人一組)を定めている枠組みは、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とする法律を立法することを「要請」しているとはいえず、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とする法律が存在しないことが憲法24条に違反することはない。
これに対し、ここでは「以上の点を総合的に考慮すると、」のように述べて、これ以前のところで述べている下記の点を「考慮」して憲法24条に違反するか否かを検討しようと試みるものとなっている。
(4)
「本件規定の憲法24条適合性について検討する。」
ア
「アイデンティティの喪失感を抱いたり、自身の存在の意義を感じることができなくなったり、個人の社会的な信用、評価、名誉感情等を維持することが困難になったりするなど、個人の尊厳を成す人格が損なわれる事態となってしまっている。」
イ
「同性間の婚姻について社会的な法制度を定めた場合の不利益・弊害を検討すると、社会的な影響を含め、社会上の不利益・弊害が生じることがうかがえない。」
「同性婚を認めることは、」「相応の人数に達する同性愛者に対する権利を保障し、個人として尊重することに意義を有するものと考えられる。」
ウ
「昨今の社会の流れ」
・「同性婚が可能となった国・地域は30を超えている」
・「国連自由権規約人権委員会は、」「指摘した」
・「同性婚の制度や判例法理を確立させ、あるいはこれに準ずる登録パートナーシップ制度を導入する諸外国が多数ある」
・「地方公共団体」「においてパートナーシップ認定制度を導入し、その人ロカバー率は65%に達している」
・「同性婚の法制化に賛同する企業の可視化に加わる企業や団体は、現在360を超えている」
・「日本家族〈社会と法〉学会や日本学術会議は、同性婚規定の新設提案や民法改正の提言を発表している」
・「国民に対する各種調査においても、同性婚を認める回答が増加しており、最近では、ほぼ半数を超える国民が同性間の婚姻を容認すると回答している」
・「最新の新聞社による世論調査では、同性婚を容認するとの回答は最低54%から、最高は72%に達しており」
・「国会においても同性婚の法制化につき議論がされるようになってきている」
エ
「同性間の婚姻に反対する立場の意見を検討する。」
・「同性愛に対する違和感、これが高じた嫌悪感、偏見を持つ場合があると考えられる。」
→ 「感覚的、感情的な理由にとどまるものといえ、」「啓蒙活動によって、」「解消していく可能性がある。」
・「男女間の婚姻についてのみ、次世代に向けての子の育成の観点から、社会的な制度保障をすることが相当」
→ 「人が生まれながらに由来する自由と権利、これに係る個人の尊厳の実現には、家族とこれに対する社会的な制度の保障が不可欠であるといえる」
→ 「男女間の婚姻について一定の意義を認めるにせよ、これを理由に、同性間の婚姻を許さないということにはならないというべきである。」
オ
「一部の自治体では」「パートナーシップ認定制度が設けられ、普及が進んでいる」
「パートナーシップ認定制度の普及により、本件規定の見直しが不要になると解することはできない。」
カ
「国民の多くが同性婚を容認し、海外でも同性婚を制度として定める国が多いという現状に鑑みれば、」「制度設計について検討の過程が必要であることは、」「憲法違反に当たるかどうかという点では」「合理的な理由にはならないと解される。」
しかし、それぞれの項目で説明したように、これらはいずれも憲法24条の「婚姻」の枠組みが「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とする法律を立法することを「要請」しているとする根拠となるものではない。
よって、これら「の点を総合的に考慮する」ことによって、次の段落の「憲法24条に違反する。」との結論が導き出されるかのように述べていることは誤りである。
「以上の点を総合的に考慮すると、」との文言は、「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」の「第4 上告理由のうち本件規定が憲法24条に違反する旨をいう部分について」の「4(1)ウ」で「以上の点を総合的に考慮すると,」と述べている部分と言い回しが同じである。
しかし、この札幌高裁判決で問われている事柄は、「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」で問われている事柄とは異なっているため、同じ言い回しを使って説明することができるという前提にないものである。
まず、憲法24条の「婚姻」の規定は、「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)の枠組みを定めており、この枠組みによって「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成することを目指すことを「要請」しており、この「要請」に従って法律上の具体的な制度として婚姻制度が定められることになるが、その婚姻制度の枠組みに付随して設けられる細目的な内容について、2項は「個人の尊厳」と「両性の本質的平等」を満たすようを求めるものとなっている。
そして、「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」は、憲法24条が「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)の枠組みを定めており、その「要請」に従って法律上で婚姻制度が一夫一婦制(男女二人一組)で定められていることを前提とし、その婚姻制度(男女二人一組)の枠組みに付随する形で設けられている「夫婦同氏制」に関する規定が「個人の尊厳」と「両性の本質的平等」を満たすか否かについて問われた事案である。
この点で、「国会の立法裁量の範囲を超えるものとみざるを得ないような場合に当たるか否か」が問われたものである。
そして、「国会の立法裁量の範囲を超えるものとみざるを得ないような場合に当たる」といえるためには、その「規定の立法目的に合理的な根拠がなく、又はその手段・方法の具体的内容が立法目的との関連において著しく不合理なものといわざるを得ないような場合であって、立法府に与えられた裁量の範囲を逸脱し又は濫用するものであることが明らかである場合に限られる」(参考となる部分:【東京一次・第3回】被控訴人第2準備書面 令和6年2月29日)と考えられる。
これに対して、この札幌高裁判決で問われている事柄は、憲法24条の「婚姻」の枠組みが、そもそも「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とする法律を立法することを「要請」しているか否かである。
これは「婚姻」という枠組みが対象とする人的結合関係の範囲そのものが問われており、2項が「婚姻」の枠組みに付随して設けられる細目的な内容について定めた規定が「個人の尊厳」と「両性の本質的平等」を満たすものとなるよう求めている部分によっては変えることのできない部分である。
なぜならば、「個人の尊厳」と「両性の本質的平等」の適用対象の範囲を定めている部分が「婚姻」の枠組みであるにもかかわらず、その「個人の尊厳」と「両性の本質的平等」の文言によってその適用対象の範囲を変えることができることになれば、そもそも適用対象が指定されていないこととなり、その「婚姻」を対象として「個人の尊厳」と「両性の本質的平等」を満たすように求めるという条文の構造そのものを覆すことになるし、実質的に「婚姻」という言葉の意味を解体させ、「婚姻」という概念を成り立たない状態とし、「婚姻」という概念そのものを雲散霧消させることを許すこととなり、「婚姻」という名前をもって意味を指定し、条文という形で予め見えるものとして規範を描き出し、将来起こり得る紛争を解決しようとする「法の支配」という営みそのものを否定することになってしまうからである。
よって、札幌高裁判決で問われている事柄と「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」で問われている事柄は論点が異なっており、これらを同一視して論じることができるとする前提になく、「以上の点を総合的に考慮すると、」のように同じ言い回しで結論を導き出すことができるかのような論じ方をしていることは誤っているといえる。
「本件規定は、異性間の婚姻のみを定め、同性間の婚姻を許さず、」との部分について検討する。
ここで「異性間の婚姻」という文言があるが、これはあたかも「異性間」の「婚姻」と、それ以外の「婚姻」が存在するかのような言葉遣いとなっており、正しい説明であるとは言い難い。
まず、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」を目的として、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす「一人の男性」と「一人の女性」の組み合わせを「貞操義務」など一定の形式で法的に結び付け、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態とすることを推進し、血縁関係を明確にする機能によって立法目的の達成を目指す概念を「婚姻」と呼んでいる。
憲法24条が「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めていることについても、すべてこの意味に対応するものである。
そのため、「婚姻」であることそれ自体において、「男性」と「女性」の組み合わせしか存在しないのであり、この判決が述べるような「異性間の婚姻のみを定め、」ているどころか、「婚姻」であれば、それはそもそも「異性間」について述べるものということである。
このことから、「異性間の婚姻」という言葉は、「異性間」という「男性」と「女性」を指す言葉と、「婚姻」という「男性」と「女性」の組み合わせを指す概念とを同時に用いるものとなっており、文法上は「同義反復」(同語反復/トートロジー)となるため誤用となる。
また、「同義反復」となることを無視して、この判決のように「異性間の婚姻」という言葉を使ったとしても、「婚姻」であることそれ自体で既に「男性」と「女性」の組み合わせによる「異性間」しか存在しないことから、それに対する形で「同性間の婚姻」というものが存在することにはならない。
そのため、「異性間の婚姻」という言葉に対する形で、それ以外の「婚姻」というものが成立するという余地はない。
そのことから、その「婚姻」という言葉だけを刈り取ってその概念が形成されている目的から切り離して考えて「婚姻」という空の箱(言葉の意味から切り離された『音の響き』に過ぎないもの)の中に何らかの人的結合関係を詰め込むことができるという性質のものではない。
◇ 本来の意味
「男性」と「女性」の組み合わせ ⇒ 法的に結び付ける形を「婚姻」とする
◇ この判決の言葉の使い方
「婚姻」は空箱 ⇒ どのような人的結合関係でも詰め込むことができる
よって、「異性間の婚姻」のように、「婚姻」という概念そのものをその概念が形成されている目的との間で切り離して、どのような意味としてでも用いることができるような前提を含む形で論じていることは、言葉の表現として適切であるとはいえない。
「同性間の婚姻」とあるが、今述べたように、「男性」と「女性」の組み合わせを備えない形で「婚姻」という概念は成立し得ないのであり、「同性間」を「婚姻」とすることはできない。
「同性間の婚姻を許さず、」とある。
この「同性間の婚姻」の意味が、「同性間の人的結合関係」を形成することを指す場合には、それは憲法21条1項の「結社の自由」で保障されており、「本件規定」はそれを規制するものではないことから、「許さず、」との認識は誤りとなる。
この「同性間の婚姻」の意味が「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを指しているのであれば、「本件規定」は「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを定めていないということができる。
ただ、これは法制度が定められているか否かの問題であるから、むやみに「許していない」という「許す・許さない」という意味の表現を用いることは適切であるとはいえない。
このような表現は、法制度の性質について客観的な視点から説明するものとして用いられる言葉遣いではなく、別の個所の「不利益」などの文言と相まって、訴訟の当事者の一方の見方や意見、感じ方に与する形で論じるものとなっていることが考えられる。
そのため、敢えてこのような表現を用いて論じていることは、公的な性質を持つ裁判所の立場で用いる言葉の選択として適切であるとはいえない。
ここでも、初めに「異性間の婚姻のみを定め、」のように、「異性間の婚姻」との部分では法制度が「定めている・定めていない」という意味の言葉を使っているのであるから、「同性間の婚姻」との部分でも「定めておらず」のような言葉を使うことが中立的なものとなるはずである。
それにもかかわらず、それをあえて「同性間の婚姻」との部分について「許さず、」のように「許す・許さない」という「肯定されるか否定されるか」というような語感を含む言葉に置き換えて論じていることは、「許されていない」のように何かが否定されているという言葉の感覚を強調することによって、その感覚を解消しなければならないはずであるという人の心の中にある正義感を呼び起こそうと意図的に仕掛けるものとなっていることが考えられる。
しかし、これを法的な視点から客観的に見ると、制度が定められているか否かの問題であって、何らかの立法目的を達成するための手段として形成されている法制度の対象となるかならないかという意味を超えて、自然人の存在が肯定されたり否定されたりする意味で「許す」とか「許さない」とかいう意味を含む問題とは性質の異なるものである。
この点で、言葉の選択として客観性や中立性が見られず、法的な視点で論じるというよりも、政治活動における運動論で用いられるような色の付いた言葉が残ったまま論じるものとなっているといえる。
このような論じ方は、法的な議論としてまとめる際に必要となる脱色がなされていないものであり、裁判所という中立性や公平性、公正性が求められている機関の用いる言語感覚として適切なものではない。
「これに代わる措置についても一切規定していないことから、」との部分について検討する。
憲法24条の論点で問われる事柄は、憲法24条の「婚姻」の枠組みが「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とする法律を立法することを「要請」しているか否かである。
憲法24条の「婚姻」の枠組みがそれを「要請」しているのであればその制度が存在しないことは違憲となり、憲法24条の「婚姻」の枠組みがそれを「要請」していないのであればその制度が存在しないことは合憲というものである。
この憲法24条の「婚姻」の枠組みが「要請」しているか否かの問題は、憲法24条の条文の意味そのものを読み解くことによって結論が導き出されるものであることから、「これに代わる措置」と称するものが存在するか否かによって左右されるものではない。
そのため、「これに代わる措置」を「規定して」いるかいないかが問われるという前提にない問題であり、ここで「これに代わる措置について」「一切規定していない」ことを考慮して結論を導き出そうとしていることは、関係のないことを述べるものとなることから、誤りである。
「個人の尊厳に立脚し、性的指向と同性間の婚姻の自由を保障するものと解される憲法24条の規定に照らして、合理性を欠く制度であり、少なくとも現時点においては、国会の立法裁量の範囲を超える状態に至っていると認めることが相当である。」との部分について検討する。
「個人の尊厳に立脚し、性的指向と同性間の婚姻の自由を保障するものと解される憲法24条の規定に照らして、」とある。
この「個人の尊厳に立脚し、性的指向と同性間の婚姻の自由を保障するものと解される憲法24条の規定」という文は、「個人の尊厳に立脚し、性的指向と同性間の婚姻の自由を保障するものと解される」の部分が「憲法24条の規定」の修飾語(修飾部)となっている。
◇ 修飾の関係
「個人の尊厳に立脚し、性的指向と同性間の婚姻の自由を保障するものと解される」
↓ (修飾)
「憲法24条の規定」
この構造により、「憲法24条の規定」が下記の二つの性質を持つと解するものとなっている。
「憲法24条の規定」は、
◇ 「個人の尊厳に立脚」「するものと解される」
◇ 「性的指向と同性間の婚姻の自由を保障するものと解される」
しかし、どちらも誤りである。
初めに、「憲法24条の規定」が「個人の尊厳に立脚」「するものと解される」との旨を述べていることについて検討する。
憲法24条2項には「婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。」と書かれており、この「婚姻及び家族」の枠組みの「要請」に従って立法される法律上の具体的な制度として定められる「婚姻及び家族」の制度の細目的な内容について、「個人の尊厳」を満たすものとなるように求めるものとなっている。
しかし、これは「憲法24条の規定」そのものが「個人の尊厳に立脚」していることを定めているものではない。
そのため、「個人の尊厳」や「立脚」の文言があることから、ここで述べている「個人の尊厳に立脚」「するものと解される」との文は、憲法24条2項に記されている文言と重なっているが、この文が憲法24条2項の条文の意味を説明しているものであるとすれば誤りである。
その他、「個人の尊厳」の文言ではないが、憲法13条前段に「すべて国民は、個人として尊重される。」との文言があることから、この「個人として尊重」の部分を「個人の尊厳」と重なるものと考え、「憲法24条の規定」がこの「個人として尊重」の趣旨に「立脚」するものと考えている場合が考えられる。
しかし、「憲法24条の規定」と憲法13条の規定は共に憲法上の条文であり、一方の条文がもう一方条文が定められている根拠となる関係にはないことから、「憲法24条の規定」が憲法13条の規定に「立脚」するという関係にあるわけではない。
そのため、「憲法24条の規定」が13条の「個人として尊重」の趣旨に「立脚」「するものと解される」と考えているとすれば誤りである。
◇ この札幌高裁判決の誤った説明
13条の「個人の尊重」
↓
↓
24条の「婚姻」 ←←← 24条の「個人の尊厳」で枠を改変
↓ ↓
↓(保障) ↓(合理性)
↓ ↓
自由な結びつき → ? → 法律上の婚姻制度
(自由権?)
◇ 本来の整合性のある説明 (再婚禁止期間制度や夫婦同姓制度の大法廷判決)
24条の「婚姻」 ← (矛盾なし) → 13条「個人の尊重」
↓ |
↓ |
↓ 24条の「個人の尊厳」の審査
↓ ↓
↓(要請) ↓
↓ ↓
法律上の婚姻制度 ←←←
次に、「憲法24条の規定」が「性的指向と同性間の婚姻の自由を保障するものと解される」と述べていることについて、検討する。
まず、この札幌高裁判決のこの段落よりも以前の部分において、「憲法24条の規定」が「性的指向と同性間の婚姻の自由を保障するもの」であると説明されている部分は存在しない。
ここでいう「性的指向と同性間の婚姻の自由」と称するものがあたかも憲法13条と関係するかのように説明している部分は見られるが、それでも憲法24条と関係するものとして述べられている部分は存在しない。
そのため、ここで「性的指向と同性間の婚姻の自由を保障するものと解される憲法24条の規定」と述べて、「憲法24条の規定」と「性的指向と同性間の婚姻の自由」と称するものを関係させて論じる内容は、ここで初めて登場する説明であり、唐突な内容である。
また、その内容についても、下記のように憲法24条と関係させて論じることは妥当でない。
ここでいう「性的指向」とは、「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかに関するものであり、個々人の内心における心理的・精神的な事柄であることから、「内心の自由」として憲法19条の「思想良心の自由」によって保障されるものである。
そのため、これについて「憲法24条の規定」で保障されるかのように述べていることは誤りである。
「同性間の婚姻」の部分について、これが「同性間の人的結合関係」を指す場合には、その「同性間の人的結合関係」を形成する「自由」は、憲法21条1項の「結社の自由」によって保障されるものである。
そのため、これについて「憲法24条の規定」で保障されるかのように述べていることは誤りである。
「同性間の婚姻」の部分について、これが「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを指す場合には、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることができるかどうかから検討することが必要である。
「婚姻」は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」を目的として、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす「一人の男性」と「一人の女性」を選び出し、その間に「貞操義務」を設けるなど一定の形式で法的に結び付け、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によって立法目的の達成を目指す枠組みである。
「憲法24条の規定」が「婚姻」について「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めていることも、この趣旨に対応するものである。
「同性間の人的結合関係」については、この趣旨を満たすものではないことから、「婚姻」の中に含めることはできない。
そのため、「同性間の婚姻」の部分について、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることができることを前提として論じようとしていることは誤りとなる。
よって、これについて「憲法24条の規定」で保障されるかのように述べていることも誤りである。
その後に続く「婚姻の自由」との部分だけを見ると、これは「再婚禁止期間大法廷判決(平成27年12月16日)」が示した「婚姻をするについての自由」について述べようとしているものと考えられる。
ただ、「再婚禁止期間大法廷判決(平成27年12月16日)」の内容は、憲法24条1項が「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めていることを前提として、その憲法24条の「要請」に従って定められている法律上の婚姻制度を利用するか否かに関する自由をいうものである。
そのため、そこで述べられた「婚姻をするについての自由」と述べているものについても、このような「男女二人一組」を対象としている婚姻制度を利用するか否かについての「自由」について述べられているものである。
そのことから、この「婚姻をするについての自由」の中に、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを求めることができるという意味は含まれていない。
これにより、「同性間の婚姻の自由」のように、これを一続きに述べたとしても、「婚姻」そのものによって「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることができることにはならないし、ここでいう「自由」についても、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として定められている「婚姻」という枠組みを利用するか否かに関する「自由」をいうものであることから、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」の中に含めることを国家に対して求めることができるという意味を有するものではない。
よって、このような意味を超える「自由」が「憲法24条の規定」によって「保障」されているかのように考えることは誤りである。
このことから、「性的指向と同性間の婚姻の自由を保障するものと解される憲法24条の規定」と述べていることも誤りである。
「個人の尊厳に立脚し、性的指向と同性間の婚姻の自由を保障するものと解される憲法24条の規定に照らして、合理性を欠く制度であり、」とある。
まず、上記で述べたように、「憲法24条の規定」は「個人の尊厳に立脚」「するもの」ではないし、「性的指向と同性間の婚姻の自由を保障するもの」でもないことから、「個人の尊厳に立脚し、性的指向と同性間の婚姻の自由を保障するものと解される憲法24条の規定」と述べている部分は誤っている。
そのため、このような理解に「照らして、」判断することができるとする前提になく、この部分に「照らして、」判断しようとしていることは誤りである。
また、この部分に「照らして、」判断することができるとする前提にないことから、その判断の過程において「合理性」が問われるとする前提にもなく、「合理性を欠く制度であり、」と評価していることも誤りである。
次に、この「個人の尊厳に立脚し、性的指向と同性間の婚姻の自由を保障するものと解される憲法24条の規定」という文は、「個人の尊厳に立脚し、性的指向と同性間の婚姻の自由を保障するものと解される」の部分が「憲法24条の規定」の修飾語(修飾部)となっている。
◇ 修飾の関係
「個人の尊厳に立脚し、性的指向と同性間の婚姻の自由を保障するものと解される」
↓ (修飾)
「憲法24条の規定」
そのため、この修飾語を省略して意味を読み解くと、この文は単に「本件規定は、」「憲法24条の規定に照らして、合理性を欠く制度であり、」と述べているだけである。
しかし、「憲法24条の規定に照らして、合理性を欠く」と述べるだけでは、「憲法24条の規定」との関係でどの点がどのような形で矛盾・抵触するものとなっているのか、あるいはここでいう「合理性を欠く」状態となっているのかについて何らの説明もなされていないのであり、「合理性を欠く」とする理由を示しているとはいえない。
また、これよりも以前の段落で述べられている内容が「憲法24条の規定」に違反するとする理由にならないことは、それらの段落の解説した通りである。
「少なくとも現時点においては、国会の立法裁量の範囲を超える状態に至っていると認めることが相当である。」とある。
「少なくとも現時点においては、」と述べている。
ここでは時代が進めば何かが変わるかのような前提で論じるものとなっているが、時代が変わったとしても、「婚姻」が「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」を目的として、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす人的結合関係を選び出し、その間に「貞操義務」を設けるなど一定の形式で法的に結び付け、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によってそれらの目的を達成することを目指す枠組みであることが変わることはない。
そのため、時代が進めば合憲であったものが違憲になり、逆に、違憲であったものが合憲になるという性質のものではない。
もしこのように論じることが可能であるとすれば、古くから一夫多妻制を採用している国々が存在しており、そのような国々が存在する中で、日本国が一夫多妻制を採用していないことは、ずっと前から憲法に違反していたことになるはずである。
また、この札幌高裁判決の導き出そうとする結論とは反対に、時代が進めば「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」の趣旨が益々明らかになり、一夫一婦制(男女二人一組)としていない場合には憲法に違反するという論じ方もまったく同様に可能である。
よって、このような「時代の進み」を根拠とする論じ方は、結局、どちらの方向の結論を述べる場合であっても、何らの論理的な根拠を示すものではなく、要するに法の支配を逸脱し、裁判官が特定の結論を導き出すために使っているそれらしい理由付けを述べようとしているだけということになる。
そのため、「少なくとも現時点においては、」のような「時代の進み論」は論じ方として不適切である。
この点について、下記の記事が参考になる。
この記事の内容は、憲法改正について論じているものであるが、解釈を変更することができるかどうかを検討する場面においても共通性を見ることができる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
このように、学問の目的はおしなべて「真理の探究」という点にあるわけですが、先ほども述べたように、憲法も「法」であり学問の一つである以上、その論理は当てはまります。
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
この点、「真理」とは物事の本質であり「矛盾がない」状態を言い、またこの宇宙が存在する限り「普遍的」にゆるぎないものを言いますので、憲法の真理は「矛盾のない普遍的なもの」と言い換えることができます。
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
そこで考えられたのが「法」です。「法」は形而上の世界の絶対的な価値観である「哲学」や「宗教」などによって導き出される命題を、形而下にある現実世界で具現化させるために用いられますので、「法」の根源(真理)には「哲学」や「宗教(神学)」などによって導き出される絶対的・普遍的な命題が内在されているといえます(※ちなみに法学は「形而下学」と呼ばれます)。
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ですから、現代に生きる我々は、哲学的命題という絶対的普遍的な価値観と矛盾しない憲法を追求することが求められているのであり、その哲学的命題という宇宙の真理に矛盾しない憲法を求めるために日々議論を重ねなければならないと言えるのです。
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
「憲法は時代に合わせて変えるべき」とか「実態社会に適合しなくなった憲法は変えるべきだ」という主張はもっともらしく聞こえますが、実はもっともな主張とは言えません。
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
このように、「憲法は時代に合わせて変えるべき」という主張は本来的にファシズムや極右思想や全体主義を呼び込む危険性を包含していることを考えれば妥当な思想ではありません。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
憲法は何を目的として改正されるべきなのか 2018.12.29
このように、解釈の変更は、より普遍性の高い規範が発見された場合に限り認められるべきものであり、そうでない場合に「時代の進み」を理由として変更を認めることは適切ではない。
もし「時代の進み」を理由として変更を認めた場合には、そのような変更は法的安定性を損なうものとなるし、国会の立法権や憲法改正の手続きを侵害するものとして司法権により正当化することのできないものとなる。
よって、「少なくとも現時点においては、」のように「時代の進み」を理由として、法規範の意味が揺れ動き、その揺れ動いた意味に合わせて解釈を変更したり、特定の結論を導き出したりすることができるかのように述べていることは誤りである。
「国会の立法裁量の範囲を超える状態に至っていると認めることが相当である。」と述べている。
まず、憲法24条の論点で問われているのは、憲法24条の「婚姻」の枠組みが「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とする法律を立法することを「要請」しているか否かである。
これは、「要請」しているのであればその制度が存在しないことは違憲であり、「要請」していないのであればその制度が存在しないことは合憲というものである。
そして、もし「要請」しているのであれば、国会はその制度を立法しないという選択をすることができないことから、「国会の立法裁量」を検討する余地はない。
反対に、「要請」していないのであれば、そもそも国会に対して何らの義務付けも行われていないことから、その制度が存在しないことについて「国会の立法裁量の範囲を超える状態」となることはない。
よって、いずれにせよ、これは「国会の立法裁量」が関わる問題ではないのであり、ここで「国会の立法裁量の範囲を超える状態に至っていると認めることが相当である。」のように述べて、「国会の立法裁量の範囲を超える」か否かによって結論が導き出される問題であるかのように論じていることは誤りである。
したがって、本件規定は、憲法24条に違反する。
【筆者】
一段落前で「以上の点を総合的に考慮すると、」「憲法24条の規定に照らして、合理性を欠く制度であり、少なくとも現時点においては、国会の立法裁量の範囲を超える状態に至っていると認めることが相当である。」と述べている。
そして、ここでこの点について「本件規定は、憲法24条に違反する。」と述べるものとなっている。
しかし、憲法24条の論点で問われているのは、憲法24条の「婚姻」の枠組みが「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とする法律の立法を「要請」しているか否かである。
これは「要請」しているのであればその制度がないことは違憲、「要請」していないのであればその制度がないことは合憲というものである。
そしてこれは、憲法上の条文に記された文言の意味そのものを読み解くことによって規範の意味を明らかにし、結論を導き出すことが必要であり、一段落前で述べている「以上の点を総合的に考慮する」ことによって結論が導き出されるという性質のものではない。
また、これはもし憲法24条の「婚姻」の枠組みが「要請」しているのであれば国会が立法しないという選択を採ることはできないことから「国会の立法裁量」が関わる余地はなく、「国会の立法裁量の範囲を超える状態に至っている」か否かを判断する前提にないし、もし「要請」していないのであれば国会に対して何らの義務付けもされていないため、「国会の立法裁量の範囲を超える状態に至っている」か否かを判断する前提にないものである。
そのため、いずれにしても一段落前で述べている「国会の立法裁量の範囲を超える状態に至っている」か否かを検討することによって結論が導き出されるという問題ではない。
よって、ここで一段落前で「以上の点を総合的に考慮すると、」「憲法24条の規定に照らして、合理性を欠く制度であり、少なくとも現時点においては、国会の立法裁量の範囲を超える状態に至っていると認めることが相当である。」という判断がされていることを引き継ぐ形で、ここで「したがって、本件規定は、憲法24条に違反する。」と述べていることは、前提となる判断の方法に誤りがあることから、それによって生じたとする結論の部分も正当化することはできず、誤りである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3)また、この点をおいても、被控訴人原審第5準備書面第3の1(3)(10ないし12ページ)において述べたとおり、憲法24条が婚姻について異性間の人的結合関係のみを対象するものとして明文で定め、婚姻に係る法制度の構築を法律に委ねているものの、それ以外の法制度の構築を明文で定めていないことからすると、憲法は、法律(本件諸規定)により異性間の人的結合関係のみを対象とする婚姻を制度化することを予定しているとはいえるものの、同性間の人的結合関係を対象とする婚姻制度を構築することを想定していないことはもとより、「同性カップルに対して、その関係を国の制度によって公証し、その関係を保護するのにふさわしい効果を付与するための枠組み」を含め、同性間の人的結合関係を対象とする新たな婚姻に準じる法制度を構築することを具体的に想定しておらず、同制度の構築を立法府に要請しているものでもないから、同制度の不存在が憲法24条2項に反することもないと解される。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【名古屋・第1回】控訴答弁書 令和5年10月12日
なお、当該判断は同性婚を許さない民法及び戸籍法の婚姻に関する諸規定が憲法に違反することを問題とするものであるから、個別の条文についての特定は要しないと解する。
【筆者】
「当該判断は同性婚を許さない民法及び戸籍法の婚姻に関する諸規定が憲法に違反することを問題とするもの」との部分について検討する。
憲法24条の論点で問われるのは、憲法24条の「婚姻」の枠組みが「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とする法律を立法することを「要請」しているか否かである。
そして、「要請」しているのであればその制度が存在しないことは違憲となり、「要請」していないのであればその制度が存在しないことは合憲となるというものである。
この事案は、憲法24条の「婚姻」の枠組みの「要請」に従った法制度が存在するか否かによって憲法に違反するか否かが判断されるのであり、「民法及び戸籍法の婚姻に関する諸規定」そのものが直接的に「憲法に違反する」か否かが問われている場合とは性質が異なっている。
そのため、憲法24条の論点で問われているものが「民法及び戸籍法の婚姻に関する諸規定が憲法に違反することを問題とするもの」であるかのような認識は誤りである。
よって、「個別の条文についての特定は要しないと解する。」との結論に至るまでの認識が妥当でない。
これとは別の視点で、もし「当該判断は」のように「判断」の内容を指し、それが「民法及び戸籍法の婚姻に関する諸規定が憲法に違反する」か否かを「問題」とするものであり、一段落前で述べるように「憲法24条に違反する。」という結論を導くものであるとすれば、当然、「民法及び戸籍法」の中に「憲法に違反する」「個別の条文」が存在するはずである。
それにもかかわらず、そのような判断を前提としている場合においても「個別の条文についての特定は要しないと解する。」と述べていることは誤っている。
4 本件規定が憲法14条1項に違反する旨の主張について(争点⑴関係)
(1) 控訴人らは、本件規定が、異性愛者の婚姻のみ定め、同性愛者の婚姻を許さない規定であるから、憲法14条1項に違反する旨を主張する。
【筆者】
この段落は控訴人らの主張をまとめたものなので、解説はしない。
(2) 憲法14条1項は、法の下の平等を定めており、この規定が、事柄の性質に応じた合理的な根拠に基づくものでない限り、法的な差別的取扱いを禁止する趣旨のものであると解すべきことは、最高裁判所の判例とするところである(最高裁昭和37年(オ)第1472号同39年5月27日大法廷判決・民集18巻4号676頁、最高裁昭和45年(あ)第1310号同48年4月4日大法廷判決・刑集27巻3号265頁等参照)。
【筆者】
ここで示された判決は、下記の通りである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
……(略)……しかし、右各法条は、国民に対し絶対的な平等を保障したものではなく、差別すべき合理的な理由なくして差別することを禁止している趣旨と解すべきであるから、事柄の性質に即応して合理的と認められる差別的取扱をすることは、なんら右各法条の否定するところではない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
最高裁判所昭和39年5月27日大法廷判決 (PDF)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
よつて案ずるに、憲法一四条一項は、国民に対し法の下の平等を保障した規定であつて、同項後段列挙の事項は例示的なものであること、およびこの平等の要請は、事柄の性質に即応した合理的な根拠に基づくものでないかぎり、差別的な取扱いをすることを禁止する趣旨と解すべきことは、当裁判所大法廷判決(昭和三七年(オ)第一四七二号同三九年五月二七日・民集一八巻四号六七六頁)の示すとおりである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
最高裁判所昭和48年4月4日大法廷判決 (PDF)
この14条1項の「平等原則」を判断する際に必要となる視点は、下記の通りである。
◇ 「法適用の平等」と「法内容の平等」の違い
14条1項の「平等原則」における審査では、「法適用の平等」と「法内容の平等」を分けて考える必要がある。
【動画】シンポジウム 国葬を考える【The Burning Issues
vol.27】 2022/09/25
◇ 「法内容の平等」の審査
「法内容の平等」については、➀「区別(差別)」の存否と、②「区別(差別)」が存在した場合における「合理的な理由」の存否が問われることになる。
そして、②の「合理的な理由」の内容については、「立法目的」とその「達成手段」が問われることになる。
➀ 「区別(差別)」が存在するか否か
② 「区別(差別)」が存在する場合にその区別に「合理的な理由」が存在するか
「合理的な理由」の判断方法
・「立法目的」の合理性
・「立法目的を達成するための手段」の合理性
しかし、この札幌高裁判決の内容は、➀の「区別取扱い」が存在するか否かという判断から誤っているため、②の判断を行おうと試みている論旨についても、全面的に誤っている。
〇 「区別」と「差別」に違いはあるか
14条1項の「平等原則」の審査を行う際に、日常用語として使われる「差別であるか否か」という議論の仕方とは明確に切り離して考える必要がある。
日常用語として「差別」の言葉が使われた場合には、何らかの否定的な意味を背負っていることが多い。
そのため、この「差別」という言葉の使われ方は、既に「合理的な理由」がないという結論を示すものであることが前提となっている。
しかし、憲法14条1項の「平等原則」を審査する際に使われている「差別」の意味は、何らかの違いを見出して異なるものに分けている状態を指しているだけである。
ここには否定的な意味合いを含んでおらず、「区別」の文言と全く同様の意味で使われている。
そのため、その「差別=区別」の内容が「合理的な理由」に基づくものであるか否かがさらに検討されなければ、未だに結論を示すものではないのである。
・日常用語:「差別」 ⇒ 「合理的な理由」のない区別があるという結論
・法的判断:「差別」 ⇒ 何らかの区別があるという状態
→ さらに「合理的な理由」があるかを審査しなければ結論の当否は分からない
このことから、14条1項についての法的な審査の際には、日常的に使われる「差別であるか否か」が問われているのではなく、「差別(区別)が存在する場合に、そこに合理的な理由があるか否か」が問われていることになる。
先ほど挙げた動画でも、14条1項における「平等」とは、「区別」の存否ではなく、「区別」の「合理性」の有無が論点であることが説明されている。
【動画】シンポジウム 国葬を考える【The Burning Issues vol.27】 2022/09/25
最高裁判決でも「差別」の文言を使っているが、「合理的」であれば禁じられないとしている。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1 憲法14条1項は,法の下の平等を定めており,この規定が,事柄の性質に応じた合理的な根拠に基づくものでない限り,法的な差別的取扱いを禁止する趣旨のものであると解すべきことは,当裁判所の判例とするところである(最高裁昭和37年(オ)第1472号同39年5月27日大法廷判決・民集18巻4号676頁,最高裁昭和45年(あ)第1310号同48年4月4日大法廷判決・刑集27巻3号265頁等)。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
損害賠償請求事件 最高裁判所大法廷 平成27年12月16日 (PDF) (再婚禁止期間違憲訴訟)
よって、法律論上は「区別」と呼ぼうと「差別」と呼ぼうと、「合理性」の存否が問題なのであり、日常的に使う言葉としての「差別であるかどうか」という問題ではない。
この点、この判決の「4 本件規定が憲法14条1項に違反する旨の主張について」の項目では、「差別」と「区別」の文言が下記のように混在しており、意味が整理されていない。
【差別】
① 「事柄の性質に応じた合理的な根拠に基づくものでない限り、法的な差別的取扱いを禁止する趣旨のものであると解すべきことは、」
② 「男か女かという性別による差別があるものではない。」
③ 「同性愛者等が法律的な婚姻等へのアクセス等において差別的な扱いに直面しており、」
④ 「国会や司法の場において、差別であるとの指摘がされてきた。」
⑤ 「本件規定が定める本件区別取扱いは、差別的取扱いに当たると解することができる。」
①と②の「差別」の文言は法的な意味で使われており、「区別」と同様の意味である。
しかし、③と④と⑤については、日常用語として使われる場合のように否定的な意味を持たせて使われていると考えられる。
この点、「差別」の言葉の意味が統一されておらず、法的な判断を行う場面であるにもかかわらず、法的な意味で使われていない部分があるため妥当でない。
【区別】
◇ 「本件区別取扱いをすることに合理的な根拠が認められない場合には、当該区別取扱いは、憲法14条1項に違反するものと解するのが相当である」
◇ 「本件区別取扱いに関する合理的根拠の有無について検討する。」
◇ 「同じように制度的な保障を享受し得る地位があり、それを区別する合理的な理由はないというべきである。」
◇ 「そうすると、本件区別取扱いは合理的な根拠がないといえる。」
◇ 「上記のような婚姻における取扱いの区別については、」
◇ 「異性婚との区別について合理的な説明がされていなかったりするものである。」
◇ 「代替的な措置により不利益を受けないことが合理的な区別の理由になるものかは判然としないが、」
【差別と区別が同時に登場】
◇ 「このような性的指向に係る婚姻制度における取扱いの区別(以下「本件区別取扱い」という。)が、合理的理由のない差別的取扱いに当たるか否かということであり、」
上記は、法的な判断の場面では「区別」と「差別」が同じ意味であることを押さえれば、「区別」に「合理的理由」があるかないかを述べればよいのであって、そこに「差別」という言葉を加えることは余分である。
このように、この判決は法的な判断における「差別」の言葉の使い方を理解しておらず、不当な内容となっている。
上記の問題は、この判決の「4 本件規定が憲法14条1項に違反する旨の主張について」の項目の内容が読み取りづらく感じる原因の一つである。
婚姻制度は、婚姻当事者の意思によって当事者間に家族の基本単位となる配偶者としての身分関係を形成し、その身分に応じた種々の権利義務を伴う法的地位が付与されるという仕組みを国において定めるものであるが、婚姻制度を定めるに当たっては、それぞれの国の伝統、社会事情、国民感情なども考慮されなければならない。さらに、現在の婚姻制度は、家族というものをどのように考えるかということと密接に関係しているのであって、その国における婚姻ないし親子関係に対する規律、国民の意識等を離れてこれを定めることはできない。これらを総合的に考慮した上で、婚姻制度をどのように定めるかは、立法府の合理的な裁量に委ねられているものというべきである。
【筆者】
この文は、最高裁の下記の判例の文面をテンプレートとして利用し、文言のあてはめを変えたものである。
(灰色で潰した部分が文言が重なる部分である。)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
相続制度は,被相続人の財産を誰に,どのように承継させるかを定めるものであるが,相続制度を定めるに当たっては,それぞれの国の伝統,社会事情,国民感情なども考慮されなければならない。さらに,現在の相続制度は,家族というものをどのように考えるかということと密接に関係しているのであって,その国における婚姻ないし親子関係に対する規律,国民の意識等を離れてこれを定めることはできない。これらを総合的に考慮した上で,相続制度をどのように定めるかは,立法府の合理的な裁量判断に委ねられているものというべきである。……(略)……
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件 最高裁判所大法廷 平成25年9月4日 (PDF)
しかし、最高裁の判例については、24条2項の「婚姻及び家族」の枠組みの「要請」に従って立法されている法律上の「婚姻及び家族」の制度の内容における「相続制度」について論じるものであり、「婚姻及び家族」の対象とする人的結合関係の枠組みそのものを対象とするものではない。
これに対して、この札幌高裁判決は、この最高裁の判例の文面を基にして、「相続制度」としている部分を「婚姻制度」に書き換えて論じるものとなっているが、そもそも「婚姻及び家族」の枠組みの「要請」に従って立法されている法律上の「婚姻及び家族」の制度の内容の一部分について論じている文面を、その文面を構成する前提となっている「婚姻及び家族」における「婚姻制度」そのものを変更するための論旨として用いることができるかのように考えていることが誤りである。
24条2項「婚姻及び家族」
↓ (要請)
法律上の「婚姻及び家族」の制度 ( ← 札幌高裁判決が変えようとしているもの)
↓ (その一部)
「相続制度」 ( ← 最高裁の判例)
最高裁の判例の「相続制度」については、24条2項の「婚姻及び家族」の枠組みの「要請」する「婚姻及び家族」の制度の根幹となっている「婚姻及び家族」の対象とする人的結合関係の範囲には触れないものであり、どのような制度とするかは立法府が決めることのできる可変的な部分であるといえるものである。
それに対して、この札幌高裁判決は「婚姻制度」の人的結合関係の範囲を論じているものであるから、24条2項の「婚姻及び家族」の枠組みそのものに関わるものであり、24条1項の「婚姻」「両性」「夫婦」「配偶者」の文言が一夫一婦制(男女二人一組)を定めていることや、「婚姻及び家族」という概念そのものが持つ内在的な限界との関係により拘束されており、24条の規定そのものが規範となるため変えることのできない部分である。
それを、24条2項の「婚姻及び家族」の枠組みの「要請」に従って立法されている「婚姻及び家族」の制度の一部分である「相続制度」についての最高裁判例を用いて、24条2項の「婚姻及び家族」の枠組みそのものに関わる「婚姻制度」の対象とする人的結合関係の範囲そのものを論じることができるかのように考えることは、最高裁判例の前提としている論旨の射程を理解しないものであり、誤った論じ方であるといえる。
最高裁判例の示す「相続制度」についての論旨は、その「相続制度」を構成する前提となっている「婚姻及び家族」の制度の対象とする人的結合関係の範囲そのものを変えることまでも可能とする意味の中において用いられている文面ではない。
「婚姻制度は、婚姻当事者の意思によって当事者間に家族の基本単位となる配偶者としての身分関係を形成し、その身分に応じた種々の権利義務を伴う法的地位が付与されるという仕組みを国において定めるものであるが、婚姻制度を定めるに当たっては、それぞれの国の伝統、社会事情、国民感情なども考慮されなければならない。」との記載がある。
「婚姻制度は、婚姻当事者の意思によって当事者間に家族の基本単位となる配偶者としての身分関係を形成し、その身分に応じた種々の権利義務を伴う法的地位が付与されるという仕組みを国において定めるものであるが、」との部分について検討する。
「婚姻」は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた枠組みである。
これは、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」という目的の下に、この目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす「一人の男性」と「一人の女性」を「貞操義務」などの一定の形式で法的に結び付け、子供が産まれた場合にその遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によってその立法目的の達成を目指すものである。
憲法24条は「婚姻」を規定しており、「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めている。
これも、上記の目的とその目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす人的結合関係について具体的な枠組みを示すものといえる。
そして、憲法24条2項の「婚姻及び家族」の枠組みの「要請」に従って、法律上の「婚姻制度」が定められている。
よって、ここでいう「婚姻制度」についても、当然、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成するための手段として設けられる枠組みであり、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」という目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす「一人の男性」と「一人の女性」を対象とし、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によって立法目的の達成を達成することを目指す制度として定められているものである。
そのため、ここでいう「婚姻当事者の意思によって当事者間に家族の基本単位となる配偶者としての身分関係を形成し、その身分に応じた種々の権利義務を伴う法的地位が付与されるという仕組みを国において定めるもの」という部分についても、この意味の制度として整合的な形で形成されるものである。
つまり、この「身分関係を形成し、」のように、「婚姻制度」が「身分関係」を形成するものとなっている理由は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成するためである。
人間は有性生殖を行うことによって子孫を生むという身体機能を有しており、その男女の間で行われる「生殖」に関わって生じる不都合が社会的な課題となっていることから、「身分関係」を形成することによって、この問題の解決を図るのである。
そのため、この「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を切り離して「身分関係」を形成する意味を捉えることはできないことに注意が必要である。
また、「その身分に応じた種々の権利義務を伴う法的地位が付与される」との部分についても、これも「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成するための手段として整合的な形で「種々の権利義務を伴う法的地位」を設定するものである。
そのことから、この「婚姻制度」に「身分関係を形成」したり、「種々の権利義務を伴う法的地位が付与される」という効果が含まれているとしても、それは常に「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成するための手段として整合的な形で定められているものであり、「婚姻制度」に「身分関係を形成」したり、「種々の権利義務を伴う法的地位が付与される」という効果があることを理由として「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成するための手段として整合的でない人的結合関係に対してまで、「婚姻制度」として「身分関係を形成」することや「種々の権利義務を伴う法的地位」を「付与」することまで予定するものではない。
これは、もし「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成するための手段として整合的でない人的結合関係に対してまで同じように「身分関係を形成」することを可能とした場合には、「婚姻制度」が「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消する制度として機能しなくなり、その社会の中で「生殖」に関わって生じる不都合を十分に解消することができなくなり、その結果、これを解消するために他の様々な人的結合関係の間で区別する形で「婚姻制度」を設けている意味そのものが失われてしまうことになるからである。
また、そのようにして「婚姻制度」が「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するための制度として十分に機能しないものに変わってしまった場合には、そのような人的結合関係に対して法的効果や一定の優遇措置を設けていることについて、その制度を利用しない者との間で生じる差異を正当化することができる理由が無くなり、不平等を生じさせることにもなるからである。
よって、「婚姻制度」の「身分関係」や「その身分に応じた種々の権利義務を伴う法的地位」については、このような「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するための機能と切り離して考えることはできないものである。
次に、「婚姻制度を定めるに当たっては、それぞれの国の伝統、社会事情、国民感情なども考慮されなければならない。」との部分について検討する。
まず、ここでいう「婚姻制度」のいう「婚姻」とは、上記でも述べたように「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた枠組みである。
具体的には、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」という目的を達成するための制度として整合的な要素を満たす「一人の男性」と「一人の女性」の組み合わせに対して「貞操義務」を設けるなど一定の形式で法的に結び付け、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によってその立法目的の達成を目指すものである。
また、憲法24条は「婚姻」を規定し、「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めており、これらの目的とその目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす人的結合関係の範囲を具体的に示すものとなっている。
そして、この憲法24条2項の「婚姻及び家族」の枠組みの「要請」に従って法律上の「婚姻制度」が定められ、そのような立法目的と立法目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす一夫一婦制(男女二人一組)が定められることになる。
この一夫一婦制(男女二人一組)の枠組みの下で、「婚姻適齢」、「夫婦同氏」、「法定相続分」、「再婚禁止期間」の長さなどの個別の効果を、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという「婚姻制度」の機能と整合的な形で「国の伝統、社会事情、国民感情なども考慮」しながら形成することは可能である。
この札幌高裁判決が参照している最高裁の判例の中でも、この憲法24条2項の「婚姻及び家族」の枠組みの「要請」に従って立法されている一夫一婦制(男女二人一組)の「婚姻制度」を定める法律上の「婚姻及び家族」の制度の下で、その一部である「相続制度」の個別の効果について問われている事例であるといえる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
相続制度は,被相続人の財産を誰に,どのように承継させるかを定めるものであるが,相続制度を定めるに当たっては,それぞれの国の伝統,社会事情,国民感情なども考慮されなければならない。さらに,現在の相続制度は,家族というものをどのように考えるかということと密接に関係しているのであって,その国における婚姻ないし親子関係に対する規律,国民の意識等を離れてこれを定めることはできない。これらを総合的に考慮した上で,相続制度をどのように定めるかは,立法府の合理的な裁量判断に委ねられているものというべきである。……(略)……
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件 最高裁判所大法廷 平成25年9月4日 (PDF)
しかし、これらの法律上の「婚姻制度」における個別の規定の内容については、「国の伝統、社会事情、国民感情など」を「考慮」することによって決めることができるが、「婚姻」という枠組みそのものを「国の伝統、社会事情、国民感情など」を「考慮」することによって自由に変更できるという性質のものではない。
なぜならば、「婚姻」とは、その社会の中で「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消する必要性の下に、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす形で形成されている枠組みであることから、「婚姻」そのものがその不都合を解消するために機能することが求められており、その不都合を解消するものとして機能しないものに変えてしまうことはできないという内在的な限界を有しているからである。
また、もし「婚姻」という枠組みそのものを自由に変更することができることになれば、法律の改正によって「婚姻」と呼んでいる制度の内容を実質的に「組合」「雇用」「会社」「宗教団体」「学校」「政党」「町内会」などを指すものに変えてしまうことも可能となることを意味し、このような文言の持つ意味と乖離した状態を許すことになれば、言語によって予め規範を定めることによって将来起こり得る人々の利害関係の調整や紛争の解決を行おうとする「法の支配」という営みそのものを否定することとなり、妥当でないからである。
そのため、ここでいう「婚姻制度を定めるに当たっては、それぞれの国の伝統、社会事情、国民感情なども考慮されなければならない。」という部分は、最高裁の判例が示す「婚姻及び家族」の制度の中の個別の効果ではなく、「婚姻制度」そのものを問うものとなっていることから、本来は最高裁の判例の文面を用いて論じることができるという前提にないものではあるが、それを別としてこの文の意味を検討するしても、常にここでいう「婚姻制度」は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた枠組みのことを指しており、その機能を果たさないものに変えてしまうことはできないという内在的な限界が含まれているものである。
そのため、「婚姻制度を定めるに当たっては、それぞれの国の伝統、社会事情、国民感情なども考慮されなければならない。」の意味を読み取るとしても、その内在的な限界に触れない形で、その目的を達成するための手段として整合的な範囲でのみ個別の効果を設定することが可能であり、その個別の効果について「国の伝統、社会事情、国民感情なども考慮されなければならない。」と述べているにとどまるものということになる。
そのことから、この文の中に「婚姻制度」の対象としている人的結合関係の枠組みそのものを「国の伝統、社会事情、国民感情など」を「考慮」することによって自由に変更できるという意味を含ませることはできない。
よって、もし法律上の「婚姻制度」の内容を「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するものとして機能しないものに変えてしまうようなことがあれば、それは「婚姻」という言葉の意味そのものを変えようとするものとなることから、「法の支配」という営みに反することになるし、憲法24条の規定の下では、「婚姻」の文言それ自体や「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言が一夫一婦制(男女二人一組)を定めている趣旨に抵触して違憲となる。
この点については、たとえ「国の伝統、社会事情、国民感情など」を持ち出したとしても、変えられるものではない。
このように、「国の伝統、社会事情、国民感情など」を「考慮」して決められる部分と、そうでない部分とがあることを押さえる必要がある。
その他、「それぞれの国」としているところについて、「それぞれの国」の法制度は「それぞれの国」の社会事情の中で生じている問題を解決することを目的として、その目的を達成するための手段として定められているものである。
そのため、外国語を翻訳する者がある国の特定の制度について「婚姻」という言葉を充てて説明している場合があるとしても、「それぞれの国」の法制度は別個のものであり、「婚姻」という同一の言葉によって統一的に把握することができるというものではない。
よって、ここで「婚姻制度を定めるに当たっては、それぞれの国の伝統、社会事情、国民感情なども考慮されなければならない。」と述べているとしても、ここでいう「婚姻制度」の意味を日本法の範囲から離れて考えているのであれば、それは外国語を翻訳する者が外国のある特定の法制度について「婚姻」という言葉を充てて説明しているものを指しているに過ぎず、その法制度がその「国の伝統、社会事情、国民感情なども考慮」されながら立法されることはその通りであるが、その外国の中でここで外国語を翻訳する者が「婚姻」という言葉を充てて説明している特定の制度の内容が「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するものとして機能しない人的結合関係を対象としているからといって、それを理由として日本法にいう「婚姻」を「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するものとして機能しないものに変えてしまうことが可能になるということはない。
この点にも注意が必要である。
もう一つ、「家族の基本単位」とあるが、ここでいう「家族」とは、法学的な意味の「家族」であり、憲法24条2項の「婚姻及び家族」の枠組みの「家族」を指すものである。
そのため、この「家族」は、「3 本件規定が憲法24条に違反する旨の主張について」の「(2)ウ」の第三段落で解説したように、「夫婦」と、「親子」による「血縁関係者」の範囲を指すものである。
これも、「婚姻」の枠組みが「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で定められ、その内容は一夫一婦制(男女二人一組)により、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によって立法目的の達成を目指す仕組みとなっていることに対応する枠組みである。
法律論としては、このような意味を離れて「家族」という文言を用いることはできないことに注意が必要である。
「さらに、現在の婚姻制度は、家族というものをどのように考えるかということと密接に関係しているのであって、その国における婚姻ないし親子関係に対する規律、国民の意識等を離れてこれを定めることはできない。」との記載がある。
まず、この文は、もともと最高裁の判例の文面が「相続制度」について述べている部分を「婚姻制度」に書き換えて論じるものである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
……(略)……さらに,現在の相続制度は,家族というものをどのように考えるかということと密接に関係しているのであって,その国における婚姻ないし親子関係に対する規律,国民の意識等を離れてこれを定めることはできない。……(略)……
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件 最高裁判所大法廷 平成25年9月4日 (PDF)
この最高裁の文面は、憲法24条2項の「婚姻及び家族」の「要請」に従って立法されている法律上の「婚姻及び家族」の制度の一部分である「相続制度」について論じるものである。
このことから、その「相続制度」の内容が定められる際の前提となっている「婚姻及び家族」の枠組みとの関係を検討する必要が生じ、「家族というものをどのように考えるか」や「婚姻ないし親子関係に対する規律」「を離れてこれを定めることはできない。」のように述べているものである。
ここで言う「家族」とは、「3 本件規定が憲法24条に違反する旨の主張について」の「(2)ウ」の第三段落で解説したように、「婚姻」している「夫婦」と、「親子」による「血縁関係者」の範囲を指すものである。
ここで「婚姻ないし親子関係に対する規律」と述べているものも、これに対応する意味である。
そのことから、「家族というものをどのように考えるか」と述べている部分は、この「夫婦」と「親子」による「血縁関係者」の枠組みが維持された中で、氏の制度、財産関係の制度、扶養の制度、親権の制度など様々な効果が存在する中の一つとして、「相続制度」を「どのように考えるか」が問われているものである。
これは、決して、「家族」や「婚姻ないし親子関係」と示している「夫婦」と「親子」による「血縁関係者」の枠組みそのものを変容させることができるという意味で「どのように考えるか」と論じているものではないし、その意味を含めることができることを前提として構成されてた文面というわけではない。
しかし、このような意味で用いられている最高裁の判例の文面を、この札幌高裁判決では「相続制度」の文言を「婚姻制度」に置き換えて、「婚姻及び家族」の「要請」に従って立法されている法律上の「婚姻及び家族」の制度の一部分の個別の効果について検討する意味で用いるのではなく、「婚姻及び家族」の対象とする人的結合関係の範囲そのものを変更することができるかどうかを検討する意味で用いようとするものとなっている。
これは、最高裁の判例の中で、憲法24条2項の「婚姻及び家族」の「要請」に従って立法されている法律上の「婚姻及び家族」の制度の内容の一部分である個別の効果を射程とした文面を、その個別の効果の前提となっている「婚姻及び家族」の制度の対象とする人的結合関係の範囲そのものを論じるものとして利用しようとするものであるから、最高裁の判例の意図している射程から逸脱する形で用いようとするものであり、不当な論じ方である。
また、この不当な論じ方により、もともと「相続制度」について「家族というものをどのように考えるか」や「婚姻ないし親子関係に対する規律」との関係を検討している文面であったものが、「婚姻制度」について「家族というものをどのように考えるか」や「婚姻ないし親子関係に対する規律」との関係を検討するものに変わっている。
この影響で、ここで「婚姻制度」の人的結合関係の範囲について論じている中で、「家族」という「婚姻」している「夫婦」と「親子」による「血縁関係者」の人的結合関係の範囲を指す言葉を用いて「どのように考えるか」と述べる文となっており、意味が重複するものとなってしまっている。
他にも、「婚姻制度」について論じる中で「婚姻ないし親子関係に対する規律」「を離れてこれを定めることはできない。」と述べるものとなっており、「婚姻制度」を「婚姻」の「規律」「を離れてこれを定めることはできない。」のように、意味が重複するものとなってしまっている。
このような、論理的な欠陥を抱えた文面となってしまっている理由は、最高裁の判例の文面が意図する射程が、憲法24条2項の「婚姻及び家族」の「要請」に従って立法されている法律上の「婚姻及び家族」の制度の内容の一部分である個別の効果に限られていることを理解せずに、その文面上の文言のみを引用してそれとは性質の異なる事案に当てはめようとしているからである。
そのため、この札幌高裁判決は引用の仕方として正当化することはできず、誤りであるといえる。
「これらを総合的に考慮した上で、婚姻制度をどのように定めるかは、立法府の合理的な裁量に委ねられているものというべきである。」との記載がある。
この文は、もともと最高裁の判例の文面が「相続制度」について述べている部分を「婚姻制度」に書き換えて論じるものである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
……(略)……これらを総合的に考慮した上で,相続制度をどのように定めるかは,立法府の合理的な裁量判断に委ねられているものというべきである。……(略)……
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件 最高裁判所大法廷 平成25年9月4日 (PDF)
この最高裁の文面は、憲法24条2項の「婚姻及び家族」の「要請」に従って立法されている法律上の「婚姻及び家族」の制度の一部分である「相続制度」について論じるものである。
この「婚姻及び家族」の枠組みは、「夫婦」と「親子」による「血縁関係者」の範囲を指すものであり、この枠組みを前提としてその「婚姻及び家族」の制度の一部分として定められている個別の効果が「立法府の合理的な裁量判断に委ねられている」ことを述べているものである。
これに対して、この札幌高裁判決では、「相続制度」の文言を「婚姻制度」の文言に置き換えて同様に検討することができるかのように論じるものとなっている。
しかし、「相続制度」は、憲法24条2項の「婚姻及び家族」の「要請」に従って立法されている法律上の「婚姻及び家族」の制度の一部分の個別の法的な効果であるのに対して、「婚姻制度」は憲法24条が定めている「婚姻」の対象とする人的結合関係の枠組みそのものに関わるものである。
これらは、異なる次元の問題であり、単に「相続制度」の文言を「婚姻制度」の文言に置き換えれば同様に意味の通じる文章になるというものではない。
そのため、ここで最高裁の判例が「相続制度」としている部分の文言を「婚姻制度」に置き換えることは、「婚姻制度」の枠組みが存在することを前提としてその枠組みに付随する形で設けられている個別の効果について論じている文面を、その個別の効果を定める際の適用範囲の前提となっている「婚姻制度」の枠組みそのものを論じる際にも同様に用いることができるかのように論じようとするものであることから、この最高裁の判例が前提としている憲法24条2項の「婚姻及び家族」の「要請」に従って立法されている法律上の「婚姻及び家族」の制度の一部分の個別の法的な効果について論じている範囲から逸脱するものであり、異なる次元の問題を同一視している点で論じ方として誤っている。
その他、最高裁の判例が論じている「相続制度」については、憲法24条2項の「婚姻及び家族」の枠組みの「要請」に従って立法されている法律上の「婚姻及び家族」の制度の一部分であり、これは「立法府の合理的な裁量判断に委ねられている」ものである。
これに対して、この札幌高裁判決が論じているのは「婚姻制度」であり、これは憲法24条が「婚姻」「両性」「夫婦」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めており、また、憲法24条2項の「婚姻及び家族」の枠組みでも「夫婦」と「親子」による「血縁関係者」として定められているものである。
この枠組みは憲法上の規定として定められているものであるから、これを自由に変えられるというものではなく、その枠を超える人的結合関係を「婚姻及び家族」の枠組みの中に含めるという権限は、「立法府」の国会であっても有しておらず、そこに「裁量」の余地はない。
そのため、その枠を超える人的結合関係を「婚姻及び家族」の枠組みの中に含めることについて「立法府の合理的な裁量に委ねられている」とはいえないものである。
よって、これがあることを前提として「婚姻制度をどのように定めるかは、立法府の合理的な裁量に委ねられているものというべきである。」と述べていることは誤りである。
「立法府の合理的な裁量に委ねられている」部分とは、氏の制度の在り方、財産関係の制度の在り方、扶養の制度の在り方、親権の制度の在り方などの個別の効果であり、「婚姻及び家族」の対象とする人的結合関係の枠組みそのものに関わらない部分に限られる。
同性愛者は、異性との間では婚姻ができることから、男か女かという性別による差別があるものではない。しかし、本件で問われているのは、本件規定が同性婚を許していないため、異性愛者は、異性と婚姻し、戸籍による公的な公証や種々の権利義務を伴う法的地位の付与及び種々の事実上のサービスの提供等を受けることができるにもかかわらず、同性愛者は、同性と婚姻してこのような効果を享受することができないことから、このような性的指向に係る婚姻制度における取扱いの区別(以下「本件区別取扱い」という。)が、合理的理由のない差別的取扱いに当たるか否かということであり、立法府に与えられた上記のような裁量権を考慮しても、本件区別取扱いをすることに合理的な根拠が認められない場合には、当該区別取扱いは、憲法14条1項に違反するものと解するのが相当である(最高裁平成24年(ク)第984号、第985号同25年9月4日大法廷決定・民集67巻6号1320頁参照)。
【筆者】
━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━
この段落が読み取りづらい理由は下記の通りである。
◇ 第二文が長すぎるため、途中で付いていけなくなる。
◇ 第二文は、始めに「しかし、」という逆接の接続詞を用いて一つ前の文を受けるものとなっている。
ただ、その一つ前の文と逆接の関係で意味が繋がっているのは、第二文の「本件で問われているのは、……(略)……が、合理的理由のない差別的取扱いに当たるか否かということであり、」との部分までであり、その後の「立法府に与えられた……(略)……相当である」の部分はこの「しかし、」とは意味が対応していない。
これにより、読み手は「しかし、」という接続詞を中心に一つ前の文との連続性を意識して文の構造を把握しようとすると、途中から話が変わってしまい、話に付いていけなくなるのである。
━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━
この段落の第二文は、参照として示している最高裁の判例を用いて論じているつもりのようである。
最高裁の判例と文面が重なるところは、下記の部分である。
(灰色で潰した部分が、第二文と文面が重なる部分である。)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
……(略)……この事件で問われているのは,このようにして定められた相続制度全体のうち,本件規定により嫡出子と嫡出でない子との間で生ずる法定相続分に関する区別が,合理的理由のない差別的取扱いに当たるか否かということであり,立法府に与えられた上記のような裁量権を考慮しても,そのような区別をすることに合理的な根拠が認められない場合には,当該区別は,憲法14条1項に違反するものと解するのが相当である。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(PDF)
この最高裁の判例の場合は、「民法900条4号ただし書の規定のうち嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする部分」を対象としており、法律の条文の中に区別取扱いが存在した事例である。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
原審は,民法900条4号ただし書の規定のうち嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする部分(以下,この部分を「本件規定」という。)は憲法14条1項に違反しないと判断し,本件規定を適用して算出された相手方ら及び抗告人らの法定相続分を前提に,Aの遺産の分割をすべきものとした。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(PDF)
これに対して、この札幌高裁判決では「性的指向に係る婚姻制度における取扱いの区別」のように取り上げているが、民法の中に「性的指向」について定めた具体的な条文は存在しておらず、そもそも「性的指向」と称するものによる「取扱いの区別」は存在していない。
よって、この最高裁の判例と同様の形で論じることができるという前提にないのであり、最高裁の判例を参照する形で論じることができるかのように述べていることは誤りである。
「同性愛者は、異性との間では婚姻ができることから、男か女かという性別による差別があるものではない。」との記載がある。
この文は、「異性との間では婚姻ができる」ということを理由にして、「男か女かという性別による差別があるものではない。」と結論付けるものである。
そのため、この文の内容は「男」と「女」の間で「性別」に基づく形で「差別」(法的な議論としては「区別」と同じ意味)が存在するかどうかが問われていることが前提となっている。
そして、「男」と「女」のどちらの「性別」の者であっても「異性との間では婚姻ができる」という理由により、「男か女かという性別による差別があるものではない。」との結論が導かれている。
◇ 男性:「異性との間では婚姻ができる」
◇ 女性:「異性との間では婚姻ができる」
⇒ 「男か女かという性別による差別があるものではない。」
国(行政府)の主張では下記の部分である。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
しかしながら,憲法14条1項が規定する法の下の平等とは,同一の事情と条件の下では均等に取り扱うことを意味すると解されるところ(芦部信喜〔高橋和之補訂〕「憲法第七版」132ページ参照),本件規定の下では,男性も女性も異性とは婚姻をすることができる一方で,どちらの性も同性とは婚姻をすることは認められていないのであるから,本件規定が性別を理由に差別的取扱いを生じさせていると評価することはできない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【東京二次・第3回】被告第2準備書面 令和3年11月30日 PDF
しかし、問題はこの文は「同性愛者は、」が主題となっており、「男か女か」ということによって「差別」があるかとは別の話となっていることである。
下記で、通常想定される文と、この文を比較する。
◇ 通常想定される文
男性も女性も「異性との間では婚姻ができることから、男か女かという性別による差別があるものではない。」
◇ この文
「同性愛者は、異性との間では婚姻ができることから、男か女かという性別による差別があるものではない。」
そのため、「同性愛者は、」の部分を主題とするのであれば、「異性との間では婚姻ができる」ことを述べた後には、「同性愛者」であるか否かという「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかについての「性的指向」と称しているものによる「差別があるものではない。」と論じることが文としては意味が通じるものとなる。
それにもかかわらず、ここでは「同性愛者は、」を主題としながら、結論部分で「男か女か」という「同性愛者」であるか否かとは対応しない事柄を持ち出して説明をするものとなっており、文として意味が通じないものとなっている。
次に、この文の「同性愛者は、異性との間では婚姻ができる」との部分に着目して検討する。
ここでは、「同性愛者は、異性との間では婚姻ができる」と述べている。
これは、婚姻制度が人の内心を審査して「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかによって区別取扱いをするような制度ではないことを明らかにしているといえる。
そのため、「同性愛者」を称する者が「同性愛者」を称するものであることを理由として区別取扱いをされているという事実はなく、区別取扱いをしていない事柄を憲法14条1項の「平等原則」によって審査することはできず、結果として、憲法14条1項の「平等原則」に違反することもないということになる。
しかし、この判決はここで「同性愛者は、異性との間では婚姻ができる」と述べているにもかかわらず、別の個所では「同性愛者」は「婚姻」できない旨を述べており、矛盾するものとなっている。
「3 本件規定が憲法24条に違反する旨の主張について」
◇ 「同性愛者は婚姻による社会生活上の制度の保障を受けられない。」
「4 本件規定が憲法14条1項に違反する旨の主張について」
◇ 「同性愛者は、婚姻によって生じる法的効果を享受することができない。」
◇ 「同性愛者等が法律的な婚姻等へのアクセス等において差別的な扱いに直面しており、」
◇ 「同性愛者が婚姻することができないことによる不利益を緩和するため、」
◇ 「同性愛者は婚姻することができず、」
◇ 「同性愛者も、婚姻することができなくても、」
◇ 「同性愛者が婚姻することができない場合の不利益を解消することができるとは認め難い。」
◇ 「同性愛者に対しては婚姻を許していないことは、」
ある特定の法制度が定められている場合に、個々人がそれを利用することができるか否かという問題と、その法制度が自己の望む通りの形となっていないことによって利用を控えるという問題を切り分けて考える必要がある。
この判決はこの点を混同しているために、矛盾が生じてしまっているのである。
「本件で問われているのは、本件規定が同性婚を許していないため、異性愛者は、異性と婚姻し、戸籍による公的な公証や種々の権利義務を伴う法的地位の付与及び種々の事実上のサービスの提供等を受けることができるにもかかわらず、同性愛者は、同性と婚姻してこのような効果を享受することができないことから、このような性的指向に係る婚姻制度における取扱いの区別(以下「本件区別取扱い」という。)が、合理的理由のない差別的取扱いに当たるか否かということであり、立法府に与えられた上記のような裁量権を考慮しても、本件区別取扱いをすることに合理的な根拠が認められない場合には、当該区別取扱いは、憲法14条1項に違反するものと解するのが相当である」との記載がある。
「本件規定が同性婚を許していないため、」との部分について検討する。
この「同性婚」の意味が「同性間の人的結合関係」を形成することを指しているのであれば、それは憲法21条1項の「結社の自由」で保障されている。
「本件規定」もそれを規制するものではないため、「許していない」と述べていることは誤りとなる。
この「同性婚」の意味が「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを指しているのであれば、「本件規定」は「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを定めていないといえる。
ただ、これは法制度が定められているか否かの問題であるから、「許していない」のようにむやみに「許す・許さない」という意味の表現を用いることは適切であるとはいえない。
このような表現は、法制度の性質について客観的な視点から説明するものとして用いられる言葉遣いではなく、別の個所の「不利益」などの文言と相まって、訴訟の当事者の一方の見方や意見、感じ方に与する形で論じるものとなっていることが考えられる。
そのため、敢えてこのような表現を用いていることは、公的な性格を持ち、中立性が求められる裁判所の立場で用いる言葉の選択として適切であるとはいえない。
「異性愛者は、異性と婚姻し、戸籍による公的な公証や種々の権利義務を伴う法的地位の付与及び種々の事実上のサービスの提供等を受けることができるにもかかわらず、同性愛者は、同性と婚姻してこのような効果を享受することができないことから、」との部分について検討する。
ここには「異性愛者」と「同性愛者」の文言がある。
まず、「異性愛者」と「同性愛者」の二分論で考えるという前提そのものが特定の価値観に基づく分類に過ぎないものである。
また、そもそも法律論としては人をその内心に基づいて区別して取扱うようなことをしてはならない。
そのため、特定の価値観で人を分類しようとする者の用いている一つの思想を持ち出して、人の内心に基づいて区別して考えることが可能であるかのような前提で論じていることそのものが誤りである。
婚姻制度は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」を目的とし、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす「一人の男性」と「一人の女性」が選び出され、その間に「貞操義務」を設けるなど一定の形式で法的に結び付け、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となる関係を推進し、血縁関係を明確にする機能によって立法目的の達成を目指すものである。
この婚姻制度は「性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や、「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いをするものではないし、「性愛」に基づいて制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもない。
そのことから、個々人の「性愛」の有無や、「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかなど、一切関知していない。
よって、婚姻制度は「男女二人一組」などの要件を満たして婚姻意思を有しているのであれば、どのような思想、信条、信仰、感情を有している者であっても利用することが可能である。
そのことから、ここで「異性愛者は、」と「同性愛者は、」のように両者を比較し、「異性愛者」を称する者は「戸籍による公的な公証や種々の権利義務を伴う法的地位の付与及び種々の事実上のサービスの提供等を受けることができる」が、「同性愛者」を称する者は「このような効果を享受することができない」かのように述べているが、「同性愛者」を称する者でも、婚姻制度(男女二人一組)の要件を満たして婚姻意思を有しているのであれば、適法に婚姻することが可能であることから、「戸籍による公的な公証や種々の権利義務を伴う法的地位の付与及び種々の事実上のサービスの提供等を受けることができる」のであり、「このような効果を享受することができない」ということはない。
実際、「同性愛者」を称する者も婚姻制度(男女二人一組)を利用している事実は認められるのであり、「戸籍による公的な公証や種々の権利義務を伴う法的地位の付与及び種々の事実上のサービスの提供等」を受けている事実は認められる。
そのため、婚姻制度が「異性愛者」と称する者と「同性愛者」を称する者を区別し、その「同性愛者」を称する者に「戸籍による公的な公証や種々の権利義務を伴う法的地位の付与及び種々の事実上のサービスの提供等」をしていないかのような認識の下に論じているとすれば誤りである。
次に「異性愛者は、異性と婚姻し、」とある。
これは「異性愛者は、異性と婚姻」するという前提を基にするのであることから、婚姻制度を利用する際に「性愛」を有していなければならず、かつ、「性的指向」と称するものが向く相手でなければならないという特定の価値観を前提とするものである。
しかし、これはその価値観を有していなければ婚姻制度を利用することは認められないとか、認めるべきではないとか、正当な利用ではないなどと評価しようとするものであるから、婚姻制度を利用する者の内心に対して国家権力が介入しようとするものということができ、憲法19条の「思想良心の自由」、憲法20条1項前段の「信教の自由」に違反するものである。
また、婚姻制度(男女二人一組)が「異性愛者」を称する者を対象とした制度であるかように考え、その他の者を対象としていないかのように考えるものであるから、その他の者との間で憲法14条1項の「平等原則」における「法適用の平等」に違反するものである。
さらに、婚姻制度(男女二人一組)があたかも「異性愛」という特定の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的とした制度であるかのように考えようとするものであるから、憲法20条1項後段・3項、89条の「政教分離原則」に違反するものである。
そのため、婚姻制度(男女二人一組)が個人の内心に対して介入しようとするものとして存在していても許されるかのように考えていることは誤りであるし、「異性愛」という特定の思想、信条、信仰、感情を抱く者を対象とした制度として存在していても許されるかのように考えていることは誤りであるし、「異性愛」という特定の思想、信条、信仰、感情を保護するものとして存在しているとしてもそれが許されるかのような前提の下に論じていること自体が誤りである。
「戸籍による公的な公証や種々の権利義務を伴う法的地位の付与及び種々の事実上のサービスの提供等を受けることができるにもかかわらず、」とある。
この「戸籍による公的な公証や種々の権利義務を伴う法的地位の付与及び種々の事実上のサービスの提供等」は、婚姻制度の立法目的を達成するための手段として設けられたものであり、婚姻制度の立法目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす人的結合関係のみを対象として定めているものである。
よって、婚姻制度の立法目的を達成するための手段として整合的な要素を満たさない場合に対してまで、婚姻制度による「戸籍による公的な公証や種々の権利義務を伴う法的地位の付与及び種々の事実上のサービスの提供等」をしなければならないということにはならない。
そのことから、「にもかかわらず、」のように別のものと比較することを含む言葉を使い、婚姻制度の立法目的を達成するための手段として整合的な要素を満たさない場合に対してまで、同様に「戸籍による公的な公証や種々の権利義務を伴う法的地位の付与及び種々の事実上のサービスの提供等」をしなければならないとか、するべきであるなどと論じようとしているのであれば誤りである。
「同性と婚姻してこのような効果を享受することができないことから、」とある。
先ほども述べたように、「婚姻」は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」を目的として、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす「一人の男性」と「一人の女性」を選び出し、その間に「貞操義務」を設けるなど一定の形式で法的に結び付け、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によって立法目的の達成を目指すものである。
「同性」間の人的結合関係については、その間で生殖を想定することができず、この趣旨を満たすものではないことから、「婚姻」とすることはできない。
よって、「同性と婚姻してこのような効果を享受することができないことから、」との部分は、「同性」間の人的結合関係を「婚姻」とすることはできず、また、「婚姻」を対象として設けられている「このような効果」を「婚姻」の対象とはならない「同性」間に対してまで設けなければならないという前提にないものである。
【札幌・第2回】被控訴人第1準備書面 令和4年3月4日 PDF (P21~24)
上記のように、「異性愛者」や「同性愛者」を基に論じることは妥当でない。
そのため、この文から「異性愛者」と「同性愛者」の部分をカットして検討する。
すると、下記のようになる。
◇ 「異性愛者は、異性と婚姻し、戸籍による公的な公証や種々の権利義務を伴う法的地位の付与及び種々の事実上のサービスの提供等を受けることができるにもかかわらず、同性愛者は、同性と婚姻してこのような効果を享受することができない」
↓ ↓ ↓ (カット)
◇ 「異性と婚姻し、戸籍による公的な公証や種々の権利義務を伴う法的地位の付与及び種々の事実上のサービスの提供等を受けることができるにもかかわらず、」「同性と婚姻してこのような効果を享受することができない」
このように、結局この文は下記の趣旨を述べているだけである。
◇ 「異性と婚姻」できるが「同性と婚姻」できない
そして、「異性と婚姻」することができるが、「同性と婚姻」することができないことは、「婚姻」が「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」を目的とし、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす「一人の男性」と「一人の女性」の組み合わせを選び出し、その間に「貞操義務」を設けるなど一定の形式で法的に結び付け、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によって立法目的を達成することを目指す枠組みであることによるものである。
婚姻制度は、その制度を利用している場合と利用していない場合との間に差異を設け、その制度を利用する者を増やすことによって立法目的の達成を目指すものであることから、制度の対象となる場合とならない場合との間に差異が生じることは、「婚姻」という枠組みを設けている時点でもともと予定されていることである。
そのため、「婚姻」の対象とならない場合に対してまで、「戸籍による公的な公証や種々の権利義務を伴う法的地位の付与及び種々の事実上のサービスの提供等」を設けなければならないということにはならない。
国(行政府)は下記のように説明している。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)本件規定に基づき同性間で婚姻をすることができないことは、憲法自体が予定し、かつ、許容するものであり、憲法14条1項に違反しないこと
被告第4準備書面第3の1(16ないし18ページ)で述べたとおり、特定の憲法の条項を解釈するに当たっては、関係する憲法の他の規定との整合性を考慮する必要があると解されるところ、憲法24条1項の定める婚姻が異性間の人的結合関係のみを対象とするものとして本件規定により制度化され、同性間の人的結合関係を対象とするものとして制度化されないという事態(差異)が生じることは、憲法24条が婚姻について異性間の人的結合関係のみを対象とすることを明文で定め、婚姻に係る法制度の構築を法律に委ねていることの当然の帰結にすぎず、同性間では本件規定に基づき婚姻をすることができないことは、憲法自体が予定し、かつ許容するものであると解するのが相当である。
そうすると、本件規定が婚姻について異性間の人的結合関係を対象とし、同性間の人的結合関係を対象とするものとして定めておらず、本件規定に基づき同性間で婚姻をすることができないことは、憲法自体が予定し、かつ許容しているものであって、憲法24条に違反するものといえないことはもとより、憲法14条1項に違反すると解することもできないというべきである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【九州・第11回】被告第6準備書面 令和4年11月30日 PDF (P11)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
このような観点から本件諸規定についてみると、本件諸規定が婚姻を異性間についてのものとして定めていることから、本件諸規定に基づき同性間で婚姻することはできないが、前記第3の2(2)及び(3)において述べたとおり、憲法24条1項が婚姻について異性間の人的結合関係のみを対象とすることを明文で定め、同性間の人的結合関係を対象とすることを想定していないことからすると、同条2項による要請に基づき同条1項の婚姻に関する事項を具体化する本件諸規定が異性間の人的結合関係のみを対象としているのは当然である。そして、被控訴人原審第3準備書面第3の2(14ないし17ページ)において述べたとおり、特定の憲法の条項を解釈するに当たっては、関係する憲法の他の規定との整合性を考慮する必要があると解されるところ、憲法24条1項の定める婚姻が異性間の人的結合関係のみを対象とするものとして本件諸規定により制度化され、同性間の人的結合関係を対象とするものとして制度化されない事態(差異)が生じることは、憲法24条が婚姻について異性間の人的結合関係のみを対象とすることを明文で定め、婚姻に係る法制度の構築を法律に委ねていることの当然の帰結にすぎず、同性間では本件諸規定に基づき婚姻することができないことは、憲法自体が予定し、かつ許容するものであると解するのが相当である。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【東京一次・第1回】控訴答弁書 令和5年6月23日 PDF (P36)
「異性愛者は、異性と婚姻し、戸籍による公的な公証や種々の権利義務を伴う法的地位の付与及び種々の事実上のサービスの提供等を受けることができるにもかかわらず、同性愛者は、同性と婚姻してこのような効果を享受することができないことから、このような性的指向に係る婚姻制度における取扱いの区別(…)が、」(カッコ内省略)としている部分について検討する。
「異性愛者は、異性と婚姻し、戸籍による公的な公証や種々の権利義務を伴う法的地位の付与及び種々の事実上のサービスの提供等を受けることができるにもかかわらず、同性愛者は、同性と婚姻してこのような効果を享受することができない」ということが、「性的指向に係る婚姻制度における取扱いの区別」の根拠であると考えることを示すものとなっている。
しかし、上記で述べたように、婚姻制度は「性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いをする制度ではないし、「性愛」に基づいて制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもない。
そのため、婚姻制度が「性的指向に係る」「取扱いの区別」をしている事実はない。
これについて、国(行政府)は下記のように説明している。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
このような観点から本件規定をみると、本件規定は、一人の男性とー人の女性との問の婚姻を定めるものであり、その文言上、婚姻の成立要件として当事者に特定の性的指向を有することを求めたり、当事者が特定の性的指向を有することを理由に婚姻を禁じたりするものではなく、その趣旨・内容や在り方自体が性的指向に応じて婚姻制度の利用の可否を定めているものとはいえないから、性的指向について中立的な規定であるということができる。さらに、本件規定は、異性間の婚姻を前提とする憲法24条の規定を受けて定められたものである上、本件規定の淵源は、被告第4準備害面第3の2(3)ウ(7)(37及び38ページ)において述べたとおり、我が国において、ー人の男性と一人の女性の人的結合関係が、今後の社会を支える次世代の子を産み、育みつつ、我が国の社会を構成し、支える自然的かつ基礎的な集団単位である家族をその中心となって形成しているという実態があって、当該実態に対して歴史的に形成されてきた社会的な承認が存在していることを背景に、男女間の結合としての婚姻の慣習が法制度化されたことにあるところ、そのような経緯で成立した本件規定の立法目的である「一人の男性と一人の女性が子を産み育てながら共同生活を送るという関係に対して特に法的保護を与えること」は、それ自体、性的指向に着目して法的な差別的取扱いを生じさせることを趣旨として含むものではなく本件規定が性的指向について中立的なものであることは明らかである。そうであるとすると、本件規定が区別の事由を性的指向に求めているものと解することは相当ではない。……(略)……
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【九州・第9回】被告第5準備書面 令和4年6月16日 PDF (P16)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
また、本件規定は、異性間の婚姻を前提とする憲法24条の規定を受けて定められたものである上、本件規定の淵源は、被告第2準備書面第5の2(3)イ(ア)(42及び43ページ)で述べたとおり、我が国において、一人の男性と一人の女性の人的結合関係が、今後の社会を支える次世代の子を産み、育みつつ、我が国の社会を構成し、支える自然的かつ基礎的な集団単位である家族をその中心となって形成しているという実態があって、当該実態に対して歴史的に形成されてきた社会的承認が存在していることを背景に、男女間の結合としての婚姻の慣習が法制度化されたことにあるところ、そのような経緯で成立した本件規定の立法目的である「一人の男性と一人の女性が子を産み育てながら共同生活を送るという関係に対して特に法的保護を与えること」は、それ自体、性自認や性的指向に着目して法的な差別取扱いを生じさせることを趣旨として含むものではなく本件規定が性自認や性的指向について中立的なものであることは明らかである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【東京二次・第5回】被告第3準備書面 令和4年6月30日 PDF
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
他方,原告らの主張が,個々の国民という個人を主体とする法令上の区別をいうものと解したとしても,被告第2準備書面第3の3 (1)イ(21ページ)で述べたとおり,本件規定は,制度を利用することができるか否かの基準を,具体的・個別的な婚姻当事者の性的指向の点に設けたものではなく,本件規定の文言上,同性愛者であることに基づく法的な差別的取扱いを定めているものではないから,この点に法令上の区別は存在しない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【大阪・第6回】被告第4準備書面 令和3年2月19日 PDF
よって、「このような性的指向に係る婚姻制度における取扱いの区別」との部分は、「婚姻制度」は「性的指向」によって「取扱いの区別」をしているものではないし、「このような」と示してる部分は、「性的指向に係る」「取扱いの区別」をしているとする根拠とはならないことから、「このような性的指向に係る婚姻制度における取扱いの区別」と述べている部分は誤りとなる。
【参考】「結婚がラブ、つまり個人の性愛の結実とするならば、それを社会が承認、支援する必要は無い」 Twitter
【参考】「同性が好き、異性が好きって国が保護すべきなん?」 Twitter
【参考】「国が個人間の恋愛に介入・承認する必要がそもそもない」 Twitter
【参考】「家族や家庭を作るとき、土台に恋愛感情が必要なんだろうか…同居、協力、扶助は恋愛感情がなくてもできる」 Twitter
【参考】「愛がなくても二人の合意さえあれば法的に結婚出来るので『愛の有無』は論点がズレてる」 Twitter
【参考】「『愛し合う』が前提だとしたら、お見合い結婚や政略結婚が偽装になってしまう。」 Twitter
【参考】「『異性婚には性的指向の前提はない』」……「婚姻=異性婚について『異性愛者でないから認められない』ということはありません」 Twitter
これに対して、この判決が「異性愛者は、異性と婚姻し、」のように述べて、「婚姻制度」が「性的指向に係る」「取扱いの区別」をする制度であることを前提として論じるものとなっている。
しかし、このように「婚姻制度」を「異性愛」を保護することを目的とした制度であったり、「異性愛者」を称する者を対象とした制度であったり、「異性愛」に基づいて制度を利用することを求めたり勧めたりする制度であるかのように説明することは、これまで法制度としては存在していなかった「性的指向」による「取扱いの区別」をこの判決の中で初めて行うものということができる。
これは、「異性愛」という特定の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的とした制度が存在するとしても許されるかのように論じるものであり、憲法20条1項後段・3項、89条の「政教分離原則」に違反するものである。
また、「異性愛者」を称する者を制度の対象とし、それ以外の「性愛」を有する者と称する者や、「性愛」以外の思想、信条、信仰、感情を有する者を制度の対象としないということになるから、憲法14条1項の「平等原則」に違反するものである。
他にも、法制度を利用する者の内心に対して国家が干渉する制度が存在するとしても許されるかのように論じるものであり、憲法19条の「思想良心の自由」に違反するものである。
よって、この判決は「婚姻制度」が「性的指向」によって「取扱いの区別」がされていることを前提に「婚姻制度」が違憲となるか否かを論じようとしているが、「婚姻制度」そのものには「性的指向」による「取扱いの区別」は存在しておらず違憲とはならないのに対して、むしろこの判決が「婚姻制度」が「性的指向」によって「取扱いの区別」をしている制度であるかのように論じていること自体が違憲となるものである。
これとは別に、法制度において「性的指向」による「取扱いの区別」が存在するといえる状態とは、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかについて審査し、その審査の結果に基づいてそれらを異なるものに区別し、その区別に従って法制度の適用の可否が分かれる場合のことである。
例えば、「小児性愛」であるか否かを審査して、その審査の結果に応じて教員採用試験を受験することを禁じるなどして「職業選択の自由」を制約するなどの場合がこれに当たるということができる。
【参考】<わいせつ行為で処分された教員は9年連続200人以上>愛知医科大准教授が小児性愛障害診断テストを開発中「日本版DBSだけでは子どもへの性犯罪を防げない」 2023.09.28
しかし、「婚姻制度」はそのような制度ではないため、「婚姻制度」が「性的指向」によって「取扱いの区別」をしているという事実はない。
よって、ここで「性的指向に係る婚姻制度における取扱いの区別」が存在するかのように論じていることは誤りとなる。
その他、「異性間の人的結合関係」が婚姻制度の対象となっており「同性間の人的結合関係」が対象となっていないことについては、「取扱いの区別」ではなく、「婚姻」が「男女二人一組」を満たすことを条件としており、それを満たさない場合を制度の対象としていないことによるものである。
この「男女二人一組」の枠組みは憲法24条の「婚姻」という概念そのものや「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言に基づくものであり、憲法上の他の条文に定められている事柄であることから、憲法14条1項の「平等原則」によって審査することはできないものである。
「異性愛者は、異性と婚姻し、戸籍による公的な公証や種々の権利義務を伴う法的地位の付与及び種々の事実上のサービスの提供等を受けることができるにもかかわらず、同性愛者は、同性と婚姻してこのような効果を享受することができないことから、このような性的指向に係る婚姻制度における取扱いの区別(…)が、合理的理由のない差別的取扱いに当たるか否かということであり、」(カッコ内省略)との部分について検討する。
上記で説明したように、そもそも「性的指向」による「取扱いの区別」は存在しておらず、「取扱いの区別」が存在することを前提として初めて検討することが可能となる「合理的理由」の存否を検討する余地がない。
また、ここでは「合理的理由のない差別的取扱いに当たるか否か」を論じる中で、「戸籍による公的な公証や種々の権利義務を伴う法的地位の付与及び種々の事実上のサービスの提供等を受けることができる」かどうかを検討しているが、これは婚姻の効力の問題ではないものを含めるものであり、これを根拠に婚姻制度の憲法適合性を検討するものとなっている点でも誤っている。
これについて、国(行政府)は下記のように述べている。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
なお、そのほか、原告らが訴状において主張する法的・経済的な権利・利益及び事実上の利益(訴状第6の3(3)〔45ないし52ページ〕)は、いかなる範囲の者を優遇措置や支給などの対象とするかという社会保障政策等の当否の問題や私人間の契約の問題であり、婚姻の効力の問題とはいえないから、やはり本件規定による取扱いの不合理性を基礎づける事情とはいえない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【大阪・第5回】被告第2準備書面 令和2年3月26日 PDF (P24~25)
「取扱いの区別(…)が、合理的理由のない差別的取扱いに当たるか否か」との部分には、「取扱いの区別」と「差別的取扱い」の文言がある。
しかし、法律論として考えた場合には、「区別」と「差別」は同じ意味であり、その「区別」(差別)が存在した場合における合理性の有無が論点である。
そのため、ここで「区別」と書いたり「差別」と書いたりして論じていることは、統一性がなく、読み手を混乱させるものとなるため適切ではない。
恐らく「差別的取扱い」の部分は、日常用語としての「差別」の意味として、何らかの否定的な意味を含ませる形で論じようとしているものと考えられる。
しかし、日常用語としての何らかの否定的な意味を含む「差別」の意味を法的に考えれば、「区別に合理的な理由がない」という結論と対応する意味で用いられているものである。
そのため、この意味をこの文に当てはめると、「取扱いの区別(…)が、合理的理由のない『区別に合理的な理由がない』取扱いに当たるか否か」のように述べていることになり、同義反復となるため文法上の誤りとなる。
よって、ここで「差別」の意味を日常用語の意味として用いようとしているとしても誤っていることになる。
「立法府に与えられた上記のような裁量権を考慮しても、本件区別取扱いをすることに合理的な根拠が認められない場合には、当該区別取扱いは、憲法14条1項に違反するものと解するのが相当である」との部分について検討する。
「立法府に与えられた上記のような裁量権を考慮しても、」とある。
まず、「異性」間の人的結合関係が婚姻制度の対象なっており、「同性」間の人的結合関係が婚姻の対象となっていないことについては、憲法24条の「婚姻」の文言それ自体や「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言が一夫一婦制(男女二人一組)を定めていることによるものである。
これは憲法上の条文として定められている事柄であることから、「立法府」はこれに従って法律を立法することが求められており、この一夫一婦制(男女二人一組)の有する「婚姻」の機能を阻害する形で法律を立法することはできない。
そのため、「男女二人一組」を超える人的結合関係を「婚姻」の中に含めるという権限は「立法府」であっても有していない。
よって、ここで「同性」間の人的結合関係を「婚姻」とすることについて、「立法府」が「裁量権」として有しているかのような前提で、「立法府に与えられた上記のような裁量権を考慮しても、」と述べていることは誤りである。
また、「男女二人一組」に対して制度を設けていることについては、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」という目的を達成するための手段として整合的な要素を満たすものであることから、その制度を利用する者に対して法的効果や一定の優遇措置を設け、その制度を利用しない者との間で差異が生じるとしても、その内容がその目的を達成するための手段として不必要に過大なものでない限りは正当化することが可能であり、憲法14条1項の「平等原則」に違反しないということができる。
それに対して、「同性」間の人的結合関係については、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的からは導かれないものであることから、そこに法的効果や一定の優遇措置を設けることは、その制度を利用しない者との間で生じる差異を正当化することはできず、憲法14条1項の「平等原則」に違反することになる。
よって、ここでは「立法府」に「裁量権」があることを前提として、婚姻制度が「同性」間の人的結合関係を対象としていないことについて憲法14条1項に違反するかを論じようとしているが、むしろ、この判決が述べるような「同性」間の人的結合関係を対象とした制度を設けることの方が憲法14条1項の「平等原則」に違反するものであるということになる。
そのため、この意味でも「同性」間の人的結合関係を対象とした制度を設けることについて、「立法府」に「裁量権」があるとはいえないのであり、ここで「立法府」が「裁量権」として有しているかのような前提で、「立法府に与えられた上記のような裁量権を考慮しても、」と述べていることは誤りである。
「本件区別取扱いをすることに合理的な根拠が認められない場合には、当該区別取扱いは、憲法14条1項に違反するものと解するのが相当である」とある。
ここでいう「本件区別取扱い」とは、「性的指向に係る婚姻制度における取扱いの区別」のことであるが、そもそも婚姻制度は「性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いをする制度ではないし、「性愛」に基づいて制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもなく、「性愛」に関わらない制度であることから、「性的指向に係る」「取扱いの区別」は存在していない。
そのため、ここで「区別取扱い」か存在することを前提として論じていることは誤りである。
また、「区別取扱い」が存在しないから、その「区別取扱い」についての「合理的な根拠」の有無についても検討する余地はない。
そのことから、「区別取扱い」が存在しないという点で、「憲法14条1項」で審査することができるとする前提になく、「憲法14条1項」に違反するということにはならないものである。
よって、「本件区別取扱いをすることに合理的な根拠が認められない場合には、当該区別取扱いは、憲法14条1項に違反するものと解するのが相当である」のように、「区別取扱い」が存在することを前提として「憲法14条1項に違反する」か否かを論じていることは誤りである。
その他、「異性」間の人的結合関係が婚姻制度の対象なっており、「同性」間の人的結合関係が婚姻の対象となっていないことについては、憲法24条の「婚姻」の文言それ自体や「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言が一夫一婦制(男女二人一組)を定めていることによるものである。
これは憲法上の他の条文に定められている事柄であることから、これを同じく憲法上の条文である14条1項の「平等原則」によって審査することはできない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
しかしながら、控訴答弁書第4の1(2)(35ないし37ページ)で述べたとおり、憲法24条1項の定める婚姻が異性間の人的結合関係のみを対象とするものとして本件諸規定により制度化され、他方、同性間の人的結合関係を対象とするものとして制度化されず、同性間で婚姻することができない事態が生じることは、憲法自体が予定し、かつ許容するものであるから、このような事態(差異)が生じることをもって、本件諸規定が憲法14条1項に違反すると解することはできない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【東京一次・第3回】被控訴人第2準備書面 令和6年2月29日 PDF
(3) 本件区別取扱いに関する合理的根拠の有無について検討する。これらの検討は、本件規定が憲法24条に違反するかどうかを説示したところとほぼ同じである。
【筆者】
「本件区別取扱いに関する合理的根拠の有無について検討する。」との記載がある。
しかし、婚姻制度は「性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いをする制度ではないし、「性愛」に基づいて制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもない。
そのため、婚姻制度は「男女二人一組」などの要件を満たして婚姻意思を有しているのであれば、どのような思想、信条、信仰、感情を有しているものであるとしても利用することが可能である。
そのことから、「性愛」という個人の内心における心理的・精神的なものがどのような対象に向かうかという「性的指向」と称するものによる「区別取扱い」は存在していない。
よって、「性的指向」と称するものによる「区別取扱い」が存在するかのような前提で「本件区別取扱い」と論じていることは誤りである。
また、「区別取扱い」は存在しないことから、その「合理的根拠の有無」について「検討」する前提を欠いており、「合理的根拠の有無について検討する。」と述べていることも誤りとなる。
「これらの検討は、本件規定が憲法24条に違反するかどうかを説示したところとほぼ同じである。」との記載がある。
まず、「憲法24条に違反するかどうか」の「検討」の結果、「憲法24条に違反する」ことになるのは、「憲法24条」の「婚姻」の枠組みが「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とする法律を立法することを「要請」している場合である。
これに対して、この項目で問われている憲法14条1項は「平等原則」について定めた規定であることから、何らの枠組みも示しておらず、当然、特定の制度の創設を「要請」しているものではない。
そのため、この「憲法24条に違反するかどうか」という点と、憲法14条1項に違反するかどうかという点の「検討」が「ほぼ同じ」となるということはない。
よって、ここで憲法14条1項に違反するかどうかの「検討」について、「憲法24条に違反するかどうかを説示したところとほぼ同じである。」と述べていることは妥当でない。
その他、憲法14条1項に違反するかどうかと「憲法24条に違反するかどうか」が「ほぼ同じ」「検討」によって結論が導き出される場合とは、憲法24条2項の「婚姻及び家族」の枠組みの「要請」に従って法律上の「婚姻及び家族」の制度が定められていることを前提として、その「婚姻及び家族」の枠組みの中の「男性」と「女性」の間の平等について問われた場合である。
これについては、憲法14条1項の「平等原則」と、憲法24条2項の「婚姻及び家族」の枠組みに対して適用される「両性の本質的平等」が同時に審査され、どちらも「平等」について定めているという点で「ほぼ同じ」になる場合が考えられる。
しかし、この札幌高裁判決で問われているのは、そもそも憲法24条の「婚姻」の枠組みが「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とする法律を立法することを「要請」しているか否かという点である。
これらは問われている論点が異なるため、この札幌高裁判決の事案において、憲法14条1項に違反するかどうかと「憲法24条に違反するかどうか」が「ほぼ同じ」であると述べることは、これらを区別できていない点で誤りである。
ア 本件規定は、憲法24条1項が文言上両性間の婚姻を定め、憲法制定当時には同性婚が想定されなかったことから、異性間の婚姻を定めたものと解されてきた。
【筆者】
ここには「両性間の婚姻」や「異性間の婚姻」という文言がある。
これはあたかも「両性間」=「異性間」の「婚姻」と、それ以外の「婚姻」が存在するかのような言葉遣いとなっており、正しい説明であるとは言い難い。
まず、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」を目的として、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす「一人の男性」と「一人の女性」の組み合わせを選び出し、その間に「貞操義務」を設けるなど一定の形式で法的に結び付け、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によって立法目的の達成を目指す仕組みを「婚姻」と呼んでいる。
憲法24条が「婚姻」を規定し、「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めていることも、すべてこの意味に対応するものとなっている。
そのため、「婚姻」であることそれ自体において、「男性」と「女性」の組み合わせによるものしか存在しないのであり、ここで述べているように「両性間の婚姻を定め、」や「異性間の婚姻を定めたものと解されてきた。」どころか、「婚姻」であればそれはそもそも「両性間」=「異性間」について述べるものということである。
このことから、「両性間の婚姻」や「異性間の婚姻」という言葉は、「両性間」=「異性間」という「男性」と「女性」を指す言葉と、「婚姻」という「男性」と「女性」の組み合わせを指す概念を同時に用いるものとなっており、文法上は「同義反復」となるため誤用ということになる。
また、「同義反復」となることを無視して、「両性間の婚姻」や「異性間の婚姻」という言葉を使ったとしても、「男性」と「女性」の組み合わせを備えない形で「婚姻」という概念は成立し得ず、「婚姻」であることそれ自体で既に「男性」と「女性」の組み合わせによる「異性間」を指す意味しか存在しないことから、「両性間の婚姻」や「異性間の婚姻」という言葉に対する形で、それ以外の「婚姻」というものが成立するという余地はない。
そのため、この「両性間の婚姻」や「異性間の婚姻」という言葉に対する形で「同性間の婚姻」というものが存在するということにはならない。
そのことから、その「婚姻」という言葉だけを刈り取ってその概念が形成されている目的から切り離して考えて、「婚姻」という空の箱(言葉の意味から切り離された『音の響き』に過ぎないもの)の中に何らかの人的結合関係を詰め込むことができるという性質のものではない。
◇ 本来の意味
「男性」と「女性」の組み合わせ ⇒ 法的に結び付ける形を「婚姻」とする
◇ この判決の言葉の使い方
「婚姻」は空箱 ⇒ どのような人的結合関係でも詰め込むことができる
よって、「異性間の婚姻」のように、「婚姻」という概念そのものを、その概念が形成されている目的との間で切り離して、どのような意味としてでも用いることができるような前提を含む形で論じていることは妥当ではない。
「憲法制定当時には同性婚が想定されなかったことから、」とある。
「想定されなかった」ことには、それが「想定されなかった」なりの事情が存在するはずである。
その理由を遡って検討しなければ、「婚姻」という概念そのものや、憲法24条の「婚姻」の文言や「両性」「夫婦」の文言が、「同性間の人的結合関係」をどのように扱っているのかを理解することはできないし、憲法24条の下で「同性同士の組み合わせ」を「婚姻」とする法律を立法することが可能であるか否かも判断することはできない。
そこで、「想定されなかった」理由を検討する。
「婚姻」は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として、「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で形成された枠組みである。
具体的には、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」を目的として、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす「一人の男性」と「一人の女性」の組み合わせを選び出し、その間に「貞操義務」を設けるなど一定の形式で法的に結び付け、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によって立法目的の達成を目指すものである。
このような経緯から、「婚姻」はこれらの目的を達成するための手段として整合的な下記の要素を満たす人的結合関係を対象とするものとして形成されている。
・子の遺伝的な父親を特定できる組み合わせとすること
・特定された子の父親にも子に対する責任を担わせること
・特定された子の父親を基に遺伝的な近親者を把握すること
・未婚の男女の数の不均衡を防止できる組み合わせに限定すること
しかし、「同性間の人的結合関係」については、その間で「生殖」を観念することができず、「生殖と子の養育」の趣旨や上記の要素を満たすものではないため、「婚姻」として「想定されなかった」と考えられる。
つまり、制度の趣旨に沿わない関係であれば、もともと「婚姻」ではないことから、「婚姻」として「想定されなかった」ということである。
このように、「想定されなかった」ことには、「想定されなかった」だけの理由がある。
そのため、この「想定されなかった」との文言だけを見て、それを単に立法者がうっかり忘れていたかのような安易な発想によるものであると意味を限定して認識し、それを反対解釈すれば「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることができるということにはならないことに注意が必要である。
「本件規定」が「異性間の婚姻を定めたもの」である理由は、下記の通りである。
その社会の中で何らの制度も設けられていない場合には、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合が発生する。
例えば、「父親不明」の子供が増える、父親を特定できない子供が増える、父親が蒸発して行方不明になった子供が増える、それらにより「子の福祉」が減少する、父親を特定できないことにより近親者の範囲を把握できずに「近親交配」に至り潜性遺伝子の発現した個体が高い確率で生じるようになる、一部の強者が多数人との生殖関係を独占することによって社会の中で「子を持ちたいと希望して相手を見つけようとする男女」の数の不均衡が生じて「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」が生まれる、低年齢での妊娠・出産により母体に危険が及ぶ、などの問題が生じることがある。
これらの不都合を解消するために、下記のような立法目的を有する枠組みを設けることが必要となる。
・「子の福祉」が実現される社会基盤を構築すること
・潜性遺伝子の発現した個体が高い確率で生じることを抑制すること
・「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」を減らすこと
・母体を保護すること
そして、これらの目的を達成するためには、下記の要素を満たす枠組みを設けることが必要となる。
・子の遺伝的な父親を特定できる組み合わせとすること
・特定された子の父親にも子に対する責任を担わせること
・特定された子の父親を基に遺伝的な近親者を把握すること
・未婚の男女の数の不均衡を防止できる組み合わせに限定すること
これらの要素を満たすものとして「一人の男性」と「一人の女性」が選び出され、その間に「貞操義務」を設け、その関係を法的に結び付ける形を「婚姻」と呼んでいる。
憲法24条はこの「婚姻」について規定しており、「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めている。
これも、これらの要素を満たす枠組みとして定めているものといえる。
そして、この憲法24条の「婚姻」の枠組みの「要請」に従って法律上の婚姻制度が立法され、そこに法的効果や一定の優遇措置を設けることによって、婚姻制度を利用する者を増やし、これらの目的を達成することを目指すことになる。
この憲法24条の「婚姻」は一夫一婦制(男女二人一組)の枠組みを定めており、この枠組みに従う形で法律を立法することを「要請」するものであることから、この「要請」に従って定められている「本件規定」は、ここでいう「異性間の婚姻を定めたもの」となるというものである。
ここで「異性間の婚姻を定めたものと解されてきた。」と「解されてきた。」と過去形で表現しているところは、あたかも現在や将来は「異性間」ではない「婚姻」というものが成立するかのように論じるものとなっている。
しかし、その社会の中で「生殖」に関わって生じる不都合を解消するという目的が存在する限りは、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす形で何らかの制度を設けることになるのであり、それを「婚姻」という枠組みが担っている以上は、その「婚姻」について定めた法制度はその社会的な不都合を解消するための制度として機能することが求められている。
そのため、そこで必要とされる「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」という目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす一夫一婦制(男女二人一組)の「婚姻」の枠組みは、現在も、将来も変わるということはない。
よって、この点の制度の根幹となる部分を維持する視点を持たないままに、「異性間の婚姻を定めたもの」という「男女二人一組」の枠そのものについて「解されてきた。」のようにあたかも過去の理解であるかのように位置付けて、現在や将来は変わることがあるかのように論じていることは適切ではない。
そこで検討すると、現在では、同性愛は、障害や疾患ではなく、各人の性的指向も、生まれながらに備わり、人の意思によって選択・変更できない事柄であると理解されている。そして、このような性的指向の性質によれば、性的指向は、個人の尊重に係る人格権の一内容を構成し得る重要な法的利益であると解される。
【筆者】
「現在では、同性愛は、障害や疾患ではなく、各人の性的指向も、生まれながらに備わり、人の意思によって選択・変更できない事柄であると理解されている。」との記載がある。
「現在では、同性愛は、障害や疾患ではなく」との部分について検討する。
法制度を立法する際には内心に対して中立的な内容でなければならないのであり、人を内心における心理的・精神的なものである「性愛」の有無や、その「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかという「性的指向」と称するものによって区別して取扱うようなことをしてはならない。
そのため、ここで「同性愛」や「性的指向」のような個人の内心にのみ存在する心理的・精神的なものを持ち出して、それに基づく形で法制度を立法することが可能であることを前提として法制度の存否を検討しようとしていること自体が誤りである。
また、婚姻制度は「性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いを行うものではないし、「性愛」に基づいて制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもない。
婚姻制度が「男女二人一組」の枠組みとして定められているとしても、それは「異性愛」を保護することを目的とするものではないし、「異性愛者」を称する者を対象とするものでもないし、「異性愛」に基づいて制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもない。
もし婚姻制度が「異性愛」という特定の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的としていたり、「異性愛者」を称する者を対象とするものとなっていたり、「異性愛」に基づいて制度を利用することを求めたり勧めたりするものとなっている場合には、それ自体で憲法に違反するものとなる。
そのため、婚姻制度はもともと「異性愛」とは関わらないものであり、それに対する形でここで「同性愛」について説明をしたところで、婚姻制度に影響を及ぼすようなことはないし、もし影響を及ぼすようなことがあれば、その時点でその制度は憲法違反となる。
よって、ここで「同性愛」や「性的指向」について述べること自体が婚姻制度との間で関係性を認めることができるものではないし、そのように個人の内心における心理的・精神的なものと関わる形で法制度を定めることはそれ自体で違憲となるため、これを論じていることそのものが妥当でない。
「障害や疾患ではなく」と述べている部分も、婚姻制度(男女二人一組)は「障害や疾患」を有するとされる者であるとしても利用することができるのであり、何かが「障害や疾患」であるか否かは関係がない。
よって、そもそも「同性愛」が「障害や疾患」であるとしても、それを理由として婚姻制度(男女二人一組)の利用が否定されているわけではないし、「同性愛」が「障害や疾患」でないとしても、婚姻制度(男女二人一組)を利用できることに変わりはない。
そのため、ここで「同性愛」が「障害や疾患」であるか否かを論じていることは、そもそも「障害や疾患」を持つ者に対して婚姻制度(男女二人一組)の利用を否定しているかのような前提を含む形で論じていることになるのであり、その前提となる認識がそもそも不当である。
「各人の性的指向も、生まれながらに備わり、人の意思によって選択・変更できない事柄であると理解されている。」との部分について検討する。
「各人の性的指向も、生まれながらに備わり、」との部分について、研究の中には「性的指向」は後天的に形成され、「生まれながらに備わ」るものではないとするものもある。
この札幌高裁判決の中でも、「2 本件規定が憲法13条に違反する旨の主張について」の項目の「(2)ア」の第二文で「性的指向が決定される原因、又は同性愛となる原因は解明されておらず、遣伝的要因、生育環境等複数の要因が組み合わさって作用している可能性が指摘されている」と自ら述べている通り、「性的指向が決定される原因」は「解明されて」いるわけではなく、「遣伝的要因」や「生育環境」等の「複数の要因が組み合わさって作用している可能性」が「指摘されている」ものである。
そのため、ここで別の研究立場を一方的に排して、「生まれながら」とする特定の立場を支持することを前提として、それに基づいて法規範の意味を論じようとすることは妥当でない。
「人の意思によって選択・変更できない事柄である」との部分についても、研究中には「性的指向」は、「人の意思によって選択・変更」することができる事柄であると考える立場も存在する。
そのため、そのような別の研究の立場を一方的に排して、「人の意思によって選択・変更できない事柄である」とする特定の立場を支持することを前提として、それに基づいて法規範の意味を論じようとすることは妥当でない。
もちろん、他者が本人の意思に反して無理やり変えさせようと強制することは、「思想良心の自由」の精神に反して許されないことは言うまでもない。
そのような本人の意思に反して他者が無理やり変えさせようと強制するような事案があった場合には、そのような行動をとることが適切ではないことを説明するために、「生まれながらに備わり、人の意思によって選択・変更できない事柄である」という見解が必要とされ、そのことを裏付ける研究の結果が強調されることがある。
しかし同時に、本人が自らの意思で変えたいと望んだ場合には、「生まれながらに備わ」るとは限らず、「人の意思によって選択・変更」することも可能であるとする見解が必要とされ、そのことを裏付ける研究の結果が強調されることもあり得るものである。
もし本人が「自らの意思」で変えたいと望むのであれば、その可能性もまた開かれるということである。
そのような中、特定のグループや個人は、自己の置かれている事情の中で生じている課題を解決するために、それらの様々な見解の中から特定の見解を引き出して論じるなどしているに過ぎないのである。
そのため、これら人の内心にのみ存在する心理的・精神的な研究については、本来的に物理的な現象を外部から観測することによって誰もが共通した認識を持つことができるという意味での客観性を保つことができるものではないのであり、もともと様々な見解が存在しており、それを一つの見解に絞ることができるというものではないし、一つの見解に絞ることが適切であるともいえないものである。
そのことから、このような学術的な知見の当否の問題については、裁判所において審判することのできる範囲を超えるものである。
よって、このような事柄に対して裁判所が特定の見解だけを拾い上げて支持・不支持を表明するようなこととなっていることは適切ではない。
また、「性的指向」と称しているものの性質についての見解の当否を前提としなければ法的な判断を行うことができないような場合(『性的指向』と称しているものの性質について特定の立場に基づかなければこの判決を構成する論旨を正当化することができない場合)については、そもそも法令を適用することによって終局的に解決することができる問題とはいえない。
そのため、このような特定の見解を採用すること基づく形で判断を試みていることは、裁判所法3条の「法律上の争訟」の範囲を超えるものであり、裁判所で審査することのできる範囲を逸脱するものである。
よって、この判決が「性的指向」について、「生まれながらに備わり、人の意思によって選択・変更できない事柄である」という特定の見解を採用した上で、その見解に基づく形で判断を行っていることは、裁判所法3条の「法律上の争訟」の解釈を誤ったものであり、「司法権の範囲」を超えた違法なものというべきである。
ここでは「性的指向」と称するものの性質について述べているが、これを根拠とする主張が通用することになれば、「以前は複数人を愛することは病気であったが、現在は病気ではない」などと論じることによって、「複婚」の制度が設けられていないことについても同様に違憲となると考えることになるのであり、妥当なものではない。
婚姻制度の「貞操義務」に反して配偶者以外の者との間で不倫関係に至った者が、損害賠償の請求や離婚の訴えを受けた際に、「自分は同時に複数名に対して『性愛』を抱く者であり、そのような者の抱く自然な心情に沿う複婚型の婚姻制度が存在しないことは違憲である。」と主張する場合も同様に違憲となると考えることになるということである。
そのため、個人の内心における心理的・精神的なことを持ち出して制度の存否を論じることはできないのであり、このような主張によって何らかの結論を導き出そうとする論旨は正当化することができるものではない。
「このような性的指向の性質によれば、性的指向は、個人の尊重に係る人格権の一内容を構成し得る重要な法的利益であると解される。」との記載がある。
「性的指向」とは、個人が「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかに関するものであり、この札幌高裁判決の「2 本件規定が憲法13条に違反する旨の主張について」の項目の「(2)ア」の第一段落第一文でも「性的指向とは、人が情緒的、感情的、性的な意味で、人に対して魅力を感じること」と述べているものである。
これは、この札幌高裁判決でも述べているように「情緒的、感情的」なものであり、「魅力を感じること」というのであるから、個人の内心における精神的なものである。
このような個人の内心を保障するものは、「内心の自由」といわれるものであり、憲法上の具体的な条文においては19条の「思想良心の自由」や20条1項前段の「信教の自由」として保障されるものである。
そのことから、ここで「性的指向」について「個人の尊重」のような憲法13条前段に対応する言葉を用いて、「人格権」として整理される事柄であるかのように述べていることは誤りである。
また、憲法19条の「思想良心の自由」や憲法20条1項前段の「信教の自由」については、「国家からの自由」という「自由権」の性質であり、国家から個人に対する具体的な侵害行為があった場合に、その侵害を排除するという場合に用いることができるというものである。
そのため、これらの「自由権」の性質を基にして特定の制度を形成することを国家に対して求めることができるというものではない。
もう一つ、「性的指向」については「内心の自由」として19条の「思想良心の自由」や20条1項前段の「信教の自由」によって保障されることが前提であるが、それとは別に、ここで登場する「個人の尊重」や「人格権」に関わる憲法13条の性質を検討するとしても、これも「国家からの自由」という「自由権」の性質であることから、国家から個人に対して具体的な侵害行為があった場合に、その侵害を排除するという場合に用いることができるというものである。
そのため、この13条を基にしても特定の制度を国家に対して求めることができるということにはならない。
よって、ここで「個人の尊重」や「人格権」の文言を持ち出したとしても、それによって具体的な制度の創設を国家に対して求めることができるとする根拠にはならないことを押さえる必要がある。
その他、「人格権」を用いることのできる場合とは、下記のような場合である。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【北京共同】人工知能(AI)で生成された自身の声を模した音声が文章読み上げソフトに無断で使用されたとして、中国の女性ナレーターが関連企業5社に損害賠償を求めた訴訟で、北京市の裁判所は4月下旬、人格権の侵害を認め、一部企業に25万元(約540万円)の支払いを命じた。国営中央テレビによると「AI音声」の権利侵害を巡る判決は中国で初めて。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
AI音声の無断使用は違法 中国初、人格権侵害を認定 2024年5月2日 (下線は筆者)
しかし、「性的指向」は個人の内心における心理的・精神的なものであり、上記のような事案ではないことから、「人格権」を用いることのできるものではない。
もっとも、婚姻や家族に関する制度は、多種多様な事情を考慮して国会が定めるべきものであり、このことは憲法24条2項が明らかにしている。性的指向が重要な法的利益であるとしても、その内容は一義的に定めることができるものではないし、同性間の婚姻について、異性間の婚姻やこれによる家族に関する制度と全く同じ制度が定められるべきものであることが当然に導き出されるものでもない。
【筆者】
「もっとも、婚姻や家族に関する制度は、多種多様な事情を考慮して国会が定めるべきものであり、このことは憲法24条2項が明らかにしている。」との記載がある。
まず、ここでいう「婚姻や家族に関する制度」とは、「憲法24条2項」の「婚姻及び家族」の枠組みの「要請」に従って立法されている法律上の具体的な制度を指すものである。
そして、「憲法24条2項」の「婚姻及び家族」とは、「夫婦」と、「親子」による「血縁関係者」の範囲を指す枠組みのことをいう。
そのため、この「夫婦」と「親子」による「血縁関係者」について規定する制度の内容について、「国会」は「多種多様な事情を考慮して」「定める」ことができる。
しかし、この「憲法24条2項」の「婚姻及び家族」の枠組みの「要請」に従って立法されている法律上の「婚姻や家族に関する制度」の中に、「夫婦」と「親子」による「血縁関係者」の範囲に含まれない人的結合関係を含めるという権限を「国会」は有していない。
これは、「憲法24条2項」が「婚姻及び家族」の制度を定めることを「要請」しているにもかかわらず、その「婚姻及び家族」の枠組みが有する「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的の達成に沿わない人的結合関係を含めようとした場合、そもそも「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するための制度として整合的に理解することを不能とし、その結果、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するための機能が損なわれ、それは結局、「憲法24条2項」の「婚姻及び家族」の枠組みが「要請」している内容を満たす制度が法律上において存在しない状態となることを意味し、「憲法24条2項」の「婚姻及び家族」の文言(の『要請』)に違反することになるからである。
「憲法24条2項」が「婚姻及び家族」を定めている以上は、その「婚姻及び家族」の枠組みが「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するための制度として機能することが求められているのであり、その「婚姻及び家族」の枠組みが有する「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」という目的とその目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす人的結合関係のみを制度の対象とし、それ以外の人的結合関係との間で差異を設けることによって、その立法目的の達成することを目指すということはもともと予定されていることである。
この意図によって形成されている枠組みを、その意図が機能しない形に変えてしまう権限は、「国会」であっても有してはいない。
この点に注意する必要がある。
そのため、ここで「婚姻や家族に関する制度は、多種多様な事情を考慮して国会が定めるべきものであり、」と述べていることは、この文そのものの意味としては正しいとしても、この判決が別の個所で述べているように、「憲法24条2項」の「婚姻及び家族」の枠組みが「要請」する法律上の「婚姻や家族に関する制度」の中に、男女間の「夫婦」と、「親子」による「血縁関係者」以外のものを含めることを「国会が定める」ことができるかのように考えることは誤りである。
その他、この文は「憲法24条2項が」「婚姻や家族に関する制度は、多種多様な事情を考慮して国会が定めるべきものであ」ることを「明らかにしている。」と述べるものとなっている。
しかし、「憲法24条2項」は、「……(略)……婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。」としているだけである。
確かに「法律」は「国会」が「定めるべきもの」であるといえるが、ここには「多種多様な事情を考慮して」とまでは書かれていない。
そのため、「憲法24条2項が明らかにしている」とまで言い切るほどの内容ではないように思われる。
どちらかというと、「婚姻や家族に関する制度は、多種多様な事情を考慮して国会が定めるべきものであ」ることを「明らかにしている。」ものとは、「憲法24条2項」そのものではなく、憲法24条について解釈した「再婚禁止期間制度訴訟大法廷判決」や「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」の文面であるように思われる。
よって、「このことは憲法24条2項が明らかにしている。」のように、「憲法24条2項」そのものが「明らかにしている。」と述べることは、「憲法24条2項」の条文そのものを解釈したものとはいえず、妥当な表現ではない。
「性的指向が重要な法的利益であるとしても、その内容は一義的に定めることができるものではないし、同性間の婚姻について、異性間の婚姻やこれによる家族に関する制度と全く同じ制度が定められるべきものであることが当然に導き出されるものでもない。」との記載がある。
━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━
この文が読み取りづらい原因は下記の通りである。
◇ 「その内容」が指し示している対象がはっきりしない。
この文の中で見ると「その内容」が指すものは「性的指向」であるように見える。
しかし、「性的指向」「の内容は一義的に定めることができるものではない」のように、「性的指向」という人の内心における精神的なものについて「内容」と示し、「一義的に定める」のように何らかの規範を「定める」ことと関係する意味で用いられているとは考えづらい。
そのため、一文前に遡って検討すると、「婚姻や家族に関する制度」がある。
これならば、「婚姻や家族に関する制度」「の内容は一義的に定めることができるものではない」のように、文面として意味が通じるものとなる。
しかし、一文前と合わせて、「もっとも、婚姻や家族に関する制度は、~~であり、~~が明らかにしている。~~であるとしても、その内容は一義的に定めることができるものではないし、~~あることが~~でもない。」という文脈の中で、「その内容」が指し示す部分が「婚姻や家族に関する制度」であると自然に読み解くことは困難であり、悪文であるといえる。
━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━
「性的指向が重要な法的利益であるとしても、」との部分について検討する。
まず、「性的指向」とは「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかについて述べるものであり、これは個人の内心における心理的・精神的なものである。
これを「重要な法的利益である」のように、「法的」に考えるとすれば、それは「内心の自由」について定めている憲法19条の「思想良心の自由」として保障されることになる。
そして、この憲法19条の「思想良心の自由」は、「国家からの自由」という「自由権」の性質であるから、国家から個人に対して具体的な侵害行為があった場合に、その侵害を排除する場面で用いることができるが、これを根拠として特定の制度の創設を国家に対して求めることはできない。
そのため、「性的指向」という個人の内心における心理的・精神的なものが、法的に保障されている(憲法19条の「思想良心の自由」によって保障される)ことを根拠として、この部分のすぐ後で「その内容は一義的に定めることができるものではないし、」のように何らかの「内容」を持つ制度を「定める」ことが導かれるかのように述べていることは、「性的指向」という個人の内心における心理的・精神的なものを保障する憲法19条の「思想良心の自由」によって特定の制度の創設を国家に対して求めることはできないという点で誤った論じ方である。
「その内容は一義的に定めることができるものではないし、」との部分について検討する。
ここでいう「その内容」の指すものは、一文前の「婚姻や家族に関する制度」やこの部分の後の部分で登場する「異性間の婚姻やこれによる家族に関する制度」の「内容」を指しているように思われる。
ただ、「婚姻や家族に関する制度」は、「性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いをする制度ではないし、「性愛」に基づいて制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもない。
そのため、この部分の直前で「性的指向が重要な法的利益であるとしても、」のよう述べて、「婚姻や家族に関する制度」が「性的指向」と称する「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかという個人の内心における心理的・精神的なものと結び付いて定められているかのように論じていることは誤りである。
この札幌高裁判決が述べるように、「婚姻や家族に関する制度」における「婚姻」を「性愛」の思想、信条、信仰、感情を保護するための制度であるかのように論じることを許すことになれば、同じく「婚姻や家族に関する制度」における「養子縁組」の制度を「小児性愛者」の思想、信条、信仰、感情を保護するための制度であるとの解釈も当然に為されることになり、問題があることは明らかである。
「性愛」を保護することは「婚姻や家族に関する制度」の立法目的にはないし、条文にも書かれていないし、法制度は内心に対して中立的な内容でなければならないにもかかわらず、「婚姻や家族に関する制度」を特定の思想、信条、信仰、感情を保護するための制度であるかのように論じていることは誤りである。
法制度を個人の内心における心理的・精神的なものと結び付けて論じることはできない。
「同性間の婚姻について、異性間の婚姻やこれによる家族に関する制度と全く同じ制度が定められるべきものであることが当然に導き出されるものでもない。」との部分について検討する。
ここには「同性間の婚姻」と「異性間の婚姻」とあるが、これがそれぞれ「同性間の人的結合関係」と「異性間の人的結合関係」を指すものであれば、それは憲法21条1項の「結社の自由」によって保障されるものである。
この憲法21条1項の「結社の自由」は、「国家からの自由」という「自由権」の性質であり、国家から個人に対して具体的な侵害行為があった場合に、その侵害を排除する場面で用いることができるが、これを根拠として特定の制度の創設を国家に対して求めることができるというものではない。
よって、人的結合関係を形成することについて、憲法21条1項で「結社の自由」が保障されているとしても、それを根拠としてここでいう「制度」を設けなければならないということにはならない。
「同性間の婚姻」と「異性間の婚姻」の意味が、それぞれ「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とするすることや「異性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを指しているのであれば、それは「婚姻」の概念から検討することが必要である。
「婚姻」は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」を目的として、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす「一人の男性」と「一人の女性」の組み合わせを選び出し、その間に「貞操義務」を設けるなど一定の形式で法的に結び付け、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によって立法目的の達成を目指す枠組みである。
憲法24条が「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めていることも、この意味に対応するものとなっている。
「異性間の婚姻」について、「異性間の人的結合関係」は上記の趣旨を満たすものであり、「婚姻」の対象となっている。
ただ、ここで使われている「異性間の婚姻」との言葉は、あたかも「異性間」の「婚姻」と、それ以外の「婚姻」が存在するかのような言葉遣いとなるため、正しい表現であるとはいえない。
「婚姻」であることそれ自体において「男性」と「女性」の組み合わせによるものしか存在しないことから、「婚姻」であればそれはそもそも「異性間」について述べるものである。
そのため、「異性間の婚姻」という言葉は、「異性間」という「男性」と「女性」を指す言葉と、「婚姻」という「男性」と「女性」の組み合わせを指す概念を同時に用いるものとなっており、文法上は「同義反復」(同語反復/トートロジー)となるため誤用となる。
また、「同義反復」となることを無視して、「異性間の婚姻」という言葉を使ったとしても、「婚姻」であることそれ自体で既に「男性」と「女性」の組み合わせによる「異性間」を指す意味しか存在しないのであり、「異性間の婚姻」という言葉に対する形でそれ以外の「婚姻」というものが成立するというものではない。
よって、その「婚姻」という言葉だけを刈り取ってその概念が形成されている目的から切り離して考えて、「婚姻」という空の箱(言葉の意味から切り離された『音の響き』に過ぎないもの)の中に何らかの人的結合関係を詰め込むことができるという性質のものではない。
◇ 本来の意味
「男性」と「女性」の組み合わせ ⇒ 法的に結び付ける形を「婚姻」とする
◇ この判決の言葉の使い方
「婚姻」は空箱 ⇒ どのような人的結合関係でも詰め込むことができる
そのことから、「異性間の婚姻」のように、「婚姻」という概念そのものを、その概念が形成されている目的との間で切り離して、どのような意味としてでも用いることができるような前提を含む形で論じていることは妥当ではない。
「同性間の婚姻」について、「同性間の人的結合関係」については、その間で「生殖」を想定することができず、上記の趣旨を満たすものではないため、「婚姻」の中に含めることはできない。
そのため、「同性間の婚姻」のように、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることができるかのように述べていることは誤りである。
「同性間の人的結合関係」について、「全く同じ制度が定められるべきものであることが当然に導き出されるものでもない。」との部分を検討する。
憲法24条の「婚姻」の文言は「生殖と子の養育」に関わる制度を一元的に集約して規律する趣旨を有しており、この憲法24条の「婚姻」を離れて別の制度として「生殖と子の養育」に関わる制度を定めることはできない。
「同性間の人的結合関係」について「制度」を定めた場合には、「生殖と子の養育」に関わる制度や影響を与える制度となることが考えられるため、憲法24条の「婚姻」の文言に抵触して違憲となる。
よって、そのような内容を持つ「同性間の人的結合関係」についての「制度」を定めることはできない。
また、婚姻制度(男女二人一組)の場合には、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的の実現に資することから、「婚姻している者(既婚者)」に対して法的効果や一定の優遇措置を設けることについて「婚姻していない者(独身者)」との間で生じる差異を正当化することができるが、「同性間の人的結合関係」についての「制度」の場合は、そのような目的により導かれているものではないことからその「制度」を利用していない者との間で生じる差異を正当化することはできず、憲法14条1項の「平等原則」に違反することになる。
そのため、この意味でも「同性間の人的結合関係」を対象とする「制度」を定めることができるということにはならない。
しかし、このような国会による裁量を踏まえたとしても、異性愛者と同性愛者の違いは、人の意思によって選択・変更し得ない性的指向の差異でしかない。そして、自由で平等な婚姻による家族の成立とその制度的な保障によって、個人が尊重され、その尊厳が実現することは、憲法24条が定める目的と理解することができる。そうであれば、性的指向に差異がある者であっても、同じように制度的な保障を享受し得る地位があり、それを区別する合理的な理由はないというべきである。そうであるにもかかわらず、本件規定は、同性婚を許しておらず、同性愛者は、婚姻によって生じる法的効果を享受することができない。そうすると、本件区別取扱いは合理的な根拠がないといえる。
【筆者】
「このような国会による裁量を踏まえたとしても、異性愛者と同性愛者の違いは、人の意思によって選択・変更し得ない性的指向の差異でしかない。」との記載がある。
━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━
この文が読み取りづらい原因は下記の通りである。
◇ この文は「このような国会による裁量を踏まえたとしても、」とあることから、この部分の後には「国会による裁量」を踏まえた形で何らかの「国会」の権限と関わる事柄についての結論が示されることを予感させるものとなっている。
しかし、その後に続く文は、「異性愛者と同性愛者の違いは、人の意思によって選択・変更し得ない性的指向の差異でしかない。」というものであり、そこで文が切れている。
そのため、この文は、「国会による裁量」とは何ら関係のない事柄の性質について述べて文を終わらせており、何を説明したいのか意味を読み取ることができない。
このような論理的な構成を整理しないままに判決を下すべきではない。
━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━
「このような国会による裁量を踏まえたとしても、」との部分について検討する。
この部分の「このような」が指しているものは、一段落前の第一文の「婚姻や家族に関する制度は、多種多様な事情を考慮して国会が定めるべきものであり、」との部分のことと思われる。
ただ、ここでいう「婚姻や家族に関する制度」とは、憲法24条2項の「婚姻及び家族」に基づくものであり、この憲法24条2項の「婚姻及び家族」の枠組みは「夫婦」と「親子」による「血縁関係者」の範囲を指すものであるから、これ以外の人的結合関係を「婚姻及び家族」の中に含めることはできない。
そのため、憲法24条2項の「婚姻及び家族」の枠組みの中に、「夫婦」と「親子」による「血縁関係者」以外の人的結合関係を含める権限は、「国会」であっても有していない。
そのことから、この一段落前の第二文では「同性間の婚姻」との文言があるが、「同性間」の人的結合関係を「婚姻」として扱う権限は「国会」であっても有していないのであり、それについて「このような国会による裁量を踏まえたとしても、」のように、「国会」に「裁量」があるかのように述べているとすれば誤りである。
この一段落前の第二文には「性的指向」との文言があるが、法制度は内心に対して中立的な内容でなければならないのであり、「性愛」という特定の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的とした制度は、憲法20条1項後段・3項、89条の「政教分離原則」に違反するし、「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いをする制度が存在した場合には、憲法14条1項の「平等原則」に違反するし、制度を利用する者の内心に対して干渉するものとなるから、憲法19条の「思想良心の自由」に違反することになる。
そのため、「国会」であっても、「性的指向」と称するものに基づいて制度を立法する権限は有していないのであり、ここで「このような国会による裁量を踏まえたとしても、」のように「国会」に「裁量」があるかのように述べていることは誤りである。
「異性愛者と同性愛者の違いは、人の意思によって選択・変更し得ない性的指向の差異でしかない。」との部分について検討する。
まず、「異性愛者」や「同性愛者」とあるが、法制度は個々人の内心に対して中立的な内容でなければならないのであり、人を内心に基づいて区別して取扱うことが可能であるかのような前提で論じていること自体が誤りである。
次に、 婚姻制度は「性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いを行う制度ではないし、「性愛」に基づいて制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもない。
そのため、「異性愛者」を称する者も「同性愛者」と称する者も、それ以外の「性愛」を有すると称する者も、「性愛」以外の思想、信条、信仰、感情を有すると称する者も、特に何も称しない者も、婚姻制度(男女二人一組)の要件を満たした上で、その制度を利用する意思があるのであれば、適法に婚姻制度を利用することが可能である。
よって、個人の内心における精神的なものである「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかという「性的指向」と称する者によって区別取扱いがなされているという事実はなく、ここで「異性愛者」や「同性愛者」などと人を内心に基づいて分類しようとする者が用いている一つの思想を持ち出して、それによって区別されているかのような前提で論じていることは誤りである。
また、婚姻制度は「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかという「性的指向」と称するものによって人を区別しているという事実が存在しないことから、「性的指向」と称するものが「人の意思によって選択・変更し得ない」ものであるか否かも、一切関係がない。
そのため、区別取扱いをしている事実が存在する上で、それが「人の意思によって選択・変更し得ない」事柄による区別取扱いであるか否かを検討するものとは性質を異にしている。
(他にも、『性的指向』と称するものが『人の意思によって選択・変更し得ない』かどうかにも学術的な議論があり、このような事柄を扱うことは『法律上の争訟』の範囲を超えるものであり、司法権を行使する裁判所の立場で判断することのできないものである。)
むしろ、ここで「異性愛者と同性愛者の違い」などと論じ、婚姻制度が「異性愛者と同性愛者」を区別していることを前提として論じていること自体が、個々人を「性的指向」に基づいて区別することが許されるかのような論じ方をするものとなっているといえる。
このような理解は、特定の「性愛」の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的とした制度が存在することを前提とするものであるから、憲法20条1項後段、3項、89条の「政教分離原則」に違反するものである。
また、「性愛」という思想、信条、信仰、感情を保護し、それ以外の思想、信条、信仰、感情を保護しないということになるから、憲法14条の「平等原則」に違反するものである。
他にも、制度を利用する者の内心に対して国家が干渉することになることから、憲法19条の「思想良心の自由」に違反するものである。
よって、婚姻制度そのものは「性的指向」と称するものによって区別取扱いを行っている事実はないことから違憲とはならないが、むしろ、この判決が婚姻制度が違憲であると論じようとする中において、婚姻制度が「性的指向」と称するものによって区別取扱いをする制度であるかのような認識を持ち、「性的指向」と称するものによって区別取扱いをする法制度が存在するとしても許されるかのように論じていること自体が違憲となるものである。
「自由で平等な婚姻による家族の成立とその制度的な保障によって、個人が尊重され、その尊厳が実現することは、憲法24条が定める目的と理解することができる。」との記載がある。
━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━
この文が読み取りづらい原因は、倒置法を用いているからである。
通常の語順では、下記のように説明することになるものである。
◇ 「憲法24条が定める目的」「は、」「自由で平等な婚姻による家族の成立とその制度的な保障によって、個人が尊重され、その尊厳が実現すること」「と理解することができる。」
これを、語順を変えて表現しているのである。
しかし、倒置法とは、語勢を強める効果や、語調を整える効果のために使われる文法上のテクニックである。
これは、表現者の心意気を伝える際に用いられる場合があるが、裁判所が判決の文面の中で論じることが求められているのは、法規範の意味について公共的な合意とすることを可能とするための客観性が保たれた形での論理的な筋道を示すことであることから、そのような場面で語勢を強めたり、語調を整えたりする効果を用いて裁判官の心意気を表現したとしても、判決文の内容としての論理的な過程を示す基準としては何らの役に立つものではない。
むしろ、判決の文面の中でこのような表現を用いることは、この判決を読み取ろうとする者にとって、不要な文法表現に惑わされることとなり、法的な規範の論理的な筋道を読み取ろうとする営みに混乱を与えることになる。
裁判官は論理的な筋道を示すことによって規範の意味を描き出すことが求められているのであり、裁判官の心意気を示すための文法上のテクニックに頼って結論を正当化しようとするようなことは適切ではない。
また、論理的な過程を示すことができないにもかかわらず、自らの望む特定の結論を導き出そうとするために、中身のないことを語勢を強める効果によって無理やり正当化しようとするような表現に流れるようなこともあってはならない。
━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━
「自由で平等な」とある。
まず、憲法との関係で「自由」という表現が用いられる場合には、「国家からの自由」という「自由権」を指すと考えることが基本となる。
また、憲法との関係で「平等」との表現が用いられる場合には、奴隷制度や階級制度が存在しておらず、すべての国民が「平等」に法的な主体となっていること(権利能力を有すること)を指すと考えることが基本となる。
そのため、憲法との関係で「自由で平等な」という理念にまで遡って考えるとすれば、もともと個々の国民は「国家からの自由」という「自由権」を有しており、奴隷制度や階級制度によって拘束されることもなく「平等」に法的な主体となっていることが前提となることを述べていることになる。
そして、この「自由で平等な」という理念に基づけば、その「平等」な個々人は何らの制度も利用していない状態で既に完全な状態であり、それが基準(スタンダード)であり、他者の「自由」(自由権)を侵害しない限り(『公共の福祉』に反しない限り)は「自由」(自由権)を保障されているといえる。
よって、このような意味の「自由で平等な」という状態については、何らかの具体的な制度が必要となるというものではない。
ただ、ここでは「自由で平等な婚姻」のように、「婚姻」と結び付けて説明され、その後「憲法24条」にも触れていることから、これは「憲法24条」の「婚姻」と関わる意味で用いられているといえる。
「憲法24条」は1項で「婚姻は,両性の合意のみに基いて成立し,夫婦が同等の権利を有することを基本として,相互の協力により,維持されなければならない。」と規定している。
「再婚禁止期間制度訴訟大法廷判決」では、この1項について「婚姻をするかどうか,いつ誰と婚姻をするかについては,当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたもの」と解し、これを「婚姻をするについての自由」と表現している。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
……(略)……また,同条1項は,「婚姻は,両性の合意のみに基いて成立し,夫婦が同等の権利を有することを基本として,相互の協力により,維持されなければならない。」と規定しており,婚姻をするかどうか,いつ誰と婚姻をするかについては,当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたものと解される。婚姻は,これにより,配偶者の相続権(民法890条)や夫婦間の子が嫡出子となること(同法772条1項等)などの重要な法律上の効果が与えられるものとされているほか,近年家族等に関する国民の意識の多様化が指摘されつつも,国民の中にはなお法律婚を尊重する意識が幅広く浸透していると考えられることをも併せ考慮すると,上記のような婚姻をするについての自由は,憲法24条1項の規定の趣旨に照らし,十分尊重に値するものと解することができる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
この意味は、婚姻制度を利用するか否かについての「自由」である。
そのため、ここでいう「自由」な「婚姻」とは、これを指すといえる。
また、「憲法24条」は2項で「婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。」と規定している。
ここには「両性の本質的平等」とあり、「両性」である「男性」と「女性」の間の「本質的な平等」について定めている。
そのため、ここでいう「平等な婚姻」とは、これを指すといえる。
よって、ここでいう「自由で平等な婚姻」とは、婚姻制度を利用するか否かの「自由」と、婚姻制度の内容が「男性」と「女性」の間で「平等」であることについて述べていることになる。
「自由で平等な婚姻による家族の成立」とある。
これは「自由で平等な」の意味を、「婚姻」の「成立」の場面と関係させて述べている。
「婚姻」の「成立」という婚姻制度を利用することについての「自由で平等」をいうのであれば、婚姻制度を利用するか否かの「自由」と、婚姻制度の要件を満たした場合にその制度の適用を受けることができるという意味の「法適用の平等」をいうものということになる。
そのため、ここで「自由で平等な婚姻による家族の成立」のようにこの意味の「自由」や「平等」について述べたとしても、それが「同性間の人的結合関係」を「婚姻」の中に含めることができるとする理由となるものではない。
そのことから、ここで「自由で平等な」などを述べることにより、その後、この札幌高裁判決が「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることができるとする結論を導き出そうとしていることは、前提となっている事柄とその結論との間に整合的な繋がりを見出すことができるものとなっておらず、論理的な過程の客観性が保たれておらず、公共的な合意として共通の理解を得るに至る基準となるものを備えているとはいえないことから、解釈の方法として誤っているといえる。
よって、「自由で平等な」と述べることにより、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることができるとする結論を導き出そうとする論旨は誤りであるといえる。
その他、「婚姻」とは、一定の枠を設けることによって「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成することを目指す制度である。
そのため、もともとどのような人的結合関係でも「婚姻」とすることができるという前提になく、そこに「自由」が存在するということにはならない。
そのため、婚姻制度を利用するか否かについての「自由」について論じられることがあるとしても、「婚姻」の中に含めることができる人的結合関係の範囲までもが「自由」であるということにはならないのであり、「自由」「な婚姻」という部分についても、もともとそのような意味を含ませることはできないものである。
もう一つ、憲法が「個人の尊厳」の原理に基づき、自然人は「個人主義」の下に「自律的な個人」として生存していくことを予定している中で、婚姻制度を設けていることそのものが「自由」や「平等」に反するものとなっていないかを検討する。
まず、婚姻制度は、国家から個人に対する具体的な侵害行為を定めるものではない。
そのため、婚姻制度が存在するとしても、個々人の有する「国家からの自由」という「自由権」が侵害されているとはいえず、「自由」に反するとはいえない。
次に、その社会の中で「生殖と子の養育」に関する制度が何ら設けられていない場合には、「生殖」に関わって不都合が生じることから、これを解消するために「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」を目的として、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす「一人の男性」と「一人の女性」の組み合わせを「貞操義務」など一定の形式で法的に結び付け、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によってこれらの目的の達成を目指すことになる。
この場合、個々人は「平等」である中で、この制度を利用している者に法的効果や一定の優遇措置が与えられることになるが、これは上記の目的を達成するための手段として整合的な範囲でのみ法的効果や優遇措置を与えるというものであることから、その制度を利用しない者との間で生じる差異を正当化することができる。
そのため、合理的な理由のない差異を生じさせるものとはいえないことから、「平等」に反するとはいえない。
よって、 婚姻制度を設けていることそのものが「自由」や「平等」に反するものであるとはいえない。
この判決は「自由で平等な婚姻」と述べているが、「婚姻」が「男女二人一組」の枠組みで定められている場合については、その内容は「自由で平等な」という意味に沿うものということができ、「自由」や「平等」に反するということにはならないものといえる。
これに対して、「同性間の人的結合関係」を対象とした制度を設けた場合には、それは上記のような「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的により導かれているものではないことから、その制度を利用していない者との間で生じる差異を正当化することができず、「平等」に反するものとなる。
次に、「自由で平等な婚姻による家族の成立とその制度的な保障によって、個人が尊重され、その尊厳が実現することは、」との部分について検討する。
憲法は「個人の尊厳」の原理に基づいており、自然人は「個人主義」の基に「自律的な個人」として生存していくことを予定している。
そのため、何らの制度も存在していない状態で既に「個人が尊重され」ているといえるし、「その尊厳が実現」されている状態ということができる。
そのため、ここでいう「制度的な保障」と称するものを受けていないとしても、「個人が尊重され」ていないとか、「その尊厳が実現」されていないだとかいうことはない。
そのことから、ここで「制度的な保障によって、個人が尊重され、その尊厳が実現する」のように、「制度的な保障」と称するものを受けることによって初めて「個人が尊重され、その尊厳が実現する」かのように述べている部分は、そもそもの前提となる認識において誤りである。
日本国内には婚姻制度を利用しないままに生活している者がいるが、その者が「個人」として「尊重」されていないとか、「その尊厳」が「実現」されていないだとかいうことはない。
何らの制度も利用していないとしても、既に「個人」は「尊重」されているし、「その尊厳」も「実現」されているのである。
よって、ここで「自由で平等な婚姻による家族の成立とその制度的な保障」によって「個人が尊重され、その尊厳が実現する」かのように述べている部分は誤りである。
「自由で平等な婚姻による家族の成立とその制度的な保障によって、個人が尊重され、その尊厳が実現することは、憲法24条が定める目的と理解することができる。」との部分について検討する。
ここでは、「憲法24条が定める目的」について「自由で平等な婚姻による家族の成立とその制度的な保障によって、個人が尊重され、その尊厳が実現すること」であると述べるものとなっている。
まず、「憲法24条が定める目的」が「自由で平等な婚姻による家族の成立」と述べている部分を検討する。
ここでいう「自由で平等な婚姻」やその「成立」とは、上記で述べたように、「憲法24条」1項の婚姻制度を利用するか否かについての「自由」(婚姻をするについての自由)の趣旨や、2項が「両性の本質的平等」のように「男性」と「女性」の間の「平等」について定めていることを指すものであるといえる。
これについて、ここでは「憲法24条が定める目的」のように「目的」という言葉を用いているが、これは「憲法24条」の条文が機能することによって生じる結果、あるいは、「憲法24条」の規定が下位の法令に対してどのような効果を与えることが意図されているかという条文の機能を指す意味の「目的」である。
このページの冒頭の「ポイント」のところの〔「目的」の意味の混同〕の項目で解説した「② 制度が機能することによって生じる結果(目的)」に相当するものといえる。
そのため、これは「憲法24条」の規定や、「憲法24条」が定めている「婚姻」という枠組みそのものが形成される原因となっている「① 国の立法目的」を指す意味の「目的」ではない。
このことから、ここで「憲法24条が定める目的」と述べられている部分の「目的」の意味を、「憲法24条」の規定や、「憲法24条」が定める「婚姻」という概念よりも上位にある「① 国の立法目的」を指すものであるかのように考えて、「婚姻」が「男女二人一組」で定められているという枠組みそのものを変更することができるとする理由となるものではないことに注意が必要である。
また、ここでいう「自由で平等な婚姻」についても、「憲法24条」の「婚姻」の枠組みの「要請」に従って立法される法律上の婚姻制度の内容について、その制度を利用するか否かの「自由」(婚姻をするについての自由)と、「男性」と「女性」の間の「平等」に基づくものであることが必要であるという意味のものである。
そのため、この意味を超えて、「婚姻」が「男女二人一組」で定められていることの枠組みそのものを変更することができるとする理由となるものではない。
そのため、「憲法24条が定める目的」について「自由で平等な婚姻による家族の成立」と述べている部分の意味そのものは上記の意味で理解することが可能であるとしても、これを理由として「婚姻」の中に「同性間の人的結合関係」を含めることができるとする理由となるものではないことに注意が必要である。
「憲法24条が定める目的」が「制度的な保障によって、個人が尊重され、その尊厳が実現すること」と述べている部分を検討する。
上記でも述べたように、憲法は「個人の尊厳」の原理に基づいており、自然人は「個人主義」の下に各々「自律的な個人」として生存していくことを予定しており、何らの制度も利用していない者の状態が基準(スタンダード)である。
そのため、何らの制度も利用していない者について、「個人が尊重され」ていないだとか、「その尊厳が実現」されていないだとかいうことはないのであり、ここでいう「制度的な保障」と称するものによって初めて「個人が尊重され、その尊厳が実現する」かのように述べていることは誤りである。
よって、それを「憲法24条が定める目的」のように述べていることについても、前提となる認識に誤りがあり、「憲法24条」の条文が意図するものではないことを述べるものであり誤りである。
その他、ここでは「制度的な保障」という文言が登場している。
しかし、憲法の解釈について問われている中で、「制度的な保障」という言葉を用いることは、憲法上の条文の性質を解釈する場合における「制度的保障論」について述べようとしているのではないかと混乱させる表現であるため、言葉の選択として相応しいとはいえない。
制度的保障 Wikipedia
憲法の教科書を三冊ほど読めば、憲法の解釈について論じる中で「制度的な保障」という言葉を用いることは、憲法学における「制度的保障」の議論と混乱する可能性があることは気が付くと思うのだが、そのような感覚なくこのような言葉を用いていることには疑問を感じるところである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
同様に、法律家のことばの使い方は、当該社会における法律家共同体の共通了解を反映している*19。定式化され、明確化されることの稀なこの共通了解に遡ることではじめて、法律学上の概念の正確な意味、全体の中での位置づけを理解できることが少なくない。
熟練した法学教師であれば、短い問答から導き出される学生の断片的な記憶やいろいろな書物や資料に印刷された言明が、より包括的な法律家共同体の共通了解を前提としていること、全体の文脈に適切に位置づけることではじめて、断片的な記憶や印刷された言明の正確な意義を理解できることを、活きた会話のやりとりの中で、学生に想起させることも可能であろう*20。そういう法学教師には、なかなかなれそうもないが。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
憲法学の散歩道 第38回 ソクラテスの問答法について 2024年4月01日
「そうであれば、性的指向に差異がある者であっても、同じように制度的な保障を享受し得る地位があり、それを区別する合理的な理由はないというべきである。」との記載がある。
この文は、文の意味そのものとしてはその通りである。
法制度は個々人の内心に対して中立的な内容でなければならず、人を内心に基づいて区別して取扱うようなことをしてはならないからである。
そのため、法制度を個人の内心における心理的・精神的なものである「性愛」の有無や、「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかという「性的指向」と称するものによって区別するような形で立法してはならない。
また、法制度を適用する場面でも、「性愛」の有無や、「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかという「性的指向」と称するものによって区別してはならない。
そして、婚姻制度(男女二人一組)についても、これは「性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いをする制度ではないし、「性愛」に基づいて制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもない。
そのため、婚姻制度(男女二人一組)について、「性的指向に差異がある者であっても、同じように制度的な保障を享受し得る地位があり、」、制度を適用する場面においても「それを区別する合理的な理由はないというべきである。」という意味で読み解く限りはその通りであるといえる。
これに対して、この札幌高裁判決は、婚姻制度(男女二人一組)があたかも「異性愛」を保護することを目的とした制度であり、「異性愛者」を称する者を対象とした制度であり、「異性愛」に基づいて制度を利用することを求めたり勧めたりする制度であるとの前提の下に論じていることから、この文の意味は、特定の「性的指向」を保護することを目的とした制度が存在しており、特定の「性的指向」を有する者を対象とした制度が存在しており、特定の「性的指向」に基づいて制度を利用することを求めたり勧めたりする制度が存在するのであれば、別の「性的指向」を有する者に対しても同じように制度を設けるべきであり、区別がないようにするべきであると述べようとするものとなっている。
しかし、そもそも法制度は個人の内心に対して中立的な内容でなければならないのであり、「性愛」を保護することを目的とした制度を立法することはできないし、「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかという「性的指向」と称するものによって区別する制度を立法することもできないし、「性愛」に基づいて制度を利用することを求めたり勧めたりする制度を立法することもできない。
もし「性愛」を保護することを目的として制度を立法した場合には、特定の思想、信条、信仰、感情を保護するための制度となるから、憲法20条1項後段・3項、89条の「政教分離原則」に違反する。
また、「性愛」を有する者を対象とした制度を立法した場合には、「性愛」以外の思想、信条、信仰、感情を有する者との間で内心に基づいて区別取扱いをすることになるから、憲法14条1項の「平等原則」に違反する。
さらに、「性愛」に関わる制度として立法した場合には、国家が個人の内心に対して干渉するものとなることから、憲法19条の「思想良心の自由」に違反する。
そのため、法制度が、「性愛」を保護することを目的としていたり、「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかという「性的指向」と称するものを審査して区別取扱いをしたり、「性愛」に基づいて制度を利用することを求めたり進めたりするものとして存在していても許されるかのような前提の下に、「性的指向に差異がある者であっても、同じように制度的な保障を享受し得る地位があり、それを区別する合理的な理由はないというべきである。」のように論じていることは誤りである。
よって、この文そのものの意味はその通りであるとしても、この札幌高裁判決の前提としている婚姻制度(男女二人一組)に対する認識を出発点としてこの文が述べようとしていることを考えると、その前提となる認識が誤っていることにより、この文の意味も誤っていることになる。
「本件規定は、同性婚を許しておらず、同性愛者は、婚姻によって生じる法的効果を享受することができない。」との記載がある。
「本件規定は、同性婚を許しておらず、」との部分について検討する。
まず、この「同性婚」の意味が「同性間の人的結合関係」を形成することを指している場合について検討する。
「同性間の人的結合関係」を形成することについては、「国家からの自由」という「自由権」の性質として憲法21条1項の「結社の自由」で保障されるものである。
また、その「同性間の人的結合関係」を形成することについて、それが法的な規制の対象となっているという事実はないし、「本件規定」もそれを規制するものではないため、それについて「許しておらず、」と理解しているのであれば誤りである。
次に、この「同性婚」の意味が「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを指している場合について検討する。
「本件規定」は、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを定めていないということができる。
ただ、これは法制度が定められているか否かの問題であることから、むやみに「許す・許さない」という意味での「許しておらず、」という表現を用いることは適切でない。
これは、ある個人が特定の法制度を利用しようと考えた場合に、自己の望む形で法制度が定められていないことを理由として望み通りとならず、利用することを控えるという視点から、その者個人の受け止め方として「許しておらず、」などと表現しているものを述べているものである。
しかし、法制度は政策的なものであり、何らかの立法目的を達成するための手段として定められるものであることから、それが自らの望む形で定められていないという場合は当然にあり得ることである。
そのことを客観的な視点から捉える場合には、「許しておらず、」という表現は必ずしも適切であるとはいえない。
そのため、ある特定の形の法制度が定められていないことについて、敢えて「許しておらず、」という表現を用いることは、法制度の性質について客観的な視点から説明するものとして用いられる言葉遣いではなく、別の個所の「不利益」などの文言と相まって、訴訟の当事者の一方の見方や意見、感じ方に与する形で論じるものとなっていることが考えられる。
裁判所は法制度の性質について客観的な視点から論じることが必要であり、このような訴訟の当事者の一方が現在の法制度をどのように受け止めているかという主観的な立ち位置から見た場合の言葉遣いをそのまま用いるような表現をすることは適切ではない。
「同性愛者は、婚姻によって生じる法的効果を享受することができない。」との部分について検討する。
まず、婚姻制度は「性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いをする制度ではないし、「性愛」に基づいて制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもない。
そのため、婚姻制度は個々人がどのような思想、信条、信仰、感情を有しているとしても、法律上の要件を満たして制度を利用する意思があるのであれば、誰でも分け隔てなく制度を利用することができるのであり、当然、「同性愛者」を称する者も婚姻制度(男女二人一組)の要件を満たして制度を利用する意思があるのであれば、適法に制度を利用することが可能である。
よって、「同性愛者は、婚姻によって生じる法的効果を享受することができない。」との理解は事実を誤認するものであり、誤りである。
その他、この判決が「同性愛者は、婚姻によって生じる法的効果を享受することができない。」と述べていることは、あたかも「同性愛者」を称する者が婚姻制度(男女二人一組)の適用を受けることができない者であるかのように扱うものであり、不当な主張である。
「同性愛者」を称する者であるとしても、他の者と同様に、婚姻制度(男女二人一組)を利用する意思があるのであれば、適法に制度を利用することが可能である。
「本件区別取扱いは合理的な根拠がないといえる。」との記載がある。
まず、ここでは「本件区別取扱い」のように「区別」が存在することを前提とするものとなっている。
しかし、婚姻制度は「性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いをする制度ではないし、「性愛」に基づいて制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもない。
そのため、「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかという「性的指向」と称するものによって「区別取扱い」をしているという事実はない。
よって、「本件区別取扱いは」と述べている部分は誤りである。
また、「区別取扱い」が存在しないことについては、「区別取扱い」の「合理的な根拠」を審査することもできないため、ここで「合理的な根拠がないといえる。」のように「合理的な根拠」の存否を述べている部分も誤りである。
イ 上記のような婚姻における取扱いの区別については、諸外国の状況も参照すべきであるが、性的指向の一つである同性愛者による婚姻の制度は、多くの国で採用されている。
【筆者】
「上記のような婚姻における取扱いの区別については、」との部分について検討する。
まず、婚姻制度は「性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかによって区別取扱いをする制度ではないし、「性愛」に基づいて制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもない。
そのため、ここで「上記のような婚姻における取扱いの区別」と述べているが、婚姻制度は「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかという「性的指向」と称するものによって「取扱いの区別」をしている事実はないため、そのような「取扱いの区別」が存在することを前提として論じていることは誤りである。
また、もし法制度が「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかという「性的指向」と称するものによって「取扱いの区別」をしている場合には、特定の「性愛」の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的とした制度ということになるため、憲法20条1項後段・3項、89条の「政教分離原則」に違反することになる。
他にも、国家が法制度を利用する者の内心に対して干渉するものとなることから憲法19条の「思想良心の自由」や憲法20条1項の「信教の自由」に違反することになる。
さらに、特定の「性愛」の思想、信条、信仰、感情を保護し、その他の「性愛」の思想、信条、信仰、感情や「性愛」以外の思想、信条、信仰、感情(友愛・友情・絆などもそれにあたる)を保護しないということになることから、憲法14条1条の「平等原則」に違反することになる。
よって、「性的指向」と称するものによる「取扱いの区別」をする法制度が存在するとしても許されるかのように述べていること自体が誤りである。
「諸外国の状況も参照すべきであるが、」との部分について検討する。
「諸外国」の法制度は、それぞれの国の社会事情の中で生じる問題を解消することを意図して構築されたものであり、その立法目的や立法目的を達成するための手段・方法には様々な違いがある。
そのため、「諸外国」の法制度と日本国の法制度との間に何らかの類似点を見出すことができる場合があるとしても、それはそれぞれの国の社会事情の中で形成された別個の制度であり、同一の制度を指していることにはならない。
そのことから、外国語を翻訳する際に翻訳者が「諸外国」の法制度との間で何らかの類似性があることを見て「婚姻」と翻訳して説明しているとしても、それぞれの国の法制度を「婚姻」という言葉を用いて統一的に理解することが可能なわけではなく、それは日本国の法制度における「婚姻」と同一の制度を指していることにはならない。
よって、「諸外国」で「同性間の人的結合関係」を対象とした何らかの法制度が存在するとしても、そのことが日本国の法制度に直接的な影響を与えることはないし、日本国の法制度における「婚姻」の中に「同性間の人的結合関係」を含めることができるとする理由になるものでもない。
「諸外国」の法制度を「参照」して比較する際には、この点を押さえる必要がある。
その他、この判決では「同性間の人的結合関係」について法制度を定めている国のみを取り上げて日本国の法制度との間で比較しようとするものとなっているが、古くから「一夫多妻制」を採用している国々も存在しているのであり、それらの事例を一切取り上げることなく結論を導き出そうとしていることは、裁判官が特定の結論を導き出すために恣意的に視野を狭めようとするものとなっており、妥当でない。
【参考】一夫多妻制 Wikipedia
また、「二人一組」の人的結合関係についての法制度のみを取り上げていることについても、人的結合関係には「三人以上の組み合わせ」も存在するのであり、それを「二人一組」のみを検討すればそれで足りるかのような前提で論じている部分も妥当でない。
このような論じ方は、なぜ「二人一組」であるのかその根拠を説明しないままに論じる「カップル信仰論」に陥っているといえる。
「性的指向の一つである同性愛者による婚姻の制度は、多くの国で採用されている。」との部分について検討する。
「同性愛者による婚姻の制度」とあるが、外国では「性愛」という特定の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的とした法制度を定めている場合が考えられる。
しかし、日本国の法制度においては特定の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的とした法制度を立法した場合には、憲法20条1項後段・3項、89条の「政教分離原則」に違反することになる。
また、国家が個人の内心に対して干渉するものとなることから、憲法19条の「思想良心の自由」に違反することになる。
他にも、特定の思想、信条、信仰、感情を有する者とそれ以外の思想、信条、信仰、感情を有する者との間で差異を設けることになるから、憲法14条1項の「平等原則」に違反することになる。
そのため、日本法の下では、「同性愛」という特定の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的として制度を立法することはできない。
そのことから、外国の法制度において「同性愛者による婚姻の制度」と称するものが存在するとしても、日本法においてそのような制度を立法することはできない。
よって、このような日本法とはもともと性質の異なる外国の法制度を「参照」して検討しようとしていることは妥当でない。
また、このような状況の下で、国連自由権規約人権委員会は、日本政府報告書において、同性愛者等が法律的な婚姻等へのアクセス等において差別的な扱いに直面しており、同性婚を含め、市民的及び政治的権利に関する国際規約に規定された全ての権利を締結国の領域の全てで享受できるようにすることを指摘した。
【筆者】
━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━
この文は文章として構造上の問題を抱えており、その結果、意味を明確に掴むことができず、読み取りづらいものとなっている。
そこで、①この文の全体について主語・述語の構造を確認し、②意味の範囲を限定している部分を確認し、③読み取りづらい原因となっている部分を検討する。
➀ 主語・述語
「国連自由権規約人権委員会は、」→「指摘した。」
② 意味の範囲を限定している部分
「日本政府報告書において、」→「指摘した。」
③ 読み取りづらい原因となっている部分
「同性愛者等が法律的な婚姻等へのアクセス等において差別的な扱いに直面しており、同性婚を含め、市民的及び政治的権利に関する国際規約に規定された全ての権利を締結国の領域の全てで享受できるようにすること」
この③の部分について、主語・述語の関係などを詳しく検討する。
・ 主語・述語
「同性愛者等が」→「直面して」(いる)
・ 名詞形
「同性婚を含め、市民的及び政治的権利に関する国際規約に規定された全ての権利を締結国の領域の全てで享受できるようにすること」
この部分では、「~~こと」と書かれている。
この「こと」の意味は、他の語句を受けてその語句の表す行為や事態を体言化するものである。(『体言』とは名詞や代名詞のこと)
そのため、その体言化されている内容について主語・述語の関係を検討する。
すると、述語については「享受できるようにする」の部分であることは分かりやすい。
しかし、この直前の部分を確認しても、主語になるような言葉は書かれていない。
・ 主語・述語
「?」→「享受できるようにする」
そのため、更に遡って検討すると、別のまとまりの中で「同性愛者等が」と書かれているため、これを前提としているように思われる。
こうなると、ここでは文の中の二つのまとまりについて、一つの主語を共有する形で書かれていることになる。
「同性愛者等が」
→ 「法律的な婚姻等へのアクセス等において差別的な扱いに直面して」(いる)
→ 「同性婚を含め、市民的及び政治的権利に関する国際規約に規定された全ての権利を締結国の領域の全てで享受できるようにすること」
しかし、これらの二つのまとまりについては、一方は「直面して(いる)」のように動詞で書かれているにもかかわらず、もう一方は「~~こと」のように名詞形で書かれている。
これは、文法上の規則性として一貫性のあるものになっていない。
つまり、一つの主語を共有する形となっているにもかかわらず、その二つのまとまりの中で文法上の規則性が統一されていないのである。
これにより、読者はこの文の構造を明確に捉えることができず、読み取りづらく感じるのである。
━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━
「国連自由権規約人権委員会は、日本政府報告書において、同性愛者等が法律的な婚姻等へのアクセス等において差別的な扱いに直面しており、」との部分について検討する。
「法律的な婚姻等へのアクセス等」とあるが、婚姻制度は「男女二人一組」などの要件を満たして制度を利用する意思があるのであれば、誰にでも制度の利用を認めている。
そのため、「同性愛者」を称する者であるとしても、その要件に従って制度を利用する意思を有するのであれば、適法に制度を利用することが可能である。
これについては、「同性愛者」を称する者だけでなく、他の「性愛」を有すると称する者であっても、「キリスト教徒」、「イスラム教徒」、「ユダヤ教徒」、「ゾロアスター教徒」、「仏教徒」、「神道を信じる者」、「武士道を重んじる者」、「軍事オタク」、「鉄道オタク」、「アニメオタク」、「アイドルオタク」であっても、「ADHD」、「アスペルガー」、「自閉症」、「強迫神経症」、「妄想症」、「境界性パーソナリティー障害」、「解離性同一性障害」、「統合失調症」を有すると称する者であっても同じである。
婚姻制度は、個々人の内心を審査して区別取扱いをするような制度ではないからである。
よって、「同性愛者等が法律的な婚姻等へのアクセス等において差別的な扱いに直面しており、」との部分は、そのような事実はないことから、誤りとなる。
ここで「同性愛者」を取り上げている部分は、婚姻制度があたかも「異性愛」を保護することを目的とするものであり、「異性愛者」を称する者を対象とした制度として定められているかのような誤った前提の下に、それに対して「同性愛者」を持ち出しているものと考えられる。
しかし、日本法における婚姻制度は「性愛」を保護することを目的とした制度ではないため、当然、「異性愛」を保護することを目的とする制度ではないし、「異性愛者」を称する者を対象として定められている制度というわけでもないし、「異性愛」に基づいて制度を利用することを求めるものでも勧めるものではない。
そのため、このような前提の下に論じることは、そもそも婚姻制度そのものと「性愛」は関係がないという点によって、誤った前提から出発したものということができる。
「同性婚を含め、市民的及び政治的権利に関する国際規約に規定された全ての権利を締結国の領域の全てで享受できるようにすることを指摘した。」との部分について検討する。
「同性婚」との部分について検討する。
憲法24条に定められている「婚姻」は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた枠組みである。
具体的には、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」を目的として、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす「一人の男性」と「一人の女性」の組み合わせに対して「貞操義務」など一定の形式で法的に結び付け、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によってそれらの目的の達成を目指すものである。
「同性間の人的結合関係」については、その間で「生殖」を想定することができず、この「生殖と子の養育」の趣旨を満たすものではないことから、「婚姻」の中に含めることはできない。
よって、ここで「同性婚」とあるが、日本法の下では「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることはできないことになる。
その他、ここでいう「同性婚」の意味が「同性間の人的結合関係」を対象とした何らかの制度を指しているとしても、日本国の場合は、憲法24条の「婚姻」の文言が「生殖と子の養育」に関わる制度を一元的に集約して規律していることから、それが「生殖と子の養育」に関わる制度や影響を与える制度となっている場合には、憲法24条の「婚姻」に抵触して違憲となる。
また、婚姻制度が「男女二人一組」に対して法的効果や一定の優遇措置を設けていることについては、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成するための手段として整合的な要素を満たすものであることから、「婚姻制度を利用している者(既婚者)」と「婚姻制度を利用していない者(独身者)」との間で生じる差異を正当化することができるが、「同性間の人的結合関係」を対象とする制度については、そのような目的を有していないことから、何らの制度も利用していない者との間で生じる差異を正当化することはできず、憲法14条1項の「平等原則」に違反することになる。
よって、ここで何らかの「指摘」を受けたとしても、それが日本国で「同性間の人的結合関係」を対象とした制度を設けることができるとする根拠となることはない。
ウ 我が国においても、地方公共団体の多くで、同性愛者が婚姻することができないことによる不利益を緩和するため、パートナーシップ認定制度を導入している。
【筆者】
「同性愛者が婚姻することができないことによる不利益を緩和するため、」との部分について検討する。
婚姻制度は「男女二人一組」の要件などを満たして制度を利用する意思があれば、誰でも制度を利用することが可能である。
そのため、「同性愛者」を称する者であるとしても、要件を満たして制度を利用する意思を有するのであれば、適法に「婚姻」することが可能である。
よって、「同性愛者が婚姻することができない」との説明は誤りである。
ここで「同性愛者が婚姻することができない」と述べていることは、この判決はあたかも「同性愛者」を称する者は、「同性愛者」を称する者であることを理由として婚姻制度(男女二人一組)を利用することが否定されているかのように論じるものとなっている。
これは、法律上で定められていない事柄を理由として「同性愛者」を称する者に対して婚姻制度の適用を否定するものであるといえることから、憲法14条1項の「平等原則」における「法適用の平等」に違反するものである。
また、婚姻制度は「性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査するものではないし、「性愛」に基づいて制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもない。
それにもかかわらず、ここで「同性愛者」を称する者を取り上げて「婚姻することができない」と述べていることは、婚姻制度を利用する場合には「性愛」を抱いて利用しなければならないだとか、「性愛」に基づく形で利用するべきであるとか、「性愛」に基づく形で制度を利用することこそが正当であるという特定の価値観に基づいて、「同性愛者」を称する者が婚姻制度(男女二人一組)を利用しているはずがないとか、利用してはならないとか、利用することは正当ではないなどという認識を前提として論じていることを意味する。
これは、「同性愛者」を称する者が婚姻制度(男女二人一組)を利用することに対して否定的な意味合いを含むものとなっており、不当な主張である。
これは、「同性愛者」を称する者に対して特定の価値観を押し付けるものということができ、憲法19条の「思想良心の自由」、憲法20条1項の「信教の自由」に違反するものである。
法制度は個々人の思想、信条、信仰、感情に対して中立的でなければならないのであり、特定の価値観に基づいて制度を利用することを求めるようなことがあってはならないし、勧めるようなこともしてはならない。
よって、この判決が「同性愛者が婚姻することができない」と説明していることそのものが誤りである。
「同性愛者が婚姻することができないことによる不利益を緩和するため、」とあるが、先ほども述べたように、「同性愛者」を称する者も適法に婚姻制度(男女二人一組)を利用することができることから、「婚姻することができない」ことを前提として論じていることは誤りである。
そのため、ここでいう「婚姻することができない」ことを理由として「不利益」について述べようとしていることは、その前提を欠くものであり誤りである。
また、「不利益」について論じる前提にないことから、その「不利益」を「緩和」するか否かについても、当然論じる余地はない。
その他、憲法は「個人の尊厳」の原理に基づいており、自然人は「個人主義」の下に、各々「自律的な個人」として生存していくことを予定している。
そのため、何らの制度も利用していない者の状態で既に完全な状態ということができ、「婚姻していない者(独身者)」の状態が基準(スタンダード)となるべきものである。
そのことから、「婚姻していない者(独身者)」の状態について、そこに「不利益」といわれるものは存在しない。
このため、「婚姻していない者(独身者)」の状態について「不利益」があることを前提として論じていることは誤りである。
また、「不利益」は存在しないことから、それを「緩和」しなければならないとする前提で論じている部分も誤りである。
よって、「不利益を緩和するため、」と述べている部分は誤りとなる。
ここで、「不利益」という言葉が用いられている背景について検討する。
上記で述べたように、「婚姻していない者(独身者)」の状態について「不利益」と称されるものは存在しないことから、ここである特定の形の法制度が定められていないという状態について「不利益」という言葉で表現していることは、法律論として客観的な視点から論じているものとはいえない。
そのため、ここで「不利益」という表現が使われている背景には、ある者にとって法制度が自らの望む形で定められている状態を完全な状態と設定した上で、現在の法制度がその状態に至っていないという認識の下に、その完全な状態と設定したゴールまでの距離(その間の差の部分)を「不利益」と呼ぼうとする動機が含まれた言葉を用いていることになる。
◇ この判決の認識
自らの望む法制度(ゴール)
↑
↑ (この差異を『不利益』と表現している。)
↑
現在地点
しかし、法的な視点から見れば、憲法は「個人の尊厳」の原理に基づいており、自然人は「個人主義」の下に各々「自律的な個人」として生存していくことを予定していることから、法制度を利用していない状態で既に完全な状態ということができ、「不利益」と称されるものは存在してない。
◇ 法律論として客観的な視点
現在地点 ← (法制度がない状態で既に完全であり、『不利益』は存在しない)
そのため、ある者が「不利益」と表現している場合があるとしても、それは自らの望む形で法制度が定められている状態をゴールと考えることを前提とした上での、そのゴールと現在地点との間の距離について述べているものであり、その者個人が抱いている理想の法制度を前提とする主観的な思いを表現しているに過ぎないものである。
しかし、そのことを法的な視点から客観的に考えると、そこに「不利益」と称されるものを認めることはできないのである。
よって、裁判所の立場では法制度の性質について客観的な視点から論じることが必要とされており、このような訴訟の当事者の一方が現在の法制度をどのように受け止めているかという主観的な立ち位置から見た場合の言葉遣いをそのまま受け入れて表現していることは適切ではない。
このような前提となる認識についての法的な整理を誤ると、その影響で誤った結論を導き出すことに繋がることとなってしまう。
そのため、法的な議論において客観性を保つことのできていないこのような色の付いた言葉をそのまま用いるようなことをするべきではない。
「同性愛者が婚姻することができないことによる不利益を緩和するため、パートナーシップ認定制度を導入している。」との文について検討する。
これは、「同性愛者」に対して「パートナーシップ認定制度」を設けていることを説明するものとなっている。
しかし、法制度は内心に対して中立的な内容でなければならないのであり、「同性愛」という特定の思想、信条、信仰、感情を保護するために制度を設けていることは、憲法20条1項・3項、89条の「政教分離原則」に違反することになる。
また、「同性愛」の思想、信条、信仰、感情を抱く者を対象として制度を設け、それ以外の「性愛」や、「性愛」以外の思想、信条、信仰、感情を抱く者を対象としないというものであるから、個々人の内心における精神的なものに基づいて区別取扱いをする制度ということができ、憲法14条1項の「平等原則」に違反することになる。
さらに、制度を利用する者の内心に対して国家が干渉するものとなるから、憲法19条の「思想良心の自由」に違反することになる。
よって、「同性愛者」称する者を対象として「パートナーシップ認定制度」を設けていることは、そのこと自体が違憲となるのであり、そのような制度が存在していても許されるかのように述べていることは誤りである。
「地方公共団体の多くで、」「パートナーシップ認定制度を導入している。」との部分について検討する。
まず、地方公共団体は、憲法や法律の範囲内でしか活動することはできない。
そのため、憲法や法律の解釈を行う際には、地方自治体の「パートナーシップ認定制度」のような憲法や法律の範囲内でしか運用することのできない事柄を持ち出して論拠を固めることはできない。
また、地方自治体の「パートナーシップ認定制度」は、憲法に定められた「婚姻」や法律上の婚姻制度に抵触している場合には、違法となる。
そのため、そもそも地方自治体の「パートナーシップ認定制度」が上位法である憲法や民法に抵触して違法となっている可能性があるにもかかわらず、このような制度が適法に成立することができることを前提として取り上げ、憲法上の規定の解釈を行うための参考となるかのような前提で論じていることは妥当でない。
この点について、詳しくは当サイト「パートナーシップ制度」で解説している。
エ 国民に対する調査においても、同性婚を容認する割合はほぼ半数を超えるに至っている。
【筆者】
この訴訟で問われているのは、憲法の解釈である。
その解釈の過程の中で、「国民に対する調査」を取り上げ、「容認する割合」を示すということは、あたかも憲法上の規範の意味がその時々の「国民に対する調査」における「賛成派」と「反対派」の数によって揺らぐものであることを前提とするものとなっている。
しかし、このような「国民に対する調査」における「賛成派」や「反対派」の数によって憲法上の規範の意味が変わることになれば、「法の支配」、「法治主義」を損なわせることになるため妥当でない。
また、その時々の国民意識によって条文に記された規範の意味が変わってしまうことになれば、そこにはそもそも「法」は存在しないも同然である。
よって、ここで「国民に対する調査」を持ち出していることそのものが、憲法を解釈する方法として正当化することのできるものではなく、誤りである。
「国民に対する調査」の問題点について検討する。
国民の多くは、「同性間の人的結合関係」を形成することや、「同性間」で共同生活をすることについては否定していないと考えられる。
そこで、国民が「同性婚」という言葉の響きを聞いた時に、多くの国民はそれをイメージして賛否を表明していることが考えられる。
しかし、「同性間の人的結合関係」を法的な意味で「婚姻」として扱おうとした場合に、婚姻制度が「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」という目的の実現を目指す仕組みとなっているにもかかわらず、その制度の内容が根本的に変容し、その目的の実現をすることができず、「生殖」に関わって社会的な不都合が生じるようになったり、制度全体を整合的に理解することが不能となって制度そのもののが成り立たなくなったり、「婚姻制度を利用しない者(独身者)」との間で不平等が生じたりすることまでは理解していないことも多いと考えられる。
そのため、このような言葉の持つイメージについて明確な認識の一致が見られないままに賛否を集計したものは、法的な議論の場で扱うことのできるとする前提を欠くものである。
このような言葉に対するイメージに齟齬が生じることによって起きる問題について、下記の記述が参考になる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
同様に、法律家のことばの使い方は、当該社会における法律家共同体の共通了解を反映している*19。定式化され、明確化されることの稀なこの共通了解に遡ることではじめて、法律学上の概念の正確な意味、全体の中での位置づけを理解できることが少なくない。
熟練した法学教師であれば、短い問答から導き出される学生の断片的な記憶やいろいろな書物や資料に印刷された言明が、より包括的な法律家共同体の共通了解を前提としていること、全体の文脈に適切に位置づけることではじめて、断片的な記憶や印刷された言明の正確な意義を理解できることを、活きた会話のやりとりの中で、学生に想起させることも可能であろう*20。そういう法学教師には、なかなかなれそうもないが。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
憲法学の散歩道 第38回 ソクラテスの問答法について 2024年4月01日
よって、法令を解釈する場面において、上記のような深い考えを持たないままに表明された国民の賛否の数を根拠として論じようとしていることは、このような観点から見ても不適切である。
これに対し、同性婚に対する否定的な意見や価値観を有する国民も少なからずいる。もっとも、これらは、感情的な理由にとどまるものであったり、異性婚との区別について合理的な説明がされていなかったりするものである。
【筆者】
「同性婚に対する否定的な意見や価値観を有する国民も少なからずいる。」との記載がある。
国民の賛成意見や反対意見を集約するのは国会の役割である。
そのため、司法権を行使する裁判所の立場で、その賛成意見や反対意見の一部を取り上げて、その意見が「感情的な理由にとどまるものであ」るかや「合理的な説明がされていなかったりするものである」かを評価しようとすることは適切ではない。
法規範の意味を明らかにする解釈において、複数の考え方がある場合に、その当否を論じることは可能であるか、特定の政策に対して国民が賛否を述べていることについて、その意見の一部を取り上げて評価を行い、特定の政策が妥当であるとか、妥当でないとかいう形で裁判所の立場で方向性を示そうとすることは、司法権の範囲を超えるものであり、越権行為である。
また、このような国民の賛否を取り上げ、その中の一部の意見を取り上げて、その一部の意見に反論するということによって、憲法上の規範の意味が左右されるということはない。
そのため、これによって憲法解釈における合憲・違憲の判断を導くための根拠とすることもできない。
よって、憲法上の規定に違反するか否かという合憲・違憲の判断が求められている中において、このような事柄を論じていること自体が誤りである。
その他、「同性婚に対する否定的な意見や価値観を有する国民」の中には、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることは法的にはできないと考えている者もいる。
これは「賛成」と「反対」の中の「反対」を意味する「否定的な意見や価値観」ではなく、それ以前の「可能」と「不可能」の次元の中の「不可能」を意味する「否定的な意見や価値観」である。
◇ 可能 (⇒ 賛成 or 反対 へ)
◇ 不可能 (⇒ 賛否を問う前提にない。)
そのため、この法的に「不可能」と考える者の「否定的な意見や価値観」について、「賛成」と「反対」の中の「反対」であると考えることは誤りであることに注意が必要である。
これは、2014年から15年にかけて「集団的自衛権の行使」としての「武力の行使」について国民の「賛成・反対」の数の割合を示すアンケート調査に問題があったことと同じ論点である。
そもそも憲法9条によって「集団的自衛権の行使」としての「武力の行使」について「可能・不可能」の次元における「不可能」と考える者について、あたかも「賛成・反対」における「反対派」であるかのように扱うことは、その取り上げ方そのものが誤っているといえる。
これについては、当サイト「存立危機事態の違憲審査」のページの「法律論と政策論」の項目や、「安保法制懇の間違い」のページで取り上げている。
「これらは、感情的な理由にとどまるものであったり、異性婚との区別について合理的な説明がされていなかったりするものである。」との記載がある。
「同性婚に対する否定的な意見や価値観を有する国民」を、ここでは「感情的な理由にとどまるもの」としている。
しかし、これは「同性婚に対する否定的な意見や価値観を有する国民」をないがしろにするものである。
【参考】「同性愛者当事者ですが、同性婚には反対です。そういう人たちの声もよく聞いてくださいよね。」 Twitter
【参考】「俺は、ホモ当事者として、ゲイ当事者として、現行憲法下で法律制定又は法律改正だけで、同性婚を認めることこそ日本国憲法に憲法違反だと考えています。」 Twitter
裁判所は司法権の行使として、憲法に違反するか否かという合憲・違憲、法令に違反するか否かの合法・違法の判断しか行うことはできないのであり、特定の政策に対する国民の意見に対して評価を行うようなことをするべきではない。
このような賛成意見と反対意見の評価を行うことになれば、この札幌高裁判決とは逆の立場から「同性婚に対する『肯定的』な意見や価値観を有する国民」についても、「感情的な理由にとどまるものであったり、」、「合理的な説明がされていなかったりするものである。」と述べることによって、逆の結論が導き出されるということになってしまうものである。
そのため、裁判所では、法の規範のみを論じることが求められているのであって、「国民」の政治的な意見における賛成意見と反対意見に対して評価を行うようなことはするべきではないし、その評価を基にして法規範を導き出すことができるかのように論じていることそのものが誤りである。
「異性婚」とあるが、「婚姻」であれば、それは「異性」間のものしか存在しないため、「異性」の言葉と、「婚」の意味である「婚姻」という「異性」間の組み合わせを指す言葉を同時に用いることは、同義反復となるため文法上は誤用となる。
また、同義反復となることを無視して「異性婚」という言葉を用いたとしても、「~~婚」という言葉は、「~~」の部分を法的な意味で「婚姻」として扱うことを可能とすることができるとする理由となるものではない。
そのため、「異性婚」という言葉に対する形で、「異性」が揃うことを満たさないそれ以外の「婚姻」というものが成立するという性質のものではない。
よって、「異性」があれば「同性」もあるだろうなどという安易な発想を基にして、「異性婚」という言葉に対する形で「同性婚」という言葉を使ったとしても、それは法的に「同性」間の人的結合関係を「婚姻」とすることができるということにはならないものである。
この点に注意が必要である。
「異性婚との区別について合理的な説明がされていなかったりするものである。」とある。
司法権を行使する中において、国民が自由に表明している政治的な意見について「合理的な説明がされて」いるか否かという評価を行うことは不適切である。
また、そのような評価を行ったとしても、それが憲法を解釈する際の根拠となるようなものではないし、法解釈は国民の意見の賛否に左右されるものではないし、左右されるようなことがあってもならないものである。
そのため、憲法の条文を解釈する中において、これを論じることによって結論を導き出そうとしていること自体が誤りである。
それとは別に、国民が自由に表明している数多の政治的な意見の中には、当然、「合理的な説明がされていなかったりするもの」も存在することは考えられるが、その一部の意見について反論したり評価を行ったりしたところで、法解釈の結論が左右されるということもない。
そのため、国民の一部の意見を取り上げて、それに対して反論や評価を行ったからといって、この判決が行っている法解釈と称している活動の結論を正当化することができることに繋がるわけではない。
よって、ここで「同性婚に対する否定的な意見や価値観を有する国民」の一部の意見について、「合理的な説明がされていなかったりするもの」と述べたところで、それはこの判決の結論の妥当性を支える理由とはならないのであり、法解釈の過程でこのようなことを述べていること自体が誤っている。
「異性婚との区別」とあるが、そもそも「婚姻」とは、「婚姻」と「それ以外の人的結合関係」や「人的結合関係以外の概念」との間で「区別」するものとして意味を形成している概念である。
これは、特定の事柄について、「婚姻」という名前を付けることによって他の事柄との間で区別し、それを識別することを可能としているものだからである。
そのため、「婚姻」という言葉を用いてそれ以外の概念と「区別」しているという時点で、「婚姻」の中に含まれる人的結合関係と含まれない人的結合関係とが存在することはもともと予定されているといえるものである。
そのことから、「婚姻」という言葉を用いて何らかの対象を指し示そうとしているにもかかわらず、「区別」をするべきではないとか、「区別」してはならないだとか、「区別」はなされるべきではないなどという前提はそもそも成り立たないものである。
そして、そこでいう「婚姻」は、人間が有性生殖を行うことによって子を産むという身体機能を有していることに着目し、その「生殖」によって生じる社会的な不都合を解消するために、その「生殖」との関係において整合的な形で「男性」と「女性」を選び出し、その間に「貞操義務」を設けるなど一定の形式で法的に結び付けるものとして不都合の解消を目指すものである。
この機能を有する概念は「婚姻」以外に存在しておらず、その社会の中で「婚姻」という概念がこの目的を達成するための手段として機能することが求められている以上は、この「婚姻」という言葉を別の意味として用いることができることにはならない。
そのため、人間が有性生殖という2つの異なる生殖細胞を有する個体が互いの生殖細胞を交配させることによって子孫を産むという身体機能を有しており、その「生殖」という営みに関わって社会的な不都合が生じる限りは、それを解消するという目的を達成するための手段として、その「生殖」との関係において異なる身体的な特徴を有する者として定義される「男性」と「女性」を区別し、その区別に従って生殖関係を整理し、社会的な不都合を解消する仕組みを持つ制度を設けるという方法は、その目的を達成するための手段として最低限必要となる要素に着目して枠組みを設けているという意味で合理的なものであるということができる。
そのことから、「生殖」との関係において定義される「異性」間の人的結合関係と、「生殖」を想定することができない「同性」間の人的結合関係とを区別することは、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成するための手段として合理的に区別されているものということができる。
そのため、「同性婚に対する否定的な意見や価値観を有する国民」の一部の意見について、「異性婚との区別について合理的な説明がされていなかったりするもの」があるかどうかは別として、法的な視点において、「婚姻」が「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するための枠組みとして「異性」間の人的結合関係と「同性」間の人的結合関係を「区別」していることは、「合理的な説明がされていなかったりするもの」というものではない。
その他、安易に合理性がないと断じてしまうことの危険性について下記の動画は参考になる。
【動画】天皇と合理性。伝統は伝統であるが故に尊い!合理性という浅知恵と何世代も培った伝統という叡智|竹田恒泰チャンネル2 2024/04/04
司法権を行使する裁判所は人権を保障することが期待されているといわれることがあるが、法制度の目的を見誤った場合には、一瞬でその制度を破壊することに繋がり、その制度によってそれまで機能していた秩序ある社会を損なわせ、人々に多くの不都合をもたらすことにもなることを心得る必要がある。
また、司法権の行使は合憲・違憲、合法・違法の判断しかできないのであり、政策的な問題は国会と内閣以下の行政機関である政治部門の役割であり、ここに踏み込むことはできないし、ここに踏み込むことは憲法そのものを構成する民意に背くものであるし、また、憲法の枠内でもともと政治部門に委ねられている立法裁量の中におけるその時々の一時期の民意における政策的な選択にも反するものとなる。
よって、裁判所が国民の賛成意見や反対意見の当否について論じるようなことはしてはならない。
これとは別に、憲法24条は「婚姻」について「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めており、これが憲法上の他の条文との間で矛盾するということはないことから、この「男女二人一組」の枠組みが憲法14条1項に違反するということにはならない。
そのため、この点は、憲法14条1項の「平等原則」の審査における「区別」が存在した場合における「合理的な理由」の存否について論じる前提にないものである。
よって、「同性婚に対する否定的な意見や価値観を有する国民」の一部の意見について、「異性婚との区別について合理的な説明がされていなかったりするもの」があるかどうかは別として、そもそも婚姻制度が「男女二人一組」の枠組みとなっていることについては、憲法24条に基づくものであることから、同一の憲法上の条文である14条1項の「平等原則」の審査における「区別」が存在した場合における「合理的な理由」の存否を論じるという前提になく、ここで「合理的な説明がされて」いるか否かを論じていること自体が妥当でないものである。
オ 上記のとおり、国民の間では様々な意見があるが、その動向も時代とともに変わってきており、これまでも、同性婚を許していないことについては、国会や司法の場において、差別であるとの指摘がされてきた。
【筆者】
━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━
この文が読み取りづらい原因は下記の通りである。
◇ 「上記のとおり、」と書かれていることから、通常は、「イ」で「諸外国」と「国連自由権規約人権委員会」、「ウ」で「地方自治体」、「エ」で「国民に対する調査」を取り上げた流れを受けて、この「オ」の項目で、それらをまとめて結論を示すことになるだろうと予測することになる。
しかし、この「オ」の項目の前半では、「国民の間では様々な意見があるが、その動向も時代とともに変わってきており、」と述べており、直前の「エ」の項目の「国民に対する調査」の話を受けているだけである。
また、この「オ」の項目の文の後半の「国会や司法の場において、差別であるとの指摘がされてきた。」と述べている部分の「国会や司法」の話は、これより「上記」には出てきておらず、ここで初めて登場する話である。
そのため、「オ」の項目の文の後半部分に対して「上記のとおり、」の文言は係っていないことになる。
よって、この文は、「イ」「ウ」「エ」の話をまとめるために「上記のとおり、」という言葉を使っているというわけではなく、直前の「エ」の項目の「国民に対する調査」のことを示すものとして使っていることになる。
そこまでは理解が可能であるが、この「オ」の項目の文の後半を見ても、「これまでも、同性婚を許していないことについては、国会や司法の場において、差別であるとの指摘がされてきた。」というものであり、前半で述べていた「国民の間では様々な意見があるが、その動向も時代とともに変わってきており、」との部分と直接的に繋がる内容であるとまでいえるものではない。
また、それが「上記のとおり、」として示している「エ」の項目の内容とも繋がるものではない。
そうなると、この「オ」の項目の前半の「国民の間では様々な意見があるが、その動向も時代とともに変わってきており、」の部分は、直前の「エ」の項目の中に吸収する形で論じるべきものであって、この「オ」の項目の後半の「これまでも、同性婚を許していないことについては、国会や司法の場において、差別であるとの指摘がされてきた。」との部分と同一の文の中で論じるべきものではなかったはずである。
このように、これらの項目は文のまとまりをどのような意図で示そうとしているのか理解することができず、読み手を混乱させるものとなっている。
━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━
「国民の間では様々な意見があるが、その動向も時代とともに変わってきており、」との部分について検討する。
この訴訟の中で問われているのは憲法の解釈であり、「国民の間」の「様々な意見」や「その動向」が問われているわけではない。
もし司法権を行使する裁判所における合憲・違憲、合法・違法の判断が「国民の間」の「様々な意見」や「その動向」によって左右されることになれば、それは法に基づいて判断を下すものではないことから、「法の支配」、「法治主義」の精神に反することになる。
そのため、法解釈の場面で「国民の間」の「様々な意見」や「その動向」を取り上げ、結論を導き出すための根拠とすることは誤りである。
また、「国民の間」の「様々な意見」や「その動向」を受け止めて憲法の範囲内で政策を実現することは立法府である国会や行政府である内閣以下の行政機関の役割である。
そのため、国家の作用が「立法権」「行政権」「司法権」の三権に分立されており、その中でも司法権しか行使することのできない裁判所の立場で、「国民の間」の「様々な意見」や「その動向」などを論じて結論を導き出そうとすることは越権行為であるということができる。
よって、「国民の間」の「様々な意見」や「その動向」を論じて合憲・違憲、合法・違法の判断の根拠とすることは、司法権の逸脱・濫用に当たるものであり、正当化することはできない。
「これまでも、同性婚を許していないことについては、国会や司法の場において、差別であるとの指摘がされてきた。」との部分について検討する。
「同性婚を許していないこと」とある。
ここでいう「同性婚」の意味が「同性間の人的結合関係」を形成することを指しているのであれば、それは憲法21条1項の「結社の自由」で保障されるものである。
そして、それが法的な規制の対象となっているという事実はないことから、「許されていない」との説明は誤りとなる。
ここでいう「同性婚」の意味が「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを指しているのであれば、「同性間の人的結合関係」は「婚姻」の対象となっていないといえる。
ただ、「同性婚を許していない」との表現について、これは法制度が定められているか否かの問題であるから、むやみに「許す・許さない」という意味での「許していない」という表現を用いることは適切であるとはいえない。
このような表現は、別の個所の「不利益」などの文言と相まって、法制度の性質について客観的な視点から説明するものとして用いられる言葉遣いではなく、訴訟の当事者の一方の見方や意見、感じ方に与する形で論じるものとなっていると考えられる。
そのため、敢えてこのような表現を用いて論じていることは、公的な性質を持つ裁判所の立場で用いる言葉の選択として適切ではない。
「国会や司法の場において、差別であるとの指摘がされてきた。」とある。
「国会」では政治的な議論が日常的に行われており、その中で特定の議員がその政治的な立場に基づいて様々な指摘を行うことはあり得るところである。
しかし、その指摘の内容は政治的な議論の中の一つであり、法的な観点から考えて正しいものであるかどうかは、別の問題である。
そのため、「国会」で特定の議員がその者の政治的な立場に基づいて何らかの指摘を行ったとしても、それが直ちに憲法を解釈する際の基準となるというものではない。
よって、憲法の解釈が問われている場面で、「国会」で「指摘がされてきた。」ことを根拠として挙げていることは、解釈の方法として適切ではない。
「差別である」との文言について検討する。
日常用語として「差別」という言葉が使われた場合には、何らかの否定的な意味を背負っていることが多い。
そのため、この「差別」という言葉の使われ方は、既に「合理的な理由」がないという結論を示すものであることが前提となっている。
しかし、憲法14条1項の「平等原則」を審査する際に使われている「差別」の意味は、何らかの違いを見出して異なるものに分けている状態を指しているだけである。
ここには否定的な意味合いを含んでおらず、「区別」の文言と全く同様の意味で使われている。
そのため、その「差別=区別」の内容が「合理的な理由」に基づくものであるか否かがさらに検討されなければ、未だに結論を示すものではないのである。
・日常用語:「差別」 ⇒ 「合理的な理由」のない区別があるという結論
・法的判断:「差別」 ⇒ 何らかの区別があるという状態
→ さらに「合理的な理由」があるかを審査しなければ結論の当否は分からない
このことから、憲法14条1項についての法的な審査の際には、日常的に使われる「差別であるか否か」が問われているのではなく、「差別(区別)が存在する場合に、そこに合理的な理由があるか否か」が問われていることになる。
ここでは「差別であるとの指摘がされてきた。」と説明するのであるが、法的な審査の場面では「差別」と「区別」の文言は同じ意味であるため、それを前提にこの意味を読み解くと、「区別」が存在することを「指摘」されているだけである。
そのため、その「区別(差別)」に「合理的な理由」が存在するか否かは、未だ明らかでないということになる。
これを日常用語として使われる「差別」の意味に置き換えて考えると、「区別(差別)」に「合理的な理由」がないことを「指摘」されていることを意味することになる。
しかし、憲法14条1項の「平等原則」の審査を行う際には、日常用語として使われる「差別であるか否か」という議論の仕方とは明確に切り離して考える必要があり、これを混同して用いているとすれば適切ではない。
また、法的な審査において何らかの結論を導き出すための考察の中では、その「合理的な理由」の存否の部分について、どのような内容であるのかを明らかにすることが必要である。
そのため、単に他の機関が示した結論を見て、それを根拠として同様の結論を述べるということでは、他の機関の示した結論に対して賛否を述べているだけということになるのであり、結論を導き出している理由となる部分の当否を審査するものとはなっておらず、そこで出した結論の正当性を支えるものとはならない。
よって、ここでいう「指摘」と称するものを憲法の解釈を行う際の根拠として示そうとしていることも妥当でない。
カ 現状を見てみると、本件規定が同性婚を許していないため、同性愛者は婚姻することができず、これによる制度的な保障が受けられないことから、異性婚の成立によって享受が可能となる様々な制度が適用されないという著しい不利益を受けている。このことは、日常の生活、職場の関係、社会上の生活の各場面においてそうであるし、不慮の出来事が起きた場合にも同様であって、要するに人としての営みに支障が生じているということである。
【筆者】
「本件規定が同性婚を許していないため、同性愛者は婚姻することができず、これによる制度的な保障が受けられないことから、異性婚の成立によって享受が可能となる様々な制度が適用されないという著しい不利益を受けている。」との記載がある。
「本件規定が同性婚を許していないため、」との部分について検討する。
この「同性婚」の意味が「同性間の人的結合関係」を形成することを指すものであれば、それは憲法21条1項の「結社の自由」によって保障されているものである。
「本件規定」はそのような人的結合関係を形成することを規制するものではないことから、「同性間の人的結合関係」を形成することを「許していない」との認識は誤りである。
この「同性婚」の意味が「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを指しているのであれば、「本件規定」は「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを定めていないということができる。
ただ、これは法制度が定められているか否かの問題であるから、むやみに「許す・許さない」という意味での「許していない」という表現を用いることは適切ではない。
このような表現は、法制度の性質について客観的な視点から説明するものとして用いられる言葉遣いとはなっておらず、後に出てくる「著しい不利益」という言葉と相まって、訴訟の当事者の一方の見方や意見、感じ方に与する形で論じるものとなっていることが考えられる。
そのため、敢えてこのような表現を用いて論じていることは、公的な性質を持つ裁判所の立場で用いる言葉の選択として相応しいものではない。
「同性愛者は婚姻することができず、これによる制度的な保障が受けられないことから、異性婚の成立によって享受が可能となる様々な制度が適用されないという著しい不利益を受けている。」との部分について検討する。
まず、「同性愛者」とあるが、法制度は個々人の内心に対して中立的な内容でなければならないのであり、ここで「同性愛者」のように法律論として個々人の内心に着目して人を区別することが可能であるかのような前提の下に論じていることは妥当でない。
次に、婚姻制度は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度である。
具体的には、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」を目的として、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす「一人の男性」と「一人の女性」が選び出され、その間を「貞操義務」などの一定の形式で法的に結び付け、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によってそれらの目的の達成を目指すものである。
この婚姻制度は、「性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いをする制度ではないし、「性愛」に基づいて制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもない。
そのため、婚姻制度(男女二人一組)の要件に従って制度を利用する意思を有するであれば、どのような内心を有する者であっても分け隔てなく制度を利用することが認められており、当然、「同性愛者」を称する者であるとしても適法に制度を利用することができる。
そのことから、「同性愛者」を称する者も「婚姻すること」はできるのであり、ここでいう「これによる制度的な保障」というものを受けることはできるし、「異性婚の成立によって享受が可能となる様々な制度」も適用される。
よって、ここで「同性愛者は婚姻することができず、これによる制度的な保障が受けられない」や「異性婚の成立によって享受が可能となる様々な制度が適用されない」と述べていることは誤りである。
また、「著しい不利益を受けている。」との部分についても、そもそも「同性愛者」を称する者も婚姻制度を適法に利用することができることから、利用することができないことを前提に「著しい不利益を受けている。」と述べていることは誤りとなる。
もし「同性愛者」を称する者が婚姻制度(男女二人一組)の要件を満たして制度を利用する意思を有するにもかかわらず、「同性愛者」を称する者であることを理由としてその制度を適用しなかったり、その利用を否定するようなことがあれば、それは憲法14条1項の「平等原則」における「法適用の平等」に違反することになる。
そのため、むしろこの判決が「同性愛者」を称する者が「婚姻することができず、」のように「婚姻すること」ができないかのように論じていることは、「同性愛者」を称する者であることを理由として制度の利用を否定するものとなっていることから、憲法14条1項の「平等原則」における「法適用の平等」に違反するものである。
「同性愛者」を称する者に対して婚姻制度(男女二人一組)を適用しないかのような論じ方をしていることは不適切である。
もし「同性愛者」を称する者であるとしても婚姻制度(男女二人一組)を利用することが可能であることを理解した上で、敢えて「同性愛者」を称する者を取り上げて「婚姻することができない」と述べているとすれば、「同性愛者」を称する者が婚姻制度(男女二人一組)を利用しているはずがないとか、利用してはならないとか、利用することは正当ではないという価値観を基にして論じているということになる。
これは、「同性愛者」を称する者が婚姻制度(男女二人一組)を利用することに対して否定的な意味合いを含むものとなっており、不当な主張である。
「同性愛者」を称する者に対して、婚姻制度(男女二人一組)を利用しているはずがないとか、利用してはならないとか、利用することは正当ではないなどという特定の価値観を押し付けるものということができ、憲法19条の「思想良心の自由」、憲法20条1項の「信教の自由」に違反するものである。
法制度は個々人の思想、信条、信仰、感情に対して中立的でなければならないのであり、特定の価値観に基づいて制度を利用することを求めるようなことがあってはならないし、勧めるようなこともしてはならない。
そのため、「同性愛者」などと人の内心に踏み込む形で論じていること自体が誤りである。
「著しい不利益を受けている。」との部分について検討する。
この「著しい不利益を受けている。」とする原因として、下記の三つが挙げられている。
◇ 「婚姻することができず、」
◇ 「これによる制度的な保障が受けられない」
◇ 「異性婚の成立によって享受が可能となる様々な制度が適用されない」
ただ、これらはいずれも、婚姻制度(男女二人一組)の要件を満たさない場合において、単に婚姻制度を利用していない状態となっていることを指しているだけである。
そのため、これを理由として「著しい不利益を受けている。」ということにはならない。
その理由は、下記の通りである。
憲法は「個人の尊厳」の原理に基づいており、自然人は「個人主義」の下に各々「自律的な個人」として生存していくことを予定している。
そのことから、「婚姻制度を利用していない者(独身者)」の状態で既に完全な状態ということができ、それが基準(スタンダード)となる状態である。
そのため、ある者が婚姻制度を利用していないとしても、その状態について「不利益」と称されるものは存在しない。
よって、婚姻制度を利用しておらず、その制度の適用を受けていない状態を取り上げて「著しい不利益を受けている。」かのように述べていることは誤りである。
上記のように、法的な視点から客観的に考えれば、「婚姻制度を利用していない者(独身者)」の状態に「不利益」と称されるものは存在していない。
それにもかかわらず、このような言葉を用いているということは、ある者にとって法制度が自らの望む形で定められている状態を完全な状態と設定した上で、現在の法制度がその状態に至っていないという認識の下に、その完全な状態と設定したゴールまでの距離(その間の差の部分)を「不利益」と呼ぼうとする動機が含まれていることになる。
◇ この判決の認識
自らの望む法制度(ゴール)
↑
↑ (この差異を『不利益』と表現している。)
↑
現在地点
しかし、法的な視点から見れば、憲法は「個人の尊厳」の原理に基づいており、自然人は「個人主義」の下に各々「自律的な個人」として生存していくことを予定していることから、法制度を利用していない状態で既に完全な状態ということができ、「不利益」と称されるものは存在してない。
◇ 法律論として客観的な視点
現在地点 ← (法制度がない状態で既に完全であり、『不利益』は存在しない)
そのため、ある者が「不利益」と表現している場合があるとしても、それは自らの望む形で法制度が定められている状態をゴールと考えることを前提とした上での、そのゴールと現在地点との間の距離について述べているものであり、その者個人が抱いている理想の法制度を前提とする主観的な思いを表現しているに過ぎないものである。
しかし、裁判所の立場では法制度の性質について客観的な視点から論じることが必要とされており、このような訴訟の当事者の一方が現在の法制度をどのように受け止めているかという主観的な立ち位置から見た場合の言葉遣いをそのまま受け入れる形で表現していることは適切ではない。
これとは別に、「本件規定」である婚姻制度が「男女二人一組」を対象としており、「同性間の人的結合関係」を対象としていないことから、「同性間の人的結合関係」では「これによる制度的な保障が受けられない」や「異性婚の成立によって享受が可能となる様々な制度」が適用されないことについて検討する。
「婚姻」は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」を目的とし、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす「一人の男性」と「一人の女性」を選び出し、その間に「貞操義務」を設けるなど一定の形式で法的に結び付け、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によって立法目的の達成を目指すものである。
婚姻制度は、この目的との関係で整合的な要素を満たす人的結合関係を対象として設けられているものであり、婚姻制度の対象となる場合とならない場合があることはもともと予定されていることである。
そして、婚姻制度における法的効果や一定の優遇措置についても、この目的を達成するための手段として整合的な形で設けられるものであり、婚姻制度の対象とならない場合にその法的効果や優遇措置を得られないことはもともと予定されていることである。
これは、もし婚姻制度が立法目的を達成するための手段として整合的な形で制度を設けているにもかかわらず、婚姻制度の対象とならない場合に対してまで同様の法的効果や優遇措置を行った場合には、婚姻制度が一定の枠を設けることによって立法目的の達成を目指す仕組みとして機能しているにもかかわらず、一定の枠を設けることによって立法目的の達成を目指すという仕組みとしての機能を阻害することになり、婚姻制度を他の様々な人的結合関係との間で区別する形で設けている意味そのものを失わせてしまうことになるからである。
そのため、婚姻制度を設けていることそれ自体において、婚姻制度の対象となる場合とならない場合との間に差異が生じるということはもともと予定されており、制度が目的を達成するための手段として整備されているものであり、目的を達成するための手段として機能することが求められている以上は、そこで生じる差異を無くすということは本来的にできないのである。
そのことから、婚姻制度の対象とならない場合に対して、婚姻制度について定めている「本件規定」として「これによる制度的な保障」というものをしなければならないということにはならない。
また、「異性婚の成立によって享受が可能となる様々な制度」についても、上記と同様に、婚姻制度が「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的との間で整合的な要素を満たす人的結合関係を対象とするものであり、その目的を達成するための手段として整合的な形でここでいう「様々な制度」を「適用」するというものであるから、それを婚姻制度の対象となっていない人的結合関係に対してまで、ここでいう「様々な制度」を「適用」しなければならないということにはならない。
よって、「婚姻」「による制度的な保障」や「異性婚の成立によって享受が可能となる様々な制度」というものを、「婚姻」の対象とならない「同性間の人的結合関係」に対してまで「適用」しなければならないかのような前提で論じていることは誤りである。
その他、「異性婚」との文言について検討する。
法的な視点で考えると、「婚姻」である時点でそれは「男女」によるものに限られることから、ここで「異性」という「男女」を指す言葉と、「~~婚」のように「婚姻」という「男女」を指す言葉を同時に用いていることは、同義反復となるため文法上は誤用である。
また、同義反復となることを無視して「異性婚」という言葉を用いたとしても、これは法的に「異性」を満たさない人的結合関係を「婚姻」とすることができるという根拠を示すことにはならない。
そのため、この「異性婚」という言葉に対する形で「同性婚」というものを法的に構成することができるということにはならないことに注意が必要である。
「このことは、日常の生活、職場の関係、社会上の生活の各場面においてそうであるし、不慮の出来事が起きた場合にも同様であって、要するに人としての営みに支障が生じているということである。」との記載がある。
この文は、「このことは、」と書かれていることから、前の文と関係させるものとなっている。
そのため、前の文と合わせて考えると、下記のようにまとめることができる。
「婚姻」「による制度的な保障が受けられない」
「異性婚の成立によって享受が可能となる様々な制度が適用されない」
↓ ↓
「人としての営みに支障が生じている」
・「日常の生活」
・「職場の関係」
・「社会上の生活の各場面」
・「不慮の出来事が起きた場合」
↓ ↓
「著しい不利益を受けている。」
しかし、憲法は「個人の尊厳」の原理に基づいており、自然人は「個人主義」の下に各々「自律的な個人」として生存していくことを予定している。
そのため、何らの制度も利用していない状態で既に完全な状態であり、当然、婚姻制度を利用していないとしても、その「婚姻していない者(独身者)」の状態こそが基準(スタンダード)となるものである。
そのことから、個々人が婚姻制度を利用していない状態であることについて、そこに「不利益」と称されるものは存在しないし、「人としての営みに支障が生じている」といえるような状態にあるともいえない。
実際に日本国内には「婚姻制度を利用していない者(独身者)」として生活している者がいるのであり、その者が「著しい不利益を受けている。」といわれる状態にあるわけではないし、「人としての営みに支障が生じている」状態にあるともいえない。
それにもかかわらず、その「不利益」のない「婚姻制度を利用していない者(独身者)」が人的結合関係を形成した段階で初めて「不利益」が生じたり、「人としての営みに支障が生じ」るかのように述べるものとなっており、基準点(スタンダード)を誤っているといえる。
よって、その婚姻制度を利用していない状態について「不利益」があるかのような前提の下に、「人としての営みに支障が生じている」と評価していることは誤りである。
その他、ここで「不利益」や「人としての営みに支障が生じている」との言葉を用いている背景を検討する。
この表現の中には、ある者にとって法制度が自らの望む形で定められている状態を完全な状態と設定した上で、現在の法制度がその状態に至っていないという認識の下に、その完全な状態と設定したゴールまでの距離(その間の差の部分)について「不利益」や「人としての営みに支障が生じている」と呼ぼうとする動機が含まれているといえる。
◇ この判決の認識
自らの望む法制度(ゴール)
↑
↑ (この差異を『不利益』や『支障』と表現している。)
↑
現在地点
しかし、法的な視点から見れば、憲法は「個人の尊厳」の原理に基づいており、自然人は「個人主義」の下に各々「自律的な個人」として生存していくことを予定していることから、法制度を利用していない状態で既に完全な状態である。
そのため、そこに「不利益」や「人としての営みに支障が生じている」などと称されるものは存在してない。
◇ 法律論として客観的な視点
現在地点 ← (法制度がない状態で完全であり、『不利益』や『支障』は存在しない)
このことから、ある者が「不利益」や「人としての営みに支障が生じている」と表現している場合があるとしても、それは自らの望む形で法制度が定められている状態をゴールと考えることを前提とした上での、そのゴールと現在地点との間の距離について述べているものであり、その者個人が抱いている理想の法制度を前提とする主観的な思いを表現しているに過ぎないものである。
これは結局、「婚姻」の中に含まれない人的結合関係に対して、新たな制度を立法することを国家に対して求めるものに他ならないといえる。
国(行政府)の主張では、下記に対応するものである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
そうすると,原告らが「婚姻の自由」として主張するものの内実は,「両性」の本質的平等に立脚すべきことを規定する憲法24条2項の要請に従って創設された現行の婚姻制度の枠を超えて,同性間の人的結合関係についても婚姻と同様の積極的な保護や法的な利益の供与を認める法制度の創設を国家に対して求めるものにほかならないのであって,国家からの自由を本質とするものではないから,このような自由が憲法13条の幸福追求権の一内容を構成するものと解することはできない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【九州・第6回】被告第4準備書面 令和3年l0月29日 PDF
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
控訴人らが本件規定により侵害されていると主張する権利又は利益の本質は、結局のところ、同性間の人的結合関係についても異性間の人的結合関係を対象とする婚姻と同様の積極的な保護や法的な利益の供与を認める法制度の創設を国家に対して求めるものにほかならず、法制度を離れた生来的、自然権的な権利又は人格的生存に不可欠の利益として憲法で保障されているものではないから、このような内実のものが憲法13条の規定する幸福追求権の一内容を構成すると解することはできない。……(略)……
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【札幌・第4回】被控訴人第2準備書面 令和5年6月8日 PDF
ただ、これは憲法24条1項の「婚姻」や憲法24条2項の定める「婚姻及び家族」の枠組みの「要請」に従って法律上の婚姻制度が立法されているか否かを審査する中で論じることができるものではない。
また、憲法14条1項の「平等原則」の審査についても、「婚姻制度を利用していない者(独身者)」の状態が基準となって、「婚姻制度を利用している者(既婚者)」が婚姻制度の立法目的を達成するための手段として不必要に過大な法的効果や優遇措置を得るものとなっていないかを審査し、その結果、不必要に過大な法的効果や優遇措置を得るものとなっている場合には、その不必要に過大な法的効果や優遇措置を定めている規定が個別に失効することによって格差が是正されるというものである。
これは、婚姻制度の対象となっていない人的結合関係を形成している者(『婚姻していない者〔独身者〕』)に対して法的効果や優遇措置を設けることによって差異を解消するというものではないため、これを憲法14条1項の「平等原則」の審査として論じることができるということにはならない。
そのため、この新たな制度を創設するよう国家に対して求める主張を、憲法24条1項や2項、14条1項に違反するか否かという審査の中で取り扱うことができるかのような前提の下に論じていること自体が誤りである。
もう一つ、法制度が自らの思い通りに定められていないことに対する不満については、下記が参考になる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
このように、原告らの主張は、結局のところ、自らの思想、信条、政治的見解等と相容れない内容である本件各行為が行われたことにより、精神的な苦痛を感じたというものであるところ、多数決原理を基礎とする代表民主制を採用している我が国においては、多様な意見を有する国民が、表現の自由、政治活動の自由、選挙権等の権利を行使し、それぞれの立場・方法で国や政府による立法や政策決定過程に参画した上で、最終的には、全国民の代表者として選出された議員により組織される国会において個々の法令が制定されるのであるから、その結果として、ある個人の思想、信条、政治的見解等とは相容れない内容の法令が制定されることは、全国民の意見が一致しているというおよそ想定し難い場面以外では、不可避的に発生する事態である。そうすると、自らの思想、信条、政治的見解等とは相容れない行為が行われたことで精神的苦痛を感じたとしても、そのような精神的苦痛は社会的に受忍しなければならないものというほかない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
国家賠償請求事件 高知地方裁判所 令和6年3月29日 (PDF)
ただ、憲法24条は「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めており、これを満たさない人的結合関係を「婚姻」とする法律を立法することは、この一夫一婦制(男女二人一組)の枠組みを定めている意図である「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」という目的を達成するための機能を阻害することになるため、憲法24条のこれらの文言に抵触して違憲となる。
また、憲法24条の「婚姻」は「生殖と子の養育」に関わる制度を一元的に集約して規律する趣旨を有しており、「生殖と子の養育」に関わる制度を憲法24条の「婚姻」を離れて立法することはできないため、「生殖と子の養育」に関わる制度や影響を与える制度を憲法24条の「婚姻」を離れて立法しようとした場合には、憲法24条の「婚姻」に抵触して違憲となる。
他にも、婚姻制度「男女二人一組」を対象としていることは、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」という目的を達成することに資することから、「婚姻制度を利用していない者(独身者)」との間で生じる差異を正当化することができるが、そのような趣旨からは導かれない人的結合関係(同性間の人的結合関係)を対象とした制度を設けることは、その制度を利用していない者との間で生じる差異を正当化することができず、憲法14条1項の「平等原則」に違反することになる。
そのため、民主制の下で国会における多数決原理の過程を経て法律を立法することを考えるとしても、そこには上記のような憲法上の制約が存在するのであり、これらの制約を超えて思い通りに制度を立法することができるというものではない。
この点にも注意が必要である。
キ 同性愛者も、婚姻することができなくても、契約や遺言により、ある程度までは婚姻と似たような一定の効果を受けることが可能である。しかし、代替的な措置により不利益を受けないことが合理的な区別の理由になるものかは判然としないが、これを措くとしても、婚姻による効果は、民法のほか、各種の法令で様々なものが定められており、代替的な措置によって、同性愛者が婚姻することができない場合の不利益を解消することができるとは認め難い。
【筆者】
「同性愛者も、婚姻することができなくても、契約や遺言により、ある程度までは婚姻と似たような一定の効果を受けることが可能である。」との記載がある。
「同性愛者も、婚姻することができなくても、」との部分について検討する。
まず、婚姻制度は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」を目的として、その目的を達成するための手段としてその間で自然生殖を想定することができる「男性」と「女性」の組み合わせを「貞操義務」などの一定の形式で法的に結び付け、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によって立法目的の達成を目指すものである。
この婚姻制度は、「性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかによって区別取扱いをするような制度ではないし、「性愛」に基づいて制度を利用すること求めるものでも勧めるものでもない。
そのため、「同性愛者」を称する者であるとしても、婚姻制度(男女二人一組)の要件に従って制度を利用する意思があるのであれば、適法に利用することができる。
そのことから、「同性愛者」を称する者が「婚姻することができな」いかのように述べていることは誤りである。
この判決の「同性愛者」を称する者が「婚姻することができな」いことを前提に論じている部分は、婚姻制度は「性愛」を保護することを目的とした制度ではなく、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いをしている事実はなく、「性愛」に基づいて制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもないにもかかわらず、勝手に個々人の内心を審査し、それが「同性愛」を抱く者であった場合には、「婚姻することができな」い存在であるかのように扱うものとなっている。
これは、婚姻制度について定めた条文の中に記されていない事柄によって「婚姻すること」の可否を勝手に判断するものということができ、法律の内容に反するものであることから、違法な判断であるといえる。
また、これは法令の適用の場面において「同性愛者」を称する者と、そうでない者とを区別し、その中の「同性愛者」を称する者が婚姻制度(男女二人一組)を利用することを否定するものであることから、憲法14条の「平等原則」の「法適用の平等」にも違反するものである。
「契約や遺言により、ある程度までは婚姻と似たような一定の効果を受けることが可能である。」との部分について検討する。
━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━
この文が読み取りづらい理由は「ある程度まで」と「一定の」の意味が重なるにもかかわらず、別々に記載され、まとめられていないからである。
下記で「ある程度まで」か「一定の」のどちらかを省略しても意味が通じることを示す。
「ある程度までは婚姻と似たような一定の効果を受けること」
◇ 「ある程度までは婚姻と似たような……(略)……効果を受けること」
◇ 「……(略)……婚姻と似たような一定の効果を受けること」
━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━
憲法は「個人の尊厳」の原理に基づいており、自然人は「個人主義」の下に各々「自律的な個人」として生存していくことを予定している。
そのため、何らの制度も利用していない者の状態で既に完全な状態ということができる。
そして、その個々人は、他者との間で「契約や遺言」などを行いながら生活していくことになる。
そのような中、その社会の中で「生殖」に関わって生じる社会的な不都合が生じることから、これを解消するために「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」を目的として、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす「一人の男性」と「一人の女性」の組み合わせを選び出し、その間に「貞操義務」を設けるなど一定の形式で法的に結び付けることで、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によってそれらの目的を目指す仕組みとして婚姻制度を定めることになる。
そのため、ここでは「契約や遺言により、ある程度までは婚姻と似たような一定の効果を受けることが可能である。」のように、「婚姻」を中心に考えて、その「婚姻と似たような一定の効果」を実現するために「契約や遺言」を持ち出すものとなっているが、どちらかといえば、「契約や遺言」が先にあって、その後に特定の目的を達成するための手段として婚姻制度が定められるという関係にあるものである。
◇ この判決の発想
「婚姻」
↓ (婚姻と似たような一定の効果を受けることが可能である。)
「契約や遺言」
◇ 本来の考え方
「契約や遺言」
↓ (法制度のパッケージ)
「婚姻」
この点の順序を誤ると、「契約や遺言」を用いた関係が他の制度を利用する関係と比べて何か劣ったものであるかような認識を引き起こし、それによって婚姻制度を利用していないことについて「不利益」があるなどという誤った認識を基にして論じる者や、客観的に見れば法制度が定められていないというだけのことであるにもかかわらずそれを「許されていない」というような表現を用いて否定的な受け止め方をする者が現れることになるため注意が必要である。
「しかし、代替的な措置により不利益を受けないことが合理的な区別の理由になるものかは判然としないが、これを措くとしても、婚姻による効果は、民法のほか、各種の法令で様々なものが定められており、代替的な措置によって、同性愛者が婚姻することができない場合の不利益を解消することができるとは認め難い。」との記載がある。
━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━
この文が読み取りづらい理由は下記の通りである。
◇ ここでは、「代替的な措置」という言葉が突然登場するものとなっている。
これは一文前で登場した「契約や遺言」によって「婚姻と似たような一定の効果を受けること」を指すものといえるが、その内容がここで「代替的な措置」という言葉に置き換わって表現されることを予感させるための「このような(代替的な措置)」などの文言が付けられていない。
そのため、読み手を躓かせる原因となっている。
◇ 通常、憲法14条1項の「平等原則」の審査においては、「区別」が存在する場合において、そこで「区別」していることの「合理的な理由」の存否が問われることになる。
しかし、ここでは「合理的な区別の理由」と記載されており、その「合理的な区別の理由になるものか」と論じていることから、「合理的な区別」という何らかの基準を用いるか否かについて「理由」になるか否かを問う意味となっている。
この点で、法的な視点から見れば意味がズレており、誤った論じ方をするものとなっている。
◇ 「代替的な措置により不利益を受けないことが合理的な区別の理由になるものかは判然としないが、」との部分は、上記で述べたように、「代替的な措置」や「合理的な区別の理由」の文言によって読み取りづらいものとなっている。
また、法的に考えれば「不利益」は存在しないにもかかわらず、「不利益」が存在するかのように述べるものとなっている。
そこで、これらを読み取りやすく修正すると、この文は下記のように述べていることになる。
・ 「代替的な措置により不利益を受けないことが合理的な区別の理由になるものかは判然としないが、」
↓ ↓ ↓ ↓
・ (契約や遺言)(が可能である)こと「により」「区別」の「合理的な」「理由になるものかは判然としないが、」
◇ 「代替的な措置により不利益を受けないことが合理的な区別の理由になるものかは判然としないが、」との部分は、訴訟の当事者の一方である国(行政府)が主張していた内容について、この札幌高裁判決の裁判官が自分なりに、国(行政府)の主張は「代替的な措置」があるから「区別の」「合理的な」「理由」になると述べているのだろうと想像し、それについて「判然としない」と論じようとしているものである。
しかし、その国(行政府)の主張を見たことがある者であれば、この部分が国(行政府)の主張のどの論点に対して論じようとしているのか読み取ることが可能であるが、この判決文の中ではその国(行政府)の主張について予め示した後にそれに対して反論するという形式にはなっていないため、この判決文を読み取ることによって初めてこの訴訟の内容を理解しようとする者にとっては、一体何の説明をしているのか意味を読み取ることができないものとなっている。
この点で、読み手を混乱させるものとなっている。
━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━
「代替的な措置により不利益を受けないことが合理的な区別の理由になるものかは判然としないが、」との部分について検討する。
「代替的な措置により」とある。
ここでいう「代替的な措置」とは、一文前の「契約や遺言により、ある程度までは婚姻と似たような一定の効果を受けること」をいうものである。
しかし、これは法的な視点から客観的に論じているものであるとはいえない。
まず、「契約や遺言」はそれ自体として単独で成立する法律行為であり、何かの「代替」といわれるような位置付けのものではない。
そのため、この「契約や遺言」を何かの「代替」であるかのような位置づけで見ていることは、特定の制度を持ち上げ、逆に「契約や遺言」を見下すという特定の価値観に基く主張を行っていることになるのであり、法制度に対して優劣を付けようとする発想に基づくものとなっている。
裁判所の立場でこのような態度を示すことは不適切である。
ここで「婚姻」を持ち上げ、「契約や遺言」を格下げして捉えることの背景には、ある個人が特定の法制度を利用しようと考えた場合に、その個人にとってその法制度が自らの望む形で定められていないことを理由に思い通りとはならず、その法制度の利用を控えて、別の手段を検討するという場合について「代替的な措置」などと表現していることがあると考えられる。
しかし、法制度そのものは立法目的を達成するための手段として定められるものであることから、制度が政策的なものである以上は、その制度が自らの望む形で定められていないことは当然起こり得ることである。
そして、ある個人が別の手段を利用することを検討する場合があるとしても、それぞれの法制度そのものには何らの優劣はないのであり、それらの法制度の関係を法的な視点から客観的に捉えた場合には、そこに「代替的な措置」などといわれるような性質のものではないのである。
これについて、裁判所は法制度の性質について客観的な視点から論じることが必要であり、このような訴訟の当事者の一方が現在の法制度をどのように受け止めているかという主観的な立ち位置から見た場合の言葉遣いをそのまま受け入れて表現していることは適切ではない。
「不利益を受けないことが」とある。
憲法は「個人の尊厳」の原理に基づいており、自然人は「個人主義」の下に各々「自律的な個人」として生存していくことを予定している。
そのため、何らの制度も利用していない状態で既に完全な状態であるということができる。
そのことから、当然、「婚姻制度を利用していない者(独身者)」であるとしても、そこに「不利益」といわれるような状態にあるわけではない。
よって、「不利益を受けないことが」のように「婚姻制度を利用していない者(独身者)」の状態が「不利益」であることを前提として論じていることは誤りである。
また、もともと「不利益」は存在しないため、ここでいう「代替的な措置」によって「不利益」を「受けない」状態になるかのような説明も、その前提を欠くという点で誤りである。
ここで「不利益」という言葉で表現している部分は、ある個人が特定の法制度を利用しようと考えた場合に、その個人にとってその法制度が自らの望む形で定められていないことを理由に思い通りとはならず、その法制度の利用を控えるという場合について、その者個人の受け止め方として「不利益」などと表現しているものを述べているものである。
しかし、法制度そのものは立法目的を達成するための手段として定められるものであり、制度が政策的なものである以上は、その制度が自らの望む形で定められていないことは当然起こり得ることである。
その状態を法的な視点から客観的に捉えた場合には、その者個人が「不利益」を受けているということになるわけではない。
そのため、このような言葉が用いられる背景には、法制度が自らの望む形で定められている状態を完全な状態として設定した上で、現在の法制度がその状態に至っていないという認識に基づいて、その完全な状態と設定したゴールまでの距離(その間の差の部分)を「不利益」と呼ぼうとする動機が含まれていることになる。
◇ この判決の認識
自らの望む法制度(ゴール)
↑
↑ (この差異を『不利益』と表現している。)
↑
現在地点
しかし、法的な視点から見れば、憲法は「個人の尊厳」の原理に基づいており、自然人は「個人主義」の下に各々「自律的な個人」として生存していくことを予定していることから、法制度を利用していない状態で既に完全な状態ということができ、そこに「不利益」は存在してない。
◇ 法律論として客観的な視点
現在地点 ← (法制度がない状態で既に完全であり、『不利益』は存在しない)
そのため、その者が「不利益」と表現している場合があるとしても、それは自らの望む形で法制度が定められている状態をゴールと考えることを前提とした上での、そのゴールと現在地点との間の距離について述べているものであり、その者個人が抱いている理想の法制度を前提とする主観的な思いを表現しているに過ぎないものである。
これについて、裁判所は法制度の性質について客観的な視点から論じることが必要であり、このような訴訟の当事者の一方が現在の法制度をどのように受け止めているかという主観的な立ち位置から見た場合の言葉遣いをそのまま受け入れて表現していることは適切ではない。
また、このような言葉を用いるか否かの判断の中には、その訴訟の当事者の一方が抱いている理想の法制度が定められている状態を完全な状態(目標地点・ゴール)として設定することを受け入れるか否かという隠れた論点が含まれている。
それを見抜くことができないままに、安易にこのような言葉を用いることは、その隠れた論点が表出しないままに、その訴訟の当事者の抱いている理想の法制度が定められている状態を完全な状態(目標地点・ゴール)として設定することを受け入れることを前提として論じていることになってしまう。
しかし、そのような前提となる状況認識の設定そのものが、法的な視点から客観性を保つ形で論じることのできていないものなのであり、これを前提として結論を導こうとすることは、判断の過程における中立性が損なわれていることとなる。
よって、裁判所の立場では、このような訴訟の当事者の一方が自己の主張を通すために行っている前提となる基準点(スタンダード)を移し替えた上で論じる表現をそのまま受け入れて用いていることは適切ではない。
この点について、国(行政府)の主張では下記のように説明されている。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
そうすると、原告らが本件規定により侵害されていると主張する権利又は利益は、憲法24条2項の要請に基づき、異性間の人的結合関係を対象とする婚姻について具体的な内容として定められた権利又は利益であり、結局のところ、これらが侵害されたとする原告らの主張の本質は、同性間の人的結合関係についても、異性間の人的結合関係を対象とする婚姻と同様の積極的な保護や法的な利益の供与を認める法制度の創設を国家に対して求めるものに他ならない。
従って、本件規定が「婚姻の自由」ないし婚姻に伴う種々の権利及び利益を奪うものとはいえないから、原告らの主張は理由がない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【東京二次・第5回】被告第3準備書面 令和4年6月20日
上記のように「代替的な措置」や「不利益」という言葉を用いていることの背景にある、法制度が自らの望む形で定められていないことに対する不満や憤りの気持ちをどのように考えるかについては、下記が参考になる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
このように、原告らの主張は、結局のところ、自らの思想、信条、政治的見解等と相容れない内容である本件各行為が行われたことにより、精神的な苦痛を感じたというものであるところ、多数決原理を基礎とする代表民主制を採用している我が国においては、多様な意見を有する国民が、表現の自由、政治活動の自由、選挙権等の権利を行使し、それぞれの立場・方法で国や政府による立法や政策決定過程に参画した上で、最終的には、全国民の代表者として選出された議員により組織される国会において個々の法令が制定されるのであるから、その結果として、ある個人の思想、信条、政治的見解等とは相容れない内容の法令が制定されることは、全国民の意見が一致しているというおよそ想定し難い場面以外では、不可避的に発生する事態である。そうすると、自らの思想、信条、政治的見解等とは相容れない行為が行われたことで精神的苦痛を感じたとしても、そのような精神的苦痛は社会的に受忍しなければならないものというほかない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
国家賠償請求事件 高知地方裁判所 令和6年3月29日 (PDF)
「合理的な区別の理由になるものかは判然としないが、」とある。
この部分の意味について、上記の「代替的な措置」や「不利益」の問題点を修正し、一文前の内容と合わせ、また、上記の文章の読み取りづらさについて解説したところで説明したように「合理的な区別の理由」の文言の問題点を修正した上で、下記のように述べているものとして検討する。
・ (契約や遺言)(が可能である)こと「により」「区別」の「合理的な」「理由になるものかは判然としないが、」
まず、婚姻制度は「性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いをする制度ではないし、「性愛」に基づいて制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもない。
そのため、婚姻制度は「性愛」と関わらない制度であり、「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかという「性的指向」と称するものによって「区別」しているという事実はない。
つまり、この判決が「(2)」の第三段落の第二文で述べるような「性的指向に係る婚姻制度における取扱いの区別」というものは存在していない。
そのことから、「性的指向」と称するものによって「区別」はされていないことから、その「合理的な」「理由」について検討する前提を欠くものである。
よって、「区別」が存在するかのような前提の下に、ここで「合理的な区別の理由になるものかは判然としないが、」のように「区別の」「合理的な」「理由」の有無を検討しようとしていること自体が誤りである。
その他、婚姻制度が「男女二人一組」が対象を対象としており、それを満たさない場合を対象としていないことについては、「婚姻」が「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた枠組みであることによるものである。
具体的には、「婚姻」は、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」を目的として、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす「一人の男性」と「一人の女性」を選び出し、その間に「貞操義務」を設けるなど一定の形式で法的に結び付け、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によって立法目的の達成を目指す枠組みである。
また、憲法24条はこの「婚姻」を規定し、「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて、上記の「婚姻」という枠組みそのものが有する目的とその目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす人的結合関係について、一夫一婦制(男女二人一組)の枠組みを具体的に示している。
このように、婚姻制度が「男女二人一組」を対象としていることは、憲法24条に基づくものとなっている。
そして、憲法上の条文の中に定められている事柄については憲法上の他の条文との間で矛盾することはないことから、その憲法24条で定められている事柄について憲法14条により審査することはできない。
そのため、憲法24条で定められている「男女二人一組」という枠組みそのものが憲法14条1項の「平等原則」に違反するということにはならないため、憲法14条1項の「平等原則」における区別の合理性を審査する前提にない。
よって、ここで婚姻制度が「男女二人一組」を対象としていることについては、憲法24条に基づくものであるにもかかわらず、同じ憲法上の条文として定められている憲法14条1項の「平等原則」によって審査することができることを前提に、「区別」の「合理的な」「理由」の存否を検討しようとしていることは、解釈の方法として誤りである。
もう一つ、憲法14条1項の「平等原則」を用いて審査することのできる事柄を検討するとしても、それは「婚姻制度を利用している者(既婚者)」と「婚姻制度を利用していない者(独身者)」とを比較して、「婚姻制度を利用している者(既婚者)」が婚姻制度の立法目的を達成するための手段として不必要に過大な優遇措置を得るものとなっていないかどうかである。
そして、もしそれが不必要に過大なものとなっていた場合には、その過大な優遇措置に関する規定が個別に失効することによって格差が是正されることになるというものである。
そのため、もし「婚姻制度を利用している者(既婚者)」と「婚姻制度を利用していない者(独身者)」との間で「婚姻制度を利用している者(既婚者)」の得ている優遇措置の内容について「合理的な」「理由」が存在しない場合には、その「婚姻制度を利用している者(既婚者)」の得ている優遇措置に関する規定が失効することによって差異が是正されることになるのであり、これは「婚姻制度を利用していない者(独身者)」に対して何らかの制度を設けることによって差異を解消するというものではない。
そのため、ここで「婚姻制度を利用していない者(独身者)」に対して「代替的な措置」という別の制度が存在するかどうかを勘案したり、別の制度を設けるという形で差異を解消するべき問題であるかのような前提で「代替的な措置により不利益を受けないことが合理的な区別の理由になるものかは判然としないが、」と述べていることは、基準点(スタンダード)の取り方を誤っており、憲法14条1項の「平等原則」を用いて審査することのできる部分についての論じ方としても誤っている。
「婚姻による効果は、民法のほか、各種の法令で様々なものが定められており、代替的な措置によって、同性愛者が婚姻することができない場合の不利益を解消することができるとは認め難い。」との部分について検討する。
「婚姻による効果は、民法のほか、各種の法令で様々なものが定められており、」について検討する。
「民法のほか、各種の法令で様々なものが定められて」いる「婚姻による効果」は、婚姻制度の立法目的を達成するための手段として整合的なものとして定められているものである。
そのため、それは婚姻制度の立法目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす人的結合関係に対してのみ適用し、それ以外の人的結合関係には適用しないというものである。
このように、婚姻制度の対象となる場合とならない場合があり、「民法のほか、各種の法令で様々なものが定められて」いる「効果」の適用を受ける場合と受けない場合があることは制度が政策的なものである以上は初めから予定されていることである。
その他、その「婚姻による効果」は、婚姻制度の立法目的を達成するための手段として整合的な範囲でのみ正当化することができるものであることから、もし「婚姻制度を利用している者(既婚者)」が「婚姻制度を利用していない者(独身者)」とを比較して、「婚姻制度を利用している者(既婚者)」が婚姻制度の立法目的を達成するための手段として不必要に過大な優遇措置(効果)を得ている場合には、その過大な優遇措置(効果)に関する規定が憲法14条1項の「平等原則」に違反することになり、その規定が個別に失効することによって格差が是正されるというものである。
「代替的な措置によって、同性愛者が婚姻することができない場合の不利益を解消することができるとは認め難い。」について検討する。
「代替的な措置によって、」との部分について検討する。
ここでいう「代替的な措置」とは、一文前の「契約や遺言により、ある程度までは婚姻と似たような一定の効果を受けること」をいうものである。
しかし、「代替的」という表現は、法的な視点から客観的に論じるものとはいえない。
まず、「契約や遺言」はそれ自体として単独で成立する法律行為であり、何かの「代替」といわれるような位置付けのものではない。
そのため、この「契約や遺言」を何かの「代替」であるかのような位置づけで見ていることは、特定の制度を持ち上げ、逆に「契約や遺言」を見下すという特定の価値観に基く主張を行っていることになるのであり、法制度に対して優劣を付けようとする発想に基づくものとなっている。
裁判所の立場でこのような態度を示すことは不適切である。
また、このような表現は、ある個人が特定の法制度を利用しようと考えた場合に、その個人にとってその法制度が自らの望む形で定められていないことを理由に思い通りとはならず、その法制度の利用を控えて別の手段を検討するという場合について「代替的な措置」などの言葉で表現しているものを述べているものである。
しかし、法制度そのものは政策目的を達成するための手段として定められるものであり、その法制度が自らの望む形で定められていないという事態は当然起こり得ることである。
そして、ある個人が別の手段を検討することがあるとしても、それぞれの法制度そのものには何らの優劣はないのであり、その法制度の関係を法的な視点から客観的に捉えた場合には、そこに「代替的な措置」などといわれるような関係にあるものではないのである。
これについて、裁判所は法制度の性質について客観的な視点から論じることが必要であり、このような訴訟の当事者の一方が現在の法制度をどのように受け止めているかという主観的な立ち位置から見た場合の言葉遣いをそのまま受け入れて表現していることは適切ではない。
「同性愛者が婚姻することができない場合」とある。
まず、婚姻制度は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」という目的の下に、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす「一人の男性」と「一人の女性」を選び出し、その間を「貞操義務」などの一定の形式で法的に結び付け、子供が産まれた場合にその子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によって立法目的の実現を目指すものである。
この婚姻制度は個々人がどのような思想、信条、信仰、感情を有しているかなどは一切関知しておらず、個々人の内心に対して中立的な内容となっている。
そのため、婚姻制度は「性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いをするような制度ではないし、「性愛」に基づいて制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもない。
そのことから、ここでいう「同性愛者」を称する者であるとしても、婚姻制度(男女二人一組)の要件を満たして制度を利用する意思があるのであれば、適法に「婚姻すること」が可能である。
実際、「同性愛者」を称する者が婚姻制度(男女二人一組)を利用している事実は認められ、「同性愛者」を称する者が「同性愛者」を称する者であることを理由として婚姻制度(男女二人一組)の適用を否定されているという事態は生じていない。
よって、ここで「同性愛者が婚姻することができない場合」のように、「同性愛者」を称する者が婚姻制度(男女二人一組)を利用しようとした際に、「同性愛者」を称する者であることを理由としてその利用を否定することがあるかのような前提で論じていることは誤りである。
これとは別に、もし「同性愛者」を称する者が婚姻制度(男女二人一組)の要件を満たして制度を利用する意思があるにもかかわらず、その者が「同性愛者」を称する者であることを理由として制度を適用しないことになれば、それは憲法14条1項の「平等原則」における「法適用の平等」に違反することになる。
そのため、むしろこの判決が「同性愛者」を称する者が「婚姻することができない」かのように論じていることは、「同性愛者」を称する者であることを理由として制度の利用を否定するものであることから、憲法14条1項の「平等原則」における「法適用の平等」に違反するものであるということができる。
その他、もし「同性愛者」を称する者であるとしても婚姻制度(男女二人一組)を利用することが可能であることを理解しているのであれば、ここで「同性愛者」を称する者を取り上げて「婚姻することができない」と述べていることは、「同性愛者」を称する者が婚姻制度(男女二人一組)を利用しているはずがないとか、利用してはならないとか、利用することは正当ではないという価値観を基にする主張であるということになる。
これは、「同性愛者」を称する者が婚姻制度(男女二人一組)を利用することに対して否定的な意味合いを含むものとなっており、不当な主張である。
これは、「同性愛者」を称する者に対して、「同性愛者」を称する者が婚姻制度(男女二人一組)を利用しているはずがないとか、利用してはならないとか、利用することは正当ではないなどという特定の価値観を押し付けるものということができ、憲法19条の「思想良心の自由」、憲法20条1項の「信教の自由」に違反するものである。
法制度は個々人の思想、信条、信仰、感情に対して中立的でなければならないのであり、特定の価値観に基づいて制度を利用することを求めるようなことがあってはならないし、勧めるようなこともしてはならない。
そのため、「同性愛者」などと人の内心に踏み込む形で論じていること自体が誤りである。
もう一つ、「同性愛者」を称する者も婚姻制度(男女二人一組)を利用することは可能であることから、「同性愛者」を称する者が「婚姻することができない」ことを前提として、ここでいう「代替的な措置」と称するもの(契約や遺言により、ある程度までは婚姻と似たような一定の効果を受けること)について検討していること自体も誤りである。
「婚姻することができない場合の不利益を解消することができるとは認め難い。」とある。
まず、憲法は「個人の尊厳」の原理に基づいており、自然人は「個人主義」の下に各々「自律的な個人」として生存していくことを予定している。
そのため、何らの制度も利用していない者の状態で既に完全な状態ということができ、その者の状態が基準(スタンダード)となるものである。
そのことから、何らの制度も利用していない者の状態について「不利益」と称されるものは存在しない。
当然、「婚姻制度を利用していない者(独身者)」の状態についても、「不利益」と称されるものは存在しない。
よって、「婚姻することができない場合」という「婚姻制度を利用していない者(独身者)」の状態について、「不利益」があるかのような前提で論じていることは誤りである。
また、もともと「不利益」と称されるものは存在しないことから、「不利益」が存在することを前提として、それをここでいう「代替的な措置」と称するもの(契約や遺言により、ある程度までは婚姻と似たような一定の効果を受けること)によって「解消することができる」か否かを検討するという前提にない。
よって、「不利益を解消することができる」か否かを検討していること自体が誤りであり、その検討の結果、それについて「認め難い」と評価していることも、前提となる認識に誤りがあることから、その評価を行うことができるとする前提にもなく、これを述べているところも誤りということになる。
その他、ここで「不利益」という表現を用いていることの背景について検討する。
上記で述べたように、法律論として客観的な視点から考えた場合には、「婚姻していない者(独身者)」の状態について「不利益」と称されるものは存在しない。
そのため、ある特定の形の法制度が定められていないという状態について「不利益」という言葉で表現していることは、ある者にとって法制度が自らの望む形で定められている状態を完全な状態と設定した上で、現在の法制度がその状態に至っていないという認識の下に、その完全な状態と設定したゴール(目標地点)までの距離(その間の差の部分)を「不利益」と呼ぼうとする動機が含まれていることになる。
◇ この判決の認識
自らの望む法制度(ゴール)
↑
↑ (この差異を『不利益』と表現している。)
↑
現在地点
しかし、法的な視点から見れば、憲法は「個人の尊厳」の原理に基づいており、自然人は「個人主義」の下に各々「自律的な個人」として生存していくことを予定していることから、法制度を利用していない状態で既に完全な状態ということができ、「不利益」と称されるものは存在してない。
◇ 法律論として客観的な視点
現在地点 ← (法制度がない状態で既に完全であり、『不利益』は存在しない)
そのため、ある者が「不利益」と表現している場合があるとしても、それは自らの望む形で法制度が定められている状態をゴールと考えることを前提とした上での、そのゴールと現在地点との間の距離について述べているものであり、その者個人が抱いている理想の法制度を前提とする主観的な思いを表現しているに過ぎないものである。
そのことを法的な視点から客観的に考えると、そこに「不利益」と称されるものを認めることはできないのである。
よって、裁判所の立場では法制度の性質について客観的な視点から論じることが必要とされており、このような訴訟の当事者の一方が現在の法制度をどのように受け止めているかという主観的な立ち位置から見た場合の言葉遣いをそのまま受け入れて表現していることは適切ではない。
法律論としては、このような法的な視点から考えて客観性を保つことのできない色の付いた言葉は取り除いて論じることが必要である。
(4) 以上からすれば、国会が立法裁量を有することを考慮するとしても、本件規定が、異性愛者に対しては婚姻を定めているにもかかわらず、同性愛者に対しては婚姻を許していないことは、現時点においては合理的な根拠を欠くものであって、本件規定が定める本件区別取扱いは、差別的取扱いに当たると解することができる。
【筆者】
「国会が立法裁量を有することを考慮するとしても、」との部分について検討する。
まず、「婚姻」は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」を目的として、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす「一人の男性」と「一人の女性」を選び出し、その間に「貞操義務」を設けるなど一定の形式で法的に結び付け、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によって立法目的の達成を目指す枠組みである。
そして、憲法24条は「婚姻」を定めており、「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めている。
また、憲法24条2項は「婚姻及び家族」について法律で立法することを示しており、「国会」はこの憲法24条2項の「婚姻及び家族」の枠組みの「要請」に従った形で「婚姻及び家族」の制度を立法することが求められている。
ただ、「国会」は「婚姻及び家族」である、一夫一婦制(男女二人一組)の「夫婦」と、「親子」による「血縁関係者」の人的結合関係の枠組みが維持されている中において、氏の制度や夫婦の財産についての制度、扶養の制度、親権の制度、相続の制度など、「婚姻及び家族」の枠組みに付随する個別の制度について「立法裁量を有する」といえるが、この「婚姻及び家族」の枠組みの中にこの「夫婦」と「親子」による「血縁関係者」の範囲を超える人的結合関係を含めることができるとする権限まで有していることはなく、そのことについては「立法裁量を有する」わけではない。
「同性間の人的結合関係」については、上記の「婚姻」という概念が形成される際の前提となっている「生殖と子の養育」の趣旨を満たすものではないし、憲法24条が具体的に一夫一婦制(男女二人一組)の枠組みを定めることによって目的の達成を目指す仕組みとなっていることに沿うものではないことから、「婚姻」の中に含めることはできない。
そのため、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とする法律を立法する権限は「国会」であっても有していない。
よって、「国会」が「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とする法律を立法する権限を有していることを前提として「国会が立法裁量を有する」と述べていることは誤りである。
その他、ここでは「同性間の人的結合関係」を対象とした制度を設けることについて「国会が立法裁量を有する」ことを前提として考えるものとなっている。
しかし、憲法24条の「婚姻」の文言は、「生殖と子の養育」に関わる制度を一元的に集約して規律する趣旨を有しており、この憲法24条の「婚姻」を離れて別の制度として「生殖と子の養育」に関わる制度を立法することはできない。
もし「生殖と子の養育」に関わる制度や影響を与える制度を憲法24条の「婚姻」の文言を離れて別の制度として立法した場合には、憲法24条の「婚姻」に抵触して違憲となる。
そのため、「同性間の人的結合関係」を対象とした制度を設けた場合には、それが「生殖と子の養育」に関わる制度や影響を与える制度となることが考えられ、憲法24条の「婚姻」に抵触して違憲となる。
そのことから、「同性間の人的結合関係」を対象とした制度を設けることについては、「国会」であっても「立法裁量を有する」とはいえない。
また、婚姻制度が「男女二人一組」を対象として設けられていることについては、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消する必要性の下に、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」という目的を達成するための手段として整合的な要素を満たすものであることから、そこに法的効果や一定の優遇措置を与えることは、「婚姻制度を利用していない者(独身者)」との間で生じる差異を正当化することができるといえるが、「同性間の人的結合関係」を対象とした制度については、そのような目的との関係により導き出されるものではないことから、その制度を利用していない者との間で生じる差異を正当化することができず、憲法14条1項の「平等原則」に違反することになる。
そのことから、「同性間の人的結合関係」を対象とした制度を設けることについては、「国会」であっても「立法裁量を有する」とはいえない。
よって、ここで「同性間の人的結合関係」を対象とした制度を設けることについて「国会が立法裁量を有する」ことを前提として考えていることは誤りである。
「本件規定が、異性愛者に対しては婚姻を定めているにもかかわらず、同性愛者に対しては婚姻を許していないことは、現時点においては合理的な根拠を欠くものであって、」との部分について検討する。
「本件規定が、異性愛者に対しては婚姻を定めているにもかかわらず、同性愛者に対しては婚姻を許していないことは、」とある。
ここでは「異性愛者」と「同性愛者」の文言が登場する。
これは「性愛」という個々人の内心における精神的なものについて、特定の価値観に基づいて分類し、その分類に従って人を区別することを前提とするものである。
しかし、法律論としては、人をその内心に基づいて区別して考えるようなことをしてはならないのであり、「異性愛者」や「同性愛者」などと人をその内心に基づいて区別することが可能であるかのような前提で論じていること自体が誤りである。
また、「本件規定」である婚姻制度は、「性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いをする制度ではないし、「性愛」に基づいて制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもない。
当然、「本件規定」である婚姻制度は「異性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、「異性愛者」を称する者を対象として設けられた制度でもないし、「異性愛」に基づいて制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもない。
そのため、「本件規定が、異性愛者に対しては婚姻を定めているにもかかわらず、」のように、「本件規定」である婚姻制度が「異性愛者」を対象とした制度として設けられているかのような前提で論じていることは誤りである。
また、「本件規定」である婚姻制度(男女二人一組)は、個々人がどのような内心を有しているとしても、制度の要件を満たして制度を利用する意思を有するのであれば、適法に利用を認めていることから、人をその内心に基づいて区別しているという事実はないし、ある特定の内心を有する者に対して制度の利用を否定しているということもない。
よって、「同性愛者」を称する者であっても適法に制度を利用することができるのであり、ここで「同性愛者に対しては婚姻を許していない」のように、「同性愛者」を称する者が婚姻制度を利用することができないかのように述べていることは誤りである。
それに対して、ここでは「本件規定が、異性愛者に対しては婚姻を定めている」と述べているが、これはあたかも「本件規定」である婚姻制度が「異性愛」という特定の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的としていたり、「異性愛者」を称する者を対象としていたり、「異性愛」に基づいて制度を利用することを求めたり勧めたりしている制度であるかのように論じるものとなっている。
しかし、「性愛」という特定の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的とした制度を立法した場合には、憲法20条1項後段・3項、89条の「政教分離原則」に違反することになる。
また、「性愛」という特定の思想、信条、信仰、感情を抱く者を対象とし、それ以外の思想、信条、信仰、感情を抱くものを対象としないことは、個人の内心に基づいて区別することになるから、憲法14条1項の「平等原則」に違反することになる。
他にも、制度を利用する者に対して「性愛」という特定の思想、信条、信仰、感情を有していることを求めることは、国家が個人の内心に対して干渉するものとなることから、憲法19条の「思想良心の自由」や憲法20条1項前段の「信教の自由」に違反することになる。
このため、法制度は個々人の内心に対して中立的な内容であることが求められており、法制度が「異性愛」という特定の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的としている場合には違憲となるし、法制度が「異性愛者」を称する者を対象として定められている場合も違憲となるし、法制度を利用する者の内心に対して干渉するものとなっている場合も違憲となる。
そのことから、この判決が「本件規定が、異性愛者に対しては婚姻を定めている」と述べていることは、あたかも「異性愛者」を称する者を対象とした法制度が定められているとしても許されるかのように論じるものとなっているが、そのような法制度が存在した場合には、それ自体で違憲となるものである。
そのため、そのような法制度が存在していても許されるかのような前提で論じているこの判決の内容そのものが違憲ということになる。
よって、「本件規定が、異性愛者に対しては婚姻を定めている」と述べていることは誤りである。
「同性愛者に対しては婚姻を許していないことは、」とある。
しかし、婚姻制度(男女二人一組)は、婚姻制度は「性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いをする制度ではないし、「性愛」に基づいて制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもない。
そのため、「同性愛者」を称する者でも、婚姻制度(男女二人一組)の要件に従って制度を利用する意思を有するのであれば、適法に「婚姻」することが可能である。
よって、「同性愛者に対しては婚姻を許していない」との事実はない。
これに対して、この判決は個々人の内心を審査して、その内心の一側面でしかない「性愛」の思想、信条、信仰、感情を取り上げ、それがどのような対象に向かうかという視点によってその性質を分類し、その分類に応じて人を「異性愛者」や「同性愛者」などと区別して考え、その中の「同性愛者」に当たる者について「婚姻を許していない」と述べている。
そのことから、「同性愛者に対しては婚姻を許していない」のは、むしろ、この判決の内容の方である。
婚姻制度(男女二人一組)そのものは、個々人の内心を審査して人を区別するようなことは一切していないからである。
よって、この判決の述べる「同性愛者に対しては婚姻を許していない」との説明は誤りである。
「本件規定が、異性愛者に対しては婚姻を定めているにもかかわらず、同性愛者に対しては婚姻を許していないことは、現時点においては合理的な根拠を欠くものであって、」とある。
これは、「異性愛者に対しては婚姻を定めているにもかかわらず、同性愛者に対しては婚姻を許していないこと」に「合理的な根拠」があるか否かを問うものとなっている。
しかし、「(2)」の第三段落の第二文では、もともと「本件で問われているのは、本件規定が同性婚を許していないため、異性愛者は、異性と婚姻し、戸籍による公的な公証や種々の権利義務を伴う法的地位の付与及び種々の事実上のサービスの提供等を受けることができるにもかかわらず、同性愛者は、同性と婚姻してこのような効果を享受することができないことから、このような性的指向に係る婚姻制度における取扱いの区別(以下「本件区別取扱い」という。)が、合理的理由のない差別的取扱いに当たるか否かということであり、」と述べていたのであり、文面が異なっている。
そのため、「合理的な根拠」、あるいは「合理的理由」の有無を検討しようとしている内容が異なっているように見える。
このように、この判決の文面において、判断しようとしている対象が明確に定まっていないことは妥当ではない。
また、「本件規定」である婚姻制度は、そもそも「性愛」に関わらない制度であり、個々人を「性的指向」と称するものによって区別しているという事実は存在しない。
そのため、この部分が「本件規定」である婚姻制度が、「異性愛者」と「同性愛者」のように「性愛」という内心における心理的・精神的なものに基づいて人を区別しているかのような前提で論じていることは誤りである。
「現時点においては合理的な根拠を欠くものであって、」とある。
しかし、「本件規定」である婚姻制度は、そもそも「性的指向」と称するものによって人を区別して取扱っているという事実は存在しないことから、区別が存在することを前提としてその「合理的な根拠」の有無を検討するという前提にない。
そのため、ここで区別取扱いがあることを前提として「合理的な根拠を欠くもの」と述べていることは誤りである。
「本件規定が定める本件区別取扱いは、差別的取扱いに当たると解することができる。」との部分について検討する。
「本件規定が定める本件区別取扱い」とあるが、そもそも「本件規定」である婚姻制度は、この判決のいうような「性的指向」と称するものによって「区別取扱い」をしているという事実はない。
よって、ここで「本件規定が定める本件区別取扱い」のように、「区別取扱い」が存在することを前提として論じていることは誤りである。
ここでは「区別取扱い」と「差別的取扱い」のように「区別」と「差別」の文言が登場する。
また、「本件区別取扱いは、差別的取扱いに当たる」のように、「区別」と「差別」の文言を連続させる形で示していることから、これらの文言に別々の意味を持たせる形で論じようとしているように見受けられる。
しかし、憲法14条1項の「平等原則」を審査する場面では、法的に異なる取扱いをした場合に、そこに「合理的な理由」が存在するか否かが問われているだけである。
そのため、「区別」という言葉の概念が有する意味に当てはまるか、あるいは「差別」という言葉の概念が有する意味に当てはまるかというような言葉の概念の射程が問われているわけではないため、異なる取扱いをしたことについて「区別」と呼ぼうと「差別」と呼ぼうと結論が変わるというものではない。
下記の動画でも、憲法14条1項における「平等」とは、「区別」(差別)の存否ではなく、「区別」(差別)の「合理性」の有無が論点であることが説明されている。
【動画】シンポジウム 国葬を考える【The Burning Issues vol.27】 2022/09/25
最高裁判決でも「差別」の文言を使っているが、「合理的」であれば禁じられないとしており、「区別」と同様の意味で用いられている。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
……(略)……しかし、右各法条は、国民に対し絶対的な平等を保障したものではなく、差別すべき合理的な理由なくして差別することを禁止している趣旨と解すべきであるから、事柄の性質に即応して合理的と認められる差別的取扱をすることは、なんら右各法条の否定するところではない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
よつて案ずるに、憲法一四条一項は、国民に対し法の下の平等を保障した規定であつて、同項後段列挙の事項は例示的なものであること、およびこの平等の要請は、事柄の性質に即応した合理的な根拠に基づくものでないかぎり、差別的な取扱いをすることを禁止する趣旨と解すべきことは、当裁判所大法廷判決(昭和三七年(オ)第一四七二号同三九年五月二七日・民集一八巻四号六七六頁)の示すとおりである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1 憲法14条1項は,法の下の平等を定めており,この規定が,事柄の性質に応じた合理的な根拠に基づくものでない限り,法的な差別的取扱いを禁止する趣旨のものであると解すべきことは,当裁判所の判例とするところである(最高裁昭和37年(オ)第1472号同39年5月27日大法廷判決・民集18巻4号676頁,最高裁昭和45年(あ)第1310号同48年4月4日大法廷判決・刑集27巻3号265頁等)。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
損害賠償請求事件 最高裁判所大法廷 平成27年12月16日 (PDF) (再婚禁止期間違憲訴訟)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2 憲法14条1項は,法の下の平等を定めており,この規定が,事柄の性質に応じた合理的な根拠に基づくものでない限り,法的な差別的取扱いを禁止する趣旨のものであると解すべきことは,当裁判所の判例とするところである(最高裁昭和37年(オ)第1472号同39年5月27日大法廷判決・民集18巻4号676頁,最高裁昭和45年(あ)第1310号同48年4月4日大法廷判決・刑集27巻3号265頁等)。
そこで検討すると,本件規定は,夫婦が夫又は妻の氏を称するものとしており,夫婦がいずれの氏を称するかを夫婦となろうとする者の間の協議に委ねているのであって,その文言上性別に基づく法的な差別的取扱いを定めているわけではなく,本件規定の定める夫婦同氏制それ自体に男女間の形式的な不平等が存在するわけではない。我が国において,夫婦となろうとする者の間の個々の協議の結果として夫の氏を選択する夫婦が圧倒的多数を占めることが認められるとしても,それが,本件規定の在り方自体から生じた結果であるということはできない。
したがって,本件規定は,憲法14条1項に違反するものではない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
損害賠償請求事件 最高裁判所大法廷 平成27年12月16日 (PDF)
このように、法律論上は「区別」と呼ぼうと「差別」と呼ぼうと、法的に異なる取扱いが存在した場合における「合理性」の存否が問題となっており、これらの言葉に対して異なる意味を持たせて論じることができるというものではない。
そのため、ここで憲法14条1項の「平等原則」における審査の結論として、「区別」と「差別」を連続して用い、これらの意味があたかも異なるものであるかのような前提の下で論じようとする試みは、法的な意味で使われる「区別」と「差別」の意味が同じであることを理解していないものであり、適切ではない。
結果として、この「本件区別取扱いは、差別的取扱いに当たると解することができる。」という文を法的な視点によって理解するために「区別取扱い」の文言に統一して意味を整理すると、「本件区別取扱いは、『区別取扱い』に当たると解することができる。」と述べていることになり、意味が重複するため文章として誤りである。
今「ボケて」とかでよくイジられている小泉構文ってなんですか?
小泉構文ってめっちゃ面白いwww 2022年8月21日
小泉構文の考察 2023年4月30日
【迷言製造機】小泉進次郎構文・名言41選!小泉構文一覧や名作集が面白すぎる?
このため、この部分は読者に無用な混乱を抱かせることを防ぐために省略するべきであるといえる。
その他、「区別」と「差別」の違いを強調して、「差別」という言葉に独特の意味を持たせようとする議論を見ることがある。
これは、日常用語としては「差別」の文言が「区別」の文言よりも否定的な意味合いを持つはずであるとの考えによるものと思われる。
しかし、日常用語の中でも「差別」という言葉は必ずしも否定的な意味合いで使われているわけではない。
例えば、「従来品とは差別化している」といった場合など、やや特別で肯定的な意味合いを含めて用いられることもある。
そのため、「差別」という言葉は必ず否定的な意味合いで使われているはずであるとのイメージを前提にする議論は適切であるとはいえない。
また、憲法14条1項の「平等原則」との関係では、法的に異なる取扱いをした場合に、そこに「合理性」があるか否かが焦点であり、これを「区別」と呼ぶか「差別」と呼ぶかということによってその結論が変わるということはない。
よって、法的な審査の中では「区別」と「差別」の意味は同じであり、これらを異なるものとして言葉を使い分けることはできない。
他にも、「区別」と「差別」を区別して、「差別」に当たれば何かを是正することができるはずであるとの期待感を持って論じようとしている者もいるようである。
しかし、それは不法行為に該当した場合に損害賠償を請求することができるという場合や、特定の組織の中で合意されているガイドラインの中でハラスメントに該当した場合に注意や戒告、減給、懲戒、失職するなどの場合において、その事案が生じた原因として日常用語としての「差別」の意識が関わったかどうかという問題であり、憲法14条1項の「平等原則」の中で問われる事柄とは性質の異なるものである。
また、憲法14条1項の「平等原則」の審査について問題となっているにもかかわらず、このようにして法的に審査することのできる範囲を離れて他者の心の中まで統制しようとする意味を含めて論じようとすることは、特定の宗教を信ずる者が他者に対して自己の考える「平等」の在り方を押し付けたり、「差別」の心を持ってはならないとする思想を強制するものであることから、憲法19条の「思想良心の自由」、憲法20条1項前段の「信教の自由」を侵すものとなる。
また、国家がこのような思想を国民に対して強制することになれば、憲法20条1項後段・3項、89条の「政教分離原則」にも違反することになる。
そのため、不法行為やハラスメントに関する文脈の中で使われることのある「差別」のイメージを、憲法14条1項の「平等原則」としての「区別」(差別)の問題と重ね合わせて論じようとすることは適切はない。
したがって、本件規定は、憲法14条1項に違反する。
【筆者】
まず、婚姻制度は「性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査するものではないし、「性愛」に基づいて婚姻制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもない。
そのため、「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかという「性的指向」と称するものによる区別取扱いは存在しない。
区別取扱いがないものを憲法14条1項の「平等原則」によって審査することはできないことから、結果として憲法14条1項に違反しないことになる。
よって、ここで「性的指向」と称するものによって区別取扱いがあることを前提として「憲法14条1項に違反する。」と述べていることは誤りである。
また、もし法制度が「性的指向」と称するものに基づいて区別取扱いを行っていることになれば、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して区別し、その区別に従う形で婚姻制度の利用の可否を決めていることになるが、それは個々人の内心に基づいて人を区別することになるから、憲法14条1項の「平等原則」に違反するし、国家権力が個々人の内心に対して干渉する制度ということになるから、憲法19条の「思想良心の自由」や憲法20条1項前段の「信教の自由」に違反するし、婚姻制度が「性愛」という特定の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的としていることになるから、憲法20条1項後段・3項、89条の「政教分離原則」に違反することになる。
そのため、もし「性的指向」と称するものに基づいて区別取扱いを行う法制度が存在している場合には、そのこと自体が違憲となるのであり、この部分で婚姻制度が「性的指向」と称するものに基づいて区別取扱いを行う制度であることを前提としてそれが「合理的な根拠を欠く」ものであるか否かを論じていることは、そもそも「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかという「性的指向」と称するものに基づいて区別取扱いを行う制度が存在していても許されるかのように論じている部分が誤りであるし、「性愛」という特定の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的とした制度が存在していても許されるかのように論じている部分が誤りである。
よって、むしろ、婚姻制度が「性的指向」と称するものに基づいて区別取扱いを行う制度であることを前提として「憲法14条1項に違反する。」と結論付けようとしているこの札幌高裁判決の内容こそが、憲法に違反していることになる。
その他、婚姻制度が「憲法14条1項に違反する。」と判断される場合とは、「婚姻制度を利用している者(既婚者)」と「婚姻制度を利用していない者(独身者)」を比較して、「婚姻制度を利用している者(既婚者)」が婚姻制度の立法目的を達成するための手段として不必要に過大な優遇措置を得ている場合である。
この場合、何らの制度も利用していない者が基準(スタンダード)となることから、「婚姻制度を利用していない者(独身者)」が基準(スタンダード)となって、「婚姻制度を利用している者(既婚者)」の得ている不必要に過大な優遇措置に関する規定が個別に失効することによって格差が是正されることになる。
しかし、この札幌高裁判決では「憲法14条1項」の審査においてこの視点で論じるものとなっていないため誤りである。
5 本件規定を改廃しないことが、国賠法1条1項の適用上違法である旨の主張について(争点(2)関係)
⑴ 国家賠償法1条1項は,国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が個々の国民に対して負担する職務上の法的義務に違反して当該国民に損害を加えたときに,国又は公共団体がこれを賠償する責任を負うことを規定するものであるところ,国会議員の立法行為又は立法不作為が同項の適用上違法となるかどうかは,国会議員の立法過程における行動が個々の国民に対して負う職務上の法的義務に違反したかどうかの問題であり,立法の内容の違憲性の問題とは区別されるべきものである。そして,上記行動についての評価は原則として国民の政治的判断に委ねられるべき事柄であって,仮に当該立法の内容が憲法の規定に違反するものであるとしても,そのゆえに国会議員の立法行為又は立法不作為が直ちに同項の適用上違法の評価を受けるものではない。
もっとも,法律の規定が憲法上保障され又は保護されている権利・利益を合理的な理由なく制約するものとして憲法の規定に違反するものであることが明白であるにもかかわらず,国会が正当な理由なく長期にわたってその改廃等の立法措置を怠る場合などにおいては,国会議員の立法過程における行動が上記職務上の法的義務に違反したものとして,例外的に,その立法不作為は,国家賠償法1条1項の規定の適用上違法の評価を受けることがあるというべきである。(最高裁昭和53年(オ)第1240号同60年11月21日第一小法廷判決・民集39巻7号1512頁,最高裁平成13年(行ツ)第82号,第83号,同年(行ヒ)第76号,第77号同17年9月14日大法廷判決・民集59巻7号2087頁参照)
⑵ そこで,本件規定を改廃しないことが,国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるかについて検討する。
本件規定は,昭和22年民法改正当時における同性愛を精神疾患とする知見(認定事実⑵,⑷)を前提とすれば,そのような同性愛者のカップルに対する法的保護を特に設けなかったとしても,合理性がないとすることはできない。
この点につき,そのような知見は,昭和55年頃には米国において否定され,平成4年頃には世界保健機関によっても否定されたものであり,その頃には,我が国においても,同性愛を精神疾患とする知見は否定されたものと認めることができる(認定事実⑹ア,イ)。
しかしながら,科学的・医学的には同性愛を精神疾患とする知見は否定されたものの,諸外国において登録パートナーシップ制度又は同性婚制度を導入する国が広がりをみせ始めたのは,オランダが2000年(平成12年)に同性婚の制度を導入して以降といえ(認定事実⑺ア),我が国における地方公共団体によるパートナーシップ認定制度の広がりはさらに遅く,東京都渋谷区が平成27年10月に導入して以降といえる(認定事実⑻ア)。
また,近時の調査によっても,20代や30代など若年層においては,同性婚又は同性愛者のカップルに対する法的保護に肯定的な意見が多数を占めるものの,60歳以上の比較的高い年齢層においては否定的な意見が多数を占めており(認定事実⑽ア,エ),国民意識の多数が同性婚又は同性愛者のカップルに対する法的保護に肯定的になったのは,比較的近時のことと推認することができる。
さらに,同性愛者のカップルに対し,婚姻によって生じる法的効果を付与する法的手段は,多種多様に考えられるところであり,一義的に制度内容が明確であるとはいい難く,どのような制度を採用するかは,前記3⑴のとおり,国会に与えられた合理的な立法裁量に委ねられている。(……削る……)
加えて,前記3⑶キで説示したとおり,同性婚や同性愛者のカップルに対する法的保護に否定的な意見や価値観を有する国民は少なからず存在するところである。
これらのことに加え,昭和22年民法改正以後,現在に至るまで,同性婚に関する制度がないことの合憲性についての司法判断が示されたことがなかったことにも照らせば,本件規定が憲法24条及び14条1項に違反することについて,国会において直ちに認識することは容易ではなかったといわざるを得ない。
そうすると,本件規定は,憲法24条及び14条1項に違反するものとなっていたといえるものの,これを国家賠償法1条1項の適用の観点からみた場合には,憲法上保障され又は保護されている権利利益を合理的な理由なく制約するものとして憲法の規定に違反することが明白であるにもかかわらず,国会が正当な理由なく長期にわたって改廃等の立法措置を怠っていたと評価することはできない。
したがって,本件規定を改廃していないことが,国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではないというべきである。
(3) 控訴人らは、第2の3(3)のとおり主張する。
確かに、我が国の同性愛者は最も少ない統計で見積もっても数百万人は存在することが窺われるのであり(認定事実(1)イ)、本件規定が同性婚を許さずに憲法に違反していることにより、国民の重要な利益に対する重大な侵害が生じているものであると認めることができる。また、諸外国の動向のみならず(認定事実(7)ア、イ)、我が国の動向(認定事実(8)ア~オ)、とりわけ、国会においても平成12年5月以降、折に触れて同性婚の法制化に関する発言等がされてきた。
【筆者】
「確かに、我が国の同性愛者は最も少ない統計で見積もっても数百万人は存在することが窺われるのであり(…)、本件規定が同性婚を許さずに憲法に違反していることにより、国民の重要な利益に対する重大な侵害が生じているものであると認めることができる。」(カッコ内省略)との記載がある。
「我が国の同性愛者は最も少ない統計で見積もっても数百万人は存在することが窺われるのであり」との部分について検討する。
まず、「同性愛者」との部分であるが、法制度は個人の内心に対して中立的な内容でなければならないことから、「同性愛者」とそれ以外の者など個々人の内心を取り上げて人を区別して考えるようなことをしてはならない。
そのため、「同性愛者」のように、個々人の内心に着目する形で人を区別して論じていること自体が誤りである。
また、婚姻制度は「性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いをする制度ではないし、「性愛」に基づいて制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもない。
そのため、ここで「同性愛者」を称する者を取り上げたとしても、そのことと婚姻制度との間には何らの関係性も認められないのであり、これを取り上げる形で論じようとしていること自体が誤りである。
次に、「最も少ない統計で見積もっても数百万人は存在することが窺われる」との部分であるが、そもそも「同性愛者」とは、個人の内心における心理的・精神的な事柄に着目して区別しようとしている性質上、どこからどこまでの範囲を「同性愛者」と考えるべきであるかについて明確な定義は存在しないものである。
そのため、ここでいう「統計」についても、ある者が「同性愛者」と称したならば「同性愛者」なのだろうと考えるという程度のアンケート調査を基にするなどして推定されているに過ぎず、明確性のないものである。
ここでも「見積もって」や「存在することが窺われる」としているとおり、あくまで推測であり、はっきりとした数字を示すことができていないことはそのような事情によるものである。
当然、このような客観性を保つことのできない「統計」と称するものを基にして法律論を組み立てることはできない。
また、このような「統計」と称するものを根拠として法律論上の規範となる枠組みが左右されることはないし、それによって結論が変わるようなこともあってはならない。
「本件規定が同性婚を許さずに憲法に違反していることにより、国民の重要な利益に対する重大な侵害が生じているものであると認めることができる。」との部分について検討する。
「本件規定が同性婚を許さずに憲法に違反していることにより、」とある。
ここでいう「同性婚」の意味が、「同性間の人的結合関係」を形成することを指しているのであれば、それは憲法21条1項の「結社の自由」で保障されているものである。
「本件規定」はそれを規制するものではないことから、それについて「許さず」と説明していることは誤りである。
また、「本件規定が」「同性間の人的結合関係」を形成することをを「許」していないという事実はないことから、憲法21条1項の「結社の自由」を侵害するという事実もなく、「憲法に違反している」ことにもならない。
よって、「憲法に違反していることにより、」と述べていることは誤りとなる。
ここでいう「同性婚」の意味が「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを指しているのであれば、「本件規定」は「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを定めていないといえる。
ただ、これは法制度が定められているか否かの問題であるから、むやみに「許す・許さない」という意味での「許さず」という表現を用いることは適切であるとはいえない。
このような表現は、法制度の性質について客観的な視点から説明するものとして用いられる言葉遣いとはなっておらず、他の部分の「不利益」という言葉とも相まって、訴訟の当事者の一方の見方や意見、感じ方に与する形で論じるものとなっていることが考えられる。
そのため、敢えてこのような表現を用いて論じていることは、公的な性質を持つ裁判所の立場で用いる言葉の選択として相応しいものではない。
また、憲法は24条で「婚姻」について定め、その具体的な内容について「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めている。
この憲法24条の「要請」に従って「本件規定」が定められており、「本件規定」の内容も一夫一婦制(男女二人一組)となっていることから、その「本件規定」が憲法24条に違反するということにはならない。
他にも、憲法14条1項の「平等原則」との関係についても、憲法の規定の内容が他の憲法上の規定との間で矛盾することはないことから、憲法24条で定められている事柄が憲法14条1項に違反するということにはならず、憲法14条1項にも違反するということにはならない。
そのため、ここで「本件規定が」「同性間の人的結合関係」を「婚姻」として定めていないことについて「憲法に違反している」ことを前提として、「本件規定が同性婚を許さずに憲法に違反していることにより、」と述べている部分は誤りである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
前記アのとおり、憲法24条1項が、婚姻について異性間の人的結合関係のみを対象としており、同性間の人的結合関係を対象とすることを想定していないことが明らかであることからすると、原判決(39ページ)が正当に判示するとおり、憲法24条にいう「婚姻」とは、異性間の婚姻を指し、同性間の婚姻を含まないものと解するのが相当である。
また、前記イのとおり、憲法24条2項は、同条1項と同様に、飽くまで婚姻が異性間の人的結合関係を対象とするものであることを前提として、これを具体化する制度の整備を立法府に要請するものであり、同性間の人的結合関係をも対象として婚姻を認める立法措置を執ることを立法府に要請しているものではない。
したがって、憲法24条1項及び2項は、国会(議員)に対し、同性間の婚姻を認める法制度を創設することまで要請しているものではないから、異性婚を前提とし、同性婚を前提としていない本件諸規定は憲法24条1項及び2項に違反するものではなく、憲法24条1項及び2項違反を根拠に、国会(議員)が現行の法律婚制度を法律上同性のカップル(ないしその子)が利用できるように本件諸規定を改正すべき立法義務を負うとはいえない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【東京一次・第3回】被控訴人第2準備書面 令和6年2月29日 PDF
「国民の重要な利益に対する重大な侵害が生じているものであると認めることができる。」とある。
上記で説明したように、「本件規定が」「憲法に違反している」との認識は誤りであり、その「憲法に違反している」との認識を基にして「国民の重要な利益に対する重大な侵害が生じている」と考えていることは誤りである。
よって、「国民の重要な利益に対する重大な侵害が生じているものであると認めることができる。」との認識は誤りであり、そのように認めることはできない。
「諸外国の動向のみならず(…)、我が国の動向(…)、とりわけ、国会においても平成12年5月以降、折に触れて同性婚の法制化に関する発言等がされてきた。」(カッコ内省略)との記載がある。
━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━
「諸外国の動向のみならず(…)、我が国の動向(…)」との部分は、「諸外国の動向」と「我が国の動向」を対比する形で述べようとしているように見受けられる。
しかし、この文章は、それらの「動向」について述べている部分が、この文の後半部分と関係するものとなっておらず、意味が成り立っていない。
「我が国の動向」の部分については、その後の「国会」における「発言等」を指す部分に係るのかもしれないが、「我が国の動向(…)、とりわけ、国会においても平成12年5月以降、折に触れて同性婚の法制化に関する発言等がされてきた。」という文の流れは、「我が国の動向」の部分がその後の文の内容をまとめたタイトルとして切り離されて存在するわけではなく、一文の中で連続するものとして繋がった形で記載されているのであるから、「我が国の動向」とその後の文との間の関係性を接続するための言葉が加えられていないことは不自然であり、意味を成り立たせるために必要となる言葉が抜け落ちていることから適切ではない。
「諸外国の動向」の部分については、そもそもその後の「国会」における「発言等」を指す部分とも対応していない。
こうなると、この文章の内容は、下記のように二つに分割していると考えるべきものということになる。
◇ 「諸外国の動向のみならず(…)、」
◇ 「我が国の動向(…)、とりわけ、国会においても平成12年5月以降、折に触れて同性婚の法制化に関する発言等がされてきた。」
しかし、このように分割すると、「のみならず」の言い回しや、「とりわけ、」の言葉遣いは、文章の構成を示すものとして不適切なものとなる。
また、このように二つに分割してそれぞれを対比して並列に並べているだけの文ということになると、この文の前の文との流れから見ても不自然であるし、これを前提として次の段落の文へと続くことも不自然である。
これらのことから、この文は、どのような読み方を検討しても妥当な文章として成り立っていないといえる。
━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━
「諸外国の動向」であるが、「諸外国」の法制度はそれぞれの国の社会事情の中で生じる課題を解決するために立法された制度であり、「我が国」の法制度とは異なるものである。
そのため、「諸外国」で特定の法制度が存在するとしても、その法制度を「我が国」の中に取り入れなければならないということにはならないし、その「諸外国」の法制度を理由として日本法の解釈が変わるということもない。
よって、「諸外国の動向」を理由として日本法の解釈における結論が左右されることを前提として論じていることは誤りである。
「我が国の動向」として「国会」において「同性婚の法制化に関する発言等」があったことを述べている部分であるが、「国会」では日々様々な議論がされているのであり、そこで政治的な議論として何らかの「発言等」があったとしても、それによって法解釈における結論が左右されるというものではない。
そのため、このような事柄を原因として法解釈としての結論が導き出される余地があるかのように述べていること自体が誤りである。
しかし、これらの認定事実を前提としてもなお、同性婚立法の在り方には多種多様な方法が考えられ、設けるべき制度内容が一義的に明確であるとはいい難いこと、同性婚に対する法的保護に否定的な意見や価値観を有する国民も存在し、議論の過程を経る必要があること等から、国会が正当な理由なく長期にわたって本件規定の改廃等の立法措置を怠っていたと評価することはできない。
【筆者】
「同性婚立法の在り方には多種多様な方法が考えられ、設けるべき制度内容が一義的に明確であるとはいい難いこと」との部分について検討する。
「同性婚」とあるが、ここでいう「婚」の意味である「婚姻」とは何かが問題となる。
「婚姻」とは、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた枠組みである。
具体的には、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」を目的として、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす「一人の男性」と「一人の女性」を選び出し、その間に「貞操義務」を設けるなど一定の形式で法的に結び付け、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によってそれらの目的の達成を目指すものである。
これに対して「同性」間の人的結合関係については、その間で「生殖」を想定することができず、この「生殖と子の養育」の趣旨を満たすものではないことから、「婚姻」の中に含めることはできない。
よって、ここでは「同性婚」のように、「同性」間の人的結合関係を「婚姻」とすることができるかのような言葉を用いているが、法律論としては「同性」間の人的結合関係を「婚姻」として構成することはできないということになる。
その他、憲法24条の「婚姻」の文言は「生殖と子の養育」に関わる制度を一元的に集約して規律する趣旨を有していることから、憲法24条の「婚姻」を離れて別の制度として「生殖と子の養育」に関わる制度を立法することはできない。
ここでいう「同性」間の人的結合関係についての制度を立法しようとした場合には、「生殖と子の養育」に関わる制度や影響を与える制度となることが考えられ、憲法24条の「婚姻」に抵触して違憲となる。
また、婚姻制度(男女二人一組)については、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成するための手段として形成されている枠組みであることから、そこに法的効果や一定の優遇措置を設けるとしても、それは「婚姻制度を利用していない者(独身者)」との間で生じる差異を正当化することができるが、「同性」間の人的結合関係を対象とした制度については、そのような目的により設けられているものではないことから、その制度を利用しない者との間で生じる差異を正当化することができず、憲法14条1項の「平等原則」に違反することになる。
よって、ここでは「同性」間の人的結合関係を対象とした制度について、「立法の在り方には多種多様な方法が考えられ、設けるべき制度内容が一義的に明確であるとはいい難いこと」と述べているが、そもそも上記のような「同性」間の人的結合関係を対象とした制度は憲法に違反するものとなることから、これを立法することができるということにはならない。
「同性婚に対する法的保護に否定的な意見や価値観を有する国民も存在し、議論の過程を経る必要があること等」との部分について検討する。
ここでいう「同性婚」の意味が「同性間の人的結合関係」を指す場合には、「同性間の人的結合関係」に対する「法的保護」について述べていることになる。
ただ、これは憲法21条1項の「結社の自由」によって保障されており、これが「法的保護」であるといえるものである。
たとえ「同性間の人的結合関係」を形成することに対して「否定的な意見や価値観を有する国民」が存在するとしても、「公共の福祉」に反しない限りは法的に制約されることはない。
ここでいう「同性婚」の意味が「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とする制度について述べているのであれば、ある法制度に対して「法的保護」という新たな保護を設けることを述べていることになり、法的な意味の論理構造として誤りである。
その他、そもそも「婚姻」は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」を目的として、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす「一人の男性」と「一人の女性」の組み合わせに「貞操義務」を設けるなど一定の形式で法的に結び付け、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によってそれらの立法目的の達成を目指す制度である。
「同性間の人的結合関係」については、その間で「生殖」を想定することができず、上記の趣旨を満たすものではないことから、「婚姻」の中に含めることができない。
よって、「同性間の人的結合関係」を法的な意味で「婚姻」として構成することができることを前提として「同性婚」という言葉を使っていることは誤りとなる。
「否定的な意見や価値観を有する国民も存在し、議論の過程を経る必要がある」との部分についても、そもそも「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることはできず、その結論が「否定的な意見や価値観を有する国民」の存否やその数の割合によって左右されるということはなく、国民の間での「議論の過程を経る必要がある」のように「議論」することによって変わるということもない。
よって、「否定的な意見や価値観を有する国民も存在し、議論の過程を経る必要がある」との部分についても、その前提を欠くものであり、誤りである。
「これらの認定事実を前提としてもなお、」「国会が正当な理由なく長期にわたって本件規定の改廃等の立法措置を怠っていたと評価することはできない。」との部分について検討する。
まず、「これらの認定事実」の部分であるが、それらは「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることができるとする根拠となるものではない。
そのため、「これらの認定事実」を根拠として「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることができることを前提として論じていることは誤りである。
また、憲法24条は「婚姻」を規定し、具体的に「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)の枠組みを定めており、この枠組みの「要請」に従って法律上において具体化される婚姻制度として「本件規定」が一夫一婦制(男女二人一組)を定めていることから、そのことが憲法24条に違反するということにはならない。
他にも、憲法上の規定が他の憲法上の規定との間で矛盾することはないことから、憲法24条で定められている事柄が憲法14条1項に違反するということにはならず、憲法24条の「要請」に従う形で立法されている「本件規定」の枠組みが、憲法14条1項に違反するということにはならない。
そのため、「本件規定」が憲法に違反するということはなく、「国会」は「本件規定の改廃等の立法措置」を行う義務を負っているとはいえない。
これにより、そもそも「国会が正当な理由なく長期にわたって本件規定の改廃等の立法措置を怠っていた」か否かを検討するという前提を欠いている。
よって、ここで「国会が正当な理由なく長期にわたって本件規定の改廃等の立法措置を怠っていたと評価することはできない。」のように、これを検討して「評価」できるか否かを論じていること自体が誤りである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 被控訴人原審第 1準備書面第3の1(2)(18及び19ページ)、同第3準備書面第4(22及び23ページ)及び同第 6準備書面第4(51及び52ページ)において述べたとおり、立法不作為が国賠法1条1項の適用上違法と評価される場合とは、法律の規定が憲法上保障され又は保護されている権利利益を合理的な理由なく制約するものとして憲法の規定に違反するものであることが明白であるにもかかわらず、国会が正当な理由なく長期にわたってその改廃等の立法措置を怠る場合などの例外的な場合に限られる(再婚禁止期間違憲判決参照)。
しかし、前記第 3で述べたとおり、そもそも本件諸規定は憲法24条1項及び2項並びに14条1項に違反しておらず、これらの憲法の規定に違反するものであることが明白であるとは到底いえないのであるから、国会が正当な理由なく長期にわたって立法措置を怠ったといえるかなどについて検討するまでもなく、控訴人らの主張は理由がないものである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【東京一次・第3回】被控訴人第2準備書面 令和6年2月29日 PDF
したがって、控訴人らの主張は採用することができない。
(4) 上記認定に付言する。
同性間の婚姻を許さない本件規定については、国会の議論や司法手続において、憲法の規定に違反することが明白になっていたとはいえないし、制度の設計についても議論が必要であると思われる。対象が少数者であって、容易に多数意見を形成できないという事情もあったのではないかと思われる。しかし、他方、そのような事情によっても、国会や司法手続を含めて様々な場面で議論が続けられ、違憲性を指摘する意見があり、国民の多くも同性婚を容認しているところであり、このような社会の変化を受け止めることもまた重要である。何より、同性間の婚姻を定めることは、国民に意見や評価の統一を求めることを意味しない。根源的には個人の尊厳に関わる事柄であり、個人を尊重するということであって、同性愛者は、日々の社会生活において不利益を受け、自身の存在の喪失感に直面しているのだから、その対策を急いで講じる必要がある。したがって、喫緊の課題として、同性婚につき異性婚と同じ婚姻制度を適用することを含め、早急に真塾な議論と対応をすることが望まれるのではないかと思われる。
【筆者】
「同性間の婚姻を許さない本件規定については、国会の議論や司法手続において、憲法の規定に違反することが明白になっていたとはいえないし、制度の設計についても議論が必要であると思われる。」との記載がある。
「同性間の婚姻を許さない本件規定については、」との部分について検討する。
ここでいう「同性間の婚姻」の意味が「同性間の人的結合関係」を形成することを指す場合には、それは憲法21条1項の「結社の自由」で保障されており、「本件規定」も人的結合関係を形成することを妨げるものではないことから、これを「許さない本件規定」と述べていることは誤りである。
ここでいう「同性間の婚姻」の意味が「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを指す場合には、「本件規定」は「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを定めていないといえる。
ただ、これは法制度が定められているか否かの問題であるから、むやみに「許す・許さない」という意味での「許さない」という表現を用いることは適切であるとはいえない。
このような表現は、法制度の性質について客観的な視点から説明するものとして用いられる言葉遣いとはなっておらず、他の部分の「不利益」という言葉とも相まって、訴訟の当事者の一方の見方や意見、感じ方に与する形で論じるものとなっていることが考えられる。
そのため、敢えてこのような表現を用いて論じていることは、客観性や中立性に欠ける表現であり、公的な性格を有する裁判所の立場で用いる言葉の選択として相応しいものではない。
「本件規定については、国会の議論や司法手続において、憲法の規定に違反することが明白になっていたとはいえないし、」との部分について検討する。
「本件規定」は、憲法24条が「婚姻」を定め、具体的に「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)の枠組みを定めていることの「要請」に従って、法律上において具体化された婚姻制度として一夫一婦制(男女二人一組)を定めているものであることから、そのことが憲法24条に違反するということはない。
また、憲法上の条文の内容が同じ憲法上の他の条文との間で矛盾するということはないため、憲法24条で定められている事柄が憲法14条1項に違反するということにはならず、憲法14条に違反するということもない。
そのため、「本件規定」は「憲法の規定に違反する」ものではない。
そのことから、ここでは「本件規定」が「憲法の規定に違反する」ことを前提として、「憲法の規定に違反することが明白になっていた」といえるか否かを検討する文脈として、「憲法の規定に違反することが明白になっていたとはいえない」と述べているのであるが、そもそも「憲法の規定に違反する」とはいえないという点で誤っている。
ここでは「国会の議論や司法手続において、」との部分についても、そもそも「憲法の規定に違反する」とはいえない「本件規定」が、「憲法の規定に違反することが明白にな」るということはあり得ず、「憲法の規定に違反することが」「国会の議論や司法手続において、」「明白にな」ることは起きないといえるものである。
「制度の設計についても議論が必要であると思われる。」との部分について検討する。
上記で説明したように、「本件規定」は「憲法の規定」に違反するものではない。
また、憲法24条は「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とする法律を立法することを「要請」するものではないため、法律上の婚姻制度が「同性間の人的結合関係」を対象として定められていないことが憲法24条に違反するということもない。
そのため、国会は制度の創設を義務付けけられていないのであり、「制度の設計についても議論」を行わなければならないという立場にあるわけではない。
よって、ここで「憲法の規定」に違反することを前提として「制度の設計についても議論が必要である」か否かを勘案するものとなっているが、そもそも「憲法の規定」に違反することはなく、「議論」の要否を論じる必要のないものである。
「対象が少数者であって、容易に多数意見を形成できないという事情もあったのではないかと思われる。」との記載がある。
前後の文脈から考えても、この文章の内容は唐突なものとなっており、意味をよく理解することができない。
また、憲法に違反するか否かは条文の意味を読み解くことによって明らかになるのであり、国民の中で「少数者」であるか「多数意見」であるかによって左右されるものではないことから、憲法を解釈する場面でこのような説明をしていることも妥当でない。
もし憲法の解釈ではなく、憲法の枠内で行われる特定の政策に対して、ここでいう「少数者」と「多数意見」の双方がある中で、「少数者」の側の意見を採用するべきであると述べているのであれば、議会制民主主義を否定することを述べていることを意味するであり、司法権の行使として正当化することはできない。
一方の意見に感情移入する形で論じていることは、司法の中立性を損なうものといえる。
「しかし、他方、そのような事情によっても、国会や司法手続を含めて様々な場面で議論が続けられ、違憲性を指摘する意見があり、国民の多くも同性婚を容認しているところであり、このような社会の変化を受け止めることもまた重要である。」との記載がある。
「国会や司法手続を含めて様々な場面で議論が続けられ、違憲性を指摘する意見があり、」との部分について検討する。
「国会」において政治家が様々な政策について「議論」し、その中で「違憲性を指摘する意見」があるとしても、それが実際に「違憲」であるかどうかは別の問題であるし、そのような「指摘」の存否によって「違憲」となるか否かが変わるというものではない。
「司法手続」とは具体的にどのような「手続」を指しているのか明らかではないが、「司法」に関わる中で何らかの「議論」があり、「違憲性を指摘する意見」があるとしても、それも実際に「違憲」であるかどうかは確定判決が出るまでは定まるものではない。
そのため、様々な議論があるとしても、その議論の過程で生じた特定の「意見」が、後に必ず正当性を持つということになるわけではないのであり、議論の過程で生じた特定の「意見」の一つを根拠として法解釈を論じようとしていることは誤りである。
法解釈として述べているのではなく、特定の政策を実施するように国会に対して指摘しようとするもの(それがたとえ結論を指定せずに何らかの議論をしなければならないとか、するべきであるとの指摘であるとしても)であるとすれば、それは「立法権」「行政権」「司法権」の三権の中において司法権しか有していない裁判所の権限の範囲を超えるものであり、司法権の逸脱・濫用として違法である。
「国民の多くも同性婚を容認しているところであり、」との部分について検討する。
「国民の多くも同性婚を容認している」とあるが、これは国家機関が公式な手続きで国民に対してアンケートを実施するなどして統計を採ったことを根拠としているわけではなく、民間の団体が独自の調査方法で実施したことを根拠とするものと考えられる。
そのため、これをもって司法判断の中で「国民の多くも同性婚を容認しているところであり、」のように、「国民の多く」が「同性婚を容認している」との前提で論じることができるかのように考えていることは誤りである。
また、国民が「同性婚」という言葉に対してイメージしている内容は、「同性間の人的結合関係」を形成して同居することを指している場合も考えられるし、法律論として「同性間の人的結合関係」を「婚姻」として構成することが可能であるかという論点も含めて、明確なイメージをもって回答しているとは限らないといえる。
そのため、法律論を論じなければならない司法判断の中で、このような曖昧さを含む統計を前提としていることも妥当ではない。
他にも、国民の賛否の数によって司法判断は左右されないのであり、これを論拠として取り上げていることそのものが誤りである。
「このような社会の変化を受け止めることもまた重要である。」との部分について検討する。
まず、憲法の枠内で、「社会の変化を受け止める」という形で特定の政策を実施するか否かを判断することは、政治部門である国会や内閣以下の行政機関の役割である。
司法府である裁判所は、合憲・違憲、あるいは合法、違法の問題しか判断することができず、これは条文に反するか否かを判断することによって結論が導き出される問題であることから、「社会の変化を受け止める」という形で結論が左右されるというものではない。
そのため、司法権の行使の過程において、「社会の変化を受け止める」という形で何らかの結論を導き出そうとしていることは誤りである。
また、国家の作用のうち「立法権」「行政権」「司法権」の三権の中で司法権しか有していない裁判所の立場では、法令に違反するか否かという問題を超えて、立法府である国会や行政府である内閣以下の行政機関の実施する政策の当否について論じることはしてはならない。
そのため、国会や内閣以下の行政機関に対して「社会の変化を受け止める」べきであるとか、「社会の変化を受け止める」とすればこのような結論となるはずであるとか、このような政策を実施することが望ましいなどという形で意見を述べることは、憲法76条1項の司法権の範囲を逸脱するものとして違憲となるし、憲法41条の立法権や憲法65条の行政権を侵害するものとして違憲となる。
よって、ここで「このような社会の変化を受け止めることもまた重要である。」と述べていることそのものが誤りである。
「何より、同性間の婚姻を定めることは、国民に意見や評価の統一を求めることを意味しない。」との記載がある。
ここでいう「同性間の婚姻」の意味が「同性間の人的結合関係」を形成することを指すのであれば、それは憲法21条1項の「結社の自由」で保障されているものである。
そのため、そのような「同性間の人的結合関係」を形成することについては、刑法などの法令で規制されているものでない限りは自由である。
これについては、「国民に意見や評価の統一を求めることを意味しない。」といえる。
ここでいう「同性間の婚姻」の意味が、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを指すのであれば、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることができるかという部分から検討する必要がある。
「婚姻」は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「生殖と子の養育」の観点から、他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた枠組みである。
具体的には、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」を目的として、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす「一人の男性」と「一人の女性」を選び出し、その間に「貞操義務」を設けるなど一定の形式で法的に結び付け、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によってそれらの目的の達成を目指すものである。
憲法24条はこの「婚姻」について規定し、具体的に「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)の枠組みを定めており、この趣旨と対応するものとなっている。
「同性間の人的結合関係」については、上記の「生殖と子の養育」の趣旨を満たすものではなく、憲法24条の文言の趣旨にも沿うものではないため、「婚姻」という概念の中に含めることはできない。
そのため、ここで「同性間の婚姻」のように、「同性間」の人的結合関係を「婚姻」とすることができるかのように述べていることは誤りとなる。
「同性間の婚姻を定めることは、」と述べていることについても、「同性間」の人的結合関係を「婚姻」として立法することはできないという点で誤りである。
「国民に意見や評価の統一を求めることを意味しない。」とあるが、そもそも「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とする法律が存在しないことについては、憲法に違反することはないことから、国会に対して制度を設けることは義務付けられておらず、制度が設けられることを前提としてその制度に対して「国民に意見や評価の統一を求めることを意味」するか否かを検討する前提にないものである。
そのため、「国民に意見や評価の統一を求めることを意味」するか否かを検討するものとして、「国民に意見や評価の統一を求めることを意味しない。」と述べていること自体が誤りである。
これが法解釈として述べているのではなく、特定の政策を実施するように国会に対して指摘しようとするものであるとすれば、それは「立法権」「行政権」「司法権」の三権の中において司法権しか有していない裁判所の権限の範囲を超えるものであり、司法権の逸脱・濫用として違法である。
「根源的には個人の尊厳に関わる事柄であり、個人を尊重するということであって、同性愛者は、日々の社会生活において不利益を受け、自身の存在の喪失感に直面しているのだから、その対策を急いで講じる必要がある。」との記載がある。
「根源的には個人の尊厳に関わる事柄であり、個人を尊重するということであって、」との部分について検討する。
まず、憲法は憲法は「個人の尊厳」の原理に基づいており、自然人は「個人主義」の下に「自律的な個人」として生存していくことを予定している。
そのため、何らの制度も利用していない状態で既に完全な状態ということができ、当然、何らの制度も利用していない者の状態で「個人の尊厳」を有しており、「個人」として「尊重」されているということができる。
そのことから、ここでいう「同性間の婚姻」と称する制度が存在しない場合には「個人の尊厳」を有しておらず「個人」として「尊重」されていないが、その「同性間の婚姻」と称する制度を設けることによって初めて「個人の尊厳」を有することになって「個人」として「尊重」されるという性質のものではない。
よって、「個人の尊厳」や「個人を尊重する」ことを持ち出して、ここでいう「同性間の婚姻」と称する制度を創設することが国会に対して義務付けられるとの考えの下に論じていることは誤りである。
「個人の尊厳」の文言について、憲法24条2項に記された「個人の尊厳」を持ち出しているつもりの場合について検討する。
まず、憲法24条2項は、憲法24条2項の「婚姻及び家族」の枠組みの「要請」に従って立法される法律上の具体的な制度としての「婚姻及び家族」の制度について、「個人の尊厳」を満たすよう求めるものである。
そのため、憲法24条2項は「婚姻及び家族」の枠組みに当てはまる対象について「個人の尊厳」を満たすことを求めるものといえるが、そもそも「婚姻及び家族」の枠組みに当てはまらない場合については「個人の尊厳」を満たすことを求めるものではない。
まして、この憲法24条2項の「個人の尊厳」の文言を根拠として、その「個人の尊厳」の文言を適用する対象の範囲を定めている「婚姻及び家族」の枠組みそのものをも変更することまで可能となるということはない。
これは、憲法24条2項の条文は、憲法24条2項の示す「婚姻及び家族」の枠組みが存在することを前提として、その枠組みを対象として「個人の尊厳」が適用されることについて定めるものであって、「個人の尊厳」の文言が「婚姻及び家族」の枠組みそのものを形成するという関係にあるわけではないからである。
これについて、下記で詳しく述べる。
「婚姻及び家族」とは、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、血縁関係を明確にする機能によって立法目的の達成を目指す枠組みである。
これは、一定の枠を設けて他の様々な人的結合関係との間で区別することにより、その目的の達成を目指す仕組みとして設けられているものである。
そのため、当然、このような一定の枠が存在することを前提として「婚姻」や「家族」という概念が形成されていることを意味しており、この枠組みがその機能を果たすことが求められている。
そのことから、もしその枠組みを形成している境界線を取り払った場合には、そもそもその枠組みそのものが立法目的を達成するための手段として機能しないものに変わってしまうこととなり、その枠組みが有している立法目的を達成しようとする機能が損なわれ、その枠組みが制度として成り立たなくなる。
よって、このような枠組みそのものを失わせることはできない。
そのことから、この「婚姻及び家族」の枠組みの対象となる人的結合関係の範囲は、「婚姻及び家族」の枠組みが有している立法目的との関係で内在的な限界があり、その立法目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす場合に限られる。
そして、憲法24条では「婚姻及び家族」と定めて他の様々な人的結合関係やそれ以外の概念との間で区別する形でその枠を指定しており、その対象となる範囲を具体的に特定するものとなっている。
そのため、憲法24条2項の規定の内容も、「婚姻及び家族」と呼ぶことのできる一定の目的を達成するための手段となっている枠が存在することを前提としており、その枠が保たれた中で形成される、その枠に付随する形で定められる個別の効果を定めた細目的な内容の規定について、「個人の尊厳」を満たすように求めるものであるといえる。
このことから、「婚姻及び家族」と呼ぶことのできる枠組みが存在することを前提として、その枠組みに対して適用される「個人の尊厳」の文言を用いて、その「個人の尊厳」が適用される範囲を指定している「婚姻及び家族」の枠組みそのものを変更することができるということにはならない。
それは、法が一定の枠組みを定めて範囲を指定し、その中でのみ適用されることが予定されている事柄を用いて、それを適用する範囲そのものを変えることができることになれば、いわば下位の規範によって上位の規範の意味を書き換えて変更しようとする試み(下剋上解釈論)と同様に、条文に記された論理的な構造そのものを損なわせることになるからである。
そのため、憲法24条2項に記されている「個人の尊厳」の文言は、その「婚姻及び家族」という枠組み自体が有している目的とその目的を達成するための手段として整合的な要素によって形成される枠組みそのものを変えることまで趣旨として含むものではない。
このことから、憲法24条2項の「個人の尊厳」の文言を根拠として、憲法24条2項の「婚姻及び家族」の枠組みを、このような目的を達成するための手段として機能しないものに変えてしまうことができるということにはならない。
そのため、「婚姻及び家族」の枠組みが有している目的との整合性の観点から「婚姻及び家族」の中に含めることのできる人的結合関係の範囲は定まっているのであり、その「婚姻及び家族」を対象として適用される「個人の尊厳」の文言を持ち出して、それを遡って「婚姻及び家族」の中に含めることのできる人的結合関係の範囲を形成している境界線の方を取り払うことを主張することはできない。
よって、憲法24条2項の「個人の尊厳」の文言を根拠として「婚姻及び家族」の枠組みそのものを書き換えることができるとの主張は正当化することができず、この「個人の尊厳」の文言を理由として「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることができるかのように論じることは誤りである。
ここでは「個人の尊厳」を持ち出すのであるが、「個人の尊厳」を用いて何かを是正することができる場合とはどのような場合であるかを検討する。
「個人の尊厳」は、自然人であれば誰もが持つとされている。
そのため、人間であるにもかかわらず物や動物のように扱われたり、奴隷のように扱われるなど、法的に自然人として扱われていない場合には、この意味の「個人の尊厳」を用いてその状態を是正することができるといえる。
また、「個人の尊厳」は、「全体主義」との対比における「個人主義」に根差すという文脈で使われている。
そのため、全体の中の一部として扱われたり、何者かの付属物として扱われたりすることがあれば、この意味の「個人の尊厳」を用いてその状態を是正することができるといえる。
他にも、「個人の尊厳」は、権利や義務を結び付けることのできる法的な主体としての地位を指すものである。
そのため、「権利能力」を喪失させられたり、「意思能力」を否定されたり、「行為能力」を制限されたりした場合には、この意味の「個人の尊厳」を用いてその状態を是正することができるといえる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
民法は我々の生活関係を権利と義務に分解して規定し、規律するが、この権利及び義務の帰属主体となりうる資格を権利能力という。民法は、権利能力はあらゆる自然人が平等に有するとしているが、このことは近代法によって確立された原則であり、近代法が発達する以前の時代、すなわち奴隷制が存在した時代や、封建時代には、人によっては権利能力を認められない自然人も存在したのである。人は権利能力があって初めて法律的に自由な経済活動が可能となるのであり、その権利能力を自然人に平等に認めるのは、憲法の要請でもある。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第15課 民法―権利義務の主体(自然人その1) (下線・太字は筆者)
【動画】〔独学〕司法試験・予備試験合格講座 民法(基本知識・論証パターン編)第8講:権利能力と胎児 〔2021年版・民法改正対応済み〕 2021/05/28
【動画】【行政書士試験対策】権利能力//権利・義務の主体となれるのは? 2023/03/25
【動画】民法本論1 01権利能力 2011/04/11
【動画】2021応用インプット講座 民法5(総則5 権利能力) 2020/11/20
権利主体とは?権利能力の発生要件・意思能力や行為能力との違い・事業者の注意点などを分かりやすく解説! 2023.05.26
このため、もし「権利能力」を喪失させたり、「意思能力」を否定したり、「行為能力」を制限したりする法律が立法された場合には、その内容について、立法目的の合理性と、その立法目的を達成するための手段の合理性を審査し、その立法目的に合理的な根拠がなく、又はその手段・方法の具体的内容が立法目的との関連において著しく不合理なものといわざるを得ないような場合であって、立法府に与えられた裁量の範囲を逸脱し又は濫用するものであることが明らかである場合には、その要件が「個人の尊厳」に反するものとして是正されることは考えられる。
しかし、「個人の尊厳」は何らの制度も利用していない状態で既に有しているものである。
そのため、何らかの制度がなければ、その者が自然人としての地位を失って物や動物のように扱われたり、奴隷のように売買される対象となったりしているということはないし、集団の中の一部として扱われたり、何者かの付属物として扱われたりするということもないし、「権利能力」を喪失したり、「意思能力」を否定されたり、「行為能力」を制限されたりするということもない。
よって、この「個人の尊厳」を得るために特定の制度が必要になるという考えは誤りである。
また、「個人の尊厳」を用いることができる場合があるとしても、これらを是正することができるということに留まるものである。
そのため、この「個人の尊厳」というだけでは、何らの規範的な枠組みを示すものではないことから、この「個人の尊厳」を用いて特定の制度を創設することを国家に対して求めることができるということにはならないし、当然、これによって具体的な制度の内容を形成することができるということにもならない。
もしそれをするための根拠として「個人の尊厳」を用いようとしても、それは「個人の尊厳」の文言を用いて是正することができるとする役割の範囲を超えており、その結論を正当化することはできない。
よって、「個人の尊厳」が理由となって、ここでいう「同性間の婚姻」と称する制度を立法することが国会に対して義務付けられているとの前提で論じていることは誤りである。
その他、ここでは「個人の尊厳」(個人を尊重する)の文言を、ある特定の制度を設けることが政策として望ましいと考える意味で用いようとしていることが考えられる。
しかし、どのような制度を設けることが政策として望ましいかということについては、「個人の尊厳」と述べるだけで、何らかの結論を導き出すことができるというものではない。
もしこのような意味で「個人の尊厳」という言葉を用いようとしているのであれば、同様に、「個人の尊厳」の実現のために一夫多妻制とするべきであるとか、「個人の尊厳」の実現のために婚姻制度を廃止するべきであるなど、様々な政策を「個人の尊厳」と述べるだけで正当化することができてしまうことに繋がる。
すると、下記のようにあらゆる制度や政策について「個人の尊厳」と結び付けて論じることが可能となる。
・ 「個人の尊厳」の実現のため、近親者との婚姻を認めるべきである。
・ 「個人の尊厳」の実現のため、一夫多妻制を認めるべきである。
・ 「個人の尊厳」の実現のため、婚姻適齢を廃止するべきである。
・ 「個人の尊厳」の実現のため、一夫一婦制(男女二人一組)とするべきである。
・ 「個人の尊厳」の実現のため、離婚後は共同親権にするべきである。
・ 「個人の尊厳」の実現のため、離婚後は単独親権にするべきである。
・ 「個人の尊厳」の実現のため、選択的個人名制(夫婦別氏制)とするべきである。
・ 「個人の尊厳」の実現のため、好きな芸能人と同じ氏に変えられるべきである。
・ 「個人の尊厳」の実現のため、氏を廃止するべきである。
・ 「個人の尊厳」の実現のため、名も廃止するべきである。
・ 「個人の尊厳」の実現のため、貞操義務を廃止するべきである。
・ 「個人の尊厳」の実現のため、愛人を解禁するべきである。
・ 「個人の尊厳」の実現のため、婚姻制度は廃止するべきである。
・ 「個人の尊厳」の実現のため、戸籍制度を廃止するべきである。
・ 「個人の尊厳」の実現のため、自動車運転を免許制で規制するのは止めるべきである。
・ 「個人の尊厳」の実現のため、安楽死は認められるべきである。
・ 「個人の尊厳」の実現のため、銃器の所持は認められるべきである。
・ 「個人の尊厳」の実現のため、ドラッグは合法化するべきである。
・ 「個人の尊厳」の実現のため、ヘイト表現は規制するべきでない。
・ 「個人の尊厳」の実現のため、ヘイト表現は規制するべきである。
・ 「個人の尊厳」の実現のため、窃盗を犯罪化するべきではない。
・ 「個人の尊厳」の実現のため、窃盗を犯罪とするべきである。
・ 「個人の尊厳」の実現のため、仇討ちは許されるべきである。
・ 「個人の尊厳」の実現のため、………。
上記で示した中には、それぞれ政策として両立しないものが含まれており、これらの対立する政策を「個人の尊厳」という同一の理由を持ち出すことによって一つの結論に収束するという性質のものではない。
そのため、「個人の尊厳」を理由とする形で、特定の結論を導き出すことができるということにはならない。
そのことから、ここで「個人の尊厳」を持ち出したとしても、それを理由としてここでいう「同性間の婚姻」と称する特定の制度を立法することについて正当化できるということにはならない。
これと同じ性質を持つ議論として、下記の「全体の奉仕者」(憲法15条)の話が参考になる。
【動画】九大法学部・憲法2(人権論)第9回〜「在監者の人権」「公務員の人権」・2021年度後期 2021/11/01
ここで述べられているのは、当たり前のことになっている抽象的な原理に対しては誰も反対しないことから、そのフレーズが都合よく利用されてしまい、それを理由にして個別の場合において自分の好む結論を出そうとする言説となっていないかに注意する必要があるというものである。
憲法学者「宮澤俊義」が「公共の福祉」について説明している部分も参考になる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(九) 要するに、基本的人権は、公共の福祉に反する場合は、保障されないか、または、基本的人権の保障は、公共の福祉のワク内でのみみとめられるか、と問い、これに対して、基本的人権の保障は、公共の福祉のワクによって、制約されるとか、されないとか、答えることによって、問題は少しも解決されない。その公共の福祉が与えられた具体的な事件において、どういう内容をもつかが明らかにされないかぎり、ほんとうの答えは出てこない。公安条例を例にとっていえば、問題は、一般的に基本的人権の保障に公共の福祉のワクがあるかどうかではない。そこで、そういうワクがある、または、ない、と答えただけでは、その公安条例の合憲性の有無は少しも明らかにされない。この点について、たとえば、公共の広場での集会についての届出制を定めることは合憲だが、許可制を定めることは違憲だとする説があるとして、━━事実そういう説が多いようであるが、━━もしそういう解釈をとるならば、届出制も集会の自由に対する制約にはちがいないのであるから、そうした制約がいったい何によって合憲とされるかが説明されなくてはならない。ここで、公共の福祉をもち出すとしても、なぜ届出制が公共の福祉によって是認され、なぜ許可制を定めることが公共の福祉によって否認されるか、を明らかにすることが必要である。したがって、ただ公共の福祉によって基本的人権の保障が制約されるか、という問いに答えるだけでは、問題は、少しも解決されない。さらに、具体的に、個々の人権につき、何が公共の福祉であるかが明らかにされなくてはならないのである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
憲法Ⅱ 宮沢俊義 (P231~233) (下線・太字は筆者) (この論点は、当サイト「人権と同じような言葉」で説明している。)
これらと同様に、ここで「個人の尊厳」と述べたとしても、そこから具体的な基準となるものが導き出されるという性質のものではないのであり、これをもって特定の結論を正当化することができるということにはならない。(マジックワード論法)
マジックワードを避けると伝わりやすい文章になる 2023.10.31
この判決が「個人の尊厳」という言葉の意味を理解して使っているとは思えない点について、「ズンドコベロンチョ」の話が参考になる。(ズンドコベロンチョ論法)
ズンドコベロンチョな話 2023/08/03
ズンドコベロンチョ Wikipedia
夢の国において魚介類と会話できるとする「ハイドロフォン」の解説も参考になる。
【動画】タートルトークの【ハイドロフォン】完全解説「これでみんなも海の仲間に!!」キャストモノマネ講座 2020/10/18
【動画】【極秘】タートルトークのハイドロフォンの秘密が判明!?仕組みがヤバすぎた… 2023/07/23
【動画】【登録2000人達成記念】TDS タートルトーク 「イケメンガイドさんの楽しい前説♪」【HaNa】 2018/11/06
【動画】2019爆笑タートル・トーク最前列中央より 2019/03/14
【動画】ハイドロフォンをクラッシュが説明 【タートルトーク】東京ディズニーシー 2019/08/13
ハイドロフォンの仕組み 2017.02.08
“サイコー”な時間をもたらした世紀の大発明品 2021年12月20日
これと同様に、「個人の尊厳」という言葉を使って論理的な過程が示されるはずの部分をブラックボックスにして覆い隠し、そのまま特定の結論を正当化しようとすることは、実質的に何も説明していないことを意味するのであり、そのこと自体が誤った論法である。(夢の国論法)
そもそも、望ましい政策を考えた結果として、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」を目的し、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす「一人の男性」と「一人の女性」を選び出し、その間に「貞操義務」など一定の形式で法的に結び付け、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によってそれらの目的を達成することを目指すこととし、「婚姻」という枠組みを形成しているのである。
そのため、「個人の尊厳」という言葉を望ましい政策と考える旨として用いているのであれば、むしろ望ましい政策という意味で憲法上の立法政策として一夫一婦制(男女二人一組)による「婚姻」という枠組みを定め、他の様々な人的結合関係やその制度を利用していない者との間で一定の差異を設けることにより立法目的の達成を目指す仕組みを採用していることになるのであり、この枠を超える人的結合関係を「婚姻」とすることをその望ましい政策を意味する「個人の尊厳」という言葉によって正当化することができるとする理由にはならないものである。
そのことから、このような望ましい政策がなされた状態とは何かを考えた結果として憲法上の立法政策として一夫一婦制(男女二人一組)の枠組みが定められているということを差し置いて、それとは異なる制度を定めることについて、それを望ましい政策を意味する「個人の尊厳」という言葉と結び付けて論じることができるというものではない。
そのため、このような意味で「個人の尊厳」と述べているとしても、それを基にここでいう「同性間の婚姻」と称する特定の制度を立法することを根拠付けることはできない。
よって、「個人の尊厳」を持ち出して、これを根拠として「同性間の婚姻」と称する制度を立法していないことについて憲法に違反すると結論付けようとしたり、特定の制度を創設するように迫ることは誤りである。
さらに、「個人の尊厳」についてある特定の制度を設けることが政策として望ましいと考える意味で用いようとしているのであれば、そもそもどのような政策が望ましいかという問題については、憲法の枠内で政治部門である立法府の国会で議論される事柄である。
これについては、法令の合憲・違憲、合法・違法しか判断することのできない司法府の裁判所の立場で論じてはならないものである。
この点について裁判所の立場から口出ししようとしていることについても、その主張そのものが越権行為であり、司法権の逸脱・濫用として違法となる。
よって、この札幌高裁判決を書いた裁判官が特定の政策を実施することが望ましいと考える旨として「個人の尊厳」という言葉を用いているとしても、そこで示された内容や結論は正当化することができず、誤った判断ということになる。
このような論理的に導き出されないにもかかわらず、結論だけを述べて正当化しようとすることは、科学における不正行為としてSTAP細胞の事例が参考になる。(STAP細胞論法)
【動画】新発見「STAP細胞」の記者発表 2014/01/30
「STAP論文」使用画像・グラフの7割「怪しい」 NHKが検証、専門家「うっかりミスではない」 2014.07.28
「NHKスペシャル」で15分にわたり厳しい追及 理研・笹井氏自殺に影響はあったのか 2014.08.05
特集:STAPの全貌 幻想の細胞 判明した正体 2015年3月
STAP細胞、米大なども「作製できず」 133回試み失敗 2015年9月24日
刺激惹起性多能性獲得細胞 Wikipedia
科学における不正行為 Wikipedia
再現性 Wikipedia
捏造の科学者 STAP細胞事件 単行本 2015/1/7
著者と語る 須田桃子 毎日新聞記者 『捏造の科学者 STAP細胞事件』 2015年04月21日
科学ジャーナリスト・須田桃子さん 「自分の頭で考えること重要」 「STAP問題」報道経験中心に講演 /北海道 2023/5/27
STAP細胞から10年 減らぬ研究不正、「調査の仕組みに限界」 2024年4月9日
「「STAP細胞を否定して捏造を許さないシステム」のことを科学と呼ぶ”
「人文系」には科学にあたるような規範が抑制的に働いておらず言いっぱなしやりっぱなしの有象無象が横行してる。」 Twitter
「デタラメを言った時に全世界規模でツッコミと否定に晒されることこそが科学の本質です。エビデンスなしの感想文を書いても怒られない界隈にはわからないでしょうが。」 Twitter
「研究者がデタラメなことを言っても、それを検証・批判しないことを学問の腐敗というんだ。」 Twitter
これらのことから、「根源的には個人の尊厳に関わる事柄であり、個人を尊重するということであって、」のように述べて、ここでいう「同性間の婚姻」と称する制度を立法するよう国会に対して迫る主張は誤りである。
「同性愛者は、日々の社会生活において不利益を受け、自身の存在の喪失感に直面しているのだから、その対策を急いで講じる必要がある。」との部分について検討する。
「同性愛者は、日々の社会生活において不利益を受け、」とある。
しかし、「同性愛者」を称する者についても自然人であることに違いはないことから、法的には「個人の尊厳」を有しており「個人」として「尊重」されているということができる。
そのため、「同性愛者」であることを理由として「個人の尊厳」を有しておらず「個人」として「尊重」されない物や動物や奴隷などのように扱われているという事実はなく、「不利益を受け」ているということにはならない。
よって、「日々の社会生活において不利益を受け、」との部分は誤りである。
「自身の存在の喪失感に直面しているのだから、」とある。
しかし、「同性愛者」を称する者が「自身の存在」に対してどのような感じ方をしているかは様々であり、一様に「喪失感に直面している」というものではない。
【参考】「「あなたたちは差別されて困ってるのね、かわいそうだから助けてあげるわ♥️」って勝手に思い込んで、厚かましくしゃしゃりでてくる「アライ」に本当に迷惑しています‼️」 Twitter
【参考】「一方的にLGBT思想の当事者の声のみを取り上げるのよ それだとね私たち市井のホモオカマ同性愛者は困るのよ」 Twitter
【参考】「私たちホモオカマは、まあそんな人もいるよねってほっといてもらえたら充分なんです」 Twitter
【参考】「【アライ】を必要としない理由 ①可哀想な存在ではない。 ②同性婚を望んでいない。 ③子供は望んでいない。 ほぼ、LGBTQ思想活動家の主張しているものが、必要ではない…。」 Twitter
【参考】「自分はゲイだから社会的弱者だと思ったことはないです。」 Twitter
また、そもそも婚姻制度は「性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いをする制度ではないし、「性愛」に基づいて制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもないことから、婚姻制度と「性愛」を結び付けてここで「同性愛者」を取り上げていること自体から誤っている。
他にも、自らの望む法制度が定められていないことに対する憤りの感情については、民主主義の下では、そのような自らの望む形で法制度が定められていないという事態が生じることは初めから予定されていることである。
これを否定するのであれば、それはそもそも民主主義の原理そのものを否定し、特定の個人が自らの思想を他者に対して押し付けるという独裁政治へと変質してしまうこととなる。
そのため、ここで「喪失感」という負の感情を抱いたことを述べたとしても、それが憲法上の条文を用いて下位の法令の内容を無効としたり、特定の制度を創設するよう国家に対して求めることができるとする根拠となるものではない。
よって、この「喪失感」を理由として特定の制度を創設することが義務付けられるとする主張は誤りである。
「その対策を急いで講じる必要がある。」とある。
しかし、法令に違反しない事柄について裁判所が「対策」を「講じる必要がある。」と述べることは、政治部門の国会や内閣に対して特定の政策を実施するように迫るものであることから、憲法76条1項の「司法権」の範囲を逸脱する越権行為であるし、憲法41条の「立法権」や憲法65条の「行政権」を侵害するものとして違憲である。
よって、「その対策を急いで講じる必要がある。」と述べていることも誤りである。
「したがって、喫緊の課題として、同性婚につき異性婚と同じ婚姻制度を適用することを含め、早急に真塾な議論と対応をすることが望まれるのではないかと思われる。」との記載がある。
「同性婚につき異性婚と同じ婚姻制度を適用することを含め、」との部分について検討する。
まず、ここでいう「同性婚」と「異性婚」の意味が、それぞれ「同性間の人的結合関係」と「異性間の人的結合関係」を指すのであれば、それは憲法21条1項の「結社の自由」によって保障されるものである。
しかし、これは法的に考えれば「婚姻」ではないため、「~~婚」という表現を用いていることは誤った表現である。
また、「婚姻」とは、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」を目的として、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす「一人の男性」と「一人の女性」の組み合わせに対して「貞操義務」を設けるなど一定の形式で法的に結び付け、産まれてきた子供の遺伝上の父親を特定することができる状態となることを推進し、血縁関係を明確にする機能によって立法目的の達成を目指す制度である。
そのため、「異性間の人的結合関係」については、上記の「生殖と子の養育」の趣旨に対応する「男女」の条件を満たすものであることから、「婚姻」の中に含まれており、法律上で婚姻制度として立法することができ、「婚姻制度を適用すること」ができるといえる。
これに対して、「同性間の人的結合関係」については、その間で「生殖」を想定することができず、上記の「生殖と子の養育」の趣旨を満たすものではないことから、「婚姻」の中に含めることができず、法律上においても婚姻制度として立法することはできないことから「婚姻制度を適用すること」はできない。
よって、ここでは「同性間の人的結合関係」「につき」「異性間の人的結合関係」「と同じ婚姻制度を適用することを含め、」と述べていることになるが、そもそも「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることはできないことから、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とする法律の立法と適用が可能であることを前提としていること自体が誤りということになる。
次に、ここでいう「同性婚」と「異性婚」の意味が、それぞれ「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることと、「異性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを指している場合には、そもそもそれらを「婚姻」とすることができるかという部分を検討する必要がある。
先ほども述べたように、「異性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることはできるが、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることはできない。
そのため、「同性婚」のように、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることができるかのような表現を用いていることは誤りとなる。
また、ここでいう「同性婚」と「異性婚」の意味が、それぞれ「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とする制度と、「異性間の人的結合関係」を「婚姻」とする制度を指しているのであれば、ここでは特定の制度に対してさらに「婚姻制度を適用する」ということを述べていることになり、制度を二重にしようとしている点でも誤りである。
「早急に真塾な議論と対応をすることが望まれるのではないかと思われる。」との部分について検討する。
上記で解説したように、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とする法律を立法していないことについて、憲法に違反することはない。
憲法に違反しないことについては国会に対して何らの義務付けも行われておらず、制度を立法するための「議論」や「対応」をすることも求められていない。
そのため、「早急に真塾な議論と対応をすることが望まれるのではないかと思われる。」のように、立法府である国会に対して義務のないことを要求していることは正当化することができず、誤りである。
この分野の訴訟の事案は、当サイトでも解説しているとおり憲法に違反するとはいえないのであるが、下級審で「憲法に違反する」との判断が何件か行われている。
これには、裁判所においてとりあえず「憲法に違反する」と判断しておくことによって、国会に対して何らかの制度を創設するように促したいとの動機が裏に隠れている可能性がある。
また、司法府から立法府に対して特定の制度の創設を求めたり、議論を促すことによって政策を形成する機能を果たそうとする意図があるのかもしれない。
しかし、憲法は国家の作用を41条で「立法権」、65条で「行政権」、76条1項で「司法権」のように三権に分割しており、それぞれの役割を区別し、機関同士の抑制と均衡によって権力の独占を防止する仕組みを採用している。
そのため、三権のそれぞれの機関は、他の機関が有する権限を行使することはできないし、他の機関が担っている権限に対して干渉することも許されない。
そのことから、裁判所が司法権を行使するに当たっては、法令に違反するか否かしか判断することはできないのであり、政治部門である国会が立法権を行使して実施する政策や内閣以下の行政機関が行政権を行使して実施する政策についての良し悪しを判断したり、政治部門の国会や行政機関に対して特定の政策を実施するように圧力を加えたりすることは許されない。
そのため、憲法に違反しないにもかかわらず、とりあえず「憲法に違反する」と宣言しておくことによって、立法府である国会に対して何らかの活動を行うように求めるという判断をすることは、極めて政治的な主張となっていることを意味し、司法権の行使として正当化することのできるものではない。
そのような意図をもって憲法を解釈することによっては導き出すことのできない結論を述べて違憲と宣言することは、裁判所の権限として与えられていない権限を行使しようとするものとなることから、司法権の逸脱・濫用に当たるといえる。
このような形で司法権を行使しようとすることは、「法の支配」「立憲主義」「法治主義」の精神に反し、正常な国家運営を損ない、法の秩序そのものを崩壊させることに繋がるものである。
そのため、憲法に違反しておらず国会に対して義務付けが行われていない事柄であるにもかかわらず、裁判所が憲法に違反すると判断して国会に対して義務付けを行い、何らかの立法をするように迫る行為は、司法権の範囲を逸脱するものとして憲法76条1項の「司法権」に違反することになる。
また、国会に義務はないにもかかわらず義務付けを行い、責任を負わせるものであることから、立法権を侵すものとして憲法41条の「立法権」に違反することになる。
よって、ここでいう「同性間の婚姻」と称する制度を立法していないことについて憲法に違反すると判断していることは誤っており、結果として、この札幌高裁判決の行った判断の内容の方が憲法に違反することとなる。
また、この憲法に違反するという判断によって国会がここでいう「同性間の婚姻」と称する制度を立法することを強制され、実際にその制度が立法されたとしても、その後、その制度が存在することによって国民の間で何らかの利害の衝突が発生した場合には、そもそも国会に義務のないことを強制し、その制度が存在することの原因となった裁判所の判断の誤りが問題として追及されることになる。
すると、今度は国会ではなく、裁判所にその誤った判断によって引き起こされた損害を賠償する責任が生じることとなる。
つまり、裁判所が国家賠償の責任を負う対象となって責任を追及されることになるということである。
これは、行政権の違法な行使によって国民に損害が生じた場合に行政官個人に対して求償権が行使される場合と同様に、その誤った判決を下した裁判官個人に対する求償権も行使されることになると考えられる。
無責任な国家権力の行使が行われても、その責任をとる者がおらず、野放しになることは許されないからである。
この意味でも、法の解釈を恣意的な形で行うことは許されず、司法権に与えられた権限の範囲を逸脱することは厳に慎むべきであり、このような誤った判断は直ちに是正されるべきである。
第4 結論
よって、控訴人らの請求はいずれも理由がないからこれらを棄却すべきであるところ、これと同旨の原判決は結論において相当であって、本件控訴は理由がないからいずれも棄却することとして、主文のとおり判決する。
札幌高等裁判所第3民事部
裁判長裁判官 齋藤清文
裁判官 吉川昌寛
裁判官 伊藤康博
■ その他
〇 文脈を理解することが不可能な部分について
この判決の内容は、文面の脈絡を丁寧に辿ったとしても、文と文の前後で話が繋がっておらず、論理展開を把握することが不能となっているところが多々見られる。
このような文脈を理解することが不能となっていることの問題性を明らかにするために、下記の動画を取り上げる。
【動画】「こいつ何見てるんだ?」と困惑させるための動画.mp4 2022/06/01
法的な判断の正当性は、論理的な整合性の積み重ねによって結論を正当化することが可能となるのであり、論理展開や文脈を理解することが不可能となっている場合には、その内容の結論を正当化することはできない。
〇 支持される解釈とは何かについて
この判決は、法を解釈するに当たって求められる作法を踏まえていない。
この点の問題点を理解するために、下記の動画を取り上げる。
▽ 支持される解釈について
(変えちゃいけないところは絶対に変えていないこと。)
【動画】【感想】Netflix 実写版ワンピースが革命的な成功例だった件 2023/08/31
(最大限のリスペクトをもって原作を表現していること。変えていいところと変えていけないところの取捨選択が成功していること。原作を理解する解像度が高いこと。)
【動画】実写版ワンピース、世界60か国で視聴数1位!評価も最高で完全勝利www【Netflix】 2023/09/02
(原作が何を表現しようとしたのかを分析すること。高い解像度で原作を理解していること。原作への深い理解が反映されていること。原作を何も理解していないし、リスペクトもしていない奴がめちゃくちゃやってはいけないこと。)
【動画】実写版ワンピースは何故成功した?失敗する実写化は●●してる【Netflix/カウボーイビバップ/ドラゴンボール/名探偵コナン/デスノート】 2023/09/03
▽ 支持されない解釈について
【動画】実写版ワンピースならず...実写版デスノートが異次元のヤバさな件【Netflix/ワンピース/カウボーイビパップ】 2023/09/07
法を解釈する際には、法の精神を理解してより明確で普遍性の高い法的安定性に資する規範を見出すことが必要となる。
しかし、解釈として示された内容が、そのようなより高い次元にある規範を正確に導き出すことができないものとなっている場合には、それまでに積み重ねられてきたより適切な規範を見出そうとする過程を台無しにし、公平性を失い、人々の納得感を得るに至らず、人々の合意を取り付けることができず、規範としての安定性が損なわれ、法の支配という営みそのものの公共性も失わせてしまうこととなる。
漫画やアニメの実写化に成功した事例と失敗した事例を検討することは、人々が納得する解釈の形と人々の納得感を得られない解釈の形との違いとは何かを考える際に参考になる。
法解釈の成功と失敗についても、共通するものを感じ取ることができる。
〇 技術者倫理
法解釈が恣意的なものとなってはならないことについて、技術者倫理が参考になる。
【動画】【シティコープセンター事件】超高層ビルが倒壊寸前!?構造計算ミスに気付いたのは、ある大学生からの電話だった。 2024/07/07
NYビル倒壊の危機を回避した技術者倫理の鑑・ルメジャーと、彼を動かした学生 2014.04.28
技術者倫理の理解を深めるための事例シリーズ第1回 シティコープビルの設計変更
シティグループ・センター Wikipedia
<理解の補強>
<主張>同性婚で高裁判決 国民常識と隔たり不当だ 2024/3/16
【社説】「同性婚」容認判決 憲法の曲解で婚姻乱すな 2024年3月16日
実はあの本のパクリだった!札幌高裁「同性婚」判決、驚きの真実 八木秀次 2024/5/10
「婚姻の自由」は性倫理の破壊だ 2024年5月24日
<主張>同性世帯と住民票 婚姻制度改変に繫げるな 2024/6/3
【九州・第2回】被控訴人(被告)ら第1準備書面 令和6年8月9日 PDF
判決の誤りを継承する解説
下記に挙げたこの札幌高裁判決の記事や解説について、当サイトをお読みの方ならば、どの部分が妥当でないかを見抜くことができるはずである。
「婚姻の自由」同性カップルにも保障。シンプルで画期的な札幌高裁判決を傍聴 2024/3/14
札幌高裁同性婚訴訟判決 これは素晴らしい! 2024/03/15
3・14札幌高裁判決─同性婚の法制化を 2024年3月27日
人と人との間の自由な結びつきとしての同性間の婚姻 2024年4月12日 PDF
同性婚訴訟、相次ぐ「違憲判決」の先に立法はあるのか? 「男女間の社会的なジェンダー不平等の解消」への期待も 2024年05月22日
憲法24条における同性間の「婚姻の自由」の位置付け 2024年5月31日 PDF
〈社説〉同性婚の法制化 政治の怠慢は許されない 2024/03/15
<社説>同性婚訴訟判決 違憲是正の法整備急げ 2024年3月15日
<社説>同性婚否定「違憲」 「結婚の自由」立法急げ 2024年3月16日
同性婚否定「違憲」 「結婚の自由」立法急げ 2024年3月16日
同性間にも「婚姻の自由」 尊厳を守る画期的判決だ 2024/3/16
(社説)同性婚訴訟 「違憲の法」いつ正す 2024年3月16日
[社説]同性婚否定二審も「違憲」 国は速やかに法整備を 2024年3月16日
<社説>同性婚訴訟/違憲是正へ法整備を急げ 2024/3/16
同性婚訴訟、二審も違憲 もはや放置は許されない 2024/03/17
【同性婚訴訟】国会は急ぎ議論を深めよ 2024.03.17
社説:同性婚訴訟で違憲 権利の保障へ法制化に動け 2024年3月17日
論説 同性婚訴訟二審も「違憲」 まだ放置するつもりか 2024/3/17
<社説>同性婚札幌高裁判決 国会の不作為許されない 2024年03月19日
【社説】同性婚の法制化 「違憲」の放置許されない 2024/3/21
[社説]早急な議論を迫る同性婚判決 2024年3月20日
【社説】同性婚高裁判決 国会は法制化に踏み出せ 2024/03/23
憲法記念日 理念確認し針路の議論を 2024/05/03
[社説]憲法と家族 24条生かす取り組みを 2024年5月3日
お読みいただきありがとうございました。